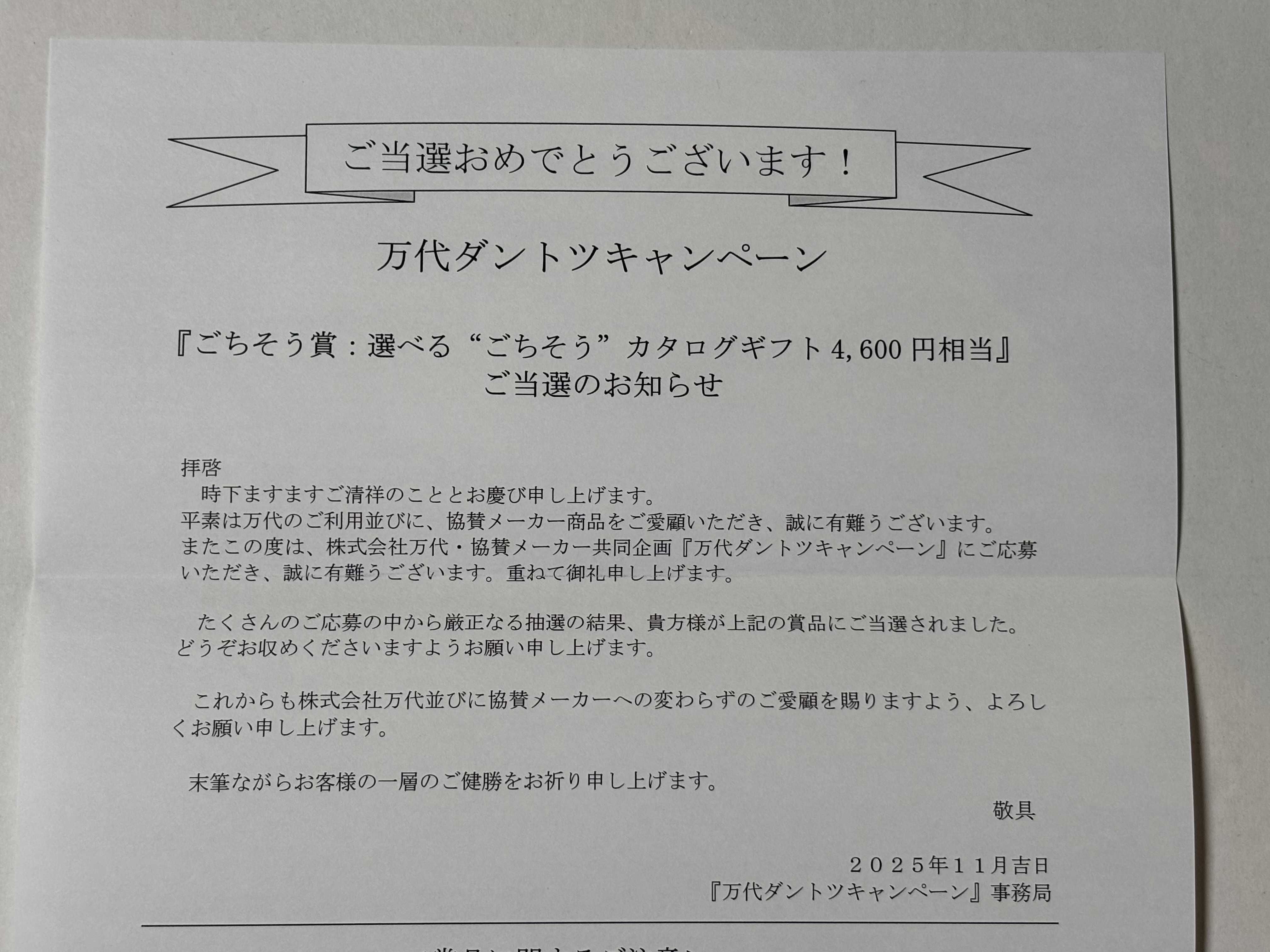2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2011年07月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
ツイッターする?
もしも仮に、つぶやきたいと思ったら「ツイッター」っていうのは便利なんだろうか。使ったことどころか見たこともないのだけれども、世の中はツイッターで溢れかえっているらしいんだが、これ知らなくてだいじょうぶなんだろか。大したことをつぶやきたいわけではない。そもそも「つぶやく」ということ自体、たいした行為ではないからつぶやいてもつぶやかなくてもどっちでもいい。というよりもオレはこのブログで十分つぶやいているつもりなんだが、やっぱり本格的につぶやくには、ブログじゃなくて本場ツイッターがいいんだろうか。唐突だが、ななろくふ、さんよんふ、はちよんふ、ななごおふこれが石田流の出だしの棋譜である。この週末は将棋の定跡書の中の棋譜をパソコンの将棋ソフトに入力する作業をしていた。第何世代かの将棋マイブームの渦中にいまいるということは前にも書いたが、久保の石田流 (amazon)という本を買ってきて読んだら非常に面白くて、実戦にはあまり役にたちそうもないものの、技術的な論理がすばらしく、真剣にマスターしようかと思い上記の作業をするに至ったのだった。電車の中では詰将棋を解き、夜な夜な定跡書をトレースし、休日にはパソコンで棋譜データベースを打ち込むとか、ほとんど受験生なみの情熱で勉強に取り組んでいるわけである。受験生がこれほどの情熱を持ち合わせているかはさておくとして、この情熱をたとえば英語とか英語とか、資格試験のようなのの勉強に打ち込んで成果をあげれば、世間様もオレのことを少しは認めてくれようとは思うものの、やっぱり興味のあることとないことでは、熱中の度合いが違いますから如何ともしがたい。しかしこれだけ情熱を注いでも5手詰めの詰将棋を解けなくて悶絶する日もあるし、それは体調が悪かったり眠かったり酔っているからだということにしても、定跡書を読むにしても「6五銀」がどこかとっさにはわからなかったりするから、やっぱり才能はないのかもしれない、と思いつつ、天才は99%の努力である、という言葉も信仰したく、でも、人とサルのDNAは99%一緒なんだっけか。ともあれ、情報を詰め込むというインプット系の作業ばっかりしていると、なにがしかのアウトプットをしたい欲求が高まってくる。対戦すればいいじゃん、とはもっともな話だが、石田流を完全にマスターするまではネット将棋で対戦するのはしばらく封印することにしている。ななろくふ、さんよんふ、はちよんふ、ななごおふという将棋ソフトが読み上げる棋譜を何百回きいたかわからないから、そのまんまをつぶやいてみたくなり、このブログを書くに至った。つぶやくにもほねが折れる。
2011.07.24
コメント(0)
-
猫背キョウセイ
最近猫背が気になりだしてきた。昔から猫背ぐせはあったが、若い頃はあまり気にならなかった。ふと街角のガラスに映る自分の姿を見たときに、あれこんなひどかったっけ、と思い、胸をはって歩くことを心がけるようになった。年齢とともに筋力も衰えて背中のふんばりもきかなくなっていって、やがて老人のような姿勢になるのであり、その時間の経過を今まさに辿っているのだということを自覚して始めて、それに逆らってみようと思い立つのである。しかし、立って歩いていても気を緩めるとすぐにもとの猫背に戻ったり、椅子に座っているときはよっぽど気をつけていないとぐでーんとなる。四六時中気をはりつめているわけにもいかないし、姿勢に意識を集中させるのはせいぜい1分ぐらいが限界であった。筋トレをして肉体改造を試みるという手もあるのだけれども、その手の努力が長く続いた試しがないし、姿勢がたるんできたから筋トレを始めるというのも老人くさくていけない。「秀英 調整式背筋サポートベルト」なるものを買ってきた。グッズに頼るわけである。これで常に肩を反らしていれば、ホネのカタチから変わってゆくかもしれないということをちょっと期待したことによる。さておき東急ハンズでは、これのお試し版が置いてあり、試着可能だったのでまずは試着してみた。幸い周囲にはそれほど人はおらず、うまくつけられなくて恥ずかしい思いをするリスクはそう多くはなかった。この商品、パッケージの写真からも想像がつくように、対象は女性限定のようである。その証拠に、他製品のLサイズでは窮屈すぎてはちきれそうで、LLサイズでようやく装着できたのだった。構造としては、タスキがけのひもをウエストのベルトで締める簡単なもので、肩のヒモが腕を吊り上げて背中を反らしているようだった。翌日からこれを装着して歩いてみた。もちろんTシャツの上からこのベルトをしたままの格好だとアヤシイ人と思われるから、シャツを羽織って隠す必要がある。炎天下に2枚がさねはうっとうしいけれども、そうもいっていられない。ちょっと歩いた感じでは、確かに肩が後ろにひっぱられて、正しい姿勢になっていそうである。締め付けられるような感じがするのも、正しい姿勢への意識に作用して、肩甲骨あたりにチカラが入る。ところが1時間ぐらいすると、なんだか具合が悪くなってきた。ウエストのところでしめるベルトの圧迫が強すぎたようである。バリバリテープをはがしてフリーにすると、具合の悪いのが治った。商品パッケージのモデルはウエストでベルトを締めているから、それにならって同じようにしたのだけれども、男性用のサイズではないことから、胸のちょうど下あたり、みぞおちのところに巻きつけるのが自然だということがわかった。2日目以降は、結構長い時間着けていても平気になった。成果が現れたかというと、そうでもない気がする。まだ2,3日しか試していないのでそれほどの効果は見込めないだろうけれども、これを外したとたんにまたもとの猫背に戻ってしまって、それが前よりもひどくなっているような感じがある。それはそらした状態との振幅が広いからそう思うだけかもしれないとも思う。いずれにしても、結論づけるのはまだ早いと思われる。あと、一つだけ決定的なことがある。それはこのサポートベルトを外したときの、その解放感である。あるいは世の女性は、ブラジャーを外す(あるいは外される)ときの解放感のために生きているんだろうか。
2011.07.20
コメント(21)
-
石田流三間飛車
Yahoo将棋のレートが1500台になった。1300~1499が初級者で、1500~1699が中級者という位置づけになっているらしい。ログインしているユーザーのリストには1499までだったときには青で表示されいた名前が、ピンク色に変わった。中級者のイメージカラーはなんとなく黄色だが、それだと見辛いためにピンクなのだと思うがそんなことはどうでもよい。とにかくレート上は中級者に昇格したわけである。とはいえ中級者を相手にするとなかなか勝つのは難しく、たまに初級者のレートに戻ったりすることはある。レートを上げるためにこのネット将棋をしているわけではないから、点数としてのレートが下がることにはこだわりはないけれども、下がるということは負けているわけだから、嬉しいわけもなく複雑ではある。1498点ぐらいだったときに1900点台のプレイヤーと対戦した棋譜をのせてみる。結果的にボクが勝ったので、上級者の証であろう1900点台というレートを持っていること自体がアヤシくも思われる。初級者狩りをして稼ぐとか、コンピュータ将棋でカンニングしたりすれば点数は上がるかもしれないから、実力が伴わないレートだけの上級者はいるだろう。■今週の棋譜■石田流三間飛車の本がブックオフで100円だったから買ってきてそれをベースにした戦法で最近は対局している。「振飛車(ふりびしゃ)」という、飛車を左側に寄せる戦法はなんとなく好きではなかったのであまりつかわなかったのだけれども、「居飛車(いびしゃ)」にこだわっていても勝てないものは勝てないので「四間飛車(しけんびしゃ)」から習いだして割と戦えるようになってきたけれどもやっぱりあまり面白くないから次は「石田流三間飛車」に挑戦中なのである。「三間飛車(さんげんびしゃ)」は、角の隣の位置に飛車を振る振飛車戦法の一つであるが、「石田流」とつくとちょっとかっこよくなるだけではなく、対抗手段を知らないとはめられてしまう奇襲戦法でもあり、初心者をたぶらかすにはもってこいの戦法でもある。ただし的確な反撃手段を知っている相手には通用しないどころか、見事な返し技を決められてしまうといういわくつきの戦法であったりもする。相手はレート1900ということもあり腕に自信があったのだろう。石田流の奇襲を防ぐ最も簡単な防御手段は、後手が4四歩として角の道を止めてしまうことであるが、このときの相手はそれをせず、石田流で仕掛けてこいという態度を示した。さすがにレート1900の懐に丸腰で飛び込んでゆくような無謀さは発揮できなかったものの、角交換からの急襲をみせつつ、返し技をけん制する「升田式」も取り入れつつ駒組を進めていくと、相手もそれにつられたのか受け気味な、どちらかというとのびのびとしていないような戦い方になっていったようだった。(余談だけれども、石田さんは江戸時代の棋士で、升田さんは昭和30年頃に活躍した棋士。 石田流を改良した「升田式石田流」は当時最強の戦法と謳われ大いに流行したそうな)30手目ぐらいまでは、主導権を握っているようでも、先手(ボク)側にこれといった仕掛け手段はなく、なんとなく王様を囲ってみたり端歩をついたりするしかなかった。33手目の7七角を見てどういうわけか後手が仕掛けてきて戦端が切られた。40手目の後手3一角を見てオレも仕掛ける。それから結果までの応接はちょっといまいちなところもあるけど、このレートにしてはなかなかいい戦いができたんじゃないかと思っている。結果として勝てたのでこうやって自慢げに棋譜を世に出せることになって、ボク本当によかったよ。
2011.07.12
コメント(200)
-
右脳左脳タイプ
システムエンジニアの仕事には2種類ある。一つは、複雑なものを感覚で捉えてイメージ化すること。もう一つは、イメージを言葉に置き換えて人に説明すること。既存のシステムの構造を理解しようとするとき、目前に現れる情報は全体の中のほんの一粒ずつでしかなく、これを一つ一つひも解いていくとものすごく時間がかかるから、ソースコードの1ページを0.5秒ぐらいの速度でめくっていってとりあえず全体を見渡すとなんとなく全体像が浮かび上がる。完全に理解する必要はなく、細分化しても、いくつかのパターンと例外とに分類すればよい。これがイメージ化する作業であるが、これだけだとおのれの頭の中に蓄積させるだけだから全くもってカネにならない。イメージを絵に描いたり文書化したり話したり表現することで我々は金をもらっているといってよい。右脳・左脳のおもしろ診断 (http://luckybrains.zero-yen.com/shindan.htm)これでオレは「右脳左脳タイプ」に分類された。『直感でとらえて論理的に表現、得する出世タイプ』悪くないね。
2011.07.11
コメント(200)
-
T-ara Bo Peep Bo Peep
T-ara(ティアラ、と読むらしい)という韓国の女性アイドルユニットに釘付けである。T-ara "Bo Peep Bo Peep"(http://www.youtube.com/watch?v=kg8dxFoxCkc)この映像限定なのだけれども、こんなにすごいアイドルグループをこれまでに見たことがない。特に偏った性向とか、アイドルマニアというわけでもないけども、カンペキだと思うんだけれども。とこんなことをいってるような男は軽蔑されるんだろか。でも、ちょうかわいんだけども。
2011.07.10
コメント(200)
-
キメラワクチン
我々の仕事とはなにか、というテーマの雑談を、夜間待機かなんかのヒマなときに同僚と話したことがあって、その話を横できいていた新人の女の子が、「けんかになってませんでした?どきどきしてたんですけど」といっていたことを思い出す。オレにしてみればけんかどころか座興として楽しい会話だったし恐れられることは予想していなかったのだけれども、女性にどきどきしてもらうのはどういうわけかちょっと嬉しい気持ちになる。ともあれ、そのとき同僚としていた会話は以下のようなものである。もう何回か同じようなことを言ったり書いたりしてるかもしれないが繰り返す。我々の仕事はコンピューターのエンジニアであり、その存在意義は、複雑な計算や事務処理の速度をはやめて人の仕事を楽にすることにある。なのに8時間労働制が6時間制になったというわけではない。この仕事に果たして意味があるんだろうか。というような感じで話ははじまっていった。「今までの仕事をコンピュータが肩代わりしてくれるようになったからといって、企業としては余った人を遊ばせておくわけにもいかない。余った人は別の仕事をしてもらうか、それでも余るなら、クビをきられるしかないんじゃないかな。」クビを切られるというということはその人の生活がおびやかされるわけで、つまりコンピュータで仕事を効率化することは、雇用のクチを減らしている?つまり我々はクビを切られる誰かを不幸に運ぶ片棒を担いでいるってこと?「効率化されたら会社の経営は潤うよね普通に考えたら。そしたら雇用も増えるから問題ない。」たとえば効率化されきったらどうなる?これ以上ないほど完璧なシステムで経営が洗練されたら、それ以上雇用は増えない。「会社はいっぱいあるし、少なくとも世の中が完全にそんなことになるのはあと100年たっても考えられないからだいじょうぶだよ」200年先に完璧なシステムに到達するとして、それまで我々は、効率化とかいう名の下に、誰かの仕事を取り上げてメシくってるわけだよね。「そうだよ。効率化されきったと思われても、新しい価値を売るんだよ。コンピュータウィルスの危険性とか、セキュリティの脆弱性とか、不安を煽れば企業はいくらでも金を出している。コンピュータウィルスやハッカーがなくならないのはなぜか知ってるか?ビジネスだからだよ。」ああ、あれだな、薬剤会社が特効薬で儲けるために、病原体も同時に開発するっていうキメラワクチン。。て話がそれてるけど、じゃあコンピュータやシステムがどれだけ発達しても、目的が達成されるってことはないわけだな。「目的ってなんだよ。その目的とやらが仮に達成されたとしたら、我々の仕事は取り上げられる。そうならないように、目的は達成しないほうがいいにきまってる。あとはどれだけ引き伸ばすか、違う目的をぶら下げるかとかね。」ふん、オトナだねい。と鼻白んで軽蔑を表現してみたが、負け惜しみの捨て台詞のようだったと反省した。
2011.07.03
コメント(1)
-
チームバチスタ
「チームバチスタの栄光」という本を借りて読んだ。心臓外科手術中に不審死が相次ぎ、窓際医師がその調査にかりだされ謎を解いていくという医療ミステリーだった。最初はどうかと思ったけど、後半、主役級のキャラが出てきてからは結構面白くなってきてだいぶ満足した。医療ミステリーの本筋とは別にこの小説の根底には、病院という組織のうにょうにょしたところが、たとえば部署同士の権力闘争や人間関係の複雑さでもって描かれており、むしろそのことを書くためにこの作家は筆をとったんじゃないかというようなことが、文庫の最後の解説でも言われており、たしかにミステリー本体よりも病院の中味をのぞき見るような視点での面白さに読み手もひきこまれてるんじゃないだろうか。そこで描かれたり語られたりしているテーマはオレの思うところ、医療の目的は患者を救うことではなく、医療組織を運営することにあり、患者を救うのはそのための手段にすぎない。ということではないかと思われる。この小説の主人公は、手術中に起きた不審死の調査として、同組織内の仲間にたいして内部調査を行う役割を任じられる。疑いをもって聞き取り調査を行うということは、それだけで疎ましがられることになるし、調査には法的な強制力はないから、取り調べられるほうは話して不利益になるようなことは話そうとはしない。疑われるようなことをしていないにもかかわらず不利益になることを厭うのは、組織内での自分の立場を悪くしないための予防線であったり、よしんば誰かを貶めたいためのちょっとしたはかりごとであったりする。組織とは、このように個々の思惑が複雑に積み重なった挙句に出来上がったものであり、けして「組織とは」というような定義や法則に従ったものではない。組織は一枚岩ではなく、だから一筋縄ではいかない。というようなことを浮き彫りにしている小説でもある。病院に限らず、事件や恋愛を通して色々な組織の実情を暴く娯楽作品は昔からあって、有名なのでは白い巨塔とか野生の証明とか踊る大走査線とか、あとたぶん坂の上の雲も組織の理不尽や難しさを描いた小説だと思う。組織とはかくもゆがんでおるのかという類の話はいくつも浮き彫りにされてきたでもこれだけ浮き彫りにされているのにもかかわらず、組織と個人との戦いを描く話の種が尽きないということは、組織の体質は変わっておらず、これからもずっと変わらないのだろうとは思われる。恥ずかしながらオレも最近ようやくこのことにうすうす気付きはじめていたけれども、にわかには信じがたくを受け入れることができずにいる。医者の使命が患者を救うことならば、政治家は国を治め、人の暮らしをよくすることが使命あり、建築家は建築で、芸術家は芸術で、人を豊かにしたり幸せにしたりすることが目的であらねばならない。組織運営の糧に甘んじてその対価で生計を成すことを果たして目的としていいのだろうか!1というところを強く言いたいのはやまやまだけれども、まずは生活するために仕事をしているわけで、オレも偉そうなことは言える身分ではない。
2011.07.03
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1