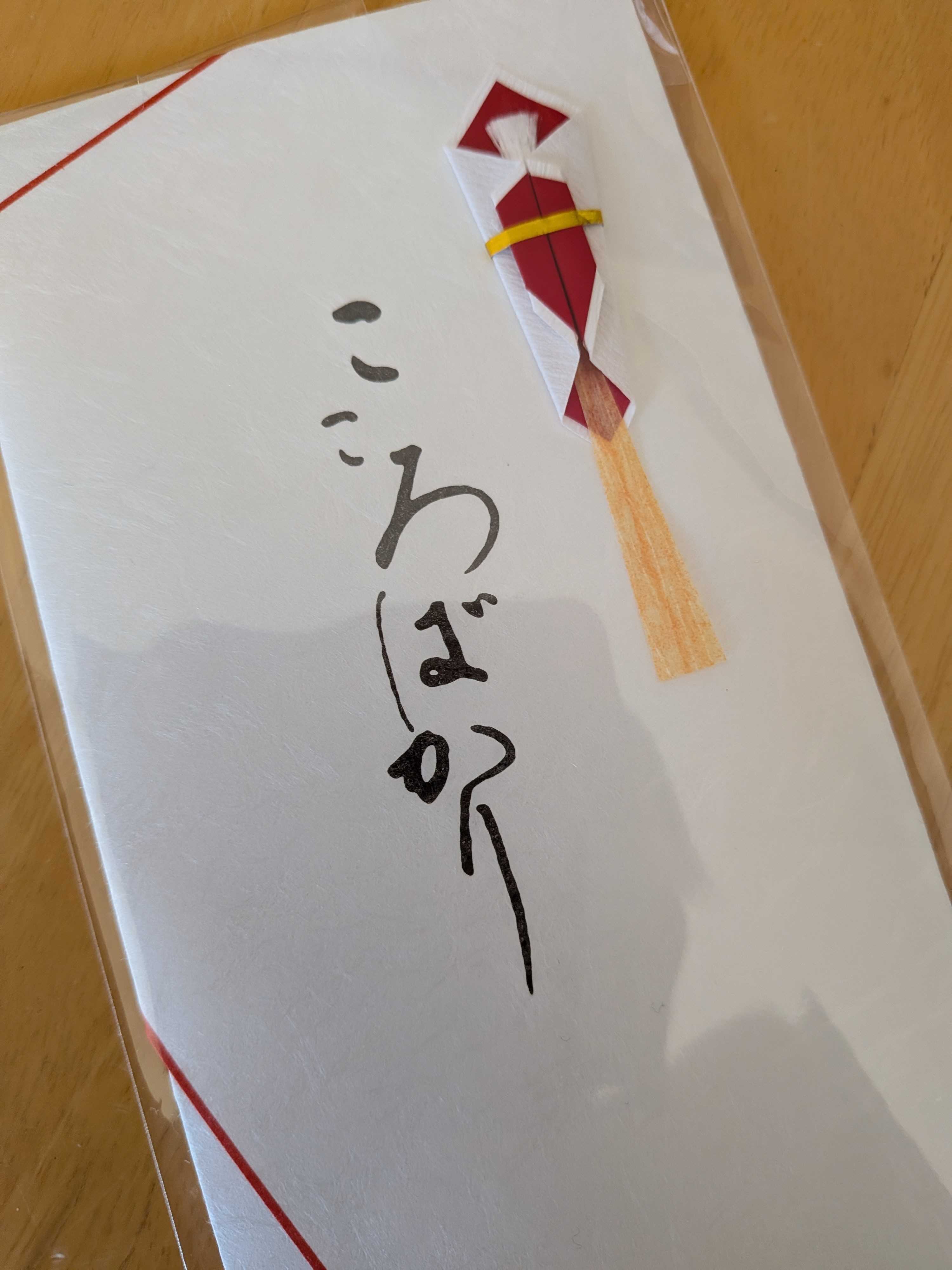2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
商品としてのナショナリズム
ラストサムライを観た感想について、それほど面白くなかったという評価を方々で撒き散らすと敵を増やすようだ。なんで?とか、あの映画を面白いと言わないなんて信じられないとか、奇をてらってそんなこといってるんじゃないかとか、まるでエキセントリックな感じで見られる。そこまで軽蔑されるとオレも折れるよりほかなく、いや確かに面白くななかったというのは言い過ぎかもしれないけど、でも泣くほどじゃないような気が、、などと少し勢いを弱めたりしてその場を繕う。よしんば、評価を「面白かった」と全面的に翻すことになったとしても、一つだけ納得できないのは、多くの「日本人で良かったと思った」という意見であった。昨日のmimiと対談で、日記として書いたラストサムライの感想の話題になり、面白かった面白くなかった、とやはり意見は真っ向から対立した。彼女もその他大多数の観客と同様に、「日本人で良かったと思った」ということを言って、オレはこのときも混乱したが、続けて彼女が言った「だって今まで日本嫌いだったもん」という言葉で初めて意味が判ったような気がした。彼女がいう「日本が嫌い」は、日本の伝統や文化風習に関することではおそらなくなく、どちらかというと対外的、世界的視点から見た相対的な日本が嫌い、ということだろう。確かにイタリア男のほうがかっこいいし、アメリカのほうがチャンスはいっぱいある気がする。映画や音楽ではまるで太刀打ちできないし、政治家もなんだか情けない。オリンピックや世界選手権でもあまり強くないし、総合的にみて他の国より劣っているような印象を日本は持っている。確かに、日本人が日本を嫌いと思う気持ちもわからないでもない。ラストサムライでは、日本人がかなりの数活躍している。サムライの精神や、スタイルもかっこよく描かれている。全編にわたって「自国の文化を大切にしなさい」というナショナリズムを喚起するメッセージが流れている。アメリカ的な手法でナショナリズムを刷り込まれながら、観客は薄らいでいた自国への愛国心を呼び覚まされつつ自分にあてはめて考えている。世界市場における日本の躍進や、さらなるイメージアップを期待しているのと同じように、オリンピックや世界選手権やワールドカップを観戦し、活躍する選手の成績に自分を勝手に当てはめて喜んだり悲しんだりしている、あるいはさせられているのと同じように、劇中の勝元の活躍をあろうことか観客は本気で応援しているのかもしれない。彼が死ぬシーンで起こったすすり泣きの大合唱は、そのことの裏付けであるといえなくもない。ともあれ、「かっこいい日本が全世界へ紹介されて嬉しい」というナショナリズムを誘発させたことと、「実は日本はすばらしいんだよ」という新しい概念を教え込まれたことの新鮮さが感動に繋がったとしかいいようがない。ラストサムライは、最もわかりやすい形で、しかもどちらかというと押しつけがましいくらいの勢いで我々にナショナリズムを伝えてくれた。大衆は、新鮮な「ナショナリズム」という商品に感激し涙を流し大喜びし、消費しまくっている。ランキング1位という形で、商品をむさぼっている。しかしそんな商品化されて押し付けられたナショナリズムなんか、大衆はすぐに忘れてしまうだろう。オレは最初から日本が好きだし、日本人であることを誇りに思っているし、ハリウッド映画に教えられなくても、そんなことは最初からわかっていた。ということを言うと右翼とか言われてしまいそうだが、確かに自衛隊のイラク派遣には賛成だし、自衛隊のことを軍隊と言ってしまう石原慎太郎のことも嫌いじゃないけれども、サヨクを批判することでしかイデオロギーを発揮できない2ちゃんねらーだと思われたら最悪だ。いやもともとそんな大それた政治思想なんかオレに備わっているはずもなく、なんだか訳のわからないことばかり言ってすみませんでした。
2004.01.27
コメント(4)
-
気味の悪い黒いヘルメット
1月27日、今日はいちだんと冷える。7時に家に帰ってきてもう2時間近く経つがまだ指先が冷たい、という冒頭で日記を書こうとしてかれこれ1時間近く経つ。つまり現在時刻は午後10時ということになる。その間にオレは皿を洗ってタバコとワインを買いにいった。エアコンを25度に設定しても部屋が全然暖まらなかったから、外に出て寒い空気に触れて、内と外との気温差でもって室内が暖かく感じるかもしれない作戦をとった。それが奏功したのかどうかはわからないけれども、指先の冷たさはなくなった。その代わりに指先はおもいっきり乾燥してしまい、たぶん今、紙とかめくれない。一日の最高気温が10度を超えるか超えないかが、通勤手段として自転車を使うかどうするかのボーダーラインだ。最高気温が8度とかの日の自転車は、本当につらい。辛いということを通り越して、なんだか悲しくなってくる。Yahooのあてにならない週間天気予報によると今週はずっと10度を越える日がない。このごろ自転車通勤はやめていたが、今日は会社に遅れそうだったため、やむなく自転車を使うことにした。朝はまだいい。明るいし、気温はのぼり調子だからだ。目白通りを長崎から椿山荘までの道のりは下りだし、西高東低の気圧配置によってかどうかわからないがいつも追い風ときている。ということは、暗い上りを向かい風の中進まなければならない帰りは最悪だということだ。向かい風ということは、冷たい風がもろに顔を直撃する。鼻に穴が開きそうになるし、耳はちぎれそうだ。「はあ、はあ、」と呼吸の音をわざと声に出すのは、理不尽な寒さによる苦痛からくる苛立ちを分散させるためだ。50メートル先の信号がだいぶ長いこと青をキープしている。その信号を通過するぐらいにちょうど赤に変わりそうだったからオレは回転を緩めてギアを3段階ぐらい下げた。そのとき、オレの右サイドに静かな自転車の気配を感じたから、「はあ、はあ、」という呼吸の発声をとっさにやめなければならなかった。自転車の気配はまもなく通過しオレの前方へと躍り出た。BD-1に似た、スポーツタイプの折りたたみ自転車だった。このときオレには、抜かれた悔しさ、スピードで負けたとか、勝ち気で劣ってしまったとかそういった感情はない。先へ行きたいなら先へ行ってくれ、もともとちんたら走っていたし、オレはオレの好きなスピードで走る。目の前に躍り出たBD-1は黒いヘルメットを被っていた。自転車用のウィンドブレイカーらしきものを着ていたが全体的に薄着で、見た目の印象として非常に寒そうだった。ヘルメットは赤信号を無視して進んだがオレも無視した。正確には無視したというわけではなく、細心の注意を払って通過した。ヘルメットはまだオレの3メートルぐらい前にいる。ペダルを高速回転しているが、ギアが軽くなっているためか、なかなかスピードが上がらない。オレもゆっくり走っていたが、目の前でスピードを上げないヘルメットがだんだん鬱陶しくなってきてきた。しかし抜きたくはない。抜いたら抜いた手前、抜いたままのスピードを維持しなければならないからだ。その原理はヘルメットもわかっているはずだが、彼はオレの前に立ちふさがっているままだ。なんだこいつは。オレは力を込めるわけでもなく、自然の運動まかせて自動的にあがるスピードのまま、ヘルメットを抜き返した。オレの前にいたときのスピードのヘルメットなら、あっというまに引き離されているはずだ。そのまま10分ぐらい進行して、山手通りとの交差点で信号に止められた。車道の端に停車して、歩道の縁石に足を乗せ停車してすぐに、歩道側をヘルメットが通過し、そして横断歩道の手前で停車した。信号が変わった。オレはヘルメットを意識しつつ直進したが、奴は横断歩道からものすごい勢いで飛び出し、車道へ、しかもオレの目の前に再度躍り出やがった。ぷっちーん、キレた。「おい、なに、なんかのいやがらせ?」オレは言った。聞こえてるのか聞こえてないのか、ヘルメットは相変わらずオレの前に立ちふさがっていてスピードを上げない。オレはまたしてもヘルメットを抜き、そしてわざとゆっくりと、ものすごくゆっくりと走った。ヘルメットは抜き返してこない。オレはやがて停車した。振り向いて確認したわけではないが、奴も停車しているらしい。また走り出した。ヘルメットはどこかへ消えてしまったかもしれない。しかし、目白通りからニコニコ商店街へ移行して20メートルぐらい進んだところで、路地からまたヘルメットがまた出てきた。ものすごく気味が悪かった。
2004.01.26
コメント(1)
-
ラストサムライ
ラストサムライはオレが必ず観なければならない映画だと思っていた。なんとなく侍が好きだし、キルビルを観に行ったときに流れていた予告編の騎馬武者の映像に痺れてしまっていたし、公開されてから聞く評判に悪いものがなかったことや、同僚や友人もみな口をそろえて、良かった、感動した、泣いたというようなことしか言わなかったことなどがその理由だ。こすりつけは正月にはもう同作品を見ていてそのとき、「日本人であることを誇りに思う」という評価をオレに刷り込んだ。会社の同僚である(リブ)タイラさんは「もう一度観てもいい、DVDは買ってしまうかも」とこれも大絶賛で、キュートな銀行員にいたっては「映画館で泣いてしまったの何年ぶりかわかりません」というようなことを言っていた。ランキングは常に1位だし、2週間前に観ようと思って行った池袋では立見だと言われて失意のまま帰ってきた。いよいよもって観なければいられない事態になってきた。しかし池袋のシネマサンシャインでまた意味もなく行列の最後尾に並ぶのは嫌だったので、違う映画館を探した。「ワーナーマイカルシネマズ板橋」。池袋より遠いが、全席指定だから無駄に並ぶ必要はないし無駄に広い空間も心地よく、安っぽいレストランも充実していて時間も無駄にならない。施設は最高だった。磐石の布陣でオレは待望のラストサムライを鑑賞したが、結論から言うと、ものすごくつまらなかった。つまらないと思わせる要素はいくらでもあったが、でも最低最悪、というわけではなく、いい部分もいくつかあって、まず戦闘シーンはめちゃめちゃカッコよかったし、どういうわけか忍者が出てきたときのアクションシーンもものすごくよかった。確かに渡辺謙の演技もよかったし、ボブ役の福本清三さんもよかった。ちなみに福本さんは、大部屋出身の斬られ役一筋として有名な老人である。しかしこの映画の中で一番カッコよかったのは真田広之だ。多分彼は、関ヶ原の島左近をイメージして役づくりしたかもしれないとオレは勝手に思っている。トム・渡辺・真田の3人が鎧を着て騎馬隊の先頭を駆けるシーンはぞくぞくした。黒澤明ばりかそれ以上かとも思ったが、よくよく考えてみたら、大将や指揮官が先頭で行軍するなんてありえない。ありえない、ということをいったらこの映画は壊滅するわけだけで、ディテールをいちいち掘り下げてけなすつもりはないが、一つだけ言わせてもらうと、ラストシーン、敵方の兵隊たちが感極まって土下座するシーンだ。侍たちに敬意をはらっているといことを表現したかった意図はわかるし、そのシーンでは周囲からだいぶすすり泣きが聞こえたが、オレはいっきに冷めてしまった。日本人が誰かに対して敬意を示す表現が「土下座」ってどういうことよ。それに感動してるおまえらって、どういうことよ。「土下座」って、無条件に従属するとか、リスクなしに謝罪するとかそういうことだろうよ。土下座には「誇り」のかけらもないんだよ。権威に対してやたら「お辞儀」させるのもかなり気になった。お辞儀を強いられている町民や農民の意思はまるで感じられなかった。それをいうなら、戦場で死ぬる兵士の痛みや苦しみがまるで感じられなかった。黒澤明が描く戦闘シーンは壮絶でスリリングでファンタジックだけれども、非常にリアルだ。なぜリアルかというと、戦うことの悲しさや死ぬ奴の「痛み」が伝わってくるからだ。敵方の兵隊はトムクルーズに敬意を表すために土下座した。戦死した仲間の死や戦いによる痛みをほとんど無視し、敵に対して土下座した。そしてこのシーンを観て劇場は、すすり泣く音で溢れていた。最低だ。
2004.01.24
コメント(4)
-
国盗り物語
司馬遼太郎の「国盗り物語」は全四巻。坊主が京の油屋を乗っ取り、今度はその財力を基盤に「国盗り」を計画、美濃をその拠点に定めた。一介の牢人から天才的資質で、出世し人望を集め、主君を騙し裏切り、やがて美濃の国主まで登りつめた「斎藤道三」の生涯を描いた「道三編」が1、2巻。道三の実質的な後継者として教育された明智光秀と、道三が果たせなかった天下統一の夢を託された織田信長。二つの強力な個性と対照的な資質、二人が「本能寺」で激突するまでを描いた「信長編」が3、4巻。道三と信長の英雄物語であると同時に、あるテーマを浮き彫りにしていて、それは、勝ち上がるために必要なのは、運や勇気や人気ではなく、精力的かつ緻密に「準備」することと、勝てる条件が揃ったら一気に攻める「決断力」である、というようなことだ。「気運(しお)が来るまで気長く待ちつつ準備する者が智者。気運がくるや、それをつかんでひと息に駆けあがる者が英雄。」という一節が直接そのことを言っている。昭和46年刊行というから、オレが生まれる1年前。娯楽のための歴史小説としてはもちろんのこと、当時のサラリーマンにはビジネス書としても読まれていたとかいないとか。ある日ツタヤに行くと、「本日旧作100円均一」と書かれていて、これは安いと思い、なにかシリーズものを借りようとするあたり貧乏根性丸出しなんだけれども、いかに1本100円で10本借りたとはいえ、10本のビデオを観るにはそれなりの時間が必要であることを差し引くと、100円がお得だとは簡単には言い難く、どのシリーズをチョイスするか悩みに悩んだ。結局借りたのはNHK大河ドラマ「国盗り物語・総集編」の上下巻。このビデオは以前から借りるかどうするか迷っていたのだが、高橋英樹の織田信長にあまり魅力を感じず、いつも見送っていたのだった。1本100円なら最悪つまらなかったとして、最後まで見なくても損した気分にならないぐらいの金額設定なので、思い切って借りることにした。昭和48年の作品というから、オレが0歳から1歳だったころにかけての大河ドラマである。あまり期待していなかったのだけれども、いやいやなんの、演出も妙に堅苦しくならず、原作全編に漂う「色気」とか「風」みたいなものを再現しようという努力がなされていてまずまずの評価といえる。そして何より、平幹二郎とか池内淳子とか三田佳子などが、ものすごく若い。30年前に作られたということは今60とかになっていたとしても当時30。松坂慶子に至ってはハタチというから驚きというか、もはや秘蔵映像。高橋英樹の信長も、顔が違うことを除けば思ったほど悪くなく、秀吉の火野正平がちょっと江口洋介に似ていた。原作でも信長編は道三編に較べてパワーダウンするんだけれども、ドラマのほう後編では、なぜか「梟の城」の葛篭重蔵が出てきたり、「功名が辻」の山内一豊のエピソードが強調されていたりして、どちらかというと司馬作品のいいとこ取り、という感じがして楽しかった。信長の背後を脅かす最強の存在「武田信玄」がついに上洛を目指した。進軍中、浜松城で篭城作戦を採ろうとした家康を信玄の軍は素通りし、家康は仕方なく野戦せざるを得なくなった。「三方ヶ原の戦い」である。戦う前から敗色濃厚だったにも関わらず、体面やプライドを重視した家康は出陣し、惨敗する。この敗戦が家康にとって教訓となり、軍団の教育や後の戦闘作戦に大きな影響を与えるわけだけれども、このエピソードをドラマでは、「負けて全てがなくなったとしても、命があればやり直せる。だが名を失えば、取り戻すことはできない。だから負けると判っていても行く、これで徳川を笑うものは、一人もいなくなる。」と家康に言わせたように、表面的な損失を恐れるよりも、名声や信用を得ること、つまり後の政治的影響力や周囲との関係の重要性を選んだ家康の、政治家としての周到性を強調した演出になっていた。戦国時代にはまだ「武士道」という概念は確立されておらず、援軍わずかにして圧倒的に劣勢の「三方ヶ原」で、例えば家康軍が戦闘を放棄したとしても、大して非難は受けなかったはずだ。それなのに家康は「実」よりも「名」を重要視し、多くの犠牲と莫大な損害を出した。「実」とはいわずもがな戦力や金のことであり、「名」はプライドや信用のことだ。このエピソードでNHKが伝えたかったことは、最終的に家康は天下を手中にしたが、それは「名」を重んじてきた立ち振る舞いと、その裏側にある、例えば「人心掌握」といったような政治のための周到なアプローチが背景にあったからであり、最終的に家康は政治家として成功したが、それは「実」より「名」をとったから、つまりプライドや信用を大切にしていると、いつかいいことがあるよ、という教訓だったのではないだろうか。昭和48年といえば、ちょうど日本は高度経済成長期が終わりを告げ、オイルショックにより激しいインフレに襲われ、消費者は買いだめ、企業は売り惜しんだ、そんな時代だ。なりふりかまわず「実」利益ばかりを追っていた当時の社会へのアンチテーゼの意味も込められていたかもしれないが「金よりもプライドの方が大切だという考え方もある」というNHKのメッセージは、大衆にはあまり伝わらなかったらしい。歴史小説を読んだり大河ドラマを見たりしながら、よく今と、その風習や文化、価値観などを較べてみたりすることがある。ふと、現代でプライドや信用といった「名」にあたるものが「実」より軽んじられているのは、必要ないからなのではないか、と思うことがある。確かに、プライドが無くても仕事にありつけるし、プライドを持ってみなぎってるような奴をなかなか見かけないし、ツタヤのバイトは何をもってプライドを維持しているのか想像もつかない。信用が無くても集団の中にいられるし、金もアパートも借りられる。性格が悪くても仕事さえこなしていればいいし、友人からの信用を失った子どもはひきこもっていればいい。成人式で大騒ぎする若者は、戦国時代の若武者が功名を立てたがるのとよく似ている。金も知識も技術も言葉も持たないから若者は、武功で名を挙げるしかない。個人としての信念が確立されていないから、徒党を組んで群れたがり、群れの中でも功名を争った。壇上で派手なパフォーマンスを繰り広げて名声を高めたい心理は戦国のそれと似ていなくもないが、一つだけ違う点は、成人式には、リスクが全く無いということだ。戦国では、若かろうが古かろうが、常に命のやり取りの中にいた。派手なパフォーマンスをすれば確かに名声は上がるかもしれないが、派手であるということは同時に、標的にもなりやすく、つまり非常にリスキーな行為でもあった。今と昔で若者の構造が変わらなくても、賭けているものが全く違う。プライドもなく、信用とは無縁の社会で育った子どもが大人になり、そういった大人を見て育った子どもにプライドが備わっているはずもなく、大人を信用するはずもなく、大人を軽蔑してるから、壇上に上り「抵抗」してみせたりする。仲間は「連帯」を維持するために、誰かのバカ騒ぎを見て大喜びする。そんな子どもたちがいつか、軽蔑していた大人たちと同等の道を歩むのだということを、まだこの時、気付いていない。カタチは変わっても、人の歩みは繰り返すのだということを、歴史をひも解くことで、気付くようになるかもしれません。その時歴史は動いた、今日はこのへんで。
2004.01.22
コメント(1)
-
T3
ときに最近見た「ターミネーター3」の感想です。これは破滅しコンピューターに支配された未来をなんとか変えたい人間側と、それを阻止しようとするコンピューターが、現代にロボットをタイムスリップさせ、未来の救世主をめぐって攻防するお話で、コンピュータ側はことごとく失敗していて救世主はなかなか死なず、だから3まで続いているわけですが、コンピュータ側の強いロボットがことごとく失敗し、つまり救世主(現代ではダメ人間)が勝ち進んでいくにもかかわらず、最終的には運命は変わらないよ、という教訓も含まれている、とそんなあらすじです。しかし、タイムスリップで過去へ行って、過去をいじくりまわして未来が変わるかもしれない、というのは錯覚です。というか破綻してます。未来から過去にロボットがやってきた、という実績は、未来の時点ですでに残っているわけで、過去の積み重ねで未来があるわけですから、今回のT-Xという女のロボットが負けた、ということは未来の人たちはみんな知ってるはずなんです。今貧乏だから過去の自分に競馬をあてさせて、大金持ちの未来を過去から切り開こうとしたところで、今貧乏だということは、タイムスリップ先の過去で失敗してるから未来でも貧乏なわけで、もし過去の競馬に成功し未来が変わったと仮定した場合、「貧乏だから過去に行って一儲けしたい」という意思つまり、タイムスリップする動機も同時に失われるわけであり、競馬で成功することと、この貧乏男がタイムスリップする、ということは絶対に繋がりません。なので貧乏男が競馬しようと過去を操作しても、貧乏男は貧乏のまま変わらないのです。じゃあなぜ負けるロボット、負けると判っているロボットをわざわざ過去へ送り出すの?といいたくなります。それと過去の実績で未来に起こる出来事を確定させられることがあっても、未来からは過去を変えられないわけです。なぜなら、過去に何台ロボットが送られ、どういう負け方をしたのか、ということが確定されて未来まで来ているわけで、未来側は、どうなるか結果がわかっているのに、送らなければならないのです。これは相当のストレスかもしれません。現状を変えるために過去を操作する意思は、それが操作された結果としての現状である限り、達成されることがありません。タイムスリップで運命は変わらないのです。おっと本編のような結論に達してしまいました。おあとがよろしいようで。ではまた来週。
2004.01.15
コメント(1)
-
循環
映画を観た感想でも書いてみようと思う。本当はカラコのところの週刊中村不思議で書こうと思ったのだけれども、ツタヤのことを書くうちに話がそれてしまい、それが意外に長くなり、結局力尽きたのだった。感想は来週とか再来週、などと言ってはみたものの、2週間も前に観た映画の内容なんて、感想を書けるほど鮮明に憶えているはずはないから、今ちょっと仕事の手が空いたので書いてみようかという気になった。しかし本当は、たまらなく映画の感想を発表したい、という気持ちではなく、どちらかというとこのHPも更新するのが目的の作業であるといえる。「辞める」って言った割にはちょくちょく更新してんじゃーん、という向きもあろうが、例えば今でも日記リンクしていただいている他の方のHPの、「おすすめ新着」の欄のタイトルがいつまでも更新されない、という状態を見るにつけ、たまにはアゲなきゃいけないかもしれない、これは、仮に自分のところが更新されてなくて廃れたように見えるのはかまわないが、自分の名前と日記のタイトルが他人のHPを一部でも装飾していることで、そのHPの賑わいぶりの要因作りにわずかながらでも加担しているかもしれず、これらのことから自分のせいで、他人のHPが「廃れた印象」を与えるほうに機能してしまう恐れがあり、これは本意ではない、というロジックが成り立ち、判断したことによるものなので大目にみてください。映画の感想を書くとか言っておきながら全然書き出せない体質をまるで自嘲するかのような冒頭の長さになってしまったけれども、楽天日記のシステムについてもう少し言わせていただけるならば、この「日記」と「掲示板」と「オススメ新着」からなるHP環境というのは、まず「1.日記を書く」、という作業それから「2.誰かの日記を読む」、そして「3.誰かの日記を読んだ感想を書く」、という3つの作業をこなすというこの3つの繰り返しで、書いたら書かれる、つまり指しつ指されつというセオリーに従うと、誰かの日記を読んだ感想を書くのは、楽天インサイドに限って言えば「4.書いた数だけのレスを期待する」、ことでもある。オレはどちらかというと書いたら書きっぱなしで、読んでもらえればいいやぐらいに思っていたが、やはり誰かのコメントが掲示板に書かれていて赤く光っていたりすると嬉しい。読んでもらっているかもしれないという実感と、たまに書いてもらえるコメントを見たときのその嬉しさを「5.モチベーション」としたときに、それは何のためかというと「1.日記を書く」というところに繋がり、1.~5.の要素が「循環」する構造に楽天はなっている。「おすすめ新着」は、新着日記のアラームという本来の機能以外に、この循環構造に組み込んだ、あるいは組み込まれたことを保証する契約書のような性質もあって、1.~5.の循環工程を完全に放棄することは、この楽天という空間で蓄積された関係への契約不履行かもしれない、というようなことを思わなくもない。つまり、リバース自身の隆盛や、作品としての完成度にほとんど興味がなくなった今、何を原動力として日記を書いているかというとそれは、各所のおすすめ新着に散らばった10個のタイトル、中村不思議を示す文字列を赤く点灯させるため、ということに尽きる。日記リンクしていただいている人のHPを見るたびに、オレの名前が最下段になっていて、それはオレ自身が何もしないで停滞していることの暗示であるという解釈の仕方も出来る。実際そんなバカげた話はあるはずもなくて、ちゃんとオレの日常は循環しているのだけれども、停滞した日記リンク欄だけを見ると停滞しているように見える。実際停滞してしていなくとも、「停滞しているように見える」というのはこれは事実で、新着マークを赤く点灯させるということは、停滞しているように見えるところに風を送る、という意味も含まれている。とかなんかとか言っているうちに、映画の感想について書く気力を失ってしまった。これで1000字ぐらいだろうか。1日に集中して書けるのはこれぐらいの長さかもしれない。それでは、また来週。そういえば今般、カラコのいちびっとんか~い!の週替りメニューとして月曜の「週刊中村不思議」を受け持つことになりました。一つの楽天日記サイトを何人かで廻すのは結構面白い試みかもしれないので、そちらもどうぞよろしく。
2004.01.14
コメント(2)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「ムキムキに見える」飼い主さんの膝…
- (2025-11-20 14:00:11)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 今日は上昇!日経平均(11/20)
- (2025-11-20 14:36:45)
-