PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Comments
まだ登録されていません
カテゴリ: 観照

奈良市は年に幾度か訪れます。市内の寺々の探訪や寺宝展の鑑賞、奈良国立博物館での正倉院展や特別展覧会などで訪れることが主な目的です。ふとマンホールのふたを意識的にウォッチングし始めたのは数年前からです。奈良市で折に触れて撮っていたものをまとめて、ご紹介します。今回から「ふた見聞考」の新規継続となります。折々に綴っていきたいと思います。
冒頭の汚水ふたが奈良市でよくみかける汚水ふたです。
左側に 「鹿」 が居て、右方向に振り向いています。その目線の先、中央部には 「市章」 が刻されています。
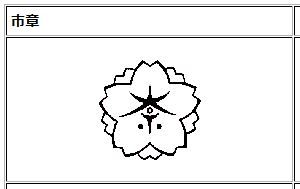
画像の市章が小さいので、 奈良市のホームページから「市章」を引用します。
あをによし寧楽 (なら) の京師 (みやこ) は咲く花のにほふがごとく今さかりなり
「寧楽(奈良)」の枕詞が「あをによし」 と学校で習った記憶があります。奈良の都を褒め称える言葉として使われるようになったのでしょう。
この歌は、『万葉集』の巻三に載っています 。改めて手許の本を繙くと、 「太宰少貳小野老朝臣の歌一首」という詞書が付されています 。この有名な歌は、太宰府に赴任していた 小野老朝臣 が、奈良の都を想って褒め称えた歌だったのですね。早く奈良の都に戻りたいなあという気持もあったのでしょうか・・・・・。今まで、どこで詠まれたかなんて、考えてもいませんでした。 (資料2)
「咲く花の」というのが、「桜の花」をさします 。現在の私たちは、「サクラ」と聞くと、「ソメイヨシノ」をまず思い浮かべるでしょう。しかし、「 江戸時代末期にソメイヨシノが発見されてサクラの主役となるまではサクラといえばこのヤマザクラをさしていた 」 (資料3) そうです。
 (2011.8.17)
(2011.8.17)
最初になぜ、この和歌を思い出したのか?
それは、この市章の説明文を読んだからです。この市章についてまず、「 天平の昔から奈良にゆかりの深い名花奈良八重桜(ナラヤエザクラ)をかたどり 」と記されていることからの連想でした。
* 「あをによし」は「青丹よし」 であり、「『青丹』は青色の顔料や絵の具に用いる青黒い土のこと。奈良地方がその代表的な産地であったために『あをによし』が『なら』の枕詞になったのであろう」 (資料4) とか。枕詞はやはり、地元と深い係わりがあるのですね。
*『万葉集』の時代には、政治の中心地が奈良にあったので数多く詠まれたようですが、遷都し、平安時代以降になると、万葉歌と関わって詠まれる歌以外で「あをによし」を詠むことはなくなったといいます。 (資料4) 都が京に遷った影響なのでしょうか。
市章は花芯の部分に「奈」の字がデザイン化されています 「日・月・星の三光にかたどられて」 (資料1) いるのです。そして、それは「昔、三笠山で鶯に三光の鳴き声を習わせたという伝説にちなんだものです」 (資料1) とのこと。この伝説の由来を知りたくて、ネット検索で調べてみた範囲では不詳です。そのルーツを辿れませんでした。
逆に、 「市徽章ノ件」という明36年5月5日告示第22号 というのをみつけました。そこには小野老朝臣の歌そのものが万葉仮名表記で引用されていました。やはり!という感じです。 (資料5)
冒頭にふたをよく見ると、市章の桜の花びらの部分が緑色になっています。

同じデザインですが、少し違うバージョンを見つけました。 (2014.5.31)

また、同じ日に見つけたこんなのもあります。 (2014.5.31)
こちらは、ふたの表面が白色系の色が塗装されていたものが魔滅で地の色との斑になってきている感じのふたです。デザイン仕様は冒頭のふたと同じです。しかし、中央の市章の花びらが少し鋭い感じを受けます。
ナラノヤエザクラがふた全面にデザインされています。 鹿と桜で奈良のイメージへと連想が働きますね。
「イチイガシ」は、春日大社境内に幹周り3mを越える木が30本以上もの巨樹群があり、奈良市の天然記念物に指定されているそうです。 (資料1)
 (2014.5.31)
(2014.5.31)
奈良国立博物館から東大寺に向かうには、 「大仏殿」の交差点 で左折して北に向かうのですが、この交差点の南方向は、道路の西側に緑地部分を挟んでもう一つ道路が金属製の垣根沿いに平行しています。その道を進むと、
 この建物が見えます。 「重要文化財 旧奈良県物産陳列所」
で、現在は 「奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター」
となっています。
この建物が見えます。 「重要文化財 旧奈良県物産陳列所」
で、現在は 「奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター」
となっています。

この前に行く数分手前で見つけたのが、こちらの汚水ふたです。 (2013.10.29)

(2016.11.02)
このデザインのふたをいままでに見つけたのはこの辺りだけです。
この2つ、周囲の舗装の具合でちょっと違ってみえたのですが、同一ですね。
ごくシンプルな機能本位のデザインがおもしろい。
(2016.11.2)

こちらは 東大寺探訪の折に、三昧堂(四月堂)傍の坂道で見つけた汚水ふた です。 (2014.9.15)
東大寺の境内地ですので、私有地扱いになるのでしょうか。
また、2017年12月に訪れた 唐招提寺の境内の道路で 、

この汚水ふたを見ました。これも独自のデザインです。 (2017.12.4)
いずれもいわば標準品の利用なのでしょうか。デザインは機能本位のシンプルなものと感じます。

こんなふたを薬師寺傍の一般道路で目にしました 。中央に「奈」とあります。これも花びらのデザインで、その花弁の中の文字は「側水 開閉弁」と読めそうです。水道管を開閉するバルブがあり、水を遮断できる箇所なのでしょうね。
「市の花」の説明のところには、 伊勢大輔の詠んだ歌 が引用されています。
いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな
この歌、 『小倉百人一首』の第61首 です。伊勢大輔が中宮彰子のもとに出仕して間にない頃のエピソードとして有名な歌だそうです。
ある日、奈良の僧都から中宮の許に八重桜が献上されてきたのです。その桜を受け取る役目を、先輩格の紫式部が出仕して日の浅い伊勢大輔にゆずったとか。式部はどんな意図があったのでしょう。ニューフェイスの働きの場を与えるためにゆずったのか、先輩の新人試しの心があったのか・・・・。すると、中宮彰子の父である藤原道長が、献上された桜を受け取るときに、歌を詠むように指示したと言います。その試練の場で詠んだのこの歌だそうです。若き才媛が晴れやかにカミングアウトするきっかけになったのです。
「いにしえ」(一昔前の過去/奈良)と「今日」(現在/京)、「八重ざくら」と「九重」(宮中)という照応・対比が巧みに織り込まれているようです。即興で詠んだのでしょうから、周囲の人々は驚嘆したことでしょう。
『応永抄』では、この伊勢大輔の当意即妙を「天生の道と平生のたしなみとのいたす所也」と評しているとか。この和歌は『後拾遺集』が初出だといいます。 (資料6)
「おそらく固唾をのんで見守っていたであろう彰子は、彼女の歌に感激し、思わず返歌を詠んだ。
九重に にほふを見れば 桜狩 重ねてきたる 春かとぞ思ふ
(宮中に桜が咲き匂って、お花見のよう。春が二回来たみたい)
新参女房の大健闘を、心からうれしく思ったのだ」 (資料7) 。
中宮彰子は、優秀なスタッフが加わってくれたことを大いによろこんだのでしょう。即興で返歌をした彰子自身も才女だったということでしょう。その返歌を聞き、伊勢大輔はこの人のために・・・という思いを抱いたのではないでしょうか。
なお、 八重桜は他の桜より遅咲きの品種で、京都では珍しい品種だったそうです。 (資料6) 。そのタイムラグが「重ねてきたる春かとぞ思ふ」につながるのでしょうね。
百人一首では、一つ前の第60首が和泉式部の一人娘である小式部内侍の歌で、彼女もまた中宮彰子に仕えた人。一方、次の第62首は清少納言の歌です。こちらは中宮定子に仕えた人であるのはご承知のとおりです。この辺りの歌の順番もおもしろいですね。
桜の序でに、奈良県の花見・桜名所はあるサイトには24ヵ所がリストアップされています。その中で、 奈良市としての桜の名所 は次の場所が列挙されています。
奈良公園、月ヶ瀬湖畔、平城宮跡資料館、帯解寺、柳生芳徳禅寺周辺 です。

(2016.11.2)
最後に、奈良の鹿は、 2017年7月16日現在、奈良公園生息数と鹿苑保護数の合計で1,498頭 。分類上では 和名が「ニホンジカ」で、 「 偶蹄目シカ科シカ属ニホンジカ亜種 」だとか。 あくまでも野生動物 であり、 天然記念物に指定されている そうです。
その食性は「奈良公園には広大なシバ地があり、シカはシバに強く依存している。その他ススキやイネ科植物などを食べて生活している。 鹿せんべいはシカにとってはおやつ です。 シカが食べない植物もあります。」と説明されています。 (資料9)

(2011.8.17)
ご一読ありがとうございます。
参照資料
1) 市の概要 :「奈良市」
2) 『新訂 新訓 万葉集 上巻』 佐佐木信綱編 岩波文庫
3) 『萬葉植物事典 普及版』 大貫 茂[著] 馬場 篤[植物監修] クレオ p50
4) 『歌枕歌ことば辞典 増補版』 片桐洋一著 笠間書院
5) 市徽章ノ件 明治36年5月5日告示第22号 :「奈良市」
6) 『百人一首』 全訳注 有吉 保著 講談社学術文庫
7) 『こんなに面白かった「百人一首」』 吉海直人著 PHP文庫
8) 2017年度版 全国お花見1000景 奈良県の花見・桜名所 :「Walker+」
9) 「奈良のシカ」について :「奈良の鹿愛護会」(ホームページ)
補遺
平城旧跡ルート :「奈良の歩き方新提案 歩く・なら」
ひたむきな愛をささやく平城京跡・佐保川・ならまち
小野 老 :ウィキペディア
ウグイスの鳴き声(囀り)。The nightingale sing. :YouTube
経読み鳥【きょうよみどり】とは、どんな鳥? :「図鑑.netモバイルブログ」
専徳寺の庭でもウグイスのさえずりが聞こえ始めました。 :「専徳寺」
奈良公園のシカの気になる10の疑問 Q&A :「NAVERまとめ」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
マンホールのふた見聞考 ウォッチング掲載記事一覧
こちらもご覧いただけるとうれしいです。奈良市域関連でまとめたものです。
観照 奈良にて -1 奈良国立博物館の庭
4回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 [再録] 奈良・氷室神社
観照&探訪 正倉院展への途次と鑑賞、そして東大寺境内へ
スポット探訪 [再録] 奈良 東大寺南大門
探訪 東大寺境内散策 -1 戒壇院(戒壇堂・千手堂)
3回のシリーズで戒壇院・指図堂・勧進所のあたりをご紹介しています。
探訪 [再録] 東大寺境内 -1 ひっそりとした境内の路沿いに
3回シリーズで、鐘楼・行基堂・俊乗堂・大仏殿・春日野あたりのご紹介です。
探訪 東大寺境内再訪 -1 手向山八幡宮・法華堂(三月堂)
2回のシリーズで、三月堂・二月堂・龍王の瀧・閼伽井屋・三昧堂あたりをご紹介しています。
スポット探訪[再録] 奈良・正倉院
スポット探訪 [再録] 奈良 興福寺境内を通り奈良国立博物館に
スポット探訪 [再録] 奈良 興福寺国宝特別公開2013 南円堂・北円堂
観照 & 探訪 [再録] 奈良 雲井坂・轟橋碑・猿沢池・采女神社ほかと奈良県立美術館
スポット探訪 [再録] 春日大社境内を巡る -1 大仏殿交差点から境内へ(憶良の歌碑、石灯籠さまざま、萬葉植物園、壺神神社、車舎)
4回シリーズで、遷宮前の春日大社境内をご紹介しています。
スポット探訪 春日大社を巡る[再訪] -1 春日東西両塔跡・参道・春日若宮神社
2回シリーズで、春日若宮神社の周辺を再訪した折のご紹介です。
探訪 [再録] 奈良・白毫寺から新薬師寺へ -1 吉備塚古墳・宝蔵院覚禅坊胤栄の墓・石仏
4回シリーズでご紹介しています。
探訪 奈良・大安寺とその周辺を巡る -1 野神古墳
6回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 奈良 唐招提寺細見 -1 南大門・記念碑・歌碑句碑・金堂
5回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 奈良 薬師寺細見 -1 玄奘三蔵院伽藍と北側境内域
3回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 奈良 薬師寺から唐招提寺への道すがらに

奈良市は年に幾度か訪れます。市内の寺々の探訪や寺宝展の鑑賞、奈良国立博物館での正倉院展や特別展覧会などで訪れることが主な目的です。ふとマンホールのふたを意識的にウォッチングし始めたのは数年前からです。奈良市で折に触れて撮っていたものをまとめて、ご紹介します。今回から「ふた見聞考」の新規継続となります。折々に綴っていきたいと思います。
冒頭の汚水ふたが奈良市でよくみかける汚水ふたです。
左側に 「鹿」 が居て、右方向に振り向いています。その目線の先、中央部には 「市章」 が刻されています。
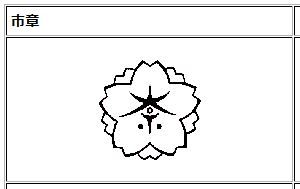
画像の市章が小さいので、 奈良市のホームページから「市章」を引用します。
あをによし寧楽 (なら) の京師 (みやこ) は咲く花のにほふがごとく今さかりなり
「寧楽(奈良)」の枕詞が「あをによし」 と学校で習った記憶があります。奈良の都を褒め称える言葉として使われるようになったのでしょう。
この歌は、『万葉集』の巻三に載っています 。改めて手許の本を繙くと、 「太宰少貳小野老朝臣の歌一首」という詞書が付されています 。この有名な歌は、太宰府に赴任していた 小野老朝臣 が、奈良の都を想って褒め称えた歌だったのですね。早く奈良の都に戻りたいなあという気持もあったのでしょうか・・・・・。今まで、どこで詠まれたかなんて、考えてもいませんでした。 (資料2)
「咲く花の」というのが、「桜の花」をさします 。現在の私たちは、「サクラ」と聞くと、「ソメイヨシノ」をまず思い浮かべるでしょう。しかし、「 江戸時代末期にソメイヨシノが発見されてサクラの主役となるまではサクラといえばこのヤマザクラをさしていた 」 (資料3) そうです。
 (2011.8.17)
(2011.8.17)最初になぜ、この和歌を思い出したのか?
それは、この市章の説明文を読んだからです。この市章についてまず、「 天平の昔から奈良にゆかりの深い名花奈良八重桜(ナラヤエザクラ)をかたどり 」と記されていることからの連想でした。
* 「あをによし」は「青丹よし」 であり、「『青丹』は青色の顔料や絵の具に用いる青黒い土のこと。奈良地方がその代表的な産地であったために『あをによし』が『なら』の枕詞になったのであろう」 (資料4) とか。枕詞はやはり、地元と深い係わりがあるのですね。
*『万葉集』の時代には、政治の中心地が奈良にあったので数多く詠まれたようですが、遷都し、平安時代以降になると、万葉歌と関わって詠まれる歌以外で「あをによし」を詠むことはなくなったといいます。 (資料4) 都が京に遷った影響なのでしょうか。
市章は花芯の部分に「奈」の字がデザイン化されています 「日・月・星の三光にかたどられて」 (資料1) いるのです。そして、それは「昔、三笠山で鶯に三光の鳴き声を習わせたという伝説にちなんだものです」 (資料1) とのこと。この伝説の由来を知りたくて、ネット検索で調べてみた範囲では不詳です。そのルーツを辿れませんでした。
逆に、 「市徽章ノ件」という明36年5月5日告示第22号 というのをみつけました。そこには小野老朝臣の歌そのものが万葉仮名表記で引用されていました。やはり!という感じです。 (資料5)
冒頭にふたをよく見ると、市章の桜の花びらの部分が緑色になっています。

同じデザインですが、少し違うバージョンを見つけました。 (2014.5.31)

また、同じ日に見つけたこんなのもあります。 (2014.5.31)
こちらは、ふたの表面が白色系の色が塗装されていたものが魔滅で地の色との斑になってきている感じのふたです。デザイン仕様は冒頭のふたと同じです。しかし、中央の市章の花びらが少し鋭い感じを受けます。
ナラノヤエザクラがふた全面にデザインされています。 鹿と桜で奈良のイメージへと連想が働きますね。
「イチイガシ」は、春日大社境内に幹周り3mを越える木が30本以上もの巨樹群があり、奈良市の天然記念物に指定されているそうです。 (資料1)
 (2014.5.31)
(2014.5.31)奈良国立博物館から東大寺に向かうには、 「大仏殿」の交差点 で左折して北に向かうのですが、この交差点の南方向は、道路の西側に緑地部分を挟んでもう一つ道路が金属製の垣根沿いに平行しています。その道を進むと、
 この建物が見えます。 「重要文化財 旧奈良県物産陳列所」
で、現在は 「奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター」
となっています。
この建物が見えます。 「重要文化財 旧奈良県物産陳列所」
で、現在は 「奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター」
となっています。
この前に行く数分手前で見つけたのが、こちらの汚水ふたです。 (2013.10.29)

(2016.11.02)
このデザインのふたをいままでに見つけたのはこの辺りだけです。
この2つ、周囲の舗装の具合でちょっと違ってみえたのですが、同一ですね。
ごくシンプルな機能本位のデザインがおもしろい。
(2016.11.2)


こちらは 東大寺探訪の折に、三昧堂(四月堂)傍の坂道で見つけた汚水ふた です。 (2014.9.15)
東大寺の境内地ですので、私有地扱いになるのでしょうか。
また、2017年12月に訪れた 唐招提寺の境内の道路で 、

この汚水ふたを見ました。これも独自のデザインです。 (2017.12.4)
いずれもいわば標準品の利用なのでしょうか。デザインは機能本位のシンプルなものと感じます。

こんなふたを薬師寺傍の一般道路で目にしました 。中央に「奈」とあります。これも花びらのデザインで、その花弁の中の文字は「側水 開閉弁」と読めそうです。水道管を開閉するバルブがあり、水を遮断できる箇所なのでしょうね。
「市の花」の説明のところには、 伊勢大輔の詠んだ歌 が引用されています。
いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな
この歌、 『小倉百人一首』の第61首 です。伊勢大輔が中宮彰子のもとに出仕して間にない頃のエピソードとして有名な歌だそうです。
ある日、奈良の僧都から中宮の許に八重桜が献上されてきたのです。その桜を受け取る役目を、先輩格の紫式部が出仕して日の浅い伊勢大輔にゆずったとか。式部はどんな意図があったのでしょう。ニューフェイスの働きの場を与えるためにゆずったのか、先輩の新人試しの心があったのか・・・・。すると、中宮彰子の父である藤原道長が、献上された桜を受け取るときに、歌を詠むように指示したと言います。その試練の場で詠んだのこの歌だそうです。若き才媛が晴れやかにカミングアウトするきっかけになったのです。
「いにしえ」(一昔前の過去/奈良)と「今日」(現在/京)、「八重ざくら」と「九重」(宮中)という照応・対比が巧みに織り込まれているようです。即興で詠んだのでしょうから、周囲の人々は驚嘆したことでしょう。
『応永抄』では、この伊勢大輔の当意即妙を「天生の道と平生のたしなみとのいたす所也」と評しているとか。この和歌は『後拾遺集』が初出だといいます。 (資料6)
「おそらく固唾をのんで見守っていたであろう彰子は、彼女の歌に感激し、思わず返歌を詠んだ。
九重に にほふを見れば 桜狩 重ねてきたる 春かとぞ思ふ
(宮中に桜が咲き匂って、お花見のよう。春が二回来たみたい)
新参女房の大健闘を、心からうれしく思ったのだ」 (資料7) 。
中宮彰子は、優秀なスタッフが加わってくれたことを大いによろこんだのでしょう。即興で返歌をした彰子自身も才女だったということでしょう。その返歌を聞き、伊勢大輔はこの人のために・・・という思いを抱いたのではないでしょうか。
なお、 八重桜は他の桜より遅咲きの品種で、京都では珍しい品種だったそうです。 (資料6) 。そのタイムラグが「重ねてきたる春かとぞ思ふ」につながるのでしょうね。
百人一首では、一つ前の第60首が和泉式部の一人娘である小式部内侍の歌で、彼女もまた中宮彰子に仕えた人。一方、次の第62首は清少納言の歌です。こちらは中宮定子に仕えた人であるのはご承知のとおりです。この辺りの歌の順番もおもしろいですね。
桜の序でに、奈良県の花見・桜名所はあるサイトには24ヵ所がリストアップされています。その中で、 奈良市としての桜の名所 は次の場所が列挙されています。
奈良公園、月ヶ瀬湖畔、平城宮跡資料館、帯解寺、柳生芳徳禅寺周辺 です。

(2016.11.2)
最後に、奈良の鹿は、 2017年7月16日現在、奈良公園生息数と鹿苑保護数の合計で1,498頭 。分類上では 和名が「ニホンジカ」で、 「 偶蹄目シカ科シカ属ニホンジカ亜種 」だとか。 あくまでも野生動物 であり、 天然記念物に指定されている そうです。
その食性は「奈良公園には広大なシバ地があり、シカはシバに強く依存している。その他ススキやイネ科植物などを食べて生活している。 鹿せんべいはシカにとってはおやつ です。 シカが食べない植物もあります。」と説明されています。 (資料9)

(2011.8.17)
ご一読ありがとうございます。
参照資料
1) 市の概要 :「奈良市」
2) 『新訂 新訓 万葉集 上巻』 佐佐木信綱編 岩波文庫
3) 『萬葉植物事典 普及版』 大貫 茂[著] 馬場 篤[植物監修] クレオ p50
4) 『歌枕歌ことば辞典 増補版』 片桐洋一著 笠間書院
5) 市徽章ノ件 明治36年5月5日告示第22号 :「奈良市」
6) 『百人一首』 全訳注 有吉 保著 講談社学術文庫
7) 『こんなに面白かった「百人一首」』 吉海直人著 PHP文庫
8) 2017年度版 全国お花見1000景 奈良県の花見・桜名所 :「Walker+」
9) 「奈良のシカ」について :「奈良の鹿愛護会」(ホームページ)
補遺
平城旧跡ルート :「奈良の歩き方新提案 歩く・なら」
ひたむきな愛をささやく平城京跡・佐保川・ならまち
小野 老 :ウィキペディア
ウグイスの鳴き声(囀り)。The nightingale sing. :YouTube
経読み鳥【きょうよみどり】とは、どんな鳥? :「図鑑.netモバイルブログ」
専徳寺の庭でもウグイスのさえずりが聞こえ始めました。 :「専徳寺」
奈良公園のシカの気になる10の疑問 Q&A :「NAVERまとめ」
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
マンホールのふた見聞考 ウォッチング掲載記事一覧
こちらもご覧いただけるとうれしいです。奈良市域関連でまとめたものです。
観照 奈良にて -1 奈良国立博物館の庭
4回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 [再録] 奈良・氷室神社
観照&探訪 正倉院展への途次と鑑賞、そして東大寺境内へ
スポット探訪 [再録] 奈良 東大寺南大門
探訪 東大寺境内散策 -1 戒壇院(戒壇堂・千手堂)
3回のシリーズで戒壇院・指図堂・勧進所のあたりをご紹介しています。
探訪 [再録] 東大寺境内 -1 ひっそりとした境内の路沿いに
3回シリーズで、鐘楼・行基堂・俊乗堂・大仏殿・春日野あたりのご紹介です。
探訪 東大寺境内再訪 -1 手向山八幡宮・法華堂(三月堂)
2回のシリーズで、三月堂・二月堂・龍王の瀧・閼伽井屋・三昧堂あたりをご紹介しています。
スポット探訪[再録] 奈良・正倉院
スポット探訪 [再録] 奈良 興福寺境内を通り奈良国立博物館に
スポット探訪 [再録] 奈良 興福寺国宝特別公開2013 南円堂・北円堂
観照 & 探訪 [再録] 奈良 雲井坂・轟橋碑・猿沢池・采女神社ほかと奈良県立美術館
スポット探訪 [再録] 春日大社境内を巡る -1 大仏殿交差点から境内へ(憶良の歌碑、石灯籠さまざま、萬葉植物園、壺神神社、車舎)
4回シリーズで、遷宮前の春日大社境内をご紹介しています。
スポット探訪 春日大社を巡る[再訪] -1 春日東西両塔跡・参道・春日若宮神社
2回シリーズで、春日若宮神社の周辺を再訪した折のご紹介です。
探訪 [再録] 奈良・白毫寺から新薬師寺へ -1 吉備塚古墳・宝蔵院覚禅坊胤栄の墓・石仏
4回シリーズでご紹介しています。
探訪 奈良・大安寺とその周辺を巡る -1 野神古墳
6回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 奈良 唐招提寺細見 -1 南大門・記念碑・歌碑句碑・金堂
5回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 奈良 薬師寺細見 -1 玄奘三蔵院伽藍と北側境内域
3回のシリーズでご紹介しています。
スポット探訪 奈良 薬師寺から唐招提寺への道すがらに
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[観照] カテゴリの最新記事
-
観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.02
-
観照 諸物細見 -25 レトロな建物(伝道… 2024.06.01
-
観照 諸物細見 -25 レトロな銅像(二宮金… 2024.05.31 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










