2024年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
『アンチ・ヒーロー』
時間の都合上、リアルタイムでは観られないことが多く、後で録画したものを観たりするのですが、今、日曜夜に放送している『アンチ・ヒーロー』、面白いですなあ。 そもそも私は『鈴木先生』以来、長谷川博己のファンなんですが、彼が主演となると、どうしても見逃せない。しかも、このドラマの脚本は『VIVANT』のスタッフだというではないですか。そんなの、どうしたって面白くなるでしょう。 で、今日も第3話を録画で観たのですが、実に面白い。進行中のドラマも面白いし、伏線もあちこちにあって、それらが一体どういう具合に収斂していくのかも興味津々。獄中の人となっている緒方直人は、どういう人物なのか。博己がしばしば訪れる施設の女の子と博己の関係は? 博己はなぜ検事から弁護士に転身したのか? などなど、謎が一杯。 当分、このドラマで楽しめそうです。 さてさてGWの後半戦ですが、私は明後日のNHKラジオ収録に備えて明日、実家に戻ります。ラジオ収録は2度目とはいえ、前回は電話を使った収録。今回のようにスタジオ収録となるとまた話は別。天下のNHKさんのスタジオに足を踏み入れるというのだけでも相当ワクワク。 ということで、GW後半戦は、例年にも増してエキサイティングなものとなりそう。また収録の経験については後日、アップしますので、どうぞお楽しみに!
April 30, 2024
コメント(0)
-
昭和の日
今日は天皇誕生日・・・と思うのは我々世代で、今は昭和の日。そんなこともあって、我が家がとっているY新聞の投稿欄では、「昭和」をテーマにした思い出が並んでおりました。 で、61歳の投稿者は、土管の思い出を語っていた。その昔、空き地の草っぱらに土管が山積みしてあって、自分たちにとってその土管は秘密基地であり、友達と一緒にマンガを読んだり、語り合った大切な場所であったと。そして59歳の投稿者は、「フラッシャー(=方向指示器)つき自転車」を買ってもらった時の嬉しさを語っておりました。 いや~、分かる、分かる。同世代のワタクシもまったく同じ! 一方、75歳の投稿者は、1960年安保闘争の時、デモ隊の真似をして訳も分からないのに「アンポ反対!」とか学校で騒いでいたら先生に怒られた話、また78歳の投稿者は、新宿ガード下で傷痍軍人を見た話し、73歳の投稿者は、学校にテレビがやってきてみんなで観た話を、それぞれ書いておられました。 だけどこの70歳代の方たちの投稿は、私からするとちょっと実感がない。まあ傷痍軍人は、子供の頃にチラッと見たことがあるけれども。 だから、同じ昭和の思い出と言っても、60代と70代ではやっぱり見ていた風景がちょっと違うんですな。当たり前のことだけれども。10~15歳の年齢差で、これだけ違いが出る。 やっぱり昭和後期って、社会がドラスティックに変化していった時代だったんでしょうな。 ま、だから何?と言われたら別に言い返すこともないのだけど、昭和の日の新聞を開いて、そんなことをちょっと思った次第。
April 29, 2024
コメント(0)
-
GWの思い出
世の中はゴールデン・ウィーク入りしたわけですな。 今から四十数年前、私が中学生くらいだった頃は、ゴールデン・ウィークといっても天皇誕生日と日曜日、それに憲法記念日と子供の日がお休みなくらいで、今のように人によっては十連休、みたいなのはなかったですけど、まあ、季節もいい頃ですし、当時としても楽しみではありましたね。 当時は、だから別にゴールデン・ウィークだからと言って特別なことをするとか、旅行に行くとか、そういうのはなかったけれど、なんだかんだ小規模なイベントみたいなものがそれぞれの町で催されることはあった。 今でもよく覚えているのは、私が中学生くらいの時だったか、ゴールデンウィークに地元のスーパーの入口付近の一角で、古本市が開かれたこと。たまたま家族で散歩に出たら、そういうのをやっていることに気づき、立ち寄った。で、そこで私が買ったのが代議士の鶴見祐輔が書いた『ナポレオン』(潮出版)という本。何でこの本だったのか、覚えていないのですが、『君たちはどう生きるか』の中で、登場人物の一人、水谷かつ子さんがナポレオンのファンだったというくだりがあり、それでナポレオンにちょっとだけ興味を持っていたからかもしれません。 そう、それで古本市に立ち寄ったその足で家族で駅前のレストランで夕食を食べて、何となく楽しく過ごした、という記憶がある。 今から思うと、それだけのことじゃないかということなんですけど、そういう何気ない初夏の休日の一日のことがなぜかいつまでも記憶に残っているというね。 それからもう少し経って、私が大学生くらいになった頃、マンションから一戸建てに引っ越して、猫の額のような庭ができた。その頃、やはりゴールデンウィークに、駅前広場で植木市が開かれる、なんてことがありまして。で、のんびり家族でそういう植木市に行って、ライラックの苗木を買って、それを庭に植えた、なんてこともありました。ライラックの薄紫色の花がとてもきれいで、毎年初夏の楽しみになったことでした。そのライラックは、その後数年して枯れてしまったのですけどね。 ゴールデンウィークというと、そういうことを、思い出します。 結局、懐かしく思い出すのって、家族全体が若かった時のことなんですよね。両親もまだ若くて、自分たち子供も中学生だったり大学生だったりっていう。 若い家族か・・・。 自分にとっては、そういう時期はもう、遥か過去のことになってしまったけれど、世の中には、今、初夏の休日を楽しんでいる若い家族がたくさんあるんだろうな。そしてずっと後になってそのことを思い出すのでしょう。 他人事ながら、日本中の若い家族に「今を楽しめ」と言いたいです。
April 28, 2024
コメント(0)
-

荒井良二著『ぼくの絵本じゃあにぃ』を読む
昨日展覧会に行ってすっかりファンになった荒井良二さんのご著書、『ぼくの絵本じゃあにぃ』を読了したので、心覚えをつけておきます。 この本、荒井さんの幼少期の頃のこと、イラストレーターになられた頃のこと、絵本の魅力に目覚め、絵本制作に取り組むようになった頃のこと、あたりから語り始め、個々の作品の制作経緯やその背後にある思い、影響を受けた他のアーティストのこと、絵本以外の仕事にも携われるようになってからのこと、山形のご出身であったことから東北の大震災の後、東北の人々の心の復興になんとか力を貸すことができればと、様々な活動を行なったことなどが書かれております。まさに「絵本」というものを中心に語る荒井さんの人生の旅のお話。 そういう中から見えてくるのは、荒井良二さんという方のお人柄ですよ。何というか、ほんとにスッとした人。大げさなところがなく、等身大で、自然体。でもそうやってごく普通の人間として素直に素直に考えて行った結果、すごく深いヒューマニズムというか、人間的洞察に到達しちゃったみたいな。でもそういうことを得意気に語るのではなく、ごく当たり前のことのように、まるで昨日の晩何を食べたかを語るがごとくに語っていらっしゃる。そういうところに、私は非常に好感を抱きます。 実際、荒井さんの描く絵に、お人柄が出てますよね! あんな絵が描ける人が悪い人であるはずないもん。 さて、そんな感じで、私は荒井さんの絵本作家としての在り方を読んでいったわけですが、その中で、「これは、絵本創作に限らず、私のような研究者とか、本を書くタイプの人間にも通用するな」と思ったことが幾つかありまして。 たとえば、荒井さんが絵を描く時に、色々な場所で色々な恰好で描くという話とか。 一般にプロの作業場となると、使い慣れた道具が決められた場所に置いてあって、すぐにいつも通りの作業に取り掛かれるようになっているように想像するではないですか。で、実際にそういう風に仕事をされる方もいらっしゃるのでしょうけれど、荒井さんはそうではないと。 昨日はあそこで描いたけど、今日はここ、明日はまたどこか別な場所で・・・という風に、描く場所を変えるというのです。またある時は机に座って、ある時は床に寝そべって・・・という風に、描く姿勢も変えたりする。もちろん、そんな描き方は効率面から言えば非効率なんだけど、それでもそうやって描く。 それはね、結局、慣れを廃して、新しい発見を得るためなんですって。それはムダなことのようだけど、長い目で見ると、メリットがあると。 同様に、荒井さんはある時、コマ漫画を描くという仕事に携わったことがあったのですが、コマ割りをするというマンガの手法は、絵本を作る手法とは大分異なっている。でもそういう、通常の絵本制作とは異なるルール/制限の上で何かを創作してみると、そのことで新しい発見があったりする。コマ割りした一つ一つのコマをそれぞれ1ページに拡大すれば、それはそれで絵本のストーリーになるよな・・・というような発見があったりするわけですよ。 だから、面倒臭くても、慣れた手法に甘えるのではなく、しょっちゅう、別なルールを敢えて自分に課してみる。で、その制限の中で奮闘することで、何か突破口になるような発見があると。 で、荒井さん曰く、そういう突破口を沢山持っている人のことを「プロ」というのだ、と。その辺り、本文から引用してみましょう。 つまりぼくが、折れた色鉛筆の先で描いてみたらどうだろうとか、立って描いたら、あるいは床で描いたらどうかとか、自分に負荷をかけるようなことばかりしているのも、何か新しい発見がないかといつも探しまわっているからです。キャリアを積んだ分だけ、いいものが見つかる確率が上がっているだけで、ぼくだってアマチュアの人と結局は同じです。 というより、一度手になじんだやり方をずっと続けるプロの人もいますが、ぼくはむしろプロとはそういうのとは反対側にいる生き物ではないかとさえ思っています。 一般的にプロの描きとは絵を描くためのコツ、いわばうまく描くための近道を知っている人たちだと思われているかもしれませんが、とんでもない。そういう近道はありません。そんな魔法みたいなものは、どこにもない。どうやったらこれまでと違う描き方ができるか、これまでに描いたものを越えていくことができるか。プロとは、そのためのデータ、つまり、こう修正したらうまくいったとか、こういう場合は失敗したとかいう、自分なりのデータをたくさんもっている人のことではないでしょうか。(106-107) ね。これよこれ。てらいも何にもない、だけどものすごく深い洞察。荒井さんというのは、こういうものを持っている人なのよ。 あとね、これも一つ感心したのだけど、荒井さんの絵本って、ストーリーがあるようでないというか、物語的な起承転結があるわけではない。だから、ものすごく自由に、フリースタイルで、絵先行で絵本を制作しているのかと思いきや、実は絵本を作る前に詳細なマッピングをする、というんですね。 で、そのマッピングというのは、一つの紙に言葉で(絵ではなく)、この絵本に盛り込むべきコンセプトや、キーワードを書き込み、それらコンセプト/言葉を線で縦横につないだりして、相互連関を明示したりすることなんですな。つまり、一つの絵本を作るのに、設計図をかなり詳細にわたって作ると。 うーん、これはね、論文を書く時のワタクシとまったく同じ。私も一枚の紙に、この論文で扱うべき事柄や、論理の運び方、キーワードなどを書き出し、それを終始眺めながら論文を書いている。論文と絵本と、まったく別のもののようで、実は同じ制作過程を通っているんだ、というのは、私としては大きな発見でした。別業種の話って、なかなか聞けないので、その点、すごく面白かった。 それから、荒井さんは、子供を集めてワークショップを開くことが多いようなのですが、そういう経験から、「子供とは何か」ということに、非常に深い洞察を持っていらっしゃるのよ。それは、「子供は我らの希望だ」とか、「子供はみんな天才だ」とか、「子供の感性が羨ましい」とか、「我々大人は、子供時代のことを忘れてしまっている」とか、そういう通り一遍の認識では全然ないのね。 たとえば、子供は未来の希望だ! というような大人の勝手な思い込みから、子供たちに「未来のことを描いてごらん」などと指示しても、現実の子供は、未来の絵なんか描けないんですって。もちろん、過去のことも描けない。自分がもっと小さかった時のことなど、彼らには関心がない。子供ってのは現在だけを生きている非常にタフでシビアな存在であると。 なるほど! また小学校3年生あたりを境に、子供が大人の世界を模倣し出し、輝きを失っていくことを荒井さんはしょっちゅう目にする。でもそれを残念とも思わず、ただ、そういうものなんだ、という認識をされている。だから、小さい子供が、それこそ天才的な感性で、思ってもみないような作品を完成させても、「ちくしょー!」なんて思わないんですって。 ただ、そうやって子供が普通に大人になってしまうことを、止めることはできないにしても、アートによって揺さぶりをかけることはできる。 ルーティーンに収束してしまいがちな世界に、アートで揺さぶりをかけ、非日常的な活動をさせることで、「決まり切った大人」から少しはみ出させることはできる。 私が思うに、多分荒井さんという人は、絵本という形で、社会に揺さぶりをかけようとしてるのではないかと。だから荒井さんの絵本は、子供向けであると同時に、大人向けでもある。 とまあ、この本を読んでいて、色々なことを考えさせられました。読んで良かった本でしたね。 ということで、荒井良二さんの『ぼくの絵本じゃあにぃ』、教授の熱烈おすすめ!です。これこれ! ↓ぼくの絵本じゃあにぃ (NHK出版新書) [ 荒井良二 ]
April 27, 2024
コメント(0)
-

「new born 荒井良二」展を堪能!
今日は家内と一緒に、刈谷市美術館で現在開催中の「new born 荒井良二」展に行ってきました、これこれ! ↓荒井良二展公式HP 刈谷市美術館というのは、そんなに大きい美術館ではないけれど、時々、非常にいい美術展を開催してくれるところで、私は愛知県美術館や名古屋市美術館よりよほど高く評価しているところがあるのですけど、今回の荒井良二展もとても良かった。 私は寡聞にしてこれまで荒井良二さんという方のことをまったく存じあげていなかったのですが、私よりもちょい年上のアーティストで、絵本などを随分数多く手がけていらっしゃる。で、今回の美術展は、そんな荒井さんの絵本の原画はもとより、オブジェも含めて300点もの展示がしてある。見ごたえがあります。 で、その作風は、上のHPを見ていただいても分かる通り、色の爆発。そしてすごく楽しい! 見ているだけで元気になってくる。 しかもね、今回の美術展は、写真撮影可なのよ。だから、私もそうですが、見ている方々はそれぞれ、自分の気に入った絵をスマホでぱちぱち撮っていた。さながら、美術展の楽しさの一部をスマホに収めて持ち帰ったような気分。 で、美術展のお楽しみは、ショップで関連グッズを買って帰ることなんですが、今回は絵葉書とマグネット、そして荒井さんのご著書も買っちゃった。これこれ! ↓ぼくの絵本じゃあにぃ (NHK出版新書) [ 荒井良二 ] これ、読み始めてみたのですが、なかなか面白いです。これを読むと、荒井さんという人は、とても素直な人で、てらいがないというか、自然体の人。すぐに友達になれそうな人です。ご本人の写真を見ても、そう思います。 というわけで、今日は荒井さんの展覧会を見て、実に実にいい気分で帰路に就くことができたのでした。今日も、いい日だ!
April 26, 2024
コメント(2)
-
どっしりと立つ
健康のために続けている四股踏みですが、依然として続いております。 で、一日30回くらい踏む程度のものですが、それでもずっと続けていると、安定感が増して来る感じがある。 最初のうちは、ぐらぐらしちゃって、四股を踏むたびにドタドタしていましたが、最近はもうそんなことはないですもんね。この調子で続けていけば、体幹もしっかりしてくるかも。そうしたら武道の方にもいい影響があるかもしれません。体幹は、どんな武道、どんなスポーツでも必須ですからね。 ところで今日は道場の日だったのですが、久しぶりにA師範に稽古をつけてもらいました。 で、今日のポイントは、地面にしっかりと立つということ。 まあ、普段、我々はしっかり立つ、なんてことにはあまり気が向いてないわけですね。でも、八光流の場合、しっかり立つ、どっしりと立つ、ということが非常に重要なんです。 足から根が生えたように、地球の上にどーんと立ち、骨盤がしっかりと両足の上に載っていて、骨盤の上に背骨がしっかりとそびえていて、その上に重い頭がずっしりと乗っていて、全部が安定しているという状態で立つ。そういう姿勢は、やっぱり意識的に修行しないと身に付かない。 で、そういう状態で立っていても、相手に技をかけるとなった場合、やはり「相手を倒す」ことに気が向いてしまうと、それにつられてこちらの体のバランスも崩れてしまう。それじゃだめなわけ。 こちらはしっかりと立つ。その上で、相手ときちんと正対し、相手が崩れる時にはそれに対応して、ついて行ってあげる。そうやって相手と常に一体化するようにして初めて、峻厳な技が成り立つわけよ。 今日はそういう、武道の根本みたいなところを勉強させてもらいました。 その際、このところ続けている四股が、少しは効果あったのなら嬉しいのですけどね。 とにかく、武道は一日にしてならず。今日の気づきを大切にして、また次の稽古に活かしたいところでございます。
April 25, 2024
コメント(0)
-

今度は共同通信インタビュー!!
いやあ、拙著の勢いは止まりません! 今度は共同通信社からインタビュー依頼が来ました~! と言っても、これは編集者が答えるもので、私は直接は関係ないのですが、とにかく、日本中の地方新聞に記事が載るわけですから、特に地方での売り上げアップは確実。 それにしても、どういうことなんすかね? 毎回、面白くてタメになる本を書いているつもりではあるけど、今回の本だけやけに世間から持て囃されるのは一体どういうことなのか・・・。だったら他の本も買って読んでよ、という気にもなる。 まあ、とにかく売れているのはありがたい。いよいよ、夢の印税生活目前って感じですかね。早く「重版出来!」の四文字言葉を耳にしたいものです。アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ]
April 24, 2024
コメント(0)
-
映画『アイアン・クロー』を観た
映画『アイアン・クロー』を観てきました。ので、心覚えをつけておきましょう。以下、ネタバレ注意です。 「アイアン・クロー」といえば、私のような往年のプロレス・ファンには懐かしいフリッツ・フォン・エリックのこと。リンゴを握りつぶす握力で、相手のこめかみを握りつぶす荒業で知られた名レスラーでございます。もっとも、役柄としてはヒールだったので、実力はありながらNWAのヘビー級チャンピオンにはなれなかった。 で、NWAのチャンピオンになれなかった、という無念さが、彼をして息子たちを鍛え上げ、自分の跡を継がせて、何としても一家からチャンピオンを出したいという執念に結び付くわけですよ。で、最初は次男(長男は若くして亡くなったので、実質彼が長男的存在なのですが)のケビンと三男のデビッドがプロレスラーとなり、次に陸上選手でモスクワ・オリンピックを目指していたものの、アメリカのボイコットで夢破れた四男のケリーも兄たちに続いてレスラーとなる。 で、いよいよタイトル戦ができるほどの実力をつけた兄弟でしたが、ベルトへのチャレンジを父から最初に許されたのは、次男ではなく三男だった。で、三男もその気になって頑張るのですが、あと少しでタイトル戦という時に、日本遠征中に急病で亡くなるという悲劇が一家を襲います。 で、次こそは次男がベルトにチャレンジと思いきや、またもや父親に許されたのは四男のケリーの方。で、この時はケリーが実際にタイトル戦に勝利してチャンピオンになるのですが、ベルトを獲ったその日、バイク事故を起こして片足を切断することに。その後彼は義足をつけてレスラーとして復活しますが、元のようには活躍できず。 一方、三男の死と四男の悲劇をみて、五男のマイクがレスラーになることを志願しますが、もともと体格的に向いていなかったのか、練習試合中の怪我がもとで昏睡状態となり、奇跡的に命拾いしたものの、障害が残ってしまう。その後、マイクはそのこともあって自殺してしまいます。 そして、さらにその後、四男のケリーも自殺。 結局、次男のケビンは、一番、父親の期待に応えたかったのにそれが出来ず、しかも仲の良かった弟たちがすべて亡くなってしまうという状況に見舞われるわけ。本当の彼は、真のファミリーマンであり、家族が一緒にいるということを誰よりも大切にしていた男だった。その男が、可愛がっていた弟たちすべてを失うという。そこがね、本当に悲しいの。 でも、この一家で唯一、生き残ったケビンには、いい奥さんがいて、いい子供たちがいて、フリッツ・フォン・エリックの息子たちの中で唯一、一家の名を後世につなぐことになるのよ。色々あったけど、ケビンが生き残って、ここを起点に4人の子供たちと13人の孫が生まれ、大家族となって今は牧場経営をしながら幸せに暮らしている。その結末がこの映画の救いになっているわけね。 『アイアン・クロー』は、そんなプロレス一家の歴史を描いた佳作だったのでした。これこれ! ↓『アイアン・クロー』公式サイト
April 23, 2024
コメント(0)
-
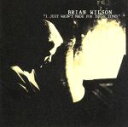
ブライアン・ウィルソン
少し前、名古屋駅前のバナナ・レコードで中古CDを何枚か買ったという話を書きましたが、その中の一枚、ブライアン・ウィルソンのこのCDが気に入りました。これこれ! ↓【中古】 駄目な僕~I Just Was/ブライアン・ウィルソン 最初の聴いた時は、何だか素人が歌っているみたいだなと思ったのですが、ずっと聴き続けているうちに良さがわかってきた。ビーチボーイズ時代の名曲をソロとしてカバーした、という趣のアルバムなんですが、クセになる味わいです。 一方、同時に買ったクイーンの『ザ・ミラクル』は、彼らのアルバムにしてはイマイチな気が。この後に出た『インニュエンド』は傑作なんだけど。もっとも、まだ聴き込んでないので、聴き込んだらまた印象が変わってくるかもしれませんけどね。
April 22, 2024
コメント(0)
-
古着YouTube を見ながら原稿書き
今日も今日とて原稿書き。なんだけど、ちょっと書くのが難しいところに入り込んでいて、なかなか原稿が進まない。苦しい、苦しい。 だけど、こちとらもベテランですから、書くのが苦しい時のやり方ってものがある。それはね、気を散らしながら書くということ。気を散らすなんて言うと、そんなんで書けるの? と思われるかもしれないけれど、我々プロのライターは、別に集中しなくたって書けるのよ。 もちろん、集中して書いてないから質は落ちる。落ちるのだけど、前には進む。 苦しい時には、前に進むことが重要なのであって、止まることが一番良くない。だから、少しくらい質が落ちても、書いている方がいい。 さて、集中せず、気を散らして書くとはどういうことかというと、今の私の場合、具体的には YouTube 動画を見ながら書く、ということになる。3分くらい動画を見て、一文だけ書き、また3分くらい動画の続きを見て、一文だけ書き・・・ということを延々と繰り返すわけ。そうしたら1時間もすれば、1パラグラフくらいは書けるわけ。苦しい時には、それで十分。 で、今、私が原稿を書きながら見ている動画がこれ。これこれ! ↓Forza Style このサイトにも色々なタイプの動画があるけれど、今はまっているのは古着系の動画ね。この前、生まれて初めて古着を買って以来、なんだか興味が湧いちゃってね。 ということで、おじさん二人が東京の片隅にあるマニアックな洋品店でウハウハしながら古着を物色している動画を見ながら、半歩ずつ原稿を書き進めている今日のワタクシなのであります。
April 21, 2024
コメント(0)
-

白山神社のパワーおそるべし! 日経新聞に書評が出た!
マジでヤバイ。一昨日、白山神社で500円玉投資したら、早くもご利益が! 日本経済新聞の書評欄に拙著の書評が出ました~!これこれ! ↓日経の書評欄 書評してくれたのは鈴木透さんというアメリカ文学・アメリカ文化の優れた研究者。さすが専門家だけあって、拙著のいいところをいい具合に引き出し、的確に評してくれております。鈴木さん、ありがとう~! で、この書評のおかげもあって、拙著も現在、めちゃくちゃ爆売れしているみたいよ。アマゾンのランキングも急上昇、ついに979位まで来ました。3ケタに入ったのは初めてかな? 今、売れています!! ↓アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ] 今のところ東京新聞/中日新聞、週刊文春、週刊新潮、週刊現代、日本経済新聞に書評が出て、さらにこの先、文藝春秋にインタビューが掲載され、NHKラジオにも出演となると、ますます売れちゃうじゃん。アマゾン・ランキング2ケタ、いや、1ケタも夢じゃない?! まあ、ありがたい限りですわ。 こういう順境の時こそ、心を引き締めて頑張らねば。今日明日と、原稿書き、頑張ります。
April 20, 2024
コメント(0)
-

新渡戸稲造著『修養』を再読
用があって、新渡戸稲造大先生の名著『修養』を再読しました。これこれ! ↓修養 (タチバナ教養文庫) [ 新渡戸稲造 ] これ、『修養』そのものではなく、その現代語訳なんですけど、まあ、内容が分かればいいかなと。 この本の原著は、明治44年に出版され、昭和9年までに148版を重ねたという超ロングセラー。元々は『実業之日本』という雑誌に連載されていたものを集めて本にしたもので、当時の新渡戸は第一高等学校校長で、かつ、実業之日本社の顧問も務めていた。片や若き学徒を束ねる立場にあり、その一方でジャーナリスティックな活動もしていたということで批判もされたようですが、そういうさがない批判に耳を傾けることなく、新渡戸は旧制高校などに進学できなかった非エリートの若者たちに対して修養を説き、向学心を煽ったと。 で、本書はそういう性質のものゆえ、市井の人々、すなわち、必ずしも学校教育を受ける機会に恵まれなかった人たちに向けて書いてある。だから、小難しいことは一つも書いてない。で、しばしば新渡戸稲造自身の経験、とりわけ失敗談などを元に、そうした失敗からの反省をもとに、「こういう風に心掛けたら、より良い人生になるのではないか」ということを説き起こしているので、著者に対して非常に親しみも増すわけよ。つまり、高所から論を説くのではなく、凡夫の立場でモノを言っている。そこが非常に好感の持てるところなんですな。 その内容は多岐にわたるけれども、勘所としては、「善用」ということ。人生、浮き沈みがあって、順風の時もあれば逆風の時もある。だけど、逆風の時はその失敗を反省し、その経験を善用して次へ進めばいいし、順風の時もまたおごらず、そこで得たものを善用し、さらなる成功に導けばよい。なんであれ、この世で遭遇することはすべて自分を磨くチャンスだと心掛けておれば、たとえ凡夫であろうとも真っ当な人生を充実して生きることができるよ、という話を、色々な観点から述べているのが本書、ということになりそうです。 だから、とってもまともな自助努力系自己啓発本であることは間違いない。いい本です。 それにしても、本書を読んでいて思うのは、昔の偉い人ってのは、実に色々な人の訪問を受けていたのだなということ。 見も知らぬ赤の他人が、新渡戸稲造を頼って、相談をしに直接、家に来ちゃうのよ。入学試験に失敗してしまったけど今更郷里にも帰れない、ついては先生のお宅の書生としてつかってもらえないだろうか、などと切羽詰まった顔をした若者がやってくる。かと思えば女子高生が何人か束になって自宅に押しかけてきて、『女大学』などという書物に書いてあることなど、とても実行できないが、先生はどう思うかと意見を聞きに来る。その他、就職のあっせんを頼む者だとか、そういう輩がやたらに訪問してくる。それも朝食前とかの時間から来るというのだから、何ともはや・・・。 すごいよね、昔の人って。今、たとえば岸田総理とかのところに朝食前に押しかけていって、就職のあっせんをお願いしたいとか言いに行ったら、下手したら逮捕されるんじゃね? でも昔はそういうのもアリだった、ってことでしょ。 でも、そういうのが通った時代ってのも、考えてみれば、なかなか豊かな時代だったと、言えるんじゃないですかね。人間的だよね。 むしろ、今もそれ、やったらいいんじゃない? 岸田首相とか、朝食前の30分、訪問してきた一般市民と面会するよ、何であれ相談に乗るよ、っていう風にしたら、支持率爆上がりじゃない? 映画『ゴッドファーザー』の冒頭場面みたいにするの。 新渡戸稲造の『修養』を、岸田首相にも読ませたいね。
April 19, 2024
コメント(0)
-
またも新書オファー! 白山宮のご利益が止まらない!
NHKラジオからのオファーに続き、今度はまたも大手出版社から新書本の執筆オファーがありました~! もう勢いが止まりません! しかもこれ、すべて白山宮のご利益だからね。先週、出勤前にちらっと神社に立ち寄り、大枚100円投資して、仕事の発展を祈願したんだけど、そのおかげで週刊誌に書評が次々出るわ、ラジオ出演のオファーは来るわ、新書の執筆オファーは来るわ、だもん。白山宮最強! 龍神最強! ということで、今日も出勤前に神社に立ち寄り、お礼参りと称して大枚500円、ぶっこんで来ましたよ。何と言っても、人間が生きていく上で大切なのは「お礼をすること」だからね。感謝、感謝。白山宮、サンキュー! だけどついでに「さらにいいことがあったら、次、1000円、行きますから」とお願いして来ちゃった。 もう、怖いわ。マジですごいオファー来たらどうしよう? それはさておき。 問題は、今回オファーしていただいた新書の内容よ。今度は一体、何を書けばいいのか? 自己啓発本研究に関して、既に2冊上梓しており、今は3冊目と4冊目の準備をしているところ。この4冊に関しては、全部、話題が異なります。 で、一つの話題について4冊の本を書くと、その時点で、結構言い尽くしたところはあるのよ。そうなると、5冊目に位置づけられる次の新書本に何を書けばいいのか、ちょっと悩むところはある。 打開策はなくもない。それはね、一人の著名な自己啓発本ライターに焦点を当て、そのライターについてモノグラフを書くこと。まあ、自己啓発本の世界には面白いライターが多いから、このやり方を採用すれば、ほとんど永久に書いていられる。 だけど、今回の新書に関して、担当編集者さんの思惑を推測するに、どうもそういうものを期待していないような気がするんだなあ。もっと一般的な話題について書いてもらいたいと思っているのではないかなと。 となると、1冊目と2冊目の焼き直しにならざるを得ないじゃん??? そこなのよ、問題は。編集者さんの期待を裏切らずに、どうやったら焼き直しでない本が書けるか、っていうね。 残念ながら、ちょっと考えたくらいでは、なかなかいいアイディアが出ない。 だけど、考え続けていれば、そのうちフッと意外なところから面白いアイディアの芽が顔を出すかもしれない。だから、考え続けなければ。 考えろ、考えろ。それが学者の生きる道。
April 18, 2024
コメント(0)
-
NHKラジオに出演決定!!
ひゃーーー! 待ちに待った日がやって参りました~! NHKからラジオ放送への出演依頼が来ました~!! いやあ、嬉しいねえ。ついにこの日が来たか・・・。 昨年、FM愛知に出演させていただきましたが、やはりローカル局。残念ながら反響は望んだほどではなかった。しかし今度は天下のNHKラジオですからね。リスナー数は200万だよ、200万!! これは結構、反響あるでしょう。 実はつい先日、例によって家の近くの白山神社にお参りして、メディアへの露出を増やしてくださいとお願いしておいたのよね。そしたら、これだもん。やっぱり神様っているのね。明日はまたお礼参りに行かなくては!! っつーことで、何だか今日は浮足立っているワタクシなのであります。さあ、これから忙しくなるぞ~!!
April 17, 2024
コメント(0)
-

穂村弘著『短歌の友人』を読む
先週の金曜日、いわば時間つぶしのために買ったものの、読みだしたら止まらなくなった穂村弘さんの『短歌の友人』という本、読み終わりました。すごく面白い本でした。これは確かに、賞に値する本だなと。 これは短歌にまつわる本、といって研究書ではないし、専門家のみならず一般読者に向けて書かれているので、「文学的エッセイ」と呼ぶべきものだろうと思うのですが、そういうものとしてピカ一の出来。実に面白く、かつ啓蒙的でありました。しかも、学術的な意味での文学論にもなっているという。こう言っちゃ同業者に怒られるかもしれませんが、今日日、アメリカ文学関連の学会でこのレベルの文学論に出会ったことがない。穂村さんの本って初めて読んだけれど、これほどのものだったのかと、目からウロコ状態でした。 この本に収められたどの文章も興味深いのですけど、私が一番「お!」と思ったのは、「〈読み〉の違いのことなど」と題された一文。この文章の冒頭近くに、次のようなことが書いてある。 いつだったか、永田和宏が、歌人以外の人の歌の〈読み〉に心から納得できたことがない、という意味のことを書いているのを見た記憶があるのだが、基本的に私も同感である。 歌人の〈読み〉の場合、それが自分の〈読み〉と異なっていても、〈読み〉の軸のようなものを少しずらしてみれば理解はできることが多い。大きくいえばそれは個々の読み手の定型観の違いということになると思う。 それに対して、他ジャンルの人の短歌の〈読み〉については、定型観がどうとか〈読み〉の軸がどうとかいう以前に、「何かがわかっていない」「前提となる感覚が欠けている」という印象を持つことが多い。これはあまりにも一方的な云い方で、ちょっと口に出しにくいのだが、そんな感じは確かにあると思う。 「前提となる感覚が欠けている」とはどういうことか。これをうまく表現するのはなかなか難しいのだが、例えば、「歌というのは基本的にひとつのものがかたちを変えているだけ」という感覚の欠如、という捉え方はどうだろう。実作経験のない読み手は、この感覚もしくは認識が欠けているように思えてならない。(176-177) うーん、どうよ。すごいことが書いてあるじゃないのですか! この先、穂村さんが言っていることをまとめると、実作経験のない、すなわち歌人ではない素人には「歌というのは基本的にひとつのものがかたちを変えているだけ」という共通認識がなく、むしろ漠然と「短歌にも色々なものがある」と思っているようで、その色々なタイプの短歌の中で自分の理解できるものをピックアップして、それに対して「いいな」とか、「そうでもないな」とか、適当にコメントしているだけだと。 では、歌人ならば持っている「ひとつのもの」への認識とは何か? 例えば正岡子規にこういうのがある。 人皆の箱根伊香保と遊ぶ日を庵にこもりて蠅殺すわれは この歌は、病床にあって物見遊山にも行けない自分を見つめた歌であるわけですが、ここにあるのは他人に代わってもらうことのできない、自分の人生の一回性、つまり「生のかけがえのなさ」であって、これこそが近代以降の短歌における「ひとつのもの」であると。 だから近代以降の短歌というのは、繰り返しこのことを歌っていると言っていい。それは例えば、花山多佳子という歌人の かの人も現実(うつつ)に在りて暑き空気押し分けてくる葉書一枚 という歌は、上に挙げた子規の歌の変奏であって、歌っている内容は「生のかけがえのなさ」ということである点では同じなのだと。 この「同じだ」という感覚が、歌人と素人の間では共有されていないのではないか、というのが、この文章で穂村さんが言っていることなわけ。 な・る・ほ・ど! なるほどね~。 こうなってくると、もうアレだね、実作しない短歌の批評家なんてのは、実作者からしたらお笑い種なんだろうね。 しかし、それはまた逆に、実作する者同士の批判のし合いとなると、もう、命がけということにもなる。だって、もし相手の歌が歌として通用するならば、それは即、自分の歌が全否定されることを意味するのだから。だから、そんなものは絶対に認めない。もし他の大勢の人がそれを認めるなら、自分は自害する――というようなところまで行っちゃうわけだから。実際、穂村さんはニューウェイブ歌人として名をあげ始めた頃、オーソドックスな歌人であった石田比呂志からそういうことを言われたことがあるそうで。 すごいよね。今、アメリカ文学の学者の間で、これほどの切った張ったなんてないもん。大体、実作するアメリカ文学者なんて、そうそういないですからね。 その他、穂村さんに腑分けされると、近代短歌の在り様と比べた上での現代短歌の位置づけというのもよく分かるし、著名な歌人の特色とかもすごくよく分かる。岡井隆なんて歌人・詩人の本質なんて、わずか数ページほどのエッセイにして、ズバッと核心をついているもんね。まあすごいものですよ。 というわけで、穂村弘、恐るべしということがよく分かった読書体験だったのでした。この本、教授の熱烈おすすめ!です。これこれ! ↓短歌の友人 (河出文庫) [ 穂村弘 ]
April 16, 2024
コメント(0)
-
『mr. & mrs. スミス』は超面白そうな予感
拙著の書評、『週刊文春』と『週刊現代』に載ったという話をしましたが、実は先週、『週刊新潮』にも載っていたのね。すごくない? 主要週刊誌制覇じゃん。 それはともかく。 昨夜、アマゾン・プライムで『mr. & mrs. スミス』の第1話を観ました。そしたらね、これがめちゃくちゃ面白かったのよ。 『Mr. & Mrs. スミス』といえば、かつてブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー主演で撮った映画がありました。これは、まあ、面白くなくはないのですが、人気者同士の夫婦が出た映画として、その話題性が際立ってしまい、内容的にはさほど・・・というところがあった。 で、その記憶があるものだから、プライム・ビデオで始まったこのドラマも、これの焼き直しなのかと思っていたわけ。 でも実際には全然違います。映画と今回のテレビ・ドラマ版は全然設定が違う。 映画版の方は、男のスパイと女のスパイがたまたま相手の本当の職業を知らないまま結婚してしまった、というありえない状況を描いたシチュエーション・コメディだったわけですが、今回のテレビ・ドラマ版は最初から男女二人のエージェントが、偽装夫婦としてスパイ活動を行うというもの。最初からお仕事で夫婦を演じるわけ。 で、昨夜観た第1話では、初めてこの二人がチームを組み、「肩慣らし」と称して、組織からある仕事を請け負うというエピソードだったのですが、非常に面白かった。男女の設定にしても、男の方が黒人、女の方が日系人という設定が実に面白い。 最近、ハリウッド映画の凋落が激しいですけど、ネットフリックスとかアマゾン・プライムとか、こっち側のドラマ制作については、優秀なものが多いんだよなあ。今や主力はこっちなのですかね? とにかく、プライムビデオの『mr. & mrs. スミス』、教授の激推し!です。これこれ! ↓『mr. & mrs. スミス』
April 15, 2024
コメント(0)
-

『週刊現代』最新号に書評が載りました~!
発売されたばかりの『週刊現代』最新号(4月20日号)に、拙著『アメリカは自己啓発本でできている』の書評が載りました~! 先週の『週刊文春』に続く朗報でございます。 しかもね、書評してくれたのが武田砂鉄さんだっていうね。そう『紋切型社会』で名高いライターさん。『週刊文春』で書評してくれた速水健朗さんといい、武田砂鉄さんといい、力ある読み手に認めてもらって、著者としては冥利に尽きますわ。 ところで、話は全然違うのですが、今日の読売新聞の書評欄を見ていたら、『世界は経営でできている』という本が書評されておりまして。で、この本、タイトルがワタクシの本とそっくり。アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ] 世界は経営でできている/岩尾俊兵【3000円以上送料無料】 いや、ただそれだけの話なんですけど、『○○は○○でできている』という本がほぼ同時に世に出たというのは、何かこう、良いことの前兆かなと。 だってさ、『○○力』とか『〇〇の品格』、あるいは『○○は○○が9割』とか、タイトルかぶりの本って、どれもベストセラーになるじゃん? その伝で行けば、『○○は○○でできている』だって、そうなる可能性がなくはない・・・んじゃないの? 希望的観測だけど。 まあ、「私は希望的観測でできている」ので、すぐ期待しちゃうんだけど、実際にそうなればいいなあ・・・。
April 14, 2024
コメント(0)
-

名古屋彷徨
昨日のブログで、昨日、まず雑誌の取材を受け、その後、元同僚と現在の同僚と三人で飲んだ、という話を書きましたが、この二つのイベントの間に挟まった三時間ほどの空き時間のことを書いておりませんでした。しかし、そこには私にとって大冒険と言いましょうか、それなりに大変な出来事があったのでした。 それはなぜか? 名古屋駅周辺で用もなく放り出された三時間をどう過ごすか問題。これが私に襲い掛かって来たからであります。 普通の人であれば、それこそ喫茶店に入って時間を潰すなりすればいいのでしょうけれども、私にはそういう手段がない。というのも、私は一人で喫茶店とかレストランに入れないから。 私は人生の中で一人で喫茶店とかレストランに入ったことが数回しかなく、それも針の筵的経験に数えられる。だから、一人で町中で三時間を潰すという課題を与えられた場合、すごく困るのよ~。 というわけで、昨日もインタビューを終え、記者さんと意気揚々と別れたはいいものの、さて、これから三時間どうするか、途方に暮れたのでした。 で、まず行ったのは「バナナレコード」という中古CD・レコードのお店。ここは前にも来たことがあるし、私にとっては大好きな場所。で、ここでブライアン・ウィルソンのソロ・アルバムなどを数枚買って楽しかったのですが、まあ、30分潰せたかどうか・・・。 さあ、あと2時間半、どうするか・・・。 私は意を決して名古屋駅の北の方を目指して歩き始めました。というのも、そちらの方向に「ノリタケの森」という施設があるらしいと知っていたから。陶器で有名なノリタケ関連の施設で、無料で見られるギャラリーなどもあるらしい。ならばそこへ行ってみようと。 かくしてずんずん歩くこと20分。到着したノリタケの森は、広い敷地に赤レンガの建物などが配された、なかなか瀟洒なところでした。で、ここで無料のギャラリーや、ノリタケ製品を売っているお店などを冷やかしたのですが、30分ほどで終了。さて、この後どうするか・・。 すると、すぐ隣にイオンが見える。どうやら蔦屋書店も入っているらしい。ならばあそこへ行ってみよう。 で、2フロアを占める蔦屋書店を徘徊し、穂村弘の『短歌の友人』というエッセイ集をゲットしたりして。これこれ! ↓短歌の友人 (河出文庫) [ 穂村弘 ] で、蔦屋内にあるスタバでコーヒーを飲みながら、この本を読んで時間を潰そうかと思ったのですが・・・ やっぱり勇気が出ない! だって、席が結構埋まっていて、その狭間に座るのが嫌なんだもの・・・。 いや、しかし待てよ。ここはイオンだ。イオンなら、フードコートがあるはずだ。平日の変な時間のフードコートなら、空いているのではないか? で、フードコートに行ってみたところ、思った通り、結構がら空き。よし、ここで時間を潰そう! そこで、マックのカフェラテを買おうとしたのだけれども、そこでちょっと考えを変えて、生ジュースを売る店に行き、バナナミルクを330円でゲット。そしてこれを手に、周囲に誰もいない座席に座り、先程買ったばかりの『短歌の友人』を読み始めたのですが・・・ これが面白かった! 穂村弘の本って初めて読んだけれども、すごく面白い。短歌の世界って、こういう感じなんだ、というのがよく分かる。穂村さんが紹介する短歌も面白いし、また穂村さんが他の歌人から批判されたことを書いたエッセイなどを読むと、短歌の世界ってこんなにキビシイのか・・・ということに慄かされたりして。 で、思いの他熱中して読んでしまったので、1時間があっという間に過ぎ去った。 で、そろそろ時間が来たということで、この救いの神となったイオン@ノリタケの森を離れ、名古屋駅に向かって歩き出した次第。 ということで、取材と飲み会の間に大冒険をしていたおかげで、結局、昨日は期せずして1万2千歩も歩いていたのでした。どうりで、ベッドに入った途端、爆睡してしまったわけだ・・・。
April 13, 2024
コメント(0)
-
またまた雑誌のインタビュー
今日は某有名月刊誌の取材があり、名古屋駅に隣接するマリオット・アソシアのロビーラウンジで記者さんからインタビューを受けてきました。 で、インタビュー受けながら思ったのだけど、マスコミの記者さんって、面白い商売だなと。 だって、取材と言えば、大抵の人に会えるわけだから。会うだけじゃなく、突っ込んだ話も聞けるわけで。 聞いた話をまとめる力量さえあれば、日本中、あちこち飛び回って人に会って取材するなんて、面白いでしょうな。ワタクシもそういうのやってみたい。 ま、それはともかく。なかなか面白い経験をさせてもらった一日となったのでした。 ところがね、今日はそれだけでは終わらなかったのであります。 前に私の勤める大学に勤めていた若手の先生で、郷里のある九州の大学に移籍したE先生が、たまたま名古屋に来るというので、同僚のN先生とも待ち合わせて三人で一緒に名古屋駅周辺で飯を食うことに。 私がE先生に会うのは、前に広島で学会があった時以来だから、6年ぶりかな? 7年ぶり? まあ、そのくらい。でも、気の置けない元同僚ですから、会えばすぐに元の調子になる。互いの近況、そして勤務先の愚痴の言い合いとか、共通の友人の噂話とか、爆笑のうちに時間があっという間に過ぎて行ったのでした。 E先生は英文学がご専門で、アメリカ文学の私とはちょっとだけ違うのだけど、英語文学という点では同じ。そういう、分野がほぼ同じ同僚が今、所属大学の同じ部署にはいないので、久々にE先生と英語文学の話もちょっとできて面白かった。 ということで、今日は取材もあり、元同僚と旧交を温めるということもありの、充実の一日となったのでした、とさ。
April 12, 2024
コメント(0)
-

教授、古着デビューする
今日は授業がない日だったので、大学から有給をいただいて、お昼、外食してきました。一昨日の誕生日の祝い延ばしです。 で、家内と向かったのは、一社というところにある「ジラソーレ」というイタリアンのお店。こじんまりとしたお店でしたが、料理もサービスもとてもよく、気に入りました。次は夜、行ってみようかな。 ところで、店を出てコイン・パーキングに向かう途中、「注文の多い雑貨店」という我々のお気に入りの雑貨屋さんに立ち寄ったのですが、ここでちょっと面白いことがありまして。 このお店では、世界各地から仕入れた様々な雑貨が置いてあるのですが、その中に、古着も混じっている。 以前は、そういうものは私には縁のないものと思って素通りしてきたのですが、このところちょっと古着なるものに興味が出てきたところだったので、今日はがっつり見ちゃった。そうしたら・・・ おお! なかなか可愛いセーターがあるじゃないの!これこれ! ↓ 写真だと見づらいですが、色はブラウン、ボタンがカーキで、襟の立ち方がカッコいい。これ、アメリカ軍のミリタリーもののデッドストックだそうで。実際、着てみるとサイズもぴったり! 値段も1万円以下と、まあまあお手頃。 ということで、還暦を過ぎてついに古着デビューしてしまったワタクシ。やった~! 一方、家内はというと、やはりミリタリー系で、チェコ軍やフランス軍、イタリア軍の薄手のコートなどを次々と試着、とくにロシア軍の女性兵士用スプリング・コートはデザインもよく、かなり心惹かれるところがありましたが、この手のコートは既に何着か持っているということで今回はやめておくことに。 その代わり、トカゲをリアルにデザインした可愛いリングをゲット。これは尻尾を指に巻き付けるような感じで、とてもいい。 ということで、今日は二日遅れの誕生日ランチ、そしてそのあとの古着デビューも含め、なかなか面白い一日となったのでした。
April 11, 2024
コメント(0)
-
「手癖が悪い学生」って・・・
四月、新学年が始まって数日、教授連の間では「今年の〇年生、どう?」的な会話がよくなされます。「今年の1年生は、割と反応がいいね」とか、「それに比べて2年生はぜんぜん・・・」とか。 で、今日もそんな話をしている時に、某先生から「今年の2年生に、手癖の悪い学生が何人かいる」という発言がありまして。 ん? 手癖が悪い? 久々に聞いた言葉遣いだけど、どゆこと?? その先生、自作のテキストを実費(500円)で学生に買わせているそうなのですが、最初の時間に学生から500円を徴収しながら、お金を払った学生に山積みしたテキストを一部ずつ持っていくように指示したそうなのですが、学生の中にそのテキストを2部、持って行こうとする奴がいると。 で、それに気が付いて「君、テキストは1部ずつだよ」と注意すると、悪びれもせず1部返却したのだとか。その様子から、間違って2部取ったのではなく、意図的に盗もうとしたことが明らかだったと。 しかも、そいつ一人ではなく、そいつには仲間が何人かいて、その連中も1部の代金を支払って2部持って行こうとしたのだそうで。要するに、うまいこと2部、ばれずに持っていくことができたら、仲間と山分けにして、半額でテキストを手に入れようとしていたわけですな。 なるほど、これは確かに手癖が悪いわ。 たかだか500円くらいのものだというのに、自専修の先生を騙そうとする学生が一つの学年に何人もいる。それが自分の勤めている大学だと思うと、本当に嫌になります。 もちろん、人間にはいろんな種類のヤツがいる、嫌な奴も大勢いるというのは、文学をやっているワタクシにしたら当然、認識していることではありますが、学問をしようと大学にまで来ている若者の中に、こういう卑劣な人間が混じっているとなると、なんだか身の毛がよだつような感じがする。 もう、なんだか、ますます早く引退したくなってきましたわ。
April 10, 2024
コメント(0)
-
クタクタの誕生日
今日はワタクシの誕生日! 誰かおめでとうって言って! たしか昨年は、9日が日曜日だったんですよね。それで休日だったので、家内と多治見の方にドライブに行って、そこでレストランで食べて、多治見の窯元を尋ねて焼き物を買ったりして楽しんだのではなかったかと。 それに比べて今年の誕生日は生憎、週のうち一番キツイ日で、3コマも授業があったのよ。しかも休み明けでまだ身体が慣れていない状態での3コマだから、もう、疲れる疲れる・・・。クタクタですわ。 こうなってくると、早く定年を迎えて、宮仕えから引退したいなあと思うけれども、どうなんだろうね、定年になったらなったで、張り合いが無くなるものなのだろうか? そうだとしたら、仕事があるうちが華なのかもね。クタクタでも、ありがたいと思わなくちゃいけないのかもしれませんな。 今週はこの先、出版社とのリモート会議あり、雑誌のインタビューありと、なかなか多忙なスケジュールですが、何とか乗り切って、週末は少しノンビリしたいものでございます。
April 9, 2024
コメント(8)
-
ナポレオン・ヒルのマスターマインド
ちょいと用があって、ナポレオン・ヒルの著作をあれこれ読んでいるのですが、読む度に不思議に思うことがあって、それは「マスターマインド」という概念についてなのですが。 ヒルはその自己啓発本の中で再三再四、成功するのに重要なのは、マスターマインドを形成することだ、と主張している。ではそのマスターマインドとは何ぞやというと、同じ目的をもった複数の人間からなる協力体制のこと。 つまり大きな仕事を成功させるには、マスターマインドを形成してかからないとダメだと。なぜなら、一人の人間にして完全な人はいないから。人それぞれ欠点があって、それゆえ死角が発生する。だから、複数の人間が協力し合い、互いの死角を消して、それでことに当たらないと、成功への道は絶対に開かれないと。 うーん。そこが分からないんだなあ。 管見によると、世に自己啓発思想家は数多あれど、こういうことを言っている人は他にいないのよ。普通、自己啓発本って、個人の成功を指南するものを言うのであって、最初から複数で協力していけ、なんて言っている自己啓発本なんてない。ヒルは、そこが独特なんだよなあ・・・。 なぜヒルは、そういうことを言うのだろう? 何か経験的なバックグラウンドがあるとも思えないのだが・・・。 その辺り、もう少し考えてみないといかんかな・・・。
April 8, 2024
コメント(0)
-

中日新聞に書評が出た~! からの『デューン』
先日、『週刊文春』に拙著の書評が出た後、書評してくれた速水健朗さんが御自身のXに「この1,2年で読んだ本の中で1番のおもしろさ」と追加ポストしてくださり、感謝感激。そう言って下さる方が一人でもいればね、この本を書いた甲斐があったというものですわ。アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ] で、今日は今日で、中日新聞の読書欄に書評が出ました~。 うちでは中日新聞を取っていないので、午前中、近所のコンビニに行って中日新聞を買ってきたんですけど、著者近影つきの書評でこっぱずかしいったらありゃしない。でも、こちらも好意的に書評してくださっていて、ホント、ありがたい限りです~。 ところで・・・。 昨夜、レイトショーで『デューン Part2』を観てきました。もうそろそろ字幕版の公開終了が迫っていたので、慌てて観に行った次第。 で、前作、すなわち「Part 1」を観た時は、「ん? これって面白いのか?」と若干、疑問符が付いたのですが、今回の「Part 2」は面白かったです。映像的に迫力もありましたしね。 「Part 1」は、主人公が父親を殺され、仲間を殺され、命からがら逃げまわる話だったのですけど、「Part 2」は逆にその倍返しというか、主人公が復讐を果たし、さらに銀河帝国の皇帝にならんか、という話ですから、忠臣蔵の爽快バージョンみたいな感じですっきりする。その点、前作に倍する面白さでした。この映画、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓『デューン』公式サイト それにしても、『デューン』も結局は陰謀と戦争の話なのよ。『デューン』だけじゃない、私が次に観ようと思っている『マッドマックス フュリオサ』だってそう。 で、これらを神話的な物語として、あるいは寓話として観るのならいいのだけど、世界を見渡せばウクライナでも戦争やってる、ガザでも戦争やっている、その他、イエメンでもティグレでもミャンマーでも内戦が進行中。もう実際の戦争ばっかりだ。 映画でも現実でも戦争ばっかりっていうね。 結局、人間ってのは、何だかんだ言って戦争が大好きなんだ、と思わざるを得ないよね。
April 7, 2024
コメント(0)
-

カレン・マクレディ著『ナポレオン・ヒルの哲学を読み解く52章』を読む
カレン・マクレディという人が書いた『ナポレオン・ヒルの哲学を読み解く52章』(原題:Napoleon Hill's Think and Grow Rich, 2008)を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 これは自己啓発本の傑作として名高いナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』という本のエッセンスを抜き出し、それを現代の視点から読み解きながら解説する本でありまして、いわば『思考は現実化する』に寄り掛かった本、ナポレオン・ヒルのまわしで相撲を取るような本なんですけど、じゃあ、面白くないかというとそんなこともなく、むしろ結構面白く読むことのできる本でした。 実際、ヒルの『思考は現実化する』は1937年の本ですから、かれこれ90年近く前の本ということになる。だから記述もちょっと煩雑なところもあるし、あがっている例も少し時代がかったところがある。そこで現代の事象に照らし合わせながら『思考は現実化する』を読み解き、ヒルの主張が90年前と同じように現代にも通用するんだよ、ということを教えてくれる本書のような本があると、現代の読者としてはとっつきやすいというか、この本をきっかけに『思考は現実化する』に手を伸ばしてみようと思う人も出て来るのではないかと。 では、『思考は現実化する』を、現代風に読み解くとはどういうことか? 『思考は現実化する』の中で、ヒルは「チャンス」というものの性質について次のように述べています。曰く「チャンスは予期していたのとは違う形で、違う方向からやってくることが多い。それがチャンスのトリックの1つである。チャンスには裏口から忍び込んでくるというやっかいな性質があるのだ」と。 で、このヒルの明察を、カレン・マクレディは「アル・ゴア」という、アメリカ人なら誰でも知っている現代の著名人のエピソードを使って解説するんですな。 アル・ゴアは、クリントン政権時の副大統領であり、2000年のアメリカ大統領選に出馬した。その際、彼のアピール・ポイントたる政治的主張は「気候変動問題」だったのですが、当時はまだアメリカの一般大衆はそこまでこの問題に関心がなかった。アル・ゴア自身は、もっと若い時からこの問題に強い関心があったので、自分が大統領になれば、まず一番にこの問題に取組もう!と思っていたのでしょうけれども、残念ながら彼は大統領選に敗れ、その夢を実現することはできなかった。 しかし、「大統領選に敗れた」ということが、アル・ゴアにとっては大チャンスだった、とカレン・マクレディは指摘します。 大統領選に敗れ、政治家としてのキャリアを終えたアル・ゴアは、環境問題に取り組む活動家として活動を始め、例の『不都合な真実』というドキュメンタリーを制作して話題となり、この分野での第一人者として環境問題への発言力を強めたばかりか、最終的にはノーベル平和賞も受賞している。結局、彼は「気候変動問題」に取り組むという夢を、ちゃんと実現させたわけですよ。 つまり、彼にとって「大統領になる」ということは「夢」ではなくて、「手段」だったわけですな。で、その手段は手に入れることができなかったけれども、逆のそのおかげで、この問題について大統領になっていたらできたであろう以上の活動をすることができた。つまり、大統領になれなかったおかげで、自分の本来の「夢」を実現することができた。 カレン・マクレディ曰く、これこそがヒルの言う「チャンスは予期せぬ形でやってくる」ということの意味であろう、と。大統領選に敗れたことが、アル・ゴアにとっては予期せぬチャンスだったのだ、と。 ヒルが『思考は現実化する』の中で主張していることを、現代の事象をもって解説する、ということがどういうことか、分かるでしょ? とまあ、こんな感じで、本書は52個の現代的なエピソードを駆使して、ヒルが90年ほど前に『思考は現実化する』の中で述べたことの妥当性を証明していくわけ。そういう意味で、なかなか面白いし、『思考は現実化する』という本の、良い意味での解説書・入門書になり得ていると思います。 っつーことで、あまり期待しないで読み始めた割に、案外、ヒルの『思考は現実化する』という名著をよりよく理解する上で役に立つ本だったのでした。教授のおすすめ!です。これこれ! ↓【中古】 ナポレオン・ヒルの哲学を読み解く52章/カレン・マクレディ(著者),藤澤将雄(訳者)
April 6, 2024
コメント(0)
-

「ほぼ日の學校」、動画公開!
昨年11月に収録した「ほぼ日の學校」の動画が今日から公開されています。今回公開されたのは前篇で、後編に関しては4月9日公開予定とか。これこれ! ↓「自己啓発本」には、かなり奥深いおもしろさがある ご一緒した『夢をかなえるゾウ』の水野敬也さん、『嫌われる勇気』の古賀史健さんも、それぞれXで動画公開の告知をされています。水野さんのポスト古賀さんのポスト X上で水野さんもおっしゃっているように、「後にも先にもここまで自己啓発本をがっつり話すことはない」という稀有な座談会ですので、有料になってしまいますが、興味のある方はぜひ、ご覧ください。 ちなみに、今回の座談会で俎上に上がっているのが、この本です! 座談会の中で、水野さんも絶賛してくださっています。 この本、動画が公開されてから、アマゾンの在庫が一瞬で消えました。これこれ! ↓14歳からの自己啓発 [ 尾崎 俊介 ] そして、今発売中の『週刊文春』の「必読図書」として書評されているのがこちら!アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ] こちらの本に関しては、今週の土日に東京新聞と中日新聞に関連インタビュー記事が出ます。こちらもぜひ!
April 5, 2024
コメント(0)
-
『デューン』を観に行って、『オッペンハイマー』を観る羽目になる
昨日の夜、レイトショーで『デューン Part 2』を観に行ったんですわ。 で、チケット売り場でチケットを買おうとして、ふと手が止まった。ん? これは「吹き替え版」ではないか?! 驚くべきことに、その映画館ではもはや字幕版の上映がなく、吹き替え版しか上映していなかったのでした。いやあ、洋画観に行って、吹き替え版しかやってない、なんて状況にこれまで立ち至ったことがなかったので、面食らったわ・・・。 あとで調べたら、他の映画館でも字幕版の上映が間もなく終了するところばかり。『デューン』ほどのSF大作が、今や日本ではこういう扱われ方をするのね。 とにかく、洋画を吹き替え版で観るなんて無粋なことはワタクシにはできないので、『デューン』はあきらめ、急遽『オッペンハイマー』を観ることに。まあ、いずれ近々に観る予定ではあったので、順番は逆になったけどいいかなと。 というわけで、予定外に『オッペンハイマー』を観ることになったのですが(以下、ネタバレ注意)、「原爆の父と呼ばれたオッペンハイマーの栄光と苦悩を描く」という謳い文句通りの映画でした。原爆の開発をめぐるエピソードが全体の6割くらい。後半の4割は、「ソ連のスパイ」疑惑をかけられ、檜舞台から引きずり降ろされていくオッペンハイマーの後半生のゴタゴタを描くことに費やされております。 まあ実際、オッペンハイマーも脇が甘いというか、女性関係のモラルがないし、共産主義の理想に共鳴するのはいいとして、そこを突かれて人に利用されることも多かった。まあ、天才物理学者とはいえ、オッペンハイマーはそこそこ欠点の多い人なわけよ。そりゃ、仕事上の才能が傑出している人に対しては、人間としての人格も一級品であってほしいとつい思ってしまうけれども、必ずしもそうならない、なんてことはどこにでもある話でね。 オッペンハイマーだって、ある意味、どこにでもいる普通の人なんですな。 でも、その普通の人が、大量殺人平気たる原爆を作っちゃった、というのは事実であって、その責任は重い。もちろん、それを開発している時には、それを開発しなければならない国家的・時代的な理由があったし、仮にナチス・ドイツがアメリカより先に原爆を開発していたらどうなったか、ということも考えなければならない。ユダヤ系のオッペンハイマーにしたら、なおさらそう。 しかし、原爆が完成してしまうと、もうそれはオッペンハイマーの手を離れ、アメリカのものになってしまう。そしてオッペンハイマーの意図とは関係なく、実際に使われてしまう。開発だけさせられて、その後は梯子を外されてしまうわけよ。しかし、そんな風に梯子を外されたにもかかわらず、原爆の父という倫理的責任だけは負わされるというね。 まあ、哀れなもんですわ。ある意味。その哀れな男の、茫然とした表情で映画が終わるというのも、実にふさわしい。 人間に火をもたらしたプロメーテウスは、その後、永遠の罰を受けることになる、という、映画冒頭に示されるテーマが、最後のシーンに引き継がれる。そういう感じでしたね。 というわけで、3時間の大作、非常に面白かったのですが・・・ではこの映画が映画史に残る傑作かと言われると、うーん、どうかな。 まあ、史実映画の限界というか、史実(あるいはその解釈)を超えるものではないからね。「そういうことだったんですよ」で終わっちゃうから。それ以上でもそれ以下でもないという。 それだったら、同じノーラン監督の史実映画でも『ダンケルク』の方がはるかにドラマチックだったかな。『ダンケルク』は二度観てもいいけど、『オッペンハイマー』をもう一度、3時間かけて再見したいとは思わないもんな。 っつーわけで『オッペンハイマー』、面白くはあったけれども、個人的には「大傑作」というよりは「大佳作」という評価だったのでした。
April 4, 2024
コメント(0)
-

有名月刊誌からインタビュー申し込み!
先日、父のお墓参りをした時に、「今度新著を出したのだけど、これが広く世間の認知を受けるよう、天国から応援してよ!」とよくよく頼んでおいたのですが、早速そのご利益が出ました。伝統ある超有名月刊誌より、著者インタビューのお申し出がありまして。 やった~! ラッキー! 本というのは、出版後1カ月くらいすると、ぼつぼつ世間の反応が出てきて、行けそうかな? それともダメかな? という見当がつくようになるんですけど、今回の本の場合、割と幸先がいいのよ。もうすぐ某新聞にインタビュー記事が出るし、某有名生命保険会社の出している雑誌にも3ページにわたる紹介記事が出る。 さらに明後日5日には、「ほぼ日の學校」で行った座談会の動画が公開されるし。波状攻撃的に、販促につながりそうなイベントが続く。 やっぱりね、ご先祖様をおろそかにしないと、こういうご利益があるわけですわ。父上、ありがとうございます! さて、こうなると、否応なく気分も上がってきますが、こういう時こそ浮かれ騒がず、次の本の執筆に力を入れるのが吉。浅学菲才の身には、努力あるのみだ! っつーことで、今日も元気に筆を執るといたしますか。皆さん買ってね~ ↓アメリカは自己啓発本でできている ベストセラーからひもとく [ 尾崎 俊介 ]こっちもね~! ↓14歳からの自己啓発 [ 尾崎 俊介 ]
April 3, 2024
コメント(0)
-
四股を踏む
最近、「四股」がマイブームでして。 もう長い事古武道をやっておりますが、今一つ、壁を乗り越えられないような気がして、あれこれ試行錯誤する日々なんですが、その中で、「体幹がしっかりしていないのではないか」と思うところがあり。 で、体幹を鍛える方法というのはあれこれあるわけですけれども、私の性格なのか、ピラティスによるものはどうも飽きてしまって、長続きがしない。 で、思いついたのが「四股」。相撲は日本の古武道だし、柔術とも通じるところがあるのではないかと。 そこで調べてみると、あるわあるわ、YouTube に関連動画が沢山ある。 例えばこんな感じ。四股の踏み方四股の踏み方(2)四股の踏み方(3) あとね、四股を応用したダイエット法もありました。四股ダイエット こういうのをあれこれ組み合わせながら、このところ毎日四股を踏んでいるのですが、上手に踏むのはすごく難しい。でも、難しいのだけど、やっているうちに少しずつ身体がぶれなくなってくるところもあって、しかも短時間に相当、きつい運動ができる。普通の、いわゆるスクワットなんかより、よほどいいような気がします。 四股は日本古来の健康法。果たして柔術の技にプラスになるかどうかは分かりませんが、とりあえずしばらく、続けてみようかなと思っているワタクシなのでありました、とさ。
April 2, 2024
コメント(0)
-
新横浜にて「教授~ズ」再会イベント!
今日は、10年前に定年で大学を辞められたO先生と、2年前に辞められたK先生、それに私の三人で新横浜に集い、旧交を温めて参りました~。 かつて同じ大学に勤める同僚であったこの仲良し3人組は、最初は「助教授~ズ」というユニットを組んでいたんですが、一人、また一人と教授に昇任してしまったため、一番年下の私が教授になった時点で「教授~ズ」に名称変更し、相変わらず仲良くつるんでいたんですな。 それからO先生が定年を迎えられ、K先生も定年を迎えられ、大学に残るは私一人、という状態になりましたが、O先生が昨年、名古屋の家を引き払って横浜に移られたため、今回、三人でこちらで会おうということになりまして。私はもともとこちらが地元ですから、春休み中はこちらにいるので、K先生だけ、わざわざ名古屋からご参加ということで。 で、O先生にお会いするのは2年半ぶりかな? 最初、杖をついて登場されたO先生を見て、あらあら、ちょっと寄る年波が…と思ったけれど、話をしているうちにどんどん昔通りの印象に戻ったのでほっと一安心。 K先生は、O先生に直接お目にかかるのは本当に久しぶりだったので、根掘り葉掘り、近況を聞き出していましたけれども、それによると、O先生もいろいろなご事情があって、なかなかにご苦労をされているご様子。まあ、若い内には想像もできなかったような突発的な変化が、人生には起こるもんなんだなと。 でも、そういうこともざっくばらんに話せる元同僚がいるというのは、O先生にとっては、結構いい息抜きになったんじゃないかな。 ということで、今日は久々に仲良し同僚ユニット「教授~ズ」の再会ができて、とてもいい一日になったのでした。
April 1, 2024
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 人は見かけによらないのだ。
- (2025-02-18 08:22:25)
-
-
-

- ひとりごと
- You Are The Inspiration..♥
- (2025-02-18 06:47:55)
-
-
-

- 楽天市場
- 令和6年産 無洗米 あきたこまち10kg …
- (2025-02-18 22:50:10)
-







