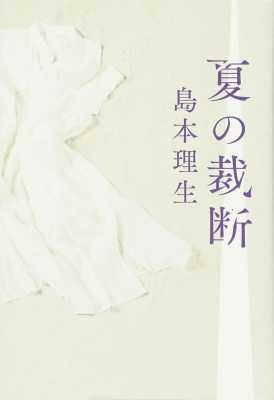2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年02月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
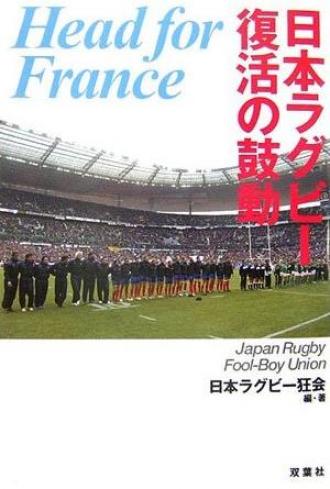
★ 日本ラグビー狂会編 『日本ラグビー復活の鼓動』 双葉社(新刊)
▼ 25日の日曜日、NHK総合は、ラグビー日本選手権を放映していた。 ポテトチップスを食べながら、白熱したスポーツ中継を眺めるのは、わたしにとって至福のひとときである。 しかし、その日はちがった。 スポーツ紙・一般紙では、トヨタ・東芝両チームの監督が、この試合で退任することを伝えていた。 なによりも、トヨタの総監督、朽木英次の老けた顔に、時の流れの残酷さと、なんとも言えない感情がわきあがるのを感じた。 ▼ 朽木英次の現役時代。 それはもう、日本ラグビー史に残る名選手でした。 歴代ベスト15を選ぶなら、かならずCTBで選出されるくらいの大選手ですよ。 ▼ ラグビーの様に、肉体の「素の力」のウェートが圧倒的な競技では、白人・黒人などには、勝てっこありません。 そんでも、戦術と技術でなんとかギャップを埋めて、欧米列強諸国と互角に戦う …… 細かいことは省くけど、早稲田出身の大西鐵之祐は、日本オリジナルのラグビーを創造した。 1968年、オールブラックス(ニュージーランド)Jrを屠り、1971年、イングランド相手に「3-6」まで追い詰める。 ▼ 徹底したフィットネスで、集散の早さによるディフェンス。 消耗戦を回避するため密集から遠い所で勝負。 必殺のサインプレーで、トライをうばう。 そんな日本オリジナルの戦術を遂行する鍵は、バックス、とくにCTBのパス能力にあった。 現役時代、朽木英次は、ハードタックルによるディフェンスの素晴らしさだけでなく、芸術的なパスをとばす選手だった。 そんな日本オリジナルな戦略を遂行するキーマンだった。 1989年、日本が欧米列強に唯一勝ったスコットランド戦を始めとして、数々の栄光に彩られた選手だった。▼ でも、僕にはもう、彼のプレーを思い出すことができない。 今も思い出せる朽木英次のプレーは、1996年1月、「トヨタ-三洋」の社会人選手権準決勝で、必殺のパスをとばそうとしたとき、トンガの怪物、セミイ・タウペアフェのタックルで吹っ飛ばされ、こぼれたボールを拾われて独走トライを奪われたシーンのみ。 よりによって、肉体的格差を埋めるため鍛錬を積み重ねた技術が、圧倒的な肉体を前にして、木っ端微塵に粉砕されたシーンしか覚えていないのだ。 ▼ そういえば、この頃までは、バブルがはじけても「残業が減って良かった」などの、のほほ~んとした空気が支配的だった。 グローバル・スタンダードにジャパン・オリジナルが木っ端微塵に粉砕された、あの1シーンは、前年(1995年)のラグビーW杯における「17-145」のカタストロフィ的大敗北もあいまって、「失われた10年」をビジュアル的に表現してくれていた。 ある幸福な時代の終焉を確かに告げていた。 だから、僕は忘れられなかったのだ。 以後、坂道を転がっていくかのような日本社会の荒廃と凋落ぶりは、あえて語る必要もあるまい。 私にとって、朽木英次の敗北と引退とは、日本がグローバルスタンダードの前に敗れ去ることと同義だったような気がする。 ▼ 閑話休題。▼ パスを出せるCTBは、朽木英次を最後にして、日本ラグビーから絶滅した。 あの難波英樹(相模台―帝京)がトヨタにくる! それを聞いたとき、朽木英次が手ほどきをして後継者になってくれれば、と心から期待した。 しかし、結局、芸術的なパスを出せるセンターにはなれなかった。 もはや、日本オリジナルなど、どうやっても遂行できやしない。 いつのまにか、私はラグビーを見るのをやめていた。 本当に久しぶりにみた、ラグビーの試合だった。 ▼ 敵役、東芝の薫田真広監督もまた、日本ラグビー史に残る名フッカーだった。みなさん、本当にご苦労様でした。▼ 前ふりが長くて申し訳ない。 そんで本書。 もう15年近く、毎年1冊、日本ラグビー狂会(Japan Rugby Fool-boy Union)の名義で、日本ラグビーについての本が刊行され続けている。 たいへん、ありがたいことだ。 この本も、久しぶりに買ったが、あいかわらず、火をふくほど熱い、ジャーナリストの憂国というか、憂「ラグビー」の熱情が伝わってくる。▼ あいもかわらず迷走する日本ラグビー界。 エリサルド日本代表監督は、フランス・クラブ・チームの監督を兼任するというなめた態度をとっているのに、何もできないラグビー協会。 希望の星だった宿沢広朗の死。 そこに世界的なラグビーの巨人、ジョン・カーワンが、日本代表監督を引き受けてくれたことで、やっとこさ、まともなラグビーになってきたようだ。▼ 中尾亘孝は、2015年W杯招致を唱え、梅本洋一は2007年ラグビーW杯のホスト国、フランスの現状を報告。 時見宗和は、早稲田黄金時代を築いた清宮監督の後釜、中竹監督が主将だったときのインタビューを掲載。 生島淳は、鹿島アントラーズの社長、大東和美にインタビュー。 わたしは、同姓同名の別人かと思ってた。 まさか70年、早稲田日本選手権優勝時の主将本人だったとわ ……。 「ラグビー畑でつかまえて」は、人気がないスポーツであるはずなのに、マスコミや政界などに強力なコネがあるため、やたら発言権があるラグビー界の人脈図として見れば、かなり面白い。 ▼ とはいえ、今年のW杯で2勝をあげるのは、いかにカーワン監督とはいえども、本当に難しい。 期待度は、マイナスからの出発。 ジーコ・サッカー代表監督とはちがい、監督としての実績はあるものの、なにぶん、選手に足りないものが多すぎる。 カーワンは、オシム代表監督のように、「日本代表を日本化する」ことを唱える。 しかし、朽木英次の後継者は、もはや地上にはいない。 走れてパワーがあるロックもいない。 ゲームをコントロールできて、ディフェンスができるスタンドオフもいない。 てか、キッカーは、だれよ。 FB有賀か?? 個人的には、日本代表のFBのディフェンスの弱さこそ、日本が勝てない原因の一つに思えます。 キックを蹴られるたびに、わたしゃ、恐怖なんですが … 戻りも遅いし、走れないし。 ましなFBはおらんのか。 ▼ そういえば、最近、中尾亘孝氏の本が4年近く出ていないけど、なぜだろう? やっぱり売れないんでしょうか。 かれの本は、毎年買っていたんだけどなー。 ブログがあるそうなので、いってみよ。▼ また、ラグビーW杯の季節がやってくる。 さまざまな思いが去来する。 ラグビーはやる分にはともかく、見るには本当に面白いスポーツです。 一度、このような本をお取りになって、ラグビーの試合にテレビのチャンネルを回してみてはいかがでしょうか?評価 ★★★☆価格: ¥ 1,785 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Feb 27, 2007
コメント(0)
-

★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について 発動編
▼ こんなひどい教養番組になるとは、思わなかったわ。 ▼ むろん、『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』のことよ。 本編見ながら、笑い転げた挙げ句、表情が凍り付いてしまったわ。 まさか、まさか。 まさか、こんな結末で、「歴史が動いた」ことにされてしまうなんて… まったく予想だにしなかった。 さすが、NHK。 一昨日の予想をさらに上をいく、すさまじい番組。 よくも、これ、放映できたものね。 恥を知らないとはこのことだわ。▼ 日露戦争のとき、野呂景義が八幡製鉄所を再開させたお話は、まだ良かったわ。 高炉内の仕組は、とても分かりやすかった。 野呂が、きちんと高炉の設計上の問題と、コークスの弱さを指摘したことが描かれていたし。 本当は、1880年代の工部省釜石製鉄所における、在来たたら製鉄と近代製鉄の技術選択に苦悩したことこそ、伝えて欲しかった。 また、官営八幡製鉄所の「溶鉱炉」を再開させたところで、質の低い銑鉄しか出てこなかったことも抜けおちているんだけど、まあ良しとしましょ。▼ 問題はそれ以降なのよ!!! 全体として、「技術立国日本のあけぼの」でもないことは、一昨日のをみれば分かってくれたと思う。 もう忘れかけているけど、あまりにひどかったので、5点ばかり指摘させていただくわ。 ▼ 問題の所在を勘違いしている、佐木隆三の発言 だいたい、鉄の技術者・野呂景義は、現場の技術を取り入れて、なんて事実はどこにもないわ。 近代技術と科学的思考にもとづいて、前近代的職人的熟練を排除して、標準化された大量生産技術を確立していく過程こそが、工業化であり、そのシンボルが「官営八幡製鉄所」でしょうが!!!! 高炉設計やコークスの改善のどこに現場が入り込む余地があるのよ。 失敗しかしていないのよ?。 いったい、この人、どうして連れてきたのかしら? これでは、日本の工業化過程が、完全に誤解されてしまうわ。 教養番組にまったくならないじゃない!▼ 無意味な八幡製鉄所の研究員たちのインタビュー 元八幡製鉄所の研究員で、鉄道レールの国産化に邁進した人物と面識のある、90歳代の生き残りのお爺ちゃんにインタビューしていたわね。 番組では、オリジナル性が研究で求められたことを言わせてる。 結局、何がオリジナルなものだったのか、技術に関する説明がとうとうなかったことをあわせると、「おじいちゃんの技術開発部署における雰囲気の証言→日本オリジナル技術」と誤解させたいのかしら。 本当に悲惨な番組よね。 人をなめないで欲しいわ!!!ぷんぷん!▼ 番組のウソ 野呂景義は、鉄道レールの破損の原因を とっくに知悉していた?!! この番組は、1923年、野呂景義が関東大震災で死んだので、1922年前後、鉄道レールが破損する事件相次いだ原因の解明は、弟子に委ねられた、とされているわ。 そして、弟子はレールが壊れた地域を回って、詳細に分析。 イギリス製のレール鋼材が壊れていないこと、寒冷地でレールが壊れていることを発見。 イギリス製のレールを切断したら、日本製レールとちがい、粒子が均一だった。 そこで、粒子を均一化される技術をみがき …… という筋書きになっていたわ。 真実なら、お涙頂戴ものかもしれない。 しかしね。 1919年、官営八幡製鉄所が「低珪素銑・塩基性平炉鋼」生産を始めるまで、官営八幡製鉄所の鉄道レール生産は、「低燐銑・酸性転炉鋼」を素材にしていたのよ。 しかも、大量に燐をふくむ、中国の大冶鉄山から入手した鉄鉱石を使い、おまけに燐除去技術がまったく不十分なままでね。 ところが、燐が0.1%以上含まれると、酸性鋼は脆くなってしまうわ。 寒い地域では、「冷間脆性」によって、レール折損することが広く知られていたのね。 ところが、当時の鉄道省のレール規格では、燐含有量は0.12%までOK。 八幡製鉄も、基準ギリギリのレール鋼材しか、作れなかった。 野呂景義は、しばしば燐分が0.15%にもなる鉄道レールが、とんでもない代物で、早急に生産の改善が行われなければならないことを語っているのよ。 1919年、八幡製鉄所では、「低珪素銑・塩基性平炉鋼」生産が始まった。 そして、1927年、酸性転炉鋼(ベッセマー転炉)生産が打ち切られた。 これは、とうとう、八幡の技術者が燐除去技術を開発できなかったのね。 なにがオリジナルよ。 1922年~23年頃、頻発したという、破損事故。 1918年まで続けられていた、多燐の酸性鋼鉄道レール生産。 始まって3~4年の塩基性平炉鋼レール生産。 塩基性平炉鋼レールによる破損事故と、酸性転炉鋼レールによる破損事故。 いったい、どちらが多いのか、考えてみたら誰だってわかるはずじゃない。 前者の事故原因なんて、とっくに知られていたわよ!!!▼ 結局、何がオリジナル技術なのか、さっぱり分からない番組構成 だから、野呂景義や弟子たちが知らなかった鉄道レールの破損原因とは、後者の「塩基性平炉鋼レール」についてなのよ。 実際、番組では、日本産のレールとイギリス産のレールの、切断面を比べていたでしょ。 日本は、粒子が集まっていたのに対して、イギリスは粒子が均一だったよね? 手の込んだ成分調整をする必要がない酸性鋼に対して、塩基性平炉鋼は、手の込んだ成分調整や化学反応をさせなければならない製鋼方法なの。 塩基性平炉鋼は、軟鋼で圧延に向くんだけど、これでは鉄道レールにまったく向かない。 だから、おそらく、炭素を浸透させて、硬度を高めることを行ったはず。 だけど、浸炭技術がいまいちで、圧延工程も未成熟。 そのため、粒子が均一になる鉄道用レールを作ることができず、破損事故が相次いだのね!! ところが、そのとき「歴史が動いた」って言いながら、どんなことをやって乗りこえたのか、まるで語らないのよ!!!! いったい、何なの?これ。 どうみても、番組として成立していないじゃない! 何がオリジナルなのよー!!!!!! キー!!!▼ 1929年の鉄道省の新レール規格の施行が、「そのとき」??? そんで、いきなり、番組最後で持ち出されるのが「鉄道省の新レール規格」。 「そのとき」は、1930年1月とされているが、どのようなことが起きての「そのとき」なのか。 最後までとうとう説明されない!!!!! …… いったい何よ、これ。 この日付は、レール規格の施行日な訳? 呆れ果てて言葉を失ったわ。 番組によれば、世界最高品質のレールを日本が作れて、国産化達成できてメデタシメデタシらしいわ。 たしかにこの頃の重軌条(レール)生産は、八幡製鉄がほぼ独占していたけど、特殊軌道のレールは、海外から輸入していたわ。 ナレーションは、若干不正確ね。 おまけに日本には、「低珪素銑」を作る技術も後れていたし、「低珪素銑」は、インドを中心に、相変わらず、海外依存していたわ。 本当にいい鋼材を作るなら、良い原料銑はかかせない。 鉄道レール国産化を言いたいなら、良質な鉄道レールを作るのに、官営八幡製鉄所がインド銑鉄に依存していなかったことを証明しないといけないんじゃないかしら? むろん、番組はなにも語ってくれない。 ▼ フィナーレ 「技術後進国日本」をわざわざ宣伝する爆笑モノの映像ナレーション この番組、「そのとき」の解説のあと、ナレーションが続くわ。 戦争のあと生き残った八幡製鉄所は、戦車などの軍需兵器を溶かして、平和に役立て戦後復興を支えた……。 鉄製品を溶かしている映像が出て、私は笑いが引きつってしまった。 結局、スタッフは、何も製鉄のことを分からずに作っているらしい。 だって、このシーンは、日本最新鋭の「銑鋼一貫生産」を誇ったはずの八幡製鉄所が、実は銑鉄設備が不十分で、「銑鉄・屑鉄」を海外に依存していたことを赤裸々に言っているんですもの。 実際、八幡製鉄所は、膨大な銑鉄・屑鉄を蓄積するための区画が、敷地内に設けられていたわ。 戦車にしても、武器にしても、そこに集められ、平炉の中に入れられたんでしょうね。 敗戦直後、銑鉄生産量と鋼鉄生産量は、「1:2」を上回り、「1:4」の年さえあったわ。 たしかに、最新鋭を誇っていた八幡製鉄所が、熱経済の面で圧倒的に優位な、「銑鋼一貫生産」を完成できなかったのは、歴然たる事実かもね。 でもさ、こんなナレーションと映像を流して、どこが「技術立国 日本のあけぼの」なのよ? ウソをつくんなら、最後までつき通しなさいよ。 「技術後進国 日本のシンボル」として、八幡製鉄所の遅れていた部分をわざわざ宣伝して終了。 いったい何なのよ、これ。 八幡製鉄所、さらしもの? ノータリンというか、最後で破綻しているじゃない。 いったい、だれが監修したのさ。 責任者でてこーい。 もはや処置なし。 もうNHKには、絶対、受信料を払ってはいけないようね。NHKふざけんな!と思う人はクリックお願いします↓↓↓↓↓↓↓ ←このブログを応援してクリックしてくださいませ今のブログ順位
Feb 23, 2007
コメント(2)
-

★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について (旧・建設予定地) 接触編
▼ みたみた?本日の番組紹介欄。 NHK総合で、こんなことやるらしいの。 本当に大丈夫かしら。次回の『その時歴史が動いた』は…鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~ 放送日 平成19年2月21日 (水) 22:00~22:43 総合 ゲスト 佐木 隆三(さき・りゅうぞう)さん(作家) 番 組 内 容 その時 … 昭和5(1930)年1月 出来事 … 鉄道レールの輸入が終わりすべて国産化された イギリス、ドイツ、アメリカなど、鉄を制した国が近代国家として胸を張れる時代に、明治政府は国家の威信を賭けて福岡県八幡村に官営製鉄所を建設する。しかし当初の製鉄技術は海外の設備と技術者をそのまま持ってきた「鉢植え」の技術。日本の原料や燃料に合わず、日本人技術者にも使いこなすことができなかった。巨費を投じた溶鉱炉は鉄を作れないまま、停止されてしまう。このままでは日本は文明国の仲間入りができない…。その時立ち上がったのが、鉄の技術者・野呂景義とその弟子たちだった。彼らは徹底した現場へのこだわりと調査で、海外から移入した技術を日本の風土に合わせて改良・改善していく。やがてようやく日本の近代製鉄は軌道にのり、課題であった鉄道レール作りが始まる。しかし野呂亡き後、国産レールの破損事故が相次ぐ。野呂の教え子たちは技術者としてのプライドを賭けて、鉄とレールの質の向上に心血を注いでいく。そしてついに日本は借り物だった製鉄技術を我が物とした。技術者たちが鉄とレールの国産化に挑む道のりを通して、のちの技術立国・日本につながる日本オリジナルの「技術力」誕生のドラマを描く。▼ 「“あるある大辞典”納豆捏造事件」のNHK版、っぽいわよねー。 番組見ていないうちに語っても仕方がないんだけど、 いったい、何がやりたいのかしら。▼ 銑鋼一貫生産を目指した官営八幡製鉄所。 でも、燐の含有量が低い鉄鉱石にめぐまれず、高炉から良質の銑鉄(原料銑)が生産できなかったわ。 だから結局、八幡製鉄所にあったベッセマー転炉は、1927年に廃止に追いこまれてしまう。 これによって、酸性鋼 ――― 燐・硫黄がない鉄鉱石に限られるけれど、機械や兵器生産にむいた良質の鍛鋼・鋳鋼ができる ――― の大量生産技術は、日本から消滅してしまうのよ。 日本では「低珪素銑 塩基性鋼」 ――― 燐/硫黄はたくさんあってもいいけど、珪素があってはダメ、軟鋼だから圧延鋼材・高張力鋼に向く ――― のみになってしまい、それすらも一貫生産体制を築けなかった。▼ となると、銑鉄や屑鉄は、輸入に頼らざるをえなくなってしまうわ。 「スウェーデン鋼」とか聞いたことないかしら? 日本は銑鉄は、酸性銑をスウェーデンやイギリス、低珪素銑をインドから輸入せざるをえなかったのね。 この銑鉄部門の低生産性は、「一貫生産」ではない、単独でマルチン平炉による小規模「塩基性鋼」部門の出現とあいまって、戦前の日本製鉄業の足かせになるわ。 ▼ とにかく、銑鉄生産が弱いのに、鋼鉄生産だけは盛んなの。 武器にしても、鉄道レールにしても、国家が欲しがれば欲しがるほど、銑鉄生産技術の弱さが、どうしても致命的欠陥になってしまうのよね。▼ たとえば1941年、「ABCD包囲網」で、日本が追い詰められたときを思い出してみて。 その中に石油輸入だけじゃなく、「屑鉄の輸入ができなくなった」ことを記憶している方、いるのではないかしら。 何の意味があるのか、分からなかった人、絶対いるでしょう。 ▼ 実は、タネを明かすと、これが原因なのよ。 日本では、銑鋼一貫生産は結局、完成できなかったわ。 だから製鋼業者は、屑鉄と銑鉄を外国から買って、それらをまぜて「塩基性平炉」に入れて、鋼鉄生産していたの。 日本鋼管とか神戸製鋼とは、そんな業者なのね。 ▼ 当然、1930年1月には、本来「何もおきていない」し「動いても」いないのよ。 というか、1930年頃の日本の銑鉄生産量は、たしかアメリカの2~3%よ。 借り物からの脱却、ってどうみてもインチキだわ。 だいたい、鉄の国産化は達成されていません。 あきらかに捏造でしょう。 ありもしないものをどうやって「動いた」としてデッチあげるのか。 これくらいしか、楽しむ方法が、ないのよねー。▼ いったい、どんな事例をあげて動いたことにするのかしら。 何個か、考えられないことはないわね。▼ 番組案内には、野呂景義の弟子たちの苦労なんてあるわ。 それなら、のちに日本鋼管の社長にもなった、今泉嘉一郎の「日式トマス転炉」 かしら。 たしかにオリジナルなものよ。 でも、これって、ドイツ・ヘルデ製鉄から直輸入したトマス転炉の改良版だわ。 おまけに、日式トマス転炉を作っても、上流部門 ――― 原料銑(低珪素銑)生産部門 ――― にますます負荷をかけるだけよ。 それでなくても日本では、低珪素銑だってまともに作れなくて、鋳物銑になっちゃうというのに。 それに,日本鋼管の日式トマス転炉の稼動は、1938年から。 とても、1930年1月の「そのとき」にはならないわよね。 ▼ それとも平川良彦を中心とした、低珪素銑製造方法の改革をあげるつもりかしら。 でも、どうして鉄道レールといった鋼材が日本でできなかったのかといえば、たんに技術が未熟だったからにすぎないわ。 ▼ だいたい、低燐で酸性銑をつくるベッセマー転炉なのに、それにあわない中国の鉄鉱石で銑鉄をつくろうとしたのよ? これですめば良かったけれど、八幡製鉄所は、ベッセマー転炉で消費しきれない銑鉄を、塩基性平炉にいれて鋼鉄生産していたわ。 できた鋼材は、どんなものになるか、想像付くでしょう? 酸性鋼でも塩基性鋼でもない、ただの「不良品」よ。 現実は、1924年頃まで、低珪素銑と低燐銑の区別を知らなかっただけなのよ。 ひどい出来のため、鉄道省も陸海軍も困り果てたわ。 だから、軍艦や兵器でさえ、銑鉄をわざわざ輸入して作らなければならなかったのよ。 1924年以降、八幡製鉄所では、低珪素銑・塩基性平炉鋼の組み合わせによる、銑鋼一貫体制が完成するけど、平川良彦の研究は、この路線の上にのって、進められたものなのね。▼ もともと、野呂景義の弟子である平川良彦は、高炉操業が手探りの状況であった1910年代、「鎔解層」なる概念を提示した人なの。 とくに、鉱石とコークスの配合方法をかえることで、「生鉱降り」現象をなくして、有名になった技術者。 たしかに、面白い研究をしているのよね。 それも大規模な実験装置をわざわざ作って何度も試験を繰り返す、今の科学そのものを感じさせるやり方で。 ▼ 八幡製鉄の銑鉄部門は、彼の手によって、1920年代を通して、高炉の操業方法がどんどん改善されていくわ。 高炉冷却水の海水使用で、鉛管を使うことを余儀なくされる羽口を、「アルミニウム製」にしたりね。 アメリカやドイツでは、1000トンの銑鉄が生産できる高炉が主流の時代に、200トン規模の高炉しか作れなかったことを除けば、かなりのことをやっている技術者なのね。▼ 一番有名なのは、「鎔解層アーチ説」と、それによる適切な高炉の形の≪原理的解明≫ね。▼ 欧米では、「朝顔の位置を低く、その角度を大きく、湯溜の径を大きく」という、高炉建設の3条件は、広く知られていたわ。 しかし、経験で練り上げられたもので、理論的背景が分かっていなかったのよ。 欧米と日本は、鉄鉱石の品位、コークスの灰分と硬度、操業方法がちがう。 だから、日本の技術者は、どのようにするべきか、分からなかったのね。 それを日本でも適用・援用できるように、原理的裏付けを明らかにした人なのよ。 かれは、日本における「低珪素銑製造法」を明らかにして、鉱石・コークスはどのようなものを使い、どのように装入したらいいか、適切な送風方法・温度・圧力、などを詳らかにしたわ。 職工の勘や技能ではなく、理論的操業方法を明快にして、完成させた人なの。 平川良彦は、良い技術者だわ。 会社が与えた状況の中で、最高の選択肢をえらびだし、それを理論化したわけだから。 ▼ ただ、これをもって「歴史が動いた」というのは、明らかに行きすぎよね。 ▼ だって、経験的に知られていたことで、技術自体、かれのオリジナルでもなんでもないわ。 それに、平川良彦の理論にもとづいて八幡製鉄所の銑鉄生産が始まるのは、1930年の2月。 平川理論採用なんかよりも、絶対、八幡製鉄の銑鋼一貫体制の建設の方が重要でしょうに。 やっぱり平川良彦でもないのかしら。▼ それにしても、NHKの番組案内は、読めば読むほどひどいしろものよね。 近代技術の定着は、「日本の風土」が阻害していた訳じゃないわ。 そもそも科学の問題じゃない。 だいたい、競争力のある低珪素銑鉄の大量生産は、戦後にならないと実現しませんよ。 どれをとっても捏造の臭いがするのよね。 どうみても、針小棒大にされそうよ。 ▼ どのようなお話になるか、確かめてみなくちゃ。 みんなも、変な話になってるかもしれないので、確認して欲しいわ! ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Feb 21, 2007
コメント(9)
-

★ 安田 敏朗 『「国語」の近代史―帝国日本と国語学者たち』 中公新書 (新刊)
▼ 最近、忙しくて、読んだ本の紹介がなかなかできない。 基本的にバカバカしい本は、採りあげないことにしているんだけど、それでも本がたまる一方なので困ってしまう。 所詮は、本の備忘録ブログ。 気を取り直して、面白い順、タメになった順番で、じんわりと紹介することにしよう。▼ 最近、面白かったのは、コレ。 国民国家の統治システム(「配電システム」by ベネディクト・アンダーソン)のインフラであった、「国語」の機能及び問題を描きだし、批判的に暴いていく。 国家的課題に答えようとした、国語学者たちの歩みを追うことで、ナショナリズムとしての「国語」を描き出そうとするのだ。▼ みんなも分かってるとおもうけど、「話し言葉」は、地域差・階級差がある。 しかし、その反面、「書き言葉」もある。 では、いったい「国語」とは、どっちなのか。 江戸期以降、明治期も、「漢文訓読体」で実質統一されていた書き言葉。 「書き言葉」のような「階層性」をもたない、それでいて「話し言葉」のような「自然さ」を持った、創造された「言語」。 国民国家に必要な、均質で単一、という条件をかねそなえ、「書いても聞いても」分かる言語。 「誰のものでもあるけれど、結局、特定の階層のもの」。 それこそが「国語」に他ならない。 だからこそ、「日本語ローマ字化」(GHQの一部)どころか、「英語」(森有礼)でも、「フランス語」(志賀直哉)でも、本来、別段、かまわない。▼ だから、欧化政策でも、国粋保存・教化政策でも、「国語」は「手段」として、不可欠である。 しかし、抑圧的とおもわれないためには、「歴史的に話されてきた」ことを偽造する必要がでてきてしまう。 だからこそ、「空間的同一性」のみならず「歴史的同一性」が必要であり、それが、歴史・民族・伝統・文化といった言説を繁茂させる原因となるらしい。 方言も、「国語」を歴史的に構成してきたものの一部とみなされ、国語を不可分に構成する位置づけが与えられる。 そうした学問の性格は、東大・京大に続いて人文系学部がおかれ、言語・歴史・文化に関する講座が開講された帝国大学とは、京城大学と台北大学であったことと無縁ではない。 ▼ 明治初期の「啓蒙」の段階をへて、日清戦争をすぎると、統一された「国語」への欲求は、たいへんな高まりを示すことになった。 官主導で「国語」を創造することが決められ、「話し言葉」に即した仮名遣いを決めたものの、「歴史」の強調と、「現実的要請(=空間的同一性?)」のハザマで引き裂かれ、1年で元に戻されたこともあったようだ。 こうした「国語」を支えたものが、「国語学」。 「国語は、国民の精神的血液」(上田万年)。 国語とは、科学であるとともに「新国学」であったという。 ▼ 植民地では、日本よりも先に、国語は誕生して、「配電システム」を構築していった。 文字による意思疎通だけでなく、話させること。 とはいえ、国語と方言の暴力的関係が再生産されるだけ。 どれだけ喋ることができても、植民地人は、決して「真の日本人」にはなれなかった、という。 ましてや「国語は国民の精神的血液」ならば、なおさらであろう。 学ぶべきは、本来、朝鮮語や台湾語ではないのか。 時枝誠記は、言語を心的過程・表現行為とする「言語過程説」をとなえ、過程を成立させる「社会」を主体とし、朝鮮語に対する国語の「価値」の優越を説き起こすことで、その疑問を封じこめる。 それは、朝鮮人は自発的に国語に参入せよ、という議論になってしまう。 ▼ 「国語」ではない、「日本語」が誕生するのは、1930年代であるという。 比較言語学、歴史重視の手法にこりかたまった「国語学」では、現代日本語の分析や、西欧言語学の輸入などに邪魔になってきたことだけが原因ではない。 この時代、東亜全体の普通語・共通語として、日本語を普及させることが、要請されてきたため、である。 国家により通用性が保証される「国語」とはちがい、「普遍性」をもたせる ――― 普遍性を獲得させて拡大化させる、「国語の帝国化」現象 ―――― ことで国家の境界線を越える。「日本語」がもとめられていたらしい。 。 しかし、この動きは、遅々として進まない。 植民地では、国語教育として「躾が重視」され、バイリンガリズムの解消を目指した強力な「皇民化教育」が施される一方、軍政現場では、「日本語教育」として、「満語カナ」「基礎日本語」など簡略化されたものが流布させた。 この2重構造は、敗戦で崩壊する。▼ 現代「日本語学」の始まりは、文語・漢語のない、汚染されていない「日本語の健康化」を主張して、音声言語としての日本語の理法を目指していた、佐久間鼎にあるという。 そのとおり。 実は、戦前と戦後は、決して断絶などしていない。 戦前的ありようが清算・総括されることなく、「言語統制」が「国語民主化」に名をかえて、合理化・簡素化が推し進められた。 だから、「配電システム」としての国語が問題視されることはなかった。 その一方、戦前との断絶もたしかに存在する。 それは、外部=植民地の喪失を反映したためか、すべて「内向きの議論」だったことである。 「日本語=日本民族」の等号は、ここに成立した。 国語にこめられた「歴史」「民族性」神話は、そのまま現在まで続いている。 現在、国語学・日本語学は、政策決定に関与していないが、戦前について何も総括していない。 筆者はどこまでも手厳しい。 ▼ 台湾的「国語」。 比較を通して科学的な国語学を普及しようとした上田万年。 言語学者がどのように国民国家と共犯であったか。 個々のエピソードも豊富で、なかなか楽しめてよい。 植民地における国語教育は、教員の出身地の方言が混じっていた。 そのため、生徒たちから、「先生の言葉はみんなウソです」としばしば批判されていたのは、なんともいえない苦い感情を引き起こすだろう。 戦後韓国に残した大きな傷跡は、日本語の語彙の残存などではない。 それは、「配電システム」を残したことで、対抗的「配電システム」が形成されたことなのだ ……… 戦後、方言採集の手法から国語論までコピーして、「民族=言語=文化」的国語論の再生産がおこなわれた韓国。 「言語・規範・ナショナリズム」のトリアーデによる言語ナショナリズムは、言語を通して思考枠組まで刻印し、始原を隠蔽する……どこまでも容赦がない。▼ なにより衝撃的なのは「敬語」「女性語」は、20世紀に登場した「発明」にすぎないことであろうか。 もともと「身分制社会システム」の言語的現われにすぎない。 それが、身分の消滅の後になって、対象化され意識化され、「日本の美徳」なる意味不明な位置づけが、与えられたらしい。 正しい表記をできた日本人は、戦時中で、わずか23%の寂しさ。 西欧近代にアプローチするための手段、大衆の欲望をかきたてるファッションに過ぎなかった日本語、という、近年の植民地における日本語を低くみる潮流に対しても、筆者は批判的だ。 曰く、国語による「同化」の暴力性とは、「欲望」の転化ではないのか、バイアスがかからずに手段として利用できるのか、と。 また「声に出して読みたい日本語」のような動きについてもメッタギリにされている。 曰く、「書き言葉」を読ませることは、「話し言葉」と「書き言葉」の乖離を促進させ、「書き言葉」の特権性への回帰に過ぎないのではないか、と。 国語がどうして、「国家愛」と結びつく必要があるのか。 なによりも、「言語はわたしのもの」ではないのか、という提起は、なかなか面白いものがあるだろう。▼ 全般的に大変示唆された本で、ナショナリズムと言語について、これ以上の入門書兼学術書は、望みようがあるまい。 高く評価させていただいた。 今はただ、「言語はわたしのもの」の「わたし」とは、いったい何ものなのか。 そして、言語を注入され「思考枠組」が刻印されることは、古来から人間としての「与件」ではないのか、とだけ問いかけておきたい。 たとえば、『神聖喜劇』。 膨大な日本の近代詩歌、短歌、俳句、漢詩群の芳醇さにふれたとき、これほど日本人として生まれた喜びを感じたことはなかった。 「刻印」を施してくれたものに、私は心より感謝した。 ▼ 「言語はわたしのもの」といったとき、真っ先に失われるのは「わたし」ではないのか。 その懸念がぬぐえない。 評価 ★★★★価格: ¥ 924 (税込) ←このブログを応援してクリックしてくださいませ
Feb 19, 2007
コメント(1)
-
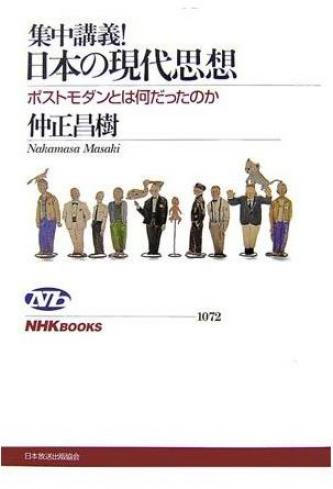
★ 仲正昌樹 『集中講義!日本の現代思想』NHKブックス(新刊)
▼ 小熊英二『民主と愛国』に関する星の数ほどあるレビューの中でも、あまりの最低さに吹き出しそうになったものは、読売新聞編集委員が執筆したものをおいて他にはない。 曰く、「保守思想の動向がほとんど触れられていない」▼ 保守思想家といえば、小林秀雄、江藤淳、福田和也……数だけは、一応、あげることができるだろう。しかし、彼らには、いったいどのような違いがあるというのだろうか。 まあ、「目的」なき所に、歴史叙述など生まれようもないわけで、ほとんどイチャモンだよなー、と思った次第。▼ それはそうと、『月刊 仲正昌樹』状態と化して、年間10冊以上も本を出す、いささか粗製濫造気味の仲正昌樹氏。 今回の本は、ポストモダン思想の解説書だ。 なかなか良い本を出されている。▼ 1980年代、脱体系化・脱中心化を図る思想として、一世を風靡した現代思想。 学問間の相互乗り入れと脱アカデミズムも実践は、なかなか回答を出さないそのスタイルもあって、不真面目な思想とおもわれがちであった。 また近年、価値観からの解放、ライフスタイルの多様化などのポストモダン的状況に疲れ、経済的条件の悪化もあいまって、現代思想は急速に流行らなくなってしまった。 今では、何それ?食べられるの?てな感じである。 そこで、日本の戦後思想を俯瞰した上で、現代思想の何を後世の遺産として残すべきか、考えてみたのだという。▼ 1章は、「空回りしたマルクス主義」。 ドイツ・フランクフルト学派とは違って日本のマルクス主義は、倒すべき敵であるはずのアメリカから、学問の自由など、戦後民主主義が与えられたという事実について、深く考えることはなかった。 そのため、資本主義のイデオロギーを最後まで批判しきれるのか。 批判しているつもりでイデオロギーの再生産に寄与してはいないか?について、思考することがなかった。 「マルクス主義」を掲げたまま、ラジカルではないという意味しか持たぬ「市民派」の仮面を使い分け、マルクス主義の内容が極めて曖昧になった。 高度成長は、マルクス主義革命を何の必然性のないものにかえ、職能的利害集団でしかない保守の前に空転をくりかえし、マルクス主義を空疎化させていく。 唯一、丸山真男だけは、西欧近代そのものを批判的にとらえ、疎外論的な問題関心も持っていたが、とりあえず西欧近代に適応することを説いた。 また、「理論の物神化」についても、西欧近代に内在する矛盾とは捉えず、日本における近代的思考の未成熟さにおいてしまった。▼ 第2章は「大衆社会のサヨク思想」。 「1968年」以降、世界では、旧来の2項対立図式で世界を描ききることは困難であるという哲学的認識が浸透して、カウンターカルチャーを活用して大衆に浸透しようとする動きが広がっていった。 しかし、日本の新左翼は、「美」によって資本主義的日常の中で見失った「真の自己」「主体性」を取り戻すことは考えても、「美」を通して見える「近代的主体の終焉」には関心を持たなかった。 彼らは「革命=目的=終焉」そのものを美学主義に表象する、「黙示録的革命主義」に走ってしまう。 広松渉は、ルカーチ以降、「疎外」「物象化(=呪物崇拝)」を同じようなものとしていたのに対して、すべての人々を拘束する「物象化=共同主観性」にこそ、シフトするべきだ、と説き、ポストモダンとの橋渡しをおこなう。▼ 第3章と第4章は、「ポストモダンの社会的条件」「近代知の限界」である。 大量消費社会の到来は、消費に絶えずいざなうべく、新たな差異=モノ=記号の産出による幻惑作用 ――― ベンヤミンのファンタスマゴリー(幻灯)論、「主体(精神)-客体(物質)」の対立において、主体を無意識的に規定にしているとする、記号論的パラダイム(ボードリヤール)への転換 ――― の支配する社会の到来である。 ただ、マルクス主義が象徴する近代哲学への挑戦であったポストモダン思想は、「構造主義VSマルクス主義」の構図 ――― 主体を無意識レベルで規定する「構造」を摘出して普遍的進歩史観を相対化する構造主義に対して、歴史の中での主体的な実践を重視するサルトル流の実存主義的マルクス主義 ――― が理解されず、1970年代まで日本では、「おフランスな思想」としての受容にとどまっていた。 文化人類学・精神分析という「人間を前提としない」領域から始まった動きは、「生権力」(フーコー)、構造主義の「構造」がなぜ発見されうるのか、その「構造主義」(レヴィ・ストロース、フーコー)の構造そのものを批判した、ポスト構造主義(デリダ)へと進む▼ 第5章と第6章は、「日本版『現代思想』の誕生」と「『ニューアカデミズム』の広がり」である。 マルクス主義者が居座った人文系アカデミズムに一撃を与えた人として、2名が採りあげられている。 バタイユを援用して「蕩尽する人間観」(人間もその対象内)へパラダイムシフトさせた栗本慎一郎。 蕩尽は象徴秩序が機能する社会でのみ可能。 「熱い社会」では、日常生活そのものが「蕩尽」化し、絶えず新しい差異が産出されて崩壊を先延ばししているだけにすぎない。 われわれは、エディプスの三角形が人々に強いるパラノ・ドライブから、「スキゾ・キッズ」として「逃走」しなければならない ――― いうまでもなく、浅田彰である。 とくに、文化人類学者の系譜が重要らしい。 山口昌男もそうだが、とくに中沢新一。 宗教的信念と、検証可能な合理的知識との区別を前提とした近代知の限界に挑戦する彼の試みは、東大駒場「中沢事件」を引き起こしてしまう。▼ 第7章と第8章は、「なぜ『現代思想』は『終焉』したのか」「カンタン化する『現代思想』」という表題がついている。 終焉したのは、フランス現代思想の中心が次々と死んでしまい、「近代の限界」の意義を認めない、英米の分析哲学にもとづく正義論・責任論にシフトしたからであるとされる。 また、唯一残された観のあるカルチュラル・スタディーズも、文化政治に限定されていて、「近代」そのものを否定していないため、いっそう現代思想は死んだ観がある。 また、不況による社会不安で、ベタな危機意識が復活。 そんな中で、「郵便的不安」は確実に増殖し、もはや「コミュニケーションを通した普遍的な合意に到達するのは無意味」というポストモダン的状況がますます強まってしまった。 ▼ そこに、ポストモダン左派がマルクス主義の退潮を埋めるように、進出しているのが現状であるという。 かれらは「ポストモダン的」であっても、「近代的思考枠組ではないもの」としての現代思想、という特色を持っているとは言い難い。 今の思想業界は、1970年代の「左右対決」に逆戻りした観があって、左の思想家のスター化&「水戸黄門化」&「知的権威低下」と、叩く相手がわからない右の迷走が、いっそう「カンタン化」スパイラルを促進させている。 あろうことか、どちらも「大きな物語」を作りはじめる始末。 今こそ、世界を切り分ける「道具」としての現代思想は有効である、として本書は終わる。▼ 保守の方が革新よりも新しい。 吉本隆明は、階級意識に還元できない、「共同幻想」の強さを指摘して、新左翼の教祖どころか、マルクス主義者ですらない。 「サルトル=レヴィ・ストロース論争」。 2項対立図式を免れて、純粋に真実を移し出せるエクリチュールは存在しない。 法も道徳も、「蕩尽」するために存在している。 面白い議論がどんどん提起されていて、飽きることはない。 ▼ ただ、問題はあまりにも多い。 ▼ 仲正昌樹の著作だけでなく、東浩紀にしてもいえるが、どうして哲学とか社会学を語る奴は、「歴史」をないがしろにするのだろう。 とかく、自分の知っている時代(=パラダイム)を特権化しがちな奴が多すぎる。 私的領域におけるエディプス的主体の再生産と、公的領域における労働主体=市民の再生産がうまく合致したため、資本主義を壊すことが不可能になったなどは、もろに「カンタン化」された議論としかいいようがない。 今現在、進行している、「脱社会化」「脱制度化」の現状をどうみるつもりなのか。 そもそも、仕事と家庭の性別分業が日本で成立したのは、団塊の世代以降、というのは常識に類する話だ。 近代日本においては、エディプス的主体や近代的な労働主体の形成は、1960年代以降にしか当てはまらないのであって、ただのバカ親父の妄言に過ぎまい。 ▼ さらに、何かといえば、得意気に持ち出す、「ポストモダンの左旋回」も、かなり疑問な概念である。 実際、柄谷行人以外、ポストモダンな人が旋回した例は、どこにも挙げられていない。 高橋哲哉にしても、もともと左の人ではないのか。 また現代思想は、本当にフランスから「直輸入」されたものとするなら、どうして日本では、「ラカン派精神分析」がそんなに影響力を持っていないのか。 ポストモダンの左旋回は、フランスではなくアメリカの影響とされるが、本当は「フランス現代思想もアメリカ経由で密輸されたもの」のような気がするのは僕だけだろうか。 実際、社会学では、1980年代、フーコーとアーレントが全盛であったが、それはアメリカで英訳されたのが、1980年代だったということと密接な関係がある(日本では70年代に翻訳されている)。▼ 何よりも、本書の致命的な弱点は、思想が押しなべて「つまらない」ものになっていることであろう。 頭の良すぎる人が、さらさらと整理してくれるため、一発で分かることは確かなのだが、戦後日本思想史の流れを知らなかった人は、こんなにつまらない思想しかなかったのか、と呆れかえるしかないだろう。 むろん、面白そうな人なのになぜか除外されている人も目立つ。 宇野弘蔵や大西巨人などは、その典型だ。 筆者が救出したいはずのポストモダン思想も、仲正昌樹の魔の手から逃れることができていない。 救い出して蘇らせたいポストモダンの精神は、「のりつつしらけ、しらけつつのること」だ、と言われて、ポストモダン思想を学びたい、などと思う奴がどこにいるのだろう。 そんな思想なら死んでもよい、と思うのが普通ではないか?▼ 仲正の書くモノは、とかく相手に内在しないため、異様に見通しはよくても、つまらなくなることが多い。 そんなことを百も承知、という人にすすめたい。評価 ★★★☆価格: ¥ 1,071 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Feb 9, 2007
コメント(2)
-
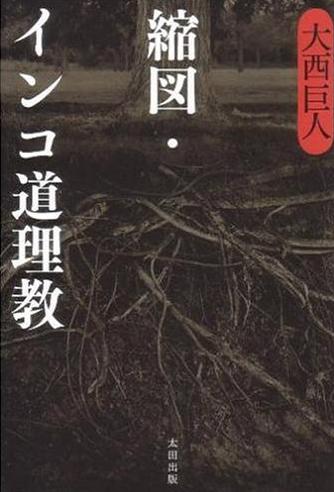
★ 大西巨人 『縮図・インコ道理教』 太田出版、2005年8月発行
▼ お会いしたこともないのに、勝手に「先生」と呼びならわして、私淑・傾倒している人は、みなさんにも何人かいるだろう。 私にもそんな「心の師」は、2名いる。 1人は由貴香織里先生、1人は大西巨人先生である。 ウソのような本当の話だ。 いや、マジで。▼ それで悪名高い本書を読んでみることにした。 読んでみた… 読んでみた… 読んでみた… … … … 何だ、これは!!!!!▼ 「AMAZON」の読者レビューのひどさは、ひろく知られたことだけど、誉めている奴をつるし上げてやりたいよ。 まったく。 てか、巨人先生を甘やかすのも、お前らいい加減にしろ!!。 可愛さ転じて憎さ百倍、であろうか。▼ そもそも、冒頭から不吉な予感が漂う。 いきなり、大西巨人の既刊小説から引用される一点からして、「堕落」の臭いを嗅ぎとれる訳だが、その予感は最後まで離れずに、とうとう、実現してしまう。 自作を引用してはいかんでしょう、大西先生。▼ なによりも、小説としても、完全に破綻しているのがイタイ。 母子草(御形)から始まる、樋口一葉の引用も、何ひとつ効果的ではない。 破綻を隠蔽するため、最後「題意」において、付け足しのように付け加えられるのは、以下の文章である。 大方の読者の中には、本編の表題『縮図・インコ道理教』を「インコ道理 教という宗教団体の縮図」と読解(誤解)した向きも、なかなかあるらし い。そのような人々は、『なんだ?インコ道理教のミニアチュアーなんか、 ほとんど書かれてないじゃないか!』その他肩透かしを食らったような 違和感的読後感を持ったとみえる。(中略)。そもそも、本編の表題は、 『「皇国」の縮図・インコ道理教』であった。しかし、それでは、あまり に説明的な・曲もない表題、と作者ないし語り手は、考えたので、現在の 形にきりつめた。 「皇国」すなわち天皇制国家は、神道系であり、インコ道理教は、仏教 系である。神道系と仏教系との相違ならびに規模の大小の差異はあれ、 両者は、いずれも宗教団体・無差別大量殺人組織であり、前者の頭 首は、天皇にほかならず、後者の頭首は深山秘陰にほかならぬ。 かくて「宗教団体インコ道理教は、『皇国』日本の縮図である。」とい う命題と、宗教団体インコ道理教にたいする国家権力の出方を、人が、 ≪近親憎悪≫なる言葉で理会する。」という命題とは、いかにも彼此照応 する。▼ 笑うべし、というしかない。 この一文は、まったくもって、的確にこの小説の主題を表現している。 アルファにして、オメガ。 この小説には、他に何も残らない。 みごとな、というよりも、「身も蓋もない整理」という他はない。 もともと、オウム真理教を題材に、日本社会に巣くうものを摘出しようとする、気宇壮大な構想なのだが、それなら何も、小説にする必要はないのであって、最初から評論にしてもかまうまい。 しかし、これが評論のすべてだとすれば、あまりにも、貧相かつ使い古しになってしまう。 だからこそ、小説にしようとして、大失敗した、とみるしかないわけだ。▼ 「題意」における補足は、小説としての表現の失敗を自覚してのことだと思うが、どうせ、生活保護を受けているのだし、絶版にしても何も問題は無かったのではないか?。 金を惜しむより名を惜しめ、とはよくぞ言ったものである。 昔、『三位一体の神話』を読了したときにも思ったが、いくら何でもあんまり、である。 大西先生は、こんな本を書いてはいけない。 ▼ とはいえ、何も収穫がない訳ではないのだ。 以下は、中野重治が島崎藤村『破戒』を評した一節の引用であるのだが、部落差別問題の本質を言い当てていて、涙がでるくらい素晴らしい。 『新しいということは、現代では恥づべき何者をもいみしない。さういふ中に あって独り新しい平民のみが特別の眼をもって見られて来たのは何故で あるか。』 それは、古いということが誇るべき何物をも意味しない ときに、古いという理由での誇りを暴力的に基礎づけねばならない 『現代』そのものの性質から理解されるのであろう ▼ これだから、大西巨人は止められない。 鷲田小弥太は、中野重治について、「俺こそ、より正しき革命的主体!」という欲望に囚われた人物と断じている。 そのためか、近年はとみに評価が低い。 中野重治は、古本屋に行けば、宮本百合子、野間宏とともに山積みにされているが、読むに値するものもそれなりに多いのであろう。 天皇制の永続は、ライ病への偏見、被差別部落の偏見と同様、その卓越性、有意義性、有益性の証明ではない、という言明と同様、心して起きたい一文である。 きちんと小説となっていれば、どれほど面白い作品だっただろうか。 ▼ 一ファンとして、心を鬼にして評価した。 次回作を神にも祈りながら期待する他はない。 とにかく、お体を大切にしてほしい。▼ なぜなら今年、大西巨人先生は、88歳になられるのだ。評価 ★☆価格: ¥ 1,365 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Feb 4, 2007
コメント(1)
全6件 (6件中 1-6件目)
1