2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
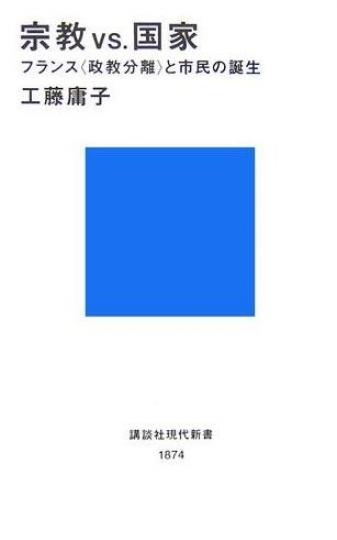
★ イスラム女性は、なぜ学校でスカーフを着用してはいけないのか? 工藤庸子 『宗教 VS 国家 フランス<政教分離>と市民の誕生』 講談社現代新書 (新刊)
▼ すばらしい。▼ 「つまらない本しか出さない講談社現代新書」、という私の偏見を吹き飛ばしてしまう快著である。 このブログを読んでいる人は、ぜひとも本屋で購入して欲しい。 ▼ マザー・テレサが人権のシンボルであることは、日本人にとって自然でも、欧米人にとって奇異であるのは何故なのか。 なぜイスラム女性は、フランスの学校で、「スカーフ」を着用してはならないのか。 そもそも、アメリカ・ドイツ・イギリスでは、宗教教育が盛んなのに、どうしてフランスではかくも厳しいのか? その淵源について、文学作品を使いながらたどってくれる、すばらしい19世紀フランス社会史になっているのだ。▼ 目次は以下のとおり。第1章 ヴィクトル・ユゴーを読みながら第2章 制度と信仰第3章 「共和政」を体現した男第4章 カトリック教会は共和国の敵か ▼ 第1章は、『レ・ミゼラブル』である。 ジャン・バルジャンの魂を買った、大司教ミリエル。 ジャン・バルジャンは、終油の秘蹟をこばみ、大司教ミリエルからもらった銀の燭台の光に照らされ、心安らかに臨終の床につく。 売春と奴隷と子供たちの悲惨をもたらす「無知」という名の暴君の絶滅をねがい、友愛と調和と黎明の共和国に賛成票を投じた、かつての国民公会議員医師Gは、ミリエルの薦めを拒絶して、無限の存在の自我こそを神(=理神論者)とする立場を捨てず、ジャンと同様、終油の秘蹟をこばんで死ぬ。 フランス革命の時代、カトリック教会は、憲法への忠誠と引き換えに、「国教会」的な形で護持され、国家の援助が与えられていたという。 カトリック教会は、プロテスタント・ユダヤ教徒・嬰児・自殺者の墓地への埋葬をこばむので、政府は衛生上共同墓地を造らざるをえない。 今や雑多な宗教でごった返すパリ最大のペール・ラシェーズ墓地だが、創立当初はライシテ(=政教分離)精神の発露どころか、忌避すべき埋葬場所だったという。 ジャン・バルジャンは、死をもって市民権を贖い、ラシェーズ墓地に埋葬される。 市民であることとは、カトリック信徒であることと対立するものであるらしい。▼ 第2章は、国家が宗教を管理しようとするナポレオン流のコンコルダートと、宗教を私的領域に囲いこむライシテ原則とは、対極にあることを強調する。 王政復古期は、カトリック教会や修道会が復興した。 「王殺し=無神論者=市民(シトワイヤン)」という概念が生まれる一方、修道会は、ボランティア活動を通して住民の福祉を支えた。 驚く無かれ。 われわれの出生証書、婚姻証書、死亡証書は、元はといえば、カトリック教会教区司祭管轄下の洗礼証書・婚姻証書・埋葬証書に由来するという。 19世紀、修道会は、職業をもたぬ女性に社会的活躍の場と生きがいを提供し、カトリック教会は女性化してゆく。 女性は、男性に比べて、強力な宗教の囲いこみを受けていた。 修道会は、フランスの中等教育において役割を高め、「家族に奉仕する性」である女性にボランティア活動を通してかけがえのないソシアビリテをあたえ、純潔を徳目とした女性教育をおこなった。 フロベールの小説に描かれる、濃厚な「宗教感情」と陶酔をさそう女子修道会寄宿学校の雰囲気は、ミッション・スクールのパロディである「マリ見て」の非ではない。 ▼ 第3章は、第3共和制である。 王党派が優勢を占めたにも関わらず、ブルボン派とオルレアン派に分裂していたため、1879年、上下両院で共和派に逆転されてしまう。 フランスのアイデンティティは、「カトリック教会の長女」なのか、「革命の理想を受け継ぐ現代フランス」なのか。 プロテスタントとユダヤ教徒、ならびに普遍的友愛の世界共和国をめざすフリー・メイソンは、後者に合流。 ジュール・フェリーは、宗教の代替物として「道徳と公民教育」、安息日の労働解禁をおこない、共和国の父、とよばれるようになる。 しかし、良家の子女は、えたいの知れぬ下流階級のかよう公立ではなく、私立のミッションスクールに通わせるのが普通だったという。 「自由・平等・友愛」の標語も、当初からあったのではない。 「責務・絆・調和・共同体」的な「友愛」の定着は、その語のもつキリスト教的イメージ(兄弟、友愛の人キリスト)もあって、「権利、状態、契約、個人」的な語彙である自由・平等より遅れたという。 「友愛」は、キリスト教信仰にかわるものとして、世俗的道徳のカナメとして、非キリスト的な「連帯」「尊厳」の概念が発見される中で、浮上してゆく。 第三共和制で女性に参政権がなかったのは、左派において女性は、「カトリック教会に取りこまれた存在」、右派においては「家族に奉仕する性」という、左右の共犯関係によるものらしい。大統領令(1944年、ドゴール)で与えられるまで、棚ざらしにされていたらしい。 ▼ かくて第4章は、ライシテの総仕上げとなる。 共和派の勝利は、フランス共和国国民の創設の必要性を生む。 かくて、構造的に要請されることになった反教権主義は、コングレガシオン(修道会)にフランス公教育から緩やかに撤退を強いることになる。 反教権主義は、決して輸出されることはなく、コングレガシオンは、かわりに「文明化の使命」をおびて、植民地教育に進出したらしい。 ドレフュス事件がおきた理由は、社会主義的な労働者陣営、カトリック主義陣営、ブルジョア自由主義に不満をもつ陣営…様々な利害のちがう集団を糾合しうる紐帯が、「反ユダヤ主義」しかなかったことが原因だという。 かくて、ドレフュス派陣営(侮蔑的意味をふくめ「知識人」とよばれた)は、反教権主義を軸に結束。 「人権リーグ」が結成されることになる。 カトリック教会との激しい闘争の末人権が獲得された、人権とカトリックとは相容れないものだ ――― などの欧米の常識は、ここに由来するらしい。 かくて共和国は、カトリック「教会」(信仰ではない!) と全面対立。 1901年、修道会を標的にしたアソシアシオン法の成立。 1905年、 政教分離法の成立。 これをもって、カトリック教会は、アソシアシオンの一つに転落した。 国家は一切、宗教を支援しない。 3万人もの修道士・修道女が、フランス国外へ出ていったという。 ▼ とにかく、フランスに対する、通俗的な認識の変更をよぎなくされる書物であることは、まちがいない。 第三共和制の大臣の6割がフリー・メイソン。 マッチョな植民地帝国である第3共和制。 そこでは、急進党・社会党・共産党の左派勢力とちがって、カトリック教会という支柱、名望家ネットワークを持つ右派勢力は、明確な政党を結成しなかったという。 政教分離法以後も、修道会系の学校は、自由学校に形をかえ、修道会メンバーが世俗の形でなら、教育に携わることが認められていたらしい。 また政教分離法当時、フランスの政策推進者たちにとって、宗教と国家の共存できる理想的状態とは、アメリカ合衆国だった ……… 現在、キリスト教原理主義に牛耳られるアメリカに対する、最大の皮肉としか言いようがない。 ▼ 「不可分の非宗教的な共和国」という国是をもつ、フランス。 そこでは、公教育の現場からは、軍や警察まで動員して、十字架が撤去された。 この史実こそ、イスラム女性のスカーフを公教育から追放する動きが、フランス人の間であまねく是認される、最大の原因であるという。 アメリカのフィルターを通しがちな日本では、フランス理解も偏見にまみれがちである。 この状況に風穴をあける入門書、といってよいのではないだろうか。 「ライシテ」とは、単なる政教分離、非宗教性ではない。 「ライシテ」とは、フランス市民社会の基本原則に加え、制度的「決断」を含意するものなのだ、という。 また、筆者は2分法に陥ることもない。 カトリック教会は、アソシアシオンの一つとして、フランス社会において女性を組織化し続け、隠然たる勢力を持ち続けた。 パンテオンでおこなわれたヴィクトル・ユゴーの国葬こそ、靖国神社の方向性とは正反対の、パンテオンの脱宗教化の完成であるという議論は、国立追悼施設に無宗教はありえない、という議論に一石を投じるのではないだろうか。 とにもかくにも、興味深い話でいっぱいなのだ。 ▼ ただ唯一の弱点は、フランス以外の欧米諸国における政教分離がはなはだ曖昧になっている点であろうか。 プロテスタント系諸国に比べると、アソシアシオンに関する法律や女性参政権などにみられるように、フランスは決して先進国ではない。 むしろ、後進国といってよい。 これは、「人権」が教会と戦うことによって得られたという結論をフランスから汲み出す筆者の意図にとっては致命的なのではないだろうか。 フランスにおける政教分離を研究する意味は、フランスが人権獲得の先進国であったことと不可分である。 もし、後進国であるとするなら、どれくらい普遍的なものといえるのか、疑念を抱かざるをえない。▼ とはいえ、これは過剰な批判なのかもしれない。 最近読んだ新書では、ピカイチの面白さだったからだ。 講談社現代新書は100冊以上読んでいるはずだが、こんな面白い本は、本書がはじめてである。 皆さんにはぜひ、お勧めしておきたい。評価: ★★★★☆価格: ¥ 756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Mar 21, 2007
コメント(0)
-
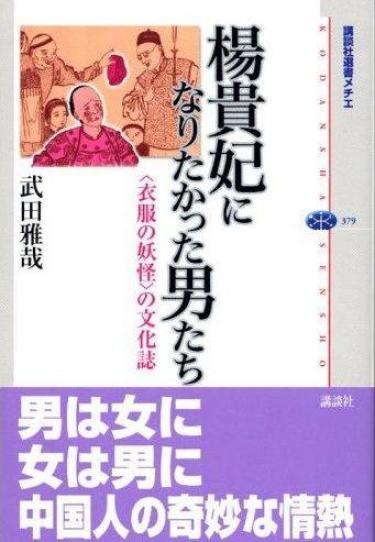
★ 男の花園 武田雅哉 『楊貴妃になりたかった男たち <衣服の妖怪>の文化誌』 講談社選書メチエ (新刊)
▼ いざ来たれ、男の花園へ。 中国男性たちが繰り広げた、てんやわんやの女装史へのいざない。 この書が面白くないはずがない。 この場をかりて、ぜひ、皆さんにもお勧めしておきたい。▼ 筆者によれば、春秋時代の昔から、女性の男装、男性の女装は、たんなる「異性装」などではなかった、という。 服装には、社会が混乱する、良からぬ前触れ・前兆があらわれる。 衣服の乱れは社会の乱れ。 これを中国では、「服妖」と称してきた。 服妖は、衣服・靴・冠のみならず、はては立ち居振る舞い、生活習慣、音楽習慣にまでおよぶ。 「服妖」は、史料が男性の視点から書かれたものしか残らないこともあって、主に「女性の服装」に関しての常套句であった。 ただ、性転換・両性具有者「半陰陽」「二形人」も、「服妖」と呼ばれていたらしい。 男性から女性に性転換することは、「犯罪」扱いを受け社会から排除されたが、女性から男性にかわることは、メデタシ、メデタシ、という。 日本の男女差別は、大陸起源というが、さもありなん。▼ 「女性の男装」は、寡婦や「木蘭従軍譚」などが見られ、男装の麗人、すなわち「男まさり」の女性の系譜は、「江湖」の世界を筆頭に、ちまたにあふれていたらしい。 オスカル様は、ゴロゴロしていたのだ。 女性は、婚約相手を探す、仇討する、商売する、など様々な理由で男装していた。 しかし、飼われている女性たちが、飼っている男性に歯向かうことは、ゆるされていない。 女装の「男装」は、最終的に解かれるものであり、貞女・良妻となってハッピーエンド、がほとんどであったという。 ▼ 中華世界、最初の「女性の男装」は、夏の桀王の后、妹喜(ばっき)。 そして、最初の「男性の女装」は、魏の何晏とされる。 魏晋南北朝には、化粧をする美少年が溢れていたらしい。 当然、趣味では終わらない。 男性の様に警戒されないことを良いことに、趣味を逸脱して犯罪――― 女性の部屋に忍びこむ、他人の家に押し入り強盗する ――― に走る「女装犯罪者」たちも、現れてくるようになる。 女性の男装は、規定はないものの、男性の女装は法に抵触していたという。▼ 中国の近世にあたる明清時代は、「男装(女性)」と「女装(男性)」の流行の頂点にあたるらしい。 近世中国は、女性美至上主義の時代であって、戯曲などは物語をすすめるため、さかんに2つのモチーフを借用した。 「男子授乳譚」 ――― 主人の幼子を守ろうと頑張る、使用人の忠義に天が感服し、能力を付与する云々 ――― は、インド説話に由来するという。 華やかな同性愛文化。 道士・仏僧の文化に支えられている男性同性愛も、明清時代に頂点に達し、京劇の「女形」役者 ――― しばしば本物の性同一性障害者もいたようだ ――― は、舞台を下りても女装を解かなかったものもいたという。 意外や、女性の同性愛文学は、『続金瓶梅』くらいしかないらしい。 ▼ 近代にもなると、異装文化は、『点石斎画報』などの画像資料が豊かなため、いっそう興味深い話で満載である。 男の遊び場をみてみたいため。 または、自分の趣味として男装を始める女性たち。 妓女は、そんな彼女たちのファッション・リーダーであったらしい。 清末以降、女学校の登場によって、「女学生」文化が到来。 妓女は、清楚な感じを出すべく、女学生を真似る、女学生は「妓女」にあこがれる …… 「妓女」と「女学生」、対極にあるもの同士がお互いに模倣し、「妓女ならぬ女学生」「ニセ学生」が出現したというから面白いではないか。 また、しばしば京劇に使われる擬似纏足の道具「きょう」を使い、美少年・美青年は、あえて妓女になるものもいたという。 むろん、男性の女装は、数え切れない。 犯罪のため、女性にちょっかいをかけたいため、女学校に忍び込む男性(逆グリーンウッド、ってチェリーウッドか【笑】) … 数えられないくらいである。▼ むろん現代文化にも、近世~近代の異装文化は大きな影を落としているらしい。 香港映画における、男優の無理矢理の女装シーンに、女性の男装シーン。 これらは、京劇における「反串」 ――― 役柄の取り替え ――― の趣向を映画に取り入れたものらしい。 女装する男性にとって、演劇文化における女形「旦」の存在は、干天の慈雨であった。 中華民国期、女装は男性文人の嗜みであったという。 周恩来は、南開学校(現・大学)在学中、劇団では「旦」ばかりやらされていた。 カラー写真が残されていないことが、残念でならない。 沿海部男性の支払う結納金目当てに、女装での結婚詐欺。 近年、大陸における、女装・男女転倒などのアヴァンギャルド・アートの流行は、明朝滅亡時、男性が女性的世界へと逃避したことと同じではないか ……… どうだろう。かなか楽しめる本であることが理解できるのではないだろうか▼ 当方が知らないことばかりで、たいへん勉強になった。 「胡服」の影響が強い唐代は、「セクシー系」の服装が好まれただけでなく、「女性の男装」華やかりし時代だったらしい。 元の風俗を一掃しようと、明代では、唐風にかえる(何故?)ことを定めたものの、明末の女性の服装はハデハデで、「水田衣」と呼ばれる、パッチワーク式の衣服 ――― まるで、ストリートファッション ――― が流行ったという。 現代日本は、「戦闘美少女」の本場であるといわれるが、古代~近世には、中華世界とは違い、ほとんど「戦う女性」がいない、という指摘には唸らされる。 どうやら、日本の戦闘美少女とは、純現代的現象らしい。 「戦わない」からこそ、戦闘美少女なんであろう。 同性愛を示す語彙は、(どうやって数えたかは知らないが)中国には42もあるという。 また正式には、四大美女(+王昭君)、四大ボイラー(+九江)というらしい。 ▼ ただ、若干苦言を述べさせてもらうと、誤字・脱字・誤訳の類が、ちょくちょく見られ、気になって仕方がない。 そもそも、「服妖」を表題の通りに「衣服の妖怪」と訳してしまっては、あきらかに不適切だろう。 むろん、本文の説明の方では、きちんと補われているが、表題で「不吉な凶事の前兆」を削ぎ落としてしまっては……。 これでは、「信・達・雅」いずれの水準にも到達しているとはいえまい。 さらに、実綿から綿実を抜く作業場のことを「綿花工場」と訳すのは、まだ許せないこともないが、清代文献に使われた「郡」を日本語訳する際に「郡」と訳した中国学者は、生まれて初めてみました。 清代に「郡」などという行政区画があるかよ。 なんで、こんな初歩的なミスが、直されていないの ? さらにいえば、第3の性、「宦官」の存在を抜きにして、ことさらに中国で「女性の男装」「男性の女装」が盛んだったことを強調されてもなー。 かえって、内在的理解を欠いた、「中国人、女装大好きアルネ」的なオリエンタリズムを増殖させることに荷担するだけではないの?。 なんとなく釈然としないまま、読了してしまった。▼ とはいえ、実に面白い。 誰にでもお勧めできる一作である。 評価: ★★★☆価格: ¥ 1,785 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Mar 13, 2007
コメント(0)
-
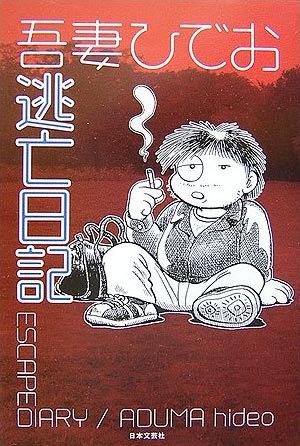
★ 吾妻ひでお 『逃亡日記』 日本文芸社 (新刊)
▼ 吾妻ひでお三部作、ついに完結。▼ もともと、吾妻ひでおはギャグ漫画家ではないのではないか、彼の作品の面白さは、もっと別の所にあったのではないか。 そんなこと書いただけに、開くのは怖かった。 ギャグ漫画だったら、どうしましょうか。 ▼ ところが。 いきなり、冒頭の漫画では、「皆さんこの本を買わなくていいです、漫画だけ立ち読みしてください」とのたまう。 ▼ 「ナンセンス漫画」をやめた吾妻ひでおが、浮き世のしがらみで断り切れなかった、『失踪日記』の「便乗本」らしい。 いったい、どういう版権になってるのか。 知りたくて仕方がない。 まーねー。 買うまでは、ビニール袋に包まれて、中身は確認できない訳だし、後の祭り。 帯に書いて欲しかった。 ▼ 『失踪日記』の落ち穂ひろい。 書けなかったこと。 書かなかったこと。 『失踪日記』を買われた方は、買っても絶対損はしない。 表紙裏、巻頭カラーでは、『失踪日記』の現場の写真が入れられていて、臨場感あふれてよい。 東伏見の竹藪なんかは、今頃武蔵野にこんな森が残っているのか、と驚愕させられるほど鬱蒼と生い茂っている。 武蔵野は広い。 失踪したら、なかなか見つからないわけである。 ▼ 落ち穂ひろい # 酒が切れると自殺する気がなくなる # シケモクは、家庭ゴミの中から # 酒の前は麻雀 # 『失踪され日記』の企画が奥さんに # なぎら健壱はウソつき # 2度目は、東伏見から石神井公園まで毎日かよう # 日本酒はすぐに酔いが回る(そうか?) # アルコールで肝硬変寸前までなると、歩いてもフラフラらしい # 失踪もアル中も、「鬱病」であったことと関係が # 詐欺師のA川さんは、「失見当識」で空間認知できない人らしい # 漫画家協会は、失踪すると退会処分になるらしい # アトムのブロンズ像。 # 伊藤理佐っちが気になる吾妻先生 # イソジンもユンケルも、アル中治療を受けている人は飲んだらダメ # 断酒会の創始者は、高知県社会党書記長、松村春繁さん # 肝臓やられてるんで長生きできないアル中 # お嬢さんがアシスタント # 西洋タンポポは食べられる # 石ノ森先生に憧れ # 「ガロ」派ではなく「COM」派 # 「カムイ伝」には批判的 # まったく残らなかった「劇画派」 # 下手でもいいからデビューせよ # 秋田書店は作家を使い捨て # アニメ顔、劇画顔のエロは嫌い # 鴨川つばめの面白さが分からない # 編集によって、ネーム素通し、勝手に改稿など違うらしい # ロリコンは、先進国でしかありえない? # ロリコン同人誌『シベール』は、50部 # 『失踪日記』『うつうつひでお日記』以外、売れていないらしい # ホームドラマに転向画策中 # 後悔していることは、「ファンの女の子に手を付けなかったこと」 # 鴨川つばめが他誌で復活した際、 秋田書店の編集曰く、「あのとき潰しておけば良かった」 # 「日本漫画家協会大賞」「文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞」 「手塚治虫文化賞マンガ大賞」の3賞制覇者は、 吾妻ひでお、ただ1人 ▼ こんな落穂拾いで、なにか面白そうだと感じられたら、ぜひ購入すべきだと思うな。▼ ただ、面白いことは確か何だけど、やっぱり『失踪日記』と比べると、なんか今一だね。 誰がしたのかは知らない。 でも、今回のインタビュアーと、『失踪日記』のとり・みき御大との力量の格差は、いかんともしがたい。 吾妻や彼が生きた時代を理解している人であることは、分かるんだけど、無難なだけ。 つっこみもボケも中途半端だった。▼ ところで、「セミの抜け殻」を食べたことがある、ゴールデン小雪のメイド服姿を撮った妄想劇場(カラー)は、かなり萌えた。 ゴールデンダンスって何?評価 ★★★☆価格: ¥ 1,260 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Mar 8, 2007
コメント(1)
-
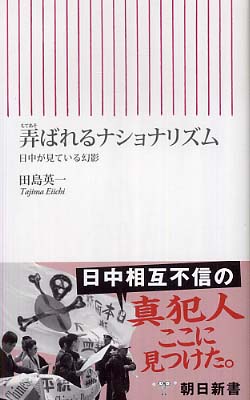
★ 田島英一 『弄ばれるナショナリズム』 朝日新書 (新刊)
▼ 驚いた。 創刊以来、お手軽路線で、重厚さのカケラもない、朝日新書。 「愛国の作法」を始めとして、昔の名前で食ってます、というラインナップ。 ちくま新書や、岩波、中公クラスを期待した人間は、肩透かしを食らわせられた感じだった。 それが現代中国入門を刊行していたなんて。 しかも、これがなかなか要を得ていてすばらしい。 ▼ 簡単にまとめておきましょう。▼ 第2章「文明中国と血統中国」では、中国のナショナリズムが、「クレオールだけがネイティヴを発見する(アンダーソン)」の言葉通り、かつて存在したとされる「想像の共同体(=エトニ)」を内面化させた、海洋中国世界のディアスポラ・ナショナリズムに由来したものであることや、先鋭化したエスニシティを輸入することで形成されたことが説かれる。 国民国家は、ひとつの「Naition=民族/国民」が主権者として統治するという仮構の上になりたつが、「歴史・言語・文化・主権の共有」というフィクションが必要(=想像の共同体)である。 マスメディア・公教育といった出版資本主義が、汎用性があり均質化された国民を作り出す。 中華帝国の時代、成員は3つの階層に分かれていたといってよい。 A 普遍的文明、B 在地リーダー(士の予備軍)、C 民衆の共同体。 在地のリーダーが、「黄金時代→堕落→復興」のV字回復の物語をつむぎだす際、2つの方法が採られることになった。 A 普遍的文明に依拠する「文明中国派(貴族的・水平的エトニ)」と、C 民衆の共同体に依拠する「血統中国派(垂直的平民的エトニ)」。 前者は康有為、後者は孫文という。 孫文は、後期三民主義になると、普遍的文明の形成者を「士」から「漢民族」に置き換えることで、「文明中国」を「血統中国」のものとして簒奪してしまう。▼ 第3章「階級中国の崩壊と『士』『民』『夷』の分裂」では、中華人民共和国建国以降の動向が触れられる。 毛沢東時代、「士」は「民」の文化への同化がもとめられ、思想改造が目指された。 孫文の国民同様、階級も「先天的」に決められていたように、中国の政治運動は、「血縁幻想」から自由になれない。 改革開放後、自由主義者、新儒家、旧左派、新左派など様々な流れが生まれてくる。 「洋の士」 ――― 人権に口やかましい自由主義者たち ――― とは違い、「文明中国」的発想をおこなう「土の士」は、イデオロギーの退潮を補う上でも、たいへん好ましい。 「文明中国」的「文化ナショナリズム」は、かくて導入され、伝統の再評価がおこなわれ、公定ナショナリズム=「愛国主義教育」になる。 しかし、経済成長の片隅で、取り残された「民工」を始めとする「半国民」は、「たった一つの哀れな卓越性に激しい憎悪の念をもって固執」せざるをえない。 ここにもう1つの「血統中国」的な大衆ナショナリズムの復興がみられ、「士」「民」「夷」が、それぞれに分裂していく。 3者を包括する戦略としての「文明中国」的公定ナショナリズム、すなわち「愛国主義」教育は、「宗族」に代表される漢族の血縁幻想に絡めとられ包括しきれない。 「血縁中国」的ナショナリズムの過激化。 自大意識と均富願望をもつ「憤青」たちは、官製メディアに飽き足らないでサイバー空間につどい、「文革世代」の親譲りの闘争方法で、漢奸たちを攻撃するという。 その様子は、滑稽といわざるをえない。▼ 第4章「失われた10年と、日中民際関係」では、2つのリアリズムのハザマに両国政府をおき綱渡りを強いている、両国民の成熟度の低さが批判の俎上にのせられる。 日中両国は、21世紀的リアリズムである「格差社会」の痛みを、19世紀的リアリズムである「ナショナリズム」という麻酔で沈静化しようとしているからである。 日中の「謝罪」をめぐるすれ違いは、始末書文化(日本)と検討書文化(中国)の差異にあり、どのように再発を防止する気なのか、日本側は何一つ明言していないことにある、という。 国際法に変化が生じ、国家対個人の補償という考えが出てきたことで、日本と華人社会の対立は、激しさを増すことになった。 そもそも2005年「反日デモ」は、華人社会の「日本安保理常任理事国入り反対運動」に発していたのであって、中国に輸入されたものに過ぎないことが、日本では忘れられている。 中国人がデモや集会をおこなう権利まで否定する日本のメディアの偏向報道は、官製メディア中国の偏向報道と大差があるとは思えない。 その結果、商品価値の高そうなニュースのみたれ流され、党・政府の国内の分裂に苦しむ姿が見えなくなってしまった。 現在の日中関係が持っているのは、「結果の民主」がもとめられる中国政府が、譲歩だと悟らせないため「非民主的」施策が採っているからである。 ▼ 日中の不毛な対立から救い出すには何が必要なのか。 中国は、少しずつ進みつつある、「結果の民主」から「過程の民主(欧米流議会制民主主義)」への軟着陸。 日本は、隣人という名の「他者」と向き合うことで、自らを支配している「文脈」を相対化する思考、という。 ▼ 分かりやすいけど、その背後には、豊かで深い中国理解がある。 こんな芸当は、なかなかできるものではない。 「チベット民族」概念は、方言分化が激しい言語的多様性を無視したもので、これに寄りかかっているチベット独立運動はかなり危険なしろものであることに言及しているのは、わたしの不勉強もあるが、この書しか知らなかった。 言われてみれば当然のことであるが、たいへんな衝撃であった。 また、雑学も面白い。 チベットの世界観は、「黒域(中国)」「白域(インド)」に挟まれた、天上に最も近い仏教の国プー、というものらしい。 「士」は、儒家の後天主義にもとづく。 「学歴無き団塊世代」のジュニアを中心とした、「憤青」たち …… 軽いタッチで書かれていながら、的確に問題の所在を押さえられていて、入門書には最適といってよいのではないだろうか。 ▼ とくに、現代中国の3つのパラドクス、「中央集権だから、地方が造反する」「一党独裁だから、厳しく結果が問われる(プロセスの民主ではない故に結果の民主が不可避)」「メディアが規制されているので、世論が地下化して暴走する」は、中国を理解する上で、絶対欠くことができないものであろう。 加えて、中国人と日本人の先の戦争に対する意識の違いは、「戦争体験の差異」、それも「地上戦であったか否か」にある。 そのように述べて、現在も長州人を嫌う会津市民(140年前の話!!)や、沖縄県民などを例にとりあげながら、中国人の持つ「わだかまり」を丁寧にほぐして「同じ人間であること」をアピールしてやめない姿勢には、たいへん胸を打たれるものがあった。 必見の書といってよい。▼ お互い知らないからこそ、罵りあう日中のナショナリズム。 われわれは、日本人、中国人などの、民族・血族の「究極的指示記号」たる「大審問官」に身を委ねてはならない。 その選択には、責任を取らなければならない。 他者を理解することの難しさ。 他者の的確な理解と「友好」とを結びつける難しさ。 そのような中で、客観的かつ丁寧に現代中国社会を腑分けした作業は、読まれるべき書物であろう。 一読をお願いしたい。 評価 ★★★★価格: ¥ 777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Mar 3, 2007
コメント(1)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 楽天ブックス
- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…
- (2025-11-18 10:54:57)
-
-
-

- 読書備忘録
- 影踏亭の怪談 大島 清昭
- (2025-11-17 09:47:27)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年51号感想その…
- (2025-11-18 13:00:34)
-







