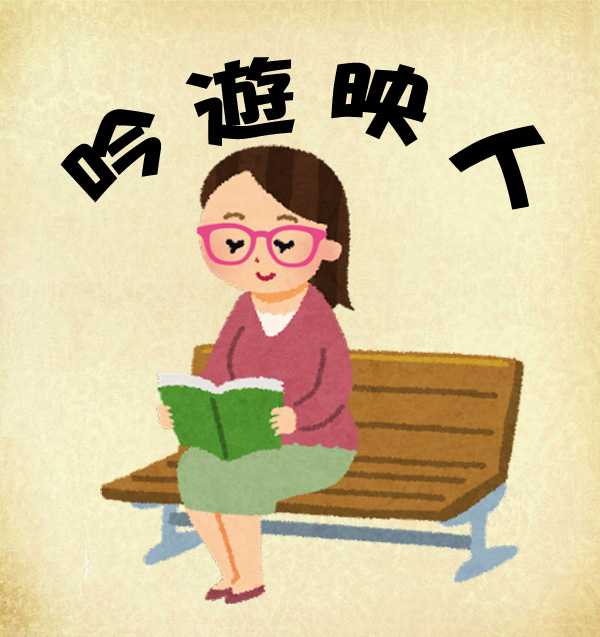PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
その他
(7)映画/アクション
(77)映画/ヒューマン
(97)映画/ホラー
(35)映画/パニック
(25)映画/歴史・伝記
(32)映画/冒険&ファンタジー
(41)映画/ラブ
(47)映画/戦争・史実
(41)映画/SF
(55)映画/青春
(23)映画/アニメ
(24)映画/サスペンス&スリラー
(143)映画/時代劇
(21)映画/西部劇
(4)映画/TVドラマ
(29)映画/コメディ
(15)映画/ミュージカル
(1)映画/ドキュメンタリー
(3)映画/犯罪
(12)映画/バイオレンス
(9)映画/ヒッチコック作品
(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』
(8)読書案内
(217)仏レポ
(2)コラム紹介
(120)竜馬とゆく
(9)名歌と遊ぶ
(70)名句と遊ぶ
(288)風天俳句
(5)名文に酔う
(16)ほめ言葉
(3)教え
(42)吟遊映人ア・ラ・カルト
(13)江畔翁を偲ぶ
(12)ガンバレ受験生!
(5)オススメの本
(3)月下書人(小説)
(6)写伝人(写真)
(6)写真
(18)名曲に酔う
(1)名画と遊ぶ
(2)訃報
(11)舞台
(1)神社・寺院・史跡
(12)テーマパーク
(2)カフェ&スイーツ
(20)要約
(23)聖地巡礼
(1)発見
(8)体験談
(1)お気に入り
(1)ヘルス&ビューティー
(3)読書初心者
(5)カテゴリ: 読書案内
【松本清張/黒い福音】

◆日本の国際的立場の弱さが事件を迷宮入りにさせた
巷にははいて捨てるほどミステリー小説が出回っているけれど、なかなか「コレ!」と思うような作品と出合わないものだ。
たとえ売れっ子作家のベストセラー小説でも、読者それぞれの好みの傾向に差があるので、万人ウケするのは難しい。
そんな中、昭和がえりしたわけでもないが、松本清張作品を久しぶりに読んでみた。
清張の小説は大衆的で読み易く、その上、緻密で丁寧な内容となっているのが頭のカタくなりつつある熟年層にはありがたい。
もちろん時代性は感じてしまうけれど、こういうアナログな小説が実はものすごく心地よかったりする。
今回読んだのは、昭和34年11月から8カ月に渡って連載された『黒い福音』である。
この小説は、昭和34年3月に起こったスチュワーデス殺人事件をモデルにした内容となっている。(ウィキペディア参照)
まずはネットで調べた実際の事件のあらましを紹介しておく。
事件の発端は、昭和34年3月10日早朝、東京都杉並区善福寺川で女の死体が発見されたことによる。
解剖結果から他殺と断定。
被害者の足取りを追うと、生前、カトリック教団サレジオ会に出入りしていたことがわかった。
捜査線上、容疑者としてあがったのは、同教会のベルギー人神父であった。
結局、この事件は容疑者が外国人ということもあり、警察はなかなか積極的に動けなかった。
取調べのため出頭を求めたところ、それに応じず、しまいには教会組織をあげて批判の声をあげたのだ。
そんな矢先、問題の神父は当局に連絡もせず、さっさと帰国してしまったという顛末だった。
この記事を読んだとき、つくづく感じたのは、当時の「日本の国際的な立場の弱さ」である。
事件の核心にあと一歩と迫りながらも、宗教の壁と外国人相手という状況に手も足も出ないのである。
そこに目をつけたのが、作家・松本清張だ。
とくに胸の空く想いだったのは、著者が「信者の主観的で妄信的な点」を痛烈に批判していることだ。
とはいえ、信仰とはそういうものだと言われたらそれまでだが、それがエスカレートしたらどうなるのか?
『黒い福音』では、著者が綿密な調査と事件資料から独自の解釈を加えてストーリーを展開している。
はっきりしているのは、サレジオ会に所属する社会事業団体の一つであるボスコ社が、戦後、日本において不足していた統制物資を横流しして莫大な資金を獲得したということ。
または、闇砂糖事件、闇ドル事件、さらには闇金融事件などでも同教会幹部が黒幕だったにもかかわらず、外国人神父に捜査のメスを入れることができず、不起訴となってしまった。
そのような苦い経験をうやむやにしてはならない、という著者の意思表示の現れなのか、作品全体にほとばしる情熱と意欲を感じさせる。
「非常に神聖な、侵すべからざる戒律をもつ」宗教と言えども、人間のやることに大して変わりはないとでも言うように、若き美男の神父が、日本人女性信者にチヤホヤされ、いつしか聖職者としての規則を破っていくプロセスが描かれている。
宗教団体の閉鎖権威主義に、一石を投じた作品なのだ。
『黒い福音』松本清張・著
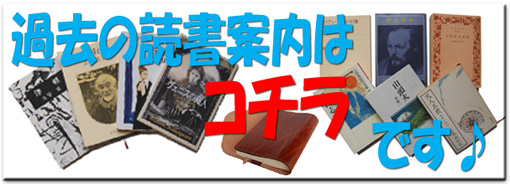
コチラ から
★吟遊映人『読書案内』 第2弾は コチラ から


◆日本の国際的立場の弱さが事件を迷宮入りにさせた
巷にははいて捨てるほどミステリー小説が出回っているけれど、なかなか「コレ!」と思うような作品と出合わないものだ。
たとえ売れっ子作家のベストセラー小説でも、読者それぞれの好みの傾向に差があるので、万人ウケするのは難しい。
そんな中、昭和がえりしたわけでもないが、松本清張作品を久しぶりに読んでみた。
清張の小説は大衆的で読み易く、その上、緻密で丁寧な内容となっているのが頭のカタくなりつつある熟年層にはありがたい。
もちろん時代性は感じてしまうけれど、こういうアナログな小説が実はものすごく心地よかったりする。
今回読んだのは、昭和34年11月から8カ月に渡って連載された『黒い福音』である。
この小説は、昭和34年3月に起こったスチュワーデス殺人事件をモデルにした内容となっている。(ウィキペディア参照)
まずはネットで調べた実際の事件のあらましを紹介しておく。
事件の発端は、昭和34年3月10日早朝、東京都杉並区善福寺川で女の死体が発見されたことによる。
解剖結果から他殺と断定。
被害者の足取りを追うと、生前、カトリック教団サレジオ会に出入りしていたことがわかった。
捜査線上、容疑者としてあがったのは、同教会のベルギー人神父であった。
結局、この事件は容疑者が外国人ということもあり、警察はなかなか積極的に動けなかった。
取調べのため出頭を求めたところ、それに応じず、しまいには教会組織をあげて批判の声をあげたのだ。
そんな矢先、問題の神父は当局に連絡もせず、さっさと帰国してしまったという顛末だった。
この記事を読んだとき、つくづく感じたのは、当時の「日本の国際的な立場の弱さ」である。
事件の核心にあと一歩と迫りながらも、宗教の壁と外国人相手という状況に手も足も出ないのである。
そこに目をつけたのが、作家・松本清張だ。
とくに胸の空く想いだったのは、著者が「信者の主観的で妄信的な点」を痛烈に批判していることだ。
とはいえ、信仰とはそういうものだと言われたらそれまでだが、それがエスカレートしたらどうなるのか?
『黒い福音』では、著者が綿密な調査と事件資料から独自の解釈を加えてストーリーを展開している。
はっきりしているのは、サレジオ会に所属する社会事業団体の一つであるボスコ社が、戦後、日本において不足していた統制物資を横流しして莫大な資金を獲得したということ。
または、闇砂糖事件、闇ドル事件、さらには闇金融事件などでも同教会幹部が黒幕だったにもかかわらず、外国人神父に捜査のメスを入れることができず、不起訴となってしまった。
そのような苦い経験をうやむやにしてはならない、という著者の意思表示の現れなのか、作品全体にほとばしる情熱と意欲を感じさせる。
「非常に神聖な、侵すべからざる戒律をもつ」宗教と言えども、人間のやることに大して変わりはないとでも言うように、若き美男の神父が、日本人女性信者にチヤホヤされ、いつしか聖職者としての規則を破っていくプロセスが描かれている。
宗教団体の閉鎖権威主義に、一石を投じた作品なのだ。
『黒い福音』松本清張・著
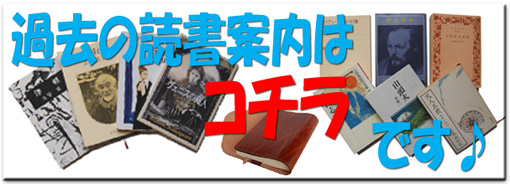
コチラ から
★吟遊映人『読書案内』 第2弾は コチラ から

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内] カテゴリの最新記事
-
吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04
-
吟遊映人が影響を受けた五冊 2024.03.23
-
読書案内No.209 村上春樹/ノルウェイの森 … 2024.03.02
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.