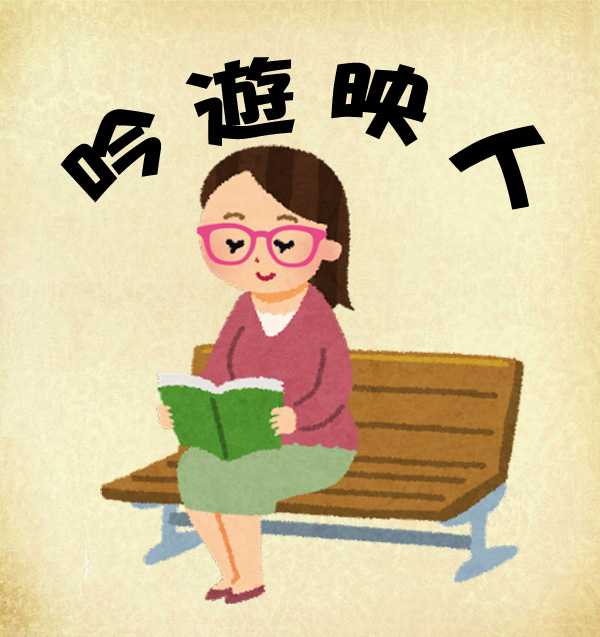PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
その他
(7)映画/アクション
(77)映画/ヒューマン
(97)映画/ホラー
(35)映画/パニック
(25)映画/歴史・伝記
(32)映画/冒険&ファンタジー
(41)映画/ラブ
(47)映画/戦争・史実
(41)映画/SF
(55)映画/青春
(23)映画/アニメ
(24)映画/サスペンス&スリラー
(143)映画/時代劇
(21)映画/西部劇
(4)映画/TVドラマ
(29)映画/コメディ
(15)映画/ミュージカル
(1)映画/ドキュメンタリー
(3)映画/犯罪
(12)映画/バイオレンス
(9)映画/ヒッチコック作品
(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』
(8)読書案内
(217)仏レポ
(2)コラム紹介
(120)竜馬とゆく
(9)名歌と遊ぶ
(70)名句と遊ぶ
(288)風天俳句
(5)名文に酔う
(16)ほめ言葉
(3)教え
(42)吟遊映人ア・ラ・カルト
(13)江畔翁を偲ぶ
(12)ガンバレ受験生!
(5)オススメの本
(3)月下書人(小説)
(6)写伝人(写真)
(6)写真
(18)名曲に酔う
(1)名画と遊ぶ
(2)訃報
(11)舞台
(1)神社・寺院・史跡
(12)テーマパーク
(2)カフェ&スイーツ
(21)要約
(23)聖地巡礼
(1)発見
(8)体験談
(1)お気に入り
(1)ヘルス&ビューティー
(3)読書初心者
(5)カテゴリ: 読書案内
【産経新聞大阪社会部/「死」の教科書 〜なぜ人を殺してはいけないか】
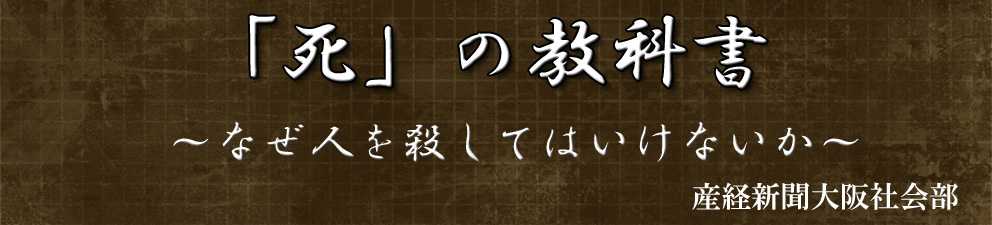
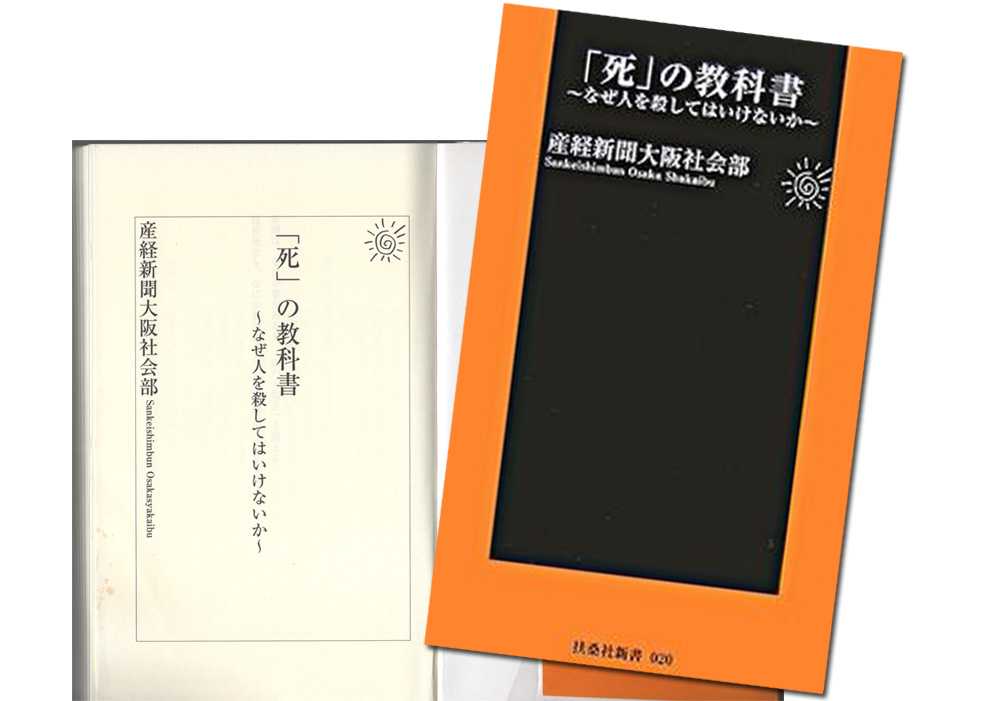
安倍元首相が凶弾に倒れて1年も経たないうちに岸田総理までもが命を狙われた。
一国の首相が狙われたという民主主義の根幹を揺るがす行為であることはもちろんだが、人の命というものをあまりに軽く見過ぎているのではと思う事件だ。
テロを起こして国家転覆を計りたいと思ったのか、革命もどきに酔いしれて英雄を気取りたかったのか。
いずれにしろ数メートル先のターゲットを狙って爆弾を投げ込んだとして、自分の命すら脅かす蛮行だったのに、そのリスクは考えなかったのだろうか?
それとも自分の命など惜しくも何ともなかったのだろうか?
2016年のWHOの調査によると、自殺率が最も高い国はロシアで、次に韓国という結果が出た。
ちなみに日本は7位だが、これを先進国7カ国にしぼると、第1位という不名誉な結果となってしまった。
つまりそれだけに国民の幸福度が低いということなのである。
社会学者ならこの結果をどのように読み解くのだろうか?
いろんな疑問が次から次へと浮かび、一体どうしたらこんな不幸な凶行を回避できたのだろうかと考えてみた。
だがその答えは見つからない。
歴史は繰り返されるという哀しい現実を目の当たりにするのみだ。
そんな折、私は産経新聞大阪社会部が発行した『「死」の教科書』を読んだ。
これは平成18年から翌年にかけて連載された「死を考える」という記事に加筆の上、単行本化されたものである。
少し古い著書ではあるが、こういうご時世だからこそ再読するべき1冊だと確信している。
本書はまず〝子供たち〟の殺人についてから話が始まる。
さかのぼること26年前の、神戸で起きた児童連続殺傷事件「酒鬼薔薇聖斗」を名乗る少年事件を振り返るところから、『なぜ人を殺してはいけないか』というテーマをほり下げるのだ。
これだけ情報過多な時代にあって、昔かたぎの大人たちが「いけないものはいけない」と言っても通じない。それでは答えになっていないので、きっと今の子どもたちは納得しないだろう。
本書では、学校の果たす役割、教育について語っている。
むしろ「死」を子どもたちから遠ざけた環境にしている。
その結果「命について考える機会も失われたのではないか」と。
次に取り上げられるのは、ある日突然、何の前触れもなく降りかかる「事故」による死についてである。
平成17年に発生したJR福知山線脱線事故は、乗客106人もの命が奪われた凄惨な事故であった。
ここでは、愛する人を突然失うという遺族の耐え難い悲しみについて、淡々と取材されている。
突然の家族の「死」とは、本人の完結を持って終わるものではなく、その遺族にとって、暗いトンネルの中を這うような人生が続くということを忘れてはならない内容となっている。
さらに、「死刑」についての死も取材されている。
ここで誤解して欲しくないのは、死刑制度に対する反論ではないということだ。
もちろん、日本という国家が、世界でも少数派の「死刑のある国」であることも踏まえた上で、その生々しい死刑執行の様子も取材されている。
だが私は、産経の持論としては、極刑の存在価値を認めているように思えた。
罪深き人間への戒めとして、「死刑」を掲げ続けておくべきという立場を取っている(と思う)。
この章は賛否両論あると思われるので、各自がじっくりと熟読し、死刑制度における持論を展開して欲しい。
人はこの世に生まれ出た瞬間から「死」と隣り合わせである。
これは致し方ないことだ。
「生」と「死」は、いわばセットになっているからだ。
私の世代であるアラフィフから上の方々は、そろそろ人生の最後について、チラッとでも脳裏を過ぎることがあるのではなかろうか。
本書では「最期をどこで迎えますか」というテーマで、終末期医療について丹念な取材がされている。
日本人の最後は、孤独死でもない限り、たいていは病名が付いて病院で看取られるのが一般的なのだ。
老衰なんて自然死は、今や夢のまた夢。
在宅で家族に看取られて大往生を遂げる方は、現代日本に何パーセントぐらいおられるのだろうか?
無粋なことを申し上げて大変恐縮だが、この著書が最初に発行されたのは2007年だが、この時点で一ヶ月間にかかる終末期医療費は平均で112万円。
現在は物価の上昇でもっと高額になっている。
人の命は決してお金には代えられない。だけど現実問題として「生きる」にはお金がかかるということ。
いや、「生きるため」というより「生かされるため」の方が正しい言い回しだろう。
一体、人の最後において、こんな結末を良しとするのを、誰が決めたのだろうか?
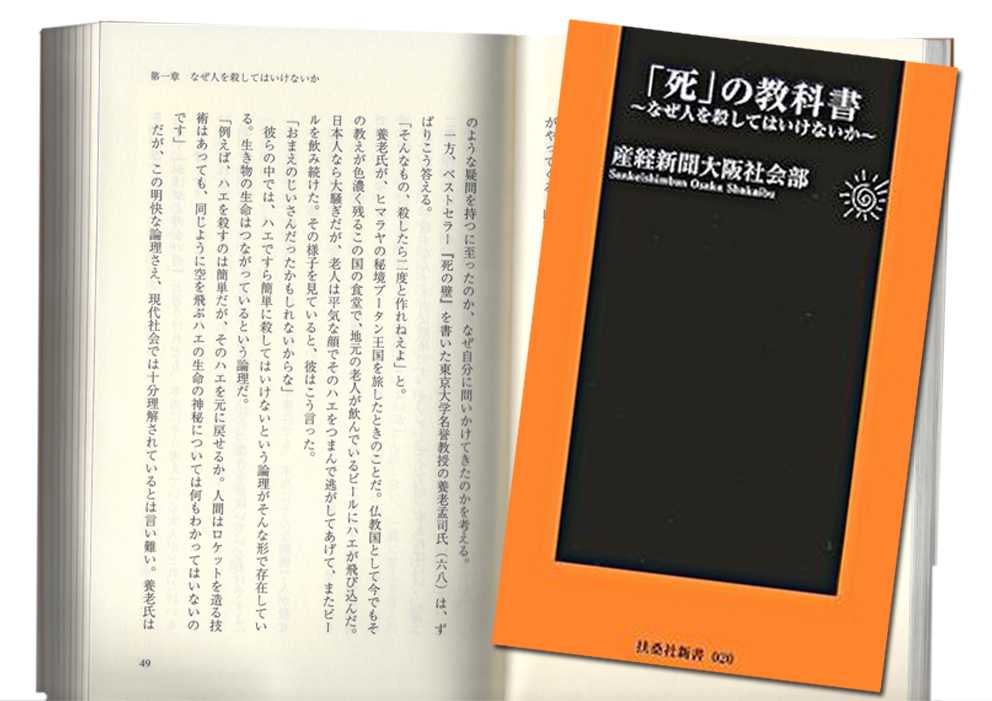
最終章は、戦争と平和について書かれている。
こちらの記述は秀逸で舌を巻いた。
ここに、現在を生きる我々の心を震わすような記述があったので紹介したい。
~~~~~~~~~~
「戦争反対」や「平和の大切さ」を叫ぶことはあっても、戦争そのものについては、考えることすら放棄してきた。タブー視してきた。むろん誰だってあの時代には戻りたくない。戦争などしたくない。ただ、「戦って死ぬ」「誰かのために死ぬ」という「究極の死」の存在から目を背けてきたことで、何か大きなものを失ってきたのかもしれない。
~~~~~~~~~~
小国ウクライナが、大国ロシアを相手に、怯むことなく戦っているのはなぜか?
簡単に答えなど出ないことは百も承知の上だが、この最終章を読むことでその片鱗が掴めるかもしれない、とだけ言っておこう。
今を生きる私たちのバイブルともなり得る本書を、今こそ皆さんに読んでいただきたい。
「死」についての意味とか意義を考えるきっかけになればと思う。
(了)
「死」の教科書 〜なぜ人を殺してはいけないか〜/産経新聞大阪社会部
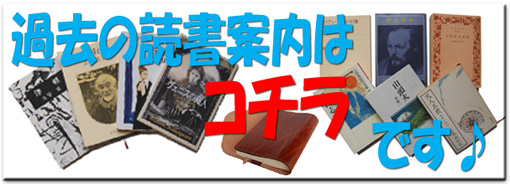
コチラ から
★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)は コチラ から
★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )は コチラ から

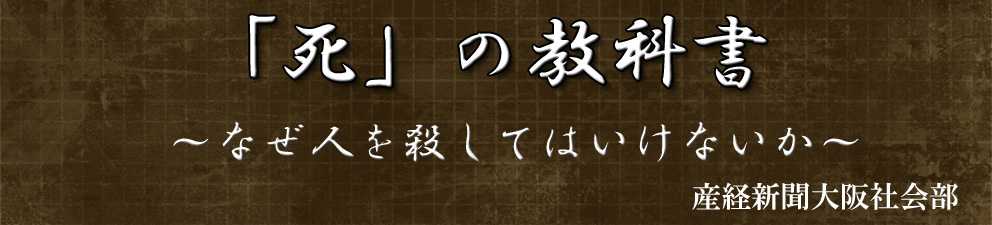
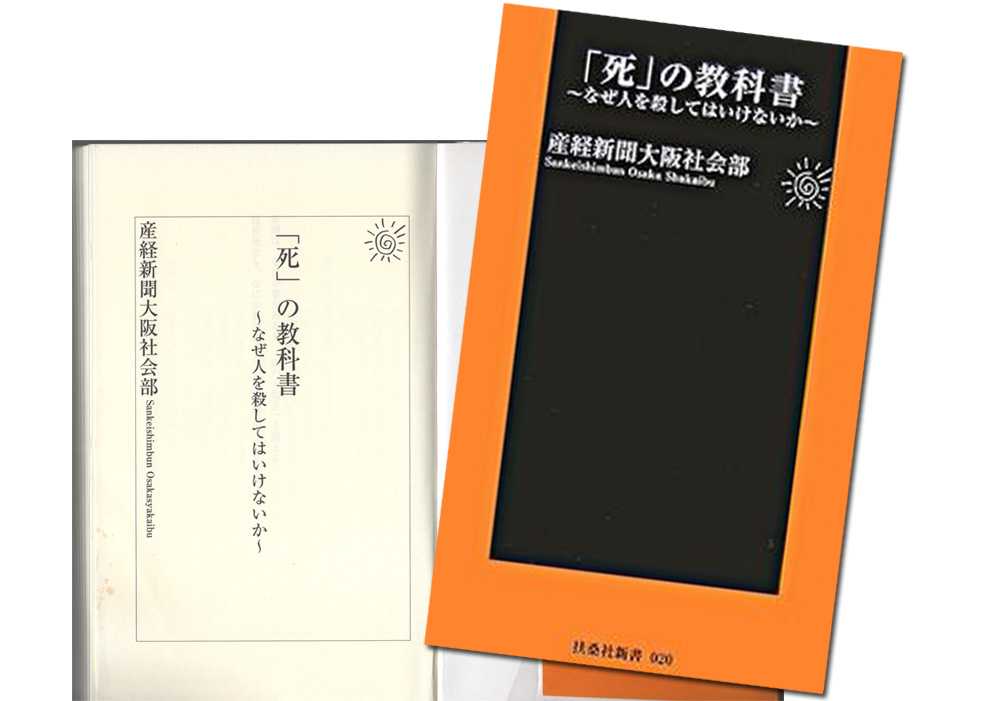
安倍元首相が凶弾に倒れて1年も経たないうちに岸田総理までもが命を狙われた。
一国の首相が狙われたという民主主義の根幹を揺るがす行為であることはもちろんだが、人の命というものをあまりに軽く見過ぎているのではと思う事件だ。
テロを起こして国家転覆を計りたいと思ったのか、革命もどきに酔いしれて英雄を気取りたかったのか。
いずれにしろ数メートル先のターゲットを狙って爆弾を投げ込んだとして、自分の命すら脅かす蛮行だったのに、そのリスクは考えなかったのだろうか?
それとも自分の命など惜しくも何ともなかったのだろうか?
2016年のWHOの調査によると、自殺率が最も高い国はロシアで、次に韓国という結果が出た。
ちなみに日本は7位だが、これを先進国7カ国にしぼると、第1位という不名誉な結果となってしまった。
つまりそれだけに国民の幸福度が低いということなのである。
社会学者ならこの結果をどのように読み解くのだろうか?
いろんな疑問が次から次へと浮かび、一体どうしたらこんな不幸な凶行を回避できたのだろうかと考えてみた。
だがその答えは見つからない。
歴史は繰り返されるという哀しい現実を目の当たりにするのみだ。
そんな折、私は産経新聞大阪社会部が発行した『「死」の教科書』を読んだ。
これは平成18年から翌年にかけて連載された「死を考える」という記事に加筆の上、単行本化されたものである。
少し古い著書ではあるが、こういうご時世だからこそ再読するべき1冊だと確信している。
本書はまず〝子供たち〟の殺人についてから話が始まる。
さかのぼること26年前の、神戸で起きた児童連続殺傷事件「酒鬼薔薇聖斗」を名乗る少年事件を振り返るところから、『なぜ人を殺してはいけないか』というテーマをほり下げるのだ。
これだけ情報過多な時代にあって、昔かたぎの大人たちが「いけないものはいけない」と言っても通じない。それでは答えになっていないので、きっと今の子どもたちは納得しないだろう。
本書では、学校の果たす役割、教育について語っている。
むしろ「死」を子どもたちから遠ざけた環境にしている。
その結果「命について考える機会も失われたのではないか」と。
次に取り上げられるのは、ある日突然、何の前触れもなく降りかかる「事故」による死についてである。
平成17年に発生したJR福知山線脱線事故は、乗客106人もの命が奪われた凄惨な事故であった。
ここでは、愛する人を突然失うという遺族の耐え難い悲しみについて、淡々と取材されている。
突然の家族の「死」とは、本人の完結を持って終わるものではなく、その遺族にとって、暗いトンネルの中を這うような人生が続くということを忘れてはならない内容となっている。
さらに、「死刑」についての死も取材されている。
ここで誤解して欲しくないのは、死刑制度に対する反論ではないということだ。
もちろん、日本という国家が、世界でも少数派の「死刑のある国」であることも踏まえた上で、その生々しい死刑執行の様子も取材されている。
だが私は、産経の持論としては、極刑の存在価値を認めているように思えた。
罪深き人間への戒めとして、「死刑」を掲げ続けておくべきという立場を取っている(と思う)。
この章は賛否両論あると思われるので、各自がじっくりと熟読し、死刑制度における持論を展開して欲しい。
人はこの世に生まれ出た瞬間から「死」と隣り合わせである。
これは致し方ないことだ。
「生」と「死」は、いわばセットになっているからだ。
私の世代であるアラフィフから上の方々は、そろそろ人生の最後について、チラッとでも脳裏を過ぎることがあるのではなかろうか。
本書では「最期をどこで迎えますか」というテーマで、終末期医療について丹念な取材がされている。
日本人の最後は、孤独死でもない限り、たいていは病名が付いて病院で看取られるのが一般的なのだ。
老衰なんて自然死は、今や夢のまた夢。
在宅で家族に看取られて大往生を遂げる方は、現代日本に何パーセントぐらいおられるのだろうか?
無粋なことを申し上げて大変恐縮だが、この著書が最初に発行されたのは2007年だが、この時点で一ヶ月間にかかる終末期医療費は平均で112万円。
現在は物価の上昇でもっと高額になっている。
人の命は決してお金には代えられない。だけど現実問題として「生きる」にはお金がかかるということ。
いや、「生きるため」というより「生かされるため」の方が正しい言い回しだろう。
一体、人の最後において、こんな結末を良しとするのを、誰が決めたのだろうか?
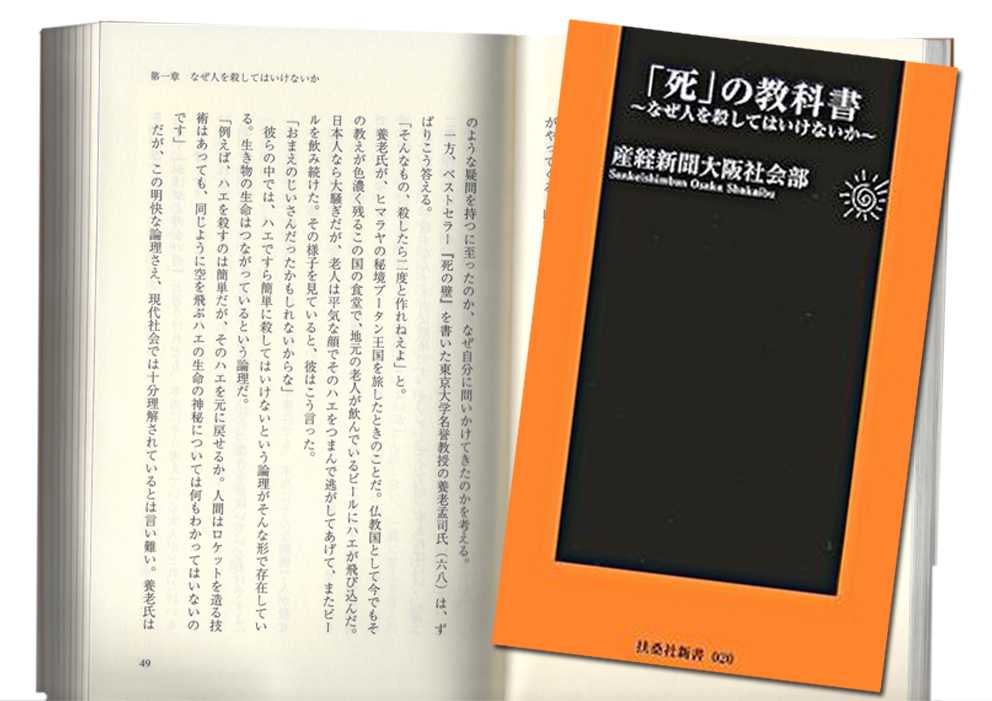
最終章は、戦争と平和について書かれている。
こちらの記述は秀逸で舌を巻いた。
ここに、現在を生きる我々の心を震わすような記述があったので紹介したい。
小国ウクライナが、大国ロシアを相手に、怯むことなく戦っているのはなぜか?
簡単に答えなど出ないことは百も承知の上だが、この最終章を読むことでその片鱗が掴めるかもしれない、とだけ言っておこう。
今を生きる私たちのバイブルともなり得る本書を、今こそ皆さんに読んでいただきたい。
「死」についての意味とか意義を考えるきっかけになればと思う。
(了)
「死」の教科書 〜なぜ人を殺してはいけないか〜/産経新聞大阪社会部
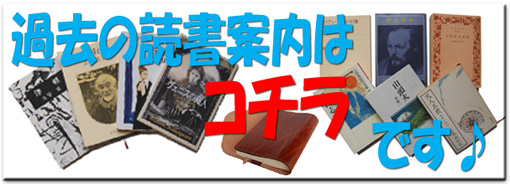
コチラ から
★吟遊映人『読書案内』 第2弾(100~199)は コチラ から
★吟遊映人『読書案内』 第3弾(200~ )は コチラ から

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内] カテゴリの最新記事
-
吟遊映人が影響を受けた五人 2024.05.04
-
吟遊映人が影響を受けた五冊 2024.03.23
-
読書案内No.209 村上春樹/ノルウェイの森 … 2024.03.02
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.