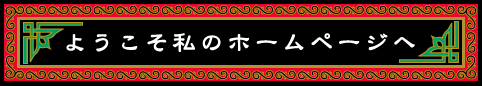全35件 (35件中 1-35件目)
1
-
卆寿の祝い
今日は、私の講義を二十四年間聴き続けて下さった中嶋さんの 九十歳のお祝い。 仲間九人で彼女をだしに祝膳を囲み、そのあと茶事をした。 昼食は白金の箒庵で済ませ、中立してメンバーの一人で品川の 御殿山にご自宅のある方の茶室へ。 僕も物陰でそっとスーツから紋付に着替えて・・・ こんな形式ばらない茶会もいいなと思った。 道具は全員の持ち寄り、私は柴田是眞の「百福」という百人の お多福が楽しく遊んでいる掛軸を、寄付きに掛けさせて頂いた。 本席の床の間は、淡々斎の「松寿千年翠」、立花大亀さんの 大亀の香合をすえて、重ね茶碗で濃茶の点前。 茶入は有栖川宮様から頂いた品とか、撫で肩の品の良い瀬戸 慶入の黒と高麗の井戸型の茶碗。亭主役は私の中学時代の 恩師。もう四十年もお付き合い、ああ!!! なんか、もうあっという間に時間が過ぎたというのを実感させ られました。人生ってうかうかしているとすぐ過ぎちゃうのかも・・・ 薄茶は花月。花月なんて僕は幼稚園のころにやったくらい・・・ 折据の扱いから直されながら、それでも全員で和気藹々と 一日が終わった。 次に卆寿の祝いが出来るのは、このメンバーでは十四年後、 それまで皆元気でいましょうと、言い合って別れた。 それにしても皆さん元気だなあ。僕も見習わないと・・・ 僕が最年少というのはいつまで経っても変わらないけどね。
2006年02月22日
コメント(2)
-
良寛様になれる日
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Monday, August 15, 2005 11:02 AM Subject: 15日の日記 「ワーイ、お坊さんだぁ。」 インターフォンで来意を告げると、家の奥で幼い子供たちの声がはじけ、玄関に小さな足音が駆けてくる。 「ネェ、お坊さん、遊ぼう」 「ウン、ちょっと待ってね。おじいちゃんにお経を上げるから」 「ネェ、ネェ、ナムナムしたら遊べる?」 「ちょっとだけね」 「ワーイ、やったぁ」 「今度来たらまた遊ぶって言ったから、ぼくプラレール全部つなげといたよ」 一年前の約束を子供たちはしっかり記憶している。仏間の隣の八畳は、部屋いっぱいにプラレールがひろがっている。 お盆に檀家を廻っていると、何軒かで、私は俄か保父さんに変身する。 でも八月十四・十五日の二日間の中で、いちばん楽しい時間だ。 ******************************************************************************* 「少しはわずらって寝込んでくれたら、親孝行の真似事ができたのに」 この春、お姑さんを見送ったお嫁さんは、読経の終わるのを待ちかねたように、胸のうちを告げる。 「ああ、まだまだお気持ちの整理がつく訳がありませんよね」 ちょっと近所へ行ってくると言った姑の声を、掃除機をかけながら見送った筈が、門に手をかけたまま息絶えているのを小一時間後に発見したお嫁さんの後悔は尽きない。 ひとしきり彼女の嘆きを聞く。 「そうそう、お義母様は、『うちは息子で外したけれど、嫁で当てたんですよ』って、いつも自慢しておられましたね」というと、こらえきれなくなったお嫁さんの目からは涙が噴き出るが、やがて明るい表情を取り戻される。 ******************************************************************************** 「その後、お加減いかがですか?」 「ええ、おかげさまでギブスはとれたんですが、湿気の多い日は痛むんですよ。」 「そうですよね。骨はつながっても疼いたり、しびれたりしますよね」 「あら、お坊さんも腕を折られたんですか?」 「いいえ、私は足ですが・・・」 「やっぱり庭で滑って?」 「いいえ、スキーで」 「あら、お坊さん、スキーをなさるんですか?」 対話のような、でもその実、この一年の間にご自身の身に起きた事ごとを報告するきっかけを待っていただけのようなやりとりもある。 ******************************************************************************** 墨染めの法衣を着ると、カウンセラーになったり、看護士になったりするけれど、私の来訪を待っていてくださるお宅がある。 いちばん好きな役回りはなんといっても保父さんだ。 師匠の寺のお檀家は約五百軒、そのうちこの二日間にお尋ねするのは三百二十軒、私の担当分はそのなかの六十軒程。一軒のお宅にかける時間は最大で二十分にしないと回りきれない計算になるが、三十分を超えるお宅もだいぶある。 とにかく、年に一度お目にかかれるかどうかのお宅である。この機会を大切にしないわけにはいかない。 でもついつい小さいお子さんと遊ぶ時間が長くなる。 「キリン作って」って折り紙を差し出されれば、折り方なんか知らなくても、それらしい形を作らなくてはならない。 粘土をもってきて「鶴折ってよ」と、さっきの子のハトコが言う。「エッ?粘土を折るの?」鶴とキリンが逆だったら簡単なのに、と思うが、子供たちにとって、こちらの都合はお構いなしだ。 リクエストに一通り応えた後の別れ方がまた難しい。大抵の場合、高く抱き上げて空中で手を離し、着地前に抱きとめるパターンが、子供たちの満足度が高い。 昨日と今日で、二十数人の子供たちと来年の約束をして、そうして別れた。 奥から若いお父さんが出てきた。そうだ、得度を受けて初めてお盆に読経に伺ったとき、このセイちゃんが何としても「帰っちゃ駄目だ」ってすねて、私を困らせたんだ。 でもあの時、「三つ高い高いをしたら帰る。でも必ず来年も来て遊ぶからね」って約束して、以来お坊さんが来たら遊べる、って待っていてくれる子供たちと楽しい時間を過ごしてきた。 あのとき四歳だったセイちゃんが、もう二人の子持ち。 子供らと 手まりつきつつ このおかに 遊ぶ春日は 暮れずとも良し 良寛様もこんな気持ちだったのかな。 ともかく私の二十四回目のお盆も無事に終わった。
2005年08月15日
コメント(1)
-
大死一番
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Wednesday, June 29, 2005 10:04 AM Subject: 29日の日記 聖心の講義を終えて、昼飯がてら銀座に出た。 いつもは避けて通るのに、ヤマハの前に差し掛かると今日はどうしても店に入ってみたくなった。 地下の楽譜売り場に下りてみた。 バルトークの「中国の不思議な役人」のピアノソロ用にアレンジされたものが欲しかったが、在庫切れだった。 あれば七・八千円のはずだ。しかしなぜか在庫切れと聞いてほっとした。 最後まで弾き通せるかどうか自信のない楽譜に投ずる金額として、今の僕には高すぎるのではないか、そんな気がしていたのも事実だ。 オーストリアから取り寄せましょうか、と係の女性は聞いてくれたのだが、それを断った。 そこで話を打ち切れば良かったのだが、ふと武満徹の「死んだ男の残したものは」はありますか、という質問を口にしてしまった。 タイトルのおどろおどろしさはやや抵抗があるが、不思議な和声の豊かな響きを、いつかパイプオルガンで弾いてみたいと思っていた曲ではある。 でもどうしてとっさに口からこんな言葉が出たのだろう。 係の人は混声合唱用とピアノ伴奏譜のついた独唱用があると即答し、さっと二種類を出してくれた。ご不要でしたらこの棚において下さいという言葉を鄭重に添えて、彼女はカウンターに戻った。 どちらも捨てがたいものだった。今すぐ帰宅して弾けるという意味なら独唱用がふさわしいし、将来オルガンで弾くためなら混声合唱用からアレンジして手鍵盤二段と足鍵盤に分けたほうが色彩感に満ちた音色になる。 二冊で七千円ちょっと。さんざんためらった。 バルトークの楽譜があれば同じ位の金額だったはずなのだが、在庫切れと聞いた瞬間、どこかで「あしなが」への寄付金が増やせる、という気持ちが起きていた。なんだかこの出費は奨学生に申し訳ないような気もした。別にだれと約束した訳ではないけれど・・・。 結局買うことにしたのは、暮れに下着を買った以外、自分のための買い物はこの一年近くしていなかったな、という言い訳を思いついたからではある。 ともあれ購入して、早速電車の中で譜読みを始めた。 谷川俊太郎の詩を実は二番までしか知らなかった。 三番の歌詞が目に入った瞬間、グサッと刺さるものを感じた。菅原伝授手習鑑の寺子屋のように、フィクションでも子供の死ぬ場面は苦手なのだ。 買ったことを後悔しはじめた。他のページを繰ってみた。 大竹伸朗の美しい挿画がたくさん入っていて、少しだけ救われた気がした。 絵を探しているうちにまた「死んだ男」の最後にきてしまったが、歌詞は六番になっていた。 そこには「輝く今日とまた来る明日」の文字が躍っていた。 欝になって以来、馬鹿な所業で大事な大事なアンカーを壊してしまったことばかり悔んでいたが、どうせ修復不能なアンカーなら、そのアンカーと一緒に僕自身も殺してしまえば済む話だった。 禅の世界ではしょっちゅう大死一番という言葉が出てくる。 そうだ、生まれなおせば良い。輝く今日とまた来る明日を信じて。 死んだ男の残したものは 一人の妻と一人の子供 他には何も残さなかった 墓石ひとつ残さなかった 死んだ女の残したものは しおれた花と一人の子供 他には何も残さなかった 着物一枚残さなかった 死んだ子供の残したものは ねじれた足とかわいた涙 他には何も残さなかった 思い出一つ残さなかった 死んだ兵士の残したものは こわれた銃とゆがんだ地球 他には何も残さなかった 平和ひとつ残せなかった 死んだ彼らの残したものは 生きてる私 生きてるあなた 他には誰も残っていない 他には誰も残っていない 死んだ歴史の残したものは 輝く今日とまた来る明日 他には何も残っていない 他には何も残っていない
2005年06月29日
コメント(3)
-
昨夜は楽しかったな
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Tuesday, June 28, 2005 10:09 AM Subject: 28日の日記 昨夜は僕の誕生日。朝、出勤前に僕の実家と家内の実家からプレゼントが届いた。 帰宅すると小百合が花籠に明るい色の花を、あふれんばかりに挿している。 これは小百合からのプレゼント。このところ僕は花さえ生ける気になっていなかったが やっぱり花があるっていいな。 健博からは龍の絵。円山応挙を模写したらしい。鉛筆画だがなかなかの迫力。 額縁を新調して飾らなくちゃ。 しげみの手料理と二十五年間僕の講義を欠かさず聴いてくださっている中嶋さんから 到来した「萬壽」で乾杯。 乾杯に続いて、この二三年途絶えていたのだけれど、僕から皆へのプレゼント。 小百合が三歳のころから始めた習慣だったろうか。 自分の希望をあらかじめ伝えて買ってもらう自分自身の誕生日とは違って、何が貰えるか 判らないプレゼントが来る日がお父さんの誕生日。 ともかくお父さんの誕生日を子供たちが心待ちにしているのは僕も嬉しいのだけれど、 意外性の追求にくたびれてしまって、なんとなくやめてしまっていた。 今年は久しぶりの復活だったからそれだけで意外性は十分効果を発揮した。 健博には学研の大きな付録がついた雑誌「科学の卵」。 しげみと小百合にはパールのイヤリング。銀座の小店で店員さんと相談しながらデザイン を決めて作ってもらった。ひょうたんの好きなしげみには大小の珠を組み合わせて揺れる様に。 イヤリングははじめての小百合には、花の形に刻んだピンクの貝殻の花芯に2ミリくらいの珠。 どれもそれほど高価なものではないけれど、みんな気に入ってくれたらしくて良かった。 とくに健博はエアーエンジンを早く組み立てて自動車やヘリコプターが作りたくて、食事中 何度も注意されるほど。小さい頃と少しも変わっていない姿をみて喜んだり安心している僕って なんだろう。ふだんはどんどん背丈が伸びて僕に追いつきそうな勢いを喜んでいる僕なのに。 禅語でいうとなんだろう?やっぱり日々是好日かな? 欝もどんどん軽減していくだろう。
2005年06月28日
コメント(0)
-
蓮の露
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Wednesday, June 15, 2005 10:13 AM Subject: 15日の日記 今日はとうとう休講にして治療を受けることにした。 鬱病の人を心配しているうちに、自分自身が鬱になっていた。 一ヶ月もの間気が付かなかったのは迂闊だが、過ぎてしまった時間は取り返しようがない。 それより、このことに気付かされたのは、昨日の本のお蔭かもしれない。 私が感謝しているのは誰だろう。次から次へと世話になった方の顔が浮かんでくる。 どうして僕にはもう誰も相手にしてくれる人がいない、などと考えてしまったのだろう。 家族や職場の同僚や心友の顔に混じって、今は休診中の漢方医の事が思い出された。 彼の心臓病はいまどうだろう。漢方で治る領域ではないから西洋医学によって加療中だが、もうすでに半年になる。 早く現場復帰してもらいたいものだ。 彼の診察の期待できない今、どうすれば・・・ 比較的軽い症状なら漢方にも鬱の対策があることを思い出した。 半夏厚朴湯という漢方の抗鬱剤を飲んだら、ものすごく眠くなった。 二時間以上連続して寝たのはどれくらい久しぶりだろう。気がついたら五時間も寝ていた。 頭の中に張っていた雲の巣が随分小さくなっている。 完全ではないが、頭痛も軽減され、体も軽い。 急ぎの仕事はあるのだが、気持ちが軽いわりに、背骨の痛みが激しい。 起き上がってゲラに目を通すのが、何となく億劫だ。 手元にあった『蓮の露(はちすのつゆ)』を取り上げた。 最晩年の良寛と知り合った貞心尼が編纂した二人の和歌を集めた歌集だ。 十六歳か十七歳で嫁いで、五年後に亭主と死別して出家した貞心尼が、良寛を噂に知ったのは二十代はじめ、二人は四十歳以上離れている筈だが、その交遊は良寛の亡くなるときまで続く。 いついつと待ちにし人は来たりけり 今は手をとり何を嘆かん 良寛 も良い歌だし、 君にかくあひ見ることのうれしさに まだ覚めやらぬ夢かとぞ思う 貞心尼 は深く心にしみこむ。 私も感謝の心で見ることが出来たなら、どれほどの感激を伴って出会いを受けとめられただろうか。 二人の歌を読んでいると、お互いに相手の事を思うだけで、心が温かいものに満たされていくのが、本当に手に取るようにわかる。 良寛が実に正直に心のうちを詠っているのが、ほほえましい。 君や忘る 道や隠るる このごろは 待てど暮らせど 訪れのなき 良寛 は、例年になく雪の多い冬に道を閉ざされて、老齢の良寛がひたすら待ちわびる心を包み隠さず詠んだものだ。 若いとはいえ貞心尼とて女の身、心に任せぬ雪道の難儀を人づてに伝えるよりなかったのであろう。 ことしげき むぐらの庵の 閉じられて 身をば心に 任せざりけり 貞心尼 やがて春になるや、翼を得た小鳥のように、貞心尼は良寛の草庵を訪ねる。 体力もめっきり落ちた良寛は、貞心尼の手を握ったままじっと離さない。 ようやく離すと、近くの紙に筆を走らせた。 天が下に 満つる玉より 黄金より 春の初めの 君が訪れ 良寛 こんなに正直に、何の衒いも躊躇いもなく心を伝え得るのは、良寛が本当に自由な境地を獲得していたからだろうな。 私も自分で自分の心に手かせ足かせをはめるのは、もういい加減によして、残る人生を楽しみたい、そう思いながら再び薬のせいか、眠りについていた。
2005年06月15日
コメント(0)
-
東山水上行と『人生を変えた贈り物』
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Tuesday, June 14, 2005 10:07 AM Subject: 14日の日記 東山水上行について話さなければいけない日が、刻々と近付いてきている。 この頃の錯乱したような精神状態で、こんな話ができるのだろうか。 しかも八日間にわたって、のべ千人以上の方々に破綻なく・・・ もうひと月続いている不眠症が、明らかに私の精神生活に異常を齎している。 この話自体は、相対性理論みたいなものだ。 雲水に「いかなるか諸仏出身のところ(もろもろの仏が生まれるのはどんなところですか)」 と訊ねられて、雲門文偃(うんもんぶんえん)が「東山水上行(山が水の上を流れて行くよ)」と答えた故事である。 通常わたしたちは、山は動かぬもの、水は流れ行くもの、と見ているわけだが、水から見れば山が流れていると見ることも当然可能になる。 天動説から地動説への意識の転換はキリスト教世界では大問題になった。 世俗の学者から提議された説が神学の世界に大きな揺さぶりをかけた事件であった。 禅の世界では宗教界の大立て者=雲門宗と呼ばれる禅の一派を形成する雲門文偃から、コペルニクス的発想の転換が促されている。 古来、あまたの人々によって解説されてきた東山水上行について、手元にある限りのものを比べてみる。 たいていは、間違っていないが真意には到達していない無難な解説ばかりで、こんなものをいくつ読んでみても始まらない。 やっと道元の『正法眼蔵』巻十四「山水経」にたどりついた。 とはいえ、『正法眼蔵』ぐらい難解至極な文章もない。 わからぬところだらけだが、ともかく講演初日まで三日しかない。 解かる所から手がかりにしようと読み進めていると、次のような一文にであった。 われわれ人間は、人間の立場から水をながめているが、竜や魚の立場に立ったら、水は宮殿に見えるだろう。ちょうど人間が宮殿を眺めるときに流れるものとは決して見ないように。もしも傍で誰かが竜や魚に「お前が現に宮殿として眺めているものは実は流水なのだ」と言ってやるならば、それはわれわれ人間が現に「山は流れるものだ」という言葉を聞いて驚くのと同じようなものであって、竜も魚も即座にびっくりして首をかしげるであろう。 この言葉なら誰にもすんなりと受け容れられるだろう、と少しほっとする。 ちょっと休憩のつもりで、原稿作りの手を休めてメールを見ると、何人もの人からアンソニー・ロビンズの『人生を変えた贈り物』の紹介が来ている。 昼休みに銀座のブックファーストまで出かけて早速入手する。 冒頭に紹介されているのは、貧しい少年が、食卓の貧しさ以上に父母のいさかいに心痛めているとき、突然現れた感謝祭のプレゼントの話だった。 このときの感謝の気持ちが少年の心を揺り動かした。いつか自分もこんな贈り物ができるようになろうと心に誓った。そして18歳になった少年は自分で稼いだなけなしの金で食料品を買い込み、その日の食べ物にも困っている二組の家族に届けて誓いをはたした。 著者アンソニー自身の逸話を読みながら、ふと気が付いた。 このひと月、私は感謝という言葉を失っていなかっただろうか。 私が苦しんでいたのは自信喪失と、それに起因する身体症状、そして喪失感の加速的増幅。 さらに一層の自信喪失という際限のない悪循環。でもそのどこに感謝の文字があったか? 私をいちばん私らしからぬ者にしていたのは、感謝の気持ちを見失ったことではなかったろうか。 私がここまで落ち込んでいるのだから、あの人なら私に安心を与えてくれて当然と、勝手に期待し、期待が満たされぬことで自信喪失が猜疑心にまで発展していったのではなかったか。 『人生を変えた贈り物』にはさまざま思い当たる節がある。 なかにドライビング・スクールのレッスンの話があった。「スリップし始めると、ほとんどの人は、いちばん怖いものに意識を集中し、壁を見てしまう」がゆえに、壁に激突するという。 「目にするものは数限りなくあるのに、多くの人は、つい嫌なこと、自分でコントロールできないことに気をとられてしまう」とも書かれている。 今の私がまさにそれではないか。 私の人生のなかで、ずばぬけて輝いている大切なもの、それさえも喪うのではないか、という恐怖心から、私の妄想を超えて現実にそれを喪いかけているのかも知れない。壁にではなく、行きたい方向に意識を向けかえられなければ・・・ 発想の転換、水は不動で山が動く、この言葉の全面的理解が可能になるかどうかはまだ解らない。 しかし感謝の二文字で意識の方向を変えられないだろうか・・・
2005年06月14日
コメント(0)
-
独坐大雄峰
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Sunday, June 12, 2005 10:12 AM Subject: 12日の日記 今日は家庭内暴力の果てに、逆にお母さんの手にかかって十六歳で亡くなった井上君の四十九日だった。 彼の同級生たちと一緒に「般若心経」「大悲心陀羅尼」「修証義」などを読んだ。 そのあと、彼の後輩たちの近況が話題に出た。彼の出た中学は今相当荒れていて、とうとう警察の介入が必要なところまできてしまったそうだ。 じつはこの町、私もかつて住んだ所で、そのままいたら私の子供たちも同窓生になった筈なのである。 とても他人事とは思えない。 寺に集まって一緒に読経してくれた高校生たちの表情には、どこかまだ幼さが残っている。 しかし友人の死をきっかけに突きつけられた命の問題に向かいあうまなざしは真剣そのものだ。 こんな難しい問題、そう簡単に正解などはないから、各人が格闘しながら獲得していかざるを得ないだろう。 そのときに何を指針にするかという話になった。 和尚の示唆は「各人が特別な命」であることをしっかり自覚するところから始めるように、というものだった。 お釈迦様が生まれてすぐに「天上天下唯我独尊」と唱えられたという伝説も示された。 そう、まずは何より自分に与えられたこの命の大切さをしっかり受けとめられてこそ、周りの命の大切さも理解できるようになるのだろうな。 このところずっと半狂乱のうちに過ごした私は、ようやく憑き物が落ちたような気がするのだが、正気を取り戻してみると、喪ったものの大きさに愕然としている。 人をあやめてしまった訳ではないのが唯一の救いだが、正直なところ途方に暮れてしまう。 かつて、世界に向かって「私はここにいる」と叫びたいほどの喜びと自信にあふれた数ヶ月があったのは、私の妄想なのだろうか。 百丈懐海(ひゃくじょうえかい)の「独坐大雄峰」を本当に我が物にするにはまだまだ階梯があることを思い知らされている。 井上君、君はもう迷いの世界から抜け出した。私が本当に「独坐大雄峰」(私はここにいる)と叫ぶことのお出来る日を見守っていて欲しい。
2005年06月12日
コメント(0)
-
心友へ、本間一夫さんへ、そして今朝の彼女へ
今朝は赤坂見附駅での人身事故のため丸の内線が一部区間不通だった。 今日は聖心女子大で非常勤講師の日。 広尾に向かうため経路変更して池袋から山手線で恵比寿まで行き、そこから日比谷線に乗換えることにした。 振替乗車券を受け取るとき、山手線で東京駅まで連れて行って欲しいと駅員に訴える声に気が付いた。白い杖をもった若い女性だった。 私とは反対方向だが同行を申し出た。 彼女の手をとって歩き始めると、「こんな忙しい時刻に自殺なんて迷惑な」とひとしきり不満を聞かされた。ごもっともと思いながら、「よほどの事情があったんでしょうね」と言うと、だったら彼女の乗らない電車でやって欲しいと言う。それもわからないでもない。 が彼女の口調にあまり棘があるのが気になった。 彼女は次に、自分が障害者で弱者であることをせつせつと訴えてきた。ああ、悲劇のヒロインと朝からお目にかかってしまった・・・・話の方向を変えたくて、私が「自分が障害者だと思う人は障害者なんだろうけれど、実はたいていの人は自分の障害に気付いていないだけです。障害は個性の一つだと考えては如何ですか?」というと「一般の人からそういう言葉を聞くと嬉しい」という返事が返ってきた。 そして「私たちは五感を使いながら毎日生活しているけれども、どの機能もフルに動員しているわけではなく、トータルで自分の考えた必要最小限を満たして、足りている気になっているだけなので、視力があるからといっても却って見るべきものを見ていないかも知れませんね。」と話すと深く頷いてくれた。 最初のうち、障害のある人に時々見受けるわがままいっぱいに育てられたお嬢さんかな、と思ったが、話しているうちに素直な感性をもっておられるのに好意を懐いた。 ホームがすごい混雑で、やってきた電車もぎゅうづめだったから、一台見送ることにした。 待ち時間ができたので、私が少しばかり「あしなが育英会」の広報活動の手伝いをしていること、あしなが奨学生をもっとも苦しめているのは経済的な問題ではなく、父親を自殺まで追い込む以前に自分に何か出来たのではないかという自責の念だという話をした。 いつの間にか彼女の声から棘がとれていた。そして私のことを気遣ってくれた。 今日は図書館で調べものをするために早く家を出たけれど、それは午後でも出来るから構わないと告げると、恐縮していた。 それから話は点字図書館や一昨年亡くなったその創立者の本間一夫氏のことになった。 短い時間だったけれど、結構いろいろなことをしゃべって楽しかった。 考えてみると、この半月、講義の時間を除けば、必要最小限の言葉しか用いず、もっぱら自分のこと、特に強い喪失感のことばかりに気をとられていたように思う。 彼女と話すことで、本間さんにどれだけ力づけられてきたかを思い出した。一時は自殺さえ考えた私が今日あるのは、彼からもらった一本の電話のお蔭だった。暖かいお人柄にふれるとつい嬉しくて、なんでもない事柄でもお話しを伺っていると、いつの間にか元気を頂いているのだった。私がサントリーホールのオープニングでチェンバロのリサイタルを開いたときにも最前列で楽しそうにしていて下さって、緊張している私にも微笑むゆとりを頂いた。次から次へ、本間さんの思い出が浮かんだ。ちょっとしたことでも毎回几帳面に頂戴した点字のお手紙の、短いけれど優しい文章も思い出した。そして、なんだか今日は本間さんが、落ち込んでいる私を勇気付けるために彼女に逢わせて下さったのかな、という気がしてきた。 そして、禅の話で勇気付けられて自殺を思いとどまってくれるお父さんが一人でも二人でもいたら嬉しい、これ以上あしなが奨学生を増やさないために、私の仕事を通じて出来ることはないだろうか、と考えて文春新書の話を受けたことも思い出した。 どうしてこんな事さえ忘れて半狂乱の半月を過ごしていたのだろう。 今朝の彼女や本間さんへの感謝を日記に記しておこうとコンピューターに向かっていたら、心友から電話をもらった。 彼と会ったらきっと僕の状態が上向くのはよくわかっていたけれど、彼がハードな日々を送っているのも知っている。ここは何としても一人で乗り切ろう。たとえ会えなくたって、彼が元気で力いっぱい仕事しているだけで嬉しい筈ではなかったか。彼が自分の夢の実現に向かって一歩一歩進んでいるだけで楽しいと思えてこそ、心友と呼んでもらえるに足るのではないか。絶対に僕からは連絡すまい。そう決めていた。 その筈だったのに、彼の声を聞いた瞬間から、どんどん上機嫌になっている僕が居る。 小さい頃、何かにすねて泣いて、その後急に機嫌をなおすと、「今ないたカラスがもう笑った」と冷やかされて、囃し立てる人の意地悪に口を尖らせながら、こみ上げてくる嬉しさをどうしようもない気分を思い出した。 この半月なんだったんだろう? 今日から六月。気を取り直して仕事に励もう。 だいぶ原稿が遅れてしまって、七月末は文芸春秋社に缶詰。その前にあれこれ済ませておかなければ。 それにしても心友がいるっていいもんだな。ありがとう。
2005年06月01日
コメント(10)
-
わが名をよびてたまはれ
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Sunday, May 29, 2005 10:15 AM Subject: 29日の日記 昨日は「禅語と墨蹟に親しむ会」の第二回目を開催した。 この二週間、夜もよく眠れず、心身ともに疲れて、休会に してしまいたいと何度も思ったのだが、始めたばかりで止 めるのだけはなんとか防げた。 しかし、こんなに自分の体調管理ができなくなったのは情 けない。 「もう私の力で出来ることはすべて終わったのだ」と自分 に言い聞かせるのだが、虚脱感はおいそれと埋められない。 そう考えてはいけないと思いながら、私の存在をまるごと 否定されたような気分がのしかかって、容易にはねのけら れないのだ。 いや、もっと正確にいうなら、自分自身の存在に実感が伴 わないといった方が近いかも知れない。 疲れているから横にはなるのだが、寝つけないし、まどろ んでも時計を見ると一時間強しか眠っていなかったりする。 輾転反側しながら夜明けを待っている。 「痩せたんじゃない?」と家内や娘に言われた。 そのうち声が出なくなってきた。 自傷行為まで考えた訳ではないが、体が衰えてくる事で、 どこかお詫びのつもりになっている自分がいる。それでど うにか心身のバランスがとれているらしいが、この状態で 禅語などしゃべるのは所詮無理だ。 特に重いテーマになると体力気力の充実が無ければ、言葉 だけが上滑りしてしまう。何を話せばよいだろう。考えて あったのは、今月一日、この日記に書き込もうとして消え てしまった「汝は是れ慧超」だったが、こんな言葉は余程 ハイテンションにならなければ伝えようが無い。 といって資料を新たに作り直す時間もない。 散々迷った挙句、この語を今の私に出来る範囲で伝える方 法を探すことにした。 ちょうど手元に鈴木秀子著『死にゆく者からの言葉』があ った。この本の伝えてくれる言葉はどれも優しい。どんな 死者も死の直前には美しいものを見て安らかに旅立ってい くらしい。彼女が見送ったさまざまな例を読んでいると、 涙はあふれてくるのにどこか心の深いところで安らぎを覚 える。いや涙を流すことで私の脳のなかにモルヒネのよう な物質が生まれ、それが私を癒してくれているのかも知れ ない。 ともかくこの本を見つけてからの一週間、随分と楽になっ たのは確かだ。その中の一章を「汝は是れ慧超」とリンク させて語ることにした。 鈴木さんの本に紹介されているのは、山中に蹲っている状 態で発見されたため「山のおじいさん」と呼ばれていたア ルツハイマーの老人の話だ。本名のわからぬまま養老院に ひきとられた「山のおじいさん」が、亡くなる少し前につ ぶやいた言葉は、 「わが名をよびてたまはれ」 ようやく聞き取れた言葉がこれだった。 しかし彼の名をなんと呼べばよいのか。人々が当惑してい ると、次第に朗々とした調子で繰り返す。 わが名をよびてたまはれ いとけなき日の呼び名もて わが名をよびてたまはれ と三度繰り返してのち、 あはれいまひとたび わがいとけなき日の名を よびてたまはれ 風のふく日のとほくより わが名をよびてたまはれ 庭のかたへに茶の花のさきのこる日の ちらちらと雪のふる日のとほくより わが名をよびてたまはれ よびてたまはれ わが名をよびてたまはれ 幼き日 母のよびたまいしわが名もて われをよびてたまわれ われをよびてたまわれ と一気に謳いあげたという。 これは三好達治の『花筐(はながたみ)』に収められた 「わが名をよびて」という作品だった。 わが名さえ忘れてしまった老人が、わが名を呼んでほしい という。しかも、最後の一節 幼き日 母のよびたまいしわが名もて われをよびてたまわれ われをよびてたまわれ は原詩にはないのだそうである。 鈴木さんは「彼が詩の一節として記憶していたのか、ある いは死を前にして心からほとばしり出たのか、私にはわか りません。私はその時、詩の一節として聞いていました。」 と記す。 そして彼女は山のおじいさんを想いながら旧約聖書の 「イザヤ書」の一節を口ずさむ。 あなたを想像された主は あなたを造られた主は 今、こう言われる。 恐れるな、 あなたはわたしのもの。 わたしはあなたの名を呼ぶ。 わたしの目にあなたは値高く、貴く わたしはあなたを愛し わたしはあなたと共にいる。 名前はそのひとのアイデンティティーです。 聖書の中で、「名を呼ぶ」ということは、ひとりの人間 に対する神の無限の愛の証しです。ひとりの人間を、固 有のかけがえのない存在として認めることです。 自分の名を呼ばれた人は、こう感じるのです、と鈴木さ んは続ける。 敬虔なクリスティアンなら「人生をさまよいつつ送る私、そ んな私を心にかけてくれる人――その他大勢の中から私を選 び出し、私に目をとめ、私を記憶にとどめ、『私は特別な人 間である』と私に信じ込ませてくれる人」としてきっと神を 感じることができるのだろう。 慧超は法眼文益和尚に「いかなるか是れ仏」と問いかけて 「汝は是れ慧超」という答えをもらい、その瞬間に大悟する。 慧超はこの一瞬に、自分の存在を根底から支えているものに、 あらためて命を与えられた思いだったのではなかろうか? アルツハイマーに冒されたあとも、愛を敏感に感じとり、人 間としての尊厳を保ち続けた「山のおじいさん」は、人間と してこの世的な存在が、すべて消え去ろうとするその時に、 全生涯をそして彼自身を、一編の詩に集約させた。 慧超は禅僧としての出発点からまだ何歩も歩き出さぬうちに、 名を呼ばれて大悟し目覚しい活躍をする。 ところで、もろもろの伝記によれば、慧超は幼名だという。 当然出家以前の名という事になる。しかし本当にそうだろう か?そもそも慧超という名は俗名らしくないし、『碧巌録』 では雲水として彼がまず自分の「慧超」という名を告げた後 に質問したことになっている。 彼がのちに帰宗策真という名になるのは確かだが、慧超は幼 名ではなく、得度ののち最初にもらった名ではなかったろう か? 私もいろいろの名を受けてきた。親からもらった博美の名、 師匠からもらった英稜の名、亡くなられた永平寺の秦慧玉管 長は、なぜか私を「山田君」としか認識されなかったが、あ れはどうしてだったのだろう。 タローと呼んでくれるグループもあった。 半狂乱のタローをわが事の様に心配してくれたノリちゃん、うるるん、トッチー、 ワンコ。早く元気になって彼らに御礼を言わなくちゃ!
2005年05月29日
コメント(1)
-
ほどける
----- Original Message ----- From: > To: ??????@s5.dion.ne.jp> Sent: Sunday, May 22, 2005 10:27 AM Subject: 22日の日記 ある青年の事がずっと気にかかっていた。友人で命の恩人の息子さんだ。 その友人からのSOSを受けて、私にも何かできるのではと、この9ヶ月あまり 突っ走ってきた。私は遮二無二頑張ってきたつもりだ。 だから見えなかったのかもしれない。彼の本当の苦しみが。 病気はだいぶ快方に向かっていたのだが、彼は治療を打ち切って外国に旅立って しまった。その病気自体も苦しいが、闘病も苦しい様子だった。 私は医者でもないのに、親と同じように医療に関心を向けていた。 しかし、彼がいなくなって十日、一人になると彼のことを思い、涙があふれてきた。 その涙は彼の苦しみに向けたものであったり、徒労に終わった私の虚脱感に向けた ものであったり、あるいは私に援助を惜しみなく与えてくれた心友へのすまなさでもあったろうか。 私が本当にすべきだったのは、親にも医者にもできないケア、彼の苦しみに寄り添い、 苦しみの縄を少しずつほどいていくことではなかったかとようやく思い至る。 「ほとけ」の語源はほどけること。 まわりの人々が決めてくれたアイデンティティに忠実であろうとしたこと自体が、彼の病気の 根本原因だったかも知れない。 僧籍まで頂きながら、彼の苦しみをほどくことに努力しなかったことは本当に申し訳ない。 どうか無事に帰国して欲しい。あなたと苦しみ悲しみをともにするから。
2005年05月22日
コメント(0)
-
風動鶴帰松(かぜうごきて つる まつにきす)
一昨日仙台に行った折、タイトルの語の読みと意味を尋ねられた。この語は表千家流では初風炉(しょぶろ)の時期に必ず掛けられるものだそうである。表千家のそうした約束は知らないが、初風炉といえばまさに今の季節。この語が五月に特に好まれる由来は、今度家元にお目にかかった折にでも伺ってみよう。それはそれとして、おとといはとっさに『廬山記』の「鶴宿千年松(つるはやどる せんねんのまつ)」を想いだしながら、思い付きを答えておいた。つまり、鶴は現実にさまざまな形で活躍する自分の姿の一つであり、松はその自己本来の姿である。「鶴舞千年松(つるはまう せんねんのまつ)」という語と対比すると「宿」が静的なのに対して「舞」は動的な印象を与えるが、無心に舞い、疲れたら休む自在さこそが、その生命であろう。そうなれば、風のゆらぎに鶴がふと一瞬、自己の帰するところを思い出したのでもあろうか。鶴も松も長寿の象徴として、めでたい席に好んで用いられる。不老長生は人類の千古変わらぬ願いだからである。そういえば『荀子』に、それでは千年生きることができるとするとどうなるだろうか、という議論があった。答えは「千載を見んと欲すれば則ち今日を審らかにすべし」とあった。たしかに一日一日を大切に生きることの積み重ねがあって、初めて千年の流れに意味がある。茶道の始まりは風炉の点前であった。風薫る五月に、初心に帰って風炉を出すこの時節、舞うに忙しい我々もひととき松に羽休めても良いのかも知れぬ。それにしてもこの語、片っ端から禅籍を繰ってみても、出てこない。一句だけでなく絶句なり律詩なりの全貌がつかめれば、もう少し当て推量ではない答えが出せそうなのだが。江湖の諸賢の御慈教を待つ。
2005年05月10日
コメント(3)
-
打つ者も 打たるる者も もろともに ただひとときの 夢のたわむれ
今日は母の日。皆さんはどういう風に過ごされただろうか。私は今朝も毎週の日曜のように、師匠の寺に、檀家の方々と一緒にお経をあげに行った。読経を始めようとしたら、見知らぬ夫人が仲間になった。般若心経・大悲心陀羅尼・修証義と型どおりに読み終えて、最後の回向文になったところで、師匠が知らぬ人の名前を読み上げた。どんな事情のある方だろう。今日の珍客にゆかりの方に違いないとは想像できたが、深く詮索すべきものでもないし、そのまま終わるものと思っていた。ところが、案に相違して、和尚が説明を始めた。いま回向したのは○○君と言って、家庭内暴力の行き着く果てとして、逆にお母さんの手にかかって亡くなられた方です、という。そして、今日の珍客はそのお子さんと同級の子供さんを持たれたお母さんだった。葬儀らしい葬儀も挙げられなかったその子のために、冥福を祈って欲しいという趣旨であった。胸ふさがる思いがした。で、いまの読経は冥福を祈るものであったとしても良いが、私たちはそれだけで良いのだろうか。ふとそんな気がしてならなかった。亡くなられたお子さんはもう手の届かない世界に行ってしまったし、もう苦しみの無い世界でもあろうから、生きながら地獄にいるお母さんのために何をして差し上げられるだろうか、と和尚に聞いてみた。和尚は余計な世話を焼くな、と強い語気でいう。私とて安直な慰めが役に立つとは思っていないが、和尚の言葉が意外で、すんなりとは合点がいかなかった。私は昔から、仏教は生きて苦しんでいる人のための救済を目指すものだと思ってきた。お釈迦様は輪廻を抜け出て、二度と生まれ変わらないために解脱したのではなかったのか。悟りはそのためではなかったのか。和尚だってそんなことは百も承知、二百も合点の筈ではなかったか。寺院経営上の問題は脇において、こんな場合はもっと真剣に本音で話しても良いではないか。しかし和尚の口調はいつになく厳しい。和尚も私もそこで口をつぐんでしまったのだが、互いにムッとするものがあった。その空気を察して、近所の内科のお医者さん=越島先生が、良寛の歌を披露された。越島先生は八十歳をとうに超えておられるが、いつも頭脳明晰で、彼の博識には舌を巻くのだが、今日は本当に救われた。それがタイトルの和歌である。越島先生はこの和歌の背景を説明された。或る年、不作のために畑荒らしが横行した。乏しい食料は奪う側にも奪われる側にも、互いに抜き差しならぬ死活問題を抱えてのことであった。夜道を良寛が通りかかると、畑荒らしと間違えられて、散々なぐられ小突き回された。やがてそれが良寛であると村人が気がついて、今度は平謝りに謝った。もとより、良寛は許したが、そのとき詠んだのがこの歌であったという。十六歳で亡くなられたお子さんにも、そのお母さんにも、いや和尚にも私にも配慮を示された越島先生の仲裁に本当にありがたいと思った。読経を終えてその足で仙台に講演に出かけた。五十人の方々と一緒に禅の典籍を一緒に読むのだが、今日で二十一回めだという。長く続いたものだなと思う。二月ぶりの仙台であったが、この間、会員の方々は話したいことを溜め込んでおられたのであろう。帰りの新幹線ぎりぎりまで次々とそれぞれの話を持ち込まれた。最後に老婦人が追いかけてこられた。お孫さんが高校の教師からセクハラを受けて、その母親も精神的な衝撃を受け、三代の女性たちがいま家庭内で苦しんでいるという。でも今日の話を聴き、きっといつか救われる日があると確信できたと喜んで私の手を握られた。少しはお役に立ったのかな、と安堵しながら、大変な母の日だったな、この一日を帰りの車中で振り返った。帰宅して母に電話した。すでに自分の母と、家内の母にそれぞれちょっとしたものを贈ってあったが、手紙を添えていなかったので子供たちと一緒に電話をした。まあ、どこにでもある平凡な、平凡ななりに幸せな母の日であった。そしてこのつつましい幸せに深い感謝を覚えた。
2005年05月08日
コメント(0)
-
汝は是れ慧超(なんじはこれ えちょう)
残念ながら先ほど書き込んだ日記が、消えてしまったようだ。10000字の字数制限ぎりぎりに削り込んで「登録」をクリックしたのだが、ちょうど楽天広場のメンテナンスの時間だったせいだろうか。ともかくこれから支度して師匠の寺に読経に行き、その足で幕張に向かわなければならない。JR福知山線の事故とJMMの冷泉彰彦氏の記事に触発されて『碧巌録』第七則を僕なりに読んだのだが、タイトルだけ残して後日また書くことにしよう。
2005年05月01日
コメント(0)
-
父母未生已前(ふぼみしょういぜん)
昨夜は同僚の父上のお通夜に、南柏という所まで行ってきた。常磐線は新松戸までしか行ったことがないものだから、アナウンスを聞き損って、通り過ぎてしまったのではないかと、まるで小学生のように緊張し、あらためて私の生活圏がいかに狭いか感じさせられた。車内で交わされる言葉のイントネーションも、ごくわずかだが違うように思われる。不意にエトランゼになった気がした。職場を挟んでそれぞれ50分程の所に住んでいるのに・・・・生活圏が狭いことは、おそらく人生の体験の幅の狭さに直結するであろう。これくらいの移動距離を大冒険のように感じているのだから、千年以上昔の中国の口語を本当に正しく読めているんだろうか・・・・根拠の無い自尊心は、こんな風にいつも脅かされている。私は禅宗を文献でたどる道を選んだわけだが、昨夜のお通夜は日蓮宗だった。それにしても、ちょっと前まで、黒い服を着るときは結婚式の披露宴ばかりだったのに、この何年かは葬儀ばかりだな、と腐っていたが、会場に入るなり聞こえてくる日蓮宗独特のにぎやかな雰囲気に、少し慰められた。読経もなかなか良かったが、説教も素晴らしかった。私どもの宗祖の教えに、「人は三度生まれる」と申します。最初は母の胎内に宿ったとき、次は十月十日経って母の胎内を出たとき、そして三度目は「往きて生まれる」往生のとき。ですので、お母様のお腹に宿ったときから数えます。したがって私どもは数え歳で申します。故人は八十八年のこちらの生涯を閉じられ、今あちらの世界にお生まれになります。もう残念ながら故人の姿を見ることも声を聞くこともできません。しかし、いま法華経の観世音菩薩普門品をお読みしました。観音様は「音を観る」と書きます。また香道では「香を聞く」と申します。音を眼で観ることも、香を耳で聞くこともできませんが、心の眼、心の耳には故人のお姿もお声も生き生きと見え、聞こえることでしょう・・・・さまざまな人生経験を持ち、一人ひとり理解度の違うであろう会葬者の誰の胸にも響く僧侶の静かな声だった。あらためて我が禅宗の言葉の特殊性を思わされた。禅宗ではしばしば「本来の自己」をしっかりつかまえているか、という意味で「父母未生以前」という言い方をする。自分が生まれる前どころか、両親が生まれるよりさらに前の世界はどうだ、なんて聞かれたって答えられる筈がない。あえてそうした問いかけをし、独特な回路を経て悟りを得る手伝いをするのが禅僧だが、しかしこの解り難さの陰に隠れて、正直者を煙に巻くような、詐欺師のような仕事をしていないだろうか。常に自戒が必要だ。一応「父母未生以前」は迷いと悟り、或いは凡と聖などといった区別を超越した絶対無差別の世界、と解説するのだけれど、じゃあお前はその世界に足を踏み入れたことがあるのか。わずか一時間四十分の距離さえとてつもなく遠く感じているお前が・・・心の中の声にひとしきり脅かされながら、いや一時間四十分の距離に、自分の足元を見つめなおすきっかけを頂いたのかな、と思いながらの家路であった。
2005年04月30日
コメント(0)
-
青雲在目前(せいうんは もくぜんにあり)
五月一日からジェームス・スキナー氏の「成功の9ステップ」というセミナーに行く。行くことは随分前に決めたのだが、受講生として行くか、ボランティア・スタッフとして行くかはなかなか決められなかった。心友にも相談し、一度は受講生として行くと決めていたのだが、直前でボランティア・スタッフになることにした。スタッフの数が少し足らないので、翻意したのだが、なぜそうしたのだろうか?自分でもなかなか自分の行動がよくわからなかった。数日して潜在意識にきがついた。このところ、ひどく自己重要感が希薄になっていたのだ。だから誰かに「手を貸して」って言われたかったのだな。でも猫の手にさえなれないかも・・・自分でももてあます始末の悪い私が出てきてしまった。こういうとき禅では、その問題がこころに浮かんでも、それ以上追い詰めない、という手法を使う。ともかく今は、セミナー直後に行わなければならない自分の仕事の段取りをしよう。そう頭を切り替えて禅語を探しているうちに、タイトルの一句が浮かんだ。唐の詩人高適の詩の一節で「白髪閑事に老い(はくはつ かんじに おい)青雲目前に在り」と詠う。青雲は青雲の志のことで、徳を修めて聖賢の域に昇らんとする志をいう。そうだ、私の髪もだいぶ白いところが増えてきたが、セミナーに行こうと即決したのは、まだまだ青雲の志を失っていない印だ。がんばってこよう。心友も一緒にいることだし。そうそう、白楽天にも「歳月徒に催す白髪の貌(さいげつ いたづらに うながす はくはつのかお) 泥塗に屈せず青雲の心(でいとに くっせず せいうんの こころ)」とあったな。いっそのこと これを題材にして話すことにしようか。白楽天は禅の修行をし、仏光如満の弟子となった程の人物でもあるし・・ただし気を抜くことのないようにだけは留意しなければ・・・この前の日記に若杉さんが寄せて下さったコメントを見ても、私以上にきちんと読める方々がお客様なのだから。
2005年04月29日
コメント(1)
-
落花を逐って回る(らっかを おって かえる)
若杉賢さん、有難うございました。まだ御目にかかりませんが、お励ましの言葉にどれほど助けられたか知れません。この場を借りて御礼申し上げます。昨日は心友一家や、心友のお兄さんの恋人もまじえて、我が家も全員で花見をしました。爛漫の花のもとに、弁当をひろげ、たあいも無い話やゲームに興じただけですが、心通う人々がいるという幸せをしみじみ感じました。今日のタイトルは『碧巌録』第三十六則の一節からです。長沙景岑(ちょうさけいしん)という唐の時代の禅僧の言葉です。長沙の生まれた年はわかりませんが、亡くなったのは西暦868年です。長沙は、放浪の好きな人物でした。住職となってたくさんの雲水を預かる身となっても、なかなか寺の中にじっとしている事ができません。うららかな春の一日、誰にも告げずに遊山に出かけました。寺では住職がいなくなったので大騒ぎになった事でしょう。首座(しゅそ)は寺の門のところで心配しながら立っています。首座というのは、寺を学校にたとえると学級委員長みたいな役割です。担任にあたる住職がいなくなれば、首座はクラスの全員にあたる雲水たちに自習を命じながら、担任が帰るまであれこれ気を配っていた事でしょう。で、首座が万策尽きて門前で放心しているところへ、長沙が帰ってきます。首座は長沙に「どこへ行ってたんですか」と声をかけます。おそらくほっとして出た自然な言葉だったでしょう。ところが、長沙は首座がやきもきしながら過ごした一日を、知ってか知らずか、のんびりと「遊山じゃ」と答えます。その答えに拍子抜けし、またちょっと批難の気持ちも籠めて首座は「どこへですって?」と重ねて問います。すると長沙は「始めは芳草に随って去き(はじめは ほうそうに したがって ゆき)、又落花を逐って回る(また らっかを おって かえる)」つまり、萌え出した草花の香りに誘われて出かけたのだが、帰りは散る花に追いつ追われつしながらだったよ、と答えました。首座は「大いに春意に似たり」いいご機嫌ですな、と精一杯の皮肉で応じます。長沙は動ずることなく「又秋露の芙渠に滴るに勝れり(また しゅうろの ふきょに したたるに まされり)」と答えます。(芙渠の渠は正しくは草冠が付きますが、文字化けするので使えません)長沙の言葉は、枯れた蓮に露が滴っているわびしい秋の景色より、やっぱり春の楽しさはずっと良いものだ、という意味です。二人の会話はこれしか記録されていませんが、この長沙の言葉の裏側に秘められた思いを、のちに雪竇(せっちょう)という禅僧が偈(げ)にします。偈というのはあまり厳密な約束にしばられない詩の一種と思ってくだされば結構です。その偈はこうです。大地 繊埃を絶す(だいち せんあいを ぜっす)何人か眼を開かざる(なんぴとか めを ひらかざる)始めは芳草に随って去きまた落花を逐って回るるい鶴 寒木に はねやすめ(るいかく かんぼくに はねやすめ)狂猿 古臺に嘯く(きょうえん こだいに うそぶく)長沙 限りなきの意(ちょうさ かぎりなき の い)咄(とつ)この世界はすべて仏様の世界ですから、そもそもきれいだとか汚いだとか、余計な意識をさしはさまなければ、塵埃などある筈がありません。そこがわかれば、仏道の奥義を開眼したと言えます。だから志をしっかり持った人物なら誰だって悟りに到達出来ますよ、というのです。そして、眼の開けた人物なら、うきうきした気分の春を存分に味わえるばかりでなく、秋にはやせ衰えて飛ぶ力も無くなった鶴が、葉のすっかり落ちた木の枝にしょぼんととまっていたり、えさが乏しくて廃墟の上で狂ったように鳴く猿の声にも、仏の世界を見て取ることができるよ、と敷衍します。長沙の春のうきうきした言葉の裏側には、うら寂しい秋の風情をしっかりと見据えた世界がある事を伝えています。秋の思いを胸に秘めながら、春の美しさを愛でる事ができれば、人生の意義は何倍にも増して深く味わう事ができるよ、と古人は教えてくれているのでしょう。いえ、古人ばかりではありません。水谷修先生も若杉賢さんも、長沙の心と通い合うものがあると思います。急に変われる訳ではありませんが、私ももう少し人生を深めながら、また禅の言葉に取り組んでいきたいと思います。皆様のお励ましに心より感謝申し上げます。
2005年04月09日
コメント(1)
-
活陥黄泉(いきながら よみに おつ)
半年ほど前から、噂に聞いていた「夜回り先生」=水谷修氏の講演を聴きに行った。長身痩躯の水谷先生は、家内から聞いていた以上にカッコウいい。これからどんな話が始まるんだろうと、ワクワクしていると、低音のよく通る声で「みなさん、こんにちわ」という第一声が響いた。氏は唯の一言で満席の二百三十人といきなり、ラポールを築いてしまった。ウワッ凄い。ノックアウトされたような気がしたが、そのあと出てくる話、どれもこれも衝撃的で参ってしまった。「私が殺した二十人の子供たちと四人の親」という言葉に度肝を抜かれた。ふつうなら、私はこういう表現の中に偽善を感じて不快に陥ってしまっただろう。しかし、その言葉になんのイヤラシサも無いのだ。何故なんだ、何故なんだ、私の頭の中はほとんど思考停止状態。夜回り先生は定時制高校の教師になったときから、夜の世界に沈んでいく子供たちを救おうと、必死に活動してこられた。いや、友人との喧嘩が元になって、定時制高校を希望する事になったときから、その覚悟は出来ておられたのだろう。その喧嘩は、友人と久しぶりに会ってすし屋でジョッキをあげるところからだった。肴に出てきた刺身を前に、「なあ、水谷。腐った魚じゃ旨いすしは握れねえよな。」その友人は定時制高校の教師、水谷氏は神奈川県内きっての優秀校で評判の高い教師だった。しかし、友人が定時制高校の生徒を「腐った魚」に喩えたのが許せなかった。「魚には腐ったのがあるかも知れないが、生徒は腐ったんじゃねえ。腐らされたんだ。俺が行く。お前は生徒を「腐った」と言ったからには教師の資格はない。辞めろ。」威勢の良い啖呵をきった。友人は教師を辞めた。そして水谷氏は勤務先の校長を脅して、定時制に移籍した。三十五歳の時だったと言う。横浜中華街の入口にあるその定時制高校に赴任したその日から、先生の生活は激変した。荒れる学校なんて生易しいもんじゃない。ともかくこの子達と、対等に付き合いたい、そのために始めた夜回りだったという。夜回りの活動を始めてから知り合った子供たちの話が繰り広げられた。母親が逃げ去り、父親と二人で暮らした少年は、六月から九月まで毎年学校を休んだ。背中から尻ににかけて一面についたたばこの火傷を友達に見せたくなかったのだ。幼い頃から続いた父親の折檻の痕だった。暴走族になった少年は、自分のバイクが欲しくて、引ったくりを働いた。彼に七メートル引きずられたおばあさんは、ガードレールに激突し、四日後に脳挫傷で亡くなった。水谷先生に罪を告白した少年は、警察に同行して欲しい、と頼んだ。しかし、先生は「その前にやることがあるだろう」と言った。必死で考えた少年は、まずおばあさんに謝りに行くべきだ、と気がついた。集中治療室の前にいた、おばあさんの連れ合いに、身を投げ出して謝ったが、おじいさんは口もきいてくれなかった。やがて少年院を出て、まじめに働いた少年は給料から生活の最低必要分を除いて、あとはおじいさんに送金し始めた。おじいさんからは葉書一枚来なかったが、許してもらえなくて当然だ、と受け止めた。職場で盗難があり、犯人呼ばわりされた。そこで少年は水谷先生を殺そうと考えた。「水谷、お前はおれを二倍不幸にした。おれを助けてくれたが、受け容れる社会を変えてくれなかったから、おれは二倍不幸になった。だからお前を殺す」これが少年の言葉だった。その日から、マスコミ嫌いの水谷先生は、積極的に社会を変える運動を始められた。こうして私が先生の講演を聴けるようになったのも、この一件のお蔭だった。次から次へと淀みなくあいだあいだに笑いをまじえながら、夜回り先生の言葉は続く。でも、先生が心の中で泣いているのはよくわかる。客席に居る私がハンカチを放せなくなってしまった。涙があふれて止まらない。私はなんと気楽な生き方しか知らなかったのだろうか。自分への怒りが頂点に達しようとした時、先生はこう言われた。今日、この西東京市のホールに来てくださった大人の皆さん、私は皆さんに、夜回りをしなさい、等と言いません。私は私のやりかたでやっているだけです。ただ、こどもたちを愛して見守ってやってください。何もかも見通しておられる水谷先生は、神父になろうと思ったほどの敬虔なカトリックだ。先生はリンパ腫で、もう永くはないと自覚しておられる。だのに治療を受けようともなさらない。生きるか死ぬかは、人間の決めることではない。神様にお任せします、という。私は雷に打たれたようになった。雨の中、二十分ほどの道のりが、来るときとはまったく違った、どこか知らない遠い国のように思いながら帰宅した。私はしばらく、この日記が書けないかも知れない。再び筆を執る様になったとしても、今日のショックは生涯続くだろう。水谷先生には決してかなわない。せめてその告白だけして、しばらく筆をおこう。今まで読んで下さった方への最低限の礼儀として。そう覚悟してPCに向かったとき、ふと思い出したのが、「活きながら黄泉に陥つ」という語だった。これは道元が五十四歳の生涯を終えるにあたって、遺した言葉だ。なぜか水谷先生と道元が重なってならない。
2005年03月23日
コメント(3)
-
日日是好日(にちにち これ こうにち)つづき
おととい『碧巌録』第五則をとりあげたので、昨日は第六則をとりあげるつもりだったが、長文を書いているうちに本題に行き着けなくなってしまった。そこで今日は第六則である。本文にはこう書かれている。雲門(うんもん)垂語(すいご)していわく十五日以前は汝(なんじ)に問わず、十五日以後、一句をいいもち来たれ。雲門文偃(うんもんぶんえん)は唐の時代が滅びようとするころに生まれた傑僧です。西暦でいうと864年に生まれて949年に亡くなっています。唐の滅亡は907年ですから、彼の生きた時代が大変な混乱期だったことはすぐにわかるでしょう。彼は大変人気のある僧で、いつもたくさんの雲水が彼の周りに集まっていました。その雲水たちに向かって十五日以前のことは問うまい十五日以後について一言言ってご覧と彼は言葉をかけます。従来、この十五日ってなんだろう、という詮索がなされてきました。いちばん有力なのが、七月十五日だろうという説です。禅寺は修行の場ですから、毎日坐禅をしますが、そのほかに雑用もあります。雑用も修行の一環として大切に行じますが、徹底的に坐禅をするのは四月十五日から七月十五日の九十日間です。これは夏安居(げあんご)といって、インド以来の習慣です。インドでは雨季にあたって外へ出て托鉢が出来なくなるこの時期に、集中的に修行する風習がありました。これがやがて中国に伝わります。で、この説法は夏安居が終わる七月十五日に、これからどういう覚悟を持って修行を続けていくのか、雲水それぞれの言葉を求めているというのです。十五日以前は汝に問わずと最初にわざわざ言っているのは、この夏安居に入る以前の境地を振り返っても仕方が無い、大切なのは今どういう境地を獲得しているからだ、という雲門の老婆心あふれる表現だと思います。おそらく、たくさんの雲水がめいめい、いろんな表現で答えたでしょう。しかし、彼らの答えは記録されていません。『碧巌録』ではそのかわりに、雲門の答えが書かれています。模範解答です。もっともこれだけが正しい答えという訳ではありません。それぞれの心に響く言葉であることが大切なのです。雲門の答えは日日是れ好日でした。これはふつうお寺では、次のように解説されるのではないでしょうか。仏の道に携わるものは、いたずらに過去を悔い、未来に望みを託さず、常に積極的に今日を生きることに励みなさい、と。過去は取り返しが付きませんし、未来に理想の実現した状態を思い描くのは大事ですが、何か実際に出来るのは今このときしかありません。「未来」は「未だ来ない」ときなのですから。日々が最上最高の日であり、かけがえの無い一日であり、今日一日を精一杯使い切ることこそ、仏の道を生きるもののあり方だ、というのです。さらに進んで、好日を吉日の意味にとり、毎日毎日がすべて仏法を普及させ高い次元で実現するための吉日である、というふうに説法する僧侶も出てきました。でも、この言葉はもっともっと広く解釈することが出来ます。宗教の違いさえ無視しても構わないと思いますし、宗教と無関係だって良いと思います。たとえばセールスマンが、セールスマンとして今日一日を目いっぱい使い切ることが出来るなら、本当に充実した気持ちが得られるでしょう。毎日毎日を充実して生きられれば、それぞれの道を極めるのは決して難しい話ではないと思います。私も今日一日を目いっぱい使い切ってみようと思います。一緒にがんばりましょう。
2005年03月22日
コメント(0)
-
日日是好日(にちにち これ こうにち)
今日は嬉しい日である。昨日、心友から元気なメッセージが届いた。ともあれほっとする。そして今日22日(私は深夜に起きて仕事を始めるので日記も日付が変わってからになるのだが、楽天日記は時差が六時間以上あるらしく、日付はいつも前日になってしまう)は、お祝いの会に招かれている。何のお祝いかというと、本の出版とその内容を六回の連続講義で紹介する、その講義が完了したお祝いなのである。二十数年前、東大総合図書館の書庫に入って、膨大な量の、ほとんど誰も使っていない書籍の山に驚いた。そのコーナーは図書分類でいうと「芸能・遊戯」の古書である。茶道・華道・囲碁・将棋などが大半を占める。所蔵印を見ると、ほとんどのものが、かつて紀州の徳川家に伝えられたものである。八十一年前の九月一日、関東大震災によって、東京大学も相当な被害を受けた。東大の中にはたくさんの図書館があるが、一番大きい総合図書館が全焼したのである。(私の専門である禅の文献も一緒だった。その数年前、先輩たちが資金調達に奔走してやっと銀閣寺から買い取った貴重な史料も灰燼に帰した。)震災から数日後、国際連盟が日本の復興に協力しようと決議した。具体的な協力の一つに、東大図書館の再建が盛り込まれ、十数カ国から図書の寄贈が実現している。図書館の建物はロックフェラー財団がプレゼントしてくれることになった。ロックフェラーからは膨大な洋書の希こう書も贈られている。日本でもいくつかの団体から図書が贈られる事になったが、一番最初に名乗り出て、一番多くの図書を寄贈したのが、紀州徳川家だった。紀州家の蔵書はちょっと変わった特色がある。和書は歴代藩主の趣味を反映して芸能万般にわたる。洋書は明治時代の当主の趣味だった西洋音楽に関するコレクションである。麻布の飯倉片町にあった紀州家の図書館は、この大震災を機に蔵書をすべて寄贈し閉館することになった。和書は東大に贈られ、洋書は東京藝術大学に日本で最初のパイプオルガンと共に贈られる事になった。このオルガンは今でも上野公園の中にある芸大の別館=奏楽堂に設置されて演奏されている。残念ながら洋書は管理が杜撰で、行方不明である。どういういきさつか知らないが日本フィルハーモニーが買い取ったという噂はしばしば聞くが、日フィルは否定している。ロマン派の作曲家の自筆譜など、世界でもこれ一点というような貴重なものが膨大な数含まれていた筈であるが、杳としてわからない。芸大に移管された分は、私の手の届くものではないが、東大の図書については、何とかこれを世間に紹介し、人類の共有財産として護っていく責任がある、と考えておりに触れてその存在を語ってきた。当時はまだ、大学関係者以外、かなり面倒な手続きを経ないと閲覧が出来ない事になっていたが、何よりそこに何があるのか知らなくては、閲覧の手続き自体が出来ない仕組みになっていたからである。だから、そこにこんな天下の孤本があるという事を示すには、蔵書の中から良書を選んで出版するのが良い、と思った。その思いは募ったが、古書の翻刻は大変で、片手間に出来る仕事ではない。誰か協力者を得たいと思っていたところ、『望月集』という本に取り組みたいという篤志家が現れた。そして彼女は何と二年間かけて一人で四冊組のこの本を、ワープロに入力したのだった。この本は、千利休の孫=千宗旦の弟子である藤村庸軒の流れを汲むものらしい。今でも庸軒流を称する茶道の流派は存在するのだが、江戸時代に断絶があって、古い時代の伝承は伝わっていない。江戸初期に今日の茶道の基礎がほぼ固まるのだが、この本は当時の茶道の実態をよく示すものらしいのである。ワープロで打ちあがった厚さ四センチ程のコピーを、彼女は十部作って、これをどこかに寄贈したいという。早速茶の湯に関する有名な著者や表千家・裏千家などの図書室に贈った。しかし、コピーを作って私費で配ったのでは、なかなか普及しない。そこで、私が寄贈を受けた分を持って二・三の出版業者に話を持ち込んだ。しかしどこも採算ベースに乗らない出版には手を出したがらない。考えあぐねてカルチャーセンターの主催者に相談した。するとセンターの講義のテキストとして出版しましょうという快諾が得られた。ただし、その講義を私が担当するという条件が付いていた。私は茶が好きだったし、茶道関係者から多大な援助を受けてきた。しかし、私でなければ出来ない仕事は茶道史ではない、と考えて二十年行ってきた茶道史の講演を今後はしない、と宣言して二年ほど経っていた。センター主催者の意図は、私にもう一度茶道史で登板させようというものだった。正直なところ、私ごときものにここまで熱い思いを懐いて下さる方々がいるのは涙の出るほど嬉しかった。しかし、好きな茶の世界から身を退いてでも、禅のメッセージを正しく伝えるのが私のミッションだと考えていたし、『南方録』という利休の肉声を伝える奥義書を最後に講ずる事で、円満に彼との提携は終了していたのである。いまさら自分の言葉を食むような事はしたくなかった。結局、特別講義を一回だけ行う事で、主催者の面子を立てた。すると彼からは有難い申し出がなされた。出版に先んじて内容を確認する作業が必要になるが、その会場を提供するから、協力者を集めて検討会を行うように、というのである。普通の出版なら、特別の会場を必要としない。大学の会議室でも出来るのだが、この本の出版には、実際に茶室で行わないと見当はずれな議論になる危険があった。本に書かれたとおりに実際に動けるか、という確認が出来なければ、文字通りの机上の空論に終わってしまう。茶室も自由に使える会議室の提供は本当に有難かった。早速協力者を集める事にした。十人からの申し出があった。七年前の事である。私はそれまでのいきさつから、『望月集』の理念を説いた部分まで出席しコメントするが、点前の具体的な記述となる後半は、私以外の人々でお願いする、という条件でスタートした。この七年の間には亡くなった方、体が思うように動けなくなって老人ホームに入ってしまわれた方もいる。中には国税庁長官を退いて次々と天下りして、四度目の転職先の仕事に忙殺されている方など、様々な方がある。結局最後まで残ったのは六人だったが、この六人が精度の高い出版を成功させ、さらに六回の講義を持ち回りで受け持って完了させて下さったのである。本当に脱帽する。私がやった事は、書庫に入って、眠っている貴重書の存在を知ったこと、それを何とかしなければと触れて回った事しかない。にも関わらず、彼らから仕事の完成を祝う席にお招きを受けた。私にその資格があるか、躊躇しないでもなかったが、いつでもまた逢えると思っていると機会を逸するかもしれない。何しろ皆私より年上で、最高齢の方は八十九歳になる。彼女は太平洋戦争中、病院船の看護婦長として辛酸をなめてきた方である。彼女は今日も横浜の自宅から杖を突きながら元気に新宿の会場まで来られるだろう。ところで、どうも今日の会は、中締めらしいのである。第一冊が無事終了したことで、元気付いた彼らは、次の仕事にとりかかるつもりらしい。いやはや何とも逞しい。そして元気な人たちと歓談するのは何より嬉しい。出版社からの出版ではなかったので、ISBNが取得できなかったが、国会図書館に収めてどなたにでも閲覧して頂く態勢も出来、京都の丸善からは店に常置したいという申し出が出て、すでに第三版、五百冊完売して増刷中なのである。それだけ売れるなら手がけたかったと大手出版社から後悔の言葉も来た。今更遅いのだ!ともかく、彼らの元気パワーが無ければ、今日の慶事は無かった。毎日毎日、こつこつと努力してこられた彼らを見習わなければと思う。あ、ところでタイトルの禅語を解説する時間が無くなってしまった。始発の電車は間に合わないが、次に乗らないと予定通り私の仕事が完了しない。故事来歴は明日書こう。
2005年03月21日
コメント(0)
-
百花 春至って 誰が為にか開く(ひゃっか はるいたって たがためにか ひらく)
私は花が好きだ。しかし、「花が好きだ」とだけ言ったとき、どんな花を思い浮かべるかは人により、状況により、また季節によってもさまざまだろう。「花」とだけ言って、多くの人が思い浮かべるのは、日本では桜である。日本びいきのジェームス・スキナー氏が、先日ひょんな弾みで古歌を口にした。 世の中に 絶えて桜の 無かりせば 春の心は のどけからましこの新古今集の歌は、千年来の日本人の心情をよく詠い上げている。世の中に、花は嫌いだと言う人は、そう多くないと思う。もっとも、花見は嫌いだ、という人は何人か知っている。桜の花などそっちのけで騒ぎ立てる人の中には、随分と迷惑な連中もいる。あの喧騒は、こちらの体や心の状態によっては耐えがたいものがあり、たまたま悪い条件が重なれば、私も花は嫌いだ、というかも知れない。しかし、人間の思惑なぞとは無関係に、春が来れば花は咲く。タイトルの語は『碧巌録』第五則の頌(じゅ)の中にある。第五則の主題は、相対世界から絶対世界へ眼を転ずる事を教えるが、その締めくくりに付けられた頌は次のようである。牛頭(ごづ)没し 馬頭(めづ)回える曹渓鏡裏(そうけいきょうり) 塵埃(じんあい)を絶す鼓を打って看来るも 君見ず百花 春至って 誰が為にか開く修行の途中には、はたしてこの道をこのまま突き進んで良いのか、という疑念がしばしば襲ってくる。牛頭も馬頭も地獄の鬼で、餓鬼道におちた人を容赦なく責め立てるそうだが、ちょうど牛頭や馬頭に追い立てられたかのように、心のバランスを失う事がある。達磨から六番目の曹渓慧能の、あの澄み切った鏡にも似た君の心には、本来、塵一つ無い。しかし、君がなかなかその開眼の作業ができないから、鼓を打って人々を集めて手伝おうとするけれど、それでも君は悟ることができない。百花らんまんの この春の風光が 君のためにこそ用意されているのに、君には見えないか?そう言われたって、見えない時は見えないのだ。でも君には経験があるだろう。体の使い方を変えれば、心の状態も変わる。うまくいかないときは、違うことをやってみるものだ。何でも良いから。君はいま青春の真っ只中。ちょっと眼を転ずれば、そこかしこに春の光があふれているよ。私は花が好きだ。しかし、どんな花も君の笑顔にはかなわない。君が憂いに沈むとき、私にも百花は色あせる。どうか愁いの眉を開いて欲しい。私は花が好きだ。そして君の笑顔は何にも増して好きだ。花の下に君の笑顔が見られたら、人生の至福だ。百花 春至って 君がために開く
2005年03月20日
コメント(0)
-
すつるたからをしらぬひとに
心友がこのところ疲労困憊している模様である。私が今までの人生のなかで、最も困難な局面に立たされたとき、彼は私のことをほとんどまだ何も知らないにもかかわらず、持っているものの最上のものを、一瞬のためらいも無く、私に与えてくれた。あの日の感激があるから、どうにか今、私は生きていられるようなものである。では私は彼に何を与えることができるだろうか。考えても考えても、何も浮かばない。考えることを一度放棄したら、本当に求めることが得られるかも知れない。そう思って、前から疑問に思いながら、きちんと読めなかった道元の『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』の中から第二十八巻の「菩提薩た四摂法(ぼだいさったししょうほう)」を開いた。(「菩提薩た」の「た」は土偏に垂と書くが、文字化けするので、ここでは残念ながらこういう表記になってしまった。)これは菩薩が衆生をいかにして救うか、その実践方法を説いたもので、『正法眼蔵』の他の巻が哲学的な思索の展開であるのと比べると、驚くほど具体的で端的な記述である。具体的に記述されたのには訳があって、この巻は道元がふだん接している修行僧のために説いたのではなく、当時の天皇のために書いたものだからである。あれほど権力を嫌い、関白だった父を憎んでいた道元が、従兄弟の天皇に諄々と仏法を説いている。それは権力というものを嫌いながらも、権力の座につかねばならなかった人間個々の中には、信を置くに足るものがあると信じていたからであろう。で、その具体的な方法として、道元は「布施」「愛語」「利行」「同事」の四つを提示する。具体的とは言いながら、そのどれもなかなか手ごわい。冒頭の「布施」に取り組んでみて、のっけからパンチを受けた。道元の言葉はその布施といふは、不貪(ふとん)なり。不貪といふはむさぼらざるなり。むさぼらずといふは、よのなかにいふ、へつらはざるなり。たとひ四洲(ししゅう)を頭領(とうりょう)すれども、正道(しょうどう)の教化(きょうけ)をほどこすには、かならず不貪なるのみなり。たとへば、すつるたからを、しらぬひとにほどこさんがごとし。遠山(えんざん)の華を如来に供(くう)じ、前生(ぜんしょう)のたからを、衆生にほどこさん、法におきても、物におきても、面々に布施に相応する功徳を本具せり。我物にあらざれども、布施をさへざる道理あり。そのもののかろきをきらわず、その功の実なるべきなり。今までわからなかったのは、『正法眼蔵』をダイジェスト版にした『修証義(しゅしょうぎ)』で、解ったようなつもりになっていたからだった。ことに『修証義』に省かれている「すつるたからを、しらぬひとにほどこさんがごとし」の一句は衝撃的だった。道元の言う「すつるたから」は要らなくなったゴミなどではない。いや最終的には同じ事かも知れないが、自分の最も大切な命そのもののことなのである。私たちは「目に見えぬ大きな力」によって、この命を授けられた。その「目に見えぬ大きな力」は「人類を平和で幸せなものとし、永遠に栄えるものとしたい」という願いをもって、次々と人間の命を生み出した。この「目に見えぬ大きな力」は慈悲と智慧であり、如来と言い換えても良い。その如来によって今生の命を与えられた事を自覚するものは、最も有意義な命の使い方を模索する。「私の人生の目的は?」と真剣に問い続ける者が最後に到達するのは、人間の小賢しい思いを超えた「目に見えぬ大きな力」にお任せする=「捨てる」しかない。お任せすると覚悟したからには、その最も大切な「たから」=命を知らない人に与える事さえある。遠くの山でやっと手に入れた貴重な花でも、それを惜しげもなく「目に見えぬ大きな力」に捧げ、前世で得た尊い宝を施すように「すつるたからをしらぬひとに」さげることは、理屈で解っても実践は困難だ。しかしそれをいとも軽やかにやってのけてくれた心友がいる。その彼が疲れきっている今、私にできることは・・・・・静かに彼の回復を見守るしかないのか・・・・むかし、山でよく歌った歌を想いだした静かな夜更けに いつもいつも想いだすのは おまえのことお休み やすらかにたどれ 夢路お休み 楽しく今宵も またきみのお蔭で、今夜は「菩提薩た四摂法」を読むことができた。これから私は師匠の寺に行く。日曜ごとに檀家の方々と共に行っている読経の会に出かける。そのバスの中で一時間、私も眠ろう。きみもまた、お休み やすらかに、そして楽しく。きみの人生の本当の目的を実現するために、疲れた体をいたわってやれ。
2005年03月19日
コメント(0)
-
柳は緑
すっかり春めいてきた。久しぶりに不忍池の周りを歩いてみたが、桜のつぼみはまだ固い。あと十日もすれば、今日はほころび始め、今日は三分咲き・・・という噂でもちきりになるだろうが・・・桜より一足先に柳が芽を拭いている。数ミリの長さだが新緑の色が枝に美しい。蘇東坡の詩の一節に「柳は緑、花は紅(くれない)の真面目(しんめんぼく)」というのがある。これは「花は紅、柳は緑」と巷間に言い習わしてきた語順を逆にして用いたものらしいが、ただそれだけの事で、人々に新鮮な感動を与えたのは、宋代の代表的な詩人ならではの腕前だ。どちらが先になろうと事態は変わらない、などといっていると味わいを少し損ねてしまうのかも知れない。ともあれ、うららかな春の景色を愛でながら、自然界のありとあらゆるものが、そのままで真実の世界を具現している事に、感嘆の声をあげているのである。表現のわかりやすさから、古来多くの人々に愛唱されてきた句である。茶道の世界でも、この句はいろいろな場面で出会う。珠光という半ば伝説の茶人は、大徳寺の一休禅師から「そなたが茶道を通じて得た境地は、禅の悟りとまったく同じものである。」として、印可(いんか)されたと伝えられているが、その直前に珠光が唱えたのが「柳緑花紅真面目」だったという。かくして、珠光の到達した高い境地を認めるにあたって、一休は秘蔵する圜悟克勤(えんごこくごん)の墨蹟を与えたという。どこまでが真実かはわからない。なにしろ、この逸話を記録で跡付けようとすると明治の森大狂まで下ってしまうのである。森大狂の創作とも思えないが、いつごろから語られだしたものだろうか。圜悟の墨蹟は珠光の在世当時、日本には数点あったと推測するが、いつの間にか、その時珠光が与えられたのが、国宝のいわゆる「流れ圜悟」だという説が登場する。圜悟は『碧巌録』の著者として、禅をかじったものなら、知らぬ者とて無い、超有名人だが、その墨蹟が海難事故によって海に投げ出され、薩摩の坊の津に流れ着いたという伝説から「流れ圜悟」の異名で親しまれる事になったものである。ご丁寧にもこの墨蹟が流れ着いたのは、この筒に収められていたからだとして、桐を刳り貫いた筒が、墨蹟と共に東京国立博物館に所蔵されている。ところで、この墨蹟は江戸初期まで大変大きかった事が知られている。東博にあるのはその冒頭の三分の一程なのだ。現存する最古の墨蹟で、これを欲しがる人は数知れぬほどいたし、寺の財政難を救うために切断されたのである。片割れを手に入れた可能性が最も高いのは伊達政宗だが、決定的な証拠もなく、また片割れ自体も現存するのか否かも不明である。で、その筒は現存する軸の幅しか無いのだ。つまり明らかに筒は贋物という事になる。噂が噂を呼んで、とんでもない形で語り継がれる事になったわけである。なべて人の世は・・・柳は緑・・・まことに自然界は真実の具現である、ふとそんな感慨にふける。
2005年03月18日
コメント(0)
-
きざみておかず
しばらく京都にいて、帰ってみると、身の回りがあまりに乱雑なので、一念発起して整理にかかりました。思い切っていろいろなものを捨てましたが、中に不思議な箱がありました。はてこの箱の中は、・・?・・??・・・・????開けてみると、本当に不思議なものがいっぱい、その中でもいちばんショッキングだったのは、中国の人が筆で書いた紙でした。きっと中国からいらした方のお土産だったのでしょう。見ると「きざみておかず」と四文字が大きく書かれています。「きざむ」という文字はここでそのまま書くと文字化けするでしょうが、金へんに契と書きます。その後の三文字は「而不舎」です。これは中国戦国時代の『荀子』という書物の「勧学編」にある言葉からの発想です。『荀子』と言ってもあまり馴染みがないかも知れませんが、「出藍の誉れ」という言葉ならご存知でしょうか?これは指導者より弟子が優れている事を言いますが、これも同じ『荀子』の「勧学編」にある言葉です。で原典には「きざみてこれをおかば、朽木も折れず」と書かれています。これは「たとえ朽木のような材木でも、振り下ろした斧が途中で投げ出されたなら折れない」という意味です。もちろん、「勧学編」の中では、「うまずたゆまず努力する」大切さを、反対の立場から説いたものです。逆に言うと、小さな願いでも、それに向かって一歩一歩進んでいくなら、どんな大木でも倒すことが出来ると教えているのだと思います。不思議に思ったのは、どうして今、これほどいろいろな意味で挫折しかかった僕に、急にこんな文字が出現したのかです。この小さな日記を書き始めましたが、これだって「きざみておかず」という言葉の通りにするのはなかなか大変です。でも長く続けて行けるとしたら、それは読者の皆様のお陰です。有難うございます。これからもどうぞよろしくお願いします。
2005年03月18日
コメント(0)
-
禅語と墨蹟に親しむ会を始めます
この日記を書き始めて、読んでくださる方はそれなりにいらっしゃるらしい事はわかったのですが、本当にお伝えすべき事が何なのか、私の一人よがりが多かったかなと反省しています。そこで、もしも本当に興味を持ってくださった方があったなら、何をどんな風にお話すべきか、考えてみたいと思います。狭い知見でも、それなりに社会のお役に立てればと念じています。ですから、もちろん、私に知恵を授けてくださる方は大歓迎です。いろんなご意見をお寄せください。四月には東京で、禅語と墨蹟に親しむ会を発足させたいと考えています。建設的なご意見にはお答えしたいと思います。私の力量を超えた問題はご容赦下さい。また、日記へのコメントでは書ききれない場合にはzengo-bokuseki@mail.goo.ne.jpに、忌憚無いご意見をお寄せ下さい。拝見して、お答えできる限りはお答えします。どうぞよろしく。
2005年03月12日
コメント(0)
-
只在目前尋無處(ただもくぜんにあり、たずぬるにところなし)
今朝は、二十年来の友人=伊住政和氏の三回忌と、そのご母堂=千登三子氏の七回忌の法要が京都大徳寺山内の聚光院で行われたので参列してきました。聚光院は利休さん以来、千家の菩提寺です。葬儀の日も、昨年の一周忌のときも、雪が残っていましたが、今日はコートも要らぬほどの暖かさ、「年年歳歳花相似たり、歳々年々人同じからず」と言いますが、列席者の顔ぶれも多少の変化を見せ、月日のたつ速さに驚かされます。山内の五箇所の塔頭(たっちゅう)=総見院・三玄院・高桐院・黄梅院・芳春院ではご供養の茶席が設けられていました。最初に伺った総見院では伊住氏の兄上=裏千家家元の坐忘斎宗匠が濃茶を練って下さいました。正客は大徳寺きっての学僧=徳禅寺の橘宗義師です。私はその脇に坐らせて頂きましたが、徳禅寺様を前にしてこんな話を、と躊躇いながら坐忘斎宗匠が床の間の掛軸を氏の独特の読みでご披露されました。それがタイトルの語です。筆者は江戸初期の名僧=清巌宗渭(せいがんそうい)です。清巌師の軸はもう何十幅も拝見しましたが、その語について坐忘斎宗匠から話を伺うのは初めてです。彼は最後の三文字を「尋ぬるところになし」と読んでみたいと話されました。語学的には無理な読み方ですが、よくその意を捕らえておられるのに感心しました。人は遠いところに目指すものが在ると思い込んで、そこに向かって精進するけれど、本当に得るべきもの=宝物は目の前にあるのに、なかなか気づかない、そういう思いでこの軸を掛けました、と氏は話されました。とても仲の良いご兄弟で、それだけに伊住氏が亡くなられてからの二年間、ほとんどお目にかかるたびに帰らぬ人を偲ぶ言葉ばかり伺ってきましたが、ようやく気を取り直されたのかな、と安心しました。夜は京都ホテルオークラで偲ぶ会が催されました。友人で俳優の辰巳琢郎氏がこんな話を披露されました。伊住氏は「金を遺すのは下、仕事を遺すのは中、人を遺すのは上」と生前よく口にしておられたそうです。ああ、私も氏が遺して下さった人の輪の中に入れて頂いて、今日あるのだな、と思うと胸が熱くなりました。兄上や父上が気持ちを新たに今日から踏み出そうとしておられるのに、私が思い出に浸っていてどうする、と思ったのですが、同じテーブルの方々の元気に助けられました。私の左から順にお名前をあげると、新進気鋭の画家千住博氏、陶芸家のリチャード・ミルグリム氏、釜師の大西清右衛門氏、袋物師の土田友湖氏、竹細工の黒田正玄氏、陶芸家の楽吉左衛門氏、同じく陶芸家の永楽善五郎氏といった方々です。皆様それぞれの分野で押しも押されもせぬ活躍をなさっておられる方々で、何故私がこの席に、と不思議に思ったのですが、でもどのかたも一度はお目にかかりたいと念じていた方ばかりです。今朝のお軸「只目前に在り、尋ぬるに処なし」とは、今夜の私にとってご同席下さった綺羅星のような方々だったな、と別の読み方をしてみました。千住氏とはこの数年ゆっくりお話をする機会がしばしばあったのですが、この席に共通の要素は何だか判りますか、という彼の謎はすぐには解けませんでした。降参して答えを伺うと、この席の人はみな物を創る人々です。彼らに「貴方の生涯を代表する作品は何ですか」と尋ねてご覧なさい。彼らは異口同音に「それは私がこれから手がける次の作品です。」と答える筈ですよ、とおっしゃっていました。そして、貴方も次の著書に渾身の力を込めてお書きなさい、という言葉を頂きました。ああ、本当に得がたいと思っていたものが、目前にあるのだな、と有難い思いを懐きながら、最終の新幹線で東京に帰ってきました。いつの日か、千住氏の絵に飾られるような本が書けたらな、という大それた夢を描きながら、常に前進を続けられる人の輪に入れて頂いた事をしみじみ有難く思いました。
2005年03月09日
コメント(0)
-
随処に主となるには
今日は東京の表千家の幹部の方たちを中心に、月江正印の墨蹟と臨済録の中から「随処に主となる」という語の出てくる部分を話してきました。月江の墨蹟は、修行途中で自分の下を去っていく若い僧侶に対して、これからの心構えを諄々と説いたもので、現在は根津美術館に収められているものです。中に「鉄樹花開く春二月」という言葉があって、この季節にふさわしい掛軸です。七十七歳の筆ですが、けっして力は弱くありません。むしろ衰えないところに禅僧の本領が発揮されているというべきでしょうか。「随処に主となる」という言葉は、万言を費やすより、実例を示した方が判りやすいだろうと思って、現代の話をしました。一つはシベリア抑留者の話です。今から60年近く前になりますが、太平洋戦争の最末期に、シベリアに連れて行かれた日本兵がありました。僕のよく存じ上げているかたなのですが、シベリアの想い出を伺う機会があったものですからご披露しました。彼は寒さと飢えに苦しみながらも、次第にレンガ積みの作業に集中していると、飢えも寒さも忘れて、楽しくなっていったと話してくださるとき、普段の好々爺の笑顔がこの世のものとも思えぬ輝きに満ちていましたので、どうしても彼の話をしたかったのです。もう一つは「こころのチキンスープ」から「子犬と男の子」の話です。ペットショップを訪れた男の子は、足の悪い子犬を見つけます。店のオーナーは、あれは売り物にならない駄目な犬だ、欲しければただであげると言うのですが、男の子はその犬を只でなんかいらない、他の子犬と同額で買うと主張して譲りません。男の子はその足の悪い犬だって他の犬には劣らないと言い張ります。最後に男の子は自分のズボンのすそをまくります。男の子の片足はギプスだったのです。そして男の子は言います。僕だったらその子犬の気持ちが判ってあげられると。そう、男の子は自分のつらさをその子犬にわかってもらおうとしているのではないのです。自分の辛い経験から、他者を思いやる気持ちを獲得していたのです。これこそ随処に主となる、という境地を楽々と身につけた生き方の例ではないでしょうか?禅の古典は今に十分通用する内容を持っています。それを現代の人々にわかりやすい実例としてお伝えするのが僕の役目かな、と思っています。皆様からの厳しく暖かいご助言をお待ちしています。どうぞよろしく。
2005年03月05日
コメント(0)
-
随処に主となるには
今日は東京の表千家の幹部の方たちを中心に、月江正印の墨蹟と臨済録の中から「随処に主となる」という語の出てくる部分を話してきました。月江の墨蹟は、修行途中で自分の下を去っていく若い僧侶に対して、これからの心構えを諄々と説いたもので、現在は根津美術館に収められているものです。中に「鉄樹花開く春二月」という言葉があって、この季節にふさわしい掛軸です。七十七歳の筆ですが、けっして力は弱くありません。むしろ衰えないところに禅僧の本領が発揮されているというべきでしょうか。「随処に主となる」という言葉は、万言を費やすより、実例を示した方が判りやすいだろうと思って、現代の話をしました。一つはシベリア抑留者の話です。今から60年近く前になりますが、太平洋戦争の最末期に、シベリアに連れて行かれた日本兵がありました。僕のよく存じ上げているかたなのですが、シベリアの想い出を伺う機会があったものですからご披露しました。彼は寒さと飢えに苦しみながらも、次第にレンガ積みの作業に集中していると、飢えも寒さも忘れて、楽しくなっていったと話してくださるとき、普段の好々爺の笑顔がこの世のものとも思えぬ輝きに満ちていましたので、どうしても彼の話をしたかったのです。もう一つは「こころのチキンスープ」から「子犬と男の子」の話です。ペットショップを訪れた男の子は、足の悪い子犬を見つけます。店のオーナーは、あれは売り物にならない駄目な犬だ、欲しければただであげると言うのですが、男の子はその犬を只でなんかいらない、他の子犬と同額で買うと主張して譲りません。男の子はその足の悪い犬だって他の犬には劣らないと言い張ります。最後に男の子は自分のズボンのすそをまくります。男の子の片足はギプスだったのです。そして男の子は言います。僕だったらその子犬の気持ちが判ってあげられると。そう、男の子は自分のつらさをその子犬にわかってもらおうとしているのではないのです。自分の辛い経験から、他者を思いやる気持ちを獲得していたのです。これこそ随処に主となる、という境地を楽々と身につけた生き方の例ではないでしょうか?禅の古典は今に十分通用する内容を持っています。それを現代の人々にわかりやすい実例としてお伝えするのが僕の役目かな、と思っています。皆様からの厳しく暖かいご助言をお待ちしています。どうぞよろしく。
2005年03月05日
コメント(0)
-
好雪片々
昨夜、窓の外は雨だったのに、今朝起きてみたら隣の屋根が真っ白だ。しきりに降り積もって止む気配が見えない。雪を見るといろいろな想い出が蘇ってくるが、時間の観念が薄いのは何故だろう。厳冬期のヒマラヤ山中で一メートル先も見えぬ程の吹雪に二日二晩閉じ込められた時の事も、遠い昔の事の様でもあり、昨日の事だった様にも思われる。前年、登山家の先輩がエヴェレスト登攀中に消息不明となり、あとから救援にかけつけた仲間が、立ったまま凍死している遺体を発見したという報告を受けていながら、あの日白魔を怖いと思わなかったのは、片思いに敗れての彷徨だったからだろうか。自然の現象は人間の思惑とは無関係に営まれる。何か人間を超えた大きな力がすべてを統御している様に思われてならない。あなたも一しずくの雨、ひとひらの雪が、眼に見えぬ糸に引かれて落ちていく様に見えた事はないだろうか。唐の時代、808年に亡くなったほう居士(ほうこじ、ほうの字は雁垂れ又は摩垂れに龍)という人物がいる。生まれた年がわからないので、年齢は不詳だが、それ以上に伝説に彩られた部分が大きくて、実像は攫みにくい。居士というのは在家の仏教者を指すが、彼の力量は並みの禅僧など、足元にも及ばぬものだった。当時の傑僧=薬山惟儼(やくさんいげん)とは、満足のいく問答が出来た。ご機嫌で薬山と別れて山をおりてくる途中、雪が降り始めた。その雪を指差して、「何と見事な雪だ。一片ひとひらが別の処には落ちない」と感嘆の声を上げた。居士の語は一片一片が本来落ちるべき場所をそれぞれに心得ていて、どの一片も間違わずに着地していく様にみえる事をいったのである。もっと踏み込んで、見送りに付いてきた薬山の弟子たちに対する督励の挨拶だったと受け止めてもよいが、むしろ単純にほう居士自身、このとき一片の雪になりきっていたと解釈するほうが好いだろう。その恍惚の一瞬を、全という名の雲水が破った。「どこに落ちるのです」と。そこで居士は平手打ちを食らわした。全は「そんないい加減な答えには騙されませんぞ」と言った。するとほう居士は「そのザマで雲水づらをすると、閻魔大王は容赦しないぞ」と言った。全は「居士どのはいかがです」と言った。居士はもう一度平手打ちを食らわせて「目は見えても盲同然、口は利けても唖も同然じゃな」と言った。宋代のひと雪竇重顕(せっちょうじゅうけん)は、この話を取り上げて、「わしだったら恍惚のほう居士に、雪の玉をぶつけてやったのに」と悔しがっている。僕だったらどうするだろう。ほう居士はもういない。そうだ、心友なら、こんな日もしっかりした足取りで一歩一歩踏みしめているだろう。よし、帰り道に待ち伏せして雪の玉を一発お見舞いしよう。きっと瞬時に少年の日に戻れるぞ。
2005年03月04日
コメント(0)
-
桃の節句にちなんで
明日は桃の節句。桃の花を見て悟りを得た霊雲志勤の話をしよう。彼は三十年修行しても悟りを得られそうにもなかった。正直なところ、今更路線変更も考えられず、といって何か禅の道でこれぞというものもつかめず、やけっぱちになったり、どうにでもなれ、という気持ちになったりしていたのではないかな、と私の人生を重ねて同情とも哀れみともつかないものを感じる。で、ああだ、こうだ、という工夫も万策尽きて、ふと遍歴の途中、山道にさしかかって里を振り返った。村の様子は一面の桃の花盛りだ。それを見た瞬間、彼は悟りを得た。三十年来、尋剣の客幾回か葉落ち又枝を抽んずる一たび桃花を見てより後直に如今に至るまで更に疑わず中国人でもここまで下手な漢詩を詠むかというぐらい、詩としての出来は良くない。しかし、その率直さは脱帽ものだ。起句の「尋剣の客」というのは『呂氏春秋』に出てくる愚か者の話。船に乗って揚子江を渡るとき、川に剣を落とした楚の人が、ここで落としたと舷側に刻みを付けて目印にしたという。船が動くことを忘れ、舷側の傷を後生大事にして剣を探すように、三十年の修行は徒労であったと自嘲する。承句は、その三十年の間も、桃は季節に応じて芽を吹き葉をひろげて散ったことを示す。心ここにあらざれば、見れども見えず、ということは誰でも経験するが、いま改めて桃の木を見れば、どうして今までこの花が見えていなかたのかと不思議に思う。転句は、もうしっかり見極めた事を詠い、結句は以後決して見失わぬと告げる。人が悟りを得るきっかけは、本当にあらゆる時、あらゆる場所にあるのだけれど、ご本人が気がつくかどうか、それはまた別の問題として存在する。でも、悟れるか、あるいは気がつけるかと言い換えても良いのだが、そうなるかならないかは、本人の賢愚というより、そこまで追い詰められたか否かではないか、という気がこの頃している。悟れるとしたら、それも幸せ、悟れないとしたら、まだそこまで苦しい場に立たされていないことに幸せを感じても良いのかな、とこの頃おもうのである。ああ、そうそう、桃の生命力は、西王母の伝説に、実を一つ食べただけで三千年の寿命を得る、とされている事からもわかるように、素晴らしいものがある。このエネルギーにあやかって、もうしばらく元気で活躍したいものだ。あと七年で私も僧籍を得て三十年、私の剣はいつ見つかるだろうか?
2005年03月02日
コメント(0)
-
古人の刻苦光明必ず盛大也(こじんのこっく、こうみょう、かならずせいだいなり)
『禅関策進』に記されている話。慈明禅師の号で親しまれる石霜楚円(せきそうそえん 987-1040)が仲間と共に修行に励んだ時、この言葉をいつも思い浮かべて励ましとしたという。道場のあった河東の地の寒さはハンパじゃなかったが、厳寒の夜を徹して坐禅した。時折睡魔に襲われると楚円は自分の腿に錐を刺して眠気と戦ったという。「慈明自錐(じみょうじすい)」として禅寺ではよく語られる。こういう古事は余程心して受け止めねばなるまい。つまり自分の心に誓って行う行為なら素晴らしいのだけれど、強制力として作用してしまうと途端に輝きを失ってしまうのである。徹夜の坐禅は、本来修行者自らの止むに止まれぬ求道心から始まったものだった。しかし、今の日本の道場では形式化し、参加しないと制裁が待っていたりする。自主トレの強制という笑えない事態が起きるのである。それで得られる結果など、たかが知れている。少なくとも「光明盛大」とはならないだろう。「光明」は比類ない輝かしい成果と訳される事が多いようだが、気をつけねばならないのは自分の内側から発する光かどうかだ。自己本来の輝かしいはたらきが光となってこそ修行の目的は遂げられるのだ。楚円の熱い求道心はやがて多くの逸材を育てる事になった。なかでも黄竜慧南(おうりょうえなん)と楊岐方会(ようきほうえ)は、その後の中国禅宗界をリードする二大巨頭となる。「古人」の語に楚円は彼の先輩たちの姿を思い浮かべていたことだろう。今日の我々は楚円その人を思い浮かべても良い。しかし、何も昔の人である必要はどこにもない。共に励んでいる仲間の中に光明の兆しが見出せるなら、これ以上の幸せはない。心友が何かをつかみかけているらしい。今日は彼にとっても大事な門出の日、まばゆいばかりの光が彼の中から輝きでようとしている。彼に心からの声援を送ると共に、僕も自分の中の光を曇らせぬよういっそう努力しよう。
2005年03月01日
コメント(0)
-
随処に主と作る(ずいしょにしゅとなる)
これは禅の言葉の中でも、とても重い語です。『臨済録』といって『碧巌録』と並んで大切にされてきた禅の典籍の中の王様です。その『臨済録』中でも白眉の一節ですが、私の心友がどうやら自分でこの境地をつかみかけているようなので、応援の意味をこめて今日はこの語を贈ります。仏界・魔界・天上・地獄・順境・逆境、私たちはいろいろな世界に出入りします。心の持ちよう次第で瞬時に地獄に落ち込む事もあれば、たわいも無い事で天上に昇ったように感じる時もあります。そしてある時は舞い上がってしまったために、ある時は落ち込んでしまったために、自分が見えなくなってしまうのは、残念ながら凡人の常です。でもそうしたことに妨げられず、何物からも自己を乱されることのない無碍自在な境地を獲得しないと、本来の力を発揮して人生の目的を遂行する事はできません。禅僧にとっては、悟りを得るのと同じ意味で、この語を用いる事ができます。私はめったにこういう境地を実現できたと思える一日を過ごすことができませんが、でも時折思い出しては気を取り直します。心友ががんばっているのを応援すると同時に、僕自身も精進しようと誓いました。
2005年02月28日
コメント(0)
-
春は千林に入り処々に花(はるはせんりんにいり、しょしょにはな)
大学入試の試験監督ほど、強い緊張感を強いられる一日は無いが(自分自身が受験生だったときの比ではない)、それでも派遣される会場が駒場だった時は一つだけほっとできる時間がある。梅林に数百羽のメジロがやって来て、咲き誇る梅の枝をびっしりと埋め尽くすのである。その様子がなんとも可愛らしい。花の蜜を吸っているのだろうが、よくこんな体勢でと感心する。ほとんど鉄棒の選手のような動きを見せる。宋代の院体画以来しばしば好んで描かれた画題を、こうして鑑賞者の目ではなく、画家の目で見られる時間は貴重で楽しい。ああ、この監督が済めば本格的な春だな、と心待ちにするのである。表題に掲げた句は、「春入千林処々花、秋沈万水家々月(秋はまんすいにしずむ、かかのつき)という対句なのだが、春の部分だけが揮毫される事が多いように思う。千利休の孫=宗旦(そうたん)はこの前半句を一ひねりして「花」を「鶯」に置き換えた。「春入千林処々鶯」という訳だ。これは元の句をたくさんの人が知っている事を前提にして、別のイメージを提示した楽しい展開例である。以来、表千家では代々の家元がこの句を揮毫して、新春の床の間に懸け、年賀の客を迎える慣わしになった。目に梅とメジロを満喫しながら、どこかに鶯の声が無いかと耳を立てる。今年もまた春に会えた、その喜びを今日は本郷で想像しながら、入試の無事終了を迎えよう。
2005年02月26日
コメント(0)
-
紅炉上一点の雪(こうろじょういってんのゆき)
今夜の東京は、春先によくあるように、雪が霏々と舞っている。こんな静かな夜に思い出すのは『碧巌録(へきがんろく)』第六十九則の冒頭に置かれたこの言葉だ。喰らいつこうにも歯の立ちようがない仏法の真髄を目指て、茨の道をも突き進んでいく雲水にとっては、襲い掛かる困難など、真っ赤に燃え盛る炉の上に、立った一ひらの雪が舞い落ちたようなもの、一瞬にして解けてしまう、というのである。小生も身に覚えがあるが、こちらの心や体の状態管理さえしっかり出来ていれば、大抵の困難は乗り越えられるし、逆に落ち込んでいれば小石ほどの躓きも大事に至る。史実ではあるまいが、この語にまつわるエピソードをご紹介しておこう。川中島の戦いで、単身武田信玄の陣営に切り込んだ上杉謙信が、「いかなるか是れ剣刃上の事(けんにんじょうのじ=絶体絶命のいま、貴公の心境はどうだ)」と問いかけると、信玄は「紅炉上一点の雪」と答えたという。おそらく禅に詳しい人々が、二人の武人の逸話としてこしらえたものであろうが、『碧巌録』の緊迫感をよく伝えている。この雪は邪念の象徴だろう。それにしても今夜は久しぶりの大雪だ。あらたまの年のはじめの初春の今日降る雪のいやしけよごと大伴家持の歌だったろうか。今日の初雪のごとくよごと(吉事)が「いやしけ(いよいよ重なれ)」と祈るとき、この雪もまた煩悩の代名詞だろう。煩悩を瞬時に消し去れたらどんなに楽だろうと、若い頃は思っていた。この頃は煩悩こそ命の証かもしれないと思うようになってきている。凡人もこんな雪の夜には越し方行く末に思いを馳せる。
2005年02月24日
コメント(0)
-
自灯明 法灯明
お釈迦様が最期のときを迎えると、それまで従ってきた弟子たちは戸惑いました。いったいこれから何を頼りに生きていけばよいのか。この弟子たちの嘆きに対して、お釈迦様は「自灯明 法灯明」と答えたといわれます。自らの内面から発する明かりを灯明とし、教えを灯明として進んで行け、という意味です。ただし、これは誤訳らしく、「自洲 法洲」と訳すべきだったようです。インドの雨季は大地を押し流す洪水になるようですが「洲」はその雨季に水没しない所です。翻訳の問題はさておき、それまで頼りきっていた存在と別れなければならないのは、人の世の常です。いつでも自分と一緒にいられるのは自分しかありません。その自分が本当に灯明になりうるか、あるいは洲になり得るか、大半の人は胸をはって答えられないでしょう。私もまだまだ。でもまだまだの自分を見つめながら、やっていくしかなさそうです。
2005年02月15日
コメント(0)
-
明日は涅槃会
お釈迦様の生没年は諸説あって確定しにくいのですが、三十五歳で悟りを得、そののち四十五年もの長い間、人々に法を説いて、八十歳の生涯を閉じたのは二月十五日という事ではだいたい一致しているようです。お釈迦様を慕って歌人の西行は 願わくは花のもとにて春死なん その如月の望月のころと歌いました。生まれてきた以上、誰でも死ぬわけですが、でも死ぬって事を体験した人の報告は誰も受けたことがありません。私の好きな作家に玄侑宗久氏がいますが、彼の近著に『死んだらどうなるの』があります。ひと段落したら是非読もうと思っていますが、まだ一月ほどさきになるでしょう。「死」はどの時代の人にとっても大問題でしたが、近年はここから目を背けることに努力を傾けてきたように思います。でも見方を変えれば、今このブログを書いている僕も、読んで下さっているあなたも生きています。生きているこの時間をどうやって充実させ、持っている能力を使い切って「ああ、我ながらよくやった」って思いながら最期の時を迎えられるようになりたい。涅槃会を前に、残された時間の有難さをしみじみと思っています。
2005年02月14日
コメント(8)
全35件 (35件中 1-35件目)
1