2024年06月の記事
全39件 (39件中 1-39件目)
1
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その20):清浄寺~稲荷社~三ヶ浦~諏訪神社
県道207号線・森戸海岸線の横にあった「脇町の庚申塔」を後にしてさらに北上する。葉山マリーナと森戸海岸の中間あたり、右手にあった「清浄寺」を訪ねた。三浦郡葉山町堀内284。「龍圓山 清浄寺」「葉山町指定重要文化財 彫刻 阿弥陀三尊立像」と。「手水舎」。イチョウの樹の下に「青面金剛塔」碑。「徳本上人の名号碑」「南無阿弥陀佛」と刻まれていた。徳本上人は江戸時代中期の浄土宗の僧。「南無阿弥陀仏」を唱えて日本各地を行脚した と。「龍圓山 見彼院 清浄寺」の「本堂」を正面から。何故か、本堂の屋根の中心と本堂の入口、参道が左にずれていたのであった。「本堂」に近づいて。本尊は阿弥陀如来像(室町時代)で左足を少し前に出して立っている珍しい仏像だそうです。幕府に篤く庇護された寺であると。入口で案内されていた「阿弥陀三尊立像」👈️リンク をネットから。ここにも「南無阿弥陀佛」碑。「當山開山上人中興上人代々上人、檀方中先祖代々有縁無縁之霊位」と。「六地蔵堂」。六地蔵の中心に鎮座するのは「延命地蔵尊」であっただろうか。左手に宝珠を、右手には錫杖を持っていたのであろうか。涎掛けには「横関?家先祖代々・・・・施主 石坂保彦 平成二十三年四月吉日」と。本堂屋根の「飾り瓦」をズームして。「三つ葉葵」の寺紋が。寺務所。次に「清浄寺」の南側の路地を上り、「清浄寺」の墓地の南角にあった朱の社を訪ねた。「清浄寺」の墓地群。石段の上に朱に塗られた社が。葉山「稲荷社」とGoogleマップには。「稲荷社」の石段の横には多くの石仏の姿が。近づいて。山百合も美しく咲いて。石鳥居を潜って。お詣りをして、「稲荷社」を後にしたのであった。そして再び県道207号線まで戻り「清浄寺」の山門を再び見る。その先、右手にあったのが「葉山うみのホテル」。2020年3月、葉山にグランドオープン。海と山に囲まれた自然豊かな葉山の森戸海岸近くに位置。湘南エリアでもトップクラスのオーシャンビューのホテル。そして「葉山うみのホテル」前を左折して海岸へ向かう。「STELLA STORIA 葉山(ステラストーリアはやま)」。三浦半島を代表する逗子・森戸両海岸に挟まれた小さな小さな海岸に佇む一棟貸しの宿泊施設。葉山町堀内の海岸、この辺りがGoogleマップによると「諏訪町下海岸」と呼ばれる場所の岩場越しに「江ノ島」を見る。「江ノ島」をズームして。海を見ながら露天風呂に入れると。以前はこの付近に、イタリア公使レナード・デ・マルティーノの別荘、そして医学博士エルウィン・ベルツの別荘が並んでいたとのことだが、その場所は確認できなかった。見事な紫色の朝顔の花。そして次に「葉山うみのホテル」の裏にあった「諏訪神社」を訪ねた。「諏訪神社御祭神 建御名方命(大国主命の御子)眼下には相模の海、遠くに冨士・箱根・伊豆の山々を望む風光明媚なこの山の麓に、江戸の昔「お諏訪さま」が祀られたと伝えられている。諏訪の大神は、古来より風占いの神として漁の安全を祈る漁業者から篤い信仰があり、古くはこの沖で捕れた魚は江戸に運ばれたと言われているように、漁業が盛んであったことから漁師の守護神として祀られたのであろう。この地域には、江戸時代から伝承されている「宮そうじ」「浜そうじ」というすばらしい風習が残っており、神社と浜辺を定期的に掃除する奉仕活動で、このような伝統が今日に受けつがれていることは、この地域の人等の誇りである。 平成ニ十ニ年四月吉日」社殿に向かって急な参道の石段を上る。靖国石鳥居には扁額が。「諏訪社」と。そして社殿を見上げて。狛犬(右)。明治44年生まれの狛犬であると。阿形像は玉取、吽は子連れの狛犬で、殆ど猿に近い顔つきをしていた。吽形像の狛犬(左)。親似の子狛の位置が中央に。社殿に近づいて。社殿の扁額は「諏訪大明神」。内陣を。「諏訪神社」の左側には境内社の「稲荷神社」。内陣には多くのお稲荷様の姿が。こちらは、「末社4社」。末社(右2社)に近づいて。末社(左2社)に近づいて。社殿前から参道を見下ろして。残念ながら境内は木々に覆われて、海の姿は・・・・。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.30
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その19): 元町会館~地蔵堂~相福寺~西東三鬼の句碑~福沢諭吉の別荘~脇町の庚申塔
「森戸神社」を後にして、再び「みそぎ橋」を渡り、「森戸川」の右岸を県道207号線・森戸海岸線に向かって進む。「もりとがわ(森戸川)」に架かる県道207号線・森戸海岸線の「森戸橋」を右に見る。県道207号線・森戸海岸線を北方向に歩く。150mほど進むと右手にあった白い建物が「元町会館」。三浦郡葉山町堀内899−5。昔はここが「葉山町役場」であったのだろうか?現在は、元町児童館や民間の教育施設があるようだ。現在の葉山町役場は1kmほど離れた三浦郡葉山町堀内2135にあるのだと。さらに、県道207号線を北に進み、右斜め前方への路地を進むと、「あずま町内会館」手前に大きな墓地があった。この後訪ねた相福寺の墓地であっただろうか。歴史を感じさせる石仏が並んでいた。その先にあったのが「地蔵堂」。「奉納百番札所供羪佛」と刻まれた石仏。石造六地蔵立像(右側)。横には中央向きの舟形後背石仏。石造六地蔵立像(左側)。横には六臂青面金剛庚申塔が2基。そして、葉山町堀内の住宅街を進み「相福寺」の山門前に到着。三浦郡葉山町堀内568。「葉山町指定重要文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 阿弥陀如来立像」案内柱。寺号標石「浄土宗 長江山 相福寺」。「掲示板」。「増上寺三大蔵について 全21回増上寺デジタル三大蔵について👈️リンク (3)」。「今月のことば一つには外をかざりて内にはむなしき人二つには外をもかざらす内もむなしき人三つには外はむなしく見えて内はまことある人四つには外にもまことをあらはし内にもまことある人「往生大要抄」法然上人」➡️「一つには外見はいかにも善人て賢そうに見せかける人で、内心は悪人で愚かな人。ニつには外見も内心も悪人で愚かな人三つには外見は悪人で愚かに見えて内心は真実な人。四つには外見も内心も真実な人この四つの姿を自分に照らし、特に1畚や2番のような煩悩具足の我身てあると気付いたならば改めたいものてす。何よりもこの気付きが大切です。よく世間ではあの人はうわペだけで心がない。あの人は何を考えているのかわからない。あの人は言葉だけでこが冷たいなどということがあります。私たちは内外相応して真実の人生を歩みたいものです。それにはお念仏が大切てす。お念仏を称えていると不思議に阿弥陀様の慈悲の心が我心に宿るのです。しっかりお念仏を申しましょう。」と「大本山 増上寺 あおい 葵 2024年5月号 No.778」。「特別展法然と極楽浄上2024年4月16日(火)ー6月9日(日) 東京国立博物館」ポスター。「本堂」に向かって参道を進む。「本堂」を正面に見る。現「本堂」は、明治6年から30年まで堀内学校校舎として児童教育の場でしあった と。「手水舎」。近づいて。水鉢は円柱状で、龍が彫られていた。「六地蔵堂」。この古木の名は?本堂の扁額「長江山」。本堂の彫刻。葉山町指定重要文化財「阿弥陀如来坐像」をネットから。葉山町指定重要文化財「阿弥陀如来立像」をネットから。「動物の墓」。水子地蔵尊。墓石が並ぶ。古木を再び。巨大な蘇鉄。寺務所であっただろうか。「相福寺」の本堂の屋根瓦を見る。飾り瓦が見事!!そして「相福寺」を後にして、次に「西東三鬼の句碑」を訪ねた。「春を病み 松の根っこも 見あきたり」。西東三鬼(1900-1962)1933年、医師業(歯科医)のかたわら、外来の患者の誘いにより俳句を始める。「三鬼」はこの時から。(英語のサンキューのもじりとも)戦後、現代俳句協会を石田波郷らと設立。山口誓子主宰の「天狼」初代編集長をへて、27年「断崖」を創刊。32年総合誌「俳句」編集長となる。昭和37年4月1日死去。61歳。こちらが終焉の地 と。「相福寺」の西側まで戻って「相福寺」の墓地を見る。大きな五輪塔が見えた。こちらは無縁塚であったか。無縁塚越しに「相福寺」の本堂を見る。そしてこの奥に「福沢諭吉の別荘」。三浦郡葉山町堀内。現在は、UBE株式会社葉山寮になっていると「福沢諭吉の別荘」をズームして。そして、再び葉山郡堀内の住宅街を県道207号線・森戸海岸線に向かって進む。そして県道207号線・森戸海岸線に面する場所にあったのが「脇町の庚申塔」。三浦郡葉山町堀内347。「葉山町指定文化財 建造物 庚申塔」。中央右は「文字庚申塔」。六臂青面金剛庚申塔。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.29
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その18):森戸神社(3/3)
森戸大明神の裏手に進み、鳥居をくぐって小さな丘に向かって石段を上る。「葉山町指定重要文化財 天然記念物 森戸大明神ビャクシン」と。「神奈川県 かながわの名木100選 森戸大明神のビャクシン」案内板。「神奈川県 かながわの名木100選 森戸大明神のビャクシン和名:イブキ(ヒノキ科)源頼朝が当地に伊豆の三島神社を勧請した際、そこの若木が飛来し、岩壁に根付いたものと言われている。古木が海上にのりだした姿は珍しい。葉山町の天然記念物に指定されている。樹高 15メートル 胸高周囲 4.0メートル樹齢約800年(推定)イプキはビャクシンも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく植えられるほか、生け垣などに用いられる。樹高27メートル、胸高周囲8メートル、樹齢約1500年に達するものもあると言われている。」石段の先に石碑が現れた。「御神木 飛柏杉」と。一般に飛柏槇とかかれ間違いないが、神社としては槇ではなく杉を使って下の写真の如く「飛柏杉(びびゃくしん)」と表現して欲しい と。森戸大明神のビャクシン(柏槙)。和名:イブキ(ヒノキ科)。源頼朝がこの地に伊豆の三島神社を勧請した際、そこの若木が飛来し岸壁に根付いたものといわれていると。古木が海上にのり出した姿は珍しいと。別の角度から。「飛柏杉(びびゃくしん)」の近くには日吉社が祀られていた。そして、「飛柏杉(びびゃくしん)」をあとにして石段を下ると、右手に見えたのが森戸大明神裏の岩の上に立つ「千貫松」。源頼朝が衣笠城に向かう途中、森戸の浜で休憩した際、岩上の松を見て「如何にも珍しき松」と褒めたところ、出迎えの和田義盛は「我等はこれを千貫の値ありとて千貫松と呼びて候」と答えたと言い伝えられている。「菜島 (名島) 鳥居」。神社裏手の磯辺より沖合い700メートルに浮かぶ小さな島で、赤い鳥居が目印。ズームして。「葉山灯台(裕次郎灯台)」ヨットマンだった石原裕次郎さんの三回忌を偲び、1980年から1993年まで日本外洋帆走協会の会長を務めた、兄の石原慎太郎さんが約1億円の基金を集めて建設しました。灯台のプレートには「海の男 裕次郎に捧ぐ 葉山灯台」と刻まれているとのこと。2018年に撮影した、富士山を背景にした裕次郎灯台と朱の鳥居の写真 を。遠く、鎌倉市長谷3丁目にある「長谷寺」の姿が確認できた。「江ノ島」をズームして。「石原裕次郎記念碑」。神社裏手の海岸入り口には、湘南で青春を過ごし、この地をこよなく愛した俳優、故石原裕次郎のブロンズ像と兄の石原慎太郎自筆の詩が刻まれていた。「夢はとおく 白い帆に のって 消えていく 消えていく 水のかなたに」「太陽の季節に実る 狂った果実たちの 先達 石原裕次郎を 偲んで」。これも、2018年に富士山をバックに立つ石原裕次郎記念碑を撮った時の写真。「森戸大明神裏の海岸」の岩場を見る。「マルチーノ公使ベルツ博士記念碑」ドイツ帝国の医師で、明治時代に日本に招かれたお雇い外国人のひとり。27年にわたって医学を教え、医学界の発展に尽くした。滞日は29年に及ぶ人物と。 彼は葉山が黒潮の影響で冬は暖かく夏は涼しい温暖の地で、風光明媚であるということに注目し「葉山」が保養の地として最適であると皇室に進言し、明治27年に葉山御用邸が造営されたのだと。その功績を称えてこの場所にこの記念碑が建てられた と。石碑には、IN MEMORIAM CHEV. RENATI DE MARTINO ET PROF. DR. ERWINI BAELZマルチイーノ公使・ベールツ先生 記念碑葉山一帯ノ地源平時代二在リテ其名己二顕 ハル而シテ近古二及ヒ却テ聞ユル所アラス明治二十年中東京駐紮伊太利公使レナード・デ・ マルチイーノ氏甚タ葉山ノ風景ヲ愛シ創メテ 其ノ別業ヲ森戸ニ営ム 後ノ細川侯邸即チ是ナリ 先師エルウイン・ベールツ先生モ亦其ノ海岸附近ノ地ニト宅シテ暇日休息ノ処卜為シ頻二此地ノ保健ニ適スルヲ推賞ス 池田徳 潤男、秋田映季子、相前後シテ別墅ヲ森戸ノ丘陵ニ建ツ 明治22年6月鉄路ノ通スルニ及ヒテ井上毅子モ亦ベールツ先生ノ説ニ聞キテ其冬一色ニ来リ住ス 翌年夏金子堅太郎伯モ亦至ル 尋テ有栖川宮家ノ別邸成ル明治27年ニ至り其1月ヲ以テ始メテ御用邸ヲ置カル 是二於テ葉山ノ名忽チ天下二鳴ル 予モ亦夙二其風光ノ明眉ト気候ノ温和トヲ愛シ蝸蘆ヲ 森戸ニ築キテヨリ己ニ三十有余年ヲ過キ 頗ル先師着眼ノ敏ナルニ服ス 予他年葉山発達ノ 歴史ノ或ハ湮滅ニ帰スルアランコトヲ憂ヘマルチーノ公使及先師ベールツ先生ノ先唱ノ功ヲ石ニ勒シテ以テ後人二諗ク昭和十一年 二月 東京帝國大學名誉教授 醫學博士 入澤達吉 識 野村保泉刻」「葉山町指定重要文化財 建造物 顕彰碑 ベルツ博士・マルチーノ公使記念碑」「詩人 堀口大学 詩碑」。 「花はいろ 人はこころ」昭和25年6月、葉山の温暖な土地柄を愛して移り、多くの業績を残して昭和56年3月15日、89歳で死去。葉山町名誉町民(昭50年)。町制50周年を記念して建てられたと。「昭和天皇御即位五十年記念碑」。「近上践祚五十年」と。昭和天皇の御即位50年を記念し、昭和50年に建てられた記念碑。「明治天皇御製・照憲皇太后御歌碑」。明治天皇 海辺雪 「波のうへに 富士のね見えて くれ竹の 葉山の浦の 雪はれにけり」照憲皇太后 里神楽 「くれ竹の 葉山の宮に きこゆるや 森戸あたりの かぐらなるらむ」「高橋是清歌碑」。「堪忍の 股よりのぞけ 富士の山」2・26事件で暗殺された高橋是清の別邸跡が「葉山交流館」になっている と。この碑は?「・・・・参拝記念建之」「大正天皇即位の御大典記念碑」。大正天皇の御即位を記念して、大正4年に建てられた記念碑。「侯爵細川家 松樹五百本寄進の碑」。侯爵であった細川家より、当神社に松の木500本が寄進された記念として建てられた と。「寄附事業記念 大正四年秋九月 東京御供講」と刻まれた石碑。「永代神楽」碑。「森戸大明神裏の海岸」の岩場を再び。鳶(とんび)襲来。ベンチに座り休憩していると、隣の御夫婦が食べていた弁当のおかずを鳶(とんび)が頭上から襲い奪って行ったのであった。御夫婦は早々にこの場所を避難して行ったのであった。そして私も早々に。森戸海岸を後にして、再び「森戸神社」の境内へ。「待合所」奥の「おみくじ所」を訪ねた。窓には「大漁旗」が。「森戸大明神御祭神 大山祇神(おおやまつみのかみ) 事代主神(ことしろのぬしのかみ)御利益 除災招福「鎌倉を守る要所に鎮座する頼朝ゆかりの社」伊豆の韮山で流人として暮らしていた源頼朝が静岡県三島市にある三島大明神(現・三嶋大社)に源氏再興を祈願した。のちに大願成就した頼朝は1180年に鎌倉に拠点を置くと、この地に三島大明神の御分霊を勧請し森戸大明神とした。大山祗神、事代主神をお祀りする。七瀬祓の霊所のひとつとして、心身浄化の禊や災厄除けの加持祈祷が盛んに行われた場所であり禊橋にその名残が見える。源頼朝の別邸があり、歴代将軍がこの地を訪れて流鏑馬や相撲などの武事を行ったことが『吾妻鏡』に記されている。和田義盛ゆかりの千貫松や三島大明神から飛んできたと伝わる「飛柏槇」などの史蹟に加え、晴れた日には海の向こうに富士山を望めるなど、風光明媚なところも魅力である。」「鯛みくじ」の「恋し鯛」、「めで鯛」。「一心泣き相撲 葉山場所」👈️リンク が令和6年10月6日(日)に開催されると。「一心泣き相撲®では日本の伝統行事を通じて、赤ちゃんとの思い出作りをお手伝いします。四百年以上の歴史を有する泣き相撲は、赤ちゃんの泣き声やしぐさに合わせて行司が勝負を預かり『 緑児泣きたるは万歳楽 』と、すこやかな成長と健康を祈願する日本の伝統行事です。化粧廻しと紅白綱を締めた赤ちゃんが人生の初土俵へあがる姿は可愛らしくも逞しくもあり、その成長をご家族皆様で感じられることから、『赤ちゃんの卒業式』と呼んでいます。会場では、相撲、御祈祷、赤ちゃん力足(四股奉納)をはじめ背伸び太鼓や、参加記念として手作りのカブトや赤ちゃんの記念手形の授与などのイベントを開催しています。」とネットから。神奈川県神社庁の5月のポスター。「まことの道 【皐月】五月 石の上にも三年」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.28
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その17):森戸神社(2/3)
「庚申塔」。猿田彦大神を祀った庚申塔は葉山町唯一で、三浦半島では珍しい流れ造りの石祠。「庚申塔庚申の信仰は、中国の道教の思想に基づくもので、江戸時代に盛んになり講中の人たちが庚申塔を建立した。六十日毎にめぐって来る庚申の日の夜、眠った人の体内から三尸と呼ばれる虫が出て、天帝にその人の罪過を報告し罰か下されるといわれ寝てはいけないと信じられていた。」●造立年号(塔に刻まれている年月日:享保11丙午天10月庚申日(1726年)●碑型、石質、其の他: 石祠(流れ造り)、安山岩、単基。●大きさ及破損度: 高さ78cm(屋根及台石共)。宮殿間口30cm。屋根右前少し缺ける。●刻像 : 無し。●銘文 : 室の内部中央に「猿田彦大神」と刻し、台石に「真名瀬庚申講中」と右から横書に刻む。 向って右側面に年号、同左側面に月日を記す。●塔の特徴: 猿田彦大神を祀った庚申塔は、葉山町ではこの塔だけで他に無い。又流れ造りの 石祠は、三浦半島でも珍しい。葉山酒商組合の「菰樽奉納(こもだるほうのう)」場。江戸時代に江戸へ酒を運ぶ時、大きな酒樽が壊れないように巻いていたのが菰(こも)である。破損を防ぐ目的で、酒樽に菰(こも)を巻き付けたのが、菰樽(菰冠樽:こもかぶりたる)の始まりといわれています。今日では菰に色々な銘柄のデザインが描かれており、それぞれの酒造メーカーよりさまざまな願いがこめられたデザインになっているのだと。「手水舎」。掲示板の「六月祭事暦」。右手奥の社の中には、無数の小石が。「子寶石納所」碑。子宝石をお受けになり、赤ちゃんを授かったご夫婦がご出産の後、お宮参りに合わせて子宝石をお戻しいただく場所です。納める際は、子宝石へお子様のお名前をご記入いただき、お子様が石のように丈夫でありますよう願いを込めてお戻しください と。近づいて。「森戸神社」の「子授祈願」・「安産祈願」の「絵馬」。こちらは「誕生奉告 成育祈願」の丸い「絵馬」。「絵馬掛所」。この絵馬は赤ちゃんの健康と成長を祈願。「水天宮」。「水天宮」。水天宮の内陣。「水天宮「まいられよ 子宝の福 さづかりに」と石碑に刻んである通り、古くから安産・子宝を求める人等の篤い信仰を受けている。左右にある「子宝の石」を手でなで、お詣りすると子宝が授かると言い伝えられている霊験あらたかな石です。」「句碑まゐられ(禮)よ 子寶の福 さ(左)づか(可)り(梨)に(耳)」。昭和3年から堀内に住んだ雪中庵東枝の句碑(昭和50年建立)。「社務所」・「御朱印受付所」。移動して。「おせき稲荷社」。近づいて。「おせき稲荷社」と。「おせき稲荷社古来より「せきが止まらない人」又「咽を使う職業の人たちの篤い信仰があります。」内陣。そして参道を進むと「森戸神社」の狛犬が迎えてくれた。狛犬(右)。狛犬(左)。そして正面に「森戸神社」の「社殿」。近づいて。内部の様子をネットから。「森戸大明神永歴元年(一一六〇)伊豆の蛭ヶ小島に配流された源頼朝公は三嶋神社を深く信仰し、源氏の再興を祈願した。治承四年(一一八〇年)その神助を得て旗上げに成功して、天下を治めた頼朝公は自らが信仰する三島神社の御分霊を、鎌倉に近き元山王の社地であった此の景勝の地に勧請して、永く感謝の誠を捧げたと伝えられる。当時のことは、社宝として奉蔵の後二條院並びに花園院の院宣によっても篤く崇敬された様子がうかがわれ、又、吾妻鏡には、この地で加持祈祷が行われ、源氏はもとより三浦、北条、足利諸氏の崇敬も篤く、天正十九年(一五九一年)にし徳川家康公により社領七石が寄進されている。その後、明治の御代に移り、葉山に御用邸が造営され、ご滞在の折には天皇、皇后両陛下を始め皇族の方々の御参拝を仰ぎ、葉山郷の総鎮守として近郷近在より多くの参詣を得ている。特に境内より富士、箱根、伊豆、江ノ島を望む光景は絶景で、「森戸の夕照」としてかながわの景勝五十選に選定されている。御祭神 大山祇命おおやまつみのかみ 事代主命ことしろぬしのかみ(えびす様)御祭日 例大祭 九月 八日 潮神楽 六月十六日史跡飛柏槙(町指定天然記念物)(かながわの名木100選) 樹齢 八百年余り 元歴元年(一一八四年)頼朝公が当社を参拝の折、三嶋神社から種子が飛来し発芽したものと 伝えられ当社の御神木である。千貫松 頼朝公が衣笠城に向う途中森戸の浜で休憩した時、岩上の松を見て「如何にも珍しき松よ」と ほめたところ、出迎えの和田義盛は「我等はこれを千貫の値ありとて千貫松とよび候」と答えた という由来がある。子宝石 「まいられよ子宝の福さずかりに」と詠まれている通り古来より信仰の篤い石である。」「拝殿」横から「森戸川」、朱の「みそぎ橋」を振り返る。疾走する馬の絵馬。「社殿」前から境内を振り返る。「砲弾」。森戸神社社殿に上る階段右手に砲弾が一基奉納されている。台座に「奉納」と刻まれているのが判読できるのみで、基壇に銘板が取付けられているが風化侵食により判読不明。砲弾は28センチ砲弾で全長約97cm。宮司さんによると日露戦争の頃に奉納されたと聞いているのみで詳細不明とのこと。 であれば、日露戦争の戦利品であるロシア軍の砲弾であろう。台石46cm、基壇80cm。「おみくじかけ」。「多幸多福みくじ」。「恋し鯛みくじ」。社殿の裏には、層が顕になった巨岩があった。「葉山町指定重要文化財建造物 森戸大明神社殿」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.27
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その16):森戸神社(1/3)
「光徳寺」を後にして、葉山町堀内の住宅街を進み、県道207号線・森戸海岸線まで戻ると正面に「森戸神社」の朱の「一の鳥居」が姿を現した。右手にあったのが社号標石「森戸神社」。朱の鳥居に向かって参道を進む。「通年勤務 巫女アルバイト募集」と。「森戸神社 配置図」。①本殿 ②おせき稲荷社 ③水天宮 ④庚申塔 ⑤畜霊社⑥総霊社 ⑦社務所・授与所・待合所 ⑧待合所 ⑨手水舎 ⑩参集殿⑪飛柏槇 ⑫千貫松 ⑬名島(菜島) ⑭みそぎ橋 ⑮マルチーノ公使ベルツ博士記念碑 ⑯詩人・堀口大学 詩碑 ⑰昭和天皇御即位の御大典記念碑 ⑱大正天皇御即位の御大典記念碑⑲高橋是清 歌碑 ⑳明治天皇御製 昭憲皇太后御歌㉑源頼朝公別墅跡 ㉒侯爵細川家 松樹五百本寄進の碑㉓石原裕次郎 記念碑 ㉔葉山灯台(裕次郎灯台)㉕森戸の夕照(もりとのせきしょう) ㉖車祓所 ㉗駐車場 ㉘森戸海岸㉙富士山 ㉚江ノ島 ㉛子宝石納所 ㉜車いす・ベビーカー用スロープ朱の鳥居を潜り進み、参道の狛犬の手前を右に曲がる。正面に朱の橋・「みそぎ橋」が見えて来た。公衆トイレの手前に掲示板が。「葉山俳句会」の作品が八句。・飛魚や地球どこでも震源地 石橋静江・若葉風言葉の美しき人と会ふ 高梨久子・陽炎の中はくすぐったいかもね 小沢一郎・・・以下省略・・・「みそぎ橋」。道路橋で、「かながわの景勝50選」に選ばれたタ照の地、森戸川の河口に架かる小橋である。木橋を思わせる橋であるが、構造は鉄筋コンクリートで、橋長22m、幅員3.4m。優美な朱色の欄干と青銅の擬宝珠が取り付けられている。絵になる橋である。青銅の擬宝珠の下には「みそぎ橋」と。この森戸の海浜は、鎌倉時代に七瀬祓の霊所と定められ、事あるごとにお祓いやみそぎが行われたと「吾妻鏡」に記されています。このような故事により、この海辺で「みそぎ」が盛んに行われ、神社から海辺に通じる橋を「みそぎ橋」と呼ぶようになったと言い伝えられています。「みそぎ」とは重大な祭事の前に海水を浴び、罪穢を祓いのけ、身を洗い清めることです。神社入り口を右方向に曲がるとご覧になれます。下を流れるのは「森戸川」。上流側を見る。下流側を見る。正面に見えたのが「森戸神社」の社殿。ズームして。「みそぎ橋」を渡り、海に向かって川沿いを進むと左手に石碑が。誰に関する石碑だったのであろうか?これも、この後訪ねた西東三鬼に関連した石碑?「葉山海岸 即事 哲五月湘南景曷ぞ優なる近く看る江島浪間に浮かぶを遠く瞻れば蓮岳天蓋に聳ゆ暫らく童児に倣い貝を拾いて遊ぶ豫徴始めて車に乗る苔花闘病三年纔に関を徹し今朝乗車湘湾に向う患し無し半ば坐し半ば横臥す快適轔々葉山に至る」伊勢神宮 内宮の御手洗場に似た光景。ここも御手洗場なのであろうか?西東三鬼(さいとう さんき)の句碑「秋の暮大魚の骨を海が引く」。「西東三鬼、1900年(明治33年)5月15日 - 1962年(昭和37年)4月1日)は、岡山県出身の日本の俳人。本名・斎藤敬直(さいとう けいちょく)。 歯科医として勤める傍ら30代で俳句をはじめ、伝統俳句から離れたモダンな感性を持つ俳句で新興俳句運動の中心人物の一人として活躍。戦後は「天狼」「雷光」などに参加し「断崖」を主宰。」とウィキペディアより。「森戸川」の対岸の高台に「森戸神社」の社殿を再び。「森戸川」の河口を見る。この後に訪ねた、飛柏槇(ひびゃくしん)と千貫松(せんがんまつ)を見る。飛柏槇(ひびゃくしん)をズームして。「森戸海岸」を見る。岩場の奥に「江ノ島」の姿が。ズームして。移動して。再び森戸神社の社殿を森戸川越しに。「みそぎ橋」を渡り「森戸神社」の参道へ戻る。参道の両脇に巨大な狛犬が。狛犬(右)。狛犬(左)。「参集殿」が参道の左側にあった。来客や祭典奉仕者などをお迎えする施設として、また、結婚式の控え室としても利用されているようであった。「命が積もり歴史に成る HaYaMa Time」第32回葉山芸術祭 👈️リンクが4/24~5/12で開催されたと。<アーティスト>ブルース・オズボーンの作品とのこと。2003年に誕生した「親子の日」の理念は “「親」と「子」の関係を見つめて、家族、地域、社会、そして自然をも含むすべての「環境」に敬意を払い平和を願う” です。 そしてまた、「親から授かった全ての命が健やかに育まれてほしいという願い」を込めた私たちからの「未来への贈り物~present to the future~」として20余年の歳月をかけて育んできました。2025年(令和7年)1月に町制100周年をを迎える葉山町と、1894(明治27)年に竣工され御用邸の中でも一番長い130年の歴史を刻む葉山の御用邸が、私たちの希望を繋いでほしいと願い、今まで撮影した9500組の親子写真の中から葉山で出会った親子の写真を選び作品にしました と。「二の鳥居」は石鳥居。右手に「総霊社」。「総霊社」。社殿に近づいて。見事な彫刻。内陣は鍵で閉ざされていた・・・・。「総霊社英霊、祖霊を始め水子の霊など、この社には多くの霊がまっられています。どなたの霊でも「おまつり」いたしますのでお申し出て下さい」こちらは「畜霊社」。かつて、多くの家畜が疫病にかかった時、この社にお参りしお願いすると病から免れることができたと云われ、以来家畜(ペット)の守護神として篤い信仰があると。「畜霊社かつて、多くの家畜が疫病にかかった時、この社にお参りしお願いすると病から免れることが出来ると云われ、以来家畜(ペット)の守護神として篤い信仰を集めている」内陣には石製の社が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.26
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その15):光徳寺
次の目的地の「葉山町堀内」にある「光徳寺」に向かって進む。こちらは「光徳寺」から少し離れた場所にあった「光徳寺の墓地」。さらに「光徳寺」に向かって進むと右手に小さな社があった。内部には五輪塔の如く石塔が安置されていた。「光徳寺 観音堂」碑。住職の?住宅の離れにあった「観音堂」。「観音堂」。「観音像」に近づいて。さらに。そしてこちらが「会館 望嶽亭」への入口。七重石塔。そして本堂への参道。六地蔵。手水舎。本堂前の石灯籠(左)と天水桶。石灯籠(右)。本堂を正面から。宗派 浄土宗山号 仏心山院号 常照院寺号 光徳寺本尊 阿弥陀如来所在地 三浦郡葉山町堀内1349番地。本堂に近づいて。扁額「慈徳殿」。本堂内陣。鐘楼。梵鐘。「重建記念碑」。「重建記念碑」「重建」とは再建の意味であると。「宗祖 円光大師」碑。寺務所。望嶽亭。寺報「おてらでは」。令和六年三月十五日号。老僧 祝 92才 記念写真。寺の屋根にも「光徳寺」と。飾り瓦。鈴木家墓地入口。鈴木竹雄家之墓 と。正面にも石灯籠、墓石が並ぶ。再び「望嶽亭」への山門。「掲示板我田引水〈意味〉 自分の田に水を引き込むこと。自分の都合のよいように言ったり、行ったりすることの たとえ。自分に好都合になるように事を取りはからうことのたとえ」。〈構成〉 「我田」は自分の所有する田、「引水」は水を引き込むこと。〈類義語〉得手勝手」左手の石碑には「従是光徳寺行」と。「南無阿彌陀佛」碑。「日露戰死病歿之英霊南無阿彌陀佛」と。再び参道を振り返る。「あじさい公園」に向かったが、まだ早そうなので引き返した。「HAYAMA Town Guide」。現在地はここ。次の目的地の「森戸神社」に向かって葉山町堀内の住宅街の路を歩く。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.25
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その14): 芝崎海岸~菜島(名島)の鳥居~葉山灯台(裕次郎灯台)~真名瀬港
県道207号線・森戸海岸線を左折して「芝崎海岸」に向けて進む。前方にあったのが「CONDOMINIUM THE HAYAMA」。相模湾に面した岬に建つ4階建て(地下1階)・総戸数34戸の低層マンション。ヨーロピアン調の外観が特徴的、共用部に設けられた屋外プールから眺める太平洋は絶景と。優雅な空間を実現できるリゾートマンション と。防波堤に沿って西方向に進む。この日の散歩ルート。「ライオンズマンション葉山マリンビュー」が前方に。「HAYAMA MARINE VIEW」と。芝崎海岸は東京から1時間強くらいで行けるシュノーケリングエリアの中では、間違いなく関東でNo’1のシュノーケリングポイントだ と。この時間は干潮時で多くの岩場が海面上に姿を現していた。芝崎海岸では多くの種類の魚を大量に目撃することができ、浅い場所から10メートルを超す深い場所までバラエティに富んだ広大なポイントである と。遠く江ノ島をズームして。柴崎海岸からの富士山の姿をネットから。防波堤に囲まれた五角形の形になっている沿岸道路をさらに進む。建物は「マイキャッスル葉山」。地上5階 地下1階建、総戸数44戸のマンション。「葉山町指定天記念物 葉山柴崎海岸及び周辺水域」案内板。「葉山町指定天記念物葉山柴崎海岸及び周辺水域 平成7年4月1日指定第44号相摸湾に面したここ芝崎海岸は、葉山層群の森戸泥岩層及び森戸凝灰岩層からなる磯で、潮間帯、潮下帯ともに転石地帯、砂礫、砂地等が広がり、変化に富んだ地形をしています。海洋環境については、黒潮系暖流の流れによる外洋水の影響を受けるため、潮通しがよく、透明度も良好です。また、黒潮系暖流の影響で、真冬でも10度以上の海水温を保ち、一部を除く暖流系生物が周年見られる海域となっています。また向芝原(岸側中央部の小高い所)から沖合いにかけての自然は残され、ここで観察される海洋生物は貝類・甲殻類・魚類・海藻類など多種多様です。かって、昭和夭皇が当地へ調査研究に来訪され、ウミウシ類、ホヤ類、ヒドロ虫類の新種を多数発見されました。中には芝崎の岩礁の一つである鮫島にちなんで「サメジマオトメウミウシ」と名付けられたウミウシの新種もあります。このように、芝畸海岸は狭いながら多種多様な海洋生物が豊富に見られる海域のひとつになっています。 葉山町教育委員会 平成23年11月」岩場で遊ぶ家族連れ?の姿も。この時は潮が引いていたのであった。「菜島(名島)の鳥居」をズームして。その先に朱の小さな社の姿も。「江ノ島」と「菜島(名島)の鳥居」のコラボを。「菜島(名島)の鳥居」の上に「江の島シーキャンドル」。「葉山灯台(裕次郎灯台)」。葉山灯台は、俳優たけでなくヨットマンでもあった故石原裕次郎氏の三回忌を記念して、兄の石原慎太郎氏が基金を募り1989年に建設しました。そのため「裕次郎灯台」とも呼ばれています と。民家の塀には濃いピンクの「マツバギク(松葉菊)」が。近づいて。葉と花の形から「マツバギク(松葉菊)」と呼ばれ、多肉質の細長い葉が密生し、キクのような花を咲かせていた。やや寒さに弱いが、乾燥や潮風に強く、やせ地でもよく育ち、横に這うように広がっていくので地面を覆うグランドカバーにも適しているとのこと。 「真名瀬(しんなぜ)漁港」。管理者 - 三浦郡葉山町漁業協同組合 - 葉山町組合員数 - 56名(2001年(平成13年)12月)漁港番号 - 2110080漁船が停泊中。漁船をズームして。「真名瀬漁港での禁止事項」案内板。「真名瀬海岸」を見る。「第1種 真名瀬漁港所在地:神奈川県三浦郡葉山町一色管理者:葉山町 都市経済部産業振興課 所管所:水産庁」漁港の種類は、漁船の利用範囲によって漁港漁場整備法 第5条第19条の3に基づき、次のように分類されます。 ・第1種漁港 : その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。・第2種漁港 : その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの。・第3種漁港 : その利用範囲が全国的なもの。・第4種漁港 : 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。・特定第3種漁港 : 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの。 以下の13港が政令で指定されている。 八戸(青森)、塩釜(宮城)、気仙沼(宮城)、石巻(宮城)、銚子(千葉)、三崎(神奈川) 焼津(静岡)、境(鳥取)、浜田(島根)、下関(山口)、博多(福岡)、長崎(長崎) 枕崎(鹿児島) とネットから。「真名瀬漁港」入口から「由比ヶ浜」方向を望む。県道207号線まで戻り、この後に訪ねた「森戸神社」方向を見る。「真名瀬海岸」からのダイヤモンド富士 をネットから。ハイキングコース案内「はやま三ヶ岡山緑地 真名瀬コース」。その奥には大きな藁葺き屋根の家が。現在は空き家になっているようであったが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.24
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸
「神奈川県立近代美術館 葉山館」の屋外展示作品を楽しんだの後は、県道207号線・森戸海岸線を横断し振り返る。そして、道路沿いにあった案内板。「趣きのある美術館と日本庭園山口蓬春(やまぐち ほうしゅん)記念館国登録有形文化財この先右折」と。案内に従い、狭い坂道を上って行った。山口 蓬春(1893年10月15日 - 1971年5月31日)は、大正時代から昭和時代後期にかけて活躍した日本画家。本名、三郎(さぶろう)。文化勲章受章者。この道は「蓬春こみち」と。細い坂道・「蓬春こみち」を上って行った。大きな石垣、そこに槙の新緑の生け垣が。そして「山口蓬春記念館」前に到着。鉄骨製の入口にガラス製ドアが。鉄骨製はややこの場所には不似合い。「山口蓬春記念館」👈️リンク 館案内板。料金:一般 600円。「生きものを愛でた蓬春」が開期:2024年4月6日(土) ~ 6月2日(日)【前期】で開催中であった。花や鳥、魚や小動物など「生きもの」を描くことは、古くから東洋では花鳥画として知られ、その多くの作例は時代を越えて人々を魅了し続けています。山口蓬春(1893-1971)は、そのような伝統的な画題を学びながらも新しい日本画の創造に邁進しました。昭和9年(1934)に野鳥の保護や調査を目的とした「日本野鳥の会」が創設されますが、蓬春はその発起人に名を連ねており、彼の野鳥や自然に対する造詣の深さがうかがえます。「花鳥畫の、作品の優劣は、その作家の自然への愛の深さと、観察のカの如何とのみが決定すると謂っていい。」(山口蓬春「花島去を描く心」「邦畫リ4月号、昭和10年〔1935〕)と述べていた蓬春。愛犬をわが子同然にかわいがる彼の作品には、生命への愛情をも実感できるほか、数多くのスケッチからは制作に対する真摯な姿勢が伝わってきます。本展ては、蓬春の日本画作品及びスケッチ・模写、ならびに彼が蒐集したコレクションを展示し、蓬春と「生きもの」という観点からその画業を探ります とネットから。その先左手にあった美しい健仁寺垣(けんにんじがき)風の竹垣。この日は、時間の関係上、入館はパス。道路から「山口蓬春記念館」の建物を見る。以下の「山口蓬春記念館」👈️リンク の写真3枚はネットから。1階の和室。庭園が見下ろせる大きな窓が開放感いっぱいの画室。山口蓬春「新宮殿杉戸楓杉板習作」昭和43年(1968) をネットから。「山口蓬春記念館」の生け垣の前を西に進む。右手には別の建物の木製の脇門があった。数寄屋門風の簡易引き戸の門。そして左手にあったのが「旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘」。この建物は一般公開されていないようであった。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治から昭和にかけて活躍した政治家金子堅太郎の別邸として、葉山御用邸に近い三ヶ岡の山を背負い正面に海を望む斜面地に所在します。金子堅太郎(1853~1942)は、福岡藩の修猷館で学んだ後、明治4年(1871)、私費留学生として岩倉使節団に藩主とともに随行し渡米、ハーバード大学で法律学を修めました。帰国後は明治憲法の草案起草に参画し、後には伊藤博文の下で農商務相や司法相、枢密顧問官などを歴任した人物です。金子堅太郎は明治20年代から現在の葉山一色公園付近に別荘を構えましたが、大正8年の御用邸付属邸建設に伴い、大正11年頃、現在の地に転出しています。関東大震災後には、葉山別邸はほぼ常住の住宅として使用されたことが記録に残っています。現在地への移転に伴い、建物の一部が移築されたと伝えられ、照憲皇太后が訪問された「松の間」がそれに当たるとされますが、明治期創建の移築は部材の一部など限定的であったようです。戦後、所有者が変わり、昭和30年頃に改修が行われていると考えられますが、皇太后訪問時に使用された「松の間」の記憶を継承するべく、大正期の金子堅太郎別邸時代の意匠を強く意識していたことがうかがわれます。平成19年にも改修が行われていますが、現在に至るまで由緒ある別荘建築として大切に住み継がれています。「松の間」には、変木の床柱や琵琶棚をもつ床の間と床脇を設け、部屋境の欄間は銅板に梅花のすかし模様と竹をあしらった質の高い意匠が施されています。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘は、明治20年代に海岸沿いに設けていた別荘が、御用邸付属邸建設に際し、大正11年頃に移転するという歴史を継承しており、御用邸とともに歩んできた葉山の歴史を反映する重要な建物です。以下の2枚の写真はネットから。旧金子堅太郎葉山別邸恩賜松荘の座敷8畳「松の間」。こちらは「旧金子堅太郎葉山別邸 米寿荘」。そして引き返して、再び「一色海岸」へ。「旧ベルンハルド・モーア邸」この美しい建物は、ドイツ人の建築家アルヌルフ・ペッツォルドが戦前に設計した。今ではペッツォルドの名前を知る人も少ないと思うが、彼の設計で現存するのは筆者はここしか知らない。ハーフティンバー様式で木材の部分は濃い青で綺麗に維持されているが、近くで見ると少し塗料の剥がれた木材が年季を感じさせる。戦前の所有者は日本シーメンス社長、ベルンハルド・モーアであった。シーメンスは当時からドイツ有数の大企業だ。ここは歴史的建造物等の指定を受けていないがその価値は十分にある。現オーナーの意向であろうか とネットから。「三ケ下海岸」方向を見る。葉山御用邸、長者ヶ崎方向を見る。そして再び県道207号線に戻り、右手の山の裾野に建っていた建物は「旧鹿島守之助別邸( 旧住友家麻布邸)」。1903(明治35)年、麻布に旧住友邸として建てられた。住友家15代吉左エ門友純邸宅。1935(昭和10)年葉山に移築。この建物も、一般公開されていないようであった。「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を振り返る。長者ヶ崎をズームして。潮の満ちた長者ヶ崎の割れ目からは三浦半島の先端方向も見えたのであった。「三ケ下海岸」バス停前のプール付き?の建物の入口。再び、「三ケ下海岸」と「一色海岸」の間にあった岩場を。岩場をズームして。大きなプール?のある建物。入口には「WATABE & CO.」と書かれていたが。岩場には海鳥?が2羽。右手の「はやま三ヶ岡山緑地」の斜面は緑に覆われていた。その先、左手にあったのが「鹿島 葉山研修センター(旧小田良治別邸)」。「鹿島 葉山研修センター」。鹿島建設の葉山研修センターは、明治から昭和にかけて活躍した、実業家・小田良治の元別荘建物。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。しかし広い敷地にゆったりと建てられたその様は、実に存在感があった。照明や建具、ステンドグラスなど今では考えられないほど手の込んだものを使っていると。窓ガラスはドイツ製、床の大理石はイタリア製と建築材料は すべて外国から取り寄せたそうです。森戸海岸線からの写真をネットから。。銅葺き屋根の緑青が良い味を醸していますが、意外とシンプルな外観。「一色海岸」、「葉山御用邸」方向を振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.23
コメント(2)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その12):長雲閣こみち~神奈川県立美術館
「森山社」を後にして、県道207号線に向かって、葉山町一色の住宅街の道を進む。「長雲閣こみち」。長雲閣とは、総理大臣や陸軍大臣を歴任した、桂太郎氏の別荘のこと。日露戦争の前後には、政府要人たちが度々会議に使用したそうです。現在は、この小道に名前が残るのみ。古い時代に想いを馳せつつ、さらに進みます。「長雲閣こみち」。県道沿いのレストランの塀に「桂太郎別荘・長雲閣跡」の案内が掛かっていた。が、私が聞いた話では、県道から少々入った建物である。下の写真は、「長雲閣こみち」と、中央に建物が写っているが、その建物が、数年前まで桂太郎別荘とされていた。しかし地元歴史家よると、ここではなく、向かい側の建物がそうだと変更になったのだと。「桂太郎別荘跡」はここであっただろうか?日露戦争前後には、政府要人による重要会議が別荘を中心に度々開かれている。司馬遼太郎原作「坂の上の雲」でも「葉山会議」と称して登場している。そして再び県道207号線に出て北上する。左手にあったのが「神奈川県立近代美術館 葉山館」。奥にあったのが屋外にある常設展示。2003年の開館以来、一部作品の入れ替えや追加を経て、2016年に旧鎌倉館から移設された9点が加わり、現在は彫刻20点が庭園に、壁画2点が建物内に常設されている。葉山館のイラストマップ「彫刻はどこにいるの?」(館内無料配布)と一緒に、一色海岸に臨んだ庭園を散策しながら野外彫刻を楽しんだのであった。三浦郡葉山町一色2208−1。茶色の石材で。中島幹夫 NAKAJIMA Mikio『軌 09 Orbit 09』1966年館内では「吉田克郎展」が、開催されていた。「吉田克朗展 -ものに、風景に、世界に触れる」会期:2024年4月20日(土)〜6月30日(日)。武蔵野美術大学の教授だった美術家、吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展と。吉田克朗『触“春に”V』。これまでほとんど紹介されることのなかった作品や、さらに油彩から版画作品までを網羅し展示していると。県道沿いには幟が立っていた。駐車場の横にあったアルミニウム&大理石の作品。清水九兵衛 KIYOMIZU Kyuubei『BELT』1978年駐車場から「神奈川県立近代美術館 葉山館」を見る。小田 襄 ODA Jo『円柱の展開 Development of a Cylinder』1983年李 禹煥 LEE Ufan『項 Relatum』1985年「神奈川県立近代美術館 葉山館」入口。若林 奮『地表面の耐久性について』ホセイン・ゴルバ Hossein GOLBA(1956~)『愛の泉 Fountain of Love』イラン出身のホセイン・ゴルバの作品『愛の泉』。最初イタリアのチェレ彫刻公園の水飲み場として制作された。樹木の幹を鋳造、他の部分を蝋型で付加。「愛」の意味とは?「飲料水 Drinking Fountain右下のボタンを踏むと水が出ます」との案内も。水桶には二人の顔が。さらに葉山館だけの作者からの「おまけ」も足元に。強く踏むと、ボタンを踏んでいる足に水がかかるのであった。鈴木 昭男『「点音(おとだて)」プレート・葉山』2012年。『地平の幕舎』。鉄板でテントのような形を。鉄の赤錆がいい色を出していた。保田春彦 YASUDA Haruhiko『地平の幕舎』1993年『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』。眞板雅文 MAITA Masabumi『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』2003年『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』。波乗りジェーンって感じで。富樫 一 TOGASHI Hajime『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』1972年ここが先程訪ねた「葉山しおさい公園」からの連絡通路。「開門時間土曜日・日曜日・祝日の近代美術館開館日のみ午前10時30分~午後4時まで」「三ヶ岡遺跡神奈川県立近代美術館葉山の建設に伴い、この地にあった三ヶ岡遺跡が発掘調査され、主に古墳時代から平安時代(4 ~ 10世紀)にかけての集落の跡が発見されました。この遺跡で特筆されることは、海浜に立地する特徴を活かした平安時代の製塩跡が見つかったことです。ムラの跡 竪穴住居が22軒、掘立柱建物が1棟密集して発見されました。ほとんどが6 ~ 7世紀のもので、継続して居住していたことがわかりました。製塩跡 約2X6mの範囲に火を受けて赤く硬くなった地面があり、そのそばから多量の土器が打ち捨てられたままに出土しました。また海水を煮詰めるためのものか、石組炉の跡も2基発見されています。」「製塩跡」と「竪穴住居跡」。『イノセンス-火 Innocence:Fire』。西雅秋 NISHI Masaaki『イノセンス-火 Innocence:Fire』1991年西雅秋『大地の雌型より』2003-5年葉山漁港の4隻の木造船にコンクリートを流し込み、ひっくりかえして木部を外したもの。「一色海岸」を望む。西雅秋『大地の雌型より』の一部。アントニー・ゴームリー『Insider Ⅶ』1998年山口牧生 YAMAGUCHI Makio『棒状の石あるいはCosmic Nucleus aBar of Stone,or Cosmic Nucleus』1976年『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』。空 充秋 SORA Mitsuaki『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』1985年湯村光『Stone Work – Stream』1987年柳原義達(1910~2004) YANAGIHARA Yoshitatsu『裸婦 座る Sitting Nude』原型 1956年(鋳造 1964年以前)『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』。近づいて。イサム・ノグチ(1904-1988)は、日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれた、20世紀を代表する世界的な彫刻家。彫刻はもちろん庭園や舞台芸術、家具そして照明のテザインも手がけるなど、現代彫刻の可能性を大きく押し広げ、作品と活動を通して世界各地て愛されつづけている芸術家である と。イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』1951年『石人 Stone Man』1966年(古墳時代6世紀後半の扁平石人の複製(岩戸山古墳[福岡県]出土・現在大分県日田市に設置)イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』を振り返って。これは、展示物ではなく、石製の休憩場所のようであった。「レストラン オランジュ・ブルー」。イサム・ノグチの作品を別の場所からも。最後に「神奈川県立近代美術館 葉山館」を再び振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.22
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その11):森山社
「玉蔵院」を後にして、国道134号を80mほど南に下り、右折すると次の目的地の「森山神社」案内板があった。そして直ぐ先、右側に「森山神社」の参道入口が現れた。石段を上ると「森山神社」の石鳥居が。「森山神社一 御祭神 奇稲田姫命(素戔嗚尊の妃神)一 祭 日 歳旦祭 1月2日または3日 祈年祭 2月中旬 例 祭 8月末日曜 新嘗祭 11月中旬 行合祭 満32年目毎に執行由 緒当社は、奇稲田姫命を奉斎し家業繁栄、家庭円満、農耕の守護神と仰ぎ 今から1270余年前、天平勝宝(749〜757年)の頃、良辨僧正によって勧請されたと伝えられる。三浦古尋録に、「此守山明神ノ祭礼ハ三十三年目毎也、此祭礼ノ時ハ例ニヨツテ小壺村ノ天王ノ神輿ヲ借用ルトナリ、祭礼神輿ニ札ヲ張、今其札三十四枚有、此札年来ヲ数レハ、文化申年(一八一二年迄一一二二年ニナル」と創建年代が如実に記されている。又、江戸で正徳5年に刊行された和漢三才図絵には、「守山大明神 佐賀岡ニ在リ、社領三石、俗ニ世計大明神ト号シ、毎年十一月十五日ニ酒ヲ醸シ翌年正月十五日明神ニ供ス、其ノ酒デ善悪ヲ試シ、歳ノ豊凶ヲ計ル」と記され、当時三ケ岡に鎮座し、天正19年11月に、徳川家康公より社領三石が寄進されている。特に世計り神事は近隣の人等の篤い崇敬を集めていた。新編相模風土記に、「森山明神社鎮守ナリ神躰ハ束帯ノ座像天平勝宝年間良辨僧正勧請スト云、天平十九年十一月社領三石ヲ寄附セラル、例祭毎年十一月十五日但三十三年ニ當ル年ハ十一月十三日小坪村天王神輿ヲ迎十四日ニ神楽ヲ奏シ當日鶴岡社人、伶人、八乙女、等来テ管絃ヲ奏シ二神輿ヲ引いて舁テ海岸ニ至ル是ヲ神忌ト唄フ」とある。海辺の当地に農耕に深い関係のある神事が今日迄伝承されていることは非常に珍らしく、この地域の人等が作付をする上で、重要な指針であった証拠であろう。昭和39年 三十三年の大祭を記念して、氏子崇敬者の浄財で現在の社殿を改築した。 謹白 宗教法人 森山社」住宅の間に参道があり、奥にある本殿までまっすぐと伸びていた。正面に石鳥居の「一の鳥居」。広場の先に、石段がありその先に「拝殿」が見えた。右側には例大祭等の時の、大きな石製の観覧席の如きものがあった。「拝殿」への石段を上る。「奉納 参道」碑。「奉納 石段」碑。石段の上に「狛犬」(右)。石段の上に「狛犬」(左)。足で押さえているのは、お花?明治35年生まれで、耳を横に張った江戸流狛犬。花は牡丹のように見えたが。「例大祭 献詠歌」「献詠歌」に近づいて。「手水舎」。「吐水口」。水を吐き出している龍には迫力があり立派。水を司る龍には火防の意味も有る。そんなわけで多くの神社仏閣で龍を見かけることがあるのだ。「花掛け」「奉納 森山社 例大祭 御寄附者一覧 令和五年八月」と。正面に「拝殿」。森山神社は正式名称を「森山社」と称し、社伝によると祭神として「奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)」を祀っています。創建は天平勝宝(西暦749年)で、鎌倉由比ヶ浜生まれの良辨僧正が勧請されたとされています。往時は「守山大明神」とか「佐賀岡明神」と呼ばれ、佐賀岡(現・三ケ岡=大峰山)にあったとのこと。「森山社の祭神は「奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)」です。(日本神話に登場するこの女神は『日本書紀』では「奇稲田姫」『古事記』では「櫛名田比売」と表記されます)奇稲田姫命は出雲国(島根県)簸の川(斐伊川)の川上に住んでいたとされ、足名推命(アシナヅチノミコト)と手名推命(テナヅチノミコト)夫婦の八人娘の末娘として暮らしていました。毎年毎年、八岐大蛇がやってきて次々と娘たちを食べてしまい、最後に残った末娘の奇稲田姫命も食べられてしまう時期がきたので、老夫婦の両親は嘆き悲しんでいました。そこへ高天原を追放された「素盞嗚尊(スサノオノミコト)」が折よく現われ、ことの次第を聞き義侠心を燃え上がらせて八岐大蛇を退治しました。(日本神話に登場するこの大蛇は『日本書紀』では「八岐大蛇」『古事記』では「八俣遠呂智」と表記されます)助けられた奇稲田姫命は素盞嗚尊と結婚して、出雲国に宮殿を造って住んだとされます」とネットから。拝殿に近づいて。本坪鈴(ほんつぼすず)が二基並ぶ。扁額「森山神社」。内陣。本殿に向かって左側にあった「神輿庫」。神輿が大きすぎて・・・。こちらは、子供用神輿か?例大祭時の神輿👈️リンク の写真をネットから。森山社の境内にはいくつかの境内社があった。■船玉神社(祠)●御祭神:住吉三神(底筒男命(ソコツツノオノミコト)、中筒男命(ナカツツノオノミコト)、 上筒男命(ウワツツノオノミコト))●御神格:海の神、航海の神、和歌の神●御神徳:海上安全、漁業・海運・貿易・造船などの業種守護、商売繁盛、開運招福 (縁結び・子授かり)■金刀比羅社(船玉神社内)●御祭神:金山毘古命(カナヤマヒコノカミ)●御神格:鉱山の神、鍛冶の神、鉱物の神、包丁の神●御神徳:鍛冶技術向上、金属加工業の守護、金運、商売繁盛、開運招福、災難避け、厄除け 漁業の守護神・商売繁盛・縁結び・子授かり●由 緒:創建不明、神奈川県郷土資料(明治12年)及び葉山郷土誌(昭和5年(1930))には「住吉神社(建物正面一間、奥行一間)」と、「金刀毘羅神社(建物正面三尺、奥行三尺)」と二社の記載がある。現在の祠は、昭和43年(1968)11月一色氏子会(連名)、一色漁業正組合員(連)により改築された。■厄神社(大国主社)(祠)●御祭神:大地主命(オオトコヌシノミコト)・大物主神(オオモノヌシノカミ)●御神格:国造りの神、農業神、商業神、医療神、縁結びの神、土地の神、家・屋敷を守る神●御神徳:縁結び、子授かり、夫婦和合、五穀豊穣、病気平癒、産業開発、交通・航海守護、 商売繁盛・国内平定・天下泰平・農業保護・医薬の神●由 緒:創建不詳、祠内に残された木札が存し、表面に「天下泰平 奉 厄神社 御造營神璽 崇敬者安全 社掌 守屋喜代太郎」、裏面に「大正8年1月14日 一色崇敬者中」の記載がある事から往時の建物か?伝によれば三ケ岡町内から氏子廃絶により移されたといわれている。神奈川県郷土資料(明治12年(1879))に「大国主神社、祭神・大地主命、由緒不詳、建物・正面三尺奥行三尺」の記載あり、また、葉山町郷土史(昭和5年(1930)には「大国主社、祭神・大地主命、由緒・ 不詳、建坪・二合五勺」の記載がある。■稲倉魂社(祠)●御祭神:稲荷神(倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)(日本書紀)・宇迦之御魂神(古事記))●御神格:五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神●御神徳:五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達田の神、五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神 ●由 緒:創建時期不明、祠内に「正一位稲倉魂命天長地久常堅右明治二己巳年(一八六九)十二月鈴木源致」と木札あり、この時期に建立されたものと思われる。神奈川県郷土誌(明治12年(1879))に、「稲荷社祭神稲倉魂命、由緒不詳、建物正面三尺奥行三尺、氏子百六拾弐戸」とあり、また、葉山町郷土史(昭和5年)に「祭神稲倉魂命、由緒不詳、建坪二合五勺」とある。古老によれば一色打鯖地区から移設されたの伝有。 平成30年(2018)、講を解散するに当たり、新たな祠を隣地玉蔵院に建立、既存の社を廃社としたが社屋のみ残されている。境内北側に在する稲荷大明神も、上原地区を中心とした講中で、当社と同様の縁起である。■神明神社(祠)●御祭神:天照大神(アマテラスオオミカミ)(日本書紀)、天照大御神(古事記)●御神格:太陽神、皇祖神、日本の総氏神●御神徳:国家安泰、子孫繁栄●御祭神:豊宇気毘売神(トヨウケビメノカミ)●御神格:食物神、穀物神●御神徳:農業・漁業の守護、産業振興、開運招福、厄除け地元では「だいじごさん(大神宮様)」と呼ばれる伊勢神宮の分社。●由 緒:創建時期不明、葉山町葉山郷土誌(昭和50年(1975)3月)記述の古老の伝によれば、大正初期(1912~1916)には御祭神が森山神社に合祀されていた。ご神体(石)碑?は明治13年(1880)に遷宮祭としてだいじごさん(大神宮山(一色1501番地付近))から深夜零時に安置したと伝わっている。 一方、神奈川県郷土誌(明治12年(1879))には、「神明社(一色字平松)、建物正面一間、奥行一間境内17坪、信徒七拾人、民有地第一種」と記述あり、拠って当地とは別地に存し、前記の時期に当社に合祀されたと思われる。 例年7月に「大神宮祭」を斎行し、氏子の崇敬を集めている。■稲荷大明神(祠)(京都伏見稲荷の分社)●御祭神:倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)●御神格:五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神、屋敷・地域の神●御神徳:五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達、金運向上、諸願成就 ●由 緒:創建不詳、伝によれば一色上原地区を中心に活動していた講が、将来の衰退を危ぶみ、森山神社に合祀されて今日に至っていると言われている。稲荷神社の多くは旧家や辻々に建立しているのを散見することができ、その中で血縁者や地縁的関係者などの小集団で社の講中を行っていた。境内西側に在する別祠稲倉神社も、一色打鯖・三ケ岡地区を中心とした講中で、当社と同様の縁起である。左側から拝殿を見る。■浅間神社(舟型石碑)●御祭神:神吾田津姫、神吾田鹿葦津姫、木花開耶姫(コノハナノサクヤビメ)(日本書紀)、神阿多都比売、木花之佐久夜毘売(古事記)●御神格:火の神、山の神、安産の神、子育ての神、酒造の神●御神徳:子授け、安産、縁結び、農業・漁業守護、航海安全、火難消除、織物業守護 浅間信仰・富士山信仰・山の神をまつる社。●由 緒: 創建明治17年(1884)6月1日、一色在の富士(浅間神社)講中が建立、富士吉田市浅間神社 には、「葉山町一色富士講中」と記された扁額を見ることができる。 神奈川県郷土資料(明治12年)には「浅間社、由緒不詳、建物正面三尺、奥行き三尺」の 記載あり、また、葉山郷土誌(昭和5年)には「浅間神社」の記載がある。 なお、同様の石碑が後背の峰岡山山頂にも凝灰岩で出来た富士講の石塔(明治16(1883)年が 祀ってある。他にも多くの歴史を感じさせる石碑が。「令和五年 森山社例大祭」案内。「森山神社 ホームページ QRコードです!!」。「拝殿」前の石段から参道を見る。小さな石祠。そして、ビービーとミツバチが訪花している木は「クロガネモチ」クロガネモチの開花は5~6月。その年に伸びた葉の脇に小さな花が複数集まって咲く。雌雄異株で雄株には雄花が、雌株には雌花が咲くが、いずれも直径4ミリほどで目立たない。花は淡い紫~クリーム色で、花弁と萼は浅く4~6つに裂け、花弁は反り返る。雄花は4~6本ある雄しべが目立つが、雌花の雄しべは退化しており、代わって中央にある柱頭が隆起する。セイヨウミツバチの姿を。ズームして。こちらはニホンミツバチ。「クロガネモチ」の「ハチミツ(蜂蜜)」をネットから。別名「山れんげ」と呼ばれる人気ある蜂蜜と。そして参道左手にあったのが「一色会館」。一色会館は、レトロでちょっとユニークな建物。通常は、上の写真の様に片側に掃き出し窓が並ぶ外観ですが、例大祭などがある時は、並んだ扉や桟などを全部外して、大きな舞台になってしまうのだと。下の写真は、お祭りの時の“舞台”になった状態であると ネットから。舞台の正面は、ひな壇になっていて客席になるのだ「。まるでちょっと昔の“芝居小屋&桟敷席”といったレトロな風情で、昭和の香りがたっぷり残る素晴らしい空間。舞台になっている部分は、畳敷きの大広間。大広間の上手も小さな舞台になっている と。こちらが「一色会館」の玄関。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.21
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その10):高野山 真言宗 守護山 玉蔵院
Googleマップの案内に従い、次の目的地の「玉蔵院」に向かって進む。Googleマップは、墓地の裏の入口を案内したのであった。墓地内そして境内を歩き、「国道134号」側の正門まで進む。「高野山真言宗三浦不動尊第2十三番三浦観世音第二十五番湘南七福神恵比寿尊干支守霊場第七番 玉蔵院」三浦観世音「第廿五番霊場」碑。参道を本堂に向かって進む。「高野山 真言宗 玉蔵院 掲示板」。「おてらヨガ」も行われているようであった。寺号標石「高野山 真言宗 守護山 玉蔵院」。この石碑は?近づいて。しかし解読不能。山門を入るとまっすぐに続く参道の脇に、幹の周囲が3m近くもある樹齢400年以上のイチョウ・エノキの巨木が聳え立っていた。右手には「エノキ」の巨木。「イチョウ」の巨木を見上げて。左側にもイチョウ(銀杏)の大木そして一番本堂よりに「エノキ」が並ぶ。「エノキ」の手前に「葉山町指定重要文化財 天然記念物 玉蔵院のエノキ・イチョウ」碑。庚申塔が二基。近づいて。左側の庚申塔道立年号(塔に刻まれている年月日) 元禄5壬申天5月吉日(1692年)碑型、石質、其の他 舟型、安山岩、2基の内向って左塔大きさ及破損度 高さ76cm(台石を含まず)。幅37cm。上部が少し缺けた外完全刻像 定印阿弥陀如来と三猿 三猿は向って右から見ざる、聴かざる、言わざるで、左右の猿は背を丸めて中央の猿に 向っている。銘文 種子は缺損 上原村 八郎衛門、六左郎、甚衛門、市衛門、勘兵衛、五兵衛 四郎兵衛、市兵衛、次郎兵衛、三郎兵衛。塔の特徴 この塔は定印阿弥陀如来を主尊にしたのが特徴で、葉山町では1基だけである。 又三猿の左右の猿が背を丸めて中央の猿に向き合っている事も特徴である。右側の庚申塔 ???「六地蔵」。「六地蔵」とは六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天からなる六つの世界)全て救うという誓願のもと、六体の地蔵があり子どもを護る仏様として知られている。因みにこの寺の六地蔵は眼病にご利益があるとされている と。境内右側の、弘法大師像。「南無大師遍照金剛」と書かれた白の幟が一対。近づいて。「弘法大師 御入定 千百五十年記念四國八十八ヶ所砂踏み霊場」と。主尊が阿弥陀如来という、立派な宝篋印塔が建っていた。六地蔵の横に建っている県下でも珍しい石塔型の転輪で、お百度参りに使われたものだと。「葉山町指定重要文化財 建造物 玉蔵院の庚申塔 二基」種別 建造物(石造)指定年月日 昭和45年8月27日所在地 葉山町一色(玉蔵院)規模 高さ114cm、幅51cm石材 安山岩時代 寛文五年(1665年)下部に三猿「言わざる」「聴かざる」「見ざる」。三猿に雌雄がはっきりと表されている大変珍しいもので、寛文5(1665)年10月吉日の陰刻から葉山最古の塔とされていいる と。「三ヶ岡講中」と。「葉山町指定重要文化財 建造物 玉蔵院の庚申塔 二基」と。「宗祖弘法大師御誕生壱千二百年記念碑」「高野山 真言宗 守護山 玉蔵院」の「本堂」。「干支守霊場 丑寅 歳の寺」。本堂内陣。守護山 玉蔵院は弘法大師(空海)を宗祖とし、高野山金剛峯寺(こんごうぶじ)を総本山とする高野山真言宗のお寺。ご本尊は大日如来(だいにちにょらい)で、拝む際は「オンバザラダトバン」とお唱えします。・開基年 奈良時代 天平勝宝年間(749~757)・開創者 東大寺別当 良弁僧正・本尊 金剛界大日如来(旧くは十一面観音)・霊場 三浦観音二十五番、三浦不動二十三番、湘南七福神恵比寿、十二支霊場丑寅年本尊 : 金剛界大日如来。本堂の左側には。丑寅歳本尊 虚空蔵菩薩。湘南七福神 葉山恵比寿。湘南七福神 葉山恵比寿。弘法大師像か?そして本堂の左側にあった境内社群。朱の鳥居が三基。お稲荷さま:正一位稲荷大明神・生目大明神・猿場大明神であると。中央が「生目大明神」。左が「正一位稲荷大明神」。右側が「猿場大明神」。境内左で、 更に右奥の庚申塔群を訪ねたが、巨大なオオスズメバチが飛来して来たので慌てて避難。この時期からするとオオスズメバチの女王蜂であっただろうか?オオスズメバチの女王蜂の姿をネットから。危険なオオスズメバチですが、冬眠から目覚めた直後の女王蜂は栄養不足で体力がなく、弱っているため人を刺す可能性は低いとのことだが、既に5月末でもあり!! ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.20
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その9):葉山しおさい公園・池泉回遊式の 日本庭園
「葉山しおさい公園博物館」を後にして、「葉山しおさい公園」の池泉回遊式の日本庭園を歩く。「葉山しおさい公園平面図」。池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)とは、広い池泉を中心都市、中島、四阿などを設け、舟遊び・納涼・散策など、庭園をいろいろな角度から干渉し楽しめる造庭技法。 桃山末期から江戸初期にかけて成熟した作庭技法。 代表的な庭園として、桂離宮・修学院離宮・六義園・後楽園(岡山)などがある。大きな池を中心に配し、その周囲に園路を巡らして、築山、池中に設けた小島、橋、名石などで各地の景勝などを再現。園路の所々には、散策中の休憩所として、また、庭園を眺望する展望所として、茶亭、東屋なども設けられていた。スイレンの濃いピンクの花も。大きな鯉がのんびりと。石の「太鼓橋」。川の如き水場にも鯉が。茶室「一景庵」。「一景庵ー景庵は、一歩ー景ともいわれる日本庭園に囲まれた変化に富んだ趣ある情景から名づけられたとする説があります。茶室は、千利休の孫の千宗旦が利休の聚楽屋敷の四畳半を再現とされる裏千家の又隠と、千少庵が利休の聚楽屋敷にあった色付九間書院を写したものと伝えられる表千家の残月亭を摸した造りとなっています。」茶室「一景庵」の内部には赤い毛氈の敷かれた長椅子が。白の「柏葉あじさい」。近づいて。池越しに先程訪ねた「葉山しおさい公園博物館」を見る。ここにも。茶室「一景庵」を反対側から。水音が聞こえる方向に向かって歩く。右側に滝が現れた。「噴井の滝湧水部が力強く水を噴き上げる井戸型をしていることから、「噴井の滝」と名づけられたとの説があります。落差3mの滝は、横に広がりながら水が落下する「布落ち」と壁面を伝うように水が落ちる「伝い落ち」の複合水流からなり、美しい段瀑の姿をしています。」横に広がりながら水が落下する「布落ち」。石の壁面を伝うように水が落ちる「伝い落ち」。「滝」からの流れ。「滝」からの流れに架かる飛び石を渡る。「噴井の滝」を振り返って。ズームして。飛び石を振り返って。「神奈川県立近代美術館 葉山館」への連絡口。連絡口。開門時間土曜日・日曜日・祝日の 近代美術館開館日のみ 午前10時30分~午後4時まで券売受付所の前にあった壺。「小村寿太郎 終焉の地」碑。終世困窮していたという小村は豪邸居並ぶ葉山で借家住いだったらしく、一色の潮騒を耳にして静かに生涯をとじた と。そして、「一色海岸」に向けて黒松樹林の中を歩く。黒松樹林の中を海の方へ向かってしばらく歩くとここだけ洋風なパーゴラテラスが。石の椅子に座って見える一色海岸をセレブな気分で味わえたのであった。「一色海岸」には巨大な海の家が建設中であった。「一色海岸」からの「相模湾」。引き返して、梅林の中を歩く。再び「噴井の滝」からの清き流れを見る。紅葉シーズンにまた来てみたいと感じたのであった。園路を巡ると、築山、池中に設けた小島、橋、名石などで各地の景勝などを再現しているのであった。先ほど、スイレンの花をみた場所の反対側から。「潮見亭休憩所」入口。その先に「菖蒲園」。「菖蒲園ハナショウブ・イチハツ・アヤメなど」と。開花はこれからであった。そして「葉山しおさい公園」を後にして、県道207号線・森戸海岸線を北に進む。右手に歴史を感じさせる家屋が。そして、路地を右折すると直ぐ左手にあった石仏。石仏を正面から。「葉山茶寮 六花 Ricca 」の角にあった石仏。三浦郡葉山町一色1664−1。「一色第五町内会掲示板」。「一色第五町内会こみちマップ」。路地を東に進んで行くと、石垣の塀が現れた。「佐島石こみち」と。一色にある森山神社に抜ける風情ある路地で、横須賀市湾岸で産出する佐島石の石垣が続くのであった。半世紀は経過している趣の石垣や土塁はほどよく風化し古民家にマッチしているのだ。鬱蒼とした庭とこんもりと色づく橙や琵琶の実。色褪せた表札はローマ字で綴られて、渋い味わいがあるのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.19
コメント(0)
-
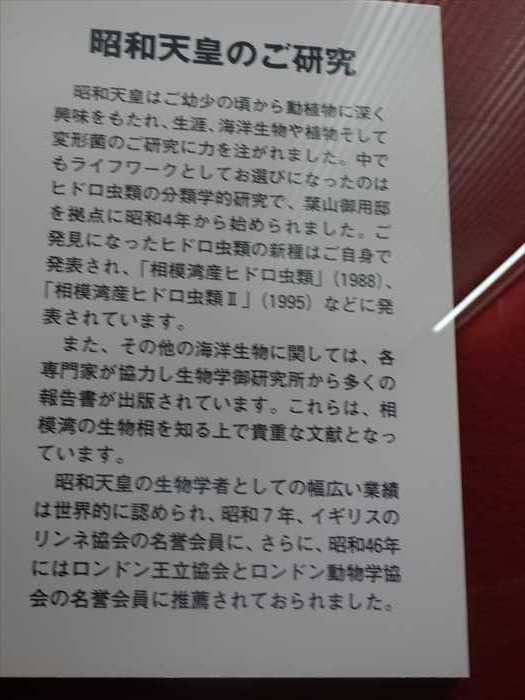
御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その8):葉山しおさい博物館(3/3)
そして「昭和天皇御下賜標本」展示コーナーへ。「昭和天皇のご研究昭和天皇はご幼少の頃から動植物に深く興味をもたれ、生涯、海洋生物や植物そして変形菌のご研究に力を注がれました。中でもライフワークとしてお選びになったのはヒドロ虫類の分類学的研究で、葉山御用邸を拠点に昭和4年から始められました。ご発見になったヒドロ虫類の新種はご自身で発表され、「相模湾産ヒドロ虫類」(1988)、「相模湾産ヒドロ虫類Ⅱ」(1995)などに発表されています。また、その他の海洋生物に関しては、各専門家が協力し生物学研究所から多くの報告書が出版されています。これらは、相模湾の生物相を知る上で貴重な文献となっています。昭和天皇の生物学者としての幅広い業績は世界的に認められ、昭和7年、イギリスのリンネ協会の名誉会員に、さらに、昭和46年にはロンドン王立協会とロンドン動物学協会の名誉会員に推薦されておられました。」「昭和天皇御下賜標本昭和天皇はご生前、葉山御用邸を拠点に相模湾の海洋生物を熱心にご採集され、それらの分類学的なご研究をされました。ここに展示されている28点の標本は葉山海岸および、その周辺における昭和天皇ご自身のご採集品で、葉山町に御下賜されたものです。資料の大半は昭和天皇のご専門であった刺胞動物のヒドロ虫類ですが、学術的に貴重なウミウシ、ウニ、ヒトデ、ホヤなどの種類も含まれています。これらの中で新種として記載された種類は次の通りです。●クラブラリア・ミカド Clavularia mikado●サガミウミウシ Cadlina sagamiensis●ハスエラタテジマウミウシ Armina magma●ニセモミジ Ctenopleura fisheri●リモニア・グロリオサ Limonia gloriosa」「御下賜標本」が並ぶ。その横には「昭和天皇のご著書」、「昭和天皇ご収集の生物に関する出版物」が。「昭和天皇のご著書」。「昭和天皇ご収集の生物に関する出版物」。「ヒドロゾアの標本を手にされる昭和天皇」と「葉山御用邸にて採集のご様子」。「昭和天皇に因む主な海洋生物」。「学習研究社 発行(1980) 天皇陛下」、「天皇陛下の生物学ご研究」相模湾、葉山の展示室。「相模湾の有毒生物」。「相模湾の有毒生物海に棲息する多くの生物がさまざまな毒をもっています。海洋生物の毒として、多くの人が思い浮かべるのはフグの仲問のもつテトロドトキシンではないでしようか。しかし、実際には特殊なタンパク質構造で作り出された毒など、未だに解明されていない毒をもつ生物か沢山います。海洋生物にとって「毒」とは、その身を守るためや、餌をとるために進化させた生態の一部であり、その毒はヒトに対して用いるものではありません。したがってこれらの生物が、積極的にヒトを襲うことは稀です。大切なことは、どの生物がどのような性質の毒をもっているのかをあらかじめ知り、万が一、出会った場合には、安全な対応がおこなえるための、正しい理解をもつことです。」「葉山の紹介神奈川県の三浦半島西北部に位置する葉山町は、東西約6.5km、南北約4km、総面積は約17km2あります。海、山の自然に恵まれ、都心に近いながらも生物が豊富で、地質学的にも興味ある所として知られています。相模湾に面した海岸線は南北に4.6km広がり、その地形は変化に富んでいます。そこへ黒潮がぶつかり、多種多様の海洋生物を産み出しています。また、美しい緑の山々に生息する動植物はとても豊かです。その間をぬって相模湾に流れ込む森戸川、下山川があり、こにも淡水産の生物が多く見られます。いっぽう、相模湾を望む景勝地としても名高く、四季を通して富士山、箱根、伊豆半島、大島、江ノ島などが眺望できるうえ、年間を通して気候が温暖なことなどが御用邸の町、別荘の町といわれるゆえんでしよう。このような素晴らしい環境の中に生活している私達にとって「葉山の自然」は貴重な財産です。大切に受けとめ、自然に親しみましょう。」「葉山町地質図」、「葉山町全図」「相模湾図」、「東京湾図」。「相模湾の漁場名」。「葉山海岸の漁場名」。ズームして。小さな島の名も判るのであった。「相模湾の貝類」「軟体動物 Mollusca貝類の仲間を学問的に軟体動物とよびます。昆虫に次ぐ種類の多い動物群で、世界に約10万種、日本には8千種類くらいいると言われています。次の7つのグループに分類されています。1 .腹足類(巻員の仲間) オキナエビス、アワビ、サザエ、タカラガイ、ミスジマイマイ、アメフラシ、など。2 .斧足類(ニ枚貝の仲問) アカガイ、アサリ、ハマグリ、ヤマトシジミ、マテガイ、タイラギ、オオジャコ、など。3 .無板類(カセミミズの仲間) カセミミズ、オオシマカセミミズ、サンゴノヒモなど。4 .単板類(ネオピリナの仲間) ネオビリナ5.多板類(ヒザラガイの仲間) オオバンヒザラガイ、ヒザラガイ、ケハダヒザラガイ、ロウソクツノガイなど6.堀足類(ツノガイの仲間) ツノガイ、ヤカドツノガイ、ミガキマルツノガイ、ロウソクツノガイなど。7.頭足類(イカ、タコ、オウムガイの仲間) スルメイカ、マダコ、アオイガイ、タコブネ、トグロ、コウイカ、オウムガイなど。」相模湾の貝類 Sea Shells of Sagami Bay南から流れ込む黒潮(暖流)と、北から親潮(寒流)の影響を受ける相模湾には、南方系と北方系の貝類が見られます。南方系の貝類にはタカラガイやイモガイの仲間などがあり、北方系ではアヤボラ、ケショウシラトリガイなどがあげられます。また、三浦半島の海岸線には多様な環境があり、潮間帯には貝類が生息するのに適しています。同時に相模湾の海底地形は、浅海から深海まで複雑なうえ、さまざまな底質の場所があり、それぞれに適応した貝類が住んでいます。特に深海には”生きた化石”として有名なオキナ工ビスなど、相模湾特有貝類が多いといえます。このように相模湾は貝類の豊富な海域で、およそ2000種が生息しているといわれています。「潮間帯の貝の分布磯の生物は水深によって住み分けをしていますが、それを知るには大潮の引き潮の時、観察するとわかります。ます露出した岩礁をま横から見ると、アラレタマキビやタマキビガイは満潮線より少し上部に住むため、最も上部で見られ、ヘソアキクボガイなどは干潮線付近、つまり潮が引いた時、水面に近い方で見られます。ここでは潮間帯の磯が左から右方向へと深くなるように表現してあり、貝類が垂直分布しているようすがわかるようになっています。」「寄生する軟体動物」。「相模湾で発見されたオキナエビスオキナ工ビス類は古生代から中生代にかけて繁栄した原始的な腹足編の一群てあり、地質時代に繁栄した種に近似した形質を殻に留める現生種は「生きている化石」とよばれている。オキナエビMikadotrochus beyrichii(Hilgendorf、1877)は旧東京大学設立の母体となる第一学区医学校から東京医学校時代に在職していたドイツ人お雇い講師のヒルケンドルフ(Franz martin hilgendorf:1839-1904)が、江ノ島の土産物屋の店先に飾られていたものを入手し、ドイツに帰国後、この標本をもとに世界で3番目のオキナ工ビス科の現生種として報告した。オキナ工ビスは、ヒルゲンドルフが新種として記載する以前に木村兼葭堂(1735-1802)による未定稿の「奇貝図譜」に「無名介 按アゲマキノー種ナラン」として図示されていたものが、最古の図示てあり、ヒルケンドルフによる記載の100年近く前に.すてに本草学的な手法で記録されていた。また.武蔵石寿(1766-1861)が1844 (弘化元)年に著したとされる「目八譜」にも「西王母 翁蛭子」として図示されている。」「長者貝の由来長者貝の由来は、帝国大学三崎臨海実験所の採集人てあった青木熊吉(1864-1940 )が採集の依頼をうけ苦心の末に採集したオキナ工ビスが、高額て買い取られた際に「長者になったようだ」と言ったことから、オキナ工ビスの別名である「長者貝」という和名が名づけられたとする逸話が通説化している。しかし実際には青木熊吉がはしめてオキナ工ビスを採集したとされる時期よりも前に.ヒルゲンドルフの後任として来日したデーデルライン(Ludwg Hinrich Philipp Döderlein: 1855-1936)らが、高額でオキナ工ビスを買い求めていたことから、江ノ島や三崎の漁師の間でオキナ工ビスはすでに「長者貝」の別名てよばれていたという記述が残っていることや.1897年に帝国大学三崎臨海実験所の箕作佳吉(1858-1909) が、標本商のオーストン(Alan Owston:1853-1915)により採集された生きたオキナ工ビスを世界に先駆け報告していることなどから、青木熊吉による「長者員」の命名とそれに関する一連の逸話の一部は、のちの時代の創作と考えられる。」「日本周辺海域から記録されたいるオキナエビス類南北に長い日本列島周辺海域からは、リュウグウオキナエビス、オキナエビス、コシダカオキナエビス、ベニオキナエビス、ゴトウオキナエビス、アケボノオキナエビス、テラマチオキナエビスの7種が記録されています。」「変化する環境と生物の消失」。「変化する環境と生物の消失相模湾沿岸域の環境は、1923 (大正12)年9月1日に発生した関東地震に伴う隆起により大きく変化した。三浦半島においては、地域によって1.0m以上の隆起が記録されている。隆起後の地形の変化の特徴の一つとして、震災以前はほとんど発達していなかった砂浜の面積が急激に増大したことがあげられる。この変化に伴い生息環境が拡大したサクラガイ類などの砂浜に棲息する生物は、個体数が一時的に増加したと推測される。震災か1世紀近くが経過した現在、三浦半島や相模湾沿岸域の砂浜は、平均すると年間3.0mm程度の速度で沈降し続けているため、再び砂浜の面積は縮小している。沈降に伴い環境も遷移し現在の相模湾沿岸域の砂浜環境の生物相は、震災直後の生物相とは異なる組成に遷移していると考えられる。ヒトの活動に伴う環境の攪乱や大規模な改変は、少なからす生物の減少の原因となりうることに疑いの余地はない。しかし、台風や暴雨、水害などの短期的な自然環境の攪乱だけでなく、断層運動に伴う大規模な環境の変化により棲息場所が縮小、消失した結果、生物の個体数が大幅に減少したり絶滅に至ることもある。地殻変動に伴い引き起こされる環境の変化も、生物相の遷移や生物の消失の原因となりうる。」様々な貝が。「三浦半島沿岸域のウミウシ類」。「三浦半島沿岸域のウミウシ類Sea slug of Sagami Bay,Miurapeninsulaこれまでウミウシの仲間は、軟体動物門腹足綱(巻貝)に含まれる後鰓亜網(もしくは後鰓目)として分類されていましたが、これら種類は、複数の系統から収斂進化したと推測さ後鰓亜網を用いない分類が用いられています。ウミウシの仲間は、頭楯目Cephalaspidea、有毅翼足目 Thecosomata.裸殻翼足目 Gymnosoma-ta、無楯目 Anaspidea、アクリッド目 Acochlidiacea、嚢舌目 Sacoglossa、ニセイワヅタブドウガイ目 Cylindrobullida、傘殻目Umbraculida、側鰓目 Pleurobranchomorpha、裸鰓目 Nudibranchiaの10目に分類されます。 ウミウシの和名は、裸鰓目に見られる体の前方にある1対の触角を、ウシの角に見立てた「海牛」が語源と考えられます。」「甲殻類の多様性甲殻類とは、甲殻亜門(Crustacea)に分類される節足動物の総称である。分子系統学的な解析の結果から、甲殻類と六脚類を併せて汎甲殻類(Pancrustacea)とし、六脚類が側系統群の甲殻類から派生したと考えられている。鞘甲亜綱(しようこうあこう Thecostraca )は固着性や寄生性の成体をもつフジツボ・カメノテ・エボシガイなどが含まれている。付属肢の形熊が、真軟甲亜綱と異なることから別の亜綱に分類されているトゲエビ亜綱(Hoplocarida)は、ロ脚目(シャコ目)が含まれている。真軟甲亜綱(Eumalacostraca)は、工ビ・ヤドカリ・カニをはじめ等脚目・端脚目・タナイス目・クーマ目などを含む一大グループである。」「タカアシガニ」に見えるが?文字の読みは「じん」と。「蟳(じん)」で「ガザミ(蝤蛑、虎蟳)」とのこと。上の蟹の写真は蟳(じん)・ガザミとは甲羅の大きさと脚の長さのバランスが違うようであるが。「訓蒙図彙 中村惕斎 寛文(1666)年成立」「甲殻亜門 Subphylum Crustacea甲殻亜門は、工ビ・カニ・ヤドカリなどに代表される節足動物門のグループである。主に海域に適応し、等脚目の一部がわずかに陸域に適応している。現生種は介形類(Osracoda)・ヒゲエビ類(Mystacocarida)、鰓尾類(Branchiura)シタムシ類(pentastomida)・カイアシ類(copepoda)・ヒメヤドリエビ類(Tantulocarida)・鞘甲類(Thecostraca)・軟甲類(Malacostraca)・鰓脚類(Branchiopoda)・カシラエビ類(Cephalocarida)・ムカデ工ビ類(Remipedia)11群に分類される。一般的に甲殻類とよばれる工ビやカニは、軟甲類に含まれている。」「イバラガニモドキ」(左)と「イガグリガニ」(右)。「タイマイ」、「セクロウミヘビ」、「マダラウミヘビ」。「相模湾から記録された爬虫類これまでに相模湾からは、コブラ科(ウミヘビ科)5種、ウミガメ科3種、オオザメ科1種の合計9種の爬虫類が記録されています。海域に棲息するヘビ類のほとんどは沿岸域のみを生息域とするのに対して、ウミガメ類は、いずれの種でも産卵・孵化以外は外洋を棲息域とします。爬虫類は、変温動物であることから、水温が低下する冬季を中心に活動が鈍くなり、海岸に打ち上げられることがあります。」「タイマイ」に近づいて。そして漁具展示コーナーへ。「葉山の漁業Fishery of Hayama相模湾に面した葉山には、刺し網漁、シラス船曳き網漁,見突き漁、もぐり漁、ワカメどり漁、ヒジキどり漁、ワカメの海面養殖などの漁業があります。古くは、定置網漁、地曳き網漁、手繰網漁、延縄(はえなわ)漁などが行われていましたが、現在では釣り船を主体とする漁業者が大半を占め、漁を専門とする漁業者が少なくなりました。ここには、かって葉山で使用されていた漁具を中心に展示してあります。」「万祝(まいわい・まんいわい)」「万祝(まいわい・まんいわい)大漁の時、船主が漁師に贈り物として配ったお揃いの「はんてん」のような着物。江戸時代中期から東北、関東の漁師のあいだで着用した晴れ着で、これを着て神社を参拝することが誇りだったと言われています。これは、葉山で使われたものですが、現在ではこの風習は残っていません。」奥には「生簀」が2基。右手に「櫓」、左に「ガラス浮き玉」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.18
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その7):葉山しおさい博物館(2/3)
葉山しおさい博物館展示室内から「葉山しおさい公園」の「日本庭園」を見る。葉山町所蔵 複製画展の展示室を訪ねた。葉山町所蔵複製画展~世界の名画の複製画展示~令和6年5月28日(火) ~ 6月23日(日)場所 葉山しおさい博物館 くつろぎゾーン時間 午前8時3 0分から午後5時まで ※入園は午後4時3 0分まで 休館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)観覧料 無料(ただし、しおさい公園人園料が必要です。) ※入園料 高校生以上: 3 0 0円 小中学生: 1 5 0円場所 葉山町立図書館 1階展示スペース時間 午前9時00分から午後6時まで休館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)観覧料 無料 間い合わせ 教育委員会生涯学習課」「リュクサンブール公園」 アンリー・ルソー 複製画「サンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂」 エドモンド・クロス 複製画「ジプシーのキャラバン」 フィンセント・ファン・ゴッホ 複製画。「ジプシーのキャラバン」 フィンセント・ファン・ゴッホ 複製画「鞭をもつ少女」 ビエール=オーギュスト・ルノアール 複製画展示室の光景。複製画展示室から日本庭園を見る。入口受付近くに展示されていた「ケンスレーダイオウグソクムシ」と「オオグソクムシ」。「ケンスレーダイオウグソクムシ」。「オオグソクムシ」。展示室の入口方向を振り返る。地下階にあった展示室(葉山の海洋生物)へ向かう。階段を下る。葉山 森戸神社裏より富士を望む。地階に展示されていた漁具類を見る。「葉山沖の深海」。「シロウリガイ類の化石」。「シロウリガイ類の化石シロウリガイ類は、相模湾の水深1000m付近をはじめとする深海の海洋プレート境界域に優占してみられる大型のニ枚貝の一種です。この化石は、逗子市池子に分布する三浦層群池子層(440 ~ 280万年前)より産出したものです。 横浜防衛施設局:提供」写真では解りにくいが。「シロウリガイの生態相模弯初島沖水深900 ~ 1200mの海底には、高密度でシロウリガイ類が生息しています。シロウリガイ類は、垂直に海底に直立し、海底下に足を嵳し込み、硫化水素(硫化水素イオン)を体内に取り込んでいます。取り込まれた硫化水素は、著しく肥大化した鰓に運ばれ、鰓の上皮細胞内部に共生している硫黄酸化細菌が、この硫化水素と水管から取り込んだニ酸化炭素を用い有機物を生成します。シロウリガイ類は、この有機物を栄養として利用していると考えられています。また、このような生態を持っため、シロウリガイ類の消化器官は退化しています。地球上に知られる生態系のほとんどは太陽の光を始点する光合成の食物連鎖のもとに成り立っていますが、シロウリガイ類をはじめとする深海の海洋プレート境界域に生息する化学合成生物は地球内部からしみだす化学物質を始点として化学合成細菌が生産者となる化学合成生態系とよばれる特殊な生態系を作り出しています。」「相模湾の深海生物カイロウドウケツモドキ 海線動物門相模満中央部の沖ノ山堆水深845mて観察されたカイメンの一種です。ガラス繊維の骨片の束で海底に固着し、珪質の骨片をもっことから「ガラス海綿」ともよばれています。ハエジゴイソギンチャク 刺胞動物門相模湾西域の小田原沖水深648mで観察されたイソギンチャクの一種です。口盤ががま口のように折れ曲がる特異な形態をしています。水深2,000m付近からも知られ、本種をクラゲイソギンチャクとする報告もあります。オオ工ンコウガニ 節足動物門相模湾中央部の相模海丘水深1,208mで観察された甲幅が20cmに達する大型のカニ類です。相模湾の水深300 ~1,000m付近に生息しています。オオ工ンコウガニの近縁種は、マルズワイガニの通称名で缶詰めなどの原材料として使われることがあります。ユメナマコ 棘皮動物門相模湾西域に位置する初島南東沖の水深1,136mで観察されたナマコの一種です。膜で連結された触手を使い、海底から数mの高さまで浮遊・遊泳します。オオグチボヤ 脊索動物門伊豆大島北方沖の門脇海丘水深1009mで観察されたホヤの一種です。ロのように見える横に裂けた大きな入水孔をもち、流れに向かい大きく開くことで、流れで運ばれる工ビなどを捕食します。」。「相模湾の深海と化学合成生物群集相模湾は、フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈みこむ境界に位置することから複雑な海底地形をもちます。相模トラフとよはれる水深1000mを越える相模湾中央部の海底谷をはさんで、伊豆半島沿岸は陸から急激に水深が深くなるのに対して、三浦半島に沿岸には広い陸棚があり、ゆるやかに水深が深くなります。相模湾初島沖の深海には、日本近海ではじめて観察されたシロウリガイ類などから構成される化学合生物群集が生息しています。」シロウリガイ類。オオエンコウガニ。「相模湾沿岸域の魚類これまでに相模湾からは、45目249科1517種類の魚類が記録されています。これらの種類を科別の出現種数で比較するとハゼ科が最も多く109種類(全体の7. 2 % )になり,次いでペラ科88種( 5. 8 % ) 、フサカサゴ科53種( 2. 9 % ) 、スズメダイ科44種( 2.9 % ) 、チョウチョウウオ科35種( 2. 3 % )の順になります。相模湾から記録されるスズメダイ科やチョウチョウウオ科の種類には、冬季の水温の低下に耐えられず姿を消す種類が含まれています。■相模湾と黒潮日本列島の太平洋岸を流れる黒潮は、いくつかの安定した流路があります。それぞれ黒潮非大蛇行接岸流路(B)、黒潮非大蛇行離岸流路(C)黒潮大蛇行(A)とよばれています。黒潮が流れるがる位置により三宅島や八丈島の潮位は変化し、この影響は相模湾内にも及びます。」水槽で飼育している魚は「葉山町沿岸域に生息する魚類」。近づいて。シマスズメダイ。サザナミフグ。石鯛(クチグロ)。「葉山海岸の魚類」。「葉山海岸の魚類Fishes from the coast of Hayama葉山海岸の地形は実に変化に富んでいます。砂浜、岩礁、転石地、河口などが連続し、浅海から深海までの海底地形も様々な底質で広がっています。ここへ南からの黒潮暖流が流れ込み、多彩な環境に適応した多くの魚類が生息しています。また、稚魚が生息するために必要なアマモ場が各所に形成され、カジメの群落など海藻が繁茂している海域も多く、魚が餌をとったり、隠れる場所が十分にあることも魚類にとって住みやすい条件のひとつです。このコーナーでは葉山海岸で見られる「魚類のすみ場所の違い」をわかりやすく展示してあります。」「やや深い海」、「深い海」に近づいて。「タカアシガニ」。「タカアシガニMacrocheira kaempferi クモガニ科 城ヶ島沖相模湾の水深100m~300m付近に生息する世界一はさみ脚の長い節足動物です。はさみ脚長く、大きな個体がオスで、はさみ脚が短く小さい個体がメスです。」深海生物の液浸標本が並ぶ展示コーナー。中央に1m以上ある「オニイソメの標本」。巨大ゴカイ的なヤツ。左下に芸術的なタコの液浸標本。マンボウ。ラブカ。「ラブカカグラザメ目ラブカ科Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884ラブカ(羅鱶)は、1884年にアメリカの生物学者ガーマン(Samuel Garman)が本州で採集された 1.5 mのメスの個体をもとに新種として報告した原始的な形態をもつサメの一種です。本種は、相模湾をはじめ、太平洋・大西洋の水深50 ~ 1570 mに広く分布することが知られています。ラブカは、胎生で、3.5年の妊娠期間を経て体長40 ~ 60 cmの仔を産みます。雌雄で体長が異なりオスは90 ~ 120 cm,メスは130 ~ 150cmで性成熟し、最大体長はオスで1.7 m、メスで2.0 mに達することが知られています。」「生物の分類」コーナー。「生物の分類これまでに地球上からは,およそ1 , 000万種の生物が記録されています。1700年代まで、これらの生物は「動物」と「植物」の2つに分けられていました。1800年代には微生物の発見に伴い、原生生物が加わり、生物は3つの世界に分類されるようになりました。1970年代以降は、原核生物はモネラ界に、真核生物は植物界,動物界.菌界,原生生物界の4つに分類する分類体系が主に使われてきました。2000年代以降、遺伝子の情報に基づく分類方法が取り入れられるようになり、これまで「原生生物界」にまとめられていた生物は、多様な真核生物の寄せ集めであることが判明し, 6つのスーパーグループに分ける分類体系が提唱されています。」相模湾に生息する海藻類。「相模湾や三浦半島に因む種名」「相模湾に因んで名がつけられた海洋生物」。「相模湾や三浦半島に因む種名相模湾は、日本の海洋生物学の発祥の地とされている。1877 (明治10)年に帝国大学理学部動物学教室の初代教授として来日したE. S、モース(1838 -1925 )により、一時的な施設であるが、江ノ島に東洋で初の臨海実験所が設けられ海洋生物の採集や研究が行われた。その後、帝国大学三崎臨海実験所が1886年(明治17)年に三浦市三崎に設立された。三崎臨海実験所の設立以前には、帝国大学医学部のお雇い教師として来日したF.ヒルゲンドルフ(1838-1904)やL. H. P.デーデルライン(1855-1936)により相模湾の海洋生物の採集調査が行われ.相模湾には、珍しい深海生物などが多く棲息している海域として海外に紹介されていた。昭和天皇により葉山御用邸を拠点とした生物学御研究所の採集調査は.相模湾東部海域を中心に、およそ60年にわたり行なわれた。この調査は、網羅的な生物相の採集調査を同一の海域で長期的に行うという世界的に見ても稀な研究である。これらの研究成果として、相模湾をタイプ産地(基準となるタイブ標本の採集された場所)として記載された生物の中には、採集地である「相模」、「葉山」、「三崎」という地名だけでなく、小さな岩礁である「鮫島」、「名島」、「亀城礁」など、より具体的な採集地に因んで名づけられた種名が少なくない。また、三浦半島を形成する地層中より採集された標本をもとに記載された化石には「三浦」など採集地に因む種名がある。」相模湾や三浦半島に因む名前の生物。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.17
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その6): 葉山しおさい公園・葉山しおさい博物館(1/3)
県道207号線・森戸海岸線を北に進むと左手にあったのが「葉山しおさい公園」の正門前広場。「葉山町指定史跡 大正天皇崩御・昭和天皇継承の地指定 昭和六十一年四月二十九日 指定第三十八号所在地 葉山町一色ニ一ニ三の一葉山御用邸付属邸の歴史この葉山しおさい公園は、葉山御用邸付属邸の跡地で、昭和62(1987)年6月3日開園し、面積は18009.28平方メートル(約5500坪)ある。ここはもと岩倉具定侯爵・金子堅太郎伯爵・井上毅子爵の各別荘を、大正6(1917)年7月にお買い上げになり、澄宮(すみのみや・現三笠宮)邸として大正8(1919)年6月に竣工されたものである。大正天皇崩御大正天皇は、葉山御用邸をこよなく愛され、最後の行幸は大正15(1926)年8月10日、付属邸で御病気ご療養のためであった。当時、たまたま本邸が関東大震災で損傷し、再建中であったため付属邸へ入られた。陛下には以来同邸においてご療養につとめられたが、同年12月25日、午前1時25分、遂に崩御(逝去)されたのである。時に御年48歳であった。昭和天皇皇位継承大正天皇が崩御(逝去)され、悲しみの中旧皇室典範第10条の定めに従って、皇太子殿下(後の昭和天皇)は直ちに葉山御用邸において天皇の位におつきになられた。新天皇陛下は、まず登極令(旧皇室令)第1条によって践祚(せんそ・皇位を受け継ぐこと)の式を行うため、剣璽渡御(けんじとぎょ)の儀が12月25日午前3時15分より葉山御用邸付属邸において執り行われた。また、宮城(皇居)賢所において践祚の儀式が同じ時刻に行われた。第124代の宝祚(皇位)をつがれた新天皇陛下は、徳川侍従長、奈良侍従武官長、一木宮相以下を従え、伊藤式部長官のご先導により静かに東京に向かわれた。時に御歳26歳。尚、付属邸における剣璽渡御の儀式は皇族、政府関係者列席のもと厳かに行われた。儀式における各役割は宝剣を捧持するもの、原侍従、神璽を捧持するもの、松浦侍従、御璽国璽を捧持するもの、松井内大臣秘書官がその任に当たった。践祚の行われた部屋は昭和56(1981)年11月再建された御用邸の中へ移設されている。 平成6年3月27日 葉山町・葉山町教育委員会」「葉山しおさい公園」正門。「葉山しおさい公園入園料一般 大人 三百円 小人 百五十円(小中学生)団体(ニ十名様以上) 大人 ニ百五十円 小人 百円開園時間 午前八時三十分から 午後五時まで休園日 月曜日 祝日の翌日 年末年始」「葉山しおさい公園」。「葉山しおさい公園 案内図」。受付・管理事務所で入園券を購入。「葉山しおさい公園平面図」。「葉山しおさい博物館」に向かって進む。前方に石碑が現れた。「今上陛下即位記念 平成ニ年十一月十二日」碑。現上皇陛下のこと。そして「葉山しおさい博物館」を正面から。旧御用邸付属邸の御車寄せを移築したものである と。「葉山しおさい博物館」。「葉山町所蔵複製画展~世界の名画の複製画展示~令和6年5月28日(火) ~ 6月23日(日)場所 葉山しおさい博物館 くつろぎゾーン時間 午前8時3 0分から午後5時まで ※入園は午後4時3 0分まで休館日 6月3日(月)、1 0日(月)、1 7日(月)観覧料 無料(ただし、しおさい公園人園料が必要です。) ※人園料 高校生以上: 3 0 0円 小中学生:1 3 0円場所 葉山町立図書館 1階展示スペース時間 午前9時0 0分から午後6時まで体館日 6月3日(月) ~ 1 2日(水)、1 7日(月)観覧料 無料 問い合わせ 教育委員会生涯学習課」「入館無料」と。「ごあいさつようこそいらっしゃいました。この「葉山しおさい博物館」は昭和62年(1987) 6月に開館いたしました。館外の敷地(葉山しおさい公園)は葉山御用邸付属邸の跡地で、大正天皇崩御、昭和天皇皇位継承の地で、いわば昭和発祥の地として知られる由緒ある所です。館内の常設展示は葉山海岸を中心に、「相模湾の海の生物」をテーマにして構成してみました。とりわけ昭和天皇の御下賜標本や珍しい深海生物の展示は当館ならではのものです。生物の宝庫として世界的に知られる身近な相模湾を認識していただき、自然に親しんでいただければ幸いに存じます。 葉山しおさい博物館」受付カウンター。正面には、ヨットが展示されていた。移動して。「上皇陛下御下賜ヨット」。御下賜品(ごかしひん)とは、皇室や宮家から贈られた品物のこと。「案内パネル」が2基。「オリンピア・ヨーレ全長 5m最大幅 1m57cmマストの高さ 6m85cm一人乗り ディンギー丸みを帯びた優美な船型は、美しく典雅な雰囲気を醸し出していると言われている。」「御下賜ヨット オリンピア・ヨーレこのヨットは昭和25年7月、日本ヨット協会(現日本セーリンク連盟)が当時皇太子殿下でいらした上皇陛下に献上した「オリンビア・ヨーレ」という級式のヨットてす。ちょうど沼津御用邸附属邸にこ滞在中の皇太子殿下の元に届けられました。上皇陛下が皇太子殿下時代に沼津でお乗りになりました後、沼津御用邸の廃止に伴い、このヨットは葉山御用邸に移されました。上皇陛下は葉山の海岸においても当時皇太子妃殿下でいらした上皇后陛下とご一緒にお乗りになり、ヨットは葉山御用邸の艇庫て大切に保管されておりました。「オリンビア・ヨーレ」という級式のヨットは昭和9年ドイツて生まれ、昭和11年のベルリンオリンピックてヨット競技の一種目として採用されました。この時、日本はヨット競技としては初めて「オリンピア・ヨーレ」競技に参加しましたが、その後のオリンビックではこの級式のヨットが競技種目として採用されたことはありませんでした。平成19年3月に上皇陛下は日本セーリング連盟にこ相談の上、この「オリンビア・ヨーレ」を葉山町に御下賜になさることとなさいました。葉山町てはその後、ヨット発祥地てある葉山港の港湾管理事務所に保管・展示しておりましたが、平成22年3月に元葉山御用邸附属邸跡地の「葉山しおさい公園」に移設いたしました。 葉山町」館内には葉山周辺の海に生息する魚類、貝類、甲殻類、海藻類などが展示されていた。中でも昭和天皇御下賜標本や深海生物の展示は、当館ならではのもの。・海洋生物の系統分類・相模湾の珍しい大型生物・相模湾で使われていた漁具等も展示されていた。「無生物の形---石の造形藝術---生物(せいぶつ)とは、細胞という単位からなり、自己増殖などの生命活動を行うものと定義される。これにして無生物(むせいぶつ)とは.生命活動を行わない石や水などの物質を示す。生物の形は遺伝子により支配され、自らの意思により形成されるのに対して.無生物の形は、物理的な要因で形成される。同じ形でも、生物と無生物では全く異なる形質形成の過程を辿っている。ここに展示した「石」は、無生物である。意思のない無生物が作りだす偶然の形には不思議な魅力がある。」左から二水石膏、しのぶ石、桜石。ニ水石膏(Gypsum:ギプサム)硫酸カルシウムCaSO4を主成分とする鉱物。骨折などの患部が動かないように外からの固定する創傷処置であるギブスの語源である。しのぶ石(Dendrite:樹枝状晶)岩石の間隙に二酸化マンガンが樹枝状に結晶化したしのぶ石は、自然現象でできるフラクタルの偽化石である。かってはシダ植物(シノブは、シダ植物の古名である)の化石と考えられたことが名称の由来である。桜石(Cordierite:コーディエライト)菫青石は、Mg2Al3 (AlSi5O18)の化学組成をもつケイ酸塩鉱物である。桜石は菫青石が熱水変質により雲母化したものである。断面を桜の花の紋様に見立てた桜石の名称は江戸時代にすでに名づけられていた。「黄鉄鉱(Pyrite:パイライト)化学組成はFeS2。鉄と硫黄からなる。一般的には六面体の結晶形を示すが、八面体や十二面体などもみられる。強い衝撃を与えると火花を散らすことからギリシャ語の「火」を意味するpyrに由来する。かっては硫酸の原料として採掘されていた。鉄礬柘榴石(Almandine:アルマンディン)十二面体あるいは偏菱二十四面体などの自形結品を作り、Fe3gAl2(Si04)3で表される。変成岩、火成岩、花崗岩ペグマタイトでもっともよく見られる。」「子産石(Concretion:コンクリーション)生物起源の炭酸塩コンクリーションは、有機物中の炭素と海水中のカルシウムなどが結合し、短時間で方解石などの鉱物が沈殿して形成される。子産石は,葉山層群中から産出するコンクリーションである。かつては安産のお守りとされた。」「へそ石(Nodule:ノジュール)へそ石は、深海底に棲息していた生物の巣穴を中心に砕屑粒子の隙間が鉱物で充填されて形成された生痕化石と考えられる。へそ石の名称は,中心のくぼみを臍になぞらえてつけられた。江戸時代から知られる三浦半島の奇石のひとつである。」「Carcharocles megalodon(Agassiz,1843 )」。「Carcharocles megalodon(Agassiz,1843 ) カルカロクレス メガロドン ネズミザメ目 オトドゥス科 Emma Longhorn氏 寄贈Carcharocles megalodonは、全長16 mに達したと推定されているサメの絶滅種です。本種は、日本をはじめアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカなどの前期中新世(1800万年前)から鮮新世末(300万年前)の地層からの産出が報告されています。近代科学が発達する前の江戸時代の日本では、この化石の正体がわからず「天狗の爪石」とよばれていた時代もありました。また、中世のヨーロッパでは「舌石(Glssopetri)」とよばれていました。本化石は, 2007年にEmma Longhorn氏により葉山一色海岸に打ち上げられた状態で採集された資料であり、産出層は不明ですが、逗子層(600万年前)の基底部にあたる礫岩層からの産出と推測されています。」「オカダンゴムシ」と「ハマダンゴムシ」。「身近な外来生物オカダンゴムシオカダンゴムシ(ダンゴムシ)Armadillidium vulgareは、1943 (昭和18)年に岩本嘉兵衛によりはじめて日本列島から記録された、明治時代以前に園芸植物と共にヨーロッパから日本に移入したと考えられる外来生物です。オカダンゴムシが日本に移入したばかりの明治時代、「ダンゴムシ」の和名は、海浜域に生息する在来種のハマダンゴムシTylos granuliferusの和名として用いられ、現在オカダンゴムシと呼ばれている種類は、「テマリムシ(手毬虫)」と呼ばれていました。戦後、オカダンゴムシは急速に分布を広げ、現在では、最も身近な環境で見られる生き物のひとつとなっています。」正面に出土した丸木舟が展示されていた。正面に出土した丸木舟。「古代~中世の丸木舟(今から約1000年前)」と。「丸木舟出土当時の様子」(左)。「丸木舟出土当時の様子」(右)。「葉山町堀内発見の丸木舟昭和42年3月、堀内児童遊園(堀内510番地)に防火貯水槽工事の際、地表から約250センチの深さから発見されたものです。「丸木舟」は、側壁は残っておらず底板のみですが、残存長278センチ、最大幅57センチを測ります。表面にはノミで加工した跡が残っているほか、削りやすくするために表面を焼いた跡がよくわかります。材質はクスノキと判定されています。丸木舟が製作された年代については、放射性炭素年代測定法によリ、10世紀初頭から12世紀初頭(平安時代: BP940±104年)と測定されています。」出土した「丸木舟の底部」。「縄文時代の葉山」と「国指定史跡 長柄桜山古墳群」案内板。「縄文時代の葉山最初に葉山に人類の足跡をうかがえるようになるのは、縄文時代になってからです。1万年以上続く縄文時代は、自然環境の変化に合わせながら、狩蝋や漁撈、植物性食料の採取、また限定的ではありますが、植物の栽培や管理も行うなど、多様な生業が営まれた時代です。葉山町内では、現在繩文時代の遺跡が5か所知られています.馬の背山遺跡(木古庭)は標高約160mの丘陵上にある遺跡で、昭和32年に赤星直忠博士が担当者となって発掘調在が行われました。遺跡は5つの地点に分かれており、りんご箱一個程度の遺物が出土しています。遺物は、縄文時代早期や前期の土器が出上したほか、石鏃などの石器が見つかっています。見つかった土器の時期は断続的で量も少ないことや、住居跡などの遺構が見つかっていないことから、定住的な生活が営まれていたとは考えにくいところがあります。おそらく狩猟や堅果類などの植物性食料の採集のために、湧水の豊富な当地が一時的なキャンプ地として適していたのではないかと思われます。同様の遺跡として、正吟遺跡(上山口)や間門遺跡(上山口)があります。縄文海進(じようもんかいしん)それまで寒冷だった気候は約1万年前から温暖になり、海水面は急速に上昇していきます。約6千5百年前には現在の海水面よりも高くなり、沿岸部の葉山の低地は海の中にありました。約5千5百年前に海水面の高さは4 ~ 5mほどに達してピークを迎えます。これを縄文海進と呼んでいます。縄文時代の自然環境縄文時代の葉山の自然環境はどのようなものだったのでしようか。約9千~ 6千7百年前の三浦半島の陸上では、森や林を作る樹木が、それまで生育していたコナラやニレ、ケヤキなどを主体とする落葉広葉樹林から、シイノキ、エノキ、スギなどを主体とする照葉樹林に種類が変わります。生育する植物の種類が変わった結果、そこに棲む動物の種類が変わった結果、そこに棲む動物の種組成も変化したと考えられています。海域ては、縄文海進とよばれる世界規模の海水面の上昇がおこり、それまで陸地だったところにまで海水が浸人することにより、「おぼれ谷」とよばれる泥の干潟が形成されました。この新たに形成された環境には、ハイガイやシオヤガイなど、現在の相模湾沿岸や関東地方の海域には棲息していない特殊な軟体動物が棲息していたことが分っています。森戸川沿いでは長柄交差点近くの海抜3 m付近から、下山川沿いでは町立ー色小学校近くの海抜8m付近から、泥干潟に棲息する軟体動物の化石が記録されています。したがって、縄文海進の最高期には、現在の森戸川や下山川の流域に沿って海が陸域に浸入し、この周辺域が当時の波うちぎわ(波打ち際)付近だったと雅測されます。この時期に形成された湾は、狄い湾口をもつ入り組んだ内湾であり、現在の一色海岸や森戸海岸のような開けた砂浜の環境ではなく、ハイガイやオキシジミ.イボウミニナなどの棲息する泥干潟の環境であったと考えられます。特に内湾的な環境に依存度の高いハイガイやシオヤガイは、その後、海退期になり海水面が低下すると、棲息地となる泥干潟が消失したため、相模湾沿岸域から姿を消してしまったと考えられます。」約6千5百年前(縄文時代)の葉山の海岸線と遺跡 ※松島(1975)を参考に作成。シオヤガイ、イボウミニナ、オキシジミ、ハイガイ。下の列にハイガイ、シオヤガイ、コゲツノブエ。「三浦半島の今からおよそ6500~5500年前の縄文時代に相当する地層中からは、現在の相模湾沿岸域には生息しない生物の化石が採集されます。およそ6000年前を中心に世界的に海水面が上昇する縄文海進期には現在よりも最大で4mほど海水面が高くなり、入り組んだ谷戸の奥にまで海が入り込み、「溺れ谷」とよばれる泥干潟の環境が形成されていたと考えられています。このような場所にハイガイ、シラオガイ、シオヤガイなどに代表される現在の相模湾沿岸には生息しない南の海域に生息する種類が優占して生息していたことが化石の記録から報告されています。」「国指定史跡 長柄桜山古墳群長柄桜山占墳群は、平成11年(1999年) 3月に、逗子市と葉山町の境にある丘の上で新たに発見されました。2基とも4世紀代の前方後円墳で、現存している神奈川県内の古墳では最大級の規模を誇ります。第1号墳古墳時代前期後葉( 4世紀後葉)全長 91.3m 後円部径 52.4m くびれ部幅 24. 2m墳丘は、後円部三段、前方部二段につくられており、後円部と前方部の高低差が大きい前期古墳の特徴をもっています。後円部は左右非対称の形をしており、現在の逗子市街地が広がる田越川流域や逗子湾から望むことができる西側を整った形に作り出しています。後円部の中央からは、長さ約7m、幅約1. 6mの落ち込みが確認されました。地下に納められた木棺が長い歳月をへて腐食してつぶれたため、古墳の表面に落ち込んだ陥没坑です。部分的な断ち割り調査により、この陥没坑の真下から粘土槨(木棺を粘土で覆った構造の埋葬施設)が1基存在することを確認しています。古墳からは埴輪がたくさん出土しています。後円部を中心に立て並べられていたものと考えられます。出土した埴輪には、三角形の透かし孔が開けられた円筒埴輪や底がない壺形埴輪がみつかっています。また葬送祭祀に使われた壺や高坏などの土器も見つかっています。第2号墳 古墳時代前期後(4世紀後葉)全長 88m 後円部径54m くびれ部幅 32m第1号墳から西へ500mほど向かったところにある前方後円墳です。後円部と前方部の高低差があまりなく、前方部は第1号墳に比べると、幅が広くなっています。古墳の表面には砂岩や丘陵岩盤の泥岩を用いた装飾(葺石)が施されていました。第2号墳からも円筒埴輪と壺形埴輸が見つかっています。前方部から西側には、相模湾に浮かぶ江の島をはじめ、天気が良けれは大山や富士山を一望することができます。古墳群築造の背景古墳群周辺の同時期の遺跡は、田越川中流域に集中して見つかっています。なかでも持田遺跡で石釧と呼ばれる腕輪形石製品が出土しているほか、池子遺跡群の竪穴住居跡からは銅製の鏡や鏃などが出土しており、これらは一般のムラから出上することが稀な、外から運はれてきたものです。田越川に沿って進むと、相模湾ー東京湾間を最短で往来できることから、当時この地域は物資流通の拠点であったと考えられます。また、古墳群より南側の三浦半島相模湾沿岸には、点々とムラが見つかっており、海上交通も重要な役割を果たしたと考えられます。長柄桜山古墳群が築かれたこの地域は、当時の太平洋沿岸における物資流通の重要な拠点であったと考えられ、往来する人々が見上げる位置にある2基の古墳は、ランドマークとしての役割を果たしたと考えられています。」「高坏(たかつき)(食器や祀りの道具)」長柄桜山古墳群から出土した埴輪。長柄桜山古墳群の1号墳と2号墳。長柄桜山古墳群と同時代の遺跡分布図。「葉山しおさい公園」ポスター。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.16
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その5): 臨御橋(りんぎょばし)~小磯の鼻~一色海岸~葉山御用邸前~恩光碑
「下山口 神明社」を後にして、次の目的地の、「葉山御用邸」に裏にある「大浜海岸」を目指す。国道134号を南に進み、振り返ると、「葉山御用邸」の塀と巨木の植栽が正面に。ズームして。神奈川県三浦郡葉山町にあるこの「葉山御用邸」は、明治時代の1894年(明治27年)、近代のお雇い外国人でドイツの医学者:エルヴィン・フォン・ベルツ博士の勧めにより、比較的温暖で風光明媚な葉山の地に『葉山御用邸』を着工。若かりし嘉仁親王(後の大正天皇)の保養地として用いられ、1926年(大正15年)の最期もこの地で迎えられました。1971年(昭和46年)に建物が焼失(葉山御用邸放火事件)したが、1981年(昭和56年)に再建された。相模湾に面する海岸沿いにあるため景色がよく、江の島や湘南、天気が良いときは富士山も眺めることができます。すぐ近くに葉山公園があり、憩いの場になっています。上皇陛下・上皇后美智子さまは、葉山御用邸裏の「小磯の鼻」をご散策されるのがお好きとのこと。「葉山御用邸」の広さ(土地)は95,796.46m2 建物(延べ面積)は3,625.70m2とのこと。土地は約▢310m、建物は▢60mということになる。この「葉山御用邸」前の国道134号は「葉山公園通り」と呼ばれているのだ。「葉山御用邸」の塀に沿って歩き「大浜海岸」に出る。右手に朱色に塗られた欄干の橋を見る。欄干に近づかないように仮設設備のある橋を渡る。「下山川」の河口と相模湾を望む。こちらは「葉山御用邸」側。臨御橋の改修工事用の為にクラウドファンディングが行われ、目標金額の2億円を達成したが、臨御橋の改修の実施には、橋の状態調査、工法の選定、原材料費や労務単価等の高騰の影響により、その準備に当初の想定を上回る時間と費用を要する見込みであり、見直しを実施中であると。再び「下山川」の上流方向を。「臨御橋(りんぎょばし)」と。臨御橋は、御用邸の中を流れる2級河川である下山川の河口付近に設置されている長さ33メートル、幅4メートルのコンクリート製の橋です。欄干が赤く塗られていることから、地元では「赤橋」とも呼ばれ、一色海岸と長者ヶ崎・大浜海岸を結ぶ連絡橋として町民や観光客の散策に使われています。現在の形になる前は木造の橋として設置されていたそうですが、老朽化や台風等による破損を繰り返し、昭和43年に葉山町施工のコンクリート橋に改修され、現在に至ります と。潮位があがり2つに分かれた「長者ヶ崎」を振り返る。「小磯の鼻」。「葉山御用邸」の裏にあり、海に向かってこんもり芝生の丘になっている場所。大浜海岸と一色海岸を隔てるように海に伸びた抜群のロケーションで、ピクニックをしたりヨガをしてみるのもおすすめの場所 と。岬の先端は葉山スコリアと呼ばれる岩場になっていて、磯遊びもできる場所。皇宮警護官の小屋もあった。「小磯の鼻」の岩場の上に朱の鳥居と石祠があった。海の守り神が祀られているのであろう。「一色の洗濯岩」を見る。お立ち台の先が「一色の洗濯岩」の名勝になる。地質は、新第三紀の葉山層群(三浦半島で最も古い地層)で砂泥互層(一部はスコリア)となっている。侵食の違いで洗濯板のように見えることで「洗濯岩」とも言われている。「小磯の鼻」から「葉山御用邸」を。警備用の皇宮警護官の姿も。ご苦労さまです。「小磯の鼻」の岩場を振り返る。「一色海岸小磯の防波堤」の先端から。「一色海岸」。三浦郡葉山町一色にある「ライオンズマンション葉山マリンビュー」をズームして、天気が良ければ、「ライオンズマンション葉山マリンビュー」の後方に「富士山」の勇姿が見えるのだが。写真はネットから。そして「葉山御用邸」の北側の「しおかぜこみち」を国道134号に向かって戻る。この附近はコンリートの壁が続いていた。そしてその先にはツタ(蔦)に覆われた壁が続いていた。そいて、国道134号と交わる県道207号線まで.戻り「葉山御用邸前」交差点に向かって進む。右手にあったのが、「葉山御用邸」の北側の通用門。「皇宮護衛官募集」ポスター。「募集 皇宮警察」ポスター。警察庁の付属機関である皇宮警察本部に所属する国家公務員として、皇居や御用地を守る「警護」、皇室の方々を守る「護衛」、これらの活動を支える「警務」の三部門があるとネットから。道路の左手にあったのが「神奈川県葉山警察署」。三浦郡葉山町一色2034。前方に大きな交差点が。この交差点で、県道207号線が国道134号に繋がっているのだ。「葉山御用邸前」と。横断歩道を渡り、「葉山御用邸正門」を見る。三浦郡葉山町一色2038。そしてその先にあった「恩光碑」。三浦郡葉山町下山口1439。「恩光碑」を見上げる。明治・大正・昭和時代の皇太子殿下の葉山行啓がなされたことを奉祝して葉山町が建立した「恩光碑」。「この碑は、明治・大正・昭和時代の皇太子殿下の葉山行啓を奉祝して、昭和十一年に葉山町が建立したものです。中央剣型塔で「恩光碑」の碑文は枢密院顧問官金子堅太郎の揮毫、設計は彫刻家青柳利男の謹作、撰文は吉田増蔵博士で、その揮毫は松平直亮伯爵によるものです。」この鳥は鶴??「我葉山町 明治以来亘千三朝荐沗 皇太子殿下行啓而明治之朝以ニ十六年ニ月三日 大正之◯以ニ秊六月ニ十九日昭和之朝以九年六月六日竝始仰 鶴駕臺臨焉頃者胥謀樹銅表以諗恩榮之辱於永世云爾」水かきがないので鶴の姿か?「昭和十一年一月 葉山町謹建之」そして「恩光碑」の手前にあった色彩豊かなマンホール蓋。「明治45年、国産ヨットが初めて帆走(はんそう)したことから、葉山町は「近代ヨット発祥の地」とされています。 相模湾に浮かぶヨットを主役に、町の花「ツツジ」、木「クロマツ」、鳥「ウグイス」をあしらったマンホール蓋で、親子蓋である本蓋は、親子あわせて壮大な海を渡るヨットを描いています。 ヨットが行きかう相模湾は、温暖な気候と黒潮の恩恵から多様な生き物が生息しており、そうした環境へ配慮し、町の浄化センターは山間部に建設しました。受枠に施された青い円は、山・川・海を廻る水を表し、「葉山の美しい水環境を未来の世代へ引き継ぐ」という思いを込めています」 と再びネットから。「葉山御用邸」正門の「皇室警護官」の姿を。そして横断歩道を渡り、青い欄干の橋に向かって戻る。国道134号・下山川に架かる橋。「下山橋」と。欄干にはヨットの姿が。近づいて。「下山川」の下流側を見る。相模湾の見える位置まで移動して。海岸に最も近い臨御橋(りんぎょばし)まで2本の橋があるようだ。「葉山御用邸」の正門前を通過。県道207号線まで戻ると「関東ふれあいの道 ④佐島・大楠山のみち」案内板。関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)は梅の木平(東京都八王子市)を起終点に東京、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、神奈川の1都6県を時計回りに巡る160コース、トータル1,803kmの自然歩道です。神奈川県内には17コースがあります。豊かな自然に触れ、名所や史跡を訪ねながら歩いてみませんか。」④佐島・大楠山のみち三浦半島最高蜂の大楠山は登り約1時間、標高242m。比較的容易に登れるコースですが、最後の階段はちょっと頑張り、下りたあとはひたすら国道の歩道を歩きます。「関東ふれあいの道佐島・大楠山のみち長者ヶ崎 1.0km」。そして県道207号線を北上し、「一色海岸」京急バス停前を通過。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.15
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その4):下山口 神明社~庚申塔
国道134号を葉山公園方向に向かって進み、次の目的地の「下山口 神明社」に向かってこの石段を上って行った。まずは「下山口 神明社」の西側にあった境内社?の「稲荷神社」へ。神明鳥居(しんめいとりい)の石鳥居には「令和二年七月 下山口神明社 建立」と朱字で。神明鳥居二本の円柱の上に円柱状の笠木をのせ、下に貫を入れた直線的な鳥居。覆堂 (おおいどう)?の中には朱の社殿が鎮座。その手前にお狐様。朱の社殿に近づいて。そして奥にあったのが「下山口 神明社」。三浦郡葉山町下山口1504。手水舎。右手にあった「社務所」。陶器製?の狛犬(右)。陶器製?の狛犬(左)。社殿。御祭神 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ) 向津比売命(むかつひめのみこと)「下山口 神明社」は森戸大明神宮司様の兼務社で、毎年8月第3日曜日に例祭と神楽の奉仕が行われていると。社殿に近づいて。「社殿」の左側に2つの社が。右手は「御札預り所」。この社の扁額は「恵比寿天」と。格子の隙間から内陣を見る。こちらは神輿庫か?振り返ると、国道134号沿いに石仏の姿が。石仏の手前に案内柱が立っていた。「葉山町指定重要文化財 建造物 神明社の庚申塔」と。歴史を感じさせる4基の庚申塔が並んでいた。一番右の大きな庚申塔。駒型 日月 青面金剛立像 邪鬼 三猿 ニ鶏。この時は、逆光であったので、はっきり解かる写真をネットから。造立年号(塔に刻まれている年月日) 天明元辛丑11月吉日(1781年)碑型、石質、其の他 角柱駒型、安山岩、四基群の内向って右端。大きさ及破損度 高さ172cm(台石を含まず)。幅76cm。破損無し。刻像 一面六臂人身を吊す青面金剛と、日月、二鶏、三猿、邪鬼。青面金剛は中央右手に剣を持ち、 左手はシヨケラと称する人身の頭髪を掴んで吊す。他は法輪、槍、弓、矢を持つ。 兜に蛇を巻き邪鬼の背に乗る。猿は向って右から見ざる、聴かざる、言わざるで、 左右の猿は中央に向き合っている。銘文 正面向って右に年号、同左に「願主当村五組講中」とある。塔の特徴 この塔は葉山町で一番大きい。又蛇頭の青面金剛はこの塔だけである。 かがんだ邪鬼は肉体美の出た優しい姿になっているのは面白い。三猿の左右の猿は、 中央に向き合っているが朗かに見える とこれもネットから。笠付角柱型(笠欠) 日月 青面金剛立像 邪鬼 三猿。正面に「濱里中」、右側面 「宝暦四甲戌九月吉日」(1754)。笠付角柱型(笠欠) 日月 青面金剛立像 邪鬼 三猿右側面 「安政七庚申二月吉日」(1860)唐破風笠付角柱型 青面金剛立像 三猿(三面)。斜めから。背面 不言猿。右側面 不聞猿右側 「當村惣子中」 左側 「奉造立三王廿一社」。左側面 一猿右側 「元禄十二年」と。「氏子会館 災害避難場所 葉山町」案内板。こちらが国道134号からの「下山口 神明社」への参道への石段であった、 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.14
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その3):万福寺(2/2)~808LAB~好日葉山工房
「万福寺」本堂を正面から。縁起を再び。「当山は、明応四年(1495)の創建、鎌倉の大本山光明寺系の浄土宗の寺である。この寺は、もと下山口平の里にあった満蔵院で、下山口を領していた鎌介という人が満蔵院本尊の薬師瑠璃光如来の信仰者であったので、明応四年に現在の地に自分の邸宅を全部寄進して寺となし平の里から薬師如来を移して祀り「沙白山満蔵院万福寺」と号した。そして、鎌倉の光明寺から浄土宗四代の法孫寂恵上人の法弟、源誓上人を招請して開山と仰いだ。なお、藥師瑠璃光如来は相模風土記に行基作と記されている。《御詠歌》 おのづから染(そ)まる心(こころ)の錦(にしき)こそ かくれやはなし木々(きぎ)の下山(しもやま)」向拝虹梁(こうはいこうりょう)の上の見事な彫刻。木鼻彫刻(右)。木鼻彫刻(左)。寺紋「八曜に月」であっただろうか?「八曜に月」紋は、真上が欠けた『半月』を描き、その周りに周囲に8つの星を配して描く。戦国武将武田家家臣の原氏の家紋 であるとのことだが。隙間から本堂内陣を。御本尊:阿弥陀如来本堂前から六地蔵、旧本堂の鬼瓦を見る。境内から山門方向を。??の老木の跡であっただろうか?寺務所。再び六地蔵を正面から。「万福寺」を後にして、ナビに従い再び国道134号に向かう。小路脇のガクアジサイ。近づいて。三浦郡葉山町下山口の住宅街の煉瓦?畳の路地を進む。右手にあったのが、カフェバー?「808LAB」。三浦郡葉山町下山口1510−4。HAWAIのナンバープレート?の如き。懐かしい公衆電話。振り返って。国道134号に戻ると角にあったのが「カヌー/カヤック ショップ」の「好日葉山工房・Goodday Hayama Workshop」👈️リンク2022年2月1日、葉山御用邸前のビル1階にオープン。工房を始めたのは、近くの高台で2012(平成24)年、「八千代 木製カヤック工房」を作った梅原雅士さんと、その工房に通っていた生徒、原田幹寿さん と。近くに住む人や週末に葉山に遊びに来る人などから作りたいという申し込みが多くあると。フォームを決めて、ベニヤ材で型を作り、細く切った杉を張り合わせていく。最後に磨き上げて、椅子や装飾を施す。標準タイプは30日~40日で仕上がるのだと。三浦郡葉山町下山口1506−6。製造途中?のカヌーか?使う木材の種類(桜、杉・・・)により、金額が大きく違うようであった。塗装も完了して。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.13
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その2):神奈川県立葉山公園~わかしおこみち~万福寺(1/2)
そして次に訪ねたのが「神奈川県立葉山公園」。入口にあった案内板。「葉山公園」柱。「神奈川県立葉山公園案内図御用邸に隣接する葉山公園は、かつては御用邸付属の馬場でした。昭和21年10月に神奈川県に払い下げられ整備し、昭和32年4月に「近隣公園」として開園しました。相模湾が眼前に広がり、富士山と江ノ島を望む絶好のビューポイントにあり、景勝の地「葉山」に相応しい公園です。クロマツ林のなか芝生が広がり、ハマナスが群生する海辺の公園で、夏は海水浴やマリンスポーツで賑わいますが、秋から春にかけては富士山を望む散策の地となります。」富士山が見える天気であれば・・・・「相模湾と富士山」。大正3年( 1914年)「葉山村海岸全景」(提供:山郷土史研究会)。葉山御用邸横の「下山川河口」と御用邸裏の「小磯の鼻」方向を見る。そして振り返ると、「葉山公園・トンビ磯」その先に「長者ヶ崎」。4匹の大型犬と散歩する御夫婦の姿。「四阿(葉山公園休憩所(海側))」。「四阿」の先から見える「箱根の山々と富士山」案内。ズームして。冬になると、天気次第ではこの絶景が見えるのであろう。「パーゴラ(葉山公園)」。「パーゴラ」とは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことです。 イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなど蔓科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮り、涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます と。江ノ島と大山の姿は確認できたが。再び「長者ヶ崎」を。「芝生広場」を歩き公園内の松林の中を歩く。「葉山公園」を出て「わかしおこみち」に出る。葉山の魅力の一つはひっそりたたずむ小径(こみち)。そして国道134号に向かって進む。次の目的地の「万福寺」に向かって国道134号「葉山公園入口」交差点を渡る。葉山町の汚水マンホール蓋。明治45年、国産ヨットが初めて帆走(はんそう)したことから、葉山町は「近代ヨット発祥の地」とされています。 相模湾に浮かぶヨットを主役に、町の花「ツツジ」、木「クロマツ」、鳥「ウグイス」をあしらったマンホール蓋。外周の円は、山・川・海を廻る水を表し、「葉山の美しい水環境を未来の世代へ引き継ぐ」という思いを込めています と。そして「万福寺」の山門前に到着。寺号標石「浄土宗 沙白山 万福寺」。掲示板。今月の言葉「比べなくても あなたは あなた」👈️リンク。「どんな一歩も大事な一歩いけらば念仏の功つもり、しなば浄土へまいりなん。とてもかくても、此の身には、思いわずろう事ぞなき(生きている問はお念仏を称えてその功徳が積もり、命尽きたならばお浄土に参らせていただきます。いずれにしてもこの身にはあれこれと思い悩むことなどないです。)私たちはさまざまな思いを抱きながら毎日を歩んでいます。思い切って踏み出した一歩も、迷いながら踏み出した一歩も、なんとなく踏み出した一歩も、どれも等しく大切で、私たちが生きる上でとても大事なもの。そんな歩みの中、私たちはお念仏をとなえることによって、阿弥陀さまにお見守りいたたき、いつか命終わる時、「極楽往生」というお導きをいただくことができます。日々、悩み戸惑い、心が散り乱れる私たちですが、お念仏の生活を送ることによって、阿弥陀さまと共に安心して毎日を歩むことが出来るのです。」正面に山門。扁額「瑞信成門」。意味は??山門をくぐり境内へ。左側にあった石碑。「浄土宗万福寺の誌明応四年(一四九五年)の創建である。下山口領主鎌介公が平の里満蔵院本尊の薬師瑠璃光如来の信仰者であったので現在地にあった自分の邸宅・敷地を全部寄進して、ここに移し、砂白山満蔵院万福寺と号した。そして鎌倉より浄土宗四代の法孫寂慧上人の法弟順誉現誓上人を招請して開山に仰いだと伝えられる。その後阿弥陀三尊が祀られたので之を本尊となし薬師如来は今は秘伝となっている。大正十二年九月一日の大震災に本堂全潰し第二十八代楽誉慶瑞上人は東奔西走堂宇再建に精根を傾け、遂に昭和ニ年四月二十ニ日現在本堂の落慶を見るに至ったのである。寺宝 薬師如来(行基作)不動尊厨子高僧筆墨 掛軸(弘法・法然・親鵉・他名僧筆になる)三浦札所 薬師如来十二番 身代り地蔵尊二十ニ番 願掛け観音三十三番白妙の真砂の上によろづ代をしめてさいわひ給ふみほとけ 昭和五十ニ年十月吉日 三十一世玄誉慶成 建立」 旧本堂の鬼瓦か?そして本堂。三浦郡葉山町下山口1515。「葉山町 ボーイスカウト ガールスカウト発祥之地」碑。「当山第30世住職坂田慶成師は 夙に青少年の健全な育成を悲願とせられ ボーイ・ガールスカウト運動の精神に深い感銘を享け当寺を草創の地と定め数名の少年達と苦楽を共にし幾多の困難を乗り越えて逐に葉山第1団を結成し昭和37年県連登録して葉山逗子における今日の隆盛の基盤を造ったものでここに記念碑を建立しその偉業を末長く称えることとした平成元年9月吉日側面:葉山町ボーイ・ガールスカウト 発祥之地紀念碑建設委員会」その先には「六地蔵尊」を祀った御堂。御堂内部に赤い帽子・涎掛けの六地蔵尊。「涙には涙に宿る仏ありそのみそのみ仏を法蔵【阿弥陀さまの事】と言う地蔵菩薩は人間のいる所常にその苦しみも哀しみも共にする同悲同苦のみ仏として現世での幸せの・・・・・・・暖かくみつめしっかりお守り下さる更に地蔵菩薩は慈悲深く子どもをお守りして下さり家庭平安・病気平癒・延命長寿・除災招福等の喜びを授けて下さる功徳がある。六地蔵尊は六道能化地蔵願王菩薩と申し人間が死んだあと之めぐるとされる六道の世界に夫々1.天道 ▶️ 日光地蔵2.人間道 ▶️ 除蓋障地蔵3.修羅道 ▶️ 持地地蔵4.畜生道 ▶️ 宝印朱地蔵5.餓鬼道 ▶️ 宝珠地蔵6.地獄道 ▶️ 檀陀地蔵がおり衆生が苦しむとすぐそばにかけつけて救ってくれる。その他六道の世界に迷う衆生を阿弥陀如来のもとにおつれし弥陀の浄土に往生させて下さるという大きな役を果たしていらしやる。」石仏がニ体そして摩尼車が。万福寺の「願掛け観音」。万福寺は、明応四年(1495)創建の浄土宗のお寺で、入って本堂左側に、この「願掛け観音」があった。「願掛け観音由来建立年代不詳。多くの人の願いを聞き、それを叶えて下さるということで参詣者が多く、関東一円からの来訪がある穏やかな心安らぐお顔はいつまでも見飽きない。最近は進学希望の学生の絵馬奉納で人気を呼ぶ。お参りするときお願い部分をたわしで洗い全体に水をかけて下さい。必ず周りをきれいにして桶には水を入れ、後の参詣者が困らないようにして下さい。」「願掛け観音」の後方にあった石仏。舟型の地蔵菩薩であっただろうか。そして更に奥のここにも合掌される石仏。合同墓か?「妙白山万福寺歴代上人墓」「妙白山万福寺歴代上人墓誌」現在の上人は三十一世のようであった。振り返って。美しいあじさいの花。近づいて。懐かしき手押しポンプの井戸。井戸前から振り返って。本堂前の石灯籠(右)。本堂前の石灯籠(左)。本堂を斜めから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.12
コメント(0)
-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その1):往路~長者ヶ崎~長者ヶ崎海岸
この日は5月30日(日)、前日の風雨も過ぎ去り、この朝は青空が。台風1号も31日朝から昼前にかけて、伊豆諸島に最も接近する見込みとのこと。神奈川県内では雷を伴った激しい雨が降り、警報級の大雨となる可能性もあるという。よって、以前から計画していた、「御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く」をこの日に決行。6:30過ぎに自宅を出て、小田急線、東海道線、横須賀線を利用して逗子駅に到着。時間は7:17。バスで「長者ヶ崎」まで行くこととし、バス停に向かう。「歩いてみよう逗子・葉山」案内板。葉山町は人口約3万2千人、面積約17km2、我が藤沢でいえば御所見と遠藤を合せたくらいの規模の所で人口密度もほぼ近い。藤沢と異なり殆ど山であるが、相模湾を西に臨む沿岸部は温暖で風光明媚な保養適地として明治天皇侍医ベルツ博士のお墨付きを得た。明治27年御用邸が竣工、多くの別荘が明治から昭和中頃まで建設された。昭和9年には500軒にも及ぶといわれた別荘も、現在はその殆どが消え跡地の多くは高級マンションなどになり、また山間部の開発も始まりすっかりべッドタウン化しているのだ。今回は、あくまでも明るい海岸部を富士、江の島などを望みながら、往時を振り返るコースを長者ヶ崎~葉山マリーナの先まで歩くことにしたのであった。JR逗子駅駅舎を振り返る。逗子駅バスターミナルへ。中央に、ヨットの帆柱そしてその頂部に時計が。京急バス・長井行き7:40発で長者ヶ崎へr向かう。京浜急行バス・長井行きが定刻に到着。かなり混雑していたが、なんとか座席を確保。7:40定刻に出発。そして少し渋滞したが、国道134号を走り、8:05過ぎに「長者ヶ崎」バス停で下車し散策のスタート。国道134号の歩道を「長者ヶ崎」に向かって歩く。遠く海の先に、我が住む市内にある「江の島」の姿が。ズームして。さらに。前方右手に、神奈川県三浦郡葉山町一色にあるライオンズマンション葉山マリンビュー、そして手前の海岸が「長者ヶ崎海岸」。「葉山公園・トンビ磯」。県立葉山公園の前にある小さく短い突堤がトンビ磯堤防だ。長者ケ崎の岬が目前の絶景のロケーションだが、釣り場としては穴場的存在であると。水深は浅く堤防先端付近でも2mもないとのこと。三浦郡葉山町下山口。その先には、標高約140mの三ヶ岡山(大峰山)一帯が。「長者ヶ崎海岸」を再び。そしてその前方の、相模湾に約400m突出する「長者ヶ崎」を見る。付け根附近の断崖。三浦半島の尾根といわれる大楠山地(おおぐすさんち)の西端にあたり、泥岩層(逗子(ずし)泥岩層)からなり、基底は凝灰岩層(御用邸岬凝灰岩)で、地質上の向斜部が、硬い泥岩層による選択侵食のために山嶺(さんれい)となったものの典型とされる。1177年(治承1)伊豆に流されていた源頼朝(よりとも)が三浦半島を訪れてここの景色を賞したが、案内していた土豪の芦名三郎(あしなさぶろう)が、あたり一帯の植林に精を出して成功した長者の物語をしたのが地名のおこりと伝える。三浦半島西岸第一の展望地で、江の島から湘南(しょうなん)海岸一帯、富士、箱根、伊豆半島、大島、三浦半島南端部が一望のもとに収められる。横須賀側の南斜面では、草花、エンドウづくりが盛んで、早咲き、早取り(正月用)で知られる。夏は海水浴場となる と。「長者ヶ崎」の先端部。静かな海に筋状の白波が先端部に。こちらは、この日は無料の駐車場の入口。こちらは、4月~6月、9~10月の土日祝休日は有料(9~18時)の駐車場。有料駐車場の奥に「長者ヶ崎海水浴場」碑。ズームして。「かながわの景勝50選 長者ヶ崎」碑。長者ヶ崎は葉山町の南端で、横須賀市との境に位置し、大楠山系の峰山(三根山)が西に突き出した岬で、遥か富士を望み、大島が眼前に見え、ここも夕陽が美しい岬として知られている。土地の古老は現駐車場海側の屏風のような岩を「峠山」、その奥の岬を「尾ヶ崎(おがさき)」または「鵜ヶ崎(うがさき)」と呼んだ。南側(横須賀)は大崩、北側(葉山)は白石という小字である。昔は峠山と尾ヶ崎の間は舟が通れたが、大正12年の関東大震災で土地が隆起し陸続きになった と。長者ヶ崎の「マイルストーン〈ヨット〉」長者ヶ崎のある葉山町は、「日本のヨット発祥の地」であり、日本有数の歴史と伝統を誇るマリーナはもちろんのこと、多数のヨットスクールもあり、素晴らしいマリンライフのひと時を過ごすには最適な場所となっているのだ。「自転車半島宣言 長者ヶ崎ヨット三浦半島観光連絡協議会」。「三浦半島一周 サイクリング」。この時は富士山の姿は・・・。昔、早春に撮った写真を。このような写真を撮りたかったが残念。「長者ヶ崎駐車場「とるぱ」ご案内」であったが・・・ネットから。「とるぱ」は、写真を撮るパーキング・安全な駐車場と、写真撮影ができるフォトスポットのセットです。・「とるぱ」では、魅力ある風景などを撮影することができます。・現在、神奈川県では7箇所の「とるぱ」があり、皆様にご利用いただいております。 また、「とるぱ」の情報はホームページで確認することができます。 (平成23年3月現在)・「とるぱ」マークの標識をみつけたら、近くのとるぱ駐車場に車を停めて、カメラ片手に フォットsポットまで歩いて行ってみませんか。 きっと美しい風景を撮影することができます。長者ヶ崎からの見どころ 富士山、伊豆半島、江ノ島を望む景色は「かながわ景勝50選」に選ばれるほど ここから見える景色は、絶景として有名です。そしてこの日の長者ヶ崎。以前に訪ねた時の写真。こちらはネットから。こちらも以前訪ねた時のダイヤモンドリングの写真。「長者ヶ崎緑地◆所在地 横須賀市秋谷字尾ヶ崎5676番1 葉山町下山口字白石2053番1◆面積 10 , 670m2◆寄贈者 鹿島建設株式会社神奈川県では、優れた自然環境及び歴史的環境を保全して後世に引き継ぐため、かながわのナショナル・トラスト運動を進めています。この緑地は、鹿島建設株式会社の御芳志を受け、かながわのナショナル・トラスト寄贈緑地として保全するものです。自然を大切に、みんなの手でふるさと神奈川に豊かなみどりを残しましよう。」再び「長者ヶ崎海岸」を見る。「尾が島」。葉山・長者ヶ崎沖に浮かぶ小島。「芝崎海岸」に負けず劣らずのシュノーケリングスポット と。三浦半島を望む。右手は「城ヶ島」方向。再び「江の島」を。「関東ふれあいの道 ④佐島・大楠山のみち アマモ場の生きものたち長者ヶ崎の北側は波の静かな内海で、海底には砂や泥が堆積しています。このような浅い海にはアマモが群生し、「アマモ場」を作っています。アマモは海底に長い地下茎と根を繁茂させ、海水中にはリボン状の葉や、花や実のついた長さ1 ~ 2mの茎をつけます。地下茎や根の周りにはイソメ類やカニ類など、葉の表面に小型の藻類やモ工ビ類、ウズマキゴカイ、コケムシ類など様々な小動物がすみ、さらにトビウオやアオリイカなどが卵を産みつけます。アマモは多くの海の生き物に生活の場を提供しています。アマモ葉は細長く、幅5 ~ 7mm、長さ約1m、直立する茎についた花は海中や水面で咲き、初夏には米粒のような実がなります。三浦半島ではアジモとも呼ばれ、このほかモシオグサ(藻塩草)、リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ(竜宮の乙姫の元結の切りはずし)などの名前があります。また、水深3 ~ 10mの海底には、直立すると5 ~ 6mになるタチアマモが群生して、アマモ場をつくります。」「アマモ」。「関東ふれあいの道⇐立石公園へ2.4Km しおさい公園へ⇒1.0Km。」そして国道134号のこの先は「横須賀市」。カーブを曲がると、右側に長者ヶ崎の裏側が見えたので撮ってみました。ズームして。再び「尾が島」をズームして。「葉山町」案内モニュメント。ズームして。葉山らしいデザインの町名看板。そして久しぶりの「長者ヶ崎」を後にして。国道134号を御用邸方向に進む。左手の小路が「さざなみこみち」と。「さざなみこみち」の入口には「津波避難経路」案内板が路面上にあった。「ここは海抜約9.5m 海抜20m地点まで約155m」と。「さざなみこみち」を「長者ヶ崎海岸」に向かって進む。「長者ヶ崎海岸」から「長者ヶ崎」の岬を振り返る。この時は、岬の途中が海で2つに隔てられていた。三ヶ岡山(大峰山)方向を望む。「長者ヶ崎海岸」を歩きながら振り返ると岬が二分されていることがはっきりと解ったのであった。ズームして。海面に出ている岩場伝いに先端に渡るのは無理そうであった。「葉山町海・浜のルール」案内板。 ・・・つづく・・・
2024.06.11
コメント(0)
-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩く(その2)
車で移動し「鷹匠橋」を渡り、車を停めて橋の袂まで戻る。橋の名は「鷹匠橋」。徳川時代に将軍が鷹狩りをする目的で、藤沢御殿が造られた。現在の藤沢市民病院の側であった。その関係で、藤沢の辺りには鷹匠も住んでいたと。このことから市民病院北東の境川にかかる橋は、『鷹匠橋』と名付けられているのだ。歴史を感じさせる橋名。藤沢市内にはもう一つの「鷹匠橋」がある。こちらは「伏見稲荷大社」に向かって進むと引地川に架かる橋であり「大場鷹匠橋」と呼ばれているのである。よって正確には「鷹匠橋」はこの橋のみなのであるが。「鷹匠橋」から「境川」上流を見る。「境川」に架かる「大清水橋」の上流約500mの場所までは「境川」が藤沢市と横浜市の境界になっているのだが、そこから南側は藤沢市が大きく「境川」を超えて、東に広がり鎌倉市と境界を作っているのである。「鷹匠橋」から「境川」の川面を見下ろすと、亀の姿が。「ニホンイシガメ」の雌であっただろうか?体長25~30cm?。そして「境川」沿いにある「大清水境川アジサイロード」を見る。ズームして。「鷹匠橋」の欄干のデザインはスミレの花であろうか。別の場所のステンドグラス風の絵。「さかいがわ」と。ここにも4枚のステンドグラス風の絵の1枚が。藤沢市民病院を見る。その手前に国道1号・藤沢バイパスに架かる「境川大橋」。再び「境川」の上流を見る。「境川」と漢字で。ここ「境川の右岸」にも多くのアジサイが植えられていたが、数年前に、「県道451号線藤沢大和自転車道線」の拡張工事の為に抜かれてしまったのであった。そして愛車に戻り帰路に。前方に見えたのが「横浜水道境川水路橋」。神奈川県と共同で運用している寒川取水ぜきから取水し、横浜市戸塚区の小雀浄水場まで約12.4Kmの導水路の1部である。そして「花應院」の先で車を停め、再びアジサイをカメラで追う。装飾花・ガクの小さなアジサイ。こちらは鮮やかなピンク。このアジサイも白の装飾花・ガクが細かく。近づいて。紫のアジサイ。近づいて。こちらは装飾花・ガクの花びらが多いのだ。こちらの装飾花も。装飾花・ガク片が大きい。「スイセンノウ」。そして帰宅して、ご近所の白の「カシワバアジサイ」。葉の形がカシワに似ていることが、和名の由来。花は円錐状あるいはピラミッド型に付く独自の形状をしており、5月〜7月に真っ白い花を付ける。八重咲きと一重咲きがある。一般のアジサイとは異なり全体の印象としては木のボリュームに比し、花が少ないのが特徴。葉には切れ込みがあり、秋には紅葉する。そしおて見事な色合いのアジサイも。近づいて。紫の装飾花のまん中にも小さな青い花が咲いているのだ。そして我が家のブルーのアジサイ。今年は例年になく花の数が多いのである。剪定の強度の影響か?近づいて。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2024.06.10
コメント(0)
-
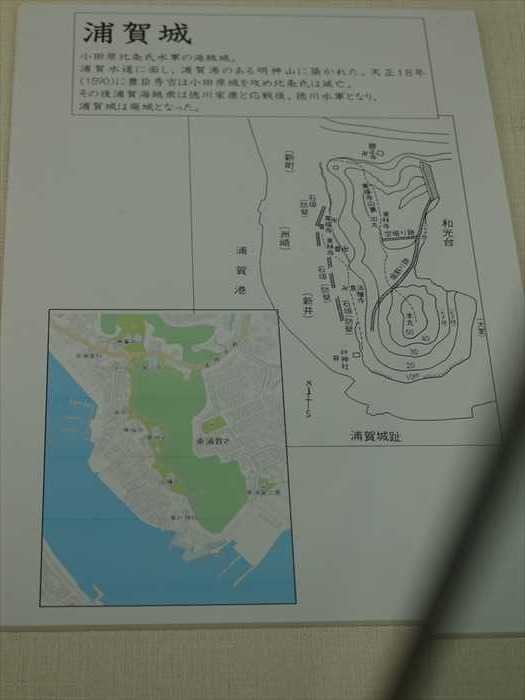
横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その40):浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)3/3
「浦賀城小田原北条氏水軍の海賊城。浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に築かれた。天正18年(1590)に豊臣秀吉は小田原城を攻め北条氏は滅亡。その後浦賀賊衆は徳川家康と応戦後、徳川水軍となり、浦賀城は廃城となった。」「浦賀城跡波静かな、浦賀港を前にして、叶神社奥の院のある、明神山一帯を本城とし、本城の前面に、東林寺出丸と、専福寺裏山出丸がV字形に位置し、全体としては、Y字形の地形になっている。本丸のあった明神山には、二段のヒナ段を造り、今ものこしている。東林寺山の東側にもヒナ段を築いてあったが、宅地造成のため一段切り崩された。また梅山切通しは、掘割だったと考えられるが、道路拡幅工事のため切り崩された。城の西方の町(東浦賀)には、法幢寺、東林寺、専福寺を海岸沿いに連続させ、石垣を築いて防衛している。また東側の大きな谷間(大室)は、船蔵跡といわれ、先年発掘調査が行われ、水堀が発見され、柱穴の一部も確認されたが宅地造成の犠牲となった。北条早雲は、永正15年(1518)三浦道寸を、新井城にて滅亡させ、三浦の地を得た。そして、北条水軍の根拠地を、三崎城におき、大改修を加えて、防備に当たらせた。当時房州の里見水軍がたびたび三浦半島に出没し、弘治2年(1556)塚原備前守、富永三郎左衛門、遠山丹波守等、三崎城にて里見左馬頭義弘の軍勢と戦い、里見軍は兵船80隻をひきいて、城ヶ島に陣を構え、大合戦となったが勝負はつかず、里見軍は房総へ引き返した。そこで浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に海賊城を構築した。これが三崎城の支城、浦賀城である。そして、「浦賀定海賊」を起用し防衛にあたらせた。天正18年(1590)豊臣秀吉は、小田原城を攻め北条氏は滅亡した。浦賀海賊衆は後北条氏に属して、三崎城に立てこもり、豊臣方の徳川家康と戦闘を交え、城が陥落した後、城ヶ島に立てこもり、応戦を続けたのちに家康と和睦し、徳川水軍となった。そして浦賀城は廃城となったのである。」「浦賀城址戦国時代に小田原北条氏が三浦半島を支配した時に房総里見氏からの攻撃に備えて北条氏康が三崎城の出城として築いたといわれています。水軍の根城として山頂には空掘など城の遺構が残り、下田山・城山とも呼ばれていました。昔から眺望の素晴らしい所で対岸に房総半島、正面に浦賀八勝の一つ燈明堂が見られます。この明神山は自然の社叢林で県の天然記念物に指定されたウバメガシ分布の北限とされています。嘉永六年( 一八五三)ペリーの黒船四隻が浦賀沖に来航した時、眼下の左辺りに停泊しました。下の絵は安藤広重の武相名所の旅絵日記の五六景の一枚です。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」先ほど訪れた明神山の山頂の南端からは「浦賀水道」の絶景が拡がっていたのであった。そして前方の眼下に見えたのが先日訪ねた「浦賀燈明堂跡」が見えた。広重の旅絵日記より「浦賀水道」には「浦賀燈明堂」が描かれているのであった。「御城印」。「浦賀奉行所の設置とその役割」「浦賀奉行所の設置とその役割江戸の町の発展につれて、船によって江戸に運ばれる商品が増大すると、三崎・走水両番所を統合してつくられた下田奉行所では統制できなくなりました。そこで、享保5年(172)の12月、幕府は浦賀に奉行所を設置し、船番所を設置して、江戸へ出入りする船をすべて検査する体制を整えました。浦賀奉行所は、浦賀奉行(1 ~ 2名)の下に与カ(10 ~ 23名)と同心(49 ~ 86名)が付属し、船改めのほか、領地の年貢徴収や治安維持などの民政も行いました。船改めの実務は、105軒の廻船問屋が請け負っています。江戸時代後期になると、異国船が江戸湾に来航するようになり、海防と応接の任務が加わります。ペリー艦隊の来航の際の奉行所役人たちの活躍はよく知られています。その後の軍艦建造など、幕府海軍の発展にも大きな役割を果たしました。」「浦賀奉行所間取模型」。近づいて。そして正面に「浦賀奉行所の模型」。正面から。「浦賀奉行所 見取図👈️リンクⅠ 浦賀奉行所の誕生享保5年(1720 ) 12月、伊豆の下田にあった奉行所を移転し、新たに浦賀奉行所が設置されました。下田から浦賀に移転した公式な理由は「下田は港の出人口に岩礁があって、船の人出港の妨げになっている」という船乗りたちからの声を聞き、より安全な湊を求めたからといわれています。しかし本当は、江戸幕府が開かれてから100年問、大きな戦乱もなく平和な世の中てあったため、生産力が向上して全国各地から江戸へ様々な品物が人るようになり、江戸に人る物資の98%以上を占めていた船による荷物を、ほぼ完ぺきに検査できる場所を探した結果、すでに湊として整備されていた浦賀が選ばれたのです。Ⅱ 浦賀奉行所の役割(江戸に出人りする船の検査)浦賀奉行所には、船の積み荷と乗組員の検査をする「船改め」を行う船番所が開設されました。この船改めは「廻船問屋」と呼ばれた105軒の問屋に委託されました。江戸へ出人りする全ての船は、浦賀で改めを受けることが義務づけられ、船の関所の役割を担っていた船番所ては、「入り鉄砲に出女」の検査はもちろん、生活必需品11品目の出入りの数が3か月ごとに江戸町奉行に報告されてしました。Ⅲ 浦賀奉行所の役割(異国船の警備と応接)浦賀奉行所が開設されて100年となる19世紀初めには、異国船が浦賀沖へ来航するようになり、奉行所に異国船への警備と応接の役割が追加されました。嘉永6年(1853) 6月、浦賀に来航したペリー艦隊は、日本が近代に進む第一歩としてよく知られていますが、浦賀奉行所にとっては、文政元年(1818) 5月に来航したイギリス船から数えて7度目の異国船の来航でした。このペリー来航時には、中島三郎助や香山栄左衛門をはじめとした浦賀奉行所の役人たちが大きく活躍し、交渉の結果、アメリカ大統領の親書を久里浜て受け取ることになりました。Ⅳ 幕府海軍と浦賀奉行所の廃止翌年の嘉永7年(1854) 1月にペリーが再来日して、日米和親条約が結ばれましたが、その頃浦賀では、日本初の洋式軍艦「鳳凰丸」が建造されていました。安政5年(1858) 6月に日米修好通商条約が結ばれ、翌年に横浜が開港されると、異国(船)の応接は浦賀奉行所から神奈川奉行所に移されました。しかし、浦賀奉行所は、開港後も引き続き「船改め」の役割を続けるとともに、鳳凰丸建造や軍艦の修理など、幕府海軍を支える重要な役割を果たしていました。安政7年(1860)咸臨丸が浦賀から出港した時も、浦賀奉行所の役人が乗船してアメリカへ渡りました。浦賀奉行所は、慶応4年(1868)閏4月、新政府軍に接収され、「船改め」以外の仕事を終えました。「船改め」の仕事は明治5年(1872)まで続けられました。浦賀奉行所は、周囲を堀で囲まれ、東面北側に表門、北面中央に裏門がありました。敷地の中には屋敷、焚出所、土蔵などがかれ、さらに屋敷には玄関、白州、地方役所といった執務の場のほか、日常生活の場(役宅や台所など)も置かれていました。焚出所異国船が来航すると、奉行所の役人をはじめ、奉行所の船を操船する近隣の漁師は24時問体制になるため、その役目についた人たちにご飯などを炊きだした場所。奉行所の門を通らずに出入りすることができました。地方役所「じかた」役所と読み、年貢の徴収や土地制度、民政に関する政務を行っていました。白州奉行所で法廷が置かれた場所。しかし、裁判ばかりでなく、町人や農民などに通達するときも白州が使われました。浦賀奉行所では灯明堂の白砂が敷かれていて、汚れると新しい砂と交換しました。役宅奉行が2人体制になった文政2年(1819)以後、浦賀詰め(在地)となった奉行が居住した場所。文久2年(1862)までは、在地の奉行は単身赴任であり、奉行の周囲には秘書役の用人と警備役の目付が数名ずついました。」浦賀奉行所 地図。★「浦賀奉行所」👈️リンク。「奉行所 模型」に近づいて様々な角度から。「歴代浦賀奉行一覧」。「浦賀奉行所の主な役人」をネットから。「浦賀奉行所間取図」。「浦賀奉行所間取図 1」:文政4年(1821)~同11年(1828)頃。文政4年、敷地が享保5年(1720)開設時以来の約500坪から約1,500坪に拡張され、建物も新築された頃の間取図面。(弘化2年での修築についての記事は追筆されたもの)「浦賀奉行所間取図 2」:天保11年(1840)~弘化元年(1844)頃。弘化2年(1845)改築以前の間取り。文政11年~天保11年にいくつかの改築が、行われた結果を表している。「浦賀奉行所間取図 3」:安政2年(1855)新築。安政2年に新築された際の間取り。西側の破線から西の部分(10間半)はこの時に増地され、敷地は約1,950坪に拡張された。これは現在の奉行所跡地と同じ面積です。以後、文久2年(1862)に建物の一部が増築されたようだが、詳細は不明で、絵図も残っていない。「中島三郎助 宅」。近づいて。「中島三郎助 宅桂小五郎、中島三郎助宅に寄食・教えを受ける安政二年(1855年)桂小五郎は、吉田松陰の勧めで中島三郎助宅を訪れ、「船艦製造の技術と西洋軍事を極めたいので教授してもらいたい」と願いました。三郎助は固辞して承知しませんでしたが、桂が熱心に懇願するので「それでは一緒に勉強しよう」ということになり、アメリカより入手した造船製造書を研究することになりました。桂は後の木戸孝允です。桂が「どこか部屋の片隅にでも置いてもらいたい」と頼むと、三郎助は自宅の裏に漬物を置く二畳半ほどの納屋に床を張って提供し、桂は約四ヶ月この部屋で寄食したといわれています。この工ピソードは、『浦賀志稿本』に収められています。」「奉行所周辺の居住図」。「現在の浦賀奉行所跡周辺の居住図」。①浦賀奉行所跡②船番所跡(現在の浦賀病院)③浦賀奉行所支配組頭役宅跡④浦賀奉行所与カ・同心等の役宅跡「会津藩の江戸湾警備」。江戸湾の警備が、重要視されるようになったのは、寛政年間です。寛政4年(1792)ロシア使節ラクスマンが、根室に来航し日本の通商を求めましたが、この際に江戸への回航を要求しました。これに驚いた老中松平定信が、江戸湾の防衛体制の整備に着手しました。しかし、松平定信が老中を辞任したことにより、この計画も頓挫しました。その後、北方でロシアとの緊張が高まったり、長崎で起きた「フェートン号事件」をきっかけに、文化年間に江戸湾の海防が再び注目されるようになりました。文化7年(1810)に、会津藩が江戸湾の相州側の警備を命じられました。対岸の房州側の警備を命じられたのは、白河藩(当時の藩主は江戸湾の警備強化を提案した松平定信)でした。文化7年1 1月には、会津藩士の移住が始まりました。遠方への長期出兵だったため家族同伴がゆるされました。そして文化8年から9年にかけて、観音崎、浦賀平根山、城ヶ島に砲台が築かれ、陣屋は観音崎、平根山、三崎におかれました。警備隊は、番頭上席を責任者として、数名の番頭に指揮された軍隊、武具奉行、普請奉行、砲術家などの技術者、郡奉行を中心に民政にあたる者で編成されていました。この江戸湾警備は10年もの長期間に及びましたが、文政3年(1820)に、相州の警備は浦賀奉行所が担当することになり、会津藩は江戸湾警備の任を解かれました。「船番所」の模型。陸軍桟橋の前の駐車場の地が浦賀奉行所の出先機関であった番所が置かれていたところ。番所では、江戸へ出入りする船の荷改め(検査)を行い、それは江戸中の経済を動かすほどの重要なものであった。その業務は昼夜を通じて行われ、三方問屋と呼ばれる、下田と東西浦賀の回船問屋100軒余が実務を担当していた。右手に「船番所」。「船番所鳥瞰模型(1/60)享保5年(1720年)幕府は下田の船番所を浦賀に移しました。船番所は海の関所です。与カ2人、同心6人が昼夜詰めており、江戸に出入りする船は必ず船番所の検査を受ける決まりになっていました。船が着くと、与カ・同心の指揮で、東西浦賀・下田の廻船問屋が、積み荷・乗組員・船の石数(大きさ)等を書類と突き合わせて検査し、間違いがあれば理由がわかるまで留められます。「入り鉄砲・出女」のほか、運んではならない品物も細かく定められていました。浦賀の船番所は、明治政府になり廃止されるまでの約145年間、船改めと江戸防備の役割を果たしました。」〇敷地総坪・・・・・798坪7合5勺7寸〇正門脇の高札・・・・・・浦高札といい、海に関するお触れが掲げられていた。〇番所内に牢があるが、お白洲は無く奉行所でお裁きを受けた。〇下田丸(元韋駄天丸)・長津呂丸は下田番所から移されたもので、船がお船庫からはみ出ている のは、おそらく地形上、お船庫をこのサイズでしか作れなかったからと思われる。 模型製作:村上太」そして「浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)」を後にして、「浦賀通り」まで戻る。正面に、前回も見た巨大なテントが旧浦賀ドックの構内に。京急浦賀駅方面に向かう。浦賀コミュニティセンター分館は(愛称)浦賀文化センター。現在地はここ。「サーカス会場」入口。「ポップサーカス横須賀公園」👈️リンク。そして「浦賀駅前」交差点まで戻り、京急、横浜市営地下鉄、小田急線を利用して帰宅したのであった。この日の、京急久里浜駅~京急浦賀駅までの散策コース。この日の歩数は23,912歩であった。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・
2024.06.10
コメント(0)
-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩く(その1)
この日6月3日(月)の朝は5時半過ぎに目が覚め起床。天気が良かったので、車で10分ほどの場所にある「大清水境川アジサイロード」に今年も向かう。藤沢市と横浜市戸塚区の境を流れる「境川」の岸に植栽されているアジサイ群。「大清水境川アジサイロード」と呼ばれている。地域住民が自宅の庭などで育てたアジサイを植栽したもので、毎年、アジサイ祭が開催されているのだ。「大清水境川アジサイロード」のスタート地点の「大清水橋」を渡り、車を道路脇に一時停車。下車して「大清水橋」を振り返って。さらに「大清水橋」の上流側に見えたのが「横須賀水道路境川水管橋」海老名市社家の相模川から有馬浄水場経由で田浦配水池へ送水される有馬系統の導水管であると。以前は半原系統の導水管(φ500)も敷設されていたが、需要減少、水質悪化、施設老朽化などに伴い2007年(H19)に取水が停止され、2015年(H27)に系統と共に撤去されたのだと。 構造種別:1径間三弦トラス(1個のトラス構造で上弦材1本と下弦材2本の三角形構造) 河口からの距離:7.1km 橋の長さ:約57m 水管径:φ1000 完成:不明そしてこの日のアジサイの開花状況。かなりの花は咲いていたが満開にはまだ少し早かったので後日出直すこととし引き上げた。そして一昨日6月8日(土)、平塚での仕事の打ち合わせを終え、帰宅の途中に、天気も良かったので再び立ち寄ったのであった。時間は11:30過ぎ。神奈川県立藤沢清流高等学校前に車を止め散策開始。アジサイの語源ははっきりしないが、最古の和歌集『万葉集』では「味狭藍」「安治佐為」、平安時代の辞典『和名類聚抄』では「阿豆佐為」の字をあてて書かれている。もっとも有力とされているのは、「藍色が集まったもの」を意味する「集真藍(あづさあい/あづさい)」がなまったものとする説である と。ほぼ満開の「大清水あじさいロード」。紫陽花の漢字の由来は、唐の詩人、白居易(はくきょい)が招賢寺というお寺を訪れた時、お寺に咲いていた紫色の花を「紫陽花」と名付けたことから来ているのだ とネットには。しかし「紫陽花」は日本原産ですからこれは誤り?で、白楽天が詩に詠んだ花とは違うのでは??とネットには。紫色のアジサイの花に近づいて。アジサイ(紫陽花)の別名には、こんなものがあるのだと。●七変化(しちへんげ) :七変化とは、咲き始めてから時間が経つにつれ、色を変える ことからついた別名●四片・四葩(よひら) :「花びら(正確にはガク)が四片あること」からつけられた名前 ●手毬花(てまりばな) :丸く集まった装飾花の形から●オタクサ :この名は、シーボルトの美しき恋心から生まれた名前。 1823年、長崎に渡来したドイツ人医師シーボルト。 植物研究にも情熱を注ぎ、とりわけ紫陽花に夢中になった。●刺繍花(ししゅうばな):手毬花と同じく、刺繍に見立てる。 刺繍から連想するのは、西洋紫陽花ではなく山紫陽花●八仙花(はっせんか) :「七変化」と同じ。さまざまな色合いに変化することから 名づけられた名前花(萼)の色はアントシアニンという色素によるもので、アジサイにはその一種のデルフィニジンが含まれている。これに補助色素(助色素)とアルミニウムのイオンが加わると、青色の花となる と。アジサイは土壌のpH(酸性度)によって花の色が変わり、一般に「酸性ならば青、アルカリ性ならば赤」になると言われている。これは、アルミニウムが根から吸収されやすいイオンの形になるかどうかに、pHが影響するためである。すなわち、土壌が酸性だとアルミニウムがイオンとなって土中に溶け出し、アジサイに吸収されて花のアントシアニンと結合し青色を呈する。逆に土壌が中性やアルカリ性であればアルミニウムは溶け出さずアジサイに吸収されないため、花は赤色となる。したがって、花を青色にしたい場合は、酸性の肥料や、アルミニウムを含むミョウバンを与えればよい。同じ株でも部分によって花の色が違うのは、根から送られてくるアルミニウムの量に差があるためである。花色は花(萼)1グラムあたりに含まれるアルミニウムの量がおよそ40マイクログラム以上の場合に青色になると見積もられている。ただし品種によっては遺伝的な要素で花が青色にならないものもある。これは補助色素が原因であり、もともとその量が少ない品種や、効果を阻害する成分を持つ品種は、アルミニウムを吸収しても青色にはなりにくい。土壌の肥料の要素によっても変わり、窒素が多く、カリウムが少ないと紅色が強くなる とウィキペディアより。また、花色は開花から日を経るに従って徐々に変化する。最初は花に含まれる葉緑素のため薄い黄緑色を帯びており、それが分解されていくとともにアントシアニンや補助色素が生合成され、赤や青に色づいていく。さらに日が経つと有機酸が蓄積されてゆくため、青色の花も赤味を帯びるようになる。これは花の老化によるものであり、土壌の変化とは関係なく起こるのだ と。上の花との違いで、花色は開花から日を経るに従って徐々に変化する。最初は花に含まれる葉緑素のため薄い黄緑色を帯びており、それが分解されていくとともにアントシアニンや補助色素が生合成され、赤や青に色づいていくのが解かるのであった。日本に自生していたガクアジサイ(額紫陽花)が母種となり、西洋にわたって品種改良されたものが世界の紫陽花の主流になったのだ と。青のガクアジサイ(額紫陽花)。紫陽花の花は、装飾花と両性花から出来ていると。まず、装飾花とは、一般的に花と認識されている部分のことを指すつまり、花びらが4~5枚あるように見えている部分のこと。一方で、両性花はガクアジサイやヤマアジサイの花房の中心部分にある、地味な花のことを指す。説明写真をネットから。ちなみに、装飾花で大きく目立つようながく片は、花粉を運ぶ昆虫を呼ぶ際に利用するために発達したといわれているのだ と。白▶️黄色▶️薄紫▶️紫▶️濃紫と開花の時の流れが一つの株で。近づいて。再び「大清水橋」方向を振り返る。ピンクの西洋アジサイ。近づいて。西洋アジサイは←が花の部分。そしてガクアジサイ。近づいて。再び濃いピンクのアジサイを。近づいて。白のガクアジサイ。まるで線香花火の如し。装飾花は薄紫になりはじめていた。一株で?紫、ピンクの花が。近づいて。「平成16年度藤沢市まづくり賞 受賞ここは、大清水小、中、高等学校がひまわりの苗1200本を植え、境川を美しく彩りました。その活動が、「第23回沢市緑と花いつぱい推進活動」において「まちづくり賞」を受賞しました。」装飾花と両性花が同じピンク色に染まったガクアジサイ。近づいて。こちらは装飾花が両性花の後を追う。再び大清水橋を振り返って。この花は色に迷いが??2種類のアジサイが開花のピークに。ガクアジサイに近づいて。藤沢市民病院を背景に。ズームして。両性花が存在を強調して。「境川」を超えた山の上には学校の校舎が。「聖園女学院高校・中学校」。神奈川県藤沢市みその台に所在し、中高一貫教育を提供する私立カトリック系の女子中学校・高等学校である。名古屋市に本部を置く学校法人南山学園の管轄である。完全中高一貫校だったが、2024年度より高校募集を再開している。毎日の朝礼時・終礼時に祈りを捧げて聖歌を歌い、6月と9月、11月、12月、2月にミサを開く。「マリアホール」「イエスの聖心聖堂」などがある。学級は、ばら組・ゆり組・すみれ組・きく組と花の名前である。生徒数の減少により、2015年度からきく組は設置していない。各組は30 - 40名程度[13]で、中学1年生 - 中学3年生の英会話は、1組を2つに分けて少人数で授業する。英語の授業は高校1年生から習熟度別に分ける。高校2年生からは、文系理系に分かれ、選択科目も科目により習熟度別を採る とウィキペディアより。 ・・・つづく・・・
2024.06.09
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その39):浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)2/3
「異国船とペリー艦隊の来航」展示コーナー。近づいて。「異国船とペリー艦隊の来航江戸時代後半になると、日本近海に異国船が頻繁に姿を見せるようになります。ペリー艦隊来航以前の浦賀にも、6回・7隻の異国船がやってきています。浦賀奉行所は、その異国船との応接に当たるとともに、台場(砲台)を築いて海防に努めました。ただし、奉行所の役人は少人数だったため、有力諸大名が増援する体制が組まれ、会津藩や川越藩など様々な藩が江戸湾防備を担当しました。嘉永6年(1853) 6月3日、4隻からなるアメリカのペリー艦隊が浦賀沖に現れました。2隻の蒸気船は、黒煙を吐き、外輪を廻して逆行するという離れ業を見せ、異国船に慣れた浦賀住民もビックリしました。ー触即発の危機かと思われましたが、香山栄左衛門ら与カ・同心の尽力で、久里浜海岸で国書を受領するという形で、とりあえず難を逃れました。しかし、翌嘉永7年1月、ペリー艦隊は再び来航し、横浜で日米和親条約が結ばれ、日本は開国の道に進むことになりました。」「江戸後期、異国船渡来年表」。嘉永6年(1853年)のペリー来航前の「19世紀前半浦賀に来航した異国船」をネットから「19世紀前半浦賀に来航した異国船」の絵図。ブラザーズ号:1818 (文政元)イギリスマンハッタン号:1845 (弘化2 )アメリカサラセン号:1822 (文政5 )イギリスモリソン号:1837 (天保8 )アメリカビットル艦隊:1846 (弘化3 )アメリカマリナー号:1849 (嘉永2 )アメリカ「ブラザース号を取り巻く警備船の図黒船初来航となった「浦賀湊蕃船漂着図」(国立公文書館所蔵)をもとに作成した模型。文元(一八一八)年江戸湾では、鎖国後初めての異国船の来航、船将ゴルドン以下九名の乗組員で交易を求めて。来航であった。会津藩は千石船を借り上げ、陣幕をはり対応している、約ニ百年ぶりの異国船を好奇の目で見る人で浦賀は混乱した と.。「浦賀湊蕃船漂着図」(国立公文書館所蔵)とブラザーズ号:1818 (文政元)イギリス。「黒船(サスケハナ号 建造 1850年) 縮尺1/80 製作 最上 満「黒船 サスケハナ号縮尺 1 / 80(最上 満 製作)総トン数 2,450トン排水量 3,824トン船 長 257フィート(約78.4m) 幅 45フィート(13.7m)速 力 12.5ノット乗組員 平時230人 戦時306人構造:外輪式スチーム・スループ、木骨、木皮 帆 :3本マストパーク型船体:木造船体に腐食防止の黒いタール塗り砲 :9門「ハイネ画「ペリー久里浜上陸の図」(横須賀自然・人文博物館所蔵)」。そしてこちらは「鳳凰丸」👈️リンク。幕末に江戸幕府によって建造された西洋式帆船。幕末に日本で建造された洋式大型軍艦のなかで最初に竣工した。蒸気船の急速な普及のため旧式化し、実際には軍艦ではなく輸送船として使用された。鳳凰は聖天子が国を治める時に現れる想像上の鳥で、「鳳」が雄で「凰」が雌を指す。「鳳凰丸(建造 1854年)縮尺 1/50 製作 最上 満」「鳳凰丸縮尺 1 / 50 (最上満製作)排水量 約600トン船 長 20間(約36m)幅 5間建 造 1854年(浦賀)構造:竜骨、肋材と外板、内張り、吃水線下を銅板仕上げ帆 :幕府の所属を表わす黒の一文字船体:朱塗りに黒のストライプ砲 :10門」「ふね遺産認定書横須賀市殿幕末建造木造帆装軍艦 鳳凰丸我が国の技術役人と船大工によって建造された大船建造解禁後初竣工の様式帆船」・・・・・略・・・・・ふね遺産二十号(非現存船第一号)に認定致します。」「咸臨丸」「咸臨丸幕府が海軍創設のためオランダに注文した木造軍艦で1857年(安政4年) 9月日本に回航し咸臨丸と命名された。長さ49メートル、幅7. 8メートル、3本マスト、砲12門。1860年(安政7年)正月、軍艦奉行木村摂津守、艦長格勝麟太郎。日米修好通商条約の批准書交換を目的とする使節・新見豊前守らの乗ったアメリカ艦ポーハタン号の随行艦として浦賀を出港した。咸臨丸は我が国の軍艦としてはじめて太平洋を横断し、37日間を要してサンフランシスコに到着、5月5日無事浦賀に帰港した。翌年には小笠原開拓に従事、以後幕未の動乱に活躍し、明治維新後は北海道開拓使の輸送船として就航した。」近づいて。「江戸湾測量嘉永6年6月(1853年7月)浦賀沖にペリー艦隊が来航しました。ペリーは次の来航に備えるため、浦賀沖に停泊した翌日からベント大尉率いる測量船を山し、江戸湾の水深や潮流を測量し始めました。この測量をしながら、鎖国以来超えることのできなかった観音崎をシーザーのローマ攻略のポイント、ルビコン川にたとえてルビコン岬、岬を超えると真っ先に見える島、猿島をペリー島、ここに広がる入江をサスケハナ湾というように、アメリカ風の地名を付けていきました。」「ペリー艦隊制作 江戸湾測量図 1854年 オリジナル」をネットから。ペリー提督が神奈川、浦賀に上陸し神奈川条約を締結した1854年に測量した江戸湾の水深図です。左上にBay of Yedo as surveyed by the officers of the US Expedition to Japan in1864と記されています。横浜、浦賀、品川、川崎、千葉県五井、鋸山、勝山の地名が記されています。右下には、伊豆の下田から千葉県の洲崎、小湊、大東崎まで描かれています。サイズは、33cmx25cmで、薄手の紙に石版で刷られています。「江戸湾西岸:モーリーその他士官らによって1854年に測量」をネットから。「浦賀の誕生」、「三浦按針と国際貿易港浦賀」、「天下一の干鰯問屋(ほしかどんや)」案内。「浦賀の誕生ー原始・古代・中世の浦賀ー豊かな自然と温暖な気候に恵まれた浦賀には、約9,000年前から人々の生活が営まれていたことが数多くの遺跡や貝塚によって知ることができます。平安時代の未期から鎌倉時代にかけて三浦一族が活躍する頃になると、「浦川」(現在の久比里のー画)が重要な湊としての役割をもつようになりました。室町時代になると、現在ある寺の大多数が開かれています。そして戦国時代、小田原の後北条氏が東叶神社の裏山(明神山)に房総の里見氏に対抗する浦賀城を築き、水軍の基地としました。これに伴い、船大工や鍛冶屋、櫓屋など、船を建造・修理する職人たちも浦賀へ住居を構えるようになり、これらの人々の生活を支える町ができていきます。これが現在の浦賀へと続く第一歩でした。」後方中央に「弥生時代(後期)甕形土器」その右に「弥生~古墳時代 壺形土器」。「三浦按針と国際貿易港浦賀徳川幕府が成立すると、三浦半島は将軍の直轄地(天領)となり、代官・長谷川長綱が愛宕山の下に陣屋を構え、半島一円を支配しました。また走水と三崎に船改め・番所を置き、江戸湾の防衛に当たらせました。徳川家康は、江戸に近い浦賀の湊に外国商館をつくり貿易港にしようと考えました。この時の外交顧間が英国人ウィリアム・アダムス(三浦按針)で、逸見に領地を与えられ、浦賀に屋敷を構え、スペイン船などを誘致して貿易を行いました。その期間は10年ほどで、来航したスペイン船は6隻でしたが、長期間滞在する船員たちで賑わい教会が建てられるほどでした(関東では他に江戸に2か所あるのみ)」「浦賀湊絵図(文化~文政期頃 1810午代)江戸時代、与力だった中島清司か浦賀港全景を描いたもの 中島清司永豊画(中島家所蔵)」「干鰯問屋干鰯とは、鰯を天日干しにして造られた肥料で、主に東海近畿地方の農家で綿花や密柑の栽培に使用されました。江戸時代、浦賀には奉行所の設置、黒船の来航といった歴史的事象を経験する以前から干鰯問屋などの多くの豪商が存在し、港町、そして商人の町として大いに繁栄しました。干鰯市場のにぎわいを再現した60分の1のジオラマや幕府が干鰯問屋を救うために出した高札、(お触書)など、干鰯問屋なくしては語れない浦賀の文化を展示しています。」中央に「干鰯」、左に「干鰯」を利用して栽培した綿花。「干鰯」。「干鰯とは鰯を天日に干して作った肥料。大坂を中心に生産量が増してきた綿花栽培に欠かせないものであった。また、鰯を大釜て、ゆで、しぼってでた油が行燈油として利用される「魚油」、魚油をとった残りを天日で干したものを「〆粕」といい、干鰯と同じく畑の肥料として利用された。」「天下一の干鰯問屋江戸時代の初期、関西(特に紀川)から鰯を求めて、たくさんの漁船が関東にやってくるようになりました。これは、近畿地方を中心に綿作が発達し、最適な肥料としての干鰯を求めてのものでした。そして、近海で水揚げし加工した干鰯を関西へ帰る廻船に積む仲買業者として、東浦賀に干鰯問屋が生まれました。最初15戸だった問屋は最盛期には倍に増え、一時は全国の干鰯商いを独占するほどにまでなりました。干鰯問屋の数が増えるにつれて船の出入りも多くなり、これらの船の安全を図るため、幕府は湊の入り口に燈明堂を設けました。その維持管理費などの経費は当初幕府の負担でしたが、元禄期からは東浦賀の干鰯問屋が肩代わりし、明治維新までその灯をともし続けました。」「燈明堂江戸時代初期の慶安元年(1648年)、幕府の命により石川六左衛門重勝や能勢小十郎頼隆らによって築かれました。廃止されるまでの200年以上の間、燈明堂は幾度かの暴風、台風、大地震に見舞われながらも修復や建て直しを繰り返し、灯台の役割を果たして来ました。現在の建物は平成元年(1989年)に復元されたものです。その果たした役割により、横須賀市の指定を得、神奈川県の三浦半島八景に指定されています。」手前には、「燈明堂の瓦(燈明堂北側の土台附近で堀出)」次に「浦賀ドック」展示コーナーへ。「浦賀ドック」展示コーナー。【浦賀ドックの町へ】、【湊町浦賀の繁栄】「明治維新を迎えた慶応4年(1868)閏4月、浦賀奉行所は解体され、やがて船改めの業務も終了します。明治3年(1870)、それまで東西に分かれていた浦賀村が合村して新しい浦賀村となります。その後、同9年(1876)に浦賀町となり、同22年(1889)には市町村制の施行にともない大津・走水・鴨居を併せた新しい浦賀町が誕生し、昭和18年(1943)に横須賀市と合併するまで自治体としての役割を果たしました。明治6年(1873)築地町に水兵練習所(後に浦賀屯営と改称)が置かれ、明治22年(1889)からは陸軍の要塞砲兵練習所に引き継がれました。明治30年(1897)、その跡地に消賀ドック(浦賀船渠株式会社)が設立され、以後、浦賀は港と商業の町から工業の町へと変わっていきます。」「奉納 ◯◯丸 明治廿八年 浦賀湊 万屋清左衛門」「江戸時代、湊町として栄えた浦賀には、諸国から多くの廻船が寄港し、おびただしい商品が水揚げられ、多数の商家と土蔵が立ち並ぶ、賑やかな町場に成長していきました。東浦賀に新井町・新町・州崎町・大ヶ谷町・築地古町・西浦賀に築地新町・谷戸町・宮下町・町、田中町・紺屋町・蛇畠町・浜町の町場があり、各町は自治組織によって運営され、祭礼を執り行いました。商家のほかに、旅籠・料理屋・湯屋・髪結などが軒を並べ、「洗濯屋」と呼ばれた遊郭もありました。相撲をはじめ芝居、人形浄瑠璃などの寄席興行が盛んに行なわれました。俳諧や和歌を興ずる結社もあり、句集や歌集も出版されるなど、高い教養をもつ文化人も輩出しています。」「浦賀屯営碑明治8年8月(一説では明治6年)に東京芝新銭座(現在の東京都港区浜松町)から、浦賀に移ってきて、明治9年9月1日に『浦賀水平屯集所』となる。『水平練習所』や『浦賀屯営』、『横須賀海兵隊』などの名称が何度も変更されているが、明治海軍が艦船の運用と海上における戦闘要員(水兵)を養成するための屯集所というは通じて同じ目的だったこの碑は現在、旧浦賀ドック構内にあり、現在公開されていない。また浦賀屯営があったとされる場所は築地新町(浦賀ドック構内)の一部。その内情は良く分かっていなく、病気などで海上勤務ができない兵隊が屯営入りする”屯営や生きた士官の捨てどころ”などと伝えられていたが近年の研究によって、日本各地から集まった優秀な人材を育成した機関だったことが判明しました。」「浦賀ドックでつくられた船たち」「浦賀ドックでつくられた船たち戦前(一部)」。「浦賀ドックでつくられた船たち戦後(一部)」。「浦賀ドック?ドック?浦賀ドックは、主に造船と船の修理を行う工場で、船以外にも鉄骨などの生産も行う総合工場でした。浦賀ドック創業前の日本では、大型の民間船の修理と検査は海軍のドックを利用していました。明治30年代初頭、浦賀と横浜に相次いで民間のドライドックができた後、民間船の修理と検査は、海軍のドックではなく民間のドックを使うよう国が取り決めを行いました。併せて、民間船を定期的に検査するような取り決めも行われました。『ドライドック』とは、船が入った後にポンプで水を抜き船底がむき出しの状態で修理や検査を行う施設です。病院でおこなう体をくまなく調べる検査を『人間ドック』といいますが、「船が長い航海のあと点検・修理のためにドックに入るように、人間も定期的にドックに入る必要がある。」という考えに由来するといわれています。」「俊英たちが集った浦賀《山口辰弥 工学博士》(安政3年~昭和2年 出身地:江戸)横須賀造船所の付属校を卒業後、フランスの「エコール・サントラル」を経てシェルプールの造船学校へ正規留学し、卒業。この造船学校は、フランスの最高学府でも上位成績者しか人れない難関校と言われた。帰国後は、黌舎教授、海軍造船総監、浦賀船渠株式会社の所長として活躍。なお、エコール・サントラルは、東京帝国大学工科大学初代総長の古市公威の母校でもある。《緒明菊三郎・実業家》(弘化2年~明治42年 出身地:伊豆戸田)西洋式帆船のヘダ号建造に参加した緒明嘉吉の子で、のちに海運王と呼ばれる。幼少期から父の元で造船業を学ぶ。父の死後、上京し洋式造船に乗り出す。明治16年(1883年)品川沖に緒明造船所を建造する。さらに、海運業を始める一方、浦賀造船所の創業に尽力。中央図書館のある小高い丘は、彼が所有していたことから「緒明山」と呼ばれる。」「浦賀ドックの誕生」と「浦賀ドックのあゆみ」、「ドライドックの作り方」。「浦賀ドックの誕生《浦賀にできた国内最大級の民間工場》浦賀は古くから湊として栄え、今から301年前の享保5年(1720年)には奉行所も設けられました。嘉永6年(1853年)にはペリー来航の舞台になるとともに、その脅威から洋式軍舟監の必要を悟り、翌年には、浦賀奉行所与カ中島三郎助を中心に日本最初の西洋式の軍艦である「鳳凰丸」が建造されます。日本における造船所の誕生です。そして明治30年(1897年)、「浦賀船渠」(通称浦賀ドック)という造船会社が設立されます。浦賀ドック誕生前の日本では、大規模工場は、国が設立して運営する官営工場が主流でした。これに対して、浦賀ドックは民間が設立、運営する民間工場でした。浦賀ドックは、創業当時、わが国でも最大級の民間工場であったと考えられます。そのため、全国から優秀な人材が集められ、帝国大出身者はもちろんのこと、海外の大学校を卒業した社員もいたほどでした。国内に2つしかない浦賀と川間のドライドックは、世界的にも珍しい赤レンガのドックで、当時の人々もその壮麗さに驚いたことでしよう。」「ドライドックの作り方①ドックの入口になる海域に仕切りの堤防をつくる。《締切堤》②堤防の仕切りの内側にある海水を取り除く。③①と②の作業と同時に本体になる部分を渠頭部から掘削していく。④掘削が終わった所からドックの底から形を整え、石やレンガ、コンクリートなどで作っていく。⑤ドックの底が完成するとドックの壁を底ができたところから同じように作っていく。⑥④~⑤の作業を繰り返してドックの入口まで作業を進める。⑦仕切りの堤防を撤去し、海水をドックに進水させる。⑧ドックの前部分の海域地盤を所定の深さまで浚渫(海底をさらって土砂などを取り除く)する。⑨浮戸(フローティングゲート)を船で⑩完成です! 連れてきてドックの入口に設置する。」「咸臨丸の修理」「浦賀ドックと浦賀の街並み《浦賀ドックとともに誕生した重要な道路の物語》浦賀ドックの誕生と拡張は浦賀地域の都市形成にも大きな影響を及ぼしました。下の写真では、ドックの造成工事に伴って山が削られ、浦賀の重要な道路が誕生していることがわかります。」「浦賀ドックと町の変遷明治33年に操業を開始した浦賀ドックは、干鰯問屋などで栄えた商業港だった浦賀を工業港に変えます。従業員のための病院や生協、社宅、娯楽施設、人港する船の船員のための宿泊施設などがつくられ、ドックの繁栄が町の中心的存在となり、活気あふれる商店街が形成されていきます。大正時代に入ると関東大震災が発生。浦賀工場から出火し、浦賀の町は山崩れとその火災で甚大な被害を受けます。町と浦賀ドックは互いに協力し、早急に復興しました。浦賀は空襲の被害に遭わなかったことから、戦後すぐに工場は再開し、町は賑わいを戻していきました。その後、時代の流れとともに造船業は衰退し、工場の撤退へと向かいます。明治期以降の浦賀の町の変遷は、ドックの盛哀と共にあったといえるでしよう。」「ポンプ室(煙突筒身建立)」「軍艦吾妻入渠」。「船渠掘削工事(海側) 明治30年代」。「1号ドック」。「浦賀船渠株式会社社歌/浦賀ドック音頭 LPレコード浦賀船渠60周年を記念してつくられたレコード。当時一流の作曲・作詞家に依頼し、社歌には三崎生まれで浦賀船渠に学徒動員で浦賀ドックで働いたことのある新進気鋭の歌手・三浦洸一を採用している」。「進水式で使われた鋼球(未使用)ヘッド、軟石ケンの代りに、直径90mのボールべアリング(鋼球)を無数に使用する方法である。ヘッド進水の難点を補うために考え出された最良の方法であり、現在、大型船にまで広く採用されている。設備費は最も高いが、消耗度は少なく、進水性能も安定している。進水台構造等はヘッドの場合と全く同じである。」「営業案内 浦賀船渠株式會社」。「船渠掘削工事(山側) 明治31年代」。「浦賀船渠株式會社第壹號舩之圖」。「浦賀船渠株式会社創業総会決議録明治29年浦賀船渠株式会社が創業する際に取締役などを決議した時の記録。層々たるメンバーに地元の有力者の臼井の名前が連なっている」近づいて。「浦賀ドック」。学研 ずかん ふね(1968年/昭和43年発行)表紙は浦賀ドックの進水式の様子ジャパンダリアは当時あった海運会社・ジャパンラインが昭和42年1月に竣工した全長232mの大型タンカー。この頃になると超大型タンカーの時代に入り、浦賀ドックでは手狭になって来た頃である。この船が出来た時の会社の名称は「涌賀重工業」でした。ガラスケースの中、中央には「竣工記念酒枡浦賀ドックで使われた枡は地元の酒屋が用意し、竣工記念の席では酒樽(四斗樽/約72リットル)が振る舞われる際に関係者に配られました。」左に「護衛艦たかなみ 部隊識別帽」前方には「船が進水式・竣工式で配られた記念品ネクタイピン、カップ」「2003年3月13日 朝日新聞最期の艦船 100年間お疲れさま浦賀ドック住重側 1号ドック保存検討横須賀市浦賀町の通称「浦賀ドック」(現・住友重機械工業浦賀艦船工場)で12日、最後の建造艦船となった海上自衛隊護衛艦が完成した。これで1世紀以上にわたり日本の造船を支えてきた浦賀ドックの業務は終了し、3月末の閉鎖に向けた施設内建物の撤去が始まる。住民の一部から博物館としての跡地利用が提言される中、住重側は同日、歴史的価値の高い一部の施設の保存を検討していることを初めて明らかにした。千隻以上の艦船を建造してきた浦賀ドックが最後に送り出したのは護衛艦「たかなみ」。午前11時から始まった引き渡し式には、海自や米海軍、住重の関係者ら約千人が集まった。今後は9万6千平方メートルの敷地にある工場施設の撤去作業と並行して、市と跡地利用の検討を進めるという。浦賀ドックの跡地利用をめぐっては、周辺住民の一部が、クレーンや船台などをすべて保存して博物館にすることを強く訴えてきた。これに対して住重側は12日、れんが造りの1号ドックと、その両脇に建てられたクレーン2基を保存する方向で市側と検討することを表明。ほかのクレーン5基や船台などは撤去するとしている。1897年に造船会社「浦賀船渠」として設立されて以来、地元では「浦賀ドック」の通称で親しまれてきた。その後、合併を繰り返し、1969年に住友重機械工業浦賀艦船工場となった。青函連絡船や練習帆船「日本丸」などの艦船建造をはじめ、国会議事堂の鉄骨工事、米空母ミッドウェーの改造工事、横浜ベイブリッジや明石大橋の製作などにかかわってきた。」海上自衛隊の「護衛艦たかなみ(JS Takanami, DD-110)」以前に訪ねた時の写真から。「たかなみ」は、中期防衛力整備計画に基づく平成10年度計画4,600トン型護衛艦2239号として、IHIMUに発注され、住友重機械工業追浜工場で2000年4月25日に起工され、2001年7月26日に進水、その後、住友重機械工業浦賀工場において艤装の後、2002年8月20日公試開始、2003年3月12日に就役し、第1護衛隊群第5護衛隊に編入され横須賀に配備された。「最後に作られた船、たかなみ2003年(平成15年) 3月12日、浦賀ドックで最後の建造となる護衛艦「たかなみ」が竣工され、同月31日浦賀工場は閉鎖しました。浦賀で生まれた「最後の船・たかなみ」は現在も現役で活躍する自衛隊たかなみ型護衛艦の1番艦として活躍中です。艦名の由来「高く立つ波」(高波)、そしてこの名を受け継ぐ日本の艦艇とし同じ浦賀で生まれたタ雲型駆逐艦「高波」、あやなみ型護衛艦「あやなみ」(三井造船玉野造船所)に続き3代目に当たります。たかなみは第一線で活躍する海外への派遣に行くことが多い艦船です。」「ミニ企画展示パトリア PATRIA空襲の被害を受けけなかった浦賀ドックは、戦後すぐに造船を再開しました。しかし、海軍の解体・海運業の壊減て大型船の受注がなくなり、手持ちの資材て細々と鍋などの家財や小さな漁船を造って会社を維持していました。ようやく受注にこぎつけても、急激なインフレや資材コストの上昇についていくことができず、なかなか会社の立て直しには至りませんてした。その頃、米ソ冷戦や朝鮮戦争が勃発したことによりアメリカによる対日政策が緩和されます。政府は、自らが全額出資した船舶公団て需要を造り日本の造船業は活気を取リ戻し始めます。昭和31年の「もはや戦後てはない」というキャッチフレーズに乗り、日本の高度成長期と共に浦賀ドックの規模も拡大していきます。当館に展示されている模型「パトリア」も、その時期に造られました。スーパータンカー「バトリア」の誕生についてご紹介します。」「SCENE URAGA昭和34年1月、総額約10億円の資金と1年3ヶ月の月日を投じてマンモス船台の建設工事は完成した。土木関係工事に於いて延べ105,000人を動員、使用鋼材1,200トン、その他を合わせて約6万トンの資材を要した。マンモス船台の完成により、マンモスタンカー「PATRIA」が進水した」「パトリア(PATRIA)船籍:リベリア竣工:昭和34年9月25日竣工船首:ZAS TANKER CORP(イスラエル)DWT:46,283.8LT(積載重量トン数)」浦賀初のスーパータンカー浦賀のDELAVALタービン1番機搭載浦賀発のスーパータンカー(油槽船)40万2707バレル(浦賀プール約178杯分)の原油を輸送浦賀DELAVALタービン1番機搭載油槽船(オイルタンカー)液体の油類をタンクに積んで輸送する船。事故などで液体物質が漏れると甚大な環境汚染になることから、二重構造となっている。世界最大のタンカー ”Seawise Giant” ( 656,000トン)同船は、当初422,000トンのタンカーとして住友重機械追浜造船所て建造されたが、竣工直前に香港企業に転売され、日本鋼管津製作所て船体延長工事が行われた。工事後の船体は全長458.5m、幅68.8 m現在は解体されているが、記録は破られていない。「超大型タンカー時代に向けて、今まであった第2・第3船台を合わせて更に幅を拡張し、昭和34年1月に総額約10億円を掛けて「マンモス船台」がつくられました。当時、世界でも屈指のこの大型船台でパトリアは建造されました。パトリアは、下から積み重ねていくエ法て造られました。建物のように出来上がっていく姿は壮大だったそうてす。」「昭和34年3月24日、パトリアは晴れて進水式を迎えました。三笠宮妃殿下によって支綱切断が執り行われました。」「パトリア」。船首側から。「パトリア号 進水」についての浦賀船渠・昭和34年4月発行の社内報記事。「浦賀船渠 昭和34年4月発行この社報は戦後昭和28年から浦賀船渠(浦賀ドック)で発刊され、ドックで作った船の情報や人事、社内で行われたイベントなどを伝えておりました。この展示している第73号は当時スーパータンカーと呼ばれたサイズのパトリア号の進水式の様子を伝えています。パトリアは浦賀ドックでも大口の受注だったことが紙面からうかがえます。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.09
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その38):浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)1/3
この日の最後に「浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)」を訪ねた。浦賀コミュニティセンター分館((愛称)浦賀文化センター)は、昭和57年(1982)4月1日に設立された文化施設で、浦賀地域の郷土資料館としての役割を担っている施設。建物の延面積は、504.23平方メートル。この施設は、展示室と3つの学習室(一般用貸室)から構成されます。まず、展示室には、浦賀奉行所関係の模型、中島三郎助関係の資料、鳳凰丸・咸臨丸・ペリー艦隊の船舶の模型等の展示がなされていた。地元の郷土史家等が特別展示等を企画するときもあるとのこと。横須賀市浦賀7丁目2−1。この場所はかつて、旧浦賀ドックの迎賓館であった「表倶楽部」の跡地だとのこと。正面玄関を見る。玄関には顔抜きパネルが。渋沢栄一(右)と勝海舟(左)。横須賀の鏝絵・辰巳忠志氏の作品が並んでいた。上段に「親子龍」、下段右から「花鳥風月」、「龍虎」、「降り竜」。「親子龍」。「花鳥風月」。「龍虎」。「降り竜」。「柿たわわ」。「浦賀の鏝絵めぐり左官職人が、壁などの仕上げに鏝で漆喰を塗り上げて作った彫刻風の絵を鏝絵(こてえ)といいます。江戸時代末期の左官職人入江長八(伊豆の長八)によって作られたのが鏝絵の起源だといわれています。長八に始まった鏝絵は、その弟子達や多くの左官載人によって全国へ広まっていきました。江戸時代より、浦賀には豪商の屋敵や土蔵が立ち並び漆喰を塗る職人が多くいました。明治期に入ると浦賀でも石川善吉らの手によって盛んに鏝絵作りが行われるようになりました。現在に残る鏝絵から、当時の浦賀の繁栄を偲ぶことができます。」「西叶神社」👈️リンク「東福寺」👈️リンク「常福寺」👈️リンク「川間町内会館」👈️リンク「八雲神社」👈️リンク「東耀稲荷」👈️リンク「法憧寺」👈️リンク「大六天神社」👈️リンク2階に郷土資料館があった。「浦賀周辺地図」。階段を上りながら浦賀地区の祭りの展示パネルを見る。「榊神社大禄天祭札 [ 5月/中旬土・日]川間の鎮守。土曜日には例祭式、神楽が奉納され、日曜日は神輿・山車が神社参拝後に町内を巡行する。また、木遣りの伝承保存に努めており、祭礼はもとより多くの祝い事で唄われている。」東叶神社例大祭[9月/第2土・日]東浦賀の総鎮守。各町内の山車彫刻が見事。東浦賀には、御座船があり、明治の頃には、海上を渡御したそうだ。彫り物が施された船に提灯が灯されてその明かりが水面に映り、お船唄が流れ皆うっとりと聞き入ったそうだ。西叶神社と同日に行われ、西東の浦賀の町が祭り一色となる。西叶神社例大祭[9月/第2土・日]西浦賀の総鎮守。例大祭には、「拝殿神楽祭」の年と三年に一度の「御神幸祭(大祭り)」の年がある。厳かに神事が執り行われた後に、町内神輿が一堂に会する様は壮観である。為朝神社祭礼[6月/第2土・日]浜町の鎮守。祭礼では「虎踊り」が奉納され、境内に設置された特設舞台で、唐子の踊りや親子虎の大胆な舞が演じられる。奉行所が下田から移された時に一緒に伝えられたといわれている。県の重要無形民俗文化財に指定されている。八雲神社の例大祭[ 6月/第2土・日]東浦賀の鎮守である八雲神社で行われる祭りで、「猩々坊(しょうじょぼう)」という大きな人形を乗せた山車が練り歩くのが特徴。この猩々坊は、疱瘡除けや不老不死の力があるといわれている。【仮面神楽「とっぴきぴー踊り」】お囃子のリズムに合わせて身振り手振りで情景を滑稽に表現する無言劇で、磯の香、土の匂いのしみ込んだ素朴な芸能です。文化文政の頃から、脇方の里人により須賀神社に拳納されてきたものです。【お浜降り】神社神興が白装束の白丁に担がれ静かに海へ入ってゆきます。その後、鴨居全域の神興が次々と海へ入り、禊をします。「浦賀文化 最新号鳳凰丸の建造①ー建造掛の人選こぼれ話ー嘉永六年(一八五三年)六月にペリー艦隊の軍艦による江戸への接近を目の当たりにして強い危機感を覚えた幕府は江戸の防備を充実させるべく同年九月十五日、これまで禁止していた大船の建造を解禁した。これをきっかけに浦賀で日本初の洋式軍艦「鳳凰丸」が建造されることになるのだが、浦賀泰行所内ではこれに先駆けて建造の準備を進めており、九月七日には軍艦建造掛が選出されていた。メンバーは、与カからは香山栄左衛門、田中信吾、中島三郎助、佐々倉桐太郎の四名、同心からは斎藤太郎助、中田佳太夫、田中半右衛門、春山弁蔵、岩田平作、田中来助の六名だった。その翌月、浅野勇之助、大久保釭之助を加えたメンバーが老中阿部正弘から正式に「御軍艦并晨風丸形御船其外附属之品御製造御用掛」に任命され、この船の建造は幕府の正式な事業となった。ただこの時、与力の田中信吾だけは「御軍艦并晨風丸御船御打建御申請中身廻」、つまり軍艦建造中の見廻り役にされたとある。田中信吾は中島三郎助の父である中島清司とも名を連ねて異国船の対応に尽力してきた与力だったが、彼がこのような役回りとなったのは事情があったらしい。ペリー来航当時の浦賀奉行戸田氏栄が同職江戸詰の井戸弘道に宛てた私信「南浦書信」の十一月二日付けの書翰の中で次のように記している。「田信(田中信吾)は御普請掛りさしゆるし、其他は緩々保養可致旨相達し、よくよく利解仕候、当春以以来の事なから、亜船にて長ロ出勤いたし候事ニて、前日之引込は水ニ成候故、御暇申渡も余り早過候故、何分不都合、夫ら之処再々応組頭江申渡置候、」これによると田中はかねてより「引込」すなわち引退を考えていたらしい。しかし「亜船」(ペリー艦隊)への対があって引退は流れてしまった。それもあって「御普請掛」、つまり軍建造掛を「さしゆるし」たという。引退を考えていた田中自身は建造掛になることに難色を示したが、この役ならと了承したのだろうか、見廻りという役に就いている。理由はわからないが少なくとも戸田としては田中に引退されると困るタイミングだったのだろう。田中のことはしばらく戸田を悩ませたらしくこの後も「南浦書信」に話題が出てくる。十一月十二日付けの書翰では田中について「魯船之沙汰承り、一日も早く引込度趣ニて、御暇伺書さし出し申候、」とある。この時にはロシア船ディアナ号が下田での地震により大破したため、その修理場所などについて対応を協議していた時で、そんな状況で田中が一日も早く引退したいと伺書を差し出してきたという。支配組頭や香山栄左衛門もいろいろと説得したが、一日も早く引退したいと聞かず、戸田も「不忠至極」とは思うが今まで引き留めていることでもあるのでどうしたらよいものかと途方に暮れている。また、田中は与力の中でも地方掛であったようで、同日の書翰で戸田は引退については、是非のないこととしながらも「跡地方の申すものニ甚だ差支、申候、」と田中がやめた後の地方掛に支障があるとしている。理由としては、地方掛は本来の地方行政に関する業務だけでなく諸々の見積や普請の担当なども兼ねるため業務が多岐にわたり、人数を減らすことができない状況にあった。支配組頭が業務を引き受けてくれれば良いがこちらも頼りにならず、後任にできる人物もいないため「是ニは困り申し候」と困惑している。その後も「南浦書信」を見ると、田中のことで戸田は井戸に相談をしていたようではあるが、詳しいことはわからない。ただ田中は嘉永七年正月のペリー再来航前には引退していたのか、御褒美の記録や以後の鳳凰丸関係の記録にも田中信吾の名前は出てこない。「浦賀奉行所跡の発掘調査(その五)幕末から明治時代以降の浦賀奉行所跡慶応四年(一八六八年)閏四月に浦賀奉行所は廃止されました。その跡地は海軍用地・用地・民有地と変遷し、昭和一六年(一九四一年)~ニ〇年(一九四五年)頃には浦賀ドックの工員宿舎が建てられ、昭和四一年(一九六六年)からは浦賀重工業株式会社、後に住友重機槭工業株式会社浦賀工場の社宅になります。平成ニ九年(二〇一七年)年一二月にその跡地が横須賀市に寄贈されて現在に至っています。図1は、それらの建物の配置図です。浦賀ドック工員宿舎の建物は、米軍撮影の航空写真に解体中の姿が朧げに残されているだけで詳細な記録は確認できません。構造は不明ですが、発見された基礎跡などから、幅約10・8m、長さ約36・5 mの建物六棟とL字状の建物が浦賀役所跡地全面に配置されていたことが判明しました。建物は厚さ5cm前後のコンクリート土台の上に赤煉瓦やアス煉瓦(石炭ガラと消石灰が原料)を積んだ基礎の上に建てられた木造建築であったと思われます。黒枠で囲った南西部の調査区を詳細に表したのが図2の平面図になります。安政二年(一八五五年)の増改築時に新たに掘られた素掘りの西堀の一部と塀跡の柱穴列などが確認され、その東側からは浦賀ドック工員宿舎のレンガ積基礎と常滑焼土管の排水管、住友重機槭工株式会社浦賀工場社宅の鉄筋コンクリート製の基礎などが並んで確認されました。(写真1)幕末期から平成時代に至る浦賀奉行所とその跡地の履歴が窺える調査箇所です。次回からは各時代の主な出土物について紹介していきます。「Dockcafe4大正六年(一九一七年)、逓信省官療であった今岡純一郎が浦賀船渠山下亀三郎社長に抜擢されて専務となった。今岡は、その五年後、七代目社長に就任する。当時、船舶業界は低迷期であり、浦賀船渠の経営もまた厳しい状況であった。そのような中にあっても、経費削減や勤務改革、陸上の機槭製造等を兼営するなどして工場能力を維持した。また、帝大造船科卒だった今岡の知識を活かし船の性能を向上させるなどの構造改革にも着手、多くの新技術の開発を成功させる。その結果、浦賀ドックの代名詞ともいえる駆遂艦や青函連絡船の建造の更なる受注に繋がっていった。そんな折、大正十ニ年九月、関東大震災が襲来、浦賀船渠は壊滅的被害を受ける。重ねて工場内からの出火と近隣からの延焼で工場の大部分を失う。社長自ら復興に向けて従業員に理解と協力を求める掲示を行っている。今岡の手腕と尽力により、浦賀船渠は再び活気を取り戻し、造船所としての地位を確立した。しかし、その栄光の時を待たずして、今岡は昭和九年、六十歳の現職のときにこの世を去った。」浦賀コミュニティセンター分館(浦賀郷土資料館)にあった中島三郎助招魂碑の拓本。「浦賀船渠 昭和34年4月10日(金曜日)」「浦賀船渠 昭34年4月発行この社報は戦後昭和28年から浦賀船渠(浦賀ドック)で発刊され、ドックで作った船の情報や人事、社内で行われたイベントなどを伝えておりました。この展示している第7 3号は当時スーパータンカーと呼ばれたサイズのパトリア号の進水式の様子を伝えています。パトリアは浦質ドックでも大口の受注だったことが紙面からうかがえます。」そして2階の展示室入口前右側にあった「上の台遺跡考古資料」。横須賀市鴨居二丁目。市立上の台中学校の敷地が鴨居上の台遺跡。昭和五十一年二月、市内の埋蔵文化財分布調査中に発見された遺跡。本遺跡は縄文時代早期・中期、弥生時代中期 から古墳時代前期、および奈良時代の各時代・時期にわたって居住、利用された場所である。 本遺跡は台地上に広く占地し、その範囲は約八千平方㍍程度と思われる。本遺跡の主体は弥生時代から古墳時代前期にかけての集落址であり、 住居址総数は百を超える。この集落址は、三浦半島東岸において最大規模のものと思われ、かつ保存状態は良好であったとのこと。 出土された土器のかけらは五万六千個以上、整理箱に四百四十箱。堅穴住居址は百四十一軒も発掘された。 縄文時代の遺物としては土器が三千五百七十八点、石器が四十七点も出土した。 縄文式土器の場合、かけらを集めて復元できるものはなかった、という。 土器は、①縄文と撚(より)糸文②押型文③無文④沈線文や貝殻文⑤貝殻条痕文⑥中期以降のもの、の六つに分けて整理された。 また、土器の底の部分が五十七点も。特徴は丸底のものは撚糸文系、乳房状の尖(せん)底は条痕文、厚みが変わらずにとがるものは、沈線文や貝殻文など。石器で縄文時代のものと思われるのは四十七点。内訳は礫器十点、刃部磨製礫斧二点、石鏃十五点、石槍一点、削り器五点、加工痕のある剥片十点、その他。上の台遺跡の発掘調査は、昭和52年10月から翌年9月まで行われた。出土された土器片は5万6千個以上、住居址は141軒。写真は、見事に日の目をみた住居址。柱の穴がはっきり見える。そして「浦賀奉行所」を模した展示室の入口。浦賀奉行所与力・中島三郎助が迎えてくれた。廻船問屋・宮井家「萬清」の当時の生活用品と。「ここに展示されている陶器類は、宮井家に伝わっているものの一部であり、時代は天明期(1781)より明治期までのものである。当家は、元禄5年(1692)、紀州 宮原の地より東浦賀に移住した「宮与」こと宮原屋 宮井与右衛門の分家として、寛延2年(1749)西浦賀 紺屋町へ独立した萬屋 宮井清左衛門家であり、代々清左衛門を世襲し「萬清」の屋号で知られ、昭和の初期まで米・酒・塩の問屋として持船3艘を動かし、関西から東北地方まで手広く商売を営んでいた。家紋は左三巴で、商標は井桁である。」廻船問屋 宮井家(萬清) 所蔵品物。まずは「中島三郎助」の展示コーナー。中島三郎助が活躍していたころに見られた浦賀奉行所の様子、奉行所のある町に根ざす文化にもスポットを当てていた。この展示では、奉行所の役人であると同時に、俳句活動などを通じて文人としてもその名が知られていた中島三郎助の一面にも触れることができた。さらに、浦賀奉行所で作成された文書や中島三郎助の遺書など、貴重な資料の展示により、改めて奉行所のまち・浦賀を知ることが出来たのであった。浦賀奉行所の役人(与力)としてペリーの来航時に黒船に乗り込み、折衝に当たった中島三郎助。「中島三郎助の生涯(略年表)」そして彼の持っていた短刀が展示されていた。中島三郎助の生涯は、日本に近代化の嵐が吹き荒れる激動の時代に、その真っ只中を幕府の役人(与力)として、また一人の武士として忠実に生き抜いた49年間でした。幕末の文政4年(1821年)に浦賀奉行所の与力・中島清司の次男として生まれた三郎助は、14歳で奉行所に出仕します。その後、アメリカ船モリソン号砲撃事件(天保8年(1837年))、アメリカ人ビッドルの来航(弘化3年(1846年))、さらに、嘉永6年(1853年)のペリー来航を目の当たりにして、日本でも大型軍艦を持つことの必要性を説きました。そして、軍艦造船にあたり委員の一人として活躍、翌年の5月には着工以来わずか8カ月という短期間で、日本人の手による最初の洋式軍艦「鳳凰丸」の誕生となります。この後、三郎助は長崎海軍伝習所の第1回生として派遣され、勝海舟や榎本武揚らとともに造船・操船技術を習得し、近代造船学の指導的な立場になりました。一方、三郎助は父の教育を受け、幼少の頃から和歌、俳諧、漢詩文など風雅の道にも才能を発揮しました。ことに俳諧においては俳人・木鶏の名をほしいままにし、江戸にまでその名が知られていました。福沢諭吉が残した『福翁自伝』にも浦賀の立派な武士として書き記されています。慶応4年(1868年)に明治新政府が樹立されると、榎本武揚らとともに函館に向かい、旧幕府勢力を中心とした政府の樹立を目指します。しかし、翌年の5月に二人の息子恒太郎、英次郎とともに新政府軍の砲弾に倒れ、49年の生涯を閉じました。その後、明治24年(1891年)に、中島三郎助を追慕する人々の手により浦賀港を見渡す愛宕山公園に中島君招魂碑が建てられました。中島三郎助を近代造船の父と慕い、彼の業績を偲ぶ人々の手により造船所の建設が提案され、浦賀は日本を代表する造船の町として新たなスタートを切ることになります。さらに「中島三郎助」の展示コーナーを進む。浦賀奉行所与力の紋付き袴が。「与力中島三郎助中島三郎助は文政4年(1821)浦賀拳行所筆頭与力、中島清司の次男として浦賀に生れた。天保6年14歳の時、与カ見習として奉行所に出仕し父と同じ道を歩むこととなった。嘉永6年(1853)、ペリーの率いる黒船が浦賀に来航した際、三郎助は応接掛として、折衝の任に当たり、黒船に乗船し艦内を調べて回るなど、このことが三郎助の生涯に大きな影響を与えることとなった。嘉永7年(1854)、幕府が日本最初の洋式軍繿「鳳凰丸」を浦賀で建造するに当り、その建造主任となり、安政2年(1855)には勝海舟、榎本武揚らと共に長崎海軍伝習所に派遣され、造船術を学んだのちに浦賀港において、咸臨丸を修理するなど、造船、操船の第一人者として活躍しました。慶応4年(1868)幕府が大政を拳還するに及び榎本武揚と共に江戸を脱出、函館五稜郭に籠城し二子恒太郎(22才)、英次郎(19才)共々官軍と戦い、戦死しました。時に明治2年( 1869 ) 5月16日、49歳でした。三郎助はまた文人として和漢の学に造詣が深く、ことに、”俳人木鶏″として国事混乱の世にあって折にふれ俳諧に想いを託し、遺詠の数々が当時の彼の心情や交際範囲の広さを余すところなく今に伝えております。」「中島家累代系譜」中島 三郎助(なかじま さぶろうすけ)は、江戸時代末期(幕末)の幕臣。江戸幕府 小十人格軍艦役、のち蝦夷共和国 箱館奉行並。諱は永胤。【与力中島三郎助の活躍と生涯浦賀で代表的な有名人物といえば、浦賀奉行所与力の中島三郎助を挙げることができます。彼は、応接掛与力として、ペリー来航の際、最初に「黒船」に乗り、折衝にあたるなどの敏腕ぶりを見せました。その後、日本初の洋式・鳳凰丸の建造に従事し、さらに長崎海軍伝習所で航海術を学び、幕府海軍の軍艦役に取り立てられています。一方、和歌、俳諧、漢詩文など風雅の道にも才能を発揮しました。ことに俳諧において、「木鶏」の俳号は江戸にまでその名を知られていました。明治維新の戊辰戦争では、榎本武揚の率いる脱走艦隊に乗って箱館戦争を戦いました。その最後の決戦において、ニ人の子息を含む浦賀関係者十数人とともに千代ヶ岡陣地で戦い、命を失った。その死闘は永く世に伝えられる。】「中島君招魂碑外務大臣海軍中将従二位勲一等子爵 榎本武揚 篆額箱館戦争前(1868年)の榎本武揚(1836-1908)の写真。函館戦争で中島三郎助と共に戦い、その意思を継いで浦賀造船所(浦賀船渠株式会社)の設立に尽力したとされる。「中島永胤君招魂碑の「発起者」の碑碑文は、江戸時代後期の浦賀歌壇のリーダーでもあった西野前知が書いています。「中島永胤君招魂の碑建てんことおもひ立ちしは明治ニ十三年九月にして成功をとげしは同ニ十四年七月なり(後略)」に始まり、浦賀港を見下ろせる愛宕山に、石をすえ土をならし、花木を植え、東屋を造り、道を整備するなどなど、公園を建設する様子と招魂碑の趣旨が、発起者36名の名前と共に記されています。愛宕山公園(浦賀園)は、浦賀の人々に敬慕されていた中島三郎助の事跡を、後世に伝える招魂碑を建立するために整備され、明治24年(1891年)に開園した、横須賀市で最も古い公園です。所在地 愛宕山公園大きさ 176 cm x 130 cm x 11 cm建立年 明治24年(1891)」。「奉行所与力の服装」「幕臣中嶌三郎助👈️リンク明治年古函館ニ於テ戦死兄弟三名倶ニ死ス◯忠勇比類無シト言傳フ」1853(嘉永6)年の黒船来航時、浦賀奉行所与力の中島三郎助はペリー側の「最高位の役人以外とは面会しない」との強固な姿勢に対し、同行した役人を「副奉行である」と嘘をつき黒船に最初に乗船した日本人です。中島は、大砲などの装備を探るため、ちょこまかと動きまわるのでペリー側の記録には「大胆で出しゃばりしつこく詮索好き」と残されています。しかし、その行動は、西洋型軍艦鳳凰丸の建造に大いに役立ちました。その後、勝海舟・榎本武揚らとともに長崎の海軍伝習所へ派遣され、江戸に戻ってからは海軍操練所教授方として後輩の指導にあたり、海国日本の造船・操船の第一人者となりました。戊辰戦争で函館五稜郭にて新政府軍を迎え撃ちますが武運尽き、ふたりの子供ともども壮絶な死を遂げました。「横須賀市浦賀地域と函館市中島町との姉妹地域関係に関する盟約書幕末の英才・中嶌三郎助翁は近代国家を誕生させる荒波の中に、その生涯を捧げ、功績は日増しに高くなってきています。生誕の地、横須賀浦賀地域を中心に活動を続ける「中島三郎助研究会」、「中島三郎助と遊ぶ会」と戦没の地函館市中島町会は、ともに中島三郎助翁が、黒船来航の折に最初の交渉役として果たした役割やその後近代日本の幕開けにふさわしい造船技術者として果たした役割やその後近代日本の幕開けにふさわしい造船技術者として、また開運設立の先覚者として残した数々の功績を顕彰し、さらに多くの市民の方に理解を深める活動をしてきました。この二つの地域の趣旨を同じくする会が、地域の諸団体の協力のもと交流を深め・・・・・・・・・偉業を顕彰、理解の輪を各分野に広め、発展させることを盟約し姉妹の会として活動をいたします。 平成8年7月20日以下略」「本日、御地において中島三郎助父子墓前祭が開催されるにあたり、一言ごあいさつ申しあげます。昨年は当町主催によります、中島三郎助碑前祭に浦賀より東林寺参詣団様始め多数のご列席を賜り厚くお礼申し上げます。その折、横須賀市長様よりご丁重なるメッセージ、並びに東林寺ご住職様よりお心のこもった和歌を頂戴し感謝に胸震えております。本年も、本日同時刻、中島町の中島三郎助父子最期の地碑前において慰霊祭を執り行っております。このように三郎助父子の生誕地と戦没地に於いて同時に慰霊の行事が行われることに深い感慨を覚えます。浦賀が生んだ最高のテクノクラート、有能な幕臣、中島は数多の業績を残し、幕末の動乱には主家報恩の殉節を貫き榎本などとともに函館に赴き歴戦を重ねましたが、明治二年五月一六日ここ千代が岡陣屋において父子共々壮絶な最期を遂げました。激しい敵の攻撃に投降兵や逃亡兵の多い中、浦賀出身の者で固めた中島隊の部下には、遁れたものなかったとききます。いかに平生の恩遇が深かったか偲ばれます。この激戦を最後に幕末維新の動乱も終局を収め、近代日本の幕開けとなりますが、もし三郎助存命であれば必ず新政府軍の重鎮、或いは造船界の嚆矢として、近代国家建設の大役に従事されたことと思えば、その死惜しみてあまりあります。函館市は昭和六年、新町名制定のとき、三郎助の遺徳を讃え、その最期の地を中島町と命名致しました。東林寺ご住職のご来函の折り、十首の和歌を詠じられましたが、そのうち一首に丈夫の 赤き血潮の 溢れ染む 中島町の 弥榮にこそと歌われ、私共にお励ましのお言葉を賜りました。このことを肝に銘じ、私達町民は御地において大切に大切に尊敬、敬愛されている中島三郎助の名に恥じぬように街の伸展に意を注いで行く所存で御座います。終わりに、硝煙砲火の中、古武士の骨を焚き了わり、義に殉じて北の果てに放華せし御魂よ靖かれとお祈りし、三郎助永胤の辞世の歌を詠唱してメッセージと致します。空蝉の かりの衣を ぬぎ捨てて 名をや残さん 千代ヶ岡辺に 平成五年五月十五日 函館市中島町 町会長 船山圭右」短刀。相模國廣光 長六尺・・・。大田戴陽老人・・・・・「大田戴陽老人追悼文軸大田戴陽老人は蜀山先生の嫡孫にして、無為の天資をつぎ、滑稽洒落の雅情を専とし、夙に官袴を脱し、ひとり風月の閑静を愛したまふこと既に幾春秋か。ことし弥生の花のうつろふ頃よりやまふの床につかれけるが、五月四日といふ日、終に残花の芳香を百草にうつして、はかなくも彼の岸に赴かれしそ、親戚のなけきはいふへくもあらされど、郷里の人、誰かなけき惜まさらんや。さみたれや ほのかに西の 月あかり」「中島三郎助函館よりの手紙」。「中島三郎助函館よりの手紙慶応4年8月に江戸を脱出した一行がさまざまな事態に当面しながら、本州最後の地、宮古へ到着したのが10月12日でした。この地から三郎助が妻すずにあてた近況報告の手紙です。この手紙からも最終目的地、蝦夷へ出発するにあたっての困難ではあるが新開地を求めた三郎助の覚悟の程がよく表われています。一筆申進候 追々寒気相増候得とも、いよいよ御替りなふ御くらしと目出度そんじ候、次に此かた一同無事に而、当節は南部宮古と申所に罷在申候両三日之内にハゑぞと申へ参り候つもり、是は定而寒気つよくと心配いたし候、乍然、八月初旬持病相おこり候のみに而、丈夫ニ御座候まゝ、先達而恒太郎其方へ参り、御めもじいたし候由、いさゐ承り、大安心いたし候、美加保丸ハなん船いたし候よし、平田其外 乗組之者 如何哉とあんじ申候一、越後辺之いくさニ而、小笠原甫三郎の忰、新太郎 高林磯次郎等うち死いたし候よし、和田 伝兵衛ハ無事ニ而回天丸ニ居り申候、一、子供一同無事とそんじ候、与曽八も定而丈夫に成長とそんじ候一、江戸へよきたより有之候ニ付、御母上様江書状差上申候、御安心可被下候、一、我等並恒太郎、英二郎等、万々一うち死いたし候へハ、浦賀之寺へ墓御立可被下候 右の通り御頼申候、先は幸便ニまかせ、早々めでたく かしく 三郎助時雨月十六日おすゝ殿尚々時かふ御いとひ可被成候、お順始一同へよろしく御申伝可被下候 以上」一筆申し上げます。日増しに寒くなってきましたが、お変りなくお過ごしこととお喜び申し上げます。私たち一同は無事で、今は南部の宮古というところに来ています。ニ、三日のうちには蝦夷という土地に行くつもりです。そこは、とても寒いところと心配しています。しかし、八月上旬に持病が起きた以外は健康に過ごしています。先日恒太郎がそちらへ行き、お目に掛かったとのこと、くわしく聞いてとても安心しました。美加保丸が難船したとのこと、平田そのほかの乗組員はどうしたのかと案じています。一 越後の戦いで、小笠原甫三郎のせがれ新太郎、高林磯次郎らが討ち死にしたとのこと。 和田伝兵衛は無事で回天丸にいます。一 子どもたちは無事と思います。与曾八も丈夫に成長していることと思います。一 江戸へはよい知らせがありますので、母上に手紙を出しました。ご安心ください。一 私、恒太郎、英次郎らが、万が一討死した時には、浦賀の寺に墓を建ててください。このような状況ですから、どこで討死あるいは戦いの中で死去した旨、墓に刻んでください。まずは幸便にまかせて 三郎助時雨月(十月)十六日お寿々どのなお、時節柄お大事にしてください。お順はじめ一同にもよろしくお伝えください。「中島三郎助 遺言状榎本武揚が朝廷に上奏した願いが脚下され官軍による討伐を予想した三郎助が家炭へあてた遺書です。文面からわずか二歳の与曽八に短刀を贈り、家族へ決別の辞を述べ、また後段では、終生徳川家に忠勤を励む幕臣の姿をみることができます。」。「中島三郎助 遺言状」。「この短刀を与曾八への形見として贈ります。私は長いこと病弱で若死にしてしまうだろうと思っていましたが、はからずも四十九年の歳月を生きながらえたことは幸いと思っています。このたびの決戦では、潔く討死する覚悟をしています。与曾八が成長したのち、私のわずかな志を継いで、徳川家のこのうえもなく大きなご恩を忘れずに長い間忠勤してくれるよう頼みます。 明治ニ年三月三日 中島三郎助 永胤なお、御母上様、積年の恩恵に報えずにお先に遠い旅路に赴くこと、恐れ入ります。ということをよろしく申し上げてください。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.08
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その8)
「百花繚乱」、「今を盛り」に咲き乱れて。「かれん Karen」。花形 半八重咲き花径 中輪香り 微香開花 四季咲き と。「かれん Karen」日:平林 浩 1995年作出。「ロアルト ダール Roald Dahl」。1輪か3~5輪の房状で咲き、形の良いカップ咲きの花は開花と共に白く退色する。中香だが質の良いフルーツ香、ティー香がありややうつむいて咲く。半横張り性で自然樹形となり、枝のトゲは少ない。返り咲き性が強く秋までポツポツと花を付ける。誘引すれば小型のつるバラとしても利用できる。品種名はイギリスの小説家にちなむ と。「ロアルト ダール Roald Dahl」英:オースチン 2016年作出。ここにも少女像。「タモラ Tamora」。初期のイングリッシュローズ。四季咲、花径8〜10cm、アプリコット、八重カップ咲、樹高1mぐらい。ミルラ香。「タモラ Tamora」英:オースチン 1983年作出。「スノーグース Snow Goose」。甘いムスク系の香り。「モーヴァン・ヒル」のように、大きくなり、繰り返し咲きます。大きなスプレーになり、輝くような白い花がつきます。外側の花弁は少し長めで、しべが中心に覗くと可愛らしい印象のデージーのような外見になります。枝はとげが少なめで、まっすぐですので、アーチや壁面、フェンス、トレリスなどに簡単に誘引することができます と。「スノーグース Snow Goose」英:オースチン 1997年作出。そして「皇族の名を冠したバラ、プリンセスローズ」👈️リンク のコーナーへ。「プリンセス アイコ Princess Aiko」現天皇皇后両陛下の御長女・敬宮愛子内親王殿下のご誕生を祝して名付けられたバラです。蕾から巻いた花弁が開いていく様子が優雅でとても美しく、愛らしい内親王様そのもののイメージの花です。花つきがすばらしく多く、長く咲き続けます。2001年JRC銅賞受賞 と。「プリンセス アイコ Princess Aiko」日:京成バラ園芸 2002年作出。「プリンセス ミチコ Princess Michiko」。「プリンセス ミチコ」は、バラの品種。フロリバンダ系の品種で、花の色は濃いオレンジ色。 1966年にイギリスのディクソン社から当時日本の皇太子妃だった現上皇后美智子に献呈された。柔らかな香り、オレンジ色で丸みを帯びた花弁が特徴。上皇后美智子の名を関したバラにはこのほかにエンプレスミチコがある。「プリンセス ミチコ Princess Michiko」英:ディクソン 1966作出。「エンプレス ミチコ Empress Michiko」。プリンセスミチコと同様、美智子皇后陛下が、立后された後、新たにイギリスの同育種家により贈られたバラです。花は淡いアプリコットをしのばせたピンクで、穏やかで上品な美しいバ ラです。花付き良く、数輪の房咲きになる。コンパクトに育ちますので、鉢植えにも向きます。「エンプレス ミチコ Empress Michiko」英:ディクソン 1992年作出。「マサコ Eglantyne」。今上陛下が皇太子としてご成婚の際、皇太子妃雅子殿下(当時)にちなんで名付けられたバラです。別名は「エグランタイン」とも呼ばれています。「マサコ Eglantyne」英:オースチン 1994年作出。「ジュビレ デュ プリンス ドゥ モナコ Jubile du Prince de Monaco」。複色花でこれほどまでに白赤の発色が鮮明な品種は他にはありません。濃緑色の照り葉とのくっきりしたコントラストも力強く美しいです。樹勢は強く、生育旺盛で花付きも良く、バランスのよい樹形になります。暑さにも強い特長があります。日当たり次第では色は薄めになります。前モナコ公国元首レーニエ3世の在位50周年(ゴールデン ジュビリー)を記念して捧げられたバラ。赤と白はモナコ公国の国旗の色です。レーニエ3世の妻グレース公妃に捧げられたグレース ドゥ モナコ、プリンセス ドゥ モナコと同じメイアン作。別名チェリーパフェ(Cherry Parfait)。「ジュビレ デュ プリンス ドゥ モナコ Jubile du Prince de Monaco」仏:メイアン 2000年作出。「イエロー クイーン エリザベス Yellow Queen Elizabeth」。名花クィーンエリザベスの枝変わり種。花色は淡いクリームイエローで、外弁にほんのりピンクがのっています。ゆるくカーブした丸弁の花びらが印象的で、優しい雰囲気のバラです。「イエロー クイーン エリザベス Yellow Queen Elizabeth」ベルギー:フラーミンク 1964年作出。そして再び「センターフィールド」横まで戻る。「三日月山」の手前には「富士山ベンチ」が。その手前に「EXPO 2027 YOKOHAMA JAPAN」と。花菜ガーデンにある「富士山ベンチ」を「富士山」を背景に。これはネットからの写真。「富士見百景」に選定されている場所であると。そして最後に訪ねたのが土産物売り場「ディア チャペック (Dear CAPEK)」。一番左に「ヒマワリはちみつ」👈️リンク と。「ヒマワリはちみつ」があることを初めて知ったのである。ミツバチがヒマワリに訪花するのは、花粉が目的と考えていた趣味の素人養蜂家の私なのだ。駐車場に戻る際にも、これでもかとバラをカメラで追う。「和音 Waon」花の中心に明かりを灯したような黄色が印象的な花をたくさん咲かせます。楚々とした雰囲気で、さまざまな花や演出したい場所に調和し、「和音」を奏でるかのようです。ぎふ国際ローズコンテスト銀賞及び世界バラ会連合特別賞受賞。「和音 Waon」日:京成バラ園芸 2004年作出。「スパークル Sparkle」。アプリコットかかったオレンジ色が綺麗な薔薇です。スパークル(Sparkle)には、閃光、きらめき、活気などの意味があります。 ワインなどの泡立ちもスパークル(スパークリング ワイン)といいます と。「スパークル Sparkle」英:フライヤー 2009年作出。「ファイヤーワックス ラッフル Fireworks Ruffles」。切れ込む花弁が特徴的な「ラッフル ローズ」シリーズ。春は菊のように細く黄色い花弁の先が赤味がかり、花火のようです。夏の高温期には、黄色一色になります と。「ファイヤーワックス ラッフル Fireworks Ruffles」蘭:インタープランツ 2014年作出。「ノース フレグランス North Fragrance」日:吉池貞蔵 2009年作出。系統 フロリバンダ(Floribunda)花色 クリーム花形 ロゼット咲き花径 大輪香り 強香(ティ&フルーツ)開花 四季咲きそして駐車場に向かい、平塚駅近くにある打ち合わせ場所のファミレスに向かったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2024.06.07
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その37): 八雲神社~津守稲荷神社~船守稲荷神社~水のトンネル
「乗誓寺」を後にして、次の目的地の「八雲神社」に向かう。東浦賀1丁目17の路地を北に向かって進むと、「八雲神社」への石段が現れた、石段の途中、左手にあった「手水舎」。石段の途中から浦賀湾沿いに建つ「ライオンズヒルズ横須賀浦賀」を振り返る。築年月(築年数) 1994年6月 (築30年)建物構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)建物階数 地上22階総戸数 314戸右手にあったのが「東浦賀1丁目町内会館」。さらに石段を上る。石段の上に「八雲神社」の拝殿が姿を見せた。祭神は須佐男命。この社は江戸時代の建物で、当時は、大谷山満宝院八雲堂という修験の寺であったと。明治以降、神社に変わりましたが、建物はそのままで、屋根に宝珠が乗る、寺院型式の御堂建築なのであった。拝殿の向拝には、漆喰で造られている「漆喰鏝絵(しっくいこてえ)」という、見事な龍が取り付けられていた。ズームして。「向背の龍」と呼ばれるこの作品は、木彫り彫刻?と見紛う、見事な出来栄えで、全国的にも珍しい存在であると。龍頭を中心に据え、全身を丸彫に造形、ガラス玉の玉眼を嵌入する。くねる龍身はしなやかで、均整がとれているが、彩色はかなり剥落し頭部の破損部分も目立つ。「伊豆の長八」とともに、漆喰鏝絵の名人として全国的に知られる石川善吉48歳時、明治35年(1902)の作品。背面左端に銘文があり、「明治三十五年/左善作/四十八才」とあった。作者の「左善」とは、左官の善吉の略で、浦賀の左官職人石川善吉のことである。明治35年(1902年)48歳の時の作品であることが分かるのであった。尚、漆喰鏝絵は八雲神社の他,西叶神社・法憧寺・川間町内会館などにも残されていたのであった。「八雲神社祭神は須佐男命(すさのおのみこと)です。この社の建物は江戸時代のもので,もとは大谷山満宝院八雲堂(おおがやさんまんぽういんやくもどう)という修験の寺でした。明治の廃仏毀釈で神社に変わりましたが建物はそのままで,寺の型式であるお堂建築になっており、鳥居もありません。現在も寺の宝珠が屋根に乗っています。お堂の内部には修験の護摩壇があります。向拝(ひさし)には漆喰で造られた龍が取り付けられ、長さ一間半の大きな木刀は大山信仰の初山競いの武勇伝が伝えられています。東浦賀一丁目の鎮守様として毎年六月に祭礼が行われ、須佐男命が乗った山車と猩々坊が(しょうじょうぼう・厄除け人形)が出ます。浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」「猩々坊」👈️リンク。行列の中で異色の存在は「猩々坊」。猩々といえば、まず思い浮かぶのが能楽の「猩々」。赤く長い髪が特徴的で、衣装も赤地または赤模様。中国において猩々は、想像上の動物で猿に似ているとされ、人の顔と足を持ち、人の言葉を理解し,酒を好むという。日本では赤面赤毛とされ、酒飲みの異名ともなっている。一方,八雲神社の猩々坊は、大きな頭と顔、黒々とした髪・髭・眉に白い顔。どこか一種異様な雰囲気が漂っているが、猩々とは共通点があまり感じられない。江戸末期に疱瘡(天然痘)が流行した時,人々は「疱瘡神」と言う疫病神が疱瘡を流行らせると考えた。猩々には能の印象から転じて赤色のものを指すこともあり、疱瘡神は赤色を苦手とし、「赤が病魔を払う」という俗信から、東浦賀の人々は「猩々」に「坊」をつけて擬人化、赤い衣装を着せて「疱瘡神除け」として祀ったようだ。全国には「赤い御幣」「赤一色の鍾馗絵」「赤い玩具の鯛車」「猩々人形」等々、赤を基調としたお守りや風習が存在するが、八雲神社の猩々坊は他に類を見ないユニークで貴重な存在と思われる。八雲神社は東浦賀町大ヶ谷の畠中という谷戸にあり、猩々坊は江戸末期の文久2年(1862)に造られた。ところが何故か、明治33年(1900)以降の祭礼においては、町内引き回しが行われなくなってしまった。それから95年が経過。これを惜しんだ町内の人達が、神社に保存されていた猩々坊の色を塗り直したり、髭をつけたりして修復、平成7年(1995)見事復活を果たし、現在に至っているようで大変喜ばしいことだ とネットから。「御宝珠」。寺から神社に変わった当時、屋根に乗っていた御宝珠。現在のものは、その後作り替えられた金属製であると。近づいて。「当町守護八雲神社御祭神 須佐男命此の社は江戸時代の建物です。当時は大谷山満宝院八雲堂と申して真言宗修験のお寺でした。明治初期に神社になりまして其の当時屋根に乗りし御宝珠です。東浦賀 一丁目町内会」つぎに訪ねたのが「津守稲荷神社」。横須賀市東浦賀1丁目14。「津守稲荷」と。石鳥居の先に拝殿。手水舎。拝殿。ご祭神は、社名からの推定になりますが、食物や穀物の神様で、五穀豊穣の神様である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)。宇迦之御魂命とも表記され、稲荷神と同一です。創建は江戸時代中期の文政9年と。詳しい創建の経緯などは不明ですが、津守の「津」は港を意味するもので、港を守るお稲荷様として創建されたと考えられます。誰の手によりどのように創建されたかなどは、残念ながらわからない。拝殿の彫刻が目を惹いた。右側には龍、左側には神様でしょうか。木鼻(右)、下の方の両端には亀もいた。木鼻(左)、下の方の両端には亀もいた。拝殿の内陣。ズームして。拝殿に向かって右手には、「青面金剛塔」と書かれた小さな庚申塔があった。ニオイバンマツリ(匂蕃茉莉)の花。咲き始めは紫色だった花は少しずつ白っぽくなり,1本の木に紫と白の2色の花が咲いているように見えます。一つの花の花期は短いのですが,次々に咲き続けるので長く2色の花を楽しむことができるのだ。観音崎通りを京急浦賀駅方向に向かって歩く。横須賀市東浦賀1丁目12−17附近。右手奥に神社の石鳥居が見えた。石鳥居の先の石段の上に朱の社殿が。正面から。「船守稲荷神社」。横須賀市東浦賀1丁目11。お狐様(右)。お狐様(左)。「船守稲荷神社」の社殿。東浦賀1に鎮座する船守稲荷神社の縁起は不明とのことだが、境内に天明5年(1785年)銘の手水鉢が奉納されて残っている。船守稲荷神社の創建は、奉行所が下田から浦賀へ移された享保5年(1720年)以降で、稲荷信仰が江戸で大流行する江戸時代後期であろう。船守は文字どおり船を守る稲荷社で、港を守る津守稲荷神社とともに港町浦賀にふさわしい名前の稲荷社。手水鉢が船守稲荷神社氏子中による奉納ならば、船守稲荷神社は天明5年(1785年)以前の創建となろう。しかし、船の前に津があるのが普通である。津守稲荷神社は文政9年(1826年)に創建されているので、船守稲荷神社の創建が津守稲荷神社の創建よりもはるかに古いことはあるまい。一方、浦賀のもう一つの稲荷社である福寿稲荷の創建も弘化4年(1847年)にまで下がるから、船守稲荷神社の創建も19世紀にまで下がる可能性もある。しかし、西叶神社の摂社である船守稲荷神社の創建が元文4年(1737年)であることから、これ以前の創建である可能性が大であろう 鳥居は朱塗りではないが社殿は朱塗りである。内部に本殿が安置されているから、おそらくは覆い屋であろう とネットから。。内部に本殿が安置されていた。そしてさらに観音崎通りを進むと、右手奥、住宅と駐車場の間の奥の山裾に赤煉瓦作りの小さなトンネル風の建造物が。「水のトンネル明治三十三年(一九〇〇)に操業を開始した浦賀ドックが工業用水を確保するために、現在の二葉二丁目にあった溜め池から掘った全長約千メートルの導水坑の出口です。この導水坑は、浦賀ドックが独自のタービンを開発するため、冷却用の水を大量に必要としそのために造られたものです。浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」横須賀市のサイトに詳しい説明があった。『明治33年(1900年)に操業開始した浦賀ドックが工業用水を確保するために、 現在の二葉2丁目にあった溜め池から掘られた、全長約1,000mの導水坑の出口です。 現在は使用されていません。 旧浦賀ドックは工業用水の確保のためにこの導水坑と荒巻用水路を整備しました。 明治33年に作成された工場の設計図には荒巻用水路しか記載がなく、その完成は明治35年(1902年)12月ですが、導水坑の記録は、 昭和に入って作成された図面に残されています。 この導水坑は、旧浦賀ドックが、独自のタービンを開発するため、冷却用の水を大量に必要とし、 このために整備されたものと考えられます。 この工場で初めて開発された、浦賀式3連成レシプロ汽機と排気タービンによる連動主機は、 昭和6年(1931年)に建造された貨客船「新京丸」に初めて搭載されているので、 タービンの開発と導水坑の整備は更に溯ることとなるのでしょう。 当時は、使用後の熱くなった冷却水が、職員のための風呂の湯として利用されたそうです』と。「浦賀式3連成レシプロ並びに排気タービン連動汽機」そして「観音崎通り」を「浦賀駅前」交差点まで戻り、「浦賀通り」・県道208号線を南に進む。目的地は「浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)」。「浦賀国際文化村推進協議会の案内絵👈️リンク黒船来航の地 ようこそ浦賀へ 明日の浦賀をつくる会」の絵を4月16日(火)以来久しぶりに見る。ズームして。「浦賀丘入口」交差点より、「ポップサーカス横須賀公演」が行われている浦賀ドック内の特設大テントを見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.07
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その7)
次に訪ねたのが「ひらきの棟」の四季ギャラリーで開催されていた、樹脂粘土で作るモダンクレイアート「花で彩る世界展」。作品展が5月7日(火)から19日(日)まで、花菜ガーデンの四季ギャラリーで開催されていたのであった。「MODERN CRAY ART」。作品が並ぶ。樹脂粘土で作られた本物の生け花のような作品。本物のバラの如くに。多くの見学者の姿が。透明感のあるオリジナル粘土を使い、花々を作っていくと。着色は自分の好みの色を作るのだと。1枚1枚手でひろげ、一輪ずつ作り上げた花々をアレンジした作品の展示会。花びらや葉の一枚一枚を手でのばして。「クレイアート」👈️リンク。そして再び「花菜ガーデン」の「センターフィールド」前に。「KANA GARDEN」と。「自家採蜜 非加熱 はちみつ」販売車。再び「花菜ガーデン」案内図。「フラワーゾーン」、「アグリゾーン」、「めぐみの研究棟ゾーン」に別れていた。この日は、平塚駅近くで15:30から仕事の打ち合わせであったが、まだ1時間近く時間の余裕があり、バラ園で訪ねていない場所に気がついたので、再び「つむぎ通り」、「春告げの小道」を利用して「バラ園」に向かう。先ほど、写真を撮らなかったバラを追う。「ラ バリジェンヌ La Parisienne」。鮮やかなオレンジと黄色のグラデーションで独特の華やかさを持ちます。花色は環境で変化しますが、花付きよく何度も咲き多様な楽しみを与えられます。健康的な葉が繁り、耐病性、樹勢が非常に強い。枝が暴れることなく育てやすいバラです。背が高い木立ちタイプくらいで育てると扱いしやすいですし、花も良く咲くように感じます。足元に背の低いフロリバンダ系を植えてバランスよくするのも素敵です と。「ラ バリジェンヌ La Parisienne」仏:デルバール 2009年作出.「ブルーライト Blue Light」。蕾の姿が、美しく、藤色の美しい花形と、素晴らしい芳香を併せ持った品種です。花弁が厚いので雨にも強いです。レディラックとマダムヴィオレの交配種です。1994年JRC金賞「香りの大賞」受賞 と。「ブルーライト Blue Light」 日:伊東良類 1995年作出。「クリアムーン Clear Moon」。名前通りの満月のような黄色のバラ「クリア・ムーン」(Clear Moon)。剣弁高芯咲き大輪で日本の大月啓仲氏の作出による作品である と。「クリアムーン Clear Moon」日:大月啓仲 2006年作出。「プロスペリティ Prosperity」。つぼみの時はややピンク色を帯びているが開くと純白になる。数輪の房咲きでややうつむいて咲く。葉は濃い緑色で小葉、新梢は赤みを帯び節間が狭くバランスがよい。自然樹形でも楽しめるが広いスペースが必要となるのでつるバラとして扱う。二番花までは四季咲きのように咲き、夏以降もポツポツと咲き続ける。強い剪定をしても開花するので利用範囲が多い。耐病性があり樹勢も強く育てやすい品種 と。「プロスペリティ Prosperity」英:ペンバートン 1919年作出。「進化するオールド・ローズ中国のバラの導入により、西洋のオールド・ローズは大きく変化します。中でも最も顕著なのが、四季咲き性である品種が増加したことです。その他では、花色に淡黄色やアプリコットが登場し、花型では剣弁咲きが、香りではティー(紅茶)の香りの品種が現れます。このコーナーのバラのうち、ティー系とチャイナ系の品種は、中国のオールド・ローズの特徴を最も色濃く現しており、中には(リージャン・ロード・クライマ一」のように中国のオールド・ローズそのものも植載されています。」「ムタビリス Mutabilis」。移り色で知られる美しい一重のチャイナローズです。花色は淡いアプリコット色から濃いピンク色へ移り変わります。枝は赤みを帯び、一株で色とりどりの花が咲き乱れる様はまさに蝶が舞うようです。細い枝は弱剪定で管理すると伸びてくるので、トレリスやフェンス、アーチなどに使用しても面白いでしょう と。「ムタビリス Mutabilis」。「エルモサ Herumosa」。スペイン語で「美しい」を意味する花名どおり、原種系チャイナながら花弁数の多いカップ状の花に驚かされます。株は花で覆われ、低めに茂ります。優しい色合いは草花との相性もよい と。「エルモサ Herumosa」仏:Marchesseau 1832年作出。バラ園の一番北の角を歩く。「野の花 Nonoka」花色は淡いピンク系、ほんのりピンク。花形はナチュラル系一重咲き。微香 と。「野の花 Nonoka」日:鈴木満男 1987年作出。「薔薇の轍」に向かって進む。「ピンク ノックアウト Pink Knock Out」。非常に花つきがよく、しかも育てやすいバラ。四季咲き性が特に強く、春から晩秋まて途切れることなく咲き続けます。特に優れた耐病性を示し、乾にも強く、低肥料て年々株が広がる画期的なシリーズです。春はかわいいピンクの花が株を覆いつくし圧巻てす。ノックアウトの枝変わりなので丈夫で育てやすく、株も大きくはならないのて鉢ても楽しめます。「ピンク ノックアウト Pink Knock Out」米:モンテシノ 2001年作出。「ブラッシング ノックアウト」。雄しべは白く、淡いピンクのグラデーションが、いっそうひきたち美しいです。可憐な雰囲気が演出できます と。「ブラッシング ノックアウト」仏:Meilland 2004年作出。「つる ピース Cl.Peace」。名花ピースの枝変わりつるばら、大輪系としてはステムが短いので枝にびっしりと咲き満開時は大変見事です。壁面のほか、花後のシュートは上に伸びますが、あえてフェンスに仕立てるのも美しいでしょう と。「つる ピース Cl.Peace」米:ブレイディ 1949作出。これぞ「百花繚乱」!!。「モダンタイムズ Modern Times」。長蕾から開花するローズ赤に白の鮮明なしぼりが最大の特徴。花は大きくなると重みで俯き加減に開花します。花型はよく整い、綺麗に入る絞りがさらにこの品種の魅力を上げています。花付きも良く、たくさん咲くと特異な花色のお陰で華やかな印象を受けます。樹の成長は少し遅いのですが、伸びないわけではなくじっくり育てればそれなりの大きさになります と。「モダンタイムズ Modern Times」蘭:ヴェルビーク 1956年作出。さらに「百花繚乱」の中を歩く。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.06
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その36):浄土真宗 東教山乗誓寺(じょうせいじ)
次に訪ねたのが県道209号線・観音崎通りの向かいにあった「浄土真宗 東教山乗誓寺(じょうせいじ)」。横須賀市東浦賀1丁目20−10。寺号標石「浄土真宗 東教山 乗誓寺」。「浄誓寺 寺域案内 江戸豪商墓地他案内図」。「掲示板」には、「乗誓寺 曽我兄弟 由緒」が。「乗誓寺 曽我兄弟 由緒乗誓寺の開基は、了源(曽我十郎の子、河津三郎信之)。この了源は、藤原鎌足を祖とし、第十八代の末裔で、父は曽我十郎祐成、母は大磯の虎御前である。鎌倉時代、源実朝に仕え。多くの武功により恩賞として相模国平塚の地を賜り、親鸞聖人が関東教化の折、その教えに帰依し出家、了源と称し、鎌倉時代(安貞元年 一ニニ七年)平塚に阿弥陀寺を建立、親彎聖人真筆十字名号を本尊とした。この本尊は親鸞聖人の直弟子であった真仏(京都本山・仏光寺)に下附された貴重な本尊で浄誓寺に現存する。その後、室時時代(寛正六年、一四六五年)、近江(滋賀)に土一揆の争いが起こり、比叡山衆徒により大谷本願寺が破却され、越中、越前、加賀、山科、摂津、紀伊などで一向一揆が勃発した。この為に当寺の相模(平塚)の阿弥陀寺の住職空浄は、碩学(有名な学者)の誉高かったため、比叡山の衆徒に攻め入られるとの報を聞き、本尊を奉じ、平塚を逃れ、室町時代(文明元年 一四六九年)に浦賀の地に移った。その当時の浦賀は、人家もまばらてあっが、一向一揆て共に戦った全国の人々が住職・空浄を慕って浦賀の地を訪れ、特に紀州・鷺森本願寺などの門徒や雑賀衆の人々が浦賀に移住し、江戸時代には賑わ町となった。その後、寛永十四年( 一六三七年)に西本願寺第十三代良如上人は、一向一揆て活躍したその当時の住職・空浄の功績をたたえ、この浦賀の地を訪れ、「阿弥陀寺」を改め、「東京山 乗誓寺」とう寺号を授kけた。さらに、江戸時代後期の浦賀は、浦賀奉行所をはじめ、黒船ペリー来航、咸臨丸のアメリカ渡航等、全国的に有名な地となり各地から人々が訪れた。江戸の文化を伝えたのは、乗誓寺が中心となり、政冶、経済、教育、芸術等、多くの著名人を招き、浦賀の人々の学問所として貢献した。当時の乗誓寺は、十間四面の本堂、山門、庫裡、郷学校舎、宝物殿、茶室、鐘楼堂、奥の院(阿弥陀仏)山頂水屋、日本庭園等が寺域内に存在した。尚、浄誓寺の住職は世襲制により脈々と継承され、曽我兄弟十郎の子孫である。」境内の石段・スロープを上って行った。正面に巨大な本堂が現れた。右手には石碑や案内板が。「横須賀市指定重要文化財絹本著色阿弥陀如来像」案内板。「絹本著色阿弥陀如来像」。「横須賀市指定重要文化財 絹本著色阿弥陀如来像 平成十六年一月二十六日指定本画像は浄土真宗形式の阿弥陀如来画像で方便法身尊像と通称されるものです。画面は少々損耗していますが、像容に大きな改変の形跡は無く、はぼ当初の姿を伝えています。肉身には金泥を塗り、面貎、手足の輸郭を細線で丁寧に描き、その画技は秀逸です。また、衣の線や文様に銀泥を用いているのは本画像の特色で落ち着いた趣に仕上がっています。画風から室町時代初期の制作と推測され、浄土真宗形式による阿弥陀如来画像の早い時期の作例として注目されるとともに、横須賀市域に遺るところの少ない中世絵画としても貴重です。 横須賀市教育委員会」上:「乗誓寺 曽我兄弟 由緒」と下:東教山乗誓寺由緒 浄土真宗本願寺派 本山 京都 西本願寺」「東教山乗誓寺由緒 浄土真宗本願寺派 本山 京都 西本願寺当山の開基は、平塚入道了源なり。了源は、藤原鎌足十八代の裔、曽我兄弟十郎祐成の子。母は大磯の虎御前なり。河津三郎信之と称す。信之は、源実朝に仕えて、武功多く恩賞として平塚の庄を賜り、積年の仇敵に感ずるところありて、親鸞聖人の教えを受けて出家し、了源と名乗り、安貞元年(西暦一二二七年)平塚に一宇を建て、阿弥陀寺と称し、親鸞聖人真筆の十字尊号を以って本尊とす。歴代相続後、文明元年(西暦一四六九年)比叡山の京都西本願寺の破却を知り、当時住職の空浄は平塚をのがれ、当地東浦賀に一宇を建て、阿弥陀寺の本尊を移す。元和元年(西暦一六一五年)空覚代に再興す。寛永十四年(西暦一六三七年)良如上人御巡教の折、東教山乗誓寺と賜る。大正十二年、関東大震災により、大本堂、庫裏、鐘楼堂等倒壊しも、昭和五十年本堂を再建、同五十九年庫裏、鐘楼堂を建之す。今や、ここに堂宇漸く整うに至り之を建て報恩感謝とす。尚 当時の歴代住職は、世襲制により脈々と継承され、曽我兄弟十郎の子孫なり。 昭和六十三年 春 東教山 阿弥陀院 乗誓寺相模国 阿弥陀寺開祖平塚入道了源より 第二十四代 浦賀乗誓寺より 第十七世住職 曽我宗允 乗誓寺 寺宝」ここにも、掲示板内と同じ「乗誓寺 曽我兄弟 由緒 乗誓寺第二十七代住職 曽我宗光」が。「東教山 乗誓寺 浄土宗本願寺派 本山 京都西本願寺曽我兄弟 ゆかりの寺」「曽我兄弟・虎御前の墓~箱根」をネットから。「乗誓寺の歴史と主な宝物」。「親鸞聖人御絵伝(桃山、江戸時代)」をネットから。「一向一揆、蓮悟書状(室町時代)」。「曽我兄弟仇討八百年記念銅像」。「曽我兄弟 十郎 五郎」像。「相模国 阿弥陀寺 曽我兄弟 十郎の子 僧:了源」「曽我兄弟仇討八百年記念銅像再建安元ニ年(一一七六年十月)工藤祐経が、伊東祐親に対し、所領争いの恨みから、伊豆、伊藤南方の山麓で待ち伏せし、弓矢を射った。その矢は、河津三郎(伊藤祐靖)に当たり、兄弟の父は亡くなった。その後、母は、相模国曽我の庄(小田原市)の曽我祐信と再婚し、幼い兄弟は、曽我の庄で成長し、元服して、兄は曽我十郎祐成、第は曽我五郎時致と名のった。そして、建久四年(一一九三年五月ニ十八日)に源頼朝により、富士野で巻狩りか催されることとなり、この報を知った兄十郎(二十ニ才)、弟五郎(ニ十才)は、父の仇討ちの好機とし、臺雨の闇夜を利とし、工藤祐経を襲い、父の仇討ちの本懐を遂げた。この仇討ちは「曽我物語」として有名である。尚、乗誓寺の代々の住職は、世襲制により脈々と継承され、曽我十郎の子孫である。 平成ニ十七年七月十三日 孟蘭盆会建立 銅像像再建願主 乗誓寺第二十五代住職 曽我宗光 由緒銘板寄贈者 当山 総代 木村鎮男殿 為、先祖代々供養」「本願寺と乗誓寺(鎌倉、戦国、江戸時代)●鎌倉時代(浄土真宗本願寺)開祖親鸞聖人(元仁元年一ニニ四年)開宗は、関東地方布教のため相模(平塚)に滞在していた時に曽我兄弟兄十郎の子がその教えに帰依し親鸞の弟子となり僧了源と名乗った。平塚に阿弥陀寺を創建し、初代住職となり後に浦賀に移り乗誓寺となる。親鸞聖人五老僧の一人である。●室町戦国時代は蓮如上人(㐧八代)の「一向一揆」の時代となり本願寺勢力が全国的に拡大し支配者(武士)と平民(農工商)との争いが続き「下剋上」といわれる「土一揆」(寛政六年、一四六五年)の乱となった。この争いは近江、琵琶湖で地主の比叡山(天台宗)と借地人(本願寺門徒)民衆との争いとなり、比叡山の衆徒により京都大谷本願寺がニ度にわたり破却され京都では「応仁の乱(応仁元年一四六七年)で騒然となり」◯◯◯◯「文明の乱(文明六年、一四七四年)の始まりは越前の守護大名富樫一族の争いから本願寺がその乱に巻き込まれたが、幸いに勝利した。その後長尾、畠山(能登)の戦いと続き、当時の「一向一揆」の頭領は本願寺の蓮悟(蓮如の子)(石川県金沢本泉寺住職)によって戦いの火蓋が切られた。その檄文「蓮悟書状(永正三年一五〇六年)が乗誓寺に送られて来た。この蓮悟の重要文書は乗誓寺に現存している。さらに「一向一揆」の戦いは、越前の吉崎御坊から京都郊外山科本願寺へ、さらに攝津大阪石山本願寺(現在の大阪城)へ。この決戦は織田信長との戦いで本願寺は苦戦し籠城したが敗北し◯◯◯援護を受け紀州和歌山の鷺森の本願寺を構えた。その後図らずも京都本能寺にて明智光秀の謀反により織田信長はあっけなく滅びた。次に天下を取った豊臣秀吉の時代には京都に本願寺の領地を与え西本願寺は現在に至っている。この激動の「一向一揆」時代を共に戦った本願寺㐧八代蓮如上人と平塚阿弥陀寺㐧八代空浄(学者)は京を逃れ空浄は平塚にも攻撃の手が伸びるとの報を聞き急遽浦賀に避難した。そして浦賀乗誓寺の初代となり現在に至っている。浦賀に移ってからは(文明元年、一四六九年)現在十八代平塚阿弥陀寺からは、二十七代曽我兄弟十郎の子了源から代々世襲制によって脈々と継承されている歴史がある。空浄が浦賀に移ってから数年後蓮如上人が浦賀を訪れ(文明七年、一四七五年)共に厳しい時代を無事生き伸び会えたことに感涙したと伝わっている。この時に境内に植樹された銀杏(イチョー)が、現在大樹となっている記念すべき銀杏の木である。(樹齢五百八十年)●江戸時代には徳川の天下となり平穏な全国統治によって、庶民の文化が栄えた江戸の文化は浦賀に伝わり紀州の鷺森本願寺の門徒や雑賀衆の人々が浦賀に移住し豪商の町となった、三浦半島一の豪商宮井一族(宮与)を始めほとんどの豪商が乗誓寺の門徒となり墓地、墓石を見てもその財力を知ることが出来る江戸の文化は乗誓寺を中心として伝えられ多くの文化人を招き文化交流の場となった。また当時の浦賀港は物流の中心として栄え、西岸から見た写真には乗誓寺の本堂が威風堂々と聳え庫裡、鐘楼堂が写っている。この賑わいの町浦賀に西本願寺㐧十三代、良如上人が訪れている。」「日本庭園 鷺吟の庭当寺の「鷺吟の庭」は中国李白の詩「魚躍青池満鷺吟緑樹低」から名付けられた。・・・・・・・・・・・・・・・鷺の鳴き声という意味があるとのこと。山々に囲まれた自然豊かな庭園には日々・・・白、青サギ、クマゲラ、キツツキや種々の野鳥や、タヌキ、リスなど、動物達が訪れる自然に満ちた風情ある名園である。」観音像であろうか、台石に山号・東教山が刻まれた石仏が安置されていた。再び「乗誓寺 寺域案内 江戸豪商墓所他案内図」。そして次に訪ねたのが「宮井与右衛門の墓所」。「江戸時代の豪商墓所屋号、宮与(本家)宮井與右衛門※宮井家一族の墓所は外塀周辺にあり」と。「宮井与右衛門(宮原屋) 出身地 紀伊国有田郡滝川原村(宮原)江戸時代から明治期にかけて、「宮与」の名で浦賀屈指の干鰯問屋であった。紀州宮原から浦賀への出店がいつであったかは詳らかではないが、十八世紀半ばにはすでに浦賀を代表する問屋となっており、多くの義援金により東浦賀村の年寄役に就任した。与右衛門は代々の通り名であり、明治三十一年には四代目町長に就任し、町政にも貢献した。」「宮井家(宮与)墓所法名図」。墓所入口から、右:三代 中央:初代 左:二代の墓石と。三代当主 宮井教遵初代当主 宮井教念二代当主 宮井教誓五代当主 宮井教淳六代当主 宮井教意手代の墓。この石仏は?そして「本堂」の前に。本堂正面。本堂の内陣。本尊阿弥陀如来像 をネットから。「本願寺第八代蓮如上人 お手植の銀杏の木」。銀杏の大木の根本に石碑が二基。「本願寺第八代蓮如上人 お手植の銀杏の木」碑。「本願寺第八代蓮如上人五百回遠忌記念蓮如上人は、中世(文明年中・一四六九年)の歴史に残る、北陸一向一揆の時代に西本願寺門主となり北陸に領主に対し民衆抑圧をいさめ、争いなきよう導かれたがやむなく戦乱となる。その後・上人は幾多の労苦を重ねながら、諸国をめぐり、門信徒の教化につとめ、本願寺の中興の祖といわれている。この蓮如上人は、この浦賀の地にもご巡教にこられこの銀杏(いちょう)(樹齢約五百年)の木をお手植された記念すべき木である。 平成十年(一九九八年)遠忌記念 平成八年四月二十五日建之 寄贈者 ・・・・・・・」本堂のわきを通り、階段を登っていくと「鐘楼堂」があった。鐘楼堂の建立は梵鐘とともに昭和五十九年、京都の嵐山の近くで製作された。下からズームして。梵鐘。重量は五百貫(約二千トン)で、鐘の周囲には百八の乳頭と呼はれる突起が付いている。この乳頭の数は、人問には百八の悩みがあり、鐘を打っことにより煩悩が消え去るということに因むものといわれているのだ。境内の新緑のモミジ葉を見上げて。陽光が差し込み、新緑の葉が輝いていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.06
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その6)
左手前方には、説明員付きの園内ツアー客の姿が。「エキウム・ウィルドプレッティスペイン領カナリア諸島テネリフェ島に自生しています。株の中心から円錐状の淡紅色の長い花穂を1 ~ 2m伸ばし、雄大な草姿となります。開花期の4月下旬から5月上旬には約20,000個の花がつき、その外見から「宝石の塔 Tower of Jewels」と呼ばれています。」テネリフェ島(火山島)に自生する3mを超す豪快な花。開花期は5~6月。開花までに3年かかり、開花するとその株は枯れてしまうのだと。小さな花が螺旋状に連なって咲いているのが解るのであった。エキウム・ウィルドプレッティから採蜜したハチミツは地元の特産品 と。別の株でミツバチ発見。「さらさ Sarasa」。花名の「さらさ」は、優しい春風の音をイメージして名付けました。2007 JRC 国際ばら新品種コンクール 銅賞。「さらさ Sarasa」日:京成バラ園芸 2009年作出。「京極 Kyougoku」。鮮やかなローズピンクで裏弁は白色をおびる。花は整形で凛々しく咲きます。早咲き。樹性はやや横張りに生育する と。「京極 Kyougoku」 日:京販園芸 1995年作出「ブラスバンド Bras Band」。オレンジに複色が特徴の、丸弁咲き、中大輪房咲きの花。ティの微香。四季咲き性。「ブラスバンド Bras Band」米:クリステンセン 1993年作出現在地はプラントハウスの前、ここ。「カーネーションの施設栽培神奈川県内のカーネーション栽培は、明治末期に露地栽培から始まり、大正末期から昭和初期にはかなりの温室栽培がありました。現在の主要な産地である秦野市では昭和8年から生産が始まり、戦争による中断がありましたが、戦後の復興は早く、昭和40年代には、麦作等から施設園芸で収益性の高いカーネーション栽培へと転換し、栽培規模の拡大が進みました。カーネーションの切花には、一輸咲きとスプレー咲きの2種類があり、県内でも100品種以上の多彩なカーネーションが栽培されています。」プラントハウス・温室ではカーネーションの栽培、販売が行われていた。この日は5月12日(日)・母の日であった。そして前方に「つどいの棟」が姿を現した。よって「花菜ガーデン」を1周したのであった。「センターフィールド」では鉢植えの各種バラが販売されていた。平塚市内にある「サンメッセしんわ」で作られた「湘南みかんぱん」等が販売されていた。「湘南みかんぱん」。「大磯・二宮の青摘みかん果汁を生地とあんこに使用し、爽やかな酸味を感じるみかんあんぱんです。また、生地には平塚産カオリ小麦を配合し、やわらかく子供からお年寄りまで食べやすく焼き上げています。知的障がいを持つ方々が利用する施設で、地域の活性化と共に手作りの美味しさをお届けします。平塚市のふるさと納税返礼品にもなっています!」とネットから。そして園内中央の「きらめきモール」まで戻る。「つどいの棟」内では藤川志朗「花のイラスト展」が開催されていた。「マドンナリリー」も香りを放っていた。「マドンナリリー学名:Lilium condidum L和名:庭白百合 ユリ科ユリ属原産地はマケドニアから小アジア南端部を経て、イスラエルへと至る地中海東部沿岸地域と推察されています。日本への渡来は、1765年にオランダよりもたらされた球根を、駒場薬園に植えたとの記録があるようですが、日本にはすでに白く美しいユリが自生していたので、マドンナリリーが普及することはありませんでした」「歴史ー1BC1500年頃のクレタ島の遺跡から発掘されたミノア文明期の壁画や壺には、マドンナリリーと思われるものが描かれており、当時すでに栽培がされていたのではないかとみられています。古代アッシリアでは神聖なる花と言われ、鉄器時代にはギリシャよリエジプトへ渡る人々によってもたらされたといわれています。古代エジプトのファラオの墓には白いユリが描かれた場所があります。」ミノス文明期の遺跡には「ユリの王子」という壁画が今も残っています。ユリを集めているところが描かれた、古代エジプトの壁画。「マドンナリリー」はレバノンのベイルート川渓谷の自生地を調査したという報告があります。ベイルート川の石灰岩地帯、北向きの日陰に自生していました。19世紀に日本から「テッポウユリ」がヨーロッパに伝わると、白い「テッポウユリ」とそれまでの「白いユリ」を区別するため「マドンナリリー」とよばれるようになってきました。日本では「ニワシロユリ」と名付けられていますが、大正時代頃は「フランスユリ」、「ヨレハユリ」等と呼ばれていました。しかし、和名、学名で呼ばれるよりも「マドンナリリー」の名前で呼ばれることが多いユリです「歴史-2ローマ帝国は領土拡大を目指し、BC58年ガリアに、BC55年ブリタニア(現在のイギリス)に遠征を行いました。ヨーロッパ北部へ侵攻することで、マドンナリリーもヨーロッパ各地に広まりました。当時はマドンナリリーの球根や花をワインの中で砕き、「うおのめ」の膏薬に利用するという事もあったようです。その後、キリスト教が誕生したヨーロッパに浸透するにつれて、白いマドンナリリーの花は聖母マリアの象徴として見られるようになっていきました。中世以降の宗教画にはマドンナリリーが多く描かれています。」「歴史-312世紀以降、フランス王の旗や衣装にユリが描かれるようになりました。また僧院では薬草園でマドンナリリーを育てていました。」ダヴィンチ作「受胎告知」1472年-1473年大天使ガブリエルがマドンナリリーを携えてマリアに受胎告知をする場面です。「歴史-4江戸時代の末期、日本のユリがシーボルトによってヨーロッパへ伝わると、一気に人気となり、次第にキリスト教の祭事などでもマドンナリリーに代わり、テッポウユリがつかわれるようになりました。いつしか日本のテッポウユリは「イースターリリー」と言われるようになりましたが、テッポウユリが伝わった後も、宗教画に描かれているユリの多くはマドンナリリーです。今日ではその可憐な姿と希少性から、マドンナリリーは日本でも注目されるようになりました。」多くの蕾も。これぞ純白。そして「ひらきの棟」の内部の常設展示へ。「わたしたちの神奈川県■県庁のあるところ:横浜市■面積: 2 , 415.81 km2 (東西約78km、南北約60km ) (2014年げんさい)■総人口: 9,148,549人(2016年11月1日げんざい)■県の花:やまゆり■県の鳥:かもめ■県の木:いちょう■なんでもランキング 人 口 :東京に次いで全国で2番目 人口密度:東京、大阪に次いで全国で3番目 面 積 :全国で43番目」「水草の水槽」。「水草の種類(★が各水槽の名称)」。エキノドルス、クリプトコリネ、アヌピアス、ナヤス、チシママツバイ、マツモ、コケ。魚。エンドラーズ'ブルースター'、オトシンクルス、サイアミーズフライングフォックス、エビヤマトヌマエビ、ミナミニマエビ、貝ラムズホーン(ピンク)。「神奈川の農産物「三浦だいこん」や「相模半日きゅうり」は昔から神奈川でつくられてきた伝統野菜。そしてたまねぎの「湘南レッド」やなすの「サラダ紫」は、品種改良で生みだされた新しい野菜。両方とも、神奈川の気候・風土や最新の栽培技術を生かしながら、大切に育てています。」市別特産品。「みかん 湘南ゴールド12年かけて開発された新種のみかん。さわやかなかおりとジューシーなあまみが特ちょうで、温州みかんがすがたを消す4月ごろが旬。県西部を中心に、生産拡大をはかっています。たまねぎ 湘南レッド1961 (昭和36)年生まれの生食用たまねぎ。ふつうの黄たまねぎにくらべ、からみや刺激臭が少なく、あまみが強いのが特ちょう。シャキシャキとした食感と赤紫のうつくしい色で、サラダにびったり。」新しい仲間もぞぞくぞく登場!「地域の特ちょうを学ぼう」同じ神奈川県でも、気候や地形などによって、地域ごとに特ちょうがあります。次の6つの地域には、どのような特ちょうがあり、どんな農業が行われているのでしょうか?1️⃣横浜川崎地域農産物をたくさん消費する大都市に近いという利点を生かし、野菜やくだもの、花き、肉など、いろいろな農産物を生産しています。2️⃣横須賀三浦地域あたたかな気侯にめぐまれた、三浦半島の水はけの良い台地では、だいこんやキャベッ、すいかなどを栽培。全国でも有名な露地野菜の産地です。3️⃣湘南地域ビニールハウスや温室を利用した野菜や花の栽培と畜産を中心に、野菜の露地栽培も行われています。県内で最もたくさん農産物を生産する地域です。4️⃣県央地域神奈川県の水源地。相模川の上流域である中山間地では、お茶やしいたけの栽培、畜産がさかん。平たんな中流域では、米や野菜、くだもの、花きなどを栽培。5️⃣足柄上地域ゆたかな緑と水にめぐまれ、山間地のお茶、丘陵地でのくだもの、水田の米とともに、牛乳や肉牛などの生産がさかん。森林地帯ではしいたけの生産も。6️⃣西湘地域海、山、川の自然にめぐまれた地域で、米やみかん、キウイフルーツ、梅、お茶、しいたけの生産や酪農がさかん。梅ぼしやジャムなどの農産加工品も人気です。様々な神奈川の特産品が紹介されていた。神奈川県下の月ごとの祭りや催事が紹介されていた。「これからの農業は環境との調和が大切」。「みんなでつくる実りのカレンダー」。この部屋の名は「Kizuki Experience Room」と。そして「花菜ガーデン」案内模型。「バラ園」周辺をズームして。「チャペックの家と庭」、「尾根見の池」周辺。各種の棟とセンターフィールド。写真左側にバラ園。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.05
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その35):東耀稲荷神社~顕正寺
「専福寺」を後にして進むと、右手にあったのが「横須賀新町郵便局」。横須賀市東浦賀2丁目6−12。東浦賀5丁目と10丁目の境の道を北に向かう。100mほど進むと、右手に朱の鳥居の神社があった。鳥居の扁額には「東耀稲荷大明神(とうよういなりだいみょうじん)」と。「横須賀市指定市民文化資産」案内板。「東耀稲荷」案内板。「東耀稲荷創建は天明ニ年(一七八二年)で、食保命(うけもちのかみ)をお祀りしています。東耀稲荷の名の由来は、隣接する東耀山顕正寺の山号からとったもので、古くは顕正寺の境内にあったといわれています。さほど大きくありませんが、欄間や格天井などには見事な彫刻が施されています。屋根には恵比寿と大黒天の飾り瓦がのり、干鰯(ほしか)で栄えた東浦賀の繁栄ぶりを今に偲ばせてくれます。また、この稲荷は、火防(ひぶせ)の神としても崇拝されています。合祀されている須賀神社は、新町の鎮守で、創建年代はわかりませんが、昔、悪い疫病(コロリ)が大流行したとき、新町にも何人かの死者がでたため、里人が、当社(祭神、素盞鳴尊すさのおのみこと)を勧請し、病気をしずめたと伝えられています。」案内板にあった拝殿の内部の格子天井の龍の写真。参道の石段を上って行った。そして正面に「拝殿」。お狐様(右)。お狐様(左)。拝殿正面に掛けられた扁額には合祀された須賀神社の名が。「内陣」を格子の隙間から。拝殿の内陣の左側:獅子の子落とし父がおそろしく深い谷に子を蹴り落とす。子獅子は一度は登ってくるが、また突き落とされると、折からの嵐に爪が立てられず、木陰でしばし休んでしまう。子がなかなか登ってこないのは怖気づいたのだろうか、育てた甲斐がなかったのかと危ぶむ父。深い谷間を覗くと、水面にその影が映り…、親と子がそれぞれの存在に気付く。父の姿を見るや子は勇み立ち、高い岩をものともせず一気に駆け上がっていく。拝殿の内陣の左側内陣の欄間の彫刻。黄石公と張良漢の高祖に仕える張良は夢の中で老翁と出会い、兵法を伝授してもらう約束をする。夢の中で約束した五日後に橋のほとりに行くと、老翁は既に来ており、「人に物を教えて貰おうというのに、先生より遅く来るとは何事だ」と咎め、また五日後に来いと言い去っていく。五日後、張良は正装をし早暁に行くと威儀を正した老翁が馬に乗って現れた。そして自らを黄石公と名乗り、履いていた沓を川へ落とした。張良は急いで川に飛び込んだが、大蛇が現れ威嚇し沓を取られる。張良はすばやく剣を抜き立ち向かい大蛇から沓を奪い返した。黄石公は張良の働きを認め、兵法の奥義を伝授しました。張良黄石公。内陣の格子天井には一面に龍の姿が。拝殿の頭貫:2匹の狐ズームして。木鼻(右):獅子。木鼻(左):獅子。そして拝殿の欄間彫刻をカメラで追う。拝殿の右面に3枚、左面に3枚、裏面に1枚が嵌め込まれていた。奥から龍。鳥。鳥。左面:ミミズクであろうか。鳥。再び龍。裏面にも龍が。屋根に鎮座する恵比寿様。もとは『鳳鳳」『狐2匹』の饅絵が存在したが、屋根を修理した際、饅絵を修復できる技術者がなく、現在は白い漆喰塗りとなったのだと。下記2枚の写真はネットから。石川善吉・橋尾親子の作と言われているが・・・そして次に隣りにあった「顕正寺」を訪ねた。浦賀の町では、この「顕正寺」と西浦賀の太子寺が日蓮宗の寺とのこと。天正元年(1573)に僧・顕正坊日実大徳が顕正庵を結んだことによって開かれたと。横須賀市東浦賀2丁目1−1。「東耀山 顕正寺」。題目碑「南無妙法蓮華経」と「中根東里先生墓」。中根東里は江戸時代中期の陽明学者。東里は、伊豆下田の生まれで、若くして僧侶になりますが還俗(僧をやめる)し、当時の一流学者である荻生徂徠や室鳩巣に師事します。しかし、あきたらず、独学で陽明学を学び、栃木県の佐野で塾を開いていました。年をとるにつれ、母が晩年を過ごし、唯一の身寄りである姉(浦賀奉行所与力の妻)がいる浦賀の地を故郷のように思い、ここで70余年の生涯を閉じました と。「盥漱(かんそう)」と刻まれた手水場。「顕正寺天正元年( 一五七三)に顕正妨日実大徳が庵を結んだのが創建と仏えられる日蓮宗のお寺てす。本堂の右上手には中根東里の墓があります。東里は江戸時代中期の陽明学者で、晩年、浦賀へ移住しました。近くには明冶時代に歌会始めに招かれた浦賀の代表的な歌人の西野前知(さきとも)の墓があります。本堂の裏手には直木賞作家の山口瞳、咸臨丸副艦長の春山弁蔵、浦賀奉行所与力で後に横須賀造船所の技師として活躍した岡田井蔵(せいぞう)らの墓もあります。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」「中根東里の墓」の写真。「南無日蓮大菩薩」碑。十三重塔か?参道右手には多くの墓石が並んでいた。「我此土安穏 天人常充満 南無妙法蓮華経萬霊養」と刻まれた「無縁諸霊位供養塔」。「我がこの土は安穏にして、天人は常に充満せり」と。上段には、大名笠と呼ばれる大きな笠をかぶったような墓石が並んでいた。正面に本堂。「庚申塚」。青面金剛像庚申塔、猿田彦大神(明治41年(1908年)銘)、「庚申塚」と刻まれた石碑等が並んでいた。青面金剛像庚申塔(天宝12年(1841年)銘)。「故海軍大尉香山君碑」浦賀奉行と称して、ペリー艦隊との交渉にあたり、アメリカ側から高く評価されたと伝えられる香山栄左衛門の長男である香山永隆さんの顕彰碑。旧幕府の軍艦役であったが、その才能から維新後の明治3年朝廷に召しだされ、翌年海軍大尉に昇進した。香山留次郎氏(子息ではないだろうか)によって明治13年8月建立された。「故海軍大尉香山君碑 故海軍大尉香山君舊幕府相州浦賀港與力諱永孝之子母岡田氏天保十一年生于浦賀嘉永六年 米國来逼乞貿易幕府令厳海防以備不虞君受命戌同港明神﨑砲臺後幕議決和親海防觧厳安政二年 蘭人厭軍艦於此君受命與麾下之士數人往長﨑受海軍術于蘭人□學成東歸幕府以為軍艦役實為 皇國海軍術之權輿明治元年徳川幕府奉還大政于朝庭徒封于駿遠参君決志歸農卜居于都之北方 巣鴨以謀其終明治三年朝庭召為海軍術教授其四年累進至正七位海軍大尉□茲十三年二月廿九日 病没于官君諱永隆為人沈静而有才思事親至孝善書畫配萩原氏生五男四女銘曰 事親至孝 於後有餘 勤業為國 海軍權輿 明治十三年八月 清水徳馨撰并書 井亀泉鐫」碑裏面:「香山留次郎建之」歴史を感じさせる墓石が並ぶ。境内の掲示板には様々な案内所が貼り付けられていた。「山口瞳」👈️リンク「山口瞳」墓。「岡田井蔵咸臨丸の偉業に参加した士官市内東浦賀にある東耀山顕正寺の墓地に、忘れ去られたように一基の墓石がひっそりと立っています。その表に「岡田井蔵 妻◯子」と刻まれていて、この墓の主が万延元年(1860)わが国の軍艦として初の太平洋横断を成しとげた咸臨丸の壮拳に、乗組士官として参加した浦賀奉行組与力・岡田増太郎の弟岡田井蔵であることがわかります。さいわいその経歴は、田口乾三(中島三郎助の女婿・内閣書記官長)が墓石に記した500余の文字によって、およそのことを知ることができます。岡田井蔵は天保8年(1837)1月20日、幕臣岡田定十郎の4男として誕生しました。早くに父母を失い、兄増太郎の庇護をうけ、天保14年兄が浦賀奉行組与力となったとき浦賀に移り,16歳で幕府学問所である昌平黌に入学して漢字を修めています。安政3年(1856)、幕府から選ばれて第2回海軍伝習生として長崎に赴き、オランダ人から機関学の実際について学んでいます。同6年正月、修学を終えて勝麟太郎らとともに朝陽丸で江戸に帰り、幕府が江戸に新設した海軍操練所の教授方手伝出役として、幕府海軍の人材養成に当たるのです。安政7年(万延元年・1860)正月、遣米使節の随行艦咸臨丸に業前の者として選ばれ、機関方の青年士官として乗艦、連日の荒天に苦闘しながらも無事難航を切りぬけ、サンフランシスコに到着、大歓迎をうけます。滞在の日々は文明国アメリカの風物に接し、新鮮な驚きと感動の連続だったようで、井蔵自身も教会を訪れ、オルガンの妙なる音に耳を傾けたといわれます。帰途は平穏で同年5月5日、浦賀港に碇をおろし、歴史的航海の大任の果たします。同年12月には幕府より恩賞があり、井蔵にも銀20枚と時服2、さらに銀20枚が贈られました。帰朝後は再び海軍操練所に出仕しましたが、文久年間には朝陽丸の機関長として伊豆、小笠原諸島の調査・開拓に従事。さらに将軍家茂の海路上洛の折には、その警護にも赴いていたようです。明治元年(1868)1月、軍艦蒸気役一等を仰せつけられ、このころ市内の深田村に居在していたことがわかります。維新後は横須賀製鉄所の出仕。『横須賀海軍船廠史』によれば、明治4年(1871)には「造船少師 月給40両」と見えています。翌年には主船少師で製図掛主任となり、軍艦盤城、海門などの諸艦建造に尽力し、同9年には主船中師となります。のち海軍3等師と改称され、やがて海軍1等師に昇進し、同17年には製図掛機関部主任と見えています。井蔵は非常に図工にすぐれていることを以てその名を知られたといわれていますが、横須賀製鉄所(造船所)の創業期に一貫として製図部門の責任者の地位にあり、その実力を以て大いに海軍造船界に貢献しましたが、惜しまれて同22年(1889)に退職しました。のち同37年(1904)7月28日、横浜市青木町で死去、菩提寺である前述の東浦賀・顕正寺に葬られました。享年68歳でした。岡田井蔵は近代日本の幕開けの地浦賀から出て、幕府海軍の創立に身を投じ、咸臨丸の偉業に参加、さらには海軍造船界で活躍するなど、近代化を目指すわが国海軍のあけぼのに参画した海の先駆者であったのです。 (上杉 孝良)」岡田井蔵の墓の写真をネットから。「春山弁蔵近代造船に貢献した男明治元年(1868)8月、榎本武揚に率いられた8隻の幕府軍艦が艦隊を組み、あくまでも官軍に抵抗し、蝦夷に新天地を求めようとする榎本らの野望に、同調した者たちを乗せて、江戸湾を出港しました。この中の1隻、咸臨丸の副隊長として、造船の近代化に大きな足跡を残した浦賀奉行所・同心春山弁蔵が乗り込んでいました。しかし、出港3日目、江戸湾を出た所で、艦隊は台風に遭遇しました。咸臨丸は一番大きなマストを切り倒して、転覆を免れたものの、走行不能に状態になり、伊豆下田に漂着。その後、船体修理のために清水港へと向かいました。この清水港が春山弁蔵の53年の生涯の終えんの地となりました。文倉平次郎著の『幕末軍艦咸臨丸』によれば、清水港に入った咸臨丸は修理のために大小の銃砲、器機等は陸揚げし、兵士は留守番をする数名を残しただけでした。こうした状況の中に、官軍の軍艦・富士山丸、飛龍丸、武蔵丸が清水港に入り、咸臨丸をめがけて大砲を発射しました。すでに航行能力も失っていた咸臨丸の留守を守っていた春山らは、甲板に上がり白旗を打ち振りましたが、なおも攻撃が続き、ついには咸臨丸船上の戦いとなり、ここで壮烈な戦死を遂げました。この戦い後、咸臨丸は拿捕(だほ)され、幕府軍の戦死者はことごとく海へ投げ捨てられました。こうした情景を見ていた清水次郎長は、海から遺体を引き上げ、手厚く埋葬し、壮士墓を立てたことはよく知られています。春山戦死の報は、勝海舟をはじめ中島三郎助など近代造船に携わった人々に大きな衝撃を与えました。春山弁蔵は、文化14年(1817)に生まれ、18歳になった天保6年(1835)に奉行所に出仕し、同心として定廻りや封印役などの職務についています。春山がいつごろから、船(造船)に関心を示すようになったのかわかりませんが、弘化3年(1846)閏5月、浦賀沖に来航したビットルが率いるアメリカ軍艦の姿を見たことがひとつの転機と考えられます。これは、春山だけが転機になったのではなく、浦賀奉行所の江戸湾防備の方針が、台場中心的なものから協力軍艦の必要性に変わっていく過程でありました。この方針は、蒼隼丸という船を建造することで第一歩が示され、ペリー来航後、日本で最初の洋式軍艦・鳳凰丸の建造で幕府も認めることになりました。蒼隼丸の建造は史料も少なく、春山がどの程度かかわったのかはっきりしませんが、鳳凰丸建造の時には、船体構造に関する知識を身につけ、そのレベルはペリーを驚かすほどになっていました。さらに春山の勉学に拍車をかけたのは、安政2年(1855)8月、長崎に開設された海軍伝習所の伝習生に推せんされ、本格的な造船学を学ぶことによってでした。長崎での伝習期間は、1年半でしたが、春山は期間が過ぎても長崎を去ろうとはしませんでした。それは、彼の性格からくるものなのでしょうか。また西洋の新しく刺激的な学問の魅力からなのでしょうか。ともかく、人の倍の期間も長崎に滞在して、造船学を学んできました。3年ぶりに浦賀へ帰ってくると、すぐに江戸に新設された海軍操練所の教授方として出役し、身につけたばかりの学問を次の世代に教え、指導する立場になりました。この間に、太平洋横断のために浦賀でドック入りした咸臨丸の修理を浦賀奉行所のスタッフとともに行っています。万延元年(1860)12月、幕府から海軍操練所のメンバーに純国産の蒸気船建造の依頼がありました。このプロジェクトの主任格は小野友三郎、船体の構造設計を春山、蒸気機関は肥田浜五郎が担当しました。慶応2年(1866)に完成したこの船は「千代田形」と呼ばれ、長さ九尺六寸(29m)あまりの小さな船でしたが、国産軍艦として、日本の近代造船史に新たな1ページを飾ることとなりました。 (山本 詔一)」春山弁蔵之墓 春山鉱平之墓。「西野前知浦賀が生んだ明治の歌人江戸時代の後期から明治にかけて浦賀を中心に三浦半島の歌壇をリードしたのが西野前知です。彼の代表する和歌は、 北の海に とるやひろめのいやひろく 国もさかゆる きみが御代かなで、前知が明治23年(1890)の御歌会始に詠進して、預選の栄に浴したときものです。家は代々回船問屋前知は、文政5年(1822)2月に生まれました。若いころの名を豊治郎といい、後に市郎左衛門。また、通称は佐六で、名を前知と言いました。家は代々市郎左衛門を名乗る回船問屋でした。前知は、ペリーが来航する直前の嘉永6年(1853)5月に前年亡くなった父の後を継ぎ、8代目の市郎左衛門として、浦賀奉行に認可されました。ここでいう回船問屋とは、浦賀奉行所の足軽役として、江戸へ出入りするすべての船の乗組員と荷物の検査をする「船改め」の業務を担当していた人々です。西野家は下田奉行所時代からこの仕事をし、奉行所の移転に伴って下田から浦賀へ移住してきました。このような人々を総称して「下田問屋」といい63軒ありました。門下は女性や商人など前知は、文久3年(1863)、40代になったばかりで下田問屋の年寄り役となり、さらに三方問屋(下田、東西浦賀の回船問屋105軒)の行司(事務を担当し世話をする役職)にもなりました。明治維新後は、請われて新政府の浦賀役所に出仕し、ここでも官と民の太いパイプ役として活躍しました。このように前知は、実生活でも大きな業績を残していますが、隠居した明治10年代からは、本格的な歌詠み三昧の毎日となります。そして、浦賀を中心として女性や商人、知識階層の人々に和歌を浸透させていきました。自らも進んで東都の歌人たちと交流を持ち、視野を広めていったのです。前知と栄えた浦賀歌壇明治23年には、友人であった中島三郎助の23回忌追悼文を著しました。これを機に、西浦賀の愛宕山に三郎助の招魂碑が建立されることになり、その趣意の文章が石碑として残されています。前知は、同27年10月に、72才でその生涯を閉じ東浦賀の顕正寺で静かに眠りについています。その墓石には、自らの手で書かれた「西野前知」と並んで、「田中勝子」と夫婦を別姓で表す当時の風潮を取り入れるなど、新しい考えの持ち主でもありました。浦賀歌壇は、前知の出現で栄え、彼の死とともに消滅していったと言っても過言ではありません。 (山本 詔一)」「顕正寺」の「本堂」は鉄筋コンクリート製。近づいて。扁額「顕正寺」。本堂向かって右側にあった「地蔵堂」。お地蔵さまが3体。そして「顕正寺」を後にし、「観音崎通り」に出ると」「顕正寺 (中野東里の墓)」案内板が見えた。旧浦賀町章も描かれていた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.05
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その5)
一旦「バラ園」を後にして「尾根見(おねみ)の池」に向かってすすむ。「紅葉重ね(もみじかさね)のほとりカエデコレクション水辺に積もる木の葉の絨毯が、秋の深まりを静かに伝えます。染まりゆく葉の美しさを堪能くたさい。葉の形がカエルの掌(てのひら)に似ていることからその名がついたカエデは、日本の秋を代表する紅葉の美しい樹木ですここでは紅葉に焦点をあて、イロハモミジとオオモミジ、ヤマモミジを中心に国内外の野生種と園芸品種を展示していますまた、尾根見の池では円沢・大山を背景に、スイレンのコレクションもお楽しみください。」「尾根見(おねみ)の池」手前のモミジの紅葉。さらに「尾根見の池」に向かって進む。この周囲は人の数は少なかった。「「尾根見の池」の植物水辺を彩る植物を展示しています。耐寒性スイレンは昼咲き性で、日が高くなる頃には花が閉じます。他にも、湿原などを好むポンテデリアやミソハギも展示しています。初夏から秋にかけ開花し、尾根見の池の景観に彩りを添えます。」。そして「尾根見の池」に到着。水面一面には耐寒性スイレンが開花中であった。白とピンクのスイレンの花が水面一面に。黄色の菖蒲の花も。薄いピンクのスイレン。ズームして。赤いスイレンの花は水面に、白のスイレンは水面から少し上で開花。濃いピンクのスイレンをズームして。白のスイレンをズームして。「華やかな水生植物 ~スイレン~スイレンは、世界各地の熱帯・亜熱帯・温帯地域を中心に約50種が自生するスイレン科スイレン属の水生植物です。園芸上の分類で、熱帯性スイレンの昼咲き系・夜咲き系と耐寒(温帯)性スイレンの大型系・小型系に分けられます。初夏から秋にかけて豪華な花を咲かせ、芳香性品種もあり、近年、熱帯性を中心に人気を伸ばしています。ここでは、熱帯性昼咲き系品種と耐寒(温帯)性の代表的なスイレンを50品種ほどを展示しています。水面に美しい花を咲かせ、丈夫で管理の手間も少ないスイレンを一度栽培してみませんか。」純白のスイレン。ズームして。こちらも。「フルーツフルファーム三日月山の斜面を利用して山肌の実りあふれる果樹園の風景をイメージしました。梨は「長十郎」「菊水」「あけみず」、柿は「禅寺丸」、柑橘類は「湘南ゴールド」など、神奈川県内育成品種を中心に植栽。木立の合間を散策しながら果実の実りや香りをお楽しみください。また、畑のとなりには「十郎」の梅、そしてパーゴラにはキウイフルーツや「藤稔」などのブドウを絡め、みなさまのやすらぎの緑陰をつくっています。」「ナシ園」。「神奈川県が育成したナシ「菊水」・「あけみず」神奈川県が育成したナシには多くの品種があり、現在の栽培品種に多大な功績を残しています。代表的な品種に、現在でも多く栽培されている「新高(にいたか)」をはじめ「菊水」や「愛宕」、「旭」、「あけみず」などがあります。特に「菊水」は、現在の主要品種である「幸水」や「新水」の親品種であり、「豊水」は「幸水」を親とし、「菊水」の血を引く品種です。このように「菊水」は現在の主要な品種の基礎を築いたといえます。「あけみず」は大玉で品質良好な極早生品種で、7月下旬には収穫できる甘くておいしい赤ナシです。」。再び「ナシ園」を見る。休憩場所には親子三代の家族の姿が。そしてオレンジ色の家は「チャペックの家と庭」。『花菜ガーデン』が理想とする、チェコの園芸家カレル・チャペック氏の家と庭をイメージしたものだ と。「House and Garden Karel Capekチャペックと庭世界中の園芸家から愛され続けている「園芸家12ヵ月」の著者カレル・チャベックは、仕事に趣味に忙しい毎日を送る中、自らも生涯庭いじりを楽しみました。そんなチャペックのライフ・スタイルや庭を愛する心は、現代へ、そしてこの花菜ガーデンへと通じています。今もなお、チェコに残る彼の家と庭を、花菜ガーデンのシンボルとして世界で初めて再現しました。池のほとりにダーシェンカが座っているかもしれません「園芸家12カ月」(1929年出版)に描かれている庭の風景・植物、そして今でもプラハに現存する家の庭を参考にして再現したガーデンです。このガーデンを訪れる方々に「チャペックのように庭づくりのおもしろさや苦労を見つけ、園芸家にとってのーっーっの作業すべてを楽しみたい」と思っていただけるような庭をつくりました。自分の庭でお客様をもてなすのが好きだったチャペック。デルフィニウム、カンパニュラ、ドイツスズランなどの宿根草を中心にここでは一年間いつ訪れても花を楽しめるように、その季節の一年草を交えて植栽しています。今もなお、存在するチャぺック邸チェコ・プラハの街に今もなお当時の面影を残して佇むチャベック邸。当時、この家を二分して、カレル・チャペックと父、兄で画家のヨゼフ・チャぺックとその妻及び娘が住んでいました。そのことから、家の前の通りは、「チャぺック兄弟通り(BRATRI CAPKU)」と名付けられています。二人の死後は、それぞれの親族とその子孫が、彼らの残した数多くのエピソードとともに、チェコにあるこの家を代々受け継いでいます。20世紀を代表するチェコの作家カレル・チャベック(Karel Capek / 1890-1938 )新聞記者であり、作家であったカレル・チャペックは、評論、小説、童話、旅行記、工ッセイ、戯曲と幅広い分野で筆をふるいました。代表作「R. U. Rロボット」(1920年出版)で「ロボット」という言葉を作り出した人物としても有名。そのほか人気作品として「ダーシェンカ」(1933年出版)「山椒魚戦争」(1936年出版)など。1938年12月25日肺炎により死去。」。「チャペックの家と庭」のフェンスの赤いつるバラ。「BRATRI CAPKUVINOHRADY-PRAHA 10」と。「チャペックの家」。邸内に入ると、レンガ造りのベンチには「ZZZ・・・・」と。展示室に入る。「プラハ郊外のカレル・チャペックの家チャペック兄弟通りと名づけられた小道の奥にその家は今も現存します。カレルの妻オルガの親族である優しい女主人がイリスと名づけた犬と一緒ににゆっくりと静かに家を守り、まるでカレル・チャペックが生きていたときそのままの時を今も刻んでいます。」。「Karel Capekカレル・チャベック(1890.1.9 ~ 1938.12.25 )20世紀前半を代表するチェコの作家、ジャーナリスト。評論、小説、童話、旅行記、工ッセイ、戯曲といった幅広い分野で筆を振い、秀作を数多く残している。なかでも、1920年に出版された戯曲『R. U. R.ロボット』は、「ロボット」という言葉を生みだした作品として知られている。また、「園芸」「ペット」「カメラ」をはじめとする多彩な趣味の持ち主だったことから、『園芸家12カ月』や『ダーシェンカ」のような趣味に関連する作品も多い。1938年12月25日肺炎で死去。享年48歳。」「カレル・チャペックの生涯」。様々な「カレル・チャペック」に関する展示パネルが。「今もなお、チェコ・プラハに存在するチャぺック邸花菜ガーデンのシンボルとして園内に再現されている「チャぺックの家と庭」は、チェコ・プラハのヴィノフラディ地区に現存する家で、1925年からカレル・チャペックが暮らしていたとされています。当時、この家を二分して、”カレルと父”、”兄で画家のヨゼフと妻と娘”が住んでいました。チャペック兄弟自ら造園に携わったというこの家の庭に、カレルはしばしば客人を招いていました。そのなかには、政界・文学界の著名人や、時の大統領マサリクの姿もあったようです。兄弟の死後は、それぞれの親族とその子孫が、彼らの残した数多くのエピソードとともにこの家を代々受け継いでいます。」。「ゆかりの品々に出合えるカレル・チャペック記念館チェコ・プラハ南部の村スタラー・フッチのある『カレル・チャペック記念館』には、カレルと兄・ヨゼフの作品をはじめ、兄弟にまつわる品々が展示されています。この建物は、カレルの結婚のお祝いに義兄から贈られた家で、カレル自身、1935第から1938年まで別宅として使っていました。広人な自然に囲まれたこの家と庭をとても、気に入ったカレルは、当時暮らしていたプラハの家はそのままに、晩年の作品の大半をここで執筆したといわれています。この記念館のほか、カレルの生地マレー・スヴァトニョヴィツェにある『チャペック兄弟記念館』でも兄弟ゆかりの品に出合えます。写真上/プラハ南部の村スタラー・フッチにあるカレル・チャペック記念館。写真下/マレー・スヴァトニョヴィツェにあるチャペック兄弟記念の"チャベック・ブラザーズ像”」「チャペックの家と庭」の前に広がっていた「花菜ガルテン(かながるてん)“クラインガルテン”はドイツ語で、市民農園のことをさすと言われています。ここでは、都市に暮らす人々に潤いを与える市民農園の参考になるような展示や体験を展開しています。こどもから大人まで、土や農業に触れることができる“トライアル農園”、体験し、観賞することの楽しさを実感する“キッチン菜園"誰もが土に触れることを楽しめるレイズドベッドの“テープル花壇"など、さまざまな形でみなさまの庭づくりをご提案します※レイズドベッド:立ち上がり花壇」。トライアル農園講座やプログラムを通して、屋外の土で園芸や農業のイロハを学べる体験フィールド。栽培ステージごとのプログラムで学ぶことができます。キッチン菜園スペースの有効活用や作業のしやすさ、観賞する楽しさなど、あなたの庭やペランダの新しい魅力づくりのヒントがみつかりますテープル花壇テープルの高さに土があることで、立ちながらでも座った状態でも植え込みや手入れ、観察をどなたにでも楽しんでいただけます.「土のパーゴラ」を見る。「パーゴラ」とは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことです。 イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなど蔓科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮り、涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます と。「触れん土ファームFriend Farmここはこどもたちが中心となって取り組む農業体験学習のフィールド。神奈川県内の主要生産品目や育成品種を中心にいろいろな野菜を栽培し、それぞれに生まれ育つ様子を目の当たりにすることができます,友だちのように土に親しみ、友たちと一緒に力をあわせて新しい発見=”きづき”を感じてほしいという私たちの想いをこめた、大切な育みの場所です。」「触れん土ファーム Friend Farm」への植え付けはこれからか。童話の世界に出てくるような小屋が絵になります!「総合案内 Information」トラクターに乗って遊ぶ子供達。こちらの水田・田んぼは、稲の植え付けの準備中か。「ユニバーサル遊具の広場誰もがみんな同じ空間で遊べるよう工夫された遊具です。お友達といっしょに仲良く遊んでね!」工夫された遊具。蓮田であっただろうか。蓮の花が咲けば・・ネットから。蓮の花が咲けば・・ネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.04
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その34):専福寺
次に訪ねたのが「東林寺」の隣りにあった「専福寺」。1504年僧久悦が創建。俳人の小林一茶が恋人の「寿」の菩提を弔うために、何度かここを訪れていると。ちなみに恋人の「寿」のお墓は、関東大震災により山崩れで見つからなくなった と。横須賀市東浦賀2丁目10−6。「永昌山 専福寺」掲示板。石段下にあった「一葉観音(いちようかんのん)」。道元禅師が仏法を求め中国に渡られ、修行を終え、帰路の船旅での出来事です。大変な嵐に遭遇され、危うく命を落すところでしたが、一心に観音経を念誦されると、蓮華の花びらに乗った観音菩薩が現れ、風雨が静まり助けられた。順風満帆な旅を約束し、交通の安全さらには水難から身を守ってくださる観音様として今も深く信仰されていると伝えられています と。お顔をズームして。龍の吐水口(とすいこう)からは清水が。本殿に向かって石段を上って行った。石碑が並ぶ。寺号標石「浄土宗 専福寺」。 「呑龍上人宝前」碑。呑龍上人といえば、「太田(群馬県)の呑龍さん」の名で親しまれ、病弱な子供の立派な成長を願うお参りが絶えなかったといわれます。しかし、専福寺とのつながりはよくわかっていません。「宝前」とは、 神仏をまつった所の前を尊んでいう語 と。石段を上った場所にも石仏が2体。「地蔵堂」。「地蔵尊」と。お地蔵様は2体。こちらの堂は?子育地蔵尊。「子育地蔵尊??」「専福寺」の「本堂」。永昌山戒寿院専福寺・浄土宗鎮西派。扁額「専福寺」。「専福寺永正元年(一五〇四)僧久悦が創建の浄土宗のお寺です。本寺の阿弥陀三尊像は高村光太郎の祖で江戸時代の仏師・高村東雲の作です。文化三年(一八〇六)ごろ俳人小林一茶が初恋の人の菩提を弔うために何度か訪れたといわれます。墓地には東叶神社の芭蕉碑を建立した俳人福井貞斎とその娘・福の墓があり、浦賀の俳人達にはゆかりの深いお寺です。本堂の脇には浦賀町長を務めた廻船屋川津屋太田又四郎や浦賀畸人伝にその名をとどめる桐ヶ谷善兵衛等の墓もあります。 浦賀行政センター協働事業・浦賀探訪くらぶ掲示より」「阿弥陀三尊(高村東雲作)」。「動物供養塔」。「洗心念佛」と台座に刻まれた石仏。石仏に近づいて。「水かけ観音」。「水かけ観音さま観音さまに水を流して浄めると病も心の汚れも流されて守られ清く美しい姿になります 住職」「一茶の句碑」。一茶の初恋の人の墓地があって、一茶は少なくとも1回、文化3年(1806、一茶44才)6月に墓参りに専福寺を訪ねています。なお、市内佐島にも同名のお寺があります と。『遠き想い出のひと寿女の碑夕立の 祈らぬ里に かゝるなり 一茶』六月一日金谷から船に乗り浦賀に渡りその人の祥月命日の六月ニ日に墓参するためだ 一日晴 浦賀ニ渡ル 白毛黒クナル薬クルミヲスリツブシテ 涼風も けふ一日の 御不二哉 二日晴 夜雨 夕立の 祈らぬ里に かかるなり 三日晴 東浦賀州崎町専福寺ヘ参ル 香誉夏月明寿信女 天明二[年]六月二日没 文化三年一茶旅日記より」「小林一茶の初恋の人"寿(ひさ)”のお墓は山際にあったと言われていますが・・・一茶の合掌する姿が目に浮かんでまいります。 住職」「無縁塚」。多くの石仏が並んでいた。裏山の擁壁の下に墓地が拡がっていた。「永代供養塔」。「聖観音立像」か?正面から。ズームして。台座には「永遠の郷」と。「永代供養塔」と。本堂の脇には、浦賀町時代に町長となった回船問屋川津屋の太田又四郎の墓碑があった。「寺務所」。「寺務所」の玄関。見事な彫刻。再び境内入口を見る。大きな石碑が二基。「陸軍工兵一等兵 勲八等功七級 二木本松蔵碑」。「橋本䞾之碑」石仏(左は延宝5年(1677年)銘、右は元文2年(1737年)銘)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.04
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その4)
「ウインドラッシュ Windrush」。どこかアルバ・セミプレナを思わせるような半八重の花が爽やか。親のゴールデンウィングスのように花つきが良い、名前はイギリスのコッツウォルズ地方を流れる川にちなむ。柔らかな花びらのバラ・ウィンドラッシュ、色もソフトホワイト。南仏の風が似合いそうな 匂いたつ薔薇。花径は、7~9センチ。「ウインドラッシュ Windrush」英:オースチン 1984年作出。前方に四阿風休憩場所。その手前に「クイーン オブ スェーデン Queen of Sweden」チャーミングで小さいふっくらとしたつぼみは、しっかりと包み込まれたカップ型からシャローカップ咲きになります。花色はソフトで輝くようなアプリコットピンクから、清らかなソフトピンクへと変化します。中輪の花姿はいつ見ても美しく、オールドローズの性質をずいぶん受け継いでいます。まろやかなミルラの香りがします。まっすぐ上に伸び、飛びぬけて丈夫でよく茂る、とても耐寒性のある品種です。トゲが少なく、花は摘み取った後も日持ちがするので、室内でフラワーアレンジメントとして楽しむのにも向いています。イギリスとスウェーデンの友好条約が結ばれて以来、350年 を記念して生まれたバラです と。「クイーン オブ スェーデン Queen of Sweden」英:オースチン 2004年作出。「レディ エマ ハミルトン Lady Emma Hamilton」色鮮やかなこのイングリッシュローズは、ボーダーの中で、ひと際目を引きます。しっかりとつぼんだつぼみは、オレンジの混じる深みのある赤で、魅力的なダークの葉との間にコントラストが生まれます。花が完全に開くと、花びらの内側はタンジェリン(濃いオレンジ色)外側はイエローオレンジが混ざり合った色合いの花になります。やや直立状に伸びますが中程度の育ち方でよく茂り、花は驚くほど次から次へと咲き続け、乾燥した地域で、よく育つ傾向があります。洋ナシ、グレープ、シトラスの調べのフルーツ系の濃厚かつさわやかな香りは、フランスのナンテスの香りのコンテストでトップ賞を受賞しました。エマ・ハミルトンは、ネルソン提督の恋人の名前です。「レディ エマ ハミルトン Lady Emma Hamilton」英・オースチン 2005年作出。ここにも蔓薔薇・クライミングローズのトンネルが前方に。花菜ガーデンの池・「願いの泉」には睡蓮の花も咲いていた。中央の黄色が美しい満開のピンクの睡蓮。こちらは別の種か?ズームして。徹底比較!「ハス(蓮)とスイレン(睡蓮)」ハス(蓮):水面よリ高い位置で咲く 花びらは1枚ずつ散り、散り終わると花托ができる。スイレン(睡蓮) 水面に浮いてるように咲く。 花が咲き終わったらしぼんで沈む。親子仲良くベンチで。その後ろのツルバラをズームして。「田毎の月 Tagoto no tsuki」。純黄色、丸弁一重のカップ咲き。日本ばら会の“2010年度 JRC新品種コンテンスト 入賞花のご紹介”というページでは、フロリバンダの部金賞になっている と。「田毎の月 Tagoto no tsuki」日:吉池 貞蔵 2010年 作出。「フラワーステーション」の壁にも。「ヒュー・ディクソン Hugh Dickson」。「ヒュー・ディクソン Hugh Dickson」英・Hugh Dickson 1905年作出。そして「風ぐるま迷図 香りのバラ香りのよい65品種のバラを選び、展示したエリアです。」「香りのバラ」コーナーは迷路になっていた。「イブ ピアッチェ Yves Piaget」 。艶のあるピンクで波打つ花弁と豪華な花容、甘い芳香が素晴らしい と。「イブ ピアッチェ Yves Piaget」仏:メイアン 1983年作出。「香りのバラ」コーナーの四阿を見る。「風ぐるま迷図 香りのバラ」。「ルージュ・ロワイヤル」。近づいて。そして純白のクレマチスも開花中。「クレマチス ’早池峰’」。「クレマチス ’早池峰’ Clematis ’Hayachine’ 早咲き大輪系」。「クレマチス 'ミセス・チョムリー' Clematis 'Mrs Cholmondeley'」。「クレマチス 'ミセス・チョムリー' Clematis 'Mrs Cholmondeley' 早咲き大輪系」。「クレマチス ’ブルー・ライト’ Clematis 'Blue Light'」爽やかなスカイブルーのセミダブル咲き咲き進むとポンポンの万重咲きになり、花持ちよく長期間楽しめる花径10cm程の大輪、強健で育て易い品種 と。「クレマチス ’ブルー・ライト’ Clematis 'Blue Light' 早咲き大輪系」。「ヨハネ パウロ 2世 Pope John Paul Ⅱ」。白バラには少ない、花の大きさ・ボリューム感・花形のどれをとっても優れたバラ。多湿な環境でも花弁にしみがつきにくく、美しい姿を保ちます。このバラは第264代ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の偉業を称え、バチカン法王庁がバチカン庭園に植樹する為に選ばれました。光沢のある純白の花弁は、高貴な法衣姿を偲ばせます。生育旺盛で耐病性もあり、濃緑色の葉が花の色を引き立てます。きりっとしたフレッシュシトラスの芳香です。2010年豪アデレード金賞、ベストローズ、ベストHT、芳香賞受賞 と。「ヨハネ パウロ 2世 Pope John Paul Ⅱ」米:ザリー 2007年作出。近づいて。「エンティンテッド イブニング」藤色、丸弁咲き、中輪房咲きの花。ブルーの強香。四季咲き性。樹勢は普通で耐病性も普通、木立樹形のバラ。トゲは普通 と。「ウィティケラ(ヴィチセラ)系ヨーロッパに自生するクレマチス・ウイテイケラの交配種のグループで、小輸の花を節々に多数咲かせます。品種によって花型は異なり、ベル型や正開咲き、八重咲きなどがあり、花の咲く向きも横向きや下向き、上向きと様々です。中には香りのある品種もあります。新梢咲きで、冬季に地上部は枯れてなくなります。開花期は初夏から秋で、四季咲き性が強く長期間楽しめます。日本の曇さや寒さにも耐え、立枯病に強く、丈夫で育てやすい品種が多いので、ガーデニングには最適なグループです。」この花は?「サニーノックアウト」黄色、丸弁咲き、小中輪房咲きの花。ティの中香。四季咲き性 と。「月光 Gekko」。輝くような黄色は「月光」の名にふさわしく、花色・花形、香りと三拍子そろった優良品種です。1999年JRC銅賞受賞 と。「月光 Gekko」日:京成バラ 1999年作出」。再び「花ぐるま迷図」の四阿。その手前に大輪の黄色いバラ。「ドゥフトゴルト Duftgold」。ドゥフトゴルトは大きさ12㎝ほどの黄色い花を咲かせるバラの品種です。半剣弁高芯咲きの花形で、春の花は花びらに切り込みが入ることが多いです。早咲きの品種で花付きもよく、強い芳香があります と。「ドゥフトゴルト Duftgold」独:タンタウ 1981年作出 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.03
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その33):浦賀山立像院東林寺(2/2)
「東林寺」の「本堂」内をガラス越しに。ズームして。本堂の正面に本尊「阿弥陀如来」が安置されていた。さらに。実はこの阿弥陀仏の胎内にある、もう一体の阿弥陀仏が本当の本尊ということになるのだ と。「延命地蔵尊」。こちらはネットから。こちらの「延命地蔵尊」の仏師等は不明だが、本尊阿弥陀如来坐像の腹籠仏として納められた三尊仏と同時代のものと考えられるとのこと。「天水桶」前の「仁王像」(左)。「天水桶」前の「仁王像」(右)。「永代供養の塋(つか)」と。「浦賀山 雲上殿」とも。「忠魂碑」碑正面:「忠魂碑 陸軍大将正二位勲一等功二級侯爵 大山巌書」と。この碑は元々、愛宕園(愛宕山公園)に日清戦争の戦病死者の忠魂のために明治30年3月に建立されたものである。関東大震災により碑は倒壊したが、昭和初期(御大典記念として昭和3,4年頃と推測)に高坂小学校校庭に移された。戦後の混乱で引き倒され放置されていたのを、昭和24年3月に井上亀之助が小学校裏山に立て直したが、その際、碑の両側に昭和になってからの戦没者も併せ慰霊するために昭和事変英霊の碑を建立した。その後、昭和38年10月15日に、現在地に移された。建立当初に合わせ建てられていた建設発起人の碑は、現在は忠魂碑の裏にある。なお、忠魂碑左手には、碑の再建に尽力した井上亀之助顕彰の碑が建てられている と。「忠魂碑」の両側には昭和事変英霊の碑、背面に重なるように「忠魂碑建設発起人碑」があった。卒塔婆には「十夜回向一会為旧浦賀地区出身の諸英霊位追善菩提 当山・・」と。六地蔵。墓地を散策する。墓地の外壁には天女が描かれていた。左の墓石には「南無阿弥陀佛 中興 練誉上人」と。ズームして。劣化が進んでいたが。こちらには、蓮の花が。ここには、無縫塔の墓石が並んでいた。ズームして。相輪の部分が、花を重ねたが如くの宝篋印塔の墓石。「延命地蔵塔」。再び「本堂」、「水子地蔵尊」を振り返る。墓地入口付近には、浦賀奉行所与力であった中島三郎助親子の墓があった。三郎助は明治維新の際、あくまで幕臣としての意志を貫き、函館千代ヶ岱台場で父子ともども戦死した。時に49歳。しかし、浦賀に残した足跡は、まことに大きいものがあるのだ。俳人としても有名で、俳号を「木鶏」といいます。いまは父子共々、浦賀港を一望するこの高台に眠っている。毎年5月に、ここで三郎助の墓前祭が執り行われているとのこと。右側に墓石が二基。手前が「中島三郎助墓」。1821(文政4)年、相模国浦賀奉行所与力中島家生まれ。1849(嘉永2)年、浦賀奉行与力となり、アメリカ・ペリー艦隊来航時に、アメリカ側使者の応対を勤めた。1855(安政2)年、長崎海軍伝習所の第一期生となり造船学・機関学・航海術などを修め、築地軍艦操練所教授方出役に任命された。その後、与力の職を長男恒太郎に譲ったが、戊辰戦争勃発後に、榎本武揚らと蝦夷地に渡り箱館戦争に参戦した。蝦夷地仮政権で箱館奉行並・砲兵頭並を務め、千代ヶ岡陣屋守備隊長として奮戦した。新政府軍の攻撃にも陣屋で抵抗したが、6月25日(旧5月16日)に、長男恒太郎・次男英次郎・腹心柴田伸助らと共に戦死した。享年49歳。左隣には次男「中島英次郎墓」中島三郎助の次男。房次郎ともいう。父と兄恒太郎とともに箱館戦争に参戦し、千代ケ岡陣屋の守備隊に就いた。1869(明治2)年6月25日(旧5月16日)、新政府軍の攻撃に対して奮戦したものの、父や兄とともに壮烈な戦死を遂げた。享年19歳。「中島三郎助」親子の写真をネットから。正面に「中村家累代之墓」。「本堂」の右・南側にあったのが「寺務所・庫裡」であっただろうか。白壁が美しかった。廻り込んで。玄関右手にも、南無阿弥陀佛碑と石仏。白壁、竹垣、新緑そして紅葉とのコラブ。新緑と紅葉をズームして。本堂の屋根には「卍」が。そもそも「卍」は、サンスクリット語で「スヴァスティカ」と呼ばれ、吉祥の印として、「幸せ」や「めでたい」という意味があります。また仏教ではこの卍紋様は仏様を象徴する印の一つとされています。寺院の建物をよく見ると色々なところに卍紋様が彫刻されているのはこのためです。地図記号に卍が用いられているのは、仏様がいる場所を示す意味を込めてこの記号が使われたということです。また、この卍が右に回っている事も重要なポイントです。仏教では「右」をとても尊重して考えています。ちなみに仏様の髪の毛なども全て右回りに巻いています。その反対に左に巻いてあるものはつむじ曲がりといい、あまり良い意味で使われていないのです とネットから。坂を下り、「東林寺」そして「三浦稲荷社」の境内を振り返る。こちらが「三浦稲荷社」の参道。参道石段下の石仏。右は元禄7年(1694年)銘。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.03
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その3)
「モダンローズ」区域の散策を続ける。「シンシア・プルック Cynthia Brooke」。少し樺色を含むオレンジ色が特徴、幾重にも重なった薄い花弁が優雅。濃い緑の葉も花色をひきたててとても魅力的。低めに茂り株のまとまりもよい。古いハイブリッドティーの良さを現在に伝える貴重な品種です。ティー香があります と。「シンシア・プルック Cynthia Brooke」アイルランド:McGredy 1943年。「クライミングとシュラブローズ」への手前の正面の生け垣前に対で。「ノック アウト Knock Out 」。ローズ色がのった赤色の花は3~5輪位の房咲きで黄色いシベを覗かせる。2018年第18回デンマーク コペンハーゲン大会で世界バラ連合の栄誉殿堂入りを果たしている と。「ノック アウト Knock Out 」米:ラドラー 1999年作出。「薔薇愛で人」の数も増えて。「ピース Peace」。20世紀を代表する傑作品種。バラの歴史を大きく変えた、フランスの大育種家「フランシス メイアン」の最高傑作の1つです。巨大輪の先駆的品種であり、黄色の花にうすいピンク色の覆輪が入るふっくらとした花容、照りのある大きな葉、まとまりよく伸びる樹に巨大輪であるにも関わらず良好な花付き、そして強健な樹勢、良質な性質を多く持ち合わせたこの品種は戦後世界的大ヒットとなりました。特徴的な照り葉は、交配親の「マーガレット マグレディ」より受け継がれたものです と。「ピース Peace」 仏:メイアン 1945年作出。「20世紀を代表する「ピース」とその子品種たち第二次世界大戦終結後の1945年、世界の平和を願って命名・発表されたパラ「ピース」は、丈夫な性質と今までにないボリューム感のある巨大輪花が評価され、瞬く間に世界中で人気品種となります。「ピース」の登場は革命的な出来事であったため、やがて「ピース」を親とした子品種が続々と登場しました。ここでは、「ピース」とその子品種たちを集めて展示しています。後に「ピース」は20世紀を代表するバラとされ、1976年に世界バラ会連合選出の「バラの栄誉の殿堂」入りの第1号品種となりました。」「ピース」とその子品種たち。「多彩なモダン・ローズの世界ハイプリッド・ティー系とフロリバンダ系に代表されるブッシュ・タイプのモダン・ローズは、20世紀に最も広く栽培されたバラで、立派な葉に色とりどりの洗練された印象の花を咲かせます。ここでは、それらの品種を色別に展示しています。多彩な品種の中でも「スーパー・スター」は、「ピース」と共に20世紀を代表するバラとされ、当時の人々が切望していた未色の大輪バラの第一号品種になります。その他にもラヴェンダーや茶色など、モダン・ローズならではの、複雑な色彩のバラをここでは見ることができます。」モダン・ローズの世界を楽しむ。「ダブルデライト Double Delight」。黄色みがかった白地に非常に強く赤色の覆輪が入る特有の花色、花容。半横張りの樹形でトゲが多いですが、その鮮やかな花は庭を華やかに彩ります。弁はしっかりしており、豊かな芳香にも恵まれています。ただ、葉質が少し弱いので春先のベト病や薬害等には注意が必要です と。「ダブルデライト Double Delight」米:スイム&工リス 1977年作出。「アブラカダブラ Abracadabra」。咲き始めは濃いピンクに中心部がアプリコットの丸弁高芯咲き。四季咲き大輪のHT(ハイブリットティー)です。黄色からクリーム色、赤ピンク、赤紫、白と、咲き進むにつれて色味が変化して移り変わります。株の状態や気温や環境によって、黄色味が強かったり、全体的に淡いピンクがかったり、白と覆輪の濃いピンクが出たりなど、色幅があります。魔法の呪文の「アブラカダブラ」、名前の通り魔法のような色変わりが美しい品種です と。「アブラカダブラ Abracadabra」 独:コルデス 2002年作出。「パローレ Parole」。ローズ色の花は巨大輪で剣弁高芯咲き。クラシック・ダマスク香を中心にフルーツ香、ティー香がのる超強香。花型もよく切花のコンテストにもよく利用される。半直立性で株のまとまりはよくあまり樹形を乱す枝の発生はない。冬季剪定では樹高の1/2位を目安に切り戻す。マドリード国際コンクールで芳香賞を受賞 と。「パローレ Parole」独:コルデス 2001年作出「ニュー バレンシア New Valencia」。四季咲き、大輪系。一茎に一輪咲かせて花の見事さを楽しみます。モダンローズの中心的存在で、バラの60%を占めます。バラが世界中の人に愛されるようになったのはこのハイブリッドティーローズがあったからこそと言っても過言ではありません。格調高い花形、豊富な彩りは花壇・鉢植え・切花にも良く、楽しみ方も育て方もいろいろ。木バラの代名詞でもあり、香りが強い品種が多いのが特徴です と。「ニュー バレンシア New Valencia」独:コルデス 1989年作出。少女像も。すずなりに咲く薔薇の花。「すずなり」正しい使い方??こちらには裸婦像が。全て同じ作者なのであろうか?「つるシャルル ドゥ ゴール Cl.Charles.de Gaulle 」。ラベンダー色と花形の華やかさが素晴らしく、香りも楽しめる優れた品種です。花つきもよく、丈夫な大株になり、棘は少ないです。花名は元フランス大統領の名前です と。「つるシャルル ドゥ ゴール Cl.Charles.de Gaulle 」2012年作出。「クライミングとシュラブローズ」のコーナー。クライミング・ツル性のバラ、シュラブ・半ツル性のバラとのこと。「ツルバラとシュラブローズモダン・ローズの中には、長く伸びた枝を構造物に誘引して楽しむクライミング・ローズ(ツルバラ)やシュラブ・ローズ(半ツルバラ)もあります。ツルバラやシュラブ・ローズは、ブッシュ・ローズよりも四季咲き性では劣るものの、一度に多数の花を咲かせるため、開花期には大変見事な景観を作り出せます。ここにも「クライミングとシュラブローズ」の世界が拡がっていた。ここは「シュラブローズ」の世界か?前方に「クライミング・ローズ(ツルバラ)」用の棚が。再び「シュラブローズ」を。近づいて。色彩豊かに。「サハラ ’98 Sahara ’98」に近づいて。黄色からだんだんオレンジ色に変わります。最盛期は見事な景観を作ります。秋にもよく咲く、丈夫で使いやすい品種です。陽当たりの良い場所で美しく発色します と。美しいグラデーションが見事!!「サハラ ’98 Sahara ’98」独:タンタウ 1996年作出。「シティー オブ ヨーク City of York」。ヨーク市はイングランド北部のノース・ヨークシャー州の都市であり、ヨーク大聖堂をはじめ中世の町並みが良好な状態で保存された、大変美しい観光地としても知られています。アメリカのペンシルベニア州にも同名の都市があり、薔薇戦争で知られるヨーク家の紋章にちなんで「ホワイトローズ・シティ」と呼ばれることもあります。ばらの「シティ・オブ・ヨーク」も大変に美しい白ばらで、半八重のシンプルな花容に黄色い大きなおしべがひときわチャーミングです。一度に大量に咲く咲き方はしませんが次々と咲かせ、時に秋にも返り咲きます。 葉も光沢のある深緑で美しく、開花がない時期にも楽しめます と。「シティー オブ ヨーク City of York」独:タンタウ 1945年作出。正面にクライミング・ローズ(ツルバラ)とシュラブ・ローズ(半ツルバラ)。そして「イングリッシュ・ローズイギリスのバラ育種家デビッド・オースチン氏はモダン・ローズがオールド・ローズの持つ繊細で儚げな美しさを失っていく中、オード・ローズの持つ美しさとモダン・ローズの優れた四季咲き性を持ち合わせたバラを目標に改良を始めます。こうして誕生したイングリッシュ・ローズは、作出当初は人々に受け人れらませんでしたが、1980年代中ごろより人気が出始め、20世紀末には一大ブームとなりました。その影響は他の育種家達にも及び、同様のクラシカルな花型の品種が近年次々と誕生しています。」「ワイフ オブ バス Wife of Bath」。品種名は「バースの夫人」という意味で、「カンタベリー物語」の一節に出てくる老婦人のことをさしています。古いイングリッシュローズ。花の中心はピンク、外に向かって次第に薄く。ミルラの香り。「ワイフ オブ バス Wife of Bath」英:オースチン 1969年作出。「L.D.ブレイスウェイト L. D. Braithwaite」。鮮やかな濃赤色の大輪花で3-5輪の房咲きになり、良い香りがあります。カップ咲きの花は開花が進むとロゼット咲きになっていきます。株は半直立性で比較的大きな株になり、少しとげが多いです と。「L.D.ブレイスウェイト L. D. Braithwaite」英:オースチン 1998年作出」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.02
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その32):三浦稲荷社~浦賀山立像院東林寺(1/2)
次に訪ねたのが「三浦稲荷社」。横須賀市東浦賀2-10-13。「三浦稲荷社」への参道の石段の手前にあったのが隣にあった「浄土宗 浦賀山 東林寺」の掲示板。「三浦稲荷社」は東林寺の境内に鎮座する稲荷社のようであった。「南無阿弥陀佛」と刻まれた六字念仏塔の碑。「深本、雷電、三浦稲荷社南無阿弥陀佛と刻まれた六字念仏塔祐天寺六世祐全(ゆうぜん)上人による名号(みょうごう)石塔で、江戸屋半五郎によって建立されました。名号の掘りも深く、半五郎の信仰の深さがうかがわれます。半五郎は浦賀で遊郭を営み繁盛していましたが、後にすべての財産を処分して遊女たちに分け与えて開放してやりました。自らは京都青龍寺で得度し、生き仏といわれた徳本上人の弟子深本(しんぽん・深心(しんしん))となり仏門に帰依しました。「浦賀事績考」によれば東林寺境内の稲荷前では文化六年(一八〇九)、当時の花形力士の雷電為右衛門(らいでんためえもん)の相撲興業が行われたと記されています。三浦稲荷社の稲荷神は倉稲魂(うかのみたま)で五穀豊穣、開運出世、商売繁盛の神です。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」深本が寄進した西叶神社手洗石と雷電(相撲博物館)。「浦賀事跡考」によれば、東林寺境内の稲荷前では文化6年(1809)、当時の花形力士の電電為右衛門の相撲興行が行われたと記されていると。三浦稲荷社の稲荷神は、倉稲魂で五穀豊穣、開運出世、商売繁盛の神。浦賀駅の近く、住友重機械工業㈱の浦賀工場の壁にあった、浦賀中学校の生徒による絵画を想い出したのであった。「三浦稲荷社」の左側には寺号標石「浦賀山立像院東林寺」。「三浦稲荷社」の石鳥居。社殿に向かって進む。社殿前の参道は駐車場にもなっているようでで、広々としていた。手水鉢。社殿の見事な彫刻。よく見ると、正面には一匹のお狐様のお姿が。木鼻(右)。木鼻(左)。扁額「三浦稲荷社」。内陣。「正一位三浦稲荷大明神」。社殿を斜めから。社殿前から石鳥居方向を振り返って。隣りにあったのが、「東方寺」の巨大な石灯籠。鹿の姿が。ズームして。そして「東林寺」の本堂に向かって石段を上って行った。参道石段脇の「延命地蔵願王尊」。三浦三十八地蔵尊霊場35番札所の御前立地蔵。小さな石仏も奉納されていた。「念佛衆生 攝取不捨」と刻まれた石碑も。仏がこの世の衆生しゅじょう、生きているものすべてを見捨てず、仏の世界に救い上げること。▽「摂取」はその慈悲心で衆生を仏の世界に救うこと。 「不捨」は仏がどのような生き物をも見捨ててしまうことはないということ と。「光明徧照 十万世界」と。大意は、「(阿弥陀仏の体から放たれる)光はあまねく十方世界を照らし、仏を念ずる衆生を救いとって見捨てることがない」と。浄土三部経の一つ『観無量寿経』に「一々光明、遍照十方世界、念仏衆生、摂取不捨(一つ一つの光明があまねく十方の世界を照らして、念仏する衆生を捨てられることがない)」と出ていて、浄土宗では普段のお勤めの時に、その文句が唱えられているとのこと。左側にあった歌碑。三浦三十八地蔵尊霊場35番札所の御詠歌か?「慈悲のうみ ちりひの船を 浮かべつつ いく世よまでも 救ふとうとき」参道石段横の御堂。シャッターには??が描かれていた。本堂の前にあった観音像の絵。龍に乗った観音様の姿か?「徳川家康遺訓人の一生は重荷おもにを負をひて遠き 道をゆくが如し いそぐべからず 不自由を常とおもへば不足なし こころに望のぞみおこらば困こん窮きゅうしたる時を思ひ出いだすべし 堪忍かんにんは無事ぶじ長久ちょうきゅうの基もとい いかりは敵とおもへ 勝事かつことばかり知しりてまくる事をしらざれば害がい其その身みにいたる おのれを責せめて人をせむるな 及ばざるは過すぎたるよりまされり」こちらにも別の絵が。観音様か?近づいて。本堂と向かい合うように石碑が。「井上亀之助顕彰の碑」卒塔婆には「旧浦賀町出身戦死病没諸英霊位追善菩提井上亀之助(井上祐一)」と。碑正面:「井上亀之助氏顕彰碑およそ、人の真価は事ある時に顕われる。意志の人、勇気の人、義侠の人、それは故井上亀之助氏その人である。戦後進駐軍の占領政策は厳しく教育の場から忠魂碑をも奪った。しかし、これを顧みる余裕すらなかった当時の世情こそあわれという外はなかった。放置された忠魂碑、これを見るに忍びず井上氏は私財を投してこれを弁天社に移した。さらに参詣者の便をはかり再びこの境内に移して英霊を守り通したのである。今は亡き井上氏しかし氏の義挙は生きている。いや、いつまでも不滅であろう。われわれは祈る。英霊永えに安らかなれと。昭和三十八年十月十五日 建設委員會建立」左手の石仏には、延宝8年(1680年)の銘が。こちらに水子地蔵尊が。「水子地蔵尊」。お顔をズームして。「本堂」。寺誌によれば、開山は唱阿上人。しかし、『新編相模国風土記稿』には、「いにしえは今の寺院を分ち唱へて二ケ寺なりしを大永三年(1523)僧良道合わせ一寺とす、故に此僧を開山と称す」とあると。本堂の正面に本尊「阿弥陀如来」が安置されていた。実は、この阿弥陀仏の胎内にある、もう一体の阿弥陀仏が本当の本尊ということになるとのこと。更にこの脇に、もう一体阿弥陀仏が安置されていると。この仏像は「善光寺式阿弥陀仏」といわれ、長野県善光寺の本尊を模して造られたもので、室町時代初期の作風をよく顕しているということで、市指定の文化財になっています。本尊の阿弥陀仏と善光寺式の阿弥陀仏を見比べると、阿弥陀仏の作風の変遷が見られます と。また、鎌倉時代の作といわれる市指定の重要文化財「阿弥陀二十五菩薩来迎図」が保存されている と。近づいて斜めから。正面から。蟇股の装飾。木鼻(右)。木鼻(左)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.02
コメント(0)
-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その2)
「れもん Lemon」。熟れたレモンを思わせるような、純黄色の爽やかなバラ。花はころんとしたカップ咲きになり、一枝に1輪~3輪ほどの蕾をつけます。芳香があり、ダマスク・シトラス・ティなどがミックスされた香り。花つきがとてもよく、秋までよく咲きます。 樹形は半直立性~やや横張り。花名の由来は花色と花形の印象から小説「檸檬」 のイメージから。同作品は大正~昭和初期の小説家・梶井基次郎の短編小説。「丸善の棚の檸檬」のフレーズで著名。「春告げの小道」の両脇のバラを楽しみながら進む。「れもん Lemon」日:今井ナーセリー 2017年作出。「サニーアンティーク Sunny Antike」レモンイエローで爽やかな香りがある。「キャラメルアンティーク」の枝変わり と。【樹 高】 約1.5m【花弁数】 40~50【花 径】 10~12cm【開き方】 半剣弁ロゼット咲き【形 状】 直立性【花 期】 四季【香 り】 中香【棘の程度】 中程度「サニーアンティーク Sunny Antike」独:コルデス 2010年作出。「プチ トリアノン Petit Trianon」。フランス王妃マリー・アントワネットが愛した離宮プチ・トリアノンの名を冠したバラです。ヴェルサイユ宮殿庭園長とメイアン社の親交により生まれたバラで、肖像画の中で、マリー・アントワネットが掲げている淡いピンクのバラをイメージしました。ソフトピンクの」花弁はデリケートな美しさがあり、株が充実すると3~4輪の房咲きになる花付きのよい品種です。葉には光沢があります と。「プチ トリアノン Petit Trianon」仏:メイアン 2005年作出。「ハイ フライヤー High Flyer」。ラージ・フラワード・クライマー[LCl] として作出された大輪咲きのつるバラです。濃緑色の葉は光沢のある照り葉です。明るくて目立ちやすく、花壇全体が引き立つ赤色バラ と。「ハイ フライヤー High Flyer」米:ウォリナー 1992年作出。「桜貝 Sakuragai」。花色は青みを帯びた淡いピンク色で、名前の通り「桜貝」の色のよう。半剣弁高芯咲きの中輪花で、花つきが非常に良く、房状にたくさん花をつけます。樹形は直立性でトゲも少なく、育て易い品種です。微香性 と。「桜貝 Sakuragai」日:平林 浩 1995年作出小輪の白い花がたわわに。「日本の野生種とその交配種バラの野生種は150 ~ 200種ほどが北半球に自生しています。園芸品種の成立過程では日本の野生種も重要な役割を担い、ロサ・ムルティフロラ(ノイバラ)は房朕き性を、ロサ・ルキアェ(テリハノイバラ)はつる性の性質を、ロサ・ルゴサ(ハマナス)は耐寒性や耐病性と芳香を付与しました。その他にも、ロサ・プラクテアタ(カカヤンバラ)も交配に使われています。ここでは、バラの園芸品種の成立に重要な役割を担った日本の野生種とともにそれらの交配種を展示しています。」近づいて。「うらら Urara」。濃いピンク、丸弁咲き、中輪房咲きの花。ティの微香。四季咲き性。樹勢は普通で耐病性も普通、木立樹形のバラ。切り花向き。トゲは普通。「うらら Urara」日:平林 浩 1993年作出。そして「薔薇の轍(ばらのわだち) ローズ・コレクション歴史上の人物たちも愛してやまなかった花、「薔薇」。長く深い歴史を持つバラの”進化の軌跡”がここにあります。古代ペルシア時代にすでに栽培されていたバラは、西洋と東洋で別々に園芸化が進みました。やがて、東洋のバラが西洋へと持ち込まれることで大いなる変革が起こり、私たちがよく知るモダン・ローズが誕生します。ここでは、野生種から将来のバラまで、悠遠の歴史をたどることができます。」「世界の野生種とその交配種バラの野生種の多くは、中国西南部からヒマラヤ、西アジアにかけて自生するため、この地域がバラの起源と考えられています。ここでは、園芸品種の成立に影響を与えた海外の野生種とその交配種を展示しており、特に園芸品種の特性に大きな影響を与えたロサ・モスカタ(房咲き性や耐病性)やロサ・ギガンテア(ティー(紅茶)の香り)、「ペルシアン・イエロー」(黄色の色彩)などを見ることができます。また、長年「幻のバラ」とされていたチャイナ・ローズの原種ロサ・チネンシス・スポンタネアも植栽されています。」自然交雑によって誕生した園芸品種のバラ・オールド・ローズを見る。別の角度から。「初期のオールド・ローズバラの栽培化の過程で野生種の中から優れた性質の個体を選抜したり、また、栽培の中で昆虫などによる自然交雑が起こるなどして、園芸品種が誕生していきました。このように自然交雑によって誕生した園芸品種のバラは、オールド・ローズと呼ばれています。初期のオールド・ローズは、ヨーロッパや中近東の野生種によって成立したもので、開花はほぼ一季咲きです。花色は白、ピンク、紅、黒赤、赤紫などで、香りの高い品種が多く、これらのバラの一部は、現在でも香料用に栽培されています。」「オールド・ローズ」をカメラで追う。「カーディナル ド リシュリューCardinal De Richelieu」 仏:Laffay.M 1840年作出 最も古い紫のバラ、と言われています。シックな紫色は咲き始め赤みが強く、のちに灰色を帯びた青紫へと移ろいます。この系統の中でももっとも青みがかる紫色が楽しめます。オールドローズの中でも大変よく知られ、知名度にふさわしい名花と思います。トゲもほとんどなくこぼれるように咲く姿は本当に見事。中輪・八重咲きで春のみに咲きます と。「薔薇の轍」。当園は、野生種から近年のバラまで約1,300品種を所有しており、関東有数の品種数を誇っています。なかでもフラワーゾーンにあるバラ園・薔薇の轍は、バラの品種改良の歴史に沿って系統、分類ごとにご覧いただける“歴史園”になっています。バラと育種家が辿った今日までの道のりを、車の通った両輪の跡=轍(わだち)に例えて“薔薇の轍”と名づけました と。「中国の4つのオールド・ローズ西洋とは別に、中国でもバラの園芸化が独自に進んでいました。1800年代になるとプラント・ハンター達によって、中国のバラがヨーロッパにもたらされます。中でも通称「4つの種馬」と呼ばれる4品種のバラは、ヨーロッパのバラの世界に大きな変をもたらします。これらのバラによってもたらされた画期的な性質としては、四季咲き性や剣弁高芯の花型、ティー(紅茶)の香り、淡黄色の色彩などです。ここでは、4品種のバラを展示していますが、これらの個体が当時の体そのものであるかは定かではありません。」バラの周囲には様々な花も開花。「マルタ ゴンザレス Martha Gonzales」。濃い赤色のバラ。ネットの検索でも詳しい品種データは見つかりませんでした。「マルタ ゴンザレス Martha Gonzales」仏:ラフェイ 1829年以前作出既に散りだしているバラの花も。紫の花の名はムラサキセンダイハギ(バプティシア・アウストラリス)であっただろうか。様々な色のバラが遊歩道沿いに。トランプのモニュメントが。近づいて。「ポール ネイロン Paul Neyron」。カップ状の堂々たる大輪花で、とても高い香りがあります。トゲがほとんど無い半つる性品種で珍しく秋にも返り咲きがあります。伸ばしたままですとあまり花付きが得られませんので誘引か弱剪定による管理で花付きをふやすようにし と。「ポール ネイロン Paul Neyron」仏:ルヴェ 1869年作出。純白の花。「フラウカール ドルシュキ Frau Karl Druschki」。1901年に発表されて以来、白つるばらの名花として100年以上愛されてきた品種です。かつては不二(ふじ:ふたつとないの意)の名で親しまれました。特徴はやはりその輝くような白さと、気品ある花型でしょうか。花つきも非常に良好で、木が成熟すると秋にも返り咲きます。蕾のうちはほんのりピンクがかかり、葉は清らかな明るい緑、花色を引き立て、芽吹きの頃はとりわけ美しく感じられます。香りが微香であることは少し残念ですが、それでもこの品種の気品ある佇まいは、やはり他の追随を許さぬものと感じます と。「フラウカール ドルシュキ Frau Karl Druschki」独:ランベルト 1901年作出。蔓薔薇(つるばら)のトンネル。漢字の「薔薇」という字は中国から来た言葉で、音読みでは「しょうび」と読みます。古今和歌集にはその読み方で登場しているそうです。「薔」は垣根、「薇」は風にそよぐという意味です。つまり「薔薇」という漢字は、「垣根に植えられた野生のバラが風にそよいでいる様子」を表しています。バラの学名はラテン語の「Rosa(ロサ)」です。しかし、一般的には英語読みの「Rose(ローズ)」が浸透しています と。「モダン・ローズ」案内板。「黎明期のモダン・ローズモダン・ローズは今から約150年前に誕生し、その第1号品種は、ハイプリッド・ティー系の「ラ・フランス」です。この品種の誕生した1867年はモダン・ローズとオールド・ローズの境界線とされますが、それはハイプリッド・ティー系が初めて人為的な交配によって誕生した系統であることと、モダン・ローズの代表的な系統になったことが理由です。また、この時期には本格的な黄色のバラが登場し、後に多彩な園芸品種が登場することへと繋がっていきます。」このバラの名は?近づいて。モダン・ローズと言われる、ピンクの薔薇の花の中に、透き通って見える衣類・???を纏ったように見える女性像。別の角度から。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.01
コメント(0)
-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その31):浦賀城址~浦賀船渠(株)殉職員慰霊塔~法憧寺
ここ、明神山一帯は浦賀城址と云われている。小田原北条早雲が三浦一帯を領した頃、房総半島・里見水軍の度々の攻撃に備え、浦賀水道に面し港のある明神山に三崎城の支城として、16世紀後半(天正~慶長初期)に3代北条氏康(2代氏綱の嫡男)が水軍を配置した浦賀城を築城した と。先には現・住友重機械工業(株)の「浦賀船渠(株)殉職員慰霊塔」があった。近づいて。「為浦賀船渠株式會社殉職貟」住友重機械工業株式会社の前身である浦賀船渠(ドック)により大正9年に、この明神山々頂に建立されたものである。会社関係で先の大戦又不慮の事故等により亡くなられた308柱の御霊をおまつりしている。毎年10月には会社幹部の方々、ご遺族代表、地元関係者参列の下、慰霊祭が執り行われているとのこと。「浦賀船渠㈱」の社章であろうか?URAGA DOCKか?そして「浦賀船渠(株)殉職員慰霊塔」の裏、山頂の南端からは「浦賀水道」の絶景が拡がっていた。「浦賀城址戦国時代に小田原北条氏が三浦半島を支配した時に房総里見氏からの攻撃に備えて北条氏康が三崎城の出城として築いたといわれています。水軍の根城として山頂には空掘など城の遺構が残り、下田山・城山とも呼ばれていました。昔から眺望の素晴らしい所で対岸に房総半島、正面に浦賀八勝の一つ燈明堂が見られます。この明神山は自然の社叢林で県の天然記念物に指定されたウバメガシ分布の北限とされています。嘉永六年( 一八五三)ペリーの黒船四隻が浦賀沖に来航した時、眼下の左辺りに停泊しました。下の絵は安藤広重の武相名所の旅絵日記の五六景の一枚です。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」広重の旅絵日記よりそして前方の眼下に見えたのが先日訪ねた「浦賀燈明堂跡」が見えた。上の安藤広重の広重の旅絵日記からすると◯あたりが、黒船の一隻・プリマス号が停泊していた場所か?ズームして。慶安元年(一六四八)幕府の命でつくられた日本式の灯台である燈明堂は明治五年(一八七二)までその役割を果たしたのだと。写真右の双子の山は房総丘陵の山の一つである「富山(とみさん)349.5m」である。「南総里見八犬伝」の始まりとなった富山。2つの峰からなる双耳峰で、標高は北峰(金毘羅峰)が349.5m、南峰(観音峰)342.0m。写真中央が「鋸山 標高329m」。「浦賀城から見た房総」。「浦賀城イメージ図」をネットから。浦賀城について「南郭」から「奥の院」方向を見る。明神山の上には土塁や帯曲輪らしきものもあったが、勝海舟関連の社や石碑などでかなりその地形は改変されているように思えたのであった。そして頂上から産霊坂(むすびざか)の石段を下る。拝殿の右の社殿近くにあった石碑には???石灯籠??「東叶神社」の「社務所」。「浦賀城」の御城印。そして「東叶神社」を後にして、来た道を引き返す。「横須賀古道散歩」案内図。「横須賀古道散歩「横須賀古道散歩」は横須賀市内を通っていたと伝えられる古代の東海道や中世の鎌倉道近世の浦賀道を古刹や古い地名をたよりにたずねる散歩道です。コースはしょうぶ園から衣笠駅付近を経て京急大津駅までの「古東海道ゆかり散歩」と京急大津駅から浦賀駅前を経て一方は東叶神社へ、一方は燈明堂へいたる「浦賀道ゆかり散歩」の2コースです。」そして次の目的地の「法憧寺(ほうどうじ)」に向かって東浦賀2丁目の住宅街を進む。右に折れ、前方の石段の上・東浦賀の海を見下ろす高台にある「法憧寺」に向かう。石段を上って行った。墓地が見えたが、隣の家は住職のご自宅なのであろうか?南側の墓地を見る。多くの石仏のお姿が。「無縁塔」と。そして「法憧寺」の「本堂」が浦賀湾に向かって建っていた。円城山宝珠院法幢寺・浄土宗鎮西派の寺。横須賀市東浦賀2丁目16−20。「法幢寺明応2年(1493)に、大本山鎌倉光明寺第八世の観誉祐崇上人によって開かれたお寺です。上人は浄土宗でお十夜法要を始めた人です。本堂には、恵信僧都(942~1017:往生要集を著し浄土教の基礎を築いた)の作といわれる、阿弥陀三尊像が安置されていおり、像の高さは約1mあります。薬師如来は、眷属(付き従うもの)の十二神将とともに本堂に安置されています。山号の円城山は、永正15年(1518)三浦一族を破り、この地を領した後北条氏が房州の里見氏に対する備えとして築いた浦賀城の一廓であったことを物語るものです。浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」「十二神将」。向拝の見事な龍の彫刻。ズームして。木鼻(右)。木鼻(左)。本堂にはこの一帯が浦賀城一廓だったことを物語る山号の扁額「圓城山」。軒下の小壁には岩田辰之助・徳太郎兄弟が大正15年(1926)に手掛けた魔除けの神獣をテーマにした合作鏝絵「牡丹に唐獅子」が遺されていた。鏝絵「牡丹に唐獅子」(右)。牡丹に岩上の一対の唐獅子が鞠と紐に戯れる図柄を、二間の壁面にわたり連続画的にレリーフ状に表現している。唐獅子頭に玉眼(ガラス玉)を嵌入。中央下段に銘文があり、「奉納/大正十五年/九月廿八日/岩田徳太郎/岩田辰之助」とある白漆喰仕上げ、一部彩色。ズームして。唐獅子頭に玉眼(ガラス玉)を嵌入。鏝絵「牡丹に唐獅子」(左)。ズームして。墓石には「故陸軍兵長桐ヶ谷信雄之墓」と。墓地の奥には多くの墓石が並ぶ。正面に立派な墓石が。「鍋洲累世之墓」と。ズームして。墓地の高台から浦賀湾を望む。「愛宕山公園」と浦賀湾に停泊する砂・砂利運搬船を見る。移動してズームして。奥にあった墓石は歴代住職の墓地であっただろうか。歴代鈴木家の墓。「鈴木累世墓」と。「南無阿弥陀佛」碑。これも無縁塔か?錫杖を持つ石仏。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.01
コメント(0)
全39件 (39件中 1-39件目)
1










