-
1

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその2
鵠沼海岸7丁目の住宅地の路地を最初の目的地に向かって進む。この先が最初の目的地であった。藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。右手に大きな石碑があった。松岡静雄先生之庵趾碑。[この場所は、かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた場所です。明治十一年(1878)生まれ、松岡家の7男。民俗学の大家 柳田国男を兄に持ちます。海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。関東大震災後の大正十ニ年末、鵠沼・堀川集落の南に隣接する納屋(ないや)地区に移り住みました。この庵を《神楽舎(ささらのや)》と名付け、在野の言語学者として日々研究を重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを発刊していました。昭和11年(1937) 5月23日松岡静雄が逝去した翌年、先生を基う弟子たちにより石碑「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。くくコラム> >民俗学の大家柳田國男線の人々:松岡静雄と丸山久子と鵠沼民俗学者丸山久子は、20歳のころよリ父が鵠沼海岸に家を建て、この近くにあった神楽舎の講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。静雄の妻の誘いを切っ掛けに、久子は柳田国男の講演「国語の将来」を受講します。これを機に本格的に民俗学を学ぶようになり、世田谷にある柳田の自宅て行われた研究会にも熱心に通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。 参考資料:『地名の会会報 117号』遠藤の民俗ー丸山久子の足跡と仕事ー粂智子著]海軍退役後、神奈川県藤沢市(当時は藤沢町)鵠沼に居を移すが、直後に起こった関東地震では、遭難死した東久邇宮師正王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に回航させたり、遭難死した住民26体の遺骸を地元青年団が荼毘に付す際の指揮を執ったりしたという逸話が残っている。震災後は鵠沼西海岸に居を構え、神楽舎(ささらのや)と名付けて言語学、民俗学を研究し、同じ軍人出身の「岡書院」店主岡茂雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。また、扇谷正造をはじめ多くの青年たちが訪れて学んだ とウィキペディアより。海軍時代の松岡静雄(ウィキペディアより)。家族・親族実父:松岡操 - 儒者、医者実母:たけ兄姉 松岡鼎 - 医師 松岡俊次(早世) 井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師 松岡芳江(早世) 松岡友治(早世) 柳田國男 - 民俗学者弟 松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。松岡家兄弟らの写真(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、後列右より、柳田國男、松岡輝夫〔映丘〕)没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑。裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??「松岡静雄先生之庵趾」碑を後にして、次の目的地に向かって鵠沼海岸7丁目の住宅地内を進む。左手に石鳥居が現れた。ここが「高根地蔵尊」。藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。石鳥居前での説明を聴く。石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。 近づいて。「高根地蔵尊」。 地蔵堂の内部に安置されていた「高根地蔵尊」。今でもお地蔵さまの足元には、子供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように積み上げられているのであった。 [高根地蔵神楽舎に近く堀川部落の南側に、高根地蔵はあります。“高根”はこの辺りの小字名て、昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の開祖山上新右衛門建立したものです。鎌倉時代のある合戦で、とあるやんごとなき若者を負い郎党四人を伴った武者が最後をとげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。『現在の藤沢』加藤徳右衛門著(昭和8年刊行)には、次のように記されています。「部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の祟ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]以下もネットから 『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。藤沢の高根地蔵藤沢町鵠沼堀川海岸にある高根地蔵と云う伝説の霊験あらたかの地蔵がある。この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。明治初年両堂改築の為め盛土を取崩した処刀身二口、断碑片若干、土器十二枚を発見したと当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の崇ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た小さな祠堂が建てられている と。決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した歴史の秘話に触れることができるのも、このような「小さな地域史」探訪の醍醐味なのであった。「高根地蔵尊」をズームして。その先を右折して、鵠沼新道線を進む。コモダ歯科医院手前の路地を左折。藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。「しらす直売所 田むら丸」前には列が。藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人でゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。美味そう!!小田急線に沿って北に歩く。そして次に訪ねたのが「浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場」。藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場。「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。「南無大師偏照」の下に「金剛」と続くのですがありませんでした。[浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場お堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。御詠歌:のりの舟出る津寺といろくすも うの浜道につとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫で、右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。]「浜道 弘法大師堂」。 本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札が掲げられていた。「準四国八十八ヶ所法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや第二十五番 宝珠山津照寺」 【仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。 この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。】と。堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められていた。地蔵菩薩立像をズームして。弘法大師像をズームして。隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作 と。いずれも「青面金剛」や「三猿」が彫られていたが、彫られた石の素材や像の姿かたち、さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、左の方が形態をよりとどめていた。こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所にまとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から続いている道。庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っていることは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・
2025.11.26
閲覧総数 140
-
2
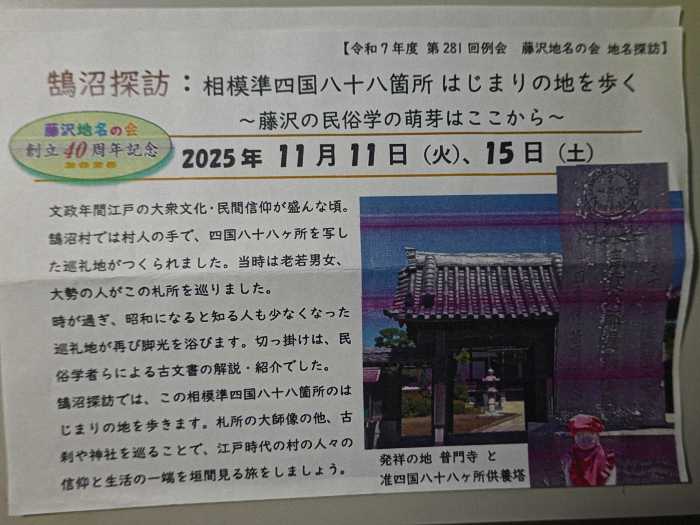
鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその1
この日は2025年11月15日(土)、「藤沢地名の会」主催の【令和7年度第28回例会・藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」に参加しました。「文政(1818年~1831年)年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。鵠沼村では村人の手で、四国八十八ヶ所を写した巡礼地がつくられました。当時は老若男女、大勢の人がこの札所を巡りました。時が過ぎ、昭和になると知る人も少なくなった巡礼地が再び脚光を浴びます。切っ掛けは、民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。鵠沼探訪では、この相模準四国八十八箇所のはじまりの地を歩きます。礼所の大師像の他、古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。」 ●予定コース鵠沼海岸駅→松岡静雄先生之庵趾→高根地蔵→準四25番→準56番→本真寺→原の辻→茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散(午後2時半頃予定)予定コース(都合により一部変更することがあります)[ 7.0km程度、高差なし]※準四:相模国八十八箇所の霊場番号、弘法大師像の場所日時:令和7年(2025)11月11日(火),15日(土) 2回開催(同じ内容です) ※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合 (午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)申込日 :11月3日(月)~11月7日(金) 受付専用電話 電話 070-9040-2614 (担当:布施) ※お電話は9:00ー17:00の間にお願いいたします.持ち物:弁当、飲み物、ゴミ袋、雨具10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、小田急線鵠沼海岸駅に40分ほどで到着。改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし会員会費200円を支払う。この日の散策用資料(全20ページ)をいただきました。そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。私は7名の2班にてスタート。鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。左手にあったのが、入口表札から法華宗本門流の晴明庵。鵠沼海岸駅周辺👈️リンクの昔からの路を進む。鵠沼海岸郵便局(藤沢市鵠沼3丁目)前の細い商店街の路地を進む。この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、江戸~明治期以前から存在した「鵠沼村の生活道」を引き継いだものと。道がゆるくカーブし、幅が急に狭くなる地点もあった。これは近代の都市計画で作られた道路には見られず、江戸~明治の農道の曲がり方(地形に沿う道)と同じ特徴であると。つまり、この曲がり道は、昔の地形に沿っていたために残った“古道の線形”と言えるのだと。今回、主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を[ ]つきで転記させていただきます。転記することにより、私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的です。[【=鵠沼地域の概要=藤沢市域は、歴史的にみても古くは鎌倉幕府、江戸幕府の周縁地域に当り、現在も東京近傍の地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。藤沢南部の鵠沼地域は、東に境川、西に引地川、南は湘南の海に囲まれ、北は旧東海道の辺りまでになります。鵠沼から茅ヶ崎一帯に続く砂丘地帯は、海の波や潮流によって形成された砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったものです。鵠沼地区全体がなだらかな平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。【鵠沼の歴史】奈良時代、相模国司が記した『相模国封戸租交易帳』には、土甘(とがみ)郷という地名があり、古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、北部にある皇大神宮は、土甘郷の総社であったと云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し“大庭御厨(おおばみくりや)“👈️リンクが成立しました。鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったとみられています。鎌倉時代から室町時代、京から鎌倉への”鎌倉街道”がこの地を通っていました。中世の和歌や紀行文に登場する“砥上が原(とがみがはら)”という地名は、この辺りが荒野てあったことを示す地名です。また、鎌倉にほど近いため、鎌倉末期からの戦乱に巻き込まれていたと見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が発達してゆきます。江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領になりました。大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで続きます。砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網による漁が行われ生活の糧となります。また、江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として使われていました。また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも度々登場しています。明治時代になると、鵠沼にも新時代の波が押し寄せます。海岸が海水浴場として注目されると、我が国初の別荘分譲地が開発力ぐ立ち上がります。明治35 (1902 )年9月1日に、藤沢一片瀬駅(現:江ノ島駅)間に江之島電気鉄道(現江ノ電)が開通、碁盤の目状の整備された別荘地には東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした旅館東屋は、「文士宿」の異名で知られ、多くの文人が集いました。また、江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気を博していきます。戦後、鵠沼南部は別荘地の名残を留めつつ、比較的緑が多い閑静な住宅地が形成されていきます。鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地となりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は、現在では藤沢市内13地区の中で最も人口が多い地域になっています。] [【鵠沼の集落】明治初期の鵠沼村には 14 の集落があり、戸数も 300 戸に満たない村でした。その中でも、人口の集中した集落は 9 つ(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、この辺りを鵠沼本村といい、いずれも皇大神宮の氏子集落です。ほとんどの家は農業を生業としていましたが、網元を営む家も数軒あり、鰺・鯖・鰯・カマスなどを主に獲っていたそうです。明治時代に入ると漁法の革新により盛んになり、漁業組合もできましたが、現在では堀川網一軒が残るのみになりました。]明治初期の鵠沼村。鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。ここ「鵠沼地区宗教史年表」👈️リンクから。 左:明治時代の鵠沼村の集落と小字右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。相模国準四国八十八ヶ所👈️リンクとは。[=四国遍路とは= 参考:「四国路八八ヶ所巡礼の歴史と文化」 森正人著古来、四国は都から遠く難れた修行の場でした。弘法大師(空海)もこの地で修行され、八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝わります。中世には修験者が、未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。四国遍路の成立時期については諸説あり、江戸時代にはいってからと見る説が有力です。四国遍路の特徴は、札所寺院の本尊は、阿弥陀如来もあれば弥勒菩薩もあり、さらに宗派も真言宗だけではありません。四国八十八ヶ所の寺院に共通しているのは、本堂の他に大師堂があり、このニつを参拝することが求められている点です。※お砂踏み~現代の四国八十八ヶ所巡り~参考: (ー社)四国八十八ヶ所震場会四国八十八ヶ所霊場各札所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りするこです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれております。江戸時代には、四国八十八ヶ所霊場を模し新四国、島四国、八十八ヶ所などと呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。=相模国準四国八十八ヶ所=相模国準四国八十八ヶ所は、文政年間に鵠沼村堀川の浅場太郎右衛門によって作られ、現鎌倉市の西部から、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の各地に札所が置かれました。その経緯は、浅場太郎右衛門の父が、下総国相馬郡に本四国を写した霊場を見たことに端を発します。後に、鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心を派遣し、霊場の砂土を採ってこさせました。相模の霊場は、元々御堂のある場所や墓地を選び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書にも記されています。この霊場の完成は、父の十七年忌(文政四年(1821))を期して、息子の浅場太郎右衛門が大師像を造り各地に設置したという説が有力です。その根拠は、大師像のいくつかの年銘が、文政3、4年であることにあります。霊場番号については、本四国が阿波から1番、2番と巡礼道の順に振られているのに対し、相模の札所番号はバラバラてす。震場として選んだ場所それぞれを、本四国の震場と環境が似ている、名前が似ているなど、何らかの類似点を見出し割り振ったのではないか見られています。なお1番札所の感応院👈️リンクは普門寺の本山であります。1番と結願の88番札所(普門寺)の2箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。この霊場をつくった縁によるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。=藤沢の「相模国準四国八十八ヶ所」研究=創設当初は巡礼者でにぎわっていた相模国準四国八十八ヶ所も、時代が過ぎ戦後になると巡拝する人もほとんどなく、「藤沢市史」等に戦前の大師講の様子が僅かに記されている程度でした。(「藤沢市史第7巻」民俗編 第六章 信仰と民間療法)] 私の「四国八十八ヶ所霊場巡り」👈️リンクは車での移動であったが、既に2015年に結願しているのだ。[昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。もう一つは、鵠沼堀川の山上家が所蔵していたものです。これらの古文書から、相模国に八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。]相模国準四国八十八か所の順路をズームして。以上 ポイントを纏めると●相模準四国八十八箇所の概要 ・概要: 四国八十八箇所の写し霊場で、弘法大師石像が各札所に祀られています。 ・構成: 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、横浜市泉区にまたがる88か所の札所。 ・起源: 江戸時代の文化・文政期に普門寺の善応師と鵠沼(くげぬま)の浅場太郎右衛門が 発願し、文化3年(1806年)に計画されました。 ・ご利益: 四国霊場を巡るのと同等のご利益があるとされ、手軽に巡拝できることから 流行しました。 ・現状: ・明治時代の神仏分離令や関東大震災、開発などにより、廃寺・移転・消失した札所が あります。 ・昭和50年代以降、調査が進み、現在では85体の弘法大師像が残っていることが 確認されています。 一部の札所では、ウォーキングイベントなども開催されています。相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。・相模国と呼ばれたエリアの弘法大師霊場。・霊場札所の御本尊は、弘法大師石仏となる。・堂となっていても、屋外に石仏が祀られているだけのケースもある。・開創者の浅場太郎右衛門は鵠沼村の住人で、善応は88番普門寺の住職だった人物。・慶応4(1868)年の神仏混淆廃止、明治2(1869)年の神仏分離、廃仏毀釈、さらに 関東大震災によって廃寺や廃堂となった札所が多い。・結果、札所の移動もかなりあり、弘法大師の石仏が行方不明のケースもある。・当時の札所配置で、春の彼岸の際に4日ほどで巡拝する人が多かったようだ。・不定期ながら、巡拝ウォーキングのイベントなども開催されている。霊場の写真もネットから。鵠沼の弘法大師像堀川の淺場太郎右衛門父子二代の発願になる「相模國準四國八十八箇所」のうち、鵠沼村内に置かれたものは次の9か所である。この他に法照寺境内には、もう1体の弘法大師像が小堂内に安置される。手前が第48番札所の大師像とされる。相模國準四國八十八箇所の概略は第0084話、詳細は相模国準四国八十八ヶ所を参照されたい。第七十九番 大東観音堂第六十三番 毘沙門堂第五番 原地蔵堂 地蔵立像と併置第二十五番 濱道堀川地蔵堂 地蔵立像と併置第五十六番 堀川大師堂 地蔵坐像と併置第四十一番 苅田稲荷社第四十七番 密嚴山遍照院普門寺大師堂第四十八番 善光山天龍院法照寺第八十八番 密嚴山遍照院普門寺本堂=結願札所鵠沼地区地蔵尊・弘法大師像年表 西暦 和暦 月 日 記事1654 承応 4 5 吉 石上の地蔵菩薩立像、造立(鵠沼最古の石仏。昔は石上の 渡し場近くにあった)1655 承応 5 石上稲荷神社境内の地蔵菩薩立像、造立(遺失)1670 寛文10 8 16 本鵠沼2-4-36大東町内会館裏の地蔵菩薩立像(南無阿弥陀仏)、造立1780 安永 9 11 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の地蔵菩薩像(立像丸彫り)、造立1820 文政 3 6 吉 法照寺境内の第48番札所弘法大師石像(坐像丸彫)、造立1820 文政 3 6 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の第25番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 6 吉 浅場邸内の準四国八十八箇所霊場第56番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 本鵠沼5-10-21苅田稲荷の第41番札所弘法大師像(坐像丸彫)、造立1821 文政 4 3 浅場太郎右衛門、普門寺境内に大師石像と大師堂建立1843 天保14 2 4 堀川山上新右衛門、鵠沼海岸7-19-12に地蔵尊立像・高根地蔵堂造立1943 昭和18 日本精工拡張で東毘沙門堂準四国第63番大師像を鵠沼墓地 髙松家墓所に移動1958 昭和33 1 20 鵠沼松が岡4-19-5小田急線一木通り踏切脇の地蔵菩薩立像、造立1986 昭和61 11 21 鵠沼神明3-4(鵠沼墓地)の延命地蔵、造立1995 平成 7 関根善之助、普門寺境内に大師堂建立、寄進 ・・・つづく・・・
2025.11.25
閲覧総数 248
-
3

龍の口竹灯籠へ-2
本堂の手前、右奥にあった日蓮大聖人像を撮ったが・・・。昼間であれば。しっとりと闇に沈む竹筒の奥、ひとつの小さな灯が、まるで呼吸するように揺れていた。外の冷たい夜気とは対照的に、内側の竹肌は炎にあたためられ、淡く琥珀色に染まり、何十年も風雨にさらされてきた竹の表情までも優しく浮かび上がっていたのだ。龍の口竹灯籠の灯りは、ただ“照らす”のではなく、見る人の心に柔らかな静寂をしみ込ませ、急ぐ時間の歩みをふっとゆるめてくれるのだった。大書院手前の「幻想庭園」。夜の闇を背景に、光・竹・水・そして“物語”がひとつの舞台のように組み上げられていた。 ■ 空間の主役 ―― 龍の姿画面右側に横たわる流木から形づくられた龍は、まるで今にも息をし、闇へと舞い上がるかの如くに。赤い点の“目”がほのかに光り、静寂のなかに潜む力を象徴しているようでもあった。近づいて。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っていた。それはまるで地から立ち上る気のよう。■ 背後に浮かぶ天女の影竹垣に映し出された天女は、光の線がかすかに震えながら形を保っており、龍が天へと昇る時に現れる導き手の如くに。龍と天女が同じ画面に収まることで、“龍口”という土地の伝承性がとても濃く演出されていた。そして右下の水面は青く照らされ、龍が棲む清浄な池のイメージ。竹の黄色い光と対比することで、「地の灯」と「水の灯」が呼応していた。様々な角度から。青い水面に散った緑の光は、ただの反射ではなく、水の上に咲く星の花の如くに。ひとつひとつの光は鋭く、しかし水のゆらぎに合わせて静かに形を変えながら漂っています。まるで、「夜の池に、緑の星座が降りてきた」そんな印象であった。青の深い水底は夜空のようで、その上に落ちた緑の光は瞬き、淡く滲み、やがてまた別の姿に生まれ変わるのであった。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っているのであった。それはまるで地から立ち上る気の如くに。■ 竹の灯りがつくる、やわらかな陰影手前の丸い竹格子の灯りは、光が細かい編み目を通って外へこぼれ、周囲にやさしい揺らぎの模様を落としていた。■ 奥に浮かぶ竹細工の明かり後ろの吊り灯籠は、竹の表皮を薄く削ったような柔らかな曲線を持ち、まるで小さな行灯(あんどん)が枝先にとまっているかの如し。木の葉がわずかに揺れると、灯りもふわりと呼応し、“晩秋の息づかい”を感じさせるのであった。ズームして。■ 編み目からこぼれる、温かな光竹の細かな輪の連なりが無数の小さな“窓”となり、そのひとつひとつから温かな光がこぼれ出ていた。強い光を受け止めながらも、編み目がそれを和らげて。そして、その先右側にあった龍の竹灯籠。■ 闇に浮かぶ金色の龍切り抜かれた竹の隙間から漏れる灯りが、鱗、爪、髭、そしてうねる体の曲線を鮮やかに浮かび上がらせていた。灯りは一点ではなく、竹一本一本に宿っているため、龍の輪郭は“燃えるような揺らぎ”をまとい、まるで今にも息を吹きかけて動きだしそうに。右側には「龍」そして「竹かぐや」の文字も浮かび上がっていた。 左側下には、山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿が。ズームして。■ 闇から現れる龍の横顔横から見ると、光が竹の奥から溢れ、彫り抜かれた線のひとつひとつが浮き彫りのように立体的に浮かび上がっているのであった。細長い鱗の並び、胸の張り、うねる胴の曲線――どれもが光の強弱と陰影で生命感を帯びて見えたのであった。山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿を見下ろして。龍口寺・大書院。その前には、竹灯籠が横向きに地面に置かれ、ただの“道の明かり”ではなく、歩く人を静かに導く、光の川のように見えたのであった。■ 線となって流れる灯り細長い竹に空けられた無数の丸い穴から、白い光が点々とこぼれていた。その光が連続すると、まるで夜の大地の上に一本の光の流線が描かれているように。歩くたびに、視線の先へすっと伸びていくその線は、流れゆく川のようでもあり、星座を地面に散らしたようでもあったのだ。近づいて。■ 粒が生む「光の流れ」竹の中を流れる光が、そのまま大地へ滲み出して。大小の丸い穴からこぼれる光は、ひとつひとつが金色の粒のように。その粒が密になったり疎になったりしながら曲線を描くことで、まるで光自身がしなやかに蛇行する一本の川になっているのであった。「遠藤笹窪谷公園竹灯籠エリア藤沢市で最も豊かな自然が残されている場所の一つである「遠藤笹窪谷公園」の【ほたるのタベ】イベントで使用された灯籠が並べられています」。 そして仁王門まで下り、「龍口刑場趾」を見る。■龍ロ刑場跡とは?龍ロ刑場跡(神奈川県藤沢市片瀬3丁目)は、鎌倉時代に設けられた処刑場で、現在の龍ロ寺周辺に位置する歴史的霊場です。1271年、日蓮聖人(日蓮大聖人)が幕府の弾圧を受け、「龍ノロの法難」として知られる処刑未遂事件の舞台となりました。この時、日蓮は斬首されそうになったものの、伝説によれば江の島方面から光の玉が飛来し、処刑が中止されたとされます。この出来事が「龍ロ法難」として日蓮宗の四大法難の一つに数えられ、現在は龍ロ寺がその歴史を伝える場所となっています。周辺は住宅地に変わっていますが、過去の処刑場の記憶が残っているとされています。 再びテント作りの「受付」を見る。 そして龍口寺前交差点を通過する江ノ島電鉄の車両を。神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目にある江ノ島電鉄と道路併用のカーブが、江ノ島電鉄・龍口寺前交差点。江ノ島電鉄は、江ノ島駅のすぐ東側、龍口寺前交差点付近から鎌倉方面の神戸橋交差点までが、道路併用区間で、龍口寺前交差点のR=28mは、普通鉄道としては日本一の急カーブとなっているのだ。そして江ノ島電鉄・江ノ島駅に到着。ポスター「SHONAN SUNSET」。夕陽に照らされた雲が、赤、橙、紫へと滑らかに溶け合い、まるで空全体が燃えているかのよう。湘南の空が時折見せる、“奇跡の色彩”が完璧に捉えられていた。 遠くに見える富士山は、赤く染まる空に黒い影として浮かび、堂々とした存在感を放って。このシルエットこそ、湘南の夕景が人の心を惹きつける大きな理由のひとつ。「江ノ島」駅。 鎌倉行きの電車が入線。■江ノ電はどこで列車すれ違いするのでしょうか?鵠沼、江ノ島、稲村ヶ崎、長谷の各駅と、鎌倉高校前-七里ヶ浜間にある峰ヶ原信号場ですれ違います。鵠沼と稲村ヶ崎は島式(1面2線)、江ノ島と長谷は対面式(2面2線)です。峰ヶ原信号場には客扱いをするホームはありません。島式ホームとは、ホームの両側が線路に接している形状のこと。まるで線路が島を取り囲んでいるかのように見えることから島式ホームと呼ばれています。そして利用した藤沢駅行きの電車が。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.11.24
閲覧総数 309
-
4

龍の口竹灯籠へ-1
すばな通りを進むと、右手にあったのが江ノ島電鉄「江ノ島」駅。 江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『江のピコ』。小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「ピコリーノ」。地元の女性が季節に合わせて手編みのカラフルな衣装を着せ替えていることで有名で、観光客の人気スポットになっている。もともとは、子どもがポールに飛び乗って怪我をしないようにという安全対策の工夫として小鳥のデザインが採用されたもの と。踏切を渡り、「江ノ島駅」を見る。 そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。和紙風のパネルに、幾何学模様(和柄・アイヌ文様にも近い図形)がプリントされていた。模様は矢羽根、山形(杉綾)、菱形などを組み合わせたデザイン。「龍口明神社(元宮)」の石鳥居が左手に。もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。大正12年 (1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年 (1933年)に龍口の在のままで改築したが、昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており(周りは藤沢市片瀬)、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。扁額は「龍口明神社」。「第十五回 龍の口竹灯籠」のポスター。・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)・時間: 午後5時~午後8時・場所: 龍口寺境内(神奈川県藤沢市片瀬3-13-37)・内容: 龍口寺境内に約3,000基の竹灯籠が並べられ、ろうそくの光に包まれる幻想的な秋の夜を楽しむイベント。詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。龍口寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に施餓鬼壇を整え、参詣の方々のご先祖様や、亡くなられた方のご供養や、お願いごとなどの祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。灯籠奉納受付所のテントが前方に。「奉納者芳名板(ほうめいばん)」が右手に。 龍口寺の仁王門(山門)前の「第十五回 龍の口竹灯籠」の入口の飾り。複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。● 左側の竹灯籠の刻字「龍 口 寺」1本の竹に「龍」「口」「寺」の3文字が、節と節の“間”に1文字ずつ縦に配列されていた● 右側の竹灯籠の刻字「藤 沢 市」(同じ構造)● 中央下部の竹筒「竹灯籠」と刻まれた短めの竹灯籠が金属製U字ガードレールの前に置かれている。仁王門。扁額「龍乃口」と。 仁王門の先の石段。山門前の石段を斜めから。山門は元治元年(1864)竣工で、欅造り銅板葺。大阪雲雷寺の発願で、豪商鹿島屋某が百両寄進し建立された。正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた竹灯籠が中央、左右に並べられ、内部に本物の蝋燭が灯されていたのであった。LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。蝋燭の灯りの特徴。・光が 揺らいでいる(ゆらぎのある光)・光の色が 温かみの強い橙色で、中心が明るく外側が徐々に弱まる・切り口から漏れる光が不均一で自然な形状をしている・同じ灯籠でも光の強弱が微妙に違う・LED特有の白っぽさ・均一な広がりがない上部から覗くが如くに。龍の口竹灯籠会場図。山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。左側。右側。「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。大小さまざまな竹灯籠。斜めの切り口から炎の橙光が漏れるのであった。光がひとつひとつ微妙に揺らぎ、均一ではない自然な光のゆらめきが生じている。LED光ではなく蝋燭のため、光の揺れ方・明滅の仕方が柔らかいのであった。参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。移動して。竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。ズームして。裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。その差が光の強弱として現れ、LED照明とは違う自然な揺らぎとなって視覚に訴えるのであった。竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると感じるのであった。手水舎手前を。大本堂とのコラボ。闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。ひとつひとつは、竹の内奥で燃える小さな炎にすぎないのに、寄り添い、並び、つながるとまるで大地そのものが灯っているかのようであった。渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。その先には、古い寺の影が青白い光に照らされて、息づいているのであった。炎は風に怯えながらも、一瞬のために命を燃やし、闇の中で人の心をそっと照らしていた。立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。左手には浄行菩薩像が。大本堂前。大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。 ・・・つづく・・・
2025.11.23
閲覧総数 376
-
5

片瀬西海岸からの夕景-2
太陽が再び顔を見せ、見事な光の帯が。反射光が細かく分断され、光の帯がざらついた質感で揺れて見えていた。手前側は比較的影になっているため、反射光の明るさがより強く際立つ状態で。光の帯の先端の砂浜で遊ぶ親子連れ。これは典型的な「サンロード(太陽の道)」と呼ばれる現象。「太陽の道」とは、弱い風が吹き、水面に小さな波が立つなど特定の条件が揃った時に、水面に光が反射して道の様に見える自然現象を指す。ズームして。太陽が水平に伸びる雲に一部隠されている状態を正面から。太陽の上半分は雲の上に出ており、下半分は雲の下から。海面には太陽の光がまっすぐ縦に反射していて、明るい光の帯が海の表面に伸びていた。水面は大きく荒れてはいませんが、小さなさざ波があり、光の帯が細かく揺れた模様に。空は太陽の周りが濃いオレンジ色で、上の雲は暗く、下の方へ行くほど赤みのある色に変わって。遠くの海は影になっていて、徐々に暗く見えて来たのであった。片瀬西浜から平塚方面へ向かって、長い砂浜がゆるやかに湾曲しながら続いている様子が見えた。相模湾沿いの特徴で、江の島を基点にして西方向へ大きな弧を描くように海岸線が伸びていた。伊豆半島がプレート運動で北北西へ押し込まれているため、相模湾全体が湾口が開いた弓形の地形になっているのだ。相模川・酒匂川などの河川が運んだ砂が、沿岸流によって東へ運ばれ、藤沢・茅ヶ崎方面に供給されることで砂浜が維持されているのだ。明るい光の帯(サンロード)が次第に弱くなり始めた。太陽をズームして。夕日が水平に伸びた雲の隙間から見えている場面。太陽はほぼ沈む直前で、細長い楕円形のように見えて来た。雲に隠れているため、上半分が覆われ、見えている部分が横に押しつぶされたような形なって来たのであった。海面が適度に揺れているため、光は一本の線ではなく、細かく分かれた光の筋が連なって帯状になっている状態に変化して。手前の海面では光が広がり、ゆらぎを伴った反射となり、光の帯がやや太く見えて来た。全体として、夕日が海面に強く反射してできる、典型的な日没時のサンロードが。太陽が水平線上部の黒い雲に隠れて、これがこの日の日没の如くに。空全体は夕方の光で淡い橙色から赤みへと変化し、上層の雲も同じ色調に染まって来た。水平線上部は暗く影になっており、その上に太陽の明るい部分だけが強く浮き上がって見えているのであった。この日の日没を追う。そしてこの日の太陽は完全に水平線上の雲に隠れて。江の島の姿を。江の島シーキャンドルの灯りは未だ。ゆるやかに湾曲する西浜からの砂浜の光景を見る。真っ赤に色づいた太陽が地平線近くに沈み、相模湾の海面からは光の帯が完全に消えて。海は夕方の暗さを帯び、表面にはわずかな揺れだけが残り、静かな水面が一様に赤みを含んだ淡い光を受け止めていたのであった。相模湾全体が静まり、光も影もゆっくりと均されていく、落ち着いた夕暮れの瞬間なのであった。江の島を背景にした、片瀬漁港周辺の夕方の光景。左奥には江の島シーキャンドル(展望灯台)があり、島全体が落ち着いた薄暗い色に包まれて来たのであった。西浜を後にして国道134号を江の島入口方向に向かって歩く。辻堂方面を振り返って。関東ふれあいの道「関東ふれあいの道」は、一都六県を巡る自然歩道です。沿線の豊かな自然にふれ名所や史跡を訪ねながら、古里を見直してみませんか。⑥ 湘南海岸・砂浜のみちこの道は、県内17コースのうちの6番目です。ここから江の島を背に国道134号を西へ、新江ノ島水族館、湘南海岸公園を通り、鵠沼橋の西縁には聶耳(ニェアル)記念碑が建っています。鵠沼橋を渡るとサイクリングロードに入り、右手に松林、左手に砂浜を眺めながら歩くと、茅ヶ崎柳島海岸が終点です。途中、海に浮かぶ烏帽子岩(えぼしいわ)や平島を見ることができます。終点からは、国道134号を渡って、北へ600mくらい歩くと、浜見平団地バス停(茅ヶ崎駅行)に到着します。片瀬橋から境川の河口そして江の島を見る。上流側には小田急線・片瀬江ノ島駅に続く弁天橋を見る。江の島上空も僅かに赤く染まって。江の島入口交差点の横に建つマンション群。小田急線・片瀬江ノ島駅を弁天橋越しに見る。片瀬江の島観光案内所のすぐ横、江の島へ渡る橋(弁天橋)に向かう歩道沿いに設置されている沿道アート(ストリートモニュメント) 。天に昇るモダンなイメージの龍が。折しも観光客を乗せた人力車が2台。中国人であっただろうか?国道134号「江の島入口」交差点越しに江の島を見る。 すばな通りを江ノ島電鉄・江ノ島駅方向に進む。「塩バニラ君」と。名物江の島塩バニラ・ソフトクリームの店。口に入れると塩気→甘味→塩気と風味が移り変わるのだと。「すばな通り」とは神奈川県藤沢市・片瀬江ノ島駅前から江の島弁天橋へ向かう商店街(約250m)の通り。観光客が江の島へ渡る際に必ず通る“江の島参道の入口”にあたります。江ノ電「江ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」から江の島に向かう道。「すばな通り(洲鼻通り)」の名前の由来は、この地域に古くからある地名 「洲鼻(すばな)」 に基づくと。● “洲鼻” の意味「洲(す)」= 川口や海辺にできる砂州(砂が堆積した細長い土地)「鼻(はな)」= 地形が突き出した部分(岬のような意味)つまり「海に向かって細長く突き出した砂州の先端部分」を意味する。江の島の付け根(片瀬側)は、昔は砂州が東西に伸びる地形で、まさに「洲鼻(すばな)」と呼ぶのにふさわしい土地であった と。「ここは すばな通り 江ノ電江ノ島駅」碑。 ハラミステーキカレー・ピザの店「Kalae Ribs kitche」。すばな通りを北へ進むと左側に「道標」と案内板。江の島弁財天道標。この道標は、平成十一年一月、ここより170メートル南の洲鼻通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたもの と。「市指定重要文化財(建造物) 昭和四十一年(1966)一月十七日指定「江の島弁財天道標」この石柱は、江の島への道筋に建てられた道標の一つです。江の島弁財天道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術を、江の島で考案したという杉山検校が寄進したと伝えられ、現在市内外に十数基が確認され、そのうち市内の十二基が藤沢市の重要文化財に指定されています。すべて頂部のとがった角柱型で、その多くが、正面の弁財天を表す梵字の下に「ゑのしま道」、右側面「一切衆生」、左側面に「二世安楽」と彫られています。この文言は、江の島弁財天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・極楽への願いが込められています。この道標は、平成十一年(1999)一月、ここより170メートル南の洲鼻(すばな)通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたものです。 平成二十六年(2014)三月 藤沢市教育委員会 」 「湘南しらす」の幟旗の店。 「湘南生しらす井 ¥1,450」と。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.11.22
閲覧総数 357
-
6

片瀬西海岸からの夕景-1
この日は11月15日(土)、朝から鵠沼へ「藤沢地名の会 地名探索」に参加し15時前に終了し解散する(後日ブログアップ予定)。17時から始まる片瀬・龍口寺で開かれている「第15回 龍の口 竹灯籠(たけとうろう)」を観に小田急片瀬江ノ島駅に向かう。片瀬江ノ島駅構内には大型のクラゲの水槽が設置されているのだ。半透明のミズクラゲでゆったり浮遊する様子は実に幻想的なのである。クラゲ水槽に近づいて。クラゲ水槽は改札内へのコンコースにあり乗降客は早速記念写真やスマホに撮っていた。この水槽は少し離れた場所にろ過装置が設置されていて、配水管を通し水質管理、水温調節、異常が生じれば新江ノ島水族館に即伝わる仕組みなどが備えられているのだと。同館クラゲ担当の方は毎日、餌やり、海水の状況、ミズクラゲの姿の確認など行うのだ と。ミズクラゲ(Aurelia aurita)をズームして。特徴は・体が円盤状で透明。・中央に四つ葉のクローバー状の“4つの輪”(=生殖腺)が見える。・触手は細く短い と。■ どこに生息している?・世界中の温帯〜熱帯海域に広く分布。・日本では沿岸部ならほぼどこでも見ることができる。・港湾や内湾など、やや富栄養化した場所にも多い。1. 傘の縁に細かい“フリル状のひだ”が並んでいるミズクラゲ最大の特徴は、傘の縁に多数の触手(短いタテガミ状)がずらりと並ぶこと。この縁の部分だけがくっきり写り、「レース」「羽毛」のように見えたのであった。・薄くて平たい傘 横から見ると、ミズクラゲは扇形・半月形に見えることがある。・傘表面に模様が無い タコクラゲ、サカサクラゲ、アマクサクラゲなどは模様があるが、 ミズクラゲは透明で模様がほぼ無いのだと。傘をゆっくり収縮→拡張のリズムで動いていた。主に“漂う”生き物で、潮流や水流に大きく影響されるのだと。小田急電鉄・片瀬江ノ島駅(2020年改築の新駅舎)。この駅舎は、日本でも珍しい 「竜宮城(りゅうぐうじょう)をモチーフにした駅」 として有名。■ 1. 竜宮城をイメージした外観・建物全体が「浦島太郎がたどり着いた竜宮城」をモデルに設計・朱色・金色・青緑の屋根という華やかな配色・千鳥破風・唐破風、曲線の軒先など“神社建築+竜宮城”のデザイン → 江ノ島観光の玄関口として象徴的な駅舎に仕上がっている■ 2. アーチ形の入口(白い「門」)・写真中央の白いアーチ部分は、・竜宮城の入口「門」のような造形を模しており、・曲線を強調した意匠になっています。■ 3. 金色の装飾・屋根の各所に金箔風の装飾が施され、・「竜宮城の豪華さ」を演出。そして片瀬西浜にある片瀬漁港に向かって進む。片瀬江ノ島駅前(駅前ロータリー付近)から美しい夕日の姿が現れた。時間は17:12。この場所のこの日の日没は17:37と。椰子(ヤシ)と夕日のシルエット。フェニックス(カナリーヤシ)。江ノ島周辺のランドマーク的な植栽で、リゾート感を演出しているのであった。国道134号線が前方に。江ノ島周辺ならではの植栽である フェニックス(カナリーヤシ) が逆光でくっきり浮かび上がり、晩秋の江ノ島らしいドラマチックな夕景が眼前に拡がったのであった。まっすぐ伸びた高いヤシの木は、江ノ島周辺によく植栽されているフェニックス・カナリエンシス。幹が真っすぐ、頭頂に大きな扇状の葉、シルエットが非常に美しい樹形なのであった。夕日との相性が抜群で、まさに「湘南らしい風景」を象徴しているのであった。雲の下に空隙(すきま)があり、太陽光がそこから漏れていた。晩秋・初冬特有の澄み切った空気によって、黄金色が強く出ていて、海面からの反射光が写真下部を明るく照らしているのであった。江の島漁港の整備完了を記念して、「無事故を祈願して」建てられたという「海の詩」の像。■ 作品名海の詩(うみのうた)■ 作者親松 英治(おやまつ えいじ)日本の彫刻家で、湘南地域に複数の作品を残しています。■ 所在地片瀬漁港(片瀬海岸)の広場江ノ島水族館の少し西側、片瀬漁港荷捌き場の前に設置。■ モチーフ海の生命力人と魚が一体化したような躍動的造形「海とともに生きる片瀬・江の島」の象徴的作品 と。「海の詩」のシルエットが完全に夕日と重なり、“躍動感”が強調された写真が撮れたのであった。移動して、江の島を背景に。片瀬漁港(片瀬江の島漁港)から見た相模湾の夕日 を捉えて。手前が片瀬漁港の内湾。静かな水面が夕日の光を伸びやかに反射していた。片瀬漁港の外側の防波堤には人影が見え、散歩や写真撮影をする人が立ち並んでいるのがわかるのであった。雲の下側が切れているため、雲と地平線の隙間から光がこぼれる“ドラマチックな夕焼け” の典型的パターンを捉えることが出来たのであった。非常に薄くだが、遠くに箱根・伊豆半島の山影が見えた。条件が良い日はこの位置に富士山のシルエットも現れるのだが、この日は富士山は雲に隠れて。海面の反射(グラデーション) が主役になっていたのであった。片瀬漁港の外側の防波堤をズームして。その手前には、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が現れていたのであった。太陽から海面にまっすぐ伸びる光が美しく、静かな片瀬漁港の雰囲気を引き立てていた。片瀬漁港から江の島を望む夕景を。漁船の静かな佇まいと、江の島シーキャンドル(灯台)のシルエット、そして海面に映る柔らかな光が融合して、まさに “片瀬漁港らしい夕景”なのであった。写っているのは片瀬漁港の定置網・釣り船・遊漁船など。写真中央の船には「第十八ゆうせい丸」と読み取れる文字があり、実際に片瀬漁港に所属する船。太陽が雲に隠れて、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が姿を消した。夕陽が沈みゆく空の中で、雲の縁だけが薄く金色をまとい、まるで空が自らの境界をそっと縁取っているように白い輝きが静かに滲んでいるのであった。雲のふちに夕陽の光が当たって、白くきらりと光っている。まるで雲が輪郭だけ輝いて浮かび上がっているようなのであった。そして沈みゆく太陽が厚い雲の下からわずかに顔をのぞかせ、その光が雲の縁を内側から焼き付けるように再び白く輝く。闇へと沈む雲の下で、陽光だけが最後の抵抗のように鋭い光の縁を刻んでいるのであった。沈む陽が雲の縁を白く照らし、港の水面まで夕光が流れ込む時間なのであった。停泊した漁船の影が静かに伸びて。いつまでも佇んで見つめていたい時間、空間なのであった。ズームして。太陽に近い部分は、黄色・白色・ややオレンジが混ざった高輝度の輝きが確認できる時間なのであった。反射の中心は太陽直下にあり、強い橙色の帯(光の道)が水面に伸びていた。水面は完全な静水ではなく、小さな揺れ(リップル)があるため、反射光が細かな線状に分解されて揺れて見える状態なのであった。太陽は水平線に向かって。円形がほぼ完全に見える状態に。厚い雲の縁は太陽が真下にあるため、逆光によって輝く「エッジライト」現象が発生しているが如くに。 ・・・つづく・・・
2025.11.21
閲覧総数 355
-
7

ウズベキスタンへの旅(その15 サマルカンド・レギスタン広場へ早朝散歩 : 5/27)
ウズベキスタン旅行6日目のこの朝も、前夜にライトアップ鑑賞に訪れたレギスタン広場への早朝散歩に。ホテルロビーのシャンデリア。ホテルの中庭の花壇にはコウノトリの置物が。中国風のオジサンの姿も。花壇の花は壺が倒れ流れ出た花。そしてプールも。ホテル正面を。この日も雲一つない晴天の下レギスタン広場に向かう。ウルグベク・マドロサ(Ulugh Beg Madrasah)。ディラカリ マドロサ(Tillya-Kori Madrasah)。チョルス-代ビジネスセンタ(Chorsu - Anсient trading center)。ペルシャ語を「十字路」または「四つの流れ」と表現し、接続経路を象徴する「Chorsu」という名前。レギスタン広場手前の緑地には芝生花壇が。倒れた花瓶から流れ出る花がここにも。正面に向かって左側にあるウルグベク・マドロサ(Ulugh Beg Madrasah)をレギスタン広場側から。ミナレット頂部。この様に美しいタイル張りのミナレットから、罪人を投げ落としたのだと。コの字型の中央に建つのがティラカリ・メドレセ (Tilla-Kari Medressa)。正面に向かって右側にあるシェルドル・メドレセ (Sher-Dor Medressa)。イスラムといえば、偶像崇拝を否定している。故にイスラム建築には人や動物のモチーフが使われていない。幾何学文様だからこそ、時代を超えた普遍的な美しい様式を創り出しているのだ。しかし、このシェルドル・メドレセの入り口アーチには、ライオンと人の顔が描かれていた。領主が権力誇示のために、あえて偶像崇拝の禁を破らせたのだと。ファサード右側のライオンと人の顔。左側のライオンと人の顔。現地青年が旅友と一緒に写真を撮りたいと。レギスタン広場の石畳を横断して西側に向かうと噴水が。カササギか?音楽を奏でる人たちの像。ネムノキの花。タンポポ。この石畳に埋め込まれたマークの意味するものは?レギスタン広場の木々は根元を防虫用の石灰で白く塗られて。芝生広場の壺から花が零れ落ちる姿を再び。観光用電動カートもこの日の出番を待っていた。レギスタン広場の先にあった像。先代の大統領カリモフ元ウズベキスタン大統領(2016年没)であると。先代の大統領の背中側から。こちらの噴水も朝から元気よく。ティラカリ・メドレセ (Tilla-Kari Medressa)の青のドーム。枝いっぱいに咲く白い花も実も美しいエゴノキ?。多くのミツバチが蜜を求めてブンブンと。時間は8:20。この日のホテル出発は9:00であるため、ホテルへ戻る。 ・・・つづく・・・
2018.06.15
閲覧総数 309
-
8

江東区・大島(おおじま)、亀戸を歩く(その8)・ 大島緑道公園~子安稲荷社~観妙寺~豊見徳龍稲荷~羅漢寺~五百羅漢跡~亀出神社
「大島緑道公園」を「新大橋通り」に向かって南に歩く。1972年に全線廃止となった都電砂町線の一部区間(堅川人道橋から新大橋通りを経て、明治通りに合流するまで)が公園として整備されていた。1978年4月1日開園。春は桜の名所としても知られている。中央の白線が往時の都電の姿を想起させるのであった。「大島緑道公園」碑。左手にあったのが「子安稲荷社」。出産の祈神霊の力により、子を安く産むという伝説により、何時のころからか子安神社と称するようになったと。子安稲荷神社は、元禄年間(1688-1704)当地域に創建したと。高砂鉄工所(子安稲荷神社近く、江東区大島3-7・8付近)の拡張工事により、昭和30年頃当地へ遷座したとのこと。「子安稲荷社」社号標。江東区大島3-21-9。「社殿」。御祭神は宇迦能魂之神(うかのみたまのかみ)。「社殿」の扁額「子安稲荷」。続いて訪ねたのが「大島緑道公園」を右に折れた場所にあった「観妙寺」。日蓮宗寺院の観妙寺は、大島山と号す。観妙寺は、昭和3年(1928)に大島教会として発足、昭和39年に大島山観妙寺と号したと。永代供養塔。「大島山観妙寺辨天講」の文字が。こちらにも同様に。「大島山観妙寺辨天講」。正面が「本堂・庫裡」。そして大島3丁目の住宅街の角の手前にあったのが「豊見徳龍稲荷」。扁額「豊見徳龍稲荷大明神」更にこの角を南に進むと「新大橋通り」に突き当たった。ここを右折して、「明治通り」に向かって進む。そして「新大橋通り」との交差点の角にあったのが「曹洞宗 羅漢寺」。山門を正面から。「曹洞宗 羅漢寺」寺号評。この扁額は「円通三匝院」と書かれているとのこと。調べてみるとこの寺は「祥安山 円通三匝院 羅漢寺」。「本堂」。江戸期、現在地(本所五之橋南)には、元禄八年(一六九五)に将軍吉宗により寺地一五〇〇坪を与えられて創建された天恩山羅漢寺という黄葉宗の寺院があり、五〇〇体の羅漢が安置されていた。なお、無檀家の新寺のため、五〇〇俵を賜る(『新編武蔵風土記稿』巻之二四)。この寺は弘化三年(一八四六) の暴風雨と安政二年(一八五五)の大地震で堂字が倒壊し、明治維新により、幕府からの援助もなくなり、田沼の間で地盤も脆弱なため、明治二〇年に本所区緑町に移転し、明治四二年には下目黒に移った(『目黒区大観』)。『大島町誌』によれば、明治三六年(一九〇三)に羅漢寺跡地に祥安寺(曹洞宗)が信徒総代の手により多摩郡氷川村から移される。戦前は毎月二日・一七日・二六日の三回縁日を催し、羅漢通りには露店が軒を並べ賑わった。昭和一一年(一九三六)に羅漢寺と改称した。扁額は「羅漢禅寺 」.「本堂内部」。境内の石仏と石灯籠。本堂前から「区文化センター前」交差点を望む。歴史を感じさせる石灯籠。「高巖院殿 尊前」と刻まれていた。「江東区総合区民センター」が正面に。「江東区総合区民センター」の所にあった「五百羅漢跡」碑。江東区大島4丁目5番1号。元禄八年この付近に黄檗宗松雲禅師作の羅漢像五百体を安置する広壮な羅漢寺が創立せられ五百らかんという名所として知られてきたが羅漢寺は明治二十年に墨田区へさらに同四十二年目黒区へ移転したが、なお当時の羅漢像の多くを残している。「五百羅漢跡五百羅漢は、元禄8年(1695)に松雲元慶禅師により創建された黄檗宗の寺院です。禅師は貞享年間(1684~1688)に江戸へ出て、元禄4年(1691)から木造羅漢像を彫り始めました。元禄8年(1695)、将軍徳川綱吉から天恩山五百羅漢寺の寺号と6千坪余の寺地を賜り、ここに自ら彫像した羅漢像など536体を安置しました。当寺の三匝堂は、廊下がらせん状に3階まで続いており、その様子がサザエのようであることから、または三匝とサザエの発音が似ていることから「さざえ堂」と呼ばれ、多くの参詣客を集める江戸名所のひとつでした。区内には、五百羅漢までの道筋を示す道標が2基現存しています。羅漢寺は明治20年(1887)本所緑町(現墨田区)へ移り、さらに明治42年(1909)現在地(目黒区)へ移転しました。ここに残る石標柱は、五百羅漢跡を示すために昭和33年(1958)に建てられたものです。」「歌川広重 名所江戸百景 五百羅漢さゞゐ堂」そして「新大橋通り」を進むと左手にあったのが「亀出神社」、「亀出子育地蔵尊」と「草分稲荷大明神」。「亀出子育地蔵尊」の社殿。扁額「亀出子育地蔵尊」。そしてこちらが「草分稲荷大明神」。朱の鳥居の扁額にも「草分稲荷大明神」。狐様の姿が。「草分稲荷祭祀草分稲荷については徳川初期現在の大島1丁目37番(釜長のならび)付近の草むらの中に小さなほこらが建てられていたと伝えられ、昭和のはじめまでは付近住民が旧初午の日に寄付をもちより祭礼を行ってきたと語り継がれているものである。往昔南葛一円の地は徳川幕府による禁領地であり、常時番人をおいて厳重に見張りをし、明治維新まで続いていた。現在の大島2丁目付近には鷹狩に使われる鴨池があり、御用屋敷と呼ばれるものが散在していたという。たまたま徳川3代将軍家光がこの池に遊猟の際、草繁き狩場で路にまよったところ、その道案内にたったのがこの稲荷であるともいわれている。稲荷神社は『うがのみたまのみこと』を祭神とし、食物一切つかさどる神とされている。城東地区はもともと農業地域であったことから稲荷社がかなり多いが、慶長から元禄の頃がもっとも多く、徳川2代の秀忠から5代綱吉にいたる頃といえよう。その後祀るものもないままに、さらに墓地改葬があり、土砂、雑草に埋もれかえりみられなかったが、ここに城東区役所が移ることになって、その新築工事が進むにつれ、ほこらも堀り出され業者によって庭の一隅に安置された。昭和15年区役所がここに移転するや庁内の有志がほこらを復建し毎年ささやかな祭をしてきた。昭和16年頃この社が香取神社宮司の夢枕にたち『火難』があるかもしれないから後世大切に祀るようにとのお告げがあったと伝えられている。昭和48年4月、江東区区民センター建設に伴い亀出神社の境内に区長並びに香取宮司立合いの上遷座したものである。」そして最奥にあったのが「亀出神社」。「社殿」。水運のために竪川が開鑿されたため、亀戸村から切り離され当地周辺を亀戸出村と称していた。寛文十二年(1672)に亀戸出村(大島村)にあった霊巌寺領の鎮守として霊巌寺の僧松風が創建したという。水運のために竪川(首都高速7号線の下)が造られた結果、江戸時代後期に編纂された『新編武蔵風土記稿』では、大島村の項に、愛宕神社として記載されており、大島村・大島町の鎮守とされている。また霊巌寺領であったことから、念仏堂が当社近くにあったといい、現在も子育地蔵尊が安置されている。昭和41年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の時代(17世紀末から18世紀初め)に松平定儀が別邸を築くに際して鬼門除として創祀した「亀出稲荷神社」と、寛文十二年(1672)に亀戸出村霊巌寺領の鎮守として創建したといわれている愛宕神社を、現在地に合祀して成立し、同48年には大島1丁目37番に鎮座していた草分稲荷神社を境内へ合祀している。扁額「亀出神社」。「内陣」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.08.22
閲覧総数 576
-
9

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その21):63番・吉祥寺、60番・横峰寺
【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】👈リンク63番札所:吉祥寺(きちじょうじ)62番札所:宝寿寺から国道11号線(讃岐街道)を東に向けて1.4km強を走ると63番札所:吉祥寺に到着。正面に吉祥寺の山門。インドの四天王の一人毘沙門天を本尊とするためか山門の前には一対の「象」の像が向き合っていた。山門の扁額には「密教山」と。宝寿寺から吉祥寺までの走行ルート。吉祥寺 境内配置案内図。「山門を入って左側に鐘楼、手水場があり、少し進んで右に庫裏と納経所、左に本堂、その左に大師堂である。」境内の「巡りゆく思い」と題された作品。伊予之二名島(いよの・ふたなのしま)、胴体が一つで、顔が四つの島、四国、その骨格たる石鎚山、見事な造形であると。福聚閣(ふくじゅかく)。庫裏前のお堀に浮かぶ極彩色の八角堂の福聚閣には本尊の毘沙門天を除いた六福神が祀られており、本尊の毘沙門天を合わせて七福神となる四国七福神は吉祥寺と近辺の横峰寺・宝寿寺・前神寺・西山興隆寺・極楽寺・安楽寺の6ヶ寺を巡るのだと。手水舎。水子地蔵尊。お迎え大師(左)と くぐり吉祥天女(右)くぐり吉祥天女は貧苦を取り除き、富貴財宝を授かるという。お迎え大師。くぐり吉祥天女成就石。本堂付近から目を閉じて金剛杖を持って石が置いてある場所まで歩いて行き、石に開いてある穴(直径約30cm)に金剛杖を突き通すと願いが叶うと伝わると。鐘楼。吉田真照の句碑。「有難や美阿登慕うて二十五歳」弐千回、参千回、八十八ヶ所 百回の文字が刻まれており参拝回数の記念碑か。本堂。寺伝によれば弘仁年間(810年-823年)に空海(弘法大師)が光を放つ檜から毘沙門天・吉祥天・善賦師童子を刻み、安置したのが起源といわれる。当初は坂元山(現在地より南へ約2kmほど登った標高368m地点 )にあったが、豊臣秀吉の四国征伐の際に焼失。詳しくは1585年(天正13年)に小早川隆景が高尾城を攻めたとき、その山中にあった当寺も兵に放火された。万治2年(1659年)に大師堂があった現在地に、坂元山にあった本尊毘沙門天坐像が移され、再建された。四国八十八ヶ所で「毘沙聞天」が本尊なのは、ここ吉祥寺だけと。持国天・増長天・広目天と共に四天王の一尊に数えられる武神であり、四天王では多聞天として表わされます。吉祥寺では「毘沙聞天」と表記する際に多聞天の「聞」の字を使っていますが、通常は「毘沙門天」と「門」の字で書くのだと。本尊・毘沙聞天像は秘仏で60年に一度だけ開帳され次回は西暦2038年とのこと。密教山 胎蔵院 吉祥寺(みっきょうざん たいぞういん きちじょうじ)宗派 真言宗東寺派本尊 毘沙門天(毘沙聞天)(秘仏)創建 (伝)弘仁年間(810年 - 823年)開祖 (伝)空海(弘法大師)所在 愛媛県西条市氷見乙1048本尊真言 ”おん べいしら まんだや そわか”大師堂。大師堂 内部。本堂前からの境内。「念ずれば 花ひらく」、この石碑は別の寺でも見かけた。熱心な信者の奉納か?左から弘法大師千五十回、一千一百回、千百五十回遠忌報恩謝徳也。境内の桜も満開。納経所へ。お遍路の可愛らしい人形が。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。「二百回 結願の碑 大本徳森翁」の石碑。ただただ脱帽。松山真講会 40周年記念碑。-----------------------------------------------------------------------------------------------------60番札所:横峰寺(よこみねじ)吉祥寺を後にし直ぐに県道142号線の狭い山道を登っていくと左手に黒瀬湖が姿を見せた。1973年(昭和48年)完成、県下でも有数の水量豊富なダムであり、西条市の産業発展の礎となっていると。鏡のような水面には、時はに「逆さ石鎚」が映り込むと。更に上って行くと、平野林道の料金所が。石鎚森林組合が管理している有料道路(約6km)であり、往復通行料金は普通車1,850円(駐車場代含む)。12月29日より2月末日までは冬季通行止(冬季通行止期間中でもゲートは開いており自己責任で通行は可能であるが、道路修復工事の為途中までで止まることがあり要注意)と。狭い林道を更に上って行く。そして頂上駐車場に到着。吉祥寺から横峰寺までの走行ルート。山の中でWIFI信号が弱いため、往復のルートがズレていますが同じ山道なのです。眼下には瀬戸内海・西条市の臨海工業地帯が望めた。今治造船・西条工場をズームで。現役の頃、この近くにあるアサヒビール四国工場に何度か通ったことを想いだしたのであった。駐車場に車を駐め、更に横峰寺に向かって山道を上っていく。横峰寺への案内表示板。横峰寺 境内配置案内図。「山門を入り参道を進むと右に手水場があり、左に行くと庫裏・客殿・納経所が、右の石段を上がると正面に鐘楼・星供大師があって、その右に本堂が建つ。本堂の向かいの参道を進むと正面に大師堂が、その右に聖天堂がある。 シャクナゲが境内一面に咲きほこる5月上旬はそれ目当ての観光客も来て、ゴールデンウイーク期間は自動車が渋滞するほどである。」境内に入ると星月堂(納骨堂)が左手に。境内への山の斜面には シャクナゲが一面に。5月中旬には写真の如く開花し、平野林道が渋滞するほどに花見客が訪れると。客殿。境内の正面に本堂が。歓喜天堂(聖天堂)。大師堂。参道左手には多くの石仏が並んでいた。弘法大師を近くから。歴史を感じさせる多くの石仏・地蔵尊が並ぶ。鐘楼。正面に大師堂、左手に歓喜天堂(聖天堂)。本堂。「寺伝によれば役行者(役小角)が石鎚山頂で修行をしていたところ、蔵王権現が現れたのでその姿を石楠花の木に刻んで堂に安置したという。その後行基が天平年間(729年 - 748年)に、空海(弘法大師)が大同年間(806年 - 810年)に入山したと伝え、空海が入山した際に大日如来を刻み、これを本尊としたという。前神寺とともに石鈇権現の別当寺であったが、明治4年に廃仏毀釈によって廃寺となり、明治13年に大峰寺の名前で復興、その後、明治42年(1909年)に元の横峰寺の名に戻される。」神社を彷彿とさせる権現造りの本堂に、神仏習合の面影が残っているのだと。大師堂とは参道を挟んで正面から向き合っていた。石鈇山 福智院 横峰寺 (いしづちざん ふくちいん よこみねじ)宗派 真言宗御室派本尊 大日如来創建 (伝)白雉2年(651年)開祖 (伝)役小角所在 愛媛県西条市小松町石鎚甲2253本尊真言 ”おん あびらうんけん ばざらだどばん”星供大師像が正面に。「星供」とは仏教系統の星祭で、『宿曜経』などの説により、北斗七星・九曜・十二宮・二十八宿を供養し、除災・延命・増福を祈る法会。冬至・正月・節分などに行う行事。西日本最高峰・石鎚山系中腹にある札所は古くから遍路泣かせの難所と言われています。開祖は修験僧の開祖・役行者小角(えんぎょうじゃおづぬ)。白雉2年(651)、星ガ森(石鎚山遥拝所)で修行中の役行者小角は、石鎚山頂で蔵王権現のお姿を見て、そのままの姿を石楠花(しゃくなげ)の木に刻んで小堂に安置しました。弘法大師が42歳の厄除け開運祈願の修行の為、この山へ登り星祭りの修行を行い、その結願の日に役行者と同じ権現様の姿を見せました。そこで大師はこの山を霊山と定め大日如来を刻み本尊として安置し第六十番札所に定められたと。星供大師像。標高750mの地でシャクナゲを背に右手に剣、左手に星供に巻物を持って立っていた。鐘楼堂。鐘楼堂を別角度から。納経所への階段を下る。納経所。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。仁王門からの参道にある手水舎。山門を見つめる旅友。手水舎前から山門をズームで。車によるお遍路の場合、山門・仁王門を潜らないケースが時々発生するのであった。納経所前から階段上の大師堂方面。大師堂を再び訪ねる。大師堂内部。「聖地巡礼 四国遍路」のポスター。「弘法大師空海ゆかりの札所を巡る四国遍路は、阿波・土佐・伊予・讃岐の四国を全周する全長1400kmにも及ぶ我が国を代表する壮大な回遊型巡礼路であり、札所への巡礼が1200年を超えて継承され、今なお人々により継続的に行われている。四国の険しい山道や長い石段、のどかな田園地帯、波静かな海辺や最果ての岬を「お遍路さん」が行き交う風景は、四国路の風物詩となっている。キリスト教やイスラム教などに見られる「往復型」の聖地巡礼とは異なり、国籍や宗教・宗派を超えて誰もがお遍路さんとなり、地域住民の温かい「お接待」を受けながら、供養や修行のため、救いや癒しなどを求めて弘法大師の足跡を辿る四国遍路は、自分と向き合う「心の旅」であり、世界でも類を見ない巡礼文化である。2015年4月に日本遺産に認定された」と。再び本堂方面の境内を見る。客殿廻りの庭園を見下ろす。そして駐車場にある休憩所・売店へ。アイスクリームを楽しむ。売店の前には多くのアルミ缶製の風車がぶら下がっていた。売店の女性が一つをプレゼントしてくれました。人になれた野鳥・ヤマガラが、餌のヒマワリの種を食べに旅友Sさんの掌に。心温まる瞬間なのであった。 ・・・つづく・・・
2018.05.24
閲覧総数 1017
-
10
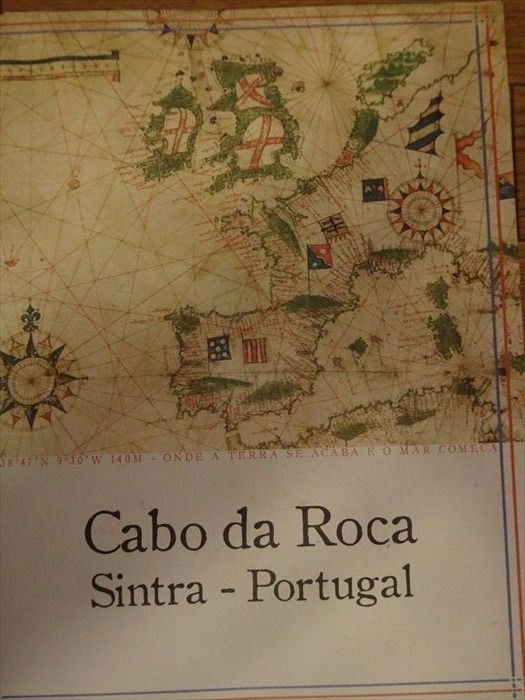
ポルトガル旅行記:その21(ロカ岬-2 2019.02.12)
添乗員に案内されロカ岬のビジターセンター(インフォーメーションセンター)に向かう。このセンターに向かった理由は自分の名前入りの『ユーラシア大陸最西端到達証明書』を発行してもらうため。証明書は2種類の中から選べて11ユーロでA3版見開きサイズ。ビジターセンター内にある申込用紙に、氏名・日付を記入し受付の人に渡すと蝋印が付いた証明書をゲットできたのであった。1枚目の表紙はヨーロッパの地図。表紙をめくると、A3見開きで左にロカ岬の石碑と上空からの写真が。そして右手にA4サイズの『ユーラシア大陸最西端到達証明書』が。『ユーラシア大陸最西端到達証明書』Certifico(証明する)Que + 【私の名前】が。そしてこの日の日付『12.Feve.2019』とポルトガル語で。封蝋(ふうろう、シーリングワックス、英: Sealing wax)。封蝋とは、ヨーロッパにおいて、手紙の封筒や文書に封印を施したり、主に瓶などの容器を密封するために用いる蝋である。手紙や文書の場合は、この上に印璽(シール)で刻印することで、中身が手つかずである証明を兼ねる。中世~近世のヨーロッパでは公式文章や親書などの重要書類に封をして本物であることの証明として使われていたとのこと。そして裏のページには『証明書』の説明文が9カ国語で。日本語の部分。『【私の名前】がポルトガル国シントラにあるロカ岬に到達されたことを証明します。 ここはヨーロッパ大陸の最西端に位置し、「陸尽き、海始まる」と詠われ、新世界を求め 未知の海へとカラベラ船を繰り出した航海者たちの信仰心と冒険魂が、今に尚 脈打つところです』と。ところで旅行前に訪ねたネットのページにはこの最西端到達証明書の保有率ナンバーワンはなんと日本人なんだと。しかも…発行枚数の3割が日本人で占めているのだと。本当に私を含め日本人は『○○限定』とか『最○端』というフレーズに弱いとは感じていたのであったが、日本国内で御朱印を集めている私にはGETする選択肢しかやはりなかったのであった。初めてのポルトガル訪問でのポルトガル土産として購入したのです。昔の書体で名前を記入してくれて、ロウ印をペタリ。これも良い記念と土産になりました。アジアの最東端・日本にいる私達が、ユーラシア大陸の最西端を訪れる。ユーラシア大陸の最西端に立っているんだなと思うと、感慨はひとしお。そんないかにも「冒険」といった感じを味わえる旅であると感傷的になった自分がいたのであった。ビジターセンター前のバス停近くの小さなロータリー状の芝生広場にあった岩庭風の中にあったこの石碑は?シントラ=カスカイス自然公園内のロカ岬周辺案内図。シュリ・チンモイの平和の花のプレート。ロカ岬は、全世界に800ヶ所ある、1989年からSri Chinmoy Peace Blossoms.という事業に認定された、平和のために捧げられた場所だと。再び灯台を目に焼き付ける。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -1。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -2。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -3。ロカ岬周辺の崖と大西洋そして灯台。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -4。国際ロータリークラブの創立750週年記念の石碑。PAUL HARRISと刻まれているのは、シントラのロータリークラブの会長の名前。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -5。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -6。ロカ岬周辺の崖と大西洋 -7。上空ではドローンが絶景を撮影中。ドローンのカメラ⬅リンクは下記の如き絶景を捉えていたのであろう。動画を切り取る-1。動画を切り取る-2.ロカ岬周辺の崖と大西洋 -8。再び頂上に十字架の在る石碑を。再び夕日を浴びたカルポブローツス・エドゥリスを。南アフリカのケープ地方が原産。北アメリカでもカリフォルニア州からメキシコに帰化。海岸沿いの砂丘や道端、断崖などに生え、高さは20センチほどになる。長さが2.7メートルにも伸びる地下茎で広がる。葉は断面が三角形の多肉質 と。ロカ岬とも今生の?別れ。 ・・・つづく・・・
2019.03.08
閲覧総数 1230
-
11

旧東海道を歩く(富士~興津)その5:蒲原宿・渡邉家土蔵~本陣跡
『旧東海道を歩く』ブログ 目次日軽蒲原第二発電所を見ながら、更に旧東海道を進むと左手には『蒲原の名所、旧跡』が写真で説明されていた。訪ね損なった『源義経硯水(よしつねすずりみず)』の案内を写真撮影。「1174年(承安4年)に源義経が東に下る時に菩提所の涌き水を使って蒲原神社へ奉納する文と愛知県矢矧(やはぎ)の長者の娘浄瑠璃姫に文を書きました。送られた文を読んだ浄瑠璃姫は源義経を慕い矢矧から奥州に下る途中に病で倒れこの地で亡くなりました。その時以来涌き水が義経硯水と言われるようになりました。1654年(承応3年)に供養塔が建てられました。その後1817年(文化14年)には地蔵尊が建てられ、「いぼ神様」として尊ばれ参詣者が絶えなかったとのことですが旅人が持ち去ってしまいました。現在の地蔵尊はのちに再建されたものです。」『歴史国道』説明。歴史国道とは、歴史上重要な幹線道路として利用され、歴史的・文化的価値を有する道路として国土交通省(建設省)が選定した道路のこと。この時に歩いている道、東海道 岩渕間宿〜蒲原宿〜由比宿(静岡県富士市 - 静岡市清水区)も歴史国道の一つであると。清水区蒲原二丁目の住宅街を歩く。すると左手奥にあったのが『渡邉家土蔵(三階文庫)わたなべけどぞう(さんかいぶんこ)』「木屋(きや)の土蔵市指定文化財(「渡邊家土蔵(わたなべけどぞう)(三階文庫)(さんかいぶんこ)」 渡邊家は、江戸時代末期に問屋職を代々務めた旧家です。また、材木を商っていたことから、「木屋」という屋号で呼ばれていました。 「渡邊家土蔵(三階文庫)」は、四隅の柱が上にいくにつれて少しずつ狭まる「四方具(しほうよろび)」(四方転(しほうころび))という耐震性に優れた技法で建築されています。三階建ての土蔵はあまり例がなく、棟札(むなふだ)から天保9年(1838)2月21日に上棟したことがわかり、市内最古の土蔵であると考えられます。この土蔵の中には、江戸時代の貴重な資料が多く保管されています。 」入口右手にあったのが『木屋稲荷』。木屋稲荷は渡邊金璙(かねよし)が天保9年(1838)に家神社として石祠を造ったと。現在は木屋江戸資料館として公開。運良くこの渡邊家の奥様(館長)が出て来て下さり、正面の入口の南京錠を解いて「木屋の土蔵」内部を案内して下さいました。「中の構造は、二重の梁や隠し階段等の工夫が凝らしてあり建築物としても大変貴重な資料として関係者の熱い視線を浴びているものです。合計23本の通し柱で各階で一寸(3cm)ずつ内側に傾いています。」写真は頂いたパンフレットより転載させていただきました。「この蔵は安政の大地震(1854年)にも耐え貴重な当時の所蔵品や資料を現在に残しています。」『渡邉家の歴代当主』の説明。蔵1回は『木屋江戸資料館』として公開中。資料館内に展示されていた長久保赤水の制作した日本地図。「伊能忠敬の「伊能図」がつくられる四十二年前に緯度と日本版の経線(京都を標準にした等間隔の南北線)を記したかなり精巧な日本地図があった。それが『日本輿地路程全図』(にほんよちろていぜんず)、世に云われた「赤水図」である。この「赤水図」は大阪の出版社によって世に流布され、当時のベストセラーとなり旅人に愛用された。これより四十二年の後、黒船が来航する江戸時代末期に幕命でつくらせた「伊能図」は国家機密とされ、江戸時代には一般人は見ることが叶わなかった。ゆえに、江戸時代中期から明治時代まで広く世に使われたのは「赤水図」だった。幕末の志士吉田松陰も「赤水図」を携えて仙台まで旅し、長州(山口県)への岐路、茨城県高萩市赤浜にある長久保赤水の墓に参詣している。また、かの医学者シーボルトもヨーロッパに持ち出し紹介しており、現在もイギリスのケンブリッジ大学やドイツの博物館など数か所に収められていることを東京大学大学院教授馬場章氏が近年発見している。」と。江戸時代後期に蒲原宿で問屋職を務めた渡辺金璙は、膨大な数の日記や記録を残しており、それがために当時の蒲原宿の様子が現在に伝わっているという貴重な文書を所蔵していると。奥様・館長の渡辺和子さんは説明がわかりやすくて話が面白く、大変勉強になった。地図を広げて『東海道の移り変わり』⬅リンクを熱く説明してくださった。最近では、テレビで活躍中の磯田 道史氏がこの蔵を訪ねて来たと。そして更に旧街道を進む。『一国之十六番 岩戸山』と刻まれた石碑。『龍雲寺』。街道がやや左に折れるところに岩戸山の石柱があり、その脇を入って行くと臨済宗妙心寺派の岩戸山龍雲寺があった。『六地蔵』。『本堂』。承応2年(1653)高松藩の槍の名人大久保甚太夫が蒲原宿西木戸辺りの茄子屋の辻で薩摩藩の大名行列と出会い、槍の穂先が相手の槍と触れたことで乱闘となった。この事件で殺された甚太夫の槍の穂先が残っていると。本堂に掛かる『岩戸山』の扁額。永代供養墓の『涅槃佛』。『聖観音菩薩』。蒲原宿 道標。懐かしい風景。いつの日かモール化を。『馬頭観音』。『「馬頭観音」供養石塔の由来』「かって馬が、貨客の運搬、農作業など、生活の重要な役割を担っていた時代、「馬頭観音」は馬の守り神として、人々の信仰を集めていました。また、路傍に立てられたその石像や供養塔は往還(街道)の道しるべとしても親しまれていました。 江戸時代、このあたりから蒲原宿東木戸にかけての間は伝馬や宿役に使われた馬を飼う家が並んでいますた。 この付近にも昭和の初め頃まで馬小屋があり、馬頭観音が祀られていたとつたえられていましたが、昨年11月、通りの北側の駐車場整備の際、半分土に埋もれた、この馬頭観音供養石塔が発見されました。 そこで、往時の人々の馬に寄せるあたたかい心を偲びその場所に新たに安置して、お祀りすることにいたしました。」『日蓮宗 佛護山 東漸寺』入口。旧八幡町と旧天王町の境目あたりには佛護山東漸寺が。『山門』。明治14年(1881)の題目碑があるので日蓮宗系の寺。元弘元年(1331年)開祖の日蓮宗の古刹。元は西より御殿屋敷付近にあったが、家光上洛時増改築のため現在地に移転した。本陣に近いことから混雑時は臨時の宿舎となったと。『本堂』。「東漸寺は、日蓮上人直弟日興上人の弟子中老僧日目上人の開創と言われ、北条重時の嫡男石川式部入道勝重の発願により、元弘元年(1331)に創建された。はじめはもっと西の御殿跡辺りにありましたが、3代将軍家光の上洛の際に、御殿屋敷を建て替えるために現在地に移転した。境内には推定樹齢400年のイヌマキ、木屋の渡邊利左衛門の起立した文政11年(1828)の法界塔がある。」『手水舎』。桜の樹の後ろに立派な鐘楼が。寺の建造物は安政の大地震(1855年)で悉く倒壊したので、すべてそれ以降のものであると。また、数度火災に見舞われているとも。鐘楼の前には木屋の渡辺利左衛門の起立した法界塔が。『渡邉利左衛門起立の法界塔』説明板。利左衛門周玞(かねのり)が法華経一部、6万9,384文字を一石に一字づつ書写し、それを礎石として利左衛門金璙(かねよし)が文政11年(1828)に起立したと。南妙法蓮華経と刻まれた日目上人 慰霊碑。日蓮大聖人の仏法は、二祖日興上人・三祖日目上人と相伝されたのだと。『なまこ壁と「塗り家造り」の家(佐藤家)』なまこ壁に近寄って。「当家は、元「佐野屋」という商家でした。壁は塗壁で、町家に多く見られる造りですが、このような町家を「塗り家造り」といいます。 「塗り家造り」は「土蔵造り」に比べて壁の厚みは少ないが、防火効果が大きく、昔から贅沢普請(ぜいたくふしん)ともいわれています。もともとは城郭などに用いられた技術であり、一般には江戸時代末期以降に広まったと考えられております。 なまこ壁の白と黒のコントラストが装飾的で、黒塗りの壁と街道筋には珍しい寄棟(よせむね)の屋根とが相俟(あいま)って、重厚感(じゅうこうかん)があふれています。 」『八坂神社』入口。『商家の面影を残す「塗り家造り」(吉田家)』。「当家は、昭和まで続いた「果堂」という屋号で和菓子を作る商家でした。玄関は、なまこ壁の「塗り家造り」で、中にはいると柱がなく広々した「床の間」づくりになっていて、商家らしい雰囲気が残っています。土間には、当時の看板が掲げられており、「中の間」には、らせん城の階段があって、二階に通じています。」「店の間」。『問屋場跡』「問屋場は、幕府の荷物の取り継ぎ、大名の参勤交代の折りの馬や人足の世話をはじめ、旅人の宿泊や荷物の運搬の手配をしたところで、宿のほぼ中央にあたる場所に設置されていた。ここに問屋職、年寄、帳付、迎番、馬指、人足方、下働、継飛脚、御触状、持夫の人々が毎月15日交代で詰めて宿の経営にあたっていた。」『椙守稲荷神社(すぎもりいなりじんじゃ)』。この神社は御殿山南麓に鎮座。参道脇には御殿山への遊歩道案内があり、ここから約10分位で「狼煙場」と呼ばれる頂上に到着出来るようです。入口や参道途中の鳥居には「椙守神社」と書かれていましたが、社殿には「椙守稲荷神社」と書いてあることがカメラズームで確認できましたので、明らかに稲荷神社と思われます。車が停まってないともっと良かったが・・・。問屋場跡の前の小川を左に沿って行くと『蒲原夜之雪』記念碑が建っていた。夜之雪記念碑には碑と共に広重の絵と案内板が掲示されていた。「夜之雪記念碑」と「蒲原夜之雪」「蒲原夜之雪」の絵は、歌川(安藤)広重が、天保三年(一八三ニ)四月、幕府の朝廷への献上使節の一行に加わって京へ上った折、この地で描いたもので、東海道五十三次シリーズの中でも最高傑作といわれています。 昭和三十五年「蒲原夜之雪」が国際文通週間の切手になりました。これを記念して広重がこの絵を描いたと思われる場所にほど近いこの地に記念碑が建てられました。」 広重の「蒲原夜之雪」「歌川(安藤)広重は、天保元年(1829)幕府の内命を受けて、「八朔御馬献上(はっさくおうまけんじょう)」の式典のようすを描くために、初めて東海道五十三次 の旅を体験した。実際に旅したのは、天保三年(1832)のこととされている。「八朔御馬献上」は、江戸の幕府から朝廷へ御料馬(ごりょうば)二頭を献上する年中行事の一つであった。 その時のスケッチや印象をもとにして、広重が五十五図の錦絵に制作したものが保永堂版「東海道五十三次」のシリーズである。この五十五図のうち、特に「蒲原夜之雪」は「庄野の白雨」「亀山の雪晴」とともに”役物(やくもの)”と称され、中でも最高傑作といわれている。 錦絵に使用する越前奉書紙の地色を巧みに生かした夜之雪、二人の駕籠屋(かごや)と一人の按摩(あんま)を配した里の情景など、抒情(じょじょう)豊かに構成された名作との評価が高い。 」『東海道五十三次夜之雪(蒲原) 安藤広重』雪道の坂を下る人は番傘を半開きにして杖を突き、足には雪下駄で、慎重な足取り。背を丸めて坂を上る人々の先頭の菅笠に合羽の男は、小田原提灯で足元を照らしている。完成度の高い構図、ふっくらとした新雪の柔らかさも感じるねずみ色の濃淡で表した雪の量感人間と自然との調和した描写は、地名を超越した普遍的な風景画として強い印象を。旧街道の建物を楽しみながら更に進む。『旅籠 和泉屋(鈴木家)』。自販機は片付けたいと我儘にも。「当家は、江戸時代「和泉屋(いずみや)」という上旅籠(じょうはたご)でした。天保年間(一八三〇~四四)の建物で、安政の大地震でも倒壊を免れました。 今に残る二階の櫛形(くしがた)の手すりや看板掛け、柱から突き出た腕木などに江戸時代の上旅籠の面影を見ることができます。 弘化二年(一八四五)の「蒲原宿商売調帳(かんばらじゅくしょうばいしらべちょう)に、「和泉屋間口間数(いずみやまぐちけんすう)六・一」とあり、現在は鈴木家四・一間、お休み処ニ間のニ軒に仕切られています。 」蒲原宿『本陣跡』「本陣は、大名宿・本亭ともいわれ、江戸時代に街道の宿場に置かれた勅使大名、公家などの貴人が宿泊した大旅籠です。主に大名の参勤交代の往復に使用されました。原則として門、玄関、上段の間(ま)がある点が一般の旅籠と異なりました。ここは当宿の西本陣(平岡本陣)の跡で、かってはここより百m程東に東本陣(多芸本陣(たきほんじん))もありました。本陣の当主は名主、宿役人などを兼務し、苗字帯刀(みょうじたいとう)をゆるされていました。 」 その4 に戻る。 ・・・つづく・・・
2019.04.24
閲覧総数 873
-
12

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その3)・龍前院~弁慶塚
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次「鶴嶺八幡宮」を後にして、その北側にあった「龍前院(りゅうぜんいん)」を訪ねた。神奈川県茅ヶ崎市浜之郷425。参道入口にあった「懐嶋山」石碑。この先「私道に付き車両通り抜け厳禁」と。「龍前院」石碑。寺号標石「正録 護國禪寺 龍前院」。古くは法相宗の寺であり、古義真言宗、鶴嶺八幡宮の僧坊から、曹洞宗寺院へとなった。また、正録護国禅寺と号したと伝えられていると。参道右手にあった「六地蔵」にはマスクはなし。近づいて。更に「本堂」に向かって私道を進む。「曹洞宗 懐嶋山(かいとうざん)」碑。近づいて。右手に「庚申塔」群。中央&右側の三体。中央に青面金剛像。四または六臂(二臂や八臂のものもあるという)で、手に、輪宝、鉾、羂索、蛇、弓矢、金剛杵、日月、劒などを持つ。邪鬼を踏むものも見受けられる。左側。中央の「見ざる言わざる聞かざる」の三猿像を彫った庚申塔は、茅ヶ崎市内にある猿を彫り出した8基(明暦~寛文期)の中で最も古い年号・明暦3(1657)年をもつ(市指定重要文化財)。人の延命招福を願って造られた と。「龍前院の庚申塔整然として並ぶこれらの石造物の多くは江戸時代に造られたものであり、長くこの地域の人々の心の支えになってきました。このうち中央にある石塔は、三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)を彫った庚申塔としては初期のもので、人の延命招福を願って造られました。市内で八基見つかっている同様な形の庚申塔の中ではこの塔が最も古いもので、明暦三年(一六五七)の年号が刻まれています。また基部には造立者十人の名が刻まれています。初期三猿像の庚申塔として貴重なものであるため、市の重要文化財に指定されました。」寺務所の入口右には巨大な石灯籠があった。「本堂」の手前の右手の「梵鐘」は、浜之郷村の領主だった山岡景忠が弟の早死をいたみ鋳造させたもの と。「元禄七年」(1694年)の銘があり、茅ヶ崎市内最古のもの。老朽化のため「梵鐘」は角材で支えられ近寄れないようになっていた。ネット越しの「梵鐘」。「龍前院の梵鐘昭和六十ニ年四月十七日茅ヶ椅市重要文化財指定この鐘は江戸時代に浜之郷村の領主であった山岡氏の五代目景忠が、弟の早死をいたみその供養のために再鋳させたものである。元禄七年(一六九四)の銘がある。第ニ次大戦中の供出もまぬがれて、現在市内最古のもので、江戸期の典型的な梵鐘の姿を伝えている。総高 一一五センチ 鐘身 八四、八センチ口径 六ニ、ニセンチ 撞座高 一九センチ乳五段五列百個 銘文陰刻 下帯に唐草文鋳物師 荻野邑 木村清兵衛正重」ここにも石仏がニ体。「錫杖」と「宝珠」を持つ地蔵菩薩像であろうか。「本堂」を正面から。龍前院の開創は古く、約800年前・行基菩薩にまで遡ることができる。行基作の薬師如来・十二神将像、三井寺より遷座された阿弥陀如来像を祀り、また、鶴嶺八幡宮の宿坊の一つでもあり、多くの人びとの信仰を集めてきた。今では、残念ながらそれらの仏像は明治の大火で失われましたが、市重要文化財である五輪塔、庚申塚、市内最古の梵鐘をもつ、由緒ある曹洞宗寺院である。扁額「懐嶋山」。内陣をズームして。「阿弥陀如来像」。「本堂」の屋根を見る。「龍」の文字の瓦。曹洞宗の久我竜胆(永平寺派)の宗紋も。二基の石碑。「馬頭観世音」碑(左)。「四国五拾七番伊豫國八幡寺写?・」と刻まれた石碑(右)。「本堂」右奥の墓地を見る。掲示板。「正見私たちの温かい「ことば」や「行い」が苦しんでいる方がたを支えますコロナ禍にあって、この苦境に立ち向かう人に敬意を表します。他方で羅漢者の方々や医療従事者とそのご家族などに対する誤解と偏見、差別事象や風評被害が引き起こされています。科学的根拠のない不正確な情報、迷信に振り回されることなく、冷静に生活を行っていくことが第一に求められています。私たちにとって今できる、大切なことはウィルスに留まらず不安と差別の感染予防なのです。「正見」とはお釈迦様が説かれた八正道の教えの中にある言葉です。八王道が説く8つの大切な教えは, それぞれに個別なものではなく、相互に密接に関係しあいながら、統合され仏教者の正しい生き方を示しています。なかでも、正しい信仰を持っための「正見」は仏教者として思考や行動の基準となるものです。」「新型コロナウイルスによるあらたな差別をなくすために私たちは誓願します。不安に駆られて「他」をきずつけることのないようお互いを慈しみあえる社会にすることを請願します」永代供養墓「龍光苑」。小さな「大師堂」が「本堂」の裏側に建っていた。これは「お大師(弘法大師)様」で、相模国準四国八十八ヶ所霊場第57番 浜之郷 八幡宮社頭 伊予栄福寺写と伝えられる石仏 であると。ブロック塀の下には小さな五輪塔が見事な数で並んでいた。墓地に並ぶ10基の五輪塔は、鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけて造られたものと考えられている(市指定重要文化財) と。「五輪塔」を正面から。「龍前院の五輪塔十基昭和六十二年四月十七日五輸塔は供養塔の一つで、密教の影響によって起こったといわれ、下から地・水・火・風・空の五輪から成っている。これは、宇宙はこの五つの要素からできているという仏教思想に基づいている。これら十基の塔は形態などからみると、全部が同時に造られたのではなく、鎌倉時代後期から南北朝時代初期(十四世紀前半)にかけて順次造られたものと考えられる。このような比較的大型の五輪塔が十基もまとまってある例は県内でも珍しく、大きさは市内では最大のものであることから、中世にこの地域を治めた有力な武家の累代の供養塔と考えることができる。」「五輪塔と卒塔婆」。五輪は、それぞれ古代インドの宇宙観にもとづき、人が死ねば、この世のすべてを構成すると考えられている五大要素(地・水・火・風・空)に還元されるという意味で、これによって死者を供養するという考えの象徴です。後世になって、五輪塔を木の板で模したものが、卒塔婆(ソトバ)です。卒塔婆とは、遺骨を埋葬するときや年忌法要などのときに、お墓の後ろにたてる細長い板のことです。卒塔婆は、古代インドの梵語である「ストゥーパ(仏舎利塔)」の音を漢字に置き換えたもの。卒塔婆を略して塔婆(トウバ)や板塔婆とも呼びます。日本では卒塔婆というと、長さ1~2mほどの「板塔婆」を指します。先端を塔の形にし、上の方には、仏教の宇宙観を表す五大要素、空・風・火・水・地をシンボル化した宝珠・半円・三角・円・方を刻み込んでいます。隣りにあったのが「龍前院開基 山岡家」の墓處。「當山開基山岡家墓處初代景長は三河国浜松城に於いて家康に仕え天正十九年来地三百石を賜り高座郡懐嶋を知行す。」山岡家墓地には多くの墓石が並んでいた。幕末までの山岡家一族の墓がおかれ、現在もその末裔とは交誼があるのだと。「龍前院開基 山岡家について山岡家の出自は大伴氏であり、大納言伴善男を始祖とする。室町時代の永享年中に美作守景廣が栗太郡勢多邑一帯を支配し、山田岡に勢多城を築城し「田」の一字を省いて山岡と称した。龍前院開基山岡家は、近江国勢多城主・山岡美作守景の次男、長門守景民を祖とし、その甥には本能寺の変において、勢多唐橋の攻防で知られる山岡景隆がいる。景民の孫・景長は浜松城において徳川家康に仕え、天正十九年に中島之郷・懐嶋之郷を併せて三百石を知行し、中島に陣屋を構えた。後、鶴嶺八幡宮より僧坊をうけて、もとよりあった薬師堂とあわせて堂宇を再興し、龍前院開基となる。(景長院殿宝菴浄珍居士)また、六代・景信は龍前院中興開基となった。(當院中興開基要法院殿固峯永堅大居士)その子、七代・景忠は早世した弟の供養の為、元禄七年に梵鐘を改鋳し、現在では茅ヶ崎市内最古の梵鐘として、市重要文化財となっている。山岡家は代々大檀越として龍前院を護持してきた。当院は山岡家の葬地であり、慕末までの墓所が祀られており、その交誼は現在まで続いている。(十八代当主・智博氏) 平成ニ十七年 吉日 三十五世大鱗浩正記す懐嶋山龍前院開基山岡氏略系図 「寛政重修諸家譜」よりその隣りにあったのが「當寺開山歴住諸位」の墓。「當寺開山歴住諸位大和尚寶塔」。龍前院の歴代住職は次の通りであるとネットから。開山楞 山周厳-暁堂元(玄)龍-松谷宗雪-聖庵泉祝-来久天撮-寛嶺周廓-愚渓如頑-異中通同-福山智厳-柏峰伝茂-地天元泰-哲宗友賢-定谷恵龍-義雲大耕- 源本明-宝州恵鏡-大悲恵聖-棹岸蘆舟-臥龍万橋-泰雲秀山-天仙安長-円山大規-金華倶胝-大龍賢道-敞連賢弘-万応大潤-放牛困剴- 参要禅-愚渓天 禅-転回玲珠-大信活道-活明良運-天雄寛龍-瑞巌喜芳-大鱗浩正(現住)左手にあったのが歴代住職等の墓であろう。「墓地」から「本堂」を見る。そして「龍前院」を後にして、「鶴嶺八幡宮」の参道を戻る。途中の桜の花を楽しむ。ズームして。車に戻り、「鶴嶺八幡宮」の一の鳥居に向かって走る。参道脇に建つ石碑には、「弁慶塚」と刻まれていた。「弁慶塚」は参道から東に入った駐車場の奥の北側の、入口には案内板もなくやや判りにくい場所にあった。所在地:神奈川県茅ヶ崎市浜之郷843-1近づいて。「弁慶塚」碑。「弁慶塚の由来武蔵国稲毛(川崎市)の領主、稲毛三郎重成が亡妻の冥福を願い相模川に橋を架け、建久九年(1198)十二月二十八日その落成供養を行った。源頼朝は多数の家臣を引きつれてこの式に参列、盛大な落成式が行われた。頼朝はその帰途鶴嶺八幡宮附近にさしかかったとき、義経・行家ら一族の亡霊があらわれ、乗馬が棒立ちになり、頼朝は落馬して重傷を負い、翌正治元年(1199)一月死去した。後年里人たち相計り義経一族の霊を慰めるため、ここに弁慶塚を造ったと伝えている。」上記の説明によれば、この「弁慶塚」は、義経一行の霊を慰めるために里人が立てたということになのであろう。この理由は?。もしもここで頼朝が倒れて亡くなったとすれば、「頼朝供養の碑」等を立てて、供養してもよいはず。それが何故義経一行・弁慶なのか。何かよっぽど、怖ろしいことが、その日に起こったのであろうか。そして、頼朝が落馬した真の場所は何処なのであろうか?JR辻堂駅南口近くにも「頼朝公 落馬地」の案内板のみがあったが。 「弁慶塚」がここにある理由についてもっと知りたいのであるが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.04.09
閲覧総数 485
-
13

汐留・築地・明石地区を巡る(その7): 中央区立築地川公園~備前橋跡~堺橋跡~工学院大学学園発祥之地碑
「築地本願寺」を後にして、北門から出て南方向に向かう。左側にあったのが、「中央区立築地川公園」。中央区築地と中央区明石町にまたがる公園。入口にあった案内板。「備前橋跡橋の名称は、橋の辺に備前岡山藩邸があったことに由来しています。震災復興橋梁の一つ。築地川南支川に架かる橋で、小田原町(現・築地七丁目)から築地ニ、三丁目の間へ渡されていました。震災前は橋長14メートル、幅4メートルの木橋だったが、震災後に橋長33メートル、幅17メートルの鈑桁橋(ばんげたきょう)に改架されました。大正14年(1925) 5月に竣工しました。備前橋の上流部分の水路は昭和40年(1965) 1月に埋立てられ、平成元年(1989) 4月に区立築地川公園として開園。また、下流部分も昭和62年に埋立てられ、区営駐車場、駐輪場となりました。」中央区築地7丁目1。「昭和11年当時の橋の位置と現在地の関係」橋名板「備前橋」。実は橋には、入口と出口があるのはご存じでしょうか?下の写真のように橋の親柱にある橋名板(きょうめいばん)の橋の名称が漢字表記だと入口になります。そしてひらがな表記が出口となるのです。ちなみにどの橋にも橋名板がついていて、漢字表記の向こう側は必ずひらがな表記となっているのです。どちらも向って左側にあるはずです。それでは、なぜ橋には入口と出口が存在するのかというと、道路には『道の始まりの地点を「起点」、終わりの地点を「終点」とする決まりがあり、起点を入口、終点を出口としたのです。昔は「すべての道路の起点は東京の日本橋」とされていて、日本橋に近い方を起点(入口)、遠い方を終点(出口)としていたそうです。現在では各都道府県や政令都市によって、県庁側が起点だとかその逆だとか、重要都市側を起点にするとか、国道や県道・市町村道によっても取り扱いが変わっているようですが。「築地川公園」の奥に歩を進める。遊歩道の脇には小川が流れていた。更に奥に進みと右手前方にも「案内板」があった。「堺橋跡」案内板。中央区築地7丁目3−1。「堺橋跡堺橋または境橋。震災復興橋梁の一つ。築地川に架かる橋で、小田原町(現・築地七丁目)から明石町へ渡されていました。震災前は橋長5.5メートル、幅4メートルの木橋あったが、震災後に橋長25メートル、幅8メートルの鈑桁橋として改築され、昭和3年(1928) 7月に竣工しました。築地川(明石堀とも呼ばれた)は、堺橋の先で分流し、南への水路が築地川南支川となり、北へ曲がる本流は合(相) 引川とも呼ばれていました。この橋を境にして築地川の川筋が分かれていました。昭和46年(1971)、首都高速道蕗の建設のため、築地川の埋立てに伴い撤去されました。」「昭和11年当時の橋の位置と現在地の関係」橋名板「堺橋」。以前訪ねた「三吉橋」👈リンク に置かれていた築地川の橋づくしの案内板。文明開化期の地図をネットから。築地川は、掘割であったため流れがほとんどなかったと。河川より運河といったほうが近かったと。現在はーー濃い青が築地川本流のあった場所。ーー薄い青が築地川南支川のあった場所。ーー水色が築地川東支川のあった場所。現在は殆どが埋め立てられ、残っているのは、浜離宮恩賜庭園の北東側河口付近のわずか750mの部分だけ。本流の大部分は川底を首都高速道路、南支川(暗渠の上部利用)は築地川公園、駐車場、駐輪場に東支川(暗渠の上部利用)は築地川駐車場・駐輪場、公共施設等になっているのだ。「中央区立築地川公園」内にはカラフルな遊具が。もう1基の「さかいはし」親柱。橋の名前をひらがなで表記する場合は「○○橋」は「○○はし」と濁点をつけずに書くそうです。これは川の水が濁らないようにという意味が込められていて、いかにも日本人らしい!!しかし、これは慣習的なものであり、多くの例外もあるとのこと。「堺橋跡」の親柱の道路の反対側、「あかつき公園」入口に向かう。入口左にあったのが「工学院大学学園発祥之地」碑。中央区築地7丁目2。「工学院大学学園発祥之地」。「工学院大学学園発祥之地明治二十一年我国工業の黎明期に当り、此地に「工手学校」👈リンクが創設された。爾来工業界の各分野に有能な技術者を送った数は実に三萬を超えその発展に多大の貢献を致した事は周知である。関東大震災の後昭和三年出身者の熱意と努力により新宿に宏壮な校舎が建設され校名も工学院と改められ、時世の進運に則して終始発展充実を続けて来た。更に昭和二十四年に至り学園に工学院大学が設立され最高の工業教育機関として工業報国の伝統精神を発揚しつゝある。近く創立七十周年を迎えんとし先輩の遺徳を偲び後進の発奮を促すため有志相図り学園発祥の地に記念碑を建てる。工学院大学校友会題字 工学博士 桂 弁三 書碑文 工学博士 野口尚一 撰学園歌一 見よ 清浄の淀橋に 校舎は高くそびえたり 実力の旗ひるがえし 我等が健児意気高し 誠実努力撓みなく 進めいそしめ国のため二 見よ先輩の螢雪は 工業日本を築きたり 築地の風に鍛えたる 師兄の意気を受継ぎて 誠実努力撓みなく 進めいそしめ国のため」「あかつき公園」に沿った道を東に進む。「THE TERRACE TSUKIJI」は賃貸オフィスであるようだ。「あかつき公園 冒険広場」。「あかつき公園」は遊具のある公園と冒険広場があり、子供たちにはとてもワクワクするスポット!?。公園にはローラーすべり台やブランコ、砂場など一通りの遊具が揃っていて、飽きずに遊べそう。冒険広場にはたくさんのタイヤや大きな土管、ターザンロープなどがあり、かくれんぼや鬼ごっこなど、体を動かしてさまざまな遊び方ができそうであったがこの時は子供の姿はなく。中央区築地7丁目19−1。そして交差点の先にあった「中央区立 あかつき公園(保健所側)」案内板。中央区築地7丁目19。平成元年作成のレリーフが並んでいた。明石小学校の児童の作品とのこと。さらに隅田川に向かって交差点を渡る。ここは昔「明石橋」があった場所。東京名勝図会 鉄砲洲明石ばし/歌川広重(3代目)(1868年)右手にあったのが「月島の渡し跡」案内板。中央区築地7丁目18−2。「月島の渡し跡所在地 中央区築地7丁目18番地域 明石町14番「月島の渡し」は、月島一号地の埋め立てが完成して間もない明治二十五年(一八九二)十一月、土木請負業の鈴木由三郎が、南飯田町(現、明石町十四)から月島(現、月島三丁目)へ、手漕ぎの船で私設の有料渡船をはじめたことにはじまるといいます(『月島発展史』)。明治三十四年(一九〇一)、月島への交通の重要性を考慮した東京市が市営化を決め、翌三十五年、汽船曳船二隻で交互運転を開始し、渡賃も無料となりました。月島は東京の臨海工業地帯として発展し、明治四十四年には、乗客の増加に対応するために徹夜渡船が開始されました。その後、昭和十五年(一九四〇)には勝鬨橋が架橋され、渡船の利用者は減少の一途をたどり、月島の渡しは廃止されることとなりました。平成十三年三月 中央区教育委員会」『東京市十五区番地界入地図』東京市京橋区全図 明治40年(1907)発行。当時の地図をネットから。①鉄砲洲橋②新湊橋(しんみなとばし)③明石橋(あかしばし)④明石堀⑤新栄橋(南明橋)⑥堺橋⑦暁橋現在の地図と埋め立てられた場所。公営住宅の角にあった「電信創業之地」碑。中央区明石町13−10。「電信創業之地東京傳信局跡明治二年十二月廿五日開始紀元二千六百年逓信省」「電信創業記念碑の由来明治2年9月19日(太陽暦10月23日)横浜裁判所と東京築地運上所に設けられた「傳信機役所」を結ぶ約32キロメートルの電信線架設工事が開始され、同12月25日に業務を開始した。これが、我が国における公衆電気通信の最初である。この記念碑は、先駆者の業務を後世に伝えるため、昭和15年に建立されたもので、昭和53年、南南東約40メートルの地点から当地へ移設されたものである。」その先にあったのが「東京税関発祥の地碑(運上所跡)江戸幕府は、慶応三年(1867年)に、江戸築地鉄砲洲明石町の一帯を外国人居留地と定め、この地に税関業務等を行う運上所を設置しました。これが、東京税関の始まりです。」。中央区明石町13−10。さらに隅田川に向かって進むと、カーブの場所にあったのが「水たき つきじ 治作」。中央区明石町14−19。「幕末、文明開化の中心地として華やいだ中央区明石町。その一角にひと際目を引く大邸宅。1899年建造の三菱財閥の旧別邸を買い取り1931年に創業した「つきじ治作」は約1000坪の古きよき伝統美をが息づく園内と、俗世を遮断したかのような静寂で贅沢な空間。多彩なコース料理をお愉しみください。 なかでも、名物「水たき」は九州出身の創業者がもたらした逸品と長年愛されております」と。数寄屋造り・木造二階建ての瀟洒な料亭。大きな滝のある和風中庭があるようだ。創業時から変わらない緑に囲まれた門構え と。「つきじ治作名物 水たき」セット。何方か、連れてって!!その先に奇妙な絵画を発見。工事現場の防音壁の「だまし絵」。ネットで調べて見ると「フォトリックアート」👈リンク と呼ぶらしい。東京都中央区の「マンホール蓋」。 区の花「ツツジ」と区の木「ヤナギ」がデザインされていた。「灯」と書かれているので、街路灯の制御を行うためのハンドホールの蓋であろうか。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.09.08
閲覧総数 275
-
14
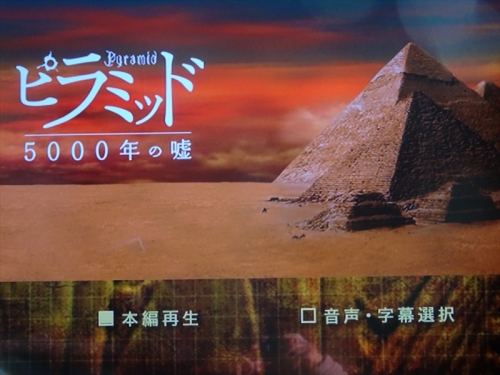
『ピラミッド 5000年の嘘』(その1)
久しぶりに地元のTSUTAYAでフランス人監督パトリス・プーヤル監督、エジプト・キザの大ピラミッドの謎に迫ったドキュメンタリー映画・『ピラミッド 5000年の嘘』を借りてきた。この映画は1999年にパトリス・プーヤル監督がジャック・グリモーの37年間に及ぶピラミッドの調査と研究を6年間に渡り、徹底的に検証した作品との事。2007年に映画を撮影開始して、ようやく2012年に日本で劇場公開となった作品。紀元前2700年から2500年代に建造されたエジプトの遺跡「ギザのピラミッド」をあらゆる面から検証し、ピラミッドの常識を覆す真実を明かす歴史ドキュメンタリー。エジプトを専門とする考古学者のみならず建築や人類学、物理学などさまざまなジャンルの学者や研究者が新説を証言。墓というだけではなく地理学・天文学の観点から重要な役割を果たしていた事実がかなり論理的に解明され、技術屋の私にとってはピラミッドの不思議に驚かされたのであった。『ピラミッド5000年の嘘』の作品の中で、エジプト考古学者たちが唱える説に物を申したこの作品、監督のメッセージは「自分達で考えて欲しい」ということを映画を通じて訴えているのです。(以下の写真は原則として、テレビ画面を撮影したものです) 『REVELATION』とは「暴露された事物」・「意外な新事実」 このドキュメンタリーでは、冒頭に数々の疑問・課題が提示されています。 NO1.ピラミッドの底は、大きな岩の塊が残されている。 そして周囲6000ヘクタールを覆う礎石の重さは一つだけでも 乗用車1台の重さ。この重大な事実を指摘した学説はほとんどない。 NO2.800Km遠方から運んだ玄室用の130個の花崗岩は一つあたりで最大70トン。 これを積み上げる作業は現在でも困難であろう。 NO3.大ピラミッドには不釣り合いなほど小さな玄室が3つしか存在しない。 長さ90m、幅90cmの通路が地下の間まで下降する精度は驚異的だ。NO4.形も大きさもバラバラな乗用車並みの重さのある石を総重量620万トン 200万個も積み上げる精度は今日でも通用するだろう。 一番上の玄室は、完璧な水平と垂直を維持している。 一見するとバラバラのように構成されているに見えるが、法則性があって 積み上げられている。法則性がきちんとされているからこそ、高い耐震性がある ピラミッドになっており、何回かの巨大地震にも完全に耐えたと。 NO5.ピラミッドが示す北は誤差が100分の5度未満。 現代に匹敵する精度。 NO6.20世紀に入って、春分・秋分の時期に四面がさらに中心線から2つに分かれて 見えることが観測されている。わずかに内部に屈折した八面体となっている。 (しかし、何故最近の写真でないのか不思議) NO7.建設期間は通説では20年だが、その工事期間で200万個以上の石を 積み上げるのは可能か。 もし定説どおりに、クフ王のピラミッドが20年で建設できたというのであれば、 20年未満の統治だったクフ王の墓という説そのものも、崩れれてしまうのではないか。 1日12時間、無休で200万個の石を積んだとしても、1個あたりの作業時間はわずか2分半。NO8.まだ車輪や鋼鉄が存在しない時代に銅製のノミや石、麻縄といった道具だけで 唯一現存する世界の七不思議は築かれたことになる。 たったこれだけで。 ドキュメンタリーではこの『クフ王のピラミッド』のとっても不思議な謎をテーマにして話が進みます。それに対して、これを否定する考古学者も頻繁に登場。更に映像はギザを中心に赤道を30度(何故30度かは言及なし)傾けた幅100kmほどの一直線上の帯上にイースター島やマチュピチュ、西安の古墳など世界遺産を含めた巨大な遺跡が存在していると。主な遺跡群は、ペルーのナスカの地上絵、オリャンタイタンボ、マチュピチュ、サクサイワマン、アルジェリアのタッシリ・ナジェールの岩絵、エジプトのギザの大ピラミッド、ヨルダンのペトラ遺跡、パキスタンのモヘンジョ・ダロ遺跡、インドのカジュラホ、タイのスコータイ、カンボジアのアンコールワット、西安、そして、最後にイースター島のモアイ像が並ぶと。 メキシコの古代都市テオティワカンも。ピラミッドの頂上にはキャップストーンと呼ばれる四角垂のブロックがあったと考えられており、キャップストーンが発掘されたものもあると。ミニピラミッドとも呼べるピラミッドの縮小モデルだったと。大ピラミッドと同じく底辺と高さの関係でもπを導き出せるのだと。その寸法は底辺1.57m 、高さ1m。底辺1mの2倍でも3.14=π(パイ)の値が導き出せると。しかし、古代エジプトでは、未だメートル法は存在せず、単位として1キュービットという単位を使っていたと考えられていると。その長さは1キュービット=0.5236mであったと。しかし高さは1mとなっておりメートル法を既に理解していたのかとも。クフ王の大ピラミッドには円周率や黄金率や光の伝搬速度を示す数値が内包されているのだと。よって大ピラミッドの設計は綿密な計算に基づいていたのだと。クフ王の大ピラミッドは、頂上部は欠け、現在の高さが138.74mになっているが、本来の高さはh=146.59m。そして底辺は一辺が230.36m(各辺の平均値の誤差11cm)。高さを2で割ると王の間の頂点に一致すると。高さを3で割ると、王の間の天井の位置の高さになると。高さを4で割ると、王妃の間の頂点の位置となると。高さを5で割ると、地下室の床と一致。高さを7で割ると、王妃の間の底面と一致すると。 ----------つづく---------
2017.03.12
閲覧総数 2167
-
15

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その28): シティマリーナヴェラシス(旧川間ドック)~陸軍桟橋~船番所跡~浦賀の渡し~愛宕丸
「千代ヶ崎砲台跡」の見学を終え、徒歩にて急な坂を下り、「川間隧道」先の交差点に向かって進む。前方に浦賀湾の入口にあるマリーナ・鴨居大室港方向を見る。「特別養護老人ホーム 太陽の家 二番館」の入口が左手に。そして「川間隧道」先のT字路交差点に到着し、ここを浦賀駅方面に向かってこの日も右折する。「シティマリーナヴェラシス(旧川間ドック)」を見下ろす。その先、左手にあったのが「住宅型有料老人ホームハビタスカーマ」。遊歩道には巨大なヤシの並木があった。これも「カナリーヤシ」であろうか?アフリカ西海岸、カナリア諸島原産なのでこの名がある。宮崎県の公式ページによると、病害虫に強く長寿なことから、不死鳥(フェニックス)の名前が付けられたとされるとウィキペディアより。幹径40cm以上になっていた。幹には葉痕が波状の模様になって残っているのであった。5m近く弓状にしなる長い葉を見上げて。旧浦賀ドックをズームして。豪華なプレジャーボートが並んでいた。路面に映り込む不死鳥(フェニックス)の葉の影も美しかった。「特別養護老人ホーム 太陽の家 二番館」の建物を振り返って。「Velasis 浦賀 2番館」。SRC造、地上14階建て、総戸数112戸、2001年5月築の高層マンション。横須賀市西浦賀4丁目11−2前庭にあった錨のモニュメント。さらに不死鳥(フェニックス)の並木の遊歩道を進む。そして「船番所跡」前に到着。浦賀湾の先には、この後に訪ねた「東叶神社」の姿が確認できた。「陸軍桟橋」には多くの釣人の姿が。「船番所跡浦賀奉行所の出先機関で、享保六年から明治5年(1872)まで、江戸へ出入りするすべての船の乗組員と積荷の検査をする「船改め」を行い、江戸の経済を動かすほどと言われた。与力、同心の監督のもと「三方(さんぽう)問屋」と呼ばれる下田と東西浦賀の廻船問屋百軒余が昼夜を通して実務を担当しました。「入り鉄砲出女」を取り締まる海の関所としても重要なものでした。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」」「船番所の模型(浦賀郷土資料館)」。左手の道路沿いにあったのが「よこすか浦賀病院」。旧住友重機械健康保険組合 浦賀病院。1897年(明治30年)に設立された「浦賀船渠」の浦賀工場診療所として大正元年8月1日開設 。昭和19年6月1日 浦賀造船所病院と改称、昭和30年4月4日 浦賀船渠(うらがせんきょ)病院として開設。この日も多くの砂・砂利運搬船が停泊していた。手前に砂、砂利運搬船「三十一勝丸 上天草」。石材・砂運搬船「第十八新幸丸 兵庫県姫路」。石灰石他運搬船「第十八住吉丸 壱岐」。砂・砂利運搬船「第十五大福丸 徳島県徳島市」。砂・砂利運搬船「第二十五郎丸 熊本県 宇城市」。そして「西渡船場(浦賀の渡し)」の待合室に到着。「東渡船場」に停泊中の「愛宕丸」が動き出した。「乗船料」案内板。「【乗船料】料金は船内でお支払いください。・大人 400円(横須賀市民200円)・小・中学生 200円(横須賀市民100円)・未就学者 大人1名につき1名まで無料・ワンデイパス大人 600円・ワンデイパス小・中学生 300円・自転車および大きな荷物 50円渡船場渡船の歴史は古く、享保18年(1733)の「東浦賀明細帳」 には、渡船を修復する際、周辺の村も東西浦賀村と応分の協力をすることとあり、操業が確認されています。当時の船頭の生活は、東西浦賀村の一軒あたり米六合で支えられていました。平成10年8月に就航した現在の「愛宕丸」は御座船風のデザインとなっています。この航路は「浦賀海道」と名付けられ、横須賀市道2073号となっており、東西浦賀を結ぶ渡船は、シンボルの一つです。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀深訪くらぶ」「ご乗船の方はこのボタンを押して下さい ➡️ ●」そして1名の客を乗せた「愛宕丸」がこちらに向かって来た。船頭の半被には「うらがの渡し」の文字が。この日はこどもの日で日の丸の旗2本が。そしてFRP製浮き桟橋の「西渡船場」に到着。浮き桟橋(西とせんじょう)の平・断面図。そして年配の御夫婦と自転車の若者そして私の4名が乗船して、船は渡船場を離れた。私は片道分の400円を船頭に手渡す。チケット等はなし。往復利用する方は、往復分を乗船時に払い、復路用のカードをもらうシステム。自転車は50円を支払っていた。浦賀湾入口方向、そして房総半島を見る。年配の御夫婦。先程見た砂・砂利運搬船を海から見る。房総半島・富山、鋸山の姿が見えた。左手、浦賀ドックの右側には巨大テントが。大型テントで全国を巡業する本格サーカス・エンターテイメント「ポップサーカス」を誘致し、4月27日(土曜日)から6月23日(日曜日)までの期間、浦賀ドックにて「横須賀公演」が開催されているのであった。そして観音崎通り沿いに建つ住友重機械工業㈱浦賀造船所の旧工場の姿をズームして。その先に建つのが「ライオンズヒルズ横須賀浦賀」。巨大テントと浦賀造船所を見る。そして3分で「東渡船場」に到着し下船。徒歩30分を渡し船で3分で。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.05.26
閲覧総数 172
-
16

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-3
六会日大前駅(旧六会駅)東口 <1983年頃>東口ロータリーは駐輪場となっていた。左の写真からズームして。ロータリー中央は駐輪場に。自転車が所狭しと駐まっていた。★六会地区 歴史年表-8年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代文化 4年 1807 亀井野村、雲昌寺の梵鐘鋳造される この頃、間宮林蔵 樺太を探検 👈️ 5年 1808 下土棚村、善然寺三一世弁誉上人の 教えを受けた一八人の筆子により 筆子塚が建立される 7年 1810 下土棚村、渋谷ヶ原に庚申塔建立される 8年 1811 西俣野村、旗本柳生氏の知行地が旗本 金田欽之助・小笠原若狭守信義両氏の 知行地となる文政 5年 1822 伊能忠敬 「第日本沿海実測地図」完成👈️ 6年 1823 ドイツ人医師シーボルト 長崎出島に着任👈️ 7年 1824 西俣野村、地誌調査が行われ 「地誌御調改書上帳」が作成される 「御調改書上帳 (相模風土記の元となる) (おしらべあらためかき 西俣野村 戸数 六〇戸 人口 三九〇名 あげちょう)」 8年 1825 下土棚村、氏子七一名が白山神社に 梵鐘を奉納する 10年 1827 下土棚村、小菅新兵衛ほか六名により 青面金剛像庚申塔を建立される 11年 1828 下土棚村、渋谷根講中白山神社に石灯篭 一対を寄進する 13年 1830 西俣野村、御嶽神社の鳥居を建立する 天保 3年 1832 下土棚村、渋谷ヶ原に広田仁右衛門ほか 安藤広重 三名により庚申塔建立される。 「東海道五十三次」完成👈️ 円行村、収穫高の調査が行われる 天保の大飢饉起こる👈️ 境川の川浚・堰・水車等の件につき争論発生 「藤沢の堰をつくったことにより西村(西富) と西俣野村が苦情」 7年 1836 下土棚村、法然上人六五〇回忌の記念事業 として善然寺の山門完成、山門の扁額の 文字は大本山増上寺冠挙大僧正の筆★六会地区 歴史年表-9年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代天保 11年 1840 浄土宗法王院十王堂(閻魔堂)の火災発生 アヘン戦争(1839~1842)👈️ 12年 1841 天保の改革始まる👈️ 13年 1842 「新編相模国風土記稿」 全巻完成👈️ 14年 1843 亀井野・石川・大庭の各村が酒、売めし、 駄菓子商の許可を関東取締役へ願い出る弘化 4年 1847 石川村天満宮の梵鐘が鋳造される 「助郷村」とは 亀井野村質地争論発生 江戸時代、宿場常備の人馬 境川堤防を守るため一人の浪士が人柱 が不足する場合、幕府・ として投身自殺 諸藩によって人馬の供を命じ 金沢橋の袂に地蔵菩薩石像が建立され られた郷村 その後、御所谷に移築される(土堤番様) 嘉永 3年 1850 亀井野村・石川村等二七ケ村が代助郷村 「石(こく)」とは、米の量 に定められる に用いる 一石は約180リットル。 亀井神社の経塚一字一石の碑文建立 6年 1853 西俣野村、神礼寺(小御嶽神社)の梵鐘 ペリー浦賀に来航👈️ 鋳造される安政 元年 1854 日米和親条約締結調印 👈️ 2年 1855 安政の大地震発生、円行村被害甚大の ため年貢金高一〇〇石につき三両割と なる 3年 1856 二宮尊徳没す(70才) 6年 1859 安政の大獄👈️万延 元年 1860 桜田門外の変👈️慶応 3年 1867 明治天皇即位、 王政復古の宣言👈️★六会地区 歴史年表-10年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料明治時代明治 元年 1868 神仏分離の礼、廃仏毀釈が起こった 江戸城無血開城👈️ 3年 1870 平民に苗字を許可 4年 1871 藤沢宿に郵便取扱所が開設 5年 1872 下土棚村、渋谷ヶ原に渋谷講中一同 横浜~品川鉄道開通 👈️ により道祖神が造立される 新戸籍法の施行、学制の公布、電報の 取扱開始、戸長制施行(名主制の廃止) 富岡製糸場開場👈️ 6年 1873 管内区画改正により石川村・亀井野村・ 西俣野村を第一八区一〇番組に 今田村・円行村・下土棚村・長後村・ 七ッ木村が第一九区一番組となる 地租の改正、徴兵令公布 石川村、石川学校設置 下土棚村、白山神社社殿改築 7年 1874 佐賀の乱👈️ 東京銀座に初めてガス灯 がつく👈️ 8年 1875 西俣野村、西俣野学校設置 亀井野村、亀井野学校設置 9年 1876 下土棚村、下土棚学校設置 10年 1877 西南戦争発生 出征一名 モース、大森貝塚発見 江の島に臨海実験所設営 👈️ 11年 1878 郡区町村編成法により、亀井野村・ 日本で初めて電灯がついた 石川村・西俣野村・今田村・円行村・ パリ万国博覧会開催👈️ 下土棚村は六ヶ村組合設立 13年 1880 藤沢の日常品の相場 米一石 八円一銭二分 乾鰮一〇シメ 二円三銭一分 農具の値段 鍬一丁 二円 鎌一丁 二〇銭 碓一個 一円 箕一個 一〇銭 銅簸一個 三円五〇銭 肥桶一荷 一円 稲マキ一丁 一円七〇銭 万能鍬一丁 五〇銭 15年 1882 下土棚村、田中典惣右衛門、日本酒の醸造 開始(造り酒屋) 17年 1884 下土棚村、長田万吉傘製造開始、多数の 徒弟を養成 藤沢地区、職人の賃銭日当 大工左官 三六銭 石屋 三二銭 瓦屋根職 三五銭 畳刺 二五銭 板屋根職 三〇銭 経師 五三銭 19年 1886 下土棚村、小菅常次郎自転車を購入して乗り 始める(当地区最初) 円行出身小菅丹治、伊勢丹呉服店創業 20年 1887 御嶽神社の本殿再建 下土棚・円行・石川・今田・亀井野・西俣野 ・長後・高倉地区養蚕が盛んになる 21年 1888 石川村、入内嶋製糸場設立 22年 1889 市制町村制開始 下土棚村・円行村・石川村・今田村・ 亀井野村・西俣野の六ヶ村は合併して 六会村となる 初代六会村村長に亀井野村の杉山信尹就任 23年 1890 石川学校・亀井野学校・西俣野学校・ 第1回帝国議会開会👈️ 下土棚学校・亀井野学校円行分校を 廃止し高等六会小学校創立 高座郡警察署、石川駐在所が六会村石川に 設置される 24年 1891 高等六会小学校初代校長に、 江の島桟橋完成👈️ 清水熊太郎就任 25年 1892 高等六会小学校を尋常高等六会小学校と改称 高座郡警察署、六会亀井野に仮屯所設置 尋常高等六会小学校、亀井野不動上に校舎を 新築し移転 下土棚、長田豊次郎染物業開始 滝山街道(現在の旧藤沢・町田線)県道に 指定される 26年 1893 高座郡警察署を藤沢警察署と改称 第二代六会村村長に杉山信尹(亀井野)留任 27年 1894 日清戦争開戦👈️ 北里柴三郎ペスト菌発見👈️ 28年 1895 久間製糸場が六会村亀井野に、 中田製糸場が六会村石川に設立される 29年 1896 第三代六会村村長に伊沢弥助(石川)就任 第四代六会村村長に斉藤太兵衛(亀井野)就任 下土棚、渡辺七五郎こんにやく製造開始 30年 1897 五代六会村村長に杉山信尹(亀井野)就任 下土棚の広田太吉、県下で最初に 稚蚕共同飼育組合を設け収繭高めた 六会人口 三八九八名★六会地区 歴史年表-11年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料明治時代 31年 1898 六会村石川に西山製糸場設立 葉タバコ専売実施👈️ 32年 1900 六会村農会設立、会長に広田兵蔵就任 六会村下土棚、川井嘉七が豆腐製造 販売開始 35年 1902 第六代六会村村長に伊沢安良(石川) 八甲田山遭難事故発生👈️ 就任 日英同盟調印 👈️ 36年 1903 藤沢税務署開設 国定教科書制確立 👈️ 37年 1904 六会村地先境川治水工事の実地調査 日露戦争始まる👈️ 六会村今田郵便箱設置了承 六会村人口調査結果 出生 三〇名 死亡 二〇名 婚姻 一〇名 離婚 七名 死産 七名 日露戦争 五人出征(内三名戦死) 38年 1905 六会村の徴兵適齢者調査の結果 三五名 六会村役場、大字亀井野字不動上 六会小学校内へ変更の件村会で決定 39年 1906 七代六会村村長に加藤九右衛門(亀井野)就任 日米海底電信開始👈️ 六会村下土棚に六会村立実業補習学校の 分教場設置 41年 1908 六会村龜井野に六会村立実業補習学校の 分教場設置 42年 1909 藤沢町、六会村・俣野村・耕地整理組合結成 境川の流域の地整理事業に着手 (大正二年竣工) 43年 1910 第八代六会村村長に加藤九右衛門(亀井野) 逗子開成中学生 再選 七里ヶ浜沖で遭難👈️ 六会村下土棚、青年同志会創立 六会村西俣野、青年団創立 六会村西俣野に六会村立実業補習学校の 分教場設置 45年 1911 明治天皇御大葬👈️ 乃木大将夫妻殉死👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.12
閲覧総数 499
-
17

旧東海道を歩く(原~富士)その5:富士市・左富士神社~富士市吉原・陽徳寺
『旧東海道を歩く』ブログ 目次そして『左富士神社』に到着。旧東海道駿河路は概ね海沿いを通っており、富士市鈴川本町から元吉原宿があって更には原宿から沼津宿にかけての街道は、海浜砂丘を防波堤代わりに利用した後背地の海抜2~3m辺にほぼ直線的に作られている。ところが街道は、元吉原を過ぎると山側へ大きく弧を描くように湾曲しながら吉原宿に達し、その先にある間宿・本市場で再び富士川へ向かってほぼ直線路に復するのだ。何故街道が大きく湾曲したのか?初期の東海道を調べてみると、街道は元吉原を過ぎた辺りで吉原湊があった旧富士川河口を迂回したのち、本市場方向へ直線的に道筋がついていたようだ。にも拘らず、その後いかなる理由で今日残るような海沿いを避ける道筋に変更されたのか。それは江戸期に起きた2度の津波が原因だと指摘されている。東海道が整備された初期の吉原宿は、現在の田子の浦港に近い海岸沿いにあった。今でも地名として元吉原が使われているが、寛永16年(1639年)に津波により壊滅し、和田川を遡った依田原辺りに宿場(中吉原)を移したのだと。『左富士神社』と書かれた扁額。溶岩岩にのる狛犬。社殿。和田川の東岸、南北に通じる東海道に東面して鎮座し、ふるくから依田橋の氏神として祀られてきた社。約150m北方の名勝・左富士にちなんで左富士神社と号するが、明治41年までは悪王子神社と称し、社叢は「悪王子の森」と呼ばれていたと。延宝8年高潮に関する宝暦5年銘の記念石碑・『義隄記』碑。『義隄記』。左富士神社境内に設ける「依田橋村一里塚」碑と一里塚のモニュメント。吉原宿の2度の移転に伴い一里塚も移され、延宝8年(1680年)中吉原から新吉原へ宿場が移ったときに、ここ左富士神社の北側に新たな一里塚が築かれた。「依田橋村の一里塚慶長七年(1602)、徳川家康は東海道(五街道)に一里毎に塚を築き榎や松を植え、旅人の憩の場所としました。『田子の古道』によると、元吉原宿時代には、田嶋村付近(現港湾付近)に一里山を築いたとあります。その後、寛永十六年(1639)、元吉原宿(現鈴川)から中吉原宿(現荒田嶋付近)に移転、その時、一里塚は『日本分国絵図』によると、津田村西側付近に描かれています。延宝八年(1680)、水害により中吉原宿は新吉原宿(現吉原商店街)に移りました。その時、一里塚は依田橋村の左富士神社の北側に描かれています(東海道分間絵図)。江戸から三十四番目の一里塚です。また、依田橋村の一里塚について、『駿河新風土記』は、『左右一つズツあり、駿河より右の方の塚は、潮除堤の上に、左の方の塚は依田橋田の内にあり、壱畝歩ばかり』とあります。現在、民有地になっているため、左富士神社の境内に、一里塚跡の石碑を建立しました。吉原宿と共に、この一里塚は三度所替えした事になります。」東海道分間延絵図 文化3年(1806)の依田橋村。境内には様々な写真が展示されていた。四季折々の姿が。富士山頂をズームで。境内にあった道祖神。『左富士神社』を後にし北に進むとあったこの石碑は?旧東海道の交差点からの富士山はまだ正面に。『東海道 名勝 左富士』「東海道を東から西に行くとき、富士山は右手に美しい姿を見せますが、この辺りは松並木の間から左手に見えることから”左富士”と呼ばれて、街道の名勝となりました。この現象は、江戸時代に、災害を逃れるため吉原宿が二度の移転をしたことに由来します。東から西に真っ直ぐ延びていた東海道が急に北方へまわり込み、道筋が一時的に北東を向くとこの辺りで、左手に富士山を望む形となります。江戸時代の著名な浮世絵師・歌川広重が描いた『東海道五十三次内吉原』は左富士の名画として大変よく知られます。今日、周辺には工場、住宅が立ち並び、かっての風情はありませんが、わずかに残る一本の老松は往時の左富士をしのばせてくれます。」『名勝 左富士右方に見える黒い山は愛广山である。左に富士山を眺めながら馬に乗った旅人が行く。前方の馬は背の両脇に荷物を入れたつづらを付け(37.5kgずつ)、その上にふとんを敷いて旅人を乗せている。この方法はのりじりといい賃銭がかかった。手前は馬の鞍の左右にこたつのやぐらのようなきくみを取り付け、それに三人の旅人が乗っている。これを「三宝荒神」といっていた。」絵にも描かれていた松の木も。静岡ではお馴染みの夢舞台東海道道標・吉原宿 左富士。『名勝 東海道左富士』と書かれた道標が。そして漸く『左富士』が姿を現す地点に。『安藤広重 東海道五拾三次 吉原 左富士』この辺りから描いた作品であろう。 【https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/hiroshige53tsugi.html】より富士依田橋郵便局脇の『馬頭観音菩薩』の石碑。その隣りにあった祠。前方に見えて来たのが『平家越え橋』。橋の入口には『平家越え』と。『平家越の碑』「平家越治承四年(1180)十月二十日、富士川を挟んで、源氏の軍勢と平家の軍勢が対峙しました。その夜半、源氏の軍勢が動くと、近くの沼で眠っていた水鳥が一斉に飛び立ちました。その羽音に驚いた平家軍は、源氏の夜襲と思い込み、戦いを交えずして西に逃げ去りました。源平の雌雄を決めるこの富士川の合戦が行われたのは、この辺りといわれ、『平家越』と呼ばれています。対岸は平家軍」絵の右上角には「駿州富治川ニ於源氏勢揃ス水鳥数多立チ平軍羽音ニ驚ク」とある。『平家越』の石碑。和田川の上流部。和田川と富士山。富士山頂の上空には傘雲が姿を現す。『依田原山神社』表参道の鳥居は昭和11年奉献され扁額には「山神社」と。『手水舎』。『拝殿』。旧東海道の南側に、大山祇命をまつる山神社が鎮座。この界隈は吉原宿の「東木戸」があったところで、これより以西が東海道の宿駅・吉原宿だった。山神社は火災で古記録を失い、創祀は判然としないが、社伝によると古くから依田原の氏神として祀られてきたという。中吉原宿を所替えに追い込んだ延宝8年(1680)の高潮をはじめ、万延元年(1860)大火、明治16年暴風、昭和49年台風26号など災害で大きな被害を受けたが、そのつど再建されたのだと。拝殿正面。神社裏の道路の角にあった『依田原山神社』の灯籠。前方に岳南電車岳南線の踏切が現れた。岳南線(がくなんせん)は、静岡県富士市内のJR吉原駅にある吉原駅と岳南江尾駅とを結ぶ岳南電車の鉄道路線である。『東海道 吉原宿 東入口 岳南商店街』案内板。踏切手前を左に入り、『青陽山 陽徳寺』を訪ねた。右手に鐘楼が。多くの地蔵様が。眼病・無病息災などで信仰を集めており本尊の地蔵菩薩が「身代わり地蔵尊」として近郷近在に知られ、地元では「身代わり地蔵さん」と親しく呼ばれているのだと。『身代わり地蔵さん』と。俗称「身代わり地蔵尊」については、次のように伝えられていると。そのむかし現在の吉原一丁目付近は寺町と呼ばれその界隈で眼病が大流行したことがありました。町の人々は困り果て、このお地蔵さんに願掛けをしたところ、病状はたちどころに快方へむかい、その代わり地蔵の目は目ヤニでいっぱいになっていたのだと。『本堂』。毎年7月23,24日にはこのお地蔵さんの縁日が盛大に行われ多くの人が訪れます。本尊のほか、閻魔王や奪衣婆、地獄・極楽を描いた大絵曼荼羅が開帳され、本堂では新盆の方のご供養が行われると。『鐘楼』。『積善供養塔』。一般的に、「積善」は善行を積むことをいい、「供養」は仏などに供物をささげること。『南無阿弥陀佛』と刻まれた石も。 ・・・つづく・・・
2019.04.21
閲覧総数 1222
-
18

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓
【寒川町の寺社旧蹟を巡る】 目次そして次に訪ねたのが「梶原景時館跡(一之宮天満宮)」。一宮という地名は、相模国一之宮寒川神社が鎮座していることによる。神奈川県道44号線線(伊勢原藤沢線)沿いの南側にあった。神奈川県高座郡寒川町一之宮8丁目6−6。この碑には「従是一之宮明神道」と。ここが寒川神社表参道の起点?かと思ったが、文政9年(1826)に土地改良で現在地に移されたものだと。「梶原景時館跡 👈リンク梶原景時は治承四年(1180)八月、源頼朝挙兵の時、石橋山の合戦で洞窟に逃れた頼朝の一命を救いました。翌年正月、頼朝の信任厚い家臣となり、鎌倉幕府の土台を築くのに貢献しました。一宮を所領としており、この地に館を構えたとされています。図に示すとおり館の規模は広大だったとの説もあり、現在も当時の堀のなごりを留めていると伝えられています。天満宮の位置はその一角で、当時は物見の場所として一段と高く構築したとも伝えられています。景時は和歌もたしなみ文武両道で秀でた武将でした。頼朝の死後、多くの家臣からそねまれ、ついに正治元年(1199)十一月、鎌倉を追放され、一族郎党を率いて一宮館に引き揚げました。その後、景時は再起を期し、上洛するため、翌正治二年正月二十日午前二時頃ひそかに館を出発しました。一行は清見関(静岡市清水区)で北条方の軍の攻撃を受け、景時以下討死という悲劇的な最期を遂げました。館の留守居役の家臣も翌年尾張(愛知県)に移ったと伝えられ、また物見のあとの高地には里人が梶原氏の風雅をたたえ、天満宮を創設したともいわれています。」「一宮館跡案内図」。「浩宮徳仁親王殿下 御成記念 昭和五十四年九月二十一日」碑。学習院大学在学中の1979(昭和54)年9月11日、当時の「浩宮さま」はご学友40人らとともに寒川神社と梶原景時館跡(一之宮)を訪れた。この研修旅行では、中世の文献「吾妻鏡」のゼミをお受けになられた宮様とご学友が4泊5日の日程で史跡を見学され、その最初の見学地が寒川町だったと。「梶原景時館跡」碑。「梶原景時」と書かれた幟が横に。「梶原景時」は、1180年(治承4年)の石橋山の戦いで平家方でありながら源頼朝の命を救ったと伝えられ、頼朝の鎌倉体制を固めるための中心人物として活躍した。ここ相模国一宮(現在の寒川町)を所領とし、「梶原景時館址」の石碑が建てられている場所は、物見のあった所といわれている。2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも、頼朝を支えた「13人」の御家人のひとりとして登場中なのである。小さな太皷橋を渡る。参道の石灯籠。「記念樹 梶の木梶原公顕彰会 建立」。右手にあったのが「角落とし」。角落し石板が並んでいた。「角落とし両側の堰柱(せきばしら)の溝に、角材や板を落と入れ、水流の調整をしたり、堰き止めなどする装置。西側の産業道路沿いにあった相模川防水堤に設けられ増水時には板を落とし、土嚢(どのう)などで補強して洪水から西町を守った。」左手に手水舎。この四角い場所は?祭事を行う場所か?正月のお焚き上げ、どんど焼き等の場なのであろうか?後日、下記の如き書き込みを頂きました。『子供のための砂場ですペットの糞尿防止のために囲いがしてあります野良猫には効果はほとんどないかと』「天満宮遺蹟碑」。この石碑には「海軍中将正四位勲二等男爵肝付兼行篆額偉哉菅神文勲赫照萬代矣此地當在聖祠創建由緒共未詳也傅曰梶原景時之勤請焉続稱西之天満宮祠宇朽廢明治四十二年合祠子一之宮八幡宮也因爲存此舊蹟有志相議而營梅林記念之以大正四年一月二十五日建碑傅後見昆云爾國幤中社寒川神社禰宜提箸亀男撰尋常一之宮小学校校長中島忠蔵書」と刻まれていた。「天満宮」の祠は、和歌をたしなむなど教養のあった景時の風雅を称え、里人が当時の館の物見台跡に創建したものといわれる。「天満宮」の祠の隣は小さな公園になっていて、ブランコと滑り台が。「天満宮」を正面から。木名「ヒトツバタゴ」と。別名は「ナンジャモンジャノキ」。「ヒトツバタゴ(一つ葉タゴ、一つ葉田子)」とはモクセイ科ヒトツバタゴ属の一種。同じモクセイ科のトネリコ(別名「タゴ」)に似ており、トネリコが複葉であるのに対し、本種は小葉を持たない単葉であることから「一つ葉タゴ」の和名がある。奥にも小さな社が鎮座していた。「天満宮」を横から。再び「鎌倉本体の武士 梶原景時 ゆかりの地」と書かれた幟。青地に白抜きの幟も。「梶原景時館跡」から県道44号線(旧大山街道:伊勢原藤沢線)を東へ進むと直ぐ右側にあったのが「西町集會所(薬師堂)」神奈川県高座郡寒川町一之宮8丁目6-31。広場(駐車場?)の横には大きなパネルが。正面から。「梶原景時と一宮館址」案内板。「梶原平三景時(生年不明~1200)は「鎌倉本體の武士」といわれ、源頼朝を補佐し鎌倉幕府の基礎を築いた文武ともに優れた武士です。梶原氏は、桓武平氏の流れをくむ鎌倉党の一族とされ、同族には大庭氏、俣野氏、長尾氏らがいました。治承四年(1180)伊豆に流されていた源頼朝が挙兵しましたが、八月二十四日、石橋山(小田原市)の合戦で大敗して椙山に逃れ、「鵐(しとど)の岩屋」(湯河原町・真鶴町の両説あり)に潜んでいました。大庭景親率いる平家方の一員として参陣していた梶原景時は、頼朝を発見したものの討たずに救いました。これが景時と頼朝の出会いでした。翌年一月景時は、関東を平定し鎌倉に入った頼朝に土肥実平の仲介により面謁し、「言語を巧みにする」と高く評価され、家臣として認知されました。以来、源平合戦で多くの功績をあげたほか、頼朝の片腕として侍所所司をはじめさまざまな重職に携わりました。頼朝の死後、正治元年(1199)十月、結城朝光謀反の疑いを将軍頼家に讒言したとの理由で御家人六六名の連署をもって弾劾され、弁明の機も得られぬまま一宮に下向。再度鎌倉に戻るものの、十二月鎌倉追放が正式に決まり、鎌倉の館は取り壊されました。正治二年一月二十日、景時とその一族は、朝廷や西国武士団の支援を軸に再起を図ろうと、一宮館をあとに京都へ向け出立します。その途中、駿河国狐ケ崎(静岡市清水区)で在地の武士吉川小次郎らに迎え討たれ、交戦の末、梶原山にて最期を遂げました。幕府内の主導権を手中にしたい北条氏と、頼朝の側近として職務に忠実すぎた景時を快く思わなかった御家人たちとの思惑が一致したことが背景にあったと言われています。」「梶原景時公像」。2022年放送の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に、源頼朝を支えた「13人」の御家人のひとりとして登場する「梶原景時」。「梶原景時」を演じているのは「中村獅童」さん。「梶原氏の足跡治承四年(一一八〇) 石橋山の合戦で敗退した頼朝を助ける。治承五年(一一八一) 上肥実平の仲介により頼朝に面謁。家臣として認知される。 小御所御厩の地の奉行寿永一年(一一八二) 政子安産祈願奉幣使として二男景高が相模国一宮(寒川神社)に遣わされる寿永三年(一一八四) 宇治川の合戦。長男景季「名馬麿墨」にて佐々木高綱と先人を争う 一ノ谷の合戦。平重衡を生け捕りにする 播磨国大山寺に大般若経典読料として田一町二段を寄進元暦一年(一一八四) 播磨国の守護に任ぜられる元暦一年(一一八五) 屋島の合戦。義経の奇襲により景時、合戦に遅参 壇ノ浦の合戦。義経と先を争う文治五年(一一八九) 衣川で討たれた義経の首実検を腰越で行う 奥州制圧軍勢着至奉行。一族あげて従軍、途中和歌を多く残す 新造の御厩別当建久一年(一一九〇) 頼朝上洛の奉行。景時、景季、景高供奉して入京建久三年(一一九二) 頼朝征夷大将軍に就任。鎌倉幕府開府建久四年(一一九三) 富士の巻狩。一族あげて頼朝に供奉する建久六年(一一九五) 頼朝上洛の随兵奉行建久十年(一一九五) 頼朝死す。 将軍頼家「吉書始」に十三宿老の一員として列席、侍所別当と傍注あり。正治一年(一一九九) 景時公弾劾の署名を六六人の御家人が提出、一宮館に下向。正治二年(一二〇〇) 一宮館を後に京を目指す。途中、駿河国狐ヶ崎(静岡市清水区)にて合戦、 一族滅亡」。「一宮館址案内図」。梶原景時館址[ー之宮天満宮] (昭和3年.寒川名所絵はがき)。「(伝)七士の墓(昭和30年頃.臼井彦太郎氏撮影)」。「集会所となっている薬師堂」。扁額「西町集會所 薬師堂」。集会所の入り口横に地蔵尊。「水無月大祓式 並 茅の輪神事」ポスター。「濱降祭駐輿記」碑。「相模國一宮國幣中社寒川神社濱降祭有里古例爾依里七月十五日神輿茅ヶ崎南湖濱爾渡御在良世良留此乃日近郷近在十数社乃神輿供奉志縣下唯一乃盛儀奈里還幸乃途次一ノ宮當所爾御休憩御發輿爾當里清淨乃地爾栽培世志麥莖爾火乎點自神輿爾投牙掛久留故事有里當地乃舊家川崎家爾氏代々奉仕世里茲爾其乃所以乎刻志永久後世爾傳閉牟登須留爾當里需爾依里記須事斯久乃如志」と。1933年に建立された石碑。石碑がある場所は、寒川神社の神輿(みこし)が浜から戻る際に小休止する御旅所。御旅所を出発する際、地域の人々が麦の茎を燃やして神輿に投げ掛ける習わしがあったと、石碑には刻まれていた。この習わしには、海の塩で清めた神輿をさらに火で清める意味があったとされると。裏面は逆光で・・・。「濱降祭駐輿記」碑の近くにあった「梶原伝七士の墓」案内板。奥に入っていくと「梶原伝七士の墓」が姿を現した。「梶原伝七士の墓」。「梶原源太景季公」。「箙(えびら)の梅」で知られる景時の長男・景季(かげすえ)が描かれている。一の谷(生田の森)の戦いで、勢いあまって敵陣深く入り込み、矢が尽きてしまった景季は、箙(えびら)(矢をいれる籠)に梅の枝を挿して奮戦した。その姿に、「吹く風を何いとひけむ梅の花 散りくるときそ香はまさりける」という和歌(凡河内躬恒『古今和歌集』)を重ね合わせた平家の公達は、雅を解する坂東武者を称賛したと。「梶原源太景季(かげすえ)は景時の長男で、勇猛果敢歌道にも秀でた弓取である。寿永三年(1184)正月、宇治川の合戦で佐々木高綱との先陣争いで愛馬「麿墨」共に武名をあげる。同年2月、生田の森・一ノ谷の合戦では、折しも咲き誇る梅が枝を箙に挿しかかれば花は散りけれど匂いは袖にぞ残るらんと戦陣を馳せる景季公の風雅を平家物語など諸本が伝え、今日でも能や歌舞伎で「箙の梅」が演じられている。八月、一之宮八幡大神例祭の宵宮の屋台巡行に加わる「西町」の屋台は館址にふさわしく、梶原氏に因む彫刻で飾られ、碑の景季公は一部を模写したものである。」「伝 梶原氏一族郎党(七士)の墓」中央の墓をズームして。「伝 梶原氏一族郎党(七士)の墓この石造物群には次のような言い伝えがあります。正治二年(1200)正月、梶原景時一族郎党が一宮館を出発、上洛の途中清見関(静岡市清水区)で討死してしまったので、一宮館の留守居役であった家族、家臣らが弔ったといいます。また、景時親子が討死してから、しばらく景時の奥方を守って信州に隠れていた家臣七人が、世情が変わったのを見て鎌倉に梶原氏の復権、所領安堵を願い出たが許されず、七士はその場で自害し、それを祀ったものという説もあります。なお、後ろの水路は当時の内堀の名残ともいわれています。」すなわち、2つの説とは1.他の御家人から追放された景時は、一族とともに一之宮の館を出発し、上洛の途中に討死して しまいます。そこで一之宮館の留守番を務めていた家族、家臣がこの地に弔ったものという説。2.景時父子が討死してからしばらく後のこと。景時の奥方を守って信州に隠れていた家臣7人が、 世情が変わったのを見て鎌倉に梶原氏の復権、所領安堵(領有権を認めること)を願い出た。 しかし許されず、七士はその場で自害しこの地に弔ったという説。後ろの水路は当時の内堀の名残ともいわれている。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.07.25
閲覧総数 520
-
19

中之島緑道の彫刻
大阪・中之島の淀屋橋から肥後橋までの土佐堀川沿いの間に、大阪市制100周年記念事業の一つとして、彫刻設置を主テーマに整備された約400mの素晴らしい遊歩道があるのです。「中之島緑道」と名付けられ、10体の彫刻が配置されています。先日の早朝散歩でこれらの彫刻作品を楽しんで来ましたので紹介します。まずは「陽だまりに遊ぶ」母子ののんびりした様子が、心を和まさせてくれます。土佐堀川を眺めているのでしょうか。母の子に対する愛情があふれ出た作品でした。「風標」朝の光をそっと反射するステンレスの材料を丹念に積み上げた作品。やわらかなそしてさわやかな風を感じることが出来たのでした。「くもの椅子」腰掛けて、土佐堀川の川面を見ることも出来ます。この「くも」というのは、「蜘蛛」ではなく、空の「雲」。雲がゆっくりと椅子に腰掛けている情景を描いたという感じなのです。「一対の座」石の材質でで、座布団のような柔らかさと温もりを表しています。文字通り座布団が二つ並べられているような作品。「椅子」の次は「座布団」?。土佐堀川の水面と同時に座布団の中で揺れている水も感じられる作品なのです。「十魚架」「十字架」の「字」を「魚」に変えて作品名にしたものです。確かに十文字を形成しているのは魚のように見えます。罪を背負った魚が十字架にかけられた姿を描いたものなのでしょうか。チョット不気味。「広場-鳩のいる風景」中腰になって2羽の鳩に話しかけているのは少女なのでしょうか?ここでは、なごやかな時間が流れていたのです。「日溜(ひだまり)」母が我が子を抱いて真昼の公園にのんびりする様を表現したのでしょうか。「TWO RING~空間の軌跡~」曲線が美しい作品です。堤防に架かる手摺りの直線との対比まで狙った作品なのでしょうか「花の天女」私と同じ?メタボな体でひまわりの花?をしっかり抱き締めている。 「肥後橋にたどり着いて「中之島緑道」の彫刻探索は終り。その他にも「そよかぜ」中之島に架かる橋はどれも由緒ある漢字の名前がつけられていますが、このオブジェのある「ガーデンブリッジ」のみが、戦後できたカタカナの橋。「緑の賛歌」 中之島公園 みおつくしプロムナード 下の土佐堀川沿いにはひときわ目立つ彫像が立っていました。 約8メートルの台座に立つ4メートル以上の高さの裸婦像2体。大同生命本社ビル四ツ橋筋側の植栽の中にある巨大なブロンズ彫刻は、アントワーヌ・ブールデルの作品。中之島緑道の早朝散歩で、歴史ある建築物、各種の花々、そして彫刻作品を大いに楽しんだ「アラカンオジサン」なのです。
2010.07.08
閲覧総数 1563
-
20
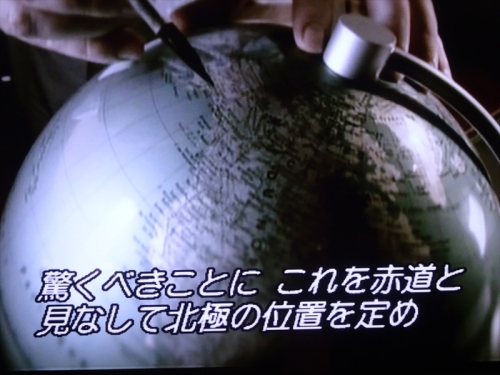
『ピラミッド 5000年の嘘』(その3)
驚くべき事に、この遺跡の帯を地球の赤道であると見なし、北極の位置を定めると・・・。ギザとナスカを結ぶと大ピラミッドの黄金比に一致すると。ギザ~ナスカ、ギザ~テオティワカンは等距離。アンコールワット~ナスカとモヘンジョ・ダロ~イースター島は等距離。イースター島~ギザまでの距離は黄金数の10000倍。ピラミッドの大きさが地球の大きさと深い関わりがあると。2底辺の和=460mは赤道上の1秒間の移動距離にほぼ等しいと。新幹線(しんかんせん)の最高速度はだいたい時速()280km=77m/sですから、地球()はその6倍以上)のスピードでまわっていることになるのです。クフ王のピラミッドの高さが地球と太陽の一番近い距離の1/10億になります。大ピラミッドの高さを10億倍すると、地球から太陽までの距離の1億4700万キロになると。同じくピラミッドの高さを43200倍すると地球の半径になると。そして、ピラミッドの総重量の100兆倍が地球の重量と同じと。 更にピラミッドの内接円と外接円を描く。 ピラミッド底辺の外接円から内接円を引くと、その差が299.79613mとなり、光の速度とほぼ同じような数字が導かれるのだと。 単位は全く桁違いですが、光速は299792458 m/s。確かに数字は良く似ていますが、ここまで来ると流石に????と。 しかしピラミッドから浮かび上がる数字は『神の業』と。 パイオニア探査機の金属板 (Pioneer plaque) 。この金属板は1972年と1973年に打ち上げられた宇宙探査機パイオニア10号・11号に取り付けられた銘板で、人類からのメッセージを絵で記したものである。 ここに刻まれているのは、人間の性別や、探査機と比較した体格、太陽系における地球の位置。複雑な情報を記号化した幾何学的な図形である。探査機が打ち上げられる数千年前、大ピラミッドの建設者たちは、同様に幾何学図形を残した。ただし、相手は宇宙の生命体ではなく、未来の人類だったのだ。つまり我々だと。ピラミッドが正確に東西南北を示していることから天体観測施設説という意見も有力。 ピラミッドの4角は4つの星座を表す。おうし座、獅子座、さそり座、みずがめ座。鷲はさそり座を、天使はみずがめ座を示す表現は、大聖堂にも見受けられると。獅子座とみずがめ座を結ぶのは、“獅子と天使の軸”。ギザに置かれたそのシンボルが、人面獣身のスフィンクスである。スフィンクスが建設されたのは、大ピラミッドより後とされ、関連はないと見られてきた。全体の位置関係を改めて検証している。大ピラミッドの側面を5倍に拡大して当てはめると、3角形の1辺がスフィンクスの頭を貫通すると。ピラミッド底面の正方形を横に並べ、右辺を垂直に下ろすと、またもやスフィンクスの頭にぶつかると。 2つのピラミッドの頂点の軸が交わる点を中心に描いた円も、スフィンクスの頭を貫通すると、これでもかと。 地球上における時北極の位置は、一定していない。1年間に40キロ近く動いていると。近年、その移動速度が速まりつつあることがわかり、状況が非常に懸念されていると。 長さ4万キロ、赤道から30度傾いた円周は、歳差運動と磁極の動きを知らせているのか?磁極の逆転は、過去に100回ほど記録として発生していると。磁極の逆転が起こった場合、地磁気は最大で数週間失われかねない。地殻が大変動を起こす恐れもある。大気とともに宇宙からの放射線を遮る地磁気が消えれば、地球は焼かれてしまうに違いない。 恐ろしい結論に至ったが、私たちはこれから、地球の動きを注意深く見守っていく必要がある。危険を回避する手だてがあるからこそ、建造者たちは古代から警告を発したのに違いないと。 ギザのクフ王のピラミッドは完成時の高さ146m、底辺230m。1つ数トンもの巨石を驚くべき精密さで積み上げたギザの大ピラミッド。現代の技術でも建造が難しいとされるこの巨大な建造物は、建設期間わずか20年で作られたという。車輪もない時代に本当にそれが可能だったのか。そもそも本当にそれは王の墓なのか。考古学から一度離れ、建築学や物理学、さらに地質学や数学、天文学などの専門家に意見を仰ぎ、ピラミッドの常識を検証し直していくドキュメンタリー映画なのであった。そんなピラミッドの謎について事実を基に新たな仮説を組み立てたのが、このドキュメンタリー映画だが、かなり衝撃的な仮説が展開されているのも事実。ピラミッドを作るために必要な計算法、円周率という考えやメートル法、黄金数という数学的知識が記録として存在していなかった時代にどう割り出していたのかという謎にも直面しているのであった。そして、ギザのピラミッドから数千キロも離れたイースター島やマチュピチュ等で同様の精巧に作られた遺跡があるという事実も発見。お互い交流がなかったはずなのに、遠く離れた場所で同様の技術が使われ、存在していたと。 そして新たな感動は、地球上に存在するそれら遺跡の場所が、法則(円周率や黄金数を基に)を伴って上手く配置されていたということ。例えば、イースター島からエジプトのギザを直線で結ぶと、その間に他の遺跡が直線上に収まるように存在していたり、またスフィンクスやピラミッドは、それ自体が宇宙の天文学を計るための大きな時計の役割になっているという結論にまで至っているのであった。 やや、無理と感じる仮説もあったが、全体的には技術屋としても十分理解出来る論理展開なのであった。そして、映画の結論は、5000年以前にはギザを中心とする高度な文明が栄えていたが、隕石の衝突や、気候の変動で文明が崩壊し、ピラミッドなどのような遺跡を残して、失った文明を後世の人々へ伝えるへメッセージだ!!と、締めくくっています。この結論に頷くことは出来ませんが、それもありなんとも・・・・・・。 不思議なことにピラミッドには設計図が存在しないのだと。たくさんの石碑や壁画は残っているにもかかわらず、設計図がないことには違和感を覚えざるを得ないが、いずれこの設計図が発見され、今回の仮説が実証される日が遠くない日に来ることを祈るのみであるが、私が生きているうちには??。 ----------完--------
2017.03.14
閲覧総数 2110
-
21

「はるばる来たぜGoto函館」(その42): 函館アイヌ協会~カール・レイモン 歴史展示館~真宗大谷派 東本願寺 函館別院~旧相馬家住宅~旧函館区公会堂~函館聖マリア教会~咬菜園跡~己巳役海軍戦死碑
「函館ハリストス正教会」を後にして、下って来た「大三坂」を振り返る。右側にあったのが「日本の道百選 大三坂道」碑。右に折れると直ぐ左にあったのが「函館アイヌ協会」。北海道アイヌ協会の函館支部で、この組織は、北方領土出身者、北千島、中部千島、釧路、根室、十勝、網走のアイヌ民族の結束を固めることが目的であるとのこと。その隣りにあったのは、「カール・レイモン 歴史展示館」。ドイツのマイスターで、本格派ハム・ソーセージを作り続けたカール・レイモン氏の生涯を紹介する展示館。レイモンハウス元町店2階では、波瀾万丈な人生を送った、カール・レイモンの人生を多数のパネルで紹介している。また、展示品やカール・レイモン語録なども取り揃えており、カール・レイモンのルーツを知る事が出来る。なお、ここレイモンハウス元町店1階では各商品を購入出来るのであった。「カール・レイモン」像。「カール・レイモン旧住宅「カール・レイモン旧住宅この建物は昭和5年(1930)に、当時函館で貿易業を営んでいた、サハリン出身のロシア人シュウェツさんが作居として建てました。その後、昭和12年(1937)ドイツのハム・ソーセージ作りに情熱を傾けたカール・レイモンが購入し、居宅として使っていました。木造2階建てで、市の伝統的建造物に指定されています。」「カール・レイモン旧住宅建てられたのは昭和5年( 1930年)。木造2階建てで、市の伝統的建造物に指定されていますドイツのハム・ソーセージ作りに情熱を傾けたカール・レイモンが居宅として使っていました。レイモンがここに移り住んだのは昭和12年(1937年)のことです。」そして更に進んで行くと右手にあったのが、「真宗大谷派 東本願寺 函館別院」。明治40年の大火で類焼、1915(大正4)年建替えに際して日本初の鉄筋コンクリート造りとした。ニ十間坂沿いに威風堂々と建つ。国指定重要文化財。東本願寺函館別院とも呼ばれる。重厚な山門が迎えてくれた。「本堂」日射しを受けて黒光りする瓦屋根の建物が威風堂々とそびえていた。 1915(大正4)年の建て替え時に、鉄筋コンクリート造りとなり、現存する鉄筋コンクリート造りの寺院としては日本最古であると。函館別院の起こりは、1668(寛文8)年、松前専念寺6世浄玄が、阿弥陀堂を創設したことにはじまる。 1710(宝永7)年に、現在の弥生小学校付近に移り、当時は僧の名前にちなんで浄玄寺と呼ばれていました。1806(文化3)年、1829(文政12)年の2度の大火に見舞われ、1879(明治12)年の大火で建物を焼失し、現在地に移転。「東本願寺函館別院」とも呼ばれる。銀杏の黄葉はこれから。「本堂」の内陣。ズームして。「二十間坂」側の脇門。「二十間坂」側の門の外から。「二十間坂」を見る。元町の駐車場に車を駐め、再び散策を再開する。左手の奥に「船魂神社」の鳥居が見えた。この角の民家の黒の板塀の前にあったのが「日和坂(ひよりざか)」案内板。坂の上から港の景色を一望でき、空模様をよく判断できるということからこの名が付いた。また、坂の上にある船魂神社辺りからはトビの飛ぶ姿がよく見えたことから、坂の上の方を「トビ坂」と呼んだ。日和もトビも共に天気に関係がある。右手に「日和坂」を見る。修学旅行生の男女グループの姿も。更に進むと右手に黒板塀の大きな邸宅が。「旧相馬家住宅」1908(明治41)年、基坂上に豪商相馬哲平の私邸として建築。延床面積680平方メートルの名建築で、2018年に国の重要文化財に指定。函館市伝統的建造物。令和3年4月から開館するとの案内板があった。旧相馬家は、1908(明治41)年築の邸宅。この豪邸を建てた相馬哲平は、1861(文久元)年に新潟に生まれ、後に箱館(函館)に渡って米穀商で財を築き、旧函館区公会堂の建設費5万8千円のうち、私財を投じて5万円を負担するなど、函館の発展に貢献しました。2010(平成22)年6月に一般公開が開始され、2018(平成30)年に国の重要文化財に指定。函館市伝統的建造物。場所は元町地区の、旧函館区公会堂、旧イギリス領事館近くにあった。老松の手入れも行き届いた大邸宅。蔵を改築した「元町ギャラリー」は歴史回廊・歴史的美術館として活用され、アイヌ絵巻や江差屏風などの展示物も見学できるとのことであったが残念ながら閉館中であった。「ようこそ『国指定重要文化財 旧相馬家住宅へ』~北海道屈指の豪商 相馬哲平の館~」徳川時代末期(1861)、28歳の時、徒手空拳で箱館に渡り、一代で北海道屈指の豪商に上りつめた相馬哲平の私邸。伝統的スタイルの邸内は当時の豪商の生活ぶりを見ることができます。隣接の土蔵(重要文化財)ギャラリーはわが国先住民族"アイヌ"の風俗を描いた美術資料を豊富に展示しています。旧相馬家住宅に興味を持っていただきありがとうございます。英語、台湾語、中国語、韓国語での案内も。左手に坂を上って行き右手の折れるとあったのが「元町公園」碑。「元町公園」の上の左手にあったのが「函館市重要文化財 旧函館区公会堂」。函館港を見下ろす高台に建つ「旧函館区公会堂」は、ブルーグレーとイエローの美しい建物。館内は貴賓室や130坪の大広間など、当時の華やかな雰囲気をそのままに残しているのだと。しかしながら、耐震補強を含めた大規模な保存修理工事が実施されていたのであった。工事用の保護シートには「旧函館区公会堂」の姿が。「旧函館公会堂明治40年(1907年) 8月の大火で、函館区の約半数、12,000戸余りが焼失した。この大火で区民の集会所であった町会所も失ったため「公会堂建設協議会」が組織され、建設資金として区民の寄付を募ったが、大火後のため思うように集まらなかった。当時、函館の豪商、初代相馬哲平氏は自分の店舗などの多くを焼失したにもかかわらす5万円の大金を寄付したため、これをもとに明治43年(1910年)現在の公会堂が完成した。この建物は北海道の代表的な明治洋風建築物で、左右対称形になっており、2階にはバルコニーを配しているほか、屋根窓を置き、玄関、左右入口のポーチの円柱に柱頭飾りがあるなど、特徴的な様式を表わしている。昭和49年(1974年) 5月、国の重要文化財に指定され、同55年(1980年)から約3年を費やして修復、平成30年(2018年) 10月からは耐震補強を含めた保存修理工事を実施。」正面入口は工事用シートで完全に覆われてしまっていた。工事前の姿。 【https://gipsypapa.exblog.jp/15031484/】より「重要文化財旧函館区公会堂の保存修理について」工事工程表。2012年春にはリニューアルオープンの予定であると。「旧函館区公会堂」前から函館の町並みを見る。湾の先に「五稜郭タワー」が見えた。「元町公園」の先の坂を見る。現住所:函館市元町12。更に進むと「東坂」。ここを下っていくと、初日に訪ねた「新島襄 海外渡航の地碑」がある。次の坂は「弥生坂」。左折して「弥生坂」を上って行くと「箱館戦争ゆかりの地」案内板が。「函館聖マリア教会」が右手に。ステンドグラスを教会内から見たかったが・・・。教会内から見るとこんな美しい世界があったのだが・・・。 【https://www.baroque-web.com/works/works_0034.html】より右手に教会へのエントランスが。左手にあったのが「咬菜園(こうさいえん)跡」。「咬菜園跡安政4(1857)年名主で慈善家として知られた堺屋新三郎が、箱館奉行から1140余坪(約3,770㎡)の土地の払い下げを受けてここに庵を作り、各地の名花、名木を移植したので四季折々の美しい花が咲き乱れ、当時の住民は箱館第一の名園として親みました。咬菜とは粗食のことで、五稜郭設計監督の蘭学者、武田斐三郎が名付親です。明治2(1869)年箱館戦争時、追討令が下り、新政府軍艦が品川を出港したとの報に接した榎本軍(旧幕府脱走軍)総裁榎本武揚は同年3月14日幹部6人と共に、今宵最後と一夜の清遊をこの咬菜園で試みました。箱館奉行並中鳥三郎助は、俳人としても知られ、数多くの秀作がありますが、「ほととぎす われも血を吐く思い哉」「われもまた 死土で呼ばれん 白牡丹」の辞世の句などはこの時残したものです。同年5月16日、三郎助は五稜郭の前線基地千代ケ岡陣屋(現中島町)で最後まで降伏を拒み、長男恒太郎(22歳)次男英次郎(19歳)ともども壮烈な戦死を遂げました。」「みなみ北海道最後の武士達の物語」ポスター・「箱館奉行並砲兵頭並 中鳥三郎助」。「土方歳三 1835~18691863 (文久3 )年、幕府兵募集に参加し近藤勇と新選組を結成し、副長を務めた。戊戦争時には第羽・伏見の戦い、東北戦争で各地を転戦し、仙台で旧幕府軍に合して蝦夷地へり、函館戦争へ従軍した。蝦夷地上陸後、函館進攻、松前・江差方面の攻略を指揮し、蝦夷地平定後は蝦夷島政権の陸軍奉行並、函館市中取締裁判局頭取に就任した。函館市中警備の新選組を指揮する一方で、俳号「豊玉」として句会にも参加するなど、文人としての側面も持ち合わせていた。宮古湾奇襲作戦や大野ニ股の戦闘に奮戦したが、5月11日の新政府軍函館総攻撃時に戦死した。」「永井玄蕃 1816~1891名は尚志。幕府の目付、長崎海軍伝習所総監理、外国奉行、軍艦奉行、京都町奉行、大目付を歴任し、旗本では最高位の若年寄に就任した。戊辰戦争勃発により、榎本武揚らとともに蝦夷地へ渡り、箱館戦争に参戦した。蝦夷島政権では箱館奉行となり、箱館の本陣(旧箱館奉行所庁舎)、運上所において、統治および諸外国領事等との交渉にあたった。明治2年5月11日の新政府軍箱館総攻撃時に、弁天台場で陣頭指揮をとって奮戦したが、新政府の勧告を受け入れて降伏した。投獄されたが特赦で出獄した後.明治政府に出仕した。開拓使御用係、左院小議官、元老院大書記官を歴任した。」「榎本武揚 1836~1908通称は釜次郎、号は梁川。蝦夷御用地掛堀利煕の小姓として蝦夷地・樺太を巡検。長崎海軍伝習所に学び、築地軍艦操練所教授に就任した。1862 (文久2 )年、オランダ留学に派遣され、帰国後、海軍副総裁に任命された。1868(慶応4 )年8月に旧幕府海軍を率いて蝦夷地へ渡り蝦夷島政権の総裁に選出された。政権樹立後は、函館本陣において政権運営にあたる一方、咬菜園に出入りして書を認めるなど、文人としての才能も豊かであった。新政府軍との戦闘に敗れ、明治2年5月18日に五稜郭で降伏し、東京で投獄されたが、出獄の後は、開拓使へ出仕し、海軍中将としてロシア特命全権公使を務め、通信、農商務、文部、外務の各大臣を歴任した。」「孤山堂無外 1819~1893常陸国生まれ、「雪耕」と号し連歌や俳諧を嗜んだ。俳友に函館や江差関係者がいたことから俳諧普及のため蝦夷地へ渡り、「孤山堂」を継いだ。1868(明治元)年の函館戦争開戦時に、俳友の中島三郎助と出逢い、七面山に庵を構えて、近所の咬菜園で定期的に句会を開催し、中島や土方歳三ら旧幕府軍の幹部参加したとされる。明治2年4月に中島三郎助が千代が岡陣屋へ転出後は、陣屋に出向いて三郎助を激励し、三郎助戦死の後に、「武士の魂か一声郭公」の句を詠んだとされる。箱館戦争後は、開拓使函館支所、函館裁判所、函館公園看守を歴任し、函館八幡宮の神主を務めた。」「旧幕府軍武士達の清遊諸術調書教授役の武田斐三郎が命名した「咬菜園」は、基坂上に箱館奉行所が有った頃から役人達が楽しんだ名園と伝えられる。函館戦争時は旧函館奉行所庁舎に旧幕府軍の本陣が置かれ、箱館奉行永井玄蕃、同並中島三郎助らが諸外国との交渉や函館の治安を司っていて、多くの旧幕府軍の武士達が咬菜園を訪れる機会は多かったとされる。中でも「木鶏」の俳号を持つ中島三郎助は、咬菜園の貯金にある七面山に庵を構えていた俳人の孤山堂無外と邂逅し、咬菜園での句会に参加していたとされる。明治元年12月15日に蝦夷島政権が誕生し、翌年3月までは戦闘がなく平穏な日々であり、函館市中取締役でもあった土方歳三も句会に参加するなど咬菜園は旧幕府軍の武士達にとって格好の清遊の場となった。同年3月14日、旧幕府軍の幹部が咬菜園に集い、新政府軍艦隊への奇襲作戦成就に向けて壮行会が行われた。この後、旧幕府軍は臨戦態勢に入り、咬菜園での清遊は終わりを告げた。函館は新政府軍に制圧され、数日後には旧幕府軍は降伏して箱館戦争は終結。咬菜園に集まった旧幕府軍の武士達は獄につながれ、あるいは戦死を遂げ、再度、この場に戻ることはなかった。」「中島三郎助 1821~1869浦賀奉行与力として、1853(嘉永6)年のアメリカ・ペリー艦隊来航時に、アメリカとの応接を務めた。長崎伝習所へ人所し、後に築地軍艦操練所教授方出役を務めた。戊辰戦争勃発後に、榎本武揚らと蝦夷地に渡り箱館戦争に従軍した。蝦夷島政権では函館奉行並として、函館本陣で諸外国との交渉にあたった。1869(明治2)年4月1日に砲兵頭並の武官へ転出し、千代ヶ岡陣屋の守備隊長に就いたが5月16日の新政府軍の攻撃により、千代ヶ岡陣屋で息子らとともに戦死した。中島三郎助は俳号「木鶏」の俳人としても知られ、函館で俳人孤山堂無外と出逢い、咬菜園での句会には三郎助も参加していたようである。」咬菜園の庭。咬菜園の庭。更に進んで、右に折れて林の中に向かって歩いていくと右手にあったのが「己巳役海軍戦死碑」。函館市船見町6-8 弥生坂上の林の中。「己巳役海軍戦死碑」「己巳役海軍戦死碑ここは、明治2年の函館戦争で戦死した新政府海軍慰霊の墓所である。同年4月、討伐体制を整えた新政府軍は、旧幕府脱走軍に攻撃を開始、5月11日函館湾海戦で新政府軍の軍艦「朝陽」は、旧幕府脱走軍軍艦「蟠龍」の砲撃を受けて沈没した。この石碑には、朝陽艦副艦長夏秋又之助以下73名の新政府海軍の戦死者名が刻まれている。建立年月は刻まれていないが、明治2年に建立されたものと思われる。碑の石は、「高田屋の亀石」と呼ばれていた石の一部である。高田屋嘉兵衛全盛のころ、現宝来町に築かれた「高田屋御殿」と呼ばれた豪邸の庭園に据えられていたものである。嘉兵衛が、貧民救済の目的をかねて住吉浜の海中にあった2畳敷ほどの巨石を多数の人を動員して引揚げさせたところ、亀に似ていたので亀石と呼ばれた。函館護国神社(青柳町)にある「階陸軍戦死人名」碑と「招魂場」碑も同じ亀石を割って作られたものであり、いずれも箱館戦争新政府軍戦没者を祀った記念碑である。」「みなみ北海道最後の武士達の物語」ポスター・「松岡磐吉」。「函館港の海戦 軍艦蟠龍が新政府軍艦朝陽を撃沈1869 (明治2)年6月20日(旧5月11日)、午前3時から新政府軍の函館総攻撃が開始された。函館港においても新政府軍艦甲鉄、春日の2艦は弁天台場を攻撃し、朝陽、丁卯の2艦は七重浜の陸軍を援護攻撃して港内へ進出した。これに対して函館港内に旧幕府軍軍艦蟠龍、回天から砲撃、弁天台場および亀田の浜一本木台場からも発泡し応戦となった。港内に乗り入れた朝陽と丁卯に対して蟠龍が交戦し、朝陽と蟠龍が約1200mの至近距離となった午前7時35分、蟠龍の砲撃が朝陽の右舷を貫き、火薬庫にて破裂し、朝陽の後部は破壊されて前部も次第に沈没した。この交戦で、朝陽艦長中牟田倉之助以下62名は英国軍艦や漁船に救助されて有川へ上陸したが副館長夏秋又之助ら54名が戦死した。朝陽を爆沈させた蟠龍は、甲鉄と春日に追撃された後に弾薬が尽き、機関に故障を起こして座礁し、艦長松岡磐吉以下乗務員は弁天台場へ上陸した。また、浮き砲台となった旧府車繿回天も自ら火を放って艦を焼いて、海軍奉行荒井郁之助以下の乗組員は一本木から上陸、五稜郭へ退却し、旧幕府海軍は全滅となった。午後4時、甲鉄と春日は戦闘を中止し七重浜に碇泊して函館港の海戦は終結した。」「松岡磐吉(ばんきち) 不詳~1871生年は不詳。長崎海軍伝習所で航海術を学び、卒業後幕府に仕え、1860(万延元)年の咸臨丸渡米時に測量方を勤めた。1868(明治元)年に軍艦頭並となり、旧幕府海軍艦蟠龍の艦長として箱館戦争に参戦した。翌年6月20日(旧5月11日)の新政府軍函館総攻撃時に函館港海戦で蟠龍を指揮して砲弾を放ち、新政府軍艦朝陽を撃沈させた。しかしながら、蟠龍も操船不能になり、松岡らは弁天台場に上陸した後に、弁天台場で降伏した。東京に護送された後、1871(明治4)年に病死した。」「中牟田倉之助1837(天保8)年、金丸孫七郎の次男として生まれ、中牟田家の養子となる。佐賀藩主鍋島直正の推薦で1856 (安政3)年に長崎海重伝習所へ入所し、幕臣榎本釜次郎らと同窓となる。伝習所卒業後は三重津海軍所で佐賀藩海軍方助役を務めた。1868 (慶応4 )年の戊辰戦争で奥州方面へ出陣し、北越戦争に参戦。1869(明治2 )年に新政府軍艦朝陽の艦長に任命され蝦夷地での函館戦争に参戦した。そして6月20日(旧5月11日)の新政府軍函館総攻撃時に、旧幕府軍艦蟠龍の砲弾が朝陽の火薬庫を直撃して朝陽は沈没したが、中牟田は一命を取り留めた。箱館戦争後の1870(明治3 )年に海軍中佐、1872(明治5 )年、海軍大佐に昇進。1877(明治10 )年の西南戦争後に海軍中将に昇進。以後、海軍大学校長、枢密願問官を歴任。1905(明治38 )年に退役し、1916(大正5 )年に死去した。享年80歳。」「箱館府在住隊碑」己巳役海軍戦死碑の脇にある「函館府在住隊碑」。撃沈された新政府軍艦「朝陽」に乗船していた林六三郎等9名の名前が刻まれていると。「海軍薩摩藩士戦死者墓」函館湾の海戦で戦死した薩摩藩士和田彦兵衛の墓、和田は新政府軍艦「春日」に乗船していた。「春日」では6名が戦死し、海軍戦死碑にも名前が刻まれているが、和田だけは遺族が後に個人の墓を建立した。かなり磨耗が激しく読み取るのも一苦労である。和田の墓に並んで、同じく薩摩藩士「土屋傳太郎直道」の墓がある。土屋も同じく「春日」に水夫として乗船していた。 更に隣には「黒阪源右衛門墓」の墓もある。「和田彦兵衛の墓」の石碑の横には「鹿児島藩士・・」の文字が。薩摩藩士「土屋傳太郎直道」の墓。更に奥に進むとあった大きな碑 ・「御華山寄附記念碑」。「御華山」の文字が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.12.24
閲覧総数 254
-
22

茨城県内「続日本百名城」と社寺巡り その7:牛久大仏
「大杉神社」を後にして国道125号を霞ヶ浦方面に向けて車を走らせる。前方に橋が見えて来た。「小野川」に架かる「新古渡橋( しんふっとばし)」を渡る。この一帯は,昭和25年の茨城百景に「古渡(ふっと)湖畔」として選定された場所。「小野川」は、茨城県南部を流れ霞ヶ浦に注ぐ利根川水系の一級河川。更に進むと左折すると「JRA美浦トレーニング・センター」へ向かう「トレセン入口」交差点を直進する。「JRA美浦トレーニング・センター」は茨城県稲敷郡美浦村にある日本中央競馬会(JRA)の施設(トレーニングセンター)である。中央競馬の東日本地区における調教拠点である。略称は「美浦」「美浦トレセン」「美浦TC」など。上空から見た「JRA美浦トレーニング・センター」。 【https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%B5%A6%E6%9D%91】より茨城県道34号線に移り進むと前方に見えて来たのが「圏央道」。ここは「圏央道」の「阿見東インター入口」交差点。「圏央道」の下を通過し300m程進むと、「牛久大仏」➡右折 の案内板。そして車窓前方に巨大な「牛久大仏」の姿が。「牛久大仏」の駐車場に向けてケヤキ並木を進む。そして駐車場に車を駐め、「牛久大仏」の散策開始。牛久大仏(正式名称:牛久阿弥陀大佛)は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ(青銅)製大仏立像で、全高120メートル(像高100メートル、台座20メートル)あり、立像の高さは世界で6番目。ブロンズ立像としては世界最大。浄土真宗東本願寺派本山東本願寺によって造られた。小動物公園や花畑などがある浄土庭園内にあり、公園墓地「牛久浄苑」との複合施設となっている。総面積は37万平方メートルに及ぶ と。牛久市久野町2083。「牛久大仏建設の事業構想は1983年に関係者によって着手された。1986年に着工、1992年12月に完成した。事業主体は浄土真宗東本願寺派本山東本願寺。浄土真宗東本願寺派の霊園である牛久浄苑のエリア内に造られた。その姿は同派の本尊である阿弥陀如来像の形状を拡大したものである。全高120メートル(像高100メートル、台座20メートル)を誇り、奈良の大仏(像高14.98メートル)が掌に乗り、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある自由の女神像(全高93メートル、手を掲げた姿勢の像高46.05メートル)の実質的な像高(足元から頭頂までの高さ33.86メートル)の3倍近くの大きさである。地上高世界最大の"ブロンズ製"人型建造物(仏像)であり、ギネス世界記録には「世界一の大きさのブロンズ製仏像」として登録されている。地上高最大の人型建造物は、インドのグジャラート州ナルマダー県にある建国の父の1人とされる指導的政治家ヴァッラブバーイー・パテールをかたどった全高240メートル(像高182メートル、台座58メートル)の「統一の像(Statue of Unity)」。なお、近代以前に造営されたものでは、唐の磨崖仏である楽山大仏の像高59.98メートルが世界最大である。」とウィキペディアより。「高さの比較」図。「牛久大仏」は全長120m。インドのグジャラート州で、最近世界一高い像・統一の像(Statue of Unity)。この像は、ガンジーの信奉者で、インドの統一に貢献した政治家サルダール・パテールに敬意を表したもの。つまり、彼を像にしたのだ。建設費は実に約4億2000万ドル(日本円で約476億円)。建設期間は、約4年。高さは182m、台座を含め約240mに達するという。 【https://guardindustry.com/reference/statue-of-unity/】より世界の像高の比較。2位は「魯山大仏」、3位に「牛久大仏」。 【https://narmadatentcity.info/how-to-reach-statue-of-unity-and-tent-city/】より再び「牛久大仏」のお顔をズームで。頭の上に避雷針が。「牛久大仏」駐車場入口から。「牛久大仏」は南南西を向いている。その方角には浅草・本山東本願寺があり、またその先には仏教誕生の地・インドがあると。超巨大な「仏」の姿。「牛久大仏」が結んでいるのが「来迎印(らいごういん)」と呼ばれる印相。親指と人差し指を合わせて輪を作っているのが特徴。来迎とは人々を救うために阿弥陀如来が迎えにくることで、右手は掌を外に向けて胸の前に上げ左手は掌を外に向けて垂れ下げ、両手とも親指と人差し指をつける印相で手が左右逆の場合を逆手来迎印という と。左掌の長さ:18.0メートル親指の直径:1.7メートル 人さし指の長さ:7.0メートル。臨終の際、阿弥陀仏が西方極楽浄土より迎えに来るときのポーズと。「牛久大仏」が正面に見える位置まで道路を進んで行った。そして塀の隙間から「牛久大仏」を。建設施工は川田工業による。建築にあたっては主に高層ビルで用いられるカーテンウォール工法が採用された。まず中央に、大仏全体の重量を支える役割を果たす鉄骨の主架構を組み上げる。次に、主幹の役割を果たすこの鉄骨の周囲に、枝を生やすように、あらかじめ地上で作っておいたブロックを組み合わせていく。高さ100メートルの仏像本体は20段の輪切り状に分割して設計されており、さらにそれぞれの輪切りが平均17個のブロックに分割されている。加えて、各ブロックは平均1.5メートル四方の青銅製の板金を9枚程度並べて溶接し、下地となる鉄骨と組み合わせることで作成された。この下地鉄骨が、複雑な形状をとりながら主架構と青銅板との間を繋ぎ、樹木でいうところの「枝」に相当する役割を果たしている。仏像表面の青銅板は葉のように浮いているだけであり、巨大な質量を支える必要がないため、6ミリメートル程度の厚みしかない。これは、銅板で全体の重量を支える奈良の大仏などとの大きな違いである。特に形状が複雑な両手部分についても、別に地上で組み上げ、巨大クレーンを用いて吊り上げられた。像の表面には、これを覆うための6,000枚以上の青銅板が用いられている とこれもウィキペディアより。そのため、像の表面を注意深く見れば正方形のタイル状の継ぎ目を確かめることができる。これらブロックの継ぎ目部分には隙間があり、台風や地震、気象変化による板金の伸び縮みに対して構造上の余裕を持たせる役目を果たしている 再び「牛久大仏」のお顔をズームで。顔の長さ:20.0メートル、螺髪(らほつ)は総数:480個。1個の直径:1メートル、1個あたりの重量:200キログラム)壁の隙間から「牛久大仏」の頭の縮小版を見つけた。高さは約2mと。「牛久大仏のお顔の大きさは、この縮小の1000個分のボリュームに相当する」と。なるほど、実物のお顔は20mあるので20m/2m=10、体積は3乗に比例するので10☓10☓10=1000個分のボリュームに相当。大仏前の「大香炉」。大仏の前に置かれて いる「大香炉」は青銅製香炉として日本一の大きさであると。壁の隙間から「牛久大仏」のミニチュアの姿も確認できた。その後ろにあるのが「發遣門」であるようだ。牛久市の雨水マンホール蓋。「かっぱの里」牛久市観光協会のマスコットキャラクターである、かっぱの「キューちゃん」。 右手に打ち出の小づち、左手にキューリを持ち、いたずら小僧みたいな表情。 郷土の画家、小川芋銭がよく描く対象がかっぱであると。 右下には水連の葉とカエルも描かれていた。「牛久大仏」の入苑入口に向かって進む。拝観料は大仏胎内入場込みのセット券で800円/人。開苑は9:30、この時の時間は9:22で開苑前であった。「牛久大仏」を再び見上げる。「牛久大仏」の内部は鉄骨構造の高層ビルディングの如きと。 【https://www.eco.kawada.co.jp/blog/on-site/4177/】より主鉄骨の外部はジャングルジムの如く、下地鉄骨が張り出していると。そして下地鉄骨から外装材の青銅板を固定した鉄骨を連結していると。 【https://www.kawada.co.jp/technology/gihou/pdf/vol36/3601_03_01P.pdf】より「牛久阿弥陀大仏頭部鉄骨模型 S=I : 30 (紙製)地上93.5メートルから119.65メートルのお顔内部の鉄骨模型。緑色に塗られている鉄骨が主架構、白色の鉄骨が下地鉄骨。下地鉄骨はお顔の形に合わせ設計されている。架設にはカーテンウォール工法を採用したため、42個のプロックに分かれる構造になっている。プロック1つの量は板を含め約6トン。」組み立てた時の写真を『ネット』👈リンク から。お顔を地上で仮組。 【http://photozou.jp/photo/show/1075137/81249567】よりそして据え付け。 【https://4travel.jp/travelogue/11695451】より大仏の胸部にあたる地上85メートルまではエレベーターでのぼることが可能で、美しい関東平野の景色を展望することができる。ただし、像自体の美観の問題から広々とした展望場所は設けられておらず、胸部からの景色は4・ 5階の「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」にある3つのスリット状に設けられた小窓◯から見ることになるのだと。3階は極楽浄土の別名「蓮華蔵世界」で、壁一 面に約3,400体の胎内仏を安置。2 階は写経を行う「知恩報徳の世界」、1階は阿弥陀如来の大きな慈悲を表す美しい光の空間「光の 世界・観 想の間」が広がっているのだと。「展望台」👈リンク4・ 5階の「霊鷲山の間」にある、3つのスリット状に設けられた小窓。 【https://hirakana.hateblo.jp/entry/2020/12/19/230651】より3階は極楽浄土の別名「蓮華蔵世界」で、壁一面に金色に輝く約3,400体の胎内仏を安置。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より2階は写経ができる「知恩報徳の世界」。心を落ち着けて写経ができる席は全部で77席。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より周囲には繋ぎ目の線が確認できたのであった。左腕にも小窓が見えた。その外にぶら下がってあったのは風速計?、地震計?桜の時期にはこの様な見事な光景に。「牛久大仏 浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺」と書かれた銘板。「エレベーターで地上85mの展望台へ」案内板。「ようこそ 牛久大仏へ」。「像の基本情報」をウィキペディアより。構造:青銅板張立像全高(地上高):120メートル像高(立像の場合、本体の長さ):100メートル台座の高さ:20メートル(うち、基壇部は高さ10メートル、蓮華座は高さ10メートル・ 直径20メートル)総重量:4,000トン(うち、本体重量:3,000トン、外被青銅版の総重量:1,000トン)顔の長さ:20.0メートル目の長さ:2.5メートル 口の長さ:4.0メートル 鼻の長さ:1.2メートル 耳の長さ:10.0メートル左掌の長さ:18.0メートル親指の直径:1.7メートル 人さし指の長さ:7.0メートル足の爪の長さ:1.0メートル螺髪(らほつ。総数:480個。1個の直径:1メートル、1個あたりの重量:200キログラム)造営期間:1989年 着工、1993年6月 落慶存続期間:1993年 - 現存内部構造と情報内部にはパネル展示等があり、歴史や仏教の世界について学ぶ事ができる。1階:光の世界(Infinite Light and Infinite Life) 観想の間:浄土の世界を観想する(思い描く)空間。2階:知恩報徳の世界(World of Gratitude and Thanksfulness) 念仏の間:毎週土曜日、ここで法話がある。阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちを籠めて 写経を行う空間。写経席は77席。3階:蓮華蔵世界(World of the Lotus Sanctuary) 約3,300体の胎内仏に囲まれた金色の世界。「蓮華蔵世界」とは極楽浄土のこと。4・5階:霊鷲山の間(Room of Mt.Grdhrakuta) ここには仏舎利(釈尊の遺骨)が安置されており、参拝できる。 また、四方に窓があり、東西南北を見渡せる。地上に置かれている巨大な右手。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より平均1.5メートル四方の青銅製の板を繋ぎ合わせているのが確認できたのであった。賑やかなペットボトル飲料の自動販売機。ここにも見事な桜と芝桜の写真が利用されていた。ここが入苑通路。両側には土産物等の売店が並んでいた。そして車に戻る途中に振り返り「牛久大仏」に別れの挨拶を。そして先程、このブログを書いている時にネットから見つけた写真。年に一度の「牛久大仏」の清掃では清掃作業員が大仏の目の部分からロープで垂れ下がり汚れを洗い落とすのだと。 【https://www.sankei.com/photo/story/news/151021/sty1510210007-n1.html】より螺髪の清掃に向かう清掃作業員。 【https://ameblo.jp/kakurekumanomi2008/entry-12635274619.html】より ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.11.06
閲覧総数 2120
-
23

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その40)・ 芹沢石仏石像群~石祠道祖神~芹沢大谷の庚申塔と道祖神と地蔵~延命子育地蔵堂跡
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次「腰掛神社」を後にして東に進むと民家の入口の横にあったのが「権現様」。神奈川県茅ヶ崎市芹沢1722。さらにスマホの案内に従い「芹沢石仏石像群」に向かって進む。途中、民家の庭にあった八重桜。そして「茅ヶ崎市斎場」の入口前を通過し東に進む。左手の丘の上に見えたのが「慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部」の校舎。そして四辻の手前右手にあったのが「芹沢石仏石像群」。神奈川県茅ヶ崎市芹沢。歴史を感じさせる多くの石碑が並んでいた。左手には石仏の姿の有る石碑が。それぞれに近づいて。頭が補修の為に繋がれたようだ。何かを持っていたのであろうか。「正徳三癸巳(1713)十二月十一日」と。「宝永七庚寅(1710)」と。削ぎ取られた如くに。こちらも。「正徳(1711~1716)」の文字が。「芹沢石仏石像群」を後にして畑の畦道を進む。路地の角にあった神社。二つ並んだ小祠のうち、左側が「宇賀神(はっとりさま)」と呼ばれていると。こちらは石祠道祖神(流造)であろうか。左の社の中にはユニークな形のものが。内陣には左右に四体の蛇のような像が祀られていた。「宇賀神も突き詰めれば不思議な神様ではありますが、一般的には穀霊・稲霊と考えられていて、稲の豊作をもたらす水神としても受け止められ、このように蛇体で現されることの多い神なのだ。しかし、ここ芹沢の宇賀神がなぜ「はっとりさま」と呼ばれているのかは良くわからないそうです。「はっとり」にどのような字をあてるのかも定かではありませんが、「はっとり」は機織りに由来する「服部」なのでしょうか。宇賀神と稲荷の祭神:宇迦之御魂神は同一視されることも多いのですが、この稲荷神は養蚕・機織りなどに精通していた秦氏が信仰していた神であり機織りの神としても知られています。また、古代において諸国の織部を統率していた服部連は秦氏同族とも言われているので、そういう意味では宇賀神と「はっとり」との間に全く関係が無いとは言えないのですが……ちょっと良くわかりません。水辺で機を織る巫女と水神の関係は民俗学者の折口信夫氏が言及して久しいですが、あるいはそのあたりと何かしらの繋がりがあるのかもしれません。」とネットから。柿園の中を進む。次に訪ねたのが「芹沢大谷の庚申塔と道祖神と地蔵」。石鳥居の奥に石祠と社が。神奈川県茅ヶ崎市芹沢411。内陣。その横には道祖神、石仏が並んでいた。右から「兜巾型文字道祖神」明治二十二(1889)年台座の横にあった五輪塔の水輪(丸石)と頭部(繭玉石)は道祖神には付き物。「青面金剛庚申塔」上部欠損は悲しい。廃仏毀釈の嵐は、地蔵の首狩りと双体道祖神の切断の形がが多く見られるのだが。この地蔵尊も首を刈られていたのか、セメントで補修の痕が。民家の入口にあった庚申塔。茅ヶ崎市芹沢308。文字庚申塔。下部に三猿が削られた痕跡?近くにあった「山王神社」。石鳥居の横から。そして今度は梨園の中を通過。たわわに咲く梨の花。「芹沢スポーツ広場 野球場」の横を進む。そして再び畦道に案内される。そして大きな民家の塀の前にあったのが「延命子育地蔵堂跡」碑。民家の庭には立派な鯉のぼりが。これが寺の山門の如き民家の門。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.05.17
閲覧総数 598
-
24

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了覚院~円蔵祇園社~輪光寺(1/2)
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次所狭しと境内に石碑・石像が並んでいた「神明大神宮」を訪ねた後は、ポツンと「本堂」と墓石群が並ぶ「了覚院」を訪ねた。神奈川県茅ヶ崎市円蔵2170。トタン屋根の上に宝珠(ほうじゅ)を載せた小さな「本堂」。ネットによると「昭和20年以降無住寺となり廃寺になっていて空き地の中に小さな堂と位牌型墓碑が二基。一つには「太田善太夫吉次之墓」吉次は家光に仕え2260石、御先手弓頭などを務め延宝八(1680)年相模国高座郡円蔵村に葬られたとある。江戸時代初期、円蔵村は旗本三家の分給支給地で大田家はその一つ。」と。「本堂」の隣には墓石群が。「高野山真言宗 輪光寺末寺了覚院 御本尊 阿弥陀如来像江戸時代の円蔵村地頭知行高二百三十石(総知行高は二千二百六十石)太田善太夫吉次が菩提の為に元和五年(一六一九)に創建。吉次は法名を了覚院と云。延宝八年(一六八〇)没。太田氏一族及歴代僧侶之墓」大きな墓石が二基。右が「太田善太夫吉次之墓」。左が「◯住院殿◯義空了禪居士正定聚位」「正定聚(しょうじょうじゅ)」とは必ず仏となることの決まった聖者。不退転の菩薩たち。真宗では、他力真実の信心を得た者 をいうのだと。「三十三度」碑。正面 : 淺草観世音 相州圓蔵邑 三十三度 大山不動尊 行者了察右 : 寛政七乙卯暦左 : 十一月日造立之大山不動尊に三十三回登拝した記念にたてられた石碑なのであろうか。ここにも「茅ヶ崎市広報板」が。そして「了覚院」の後方に同様の「御堂」が見えたので訪ねてみた。「円蔵祇園社」。所在地:神奈川県茅ヶ崎市円蔵2163-2御堂を正面から。「了覚院」の御堂の一つであったのだろうか。小さな社も横に。道祖神であったのだろうか。注連縄が奉納されていた。寺院の御堂のようであったが。御堂の前から「了覚院」を見る。この畑の場所は、「了覚院」の境内であったのだろうか。そして次に訪ねたのが5分ほどの場所にあった「輪光寺」。「高野山真言宗天慶山輪光寺」。掲示板。二宮尊徳の少年時代(金次郎)の像。境内左側には「庚申塔・石碑群」が。近づいて。「輪光寺の庚申塔(こうしんとう)昭和四十四年八月十五日茅ヶ崎市指定重要文化財庚申塔は、庚申信仰に基づいて江戸時代に盛んに造られるようになったもので、人の延命招福を願ったものである。この塔は寛永十七年(一六四〇)の年号が刻まれ市内に所在する九十基余りの庚申塔の中で最も古いものである。舟形光背で、頭上に烏帽子をのせ、しやがんだ姿の三猿(上に聞かざる、下に向かって右に言わざる、左に見ざる)がニ段に浮き彫りにされている。このような形は同時期のものに他に類例を見ず塔の移り変わりからはやや異質であるが、年号からは全国的にも古い三猿塔である。」上記案内板の「庚申塔」はこれであろう。舟形光背型庚申塔寛永17年(1640)5月ケン?・バン・バン(梵字)・三猿正面右側「當六具供養勧功徳伴成佛 寛永拾七年 庚」 〃左側「辰 五月吉日 相州宅良郡圓像人殺嶋村天□岩戸久右衛門 」「人殺」は「人殿」????頭上に烏帽子をのせ、しやがんだ姿の三猿(上に聞かざる、下に向かって右に言わざる、左に見ざる)がニ段に浮き彫りにされていた。唐破風笠付角柱型庚申塔元文4年(1739)9月月日(手持)・青面金剛像(合掌・六臂)・三猿右側面「元文四己未年」・5人の名左側面「九月吉祥日」・5人の名「廿三夜供𫝥塔」。以下、六地蔵を右から。「栖蓮院殿俊譽妙順大姉 霊位 亨保十五戌天(1730)十二月上十日」。右手に錫杖、左手に宝珠(欠損)を持っ。年銘は没年日と思われる。「華香院殿夏屋清月信女 寛文十年戌四月十一日」両手で香炉を持っ。年銘は没年日と思われる。「智教院隋譽清順大姉 元文三午天八月十四日」「一乗院妙喜日理 正徳二壬辰天四月十五日」と。「雲庵心晴信女 寛文十一年亥十二月廿四日」と。「随源院順譽教哲居士 元文五申年十月廿九日」と。「弘法大師修行像」。「弘法大師修行像」碑。「大師堂」。「弘法大師像」。「本堂」前の石庭。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.06.26
閲覧総数 764
-
25

不思議な数(その1):【完全数】
7月13日(水)からNHK総合で毎週水曜 午後11時 (2022年7月~9月)に『笑わない数学』と題して、パンサー尾形貴弘が難解な数学の世界を大真面目に解説する異色の知的エンターテインメント番組が放送されている。現在までに7月13日放送 『素数』7月20日 『無限』7月27日 『四色問題』8月 3日 『P対NP問題』8月10日 『ポアンカレ予想』8月17日 『虚数』 8月24日 『フェルマーの最終定理』 が放送されてきた。そして先週の『フェルマーの最終定理』は17世紀、フランスの天才数学者フェルマーは、あるメモを書き残した。「“xのn乗+yのn乗=zのn乗”を満たす自然数x、y、zは存在しない(nは3以上)」。すなわち「3 以上の自然数 について、xn + yn = zn となる自然数の組 (x, y, z)は存在しない」、という定理のことである。ところが、これが正しいことを示す証明が「紙の余白がない」という理由で残されていなかったのだ。果たして、フェルマーの言葉は正しいのか?中学生でも理解できるこの問題に、多くの数学者たちが挑戦し、敗れ去った。証明に至るまで350年、苦闘のドラマをテレビは描いたのであった。放送内容が非常に面白かったので、学生時代を想出しながらもう少しこの内容を学びたいと思い、市民図書館で下記の本『サイモン・シン 青木薫訳 フェルマーの最終定理』を借りて読み始めているのである。その中の、導入部で『不思議な数』についても触れられており、これらの内容についても、昔を想い出しながら私も学びたいと考えたのである。1回目の今回は【完全数】について学んだので、ここに私の『備忘録』&『メモ』として、アップさせて頂きたく。【完全数】(かんぜんすう、英: perfect number)とは、自分自身が自分自身を除く正の約数の和に等しくなる自然数のことである。完全数の最初の4個は6 (= 1 + 2 + 3)、(6の約数は1,2,3、以下同じ)28 (= 1 + 2 + 4 + 7 + 14)、496 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248) 、8128 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064)である。「完全数」は「万物は数なり」と考えたピタゴラスが名付けた数の一つであることに由来するが、彼がなぜ「完全」と考えたのかについては何も書き残されていないようである★完全数は限られている実は、完全数は、現時点で確認されているものは51個しかない(2021年1月時点)。小さい順に、6、28、496、8128……と続くが、1万以下の完全数はこの4つしかないのだと。この後33550336、8589869056、137438691328、2305843008139952128、・・・・・とつづく。2018年に見つかった51番目の完全数は4900万桁以上もある、とてつもなく大きいものである。そして、その全てが「偶数」であると。紀元前4世紀頃から続く研究の中で、わずか51個しか見つかっていないのだから、完全数は相当珍しい数であることは間違いない。しかし、完全数は無数に存在することが期待されている(証明はされていない)。★完全数を巡る未解決問題完全数については、・「完全数が無数に存在するのか、有限なのか」、・「奇数の完全数は存在するのか」、・「1の位が6か8以外の完全数は存在するのか」といった問題は未解決のままであるのだ と。これらの問題自体はシンプルで、数学者でなくても理解できるが、その解答は極めて難しい と。★メルセンヌ素数とは「メルセンヌ数(Mn:Mersenne number)」とは、メルセンヌ数Mnが素数であるとき,メルセンヌ素数 (Mersenne prime) という完全数については、「偶数の完全数は、全て2n-1×(2n-1)の形である」ことが知られている。より、詳しくは、2n-1が素数であるような正の整数nに対して、2n-1×(2n-1)は完全数となるが、逆に、偶数の完全数は2n-1が素数であるような正の整数nを用いて、2n-1×(2n-1)という形で表される。「メルセンヌ素数と偶数の完全数は1対1に対応している」ことが知られている。また、現時点で確認されている完全数は限られており、2021年6月に51個目が発見されていた。整数 完全数n=2 6=21× (22-1) n=3 28=22 × (23-1)n=5 496=24 × (25-1) n=7 8128=26 × (27-1)n=13 33550336=212× (213-1)★完全数の興味深い特徴完全数はいくつかの興味深い特徴を有している。例を挙げると以下の通りである。(1)6以外の完全数は、奇数の立法和で表される。 具体的には、以下の通りである。 28=13+33 496=13+33+53+73 8128=13+33+53+73+93+113+133+153 33550336=13+33+53+73+93+113+133+153+ ・・・・・ +1233+1253+1273(2)6以外の完全数は4の倍数となっている。(3)完全数は、連続した自然数の和で示される。 具体的には、以下の通りである。 6=1+2+3 28=1+2+3+4+5+6+7 496=1+2+3+ ・・・・・ +31 8128=1+2+3+ ・・・・・ +127 33550336==1+2+3+ ・・・・・ +8191完全数の歴史紀元前3世紀にユークリッド(Euclid)が、既に先に述べた「2n-1が素数であるような正の整数nに対して、2n-1×(2n-1)は完全数となる」ことを証明し、最初の4つの完全数を発見したといわれている。従って、極めて古い歴史を有している。 なお、現在51個の完全数(メルセンヌ素数)があると述べたが、通常我々は、これは小さい順に発見されており、今後発見される新たな完全数は現存する最大のもの以上になるだろう、という感覚がある。ところが、現実は47番目の完全数が見つかった後に、それよりも小さい45番目の完全数が発見されている。2016年9月に、現在の45番目までのメルセンヌ素数より小さいものは存在しないことが確認されているが、46番目から、現時点で最大のメルセンヌ素数までの間に、新たなメルセンヌ素数がないことは未だ確認されておらず、新たなメルセンヌ素数が発見されるかもしれない、とのことである。多くの方々は、数学のような世界では、もっとシステム的に秩序だって事実が解明されていくものだと認識していると思われるが、必ずしもそうとは限らないというところが、何とも不思議な話ではないだろうか と。完全数は、どんな意味を有しているのか完全数の6は「神が世界を6日間で創造した」ことに関係していると言われている。6といえば、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種の曜からなる「六曜」があるが、これは1ヶ月(≒30日)を5等分して6日を一定の周期とし(30÷5 = 6)、それぞれの日を星ごとに区別するための単位として使われたとのことであるが、これに完全数が関係しているのかは定かではない。さらに、6という数字は各種の単位の基礎数字となっている。例えば、12(=6×2)は、1年の月数であり、干支や星座の数でもある。24(=6×4)は1日の時間数であり、30(=6×5)は1ヶ月の日数である。60=(6×10)は1時間の分数であり、360(=6×60)は円の角度である、といった具合である。28は「月の公転周期が28日である」ことに関係していると考えられている。28といえば、成人の頭蓋骨は舌骨を除いて28個の骨からなっており、人間の歯の本数は、親知らずを含めなければ28本ある。496は、古代ギリシャ人が「天地創造の神の数字」として崇めていた神秘的な数字と言われている。数字はいろいろと面白い性格を有している。暇な時には、数字遊びをしてみるのも、頭の体操にはよい事間違いなし。そして【擬似完全数】もあるのだ。【擬似完全数】とは自分自身を除く『いくつかの約数の総和』が元の数に等しい ということ。例えば12は【擬似完全数】です。12の約数は、1, 2, 3, 4, 6, 12です。このうち、2と4と6を使うと、2+4+6=12となり、12と等しくなります。よって、12は【擬似完全数】であることがわかります。そしてΠ(パイ)の数字に似た304も【擬似完全数】である。304の約数は、1, 2, 4, 8, 16, 19, 38, 76, 152, 304このうち、1, 2, 16, 19, 38, 76, 152を使うと、1+2+16+19+38+76+152=304となるので、【擬似完全数】の条件を満たすことがわかります。【擬似完全数】を小さい順に列記すると6,12,18,20,24,28,30,36,40,42,48,54,56,60,66,72,78,80,84,88,90,96,100・・・・更に【擬似完全数】のうち、その約数に他の擬似完全数を含まない数を【原始擬似完全数】という。【原始擬似完全数】は無数に存在し、そのうち最小の数は 6 である。【原始擬似完全数】を小さい順に列記すると6, 20, 28, 88, 104, 272, 304, 350, 368, 464, 490, 496, 550, 572, 650, 748, 770,910, 945, 1184, …となる。20の約数は1,2,3,4,5,10,20であるが、20=1+2+3+5+10であり【擬似完全数】が含まれない。上記の304も【擬似完全数】が含まれないので【原始擬似完全数】である。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.08.30
閲覧総数 400
-
26

新潟県柏崎市北条地区へ(その3):毛利氏の城館址・佐橋神社
「北条中学校」手前で、北条地区を案内していただける地元役員の方と合流しバスはUターンする。一面の田園が拡がる。事前に北条地区の案内書をOBの方から見せていただく。「歴史と文化の香るまち北条 越後北条城山圖」。「歴史のまち北条 ~越後毛利氏と北条城~毛利氏は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の重臣大江広元(おおえひろもと)の子・季光(すえみつ)が相模国毛利荘(神奈川県)を譲り受け、毛利氏を名のったことから始まります宝治合戦(ほうじのかっせん)でその一族は北条氏に滅ぼされました。この時、本拠地の相模国毛利荘などは没収されましたが、佐橋荘と安芸国(あきのくに)吉田荘は領地として認められ、季光の子経光(つねみつ)が南条に移り住んでいたことから、北条(きたじょう)が越後毛利発祥の地になりました。また、西国最大の戦国大名となった毛利元就は、遠隔地の領地を維持するために安芸国吉田荘に土着した一族の末裔(まつえい)です。経光の長男基親(もとちか)は北条毛利(きたじょうもうり)となり、その子時元を初代城主に迎えた北城は戦国の時代まで続きました。城主の中でも、上杉謙信の重臣として上野国厩橋(うまやばし・現前橋市)に派遣さた北条高広(きたじょうたかひろ)と、御館の乱(おたてのらん)に関わったその子北条景広は、鬼丹後としてともに有名です。北条城は、この御館の乱で景広を最後に約300年間の歴史に幕を閉じました。「石仏のまち北条北条のまちを歩いてみませんか、きっとあなたはたくさんの石仏に出会います。ほほえみかける石仏、歴史を刻む石仏、そのお顔やお姿、そしてそこに彫られた文字は遠い先人たちの暮らしの証です。北条は道祖神の宝庫です(13基)。男女神が肩を抱き合い、お酒を酌み交わす姿はいとおしいばかりでなく、素朴な祈りの心がにじんでいます。盲人米山検校(けんぎょう)の話をご存じですか。検校は宝暦の飢饉(1755 )のとき、私たちの祖先を救ってくれました。出身地杉平には墓があり、十二の木と大角間(おおがくま)にはお礼の塔が建っています。廃村した鷹之巣には「祖霊之碑」があります。この碑は先祖の眠る山河が私たちの心のふるさとであることを教えてくれます。」「北条マップ」。ズームして。「北条の宝物」。「北条小唄👈リンク春はうれしや城山ざくら 唄に流れる 唄に流れる 斧の音(北条城跡)思い出します縦貫道路 可愛いあの娘の 可愛いあの娘の 片えくぼ(縦貫道路)丘のほとけをおぼろに染めて さくら参道は さくら参道は 七曲がり(入定上人遺蹟)夏の涼みは長鳥川よ 闇に浮かんだ 闇に浮かんだ 豆木橋(専称寺の豆木門)とけた情けも大師のふしぎ 千とせ塩ふく 千とせ塩ふく 法の水(弘法の塩水井戸)検校米山困窮塚の むかし語りも むかし語りも 草の底(米山検校)秋は十五夜祇園の拍子 火防係の 火防係の 意気姿(北条の十五夜祭り)想いこがれてトンネル抜けて 逢いに来たぞや 逢いに来たぞや 月あかり(畔屋~山澗トンネル)」手に手結んで大杉さんに なんの願いを なんの願いを かけたやら(中村の大杉)肩を並べて金倉スキー 日本海まで 日本海まで ひと息に(金倉滑降)恋のかよい路吹雪にくれて 広田恋しや 広田恋しや 湯のけむり(広田鉱泉)雪にうもれた愛宕の山に 恋のスロープ 恋のスロープ 花が咲く(愛宕山)「北条の伝承料理丹後のやきもち さしみコンニヤク 手打ちそば北条には、古くから伝わる数々の伝承料理があります。それは、自然の素材を慈(いつく)しみ調理された心温まるおふくろの味です。」。そして最初に案内していただいたのが「佐橋神社(さはしじんじゃ)」。バスを下りると、こんな物がありました。右に曲がって、もう少し上れと言うことのようです。「毛利氏の城館址(じょうかんし)と佐橋神社鎌倉時代、この丘に佐橋庄の地頭毛利氏の居館があった。子孫は各地に分散。ここに残った一族は南条氏といい、上杉氏に仕える。慶長3年(1598)廃城。天和3年(1683)、城跡保護のために神社が建てられ、慶應元年(1865)佐橋神社と改称。」参道を進む。モミジの黄葉。ズームして。石灯籠。土塁跡のような土盛りを、神社の周りで見かけた。「毛利元就ルーツの地」碑。佐橋神社は、佐橋庄の荘園居館のあった場所で、ここを拠点に7が村に及ぶ広大な領地を経営し現在の「鯖石」の語源になりました。鎌倉時代、源頼朝の重臣、大江広元の孫にあたる毛利経光がこの丘に移り住み、その後の越後毛利、西国毛利の発祥の地になったことでも知られています。「三本の矢」の故事をのこした毛利元就ルーツの地であり、学問を好む風土は江戸時代の教育者藍澤南城(あいざわなんじょう)にも引き継がれました。「毛利氏略系図(戦国時代まで)」をネットから「鎌倉殿の13人」で「政所別当 大江広元」役は栗原英雄さん。大江広元は北条親子に次ぐNo.3の座につき、「承久の乱」では大江広元の嫡男だった大江親広は後鳥羽上皇に呼び出され官軍側となり、大江広元と大江親広は親子で戦うことになったのだ。生涯を通じて鎌倉幕府に尽くして幕府の発展を支えた大江広元だが、1225年(元仁2年/嘉禄元年)に激しい下痢を伴う病気を患い、亡くなったと。墓所は源頼朝の墓の近くにありますが、現在の神奈川県鎌倉市にある明王院(みょうおういん)の裏山にある、「五重塔が大江広元の墓所」👈リンク と考えられているのだ。「佐橋神社」の拝殿。近づいて。扁額「佐橋神社」。木鼻の彫刻。神楽殿。毎年恒例の春季大祭時にこの神楽殿で行われている「子供神楽」の写真をネットから。境内の石祠。『毛利氏供養塔』。建立された関修さんは、仕事の関係で福島県いわき市に移住されたとのこと。供養塔の後ろに見える建物は、「ごぼう庵」。「毛利氏供養塔建立の趣意この地は大正十二年まで関修家の居住地であった。往昔、東隣高台に毛利氏の城館があったことから、屋号を「城」といい先祖以来毛利氏の霊牌を奉祀してきた。毛利氏は大江広元の四男季光が毛利庄(神奈川県厚木市)に住む毛利家を称したことにより誕生した。宝治元年鎌倉で三浦氏の乱が起こり、毛利の一族が族滅した。偶然にも季光の四男の経光が生き残った。経光は毛利庄から佐橋庄へ下向し、東隣高台に居館を構い、佐橋庄(柏崎市)と吉田庄(広島県安芸高田市)を支配した。経光の子孫は当地南条から北条、安田、石曽根、善根へ分流し、越後毛利氏を形成した。また毛利元就、同輝元らが出た西国毛利氏の先祖は、経光の四男時親である。兼ねてから関修は毛利氏とゆかりの南条の歴史的価値が永く伝え継がれることを願うとともに、毛利一族の供養を宿願してきた。このたび、知友関喜四郎氏の協力を得て旧宅地を整備し、毛利氏供養塔の建立を志した次第である。 合掌 平成二十四年十一月二十六日 建立者 関 修 施工者 関 喜四郎 撰文 関 久」「墓誌」。毛利経光の戒名は「盛生院法榮佑徳信士」と。竹林前にも案内板が。「妙姫庵跡(みょうきあんあと)弘化元年(1844)、藍澤南城の妹佐和47才が出家して玄妙と名のり、妙姫庵を開いた。玄妙・妙真・貞順・厚順・良仙・仙宗が在庵し、通称観音堂とよばれた。昭和46年(1971)以後に仙宗が小出に去り、廃庵となる。」墓地には無縫塔が並ぶ。関氏の墓地。「先祖 関儀右庄門」と刻まれた碑。多くの石仏が刻まれた石塔。ここにも歴史を感じさせる石碑、石仏。「大乗妙典供養塔」と。衆生を迷いから悟りの世界に導いてくれる教えを記した仏教経典である「大乗妙典」を一千回以上、独誦したときの記念に建てた石碑であると。「城址殉難者碑」。「城址殉難者碑明治31年(1898)、妙姫庵3代山岸貞順が建てた。同18年(1885)佐橋神社境内から出土した頭骨を埋葬したものである。大正12年(1913)、地元の旧家関周三郎は山口県毛利公爵家にこの頭骨は毛利経光のものではないかと照会している。」大きな墓石、塔婆には「大姉 廿七回 追善供養」の文字が。「祖先累代法塔」「童女」の供養塔・石仏が並ぶ。廃寺の本堂を移築して「ごぼう庵」と名づけてお茶を飲ませてくれる店と。ネットには休業中ともあったが。店の前には、多くの盆栽が置かれていた。「ごぼう庵」店主の趣味なのであろうか? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2023.01.31
閲覧総数 1000
-
27

飯田橋ウォーキングガイド・東京の歴史と文化を巡る(その2):讃岐高松藩上屋敷の土蔵跡~平川の径~讃岐高松藩上屋敷庭園跡~ひかり・空中に~歴史のプロムナード碑~徽章業発祥の地碑~飯田橋むかしむかし~北辰社牧場跡~台所町跡~飯田町~東京女子医大 発祥の地
首都高速5号池袋線下の神田川から流れ込む「日本橋川」沿いの桜並木を歩く。「日本橋川」は、小石川橋下流で神田川から分流し、日本橋を経て隅田川に注いでいる河川。右手に案内板があった。「讃岐高松藩上屋敷の土蔵跡」案内板。千代田区飯田橋3丁目10。「讃岐高松藩上屋敷の土蔵跡飯田橋二丁目から三丁目に広がる飯田町遺跡からは、讃岐高松藩(現在の香川県)の上屋敷跡が発掘されました。上屋敷は1706年(宝永3年)に幕府から与えられたもので、藩主が住み、政務を執り行った屋敷です。12万石の領地を支配した高松藩松平家は、初代藩主松平頼重(まつだいらよりしげ)が水戸藩2代藩主徳川光圀の兄にあたり、徳川御三家である水戸藩ゆかりの大名でした。発掘調査では御殿をはじめ庭園跡、上下水道跡、土蔵跡などが見つかっています。土蔵跡の基礎には、大きな礎石の下に木の土台が用いられていました。その礎石は、現在川沿いの遊歩道のベンチに再利用しています。」「遺跡北半(I区)の出土状況と土蔵基礎の蝋燭地業(ろうそくじぎょう)」。表面の地盤が悪い場合で、しかも良質な地盤までが浅いときは、蝋燭状の石材をたてて基礎を支持させることがある。この時の石を蝋燭石とよび、こうした地盤改良を蝋燭地業という。「日本橋川」の上部には首都高速5号池袋線が走る。その先に中央線の車輌が見えた。潮位の影響でゆっくりした流れは逆の神田川方向に。ズームして。手前が「日本橋川」に架かる「新三崎橋」その先にJR中央線そしてその先に「神田川」。「日本橋川」と「神田川」の流れ。「ガーデンタワー」と「トミンタワー飯田橋三丁目」の間の中庭・公開空地を歩く。大きな石には文字が刻まれていた。「平川の径かって、この付近には「平川」という川が流れていました。平川は江戸時代初期の大工事により、現在の神田川に流れを変え、当時の古地図にのみ名残りを留めていました。この「平川の径」は、讃岐高松藩上屋敷 の遺構 の下より発見された平川の護岸石 を用い、往時を偲ぶ小径としました。」千代田区飯田橋3丁目10。さらに広場を南方向に進む。右手にも文字の刻まれた石が。「讃岐高松藩上屋敷庭園跡かって、ここには讃岐高松藩上屋敷がありました。その庭園には景石と中島をもつ泉水があり、釣り遊びの浮きも出土しています。ここに遺跡調査により発掘された泉水の護岸石や景石をほぼ当時の位置に配し、往時の名残といたします。」千代田区飯田橋3丁目10。「平川の径」現在の日本橋川と平行するあたりに江戸初期には平川という川が流れ、その下流の江戸城正面あたりは水害に悩まされていた。そのために、平川は埋め立てられて神田川へ流されるように流路変更されたと。現在神田川は小石川橋のところで日本橋川へつながっているが、これは明治になって再び掘られたもの。屋敷の遺構の下から川の護岸石が多く発掘されたと。アイガーデンエアに平川の流れを再現した小路が作られていた。石垣から江戸前期の地形、平川の流れを感じることが出来たのであった。反対側から「平川の径」を振り返って。「東京しごとセンター(旧シニアワーク東京)」下の広場にあったパブリックアート。千代田区飯田橋3丁目10。「ひかり・空中に」伊藤隆道。流麗な螺旋形が特徴的な作品。近づいて。球体から反射した光が上空に舞い上がるが如くに。再び「目白通り」に戻る。角にあったのが「飯田橋散歩路 歴史のプロムナード」。千代田区飯田橋2丁目8。「歴史のプロムナード(プロローグ)昔々、縄文時代の頃、このあたりは波の打ち寄せる入江でした。その後、海は後退して、葦の生い茂る広い湿地となりました。徳川家康が江戸に来て大規模な築城工事が行われ、このあたりは湿地から旗本屋敷にかわりました。九段坂、中坂を中心とした元飯田町は、町人の町として 賑わいましたが、明治になって旗本屋敷の後は住む人もなくなり、一時は大変さびれました。しかし、次第に賑わいを取り戻し、現在のようなビル街に変わりました。この飯田橋散歩路に標柱を建て、この町の移りかわりを示します。」飯田橋からに九段下通じる目白通り沿いには多くの歴史の標柱や地図版が並んでいたのであった。そして「目白通り」の反対側にあったのが「徽章業(きしょうぎょう)発祥の地」石碑。徽章(きしょう)とは、主にバッジ(Badge)、メダル(medal)のこと。千代田区飯田橋1丁目7。「徽章業発祥の地この奥、大神宮通り向って左側に明治18年(1885)、鈴木梅吉により日本帝国徽章商会が創られました。これは民間の徽章業(きしょうぎょう)のはじめて、特に明治末期、大正の初期においては日本で唯一の徽章(きしょう)の製作工場として大変栄えました。現在の徽章業(きしょうぎょう)の方々の大多数は、この商会の流れを汲み、徽章業(きしょうぎょう)は飯田町の日本帝国徽章商会から生まれたといわれています。そして現在もこのあたりは徽章業(きしょうぎょう)に従事する人が沢山います。」「飯田橋むかしむかし 明治のはじめ 1872年(明治5年)」。千代田区飯田橋1丁目5−8。まだ飯田橋は掛かっていませんが、神田川の南側には屋敷が立ち並んでいる。「目白通り」を九段下に向かって進む。そしてここには「北辰社牧場跡」石碑。千代田区飯田橋1丁目5。「北辰社牧場跡榎本武揚は明治の始め、北辰社牧場をここに開きました。幕臣榎本は文久2年(1862)オランダに留学を命じられ、当時のヨーロッパ事情や法律、化学などを広く習得しました。幕府が瓦解すると榎本は指揮下の海軍をひきいて函館までも転戦しますが、黒田清隆や山田顕義らの率いる官軍の軍門に下り、捕われの身となります。しかし、彼の新知識を惜しまれて許され、新政府では幾多の要職を歴任しました。一方、旧幕臣子弟のための育英黌農業科や北辰社牧場などを作りました。最盛期には乳牛が四、五十頭もいて新しい飲物、牛乳を提供していました。」再び「目白通り」を渡り反対側に。「台所町跡」石碑。「台所町跡江戸のはじめから元禄の頃まで、飯田町紙流通センターの所に江戸城の台所衆の組屋敷がありました。そして台所頭をはじめとして、台所衆、台所者と呼ばれる役人が住んでいました。武鑑にお台所頭、四百石、たい所町、鈴木喜左衛門と記されています。その後大名や、旗本の屋敷に移り変わりましたが、なお付近は台所町の名が残りました。」その横にあったのが「千代田区 総合防災案内板」。「千代田区 総合防災案内板」現在地はここ。ここにも「飯田町」案内板が。再び、現在地はここ。「飯田町かつてこのあたりは千代田村と呼ばれるのどかな農村でした。ここに飯田(いいだ)という地名が生まれたのは、徳川家康が江戸にやってきてからのことです。天正十八年(1590年)、江戸に入府した家康は、千代田村とその周辺を視察します。このとき案内役を買って出たのが、村の住人飯田喜兵衛でした。「所(ところ)の巨細(こさい)とも申上(もうしあげ)(土地のことについて、細かく詳しく申し上げた」(『新撰東京名所図会』より)という喜兵衛の案内に感心した家康は、彼を名主に任命し、さらに地名まで「飯田町」とするように命じたのです。以来、江戸の町の開発が進み、この界隈に武家屋敷がひしめくようになっても、飯田町という名前は残りました。ただし江戸時代の武家地は町名をもたなかったため、飯田町は通称として使われていました。飯田町が正式な町名となったのは、元飯田町や周辺の武家屋敷などが、飯田町一丁目~六丁目に再編された明治五年(1872年)のことです。ここには飯田町三丁目と同四丁目などが誕生しました。昭和八年(1933年)になると、区画整理によって飯田町三丁目の東側と同四丁目の南側、同五丁目の一部などが、新たに飯田町一丁目となります。さらに、昭和四十一年(1966年)住居表示の実施により、飯田町一丁目は、飯田橋一丁目、同二丁目などに再編されました。ちなみに、目白通りに対して西側は飯田橋一丁目に、東側は飯田橋二丁目として区分けされ、現在に至っています。」現在地は「酒井備中守忠讜(ただなお)の屋敷」であったようだ。「飯田橋一丁目」交差点。この辺りに「東京女子医大 発祥の地」石碑があるはずであったが。右手は工事地中であったので、一時避難中なのか?千代田区飯田橋1丁目1。これであったが・・ネットから。「東京女子医大 発祥の地吉岡彌生は 明治33年(1900)12月5日、この地にあった 至誠医院のなかに 東京女医学校を創立しました。翌34年4月、同校は牛込区市ケ谷仲之町に移転。 のちに 市ケ谷河田町へ移転して現在の東京女子医科大学に続きます。 吉岡彌生の至誠医院は明治41年(1908)に 旧飯田町四丁目31番地に移り,、関東大震災までありました。」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・iPhone 15 香港版 A3092 海外SIMフリースマホ【アルミボディでカラーも豊富・Type-Cケーブルへ変更・4.8MPメイン2眼カメラ搭載】
2023.10.08
閲覧総数 445
-
28

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その12):長雲閣こみち~神奈川県立美術館
「森山社」を後にして、県道207号線に向かって、葉山町一色の住宅街の道を進む。「長雲閣こみち」。長雲閣とは、総理大臣や陸軍大臣を歴任した、桂太郎氏の別荘のこと。日露戦争の前後には、政府要人たちが度々会議に使用したそうです。現在は、この小道に名前が残るのみ。古い時代に想いを馳せつつ、さらに進みます。「長雲閣こみち」。県道沿いのレストランの塀に「桂太郎別荘・長雲閣跡」の案内が掛かっていた。が、私が聞いた話では、県道から少々入った建物である。下の写真は、「長雲閣こみち」と、中央に建物が写っているが、その建物が、数年前まで桂太郎別荘とされていた。しかし地元歴史家よると、ここではなく、向かい側の建物がそうだと変更になったのだと。「桂太郎別荘跡」はここであっただろうか?日露戦争前後には、政府要人による重要会議が別荘を中心に度々開かれている。司馬遼太郎原作「坂の上の雲」でも「葉山会議」と称して登場している。そして再び県道207号線に出て北上する。左手にあったのが「神奈川県立近代美術館 葉山館」。奥にあったのが屋外にある常設展示。2003年の開館以来、一部作品の入れ替えや追加を経て、2016年に旧鎌倉館から移設された9点が加わり、現在は彫刻20点が庭園に、壁画2点が建物内に常設されている。葉山館のイラストマップ「彫刻はどこにいるの?」(館内無料配布)と一緒に、一色海岸に臨んだ庭園を散策しながら野外彫刻を楽しんだのであった。三浦郡葉山町一色2208−1。茶色の石材で。中島幹夫 NAKAJIMA Mikio『軌 09 Orbit 09』1966年館内では「吉田克郎展」が、開催されていた。「吉田克朗展 -ものに、風景に、世界に触れる」会期:2024年4月20日(土)〜6月30日(日)。武蔵野美術大学の教授だった美術家、吉田克朗の全貌に迫る初めての回顧展と。吉田克朗『触“春に”V』。これまでほとんど紹介されることのなかった作品や、さらに油彩から版画作品までを網羅し展示していると。県道沿いには幟が立っていた。駐車場の横にあったアルミニウム&大理石の作品。清水九兵衛 KIYOMIZU Kyuubei『BELT』1978年駐車場から「神奈川県立近代美術館 葉山館」を見る。小田 襄 ODA Jo『円柱の展開 Development of a Cylinder』1983年李 禹煥 LEE Ufan『項 Relatum』1985年「神奈川県立近代美術館 葉山館」入口。若林 奮『地表面の耐久性について』ホセイン・ゴルバ Hossein GOLBA(1956~)『愛の泉 Fountain of Love』イラン出身のホセイン・ゴルバの作品『愛の泉』。最初イタリアのチェレ彫刻公園の水飲み場として制作された。樹木の幹を鋳造、他の部分を蝋型で付加。「愛」の意味とは?「飲料水 Drinking Fountain右下のボタンを踏むと水が出ます」との案内も。水桶には二人の顔が。さらに葉山館だけの作者からの「おまけ」も足元に。強く踏むと、ボタンを踏んでいる足に水がかかるのであった。鈴木 昭男『「点音(おとだて)」プレート・葉山』2012年。『地平の幕舎』。鉄板でテントのような形を。鉄の赤錆がいい色を出していた。保田春彦 YASUDA Haruhiko『地平の幕舎』1993年『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』。眞板雅文 MAITA Masabumi『天地の恵み Blessings of the GOOD Earth』2003年『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』。波乗りジェーンって感じで。富樫 一 TOGASHI Hajime『ハーモニーⅡ HarmonyⅡ』1972年ここが先程訪ねた「葉山しおさい公園」からの連絡通路。「開門時間土曜日・日曜日・祝日の近代美術館開館日のみ午前10時30分~午後4時まで」「三ヶ岡遺跡神奈川県立近代美術館葉山の建設に伴い、この地にあった三ヶ岡遺跡が発掘調査され、主に古墳時代から平安時代(4 ~ 10世紀)にかけての集落の跡が発見されました。この遺跡で特筆されることは、海浜に立地する特徴を活かした平安時代の製塩跡が見つかったことです。ムラの跡 竪穴住居が22軒、掘立柱建物が1棟密集して発見されました。ほとんどが6 ~ 7世紀のもので、継続して居住していたことがわかりました。製塩跡 約2X6mの範囲に火を受けて赤く硬くなった地面があり、そのそばから多量の土器が打ち捨てられたままに出土しました。また海水を煮詰めるためのものか、石組炉の跡も2基発見されています。」「製塩跡」と「竪穴住居跡」。『イノセンス-火 Innocence:Fire』。西雅秋 NISHI Masaaki『イノセンス-火 Innocence:Fire』1991年西雅秋『大地の雌型より』2003-5年葉山漁港の4隻の木造船にコンクリートを流し込み、ひっくりかえして木部を外したもの。「一色海岸」を望む。西雅秋『大地の雌型より』の一部。アントニー・ゴームリー『Insider Ⅶ』1998年山口牧生 YAMAGUCHI Makio『棒状の石あるいはCosmic Nucleus aBar of Stone,or Cosmic Nucleus』1976年『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』。空 充秋 SORA Mitsuaki『揺藻(ゆれも) Swaying Alga』1985年湯村光『Stone Work – Stream』1987年柳原義達(1910~2004) YANAGIHARA Yoshitatsu『裸婦 座る Sitting Nude』原型 1956年(鋳造 1964年以前)『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』。近づいて。イサム・ノグチ(1904-1988)は、日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれた、20世紀を代表する世界的な彫刻家。彫刻はもちろん庭園や舞台芸術、家具そして照明のテザインも手がけるなど、現代彫刻の可能性を大きく押し広げ、作品と活動を通して世界各地て愛されつづけている芸術家である と。イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』1951年『石人 Stone Man』1966年(古墳時代6世紀後半の扁平石人の複製(岩戸山古墳[福岡県]出土・現在大分県日田市に設置)イサム・ノグチ Isamu NOGUCHI『こけし Kokeshis(Japanese Wooden Dolls)』を振り返って。これは、展示物ではなく、石製の休憩場所のようであった。「レストラン オランジュ・ブルー」。イサム・ノグチの作品を別の場所からも。最後に「神奈川県立近代美術館 葉山館」を再び振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.06.22
閲覧総数 825
-
29

自治連の親睦旅行・豊洲~川越へ(その2):豊洲 千客万来(1/3)
大型バス駐車場にてバスを降りて「豊洲 千客万来」の散策開始。豊洲市場に隣接する「豊洲 千客万来」は、食楽棟「豊洲場外 江戸前市場」と温浴棟「東京豊洲 万葉俱楽部」から成ります。2024年2月1日にオープン。食楽棟「豊洲場外 江戸前市場」では、築地の伝統を引き継いで、豊洲ならではの新鮮な食材などを活かした飲食・物販店舗を展開いたします。江戸の古い街並みを再現したオープンモールで、食べ歩きやお買い 物をお楽しみください。温浴棟「東京豊洲 万葉俱楽部」では、専用トレーラーにて、箱根・湯河原の温泉を毎日運搬して、豊洲の地に“東京都心の温泉郷”を実現します と。「1F 豊洲場外 江戸前市場」案内。「1F~3F案内板」。・日本最大規模の木造耐火商業施設。・1階 鉄骨造、2~3階 木造の立面混構造。・2~3階の木造部の柱と梁に、“東京の木 多摩産材”を活用した木質耐火部材 「COOL WOOD(1時間耐火仕様)」 を採用。・御影石や淡路瓦などの伝統的な建築素材を用い、江戸の風情ある街並みを現代に再現。そして最初に2Fを訪ねた。「2F 豊洲場外 江戸前市場」案内図。「木戸門前広場」。「逸品屋えどこ」👈️リンク 前には多くの外国人観光客の姿が。ブルーのお揃いのTシャツを来た外国人観光客。「目利き横丁」の入口。仲卸が目利きした新鮮な旬の食材や珍味を、食べ歩きやカウンターで楽しむことができ、各店舗から食欲をそそる香りが漂う食の賑わいを体感いただけるエリア。「木戸門」から入り「豊洲目抜き大通り」を訪ねた。右手最初にあったのが「つきぢ神楽寿司」👈️リンク「豊洲目抜き大通り」を進む。寿司やうなぎなど、江戸前の食が楽しめる飲食店街や地元江東区で人気の店舗が並ぶエリア。東京の⾷の魅力の新たな発信源としての役割を担っている と。その先に、左手にあったのが「江戸 深川屋」👈️リンク。江戸時代の防火用水を再現。その先、右手にあったのが「千客万来屋台店」👈️リンク。3階の連絡通路下を進む。「玉子焼 力武-Premium-」👈️リンク。大正末期創業、玉子焼専門店。特選卵を使用した新しい出汁巻き玉子、プリン、ソフトクリーム等スイーツや、休市日限定メニューも豊洲場外でしか味わえません。築地で大人気焼たて食べ切りサイズもご賞味ください と。人気の「厚焼玉子」も店頭で焼いて。これぞ「厚焼玉子」!!。丸武のプレミアムたまごやき 300円。「うなぎ 北鎌倉 名月川」👈️リンク。「炭火焼 うなぎ 北鎌倉 名月川」。「うな重 松(うなぎ一尾半) 5,910(6,500)円」「うなぎ一品料理」。ウナギの香りが写真からも溢れ出て来るが如くに。食べたかった!!!!・・・・。右側に「十割そばと江戸前天ぷら 囲炉裏」👈️リンク、左側「軽食・スイーツ・ドリンク かねす」👈️リンク。「ふわふわサクサク まんじゅうの天ぷら」。「当店限定の 『まんじゅうの天ぷら』 は、「酒まんじゅう」・「黒糖まんじゅう」・「紫芋まんじゅう」 の3種で、まんじゅうに衣をつけてサクッと揚げたオリジナル天ぷらです。まんじゅうを天ぷらにする(熱を加える)ことで、より一層中身の “餡の甘み“ を感じていただける商品となっております。豊洲千客万来店ならではの “食べ歩きグルメ” としてぜひお楽しみください! 」と。さらに進む。「月島もんじゃ 十五夜」👈️リンク。「しらすもんじゃ」。「あんバターたい焼き」。「あんバターたい焼き 400円」。大きなバターを口に咥えた「あんバターたい焼き」。「肉好き 大黒天」👈️リンク。「九州産黒毛和牛 黒火乃牛と岩中豚のメンチカツ」。卸ならではの厳選した牛肉、豚肉、鶏肉を使用し、大きな肉の串焼きや、肉の煮込み、豪快な肉炒め、揚げたての肉惣菜をご用意しています と。「大黒天甘辛すき焼豆腐」。そして右手には「時の鐘広場」が現れた。「豊洲 千客万来」のランドマーク、時の鐘。時の鐘とは、江戸時代に時を告げる役割に使われていた。時の鐘の下には時の鐘広場があり、多くの人が集う空間となります。定期的にイベントなども開催しています と。このあと、川越にある「時の鐘」を訪ねたのであった。「時の鐘広場」のベンチにて多くの観光客が買った食べ物を楽しんでいた。「千客万来 大入」と。和カフェ「豊洲 ふくらすずめ」。芝居小屋「江戸遊楽座」の中に、“見てよし、食べてよし、飲んでよし! 縁起物を取り揃えて、みなさまに福をもたらす場所に”を合言葉に、食品や雑貨を扱う土産店「豊洲えんぎもの」、素材にもビジュアルにもこだわった和カフェ「豊洲ふくらすずめ」、約30種の日本酒を楽しめる「豊洲のみよし」の3店舗がオープン と。歌舞伎役者の錦絵が。「花飾駒道中双六 うかい勘作 中村芝翫」豊原国周 画 。 「女房お傳 大谷友右衛門」豊原国周 画 。「役者絵 すごろく」。「三芝居三言音雙六(さんしばいこわねすごろく)」👈️リンク と古文字の師匠から。「豊洲市場 相馬水産」には長い列が。“創業60年 豊洲まぐろ仲卸し”相馬水産のファーストフード店。王道の刺身、仲卸しだからこその希少部位、前代未聞のまぐろ料理等、“とにかく旨いまぐろを食べてもらいたい”との一心で創り上げたメニューの数々をご賞味ください と。「まぐろ串」。「江戸有楽座」の北西側、土産物屋「豊洲えんぎもの」の入口の上にあった「鼠小僧次郎吉」、「鳴神」、「毛抜」の歌舞伎の題目が書かれた看板。中央に「優長市川系譜」👈️リンク。右「一世一代 吃の段中村歌右衛門 豊国画 けいせい反魂香」左「女房お徳 中村大吉 豊国画 けいせい反魂香」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.07.05
閲覧総数 399
-
30

牛久大仏へ(その4)
牛久大仏の内部見学を終えて、地上へ。「本願荘厳の庭(ほんがんしょうごんのにわ)」・本願(ほんがん) 阿弥陀仏の「本願」(衆生を救う誓願)を意味します。・荘厳(しょうごん) 仏教語で「飾り整えること」「厳かに美しく整えること」。 仏や浄土を荘厳=美しく表現する、という意味があります。・庭(にわ) そのまま「庭園」。つまり 「本願に基づいて荘厳(美しく整え)られた庭園」 という意味で、牛久大仏周辺にある浄土庭園の一部(日本庭園)を指す案内板牛久大仏の敷地内にある 「本願荘厳の庭」 の一部、つまり日本庭園の中心となる 池泉回遊式庭園 の景観。① 池泉(ちせん)庭の中心に広がる大きな池で、水面に周囲の木々が映っていた。池泉回遊式庭園は、日本庭園の中でも歩きながら景観を楽しむタイプで、牛久大仏の庭園でも代表的な構成。② 配石(石組)右側に大きな岩が配置されていた。これは山や島を象徴し、庭園の構図に重心と静けさを与える伝統的な手法。③ 滝口と流れ左奥には小さな滝(流れ)が見えた。水が動くことで庭に生命感を与え、「浄土」の象徴としても用いられていた。④ 植栽(松・低木・刈込)池の周囲には松やサツキ、日本庭園らしい丸く刈り込まれた低木を配置。これらの植栽は四季を感じるために計算されて配置され、春の花・夏の緑・秋の紅葉・冬の雪景色を楽しめるのであった。■ この場所の意味牛久大仏の庭園は「浄土の世界」をイメージして造られており、・水面の静寂・石の安定感・緑の優しさなどが調和した、非常に落ち着いた雰囲気の庭となっていた。滝口と流れ。「大心海(だいしんかい)阿弥陀如来(あみだにょらい)は大海のように広く深い慈悲と智慧のお心ゆえに「大心海」とも言われます。この池は阿弥陀如来そのものを顕わしています。」 ● 「大心海(だいしんかい)」とは?仏教で阿弥陀如来の心を形容する言葉で、「大海のように広く、深く、限りない慈悲と智慧を持つ」という意味がある。「心」が海のように無限に広がり、すべての存在を受け入れ救うという阿弥陀如来の性質を表した表現。● この庭園の池=阿弥陀如来を象徴看板にあるとおり、この池は単なる景観要素ではなく、阿弥陀如来の大いなる心を象徴するために造られた池 です。浄土庭園では、水面に「浄土」を表す意味があり、牛久大仏の庭園でもその伝統が受け継がれている。アジサイの花が開花中。近づいて。牛久大仏の胸部にある三つの長方形のスリット窓(展望窓)を下から見上げて。・大仏の胸(胸部外壁) を下からアップで撮影。・中央に 縦長の窓が3つ・下には袈裟(けさ)のひだを表した曲線の外装パネルが見えた■ この三つのスリット窓の役割① 展望窓(胸部展望室)牛久大仏の内部にはエレベーターで上がれる展望フロアがあり、高さ約85m付近(胸の位置)に展望室があった。そこから外を見るために設けられているのが、この3つの窓。② 外から見るとスリット状に見える理由・仏像の外観デザインを損なわないように細い形になっていた・内部の明かりが外に漏れさせない工夫でもある と。構造上、強風の影響を受けにくい窓形状■ この位置から見える景色胸の展望室からは牛久市一帯、天気がよければ筑波山遠方にはスカイツリー、反対側は霞ヶ浦方向まで見渡せる非常に見事な眺望とのことだが、この日は曇天で視界はあまり良くなかった。再び牛久大仏を正面から。ズームして。戻りながら、牛久大仏の境内にある「売店エリア(仲見世通りのような商店街)」 の様子を。青唐辛子 ちびっこみそ、れんこん関係の商品、にんにく味噌漬けごぼう、野沢菜、きゅうりなどの漬物などが並んでいた。牛久大仏の入口付近に並ぶ土産店のひとつ・「時代屋」。特に 漬物・佃煮・味噌・干し芋・れんこん加工品 など、茨城らしい特産品を多く扱っている店。牛久大仏の「阿弥陀如来像(立像)」を描いた絵馬。牛久大仏のスタンプ(御朱印ならぬ“記念スタンプ”)。丸い頭、柔らかい表情、赤ちゃん風の体型で描かれているのは阿弥陀如来をデフォルメした「子ども阿弥陀さま」 です。・頭の粒々 → 螺髪(らほつ)のデフォルメ・手を合わせている → 合掌(礼拝)・衣は阿弥陀如来の定型の袈裟(衣紋)・足は結跏趺坐ではなく、キャラ風に簡略化牛久大仏の巨大さとは対照的に、親しみを持ってもらうための“癒やしキャラ” に仕上げられていた。御朱印を頂きました。光雲無礙(こううんむげ)意味:阿弥陀如来の光明(慈悲の光)は、雲のようにすべてを覆い、何ものにも遮られることなく(無礙)、すべての衆生に届く。浄土三部経(特に『無量寿経』)に基づく思想で、“阿弥陀仏の光はあらゆる人を隔てなく照らす”という浄土真宗の中心思想。中央の角印は「東本願寺印」(ひがしほんがんじ)を 篆書体(てんしょたい)で分割して図案化したものであろうか。そして帰路へ。大黒PAにてトイレ休憩後、横浜ベイブリッジを渡る。海運業・T.S. Linesの大型トラック。横浜ランドマークタワーがある「横浜みなとみらい21」地区を望む。日本船籍の大型クルーズ客船「飛鳥Ⅲ(Asuka Ⅲ)」。船籍港 日本/横浜全長・全幅 230m×29.8m総トン数 52,265GT喫水 6.7m航海速力 最高20ノット横揺れ減揺装置 フィン・スタビライザー乗客数 740名乗組員数 約470名客室数 381室 (全室海側バルコニー付き)そして、定刻に無事到着し、この日の日帰り旅行を終えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.20
閲覧総数 302
-
31

バルト3国感動紀行10日間(その7 カウナス~ヴィリニウス ・4/22-1/4)
この日も早朝起床し6時過ぎにカウナスの街の散策に出発する。まずはホテルから5分強の場所にあるカウナス駅へ。ドイツ軍侵攻に伴い隣国ポーランドから迫害を逃れて流入してきた大量のユダヤ人に対し、当時在カウナス日本領事館に領事代理として赴任していた杉原千畝(ちうね)は、盟邦ドイツへの配慮から査証発給を避けるよう訓令を発していた本国外務省の意向に反し、ユダヤ人に対して日本通過を可能とした査証及び渡航証明書を発給して欧州からの脱出を支援したのであった。杉原千畝がリトアニアからの国外退去を命じられドイツへ移動する際、汽車が発車する直前まで「命のビザ」を発給し続けたのがこのカウナス駅なのだ。 列車案内板、時間は6:24。ホームに出て、杉原千畝の記念プレートを探したが見つからなかった。 新型の電車が出番を待っていた。ホームにはオランダ・アムステルダムまで1576km、ヴィリニウスまで104kmの表示が。 カウナス駅を後にし更に歩を進めると前方にあったのがKauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia教会。 次に訪れた聖ミカエル教会(St. Michael the Archangel Church)。これがライスヴェス通りの端に通せんぼするが如く立っている巨大な聖ミカエル教会。カウナスがロシア帝国支配下であった1891~1895年にかけて、正教のカウナス要塞として新ビザンチン様式で作られたとのこと。第一次大戦でカウナス砦が陥落後、鐘はドイツに運ばれ、教会は1919年まで閉鎖。そして二次大戦中はカウナス砦のローマカトリック教会となり、またその後ソ連占領下ではキリスト教が奪われ、アートギャラリーとして使われた。独立回復後は再びローマカトリック教会として復活したと。 天を仰いで横たわる男の像は何を訴えていたのだろうか? 聖ミカエル教会の裏側。 暫く歩くと左手にナショナルムク・シアーリオニス美術館。 壁に描かれた不思議な絵。悩む?女性像。ホテルの近くにはロシア正教会が二つ。 ロシア正教会 Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedra。ロシア正教会 Kristaus prisikėlimo cerkvė 。そしてカウナスのバスターミナル。 ホテルに戻り朝食。 9:30に出発しカウナス市内観光へ。最初に訪れたのが、15世紀前半に建てられたゴシック様式のヴィタウタス大公教会。この教会はヴィタウタス大公が、タタール征伐に出かけた際に、戦場で奇跡的に難を逃れたことがあり、感謝の印に建てたものと言われていると。 この教会はネムナス川の横にあった。ネムナス川の流れは思いのほか速かった。1946年にカウナスは大洪水の被害に遭い教会も一部が水没したと。教会に取り付けられたプレート。洪水被害の最高水位が印されていた。 15世紀に建てられたゴシック様式の傑作と言われる「ペルクーナスの家」。ヨーロッパの古い言い伝え的な話だが、かつてこの場所には雷神ペルクーナスを祀る神殿があったのだと。その言い伝えを裏付ける証拠として19世紀に修築が行われたときに、30cmのブロンズ像が見つかったのだと。ただ、「ペルクーナス説」、「タタールによってもたらされたインドの神像だという説」という二つの説で論争が起こったと。この論争が原因なのか不明だがその像は、失われてしまい現在では残っていないと。像は失われたものの、ペルクーナスの名前は定着し今に至っているのだと。 カウナス旧市庁舎へ向かう道を振り返る。左側がヴィタウタス大公教会 、右側が「ペルクーナスの家」。 カウナス旧市庁舎(Kaunas town hall)広場に到着。塔を持つ白い建物がカウナス旧市庁舎だが私には教会のように見えたのであった。16世紀半ばに建設され,1775年,『白鳥』にも例えられると云う現在のバロック様式の優美な姿に再建されたそうだ.ロシア支配下時代は政治犯の牢獄,後に皇帝の別宅等々に変遷し,現在は結婚式場や婚姻届の提出場所となっているのだと。また旧市庁舎の古い地下室は、現代作家の陶器博物館として利用されていると。 市役所の前は広場となっており,タリンでも旧市役所前に広場があったのと似ていた。青空に映える旧市庁舎。 旧市庁舎入り口。左側に黄色・緑・赤の3色のリトアニア国旗が。黄色は太陽、光、繁栄、緑は自然の美しさと自由と希望、赤は大地と勇気と祖国のために流された血を表していると。右側はリトアニア国章。赤い盾の中心に、銀色(白色)で右手で剣を振り上げた馬に乗った騎士が描かれていた。イエズス教会(St. Francis Church & Jesuit Monastery)。旧市庁舎の左手に見えたのは,17世紀建立で,修道院併設のイエズス教会。他の教会同様,ソ連占領下では他用途に転用され,独立回復後教会に復活したと。ぱっと見,このイエズス教会が市役所,旧市庁舎が教会に間違えそうな雰囲気も。 この「考える人」?は詩人マイロニス 。市庁舎広場の水飲み場? ベルナディン修道院とその前に立つ銅像。旧市庁舎の右背後に隠れたように建っているのが、ベルナディン修道院だが、その門の右に人物像が立っていた。ガイド氏からも説明がなかったが、聖人なのか?。手元のガイドブックにも触れられていない。 書かれていたMotiejus Valančiusで検索すると、カトリック主教だが、19世紀リトアニア・サモギティア地方では有名な作家だったらしい。旧市庁舎広場は絵になる光景。 カウナス大聖堂(Kaunas Cathedral)。正式には聖ペテロ&パウロ大聖堂(St Peter and St Paul's Cathedral)と呼ばれ,聖ペテロと聖パウロに捧げたカトリック教会。翌日首都ヴィリニュスで訪ねた聖ペテロ&パウロ教会も同じ名を冠してあった。赤いレンガ造りの外側は直線主体の比較的さっぱりした形態だが,ゴシック様式だそうで,1671年頃建てられたと。そして1655年の戦禍で被害を蒙り,1671年にいくらかルネッサンス様式を付加して再建されたと。 カナウス大聖堂の内部。さっぱりした外側に対し,内部は多くの彫刻やフレスコ画で埋められ,とても見応えが。壁や柱が淡いピンクやパープル等で彩色され,所々に金箔が貼られ,華やか。こうした色使いで,ケバケバ感なくして落ち着いた美しさを演出していた。改装の一環として,1771年にポーランドリトアニア共和国最後の国王スタニスワフアウグストポニャトフスキ(Stanislaw August Poniatowski:1732~1798年)が内部装飾の基礎を作ったと。1775年には聖書台や聖歌隊席が設けられ,現在の形態になったのは1800年からのさらなる改築の結果だとのこと。
2017.04.25
閲覧総数 167
-
32

旧東海道を歩く(原~富士)その6:富士市・吉原本町駅~青嶋八幡宮神社
『旧東海道を歩く』ブログ 目次富士市吉原一丁目にある『吉原本町駅』。1949年(昭和24年)11月18日 - 岳南鉄道の駅として開業。 2013年(平成25年)4月1日 - 経営移管に伴い、岳南電車の駅となる。単線のホーム。駅には日中のみ駅員が配置されているようであった。吉原本通りの商店街を歩いて行ったが、人の数はほとんど無くこれぞ「シャッター通り」。時間は14時前であったが。右手に『天神社参道』、奥に石鳥居が見えた。日本国旗が掲げられた石鳥居。東海道の宿場町、吉原。その鬼門を護る天神社は、宿が鈴川にあって「見付」と呼ばれたころからの産土神だ。社記は、建久4年(1193)源頼朝が富士の巻狩のおりに、天正18年(1590)豊臣秀吉が小田原攻めの途路に参拝したと伝え、明治19年の『神社明細書』は『駿河国神名帳』に列する「正五位下 富士河天神」にあてていると。『天満宮』と書かれた扁額。「当社は往昔吉原宿見附産土神総社にして天の香久山(香久山浅間宮)の高処(み)に在りましたが度度砂を押し上げられ、所を迫られ鎮座なり難く元吉原今井・鈴川の地に引き移りました。しかし延宝八(1680)年八月の台風津波にてまたも鎮座成り難く、天和ニ(1682)年現在の地に引き移りました。宝永五(1708)年回祿の災で宮殿灰燼となり、現今のご本殿は寛政元(1789)年のご造営であります。 御祭神は元来右記の二神が奉祀されており寛永四(1627)年現在の菅原道真公の神霊が相殿に合祀されたもので、計三神であられます。 社名に関わる御祭神の菅公につきましては平安前期の公卿、学者、三書聖の一人で世に学問文道の神として知られ、入学進学等の御祈願参拝者数多く、通称 天神様 と呼ばれ尊崇されております。 」『吉原祇園祭 天神社』。「毎年六月第二週頃の二日間、吉原の六つの神社の氏子町内が合同で行う祭りである。「吉原のお天王さん(おてんのさん)」と呼んで、夏の邪鬼祓いをしている。各神社の天王神輿は二日間に担ぎ出され、山車は二日間曳き回され、お囃子が演奏される。山車同士のすれ違いでは競り合いとなり、お囃子の腕比べが祭を盛り上げる。吉原祇園祭の六社は①天神社 ②木之元神社 ③山神社 ④八坂神社 ⑤八幡宮 ⑥和田八幡宮」であると。主な会場となる吉原商店街には、約1kmにわたって200軒を越す露店が立ち並び、人出は二日間で20万人を超えるのだと。天満宮の牛さん。興味の在る方は天満宮と牛の関係⬅リンクを参照下さい。手水舎。ここにもウッシーが。『拝殿』。昔はかなり大きな神社だったようで、源頼朝が富士の巻狩のおりに、天正18年(1590)豊臣秀吉が小田原攻めの途路に参拝したと。境内に咲く紅梅であろうか?『菅原道真公の石像』。色彩も豊かな見事な拝殿の彫刻。拝殿を正面から。そして天満宮を後にすると、富士市の汚水マンホールの蓋がこれも色彩豊かに。富士山と白波のデザイン。「ふじし」「うすい」の文字。「蓋に描かれいる富士山の「山頂方向」に水が流れる設計になっているのだと。富士山に使われている赤色から、葛飾北斎の「富嶽三十六景」の朝焼けに染まる富士山を描いた 「凱風快晴」から?。『旅籠 鯛屋』創業1682(天和2)年、吉原で唯一江戸時代から経営を続けている旅館。幕末には清水次郎長や山岡鉄舟が常宿としたと。江戸から14番目も宿場『吉原宿』。原から吉原まで東西13km、南北2kmの広大な沼地があったので「葦の茂った原」から吉原と名付けたと伝わる。吉原宿は開設から約80年の間に、度重なる津波や高潮の被害に遭い、二度所替えをした。そのため東海道は大きく北へ迂回することになり、右手に見えていた富士山が、左手に見えるようになり「左富士」と呼ばれる景勝地となった。移転後の吉原宿の町並み長さは東西1町10間(約1.3km)。吉原の町並みは近代化され昔の面影は残っていないのであった。『東海道 吉原宿』。蒲原宿(三里:12km)、京都(九十里:354km)であると。『長さん小路』と書かれたプレートが柱に。ザ・ドリフターズのリーダーとして活躍し、「踊る大捜査線 THE MOVIE」など映画やドラマで存在感のある俳優として活躍されたいかりや長介(本名・碇矢長一)は、1931年東京都墨田区に生まれ、1944年小学校卒業と同時に富士市に疎開し、青春時代の16年間を富士市で過ごし、富士市にゆかりのある人物であると。勤務先の製紙工場の仲間とバンド活動を始め、吉原のダンスホールなどでの演奏を経て1959年に28歳で上京し、ミュージシャンからザ・ドリフターズのリーダーとして活躍の場を広げ、テレビ「8時だヨ!全員集合」は最高50.5%の視聴率を記録するなど国民的人気を集めたのであった。しかし14時過ぎであったが、この路にも人影は少なく。旧東海道を中央駅交差点で左折して進むと交差点の角に『かりん糖 和田屋』が。2012年開店。旭製菓の「隠れ河原のかりん糖」専門店。ここを右折して進む。そして更に旧東海道(県道22号線・三島富士線)を進んでいくと、左手に曲がった場所にあった『曹洞宗 芙蓉山 立安寺(りゅうあんじ)』を訪ねた。境内左手に『六地蔵』。美しい仏像の姿が刻まれた石碑。「福聚海無量、是故應頂禮」の文字も。『妙法蓮華経』観世音菩薩普門品第二十五よりの言葉であり福の聚(あつま)れる海は無量なり この故に応(まさ)に頂礼すべし と。『本堂』「当寺の由緒書きによりますと、保泉寺の第二世護峰吟守和尚は、寛永の頃、ささやかな隠居所を作って住んでいました。たまたま江戸深川の材木商 高須屋善助(兄)と伊藤善二郎(弟)という兄弟が、伊勢参宮の帰り道に寺のある吉原宿に泊まったところ、夜中に夢の中で悪龍に悩まされましたので、その龍霊を供養しようと考え、近くの庵居に住んでいた吟守和尚と協力し、一寺を建立して、山寺号を芙蓉山龍安寺としたのが、立安寺の始まりです。創建当時のこの辺りは、まだ富士川の川原に広がる葦原でした。以前、この寺の境内には、太子堂と観音堂とがありましたが、今では古くなった為取り払われ、そこにお祀りしてあった聖徳太子像と石造の聖観音像は、現在本堂に移されて安置されています。」本堂前の白き仏像。次に『浄土宗 称念寺』を訪ねた。富士市中央町、旧東海道吉原宿の西外れにある浄土宗鎮西派の寺。捨世派の祖称念によって建立された「宝樹院」が前身とされ、「前富山宝樹院称念寺」と号する。本尊は阿弥陀如来。境内に入ると、まず山門が目に入った。鉄筋コンクリート製の2層建築で、下層は仁王門、上層は法隆寺夢殿風の八角円堂となり、「庚申山門」の扁額を掛けていた。界隈に類例のない奇抜なレイアウトで、漬物石をのせた樽のように重々しく、頑丈な造り。上層に祀る青面金剛(廃寺となった末寺・庚申院の本尊)が名称由来らしい。『本堂』。山門を抜けると、和順霊堂が南向き、本堂が北向きで正対するように建っていた。現本堂は昭和8年再建されたと。本堂蟇股の透かし彫りが見事であった。和順霊堂の内部であっただろうか?『六地蔵』。円空仏風の木彫り仏像。稱念寺の前を流れる小潤井川に架かる錦橋から。青葉通りを錦町交差点に向かって歩く。正面に見えた富士山の山頂は完全に雲に隠れてしまった。錦町交差点を横切ると、『(新)吉原宿・西木戸跡』。本来の西木戸跡はもう少し北側にある。青葉通りのここを左折して旧東海道を更に進む。 ここは市役所南東。この付近にはQRコード付きの案内図が。『青嶋八幡宮神社』の駐車場にあった漫画絵。青嶋八幡宮の由緒書は漫画で描かれていた。これらの絵は、八幡宮神社中興に際し、富士市吉原出身のマンガ家、望月あきらさんから寄進いただいた絵馬及び紙芝居の原画から写したのだと。石鳥居と社殿。『青嶋八幡宮神社中興の碑』。徳川綱吉の時代に、高潮などの被害で苦しめられているにもかかわらず検知の労役が村人に課せられ、これに異を唱えた名主・川口市郎兵衛は、処刑されてしまいました。村人は市郎兵衛に感謝し、密かにこの青嶋八幡宮に祀ったと。境内の川口市郎兵衛の碑や石碑群。『道祖神』。 ・・・つづく・・・
2019.04.21
閲覧総数 584
-
33

横浜市泉区の古道を巡る(その30) 中田町宮ノ前公園~石巻康敬の墓~稲荷社~中田寺(1/2)
「御霊神社」を後にして、県道22号線・長後街道に向かって進む。「中田町宮の前公園」が左側にある「東中田小学校入口」交差点まで進む。交差点角の公園入口には2基の石碑が。二基の「庚申塔」「中田町宮ノ前公園」の南端、東中田小学校入口の信号柱の傍らに2基の庚申塔が立っていた。横浜市泉区中田東4丁目58。大きい方は元禄15年(1702)2月、南ふじ沢道、北八王子道と刻まれて、道標もかねていた。小さい方は安政7年(1860)2月の建立。「石巻康敬の墓」に向かって左折し住宅街を進み右に折れる。右手に「横浜市地域史跡 石巻康敬の墓」があった。江戸初期に中田村の領主になった石巻康敬の家は、戦国時代に小田原北条氏の評定衆や相模西部の郡代を勤めた家で、本国は愛知県姫街道沿いの、石巻山を越える本坂峠を下った辺りです。康敬は中田の石巻館で23年間を過ごし村の発展に力をそそぎました。慶長18年( 1613 ) 10月1日80歳で逝去、持仏の観音堂(稲葉堂)の地であったこの地に眠っています。横浜市泉区中田東4丁目56-19。「横浜市地域史跡 石巻康敬(いしまきやすたか)の墓石巻下野守康敬は小田原北条家の重臣で北条氏康、氏政、氏直の三杙に仕えた後徳川家の旗本に入り、中田村を知行し、慶長十八年(一六一三)八十歳で逝去しました。その地に七代の孫、康福が康敬の一五〇回忌の法要(宝歴十ニ年、一七六ニ)に当って、撰文を岡井孝先に依頼して墓碑を建立しました。」石段を上がって中央墓石に近づく。「墓誌」碑。「墓誌江戸時代中田村領主鎮守御霊神社再興中田寺開基石巻康敬殿法名至徳院殿譽歓翁宗喜大居士慶長十八年十月一日逝去まで二十余年当地開発に務む宝暦十二年九月康敬百五十回忌法要に当たりその末裔康福墓碑を建立す。爾来二百十二年を経過今年法然上人浄土開宗八百年に当たり当山慶讃事業として開基の遺徳を偲び墓所の大改修を志し完工し報恩謝徳の微意をささげまた永く当地開発の一端を後世に伝えることを願い謹んで誌す。維持昭和四十九年浄土開宗八百年記念修復昭和四十九年十月吉詳貯徳山盁満院中田寺十九世住職香川隆善撰」「故従五位下(じゅうごいのげ)下野守石巻君墓」と刻まれた墓石が中央に建ち回りは岩垣で囲われていた。彼の功績をたたえる和歌『中田寺の御詠歌』の『福田の 石巻さまの 御功徳 貯めたる中に 念佛聞こゆる』が刻まれていた。そして来た道を引き返し県道22号線・長後街道に交わる道を渡り奥に進むと向かいには石の鳥居の小さな「社」があった。「稲荷社」。横浜市泉区中田北2丁目14。「社殿」。そして次に訪ねたのが「中田寺」。横浜市泉区中田北2丁目11-41。江戸期に中田村の領主であった石巻康敬(いしまきやすたか)が開基となり、慶長17年(1612)に本誉良廓上人(ほんよりょうかくしょうにん)が創建した、本尊阿弥陀如来像を置く浄土宗の寺。境内には石巻康敬の持仏堂であった十一面観音を置く稲葉堂や、「南無阿弥陀仏」と刻まれた十七世住職香川法隆上人(かがわほうりゅうしょうにん)の頌徳碑、当地小島家出身の中田寺二世辨良上人(べんりょうしょうにん)の墓や力士戸田川の墓があった。寺号標「浄土宗 貯徳山 示福院 中田寺」正面に「山門」。山門屋根に上がる蕾付き牡丹の飾り瓦が印象的。扁額「貯徳山」。「貯徳山 示福院 中田寺」碑。ここにも『中田寺の御詠歌』の『福田の 石巻さまの 御功徳 貯めたる中に 念佛聞こゆる』が刻まれた碑が。「山門」を潜り境内に。正面に「本堂」。「森菊松君碑」。日露戦争で明治37年(1904年)に戦死した陸軍上等兵であると。「六地蔵」。「六地蔵」の横に地蔵さま。「稲葉堂」。扁額にも「稲葉堂」と。「慰霊塔」。「鐘楼」。鐘楼の屋根には「蕾付き牡丹の飾り瓦」が。「梵鐘」「南無阿弥陀佛」碑。(昭和15年(1940年)銘)と刻まれた香川法隆上人の頌徳碑(しょうとくひ)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.03.30
閲覧総数 887
-
34

古都「鎌倉」を巡る(その31): 円覚寺(1/7)・塔頭白雲庵~伝宗庵~富陽庵~北鎌倉幼稚園~円覚寺・三門~松嶺院
『鎌倉散策 目次』👈リンク「雲頂禅庵」の前の風情ある板塀と白壁の道を振り返る。そしてここを左に曲がると石段が続いていた。円覚寺は今までに何回か訪ねたが、この道、塔頭を訪ねたのは初めてであった。石段を上り終え道なりに右に曲がり進むと左手にあったのが「白雲庵」への入口。「白雲庵」碑。花崗岩の石段を上っていくと大谷石の石垣と花崗岩の石畳が綺麗な「白雲庵」の「本堂」が左手に。「本堂」前の対の「七重石塔」。「本堂」。臨済宗大本山「円覚寺」の塔頭のひとつである。円覚寺第十世で暦応3年(1340)10月4日に示寂(じじゃく)した東明恵日(とうみんえにち)禅師の塔所(たっしょ)。塔所とは僧侶の墓所のことと。正和年間(1312~16)に退居寮として開創。禅師は曹洞宗を修めた中国元の高僧で、1309年、時の執権北条貞時の招きで来日し、1310年円覚寺第10世となり、暦応3年当寺にて遷化するまで、建長寺(18世)、寿福寺などの住職を務めた。また、白雲庵学林を形成し、関東五山文学の中心拠点となった。室町時代末期に臨済宗に転宗。扁額「白雲庵」。「白雲庵」の名の由来は、禅師が中国白雲山の住職だったこと、また「白雲抱幽石」という漢詩の一節に因んでいる。円覚寺には、江戸時代前期には40の塔頭があった。現在は18寺の塔頭があり、そのうち住職のおられるところは13寺。白雲庵はその中で最も古い塔頭である と。庫裡であろうか。右手に五重石塔が三基。扁額「幽石軒」墓地の前の見事な石塔。赤い牡丹の花。近づいて「本堂」を斜めから。少し離れて。「白雲庵」を後にして進むと石畳の道路脇には顔だけの石像が。羅漢像でもなさそう・・・!?。頭だけなのでかなり不気味な光景。なぜここに??まとまって、現代アート??更に進むと右下に下がる石段があり「塔頭 伝宗庵(でんしゅうあん)」と刻まれた石碑があった。しかし、この「塔頭 伝宗庵」も一般開放はしていない模様。円覚寺の「塔頭 伝宗庵」は、第十一世南山士雲(なんざんしうん)の塔所。本尊:地蔵菩薩。士雲が自らが開いた。土紋装飾の「木造地蔵菩薩坐像」は国の重要文化財(鎌倉国宝館に寄託)。その他、室町時代作の「木造南山士雲坐像」、「慈恩寺詩板」、「中世文書」を伝えている。境内には、北鎌倉幼稚園が設置されている。「伝宗庵」を樹の間から見る。左手にあったのが「富陽庵」と刻まれた石碑。石段の上に「山門」が見えた。「山門」。富陽庵(ふようあん)は、第六十一世東岳文昱(とうがくぶんいく)の塔所。本尊は文殊菩薩。文昱は、壽福寺に住し、建長寺七十一世となり、その後、円覚寺に移った。開基は上杉朝宗。開祖木像と大仙庵開祖桃渓徳悟像を安置している。その他、百二世大雅省音像などの蔵物があり、1416年銘の開祖供養塔がある。「富陽庵」の境内。ここも一般開放していなかった。更に進むと右側に「北鎌倉幼稚園」の正門が。「幼稚園 園内」。「北鎌倉幼稚園」。北鎌倉幼稚園は、戦後人心の虚脱と混迷の中で、幼児の将来を案じた地元の人々の要望に応え、当時円覚寺管長であった朝比奈宗源老師が設置者となり、昭和23年4月より開園した幼稚園と。そして「道標」今まで訪ねてきた3つの庵の名が。「これより左え 冨陽庵 白雲庵 雲頂庵」そして坂道を下って行くと受付もなく「三門」の横に出たのであった。「円覚寺」案内図。そして久しぶりに、「円覚寺」中心部の散策をゆっくりと。「三門」を正面から。楼上には十一面観音、十二神将、十六羅漢像が安置されている。現在の山門は、天明年間(1781~89年)、第189世誠拙周樗によって再建されたもの。山門は「三門」とも呼ばれ、三解脱門の略。解脱・涅槃に至る方法である3種の三昧(さんまい)。一切を空と観ずる空解脱、一切に差別相のないことを観ずる無相解脱、その上でさらに願求(がんぐ)の念を捨てる無願解脱。扁額「圓覚興聖禅寺」は伏見上皇の勅筆と伝えられている。「山門(三門)県重要文化財山門は三解脱門(空・無相・無願)を象徴するといわれ、諸々の煩悩を取り払う門とされます。山門を通って娑婆世界を断ち切り、清浄な気持ちで佛殿の本尊さまをお参りしなければならないとされます。現在の山門は一七八五年(天明五年)開山五百年遠諱の年に大用国師(誠拙周樗)によって再建され、「円覚興聖褝寺」の扁額は伏見上皇(北条貞時の時代)より賜りました。楼上に十一面観音、十二神将、十六羅漢像をおまつりしてあり毎年六月十八日に楼上で観音懺法(観音さまに懺悔をする儀式)が行われます。また毎年八月には山門を取り巻いての盆踊りがにぎやかに行われています。」「三門」の天井。「三門」を抜けると、その先に「仏殿」がある。巨大な「仏殿」は後に訪ねた。左手に見えたのが「松嶺院」。近づいて。扁額「松嶺院」。「松嶺院」を訪ねることにする。「山門」。扁額は「圓通山」。「山門」の先の左手には見事な牡丹の花が。100円を賽銭箱に入れて境内に入る。「円覚寺」境内の塔頭。「円覚寺」第150世・叔悦禅懌(しゅくえつぜんえき)の塔所。もともとは「不閑軒」といわれていたが、松嶺院月窓妙円尼から寺領の寄進があったことから「松嶺院」と呼ばれるようになった と。「松嶺院」の建物の周囲・「遍路道」を巡り牡丹を中心とした花々を楽しむこととした。「たんちょうそう(丹頂草)」。「本堂」。 <宗派> 臨済宗円覚寺派 <山号寺号> 圓通山(えんつうざん)松嶺院 <開山> 廣圓明鑑禅師・大拙祖能 松嶺院は、1535年(天文4)に示寂した円覚寺第150世の叔悦禅懌(しゅくえつぜんえき)の 塔所で、もともとは不閑軒と称し寺地には円覚寺第40世の大拙祖能(たいせつそのう)の塔所で ある。青松庵があったと伝えられており、足利高基の息女である松嶺院月窓・妙円尼 (みょうえんに)から寺領の寄進があったことなどから改称された。 境内には木造の大拙祖能坐像や木造の叔悦禅懌坐像が安置されている。その先に小さな枯山水の庭があった。そして「遍路道」沿いに咲く様々な色・種類の牡丹の花を楽しんだのであった。曲がった先にも。この日が「遍路道」の牡丹の花見のピークか。菩薩立像。白壁沿いに緩やかな階段を上る。歩いて来た道を振り返る。「松嶺院」の先に「円覚寺」の「三門」と「仏殿」が見えた。これでもかと真っ赤な牡丹。藁葺の「選仏場」の先に「仏殿」が見えた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.05.24
閲覧総数 745
-
35

大和市の神社仏閣を巡る その27: 聞称寺~正一位伏見稲荷神社~本道宣布会皇神乃宮~中央林間駅~帰路へ
【大和市の神社仏閣を巡る】目次真宗大谷派(京都 東本願寺派)の「聞稱寺(もんしょうじ)」に到着。大和市南林間6丁目9番11号。狭い参道を進んでい行く。正面に「親鸞聖人像」。お顔をズームで。掲示板。「精一杯咲くとどんな花も美しい」。残酷な現実だが、人もまた花である。 いつまでも若く美しく咲き続ける花はない。しかしだからこそ花は美しい。精一杯生きる人はやはり花のごとく美しい と最近しみじみと感じる自分がいるのだ。「本堂」浄土真宗大谷派妙香山聞称寺の支院として、平成22年2月に建立。「蓮如上人像」。お顔をズームで。小田急江ノ島線に向けて東に進む。「大和学園前」交差点角の「聖セシリア小学校・幼稚園」の校門。「大和学園前」交差点を渡った角にあった「聖セシリア 女子中学校・高等学校」の校門。1929年 伊東静江により大和学園を創立。大和学園女学校開校。1930年 大和学園高等女学校に改称。1947年 大和学園中学校開校。1948年 大和学園高等女学校を大和学園女子高等学校と改称。1980年 聖セシリア女子中学校・聖セシリア女子高等学校と改称。2013年 高等学校からの生徒募集を停止し、完全中高一貫校化。2020年 高等学校からの生徒募集を再開。 とウィキペディアより。交差点の名前「大和学園前」は歴史を残すためにそのままになっているのであろうか?更に進むと「聖セシリア 女子中学校・高等学校」の脇門。そして小田急線の「中央林間4号踏切」を渡る。踏切を渡りながら「中央林間駅」方面を見る。「南林間駅」方面を見る。踏切を渡り左折し線路沿いの道を「中央林間駅」方面に進む。歩道には「天然記念物 なんじゃもんじゃの木」のタイルが埋め込まれていた。「天然記念物 なんじゃもんじゃの木」は深見神社境内にあった。「市の花 野ぎく」。「たぶの木」、「市の木 山さくら」。「天然記念物 けやき」。大津家の敷地内にあるケヤキ、特に目につく巨木(樹高25m、胸高周囲4.2m、樹齢約500年)。大和市の重要文化財(天然記念物)に指定され、「かながわの名木100選」にも選定されている。道路脇にあった「大和市の古地名」案内板。「大和という地名の起こりは、明治22年4月に下鶴間村、深見村、上草柳村、下草柳村の4村が合併して鶴見村となったものの村名などについて紛糾し、明治24年9月に大和村と改名されたことに起因します。明治22年の市町村制の実施により、一般的には江戸時代の村名が大字となり、検地帳などに小名、一筆書きなどといわれた耕地名が小字となりました。しかし、市域では江戸時代にっくられた絵図がほとんどないことや、古くからの区画整理などの実施や近年の住居表示の実施などにより、しだいに小字が用いられなくなり、失われつつあります。聞き取り調査により地名やその他の名称を掘り起こしてみたのが右の図です。朱色が小字、黄色が地域に伝承された名称で、おおよその位置に示しています。大和市教育委員会」そして県道50号線・座間大和線下を潜る。そして150m程進むと右手角にあった「正一位伏見稲荷神社」。「稲荷大神の御神徳伏見稲荷大社は、今を遠く千ニ百七十余年の昔、稲荷大神が稲荷山の三ケ峯に御鎮座せられたのにはじまると、伝えられております。稲荷大神とは宇迦之御魂大神(うがのみたまのおおかみ)、佐田彦木神(さだひこのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、田中大神(たなかのおおかみ)、四之大神(しのおおかみ)の五柱を総称した御名であり、正一位稲荷五社大明神ともたたえられております。その御神徳は、世の人々からそれぞれの精神(こころ)、生命(いのち)、生活(くらし)生業(つとめ)、生産(つくり)の守護神として篤く信じられ、御神威は、心身健全、五穀豊穣、商売繁昌、福徳円満、交通安全等々に極めて著しいのであります。」朱の鳥居の扁額は「正一位稲荷大神」。「社殿」。近づいて。後にして振り返る。更に「中央林間駅」方面に進み右折し住宅街を右に折れ進む。汚水管マンホールの蓋大和市の市の花「のぎく」をデザイン。「やまとし」「おすい」の文字。 そして「本道宣布会 皇神乃宮(はんどうせんぷかい すめかみのみや)」の一の鳥居に到着。直線的なデザインが特徴の「神明鳥居」大和市中央林間4丁目19-12。参道を進むと二の鳥居が現れた。木が鬱蒼としていたが、狛犬は無し。「境内」の「案内板」。「神明造」の「拝殿」。天照大御神をご神体とする神社。「拝殿」に近づいて。「中央林間東急スクエア」前の道を西に進む。そして「中央林間駅」東口のロータリーに到着。「大和の文化財 中央林間駅周辺」。昭和初期の林間都市林間都市は、スホーツ都市の機能を備えたものとして計画されました。クラブハウスを中心とした四面の野球グラウンドやテニスコート、ホッケー場、ラグビー場が整備されました。この企画運営には、雑誌「べースボール」の編集に携わっていた鷲沢與四ニ(衆議院議員)や田中清隆(画家)が参加しました。また、昭和初期の林間都市には吉井勇(歌人)、高木蒼梧(徘人・俳文学者)、唐木順三(文芸評論家)、龍瞻寺雄(作家)らが移り住んでいます。檀一雄作家 明治45年~昭和51年昭和26年に「真説石川五右衛門」で直木賞を、昭和51年の没後には、連作長篇「火宅の人」で読売文学賞と日本文学賞を受賞しています。昭和35年、檀の母とみは練馬区南田中の家ーー檀が昭和23年から25年まで住んでいた家ーーに、檀の長男太郎を預かっていました。ですが、太郎の通う玉川学園には遠かったことから、南田中の家を売却し、中央林間(一丁目)に家を購入、移り住みました。とみと太郎が暮らしたこの家を、檀もたいへん気に入り、よく友人たちゃ編集者を案内しては、夜おそくまでの酒宴をひらいたといいます。龍膽寺雄(りゅうたんじゆう)作家 明治34年~平成4年昭和3年、雑誌「改造」創刊十周年記念の懸賞小説に「放浪時代」が当選。昭和初頭のモダンライフの反映ともいえるモダニズム文学流行の波に乗り、一躍文壇に登場。反プロレタリア文学を標傍する新興芸術派倶楽部の結成に奔走し、その中心的存在でした。また、シャボテンの栽培、研究で国際的に知られています。鷲沢興四ニに奨められ、昭和10年に中央林間(二丁目)に転居。滝山街道【古道】--------- 戦国時代の滝山城(八王子市)と玉縄城(鎌市)を短距離で結び、小田原北条氏の 領国支配上重要な道でした。巡見使道【古道】---------- 巡見使は将重の代替わりに府が派遣する調査団。天保9年、十ニ代将重家に就任の 際の巡見使が通ったといわれる。矢倉沢往遠【古道】--------- 江戸時代東海道の脇往還。港区青山なら、南足柄市矢沢一足柄峠へ至る。 大山道ともいい参詣に利用されました。「林間都市計画と小田急江ノ島線」小田原急行鉄道株式会社は、昭和2律に小田原線を開通、同4年には江ノ島線を開通しました。この鉄道建設と平行して江ノ島線沿いの約80万坪に、「林間都市」と称する都市計画がたてられ、「中央林間都市」・「南林間都市」として具体化されました。昭和16年、駅名にあった「都市」の文字がなくなり今日に至っています。都市デサインは、格子状の街路を基調とし、駅前広場を配置しています。現在も、当初のデザインは大さく改変されることなく残されています。「つきみの駅」周辺の遺跡。正面に東急東横線「中央林間駅」表示板「中央林間駅」2Fの「大阪王将」で腹こしらえ。「餃子」も。そして小田急線を利用してこの日の大和市散策を終え、「大和市の神社仏閣を巡る」を延べ3日間で完遂し帰宅の途についたのであった。この日の歩数は「23,411歩」であった。明日から再び「古都「鎌倉」を巡る」をアップさせていただきます。 ・・・もどる・・・ ・・・大和市 完・・・
2021.09.14
閲覧総数 2184
-
36

源頼朝と北条氏ゆかりの伊豆の地を訪ねる(その16): 真鶴・源頼朝船出の浜碑~岩の浜~瀧門寺~魚座
県道739号線を利用して「岩漁港」に向かって進む。左手にあったのが「石工先祖の碑」。「石工先祖の碑平安末期に石材業を始めた土屋格衛や江戸城造営の採石に当たって小松山に口開丁場(くちあけちょうば)を開拓した黒田長政配下の7人の石工たちの業績をたたえ、江戸末期に再建された供養碑がこの山の上にあります。真鶴町は、こうした人々の開発の努力を受け継いで、いまなお、名石小松石に代表される全国有数の石材産地としての伝統を誇っております。」石段の上の小さな広場にあった「石工先祖の碑」。真鶴の石材業は、平安時代末、京より下ってきた土屋格衛という人物によって始められたのだといいます。源頼朝が鎌倉に幕府を開くと、多くの巨石が鎌倉へ運ばれ、寺社などの建設に使用されたそうです。江戸城築城の際にも大量の石が積み出されました。「石工先祖の碑」は、真鶴石材業の生みの親・土屋格衛と、江戸城を築くための採石にあたった黒田長政支配下の7人の石工たちの業績をたたえた碑。そしてその先の三叉路の角にあったのが「謡坂」碑。「謡坂之記」碑。下記はネットから。「この地の謡坂荘主高井徳造氏が謡坂の由来を知り、頼朝の遺跡を顕彰するために昭和9年1月に建てた碑であると。長い碑文を要約すると「治承4年8月23日、石橋山合戦に敗れ8月28日にここまで逃れてきた頼朝主従が土肥実平の館のある西の方を望むと土肥村から兵火が上がり炎が空を覆った。実平は之を見て頼朝が危険を脱したことを喜び、併せてその前途を祝福し『土肥に三つの光あり。第一には、八幡大菩薩、我君を守り給う和光の光と覚えたり。第二には、我君平家を討ち亡ぼし、一天四海を照らし給う光なり。第三には、実平より始めて、君に志ある人々の、御恩によりて子孫繁昌の光なり。嬉しや水、水、鳴るは瀧の水。悦び開けて照らしたる土肥の光の貴さよ。我家は何度も焼かば焼け。君が世にお出になったら広い土肥の椙山に茂る木を伐って邸など何度でも造りかえる。君を始めて万歳楽我等も共に万歳楽』と勇み踊り謡った地であり爾来此地は謡坂と称されるようになった。この十二年後、頼朝公は建久三年征夷大将軍に任じられ鎌倉幕府をお開きになった。公の史跡は天下に多いけれども、この地は挙兵の当初、敵の虎口を脱した地であることを石に刻んで後世に伝えるものである。」「和光の光」とは仏が日本の地に神として顕れるその光をいい、土肥実平が自分の家が敵勢に焼かれるのを見て「あの光は、我が君や我々の未来を照らす光だ。」と謡い舞ったという『源平盛衰記』にちなむ話。「神奈川県の地名」によると、岩村について敵の追跡を免れた頼朝が喜びのあまり「祝村」と命名したという村民の伝承を記しているのだ」と。「謡坂治承4年(1180年)石橋山の合戦に敗れた源頼朝の一行は、箱根山中を逃れでて、岩海岸から房州(千葉県)へ向けて船出しました。その途中、無事を祝い再起を願って土肥実平がうたい踊ったと「 源平盛衰記 」 にあります。この付近の謡坂という地名は、それに由来するといわれます。」そして再び「真鶴町岩の浜」・岩漁港入口(町道1号線側)まで戻る。「源頼朝船出の浜」碑が「源頼朝開帆處」碑と背中を合わせる位置にあった。「石橋山の合戦 治承4年(1180年)に敗れた源頼朝は、箱根山中や鵐窟(しとどのいわや)などに難をのがれ、謠坂を経てこの海岸から房州(千葉県)に向かって船出し、虎口を脱したと伝えられています。船出に協力した村民たちの鮫追船(さめおいぶね)2そうについては税が免除されたといわれ、小田原北条氏によるその確認の文書が伝えられています。海岸東の崖の下には、塩谷温博士の文による源頼朝開帆記念の碑があります。」「岩の浜」は真鶴半島唯一の砂浜の海岸であると。「弁天島」。岩海岸(岩海水浴場)の左手にある直径10mほどの島である。波間に浮かぶ岩に聳える松と鳥居があり、背後にはかながわの橋100選に選ばれた岩大橋がある。朱の鳥居が。奥には社があったのだろうか。それとも弁天島自体が社なのであろうか。再び「弁天島」と「岩大橋」を。石橋山の戦い後の源頼朝の敗走ルートをネットから。 【https://ameblo.jp/oyomaru-0826/entry-12336753749.html】より以下は2月13日(日)のNHK「鎌倉殿の13人(6)「悪い知らせ」」のテレビ画面より。北条時政(坂東彌十郎)と三浦義村(山本耕史)らは頼朝を待つが、敵に追われて先に安房へと舟で逃亡。源頼朝(大泉洋)と北条義時(小栗旬)も追って真鶴町「岩海岸」より土肥実平が手配した小舟で安房へ逃げる。1艘(そう)の小舟(平舟)に、武将2名程度と、漕ぎ手3名の組み合わせだったと。頼朝他6人の武将が同行し(七騎落ち)とのことであるので、4~5艘(そう)の小舟(平舟)で安房に逃げたのであろうか。真鶴から安房への海上ルート。そして何とか安房国・「竜島海岸」に上陸。湯河原町の城願寺に伝わる七騎落ちの伝説によると、頼朝とともに真鶴岬から安房国へ向けて船出したのは、安達盛長・岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱。しかし、ここには北条義時の名はない、史実は如何に?そして、主従七騎のうち、土肥実平の息子・小早川遠平(こばやかわ とおひら)は舟に乗らず、伊豆山権現へと向かった。頼朝の妻・北条政子へ、頼朝が伊豆を出発してからこれまでの経緯を知らせるためであった と。安房国へ命からがら逃げ延びた頼朝。そしてこちらが「源頼朝」が上陸した「竜島海岸」。以下の3枚の写真はネットから。「源頼朝 上陸地」碑が2基。安房国へ逃れた時に頼朝が上陸した地点については、伝承をもとに数か所の地名があげられてきた。なかでも、安房郡鋸南町竜島(りゅうしま)と館山市洲崎は、その代表的な地点として有力視されてきたが、大森金五郎文学博士の研究により、『吾妻鏡』の「武衛相具実平、棹扁舟令着于安房国平北郡猟島給」(頼朝、土肥実平を相具して、扁舟棹さして、安房国猟ヶ島に着かしめ給う)という記載などから、現在の竜島付近が上陸地点として認定された。先に到着していた北条時政らが迎えたのだという。安房郡鋸南町竜島165-1。「源頼朝上陸地治承四年(一一八〇)八月、伊豆で挙兵した源頼朝は、二十三日、平家方の大庭景親との石橋山の戦いに敗れ、真鶴より海路小舟で脱出し、安房国へ向かいました。「吾妻鏡」によれば、「二十九日、武衛(頼朝)、(土肥)実平を相具し、扁舟に棹さし安房国平北郡猟島に着かしめ給う。北条殿以下人々これを拝迎す」とあり、上陸地点の猟島が現在の鋸南町竜島とされています。頼朝はここで先着の北条時政、三浦義澄らと合流し、再起を図りました。当時房総には、下総の千葉常胤、上総の上総広常、安房の安西景益、丸信俊ら源氏恩顧の豪族が多く、また内房沿岸は対岸三浦半島の三浦氏の勢力範囲でもあり、頼朝が房総での再起を選んた理由と考えられています。房総一の兵力を誇っていた上総広常のもとへ向かうべく、外房の長狭(鴨川市)へ進んだ頼朝一行は、九月三日、平家に味方する地元の豪族長狭常伴の襲撃を一戦場で撃破。ひとまず安西景益の館(南房総市池ノ内)へ入り、各地の豪族へ使者や書状を送り、情勢を見極めます。その間、洲崎神社(館山市)、丸御厨(南房総市丸山)などへ足を運び、十三日、安房を進発して兵力を加えつつ房総を北上、鎌倉へと入りました。東国の豪族たちを糾合し、平家を減ぼし、鎌倉幕府という武家政権を樹立した源頼朝の再起の一歩はここから始まったのです。」そして真鶴半島巡りの最後に訪ねたのが「瀧門寺(りゅうもんじ)」「瀧門寺」は神奈川県足柄下郡真鶴町岩にある曹洞宗の寺院である。山号は久遠山不動院、本尊は阿弥陀如来(但唱作)。真鶴町指定文化財の五層塔と頌徳碑と宝篋印塔がある。「宝篋印塔」と「石仏」。「奉納大乗妙典六十六部供養」と刻まれた石仏。「宝篋印塔」。基台を含め6.8m、明和四年(1767)に十三世鳳洲了悟和尚(ほうしゅうりょうごおしょう)が万民の幸せを祈って建立したもの。多くの善男善女の浄財と労力奉仕により、宝篋印塔が建立されたと刻まれている。宝篋印塔は小松石による関東随一の石造物といわれている。小松石は箱根の火山活動によってできた安山岩。真鶴しか採れない石で、鎌倉に幕府を開いた源頼朝も小松石の巨石を運ばせたのだという。「観世音菩薩」碑。参道の左手には風雪に耐えた多くの石碑が並んでいた。六地蔵。山門への石段に向かって進む。山門への石段の前。右手に「五層塔」が。「五層塔」(左)と「大乗妙典六十六部供養塔」(右)。「五層塔」は、万寿冠者を葬った塔で、もとは光西寺(廃寺)にあったものだという。万寿は、土肥遠平の子で、母は伊東祐親の娘・万劫。父は源氏に、母は平氏に別れてしまったことを嘆き、海に身を投げたのだという。近くの児子神社には、村人によって万寿が祀られたと伝えられている と。「頌徳碑(しょうとくひ)」。1831年天保2年に建立。宮石工の功績をたたえたものである。「五層塔と頌徳碑山門に向かって階段下右手にある五層塔は、廃寺となった岩松山光西寺の遺物です。塔身は一つの石から作りあげられたもので、江戸初期(1654年建立)の彫刻技術水準の高さを示しています。また参道の左手にある頌徳碑は、東叡山寛永寺(東京・上野)の宝塔造営事業をなしとげた宮石工の三津木徳兵衛の功績をたたえた、天保二年(一八三一)に建てられたものです。いずれもこの地方の石材業や石材技術を示す貴重な資料です。」左手に古くから伝わっているのであろう石仏の姿が。水子・子育地蔵の社が右手前方に。水子・子育地蔵。近づいて。水子・子育地蔵菩薩碑本来「水子」は「すいじ」と読んで、生後間もない赤ちゃんのことを指していたと。江戸時代を含めいわゆる流れてしまったほうの「水子」は多数存在しましたが、特にその魂の行方について心配する風習はなかったのだと。人間の魂はあくまで生まれてから7日たった以降しか宿らないと考えられていたためであると。これも藁葺の鐘楼堂。山門。藁葺き屋根の「本堂」。瀧門寺は、弘法大師の草創と伝えられる寺。1374年(応安7年)、熱海に湯治に行く途中に立ち寄った義堂周信は、詩集『空華集』の中に「遊瀧門寺観瀑布題観音堂壁」という文字を残している。(瀧門寺に遊び瀑布を観、観音堂壁に題す)伝説によると、開山の道禅は、かつて寺の背後にあった瀧に鬼神を感じて一夜にして堂宇を建てたのだという。その後、瀧門寺は周辺の村々に6つの末寺を抱える当地でも有数の寺格寺院の1つであった。 山号は瀧門寺背後の山の頂に多宝塔があったところから、また寺号は背後に滝を抱えていたところから名付けられたとされている。伊豆の国市(旧韮山町)の昌渓院を本寺とするが、古い時代は密宗だったと伝えられている。1573年(天正元年)に林屋(りんおく)という僧によって中興開山され曹洞宗に寺院になった。「本堂」の右側には「寺務所」・「庫裡」が。本堂の内陣では住職による「節分会」追儺式が行われていた。本堂前から山門、鐘楼堂を振り返る。扁額「多寶山」。順番に焼香を行ったのであった。この日の「節分会」の案内。近所の檀家の方達であろうか15人前後が集まっていた。住職がご挨拶。唐の玄奘三蔵(602~664)が漢訳した経典・大般若経について説明する御住職。御住職が十六尊の大般若経を守るとされる護法善神の十六善神名(じゅうろくぜんしんめい)の書かれた経本を見せて下さいました。ズームして。正面は釈迦如来で、その右手前に獅子に乗っておられる文殊菩薩、左に象に乗った普賢菩薩。文殊菩薩が智恵、普賢菩薩は慈悲の象徴です。仏徳は慈悲と智恵とを円満に備えているとの事です。他に優しい顔の法涌菩薩、泣き顔をした常啼菩薩、ともに大般若経に深い因縁のある菩薩です。向って右一番前にお経を背負った玄奘三蔵。玄奘三蔵と向き合って左の方に、シャレコウベをネックレスにしている深沙大王という元・悪魔の王が居ます。深沙大王はシルクロード途中の砂漠に潜み、仏教を研究してお経を持ち帰るお坊さんを殺し、仏教が外国に伝わるのを妨害してました と。御住職が転読(宗門では最初に「大般若波羅蜜多経巻第何々巻」と唱え、教典を一巻一巻パラパラとめくりつつ転読唱文などの偈文を誦し、最後に「降伏一切大魔最勝成就」と喝破、一巻を読誦したことにするのが、一般的な大般若会の儀式作法 と。そして豆まき用の豆を頂きました。御住職から豆まきの掛け声の説明がありました。そいて全員で大きな声で!!「コロナ退散」と。自宅へのお土産に、封筒に入った「福豆」を頂きました。御住職と記念撮影する方々。我々は「鐘楼堂」に近づいて。「梵鐘」。そして帰路に「ししどの窟」の前の「真鶴 魚座」に立ち寄り昼食を。入口の水槽には鯵が元気に。入口の「大漁旗」。店内の「大漁旗」。新鮮な「海鮮丼」を楽しみ早目の帰路についたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.02.27
閲覧総数 324
-
37

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その8)・本村 八王子神社
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次そして「本村のタブノキ」を後にして、その先にあった「本村 八王子神社」を訪ねた。神奈川県茅ヶ崎市本村4丁目13−40。石鳥居の扁額「八王子神社」。「手水舎」。「手水舎」には龍が二体。「八王子神社 御沿革祭神 天照大神と須佐之男命の誓約の基に生まれた五柱の男神と三柱の女神 天之忍穂耳命(あめのおしほみみ) 天之菩卑能命(あめのほひのみこと) 活津日子根命( いくつひこねのみこと ) 天津日子根命(あまつひこねのみこと) 熊野久須毘命(くまのくすびのみこと) 田心姫命(たきりびめのみこと) 市杵島比売命 ( いちきしまひめのみこと ) 湍津姫命(たきつひめのみこと)神徳 家内安全 身體壮健 交通安全 武運長久等の郷土開拓の守護神で、往古は郷民の崇拝の 外、旅人の道中安全祈願のため賑わったと傳えられている。沿革 創立年代は不詳なれど、社領民に郷民が祖先の墳墓を築き、その霊を社に記して八王子権現 として敬神榮祖の誠を表したものと思われます。 当神社を中心とする一帯を本村と称するは茅ヶ崎發祥の本源を立証するものであります。 鎌倉幕府開府後は、武士の武運長久を祈る者多く、元弘参年(一三三三)五月拾八日、 新田義貞鎌倉討入の際、当神社に祈請し、神火を拝げて兵勢を挙げ北条氏を滅し、依って 建武貳年(一三三五)上洛の途次社参し、社殿を改修し、奉齋の誠を捧げております。 天保拾壹年(一八四〇)子歳秋八月、拝殿幣殿が再興されております。 明治維新の際は、八王子権現を八王子神社と改稱し、圓蔵寺の別当を務め、明治四拾年 (一九〇七年)四月指定村社に列格されました。 現在の社殿は関東大震災後、氏子の方々の浄財奉納に依って、昭和貳年(一九ニ七)四月、 再建されたものです。」まずは境内の右奥にあった「本村天満宮」、「護国社」を訪ねた。こちらは「八王子神社」への東側からの入口。そして「本村 天満宮」の木製鳥居を潜る。「本村 天満宮」と書かれた木製の碑。「天満宮」の対の「御神牛」(向かって右側)。無実の罪で太宰府に左遷されることになった道真。太宰府に向かう途中、刺客(笠原宿禰など)に襲われた。このままでは命が危ない!…と、その瞬間、どこからか一匹の牛が飛び出してきて道真を救ったのだ。実はこの牛は道真が京都で可愛がっていた牛。左遷決定後、どこかに逃げてしまっていたのだが、大ピンチに再び登場したんだとか。道真は涙を流して喜び、太宰府に連れて行ったと。道真が亡くなったのは、延喜3年(903)2月25日。丑の日!!そして道真の遺骸は牛車によって運ばれるのだが、牛はある場所で突然足を止め、その場に座り込んでしまった。さまざまな手を打ったが、牛はまったく動かず。さては道真公はココでゆっくりと休まれたいのだと弟子は考え、そこを墓地に定めたのだと。その場所は「安楽寺」。今は名前を変えて「太宰府天満宮」となっているのだ と。お顔に近づいて。「天満宮」の対の「御神牛」(向かって左側)。お顔に近づいて。神紋「丸に梅鉢」が描かれた天満宮の提灯が両脇に。「本村天満宮由緒御祭神 菅原道真公菅原道真は(八四五~九〇三)平安初期の公卿、文人。文章家としての基礎を築いた祖父以来の菅家を名實ともに建立した人物。東風吹かば 匂ひいおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ八七四年 従五位下となり、文人としては異例の榮達をした。八七七年文章博士となり、八八六年には国守として讃岐に赴任し、八九〇年平安京に歸任した。宇多天皇の命により六國史を編集し、八九九年には右大臣になり、九〇一年従二位に昇進直後太宰権帥に就任、九〇三年太宰府で薨去す。菅原の祖神をたどると、天之菩卑能命にたどりつく。又、命は武蔵國造り祖とも傳えられる。八王子神社境内に、南湖分校(茅ヶ崎小學校)を設立し(明治十三年から明治ニ十五年)本村地区児童の初等科の教育にあてた。」別の場所にも「本村 天満宮 由緒御祭神 菅原大神(菅原道真公)御神徳 學業向上 受験合格への導きの神創立年代不詳なれど、古老の記憶する限り、古きより當神社境内に末社として祀られていました。近年に至り、社殿老朽化しつつある状態であり、此の度、氏子岸芳雄氏・伊藤岩治氏の赤誠な御芳志により再建されたものです。菅原道真公平安時代の最も優れた學者として、詩歌に優れ、政治家として重要な地位につかれた方です。神輿シンヨ・ミコシと呼ばれ、文字通り神の乗る輿のことで、神の移動に用いられたものです。御輿とも書かれます神輿の中には、神體が納められており、あくまでも來臨した神が氏子圏を渡御するのが目的です。これに對して賽銭を投げ供えたり、手を合わせ拝む人があるのはその為です。※神輿、淘綾群山西村、杉橋英之助製作 明治貳拾貳年(一八八九)五月五日」神輿再興記(年代不詳)。夫祭祀皇大御國大本而・本村古来之神輿殿壊・・村内同心協力・・募財テ神輿再興セン事ヲ欲ス。神恩ニ報ヒ名ヲ子孫ニ傳ヘム事ヲ希望ス・・※この記事から推察するに、現在の神輿は三代目となる。禊祭から浜降祭建久貳年(一一九一)、今から八百年も昔の話。鶴嶺八幡社の参道先で「禊祭」が祖先の手によって厳かに行われていた。「南無八幡大菩薩」の信仰は、茅ヶ崎に多くの氏子や信者を集め、鎌倉時代、江戸時代の昔から郷土の信仰の中心であった。明治の時代を迎え、鶴嶺八幡社の禊祭と寒川神社神輿の御體詣りが、明治九年(一八七六)合同で行う事とし、合同祭典の儀式が行われた。それ以降、この祭典を浜下(はまおり)の行事であることから、浜降祭(はまおりさい)と決め、七月拾五日とした。昭和参拾六年(一九六一)県無形民族資料に指定。昭和五拾貳年(一九七七)県選擇無形民族文化財に指定。昭和五拾参年(一九七八)県無形民族文化財に指定※平成拾八年 浜降祭実行委員会で七月第参月曜日と決める。特殊神事官國弊社特殊神事調、大正拾参年(一九ニ四)によれば、寒川神社を中心とした浜降祭の様な特殊神事が、その神事を列挙してみると、①神の降臨出現を中心とする神事②斎祀を・・③禊祭を・・④供物・舗設を・・⑤渡御に関する・・⑥卜占⑦農耕・・⑧採取・・⑨火に⑩疫病除け・・⑪競技・・⑫藝能※この「神事」に「複数神社の連合を中心とした神事」を加える。神事の基礎・市史・茅ヶ崎の昔話より」「浜降祭」👈リンク の光景をネットより。今年は是非この「浜降祭」👈リンク に行ってみたいが、開催は??次に隣に鎮座する「護國社」を訪ねた。「本村護国社」と書かれた木製の碑。神紋「澪標(みおつくし)」が描かれた護国社の提灯が両脇に。澪標とは浅瀬に乗り上げないように水中に立てた航路をしめす木製の杭。平安時代の『類聚国史(るいじゅうこくし)』に「浪速江始めて澪標を立つ」とある。読みが「身を尽くす」に通じることから、恋歌などで愛情表現として用いられた。家紋としては、主君への忠義の意味から尚武(武道・軍事などを大切なものと考える)的な家紋である と。「護國社八王子神社氏子内より日清、日露、大東亞戰争にあたり、護國のために導き人命を捧げられた方々の御尊名は、護國の神として八王子神社に相談して祀られ、九月一日の例大祭には、合わせて感謝と慰霊の祭儀をご奉仕してまいりましたがここに、「本村護國社」を創建し、相殿として祀られている方々の御霊をお還しいただき、より一層丁重に祭儀を嚴修し、感謝と慰靈の誠を捧げることと致しました。」「社務所」。「社務所」前から「八王子神社」の「拝殿」、「鐘楼」を見る。「八王子神社」の「拝殿」。唐破風下の懸魚には鶴に乗った翁像が。ズームして。その上には「三つ巴紋」が。向拝には男女像や大蛇(オロチ)などの見事な彫刻が施されていた。ズームして。素戔嗚尊(スサノオノミコト)がヤマタノオロチを退治している場面。作者は「昭和丁卯(ひのとう)作」・「佐藤光重」であると。境内社の「八坂神社」を訪ねた。御神木「公孫樹」。「垂乳根の大銀杏」と呼ばれ、子孫繁栄の願の神木として崇拝されています と。「力石」が弐個。「力石昔、何年頃から行われるように成ったかは不詳なれど、祭禮など氏子の若者達が集まった際、この石を持ち上げて己の力量を競い合った事から、誰云うと無くこの弐個の石を力石と名付けた。」「本殿」を見る。「神輿庫」。「八坂神社」の鳥居を見上げる。扁額「八坂神社」。「八坂神社」の「社殿」。「本村 八坂神社御由緒御祭神 須佐之男命(すさのおのみこと)御神徳 五穀豊穣 招福 疫病除く創立年月不詳須佐之男命 人間の罪穢れや悲しみ喜び生死といった自然界人間界の避け難い運命を一身に負いながらそれを良い方向に導く為苦労をなさった弟神様で祇園さま・氷川さま・熊野さまとも呼ばれました。」先代の「本堂」の瓦であろうか。扁額「八坂神社」。見事な龍の彫刻(右側)。見事な龍の彫刻(左側)。「八坂神社」の「社殿」の横の石碑群。様々な形状の石碑が並んでいた。そして「鐘楼」。場所を変えて「鐘楼」を見る。「鎮守 八王子神社 鋳師 京都 岩澤徹誠黨八王子神社には、元禄拾五年(一七〇ニ)壬午八月、伊藤奥左ェ門外七拾一名奉献の名鐘が在し、その名音は日々の生活に活気を與え勇気を鼓舞し、朝夕氏子に親しまれしも、大東亜戦争中供出の犠牲となり、貴き姿を消す。爾来、名鐘の音を慕う聲絶えず、遂に神社役員及び志を同じくする氏子等相謀り、浄財の奉賽を得て之を再興す。鐘音永久に氏子の幸福と平和を護るものなり」隣には「正一位 稲荷大明神」が。「正一位 稲荷大明神」碑。「社殿」。ここにも多くの石碑が鎮座していた。石碑群案内書。「為庚申供養 二世菩提也 寛文4(1664)」。「為庚申供養 二世安楽也 延宝8(1680)」。「廻国供養塔 文化4(1807)」。「庚申塔 寛文7(1667)」。「道祖神 安永5(1776)」。「関東大震災により倒壊した「八王子神社大鳥居」が境内の地面に保管されていた。「関東大震災により倒壊した八王子神社大鳥居大地震が起きた大正十二年九月一日は、当神社の例大祭で招待者役員等多数の方々が参列し盛大に式典が斎行された。式終了直後(午前十一時五八分)突然マグニチュード七・九と云う大地震が襲った。当地域は震源地内の為、殆どの建物等は全壊した。当社の社殿工作物等もことごとく倒壊した。境内はお祭りの為参拝者で大賑わいであったにも拘らず、幸いに一人の犠牲者も無く誠に奇跡であった。これは、八王子大神の加護によるものであると云われ、この鳥居も我々の身をかばい倒壊したのではないかと言い伝えられています。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.04.15
閲覧総数 560
-
38
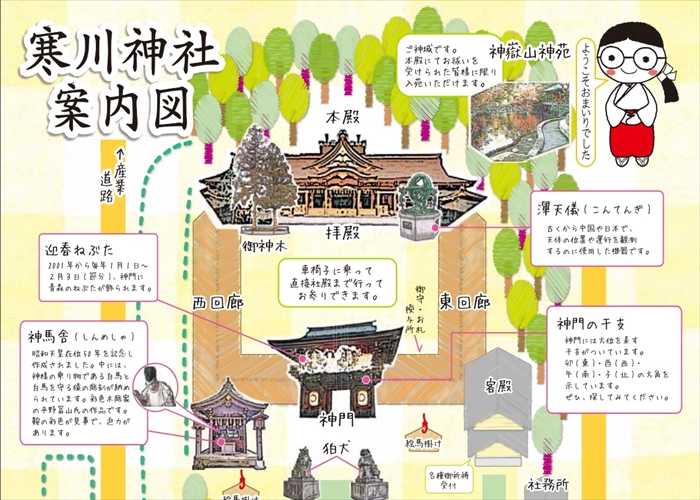
寒川町の寺社旧蹟を巡る(その7) ・ 寒川神社(1/4 ):寒川神社参集殿~石灯籠~神池橋~三之鳥居~重修寒川神社太鼓橋記碑
【寒川町の寺社旧蹟を巡る】 目次そして「寒川神社」の散策に向かう。「寒川神社案内図」。本殿及び拝殿の手前には神門がある。参道は当社境内から南に1kmほど進んだJR相模線の踏切近くにある一之鳥居から始まり、参道途中には二之鳥居(大鳥居)、境内入口には最後の鳥居となる三之鳥居がある。2001年より新年から2月の節分まで、神門に神話にちなんだ迎春ねぶたが飾られるようになり、夜にはライトアップもされている。 2012年まではその年の干支にちなんだねぶたが飾られていたが、干支が一巡した2013年からは神話ねぶたが飾られている。最初に「寒川神社参集殿」を訪ねた。ツツジの植栽の中の遊歩道を歩く。「寒川神社参集殿」には、結婚式場、披露宴会場、宴会場・会議室 、その他レストランあおば等が設けられている。「寒川神社参集殿」。「鎌倉本体の武士 梶原景時 ゆかりの地」と書かれた幟。上部には梶原氏の家紋「丸に並び矢」が。梶原 景時(かじわら かげとき)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。鎌倉幕府の御家人。石橋山の戦いで源頼朝を救ったことから重用され侍所所司、厩別当となる。当時の東国武士には珍しく教養があり、和歌を好み、「武家百人一首」にも選出されている。源義経と対立した人物として知られるが、頼朝の信任厚く、都の貴族からは「一ノ郎党」「鎌倉ノ本体ノ武士」と称されていた。鎌倉幕府では頼朝の寵臣として権勢を振るったが、頼朝の死後に追放され一族とともに滅ぼされた(梶原景時の変)。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では日本の歌舞伎役者、俳優・声優の「二代目 中村 獅童(にだいめ なかむらしどう)」氏が「梶原景時」を演じている。そして7月10日に「中村 獅童」氏出演の「鎌倉殿の13人 スペシャルトーク in 寒川」が行われるとのことで、申し込んだのであった。しかしながら、落選の通知が届いたのであった。茅ヶ崎市で行われた「鎌倉殿の13人 スペシャルトーク in 茅ヶ崎」👈リンク には参加できたのであったが。やはり「中村 獅童」氏の競争率は高いのであった。そして「参集殿」前にあったのが、「浄明正直(じょうみょうせいちょく) 寒川神社宮司 竹内武雄書」の銘がある銅像。お顔をズームで。台座の裏には「寒川神社中興の宮司竹内武雄大人彰徳像竹内大人は明治三十一年二月十七日京都府船井郡瑞穂町に出生、大正六年京都府皇典講究分所を卒業、常に神社神道を究め祀職の道を精進され、生来至誠圓満實直にして正直を旨とし人に親しまれること慈父慈兄の如し、昭和十三年六月官幣大社平安神宮禰宜より當國幤中社寒川神社宮司に任ぜられ、昭和十八年九月別各幤社護王神社宮司に任ぜらる。昭和二十一年官國幤社職制が廃止され國及地方公共團體よりの經濟的援助を断ち切られた全國の神社は、維持經營に困窮を究め、特に寒川神社は一名の神職すら置く能わず、日々の御祭事は勿論御社頭の衰微は日に増す状態となり、時の責任役員、氏子總代町長等憂慮に耐えず再三神社本廳に請願して竹内大人の再任を乞う。大人は氏子の切望に應え、京都の私財を整理し死を決して家を擧げ、昭和二十六年十月再び當神社宮司に赴任す。爾今全國神社の範たることを期し、自ら御社頭の清掃に勤め、信仰を興して全國に八方除けの御神徳を恢弘し、報賽者年を追うて増し昭和三十六年崇敬者は數十萬に至れり。斯く衰微せる御頭社を興せし功績は廣く世の稱贊する所となり、昭和三十七年三月神社本廳より浄階並神職身分一級を授けらる。更に竹内大人は御社頭の隆昌に伴う施設の狭隘を憂い参集殿の建設を計畫、將に設計の運びとなりし時、俄に病を得て昭和三十八年十一月二十六日急逝せらる。然し大人の遺せし大望を達成し、生前の恩顧に報いむと氏子崇敬者一つ心に参集殿建設奉贊會を結成して工を起し美事短年月を以って完成す。慈に竹内大人の十年祭を執行するに當り参集殿の邊りに尊像を建立し以って寒川神社中興の遺徳を偲び、永久にその功績を讚えるものなり。」「寒川神社参集殿」の内部に入ると正面には、ねぶた「「箙(えびら)の梅」梶原景季(かげすえ)」が展示されていた。近づいて。ここ寒川ゆかりの武将で、大河ドラマで注目されている梶原景時。その嫡男で源平合戦に従軍した景季(かげすえ)の雄姿。刃を構える背には梅の枝が。ねぶた師の諏訪慎さんが制作と。景季は木曾義仲と源義経が宇治川(京都)で戦った時に先陣争いを繰り広げたり、生田の森(神戸)での平家との戦いでも奮戦、梅の枝を箙(えびら=矢を運ぶ道具)に挿して戦ったエピソードなどがあるとのこと。正治元年(1199年)正月に頼朝が死去すると梶原一族の運命は暗転。同年11月に景時は三浦義村、和田義盛ら御家人66人の連名の弾劾を受けて、鎌倉から追放され、所領の相模国一ノ宮へ退いた。正治2年(1200年)正月、景時、景季は一族とともに相模国一ノ宮を出て上洛を企てた。途中、「駿河国清見関」👈リンク で在地の武士と諍いになり、弟たちは次々と討ち死にしてしまった。景季は景時とともに山中に退いて戦い、ここで一族とともに自害したのであった。享年39。鎌倉市笛田の「佛行寺」には、景季の片腕を埋めたと伝わる「源太塚」👈リンク が残っているのである。「人力車」も展示されていた。結婚式の記念撮影や境内移動用に使われているものであろうか。神前結婚式場。 【https://nihon-kekkon.com/party/sansyuden/】より「寒川神社参集殿」を後にすると正面の道路の分岐場所には大きな石灯籠があった。もともと、石灯籠は、奈良時代から僧侶が使い始め主に寺院で用いられていたようです。仏像に灯をともすために、仏道の前に置かれた。仏教の考え方の1つに、灯が邪気を払うという意味があるようです。その後、神社の献灯として使われるようになったのだと。神奈川県高座郡寒川町宮山3929。「寒川神社参集殿」の前の道路の南、一の鳥居方向を見る。そして「寒川神社」方向には「相模國一之宮 寒川神社」案内塔が。三角ロータリーの中には、巨石その奥には淡いピンクの桜の花が。「八重紅枝垂(やえべにしだれ)」と。寒川神社神嶽山神苑開苑10周年を記念して、2020年2月に植樹された「八重紅枝垂」。枝垂桜の中でも特に人気の高いエドヒガン系の園芸品種。江戸時代から栽培されていて、別名:「遠藤桜」「仙台八重枝垂」「仙台小桜」「平安紅枝垂」とも呼ばれる と。薄紅色の小輪で八重咲きの花を枝いっぱいにつける枝垂れ桜で、たいへん優雅なのであった。そして「寒川神社前」交差点に。横断歩道の先に太皷橋「神池橋」と「三の鳥居」が現れた。社号標石「相模國一之宮 國幤中社寒川神社」。近づいて。その先の「神池」の噴水の先には「石橋(しゃっきょう)」が見えた。ズームして。昭和45年から、毎年8月15日に開催される「相模薪能」の20回目を記念して作成。寒川町在住であった彫刻家、原田純成さんの作品であると。横の石橋から太鼓橋「神池橋」を見る。「神池橋」とその先に「三の鳥居」。「神池橋」は「神池」にかかる太皷橋。平成二三年老朽化により架け直され「神池橋」と命名された。神様がお渡りになる橋と。正面から。横の橋とその先には「神池」の噴水が。「三の鳥居」。「三の鳥居」は、境内にある桧造りの明神島居。平成ニ年・皇紀二六五〇年奉祝記念事業として建て直されたとのこと。「寒川神社」案内板。「寒川神社(さむかわじんじゃ)御祭神 寒川比古命(さむかわひこのみこと)・寒川比女命(さむかわひめのみこと) ニ柱の神を奉称して寒川大明神と申します。例祭日 九月ニ十日(九月十九日 例祭宵宮祭・流鏑馬神事)由緒 当神社は総国風上記によりますと、雄略天皇(四五七年~四七九年)の御代に奉幣(天皇より 神社に献上品がされること)の記録かあり、神亀四年(七ニ七年)に社殿建立とも伝わり、 一六〇〇年以上の歴史を有しています。 以後、延暦十六年(七九七年)桓武天皇を始めとして歴代奉幣の記録があり、承和十三年 (八四六年)に神階従五位下を始めとする神階授与もなされています また醍醐天皇の御代に制定されました延喜式神名帳によれば相模國十三仕の内、明神大社と されており、関東地方の信仰の中心をなしていました。 中世においては源頼朝、小田原北条氏累代による社殿造営や社領寄進がなされており、 武田信玄からは武運長久を祈願して鉄錆地六十ニ間筋兜(神奈川県指定重要文化財)が奉納される など特に崇敬の念は篤く、徳川家代々においても社殿再建、社領寄進など古来より武家からの 崇敬は極めて篤いものがありました。 明治期になりますと、明治四年五月に制定されました官国幣社制度によって、例祭におきて 国費から幣帛料が奉納される「国幣中社」に列せられました。 その後、大正時代における関東大震災、昭和の御大典という時代を経て、昭和ニ十年八月十五日、 大東亜戦争の終戦後、同年十ニ月の神道指令によって、神社の国家管理制度が廃止されました。 昭和ニ十一年ニ月、神社神道の宣布と祭祀の執行による氏子の教化育成を目的として、全国の神社 及び神社関係者を統合する神社本庁が設立され、当神社も神社本庁による包括神社となって おります。 戦後、日本全体の復興とともに、八方除信仰を中心とした御神徳の宣揚に努め、全国の崇敬者 からの御崇敬と多くの御参拝をいただいております。社殿 平成の御大典記念事業として平成九年に御本殿、幤殿、拝殿、翼殿、廻廊等の増改築が 行われました。境内 神聖なる神嶽山を背に、約一万五千坪を有しており、平成ニ十一年には御本殿奥庭の禁足地を 「神嶽山神苑」として開苑致しました。」「境内のご案内」。主要な建物が案内されていた。「定一、魚鳥ヲ捕ルコト一、樹木ヲ伐ルコト一、車馬ヲ乗リ入ルコト右境内於禁止」。「神池」の噴水を再びズームして。参道を見る。左手に大きな石碑と下部には詳細な案内碑があった。「重修寒川神社太鼓橋記」碑。「重修寒川神社太鼓橋記 陸軍大将大勲位熾仁親王篆額相模國高座郡の寒川神社は、平安朝の延長五年(九ニ七)、延喜式に大社と記載される国家公共の祭場であるあり、明治四年(一八七一)六月に天皇の大命によって國幤中社に列せられた。古記によって創建を考えると神亀四年(七ニ七)、或いは天平神護元年(七六五)とも言われるが、何れとすべきか詳らかではない。承和十三年(八四六)九月に始めて神位を授けられ、その後、斉衡・貞観・元慶年間に累進していった。源氏が鎌倉に開府してより、常に武家の崇敬する所となり、奥深い神域と壮麗な社殿とをみるに至った。また各時代に幤帛や神田が奉られ、春秋の祭礼を順調に営まれた。天正(一五七三~)以後、時々に殿舎から回廊まで修繕されたが、それらは頗る縮小して附属の小社も多く荒廃し、昔日の景観も見られなくなってしまった。さらに明治初め、神田百石を政府のために割き、玉垣他の地五町余りを上納した。加えて鬱蒼とした老樹を伐り、粗末な民家が建てられるなど、神域の雑然たる有様もここに極まった。宮司丹羽与三郎はこれを深く嘆いて、郷里の人々に相談し土地を眺めて、帝室御料林に関する委託林の規定に副って願い出で、明治二十四年(一八九一)三月に許可が下りた。そこで民家を撤して花木を植え、広く敬神家を募って大いに復旧のことを計画した。天下四方に応じる者は数多く、社殿を大改修せんと欲して、往時の荘厳さを見事に取り戻したのである。その費用は巨額にのぼり、容易なことで工面できるものでは無かった。よって先ず長さ三十三尺の橋を修理し、その形を皷に似せて太皷橋と称し、次に玉垣六十三間を石で築き、堅牢にして麗しく修復した。その工事は明治二十五年(一八九ニ)六月に始まり、十一月に完成して、経費三千円・職工三千人を要した。人々の中心になったのは菊池小兵衛・左藤平兵衛・伊東祐吉・真田喜三郎・金子四郎右衛門である。十二月一日に神輿渡橋の盛儀が斎行され、遠近の奉拝者が数千人にも及んだ。この日、内務大臣の特使として社寺局長の國重正文が臨席した。私も神奈川県庁に在官しており、かって奉幣使として奉仕した際、橋の壊れた状況を観ていただけに、その盛衰の迹には感慨一入のものを覚える。古今にわたる人心の移り変わり、祭祀を重んじる歴代の祭典や礼式、神祇を敬う國民精神の美徳が、この壮挙を今に有らしめた。小兵衛などが政府の方針をよく理解して、人心を振い興したものと言えよう。皆人が誠意をもって怠りなければ、神社本来の真姿を回復するのも、遠い先のことでは無いと想われる。丹羽与三郎が石碑を建てようと欲し、私に案文を求めてきたので、これを深く諒として記文を刻ませるものである。明治廿六年一月 神奈川県書記官従五位勲六等 田沼 健 撰 正五位 日下部東作 書 井亀泉 刻」「相模國一之宮寒川神社「神池橋」記「重修寒川神社太鼓橋記」によりますと、鎌倉時代以降、多くの武将たちの崇敬をあつめ、広壮な御神域と御社殿を有した寒川神社は、天正年間以後次第に御神域が荒廃し、明治の初めには、昔の姿を留めていなかったとあります。それを嘆いた宮司丹羽与三郎は、明治二十四年三月から御神域の整備に取り掛かり、神社復旧の手始めとして、明治二十五年六月には、長さ三十三尺、本石造りの太鼓橋の再建に着手し、同年十一月に完成いたしました。しか大正十二年九月一日に関東地方南部を襲った関東大地霎により、太鼓橋の橋桁が水路に落下するなど、甚大な被害を被りましたが、昭和六年には、それまでの本石造りの太鼓橋から、長さ十六尺・幅十五尺の鉄筋コンクリート造りの太鼓橋に架け替えられました。その後、平成二十三年までの約八十年にわたり氏子崇敬者の皆様をお迎えしてまいりました。平成二十二年十一月には、宮司利根康教により境内整備事業工事委員会が招集され、老朽化が進んできていた太鼓橋の改築並びに周辺整備事業の施工が決まりました。平成二十三年二月に、太鼓橋工事が始まると共に、改築される太鼓橋の名称が公募されました。同年九月に多数の応募の中から、厳選の結果「神池橋」の名称に決定しました。同年十二月には神池橋と周辺整備工事が完了し、白御影石で整えられたその姿は、参拝者を迎えるにふさわしい清浄で重厚かつ麗美な佇まいとなりました。」「寒川神社太鼓橋記」上記と同様な内容が漢文で刻まれていた。「明治二十五年の様子」。「明治六年の様子」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.07.05
閲覧総数 1737
-
39

『港・ヨコハマ』を巡る(その19): 往路~桜木町南改札口前~桜木町駅前広場~東横浜駅の碑~YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅~桜木町駅北改札東口~鉄道発祥の地
この日は8月19日(金)、天候も回復したので、久しぶりに『港・ヨコハマ』を訪ねることに。2019年の9月に『港・ヨコハマ』を巡る で(その18)までアップしたが、まだまだ訪ねていない場所があったので、更に!と思っていたが、この日に『落穂拾い』を決断し向かったのであった。前回訪ねた2019年9月はコロナの前。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2019年12月初旬に、中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されてから、わずか数カ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。わが国においては、2020年1月15日に最初の感染者が確認されたのであった。そして2020 年1月から2月にかけて、アジア各国を周遊してきた大型客船ダイヤモンドプリンセス号(DP 号)船内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の集団感染が起きた。DP 号船内では 3,711人の乗員・乗客のうち、最終的に672名の感染が報告されたのであった。DP号は2020年2月3日に、ここ横浜港大黒ふ頭に接岸し、乗員・乗客の検疫が始まるとともに、無症状者、軽症者は主に関東地方各地および遠方の医療施設へ、医療を必要とする中等症、重症者は主に神奈川県内の医療機関に転送された。患者の転送は2020年2月3日から3月1日まで続いたのであった。そして神奈川県内12施設に転送されたCOVID-19感染者は70名にも及んだのであった。そして現在も継続しており、8月26日時点 のおいて全国の感染確認数19,413人、死亡者数321人、それぞれ延べ人数としては感染確認数1821万2025人、死亡者数3万8582人の深刻な状況が継続しているとのことである。上記の如きコロナの影響で、ここ1年以上は我が住む市の隣都町の『社寺旧跡』巡りをひたすら巡り続けて来たが、気分転換もあり、再び『港・ヨコハマ』を巡ることにしたのでもあった。この日も早朝に自宅を出発し、小田急線で湘南台駅に。そして横浜市営地下鉄で桜木町駅に向かったのだ。そして35分程で桜木町駅に到着。JR桜木町駅周辺の地図をズームして。JR根岸線 桜木町駅西口へのエスカレーターを上る。エスカレーターを下り、振り返る。「野毛ちかみち」は、はにかんだピエロがお出迎え!「ちかみち」は「地下道」それとも「近道」それとも「両方」の意か?ーーがこの日・(その19)の散策ルート。桜木町駅周辺を散策。JR桜木町駅南改札前(西口)が前方に。南改札口を出た正面には、なんと柱一つ一つが桜木町駅や鉄道にまつわる資料展示スペースになっていたのであった。「桜木町にやってきた鉄道車両初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。」「追憶の野毛・桜木町駅」「庶民の街として親しまれてきた野毛、またその玄関口として街の変遷を見守って来た桜木町界隈は、いつの時代も人々の活気ある息吹を感じ取る事ができます。野毛の風景 明治から大正、昭和まで、桜木町周辺の写真が展示されていた。夕焼けのような演出も相まって、ノスタルジックな雰囲気が。」「2代目桜木町駅舎と昭和40年代半ばの街初代横浜駅舎は改装を重ね、大正時代まで使用された。その後2代目駅舎は初代駅舎とほぼ同し位置に建てられた。駅が終点であった頃は、左写真のように左右対称の姿だったが、根岸線の開通、延伸とともに展示模型のような形になった。」「昭和の桜木町駅プラットフォーム昭和40年代、奥に見える商店街は間もなく消えようとしている。駅のプラットホームは街の移り変わりを見つめて来た。「横浜停車場」(初代桜木町駅)と「桜木町駅」( 2代目)の位置左 1883 (明治16)年の地図(青色)十2020 (令和2)年の地図 初代横浜停車場(初代桜木町駅)の歴史 1872(明治5)年 横浜停車場(初代横浜駅)開業 1915(大正4)年 横浜駅移転につき、桜木町駅に改名 1923(大正12)年 関東大震災のため駅舎等消失右 1932(昭和7)年の地図(緑色)十2020 (令和2)年の地図 2代目桜木町駅の歴史 1927(昭和2)年 2代目駅舎完成(関東大震災の4年後) 1964(昭和39) 根岸線延伸に伴い、駅舎の一部改築 1989(平成元)年 駅舎移転に伴い、旧駅舎はその設割を終え、解体」「鉄道が発信する文化鉄道創業時に、早くも横浜停車場の構内で商いをする人たちが現われました。以来、鉄道に関連した数多くの商売や文化が生まれてきました。・構内販売の変遷・明治~昭和 停車場と周辺の風景・鉄道がテーマの趣味と芸術」「鉄道旅行のお楽しみ江戸期の旅は徒歩による信仰と巡礼が目的でした。明治期、鉄道が利用されるようになると、やがて旅の目的は観光や仕事など、多様なものとなりました。・時刻表と観光案内詩のはじまり・鉄道の旅路で楽しんだ様々な飲食・明治~昭和 横浜ゆかりの名物たち「明治の横浜・鉄道路線案内明治初期、当時の人々にとって鉄道への関心は高く、多くの錦絵が残されましたり開業時の路線は現在でもほぼ同じルートをとりながら、高度に複線化されています。浮世絵展示が画面スクリーンに表示され、数秒ごとに桜木町駅にまつわる様々な絵に変わっていくのでついつい長居してしまいそう。この映像で桜木町駅周辺にたくさんの跡地が今も現存していることもわかります。・神奈川駅・鶴見駅・横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけて鉄道関連の史跡が数多く存在します。「横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけての鉎道連の史跡が多く存在します。」①神奈川駅跡②3代目 横浜駅跡③高島ヤード跡④2代目 横浜駅跡⑤鉄道発祥の地記念碑と初代横浜駅長室跡⑥東横浜駅跡⑦汽車道と橋梁⑧旧横浜駅プラットホーム跡⑨鉄軌道と転車台跡⑩外国人鉄道技術者の墓「錦絵」が画面に次々と。「河崎鶴見川蒸気車之図」。「横済ステーション蒸気入車之図」。「横浜新埋地高嶋町掲屋三階造海岸遠景之図」。「横浜鉄道蒸気出車之図」。「初代横浜駅と発着場の情景」初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。「初代横浜駅舎 半立体模型明治--大正の頃、初代横浜駅は観光スポットであった。桜木町駅時代も含め、多くの古写真が残っている。」「初代横浜駅乗車場 半立体模型明治初期、鉄道を題材にした錦絵が数多く出版された。和と洋が混在した人や街の様子がイメージできる。」「開業直前の横浜停車場1872 (明治5)年の舂頃に撮影されたと思われる横浜停車場の写真です。これにより鉄道創業期の客車の様子など、新たな発見がありました。」「鉄道創業の地・桜木町駅(旧横濱停車場)日本人と鉄道の出会いは江戸時代の末期でした。明治時代になるとその導入が決定し、1872 (明治5)年、横浜と新橋の間で日本初の営業運転が始まりました。・日本人と鉄道の出会い・鉄道敷設の計画と工事 1869 (明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。・双頭レール 明治初期の鉄道創業当時は、英国から輸入された錬鉄製の双頭レールが使用された。 このレールは上下対称の形状になっており、裏返して再利用する予定だった。 (実際には再利用されなかった) 当駅、新南口に隣接するJR桜木町ビル1階には、1873年製の双頭レールか設展示されています。・華やかな開業式典 1872 (明治5)年新暦の10月14日、秋晴れのもとで執り行われた開業式典の記録。」「日本人と鉄道の出会い」。「鉄道敷設の計画と工事1869(明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。」「華やかな開業式典」。「日本の産業を支えた横濱停車場鉄道開業の翌年、1873 (明治6)年9月、横浜~新橋間の鉄道による貨物営業が始まりました。以来、横浜は日本の産業における重要な物流拠点となりました。・貨物輸送のはじまり 創業期の貨物輸送は貨車75両で始まづた。 ・明治初期の貨物 1873(明治6)年の貨物営業開始時の輸送量は合計2千トン程度であった。初期の貨車には 家畜車、魚車、木材車などがあったが、その後、鉄道延伸のための工事に必要な土砂車が 増加した。鉄道網が拡がった1897 (明治30)年の貨車は、全国の官営と私鉄あわせて1万両を 超え、輸送量は876万6千トンとなった。」・延伸する鉄道路線 明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。「延伸する鉄道路線明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。」「みなとみらい時層マップ明治初期から平成までの海岸線の変化を俯瞰しながら、この地区の産業や街並みの発展を「時間を旅する」感覚で観察すると、新たな発見があるかもしれません。「明治初期の周辺地図」。明治:横浜開港後、臨海地区には港湾の付帯施設として、造船と鉄道という2つの 産業が生まれ発達しました。それに伴い、周辺の海は急速に埋め立てられました。大正:造船と鉄道流通の関連産業は、戦前から戦後にかけて最盛期を迎え、昭和 日本の高度成長期を支えてきました。昭和末期になると、これらの産業は転換期を 迎えます。現在:「みなとみらい21地区」となって、この一帯は日本屈指の国際ビジネスセンターとなり、 さらに、これまでの産業遺産を活かした観光地として、進化と発展を続けています。「みなとみらい地区の記憶明治から昭和までの臨海地域は造船と鉄道物流の拠点で、この街のシンボル的存在でした。現在は国際的なビジネスと観光の街として生まれ変わリました。」「YES’89横浜博覧会 横浜博覧会は「宇宙と子供たち」をテーマとして1989年(平成元年)に開催されました。 これを機に、みなとみらい地区は大きく変貌、発展しました。」「造船産業の隆盛 明治半ば、付近の臨海地域に横浜港の付帯施設として造所所が設けられました。 その後、日本の基幹産業の一翼を担い、昭和末期まで稼働していました。」「鉄道流通の拠点 鉄道はその開業以来、横浜港をはじめその付帯施設に関連する流通を支えました。 そして日本の貿易や工業の発展とともに貨物の取扱量は増加しました。」そして駅舎を後にして、この日の散策の本格的なスタート。正面に久しぶりに見る「横浜ランドマークタワー」の姿が。「横浜ランドマークタワー」は、神奈川県横浜市西区みなとみらいの超高層複合ビル。「横浜みなとみらい21」地区の開発を主導した三菱地所が建築・設計・保有している。1990年3月20日に着工し、1993年7月16日に開業した。タワー棟は、地上70階建て、高さは296.33mで、超高層ビルとしては、あべのハルカス(300.0m)に次いで日本で2番目に高い。また、構造物としては東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)、あべのハルカス、明石海峡大橋(298.3m)に次ぐ日本で5番目の高さである。桜木町駅前広場の右手、歩道橋への階段の下にあった「昔の桜木町駅前」の写真。「この光景は、明治20年(1887)頃の初代横浜停車場(現桜木町駅)前を撮影したものです。写真中央の噴水塔は、高さ約4.4m、重さ約1.3tの鋳鉄製で、日本初の近代水道創設を記念して設置され、往来する方々に親しまれていました。この噴水塔は、現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されています。」と写真右下部に。この姿は竣工当時の新橋停車場に酷似しているのであった。この塔の下部はその名も『獅子頭共用栓(ししがしら きょうようせん)』と呼ばれていたと。そう言えば、日本の水道事業は、明治20年(1887年)に横浜で初めて近代水道が布設されたことから始まったのだ。これは当時、外国の窓口であった港湾都市を中心に、海外から持ち込まれるコレラなどの伝染病が、水を介して広がり蔓延するのを防ぐことを目的としたもの。横浜に続いて、明治22年に函館、明治24年に長崎と、港湾都市を中心に次々と水道が整備されて行ったのであった。この辺は、私の昔の仕事の関係で。現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されている噴水塔の写真。桜木町駅前のワシントンホテルを見上げる。そして正面に案内プレートがあった。ここにも何か書かれているようであったが解読不能。「東横浜駅の碑」と。案内板が2枚。『ここに駅があった 大きな貨物駅だった 往時は六十五万トンが発着 多くの人が働き汗を流した ある時代は生糸だった ある時代は疎開荷物だった ある時代は進駐軍輸送 それに輸入食料だった そしてこの駅はいつの時代も 市民の生活とともにあった 一九七九年十月 この駅の使命は終わった かって日本の鉄道開業の 栄えをになった駅 追憶のなかに永遠 東横浜駅』「東横浜駅について 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社明治五年汽笛一声新橋を発した日本初の鉄道の終着駅横浜はこの地でした。時を経て横浜駅は現在の位置に移り、この地の駅は客貨の機能を分離して桜木町駅、東横浜駅となりました。さらに幾星霜、国運いよいよ隆昌に向かう我が国現代史の過程において、鉄道の果たした役割はかぎりなく大きいものがありました。この間市民生活の一部としてその責めを全うした貨物駅東横浜は昭和五十四年その終焉を迎えました。いまこの地は新しい都市みなとみらいとして秀麗かっ壮大な偉容をととのえつつあります。古より世のため人のために日々営まれる活動に支えられて、暮らしが、社会が、街並みが時代に応じて生き生きと発展するさまは無量の感慨を私たちに与えてくれます。この碑文は東横浜駅廃止に際し往時ここに汗となみだをながした人びとの意をうけて書かれたものです。 平成十八年三月」つまり、東横浜駅は新橋-横浜駅間の鉄道開業時の初代横浜駅のあった場所に位置し、貨物専用駅として大正4年12月に開業。1979年(昭和54年)10月1日に廃止された と。「桜木町駅西口」を振り返る。「桜木町駅前広場」を「横浜ランドマークタワー」方向に進むと正面にあったのが「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」。「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」の前から「ランドマークタワー」を。横浜市は、下水道事業のPRと市の魅力発信などを目的としてポケットモンスターのキャラクター「ピカチュウ」とコラボレーションしたマンホール「ポケふた」を、みなとみらい21地区周辺に2019年8月5日(月)から設置した と。「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」を正面から。桜木町駅前と横浜ワールドポーターズ前を結ぶ"日本初"の都市型循環式ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマエアキャビン)」が2021年4月22日(木)に運行開始。【全 長】 約1,260m(片道約630m)【最大高さ】 約40m【ゴンドラの特徴】・36台(1台の定員:8名)・バリアフリー対応・冷房完備・夜間景観を演出【事業主体】 泉陽興業株式会社(よこはまコスモワールド 運営会社)【営業時間】10:00~22:00 とのことでこの時はまだ動いてはいなかった。【運 賃】 片道券:大人 1,000円、子ども(3歳~小学生) 500円 にビックリ!!「ランドマークタワー」、階段状の建物「みなとみらい東急スクエア」を見る。その右奥に見えたのが「横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)」、大観覧車「コスモクロック21」。桜木町駅の北改札東口の出口に向かって進む。線路下の通路を進み西口に出ると左側に案内板があった。「温故知新のみち 鉄道発祥の地」。「鉄道発祥の地明治5 (1872)年、品川一横浜間で日本初の鉄道事業の仮営業(本営業は新橋ー横浜間)が開始されました。現在の横浜駅から桜木町駅までの土地は埋立によリ造成され、初代横浜駅(現桜木町駅)が置かれました。鉄道資機材は横浜港から陸揚げされ、横浜から工事が進められました。駅舎は米国人建築家R. P.プリジェンスによリ設計され、ほぼ同しデザインの新橋駅と初代横浜駅は双子の駅と称されました。鉄道事業にはエドモンド・モレルをはじめとする外国人技師が携わり、現在の掃部山(かもんやま)公園には外国人技師の拠点となる官舎が建てられました。掃部山は鉄道開業後も鉄道院用地として利用され、山の地下水が鉄道用水に用いられたことなどから、当時は「鉄道山」と呼ばれていました。明治20 (1887)年に横浜ー国府津間が開通し、初代横浜駅は中間駅となりました。この際行われたスイッチバック運転は輸送能率が悪かったため、貨客利用の増加に合わせ、大正4 (1915)年には現在の高島町駅付近に横浜駅を移転し、初代横浜駅を経由しない新路線が整備されました。あわせて初代横浜駅は桜木町駅へと改称されました。大正7(1918)年には2代目横浜駅と桜木町駅間が高架化され、桜木町駅は京浜線(現在のJR根岸線)の専用駅になりました。大正12 (1923)年には、震災により桜木町駅(初代横浜駅)は駅舎を失いますが、昭和2 (1927)年に移転開業した3代目横浜駅と共に新たな駅舎が建てられました。現在の駅舎は平成元( 1989 )年に建てられました。平成16(2004)年、みなとみらい線の開通により、東横線の桜木町駅が廃駅となりました。それにともない、桜木町駅の整備が行われて、平成26 (2014)年には北改札が新たに開設されました。」「絵葉書「横浜停車場」(明治末~大正初期)・(様浜開港資斟館所蔵)」。「初代横浜駅に停車する列車、(横浜開港資料館所蔵)」。「横浜停車場遠景(明治初期撮影)・(長崎大学附属図書館所蔵)」。「桜木町駅」周辺の観光案内図。現在地は、北改札西口出口。「温故知新のみち」とは安政6年の開港以来、横浜の成長と共に大きく変貌してきた西区のまち。立ち止まってよく見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」はそんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくリ歩いてみてください。きっと新たな発見があリます。「横浜実測図 明治14 (1881)年(中央図書館所蔵)」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.08.30
閲覧総数 562
-
40

3か月でマスターする数学・『酒屋さんの知恵』
この日の学習のテーマの一つは『六合枡から、五合、四合、三合……を得るにはどうすればよいか』と。我が住む地域の名は「六会」、この「六合」の言葉に親近感を覚えるのです。 昔の米屋さんや造り酒屋さんでは六合升というものがあって、それがあると一合から六合まですべてをはかることができると。様々な大きさの枡。「枡」👈️リンク サイズ一覧。6合枡のサイズは抜けているが、内寸125.5☓125.5☓68.6=1080ml程度であろうか。表にないのは、6合枡はあまりポピュラーな枡ではなっかったのであろうか。昔の酒屋さんは、目盛りがついていない6合升を使い、酒樽から1合、2合、3合、4合、5合、6合を正確にくみ出していたのです。このような升を6合万能升と呼びます。6合は升1杯分だからよいとして、ほかの量についてはどのように量っていたのでしようか?その方法を考えてみましよう。酒樽から6合升で酒をくみ出すのは1回限りとしますが、6合升から酒樽へ酒を戻したり、お客さんの容器に酒を注ぐことは何回行ってもよいものとします。●3合の量り方これは簡単です。6合升を、水の部分が三角柱になる。すなわち下図1️⃣のように傾ければ、6合のちょうど半分の3合となります。●1合の量り方6合升を2️⃣のように、水面が底面の対角線と上面の1点を通る三角形となるように傾けると、容器に残る量はちょうど1合になります。この量がちょうど1合であることは3️⃣のようにして確かめられます。1️⃣の3合は三角柱になっていますが、2️⃣は高さと底面が1️⃣の三角形と同じ三角錐(さんかくすい)だから、3合の1/3で1合ということになります。下図の如く、6合升を2️⃣のように、水面が底面の対角線と上面の1点を通る三角形となるように傾ける。2️⃣は高さと底面が1️⃣の三角形と同じ。 三角錐(さんかくすい)だから、3合の1/3で1合ということになります。この量がちょうど1合であることは3️⃣のようにして確かめられます。三角柱水の容積=S(底面積)☓h(高さ)=3合(6合の半分)。テレビの画面。三角錐水の容積=1/3☓S(底面積)☓h(高さ)=1/3☓3合=1合。5合と2合の量り方ます6合升いつばいに酒をくみ、2️⃣の状態になるまでお客さんの容器に酒を注げば、升に残るのは1合。つまリお客さんの容器には5合入ったことになります(4️⃣)。同じようにして1️⃣のように6合の半分の3合くんでから、2️⃣の状態になるまでお客さんの容器に酒を注げば、2合がくみ出せます(5️⃣)。4️⃣:5合の量り方5️⃣:2合の量り方テレビの画面。2合、5合の場合。4合の量り方4合を量るのは少し手間がかかります。まず、6合升いつばいに酒をくみ出し、升に3合だけ残るまでお客さんの容器に酒を注ぎます。この時点で、お客さんの容器には3合の酒が入っています。次に、升に1合が残るように酒樽へ酒を戻し、残った1合をお客さんの容器に注げば、合計で4合が量れたことになります。昔は、一度樽から汲み出した酒を、客の前で元に戻す事に抵抗はなかったのであろうか? ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2024.09.26
閲覧総数 1015
-
41

アイルランド・ロンドンへの旅(その39):Ashford Castle・アシュフォード城
「Ashford Castle Front Gate」から「Ashford Castle・アシュフォード城」の敷地内に入り広大な敷地を道なりに進むと、正面に「Ashford Castle・アシュフォード城」の建物が姿を現した。 手前の道の両脇はゴルフのミニコース?になっているようであった。アッシュフォード城 (Ashford Castle) は、何世紀にもわたって拡張され、メイヨー県とゴールウェイ県の境界のコングの近くで5つ星高級ホテルとなった中世の城であり、アイルランドにあるコリブ湖のほとりに建てられている。建設: 元は1228年、アンガロウ家(Anglo-Norman de Burgo family)によって建てられた 中世の城が起源。拡張・改築: 19世紀後半にギネス家(Guinness family)によって拡張・整備され、現在のような 壮麗な姿に。現在: 「レッド・カーネーション・ホテルズ(Red Carnation Hotels)」という高級ホテル グループが所有・運営。完全なラグジュアリー体験を提供する5つ星ホテル。正門の橋周辺まで歩いて行き、写真撮影することにする。城の裏側に広がる「Lough Corrib(コリブ湖)」沿いの遊歩道やGuinness Tower方面の散策ルートを利用することも可能なようであった。Cong Abbey(コング修道院)から続く森林トレイルもおすすめです と。Ashford Castle・アシュフォード城の上空からの写真をネットから。右奥に見えたのが、「Mrs Tea's on the Ashford Estate」。旬の食材、焼きたての菓子、温かい飲み物、パティオ、そして土産物等を用意した店。近づいて。店の入口。「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」。 土産物。正門の石橋に向かって歩く。アッシュフォード城は、正門の石橋(城門の手前にある橋)を渡った先が私有地になっており、基本的には宿泊者またはレストラン・アフタヌーンティーなどを予約したゲストのみが橋を渡って内部に入ることができるとのこと。一般の立ち入り制限について: 条件 橋を渡れるか 説明・宿泊予約がある ✅ 可能 ホテルゲストとしてフルアクセス可能・レストラン・ アフタヌーンティー等を予約 ✅ 可能 時間制限付きの立ち入りが許可される・観光目的のみ(予約なし) ❌ 原則不可 橋の手前のゲートで止められます・敷地周辺を散策 ✅ 一部可能 コング村側の湖畔や森(公道・遊歩道) は自由に散策可能石橋の手前からアッシュフォード城 (Ashford Castle) を。アッシュフォード城 (Ashford Castle) の塔の上にはアイルランド国旗がはためいていた。1. 中世の城塞風のデザイン ・13世紀に創建され、元々はアングロ・ノルマンのデ・バーク家が築いた防衛用の要塞でした。 ・厚い灰色の石造りの壁と高い塔、狭間(さま)付きの胸壁(防御用のギザギザした上部)が、 中世の風格を今に伝えています。2. ビクトリア朝の増築 ・19世紀後半、ギネス家(ビールで有名な家系)が大規模に改築。 ・ゴシック・リバイバル様式の要素を取り入れ、現在のようなロマンチックな外観に。 ・大きな窓、尖塔、時計塔などもこの時期の特徴です。3. 美しい湖畔の立地 ・アシュフォード城は**ロッホ・コリブ湖(Lough Corrib)**の湖畔に立ち、湖面に映る 城の姿が非常に美しいです。 ・湖を望むテラスや庭園も整備されており、建物の荘厳さと自然の静けさが融合しています。4. 入口の石橋と門塔 ・城の敷地にはアーチ型の石橋がかかっており、その橋を渡ると警備付きのゲートハウス(門塔) があります。 ・ゲートをくぐらないと本館の全景は見えません。前述のように、予約なしでは進入できません。アイルランド国旗をズームして。さらに。アイルランドの国旗は、緑、白、オレンジの縦三色旗です。緑色はカトリック教徒、オレンジ色はプロテスタント教徒を表し、白色は両者の平和と友情を表しています。アイルランドの国旗は、1922年にアイルランド自由国の国旗として採用され、1937年に新憲法で国旗として定められました。国旗の由来と意味:緑色:ケルトの伝統とカトリック教徒を表します。オレンジ色:プロテスタント教徒を表します。白色:カトリック教徒とプロテスタント教徒の平和と友情を表します。アイルランドの国旗は、異なる宗教間の調和と平和を象徴する、アイルランドのアイデンティティを象徴する重要な旗です と。五つ星ホテルの部屋をネットから。石橋を横から。・材質:石造り(切り石)・構造:7つのアーチからなる多連アーチ橋・用途:アシュフォード城の正門へと続く唯一の車道/歩道橋・建設年代:19世紀(城の拡張期)に現在の姿に整備されたと考えられます構造と特徴アーチ型: 水の流れを妨げず、重さを均等に分散するために最適な構造。石材 : 現地産の石灰岩を使用していると推定され、城と調和した灰色の外観。防衛性: 観光目的で設計されたわけではないが、橋の両端に小さな塔を配置し「城門風」に 演出されている。中世の城塞風の美観を意識した意匠です。修復歴 : 近年では観光施設としての維持管理のために補修されているが、橋の原型は 19世紀の拡張工事に基づくものです。7つのアーチからなる多連アーチ橋。橋の両端に小さな塔を配置し「城門風」に。入口には警備員の姿が。そして、アシュフォード城の石造りの門の前には、伝統的なアイルランドの衣装(黒のローブ、緑の帽子、白いソックス)を着たバグパイプ奏者の姿が。宿泊客の歓迎セレモニーや結婚式、イベントの一環として登場するのであろう。この写真の船は、アイルランド西部のコリブ湖(Lough Corrib)をクルーズする観光船 「ISLE OF INISHFREE(イニシュフリー島号)」。船体の側面にその名前が見えた。ズームして。クルーズ内容:・Lough Corrib(コリブ湖)を遊覧・美しい湖の景色や野鳥観察、歴史の紹介など・しばしばアシュフォード城近くから出発し、湖に浮かぶ島々(Inchagoill など)を巡る と。クルージング客の姿はなかったが、次の出発時間は?。そして、駐車場所に戻る。再び「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」の看板を。「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」。こちらもレストラン「Cullen's at the Cottage」。 植栽の中央にあった「ケルト十字(Celtic Cross)」。精巧に加工された花崗岩または石灰岩が使用されており、風化にも耐える重厚な造り。周囲には噴水が。ゴルフコース案内。小規模ながら高級感のある9ホールのコース と。宿泊客専用または予約制のプライベートコースであることが多いようだ。再び「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」を見る。そしてレンタカーに戻り、「アシュフォード・キャッスルST」を利用して帰路に。 敷地内にあった「St Mary's, Church of Ireland・英国国教会」が右手に現れた。・ネオ・ゴシック建築:尖塔(スパイア)と尖頭アーチの窓が特徴的で、19世紀に流行した ネオ・ゴシック様式。・尖塔の高さ:非常に高く、遠くからでも視認可能。・石造りの重厚感:アイルランド西部でよく見られる灰色の石材(おそらく地元産)。Cong Abbey・コング修道院の横を再び通過し、Cong Abbeyの見学時に駐めていた駐車場手前にも入口表示があった。一般観光客のメインエントランスとは別のサービスゲートもしくは関係者専用ゲートのようであったが。そして「Ashford Castle Front Gate」が右手に。先程、探し回って入った正門・メインゲートがこれ。 一時停止してもらって。・構造様式: 厚い灰色の石造りで、2つの塔とアーチ状の門からなる堂々たるゲート。 これは中世の城郭の防御門を模したゴシック・リバイバル様式。・門の上部には防御用の「マシコレーション(machicolation)」風の張り出しがあり、 まさに要塞のような外観。・中央の小さな紋章: アシュフォード城の旧家の紋章、あるいはギネス家時代の装飾の一部と思われます (19世紀、ギネス・ビールの創業者の一族が所有していました)。・門の奥には観光バスが見えたが、これは宿泊者やレストラン利用者を迎え入れる際に使用される 正式なエントランスであることが確認できたのであった。振り返って。そして3連泊のGALWAYのアパートに戻ったルート。R346~R334をひたすら走る。私は助手席でナビっていたが。この日は、部屋での夕食とすることとし、途中のスーパーマーケット・「DUNNES TERRYLAND HEADFORD ROAD」で4人で買い出し。そして部屋にて長い1日であった、この日の反省会を。生ハムはあっという間に無くなったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.06
閲覧総数 125
-
42

アイルランド・ロンドンへの旅(その95): ロンドン散策記・テムズと歴史の道をたどって-10
10月になりましたが、我が「アイルランド・ロンドンへの旅」のブログ・備忘録はまだまだ1ヶ月以上続きますので、ご笑覧ください。 再び、テムズ川から見たロンドンの典型的な景観。手前に川、その向こうに橋と都市のランドマークが広がっていた。左側・St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) ・大きな白いドームと尖塔が目立ちます。 ・17世紀にクリストファー・レン卿が設計したロンドンの象徴的建築。中央手前(橋)・Blackfriars Bridge・ブラックフライアーズ橋 ・赤と白の鉄骨アーチが特徴的な橋。中央奥(橋)・Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋) ・上を走るのはテムズ川を横断する鉄道路線で、Blackfriars駅のホームが橋上にある。右側(高層ビル群) ・一番右端、台形状のビルが20 Fenchurch Street(Walkie Talkie ビル)。右側(高層ビル群)をズームして。左から・Signature by Regus - London Tower 42(茶色のビル、183m)・22 Bishopsgate(ロンドンで最も高いオフィスビル、278m)・The Cheesegrater(Leadenhall Building)(三角形に傾いた形、225m)・The Scalpel(鋭い刃のようなシルエット、190m)Tate Modern(テート・モダン美術館) 付近、Bankside(バンクサイド) に設置されている歩行者用の地図案内。・この地図は 「Legible London(レジブル・ロンドン)」という街歩き用サインシステム の一部。・徒歩での移動時間を示しているのが特徴で、観光客が迷わず歩けるように工夫されています。・特にここでは テート・モダン、セント・ポール大聖堂、ロンドン・アイ といった観光名所に 徒歩で行ける距離感を強調。地図中央に "You are here"(現在地) と書かれており、テムズ川南岸の Bankside、Tate Modern のすぐそばであることが示されていた。この写真の看板はロンドンのテムズ川沿い、South Bank(サウスバンク)エリアにあった。「This is a residential area.Please respect our neighbours while enjoying this space.」 【ここは住宅地です。この場所を楽しむ際は、近隣住民への配慮をお願いします。】テムズ川北岸のランドマーク建築と橋を。中央奥の建物・Shell Mex House(シェル=メックス・ハウス) ・1930年代に建設されたアールデコ様式の大規模ビル。 ・正面中央上部に大きな時計があり「ビッグベンに次ぐロンドンで2番目に大きい時計」。 ・かつては石油会社 Shell-Mex and BP Ltd. の本社として使用された。手前の橋・Waterloo Bridge(ウォータールー橋) ・第二次世界大戦中に建設され、1942年に完成。 ・設計は Sir Giles Gilbert Scott(セント・ポール大聖堂の修復や赤い電話ボックスのデザイン でも知られる建築家)。テムズ川サウスバンクにある Oxo Tower(オクソ・タワー)。 Oxo Tower(オクソ・タワー) のタワー基部の入口と階段を。Oxo Tower(オクソ・タワー)・高さ約69mの塔部分デザイン・白いアールデコ調の塔に、縦に並んだ円形と菱形の窓が配置されていた。・窓の形で「OXO」の文字を表現しているのが最大の特徴。・上部には緑色の銅製の屋根(尖塔)が載っていた。現在は利用されていない?木製の桟橋。テムズ川から Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋)越しに、背後のロンドン中心部を望んで。手前・Blackfriars Railway Bridge(ブラックフライアーズ鉄道橋) ・赤と白の鉄骨装飾を持つアーチ橋。 ・その奥には、Blackfriars 駅のプラットフォームが川をまたぐように造られていて、 列車が行き交うのであった。・St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) ・17世紀にクリストファー・レン卿が設計した、ロンドンを象徴するバロック様式の大聖堂。 ・大ドーム(Great Dome) が中央に堂々とそびえていた。高さ約111m。 ・ドームの左右にある二つの尖塔は 西正面の双塔(West Towers) で、建物正面(西側)に 配置されていた。ズームして。ドームと西正面の塔がセットで見えており、まさにセント・ポールの特徴的なシルエット。テムズ川の北岸、Blackfriars Bridge(ブラックフライアーズ橋)付近の建物群を。左側(尖塔と緑色の屋根のある建物)・City of London School(旧校舎) ・1882年建設のヴィクトリア様式の建物。 ・黒い尖塔と、特徴的な緑青色の屋根。 ・元々はシティ・オブ・ロンドン・スクールの校舎であったが、現在は文化施設・イベント などに利用されていいる と。右側(大きな列柱のある白い建物)・Unilever House(ユニリーバ・ハウス) ・1930年代に建てられた本社ビルで、現在もユニリーバの拠点として使用。 ・古典主義的な大列柱のファサードが特徴。 ・2007〜2008年に改修され、現代的なオフィス機能を。テムズ川沿いのブラックフライアーズ橋への道路下の地下トンネル歩道にあった陶板タイルの壁画(歴史的風景画の再現)。描かれていたのは、・旧ブラックフライアーズ橋(Old Blackfriars Bridge) ・1769年に完成した最初のブラックフライアーズ橋を描いた図。 ・石造の多アーチ橋で、中央に大きなアーチ、両端に複数の小アーチを持っていた。 ・このデザインは当時の版画(18世紀の銅版画)をもとにしている と。・川の情景 ・橋の下を小舟や帆船が行き交い、川面には多くの人々の営みが描かれていた。 ・手前には川を眺める人物や荷物を運ぶ船なども見え、当時のテムズ川のにぎわいを 伝えていた。この壁画もテムズ川沿いの通路に設置されている陶板タイル絵 で、描かれているのは橋の建設風景。・石造アーチ橋の建設過程 ・巨大な木製の支保工(仮設の骨組み)を使い、石を積み上げてアーチを構築している様子。 ・川面に杭や足場を立て、石材を一つずつ積んでいる。 ・完成したアーチと、まだ工事中のアーチが並び、建設途中であることが強調されていた。・作業する人々 ・アーチ上や足場に職人や作業員が描かれている。 ・当時の工法がわかる貴重な記録画。・右端の帆船 ・材料の運搬に船が使われていたことを表現。 ・テムズ川が物流の動脈だった様子が伺えた。この壁画も、初代ブラックフライアーズ橋(1760年代建設、1769年完成) の工事風景。・巨大な木製の仮設構造(センタリング) ・アーチ橋を建設する際に、石が積み上がるまで支えるための木組みの骨組み。 ・完成後に外される一時的な構造物で、18世紀の橋梁建設の典型的な工法。・半完成の石造アーチ ・左側のアーチでは、すでに石材がある程度積み上げられている。 ・右側はまだ木組みの形が強調され、工事の進捗が対比的に示されていた。タイル壁画のキャプション部分。「PART OF THE BRIDGE AT BLACKFRIARSAS IT WAS IN JULY 1766Published by John Boydell, Cheapside」 【ブラックフライアーズの橋の一部1766年7月当時の姿チープサイドのジョン・ボイドル出版】・Blackfriars Bridge(ブラックフライアーズ橋)・最初の橋は1760年から建設され、1769年に完成。・設計者は ロバート・ミルン(Robert Mylne)。・このキャプションは、建設途中(1766年時点)の姿を描いた版画を元にした と。テムズ川から見たセント・ポール大聖堂と旧ブラックフライアーズ橋を描いた歴史的版画の再現。・中央奥:St Paul’s Cathedral(セント・ポール大聖堂) ・クリストファー・レン卿設計、1710年完成。 ・大きなドームと両脇の双塔が特徴的で、当時のロンドンのスカイラインを象徴していました。この陶板タイルの壁画は、19世紀後半のブラックフライアーズ橋周辺の光景を描いた版画の再現。壁画シリーズは、・1760年代:初代橋の建設途中(John Boydell)・1797年:完成後の景観(Thomas Malton)・1860年代:鉄道橋と駅の登場(Illustrated London News)と、時系列でロンドンの交通発展を描き出していた。2代目ブラックフライアーズ橋の開通を祝う行列の様子を描いた歴史的版画の再現。この陶板壁画はセント・ポール大聖堂を背景にしたブラックフライアーズ橋とテムズ川を描いた歴史的な版画の再現。Blackfriars Bridge(ブラックフライアーズ橋)は 2代目ブラックフライアーズ橋(1869年完成)を描いたと考えられると。現代のロンドンのテムズ川沿いのパノラマを描いたカラフルな都市風景画。近づいて。ブラックフライアーズ橋(Blackfriars Bridge) と、その隣に残されている 旧鉄道橋の橋脚跡。右側の赤い円筒状の構造物は、初代ブラックフライアーズ鉄道橋(1864年完成) の橋脚跡。鉄道需要拡大で橋自体は撤去されたが、橋脚だけが現在も川に残っているのだ と。隣接する新しい鉄道橋(現行のBlackfriars Railway Bridge)がすぐ横に架かっているのだ。テムズ川に架かるブラックフライアーズ橋下からロンドンの金融街(シティ・オブ・ロンドン)を望む風景。川面中央付近の細い歩道橋は ミレニアム・ブリッジ(Millennium Bridge)。2000年に開通した歩行者専用吊橋で、テート・モダンとセント・ポール大聖堂を結んでいる。その後方には、前述したロンドンの シティ地区の高層ビル群が。ズームして。右に目を移すと、セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)が。その前に広がる低層の灰色の建物群は シティ・オブ・ロンドン・スクール(City of London School) の校舎。ズームして。さらにドームをズームして。ブラックフライアーズ鉄道橋(Blackfriars Railway Bridge)を振り返って。この橋は石の橋脚と鉄製のアーチ構造を持ち、その上に ガラス張りの屋根 が長く続いています。この屋根は ブラックフライアーズ駅(Blackfriars Station) の一部で、テムズ川をまたぐ形で駅舎が広がっているのが大きな特徴。2012年に改修され、駅のホーム全体がテムズ川の上に広がる形となったのだと。上の屋根には太陽光パネルが設置されており、環境に配慮した「ソーラー駅」としても有名 と。「テムズ川を跨ぐ駅舎を持つ唯一の橋」、ブラックフライアーズ鉄道橋なのであった。One Blackfriars(ワン・ブラックフライアーズ) と呼ばれる超高層ビル。・愛称:「The Vase(花瓶)」とも呼ばれる独特の形状を持つ建物。・高さ:約 170m、50階建て。・竣工:2018年。・用途:高級住宅を中心に、ホテルやレストラン、商業施設が入っている。・設計者:建築家イアン・シンプソン(Ian Simpson)によるデザイン。テムズ川を下る 「Uber Boat by Thames Clippers」。・テムズ川を走る高速通勤・観光用のカタマラン型(双胴船)フェリー。 西は パットニー(Putney) から、東は ウーリッジ(Woolwich Arsenal) まで 全長約25kmにわたって停留所を持ち、観光地やビジネス街をつないでいる と。テムズ川を下る 「Uber Boat by Thames Clippers」を追う。テムズ川南岸にある 「BANKSIDE(バンクサイド)」の観光案内マップ。バンクサイドとは、テムズ川南岸、ロンドン橋(London Bridge)とブラックフライアーズ橋(Blackfriars Bridge)の間に広がる地域。歴史的には劇場・倉庫・造船所が多かったエリアで、現在は文化・芸術・観光の拠点に再開発されているのだ と。中央の大ドームはセント・ポール大聖堂 (St Paul’s Cathedral)。クリストファー・レン卿による設計(完成1708年)。ロンドン大火(1666)の後に建てられたバロック建築の傑作。左の双塔は大聖堂西正面の鐘楼。左右対称に建てられており、教会正面の特徴的なシルエットを形成。手前の赤レンガ建物群はテムズ川沿いのバンクサイド(Bankside)エリアの施設。テート・モダンの近くにあり、川沿い散策でよく目にする建物。Uber Boat by Thames Clippers と違い、この「London Eye River Cruise」は観光解説付き・周遊型 で、通勤や移動のための定期便ではない と。テムズ川南岸の名所 テート・モダン (Tate Modern) の 煙突タワー。・高さ 99メートル のレンガ造り。・発電所時代の象徴をそのまま残しており、テート・モダンのランドマーク的存在。・上部は展望フロア「Blavatnik Building(新館)」とつながり、テムズ川や セント・ポール大聖堂を望む絶景スポットになっている と。この建物は元は火力発電所(Bankside Power Station)・設計者はサー・ジャイルズ・ギルバート・スコット(赤電話ボックスのデザインでも有名)。・1947年から1981年まで稼働していた発電所。現在は美術館・2000年に現代美術館「テート・モダン」としてリニューアルオープン。・ロンドンでも人気観光スポットのひとつで、ピカソ、ダリ、ウォーホル、草間彌生などの 作品を収蔵。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.01
閲覧総数 499
-
43

アイルランド・ロンドンへの旅(その134): ロンドン散策記・日本への帰路-3
北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3) の降機ゲート付近を写す。「阿里云全力支持中国企业出海」→【アリクラウド(阿里雲)は、中国企業の海外進出を全力で支援します。】 阿里云(アリクラウド / Alibaba Cloud) は、中国の大手IT企業アリババ・グループのクラウドコンピューティング部門。飛行機を降りてボーディングブリッジ(搭乗橋)を進み、入国審査(Immigration)・手荷物受取(Baggage Claim)・乗り継ぎ(Transfer) への通路に向かう青地に白文字の案内板には、「出口・行李提取・转机(Exit・Baggage Claim・Transfer)」 と書かれていた。北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3) のエスカレータを上がって。天井の赤い格子状ルーバーと、ガラス壁+赤い鉄骨構造がT3特有のデザインであり、特にT3-CコンコースからT3-E(国際線入国審査)へ向かう通路がここ。🔹標識の内容(原文・英訳・和訳)中国語表記 英語表記 日本語訳转机 Transfer 乗り継ぎ(トランジット)出口、行李提取 Exit, Baggage Claim 出口・手荷物受取所洗手间 Toilet トイレ外国人指纹自助留存 Fingerprint Self-collection 外国人指紋登録機(自動登録機)临时入境许可申请 Temporary Entry 一時入国許可申請(トランジットで Permit Application 一時入国する際に必要) 「入国審査(Immigration)」へ向かう長い移動通路(moving walkway zone)の様子を。ムービングウォーク(動く歩道) の上から入国審査(Immigration)方面へと進む。Transfer・乗り継ぎ(トランジット)審査を通過し進む。北京首都国際空港 第3ターミナル(T3)国際線到着ロビー付近に設けられた中国伝統建築風の庭園パビリオン(中庭式東屋)。T3の設計は「龍が天に昇る空港」をテーマとしており、このような伝統的な中華様式の装飾空間を、ハイテクな建築空間の中に融合させているのが特徴 と。🔹建築様式の特徴この構造は典型的な清朝様式の四阿(あずまや)で、以下の特徴が見られる と。 要素 特徴・意味屋根 青灰色の瓦屋根(歇山頂式、Xieshan Roof)。高貴な建築様式。柱・梁 朱塗りの円柱に彩色(藍・緑・金)を施した「彩画」装飾。天井 「斗拱(ときょう)」構造が装飾的に強調され、金彩と雲文様。揮毫(書額) 上部中央の黒地金文字「月潭华泽(Yuètán Huázé)」が掲げられ、 側面の対聯(ついれん)も金字で書かれています。周囲 岩石・樹木・人工水路などを配置し、「庭園と建築の調和」を演出。中央の扁額には、輝澄月日(huī chéng yuè rì)。これは直訳すると「月と太陽のように光り澄みわたる」という意味であり、清朗な光・明徳・調和の象徴であると。右柱には「天香低度金蠟暖」→【天上の香りが静かに漂い、金の蝋燭のあたたかな光が 柔らかく照らす。】 左柱には「玉殿遥看鳳飛」→【玉の殿堂を遠く望めば、鳳凰が舞い飛ぶ】すなわち【天の香りが柔らかに漂い、金の灯火が温かく輝く。 玉の殿堂を遠くに望めば、鳳凰が舞い昇る光景が見える。】と。空港という「国家の玄関」において、「明るく澄んだ光の中に温かい繁栄と和を祈る」という寓意が込められているのだと。「輝澄月日」扁額と対聯(天香低度金蠟暖/玉殿遥看鳳飛)を掲げた東屋を、少し離れた位置から斜め方向(右前方)に眺めた全景。ここは、国際線到着ロビー内の「中国庭園風休憩区」(通称:国風長廊 Guofeng Gallery)。第3ターミナル(T3)出発フロアに設置されている国際線出発案内モニター。日本・羽田への帰国便は12:45発 CA167 東京羽田。第3ターミナル(T3)国際出発エリア内の中央ホールにある噴水広場。・噴水の中心部は三層式で、上段の水柱が高く噴き上がり、下段には円形に整列した 小噴出口から紫色照明の水流が放射状に広がっています。・周囲を囲む熱帯植物(モンステラ、アグラオネマ、シダなど)が、人工照明下でも 「緑のオアシス」的な雰囲気をつくっています。・手前中央には説明板が設置されており、これはおそらく「首都空港文化展示 (Capital Airport Art & Culture)」シリーズの一部。 内容は噴水の設計コンセプトや、中国文化での「水」の象徴(富・調和・生命)について 触れているもの。解説プレート(案内板)「In October 1979, Yuan Yunsheng, a well-known contemporary painter, completedthe muralThe Water-Splashing Festival – A Hymn of Life for Terminal 1, Beijing Capital International Airport.Based on folklore, it mainly describes the grand scene of carnivals on the Water-Splashing Festival and reveals people's beautiful wishes for loving life, pursuingfreedom and yearning for happiness.In order to better narrow the boundary between art and society, and release the liveliness and vitality of art, Beijing Capital International Airport stereoscopically restores the mural content in a ratio of one to one. It interprets works in anotherform and pays tribute to the classics.This sculpture is one character from the original work of art.」 【1979年10月、現代中国の著名画家・袁运生(ユエン・ユンシェン) は、北京首都国際空港第1ターミナルのために壁画『潑水節—生命の頌歌(The Water-Splashing Festival – A Hymn of Life)』を完成させました。この作品は少数民族の伝承に基づき、潑水節(ポースイジエ、Water-Splashing Festival)の祝祭を題材として、人々の「生命を愛し、自由を求め、幸福を願う」美しい心情を描いています。北京首都国際空港では、芸術と社会との境界を取り払い、芸術の生命力と活力を広く伝えるために、この壁画の一部を原寸大の立体彫刻として再現し、古典的名作への敬意を表しています。※この彫刻は、元の壁画に登場する登場人物の一人を立体化したものです。】潑水節—生命の頌歌(The Water-Splashing Festival – A Hymn of Life)をネットから。有名なモニュメント 「I ❤️ Beijing」 の前景。このモニュメントは、北京空港の「都市アイデンティティと国際的歓迎の象徴」として設置されたもの。北京首都国際空港 第3ターミナル(T3)国際線出発ロビー中央エリアにある伝統建築様式の東屋「国風長廊(Guofeng Gallery)」の一棟を、正面からまっすぐに撮影。東屋「国風長廊(Guofeng Gallery)」の周囲を移動して。北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3)出発エリアの搭乗ゲート付近から見た駐機場(エプロン)の様子。T3Eコンコース(国際線側)のガラス張りの搭乗橋(ボーディングブリッジ)連絡通路から、滑走路南西方向に向かって撮影。第3ターミナル(T3)Eコンコースの国際線出発ゲート付近の待合ロビーを。第3ターミナル(T3E)国際線出発エリアの案内標識とフロアマップ。第3ターミナル(T3)エリアの管制塔(Air Traffic Control Tower)。・名称 北京首都国際空港 管制塔(Beijing Capital Airport ATC Tower)・位置 第3ターミナル(T3)西側滑走路(36R/18L)付近中央・完成年 2007年(T3の開業時)・高さ 約90メートル(地上27階建てに相当)・設計意匠 ノーマン・フォスター建築事務所(Foster + Partners)によるT3全体の デザインコンセプトの一部として設計・外観構造 鋼鉄とガラスで構成された有機的フォルム。 塔身は「花瓶(Vase)」または「竹の幹(Bamboo Stem)」を思わせるくびれ形。・機能 北京空港の全滑走路・誘導路を統合監視し、地上管制・離着陸管制を一元的に行う。北京首都国際空港 ・第3ターミナル(T3)の天井構造を見上げて。天井構造 : アルミニウム製の格子ルーバー(sun louver grid)によって構成。 金色と灰色のラインが幾何学的に交差しています。支柱(柱): 巨大な白色円錐柱(tapered concrete columns)。下から上に向かって 細くなる設計で、天井を軽やかに支える印象を与えています。 採光設計 : 天井の一部に配置されたトップライト(天窓)から自然光を導入。 昼間は人工照明をほとんど使わず、柔らかな拡散光が空間を包みます。色彩構成 : 金(黄)・赤・灰の組み合わせで、中国の伝統的配色「朱金灰」をモダンに再構成。 金は「富と吉祥」、赤は「生命と幸福」を象徴。この天井デザインは、ノーマン・フォスターによる設計思想「竹林を思わせる天井(A Forest of Light)」に基づいている と。T3の屋根は、全長3.25 km/総面積98万㎡という世界最大級の屋根構造の一つ。先ほど見上げた「天井構造」を今度は遠近軸(中央コンコースの縦軸方向)から見通したもの。支柱:白いテーパード円柱が規則的に配置され、構造的にも視覚的にもリズムを形成。 柱の間隔は約60m、1本あたりが「竹」の象徴。「パンダ・フォトフレーム像(Photo Frame Panda)」丸いフォルムのパンダが、インスタグラム風の「撮影フレーム」を持っている。下部にはSNSアイコン(ホーム・検索・ハート・カメラなど)が描かれており、観光写真を意識した現代的演出。滑走路と誘導路の見えるエプロンエリアを。北京首都国際空港 管制塔(Air Traffic Control Tower)🔹概要項目 内容名称 Beijing Capital International Airport ATC Tower(首都机场塔台)完成年 2008年(T3オープン時)高さ 約 97 m(地上から)設計 北京建築設計研究院 × Norman Foster(フォスター&パートナーズ)監修エリア内の 一貫設計役割 滑走路の離着陸誘導、地上走行の管理、気象観測連絡など航空交通の中枢。壁面パネル越しに、外の管制塔が映り込んでいる光景。第3ターミナル(T3)の象徴である航空交通管制塔(Air Traffic Control Tower)をクローズアップで捉えて。・形状 ― 「蓮のつぼみ」または「花瓶」型 塔身は下部が広く、中央がくびれ、 上部が再び開く優雅な流線形。この曲線は中国伝統の「蓮花瓶(れんかびょう)」をモチーフとしており、平安・調和・上昇を象徴します。搭乗便・中国国際航空(Air China、中国国际航空公司)の大型旅客機。Airbus A321-200型機。第3ターミナル(T3)の搭乗ゲート E20 に設置された出発案内表示(Gate Information Board)。搭乗ゲート E20航空会社 中国国際航空(Air China, 中国国际航空公司)便名 CA167行き先 東京・羽田(Tokyo Haneda)出発予定時刻 12:45現在時刻(撮影時) 11:42(June 10, 2025)気温情報(目的地) 23°C/20°C(Heavy rain:大雨)中国国際航空(Air China)の旅客機、奥には同空港のメイン管制塔(Air Traffic Control Tower)を再び。第3ターミナル(T3)Eコンコースの搭乗ゲートE20へ向かう通路から。駐機中の 中国国際航空(Air China, 中国国际航空公司)機・便名 :CA167便・出発地 :北京首都国際空港(PEK)・到着地 :東京・羽田空港(HND)・出発時刻:12:45・使用機材:Airbus A321CA167便に乗り込む。特徴的なフォルムの管制塔(Control Tower)が聳えていた。・高さ 約97メートル・構造 鋼鉄とガラスのハイブリッド構造・外観形状 下部が広がり、中央がくびれた「花瓶型」フォルム(中国の伝統陶磁“瓶”を象る)・機能 滑走路・誘導路・駐機場の航空交通管制(Air Traffic Control)ヨーロッパのエアバス社が製造する 中距離向け・単通路(ナローボディ)旅客機 の代表的モデル。✈️ 基本情報|Airbus A321-200(エアバスA321-200)製造会社: Airbus S.A.S.(フランス・トゥールーズ本社)機種分類: 単通路(ナローボディ)型旅客機シリーズ: A320ファミリー(A318 / A319 / A320 / A321)中で最大初飛行: 1993年運用開始: 1994年(ルフトハンザドイツ航空)Air Chinaへの導入: 1990年代後半から運用開始🧩 A321-200の構造的特徴全長: 約44.5 m(A320より約7 m長い)全幅: 約34.1 m全高: 約11.8 m胴体: A320を延長した設計。座席数を増やし、航続距離も延伸。客席数: (2クラス制) 約180〜200席(ビジネスクラス12席+エコノミー168席など)航続距離: 約4,000〜5,600 km(モデル・積載による)巡航速度: 約840 km/h主なエンジン: CFM56-5B または IAE V2500 シリーズ燃料タンク: A321-200では追加タンクを搭載可能(A321-100より長距離対応。そして定刻に北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)を出発し東京羽田空港へ。最初の機内食。久しぶりの白米を楽しむ。そして羽田空港に到着し、到着、入国審査の方向に進む。羽田空港(Tokyo International Airport/東京国際空港)第3ターミナル。雨で濡れたエプロン(駐機場)と、航空機への給油車や手荷物搬送車などの地上支援車両が見られたのであった。到着ゲートから入国審査(Immigration)や乗り継ぎエリアに向かう途中のエスカレーター手前。長い 動く歩道(moving walkway) が続くガラス張りの通路で、右側は白い壁、左側は全面ガラスの吹き抜け構造。床は赤と緑の模様が入ったカーペットで、これは第3ターミナルの到着・乗り継ぎ導線に共通するデザイン。外に見えたのが羽田空港第3ターミナルビル(旧・国際線ターミナル)。駐機中のJAL機が並ぶ、南側エプロン(滑走路A側)に面した位置。この場所は、羽田空港第3ターミナルの名所の一つである羽田空港第3ターミナル・国際線エリアの連絡通路(サテライト⇔本館)で、動く歩道から外を望む。外のJAL機と連続する広告照明が織りなす、美しい構図。・デザイン意図 北京の伝統文化(壺・蓮)とハイテク空港の未来性の融合Airbus A321-200。中央に見えるのは、羽田空港の管制塔(Control Tower)。これは羽田空港の第二管制塔(現・主管制塔)で、2010年に供用開始された高さ約116メートルの構造物。現在は羽田空港全体(第1〜第3ターミナルおよび滑走路A〜D)を統括。搭乗口番号「140」が見えた。これは第3ターミナル(国際線)サテライト側ゲートの一部。写真中央には動く歩道(moving walkway)が2本並行して設置されており、左右に人々が移動中。「日本へ帰ってきた瞬間」—長旅を終えて入国審査に向かう、羽田空港ならではの“帰国動線”の一場面なのであった。そして1.検疫→2.入国審査→3.手荷物受取り→4.動物検疫・植物検疫→5.税関検査→6到着ロビー へと。入国審査(Immigration)。3.手荷物受取り私は、ロンドン・ヒースロー空港にて荷物が行方不明・「ロストバゲージ」になったため、ここ、 baggage carousel(バゲージ キャロセル)に出て来ることを期待して待ったが、荷物には再会できなかった。そして荷物引取所(バゲージクレイム)に向かい、荷物がヒースロー空港で行方不明になったこと、その経緯を、女性担当官に説明し、クレームタグ(預けた際にもらったタグの半券)と航空券を渡す。クレームタグ。そして女性係員が「手荷物紛失証明書(PIR)」に私からの情報を書き込んでくれた。・氏名、住所、連絡先・搭乗便名、日付・手荷物の特徴(色・形・ブランド・サイズ・タグ番号) また、トランクのKEY番号、ベルトのKEY番号を知らせ、ハードKEYを手渡した。・不具合の内容(紛失・遅延・破損 など)「手荷物紛失証明書(PIR:Property Irregularity Report)」は、航空会社が預かった手荷物が目的地で見つからない、破損している、または遅れて届いた場合に発行される公式なトラブル報告書。PIRは、航空会社またはその地上取扱会社(ハンドリングエージェント)が、手荷物に関する不具合(Irregularity)を正式に記録する書類。これは「手荷物が紛失・遅延・破損した」という事実を証明する重要な書類であり、後の捜索・補償・保険請求の基礎資料となるのであった。・さらに係員から、荷物の捜索情報は、スマホに連絡をもらえる。・荷物が発見された場合は、自宅まで無料送付する。 しかし、荷物の中に禁止物が入っていたことが判明したら、その品物は回収されたのち、 羽田空港から自宅までの運送費は着払いになると。そして手続きを完了し、係員の方が税関窓口まで同行してくれて、税関職員に事情を説明してくれて、税関を通過したのであった。そして、バスにて横浜駅・Yキャットへ。そしてJR東海道線、小田急線を利用して帰宅したのであった。そして帰宅後の次の日に、我がトランクはヒースロー空港にあり、北京空港に送付されると。そしてその2日後に北京空港から羽田空港への移動中であるとの連絡をいただいたのであった。そして私が帰宅してから5日後に、遅れて我が荷物も無料で帰宅したのであった。内部を確認したが、全てが無事に、破損等もなく帰宅したのであった。わがトランクは何処を彷徨っていたのかは依然として不明なのであるが・・・やれやれ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アイルランド8日間、ロンドン4日間、高校時代の親友4人、合計≒300歳での旅であった。アイルランド・緑と石の国——どこまでも広がる牧草地と石垣の風景に、時間の流れの穏やかさを感じた。・人の温かさ——道を尋ねても、店に入っても、どこか親しみのこもった笑顔と会話が印象的。・修道院や教会の静謐 Kylemore AbbeyやCong Abbeyなど、廃墟や修道院に漂う静けさが心に残る。・歴史が息づく街並み AthloneやGalwayの街角では、中世から続く建物と現代の暮らしが自然に共存していた。・音楽と酒場文化 パブで流れるアイリッシュ音楽と人々の歌声に、土地の誇りと人生の楽しさを感じた。・自然の雄大さ ConnemaraやKillarneyの湖水地方の眺望は、まさに「神に守られた緑の楽園」。・ステンドグラスと芸術性 教会や博物館で見た彩色ガラスの美しさに、信仰と美の融合を感じた。・交通と気候の印象 雨と霧が交互に訪れ、風景の色合いを刻々と変える「変わりやすい天気」も旅の一部として 楽しめたのであった。日本との時差 -9時間フライト時間 約15~16時間公用語 英語・ゲール語通貨 ユーロアイルランド。アイルランドはEUの一部であり、協力関係を築きながら、欧州全体の自由な移動を可能にするシェンゲン協定には参加せず、独自の国境管理を維持。アイルランド国旗。北海道との広さの比較。緯度の比較。ダブリン:53.43°N宗谷岬 :45.52°Nダブリン~宗谷岬 距離差 :850km北アイルランド特有の石碑である ハイクロス(High Cross)、別名 ケルト十字(Celtic Cross)。モハー断崖。海上の岩柱 ブリーナン・モア(Branaunmore)。カイルモア・アビー(Kylemore Abbey)。ハーフペニー橋(Ha’penny Bridge)。THE TEMPLE BAR。名門大学 トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)。ダブリン城。ロンドン・歴史と現代が共存する都市 セント・ポール大聖堂からタワー・ブリッジまで歩くと、過去と現在が交錯する時間の旅のよう。・テムズ川の流れ ゆったりとした川の流れが、ロンドンの壮大な歴史を静かに語っているようだった。・建築の多様性 古典的な石造建築と近代的なガラスの高層ビルが見事に共存している。・象徴的なランドマーク ロンドン・アイ、ウェストミンスター宮殿、タワー・オブ・ロンドンなど、どこを見ても 「物語の舞台」。・街歩きの楽しさ 橋を渡るごとに風景が変わり、歩くことそのものが「観光」になる街。・芸術と知性の香り 博物館やギャラリーの無料公開、街角の彫像や記念碑にも文化の厚みを感じた。・夜景の美しさ ライトアップされた橋や建物が川面に映り、幻想的な光景をつくり出していた。・多国籍都市のエネルギー 人々の多様な言語と文化が混ざり合い、世界都市の鼓動を肌で感じた のであった。イギリス国旗。 ビッグ・ベン、ウェストミンスター橋。 ロンドン・アイ。タワー・ブリッジ。ロンドン塔。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)。ケンジントン宮殿(Kensington Palace) と、その前庭に立つ ヴィクトリア女王像(Statue of Queen Victoria)。 Lost Luggag!! 無事に我が家に戻ったトランク(右)。 ・・・もどる・・・
2025.11.09
閲覧総数 403
-
44

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5
★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹👈️ ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設👈️ 六会中学校にプール完成 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」発表👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.14
閲覧総数 781
-
45

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6
★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進 が分裂 森友・加計政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界 で不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 【以下 後日記入】 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 202 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・
2025.11.15
閲覧総数 375
-
46

成田山新勝寺へ
ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。
2025.11.16
閲覧総数 385
-
47

牛久大仏へ(その2)
牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.18
閲覧総数 377
-
48

藤沢・用田散策(その1):薬王寺~女坂石塔列~中将姫祠~寿昌寺~
【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク用田の女坂一般廃棄処分場の近くに、特徴のある屋根の本堂が。中央が突き出ている本堂の屋根。「女坂の花桃のお寺」で知られる用田の日蓮宗妙龍山薬王寺。寺標の向うに日蓮上人の立像。 3代続く尼寺とのこと。ご本尊は薬王菩薩。 『薬王寺』 と書かれた扁額。本堂内部。 薬王菩薩石造か? 境内右手には3本の石柱が。 薬王寺を後にし、中将姫祠に向かう途中の中原街道手前の藤沢市用田33、女坂の石塔列。一番右から馬頭観世音塔、単体道祖神、安曇野型双代道祖神、不明石、そして一番左に文字庚申供養塔。馬頭観世音。安曇野型双代道祖神。比較的新しそう。 その先の小さな祠には地蔵様が。 東海道新幹線の下を潜り、狭い農道を進むと『中将姫入口』の案内板を発見。 畑道を通り林の中を下ると竹林が拡がりその中に中将姫の祠が鎮座。『中将姫は奈良時代の右大臣藤原豊成公の娘で、幼くして母を失い継母に育てられた。しかし、その美貌と秀でた才能から継母に嫉まれ、命を狙われ面で顔を隠す逃亡生活。その面は寿昌寺に預けられた後、用田の寒川神社へと納められたが盗難に遭い現存していない。その後、姫は父と再会し一度は都に戻ったが願いにより当麻寺へ入り、17歳で中将法如として仏門に入り称賛浄土経一千巻の写経を達成した後、阿弥陀如来と観世音菩薩の力の元に、百駄の蓮の茎より一夜にして一丈五尺(約4m四方)もの蓮糸曼荼羅を織り上げた。その後29歳を迎えられた中将法如は、光仁天皇の宝亀6年(775)3月14日、諸仏の来迎を受けて大往生を遂げた。』と案内板に書かれてあった。鎌倉材木座の光明寺には、中将姫の伝説を描いた『当麻曼荼羅縁起絵巻』が伝えられ、鎌倉国宝館に寄託されているとのこと。この祠は、逃避行中に姫がこの地に隠れ住んだという伝承があり、お参りすると子宝に恵まれるといわれていると。中将法如の命日である毎年3月14日には地元の中条の人々が集まってお祭りを行うとのこと。中将姫祠内部。中央に中将姫の姿が描かれた額に入った絵画。『当麻曼荼羅縁起絵巻』(二巻)は、奈良当麻寺の浄土変相図の由来を描いたもので国宝。奈良時代、聖武天皇の頃、横佩の大臣(藤原豊成)の姫が極楽往生を祈念し、蓮糸で曼荼羅を織りあげ、やがて阿弥陀如来のお迎えを受け、極楽へ旅立つという物語。この後は更に歩を進め、相模丘陵の間を流れる目久尻川沿いに建つ寺 寿昌寺を訪ねる。 護法山と号する用田の字中条にある曹洞宗の寺院。1613(慶長18)年に創建され、開基は用田区の豪農にして大庄屋として知られる伊東家の伊東孫右衛門、開祖は僧・通山。元遠藤宝泉寺の末寺で、6世悦道が中興の祖とされている。山門付近には大銀杏が2本あり寺のシンボル、続く参道も石燈籠が並び豊かな緑に囲まれていた。また、創建以来ほとんど火災に会っていないほか、関東大震災でも倒壊しなかった数少ない寺院のひとつで、本堂には地獄絵図2幅、十六羅漢像、まわり地蔵などが残されていると。 『曹洞宗 寿昌禅寺』と刻まれた寺標とその横に『寿昌寺略縁起』の石碑が。『無縁之塔』には多くの無縁仏の墓碑がピラミット状に積まれていた。 山門横に六地蔵とその左に3体の仏像が。歴史を感じさせる重厚な姿の石灯籠。 境内にあった小さな社。 山門は質素ではあったが、歴史が感じられる造り。山門から本堂までの参道は良く手入れた植栽が左右に。参道を進み、本堂手前まで進む。 十三石塔。 参道脇のお堂。 屋根が拡がる本堂。 『護法山』と書かれた扁額。 本堂内部。本堂手前の観音像。 優しいお顔の掃除小僧にお会いしました。 菩薩石造。 歴代大和尚の名が刻まれた大きな石板碑。開山の僧 通算ぎん(門篇に言)達大和尚 慶長4年(1599)から現和尚まで34代の名が。境内から再び山門を見る。 道に迷いながらも伊東家墓地へ。この伊東家の墓は、かつてこの地にあった豪族伊東家の墓が集まる史跡。伊東氏は、戦国時代に伊豆からこの用田の地に移り、用田村を草創した一族。江戸時代には相模でも屈指の豪農・大庄屋として栄え、菩提寺である寿昌寺や示現寺、用田村の鎮守である用田寒川社を創建するなど、現在でも残る寺社を残しているのだ。この史跡は、深い森のなかに寛永年間から近年までの一族代々の墓碑や庚申塔など、300基近くがが並んでいるのだと。
2016.11.20
閲覧総数 1808
-
49

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その25)・ 浜須賀海岸~八大龍王碑~ヘッドランド(Tバー)~茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館~恵泉キリスト教会湘南グレースチャペル~佐々木氏追悼記念碑
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次国道134号「小和田浜公園東側」交差点を渡り海岸に向かって進む。海岸に出た場所が「浜須賀」と「汐見台」の境界近くで現在の「サザンビーチちがさき」の最も東側の場所。遠くに「江の島」の姿が確認できた。この先約500mで藤沢市の「辻堂海岸」。「江の島」をズームして。更に「江の島シーキャンドル」を。そして「姥島(烏帽子岩)」。ズームして。そして「浜須賀」海岸を見る。1953(昭和28)年の浜須賀の海岸の写真。「太平洋戦争」後、「茅ヶ崎海岸」の旧「日本海軍」施設は、「連合国軍」(のち「米軍」)に接収された。「烏帽子岩」を含む沖合一帯も含まれ、「チガサキ・ビーチ」と名付けられた。特に「横須賀海軍砲術学校 辻堂演習場」跡地の約103万㎡(「東京ドーム」約22個分)の広大な敷地では、上陸、砲撃、爆発物の処理などの訓練が行われた。下記写真は1953(昭和28)年に撮影された、「米陸軍第1騎兵師団」の上陸演習風景。右奥にはうっすらと「江の島」が見える。演習は、騒音などで住民に多大な影響を及ぼし、戦車の砲撃訓練では「烏帽子岩」に照準が合わせられ、先端が吹き飛ばされた。「チガサキ・ビーチ」は1959(昭和34)年に日本に返還された。演習場を迂回していた「国道134号」(旧「湘南遊歩道」)は、翌1960(昭和35)年に海岸沿い部分が開通した。現在、演習場の跡地は「神奈川県立辻堂海浜公園」をはじめ「UR(都市再生機構)」の「辻堂団地」「湘南工科大学」「松下政経塾」などになっている。「湘南海岸サイクリングロード ランニングコース」を「ヘッドランド(Tバー)」に向かって進む。「湘南海岸サイクリングロードコースマップ」。【コースデータ】・距離:5.8km 鵠沼海浜公園の起点~茅ヶ崎サザンCまで・距離表示の有無:時々出現・道幅/道の状態(アスファルト、砂など):アスファルト ※風の強い日は砂に覆われていることも・・・・高低差:15m ※ほぼ平坦・信号の有無:無・トイレの有無:有・給水箇所:スタートとゴール地点には自販機があるが、道中は無。辻堂海浜公園などに コースアウトすれば有り。・ランステなど着替え/シャワー施設の有無:スタート地点付近の鵠沼スケートパーク内、 ゴール地点の茅ヶ崎サザンビーチで有料シャワー有り・ランナーの多さ:休日はランナー、自転車は多いが混雑は無・車の往来:無・夜の走りやすさ(明るい、暗い):暗い・駅からのアクセス:鵠沼海岸駅徒歩15分・景色の良さ:良好「津波避難情報」。現在地は海抜5.8mと。「湘南海岸サイクリングロード」の車止め?の反射板が取り付けられている石も「烏帽子岩」の形で。「S-29 茅ヶ崎市浜須賀柳島4.7km← →鵠沼海岸3.0km」「S-29 」の意味は? S:SOUTHか?竹造りの防砂垣をすり抜けて多くの砂がランニングロードにあったが、係の方に隅に片付けられていた。そして右側奥の防砂林の中に朱の鳥居があった。朱の鳥居の扁額は「八大龍王」。「八大龍王」碑。裏側には「元治元(1864年)甲子卯月吉日 再建」とあった。再び「烏帽子岩」を見る。神奈川県茅ヶ崎市9 相模湾 と。再び「サザンビーチちがさき」の「浜須賀海岸」&「江の島」を見る。海岸で投釣りをする御夫婦の姿を。「ヘッドランドビーチ」から「ヘッドランド(Tバー)」越しに「茅ヶ崎港」方向を見る。「明治後期のヘッドランドビーチ」「相模湾」では鎌倉時代から地引網漁が行われていた。明治後期、小和田村には10軒の網元がいたという。明治期から大正期にかけて、浜が忙しいときは漁に出て、漁がなければ畑を耕すという半漁半農だった。中海岸にある「カネサ網重政商店」は1887(明治20)年創業の老舗で、「相模湾」で専業漁業地引網元として漁師を営むかたわら、加工業も行っている。 【https://smtrc.jp/town-archives/city/chigasaki/p07.html?id=a03】より「ヘッドランド(Tバー)」をズームして。茅ヶ崎「ヘッドランド(Tバー)」は砂浜と石積の堤防からなる釣り場。ヘッドランドは砂浜の浸食を防ぐための人口の岬で、T字型になっているので「Tバー」とも呼ばれている。「現在の湘南の海は、マリンレジャーや海水浴客が多く、かつての地引網漁の風景から大きく変わっている。1950年代、駐留する米兵が、日本にサーフィンを持ち込んだといわれる。1960年代後半には、雑誌『平凡パンチ』にサーフィンの記事が掲載され話題を呼び、茅ヶ崎・辻堂近辺のショップも紹介されるようになった。また、1970年代後半には雑誌『POPEYE』などでも湘南エリアのサーファーやサーフショップが特集され、特に湘南がサーフィンの地として脚光を浴びることになった。湘南の海岸は東京からアクセスしやすいこともあり、多くのサーファーたちが訪れるようになっている。」手前には波を待つサーファーの姿が。烏帽子岩を最大ズームで。釣り人の姿が左側に。そして海岸を離れて国道134号「菱沼海岸」交差点に出る。交差点の向かいの前方に高級マンション「パシフィックガーデン茅ヶ崎」の建物が。4380万円(3LDK)と。LDKは約19帖、全居室6帖以上の広さの南向き3LDK住戸。南北の両面バルコニーにつき通風良好。リゾート感あふれる白壁のマンションであると。「茅ヶ崎菱沼海岸 N-31」。「菱沼海岸」交差点を渡り、高級マンション「パシフィックガーデン茅ヶ崎」を左に見ながら進む。実はこの「パシフィックガーデン茅ヶ崎」の建つ場所には、昔は「パシフィックホテル茅ヶ崎」があったのだ。1965年(昭和40年)湘南海岸・国道134号線沿いに、俳優の上原謙、加山雄三、小桜葉子(本名:岩倉具子)の弟岩倉具憲らが共同オーナーとなって建設・開業されたホテルである。当時の「パシフィックホテル茅ヶ崎」。残念ながら、1970年運営会社株式会社パシフィックジャパンが倒産。ホテルは売却され、その後、休業・再開を繰り返すも1988年完全に廃業となった。廃墟と化した建物も1998年に取り壊され、1999年跡地にはリゾートマンション「パシフィックガーデン茅ヶ崎」が建設されたのであった。国道134号線 湘南海岸に異様とも見える、ひときわ高くそびえたっていた姿が懐かしいのであるが。 【https://ameblo.jp/sayojikan/entry-12177868827.html】よりそして茅ヶ崎市東海岸南6丁目6の住宅街を北に進む。道路沿いの左手に「茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館」案内板があった。「茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館」案内がその先にもあった。左に折れ「茅ヶ崎市開高健記念館」に向かって進む。正面に門柱と両開きの白い門扉が。「茅ヶ崎市 開高健記念館」。この時まで「かいこうたけし」ではなく「かいこうけん」と思っていたのであった。(1930-1989)大阪市生れ。大阪市立大卒。1958(昭和33)年、「裸の王様」で芥川賞を受賞して以来、「日本三文オペラ」「流亡記」など、次々に話題作を発表。1960年代になってからは、しばしばヴェトナムの戦場に赴く。その経験は「輝ける闇」「夏の闇」などに色濃く影を落としている。1978年、「玉、砕ける」で川端康成賞、1981年、一連のルポルタージュ文学により菊池寛賞、1986年、自伝的長編「耳の物語」で日本文学大賞を受けるなど、受賞多数。『開高健全集』全22巻(新潮社刊)。「臨時休館」と。表札には「開高健 牧羊子」と。牧羊子は大阪府生まれ。奈良女子師範学校物理化学科(現、奈良女子大学)卒業。教師を経て戦後、壽屋(現・サントリー)に勤務。同人誌「えんぴつ」で7歳年下の開高健と知り合い、1951年に結婚。開高の壽屋入社と入れ違いに退社し創作活動に入る。娘はエッセイストの開高道子。詩のほか料理に関するエッセイが多かった。2000年1月19日、夫、娘に先立たれて一人住まいをしていた茅ケ崎の自宅で持病の悪化のためにひとり倒れて亡くなっているのが発見された。検死の結果、病死で死後数日と見られた。墓所は鎌倉・円覚寺塔中、松嶺院にある と。茅ケ崎市開高健記念館リーフレット(表面)。■開高健略年譜1930 (昭和5)年 12月30日、大阪市天王寺区東平野町に生まれる。1948 (昭和23)年 旧制大阪高等学校文科甲類に入学。1949 (昭和24)年 学制改革により、大阪市立大学法文学部法学科に人学。1950 (昭和25)年 処女作「印象生活」を「市大文芸」に発表。 同人誌「えんびつ」に加入。1951 (昭和26)年 「あかでみあ めらんこりあ」を「えんびつ」解散記念とし て刊行。1952 (昭和27)年 住吉区杉本町の牧羊子の家へ移る。長女道子生。1954 (昭和29)年 寿屋(現・サントリー)に入社、宣伝部員に。 1957 (昭和32)年 「バニック」を「新日本文学」に発表。一躍新人作家として 注目される。1958 (昭和33)年 「裸の王様」で第38回芥川賞を受賞。寿屋を退職。嘱託となる。 杉区矢頭町に自宅をかまえる。1959(昭和34)年 「日本三文オペラ」を文藝春秋新社より刊行。1960(昭和35)年 中国訪問日本文学代表団の一員として中国を訪問。 「ロビンソンの末裔」を中央公論社より刊行。1961 (昭和36)年 「過去と末来の国々」を岩波書店より刊行。 アイヒマン裁判の傍聴にイスラエルに赴く。1964(昭和39)年 「ずばり東京」を朝日新聞社より、「見た揺れた笑われた」 を筑摩書房より刊行。 朝日新聞社臨時海外特派員としてベトナムへ出発。1965 (昭和40)年 戦地取材中、ベトコンに包囲されるが、死地を脱出。 「ベトナム戦記」を朝日新聞社より刊行。1968 (昭和43)年 「輝ける闇」を新潮社より刊行、毎日出版文化賞を受賞。1969 (昭和44)年 ビアフラ・中東戦争を視察。1971 (昭和46)年 「フィッシュ・オン」を朝日新聞社より刊行。1972 (昭和47)年 「夏の闇」を新潮社より刊行、文部大臣賞を打診されたが辞退。1974 (昭和49)年 茅ヶ崎市東海岸南に仕事場を完成し、移り住む。1978 (昭和53)年 「ロマネ・コンティ・一九三五年」を文藝舂秋より、「オーパ!」を 集英社より刊行。芥川賞選考委員に加わる。1979 (昭和54)年 「最後の晩餐」を文春秋より刊行。 「玉、砕ける」で川端康成文学賞を受賞。 南北アメリカ大陸縦断旅行。1981 (昭和56)年 「もっと遠く!」、「もっと広く」を朝日新聞社より刊行。 ー連のルポルタージュ文学により菊池寛賞を受賞。1983 (晒和58)年 「オーバ、オーバ!!」を集英社より刊行。1986 (昭和61)年 「耳の物語」を新潮社より刊行、翌年、日本文学大賞を受賞。1989 (昭和64・平成元)年 「珠玉」第三部を脱稿、翌年文藝春秋より刊行。 12月9日、食道潰瘍に肺炎を併発し逝く。 北鎌倉・円覚寺松嶺院に眠る。」茅ケ崎市開高健記念館リーフレット(裏面)。「ふつう私は小説家として暮している。ここ五年ほどは湘南海岸の茅ヶ崎市である。海岸から三百メートルか四百メートルほどのところでひっそりと起居している。月曜日と木曜日の夕方になると二キロ離れたところにある水泳教室へ行くために外出するが、それ以外はほとんど家にたれこめたきりである。」(「国境の南」から)作家開高健は1974 (昭和49 )年に茅ヶ崎市東海岸南のこの地に移り住み、亡くなるまでここを拠点に活動を展開されました。その業績や人となりにふれていただくことを目的に邸宅を開高健記念館として開設。書斎は往時のままに、展示コーナーでは、期間をさだめてテーマを設定し、原稿や愛用の品々を展示してまいります。これらを通じて、たぐい稀なその足跡を多くの方々にたどっていただけるなら幸いです。」隣にあったのが「茅ヶ崎 ゆかりの人物館」案内板。「ラチエン通り沿いの、海を望む小さな丘に、「ひと」と「まち」をつなぐ新しい文化交流の拠点として、平成27年2月に誕生した「茅ヶ崎ゆかりの人物館」。茅ヶ崎の新しいまちづくりに貢献するために、ひとを結び、賑わいを創る次世代型のミュージアムとして市民と共に成長していきます。」と。丘の上に在る「茅ヶ崎 ゆかりの人物館」。「茅ヶ崎市開高健記念館・茅ヶ崎ゆかりの人物館」入館案内。「茅ヶ崎ゆかりの人物館」をネットから。 【https://www.shonan-navi.net/shop/shop.shtml?s=4790】より再び「茅ヶ崎市開高健記念館」👈リンク を見る。庭先には「朝露の一滴にも天と地が映っている 開高健」と。「この石のことを思い出すたびに月下に輝く白い宮殿と巨大な鐘の沈んだ深い淵という光景を思い出す。(略)エンドウ豆ほどの石から宮殿を喚起するのは誇大妄想に近いけれど、最初の一瞥の魔力にとらえられているのだし、朝露の一滴にも天と地が映っているのだという託宣からすれば荒唐とは感じられない。(「珠玉」文藝春秋刊 147頁)スマホの案内に従い次の目的地の「恵泉キリスト教会湘南グレースチャペル」に向かって茅ヶ崎市東海岸6丁目の住宅街を進む。民家の庭の桜を楽しむ。そして「恵泉キリスト教会湘南グレースチャペル」に到着。神奈川県茅ヶ崎市東海岸南6丁目1−20。「キリスト教は初めてという方には、キリスト教の団体はとても分かりにくいと思います。日本で良く知られているのは、カトリック、プロテスタント、正教会(ギリシャ正教・ロシア正教など)の3つだと思います。私たちはプロテスタントの教会です。プロテスタントにはたくさんの団体があり、その中で「保守バプテスト同盟」という団体に所属しています。所属教会は東北地方に多く、約60教会が加盟しています。さらに、湘南グレースチャペルは、「恵泉キリスト教会」という教会の1つのチャペルです。恵泉キリスト教会はもともと1つの教会でしたが、教会員の転勤や被災地支援などがきっかけで新しい教会を作り、現在は11のチャペルがあります。山形県米沢市にある恵泉キリスト教会米沢チャペルに通っていた教会員が転勤で茅ケ崎市に戻ることになり、自宅で教会を始めることにしました。牧師がいない教会でしたので、恵泉キリスト教会の他のチャペルの牧師が毎週応援に来てくださっていました。最初は自宅のリビングで集会をしていましたが、手狭になり、現在の会堂を増築しました。その後、家と教会を切り離したため、現在の民家のような会堂が残っています。2010年に牧師を迎えて現在に至ります。」とHPより。茅ヶ崎市東海岸南5丁目2にあった樹々に囲まれた巨大な屋敷の山門が左手に。住居を樹々の隙間から見上げる。そして前方に「鉄砲道」が見えて来た。「鉄砲道」との合流地点の角にあったのが「佐々木氏追悼記念碑(佐々木卯之助)」。写真は「東海岸北五丁目交差点」で、ここまで歩いて来た右の道が旧「鉄砲道」、左が現在の「鉄砲道」。この分岐点に「佐々木氏追悼記念碑」(写真中央付近)が建てられていた。佐々木伝左衛門の子として生まれた卯之助は、1824(文政7年)、29歳の時に江戸幕府の相州炮術調練所の責任者として、幕府大筒役となった。当時茅ヶ崎の海岸は幕府による天領とされていて、鉄炮方役人の銃術鍛錬の場として茅ヶ崎柳島村から藤沢の片瀬までの広域に調練場が設置されていた。赴任中に、いわゆる佐々木卯之助事件が発生する。時は天保(1833~1839)。大筒役を命ぜられた卯之助であったが、世は大飢饉に見舞われ、民は食料に困窮し、餓死者が発生。天保の大飢饉に発展した。この茅ヶ崎の民の惨状を目の当たりにし、卯之助は相州炮術調練場の敷地(茅ヶ崎市南湖の周辺)の一部を開放、耕作することを事実上黙認。卯之助の計らいは、茅ヶ崎の民から大変感謝された。しかし、のちの検地により、この耕作が発覚し卯之助は長男の菊次郎と共に、伊豆の離島青ヶ島へ遠島の判決を受けた。1868(明治元年)に赦免となるが、明治9年、82歳で青ヶ島で死去する。死後、初代茅ヶ崎村長の発起人により、感謝を表し茅ヶ崎市東海岸五丁目に追悼の碑を建立。また、半農半漁だった茅ヶ崎市南湖の人たちは、鉄砲場内の耕作の恩恵に感謝し、南湖地区中町八雲神社境内に記念碑を建てた。墓標は当初青ヶ島にあったが、のちに海前寺(茅ヶ崎市本村四丁目)に移されている。茅ヶ崎には鉄砲道と呼ばれる通りがあり、この相州炮術調練場まで、伊豆の韮山反射炉で作られた鉄砲が運ばれる道であったという説がある。「佐々木氏追悼記念碑」茅ヶ崎の農民は、卯之助への感謝を忘れることはなく、1898(明治31)年、初代茅ヶ崎村長が発起人となり「佐々木氏追悼記念碑」を建立した。「佐々木卯之助追悼記念碑のいわれ茅ヶ崎一帯の海浜は享保十三年以来幕府の鉄砲場となっており、区域内への村民の立入りや耕作などは禁じられていた。佐々木卯之助が大筒役(鉄砲方役人)になったのは文政七年のことで、そのころ南湖では田畑が少なく農民はこの地の耕作を願っていた。それを察した佐々木氏は上司に内密で耕作を許可し、農民はこの情けある計らいに心から感謝していた。しかし、この事が発覚するに至り天保六年その罪で佐々木氏は八丈島を経て青ヶ島へ遠島となりその後赦免となったが、かの地で一生を終えた。時移り明治三十一年、茅ヶ崎村村長、伊藤里之助が発起人となり村の恩人・佐々木氏を追悼してこの碑を建立した。初め南湖六道の辻に建てられたが逝たびか場所が変わり末永くこの地に収めることになった」裏面には「昭和五十六年五月五日 佐々木卯之助記念碑移設委員会 東海岸自治体」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.05.02
閲覧総数 693
-
50

ナスカの地上絵 新発見と
『山形大の研究グループは8日、世界遺産「ナスカの地上絵」で知られる南米ペルーのナスカ台地とその周辺で、新たに168点の地上絵を発見したと。研究グループが発見した地上絵は、今回の発表分を含め、計358点に上る。』とのニュース報道一昨日・12月10日(土)のテレビで見ました。以下の写真はテレビ画面をカメラで撮影したものです。同大ナスカ研究所副所長の坂井正人教授らの研究グループが2019~20年にドローンを活用して現地調査を行い、168点の地上絵を確認した。16~18年の調査でも142点の地上絵を発見しており、分布の傾向がある程度明らかになっていたことから、ドローンを用いて計画的に調査した。今回見つかった地上絵は、人間や鳥、ヘビなどの動物が描かれており、絵柄の特徴から紀元前100年~紀元300年頃に作られたと考えられる。最も大きいもので全長50メートル以上あったが、ほとんどが10メートル以下の小型のものだという。下の写真は分かりやすくするため線を加えたもの(山形大学提供)とのこと。新発見のナスカの地上絵は『かわいい人型』。『人形』。『人形』。『人と首』と。『鳥』。20m以上の大きさと。『ネコ』。10mほどの大きさと。『ヘビ』。これも10mほどの大きさ。『ナスカの地上絵』の配置図。以下の写真は、私が2009年にペルーの『ナスカの地上絵』👈リンク を訪ね、『遊覧飛行』にて撮影したものです。『ハチドリ』。『コンドル』。『犬』。『猿』。ナスカの地上絵が描かれた年代は今からおよそ2000年前、パルパの地上絵は更に古く今から3000年ほど前に描かれたものと言われている。地上絵にはサル、リャマ、シャチ、魚、爬虫類、海鳥類が描かれ、ナスカ式土器の文様との類似点が指摘されてきた。ナスカの地上絵は何のために描かれたのか?下記の如き説があると『ネット』👈リンク には。 1.「カレンダー説」 2.「雨乞い儀式説」 3.「巡礼に関する役割説」 4.「水のありかを示していに説」 5.「権力者の埋葬説」 6.「UFOの発着場説」 1.「カレンダー説」 ナスカの地上絵を構成する直線には、意図的に太陽と星の動きを表しているものが あり、農業用のカレンダーとして描かれたという説。 この説だと、他の地上絵の線はいらないですし、何のためにあれほどまでに 大きな絵を描いたのかも謎 と。2.「雨乞い儀式説」 ナスカは地球上で有数の乾燥地帯なので、雨乞いのために描かれたという説。 地上絵の中にクモを描いたものがあり、クモは雨を象徴するものだったと言われている。 また、古代ナスカ人が雨乞いの儀式に使っていた貝殻(エクアドル産)が地上絵周辺で 多数発見されている。 ナスカの地上絵には「水源を確保する」といった実用的な機能はないので、古代の人たちが 宗教的な意味合いで地上絵を描いた可能性はあると。 ただし、この説だと雨とは関係のない植物や動物などの地上絵をなぜ描いたのか? という 謎は残る と。3.「巡礼に関する役割説」 古代の人々はナスカの地上絵を歩いて渡り、聖なる場所に向かったという説。 もしかしたら、巡礼地に向かうための目印としてや途中で儀式を行うポイントと して地上絵が機能していたのかもしれない と。4.「水のありかを示している説」 ほとんど雨が降らないナスカでは、地下水に頼って生活する必要がありました。 そのため、水脈や水源を示す目印としてナスカの地上絵を描いたという説もあります。5.「権力者の埋葬説」 ナスカ文化では権力者が埋葬された際、地上絵をひとつ描いたという説。 ナスカ文化では死者は太陽に帰るとされていて、太陽に向けて地上絵を描いた のだとか。6.「UFOの発着場説」 ナスカの地上絵は宇宙人によって描かれ、UFOの発着場になっていたのでは? という説。 ナスカの地上絵のひとつに宇宙飛行士(もしくは宇宙人)を描いたような絵もあります。 確かにこの説なら、たやすく200メートルを超える地上絵を描くことができたでしょう。 地球を訪れることができるほどの科学技術を持った宇宙人 と。現時点では、有力な説はあれど、決定的にこの説が正しいと証明されたものはない。おそらく、ナスカの地上絵はひとつの目的でつくられたのではなく、複数の目的でつくられたのだと。また、時代の移り変わりや気候変動によって、ナスカの地上絵を描く目的が変わった可能性もあるのでは と。
2022.12.12
閲覧総数 975










