2025年11月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

牛久大仏へ(その2)
牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.18
コメント(0)
-

牛久大仏へ(その1)
利根川の排水機場。道の駅 発酵の里こうざきに立ち寄る。千葉県香取郡神崎町にある、発酵食品をテーマにしたユニークな道の駅「発酵の里こうざき」、住所:千葉県香取郡神崎町松崎 855。「発酵」をテーマにした全国でも数少ない道の駅。味噌、醤油、酒といった発酵食品が盛んな地域で、発酵文化を「食」と「体験」で発信していた。建物は「新鮮市場」「発酵市場」「レストラン」「カフェ(はっこう茶房)」など複数のゾーンで構成。観光案内板「発酵の里 こうざき」。左側のマスコットキャラ:「なんじゃもん」(神崎町のシンボルキャラクター、巨大な樹の精霊)発酵の魅力が詰まった「発酵市場」。全国から集めた発酵食品をとりそろえた、土産ショップ。店に入ると、みそやしょうゆ、甘酒、チーズ、漬けもの、日本酒など約500種類の商品がずらり。店内で土産物を買う旅友。親しい「仁」の文字がある日本酒。 仁勇(じんゆう)ラベルに大きく「仁勇」と書かれている緑色の瓶。蔵元:鍋店(なべだな)株式会社所在地:千葉県香取市(佐原)利根川流域の代表的な酒蔵のひとつ青ラベル(本醸造)赤ラベル(辛口)緑ラベル(純米)など複数の種類が並んでいた。仁勇は利根川流域(“水郷地域”)でもっともよく見かける地酒の一つであると。「鍋店 神崎酒造蔵」や「寺田本家」など、地元酒蔵の甘酒や酒かすを使った商品も豊富。新利根川大橋。利根川を渡る。すぎのや本陣 阿見店で昼食。稲敷郡阿見町、国道125号線バイパス沿いの店舗。蕎麦、うどんと各種セットが充実している和食レストラン。そば定食を楽しむ。そして目的地の牛久大仏が姿を表した。牛久大仏👈️リンク を訪ねるのは2021年以来、4年ぶり。・全高120m(台座含む) → 自立型の青銅仏として世界最大級・建設:1993年・参拝者は内部に入ることができ、 ・地下1階:蓮華蔵世界 ・1階:知恩報徳の世界 ・2階:御慈光の世界 ・3〜5階:展望室(地上85m) までエレベーターで上がれた。・周囲には広い庭園と小動物公園もあり、家族連れにも人気 と。牛久大仏の入口案内板。近づいて。正式名称:牛久大仏(正式には「牛久阿弥陀大佛」)所在地:茨城県牛久市久野町2083右側に大仏の全身写真下部に ギネス世界記録 認定 のロゴ → 「世界最大の青銅製仏像」として登録された記念牛久阿弥陀大仏(内部フロア説明)案内板には、大仏内部の各階の施設が紹介されていた。1F:光の世界・青い光に満たされた幻想的な空間・参拝前の「心を整える場所」という意味合い2F:知恩報徳の世界・阿弥陀如来への信仰や感謝をテーマにした展示・仏教美術や資料が並ぶ3F:御慈光の世界(銅板写経の間)・約3万枚の金色の小さな仏像が並ぶ荘厳な空間・「写経」を奉納する場所として知られる4F(外周部):展望室(地上85m)・牛久市や関東平野を一望できる大パノラマ・晴れていれば筑波山がよく見える5F:御膳台・大仏内部の最上部・一部は構造上のスペース(一般公開はフロアによって制限あり)牛久大仏の大きさ(案内板の比較表)大仏の高さ(本体):100m蓮台(台座):10m総高さ:120m→ 自由の女神(約93m)より高いその他、奈良の大仏や鎌倉大仏との高さ比較も描かれていた。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)エリア全体の案内図。■ 1. 牛久阿弥陀大仏(中央) 敷地の中心にそびえる高さ120mの大仏。 内部に入れる日本でも珍しい巨大仏です。🌼 周辺の庭園・スポット■ 2. 牛久浄苑(うしくじょうえん) 大仏の背後に広がる広大な霊園エリア。春は桜、初夏は新緑が美しい場所。■ 3. ふれあいガーデンテラス 大仏横にある花壇と散策路。 季節ごとの花が楽しめるスポットです。■ 4. 大香炉(だいこうろ) 大仏前にある大きな香炉。 参拝前にお線香を供える場所です。🌷 花エリア 写真の左側に広がるカラフルな場所。■ 5. 群生海(ぐんせいかい) 季節の花々(ネモフィラ、コスモス、ポピーなど)が一面に咲き誇る広場。■ 6. 釈迦三尊像 三体の仏像が並ぶ厳かなエリア。写真にも小さく写っていた。🌳 その他の見どころ■ 7. 定業苑(じょうごうえん) 休憩所やお土産コーナーのある施設付近。車椅子対応のトイレもある。■ 8. 本願荘厳の庭 滝や池がある和の庭園。涼しげな雰囲気で、写真によく合うスポット と。■ 9. 本願荘厳の滝(右下) 庭園内にある滝。流れ落ちる水が美しい場所。■ 10. 想い出処「浄蓮門」(入り口付近) 入場ゲート近くのお土産・記念写真スポット。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)内部へ入るための「大仏入口」案内板。「東本願寺 牛久阿弥陀大仏」→ 牛久大仏の正式名称で、宗派は浄土真宗東本願寺派。牛久大仏の「入場受付・料金案内」付近。■ 1. 営業時間(上部の紫の帯) 季節によって営業時間が変わる。 3〜9月(平日) 9:30〜17:00 3〜9月(土日祝)9:30〜17:30 10〜2月(平日・土日祝)9:30〜16:30 ※最終入場は閉園30分前まで■ 2. 料金案内(中央の大きな表) 大仏胎内or園内散策の料金が。● セット券(庭園+大仏胎内) 大人:800円 子ども:400円● 入園券(庭園のみ) 大人:500円 子ども:300円入場チケット。移動しながら牛久大仏を。これは 牛久大仏の「顔の模型」 。「大仏様のお顔は、この模型1000個分のボリュームに相当します。」と。「大仏入口(順路)」案内板。 通路のマンホールは牡丹(ぼたん)文様のモチーフ・中央に大きな花弁・両側に蕾(つぼみ)・周囲に茂る葉という構成で描かれており、典型的な牡丹唐草や牡丹文様の構成。牡丹は、仏教美術でも寺院装飾でもしばしば用いられる吉祥文様(めでたい文様)で富貴、高貴、美、吉祥を象徴すると。牛久大仏世界最大 120M 青銅製仏像鎌倉時代、御開山親鸞聖人は、常陸国(茨城県)で、他力念仏の教文を人々に伝えられるとともに、浄土真宗の根本聖典となる「教行信証」のご執筆にかかられました。 このご著書の成立年をもって、浄土真宗立教開宗の年(1224年)とされております。そして、立教開宗からおよそ800年の時代を超えてそのゆかりの地に、東本願寺第25世興如上人のご発願により、人類救済、世界平和の願いを込めて西方極楽浄土の主である阿弥陀如来(牛久大仏)が建立されました。牛久大仏の一部を実物大で再現した展示物のひとつでこれは大仏の頭頂部「螺髪(らほつ、大仏さまの髪の毛)」=頭の盛り上がり部分の実物大模型「この螺髪は阿弥陀大仏の頭部螺髪と同じものです。概 要 直径 1m 重さ 200kg 総数 480ケ」 牛久大仏の総重量は4,000t、顔の長さ20m、左手の平18.0m、目の長さ2.5m、鼻の長さ1.2m、とすべてが規格外の大きさ。牛久阿弥陀大仏阿弥陀如来は方便法身の大尊形として顕現されたもので、高さは阿弥陀如来の十二の光明にちなみ120m。その尊形を外から仰ぎみるだけでなく、胎内で阿弥陀如来の広大無辺なる本願の世界を体感することができます。四季の移り変わりや朝夕の光により、また見るものの心により、さまざまな表現を見せてくれる阿弥陀大仏、その御慈悲とは常に智慧と慈悲に満ち、すべてのものをやさしく包み込みます。地上高 高さ 120m重 量 本体主鉄骨 3,000トン 外殻鋼板重量 1,000トン左 手 挙手 18.0m親 指 直径 1.7m足の爪 長さ 1.0m人差指 長さ 7.0m 目 長さ 2.5m 鼻 高さ 1.2m 口 長さ 4.0m 耳 長さ 10.0m顔の大きさ 20.0mラホツ(頭部) 直径 1個1m 重さ 200kg 全体 480ケ基壇部 高さ 10m蓮台部 直径 30m 高さ 10m製造期間 10年再び牛久大仏(牛久阿弥陀大仏) 園内マップ「SORA × HOTOKE(そら × ほとけ)」の案内板。■ 左上:園内写真と名称● 大香炉(だいこうろ) 大仏の正面にある巨大な香炉● 群生海(ぐんせいかい) 季節ごとの花が広がる花畑エリア● 釈迦三尊像 ミニ仏像が三体並んだエリア● 浄蓮門(じょうれんもん) 入口付近の門と休憩場所■ 中央地図(園内図) 観光スポットがイラストで示されており、色分けされているのが特徴● 牛久阿弥陀大仏(メイン) 園内中央に大きく描かれた大仏像 胎内(内部)に入るルートもここから● ふれあいガーデンテラス 花畑・フォトスポットがある休憩エリア● 本願荘厳の庭 滝や池、水のある庭園● 仲見世 お土産・軽食・物販が集まるエリア● 足湯苑 無料または低料金で利用できる足湯施設● 駐車場(P) 園全体にアクセスしやすい大きな駐車場● 現在位置(YOU ARE HERE) 赤色の表示で、案内板のある場所が指示されています。牛久阿弥陀大仏を正面から。青空であれば(ネットから)。 ・・・つづく・・・
2025.11.17
コメント(0)
-

成田山新勝寺へ
ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。
2025.11.16
コメント(0)
-
六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6
★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進が分裂 森友・加計・日報、政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界で 不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 2020 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 東京五輪・金メダル27個 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷 2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・
2025.11.15
コメント(0)
-
六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5
★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹 👈️ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設 六会中学校にプール完成 👈️ 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島 で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」 発表👈️] ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.14
コメント(0)
-
六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-4
★六会地区 歴史年表-12年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料大正時代大正元年 1912 六会村人口 三九四九名 東京市よりワシントン 戸数 五九五戸 ポトマック湖畔に桜三〇〇〇本 六会村西俣野に瞽女淵記念碑建立 寄贈👈️ 2年 1913 横須賀海軍水道完成(水源は中津川) 藤沢警察署亀井野駐在所設置 (旧道亀井野下 下山酒店先下屋敷側) 3年 1914 厚木県道改修工事完了 桜島大噴火👈️ 六会村人口 四四七七名 戸数 六一〇戸 第一次世界大戦始まる👈️ 4年 1915 第九代六会村村長に加藤九右衛門 第一回全国中学校野球👈️ (亀井野)再選 大会大阪で開催 六会村下土棚、長谷川巳之助、 厚木県道沿いで酒屋を開業 5年 1916 長後・戸塚間ツルヤ自動車バス運行 開始 広田清治、尋常高等六会小学校校長に 任命 6年 1917 六会村 人口 四五八四名 戸数 六三一戸 (亀井野 一六一戸 今田 三七戸 下土棚 九六戸 西俣野 八七戸) 六会村吏員給料 村長一二〇円 助役 一〇〇円 収入役 一〇五円 書記 九八円 7年 1918 第一〇代六会村村長に杉山松五郎 第一次世界大戦終結👈️ (今田)就任 藤沢に初めて電話架設 米価高騰により各地で暴動発生 六会村下土棚東側に電灯点る (六会村で最初) 8年 1919 藤沢町田線(藤沢町5町田町)が県道に 認定された 9年 1920 第一回国勢調査実施 11年 1922 六会村青年団結成、団長に尋常高等 六会小学校長の広瀬正治就任 六会村下上棚、金子春吉自転車業を開始 12年 1923 六会村に自転車が見られるようになる 関東大震災発生 六会村の被害死者一五名 負傷者一四名 行方不明一名 家屋全壊七五七棟 半壊五九六練 13年 1924 第一一代六会村村長に広田兵蔵(土棚)就任 尋常高等六会小学校訓導塚越喜一、高一 児童約四〇を引率し大山登山実施 大山登山の歌(広田俊夫作詞)成る 14年 1925 尋常高等六会小学校同窓会設立、 ラジオ放送開始👈️ 初代会長小倉喜一 東京六大学野球リーグ戦 六会村処女会結成、初代会長小泉セイ 始まる👈️ 東京~上野間に地下鉄開通★六会地区 歴史年表-13年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和元年 1926 六会村、晩霜のため桑・茶の被害甚大、 桑相場高騰 六会村青年・処女会・同窓会の機関誌 「六会の叫び」第二号発行 2年 1927 六会村下土棚消防組結成、初代組頭に 第一回都市対抗野球大会 金子友治就任 始る(最初の野球実況放送) 大正天皇御崩御 3年 1928 六会村亀井野駐在所改築移転 第九回オリンピック、アム 六会村亀井野下より西俣野上を経て ステルダム大会、初めて 大船に通ずる道路(大船用田線)開通 日章旗上がる(織田幹雄、 鶴田義行)👈️ 4年 1929 第一二代六会村村長に飯田伝之輔 世界一周ドイツ飛行船 (俣野) 就任 ツェッペリン伯号霞ヶ浦に 小田原急行鉄道、江の島線開通 着陸👈️ 六会駅開設 片瀬江の島~新宿間の運賃 九五銭 初の国産ウィスキー・ 六会村役場新築落成、二階家となる サントリー発売 6年 1931 六会農民組合結成、組合員五四名 小作料の引下げを目指す 7年 1932 一三代六会村村長に長谷川周作 チャップリン来日👈️ (亀井野)就任 五・一五事件勃発👈️ 8年 1933 六会村下土棚、模範耕地整理組合結成、 国際連盟を脱退👈️ 組合長矢地要吉 六会村石川の秋本信善、秋本漬物工場 発足 六会村産業組合創立、組合長渡辺時蔵 横須賀海軍通信隊六会分遣隊、六会村 亀井野に駐屯 六会村 人口 四九三〇名 戸数 七二一戸 9年 1934 尋常高等六会小学校教員広田俊夫、 渋谷駅前に忠犬ハチ公の 郷土史「六会読本」を編纂刊行 碑が立つ👈️ 11年 1936 第一四代六会村村長に小菅一鉱 二・二六事件勃発👈️ (土棚)就任 尋常高等六会小学校校庭に二宮金次郎 銅像建立 六会村電井野の長谷川敏夫、町田線沿に 六会郵便局を開設 12年 1937 御所見・六会両村境に県立診療所設立 日中戦争始まる👈️ (盧溝橋事件) 14年 1939 第一五代六会村村長に小倉久武(亀井野) 就任 15年 1940 藤沢市制施行 国民服令公布👈️ 16年 1941 初代市長に大野守衛就任 米穀配給通帳制実施👈️ 太平洋戦勃発 (真珠湾攻撃)👈️ 17年 1942 六会村藤沢市へ合併 金属回収令👈️ 六会村人口 四九九六名 (神社・寺院の仏具・梵鐘等 職業内訳 農業五七〇戸 工業二 戸 強制供出) 商業 一四〇戸 公務・自由業 二四戸 爆撃機本土初空襲 その他 六石 六会消防団は藤沢市警防団となる 18年 1943 下土棚の白山神社の梵鐘供出 日本大学農獣医学部創立 19年 1944 下土棚に海軍横須賀通信学校 藤沢分校開校、その後横須賀海軍電測 学童集団疎開実施👈️ 学校と改称 20年 1945 広島・長崎に原爆投下 👈️ 農地調整法改正公布 第一回国民体育大会開催 👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.13
コメント(0)
-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-3
六会日大前駅(旧六会駅)東口 <1983年頃>東口ロータリーは駐輪場となっていた。ズームして。★六会地区 歴史年表-8年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代文化 4年 1807 亀井野村、雲昌寺の梵鐘鋳造される この頃、間宮林蔵 樺太を探検 👈️ 5年 1808 下土棚村、善然寺三一世弁誉上人の 教えを受けた一八人の筆子により 筆子塚が建立される 7年 1810 下土棚村、渋谷ヶ原に庚申塔建立される 8年 1811 西俣野村、旗本柳生氏の知行地が旗本 金田欽之助・小笠原若狭守信義両氏の 知行地となる文政 5年 1822 伊能忠敬 「第日本沿海実測地図」完成 👈️ 6年 1823 ドイツ人医師シーボルト 長崎出島に着任👈️ 7年 1824 西俣野村、地誌調査が行われ 「地誌御調改書上帳」が作成される 「御調改書上帳 (相模風土記の元となる) (おしらべあらためかき 西俣野村 戸数 六〇戸 人口 三九〇名 あげちょう)」 8年 1825 下土棚村、氏子七一名が白山神社に 梵鐘を奉納する 10年 1827 下土棚村、小菅新兵衛ほか六名により 青面金剛像庚申塔を建立される 11年 1828 下土棚村、渋谷根講中白山神社に石灯篭 一対を寄進する 13年 1830 西俣野村、御嶽神社の鳥居を建立する 天保 3年 1832 下土棚村、渋谷ヶ原に広田仁右衛門ほか 安藤広重 三名により庚申塔建立される。 「東海道五十三次」完成 👈️ 円行村、収穫高の調査が行われる 天保の大飢饉起こる👈️ 境川の川浚・堰・水車等の件につき争論発生 「藤沢の堰をつくったことにより西村(西富) と西俣野村が苦情」 7年 1836 下土棚村、法然上人六五〇回忌の記念事業 として善然寺の山門完成、山門の扁額の 文字は大本山増上寺冠挙大僧正の筆★六会地区 歴史年表-9年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代天保 11年 1840 浄土宗法王院十王堂(閻魔堂)の火災発生 アヘン戦争(1839~1842) 👈️ 12年 1841 天保の改革始まる👈️ 13年 1842 「新編相模国風土記稿」 全巻完成👈️ 14年 1843 亀井野・石川・大庭の各村が酒、売めし、 駄菓子商の許可を関東取締役へ願い出る弘化 4年 1847 石川村天満宮の梵鐘が鋳造される 「助郷村」とは 亀井野村質地争論発生 江戸時代、宿場常備の人馬 境川堤防を守るため一人の浪士が人柱 が不足する場合、幕府・ として投身自殺 諸藩によって人馬の供を命じ 金沢橋の袂に地蔵菩薩石像が建立され られた郷村 その後、御所谷に移築される(土堤番様) 嘉永 3年 1850 亀井野村・石川村等二七ケ村が代助郷村 「助郷村」とは に定められる 江戸時代、宿場常備の人馬 亀井神社の経塚一字一石の碑文建立 が不足する場合・諸藩に よって人馬の堤供を命じ ら れた郷村 「石(こく)」とは、米の量 に用いる 一石は約180リットル。 6年 1853 西俣野村、神礼寺(小御嶽神社)の梵鐘 ペリー浦賀に来航👈️ 鋳造される安政 元年 1854 日米和親条約締結調印 👈️ 2年 1855 安政の大地震発生、円行村被害甚大の ため年貢金高一〇〇石につき三両割と なる 3年 1856 二宮尊徳没す(70才) 6年 1859 安政の大獄👈️万延 元年 1860 桜田門外の変👈️慶応 3年 1867 明治天皇即位、 王政復古の宣言👈️★六会地区 歴史年表-10年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料明治時代明治 元年 1868 神仏分離の礼、廃仏毀釈が起こった 江戸城無血開城 👈️ 3年 1870 平民に苗字を許可 4年 1871 藤沢宿に郵便取扱所が開設 5年 1872 下土棚村、渋谷ヶ原に渋谷講中一同 横浜~品川鉄道開通 により道祖神が造立される 👈️ 新戸籍法の施行、学制の公布、電報の 取扱開始、戸長制施行(名主制の廃止) 富岡製糸場開場 👈️ 6年 1873 管内区画改正により石川村・亀井野村・ 西俣野村を第一八区一〇番組に 今田村・円行村・下土棚村・長後村・ 七ッ木村が第一九区一番組となる 地租の改正、徴兵令公布 石川村、石川学校設置 下土棚村、白山神社社殿改築 7年 1874 佐賀の乱👈️ 東京銀座に初めてガス灯 がつく👈️ 8年 1875 西俣野村、西俣野学校設置 亀井野村、亀井野学校設置 9年 1876 下土棚村、下土棚学校設置 10年 1877 西南戦争発生 出征一名 モース、大森貝塚発見 江の島に臨海実験所設営 👈️ 11年 1878 郡区町村編成法により、亀井野村・ 日本で初めて電灯がついた 石川村・西俣野村・今田村・円行村・ パリ万国博覧会開催👈️ 下土棚村は六ヶ村組合設立 13年 1880 藤沢の日常品の相場 米一石 八円一銭二分 乾鰮一〇シメ 二円三銭一分 農具の値段 鍬一丁 二円 鎌一丁 二〇銭 碓一個 一円 箕一個 一〇銭 銅簸一個 三円五〇銭 肥桶一荷 一円 稲マキ一丁 一円七〇銭 万能鍬一丁 五〇銭 15年 1882 下土棚村、田中典惣右衛門、日本酒の醸造 開始(造り酒屋) 17年 1884 下土棚村、長田万吉傘製造開始、多数の 徒弟を養成 藤沢地区、職人の賃銭日当 大工左官 三六銭 石屋 三二銭 瓦屋根職 三五銭 畳刺 二五銭 板屋根職 三〇銭 経師 五三銭 19年 1886 下土棚村、小菅常次郎自転車を購入して乗り 始める(当地区最初) 円行出身小菅丹治、伊勢丹呉服店創業 20年 1887 御嶽神社の本殿再建 下土棚・円行・石川・今田・亀井野・西俣野 ・長後・高倉地区養蚕が盛んになる 21年 1888 石川村、入内嶋製糸場設立 22年 1889 市制町村制開始 下土棚村・円行村・石川村・今田村・ 亀井野村・西俣野の六ヶ村は合併して 六会村となる 初代六会村村長に亀井野村の杉山信尹就任 23年 1890 石川学校・亀井野学校・西俣野学校・ 第1回帝国議会開会👈️ 下土棚学校・亀井野学校円行分校を 廃止し高等六会小学校創立 高座郡警察署、石川駐在所が六会村石川に 設置される 24年 1891 高等六会小学校初代校長に、 江の島桟橋完成👈️ 清水熊太郎就任 25年 1892 高等六会小学校を尋常高等六会小学校と改称 高座郡警察署、六会亀井野に仮屯所設置 尋常高等六会小学校、亀井野不動上に校舎を 新築し移転 下土棚、長田豊次郎染物業開始 滝山街道(現在の旧藤沢・町田線)県道に 指定される 26年 1893 高座郡警察署を藤沢警察署と改称 第二代六会村村長に杉山信尹(亀井野)留任 27年 1894 日清戦争開戦👈️ 北里柴三郎ペスト菌発見 👈️ 28年 1895 久間製糸場が六会村亀井野に、 中田製糸場が六会村石川に設立される 29年 1896 第三代六会村村長に伊沢弥助(石川)就任 第四代六会村村長に斉藤太兵衛(亀井野)就任 下土棚、渡辺七五郎こんにやく製造開始 30年 1897 五代六会村村長に杉山信尹(亀井野)就任 下土棚の広田太吉、県下で最初に 稚蚕共同飼育組合を設け収繭高めた 六会人口 三八九八名★六会地区 歴史年表-11年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料明治時代 31年 1898 六会村石川に西山製糸場設立 葉タバコ専売実施👈️ 32年 1900 六会村農会設立、会長に広田兵蔵就任 六会村下土棚、川井嘉七が豆腐製造 販売開始 35年 1902 第六代六会村村長に伊沢安良(石川) 八甲田山遭難事故発生👈️ 就任 日英同盟調印 👈️ 36年 1903 藤沢税務署開設 国定教科書制確立 👈️ 37年 1904 六会村地先境川治水工事の実地調査 日露戦争始まる👈️ 六会村今田郵便箱設置了承 六会村人口調査結果 出生 三〇名 死亡 二〇名 婚姻 一〇名 離婚 七名 死産 七名 日露戦争 五人出征(内三名戦死) 38年 1905 六会村の徴兵適齢者調査の結果 三五名 六会村役場、大字亀井野字不動上 六会小学校内へ変更の件村会で決定 39年 1906 七代六会村村長に加藤九右衛門(亀井野)就任 日米海底電信開始 六会村下土棚に六会村立実業補習学校の 👈️ 分教場設置 41年 1908 六会村龜井野に六会村立実業補習学校の 分教場設置 42年 1909 藤沢町、六会村・俣野村・耕地整理組合結成 境川の流域の地整理事業に着手 (大正二年竣工) 43年 1910 第八代六会村村長に加藤九右衛門(亀井野) 逗子開成中学生 再選 七里ヶ浜沖で遭難👈️ 六会村下土棚、青年同志会創立 六会村西俣野、青年団創立 六会村西俣野に六会村立実業補習学校の 分教場設置 45年 1911 明治天皇御大葬👈️ 乃木大将夫妻殉死👈️ ・・・もどる・・・👈️ ・・・つづく・・・👈️
2025.11.12
コメント(0)
-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-2
以下 表にすべき内容ですが、スペースで文字配置を調整していますが、上手くいきません。ご容赦願います。旧六会駅の写真(1984頃)をネットから。★六会地区 歴史年表-3年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料室町時代応永30年 1423 小栗判官満重、鎌倉への謀反により 常陸の小栗城落城後行方不明となる その後の巷の噂を基に小栗判官と 照手姫の伝説が生まれる 33年 1426 遊行寺焼失 小栗判官満重没すと伝わる永享 5年 1433 関東に大震災発生(九月一六日) 12年 1440 照手姫没すと伝わる長禄 元年 1457 北条早雲、小田原城に入る 👈️明応 4年 1485 北条早雲、小田原城に入る天文 5年 1536 下上棚、白山神社創建し村中安穏を 祈願して鎮守とする元亀 2年 1571 武田信玄、遊行寺に藤沢二〇〇貫、 「貫」とは田地の収橋高を 俣野のうち一〇〇貫の土地を寄進する旨 銭に換算して表したもの 書状を渡す 面積は一定しない 天正 3年 1575 長篠の戦👈️天正10年 1582 武田勝真、識田信長・徳川家康らに 本能寺の変👈️ 天目山で滅ぼされる、その残党多数、 相模国に逃亡★六会地区 歴史年表-4年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料室町時代天正13年 1585 大阪城築城👈️天正18年 1590 徳川家康、江戸城に入る 「禁制」とは、 禁示事項 今田村・西俣野村・円行村は徳川の 領地となる 亀井野村に不動堂建立される 豊臣秀吉、亀井野村雲昌寺に禁制を 揚げる 19年 1591 石川村、旗本中根権六郎貞重の 「知行地」とは 知行地となる 将軍、大名が家臣に俸給 下土棚村、旗本竹尾伝九郎元成の として支配権を与えた土地 知行地となる 「検地」とは土地の測量、 亀井野村、幕府代官彦坂小刑部元正 調査 により検地が施行される 20年 1592 朱印船貿易始まる👈️ 22年 1594 太閤検地施行一反を 300歩とする👈️慶長元年 1596 亀井野村雲昌寺、水害を被り今田村より 現在の藤沢工科高校の 亀井野村に移建されこの時より寺号 グランド裏と境川の間に 雲昌寺と改む👈️ あった。(現在住宅地)慶長 3年 1598 豊臣秀吉没す(六十三才)慶長 5年 1600 西俣野村に浄土宗法王院十王堂 関ヶ原の戦👈️ (通称閻魔堂)建立と伝わる。 8年 1603 徳川家康、江戸幕府を開く 👈️ ★六会地区 歴史年表-5年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代慶長 9年 1604 俣野村に曹洞宗花應院建立と伝わる👈️ 石川村、自性院建立、開基は領主旗本 中根臨太郎、開山は龍見とされる👈️ 19年 1614 大阪冬の陣 👈️ 20年 1615 大阪夏の陣 👈️元和 9年 1623 亀井野村、領主旗本青山氏の減転封 により幕領支配地となる寛永 3年 1626 石川村、領主旗本中根権六郎貞重 により検地施行寛永 4年 1627 亀井野村、松平伊豆守信綱(川越藩)の 領地となる寛永12年 1635 外様大名参勤交代始まる 👈️ 寛永14年 1637 島原の乱 👈️寛永16年 1639 亀井野村 、領主松平伊豆守信綱 松平氏の加増転封により亀井野村は 「幕領支配」とは 幕領支配となる 徳川幕府の領地正保元年 1644 円行清雲寺(現存せず)👈️ 雲昌寺住僧の退穏所として同僧により 開山(相模風土記稿) 正保 3年 1647 代官成瀬五左衛門、代官坪井次右衛門に よって俣野村の検地が進められ幕領と なる慶安 4年 1648 亀井野村の雲昌寺、幕府より寺領九石の 朱印状を与えられる万治元年 1658 亀井野村、町野壱岐守幸長の知行地となる 「朱印状」とは徳川幕府の 公認の文書👈️寛文 4年 1664 下土棚村の白山神社、広田主水ほか氏子に より再建される 4年 1665 亀井野村、町野壱岐守幸長により検地施行宝永11年 1671 円行村、代官成瀬五左衛門により検地施行 今田村の一部(幕領)が旗本細井左次衛門勝茂の 知行地との二給支配となる延宝元年 1673 西俣野村 戸数 66戸 人口404名★六会地区 歴史年表-6年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代延宝 2 年 1674 西俣野村、新田検地施行 5年 1677 亀井野村、不動堂に経塚奉納碑が 建立される 8年 1680 猿田彦大神の石廟が御所ヶ谷に 建立される元禄 7年 1694 西俣野村、松波重純(重隆流)の知行地 となる 下土棚村、善然寺炎上元禄10年 1697 西俣野村、旗本長谷川玄通道可の知行地 となる 14年 1701 下土棚村、旗本竹尾氏と遠山久四朗安算の 両氏の知行地 亀井野村、旗本町野氏知行地、上地とされ 上地とは、幕府に理行地 幕領となる を没収されること元禄16年 1703 関東に大地震、津波来襲、 (元禄地震)👈️ 浅間山噴火宝永 3年 1706 円行村、畑方名寄帳作成される 名寄帳(なよせちょう)」 円行村、一部が旗本石川織部の知行地となり とは年貢負担ごとにその 二給支配となる 土地の種類、面積、年貫 の額などを書いた帳簿 4年 1707 富士山の噴火により宝永山出現 20cm~30cm の降灰で被害甚大(宝永大噴火)👈️ 亀井野村の幕領の一部が旗本岡部石見守長倶の 知行地となり二給支配となる 岡部石見守長倶により亀井神社の社殿改築 7年 1710 円行村、幕領の一部が旗本石川織部盛行の 知行地となり二給支配となる 自家用酒製造許可 享保元年 1716 徳川吉宗将軍に就任 👈️ 10年 1725 円行村、神明社建立(棟札あり) 16年 1731 境川の洪水により堤防2000間の 所々決壊する ★六会地区 歴史年表-7年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代享保17年 1732 水車設置の許可 境川の淵に横土手(御公儀様御役場通り) 構築される元文 5年 1740 石川村、御林帳が作成される延享 2年 1745 石川村、神尾若狭守春英による 新田検地施行 3年 1746 円行村、八幡社に梵鐘が作ら寛延 元年 1748 一人の瞽女が境川に落ちて溺死する 「瞽女(ごぜ)」とは 盲目の女旅芸人宝暦13年 1763 下土棚村、善然寺炎上安永 4年 1775 引地川に船を出す事について大庭 ・ 稲荷・石川・円行・羽鳥・辻堂の 各村より差し支えない旨、幕府に書状を 提出する 下土棚村、白山神社改築天明 2年 1782 石川村、自性院の梵鐘鋳造される 6年 1786 猿田彦大神の石廟、御嶽神社内に移築 7年 1787 円行村、村負担による水田開発を実施 8年 1788 下土棚村の夏刈に四臂(よんび)金剛像供養塔 「四臂金剛像」とは 造立される 四本の腕を持つ金剛像 下土棚村、善然寺火災により本堂・ 寺宝・過去帳焼失する寛政 元年 1789 西俣野村、旗本柳生久通の知行地となる 8年 1796 西俣野村、御嶽神社の梵鐘が鋳造される 文化 3年 1806 石川村、鯖明神社の梵鐘が鋳造される 下土棚村、地頭旗本竹尾氏の知行分幕領となり 代わって松平筑前守地頭となる 「地頭」とは土地の領主 下土棚村の夏刈、柳生五兵衛ほか四名が 八臂青面金剛像庚申供養塔を建立する ・・・もどる・・・👈️ ・・・つづく・・・👈️
2025.11.11
コメント(1)
-
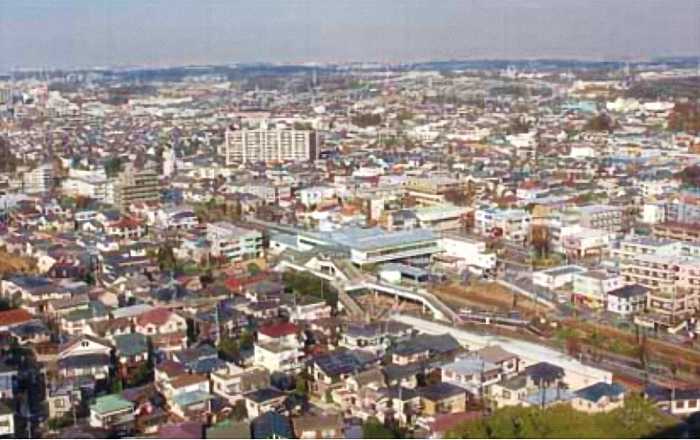
六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-1
私は後期高齢者の75歳、生まれも育ちもそして現在もこの町に75年間継続して住み続けているのである。そして今後も??年かはこの町に。しかし、この町の歴史については、ほとんど知識を有していないのである。今更ながらであるが、この町の歴史について知りたいと思い、ここにこの町に住む先輩の皆さまが、過去に纏めていただいた資料、そして私がこの町を過去に散策した時にあっぷしたブログを元に復習を兼ねて纏めて見ましたので、ここにアップさせていただきます。この町・六会に居住される皆様の参考になればとの想いもあるのです。六会(むつあい)のあゆみ。住所:神奈川県藤沢市・・・・・であり、住所地名として「六会」の名はないのである。 私の住む「六会地区」は相模台地のほぼ南端に立地している。旧石器時代から奈良、平安時代の集落は発見れた遺跡・遺物の所在から、境川と引地川の周辺に散在していたと。その後この地域のことが古い書物にみられるのは、平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集「天養記」にでてくる大庭御厨の東の境である俣野川(境川)の名前と、鎌倉時代の武家日記「吾妻鏡」にでてくる俣野という地名であると。六会駅(現六会日大前)南西側上空からの写真。(ネットから)まずは我が町「六会」の近代の歴史概要を。 ・明治11年(1878)、大小区制の廃止と郡区町村編成法の制定によって亀井野、西俣野、石川、 円行、今田、下土棚の6ヶ村組合が設立され、・明治22年(1889)、村町制の施行により六会村が誕生しました。・昭和4年(1929)年2月には小田急江の島線が開通し六会駅が設置され、交通の便が飛躍的に よくなりました。・六会村は昭和17年(1942)年3月、藤沢市と合併するまで約55年間村政を維持、運営して きました。・翌年の昭和18年(1943)には、日本大学の農学部が開設されました。・藤沢市に合併した当時は人口4,996人の農業中心の地域でしたが、昭和30年(1955~)代の 工場誘致などを契機に北部開発、六会・石川東部上地区画整理事業の進捗と・昭和41年(1966年)11月7日に小田急線湘南台駅の開設に伴い急激に都市化が 進んできました。 これらの発展の結果、・昭和47年(1972)に下土棚が長後地区へ、平成元年(1989)には今田、円行の大部分が 湘南台地区へそれぞれ移行されました。・その結果、石川、亀井野、西俣野と今田、円行の一部が藤沢市の六会地区となり、その後も 発展を続け、現在人口は約34500人の自然に恵まれた宅地と農地が共存する地域となりました。六会市民センター👈️・昭和45年(1970)現六会市民センター開館。・住所:〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4丁目8−1・緯度:北緯35.38526119度・経度:東経139.47476885度・標高:36m・海岸からの距離:約8km(直線距離・~片瀬西浜海岸)・過去の六会村役場: 明治22年(1889年)に誕生した六会村の村役場 現六会小学校の隣・「藤沢市 六会子供の家・どんぐりころりん」の場所にあった。 ★我が住む藤沢市の現在の人口と世帯数。★藤沢市における六会地区(2025年3月1日現在)。★六会地区 自治会・町内会名★六会地区の学校環境(上図参照ください)1、小学校◯ ・六会小学校 ・亀井野小学校 ・俣野小学校 ・天神小学校 ・石川小学校 ・日本大学藤沢小学校2.中学校◯ ・六会中学校 ・日本大学藤沢中学校3.高等学校◯ ・日本大学藤沢高等学校4.大学◯ ・日本大学生物資源科学部5.特別支援学校◯ ・神奈川県立藤沢支援学校★六会地区(日大周辺)👈️リンク 電車環境小田急江ノ島線、藤沢から新宿方面に3つ目の駅「六会日大前」駅。1日平均乗降人員: 27,821人(小田急電鉄 2024年度データ)藤沢市内の鉄道駅一覧(合計22駅)因みに平塚市:1駅(JR平塚駅)、茅ヶ崎市:2駅(JR茅ヶ崎駅、JR北茅ヶ崎駅)藤沢市と同等な人口規模の国内の都市としは、駅数が極めて多いと感じているのである。 ★現存する歴史上の文献に初めて出て来る六会地域以下3枚の写真はネットから。平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集「天養記」にでてくる大庭御厨(おおばみくりや)👈️大庭御厨は、相模国高座郡の南部(現在の茅ヶ崎市、藤沢市)にあった、寄進型荘園の一つ。鎌倉時代末期には13の郷が存在した相模国最大の御厨(伊勢神宮領)である。寄進型荘園とは、『地元の有力者(開発領主)が、自分の開発した土地を、税金(租税)や徴収権を持つ有力な貴族や寺社に「寄付」することで、税金から逃れつつ、その土地の管理を続ける「荘園」』のこと。中央の有力者は保護を与え、地元領主は税負担が減るという「お互いに得をする関係」から生まれた。御厨として寄進すると税金がかからなくなります.次に土地をうばったり、むりやりタダ働きをしろという国府の役人の命令を聞く必要もなくなります.また、領地争いもぐっと減ります。ですから、この時代の豪族(ごうぞく=広い土地を支配する大農民=武士)はこぞって、自分の土地を力のある貴族や寺や神社に寄進しました.厨(くりや)とは調理場のことです。御厨は神様の食べるものを作る場所という意味が込められています。ですから収穫されたお米の何パーセントかは,特産品とともに名目上の持ち主に届けられました。大庭の御厨の場合は伊勢神宮(いせじんぐう=三重県)に送っていました。つまり大庭氏は伊勢神宮に収穫されたものを送るみかえりに、領地をまもってもらっていたというわけです。「(推定)大庭御厨範囲」図。大庭御厨は長治元年(1104年)頃、鎌倉景正が大庭郷を中心に山野未開地を開発したものである。伊勢恒吉の斡旋で永久5年(1117年)伊勢神宮に寄進した。鎌倉景正は後三年の役(1083年 - 1087年)の勇者として有名である。大庭御厨の境界は、東は俣野川(藤沢市の境川)、西は神郷(寒川)、南は海、北は大牧崎だった。伊勢神宮の記録「天養記」によると、大庭御厨の範囲は、東は俣野川(境川)・西は神郷(寒川神社の社領)・南は海・北は大牧崎とあります。大牧崎はこれまでの研究で亀井神社南側一帯を指すと考えられています。大庭御厨は中世の藤沢の重要な土地の一つであった と。すなわち、藤沢市南半部から茅ヶ崎市全域に及んでいた。小糸👈️・台谷などの神明社は伊勢神宮の所領経営の拠点だったと考えられているとのこと。田地の面積は、久安元年(1145年)で95町、鎌倉時代末期には150町に達した。1町≒3,000坪≒10,000m2。よって100町≒1000m四方。大庭郷の成立は、9世紀以前と思われる。「大庭」「庭」も祭司の場を意味すると言う。現在も藤沢市に大庭の地名が残る。御厨は天皇家や伊勢神宮、下鴨神社の領地を意味する。鎌倉景政像の写真をネットから。鎌倉 景政(かまくら かげまさ/平 景政(たいら の かげまさ))は、平安時代後期の武将。名は景正とも書く。通称は権五郎。略歴父は桓武平氏の流れをくむ平景成とするが、平景通の子とする説もある。父の代から相模国鎌倉(現在の神奈川県鎌倉市周辺)を領して鎌倉氏を称した。居館は藤沢市村岡東とも、鎌倉市由比ガ浜ともいわれる。16歳の頃、後三年の役に従軍した景政が、右目を射られながらも奮闘した逸話が「奥州後三年記」に残されている。戦後、右目の療養をした土地には「目吹」の地名が残されている(現在の千葉県野田市)。長治年間(1104年 - 1106年)、相模国高座郡に大庭御厨(現在の神奈川県藤沢市周辺)を開発した。永久4年(1116年)頃伊勢神宮に寄進している。子の景継は、長承4年(1134年)当時の大庭御厨下司として記録に見えている。また『吾妻鏡』養和2年(1182年)2月8日条には、その孫として長江義景の名が記されている。江戸時代になると、天領地(幕府直轄地)または大名、旗本の知行地となり各村ごとに領主が置かれました。一村は必ずしも一人の領主とは限らず、数人の領主によって分割支配されていたこともありました。「相模国風上記稿」によると、村は村高に応じて助郷役が課され、亀井野村、円行村、石川村、西俣野村は藤沢宿の助郷役を務め、下土棚村は長後村とともに戸塚宿の助郷役を務めていました。明治時代になり明治11年(1878年)に大小区制が廃止され郡区町村編成法により下土棚村、円行村、石川村、今田村、亀井野村、西俣野村が新しい行政区画となり六ヶ村組合が設立されました。明治22年(1889年)市制、町村制施行により1.下土棚村、2.円行村、3.石川村、4.今田村、5.亀井野村、6.西俣野村が合併して「高座郡六会村」が誕生しました。高座郡の位置図。かつて高座郡に属していた地域は現在以下の市となっている。・綾瀬市・海老名市・相模原市(中央区・南区の全域、緑区他)・座間市・茅ヶ崎市・藤沢市(西富一・二丁目、大鋸一 - 三丁目、藤が岡一 - 三丁目、弥勒寺一 - 四丁目、 渡内一 - 四丁目、村岡東一 - 四丁目、川名一・二丁目、片瀬一 - 五丁目、 片瀬山一 - 五丁目、片瀬目白山、片瀬海岸一 - 三丁目、江の島一・二丁目および 大字西富、大鋸、弥勒寺、小塚、宮前、高谷、渡内、柄沢、川名、片瀬を除く全域)・大和市★6つの村が合併して誕生したので「六会」。「六会(むつあい)」という地名そのものに、「むつみ合う(睦み合う)」という美しい響きが重なっているのである。地域連携・地域親交の観点から見ると、『睦み合い』はまさに六会地区の理想を象徴する言葉と言えるのです。「睦」 の意味や由来は?「睦」「睦」は「目」と「坴」を組み合わせた漢字。「目」は人の目を表す象形であり、「坴」は、土が盛り上がる、寄せ集まるという意味を持つ。そのため、人々が目を寄せ集めるという意味から、たくさんの人が寄り集まること、転じて「人々が仲良くする、親しくする」という意味になるのです。🏡『睦み合い』の語義・「睦み合い」とは、互いに親しみ、仲よく助け合うこと・人と人との間に温かい心のつながりがある状態を意味します。語源の「睦(むつ)」は「親しみ」「和らぎ」「調和」を表し、「睦月(むつき)」=人々が年始に親しみ合う月、という言葉にも通じます。🤝 地域連携の観点から「睦み合い」は、地域連携の根幹となる “相互理解と協働の姿勢” を示します。六会地区には33の自治会があり、それぞれが地域課題に取り組みながらも、連合会として一つの「むつあいの心」でつながることが大切なのです。具体的には:・災害時の助け合いの仕組みづくり・高齢者や子どもを地域で見守る体制・祭り、生活環境、社会福祉、防災、交通安全、防犯活動、地域学校連携などを通した 顔の見える関係これらはすべて「睦み合い」の実践であり、『共に支え合う地域力』の象徴です。🌸 地域親交の観点から「睦み合い」は、単なる行政的な連携ではなく、心の通う親しさを育てることを意味します。六会ふるさと祭りや年末のイルミネーション、コンサート発表など、地域行事で人々が語り合い、笑い合うことそのものが「睦み合い」の形です。そこには、世代を超えたつながり新旧住民の融合、「お互い様」という温かい文化が息づいているのです。🌈 総括:六会の名にこめられた理念「六会(むつあい)」という地名に、「睦み合い」の精神を重ねるとき、それは単なる偶然の語感ではなく、地域の未来像そのものを表します。“人がむつみ合い、まちが調和し、心が通い合う六会”この理念こそが、地域連携と親交の両輪を支える「むつあいの心」と言えるでしょう。そして『六会』の『六(ロク・リク)』は、覆(おお)いをした穴や高い土盛りをした場所を表す象形文字。神様を呼ぶための幕舎を表すともいわれています。やがて『高い』に関係なく数字の六を示すようになりました。このような漢字の用法を仮借(カシャ)といいます。六~九の漢字はもともと意味の違う漢字を借りて、数字を表すようになったものです。漢字の部首は『八』、意味は『六(ロク)』、『高い』です。『高い』の意味は『陸(リク)』に引き継がれているといわれています。繰り返しになりますが『坴(ロク)』は、高い土盛りをした場所を表す漢字。漢字の足し算では土+八(広がる)+土=坴(高い土盛りをした場所)です。漢字の部首は『土』、意味は『高い場所』、『丘』です。我が国では『坴』の漢字が単独で用いられることはありませんが、陸、睦の旁(つくり)として活躍しているのです。つまり、「六会」の「六」は数字の六と共に高い場所、丘の意味もあるのです。 その後、55年間、村政を維持・運営して来ましたが昭和17年(1942年)に六会村が藤沢市に合併され、六会地区の下上棚、円行、石川、今田、亀井野、西俣野となりました。昭和47年(1972年)に下土棚が長後地区に編入されました。昭和59年(1984年)には、石川東部区画整理事業が完了して天神町が誕生しました。そして平成元年(1989年)に今田、円行の大部分が湘南台に編入され、六会地区は、石川、天神町、亀井野、西俣野と今田、円行の一部となり現在に至っています。六会地区郷土ずくり推進会議が2023年に作った『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』その中で、『亀井野・西俣野・石川・円行・今田・下土棚のあゆみ』について『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』から転記いたします。下記の写真は、私の写真に変更させていただいたものもあります。①亀井野亀井野という地名は、この地に住んでいた源義経の四天王の1人、亀井六郎重清が不動王を祀って崇拝していたことから名付けられたという説と、地形が亀の甲形をしている丘と湿地帯の野原からなっているからという説と東側境界線が亀の甲形をしているからという説が言い伝えられています。江戸時代には深い井戸を掘る技術が確立し、亀井野の集落が発展し、その中心は雲昌寺前の八王子街道(滝山街道)沿いでした。横浜の金沢や六浦から運ばれてくる塩を売る「塩の市」が開かれ、継立場もおかれ、八王子街道の要地となりました。亀井野の南西に位置する地域は入会地の秣場(まぐさば・牛馬のエサとなる草刈場)として利用されていましたが、明治になって開拓が進み広大な農地ができ、通称亀井野新田と呼ばれています。明治以降、亀井野は六会の中心的な地域となり、六会小学校、六会中学校、六会郵便局、市役所の支所等が開設されました。特に昭和4年( 1929年)に小田急江ノ島線が開通した後は、多くの商店が六会駅(現六会日大前駅)の周りに集まってきました。昭和47年( 1972年)に始まった六会東部土地区画整理事業で、駅前広場の新設と住宅環境が整い住み良い地域となりました。雲昌寺曹洞宗光輝山雲昌寺建保年間(1213年~1219年)に鎌倉幕府二代執権 北条義時が唐より帰朝後、藤沢今田村の地に建立した瑞龍寺を起源とします。慶長元年(1596年)7月水害で罹災した後、鎌倉市植木の龍宝寺四世玖山宗順和尚を開山に迎え、現在地亀井野に移り寺号を曹洞宗光輝山雲昌寺と改めました。関東大震災で倒壊した後に、再建した本堂を昭和61年に増改築し、現在に至っています。藤沢市亀井野1457。②西俣野俣野は大庭御厨俣野郷と呼ばれ、俣野五郎景久の領地でした。大庭御厨というのは俣野五郎景久の曾祖父の鎌倉権五郎景政が伊勢神宮に土地を泰納して「御厨」の名を受けて、他の豪族の侵入を防いだと言われています。その後、現在藤沢市の西俣野と境川を挟んで現在横浜市の東俣野、上俣野にわかれました。俣野の名称は、川を挟んで両方に分かれた野原、股になった野原という地形から名付けられたという説と領主であった俣野五郎景久の名前から引用されたという説があります。西俣野には史跡が多く、小栗判官と照手姫の伝説が伝わっています。毎年1月16日と8月16日に花應院の住職による「小栗伝説・地獄変相十王図絵解き」が開催されています。昔の境川は曲がりくねっており、たびたび堤防が決壊して水田が水浸しとなり、深い淵ができました。そういう中で、1人の瞽女が淵に落ちて死んだり、1人の浪人が堤防を守るために人柱となりました。このような歴史を背景に、明治42年( 1909年)に「藤沢町・六会村・俣野村連合耕地整理事業」が始まりました。「蛇行河川改修工事」や「暗渠によるニ毛作可能な乾田工事」等が行われ、その活動は第ニ次世界大戦まで続きました。その結果、川と森に挟まれた肥沃な田園地帯となり、ハウス栽培が盛んとなりました。花應院。曹洞宗西嶺山 花應院。慶長9年(1604年)に開山は国境と開基は祖桂として創建された。 近くにあった閻魔堂(法王院 十王堂、浄土宗、常光寺末寺、武蔵国六浦金沢からの金沢道沿い。小栗判官の墓がある。天保11年間(1840年)に火災にあい閻魔大王像が運び込まれた。藤沢市西俣野866番地。③石川石川とは小石が多い底の浅い川という意味があり、この辺は古相模川が作った相模野礫(小石を多く含んだ土壌)の砂利が露出しています。昔は「伊志加波牟良」(いしかわむら)と名付けられていました。寛政10年(1798年)に「石河村」となり、安政6年(1851年)に現在の「石川」となりました。江戸時代は、旗本中根氏が明治になるまで約300年間支配していたと言われ、自性院がその菩提寺で、境内には墓所があります。自性院は、石川自性院龍見寺という浄土宗の寺です。浄土宗を開いた法然上人に帰依した石川禅門(ぜんもん)・渋谷七郎入道同遍がこの地に住んでいたことから「石川」と呼ばれるようになったという説もあります。小田原北条氏の時代に石川の半分を領した武士団が帰農して農地を開墾して収穫高を大幅に増加させました。その武士団はその後「石川六人衆」と呼ばれていました。「石川六人衆」とは、主に神奈川県藤沢市にかつて存在した戦国末期の有力な一族の集団を指します。この六人衆は、源義朝を祭神とする佐波神社を勧請したと伝えられており、入内嶋、西山、田代、伊沢、佐川、市川氏の名前が挙げられています。昭和35年(1960年)に策定された藤沢市北部工業開発計画に基づき、石川を中心に土地区画整理事業が進められました。桐原工業団地の開発、道路網の整備や宅地整備等が進められました。更に、石川東部土地区画整理事業では、日本大学のキャンパスと引地川の間の宅地化造成工事が施工され、天神町が誕生しました。区画整理事業に先立ち、遺跡の発掘が行われ「下の根遺跡」や「南鍛冶山遺跡」が発掘されました。「下の根遺跡」では、約1万年以上前の先土器時代の足跡が発見され、「南鍛冶山遺跡」では奈良時代~平安時代の「ムラ」が見つかり、竪穴式住居跡や鉄製品がたくさん出土しました。奈良・平安時代の十師器・須恵器「南鍛治山遺跡」④円行円行という地名は、南北朝時代(1336 ~ 1392年)に引地川沿いの平坦地で梅田と呼ばれる所に円行寺という寺があり、村民の信仰を集めていたことから寺の名前をとって「円行」と呼ばれるようになったと伝えられています。引地川の円行堰あたりは、しばしば決壊したため道が悪く「座頭転」という地名がありました。川沿いには各所に個人所有の水車を設置して、水田用の水を汲み上げていました。また、六会小学校前を流れる不動川は、昔は水量が多く、洗濯をしたり、野菜を洗ったりして、村人の生活と大きな係わりをもっていました。円行は農業を主に営む純農村地帯で、引地川を挟んで田畑が広がる緑の多い地域でした。しかし、水田は湿田が多くて泥沼のようでした。昭和30年(1955年)頃、余分な山からの湧き水を田の中に埋められた配水管を通して川流す暗渠排水工事が行われたことで、水はけの良い田に変りました。その後の土地区画整理事業により、急速に市街化が進み、平成元年(1989年)に大部分が湘南台に編入されました。円行公園。湘南台駅から引地川に向かって坂道を下りていくと、緑豊かな円行公園がみえてきます。遊び場としての要素だけでなく、斜面地形を利用した竹林、梅を楽しめる庭園的要素を取り入れたこの公園は、引地川沿いの桜並木と共に、季節に彩りを添えています。藤沢市湘南台3丁目6番。⑤今田豊臣秀吉が小田原北条氏を攻めた時に出した味方の軍勢の乱暴を禁止した制札があります。その中に「今田、亀井野」と書かれていたことから、この頃には今田村が存在していたようです。天保13年(1842年)に発刊された「新編相模国風土記稿」には、元々今田と亀井野は一村であった。分村して今田村になったと書かれていますが、その時期は不明です。現在、亀井野にある雲昌寺は建保年間( 1213年~ 1218年)に今田に創建され「瑞龍寺」と言われていました。慶長元年( 1596年)の水害でお堂が流されたために亀井野に移され「雲昌寺」と言われるようになりました。今田に創建されていた「瑞龍寺」は、現在の県立藤沢工科高等学校のテニスコートの裏の北側の境川沿いにあったとのことです。今田を流れる境川は河川改修が行われるまでしばしば決壊して人々を悩ませていましたが肥沃な土砂も運ばれて来ていたので、おいしい米が収穫できたという利点もあり、農業の盛んな地域でした。昭和35年( 1960年)に策定された藤沢市北部工業開発計画に基づき行われた土地区画整理により、水田は梨、ぶどう、栗の観光果樹園に変わる一方、急速に市街化が進み、平成元年(1189)に大部分が湘南台に編入されました。果樹園。県立境川遊水池公園近くの今飯橋から自転車道路に沿った場所にあります。藤沢市北部には昔から多くの梨園がありますが、最近ではブドウも特産。梨は幸水と豊水。ぶどうは地元で作出されたブドウ品種の藤稔を中心に栽培。⑥下土棚鎌倉時代、現在の下土棚、長後、高倉、上土棚、円行地域は渋谷庄司重国の支配下にありました。天正19年(1591年)、三河の国より徳川家康に従って来た竹尾伝九郎元成が地頭を命ぜられ、下土棚を支配するようになり、7代目の竹尾喜左衛門元貞まで続きました。善然寺にあるその墓碑の中に「相模国土棚郷」と書かれており、「土棚」という地名の最古のものです。下上棚の「土棚」という地名は、引地川の長年にわたる浸食作用で関東ローム層の赤土の断崖が数メートルになり、土の棚になったとする説と源氏と平氏の合戦の時、大庭景親と渋谷庄司重国が戦って、引地川の水を堰き止めたため、一帯が湖のようになり、水が引いた後、土砂が棚状に残った史実からとする説が伝えられています。善然寺では歴代の住職が子弟の学問の指導にあたっていました。文化5年(1808年)に善然寺31世弁誉上人の教えを受けた18人の筆子により「筆小塚」が建てられました。昭和19年( 1944年)に下土棚の西部に海軍横須賀通信学校藤沢分校が建てられ、多くの海軍兵士が駐留していました。戦後、跡地は旧地主に返還され、昭和36年( 1961年)には、その跡地に「いすゞ自動車(株)の藤沢工場」が建設されました。その後、昭和47年(1972年)に下土棚すべてが長後地区に編入されました。善然寺(ぜんねんじ)浄土宗。龍玉山西光院善然寺創建:寛元4年(1246年)と伝承されています。龍玉山西光院。開山は西光上人といわれています。本尊は阿弥陀如来。境内にある筆子塚5基は寛延4年(1751)から元治2年(1865)までの5代に渡る住職のための塚です。善然寺にできた寺子屋の生徒が、先生である住職に報いるために墓碑を建て供養したものです。(市指定重要史跡)このほかに下土棚を治めていた旗本竹尾氏の墓などがあります。藤沢市下土棚999そして、先輩の方々の大作「六会地区歴史年表」を転記して紹介いたします。今後も、六会に関する大切な歴史資料として、横書きでのデジタル化も必要と考え横書きにて転記させていただきました。この歴史年表は平成20年代~令和初期の・『六会地区郷土づくり推進会議 人・自然あふれるまちづくり部会』・『六会市民センター地域担当』の方々のご努力により作成されたものです。以下の参考資料・現地調査等によって作成されたとのことです。以下、この六会地区歴史年表を転記させていただきました。そして、その歴史を解りやすく理解するために、参考資料部に👈️(リンク) を貼り付けさせていただきました。👈️の青字の部分をクリックすると、リンクのURLが開くようになっています。★六会地区 歴史年表-1 年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平安時代寛治 元年 1087 鎌倉権五郎景政は源義家に従い奥州の 後三年の役で活躍する永久 5年 1117 鎌倉権五郎景政、高座郡の私領を 「御厨」👈️とは、供祭の 開発し 伊勢神宮へ寄進(大庭御厨の成立) 魚介類、果物等を調達 その後、俣野郷大日堂建立(現在の御嶽神社) するところ 平治 元年 1159 平治の乱に敗れた源義朝の従者、渋谷金王丸 は東国に逃れ渋谷の荘(下土棚)に入ると 伝わる(平治物語) 治承 4年 1180 俣野五郎景久(鎌倉権五郎景政の曾孫) 「石橋山」👈️とは 大庭景親(俣野五郎景久の兄)石橋山で 小田原市の南部にある 源頼朝と戦う 養和 2年 1182 俣野五郎景久、木曽義仲と越中砥並山で 戦い敗走、続く篠原合戦で闘死(平家物語)★六会地区 歴史年表-2年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料鎌倉時代建久 3年 1192 源頼朝、鎌倉幕府👈️ を開く 1185年説 あり 6年 1195 大庭御厨、俣野郷大日堂に田畑寄進、 仏聖燈油に充てられる 俣野五郎景久、後尼の彼岸を聞かれ 三浦義澄興隆興行の儀執行 (御嶽山神札社) 承元 3年 1205 源実朝、俣野郷大日堂の修復を 北条義時に命ず建保 元年 1213 和田氏の乱が起こり、渋谷金王丸(下土棚)、 北条義時の軍に打たれる 6年 1218 光輝山(こうたくさん)瑞龍寺(雲昌寺の前進) 今田に創建される、開基は北条義時という 弘安 5年 1282 北条時宗「円覚寺」創建 👈️ 正中 2年 1325 遊行寺建立、開基は俣野郷地頭、 「開基」:寺を建立するため 俣野五郎影平( 鎌倉の征夷大将軍 に資金や土地を提供した人 守邦親王の執事) 「開山」:寺で最初に住職と 開山は呑海上人(遊行四世) なり、宗教的指導を行った人 嘉暦 2年 1327 呑海上人没す(63歳) 元弘 3年 1333 西光法師、下土棚の夏苅に善然寺を 創建する建武 3年 1336 湊川の戦い、楠木正成戦死 👈️ ・・・つづく・・・👈️
2025.11.10
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その134): ロンドン散策記・日本への帰路-3
北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3) の降機ゲート付近を写す。「阿里云全力支持中国企业出海」→【アリクラウド(阿里雲)は、中国企業の海外進出を全力で支援します。】 阿里云(アリクラウド / Alibaba Cloud) は、中国の大手IT企業アリババ・グループのクラウドコンピューティング部門。飛行機を降りてボーディングブリッジ(搭乗橋)を進み、入国審査(Immigration)・手荷物受取(Baggage Claim)・乗り継ぎ(Transfer) への通路に向かう青地に白文字の案内板には、「出口・行李提取・转机(Exit・Baggage Claim・Transfer)」 と書かれていた。北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3) のエスカレータを上がって。天井の赤い格子状ルーバーと、ガラス壁+赤い鉄骨構造がT3特有のデザインであり、特にT3-CコンコースからT3-E(国際線入国審査)へ向かう通路がここ。🔹標識の内容(原文・英訳・和訳)中国語表記 英語表記 日本語訳转机 Transfer 乗り継ぎ(トランジット)出口、行李提取 Exit, Baggage Claim 出口・手荷物受取所洗手间 Toilet トイレ外国人指纹自助留存 Fingerprint Self-collection 外国人指紋登録機(自動登録機)临时入境许可申请 Temporary Entry 一時入国許可申請(トランジットで Permit Application 一時入国する際に必要) 「入国審査(Immigration)」へ向かう長い移動通路(moving walkway zone)の様子を。ムービングウォーク(動く歩道) の上から入国審査(Immigration)方面へと進む。Transfer・乗り継ぎ(トランジット)審査を通過し進む。北京首都国際空港 第3ターミナル(T3)国際線到着ロビー付近に設けられた中国伝統建築風の庭園パビリオン(中庭式東屋)。T3の設計は「龍が天に昇る空港」をテーマとしており、このような伝統的な中華様式の装飾空間を、ハイテクな建築空間の中に融合させているのが特徴 と。🔹建築様式の特徴この構造は典型的な清朝様式の四阿(あずまや)で、以下の特徴が見られる と。 要素 特徴・意味屋根 青灰色の瓦屋根(歇山頂式、Xieshan Roof)。高貴な建築様式。柱・梁 朱塗りの円柱に彩色(藍・緑・金)を施した「彩画」装飾。天井 「斗拱(ときょう)」構造が装飾的に強調され、金彩と雲文様。揮毫(書額) 上部中央の黒地金文字「月潭华泽(Yuètán Huázé)」が掲げられ、 側面の対聯(ついれん)も金字で書かれています。周囲 岩石・樹木・人工水路などを配置し、「庭園と建築の調和」を演出。中央の扁額には、輝澄月日(huī chéng yuè rì)。これは直訳すると「月と太陽のように光り澄みわたる」という意味であり、清朗な光・明徳・調和の象徴であると。右柱には「天香低度金蠟暖」→【天上の香りが静かに漂い、金の蝋燭のあたたかな光が 柔らかく照らす。】 左柱には「玉殿遥看鳳飛」→【玉の殿堂を遠く望めば、鳳凰が舞い飛ぶ】すなわち【天の香りが柔らかに漂い、金の灯火が温かく輝く。 玉の殿堂を遠くに望めば、鳳凰が舞い昇る光景が見える。】と。空港という「国家の玄関」において、「明るく澄んだ光の中に温かい繁栄と和を祈る」という寓意が込められているのだと。「輝澄月日」扁額と対聯(天香低度金蠟暖/玉殿遥看鳳飛)を掲げた東屋を、少し離れた位置から斜め方向(右前方)に眺めた全景。ここは、国際線到着ロビー内の「中国庭園風休憩区」(通称:国風長廊 Guofeng Gallery)。第3ターミナル(T3)出発フロアに設置されている国際線出発案内モニター。日本・羽田への帰国便は12:45発 CA167 東京羽田。第3ターミナル(T3)国際出発エリア内の中央ホールにある噴水広場。・噴水の中心部は三層式で、上段の水柱が高く噴き上がり、下段には円形に整列した 小噴出口から紫色照明の水流が放射状に広がっています。・周囲を囲む熱帯植物(モンステラ、アグラオネマ、シダなど)が、人工照明下でも 「緑のオアシス」的な雰囲気をつくっています。・手前中央には説明板が設置されており、これはおそらく「首都空港文化展示 (Capital Airport Art & Culture)」シリーズの一部。 内容は噴水の設計コンセプトや、中国文化での「水」の象徴(富・調和・生命)について 触れているもの。解説プレート(案内板)「In October 1979, Yuan Yunsheng, a well-known contemporary painter, completedthe muralThe Water-Splashing Festival – A Hymn of Life for Terminal 1, Beijing Capital International Airport.Based on folklore, it mainly describes the grand scene of carnivals on the Water-Splashing Festival and reveals people's beautiful wishes for loving life, pursuingfreedom and yearning for happiness.In order to better narrow the boundary between art and society, and release the liveliness and vitality of art, Beijing Capital International Airport stereoscopically restores the mural content in a ratio of one to one. It interprets works in anotherform and pays tribute to the classics.This sculpture is one character from the original work of art.」 【1979年10月、現代中国の著名画家・袁运生(ユエン・ユンシェン) は、北京首都国際空港第1ターミナルのために壁画『潑水節—生命の頌歌(The Water-Splashing Festival – A Hymn of Life)』を完成させました。この作品は少数民族の伝承に基づき、潑水節(ポースイジエ、Water-Splashing Festival)の祝祭を題材として、人々の「生命を愛し、自由を求め、幸福を願う」美しい心情を描いています。北京首都国際空港では、芸術と社会との境界を取り払い、芸術の生命力と活力を広く伝えるために、この壁画の一部を原寸大の立体彫刻として再現し、古典的名作への敬意を表しています。※この彫刻は、元の壁画に登場する登場人物の一人を立体化したものです。】潑水節—生命の頌歌(The Water-Splashing Festival – A Hymn of Life)をネットから。有名なモニュメント 「I ❤️ Beijing」 の前景。このモニュメントは、北京空港の「都市アイデンティティと国際的歓迎の象徴」として設置されたもの。北京首都国際空港 第3ターミナル(T3)国際線出発ロビー中央エリアにある伝統建築様式の東屋「国風長廊(Guofeng Gallery)」の一棟を、正面からまっすぐに撮影。東屋「国風長廊(Guofeng Gallery)」の周囲を移動して。北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)第3ターミナル(T3)出発エリアの搭乗ゲート付近から見た駐機場(エプロン)の様子。T3Eコンコース(国際線側)のガラス張りの搭乗橋(ボーディングブリッジ)連絡通路から、滑走路南西方向に向かって撮影。第3ターミナル(T3)Eコンコースの国際線出発ゲート付近の待合ロビーを。第3ターミナル(T3E)国際線出発エリアの案内標識とフロアマップ。第3ターミナル(T3)エリアの管制塔(Air Traffic Control Tower)。・名称 北京首都国際空港 管制塔(Beijing Capital Airport ATC Tower)・位置 第3ターミナル(T3)西側滑走路(36R/18L)付近中央・完成年 2007年(T3の開業時)・高さ 約90メートル(地上27階建てに相当)・設計意匠 ノーマン・フォスター建築事務所(Foster + Partners)によるT3全体の デザインコンセプトの一部として設計・外観構造 鋼鉄とガラスで構成された有機的フォルム。 塔身は「花瓶(Vase)」または「竹の幹(Bamboo Stem)」を思わせるくびれ形。・機能 北京空港の全滑走路・誘導路を統合監視し、地上管制・離着陸管制を一元的に行う。北京首都国際空港 ・第3ターミナル(T3)の天井構造を見上げて。天井構造 : アルミニウム製の格子ルーバー(sun louver grid)によって構成。 金色と灰色のラインが幾何学的に交差しています。支柱(柱): 巨大な白色円錐柱(tapered concrete columns)。下から上に向かって 細くなる設計で、天井を軽やかに支える印象を与えています。 採光設計 : 天井の一部に配置されたトップライト(天窓)から自然光を導入。 昼間は人工照明をほとんど使わず、柔らかな拡散光が空間を包みます。色彩構成 : 金(黄)・赤・灰の組み合わせで、中国の伝統的配色「朱金灰」をモダンに再構成。 金は「富と吉祥」、赤は「生命と幸福」を象徴。この天井デザインは、ノーマン・フォスターによる設計思想「竹林を思わせる天井(A Forest of Light)」に基づいている と。T3の屋根は、全長3.25 km/総面積98万㎡という世界最大級の屋根構造の一つ。先ほど見上げた「天井構造」を今度は遠近軸(中央コンコースの縦軸方向)から見通したもの。支柱:白いテーパード円柱が規則的に配置され、構造的にも視覚的にもリズムを形成。 柱の間隔は約60m、1本あたりが「竹」の象徴。「パンダ・フォトフレーム像(Photo Frame Panda)」丸いフォルムのパンダが、インスタグラム風の「撮影フレーム」を持っている。下部にはSNSアイコン(ホーム・検索・ハート・カメラなど)が描かれており、観光写真を意識した現代的演出。滑走路と誘導路の見えるエプロンエリアを。北京首都国際空港 管制塔(Air Traffic Control Tower)🔹概要項目 内容名称 Beijing Capital International Airport ATC Tower(首都机场塔台)完成年 2008年(T3オープン時)高さ 約 97 m(地上から)設計 北京建築設計研究院 × Norman Foster(フォスター&パートナーズ)監修エリア内の 一貫設計役割 滑走路の離着陸誘導、地上走行の管理、気象観測連絡など航空交通の中枢。壁面パネル越しに、外の管制塔が映り込んでいる光景。第3ターミナル(T3)の象徴である航空交通管制塔(Air Traffic Control Tower)をクローズアップで捉えて。・形状 ― 「蓮のつぼみ」または「花瓶」型 塔身は下部が広く、中央がくびれ、 上部が再び開く優雅な流線形。この曲線は中国伝統の「蓮花瓶(れんかびょう)」をモチーフとしており、平安・調和・上昇を象徴します。搭乗便・中国国際航空(Air China、中国国际航空公司)の大型旅客機。Airbus A321-200型機。第3ターミナル(T3)の搭乗ゲート E20 に設置された出発案内表示(Gate Information Board)。搭乗ゲート E20航空会社 中国国際航空(Air China, 中国国际航空公司)便名 CA167行き先 東京・羽田(Tokyo Haneda)出発予定時刻 12:45現在時刻(撮影時) 11:42(June 10, 2025)気温情報(目的地) 23°C/20°C(Heavy rain:大雨)中国国際航空(Air China)の旅客機、奥には同空港のメイン管制塔(Air Traffic Control Tower)を再び。第3ターミナル(T3)Eコンコースの搭乗ゲートE20へ向かう通路から。駐機中の 中国国際航空(Air China, 中国国际航空公司)機・便名 :CA167便・出発地 :北京首都国際空港(PEK)・到着地 :東京・羽田空港(HND)・出発時刻:12:45・使用機材:Airbus A321CA167便に乗り込む。特徴的なフォルムの管制塔(Control Tower)が聳えていた。・高さ 約97メートル・構造 鋼鉄とガラスのハイブリッド構造・外観形状 下部が広がり、中央がくびれた「花瓶型」フォルム(中国の伝統陶磁“瓶”を象る)・機能 滑走路・誘導路・駐機場の航空交通管制(Air Traffic Control)ヨーロッパのエアバス社が製造する 中距離向け・単通路(ナローボディ)旅客機 の代表的モデル。✈️ 基本情報|Airbus A321-200(エアバスA321-200)製造会社: Airbus S.A.S.(フランス・トゥールーズ本社)機種分類: 単通路(ナローボディ)型旅客機シリーズ: A320ファミリー(A318 / A319 / A320 / A321)中で最大初飛行: 1993年運用開始: 1994年(ルフトハンザドイツ航空)Air Chinaへの導入: 1990年代後半から運用開始🧩 A321-200の構造的特徴全長: 約44.5 m(A320より約7 m長い)全幅: 約34.1 m全高: 約11.8 m胴体: A320を延長した設計。座席数を増やし、航続距離も延伸。客席数: (2クラス制) 約180〜200席(ビジネスクラス12席+エコノミー168席など)航続距離: 約4,000〜5,600 km(モデル・積載による)巡航速度: 約840 km/h主なエンジン: CFM56-5B または IAE V2500 シリーズ燃料タンク: A321-200では追加タンクを搭載可能(A321-100より長距離対応。そして定刻に北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport)を出発し東京羽田空港へ。最初の機内食。久しぶりの白米を楽しむ。そして羽田空港に到着し、到着、入国審査の方向に進む。羽田空港(Tokyo International Airport/東京国際空港)第3ターミナル。雨で濡れたエプロン(駐機場)と、航空機への給油車や手荷物搬送車などの地上支援車両が見られたのであった。到着ゲートから入国審査(Immigration)や乗り継ぎエリアに向かう途中のエスカレーター手前。長い 動く歩道(moving walkway) が続くガラス張りの通路で、右側は白い壁、左側は全面ガラスの吹き抜け構造。床は赤と緑の模様が入ったカーペットで、これは第3ターミナルの到着・乗り継ぎ導線に共通するデザイン。外に見えたのが羽田空港第3ターミナルビル(旧・国際線ターミナル)。駐機中のJAL機が並ぶ、南側エプロン(滑走路A側)に面した位置。この場所は、羽田空港第3ターミナルの名所の一つである羽田空港第3ターミナル・国際線エリアの連絡通路(サテライト⇔本館)で、動く歩道から外を望む。外のJAL機と連続する広告照明が織りなす、美しい構図。・デザイン意図 北京の伝統文化(壺・蓮)とハイテク空港の未来性の融合Airbus A321-200。中央に見えるのは、羽田空港の管制塔(Control Tower)。これは羽田空港の第二管制塔(現・主管制塔)で、2010年に供用開始された高さ約116メートルの構造物。現在は羽田空港全体(第1〜第3ターミナルおよび滑走路A〜D)を統括。搭乗口番号「140」が見えた。これは第3ターミナル(国際線)サテライト側ゲートの一部。写真中央には動く歩道(moving walkway)が2本並行して設置されており、左右に人々が移動中。「日本へ帰ってきた瞬間」—長旅を終えて入国審査に向かう、羽田空港ならではの“帰国動線”の一場面なのであった。そして1.検疫→2.入国審査→3.手荷物受取り→4.動物検疫・植物検疫→5.税関検査→6到着ロビー へと。入国審査(Immigration)。3.手荷物受取り私は、ロンドン・ヒースロー空港にて荷物が行方不明・「ロストバゲージ」になったため、ここ、 baggage carousel(バゲージ キャロセル)に出て来ることを期待して待ったが、荷物には再会できなかった。そして荷物引取所(バゲージクレイム)に向かい、荷物がヒースロー空港で行方不明になったこと、その経緯を、女性担当官に説明し、クレームタグ(預けた際にもらったタグの半券)と航空券を渡す。クレームタグ。そして女性係員が「手荷物紛失証明書(PIR)」に私からの情報を書き込んでくれた。・氏名、住所、連絡先・搭乗便名、日付・手荷物の特徴(色・形・ブランド・サイズ・タグ番号) また、トランクのKEY番号、ベルトのKEY番号を知らせ、ハードKEYを手渡した。・不具合の内容(紛失・遅延・破損 など)「手荷物紛失証明書(PIR:Property Irregularity Report)」は、航空会社が預かった手荷物が目的地で見つからない、破損している、または遅れて届いた場合に発行される公式なトラブル報告書。PIRは、航空会社またはその地上取扱会社(ハンドリングエージェント)が、手荷物に関する不具合(Irregularity)を正式に記録する書類。これは「手荷物が紛失・遅延・破損した」という事実を証明する重要な書類であり、後の捜索・補償・保険請求の基礎資料となるのであった。・さらに係員から、荷物の捜索情報は、スマホに連絡をもらえる。・荷物が発見された場合は、自宅まで無料送付する。 しかし、荷物の中に禁止物が入っていたことが判明したら、その品物は回収されたのち、 羽田空港から自宅までの運送費は着払いになると。そして手続きを完了し、係員の方が税関窓口まで同行してくれて、税関職員に事情を説明してくれて、税関を通過したのであった。そして、バスにて横浜駅・Yキャットへ。そしてJR東海道線、小田急線を利用して帰宅したのであった。そして帰宅後の次の日に、我がトランクはヒースロー空港にあり、北京空港に送付されると。そしてその2日後に北京空港から羽田空港への移動中であるとの連絡をいただいたのであった。そして私が帰宅してから5日後に、遅れて我が荷物も無料で帰宅したのであった。内部を確認したが、全てが無事に、破損等もなく帰宅したのであった。わがトランクは何処を彷徨っていたのかは依然として不明なのであるが・・・やれやれ!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アイルランド8日間、ロンドン4日間、高校時代の親友4人、合計≒300歳での旅であった。アイルランド・緑と石の国——どこまでも広がる牧草地と石垣の風景に、時間の流れの穏やかさを感じた。・人の温かさ——道を尋ねても、店に入っても、どこか親しみのこもった笑顔と会話が印象的。・修道院や教会の静謐 Kylemore AbbeyやCong Abbeyなど、廃墟や修道院に漂う静けさが心に残る。・歴史が息づく街並み AthloneやGalwayの街角では、中世から続く建物と現代の暮らしが自然に共存していた。・音楽と酒場文化 パブで流れるアイリッシュ音楽と人々の歌声に、土地の誇りと人生の楽しさを感じた。・自然の雄大さ ConnemaraやKillarneyの湖水地方の眺望は、まさに「神に守られた緑の楽園」。・ステンドグラスと芸術性 教会や博物館で見た彩色ガラスの美しさに、信仰と美の融合を感じた。・交通と気候の印象 雨と霧が交互に訪れ、風景の色合いを刻々と変える「変わりやすい天気」も旅の一部として 楽しめたのであった。日本との時差 -9時間フライト時間 約15~16時間公用語 英語・ゲール語通貨 ユーロアイルランド。アイルランドはEUの一部であり、協力関係を築きながら、欧州全体の自由な移動を可能にするシェンゲン協定には参加せず、独自の国境管理を維持。アイルランド国旗。北海道との広さの比較。緯度の比較。ダブリン:53.43°N宗谷岬 :45.52°Nダブリン~宗谷岬 距離差 :850km北アイルランド特有の石碑である ハイクロス(High Cross)、別名 ケルト十字(Celtic Cross)。モハー断崖。海上の岩柱 ブリーナン・モア(Branaunmore)。カイルモア・アビー(Kylemore Abbey)。ハーフペニー橋(Ha’penny Bridge)。THE TEMPLE BAR。名門大学 トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)。ダブリン城。ロンドン・歴史と現代が共存する都市 セント・ポール大聖堂からタワー・ブリッジまで歩くと、過去と現在が交錯する時間の旅のよう。・テムズ川の流れ ゆったりとした川の流れが、ロンドンの壮大な歴史を静かに語っているようだった。・建築の多様性 古典的な石造建築と近代的なガラスの高層ビルが見事に共存している。・象徴的なランドマーク ロンドン・アイ、ウェストミンスター宮殿、タワー・オブ・ロンドンなど、どこを見ても 「物語の舞台」。・街歩きの楽しさ 橋を渡るごとに風景が変わり、歩くことそのものが「観光」になる街。・芸術と知性の香り 博物館やギャラリーの無料公開、街角の彫像や記念碑にも文化の厚みを感じた。・夜景の美しさ ライトアップされた橋や建物が川面に映り、幻想的な光景をつくり出していた。・多国籍都市のエネルギー 人々の多様な言語と文化が混ざり合い、世界都市の鼓動を肌で感じた のであった。イギリス国旗。 ビッグ・ベン、ウェストミンスター橋。 ロンドン・アイ。タワー・ブリッジ。ロンドン塔。セント・ポール大聖堂(St Paul’s Cathedral)。ケンジントン宮殿(Kensington Palace) と、その前庭に立つ ヴィクトリア女王像(Statue of Queen Victoria)。 Lost Luggag!! 無事に我が家に戻ったトランク(右)。 ・・・もどる・・・
2025.11.09
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その133): ロンドン散策記・日本への帰路-2
この日は8時過ぎに起床。Hilton London Heathrow Airport Terminal 5(ヒルトン ロンドン ヒースロー エアポート ターミナル 5)の我が部屋の洗面所。・鏡の背面にLEDイルミネーションが組み込まれており、ピンク〜紫のグラデーション光が空間を 幻想的に演出。・照明はおそらく調光式(色温度変更可能タイプ)で、ムードや時間帯に応じて変更できる仕様。・ミラー右側に円形の拡大ミラー(メイク用ライト付き)も設置されており、海外高級ホテルでは 定番の設備壁掛け式トイレ(Floating Toilet)・床から浮かせた「ウォールハンギングタイプ」で、ヨーロッパの高級ホテルによく見られる形式。・床掃除がしやすく、見た目にも軽やかで空間を広く見せる効果があります。・背後の壁に埋め込み型の水洗ボタン(フラッシュプレート)が設置され、機能的でミニマルな デザイン。・洗面カウンター背面にも、同じくピンク色のイルミネーションパネルが走っていた。浴槽(バスタブ)兼シャワーブース。・長方形の洋式バスタブで、シャワー兼用タイプ。・浴槽縁の高さが低めで、入りやすい設計です。・英国のホテルではシャワーブースのみの場合も多い中、ヒルトンT5は全室バスタブ付き (上級仕様)なのが特徴。Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 の客室に備え付けられた 多国対応電源パネル(ユニバーサル・アウトレットボード)。① イギリス式コンセント(Type G) ・差込口が「三角形配置(3ピン)」のUK規格。 ・電圧は AC 220〜240V / 50Hz。 ・上部にある2つのスイッチは、それぞれの差込口の電源ON/OFFを独立して制御する安全設計。 (イギリスでは「差しっぱなし防止」や「感電防止」のため、スイッチ付きが一般的)② ユニバーサルタイプ(中央) ・上部の小さな穴が「安全シャッター解除用」で、ほとんどのプラグ形状(A・C・Iなど)を 差し込めます。 ・ただし、変圧機能はありません。日本(100V)対応機器を使う場合は、電圧対応を確認する 必要があります。③ アメリカ式コンセント(Type A/B) ・平行2ピン+アース穴付きタイプ。 ・北米・日本のプラグをそのまま差し込めますが、電圧は240Vなので注意が必要。 → スマートフォン充電器・ノートPCのACアダプタのように「100–240V対応」なら問題なく 使用可能。④ LANポート(右端) ・有線インターネット接続用RJ45ポート。 ・Wi-Fiが利用できない場合や高速通信を求めるビジネス客向けに設置。 ・現在は多くの宿泊者がWi-Fiを利用するため、ややサブ的存在になっている。Hilton Honors(ヒルトン・オナーズ)会員プログラムの案内カード。ルームキー・ホルダー(カードケース)。「JOIN TODAY AND GET MORE BENEFITS THAN EVER BEFORE.Hilton Honors benefits include:・Best Price・Free Wi-Fi・Choose Your Room・Digital Check-InDownload the award-winning Hilton Honors app to access even more benefits.」 【今すぐ入会して、これまで以上の特典を。Hilton Honors会員になると、以下の特典が受けられます:・ベストプライス保証・無料Wi-Fi(スタンダード)・部屋を事前に選択可能・デジタルチェックイン対応さらにHilton Honorsアプリを使えば、より多くの特典を利用できます。】・Room Number: 266・Check-Out Date: 10/06/25(2025年6月10日)「The Gallery」レストランで朝食を。ロビーエリア(Reception / Lobby Lounge)。1. 中央の円形レセプションカウンター ・写真中央に見える白い円形のカウンターが、メイン・レセプション(チェックインデスク)。 ・柔らかなカーブを描く造形で、ヒルトンT5のインテリアテーマである 「流線と光の調和(flow & light)」 を象徴。 ・台座部分は黒い大理石調で、上面はマットな白。 滑らかな質感が落ち着いた高級感を演出。2. ロビー空間のレイアウト ・写真右手前には階段があり、上階のレストランやバーラウンジへつながっていた。 上階には照明が吊るされた回廊(メザニンフロア)が。 ・左奥にはラウンジスペースが広がり、ソファ席と電子掲示板(フライト情報表示モニター)も 設置。 空港ホテルらしく、出発情報をリアルタイムで確認できる仕様。 ・天井は吹き抜け構造で、自然光と照明のバランスが美しい開放的な空間。ホテルの外へ。銘板「Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 」。建物の中央を見上げて。1.建物の様式 ・外壁は赤褐色のレンガ造り(Brickwork)で、英国建築の伝統的意匠を反映。 ・白い帯状のストライプ(水平装飾モールディング)が階層を区切っており、 全体に整った安定感。 ・上階の三角形屋根部には「Hilton」の青いロゴサインが掲げられ、シンボル的存在。2.エントランス・キャノピー(車寄せ屋根) ・玄関前には大きなキャノピー(雨避けの庇)が張り出し、車での送迎時に雨風を防ぐ構造。 ・天井には小型の埋め込み照明が多数配置され、夜間には柔らかく光る設計。 ・支柱は黒いスチール製で細身、モダンな印象に仕上げられていた。3.窓の配置 ・窓は上下で規則正しく配置され、外観にリズムを生み出していた。 ・1階部分(地上階)はガラス面積が広く、内部ロビーの自然光を取り込む設計。 ・上層階の客室窓は二重ガラスで防音・断熱性を確保。空港近接ホテルならではの構造 と。Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 の建物を、正面玄関側からやや斜めに見上げて。1.窓の構成 ・1階部分(地上階)は大きなガラスウィンドウで、ロビー・レストラン・会議室エリア。 ・2階以上は宿泊客室フロアで、均等配置の矩形窓が整然と並ぶ。 ・ガラスは反射率の高いティント加工(淡いグリーン色)で、外光を取り込みつつ プライバシーを守る設計。2.アーケード(庇下の回廊) ・地上階の柱列に沿ってアーケード(屋根付き通路)が設けられていた。 ・雨天でも玄関から車寄せ・エントランスへスムーズに移動できるように設計。 ・柱と梁の白色ストーンが、レンガ壁と美しいコントラストを。上空には、ヒースロー空港(Heathrow Airport)上空を飛行する旅客機の姿が。 ・ヒースロー空港は南北2本の滑走路(09L/27R、09R/27L)を持ち、 西風時には東から西へ着陸する運用(27方向運用)が一般的 と。 ・空港への最終進入(Final Approach)前、もしくは離陸直後(Climb-out)のいずれか。 ・エアバスA320シリーズまたはボーイング737シリーズクラスの中型機か?空港送迎用の車寄せ(ポートコシェール)と、赤レンガの建物ファサードを。・外壁は赤褐色レンガと白いストーン帯で構成されたブリティッシュ・モダン様式 (British Contemporary Brick Style)。そして、12:00過ぎに空港への送迎バスが到着。Bath」Rdを進み、M25を渡る。M25 モーターウェイ (M25 motorway) またはロンドン・オービタル (London Orbital) は、イギリスおよびイングランドの首都ロンドン(グレーター・ロンドン)の周囲を繋ぐ総延長117-マイル (188 km)の環状高速道路。Northern Perimeter Road West(ノーザン・ペリメータ・ロード・ウェスト)を進む。Northern Perimeter Rd W沿いの巨大な駐車場。Heathrow Fire Station(ヒースロー空港消防署) の入口付近。中央奥に見える赤レンガの高い塔は、ヒースロー消防署(Heathrow Fire Station)の訓練塔(drill tower)。左手下に見えたのが、ヒースロー空港(London Heathrow Airport)近くの道路沿いに設置されているエミレーツ航空(Emirates)A380模型ディスプレイ。空港アクセス道路(Bath Road, A4)沿いにあり、ヒースローを代表するランドマーク広告オブジェクトのひとつ。Emirates Airbus A380。このモニュメントは、ヒースロー空港ターミナル5へのアクセス道路(A4 Bath Road)沿いにあり、Hatton Cross(ハットン・クロス)交差点付近。エミレーツ航空が支援する「United for Wildlife」キャンペーンの一環で、絶滅危惧種の密猟・密輸防止を訴える国際的プロジェクト。機体に描かれている動物たち(ゾウ、ライオン、ゴリラ、サイ、ヒョウなど)は、“空の旅を通じて地球の野生を守る”というメッセージを象徴しているのだ と。旧ヒースロー空港管制塔(Old Heathrow Control Tower)か?・駐車場エリア(Terminal 2 & 3 Short Stay Car Park)のそばに位置。・建設時期:1950年代後半・使用期間:1950年代後半〜2007年ごろまで、約半世紀にわたり空港の主要管制塔として機能。・かつては滑走路04/22(現在は閉鎖)や北滑走路を監視する位置にあり、 ヒースローの空港運用を統括していた。「ターミナル前車寄せエリア(Terminal Drop-Off Zone)」の有料化案内標識。£6 Terminal Drop-Off Charge(ターミナル前車寄せ料金:1回あたり6ポンド)と。「第2ターミナル」方面へ。The Queen’s Terminal として知られる、2014年に全面改築された新ターミナル。この建物は、ロンドン・ヒースロー空港(London Heathrow Airport)第2ターミナル(Terminal 2 – The Queen’s Terminal)のすぐそばに建つHilton Garden Inn London Heathrow Terminal 2 and 3(ヒルトン・ガーデン・イン・ロンドン・ヒースロー・ターミナル2&3)。ボイラーハウス(boiler house)/プラント施設(utility plant)の一部を見上げて。上部に2本の太い円筒形煙突(chimneys / exhaust stacks)が。第5ターミナル(Terminal 5) 前の車寄せ(Departures Forecourt / Drop-Off Area)を。・背景に見える建物の屋根は、ヒースロー第5ターミナル(Terminal 5 Main Building)の 特徴的な「ゆるやかな曲線屋根(wave-form roof)」です。・これは建築家リチャード・ロジャース(Richard Rogers)による設計。Terminal 5 Arrivals Forecourt(ヒースロー第5ターミナル 到着階車寄せエリア)に到着。そしてAIR CHINAカウンターでチェックイン。しかし、我が荷物は依然として行方不明との返事。日本に帰国したら、羽田空港で「荷物紛失証明書:PIR」を書いて提出しろ!!と責任転嫁、逃げの 返事ばかり!!私の英会話力では、これ以上の交渉は難しいと判断し、羽田空港で日本語でしっかりと!!を決断したのであった。そして、この日のCA(中国国際航空)の代替便は予定時刻の16:00に離陸し、北京空港へと向かう。飛行機の座席モニターに表示されたフライトマップ(機内航路画面)を追う。大きく旋回。北海に向かって。大雅茅斯(Great Yarmouth)上空から北海へ。グレート・ヤーマスはイギリスのノーフォーク州にある海岸沿いの町で、ノリッジの東20マイル(30km)に位置。 グレート・ヤーマスは1760年から海辺のリゾート地として栄えて来た と。オランダ北部(Netherlands, northern region)の地図で、機体は「デン・ヘルダー(Den Helder)」の北東方向から「リーワルデン(Leeuwarden)」方向に向けて飛行中。見えた浅瀬と島々は、ワッデン海(Wadden Sea)と西フリースラント諸島(West Frisian Islands)。飛行機の進行方向右側(南側)には:・IJsselmeer(アイセル湖):オランダ最大の淡水湖。 堤防「アフスライトダイク(Afsluitdijk)」でワッデン海と分離。・Afsluitdijk(アフスライトダイク):全長約32kmの堤防。左上のDen Helder付近から東に 細長く伸びる線として見えることも。これらは人工干拓によって生まれたオランダの象徴的な景観なのであった。全長約32kmの堤防のAfsluitdijk(アフスライトダイク)をネットから。ドイツ・Flensburg(フレンスブルク)上空。離陸後1時間15分。デンマーク・Roskilde(ロスキレ)上空。そして最初の機内食。スウェーデン・Malmo(マルメー)上空。エストニア・ESTONIA上空。フィンランド・FINLAND上空へ。2回目の食事。そして爆睡。離陸後9時間、北京首都国際空港(BCIA)に向けて。モンゴル・Ulaanbaatar(ウランバートル)上空。この日の飛行ルートをネットから。北京首都国際空港(BCIA)に向けて降下開始。この日の機体はB777-300ER。飛行時間・約9時間50分で北京首都国際空港(BCIA)に到着したのであった。機窓から北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport / 北京首都国际机场)の第3ターミナル(Terminal 3)を。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.08
コメント(0)
-
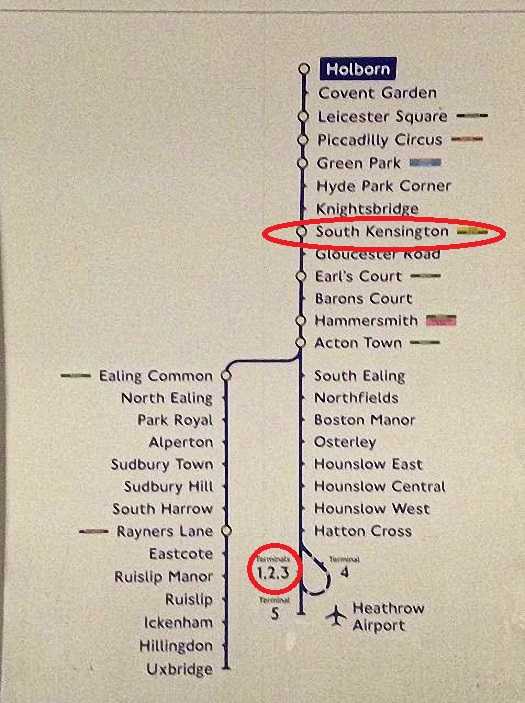
アイルランド・ロンドンへの旅(その132): ロンドン散策記・日本への帰路-1
Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館まで戻り待ち合わせ場所の博物館のクロークに到着。時間は15:45。トランクを受け取り、地下鉄サウスケンジントン駅から Piccadilly Line・ピカデリー線にてヒースロー空港に向かう。地下鉄サウスケンジントン駅は博物館、美術館の多いロンドンでも指折りの博物館であるロンドン自然史博物館とヴィクトリア&アルバート博物館の最寄り駅。Piccadilly Lineの路線図。SOUTH KENSINGTON駅。Piccadilly Lineの車両が到着し乗車。そしてHeathrow Airport・ロンドン・ヒースロー空港駅に到着し、第2ターミナルを目指す。ヒースロー空港ターミナル2の正式名称はThe Queen’s Terminal(ザ クィーンズターミナル)。ヒースロー空港と女王エリザベス2世の長年の結びつきに敬意を表し、「The Queen’s Terminal」と称されることになったと。2014年6月にオープン。スターアライアンス加盟の航空会社が中心となるターミナルである。T2以外のターミナルでは、スターアライアンスの航空会社は乗り入れしていない。ロンドン・ヒースロー空港(London Heathrow Airport)第2ターミナル「The Queen’s Terminal」の館内マップ(出発エリア)。主に出発客向けの構造を示しており、上階(Departures upper level)と下階(Departures lower level)の2層に分かれていた。全体構成ターミナル名称:Terminal 2 – The Queen’s Terminalゲート範囲:B28–B49(サテライト棟「T2B」へは地下通路“via subway”経由)フロア構造:Upper Level(上階):チェックイン、手荷物預け、セキュリティゲートLower Level(下階):免税店・飲食・搭乗ゲートへのアクセス✈️上階(Departures upper level) ・中央部に「You are here」の表示(現在地)があり、その先が Security(保安検査場)。 ・左側(West Wing): ・チェックインゾーンA〜D(スターアライアンス系航空会社) ・店舗例:WHSmith, Caffè Nero など ・右側(East Wing): ・チェックインゾーンE〜H ・店舗例:Pret A Manger, Travelex, Heathrow Family Lounge ・セキュリティ通過後、下階へエスカレーター・階段で降り、出国エリア(免税・搭乗口)へ 移動。🛍 下階(Departures lower level) ・出国後の主要なショッピング・飲食エリア。紫色ゾーンが店舗区域を示す。 ・ Shopping(買い物)、 Food and Drink(飲食)、Services(サービス)🚇 移動ルート ・Gates B28–B49 へは「T2B via subway」からアクセス(自動歩道付きの地下通路で 約5〜10分)。 ・保安検査後、案内標識に従って進むと「Flight Connections」や「T2B」分岐があった。別便で帰国する旅友Yさんと別れる。出発案内板。チェックイン、 Security(保安検査場)を通過し出国手続きも完了。帰路の利用便は中国国際航空・北京でトランジットし羽田空港へ。搭乗ゲートはB31。案内板に従って進む。ヒースローはハブ空港としての機能も大きいため、「ロンドン体験が空港内だけになる人も結構多い」と。そんな背景もあり、T2にはロンドンの街中にある、ありとあらゆるジャンルの店が揃っていた。建物内にはショップ33軒とレストランなどの飲食施設17軒が入っているとネットから。有名百貨店・ハロッズ。有名百貨店ハロッズはもとより、日本人に人気の英国雑貨キャスキッドソンが出店。有名ブランドのブティックも軒を連ねており、バーバリーやポールスミスなど英国を代表するブランドはもちろん、さらにT2には、百貨店ジョン・ルイスが空港内初出店。ロンドンをモチーフとしたグッズの他、アイルランドのデザイナー、オーラ・カイリの各種アイテムを揃えたコーナーもあった。スマイソン(Smythson)は、ロンドンに拠点を置く英国の文房具、革小物、日記帳、ファッション製品の製造販売店。百貨店John Lewis・ジョン・ルイス。NATURALLY FIRST FOOD店・LEON(レオン)。搭乗口B31はターミナル2Bの最奥の搭乗口◯。B31,B32の案内板。そして15分ほど歩いて搭乗口B31に漸く到着。多くの乗客の姿が。ほとんどが中国人のようであった。予約便は20:25発、中国国際航空(CA)・CA938+TP8328 の共同運航便。TP8328はTAPポルトガル航空(英語: TAP Air Portugal)。搭乗開始時間を待っていると、放送で機体に「技術的トラブル」があり修理中の為、出発が遅延すると。待つこと2時間以上、ひたすら搭乗開始の放送を待ったが・・・・・。これが登乗予定便であったが。途中、技術員が懸命に対応中であるのでもう少し待って欲しいとの放送が繰り返された。しかし、その後突然に「フライトは機体故障によりキャンセル」との放送。 乗客の中国人が騒ぎ出して放送の聞き取りが困難に。席を離れて係員の近くまで行くと、代替便の時間は現在調整中であるが、明日の午後の便となるであろうと。引き返して、入国手続を再度行い、手荷物受取所( Baggage reclaim)でトランクを回収して欲しい。ホテル、移動バスは現在調整中であると何とか理解した。Arrivals、Baggage Reclaimの案内に従い引き返す。入国手続きを行い手荷物受取所( Baggage reclaim)に到着。漸く、荷物が出てきたが私のトランクがななかな出てこない!!そして私他3名?のトランクが「ロストバゲージ」!!よって、他人が持って行ってしまったのではなさそうと理解はしたが。ネットから。預け荷物の半券(控え)&航空券を持ち係員のところへ。別の係員の所に連れて行かれ、カタコトの英語を駆使して事情を説明。・My baggage didn't come out!!・I am looking for my suitcase, but it is missing!! This is my claim tag!!・Could you find out where is my baggage?・My baggage nummber is “○○・・・○◯” .・How long will it take to receive my baggage?!・???????????????????・ロストバゲージ対応のカウンターへは連れていかれずに。・トランクの形状、色、材質、荷物の中身等を説明。 トランクはスマホで写真を撮っていたので写真で説明できたのであった。・トランクに入れてはいけないものは入っていないことを強調。 整髪用スプレーが入っているが、小型・100cc以下であり問題ないはずと。★明日までに探しておくので、明日の再チェックイン時に再度同じ説明をしろと!!★ホテルへの移動バス内で乗客が待っているから、早く戻って乗れと!! やむなく、この日は諦めて、別の係員にバスへと連れて行かれたのであった。ビジネスクラスの乗客が乗り込んだバスに連れて行かれる。・宿泊ホテルはバスで10分ほどの Hilton London Heathrow Airport Terminal 5・ヒルトン ロンドン ヒースロー エアポート ターミナル 5 と。・四つ星★★★★のホテル。・代替便は明日16:00発 と。・ホテルから空港への送迎バスは12:00に出発すると。・夜食が欲しい方は、部屋へのルームサービスが無料で利用可能と。・その他にもいろいろと言っていたが、聴くのも疲れて・・・???そしてホテルに到着。6階にあったツインの部屋に転がり込む。夜食も取らずに、シャワーだけ浴び、着替えも出来ず、疲れもあって爆睡したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.07
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクAlbert Memorial・アルバート記念碑を後にして、Kensington Gardens(ケンジントン・ガーデンズ)を歩き、Kensington Palace(ケンジントン宮殿)方向に進む。写真の並木は、ハート形の鋸歯のある葉・こんもりした樹形から見てリンデン(ボダイジュ/lime tree)、とくに セイヨウボダイジュ(Tilia × europaea, common lime)の並木であっただろう。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)が右手斜め前方に現れた。ケンジントン・ガーデンズの中にある赤レンガの宮殿で、17〜18世紀にかけてクリストファー・レンらが増改築しました。かつてウィリアム3世&メアリー2世、ジョージ1世・2世、そしてヴィクトリア女王が幼少期を過ごした王宮として知られ、現在は公開エリア(ステート・アパートメントや企画展)と王室関係者の居住・事務スペースが同居しています。宮殿の外壁の一部が保守工事用の足場とシートで覆われ、手前にはケンジントン・ガーデンズの草地(ワイルドフラワー・メドウ)が広がっていた。見えている翼は宮殿本体の外観の一部で、見学者が入る公開エリアはこの建物群の反対側の入口側から入場するのだと。この案内板は ケンジントン宮殿(Kensington Palace) のウェルカムボード。「WELCOME TOKENSINGTON PALACEPublic palace Family homeWelcome to Kensington Palace, hometo Britain's young royals for 300 yearsDISCOVER300 years of Royal HistoryTake a glimpse into the private lives of the Stuartmonarchs, the glittering court of the Georgiansand Queen Victoria's extraordinary childhood.EXPLOREThe palace is open all yearTravel back in time and walk in the footsteps ofkings, queens and courtiers discovering historywhere it happened.ENJOYThe taste of luxuryRelax with coffee in our café or afternoon teain beautiful surroundings and treat yourselfto an exclusive souvenir from our gift shop.Entry ticket not requiredSummer: 10:00 to 18:00Winter: 10:00 to 16:00(last admission 1 hour before closing)Please check website for detailsHISTORIC ROYAL PALACESWe are a team of people who love and look after six of themost wonderful palacesin the world. We create space for spirits to stir and be stirred. We want everyone tofeel welcome and accepted. We tell stories about the monarchs you know, and thelives you don’t. We let people explore and we set minds racing.We are a charity, andyour support gives the palaces a future, for everyone.To find outmore visithrp.org.ukSPACE TO STIR AND BE STIRREDTOWER OF LONDON . HAMPTON COURT PALACE . BANQUETING HOUSEKENSINGTON PALACE . KEW PALACE . HILLSBOROUGH CASTLE AND GARDENS」【ケンジントン宮殿へようこそ公共の宮殿、家族の住まいケンジントン宮殿へようこそ。ここは、イギリスの若い王族たちが300年間暮らしてきた住まいです。DISCOVER(発見)300年の王室の歴史スチュアート王朝の私生活、ジョージ王朝のきらびやかな宮廷、そしてヴィクトリア女王の特別な幼少期を垣間見ることができます。EXPLORE(探検)宮殿は一年中公開されています時をさかのぼり、王や女王、廷臣たちが歩んだ足跡をたどりながら、歴史が実際に起こった場所を探索できます。ENJOY(楽しむ)贅沢なひとときをカフェでコーヒーやアフタヌーンティーを楽しみ、美しい環境の中でくつろぎながら、ギフトショップで限定のお土産をどうぞ。※入場券は不要です。開館時間夏季:10:00~18:00冬季:10:00~16:00(最終入場は閉館の1時間前まで)詳細は公式サイトをご確認ください。HISTORIC ROYAL PALACESヒストリック・ロイヤル・パレス私たちは、世界で最も素晴らしい宮殿のうち六つを愛し、守り、世話をしているチームです。心が動き、また心を揺り動かされる場をつくります。誰もが歓迎され、受け入れられていると感じられることを願っています。皆さんが知っている君主たちの物語も、あまり知られていない人生の物語も語ります。人々が自由に探検できるようにし、想像力をかき立てます。私たちは慈善団体であり、皆さまのご支援が、すべての人のために宮殿の未来を支えます。詳しくは hrp.org.uk へ。心を揺さぶり、また揺さぶられる場所ロンドン塔 ・ ハンプトン・コート宮殿 ・ バンケット・ハウケンジントン宮殿 ・ キュー宮殿 ・ ヒルズボロー城と庭園・ロンドン塔】 ケンジントン宮殿(Kensington Palace) の正面中央に見えるのは ウィリアム3世(William III, 1650–1702) の銅像。・ウィリアム3世とその妃メアリー2世が、もともと「ノッティンガム伯の邸宅」であったこの建物を購入し、1690年代に「ケンジントン宮殿」として拡張しました。・彼らの時代以降、ケンジントン宮殿はイギリス王室の重要な居所となり、ヴィクトリア女王もここで生まれ育ちました。背景の赤レンガ造の建物は、クリストファー・レン卿の設計による増築部分で、シンプルながら王室の威厳を感じさせる「オランダ風クラシック様式」の外観。ウィリアム3世(William III, 1650–1702)・オレンジ公としても知られる。・1689年にイングランド王位に即位し、妻メアリー2世(Mary II)と共同統治。・いわゆる「名誉革命(Glorious Revolution, 1688)」を経て王位につき、立憲君主制の 基盤を築いた。・彼の治世は、イングランド銀行の設立や議会政治の強化など、近代的国家体制の形成に 大きな影響を与えた。」 台座の銘文(碑文)「WILLIAM IIIOF ORANGEKING OF GREAT BRITAINAND IRELAND 1689–1702PRESENTED BY WILLIAM IIGERMAN EMPEROR ANDKING OF PRUSSIA TOKING EDWARD VII FORTHE BRITISH NATION1907」【ウィリアム3世オレンジ公グレートブリテンおよびアイルランド王(1689–1702)この像は、ドイツ皇帝・プロイセン王ウィルヘルム2世より、英国王エドワード7世と英国民へ贈られたもの1907年】 ウィリアム3世(William III, 1650–1702) の像にズームして。🔹 特徴からの識別ポイント・17世紀後半のオランダ風の服装(膝丈の上衣・マント・大きな帽子)。・威厳のある立ち姿で、片手は腰に当て、もう片手には杖(司令杖のようなもの)を 持っています。・像は1713年に彫刻家 ジョン・マイケル・リスブラック(John Michael Rysbrack) に よって制作されました。🔹 歴史的背景・ウィリアム3世とメアリー2世が、ロンドン郊外の館を購入・拡張して現在の ケンジントン宮殿 としました。・宮殿を王室の居所にした功績から、彼を称えるためにこの像が設置されています。・像は1713年に鋳造され、オランダから輸入された青銅を用いています。1.衣装 ・17世紀末の軍装・王侯風の衣装をまとっています。 ・肩章・胸の飾り帯・長い外套は王としての威厳を示しています。2.帽子 ・羽飾り付きの広つば帽を被っています。 ・これはオランダ出身の彼の個性を強調するとともに、当時の騎士的・軍人的イメージを象徴。3.姿勢 ・堂々とした直立姿勢で、片手を腰に置き、もう片手に杖(司令杖=権威の象徴)を 持っています。 ・これは彼の軍事的指導力と王権の象徴です。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)正面の金飾りの鉄製ゲート(ゴールド・ゲート)越しに宮殿を望む景観。🔹ゲートについて・名称:一般的に「Kensington Palace Gates」または「Golden Gates (ゴールデン・ゲート)」と呼ばれる装飾門。・特徴: ・黒い鉄製の門に、金箔で飾られたスクロール文様や王冠、植物装飾が施されている。 ・バロック様式のきらびやかな意匠は、17世紀末から18世紀にかけての王宮装飾の典型。 ・特に中央の門には王室紋章や百合・蔦をモチーフとした金装飾が集中しています。🔹背後の建物 ・奥に見えるのはケンジントン宮殿の南面(South Front)。 ・赤レンガ造りのシンプルなファサードは、ウィリアム3世とメアリー2世の時代に 建てられたオランダ風クラシック様式。 ・宮殿の正面中央には、先ほどご覧いただいたウィリアム3世像が配置されており、 このゲート越しに真正面に見えるよう設計されています。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)正面玄関(西正面 / West Front)。1.中央の玄関ポーチ ・半円形の車寄せ(ポルチコ)付き玄関があり、ここが公式な来客用の出入口。 ・現在も王族の住居として使われるため、儀式や特別な訪問の際に利用されます。2.建物の構造 ・赤レンガ造りのジョージアン様式。 ・中央に三角破風のペディメントがあり、そこに大きな窓と装飾が配置。 ・左手は工事用の足場で覆われています(改修中)。3.前庭(Forecourt Garden) ・整然と刈り込まれた円錐形の植木が並び、バロック的なシンメトリーを形成。 ・正面の芝生広場は「到着の場(Arrival Court)」としての性格を持ちます。ヴィクトリア女王像(Statue of Queen Victoria)。近づいて。1.即位時の若きヴィクトリア女王 ・ケンジントン宮殿で生まれ、1837年に女王となったことを記念して制作。 ・若く清楚な姿で描かれており、他の「晩年の厳格なヴィクトリア像」とは対照的。2.服装と装飾 ・王冠を戴き、左手に宝珠(sovereign’s orb)、右手に笏(sceptre)を持ち、 戴冠式の姿を表現。 ・儀礼的な荘厳さの中にも、娘であるルイーズによる柔和で親しみやすい造形が感じられます。3.設置の意義 ・ヴィクトリア女王が生まれ育ったケンジントン宮殿と、その治世を記念するために設置。 ・宮殿を訪れる人々に「ここがヴィクトリア女王の生誕地である」という象徴を示しています。横から。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)の西正面入口を見る。 ・中央部分:大きな三角破風(ペディメント)を持つ正面玄関。 ・玄関上部:大きなアーチ窓があり、その下に3つの長窓が並んでいます。 ・玄関入口:緑色のガラス製キャノピー(庇)が取り付けられ、来訪者を迎える入口と なっています。 ・両翼部分:赤レンガ造りで、長い窓列が左右に伸びています。ケンジントン宮殿(Kensington Palace)のメインエントランス正面(西側正門から入った中央玄関部) をクローズアップ。1.ペディメント(三角破風) ・典型的なジョージアン建築の要素。 ・宮殿の正面性を強調し、格式を示しています。2.大窓(中央のアーチ窓) ・上部に半円形のアーチを持つ大窓が設けられています。 ・小さなコラム(柱)で装飾され、威厳を持たせています。3.赤レンガと白い石の組み合わせ ・イギリス王宮建築の伝統的手法で、ジョージアン様式らしい端正さを見せます。 ・窓枠の上には白い石の「キーストーン」風装飾が施されています。4.玄関のキャノピー(庇) ・緑色の鉄とガラス製の大きな庇が設置され、訪問者を迎える構造になっています。 ・19世紀ヴィクトリア時代に加えられたもので、機能性と優雅さを兼ね備えています。「WELCOME TO KENSINGTON PALACEPublic palace Family homeWelcome to Kensington Palace, home to Britain’s youngroyals for 300 yearsDISCOVER300 years of Royal HistoryTake a glimpse into theprivate lives of the Stuart monarchs, the glinting court of theGeorgians and QueenVictoria’s extraordinary childhood.EXPLOREThe palace is open all yearTravel backin time, and walk in the footsteps of kings, queens and courtiers discovering history where it happened.ENJOYThe taste of luxuryRelax with coffee in our café or afternoontea in beautiful surroundings and treatyourself to an exclusive souvenir from our giftshop. Entry ticket not required.Summer:10.00 to 18.00 (last entry 17.00)Winter:10.00 to 16.00 (last entry 15.00)」 HISTORIC ROYAL PALACESWe are a team of people who love and look after six of the most wonderful palaces in the world. We create space for spirits to stir and be stirred. We want everyone tofeel welcome and accepted. We tell stories about the monarchs you know, and thelives you don’t. We let people explore and we set minds racing.We are a charity, and your support gives the palaces a future, for everyone.To find out more visit hrp.org.ukSPACE TO STIR AND BE STIRREDTOWER OF LONDON · HAMPTON COURT PALACE · BANQUETING HOUSEKENSINGTON PALACE · KEW PALACE · HILLSBOROUGH CASTLE AND GARDENS」 【ケンジントン宮殿へようこそ公共の宮殿、そして王族の家ケンジントン宮殿へようこそ。ここは300年間、英国の若い王族たちの住まいでした。発見する(DISCOVER)王室の歴史300年ステュアート朝の君主たちの私生活、ジョージアン時代の華やかな宮廷、そしてヴィクトリア女王の特別な子供時代を垣間見ることができます。探検する(EXPLORE)宮殿は一年中公開されています時をさかのぼり、王や女王、廷臣たちの足跡をたどりながら、歴史が実際に起こった場所を歩きましょう。楽しむ(ENJOY)贅沢なひとときをカフェでコーヒーやアフタヌーンティーを楽しみ、美しい環境の中でくつろぎませんか。ギフトショップで特別なお土産を探すのもおすすめです。入場券は不要です。開館時間 ・夏期:10時~18時(最終入場17時) ・冬期:10時~16時(最終入場15時)】ヒストリック・ロイヤル・パレス私たちは、世界で最も素晴らしい宮殿のうち六つを愛し、守り、世話をしているチームです。心が動き、また心を揺り動かされる場をつくります。誰もが歓迎され、受け入れられていると感じられることを願っています。皆さんが知っている君主たちの物語も、あまり知られていない人生の物語も語ります。人々が自由に探検できるようにし、想像力をかき立てます。私たちは慈善団体であり、皆さまのご支援が、すべての人のために宮殿の未来を支えます。詳しくは へ。心を揺さぶり、また揺さぶられる場所ロンドン塔 ・ ハンプトン・コート宮殿 ・ バンケット・ハウスケンジントン宮殿 ・キュー宮殿 ・ ヒルズボロー城と庭園ロンドンのハイド・パーク内にある「サーペンタイン(The Serpentine)」湖。場所:ハイド・パークとケンジントン・ガーデンズの間に位置し、18世紀に造られた人工湖。由来:「サーペンタイン」という名は、湖が蛇のように曲がりくねった形をしていることに 由来します特徴: ・湖の一部は「ザ・ロング・ウォーター」と呼ばれ、ケンジントン宮殿の近くまで 続いています。 ・夏には湖でスイミングやボート遊びができ、白鳥やカモなどの水鳥も多く生息。 ・湖畔にはカフェやギャラリー(Serpentine Gallery)があり、散歩や休憩の名所と なっています。サーペンタイン湖について ・場所:ハイド・パークとケンジントン・ガーデンズの間に位置し、18世紀に造られた人工湖。 ・由来:「サーペンタイン」という名は、湖が蛇のように曲がりくねった形をしていることに 由来します。・特徴: ・湖の一部は「ザ・ロング・ウォーター」と呼ばれ、ケンジントン宮殿の近くまで 続いています。 ・夏には湖でスイミングやボート遊びができ、白鳥やカモなどの水鳥も多く生息。 ・湖畔にはカフェやギャラリー(Serpentine Gallery)があり、散歩や休憩の名所と なっています。・前景:湖畔の遊歩道が写り、すぐ近くの水面にカモ類(水鳥)が泳いでいます。・湖面:赤いブイが浮かんでおり、湖の区切りやボート利用エリアの目印になっています。・背景:木々が生い茂る緑豊かな湖畔。都会の中心とは思えない自然環境です。・遠景:木々の間から高層ビルが見え、ハイドパークが大都会ロンドンの真ん中にあることを 実感させます。サーペンタイン湖の特徴・人工湖:1730年にジョージ2世の妃・キャロライン王妃の命で造成。・形状:蛇(サーペント)のように曲がりくねっているため「サーペンタイン」と命名。・利用: ・夏はボート遊びや水泳(指定区域のみ)。 ・水鳥(白鳥、カモ、カナダグースなど)の観察も人気。・周辺施設: ・湖の東側には「サーペンタイン・ギャラリー」や「サーペンタイン・ブリッジ」があり、 文化と自然が融合。湖面に大きな白鳥(Mute Swan:コブハクチョウ)が悠々と泳いでいる姿が。1. 白い大きな鳥(2羽)・コブハクチョウ(Mute Swan) ・白く大きな体、オレンジ色のくちばし、黒いコブ(基部)が特徴。 ・イギリスを代表する水鳥で、ハイドパークやケンジントン・ガーデンズでは特に多く 見られます。2. 灰褐色のガチョウ(3羽)・マガンに似たカリガネではなく、グレイラググース(Greylag Goose:ハイイロガン) ・体は灰褐色で、白い尾羽。 ・くちばしがオレンジ色で太めケンジントン・ガーデンズ(Kensington Gardens) 内から、視線の正面奥に見えるのはヴィクトリア女王の白い大理石像(Queen Victoria Statue)。引き返すと、リスの姿が。イギリスの都市公園でよく見られるハイイロリス(Grey Squirrel, Sciurus carolinensis)??逃げない!!ハイイロリスは北アメリカ原産で、19世紀にイギリスへ持ち込まれた外来種 と。Alan Rickman Memorial Bench(アラン・リックマン記念ベンチ)。・Alan Rickman (1946–2016) 英国の俳優で、『ハリー・ポッター』シリーズのセブルス・スネイプ役や、 『ダイ・ハード』のハンス・ グルーバー役などで世界的に有名です。 舞台俳優としても長いキャリアを持ち、英国演劇界に多大な貢献をしました。・記念ベンチの設置 ロンドンの ケンジントン・ガーデンズ 内に設置されたベンチは、リックマンを偲ぶファンや 友人、関係者による寄贈の一つです。 多くのロンドン公園のベンチと同様に、故人を記念して献辞(dedication plaque)が 取り付けられており、訪れる人が座って彼の思い出に浸ることができます。 このベンチに付けられている献辞プレートの文言は、次のようなものと報じられています。 「“It would be wonderful to think that the futureis unknown and sort of surprising” ~ Alan Rickman」 【「未来が未知で、ちょっと驚きに満ちていると考えられたら素敵だろう」 ~ アラン・リックマン】と。・場所の意味 ケンジントン・ガーデンズはロンドン中心部の美しい庭園で、アラン・リックマンが生前に 好んで訪れたとされる場所のひとつ。 静かな環境と緑の中で、彼の温かい人柄や芸術的な遺産を思い起こす場所になっています。再び、ロンドンのケンジントン・ガーデンズにある「アルバート記念碑(Albert Memorial)」、そして奥に見える円形の大きな建物は「ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)」 。「THE MAGIC OF KENSINGTON GARDENSThis area dates back to the 1700s, when nearby Kensington Palace was occupied byKing George II (1683–1760) and his wife Queen Caroline (1683–1737).The Queen’s role transformed a rural countryside landscape into a formal pleasure garden. Under the influence of Queen Caroline, Kensington Gardens were separated from Hyde Park and developed into the royal gardens you see today. They became afashionable place for Londoners to stroll, take the air, and display the latest fashions.KENSINGTON GARDENS IN LITERATUREThe beauty of Kensington Gardens has inspired generations of authors and poets.J. M. BarrieBarrie’s famous play Peter Pan (1904) and novel Peter Pan in Kensington Gardens(1906) were both inspired by Kensington Gardens. He often walked here and notedthe sense of magic in the air.Thomas TickellPoet and satirist Tickell (1685–1740) wrote Kensington Gardens (1722), a long poem describing the gardens as a place of mythology and imagination.Matthew ArnoldPoet and cultural critic Arnold (1822–1888) used Kensington Gardens as a backdropfor his reflective poetry, connecting nature and human experience.Virginia WoolfWoolf (1882–1941), one of the foremost modernist writers, drew inspiration from the atmosphere of Kensington Gardens, which features in her essays and novels.She observed how the gardens represented both the continuity of tradition andthe fleeting moments of modern life.DELVE A LITTLE DEEPERScan the QR code for audio trails and more information on the history of Kensington Gardens.A REVOLVING SUMMERHOUSEA man-made hill known as The Mount once stood close to here. On top of this hill stood a revolving summerhouse.」 【ケンジントン・ガーデンズの魔法この地域の歴史は1700年代にさかのぼります。当時、近くのケンジントン宮殿には、国王ジョージ2世(1683〜1760)とその妃キャロライン王妃(1683〜1737)が住んでいました。女王の影響:新しい風景の創造キャロライン王妃は園芸に造詣が深く、彼女の依頼で造園家チャールズ・ブリッジマンがケンジントン・ガーデンズを新しい形式の公園に作り替えました。整然とした並木道や広大な芝生を、自然な植栽と組み合わせたこの設計は、のちに「ケイパビリティ・ブラウン」として知られる造園家に影響を与えました。文学に描かれたケンジントン・ガーデンズケンジントン・ガーデンズの美しさは、数多くの作家や詩人たちに創作のインスピレーションを与えてきました。J.M. バリー『ピーター・パン』の生みの親であるJ.M.バリーは、1902年の小説『小さな白い鳥』の中で初めてピーター・パンというキャラクターを登場させました。この作品ではケンジントン・ガーデンズが生き生きと描かれており、現在ロング・ウォーターのほとりにはピーター・パン像が立っています。トマス・ティッケルティッケルの詩『ケンジントン・ガーデンズ』(1722)は、公園に住む妖精や精霊たちの物語を語っています。この詩は、18世紀初頭の人々が神話と風景を融合させることに魅了されていた様子を反映しています。マシュー・アーノルド詩人であり評論家のマシュー・アーノルド(1822〜1888)は、瞑想的な詩『ケンジントン・ガーデンズにて』(1852)で、この庭園を歩く自身の心情を描きました。ヴァージニア・ウルフ小説家ヴァージニア・ウルフ(1882〜1941)はこの近くに住み、しばしば庭園を散歩しました。代表作『ダロウェイ夫人』(1925)では、登場人物たちがロンドンの生活を描く一場面としてケンジントン・ガーデンズを通ります。さらに深く知るQRコードをスキャンすると、ケンジントン・ガーデンズの歴史についてさらに詳しく知ることができます。回転するサマーハウスこの近くにはかつて「ザ・マウント」と呼ばれる人工の丘があり、その頂上には回転式のサマーハウス(夏の休憩小屋)が建っていました。】Kenjinton Roadからロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)を再び見る。ロンドンを代表するコンサートホールで、1871年に開館し、クラシック音楽からロックコンサート、プロムス(BBC Proms)など多彩な公演が行われる会場です。上部にはギリシャ風の装飾帯(フリーズ)がぐるりと巡り、人類の芸術と科学の偉業を描いていた。左手に見える赤レンガの建物群は、アルバートホール周辺にある19世紀の住宅や施設で、ロンドン特有の赤レンガ建築が並んでいます。このエリアは サウス・ケンジントン(South Kensington) に属し、周囲にはロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックや、アルバート・メモリアル、さらに少し歩けばヴィクトリア&アルバート博物館や自然史博物館もあるのであった。こちらは、エキシビジョン ロード沿いにあった末日聖徒イエス・キリスト教会(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 通称モルモン教会) の礼拝堂、」塔の上に伸びる金色の尖塔(スパイア)が特徴的で、モダニズム建築の要素を持つデザインとなっています。正面入口上部には英語で"THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS"と表記されています。この建物は ロンドン・ハイドパーク支部(London Hyde Park Chapel) として知られ、住所は 64-68 Exhibition Road, South Kensington にあります。ヴィクトリア&アルバート博物館や自然史博物館の近くであった。・両腕を広げて人々を迎え入れる姿のキリスト像。・胸には磔刑の傷跡が刻まれており、復活した救い主としての姿を示しています。・世界中の末日聖徒イエス・キリスト教会の礼拝堂や来客センターに複製像が設置されており、 このロンドンのハイドパーク礼拝堂のガラスケース内の像もその一つです。サイエンス・ミュージアム(Science Museum)。サイエンス・ミュージアム概要・設立:1857年・場所:Exhibition Road, South Kensington・展示内容:科学技術の歴史と発展をテーマに、産業革命の蒸気機関から宇宙探査、医療、通信、 エネルギー、コンピュータ技術など幅広い分野を網羅。・特徴: ・ワットの蒸気機関(18世紀) ・初期の飛行機や自動車 ・アポロ月着陸に関連する宇宙探査展示 ・子ども向けのインタラクティブ展示や体験型展示が多い・付属施設:IMAXシアター(大画面で科学映画を上映)自然史博物館(Natural History Museum, South Kensington)内部展示。・地球ホール(Earth Hall / Earth Galleries) の入口付近。・写真奥に見える大きな球体(地球をイメージしたモニュメント)は、このホールのシンボル。 エスカレーターでその内部を通って上階に上がる仕組みになっていた。・手前に見えるのは ステゴサウルス(Stegosaurus) の化石骨格。・自然史博物館が所蔵するステゴサウルスの標本は、世界でも保存状態が非常に良いとされ、 2014年に公開が始まったもの。・背中の大きな骨板や尾のスパイク(「サグマイザー」と呼ばれる)が特徴的。ステゴサウルス(Stegosaurus stenops) の化石標本に近づいて。・種:Stegosaurus stenops・時代:ジュラ紀後期(約 1億5,500万年前)・産地:アメリカ・コロラド州モリソン層・全長:約5.6メートル・保存状態: ・世界で最も保存状態が良いステゴサウルス標本の一つ。 ・約90%がオリジナルの骨で構成されており、背中の板や尾のスパイク (通称「サグマイザー」)もほぼ完全。 ・2014年に博物館に導入されて以来、人気の展示物となっている。「touch a piece of the moon todaySPACECould Life Exist Beyond Earth?Members and patrons go freeVisit today in the Green Zone」 【今日は月のかけらに触れてみよう宇宙地球以外に生命は存在するのか?メンバーと後援者は無料本日、グリーンゾーンで見学できます】自然史博物館(Natural History Museum, South Kensington) 内部、「地球ホール(Earth Hall / Earth Galleries)」にある象徴的なエスカレーター・奥に見える巨大な球体は「地球」をモチーフにしたモニュメントで、割れた岩盤のような デザインになっていた。・訪問者は、地球の内部(マントルや核)に突入していくような感覚で、このエスカレーターを 使って上階に移動する。・壁面には星座の図や天体のイラストが描かれており、宇宙と地球科学をつなぐ演出が されていた。・赤い照明が加わることで「地球内部のマグマ」や「宇宙的スケールの迫力」を体感できる 空間デザインに。「VOLCANOES AND EARTHQUAKES(火山と地震)」ギャラリー の入口サイン。ギャラリー概要・テーマ:地球のダイナミックな活動 ― 火山噴火と地震展示内容:・世界各地の火山噴火の映像や火山岩・火山灰の標本・地震を引き起こすプレートテクトニクスの仕組み・日本の地震多発地域に関する解説・有名な地震災害(例:1995年阪神・淡路大震災、2011年東日本大震災など)を紹介する資料「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーに展示されている 世界地図パネル。展示の内容・世界地図上に赤い点が示されており、これは 火山活動や地震の多発地域 を表しています。・特に以下の地域が強調されています: ・環太平洋火山帯(Ring of Fire) ・日本、フィリピン、インドネシア、ニュージーランド、太平洋沿岸のアメリカ大陸 (アラスカ~南米アンデス山脈まで) ・大西洋中央海嶺 アイスランドを含む大西洋の中央を縦断する海底山脈帯 ・地中海地域 イタリア(エトナ山、ベスビオ山)、ギリシャなど ・ヒマラヤ山脈周辺 インドとユーラシア大陸のプレート衝突帯「VOLCANOESWhen a volcano erupts things change. For many, an eruption brings fear, death and destruction, altering the course of lives and civilisations. For others it can inspire art, religion and science. In some parts of the world eruptions are a constant threat, but here in Britain we haven’t had one for 55 million years.Not all volcanoes are the same. By studying them around the world scientists know that some have violent and explosive eruptions, while others have gently flowing ones.Both offer a glimpse of the dramatic forces deep beneath our feet and both shape thechanging face of our planet.」【火山火山が噴火すると、あらゆるものが変わります。多くの場合、噴火は恐怖・死・破壊をもたらし、人々や文明の運命を変えてきました。一方で、それは芸術・宗教・科学をも刺激することもあります。世界のいくつかの地域では噴火が常に脅威であり続けていますが、ここイギリスでは5,500万年間噴火は起きていません。すべての火山が同じというわけではありません。世界中の火山を研究することで、科学者たちは、あるものは激しく爆発的に噴火する一方、別のものは穏やかに溶岩を流すことを知っています。どちらも私たちの足下深くにある劇的な力を垣間見せ、そして地球の姿を変化させ続けています。】 「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー内の展示の一部写真中央にある縦長のパネルは、火山噴火の映像インスタレーション を再現したもの。炎や火山弾、マグマの赤い輝きがスクリーンに投影され、火口から吹き上がるマグマや火山灰の迫力を体感できる仕掛けになっていた。訪問者はこの映像を通じて、火山噴火の「爆発的なエネルギー」と「視覚的なインパクト」を直感的に感じられるようになっていたのであった。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーの解説パネルで、ハワイ火山に由来する溶岩と噴火産物 を紹介「Pāhoehoe lavaPāhoehoe lava (pronounced pa-hoy-hoy) flows down the volcano in shiny sheetscalled toes.As the surface begins to cool and dry the lava underneath continuesto flow,causing thefolded appearance.Pele’s hairThis beautiful material is called Pele’s hair, after the Hawaiian goddess of volcanoes.The golden strands form when tiny pieces of lava are thrown in the air and spun by the wind into volcanic glass.‘A‘ā lava‘A‘ā (pronounced ah-ah) is a Hawaiian word that volcanologists use to describe thiskind of lava flow.‘A‘ā forms as the surface of a lava flow cools and hardens while the inner partcontinues to flow, breaking it into sharp and jagged clinkers.」【パホイホイ溶岩(Pāhoehoe lava)「パホイホイ溶岩」(発音:パホイホイ)は、光沢のあるシート状の流れとして火山を下ります。表面が冷えて乾くと、内部の溶岩が流れ続けるため、波打ったような折り重なった模様が生じます。ペレの髪(Pele’s hair)「ペレの髪」と呼ばれる美しい物質で、ハワイの火山の女神ペレにちなんで名付けられています。黄金色の繊維は、微小な溶岩片が空中に投げ出され、風に吹かれて引き延ばされ、火山ガラスとして形成されたものです。アア溶岩(‘A‘ā lava)「アア溶岩」(発音:アア)は、火山学者が特定の溶岩流を表すのに使うハワイ語です。流れの表面が冷えて固まり始める一方、内部はまだ流れ続けるため、表面が割れて鋭くゴツゴツした岩塊(クリンカー)になります。】 「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーにある、マグマチャンバーと火山噴火の仕組み を解説する展示(上部パネル)How and when a volcano will erupt depends on if there is any rising magma, what type of magma it is and the amount of gas it contains.The pressure and temperature in a magma chamber are immense. Magma can reach more than 1,000°C.(下部パネル)Geologists propose the magma chamber beneath a volcano could look like this.More magma chambers are deeper beneath the volcano, but they don’t connect up.Eruptions may happen nearer the surface and magma must have a route through tothe volcano’s opening to escape.【(上部パネル)火山がどのように、いつ噴火するかは、上昇するマグマがあるかどうか、その種類、そして含まれるガスの量に左右されます。マグマ溜まり(マグマチャンバー)の圧力と温度は非常に高く、マグマは1,000℃以上に達することがあります。(下部パネル)地質学者たちは、火山の下のマグマチャンバーはこのような構造をしていると考えています。多くのマグマチャンバーは火山の下のより深い場所にあり、互いに必ずしもつながっているわけではありません。噴火は地表近くで起こることもあり、マグマが火口へと到達するための通路が必要です。】「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーの展示の一部で、プレートテクトニクスと地球のダイナミズム を説明するコーナー。「Dynamic EarthThe world’s continents and ocean floors are covered with features marking where tectonic processes have shaped the surface.On the sea floor, underwater vents pass 50 times more magma into closerto thesurface. Mid-ocean ridges are plate boundaries where ocean crust is being made and deep-sea trenches mark where plates are destroyed as they are forced backdown into the mantle.On land, huge rifts scar the landscapes where continents are splitting while mountainsrise up where plates collide.Volcanic eruptions and earthquakes occur around the world as the planet reshapes itself.」 【ダイナミック・アース(動き続ける地球)世界の大陸や海底には、プレート運動が地表を形作ってきた痕跡が刻まれています。海底では、海底火山の噴出口から地表近くへ50倍ものマグマが送り込まれます。中央海嶺は海洋地殻が生み出されるプレート境界であり、深海の海溝はプレートがマントルへ沈み込み、破壊される場所を示しています。陸上では、大地溝帯のように大陸が裂ける場所に巨大な裂け目が走り、プレートが衝突するところでは山脈が隆起します。火山噴火や地震は、地球が自らの姿を作り変える過程で世界中に起こるのです。】「EARTHQUAKESEarthquakes can happen without warning, causing death and destruction ona massive scale. When they strike we feel a sudden, violent shaking of the ground; but they are caused by slowly moving plates on Earth’s surface. As these plates move,pressure builds up until it finally gives way.Throughout history, earthquakes have shattered communities across the world. But we’re slowly learning how to cope with them. By understanding how and wherethey happen, science can help us prepare for future earthquakes, and limit the damage they cause.」 【地震地震は予告なしに発生し、大規模な死と破壊をもたらすことがあります。発生時には地面が突然激しく揺れるのを感じますが、これは地球表面でゆっくりと動くプレートによって引き起こされます。プレートが動くにつれて圧力が蓄積し、最終的に限界を超えた時に放出されるのです。歴史を通じて、地震は世界中の共同体を破壊してきました。しかし私たちは少しずつ、その影響に対処する方法を学んできています。地震がどのように、そしてどこで起こるのかを理解することで、科学は将来の地震に備え、その被害を軽減する助けとなるのです。】自然史博物館(Natural History Museum) の「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリーにある 地震シミュレーター展示(日本のスーパーを再現したコーナー)天井から吊られている赤いバナーには、1995年1月17日の 阪神・淡路大震災 に関する新聞風の見出しが書かれていた。・左のバナー:"Quake delivers devastating wake-up call January 17 1995"(地震が壊滅的な目覚めの警鐘を鳴らす 1995年1月17日)右のバナー:"'Safe' area of Japan ill-prepared January 17 1995"(「安全」と思われていた日本の地域、備え不十分1995年1月17日)下には日本のスーパーを模した陳列棚(食品や生活用品のパッケージ)が並んでおり、中央には「BIG QUAKE PHASE ONE」と書かれたモニターが設置されていた。地震シミュレーター展示の入口。「KOBE SUPERMARKET神戸スーパーマーケット」 地震シミュレーター「Kobe Supermarket(神戸スーパーマーケット)」 の内部。・日本のスーパーマーケットの店内 を忠実に再現。・棚にはインスタントラーメン、醤油、調味料、乾物、缶詰など、日本の商品パッケージが 並んでいます。・壁には昭和〜平成初期を思わせる広告ポスター(焼酎や日用品の宣伝)が貼られ、 リアルな生活空間を演出。・壁の一部が「ひび割れた」状態で再現され、地震の被害を視覚的に示しています。・買い物カートが複数置かれ、来館者は実際にその場に立って体験します。・阪神・淡路大震災(1995年1月17日, M7.3) をモデルにした地震体験。・シミュレーション中、部屋全体が大きく揺れ、棚の商品が落ちそうになるような臨場感を演出。・音響(地鳴りや崩れる音)、照明効果も加わり、来館者は実際に被災したかのような体感を。・壁の右側は「ひび割れ」風に造形されており、地震の被害を演出しています。・天井からは、赤いパネルに「震災に関する新聞見出し」が掲げられています (例:「Quake delivers devastating wake-up call」など)。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー の展示の一部で、テーマは 「地震後の二次的な危険(Dangers After the Quake)」。・大見出し「DANGERS AFTER THE QUAKE(地震後の危険)」「THERE MIGHT BE WORSE TO COME(さらに悪いことが起きるかもしれない)」・映像スクリーン 5つの映像が映し出されており、地震やその後の被害の実例を紹介。 ・津波の映像 ・地すべりや土砂崩れ ・液状化の様子 ・都市の瓦礫と破壊された街並み・解説パネル 左側には立体的な地形模型図があり、地震後の地盤変化や地形のリスクについて説明。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー にある展示の一部で、東日本大震災(2011年3月11日)の記録映像を紹介。5つの映像1.Initial earthquake 14:46(最初の地震発生 14:46)・店舗内(衣料品売り場)で揺れが始まる映像。・買い物中の人々が混乱する様子を示している。2.Tsunami approach 14:46–15:00(津波接近 14:46~15:00)・沿岸部のカメラが捉えた津波の接近。・海面が盛り上がり、黒い波が内陸に迫る様子が見える。3.Tsunami impact 14:46–15:30(津波襲来 14:46~15:30)・自動車や建物が飲み込まれていく映像。・港湾や道路が津波に覆われる瞬間を記録。4.Destruction of Minamisanriku 15:20(南三陸町の破壊 15:20)・宮城県南三陸町の全景。・津波により住宅や公共施設が壊滅的な被害を受けている。5.Aftermath and recovery(被害と復興)・津波後の街並み。・瓦礫に覆われた町と、復興への長い道のりを示唆。2011年 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) を取り上げたマルチスクリーン映像の別バージョン。5つの場面1.Initial earthquake 14:46(最初の地震発生 14:46)・シャンデリアが激しく揺れている映像。・建物内での地震の恐怖を表現。2.Tsunami approach 14:46–15:00(津波接近 14:46~15:00)・船のデッキから海を捉えた映像。・海面が不自然に盛り上がり、津波が迫る様子を示している。3.Tsunami impact 14:46–15:30(津波襲来 14:46~15:30)・人々が津波から必死に逃れる映像。・水流と共に濁流に巻き込まれる恐怖を伝えるシーン。4.Destruction of Minamisanriku 15:20(南三陸町の破壊 15:20)・津波により壊滅した宮城県南三陸町の様子。・町全体が瓦礫と化し、建物が消え去っている。5.Aftermath and recovery(被害と復興)・泥にまみれたアナログ時計が写されている。「Volcanoes and Earthquakes(火山と地震)」ギャラリー 内の展示の一部。テーマは 「地震の仕組みと体験」。1.大見出し・「MAKE YOUR OWN EARTHQUAKE(自分で地震をつくろう)」・「HOW DO EARTHQUAKES HAPPEN?(地震はどのように起こるのか?)」・サブタイトル:「LIKE CLICKING YOUR FINGERS(指を鳴らすように)」 → 地震の発生を「パチンと指を鳴らすような瞬間的な力の解放」として説明。2.展示写真・イラスト・倒壊した建物の写真 → 地震の破壊力を強調。・地図や地層断面のイラスト → プレート境界の動きを示す解説資料。3.体験型展示・「MAKE YOUR OWN EARTHQUAKE」とあることから、来館者が自分でスイッチを押したり 装置を操作して、小さな「人工地震」を起こし、その波形や揺れの影響を学ぶインタラクティブ 展示になっていた。自然史博物館(Natural History Museum, South Kensington) にある「地球のホール(Earth Hall)」の象徴的な展示空間を再び。・中央に巨大な 「地球の球体」 が配置されている。 → 鉱石や岩石のような断片で覆われており、地球の外殻(地殻プレートや大地の象徴)を表現。・赤い光で照らされた エスカレーター が球体の中へと突き抜けている。 → 来館者は「地球の内部に入っていく」ような体験を味わえる。・両側の壁には 星座図や惑星名(Neptuneなど) が描かれており、地球科学と宇宙のつながりを 示唆している。地球科学ゾーン(Earth Hall / Volcanoes and Earthquakes gallery) にある導入部の壁面パネル。「The Earth is a restless planet.Powerful forces shape and reshape its surface in continuous cycles of change.This exhibition explores the processes of surface change, and investigates howwe detect these actions in the rocks.」 【地球は落ち着くことのない惑星です。強大な力がその表面を形作り、そして絶え間ない変化のサイクルの中で再び作り変えていきます。この展示では、地表が変化するプロセスを探り、その痕跡を岩石の中からどのように見出すのかを解き明かします。】鳥類展示(Bird Gallery) の一角。・中央に非常に大きな ダチョウ(Ostrich, Struthio camelus)の剥製標本。 → 世界最大の鳥であり、飛べない鳥(Ratite, 平胸類)の代表。・周囲の壁面には、小型から中型の鳥類の剥製が数多く展示されており、分類・生態に応じて 並べられている。・右下にはシラサギ(Heron/Egret)と思われる水鳥。・中央部の壁には、鳥を描いた肖像画が額縁に収められて展示されており、 「鳥の文化史的な位置づけ」も補足している。・それぞれの標本には小さなラベルが付いており、種名や学名が示されている。ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London) の正面ホール、通称 Hintze Hall(ヒントツェ・ホール) を。・天井から吊るされている巨大な骨格標本 → これは シロナガスクジラ(Blue Whale, Balaenoptera musculus)の骨格 で、 愛称は 「Hope(ホープ)」。 2017年にホール中央に展示され、博物館の新しい象徴的存在となっています。 以前はここに恐竜の「ディプロドクス(Dippy)」のレプリカ骨格がありましたが、 現在はHopeに置き換えられました。・建築様式 → 赤レンガとテラコッタによる壮大なロマネスク様式の建物。 → 建築家アルフレッド・ウォーターハウス設計、1881年開館。 → 内装には動植物や地質をモチーフとした装飾が随所に施されています。・中央の大階段 → 2階へと続き、かつてはダーウィン像が中央に置かれていました (現在は上階のバルコニー部分に移設)。マンモスの骨格標本。・長い湾曲した牙(tusks) → この大きく前方へ湾曲する牙が、マンモス類やマストドン類の最大の特徴です。・頭骨の大きな空洞 → 象に近い仲間で、鼻(長い鼻=象鼻)の付け根部分の空洞が目立ちます。・体格 → 現代のアジアゾウやアフリカゾウよりも骨格がややがっしりしています。・マンモス(Mammuthus primigenius)は氷河時代(更新世)に生きていた象の仲間で、 ヨーロッパ、アジア、北アメリカなど広い範囲に分布しました。・厳しい寒冷地に適応しており、長い毛に覆われ、脂肪層を持っていました。・氷河時代の終わり(約1万年前)に大部分が絶滅しましたが、一部はシベリアの孤島で 約4000年前まで生き残っていたことが分かっています。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.06
コメント(1)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その130): ロンドン散策記・ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall-2~アルバート記念碑(Albert Memorial)-1
Royal Albert Hall・ロイヤル・アルバート・ホールの西側を歩き北側へ。西側入口(West Porch) を斜め正面に見る。・中央左のアーチ → 「ROYAL ALBERT HALL」と金文字が掲げられた西玄関。 現在、一般来館者が最も多く利用する主要出入口。・バナー旗(Welcome) → 「Welcome」の文字と共に、イベント案内や来館者向けのカラフルなバナーが並んでいた。 青、赤、紫など色分けされており、施設案内や各種プログラムの告知を兼ねていた。・背景のフリーズ(装飾帯) → 建物上部を一周するテラコッタ製の装飾帯には、「芸術と科学の勝利(The Triumph of Arts and Sciences)」と題された連続レリーフが見えた。 人類の活動(音楽・学問・産業・農業など)を寓意的に表したもの。この西側ポーチは、 南の「ダイヤモンド・ジュビリー・ステップス」、 北の「アルバート記念碑と対面する正面ポーチ」と並ぶ、ホールの三大出入口のひとつ。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)の入口「DOOR 6」に近づいて。・上部: 「ROYAL ALBERT HALL」の金文字サイン。・中央: 「DOOR 6」と大きく表示。観客の入退場に使われる個別ゲートのひとつ。・下部の案内表示: ・「Go to Door 12 for:」とあり、以下の施設がDOOR 12に集約されていると説明。 ・Box Office(チケット売り場) ・Gift Shop(ギフトショップ) ・Tours Meeting Point(館内ツアー集合場所) ・Food and Drink(飲食施設)さらに中央にはホールを円形に見立てた図(扇形の配置図)があり、入口番号が時計のように配置されていることがわかったのであった。そして正面に見えたのがアルバート記念碑(Albert Memorial)。・建立:1872年完成・建立者:ヴィクトリア女王(1819–1901)が、1861年に逝去した夫 アルバート公 (Prince Albert, 1819–1861) を偲んで建てさせた記念碑。・建築様式:ゴシック・リヴァイヴァル様式(ジョージ・ギルバート・スコット設計)。 高さ約54m。・中心像:金色に輝くアルバート公の坐像。 手には「1851年ロンドン万国博覧会」の目録を持ち、 彼の文化・科学振興の功績を示しているのだ と。アルバート記念碑(Albert Memorial)をズームして。場所は ケンジントン・ガーデンズ(Kensington Gardens) の南側、ロイヤル・アルバート・ホールの真正面に位置。・中央下部(金色の像) ヴィクトリア女王の夫であった アルバート公(Prince Albert) の座像。 右手には 「大博覧会カタログ」 を持ち、これは1851年の「ロンドン万国博覧会」に 深く関わったアルバート公の業績を象徴。・中央上部(屋根の三角破風部分) 三角破風内にはモザイク画(Mosaic)があり、寓意的人物像(Arts, Sciences, Learning など 文化的主題)を描いていた。・尖塔・彫刻装飾 ゴシック様式の華麗な尖塔群と、黄金で装飾された聖人像や寓意像が立ち並び、アルバートの 栄誉を永遠に記念する構造になっていた。・全体構造 白大理石の基壇 → 金のアルバート像 → ゴシック様式キャノピー(天蓋) → 上方に高く 伸びる尖塔、とピラミッド状に積み上げられていた。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) の北口正面入口。ロイヤル・アルバート・ホールは 1867–1871年 に建設され、当初から アルバート記念碑(Albert Memorial) と真正面に向かい合う配置で設計された。したがって、ここ北側(ケンジントン・ゴア側、Albert Memorial を望む側) が建築的に「正面 façade」とされているのだ と。よって、こちらがロイヤル・アルバート・ホールの“顔”ともいえる正面入口。掲げられていた旗は「Progress Pride Flag(プログレス・プライド・フラッグ)」(ネットから)。・1978年にギルバート・ベイカーがデザインした「レインボーフラッグ」は、性的少数者 (LGBT)の誇りと多様性を象徴しました。・しかし時代が進むにつれ、特に有色人種コミュニティやトランスジェンダーの人々の経験 が十分に反映されていない、という声が高まりました。・そこで2018年、ダニエル・クアサー(Daniel Quasar) が新しいデザインとして 「プログレス・プライド・フラッグ」を提案しました。・虹色の6色:従来のレインボーフラッグ(多様性の象徴)。 赤:生命 橙:癒し 黄:太陽・光 緑:自然 青:平和・調和 紫:精神・三角形の追加部分:左側に黒・茶・白・水色・ピンクが加わっています。 ・黒と茶:人種的多様性(有色人種コミュニティ)への包摂。 ・水色・ピンク・白:トランスジェンダーの旗を組み込み。 ・黄色地に紫の円:最近のバージョンでは「インターセックス(Intersex)」を象徴する 要素が加えられています。この白い大理石像は、プリンス・アルバート公(Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha, 1819–1861)― ヴィクトリア女王の夫 ― 。ロイヤル・アルバート・ホールは彼の名を冠して建設され、彼の文化・教育振興の理念を記念するために数々の像や装飾が配置されているのだ と。・衣装:軍装風の制服にマントを羽織り、威厳ある立ち姿。・勲章のチェーン:胸にはガーター勲章(Order of the Garter)などの首飾りが掛けられていた。・ポーズ:左手は腰に置き、右手は少し握りかけて下げる ― 思索的で品位ある姿勢。・様式:ネオクラシカルな大理石彫刻で、ホールのファサード(外壁)に設置されている ニッチ(壁龕)の中に収められていた。ヴィクトリア女王(Queen Victoria, 1819–1901)像。ロイヤル・アルバート・ホールは、彼女の夫 アルバート公 を記念して建てられましたので、正面に並んでヴィクトリア女王とアルバート(夫)とが配置されていた。・王冠:イギリス女王としての権威を示す王冠を戴いていた。・装束:重厚なローブ(マント)と長衣をまとい、威厳ある姿。・持ち物:右手には笏(sceptre、王笏)を持ち、君主としての権力を象徴。・表情と姿勢:荘厳かつ厳格な立ち姿で、アルバート像と対を成していた。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)北正面(メイン・エントランス) の中央アーチ部分を振り返って。・上部に「ROYAL ALBERT HALL」と金色で刻まれたサインが。・扉の両脇には、現在のコンサートやイベント(この日は Holly Johnson)のポスターが 貼られていた。・黒地に「RAH」のモノグラム(王冠付き)が中央にあり、ホールの公式ロゴデザインである。・ガラス越しに、正面向かいにある アルバート記念碑(Albert Memorial) の黄金像が反射で 見えていた。ロイヤル・アルバート・ホール東側(Kensington Gore沿い)に建つ赤レンガの壮麗な建物群。これは Albert Hall Mansions(アルバート・ホール・マンションズ)と呼ばれる高級アパートメント群であったようだ。・1870年代に建設されたビクトリア様式の集合住宅。・赤レンガと石材の装飾を組み合わせた外観で、ロイヤル・アルバート・ホールと景観的に 調和するよう設計されたのであろう。ケンジントン・ガーデンズ(Kensington Gardens)とハイド・パーク(Hyde Park)一帯の案内地図。ケンジントン・ガーデンズ(Kensington Gardens)南部をフォーカスして。下中央右に「YOU ARE HERE」と。この後に訪ねたKensington Gardens 内の主要施設。・Round Pond(ラウンド・ポンド)(左上):ケンジントン宮殿の前に広がる池。・The Long Water(ロング・ウォーター)(右上):ハイド・パークへ続く湖。・Physical Energy Statue(フィジカル・エナジー像)(上部中央):ジョージ・ワッツ作の 大きな騎馬像。 ・Queen Caroline’s Temple(カロライン王妃の神殿)(右中):18世紀の小さな庭園建築。アルバート記念碑(Albert Memorial) を南側(ロイヤル・アルバート・ホール方向)から。・中央の金色の像 アルバート公(Prince Albert, ヴィクトリア女王の夫)を表す座像で、1876年に完成。 彼は「グレート・エキシビション(1851年万国博覧会)」の主催者としても有名。・ゴシック・リバイバル様式の天蓋(カノピー) 金箔で装飾された高さ約54mの塔が、公の像を覆っていた。 建築家ジョージ・ギルバート・スコット卿(Sir George Gilbert Scott)の設計によるもの。・基壇の白い大理石彫刻群 4隅に配置された群像は「四大陸」を寓意していると。・さらに基壇の周囲 彫刻家たちによる「芸術・科学・産業・農業」を象徴する彫刻群が飾られており、 19世紀英国の進歩と繁栄を象徴 と。アルバート記念碑(Albert Memorial)前に設置されている解説板 。全体を「Take a closer look…」と題して、モニュメントの構成要素を分かりやすく説明。アルバート記念碑(Albert Memorial)の解説板の中央部分に近づいて。1.CROSS(十字架) 塔の最上部のクロス。2.ANGELS(天使像) 塔の上部に配置された黄金の天使像群。3.THE FOUR ARTS(四芸術) 装飾モザイク(絵画・彫刻・建築・音楽)。4.CELEBRATION(祝典モザイク) 尖塔破風に描かれた寓意モザイク。5.PRINCE ALBERT(金色の座像) 中央に座るアルバート公。6.CANOPY(天蓋の装飾) 四方を覆う天蓋と彫刻装飾。7.INDUSTRIAL ARTS(産業芸術の彫刻群) 基壇部分に表現されている産業革命の象徴。8.THE CONTINENTS(四大陸群像) 台座四隅の巨大な白い大理石群像(Africa/Asia/Europe/America)。左側の1~5の案内。「1.CROSSThis cross, influenced by those flourish of medieval architecture, reflects the Christianinspiration that lay behind Albert’s principles. Sitting abovethe apex of a spire,it symbolises hope.」 【1. 十字架(CROSS)この十字架は、中世建築の装飾的な様式の影響を受けており、アルバート公の理念の背後にあったキリスト教的霊感を反映している。尖塔の頂点に掲げられ、希望を象徴する。】十字架(CROSS)の下の2段の黄金の天使像。Sculpted by John Birnie Philip(ジョン・バーニー・フィリップ作)上部・4体の黄金の天使像(Angels) ・記念碑の尖塔(spire)の最上段に位置し、四方を向く形で配置。 ・各天使は両腕を大きく広げ、上方や外側を指し示す姿勢。 ・これは 「神への祈り」や「霊的な守護」 を象徴し、アルバート記念碑全体を天上界へと 結びつける役割を持ちます。 ・ゴシック様式の塔尖部をさらに荘厳にするために、まばゆい金箔仕上げが施されている。下部・4体の黄金の立像(Virtues, or Angels with Instruments) ・4体の立像が四方に配置され、それぞれが外側に向けて腕を広げています。 これは「迎え入れる」「祝福を広げる」ようなジェスチャーで、象徴的には 慈愛・受容・調和 を示すものと考えられます。 ・中央には翼を大きく広げた 黄金の大天使像(背後に配置)がおり、天上界への導きと 記念碑の精神的守護を表しています。「2. VIRTUESThe four figures on the corners represent the moral virtues of prudence, temperance, fortitude and justice. They also embody the Christian virtues of faith,hope, charity and humility.」 【2. 美徳(VIRTUES)四隅に立つ4体の像は、「分別・節制・剛毅・正義」という道徳的美徳を表す。また、キリスト教的美徳である「信仰・希望・慈愛・謙遜」をも体現している。】「不屈の精神、慈愛、そして慎重さ」像をズームして。 「3. THE FOUR ARTSThese triangular mosaics represent the arts of poetry, painting,architecture and sculpture. Each is supported by two smaller mosaics underneath, huggingthepointed arch.」【3. 四芸術(THE FOUR ARTS)三角形のモザイクは、「詩・絵画・建築・彫刻」という芸術を表現している。各モザイクの下には、さらに2枚の小さなモザイクがあり、尖塔アーチを抱き込むように配置されている。】「ポエシス」をズームして。 ネットから。「4. DEDICATIONAbove each pointed arch is a dedicatory message that underlines the memorial:“To the memory of Albert, Prince Consort. As a tribute of their gratitude.For a life devoted to the public good. Queen Victoria and her people.”」 【4. 献辞(DEDICATION)各尖塔アーチの上には、記念碑を裏付ける献辞が刻まれている:「アルバート公コンソートの記憶に。感謝のしるしとして。公共善に尽くした生涯に。ヴィクトリア女王とその国民より。」】下の写真には「QUEEN VICTRIA AND HER PEOPLE(ヴィクトリア女王とその国民より)」。 「5. SCIENCESThese eight sculptures, in two tiers, represent the sciences.Four at the bottom symbolise chemistry, astronomy and geology. The top four represent rhetoric, medicine,philosophy and physiology.」 【5. 科学(SCIENCES)8体の彫像が2層に配置され、科学を表している。上段の4体は「幾何学・天文学・化学・地質学」を象徴し、下段の4体は「生理学・レトリック(修辞学)・医療・哲学」を象徴している。】ネットから、「2.天文学」 を。右側の6~10の案内。「6. CANOPYThe ornate underside of this canopy features the coats of arms belonging to both Queen Victoria and Prince Albert. The Latin motto, ‘Prince Albert - of Faithful andTrue’ They sit amongst a sea of golden stars.」 【6. 天蓋(Canopy)この天蓋の豪華な内側には、ヴィクトリア女王とアルバート公の紋章が描かれています。ラテン語のモットー「忠実かつ誠実なるアルバート公」が記され、黄金の星々に囲まれています。】ネットから。「7. PRINCE ALBERTAlbert is shown in an informal rather than regal pose. In his hand he holds a copy of the catalogue of the Great Exhibition of 1851, which he helped to organise.」【7. アルバート公(Prince Albert)アルバート公は威厳ある王侯の姿ではなく、親しみやすい姿で表されています。手には彼が組織に尽力した「1851年大博覧会のカタログ」を持っています。】ネットから。 「8.INDUSTRIAL ARTSThis series of four sculptures represents agriculture, manufacture, commerce andengineering. They link Prince Albert to industrialised Britain.」 【8. 産業芸術(Industrial Arts)4体の彫刻群は農業・製造業・商業・工学を表しています。これらはアルバート公と産業化された英国とを結び付けています。】アルバート記念碑(Albert Memorial) の四隅にある「産業芸術(Industrial Arts)」群像のひとつ、「Agriculture(農業)」を表す彫刻。1.中央の女性像(擬人化された農業の女神) ・優雅な立ち姿で、前にいる男性へと手を差し伸べています。 ・その姿は、農業が人々に「恵み」を授ける様子を象徴しています。2.左の男性像(農夫・技術者) ・膝をつき、手には「鎌」や「測定器具」のようなものを持っています。 ・背後に農耕用の道具(犂や車輪)が配置され、労働や農業技術を象徴しています。3.右下の女性像(豊穣の象徴) ・座った姿で、膝には「収穫した麦の束」を抱えています。 ・これは「豊穣」「収穫の恵み」を示し、農業の成果を表現しています。4.象徴物 ・麦の束(豊穣) ・農具(生産) ・計測器(科学的農法の導入)「産業芸術(Industrial Arts)」群像のひとつ、「Manufactures(製造業)」を表す彫刻。1.中央の女性像(擬人化された製造業の女神) ・威厳ある立ち姿で、片手には「織機の杼(シャトル)」を持っている。 ・彼女は「製造・生産」の知恵を与える存在。2.右の男性像(力強い労働者) ・半裸の筋肉質な姿で立ち、大きな槌や金属加工の道具を持っている。 ・これは「工人・鍛冶職人」を象徴し、製造業に不可欠な肉体労働を表現。3.左の人物(作業に従事する女性) ・下を向き、織物あるいは道具を扱っている姿。 ・繊維産業や衣類生産を象徴。4.下部の人物(若い男性) ・車輪や歯車に触れている姿。 ・これは産業革命を象徴する「機械化」「工業生産」の意味を持つ。Industrial Arts(産業芸術) 群像のひとつ、「Commerce(商業)」を表す彫刻。1.中央の女性像(商業の女神) ・威厳ある立ち姿で群像を統括。 ・彼女は「商業そのものの擬人化」であり、交易を監督する立場を示しています。2.左の若者(ヨーロッパ風の商人) ・手に巻物(契約書や商業文書)を持ち、知識と取引を象徴。 ・若さは「未来の発展」を表します。3.右の人物(東洋風の商人、ターバン姿) ・国際交易・海外貿易を示す異国風の姿。 ・19世紀の大英帝国のグローバル貿易を象徴しています。4.前景の人物(地図や商品を広げる姿) ・足元に帳簿や商品を並べ、実際の交易を支える役割。 ・実務的な商業活動を表現しています。Industrial Arts(産業芸術) 群像のひとつ、「Engineering(工学)」を表す彫刻。1.中央の女性像(工学の女神) ・群像全体を統括する中心的存在。 ・片腕を差し伸べる姿で「導き」と「指導」を象徴しており、科学知識と技術革新を人々に 授ける役割を担う。 ・工学そのものの擬人化であり、産業革命期の技術進歩を象徴。2.左手前の男性(工兵/建設労働者) ・座った姿で作業具(石材や測量器具)を扱っている。 ・土木や建築技術を担う存在として、工学の基盤を象徴。3.中央手前の青年(技術者) ・前傾姿勢で器具を操作するように描かれている。 ・実際に機械や道具を扱う「現場の技師」を表現。 ・新しい技術の創造的応用を象徴している。4.右手前の若者(発明家/工学徒) ・両手に機械部品(歯車や道具)を持ち、工学の進歩に直接関わる姿。 ・若さは「未来の技術発展」「新世代の革新」を示す。「9. FRIEZEThe ‘Parnassus frieze’ depicts 169 figures of greats like Shakespeare and Beethoven. The sculpture is based on Raphael’s fresco, designed by artists Henry Hugh andVenetian company.」 【9. フリーズ(Frieze)「パルナッソスのフリーズ」にはシェイクスピアやベートーヴェンといった169人の偉人たちが描かれています。これはラファエロのフレスコ画に基づき、芸術家ヘンリー・ヒューズやヴェネツィアの工房が手掛けました。】ネットから。フリーズ(Frieze・水平の帯状の部分)をズームして。アルバート記念碑(Albert Memorial, ケンジントン・ガーデンズ)にある彫刻装飾の一部「フリーズ・オブ・フェイマス・メン(Frieze of Parnassus)」 。このレリーフは、芸術や学問の偉人たちを浮彫で表したもので、記念碑の基壇部をぐるりと取り囲むように配置されていた。全部で 169人の文化人・芸術家・科学者など が登場する と。アップロードされた部分には、以下のような著名な人物が含まれていると(彫刻下部の銘文から判読可能)Leonardo da Vinci(レオナルド・ダ・ヴィンチ)Raphael(ラファエロ)Michelangelo(ミケランジェロ)Donatello(ドナテッロ)Titian(ティツィアーノ)これらはルネサンス期の巨匠たちで、特に中央に座っている人物は Homer(ホメロス) が象徴的に置かれ、彼を囲むように芸術家・思想家たちが並んでいる と。アルバート記念碑の全体案内。写真中央に描かれている人物は、アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)。「THE ALBERT MEMORIALThe premature death of Prince Albert (1819–1861) was a shock that sparked a nation’s grief. Queen Victoria (1819–1901), consumed with sadness, commissioned this magnificent memorial to her beloved husband.」 【アルバート記念碑(The Albert Memorial)アルバート公(1819–1861)の早すぎる死は国中に衝撃を与え、人々を深い悲しみに包みました。ヴィクトリア女王(1819–1901)は悲嘆に暮れる中、最愛の夫のためにこの壮大な記念碑を建てることを命じました。】「WHO WAS PRINCE ALBERT?Albert of Saxe-Coburg and Gotha married his cousin Queen Victoria in 1840.A talented and cultured man, he supported the arts, science, trade and industry.He was instrumental in organising the Great Exhibition of 1851, and promoted socialissues such as housing and education.」【アルバート公とは誰か?ザクセン=コーブルク=ゴータ家出身のアルバート公は、1840年に従姉のヴィクトリア女王と結婚しました。教養豊かで有能な人物であり、芸術・科学・貿易・産業を支援しました。彼は1851年の「ロンドン万国博覧会(大博覧会)」の開催に尽力し、住宅や教育などの社会問題の推進にも関与しました。】「WHY HERE?The memorial was designed by George Gilbert Scott and unveiled in 1872. The location was chosen for its line of sight across to the Royal Albert Hall, creating anenduring visual connection between the two monuments.」【なぜここに?記念碑はジョージ・ギルバート・スコットによって設計され、1872年に公開されました。この場所は、向かいに建てられたロイヤル・アルバート・ホールと視覚的なつながりを持たせるために選ばれました。】「RAISING THE MEMORIALThe memorial cost £120,000, paid for by public subscription. Hundreds of leadingsculptors and craftsmen of the day were involved. The statue of Albert, designed byJohn Henry Foley, was gilded in 1875.」【記念碑建立建設費用は12万ポンド、すべて国民からの寄付によって賄われました。当時の多数の著名な彫刻家や職人が制作に携わりました。アルバート像はジョン・ヘンリー・フォーリーによってデザインされ、1875年に金箔が施されました。】 A LATE ARRIVALThe statue of Albert was not ready in time for the unveiling of the memorial in 1872. It was finally installed three years later, in 1875.「Quotation (bottom right, attributed to Queen Victoria):“His life is a work, a vast, and earnest, and end as a work. More than his great intellect, his affection is difficult to describe. His perfection, perception in every way — in beauty,in everything.”」 【引用(ヴィクトリア女王)「彼の人生は一つの作品そのものでした。壮大で真剣で、そして完成された作品でした。偉大な知性以上に、彼の愛情を言葉で表すことは難しいのです。彼はあらゆる意味で完璧で、審美眼を備え、美しさにおいてもすべてにおいても。】再びアルバート記念碑(Albert Memorial)をズームして。アルバート公(Prince Albert)。移動して横から。後方から。アルバート記念碑の四隅の大陸群像(The Continents) のひとつで、モチーフから判断すると南東・「Asia(アジア)」像。・象(Elephant):アジアを象徴する動物として必ず登場。・人物群: ・玉座に座る女性像 → アジア大陸の擬人化(女神像のような表現)。 ・周囲に東洋風の衣装や頭飾りをまとった男性像(ターバン姿、東アジア風、ペルシャ風など)。・象の装飾:頭部の布飾りが「異国・東洋」を象徴。移動して南東・「Asia(アジア)」像を。四隅の大陸群像(The Continents) のひとつで、こちらは南西・「Europe(ヨーロッパ)」像を表す。・牛(Bull):ギリシア神話の「エウロペとゼウス(牡牛に変身したゼウス)」に由来し、 ヨーロッパの象徴。・中央の女性像(冠と笏を持つ女王風):ヨーロッパの擬人化(権威と統治の象徴)。・周囲の女性像たち:文化・学問・芸術を象徴する従者的存在。移動して南西・「Europe(ヨーロッパ)」像を。四隅の大陸群像(The Continents) のひとつで、こちらは北西・「AMERICA(アメリカ)」像を表す。・主な動物:バイソン(アメリカバイソン) アメリカ合衆国の国獣に指定されており、合衆国では毎年11月の第一土曜日は バイソンの日に制定されている。・人物特徴:羽根飾りを持つ人物、開拓民・先住民を想起させる像・象徴するもの:新世界アメリカ、自然とフロンティア精神・識別ポイント:バイソンの大きな頭部、アメリカ先住民的衣装の人物像。移動して北西・「AMERICA(アメリカ)」像を。四隅の大陸群像(The Continents) のひとつで、こちらは北東・「AFRICA(アフリカ)」像を表す。・主な動物:スフィンクスやラクダ・人物特徴:アフリカ的要素(頭飾りや裸身)、 ナイルを象徴するモチーフも見られる・象徴するもの:アフリカ大陸、特にエジプト文明・識別ポイント:ラクダまたはスフィンクス像が必ず含まれる。移動して北東・「AFRICA(アフリカ)」像を。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.05
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その129): ロンドン散策記・自然史博物館(Natural History Museum)-2~ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)へ
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクロンドン自然史博物館(Natural History Museum)の地下入口の様子。・レンガ造りのアーチ ヴィクトリア時代の雰囲気を残すアーチ構造で、外壁の煉瓦と鉄格子の組み合わせが印象的。・装飾デザイン 上部に円形モチーフ(赤色の円と十字)があり、その周囲を扇状に広がる白い格子が 取り囲んでいた。 両脇の柱上には青色の装飾(ランタン風のデザイン)が施されていた。・入口の機能 これは地上正面玄関(サウス・ケンジントン側)ではなく、地下通路 (サウス・ケンジントン駅からの連絡通路を通じたエントランス) の出口・入口の一つ。 ロンドン地下鉄サウス・ケンジントン駅から博物館へは、専用の地下歩行トンネルで直接 アクセスでき、その出口がこの写真の場所。ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London)を南西側(クロムウェル通りの反対側)から見上げた景観。・手前の庭園 熱帯的な雰囲気のシダ植物(Tree Ferns)が植えられており、これは 「ジュラシック・ガーデン(Jurassic Garden)」の一部。 恐竜が生きた時代の植物景観を再現しており、博物館の外構デザインとして 来館者に人気のエリア。・建物の構造 正面双塔ではなく、建物の南西の角(ウエスト・タワー側)を斜めに見たアングル。 右奥には現代的なガラス張りの建物(ダーウィン・センター)が部分的に映り込んでいる。・建築様式 ロマネスク・リヴァイヴァル様式で、アーチ型の窓やテラコッタ装飾が規則正しく並んで いるのが特徴。 遠方にもう一つの塔(イースト・タワー)が奥に見えた。引き返して、ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A) の中庭広場を見る。・左手前 ガラスと白い曲線的な屋根が印象的な現代的建築は、エントランス・パビリオン (Exhibition Road Entrance)。 2017年に完成した新しい出入口で、建築家アマンダ・レヴェット(AL_A)が設計しました。・正面の建物 V&Aのクラシックな本館建築。赤レンガと白石のコンビネーションが特徴。 「GALLERIES」の垂れ幕が見え、ここから館内の展示エリアへ入館できた。・広場の空間 世界初の「完全な磁器タイル張りの公共広場」とされ、床一面に白い磁器タイルが敷き詰め られていた。 夏季はここでイベントや野外展示も開催され、カフェスペース(赤い椅子とテーブル) も人気と。ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum, V&A)の中庭「サックラー・コートヤード(The Sackler Courtyard)」からV&Aの本館の一部を見る。・赤レンガと白い石材のクラシカルな建物 これはV&Aの本館の一部で、19世紀ヴィクトリア朝の建築様式を典型的に示している。 レンガ造と石材装飾の組み合わせは、当時のロンドンの公共建築でよく使われた。・手前の現代的な構造物 ガラスと鋭い庇をもつ建物は、2017年完成の Exhibition Road Entrance Pavilion (展示路エントランス・パビリオン)。 設計は建築家アマンダ・レヴェット(AL_A)。 中はカフェ兼入口ホールになっており、外のカフェテラス(赤い椅子とテーブル)が広場に 面していた。ロンドン自然史博物館(Natural History Museum)の「Geological Museum(旧地質学博物館)」の正面入口。・大きなイオニア式円柱が4本並ぶ古典様式の外観・三角破風(ペディメント) と中央の丸い装飾場所はサウス・ケンジントンの Exhibition Road 沿いにあり、現在は Natural History Museum(自然史博物館)の一部に統合 されていると。・創建:1935年完成(銘文は1933年着工を示す)。・元の役割:英国地質調査所(British Geological Survey)の本部と地質学博物館。・現在:1998年に自然史博物館と合併し、リニューアル後は「地球ギャラリー (Earth Galleries)」として利用。・建物正面下に「GEOLOGICAL SURVEY & MUSEUM(地質調査所および地質学博物館)」と。・さらに下に「A.D. 1933」 と刻まれていた。Geological Museum(地質学博物館) の建物のペディメント(切妻部)のアップ。屋根の頂部に掲げられているのは レインボーフラッグ(プライド旗) 。ロンドンの多くの公共施設と同様に、自然史博物館(Natural History Museum)やその関連施設も LGBTQ+プライド月間(毎年6月)などに合わせて掲揚 しているのだと。Exhibition Rdの右側にあったのがヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, Victoria and Albert Museum) の一角、Henry Cole Wing(ヘンリー・コール棟)。建物の壁面に「VICTORIA AND ALBERT MUSEUM HENRY COLE WING」と刻まれた銘板が。建設年:1868年完成(当初は「1868 Building」と呼ばれた)。設計者:建築家 Henry Scott と Major-General Henry Y.D. Scott。名称由来:ヴィクトリア&アルバート博物館の創設に尽力した Sir Henry Cole(1808–1882) にちなんで命名。彼はロンドン万国博覧会(1851年)を推進し、その収益を 博物館群(V&A、科学博物館、自然史博物館の礎)に結びつけた人物。その先左にあったのが、サイエンス・ミュージアム (Science Museum, London) の建物正面。The Clockmakers' Museum(時計師協会博物館) は、現在この サイエンス・ミュージアムの中に展示されているとのこと。建物上部に金文字で 「SCIENCE MUSEUM」、両脇の黒いバナーにも同じく SCIENCE MUSEUM と表記されていた。The Clockmakers' Museum(時計師協会博物館) は、このサイエンス・ミュージアム内部に常設展示されている と。サイエンス・ミュージアム (Science Museum, London) の外観特徴的なのは、クラシックなコリント式の列柱(columns)と、長く連なる大きな窓のデザインで、正面入口横のファサード部分にあたります。写真下部に見える黒いバナーにもSCIENCE MUSEUM と記されていた。ロンドンの エキシビション・ロード (Exhibition Road) に並ぶ白いテラスハウス群。建物は典型的な ヴィクトリア朝の白い漆喰仕上げのテラスハウスで、現在は大使館、教育施設、研究所、オフィスなどに利用されているものが多いとのこと。サウスケンジントンの「エキシビション・ロード (Exhibition Road)」 の風景。・左側の赤レンガ建物は典型的な ヴィクトリアン・ゴシック様式で、現在は大学や研究所、 大使館関連のオフィスとして使われている建物が多いです。建物の壁に 「EXHIBITION ROAD」のストリートサインが見えた。・右側には白やベージュのテラスハウスが並び、こちらも大使館やレジデンスとして利用されて いるものが多い と。・道路中央の広いスペースには、以前から現代的なデザインの街灯やポールが整備され、 歩行者が優先される空間になっていた。つまり、この場所は 自然史博物館・V&A・科学博物館へ続く文化エリアの中核で、観光客が必ず通る動線の一部であるのだ。左折して、Prince Consort Road(プリンス・コンソート・ロード)から。左側がImperial College・インペリアル大学。右角にあったのがHigh Commission of Jamaica・ジャマイカ高等弁務官事務所。・左側の壮大な石造建築は Imperial College London 本館 (Imperial Institute Building の後継部)。 中央の大きなアーチとその両脇の彫刻が特徴的で、王立勅許を受けた名門理工系大学の 象徴的ファサード。 右奥に見える赤レンガの建物は、Royal College of Music・王立音楽大学。・正式名称:Imperial College London・設立:1907年(ロンドン大学のカレッジとして発足、2007年に完全独立)・形態:公立研究大学・専門:理工学・医学・ビジネス に特化した世界的名門大学・QS世界大学ランキングやTHEランキングで常にトップ10前後に位置 イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(英語版)が毎年9月に公表している 世界大学ランキング。・強みの分野: ・工学(特に機械、航空宇宙、土木) ・自然科学(物理学、化学、生物学、数学) ・医学(Imperial College School of Medicine は英国最大規模の医学部) ・ビジネス(Imperial College Business School はテクノロジー連携に強み) ・研究資金調達力が非常に強く、産業界との連携が盛ん。→ ロールス・ロイス、BP、 グラクソ・スミスクラインなどと共同研究。 ・ノーベル賞受賞者やフィールズ賞受賞者を多数輩出。1. 左側(西側) ルイス・パスツール(Louis Pasteur, 1822–1895)・細菌学の父 近代細菌学の父。狂犬病ワクチンやパスチャライズ(低温殺菌法)を確立。 パスツールの周囲には、科学者や学生を象徴する副像が配置されており、 生命科学・医学研究の象徴となっています。2. 右側(東側) トマス・ヘンリー・ハクスリー (Thomas Henry Huxley, 1825–1895)・進化論の擁護者、教育者 博物学者・教育者。ダーウィンの進化論を強力に擁護したことで「ダーウィンの番犬」と 呼ばれる。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)付近の風景。奥の左側に、半円形の外観が特徴的な ロイヤル・アルバート・ホールの一部が見えて来た。手前から奥へと続く赤レンガの大きなカーブを描いた建物群は、Albert Hall Mansions(アルバート・ホール・マンションズ)と呼ばれる高級集合住宅。赤レンガとテラコッタ装飾を用いたヴィクトリア朝後期のデザイン。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) をズームして。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 東側前からロンドン・ケンジントン・ガーデンズにある アルバート記念碑(Albert Memorial)を見る。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall) 東側を見る。・竣工:1871年・様式:ヴィクトリア時代のイタリア・ルネサンス風の円形建築・材質:赤レンガとテラコッタの装飾が特徴・外壁のフリーズ:上部に一周ぐるりと 「芸術と科学の勝利(The Triumph of Arts and Sciences)」を描いたモザイク・フリーズ があり、さまざまな分野の人々が表現されていた。・左側に小さな別棟(ガラス張りのアーチ入口を持つ部分)が見えたが、これはホールの 付属的な出入口エリアで、ホール本体と連結していた。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)正面・南側からさらに南側を望む。この建物が Royal College of Music(王立音楽大学)。・中央のアーチ状玄関が正門。上部に飾られた装飾彫刻や尖塔が重厚さを与えていた。・左右に伸びる赤レンガの建物がシンメトリーを強調し、大学の威厳を感じさせた。中央上部をズームして。・円形の装飾 ここには「時計」または「レリーフ」が収められています。現在はシンプルな円形デザイン ですが、創建当時は象徴的な装飾や紋章が施されていたのだ と。・周囲の飾り 円形の周囲には植物文様風の石彫装飾(スクロールやアカンサス葉に似た意匠)があり、 ルネサンス・ゴシック様式の折衷デザインを反映していた。・両脇の塔状装飾 左右に「小尖塔(ミニチュア・ピナクル)」が配置されており、垂直性を強調していた。 これはヴィクトリア朝建築でよく見られる装飾的モチーフ。・二連アーチ窓 円形の下にはアーチが並ぶ2連窓(トリフォリウム風)があり、建物正面の中心性を 際立たせていた。右側の尖塔。ドーマー窓(屋根窓)があり、こちらはアーチではなく直線的な開口部。左側の尖塔。再び王立音楽大学の正面全体を。Royal Albert Hall(ロイヤル・アルバート・ホール)を再び正面から。石段を上り終えた場所に埋め込まれて銘板。「THE QUEEN ELIZABETH IIDIAMOND JUBILEE STEPSwere named in celebration ofHER MAJESTY’S Diamond Jubilee 2012This inscription commemorates the visit ofHER MAJESTY THE QUEENPatron of The Royal Albert Hall and ofThe Royal British Legion before the annualFestival of Remembrance 9th November 2013」 【エリザベス2世女王 ダイヤモンド・ジュビリー・ステップスこの階段は、2012年の女王陛下のダイヤモンド・ジュビリー(即位60周年) を祝して名付けられた。この碑文は、2013年11月9日、女王陛下がロイヤル・アルバート・ホールおよび英国王立退役軍人会(Royal British Legion)のパトロンとして「追悼祭(Festival of Remembrance)」に臨席したことを記念する。】ロイヤル・アルバート・ホール正面に立つアルバート公記念像(Prince Albert Memorial Statue) をクローズアップで。上部の立像・アルバート公(Prince Albert, 1819–1861) ヴィクトリア女王の夫で、芸術・科学・産業の振興に尽力した人物。 ロイヤル・アルバート・ホールも、彼の構想「アルバート計画(Albertopolis)」の 一環として建てられました。台座の構成 ・中央の高い円柱型台座 の上にアルバート公の立像。 ・その周囲に配置された 4体の座像(女性像) は、芸術の分野を象徴。座像(4体)の象徴 四大陸(Europe/Asia/Africa/America)を表す像群。アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)像 のクローズアップ像の特徴・衣装:チューダー風の衣装(短い上衣とタイツ)に、長いマントを羽織っています。 これは当時の「歴史的な宮廷服」を理想化したもので、彼の芸術保護者としての側面を 強調しています。・装飾:胸には「ガーター騎士団(Order of the Garter)」の徽章を下げています。 英国最高位の騎士団のシンボルで、アルバート公がその騎士であったことを示しています。・ポーズ:片手を腰に置き、もう片方の手には巻物(もしくは手袋)を持っています。 これは「計画を示す人物像」としての典型的なポーズで、彼が文化施設 (アルバート・ホールやサウスケンジントンの博物館群)の構想者であったことを 象徴しています。アルバート公記念碑の台座四隅にある 寓意像(Allegorical Figure) の一つ。特徴・頭部:城壁をかたどった冠(mural crown)をかぶっています。 → 古代ローマ以来、都市や文明を象徴する冠。・持ち物:左腕に巻物(あるいは書物)を抱えています。 → 文明・学問・知識の象徴。・衣装:古典的なギリシャ風のトーガ。この像は、四大陸のうちの 「Europe(ヨーロッパ)」 を寓意的に表したもの。ヨーロッパ=文明・都市・知識の中心という認識を反映。冠(都市の守護)と書物(学術・文化)によって、西欧文明の繁栄を示しています。・頭飾り:ターバン風の頭巾をかぶり、額に宝石状の装飾を付けています。 → 異国趣味の東洋的要素を強調。・衣装:厚手の布をまとい、胸元に装飾的な留め具、手首にはブレスレット。 → インドや中東を意識したコスチューム表現。・付属モチーフ:像の隣に象(Elephant)の頭部があり、アジアの象徴として表現。この像は「アジア大陸」を寓意的に表しています。ヨーロッパの美術では、アジアを表す際にしばしば「象」と「ターバンをかぶった女性」が組み合わされました。象はインドを象徴、宝飾品や衣装は東洋的な豊かさを示しています。ロイヤル・アルバート・ホール正面入口(北側のメイン・ポーチ)。アルバート公(Prince Albert, 1819–1861)像 の裏に移動して。ロイヤル・アルバート・ホール南側の「1851年大博覧会記念碑」(Memorial for the Exhibition of 1851)に配された四体の寓意像のうちの一体。・上半身を裸にした女性像:西洋美術ではアフリカの「自然」や「素朴さ」を表す図像として 用いられました。・装身具:首飾りや耳飾りをつけており、異国的な印象を強めています。・衣装:腰に巻いた布(腰布)と、その裾の装飾模様が民族的意匠を示しています。・表情と姿勢:堂々とした座姿で、身体性と力強さを強調。この像は アフリカ大陸の寓意像。西欧の19世紀芸術に典型的な「大陸擬人像」の表現で、アフリカはしばしば「半裸の女性」として描かれました。豊かな自然や身体的強さを象徴すると同時に、当時のヨーロッパ的視点による「エキゾチシズム」も反映しています。・弓と矢筒を持っている → 新大陸の「ネイティブアメリカン文化」を象徴する 典型的なモチーフ。・姿勢:戦士的な威厳を強調しつつも、古典的なトーガ風衣装をまとっている。・髪飾り:シンプルながら異国性を感じさせる。この像はAmerica (アメリカ)の寓意像。アメリカ大陸は、ヨーロッパ美術においてしばしば「弓矢を持つ女性」として表現されました。これは「新世界の戦闘性・野性」を寓意化したもの。バイソンや羽飾りを伴う場合もありますが、この記念碑では弓矢が主要な属性となっています。ロイヤル・アルバート・ホール南ポーチ(South Porch) の壁龕に設置されていたエリザベス2世女王(Queen Elizabeth II, 1926–2022) の立像。2013年11月9日、エリザベス女王がロイヤル・アルバート・ホールの「Festival of Remembrance(追悼祭)」に臨席したことを記念して、南側の改修時に設置されたものです。向かい側には アルバート公の立像 が配置され、ヴィクトリア朝の創設精神と現代王室のつながりを象徴しています。衣装:公式のローブ(長いドレス)をまとい、胸には勲章(ガーター勲章など)が表現されています。頭部:ティアラ(王冠に近い宝飾冠)をつけ、君主としての格式を示しています。姿勢:両手を前で重ね、厳かな立ち姿。視線はやや遠くに向けられています。この像は ロイヤル・アルバート・ホール南ポーチ(South Porch)の壁龕に設置された立像の一つで、エジンバラ公フィリップ殿下(Prince Philip, Duke of Edinburgh, 1921–2021)。服装:モーニングコート風のスーツ姿。王族の儀礼服ではなく、現代的かつ公的な場に ふさわしい服装。姿勢:両手を後ろに組み、軽く歩を進めたような自然体の立ち姿。表現:女王エリザベス2世像の厳かな直立姿と対照的に、リラックスした佇まい。両者は夫婦として長くロイヤル・アルバート・ホールの活動を支援し、とりわけ毎年の「Festival of Remembrance(戦没者追悼祭)」に臨席していたのだと。この写真の高い四角柱状の建造物は、ロイヤル・アルバート・ホールの換気塔(Ventilation Tower, 通称「スモーク・スタック」)近づいて。・形状:赤レンガ造りの細長い塔で、装飾的な石の基壇と頂部を持つ。・素材:ロイヤル・アルバート・ホール本体と同じ赤レンガを基調としており、周囲の景観に調和。・用途:ホール建設当時(1871年)からの暖房用ボイラーの煙突兼換気塔として設計。今では実用的な煙突としては使われていませんが、ホールの外観を特徴づける付属構造物として保存されているのだ と。1991年にジャパン・フェスティバルの一環で行われた、大相撲のロンドン公演がここロイヤル・アルバート・ホールで行われたのだ。通常の15日を5日間に短縮した「ロイヤル場所」には、幕内力士40名が出場。アリーナに作られた土俵で勝負をしたのだと。そして2025年10月15日(水)から10月19日(日)まで、英国ロンドンの劇場、ここ「ロイヤル・アルバート・ホール」で「大相撲ロンドン公演(The Grand Sumo Tournament)」👈️リンクが開催されたのであった。大相撲ロンドン公演初日の会場捉えた様子(画像は日本相撲協会公式Xのスクリーンショット)。Royal Albert Hall(ロンドン)で開催された、Grand Sumo Tournament (London 2025)](大相撲ロンドン大会)での集合写真。大相撲ロンドン公演を記念して発行された絵葉書が話題に と。葛飾北斎の《神奈川沖浪裏(The Great Wave off Kanagawa)》をモチーフに、ロンドンの「ロイヤル・アルバート・ホール」と相撲力士を組み合わせたパロディ版右側に見えるのが半円形のドーム屋根をもつ赤レンガ造りの建物が、ロンドンの象徴的コンサートホール「Royal Albert Hall」(1871年完成、アルバート公を記念して建設)。赤レンガと円形ドーム屋根が特徴で、ロンドンを象徴する建築の一つ。この建物を、北斎の「富士山」の位置に置き換えているのだ。→ つまり「富士山=ロンドン文化の象徴」へ。波間には、相撲力士(sumo wrestlers) や 行司(審判役) が描かれており、日本文化の代表的要素をユーモラスに取り入れていた。力士たちは舟や波に乗り、「大相撲ロンドン公演」を表現した構図。波と構図・北斎の波の造形を忠実に再現しつつ、筆致と陰影を明るくデフォルメ。・波頭の白い飛沫が、ほぼオリジナルと同じリズムで描かれています。・奥行きのある3層構造(手前の大波/中波/背景)が保たれています。そして、大相撲のロンドン公演は19日、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽を迎えた。5日間の本割で争った公演は、豊昇龍が大の里との全勝対決を制して優勝した。力士40人が締め込み姿で勢ぞろいした閉会式では、大の里が英語で「Hello everyone.London is great.Thank you and see you again.Goodbye」とあいさつ。約5400人の観客から万雷の拍手が送られた。三賞は殊勲賞が翔猿、敢闘賞が高安、技能賞が宇良。5日間の観客の投票で決まる「観客賞」は宇良が受賞した。ロンドン公演は1991年以来34年ぶりの開催で、チケットは全日完売。5日間で計約2万7000人の観客を動員した と。ロイヤル・アルバート・ホール前の横綱・大の里。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)の内部をネットから。ロイヤル・アルバート・ホール(Royal Albert Hall)西側(West Porch/西玄関)。・大きなアーチ状の入口 → 西玄関(West Porch)のメインゲート。現在はガラス扉に改修され、観客の出入りに 利用されます。・建物装飾 ・赤レンガの壁面とクリーム色のテラコッタ装飾。 ・2階部分に並ぶアーチ窓の上に、ホールを一周する有名な フリーズ装飾 (テラコッタの帯状浮彫) が確認できます。・フリーズの内容 → 科学・芸術・産業・人間活動をテーマとしたモチーフが連続的に描かれています。ロイヤル・アルバート・ホール西玄関(West Porch)付近から、北方向(アルバート記念碑側)を見て。・右手前:ロイヤル・アルバート・ホールの壁面と西玄関のアーチ。・中央奥:木々の向こうにチラリと見える金色の像と屋根 → これは アルバート記念碑(Albert Memorial)。・道路の中央部:カラーの垂れ幕(赤・青・黒)が並んでおり、ホールのイベント告知用バナー。西洋トチノキ(Horse Chestnut, 学名 Aesculus hippocastanum) の花。・花序:円錐状に立ち上がる白〜淡いピンクの花房。1本の花房に多数の小花が集まっています。・花色:白地に黄色や赤の斑点が入ることが多い。写真でも中心部がピンク色を帯びています。・葉:掌状複葉(1つの葉柄から5〜7枚の小葉が放射状に広がる)。西洋トチノキ(Horse Chestnut)の花をズームして。・開花期はイギリスでは 5月〜6月初旬。・この時期はロンドンのケンジントン周辺やロイヤル・アルバート・ホールの外周に 植えられたトチノキも一斉に花を咲かせ、街路や公園を彩るのだと。・花房(花序):円錐状に直立し、1本の花穂に多数の小花が集まる。・花色:白を基調に、花の中心部が鮮やかなピンクや黄色で彩られています。 特に蜜標(花の中心の模様)は、昆虫を誘うガイドの役割を果たします。・雄しべ:長く突き出た白い糸状の雄しべが花全体に繊細な印象を与える。更にズームして。和名は「マロニエ」。 マロニエの実の写真をネットから。マロニエの実は、栗と間違われやすいですが、食べることができません。マロニエの実は「マロン(marron)」と呼ばれますが、このマロンはフランス語でトチの実のことで、日本の栗とは異なり、不味いだけでなく毒性もあるため食用にはしないのが一般的です と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.04
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その128): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-11~自然史博物館(Natural History Museum)-1
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクここもCeramics Galleries(陶磁器ギャラリー)。V&Aの陶磁器コレクションは非常に大きく、主要展示室は Rooms 136–146(Ceramics Study Galleries) と呼ばれるエリア。この写真は、その長いギャラリー通路のひとつで、ヨーロッパ・中東・アジアの陶器が並んでいる展示ゾーン坐像 菩提達磨(Bodhidharma)。出土地:北中国時代:明代、1484年(成化年間)材質:石器質陶(Stoneware)、緑釉・褐釉・胴体から衣にかけて緑釉(銅緑系)が美しくかけられている。・褐色の顔や胸部との対比が強く、精神性と力強さを表現。・姿勢は端正な結跏趺坐(けっかふざ)で、禅定(瞑想)を象徴。「Seated BodhidharmaNorthern ChinaMing dynasty, dated 1484This life-size temple sculpture represents Bodhidharma or Da Mo, an Indian Buddhist monk who reached China around 520, bringing Buddhist scriptures with him. He is regarded as the founder of Chan (or Zen) Buddhism.Such temple sculptures were specially commissioned by Buddhist devotees. They were made in moulds, finished by hand, biscuit-fired and then glazed and fired again.Stoneware, with green and brown glazes」 【坐像 菩提達磨(Bodhidharma)中国北部明代、1484年この等身大の寺院用彫像は、菩提達磨(または達磨大師、Da Mo)を表しています。彼はインド出身の仏教僧で、約520年頃に中国へ渡り、仏典をもたらしました。彼は禅宗(Zen、または中国の「禅=Chan」)の開祖として尊敬されています。このような寺院用の仏像は、仏教信者によって特別に依頼されて制作されました。像は型を用いて成形され、手作業で仕上げられ、素焼き(bisque firing)の後、釉薬をかけて再度焼成されました。石器質陶、緑釉および褐釉】・手前の大きな青いピッチャー(右下)は、イギリスの陶器(19世紀前半のトランスファー 印刷陶器)に見えます。青地に風景が描かれた典型的な「Blue and White transferware (銅版転写陶器)」です。・左奥の壺はイスラム陶器(ペルシア/オスマンの影響)やヨーロッパ装飾磁器と思われます。・中央棚の茶色い装飾物は東南アジア系(タイやビルマの寺院装飾陶器)に近い形状。・奥の展示壁(背後)には皿がびっしりと並び、18世紀以降のヨーロッパ陶磁器の展示構成に なっています。・壁に「1800」と表示されているので、このケースは 18世紀末から19世紀(近代初頭) ヨーロッパ陶磁器 をテーマにしたセクションと考えられます。ここは Room 145。中に見える展示ボードには「British Studio Pottery and the V&A」(英国スタジオ陶芸とV&A)と書かれていた。Room 145 の概要・ギャラリー名:British Studio Pottery(英国スタジオ陶芸)・展示内容:20世紀以降の英国におけるスタジオ陶芸(Studio Pottery)の流れを紹介。 ・バーナード・リーチ(Bernard Leach, 1887–1979)を中心に、 東洋陶芸(特に日本の民藝運動や濱田庄司)と英国の陶芸が結びついた歴史を紹介。 ・その後の現代英国陶芸作家(ルーシー・リー Lucy Rie、ハンス・コパー Hans Coper など) の作品も展示。・テーマ:産業化された大量生産品ではなく、作家個人による芸術的表現を陶器に込めた 「スタジオ陶芸」の意義。V&A陶磁ギャラリーの中央付近に展示されている 非常に大きな現代陶芸作品(フロア展示の円筒形花器)。・高さ2m近い円筒形の大壺(vessel)。・表面には白地に藍色の大きな筆致で、植物や抽象的な渦のような模様が描かれていた。・足元は黒い台座に載せられており、床置きのモニュメント的展示。・背後の壁には「1800」と書かれているので、この展示は 近現代陶芸 (1800年以降のセクション) の一環として置かれていた。グレイソン・ペリー作「対の壺(Matching Pair)」左の壺(「Remain(EU残留派)」を象徴)・中央に腕を組む若い女性像(若い世代の希望や自立の象徴)。・背後にはカジュアルな服装の人々、文化人や都市的生活を想起させる人物。・価値観としては「多様性」「文化的開放」「国際主義」を象徴。右の壺(「Leave(EU離脱派)」を象徴)・中央にはユニオンジャック柄を思わせる衣装を着た中年男性サイクリスト。・周囲には伝統的・保守的な価値観を想起させる人物像やシンボル。・「ナショナル・アイデンティティ」「地域主義」「自国主義」を象徴。近づいて。・作家:Grayson Perry (1960– )・作品名:Matching Pair・制作年:2017年・素材:釉薬を施した陶器(glazed earthenware)、手作業成形、彫文・彩色・印刷装飾併用・寸法:高さ 約105 cm × 幅 約51 cm・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, ロンドン)「Grayson Perry: ‘Matching Pair’An artist and a frank cultural commentator, Grayson Perry uses his work to dissect social issues like class, gender and politics. After the EU Referendum in 2016,Perry began making a pair of vases to represent the two sides of the Brexit debate. For the first time he crowdsourced imagery through social media, asking ‘Leave’ and ‘Remain’ voters for suggestions of things they love about Britain, people that represent their values, their favoured colour and brands, and self-portraits. The resulting pots look remarkably similar, which Perry describes as: ‘a good result, for we all have much more in common than that which separates us.’‘Matching Pair’Grayson Perry (born 1960)Made in London, 2017 Glazed earthenware, hand-built, with incised, painted and printed decorationPurchased with the support of the Ruddock Foundation for the Arts, V&A Members, Sarah Nichols, the William Brake Charitable Trust and an anonymous donorMuseum no. C.13&A-2018」 【グレイソン・ペリー:《対の壺》(Matching Pair)芸術家であり率直な文化評論家でもあるグレイソン・ペリーは、階級、ジェンダー、政治といった社会問題を解剖するために自身の作品を用いています。2016年のEU国民投票(ブレグジット)後、ペリーはブレグジット論争の両陣営を表す一対の壺を制作し始めました。彼は初めてSNSを通じて群衆からイメージを集め、「離脱派(Leave)」と「残留派(Remain)」の投票者に、イギリスで愛するもの、自らの価値を体現する人物、好みの色やブランド、そして自画像を提案するよう依頼しました。その結果生まれた壺は驚くほど似ており、ペリーはこれを「良い結果だ。我々には互いを隔てるものよりも、はるかに多くの共通点があるのだから」と述べています。《対の壺》(Matching Pair)グレイソン・ペリー(1960年生)2017年、ロンドン制作釉薬を施した陶器。手作り成形。彫刻、彩色、印刷装飾。ルドック財団、V&Aメンバーズ、サラ・ニコルズ、ウィリアム・ブレイク慈善信託、匿名の寄付者の支援により購入。所蔵番号:C.13&A-2018】内部の展示品の見学を終え、再び、V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館) の中庭(John Madejski Garden, ジョン・マデジスキ・ガーデン)を。・赤レンガと白石の装飾的な外壁は、V&A本館の19世紀ヴィクトリアン様式の典型。・中央には大きな樹木と芝生、その周囲にベンチやカフェ用テーブルが配置。・天気の良い日には訪問者がここで休憩したり、飲食を楽しんでいる光景が見られた。・この中庭の中央には通常、浅い池(fountain pool)があり、夏には子どもが水遊びできる スペースとしても有名。John Madejski Garden(ジョン・マデジスキ・ガーデン) の中心にある浅い噴水池。・円形に近い浅いプール(水盤)で、床面は赤褐色のタイルで仕上げられていた。・周囲には低い段差があり、腰掛けたり足を浸したりできるよう設計。・数本の噴水が一定のリズムで水を吹き上げ、夏には子どもたちが水遊びを楽しむ場所として有名。・プールは通常は水を張っているが、特別イベント時には水を抜いて展示スペースや舞台として 使われることもあるのだ と。・中庭は、1857年の創建当時から「教育と憩いの場」として設計された部分。・2005年に再整備され、現在のデザインは建築家 Kim Wilkie によるもの。・レンガ造りのクラシックな建物に囲まれながら、現代的な水盤と芝生が融合した空間。V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)正面ファサードを再び。・建物は赤レンガと白い石材のストライプ模様が特徴的で、19世紀ヴィクトリア朝の ハイブリッド建築様式。・上部には装飾的な塔(クロック・タワーに近い部分)が見える。・壁面には大きなバナーがかかっており、ここでは「CARTIER(カルティエ展)」の特別展が 開催されていることを示していた。・バナーには白いバラの図柄と「V&A」ロゴが入っていた。V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)外観、クロムウェル・ロード(Cromwell Road)側のファサードの一部を。・この正面部は Aston Webb(アストン・ウェッブ卿) による1909年完成の 「クロムウェル・ロード正面玄関」部分。・V&Aは1852年に前身が創設され、その後拡張を繰り返しましたが、このファサードは 20世紀初頭のクラシカルな仕上げ。・全体的に「ルネサンス復興様式」と「バロック様式」を融合させた重厚な構成で、 大英帝国時代の国威発揚を象徴 と。正面に見えたのが「自然史博物館(Natural History Museum, London)」。・中央にそびえる壮大なロマネスク様式の建物は、1881年完成の自然史博物館本館 (サウス・ケンジントン)。・設計者は建築家 アルフレッド・ウォーターハウス(Alfred Waterhouse)。・クリーム色と青灰色のテラコッタ・タイルを組み合わせた独特の外観。・左に見えるのは高い塔で、教会のような荘厳さを感じさせる。・手前の庭園は「Darwin Centre / Wildlife Garden」として整備されており、 シダ植物や岩石展示があり、自然との共生を意識した空間になっていた。 Natural History Museum(自然史博物館) の入口サイン。・黒い縦長の案内板に、カラフルなロゴマークと「Natural History Museum」の白文字。・ロゴは N・H・M の文字を円形に配置したデザインで、生命や自然の多様性をイメージ。・背景には前の写真と同じく、自然史博物館の建物(アルフレッド・ウォーターハウス設計、 ロマネスク様式)が一部見えた。 「Welcome to the Natural History Museum・自然史博物館へようこそ」と。 ・ロンドンの「ミュージアム・マイル(三大博物館)」の一つで、 隣には V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)、科学博物館(Science Museum) が並ぶ。・所蔵は8000万点以上(恐竜化石、鉱物、植物標本など)。・入口ホール(ヒントゼ・ホール Hintze Hall)にはかつて恐竜ディプロドクスの骨格模型 “Dippy”があり、現在は巨大なシロナガスクジラの骨格“Hans Sloane”が 吊り下げ展示されていた。Natural History Museum(自然史博物館)本館 を下から見上げて。・設計:アルフレッド・ウォーターハウス(Alfred Waterhouse)・竣工:1881年・様式:ロマネスク・リバイバル建築(丸いアーチ窓、縦のリズムを強調した柱列、 彫刻装飾が特徴)・素材:クリーム色とブルーグレーのテラコッタ・タイルを組み合わせており、ロンドンの 煤煙に耐えるために選ばれました。左側に見えるのは西塔(West Tower)、中央は正面玄関に続くヒントゼ・ホール(Hintze Hall)部分。・建物:アルフレッド・ウォーターハウス設計による1881年竣工のロマネスク・リバイバル様式。 ・丸窓・アーチ窓が連続し、縦方向の強いリズムを持つ外観。 ・外壁は クリーム色とブルーグレーのテラコッタ・タイルで装飾され、自然をテーマにした 動植物のレリーフが刻まれていた。・前景の岩柱:これは博物館前庭に設置された自然展示の一部。・樹木の化石(珪化木)や、地質標本としての岩石を野外に配置しており、訪問者が「自然史」の 一端を屋外でも体験できるようになっていた。・周囲の雰囲気:博物館前の広場は、展示パネルや植栽とともに「ワイルドライフ・ガーデン (Wildlife Garden)」へとつながっていた。自然史博物館(Natural History Museum) の正面側、ワイルドライフ・ガーデン(Wildlife Garden) と屋外展示エリアを捉えて。・恐竜骨格模型 ・左側に恐竜のブロンズ(または金属製)骨格模型が見えます。 ・これは来館者を惹きつけるシンボル展示で、屋外でも博物館のテーマを感じられる工夫。・植栽と岩石展示 ・庭園にはシダ類や針葉樹など、太古の地球を思わせる植物が植えられていた。 ・周囲に赤茶色の大きな岩石が配置され、地質学的な展示意図も含まれていた。・人々の憩いの場 ・ベンチや石の座席に座って休む人々がおり、博物館の「教育+市民の憩い」という 二重の機能が表れていた。・背景建物 ・博物館本館の長大な壁面(ロマネスク・リバイバル様式のアーチ窓の連続)が写っており、 その荘厳さと対比するように「自然と恐竜の展示」が前景に。 ・左奥には本館の西塔(West Tower)がそびえていた。前庭に展示されている 恐竜の全身骨格模型に近づいて。・全長20m以上の長大な骨格。・細長い首と尾、大きな胴体を持つ四足歩行の草食恐竜。・体型から、ディプロドクス(Diplodocus) の竜脚類恐竜を模したレプリカ と。恐竜骨格模型の 尾の部分(長大な脊椎) をクローズアップして。骨格の構造・長く連なる椎骨(背骨)が連結され、竜脚類恐竜特有のしなやかな尾のカーブを再現。・一つ一つの椎骨の形が強調され、実際に恐竜がどれほど巨大であったかを実感できた。廻り込んでディプロドクス(Diplodocus)像の首と頭部 のアップ。・恐竜の種類 ジュラ紀後期(約1億5千万年前)に生息した大型の竜脚類恐竜。 体長は最大約24〜27mに達し、長い首と尾が特徴。・頭骨の特徴 ・頭部は小さく、鼻孔は頭の上方に位置。 ・歯は前方に並び、枝葉をかき集めるのに適していた。 ・写真の骨格からも「細長い頭部」と「軽量化された構造」がよく分かった。ディプロドクス(Diplodocus)の頭骨模型。ジュラ紀後期(約1億5千万年前)に北アメリカで生息した大型の竜脚類。頭骨の構造・細長い形状で、軽量化された骨格。・頭頂部付近に大きな鼻孔の穴。・前方に細長く並んだ「ペグ状の歯」があり、葉や枝をかき取るのに適した。・脳の容積は体の大きさに比して小さめ。「Diet of a gianLived 150 million years agoNo other land animals have grown as big as the long-necked dinosaurs.Diplodocus was one of the largest, with an adult reaching up to 24 metres(79 feet) long and weighing more than three elephants.Its size was mostly down to the food it ate. Its whole body evolved to eat vast amounts of plants. Its height allowed it to browse on leaves from branches. Its huge digestive system contained bacteria that were crucial to breakingdown tough leaves.This bronze cast is known as Fern the Diplodocus. The Museum’s neighbours – young people from across the local community – named the dinosaur, inspired by the plants living alongside dinosaurs at this time.Diplodocus carnegiiUSA」図解キャプション・Blunt, peg-like teeth stripped leaves from branches・Bacteria in its giant digestive system broke down huge quantities of leaves it needed to survive.Four thick sturdy legs supported this giant plant-eating machine.下部注記Fern the Diplodocus and the Jurassic Garden generously supported by Kusuma Trust【巨獣の食事約1億5000万年前に生息長い首を持つ恐竜ほど巨大に成長した陸上動物は他にいません。ディプロドクス(Diplodocus) はその中でも最大級の恐竜の一つで、成体は全長24メートル(約79フィート)に達し、体重はゾウ3頭以上にもなりました。その巨体は主に食べ物によるものでした。体全体が膨大な量の植物を食べるために進化していたのです。高さを活かして枝から葉を食べ、大きな消化器系にはバクテリアが存在し、硬い葉を分解するのに欠かせない役割を果たしていました。この青銅像は「ファーン・ディプロドクス」として知られています。博物館の近隣に住む若者たちが、当時恐竜とともに生えていた植物・シダ(ファーン・Fern)にちなんでこの恐竜の名前をつけました。ディプロドクス・カーネギー(Diplodocus carnegii)アメリカ合衆国】 図解の説明・丸みのある杭のような歯で枝から葉をむしり取った。・巨大な消化器官の中のバクテリアが、大量の葉を分解して生存を助けた。・頑丈な4本の脚が、この巨大な草食恐竜を支えた。下部注記・ディプロドクスの“ファーン”とジュラ紀ガーデンは、クスマ・トラストの寛大な支援によって 実現しました。】アンモナイト(Ammonite)の大型化石。・アンモナイトは 約4億年前(デボン紀)から白亜紀末(約6600万年前) まで繁栄。・恐竜と同じく白亜紀末の大量絶滅で姿を消した。・らせん状の殻 外洋に生息していた頭足類(イカやタコの仲間)の一種で、殻が渦巻き状に巻いていた。・リブ(肋状の縞模様) 殻表面に規則的なリブ(隆起線)が見えるのが典型的な特徴。・大きさ 直径50cm以上あり、かなり大型の標本。「Ocean giantsLived 150 million years agoAmmonites lived in ancient oceans. They can easily be recognised by their coiled shells, but their soft tissues – including their octopus-like arms – are rarely fossilised. Some ammonites fed on tiny particles of food and others were probably predators or scavengers of sea creatures.AmmoniteEnglandIts hard, outer shell was made up of multiple chambers.Smaller chambers filled with a mix of liquids and gasses kept the ammonite afloat.New chambers were added as the animal grew.」 【海の巨人たち約1億5000万年前に生息アンモナイトは古代の海に生息していました。巻き貝状の殻によって容易に識別できますが、タコに似た腕を含む柔らかい体の部分は化石として残ることはほとんどありません。一部のアンモナイトは微小な食物粒子を食べており、他の種類はおそらく捕食者、あるいは海の生物をあさるスカベンジャーだったと考えられます。アンモナイトイングランドその硬い外殻は複数の部屋から構成されていました。小さな部屋には液体とガスの混合物が満たされ、アンモナイトを浮かせていました。成長に伴い、新しい部屋が次々と追加されました。】自然史博物館(Natural History Museum) の西側外観と西塔(West Tower) を。建築の特徴・ロマネスク・リバイバル様式 ・丸いアーチ窓が規則的に並び、柱と装飾が縦のリズムを強調。 ・彫刻や細部装飾は「自然」をテーマにしており、動植物や化石のモチーフが刻まれている。外壁の素材 ・クリーム色とブルーグレーのテラコッタ・タイルが交互に使われており、煤煙に強く、 かつ美しい縞模様を形成。 ・建物全体に温かみと荘厳さを与えています。西塔(写真左奥) ・ゴシック建築を思わせる尖塔を持つが、全体はロマネスクの重厚さが強い。 ・博物館の象徴的なランドマークのひとつ。巨大フリント(火打石)。「Giant flintsFormed 94 to 72 million years agoThese large, knobby flints with their hollow centres are puzzling. How were they formed? The silica from which they are made originally came from the skeletons of glass sponges, but how the flints later took shape is less certain.One idea is that they formed around burrows made by giant ribbon worms. Another is that they are the remains of barrel-shaped sponges.Chalk GroupEngland」 【巨大フリント(火打石)形成時期:9400万~7200万年前この大きくでこぼこした中空のフリントは、謎に満ちています。どのように形成されたのでしょうか?その素材となる二酸化ケイ素は、もともとガラス海綿の骨格に由来しています。しかし、これらのフリントが後にどのように現在の形をとったのかは、はっきりしていません。ひとつの説は、それらが巨大なリボンワーム(紐状の蠕虫)が作った巣穴の周囲で形成されたというものです。もう一つの説は、樽型の海綿の残骸だというものです。チョーク・グループ(Chalk Group)イングランド】西塔(West Tower)と、西側ファサードを、再び下から見上げて。正面入口(サウス・ケンジントン側)。建物の正面(南側ファサード)・設計者:アルフレッド・ウォーターハウス(Alfred Waterhouse, 1830–1905)・建築様式:ロマネスク・リバイバル(特にドイツのルンダル=大聖堂様式を参照)・完成:1881年特徴1.双塔構造・写真中央に見える二つの高い塔は、大聖堂を思わせる象徴的デザイン。・「自然史の大聖堂」と呼ばれる理由のひとつ。2.大アーチ入口・半円アーチのポータル(玄関アーチ)には精緻な装飾があり、来館者を荘厳に迎え入れる造り。・外壁のテラコッタには、動植物や化石をモチーフにした彫刻がちりばめられていた。3.外壁素材・ロンドンの煤煙に耐えられるよう、ウォーターハウスが採用した耐久性のある テラコッタ製タイル。・クリーム色とブルーグレーの縞模様が美しく、同時に汚れが目立ちにくい工夫が。ロンドン自然史博物館(Natural History Museum)正面の鉄柵(フェンス)。・色彩:深い赤(バーガンディ色)の鉄製フェンスに、金色の装飾(王冠・尖塔・飾り金具)。・様式:ヴィクトリア朝後期のデザインで、ゴシック的な尖塔と幾何学的模様を 組み合わせています。・装飾:円形の部分には、博物館を象徴する紋章風の模様が見えます。・役割:博物館の正面広場を取り囲む柵として、荘厳な雰囲気を演出。 外からの眺めも「大聖堂のような科学殿堂」を強調するデザイン。正面の鉄柵(フェンス)に近づいて。正面ゲートの石柱部分。・石柱の構造 灰色の石材で作られた堂々とした門柱。上部には八角形のガス灯風ランタンが載っており、 装飾性と実用性を兼ね備えています。 ランタンの支柱は鉄細工で、先ほどの赤と金のフェンス装飾と一体感を持っています。・浮彫(レリーフ)装飾 石柱中央には3面にわたって細かいレリーフが彫られています。 ・上段:盾や動物モチーフのように見える複雑な装飾。 ・中段:渦巻き状の唐草模様や植物的な要素。 ・下段:花束あるいは果実を思わせる植物文様。 → これらは自然史博物館のテーマに合わせた「自然界のモチーフ (動植物・植物文様)」を象徴している と。正面入口(サウス・ケンジントン側のメイン・エントランス)。・双塔(ツインタワー) 大聖堂のような左右対称の双塔を構え、教会建築を思わせる厳かな外観。・ロマネスク様式 設計者 アルフレッド・ウォーターハウス が1873–1880年にかけて建築。 → 丸いアーチ、分厚い壁面、装飾的な列柱が特徴で、「ロマネスク・リヴァイヴァル様式」の 代表例。・彩色されたテラコッタ装飾 壁面には動植物のレリーフが多数刻まれており、恐竜や植物など自然史のテーマを象徴。 雨に強いテラコッタを用いたのはロンドンの煤煙環境に耐えるため。・大階段 訪問者を迎え入れる正面階段。中央の三連アーチの奥がメインホール (現在はヒントゼー・ホール)につながる。正面中央部の上部(ファサードの双塔部分) をアップで。・双塔(ツインタワー) 正面入口の両脇にそびえる代表的な二つの塔。 尖塔(spires)には装飾的なタイル模様が施され、ロマネスク様式を基調にしつつ ゴシック的な垂直性も感じさせた。・中央切妻(三角破風部) 二つの塔の間には三角形の破風(pediment)があり、その中にアーチ窓が3つ+小窓2つ 並んでいた。 窓の下には小さなバルコニー状の装飾(ギャラリー)が付属。・装飾的なテラコッタ 建物全体と同じく、黄色と灰色の縞模様が施されたテラコッタ(耐煙素材)が使用されていた。 この模様は単なる装飾ではなく、当時のロンドンの煤煙から建物を守る実用性もあった と。ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London)南側外観を。・長大な翼廊(ウィング部分) 正面入口から東西に延びる長い建物の一部で、規則的に並ぶアーチ窓が特徴。 大聖堂の回廊を思わせる荘厳さがあった。・ロマネスク・リヴァイヴァル様式 連続アーチ、厚みのある壁面、装飾的な柱頭を持つ二連窓・三連窓など、 中世ロマネスク様式を再現。・テラコッタ装飾 建物全体は彩色テラコッタで覆われ、動植物のモチーフが随所に刻まれていた。 これは「自然史」を象徴するデザインであり、煤煙に強い耐久性も兼ねている と。西翼部分(ウエスト・ウィング)の大屋根と装飾的な窓列をズームして。・急勾配の大屋根 階段状に帯模様(ストライプ)の入ったスレート葺き。これは館全体の特徴である 「縞模様のテラコッタ装飾」と調和。・ロマネスク風の連続アーチ窓 下の部分には長く伸びた半円アーチ窓が並び、その上に小さな三角破風(ギャブル)で リズムを与えていた。 → これはまるで修道院の回廊や大聖堂の身廊の上部を思わせる造り。・塔状の付属建物 屋根の四隅には小さな塔(タレット)が配置され、要塞的かつ荘厳な印象を強めていた。本館外壁の上部装飾部分 をクローズアップ。・アーケード型の窓 ・丸アーチ窓(二連や三連)で構成され、ロマネスク建築風の重厚な様式。 ・窓の周囲には装飾的な柱(小円柱)と彫刻フレームが施され、立体感を強調。・屋根下の小さな三角破風(ペディメント) ・各窓上に小さな三角形の破風があり、その中にも開口部(二連窓)が組み込まれていた。 ・これによりリズム感と垂直性が強調され、建物全体の壮麗さが増して。・彫像(スタチュー) ・ペディメントとペディメントの間に、複数の彫像が立っていた。 ・多くは立像で、何らかの自然界を象徴する動物像。 自然史博物館では、外壁装飾として動植物・化石・科学者や寓意的存在が表現されて いるのが特徴。 ・この部分は「自然界の守護者」的な意味合いを持ち、来館者に「ここは自然の殿堂である」と 印象付けていたのであった。西ウィングの全景。・右側手前 正面中央入口のアーチとその右側の塔が部分的に見えています。ロマネスク様式の 連続アーチが特徴。・中央~左方向へ 西ウィングの長い側廊(側面)が伸びており、均整のとれた二連窓・三連窓が連続。 屋根は急勾配の切妻屋根。・左奥 西端に位置する高い角塔(West Tower)が確認できた。先ほどの写真でも写っていたもの。こちらは反対側をズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.03
コメント(0)
-
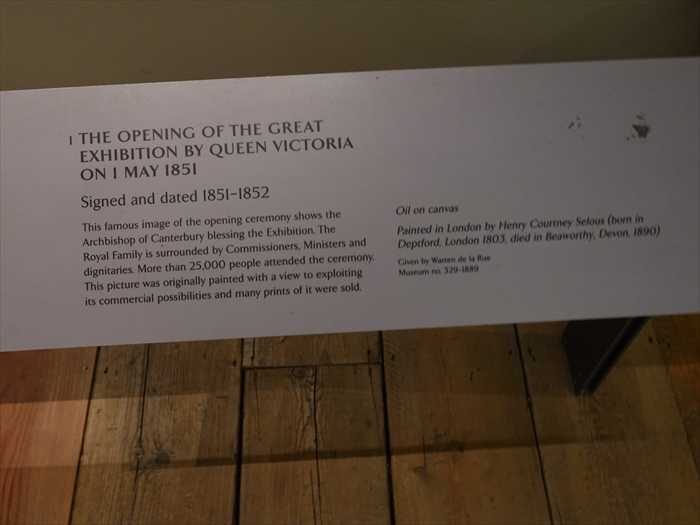
アイルランド・ロンドンへの旅(その127): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-10
【海外旅行 ブログリスト】👈リンクこの絵画は 「The Opening of the Great Exhibition by Queen Victoria on 1 May 1851(1851年5月1日、ヴィクトリア女王による万国博覧会開会式)」。・画家:Henry Courtney Selous(ヘンリー・コートニー・セロウス, 1803–1890)・制作年:1851–1852年(署名・日付あり・素材:油彩・カンヴァス・所蔵:V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)・展示場所:1851年の グレート・エキシビション関連コーナー(イギリスの19世紀デザイン・ 産業展示を扱うギャラリー)中央をズームして。ロンドン・ハイドパークの水晶宮(Crystal Palace)で行われた「第1回ロンドン万国博覧会(Great Exhibition)」の開会式を描いている と。ヴィクトリア女王とアルバート公、そして王室一家 が描かれている。左から順に:1.ヴィクトリア王女(Princess Victoria, 1840–1901) ・後のドイツ皇后、ヴィルヘルム2世の母。白いドレスを着た少女として描かれています。2.アルバート・エドワード王子(Prince Albert Edward, 1841–1910) ・スコットランド風の衣装を着ている少年。後の エドワード7世。3.ヴィクトリア女王(Queen Victoria, 1819–1901) ・中央の華やかなピンクのドレスを着た女性。王冠を戴いています。4.アルバート公(Prince Albert, 1819–1861) ・女王の右隣、赤い軍服に青いサッシュをかけた男性。その背後にいるのは王女たちで、例えば: ・アリス王女(Princess Alice, 1843–1878) ・ヘレナ王女(Princess Helena, 1846–1923) ・ルイーズ王女(Princess Louise, 1848–1939) ・アルフレッド王子(Prince Alfred, 1844–1900) など絵には一家の多くの子どもたちが描かれていますが、画家は公式的・象徴的に配列しているため、実際の幼少の姿や年齢とは少し異なる表現になっている とのこと。左側をズームして。女王の前方左手に集う要人・聖職者・貴顕。中央人物・白い祭服にストールをつけて手を合わせている人物が カンタベリー大主教 John Bird Sumner(1780–1862)。 → 実際の開会式でも彼が祝祷を行った と。周囲の人物 この群像は、当日の式典に参加した 政府要人・宮廷高官・王族随員・軍人 を写実的に描いたもの。・手前に並ぶ赤い軍服や勲章を帯びた人物は、王室の護衛や近衛将校。・濃茶色の服装に白いストッキング姿の人物は、宮廷の儀礼官や政府委員(Commissioners)。・後方には当日の観客席(ギャラリー)と、全体を見守る石膏像 (ギリシア彫刻風のアレゴリー像)が配置されている。「THE OPENING OF THE GREAT EXHIBITION BY QUEEN VICTORIA ON 1 MAY 1851Signed and dated 1851–1852This famous image of the opening ceremony shows the Archbishop of Canterburyblessing the Exhibition. The Royal Family is surrounded by Commissioners, Ministers and dignitaries. More than 25,000 people attended the ceremony.This picture was originally painted with a view to exploiting its commercial possibilities and many prints of it were sold.Oil on canvasPainted in London by Henry Courtney Selous (born in Deptford, London 1803, died inBeaworthy, Devon, 1890)Given by Warren de la RueMuseum no. 529-1880」 【1851年5月1日、ヴィクトリア女王による大博覧会開会式署名・日付:1851–1852年この有名な開会式の絵には、カンタベリー大主教が博覧会を祝福する場面が描かれています。王室一家は、委員や大臣、要人たちに囲まれています。式典には 2万5,000人以上 が出席しました。この絵画は当初から 商業的な可能性を利用する目的 で描かれ、多くの版画が販売されました。油彩・カンヴァス制作:ロンドン、ヘンリー・コートニー・セロウス(1803年ロンドン・デプトフォード生まれ、 1890年デヴォン州ビーヴォーシー没)寄贈者:ウォーレン・ド・ラ・ルー所蔵番号:529-1880】「グレート・エキシビション(1851年博覧会)」関連セクションに並んでいる家具・装飾美術品。1851年ロンドンの「大博覧会」で出品された、技術と芸術の粋を集めた家具・装飾品が並ぶ。・ゴシック・リヴァイヴァルの豪奢な椅子・陶磁器の一対の巨大装飾壺 高さのある装飾的なペア・ヴェース(urns / vases)。 黄金色に輝き、人物画(恐らく古代神話や寓意的テーマ)を描いた陶器こうした豪奢な装飾壺は、1851年の博覧会で各国が「技術力と美術性」を誇示するために出品した典型的な展示品であると。19世紀絵画ギャラリー内の展示。先程訪ねた「Britain 1760–1900」ギャラリー(展示室123–125C) の入口。・タイトル:Bust of Queen Victoria(ヴィクトリア女王胸像)・制作年:1843年・作者:Johann Jacob Flatters(ヨハン・ヤコブ・フラッターズ, 1786–1845) ・ドイツ(Krefeld)生まれ ・ロンドンで制作 ・1845年にパリで没・素材:大理石(Marble)「3 BUST of Queen Victoria 1843The youthful Queen Victoria is shown here as an idealised figure, in contrast with other, more lifelike portraits of her. She is dressed in a version of classical robes and wearsa wreath of roses in place of the laurel wreath of a Roman hero or emperor.MarbleCarved in London by Johann Jacob Flatters (born in Krefeld, Germany, 1786, died in Paris, 1845)Museum no. A.36-1952」 【3 ヴィクトリア女王の胸像 1843年ここでは若き日のヴィクトリア女王が理想化された姿として描かれています。これは、彼女のより写実的な肖像画とは対照的です。女王は古典的なローブの一種を身にまとい、ローマの英雄や皇帝が戴く月桂冠の代わりに、薔薇の花冠をかぶっています。材質:大理石作者:ヨハン・ヤコブ・フラッターズ(1786年、ドイツ・クレーフェルト生まれ ― 1845年、パリ没)ロンドンにて制作。所蔵番号:A.36-1952】この豪華な金色の卓上装飾は ヴィクトリア女王の即位50周年を記念する作品 であり、聖ジョージと勝利の女神を表現した アルフレッド・ギルバートの作品。写真はネットから。・中央:イングランドの守護聖人 聖ジョージ(St George) が竜を槍で突き刺す場面。・頂部:翼を広げた 勝利の寓意像(Victory) が軽やかに立つ。・土台:シェル(貝殻)のようにうねる形態で、流動的で躍動感のあるロココ的要素を持つ。・全体構造:下部から上部へ向かって螺旋的に視線を導く「動的構成」。 豪奢でありながらも上昇感を強調している。「2 CENTREPIECE commemorating the Golden JubileeCommissioned 1887, completed 1890This centrepiece was given by the officers of the volunteer military forces to QueenVictoria for her Golden Jubilee. It mainly shows the figure of St George, patron saint of England, which, thrusting his spear, overcomes a dragon, and the allegory Victoryon the top. Gilbert’s boldest ornamental work is the sculpture of Eros at Piccadilly Circus in London.Silver, parcel-gilt and gilted, chased and shell-shaped and made by Alfred Gilbert.Born in London 1854, died there in 1934Museum no. M.108-1960」 【2 センターピース ― ゴールデン・ジュビリー(在位50周年)記念1887年制作依頼、1890年完成このセンターピースは、志願兵軍団の士官たちからヴィクトリア女王に「ゴールデン・ジュビリー(即位50周年)」を記念して贈られたものです。主なモチーフはイングランドの守護聖人・聖ジョージで、槍を突き立てて竜を打ち倒す姿が描かれています。その頂部には「勝利(Victory)」の寓意像が置かれています。製作者アルフレッド・ギルバートの最も大胆な装飾作品は、ロンドン・ピカデリー・サーカスの「エロス像」として知られています。材質:銀(部分的に金鍍金)、打ち出しと彫金による装飾作者:アルフレッド・ギルバート(Alfred Gilbert, 1854–1934、ロンドン生まれ)所蔵番号:M.108-1960】ロンドンの アルバート記念碑(Albert Memorial, Kensington Gardens, 1872 完成) の縮小模型。後に訪ねた、実物のアルバート記念碑(Albert Memorial, Kensington Gardens, London)の写真。V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)館内のフロア案内柱(3階の表示)。V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の 4階(Level 4)エリア。奥に「CERAMICS」と書かれた入口 → ここから 陶磁器ギャラリー に入れた。手前のガラスケース → 「BRITAIN」とラベルがあり、18世紀~19世紀のイギリス製セラミック(磁器・陶器フィギュア、ティーポット、装飾壺、胸像など)が多数展示。「CERAMICS(陶磁器ギャラリー)」入口。部屋番号は 「Rooms 139–146」 と表示。・世界最大級の陶磁器コレクションを誇るエリアで、中国・日本・中東・ヨーロッパ各地の作品が 一堂に展示。・ルーム番号ごとにテーマが異なり、例えば: ・ルーム 139–140 → イギリス陶磁器(Staffordshireフィギュアなど) ・ルーム 141–142 → 中国陶磁器(青磁・白磁・染付など) ・ルーム 143–144 → 日本陶磁器(伊万里、薩摩、京焼など) ・ルーム 145–146 → イスラム陶器、スペイン・イタリアのマヨリカ、ルネサンス陶磁器 など・陳列はガラスケースを中心に、用途別(食器、装飾品、彫像)や地域別、年代別で 整理されていた。「Ceramics(陶磁器ギャラリー)」 内の展示ケース。・展示方法 陳列はガラスケースの中に、器形ごとに棚を分け、番号(1, 2, 3, 4 …)とラベルで解説が 付けられていた。・器の種類 主に 素朴な釉薬陶器(Earthenware)、特に スリップウェア(Slipware) と呼ばれる、 化粧土で模様を描いた陶器が多く並んでいた。 ・大皿(プレートやディッシュ) ・ジャグ(取っ手付き水差し) ・壺(ストレージジャー) ・ボウル ・小型のマグカップやタンカード・装飾技法 ・スリップ(化粧土)で描かれた渦巻きや幾何学模様 ・マーブリング(流し掛けによる模様) ・一部には釉薬の色変化(緑・黄・褐色)V&A博物館「Ceramics Study Galleries(陶磁器研究ギャラリー)」 の入口案内板「BRITAIN & EUROPECeramics Study GalleriesThese galleries house the most important study collection of ceramics in the world.It brings together the best of European ceramics and pottery from other parts ofthe world.The ceramics displayed are the best quality. They are arranged to give a representativepicture. The wide range in the galleries gives a sense of the scale of the collections,arranged according to place of origin and time of manufacture.For more information, please consult the Label Books provided. These give details ofevery object on display, arranged according to case and shelf number.This area is also used by students and researchers and is an important resource forthe study of ceramics.」 【陶磁器研究ギャラリーこれらのギャラリーは、世界で最も重要な陶磁器の研究コレクションを収蔵しています。ここにはヨーロッパの優れた陶磁器と、世界各地の陶器が集められています。展示されている陶磁器は最高品質のものであり、代表的な姿を示すように配置されています。ギャラリーの広範囲な展示は、このコレクションの規模を示しており、産地と製作年代に基づいて整理されています。さらに詳しい情報については、備え付けの「ラベルブック」を参照してください。そこには展示されているすべての作品について、ケース番号や棚番号ごとに解説が掲載されています。このエリアはまた、学生や研究者によっても利用されており、陶磁器研究の重要な資源となっています。】こちらは ヨーロッパ磁器(18世紀頃、ドイツやイギリス窯を想起させる作風) の展示ケースの一部。・25番と27番(花綱模様の小壺・対作品) Rococo(ロココ)様式を思わせる華やかなスクロール装飾と、濃いピンク(マゼンタ系) の彩色。壺の 中央には小さな花籠や人物のレリーフが付けられており、磁器彫刻と絵付けの 融合が見られます。・26番(人物小像:樽に座る子供) バロック以降のヨーロッパ磁器人形(MeissenやChelseaの影響が顕著)。牧歌的で愛らしい 子供像が題材で、日常生活や祝祭の一場面をユーモラスに表現しています。・中央奥(蓋付き壺/ポプリ壺のような器) 上に子供が座る人物像を冠し、器全体は白磁にピンクの帯飾り。ロココ後期の室内装飾を 彩る室内器で、香料や花を入れる「ポプリ入れ」の可能性が高いです。・28番(女性像) 白磁を基調とした人物彫刻。花を抱える女性の姿は「春」や「豊穣」の寓意像か、または 牧歌的な田園の乙女像を表したものと考えられます。18世紀ヨーロッパ磁器人形(フィギュリン) の展示群。左右には ロココ風衣装の男女 が並んでおり、楽器を奏でたり踊ったりする姿が見えます。これらは「田園の祝宴」「舞踏会」など、18世紀ヨーロッパ貴族社会の牧歌的・華やかな理想像を反映したシリーズの一部と思われます。19世紀ヨーロッパの高級磁器(特にフランスのセーヴル Sèvres あるいはドイツのマイセン Meissen 系列)。1.手前左の蓋付きカップ&ソーサー ・側面に風景画(渓谷と川、断崖)が細密画として描かれている。 ・金彩の葉模様(oak leaves? laurel?)が縁取りを飾っている。 ・19世紀のセーヴル工房やベルリンKPM磁器に見られる「風景画入り磁器」の典型。2.手前右のカップ&ソーサー ・カップには胸像肖像画(若い女性、赤毛〜茶色の髪、白衣)が描かれている。 ・周囲を金彩の星形パターンとロイヤルブルーの縁取りで装飾。 ・肖像磁器(Portrait porcelain)は19世紀に大流行し、貴族や有名人のイメージが 多数描かれました。3.奥中央のターコイズブルーのオブジェ ・複雑な形状(透かし窓と装飾柱)、濃いターコイズと白金彩。 ・香水瓶、あるいは記念的な装飾置物の可能性。セーヴル工房の豪華な見本市向け作品に 似ています。4.奥の赤褐色(プラム色)の花瓶 ・白のガーランド(花環状)文様と金彩。 ・これもセーヴルやウィーン磁器のレパートリーに典型的。このショーケースの陶磁器群は、19世紀ヨーロッパ磁器の「装飾絵画的表現」をよく示す作品。特にセーヴル(Sèvres)、ベルリンKPM、ウィーン窯などに典型的な要素が見られる。1.左の花瓶(青地に金彩装飾、白い図像のパネル)・濃いターコイズブルーに金彩の唐草文様。・白いレリーフ風の図像(愛らしい子供=プットー像)が矩形パネルに描かれる。・これは「セーヴル風の画中画」手法で、19世紀後半に流行。2.中央左の皿(白い半透明の図像)・青地に白い人物像(神話的場面かヴィーナス像)。・これは「ジュリアス・クルッツ風のKPM」や「セーヴルの pâte-sur-pâte(透かし技法)」に 近い表現。・pâte-sur-pâte とは、磁器の上に白い磁土を何層も塗り重ねて透け感あるレリーフを作る技法。3.中央の大きな壺形花瓶・青地に白いプットー像(天使/キューピッド)、金彩の台座と持ち手。・これは完全にセーヴル工房のpâte-sur-pâteスタイル。・「豪華磁器の頂点」とされ、万博や王室献上品に多く使われた。4.右の皿(子供たちのモノクロ風図像)・まるで版画のように、2人の子供(プットー)が布を持ち戯れる姿。・「グリザイユ装飾(Grisaille painting)」と呼ばれる、単色(灰色・茶色)で陰影を描く技法。・古典主題を「絵画的磁器」にした典型例。5.右下の白い籠(透かし細工)・白磁のレース細工のような透かし編み。・マイセン窯やドレスデン窯の名技法「籠細工(basketwork porcelain)」の系譜。展示室「139室」の入口。遠方の壁に「2000–」という表示 → 「2000年以降」のセクション(現代デザイン/コンテンポラリー展示)の方向である。陶磁器展示室(Ceramics Study Galleries)139室 の内部。・左壁面に「1900–2000」、右壁面に「2000–」の文字 → 20世紀から21世紀の陶磁器を 時代順に展示。・大型のガラスケースに、国際的な陶芸作品が多数並んでいた。・中央に案内デスクがあり、学芸員らしき人物が立っていた。展示の内容1.1900–2000(左側)・アール・ヌーヴォーやアール・デコの陶磁器・モダニズム陶芸、英国スタジオ陶芸(バーナード・リーチ、ルーシー・リー、ハンス・ コッパーなど)・欧米のデザイン陶器(ミッドセンチュリー)2.2000–(右側)・現代陶芸・コンテンポラリーアートとしての陶磁器・インスタレーション的作品や彫刻的アプローチの陶器・国際的デザイナーや現代作家による試み(日本の現代陶芸家の作品が含まれる場合もある)V&A陶磁器展示室(Ceramics Study Galleries, Room 139) の一角をさらに。中央ガラスケースには各時代の代表的な作品が「選抜展示」として置かれ、周囲の壁面展示と対応しているのであった。1.1900–1925・アール・ヌーヴォー様式の陶器(流麗な植物文様、線的装飾)・初期アール・デコ(幾何学的デザイン)・イギリスやフランスのアート・ポタリー(ドールトン、クラリス・クリフ前期など)2.1975–2000・現代デザイン陶器・スタジオ陶芸(ルーシー・リーやハンス・コッパーに続く世代)・実験的な釉薬や造形を取り入れたコンテンポラリー作品・インダストリアルデザインの影響を受けた日常食器20世紀前半〜中頃のセクションの中央ケースに並べられた作品群。① 左手前:オレンジ色の壺(ジャー)・特徴:鮮やかなオレンジ地に、幾何学化された山や稲妻のようなデザイン。・様式:アール・デコ(1920–30年代)。・作家/工房:クラリス・クリフ(Clarice Cliff, イギリス)による「バイザンタイン」や 「ブルータス」シリーズに近い作風。・意義:大量生産陶器にアバンギャルドなデザインを導入し、日常生活にモダンアートを 持ち込んだ。② 右手前:紫と青の縞模様の壺・特徴:細かい放射状の縞模様、球体に近いフォルム。・様式:バウハウスやモダニズムの影響を受けた装飾性。・背景:1920〜30年代に流行した幾何学的意匠。ドイツやチェコスロヴァキアの工房にも 類似品がある。③ 中央:金色に輝く立像・特徴:人物像を立体的に表現。表面は金属光沢(ラスター彩)。・様式:アール・デコ彫刻風。陶芸と彫刻の中間的存在。・背景:Susie CooperやRoyal Doultonといった英国スタジオ陶芸でも人形的造形が展開された。④ 奥の壺(茶色)・特徴:幾何学模様の帯装飾。落ち着いた色彩。・背景:20世紀初頭のアーツ・アンド・クラフツ運動やスタジオ・ポタリーの伝統を継承。⑤ 右奥の白地+青紫の小皿・特徴:放射状の幾何学模様。・様式:アール・デコ。ティーセットやサーヴィスの一部。・背景:クラリス・クリフやSusie Cooper作品と同じ潮流。セラミックス部門の展示室「Room 140」 の入口。・Room 139(前の写真)には「2000–」や「1975–2000」と書かれたセクションがあり、 20世紀後半から21世紀の陶磁器が並んでいました。・この Room 140 は、その流れを受けて「現代陶磁器」や「特別テーマ展示」に接続する 空間で、モダンな作品や新素材を取り入れた実験的な陶芸作品が展示されています。V&A Ceramics Study Galleries(陶磁器スタディ・ギャラリー、4階部分)。この Room 140 は、その流れを受けて「現代陶磁器」や「特別テーマ展示」に接続する空間。壁面サインに「Contemporary Ceramics」と明示。床は寄木張り、黒い展示台がカーブして作品を並べていた。写っている主な作品:左:地図や風景を描いた装飾壺中央:白い布を巻き付けたような大きな彫刻的陶器右:穴の空いた網状の白い陶彫奥:横たわる人物像のような陶彫韓国の現代陶芸家 郭魯勳(Guac Roh-Hoon)による《Form–Series I》(2005年)。「Guac Roh-Hoon (born 1959)‘Form-Series I’2005This monumental piece depicts three trees, blended together through their foliage. It was entirely builtusing small coils of clay assembled in a delicateopenwork structure. The technical virtuosity of this Korean artist balances weightiness and lightness,drawing on a rudimentary method to build a complex and elegant sculpture.Made in South KoreaMixed clay」 【郭魯勳(Guac Roh-Hoon, 1959年生『Form–Series I(フォーム・シリーズ I)』2005年この記念碑的な作品は、3本の樹木が枝葉を通じて一体化した姿を描いています。小さな粘土の紐を用い、精緻な透かし構造として組み上げられたものです。この韓国人アーティストの高度な技術は、重厚さと軽やかさを巧みに調和させ、素朴な方法を用いながらも複雑で優雅な彫刻を創り出しています。制作地:韓国素材:混合粘土】ギャラリー番号(Room 141)。・エリア:V&A 4階、Ceramics Galleries(陶磁器ギャラリー)の一部・テーマ:近現代の陶芸を中心に展示・近接する Room 144「Contemporary Ceramics」 とつながっており、先ほどの Guac Roh-Hoon《Form–Series I》 など現代陶芸作品はこの一連のエリアに展示されていた。・中央展示:大きな抽象的な壺(現代陶芸、破片を重ねたような造形)・左右のガラスケース:古代から近代までの陶磁器コレクション(壺・瓶・器など)を並べている。・床:寄木張りのフローリング(V&Aの陶磁器ギャラリー共通の特徴)。・奥の扉:黒い大理石風の枠に囲まれた通路。そこから隣のギャラリーに続いている。【ピーター・ヴォルコス(Peter Voulkos, 1924–2002)作の《ピナトゥボ(Pinatubo)》。作品名はフィリピンの活火山「ピナトゥボ火山」に由来。1991年の大噴火を想起させる題名。「スタック(stack=積み重ね)」と呼ばれる彼の後期の代表的なフォルム。崩壊寸前の塔や噴火後の火山体を思わせる有機的な造形で、力強さと不安定さが同居。焼成によって生じた多層的で荒々しい表面(ひび割れ、焦げ、溶けなど)は、薪窯特有の偶然性・即興性を捉えている と。「Peter Voulkos (1924–2002)‘Pinatubo’1994Peter Voulkos was a pivotal figure in post-war American ceramics. His work wasinstrumental in positioning ceramics as a form of abstract sculpture. This monumental ‘stack’ from his later period appears in a state of near-collapse. Its rich surface captures the spontaneity of the wood-firing process. The title is a reference to an active volcano in the Philippines.New Jersey, USAStoneware, wood-fired」 【ピーター・ヴォルコス(Peter Voulkos, 1924–2002)《ピナトゥボ(Pinatubo)》1994年【ピーター・ヴォルコスは、戦後アメリカ陶芸における重要人物であり、陶芸を抽象彫刻の一形態として位置づける上で決定的な役割を果たしました。この記念碑的な「スタック(積層造形)」は、彼の後期の作品であり、崩壊寸前の状態を思わせます。その豊かな表面は、薪窯焼成の自発性を捉えています。作品タイトルは、フィリピンの活火山ピナトゥボ火山に由来しています。制作地:アメリカ合衆国ニュージャージー州素材:ストーンウェア(陶器)、薪焼成】4階 Ceramics Galleries(Room 137–146) のうち、特に 英国やヨーロッパの陶磁器展示室。・左右に長く伸びる「ギャラリー型の展示室」・長い天窓(トップライト):自然光が入る白いアーチ型天井。・展示ケース:左右の壁面と中央にガラスケースが並び、食器・陶磁器コレクションを展示。・展示内容:右側のケースには18~19世紀ヨーロッパの磁器(ティーセットや装飾皿)が 見えた。「Making CeramicsOver the course of thousands of years, potters have developed a virtually endless variety of making and decorating ceramic materials. At the centre are the hand-modelled, firedvessels, but each phase of the potter’s art has also inspiredother processes, made for making complex procedures and craft with elaborate decoration.This gallery explores many of the most important of these materials and processes. The basic principles of the techniques are introduced (from the earliest use ofhand-forming and decoration) plus the context of the room, including the importance of workshops and studios. Potters have often worked in workshops or factories. Many of these galleries include a working environment. The gallery also exploresthe global dimension of ceramics by showing how materials and techniques have beenshared and adapted between cultures.The gallery includes a working ceramic studio with a changingprogramme of workshop classes, artist-in-residence,demonstrations and similar activities.」 【陶芸の制作数千年にわたり、陶工たちは実に無限ともいえる多様な陶磁器の制作法と装飾法を発展させてきました。中心となるのは手で形作り、焼成された器ですが、陶芸の各段階はまた、複雑な工程や精緻な装飾を伴う他の技法を生み出してきました。このギャラリーでは、そうした最も重要な素材や工程を数多く紹介しています。基本的な技法の原理(最初期の手びねりや装飾の使用から)に加え、作業場や工房の重要性など、その文脈も提示しています。陶工はしばしば工房や工場で活動してきました。これらのギャラリーの多くには、実際の作業環境を再現した展示が含まれています。さらにこのギャラリーは、陶芸の素材と技法が文化を越えてどのように共有・応用されてきたかという世界的な広がりも探究しています。またこのギャラリーには、実際に陶芸を行うスタジオがあり、ワークショップ、アーティスト・イン・レジデンス(滞在制作)、実演、その他の活動が随時行われています。】このケースは 「Making Ceramics(陶磁器の制作)」の一部 で、特に 青花磁器の制作過程 を紹介。中央の二つの大壺・左側:白素地の壺(装飾前の状態)。上下で分割できるようになっており、焼成工程や 成形過程を示す「展示用のプロセスモデル」。・右側:青花の風景画で装飾された完成品の大壺。典型的な 中国の青花磁器 (Blue-and-White Porcelain) の様式で、山水図が描かれています。背景の展示物・上段:青花の皿や鉢(龍文様や幾何学文様)。明・清代中国の典型的な輸出磁器スタイル。・下段:型や半製品、小さな碗類。磁器製造のプロセスを学べる教育的展示。ここも陶磁器ギャラリー(Ceramics Galleries) の入口の一つ。・部屋番号 143 左上に「143」の表示があり、これはギャラリー番号。・上部の黒いサイン 「CERAMICS」 とあり、その下に 144–146 と番号が書かれていた。つまり、この入口を 進むと陶磁器ギャラリーの 144~146室に繋がるということ。・右の青いパネル「Making Ceramics」の解説パネル。陶磁器制作の展示テーマの紹介。・左の壁の陶板彫刻 白地に彩色のレリーフで、聖母子像。イタリア・ルネサンス期のデルラ・ロッビア工房 による「マヨリカ装飾陶板」のような作品。マヨリカ陶器のストーブ(Majolica stove)。特徴・形状:塔のように縦に積み上げられた円筒形のストーブ。上部に装飾的な壺が載せられていた。・材質:鉛釉をかけた陶器(マヨリカ焼)。・装飾:リリーフとして ・豊穣を象徴する果物や花のガーランド ・神話や寓話的な場面のメダリオン ・紋章を囲むような象徴図像 などが表現されています。・用途:本来はヨーロッパの邸宅で暖房に用いられた陶製ストーブ。移動して正面から。・中央の大メダリオン ・上部には盾型のモチーフと王冠的装飾。紋章を思わせる意匠で、貴族的権威や家系を 象徴している可能性があります。・下部の円形メダリオン ・人物群像の浮彫(複数の人物が集まり、祭礼または神話的な場面を描いているように見える)。 ・ガーランド(花綱)に囲まれており、豊穣や祝祭のシンボル。・全体を囲む装飾 ・果実や花を組み合わせたガーランドが連続しており、古代ローマ以来の「豊穣」「祝福」を 意味する装飾モチーフ。・上部の壺(アーバン) ・四方に獣頭(雄羊など)が突き出し、その周囲にも果実のレリーフ。 ・これも収穫・犠牲・繁栄を象徴する要素。左側面。・上部に大きな壺状の装飾・花綱(ガーランド)や果物のレリーフ・メダリオン(楯形の浮彫)に神話・寓意・紋章的モチーフ・古典様式(円形ロゼットや葉飾り)が多用され、新古典主義的デザインを反映右側面。・上部:壺型の飾りには、羊(あるいは雄羊)の頭部レリーフ、果実や葉のガーランドが 絡みつき、豊穣と繁栄を象徴。・胴部(円筒部分): ・ロゼット(花型装飾)の連続模様。 ・その下には「ガーランドを支える仮面(マスク)」モチーフ。古代ローマの祝祭や劇場文化を 連想させます。・円形メダリオン(下部正面):人物群像の浮彫。神話的あるいは寓意的場面が描かれていた。・右側突起部分:炉の実際の燃焼部につながる構造。装飾パネルにもロゼット模様が施されており、 機能部も美観に合わせていた。イギリスにおける 1800年以降の壁タイル(English wall tiles after 1800)。・上段左(赤地に牛と農夫):ラスキンやモリスの影響を感じる農耕図。・縦長の天使図(中央左):宗教的・寓意的なモチーフ。・青地の植物文様(中央右):ウィリアム・モリス風の自然主義的装飾。・縦長の幼児像(右端):ルネサンス風、アーチ装飾の中の裸児。・下段の獅子文タイル・モノグラム文様:装飾的シンボルとしての壁面装飾タイル。「English wall tiles after 1800From the 1830s, a new industry for domestic and industrialarchitectural ceramics evolved in England. Factories in theStaffordshire Potteries produced large quantities of wall tiles,...」 【1800年以降のイギリス壁タイル1830年代以降、家庭用および産業用の建築陶器の新しい産業がイングランドで発展しました。スタッフォードシャー・ポタリーズ(陶磁器産業地帯)の工場では、大量の壁タイルが生産され、…】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.02
コメント(0)
-
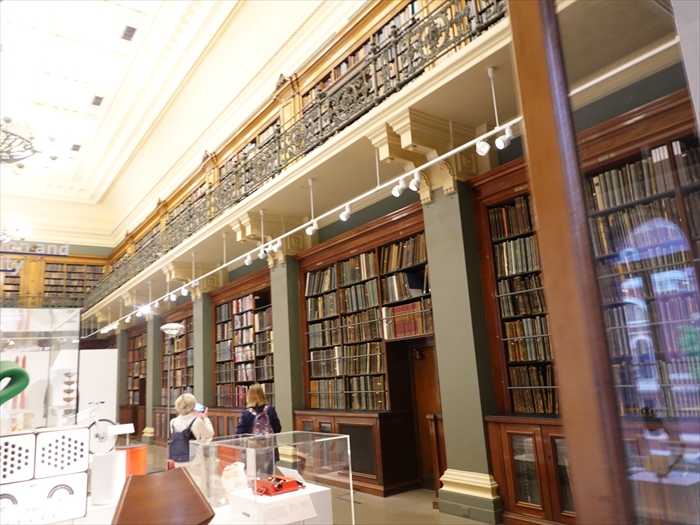
アイルランド・ロンドンへの旅(その126): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-9
【海外旅行 ブログリスト】👈リンク部屋の全景をネットの写真から。Design 1900–Nowギャラリーの長い通路・Room NO 76.V&A の National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー) の書庫が見える一角二層吹き抜けに鋳鉄の手すり、壁一面の木製書架、天窓からの採光という内装が決め手。手前にあるプロダクトの展示ケースは、ギャラリー側の通路に置かれており、ガラス越しに実際のライブラリーの本棚が見える構成になっていた。中の書籍は本物で、閲覧は登録制(閲覧室は別室)とのこと。・英国随一の装飾美術・デザイン専門図書館。展覧会図録、装飾美術・建築・ファッション・ 写真などの大型資料や雑誌合本を所蔵。・書庫はクローズドスタック(直接は取れず、請求して閲覧)。閲覧室の参考棚のみ開架。利用の基本(実務メモ)・無料で利用可。ただし資料の閲覧は利用者登録(身分証)が必要。・事前にオンラインで請求→来館時に閲覧、の流れが標準。・閲覧室では通常鉛筆のみ使用、飲食不可。資料撮影は可否が分かれるので 係員の指示に従う。・落下防止バー:各段の前面に通る金属バー。地震・人の動き・清掃時に閲覧ゾーン側への 落下防止&整列保持の役割。 必要に応じて上げ下げして本を出し入れしする と。・下段のガラス扉:大型判(フォリオサイズ)の画集・製図集・製本済み雑誌などを収納。 湿度や埃から守るためガラス扉付き と。「Design 1900–Now」ギャラリー側通路から見た、National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー)書庫の外壁。右手の背の高い木製書架は図書館の実物の書庫、左手の白い展示ケースと“Sustainability and Subversion”のサインはデザイン・ギャラリーのテーマ展示の一部。二層構成になっており、上階は鋳鉄手すりの回廊、天井からシャンデリア。「Design 1900–Now」ギャラリー通路から見た、National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー)書庫の外壁。右側:John Madejski Garden左側:National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー)の入口 金文字「NATIONAL ART LIBRARY」扉はこの左壁沿い(写真フレーム外)にあった。前方:西(Room 74 側)Level2のMAP。■がRoom NO 76そしてこれが金文字「NATIONAL ART LIBRARY」の入口。近づいて。Art Library(閲覧室)への入口。Art Library(閲覧室)内部の写真。・まっすぐ先のガラスの両開き扉が、外の Design 1900–Now(Room 76)通路へ戻る出入口。・右側のアーチ窓は 南側(外光が入る窓列)。・左側の高い本棚の壁が 北面で、この壁の向こう側が先ほど歩かれた展示通路(Room 76)。・机の並びや緑色シェードのスタンドは、閲覧室の標準レイアウト。ズームして。・机が整然と並び、緑のスタンドランプと胸像(バスト)が列状に配置されているのが 閲覧室の標準レイアウト。・画面一面に見える高い本棚の壁は、歩いた Design 1900–Now(Room 76)の通路と 背中合わせの“北面”。・金文字「NATIONAL ART LIBRARY」の入口は、この本棚の並ぶ北面の中央付近 (写真の右奥方向にあたる位置)にあった。 扉を出ると、先ほどの展示通路(Room 76)に出た。中庭南辺の通路(Room 76)から東寄り(No.25 付近)の階段/エレベーターで Level 3 へ上がり、Rooms 118–125 の表示に従って進む。V&A の “BRITAIN (1760–1900)”(British Galleries)への案内サイン。表示の 118–…(~125c など) は該当する部屋番号を示す。産業革命期からヴィクトリア時代までの英国の家具・銀器・陶磁・室内装飾などを展示。このケースは、V&Aの英国ギャラリーで紹介されているVasemania(花瓶熱)を一望できる展示。正面から。18~19世紀の新古典主義期、古代ギリシャ・ローマの「壺(vase)」の形や装飾が大流行し、実用品や室内装飾までをも壺風にしてしまった――という現象を、実物で示していたのだ。・中央の大壺:古代ギリシャのクラテル(混酒壺)型。黒地に赤い人物像の帯状画 (赤絵式”を思わせる意匠)で、18~19世紀の工房が古典壺を写したり 再解釈して作ったもの。 暖炉やコンソール上に飾る「ガーニチャー(壺飾りの組)」の主役であった。・上段の小ぶりの壺群:取っ手付きのアンフォラやオイノコエ型など、古典形のバリエーション。 素材は磁器・ストーンウェア・ガラスなどさまざま。・右下の金色の燭台:よく見ると胴体が「壺の胴」形。花瓶のフォルムが燭台・茶筒・香水瓶 などの実用品にも転用されたことを示す好例です。・左右に見える色ガラスの器:多層ガラスを削って文様を出すカメオガラスや、色被せ ガラスに金彩を施したものなど、壺モチーフがガラスにも波及 したことが分かります。・背面の赤×金の額装パネル:メダリオン(円形レリーフ)や古典主題の装飾で、壺と同じ 古代趣味を室内全体の意匠に広げた例。 ・18世紀後半、ウェッジウッド(Josiah Wedgwood)が壺形の器を大量に生産し、彼自身が この流行をvasemania(花瓶狂)と呼んだ。 ・ポンペイやヘルクラネウムの発掘、ギリシャ壺の版画集の出版(コレクターのハミルトン卿 など)がデザイン資料となり、陶磁器・金工・ガラス・家具の意匠にまで壺の語彙が 広がった。「VasemaniaLabels for the objects in this case are in a booklet to the right of the case.Vases were a very important element of the Neo-classical style. The pottery manufacturer Josiah Wedgwood, who could hardly make them fast enough, spoke of“vasemania”. They appeared as three-dimensional objects and as decorative motifs. Vase forms also influenced the shape of practical items of all sorts, from teacanistersto candlesticks. Designers plundered sources far and wide for new designs, from Greekpottery to 16th- and 17th-century prints.」【ヴェーズマニアこのケース内の各作品ラベルは、ケース右手に置かれた冊子にあります。花瓶は新古典主義様式において非常に重要な要素でした。陶磁器メーカーのジョサイア・ウェッジウッドは、需要に追いつけないほどで、この現象を「ヴェーズマニア」と呼びました。花瓶は立体作品としてだけでなく、装飾モチーフとしても登場しました。さらに花瓶の形は、茶葉用キャニスターから燭台に至るまで、実用品の造形にも影響を与えました。デザイナーたちは新しい意匠を求め、ギリシャの陶器から16~17世紀の版画にいたるまで、広範な資料を貪欲に参照しました。】国王のゴールド・ステート・コーチの模型。・ロココ~新古典主義的な重厚な鍍金装飾に、四隅や側面にトリトンや海のモティーフが。・実物のゴールド・ステート・コーチは戴冠式や大規模な儀礼で使われる王室馬車で、 ここでは展示用の縮尺模型として紹介されていた。・手前のパネルが下の説明板(オブジェクト番号 53)。 材質や設計者・装飾担当者の名がまとめられていた。材質:鍍金・彩色木、金属、絹、革、ビロード張り。設計:ウィリアム・チェンバース(1723–1796、スウェーデン生)絵画:G. B. チプリアーニ(1727–1785、イタリア)彫刻:ジョゼフ・ウィルトン(1722–1803、英国)製作(車体):サミュエル・バトラー(活動 1749–1798、英国)発注:王室(国王造営局)〔ジョージ三世の戴冠に関連して〕。この模型は1760年ごろに作られた。実物のゴールド・ステート・コーチは戴冠式や大規模な儀礼で使われる王室馬車で、ここでは展示用の縮尺模型として紹介されていた。「53 MODEL OF THE STATE COACHAbout 1760The basic design of this State Coach was intended to reflect Britain’s [power] underthe new King George III. In the decoration by William Chambers, [painted] panels by Giovanni Cipriani and carving by Joseph Wilton show [sea-gods] and figures of[Tritons] symbolising sea-power. The coach has been used since 1762 and is still used onimportant ceremonial occasions.Gilded and painted wood, metal, silk, leather and velvet upholsteryDesigned by William Chambers (born in Gothenburg, Sweden, 1723–1796); painted byGiovanni Battista Cipriani (Italian, 1727–1785); carving by Joseph Wilton(British, 1722–1803); coach built by Samuel Butler (British, active 1749–1798). Commissioned for the Office of the [King’s/Works] for the [Coronation] of George III; completed in 1762. This model was made c.1760.Museum no. [----]」【53 国王のゴールド・ステート・コーチの模型1760年ごろこのステート・コーチ(王室儀礼用の馬車)の基本設計は、新王ジョージ三世のもとでのイギリスの(海上)パワーを表す意図で作られました。建築家ウィリアム・チェンバースのデザインにより、ジョヴァンニ・バッティスタ・チプリアーニの絵画パネルと、ジョゼフ・ウィルトンの彫刻が施され、トリトン(海神)などの像が海軍力を象徴しています。実物のコーチは1762年に完成し、以後も重要な国家儀礼で用いられてきました。】 「Britain (1760–1900)」セクションに展示されている部屋の装飾の一部。壁面と扉を含む豪華なインテリアで、19世紀の英国室内装飾様式を示していた。・扉 緑色の地に金の装飾枠をあしらった両開きのドア。枠には古典的なアカンサス文様や 幾何学的パターンが施され、華やかな仕上がり。・壁面パネル 深紅の地に、金の植物文様・幾何装飾が浮き上がるデザイン。ネオクラシカルな 「シンメトリー」と「規則性」が強調されており、18世紀末から19世紀初頭に流行した様式。・円形メダリオン画 扉の上には円形画(メダリオン)が額装されており、古典風の人物群像が描かれている。 これは神話や寓意画を題材にしている可能性が高く、部屋全体のテーマ性を示す装飾の一部。・装飾要素 周囲には丸いロゼット(花飾り)、蔓草文様、金の縁取りが連続しており、ルネサンス風・ 古代ローマ風のモチーフを取り入れている。「32 PART OF THE GLASS DRAWING ROOM, NORTHUMBERLAND HOUSE, LONDONDesigned from 1770; made 1773–1775This panelling was from the glittering drawing room, panelled entirely in glass, that the architect Robert Adam designed for the 1st Duke and Duchess of Northumberland at their London house in the Strand. The scheme was based on the richly ornamentedinteriors of ancient and modern Rome. Adam used glass backed with coloured pigmentsand metal foils to imitate the porphyry of Roman decoration and copied plaster and painted decoration in gilded metal, cast from moulds.Given by Dr. R. A. McIntosh FSAMuseum No. W.12-1972」【32 ガラス張り応接室の一部 ノーサンバーランド・ハウス(ロンドン)1770年に設計、1773~1775年制作このパネル装飾は、ロンドンのストランド通りにあったノーサンバーランド公爵・公爵夫人邸の、きらびやかな「ガラス張り応接室」から移されたものです。建築家ロバート・アダムが設計しました。デザインの構想は、古代ローマと近代ローマの華麗な装飾的室内に基づいています。アダムは、ガラスの裏に着色顔料や金属箔を貼り、ローマ装飾に見られる斑岩(ポルフィリー)を模倣しました。また、石膏細工や彩色装飾を、鋳型で鋳造した金メッキ金属で再現しました。寄贈者:R.A. マッキントッシュ博士(FSA会員)収蔵番号:W.12-1972】 ピア・グラスに取り付けられた祭壇額。・「ピア・グラス(pier glass)」とは、壁と壁の間(柱=pier の間)に置かれる大型の姿見鏡を 意味します。しばしば家具調の装飾が施され、室内を豪華に見せる効果がありました。・この鏡は、先ほどの案内板にあった「ノーサンバーランド・ハウスのガラス張り応接室」の 一連の装飾の一部であり、部屋の豪華さを象徴する重要な要素 と。・フレームの左右に配置された人物像(天使や寓意像)は、当時流行したネオクラシカル装飾の 典型で、金箔仕上げによって室内照明の輝きをさらに増す役割を果たしました。「38 MIRRORMounted in a pier glass1770–1771This pier glass was made in Rome between 1770 and 1771 for Robert Adam, one of the most fashionable architects in England. It was designed for the glass drawing room at Northumberland House, London. The richly carved and gilded frame was made by Seffer in Alken, one of the best carvers in London in the 18th century.Carved and gilded wood frame」 【38 ピア・グラスに取り付けられた祭壇額1770–1771年このピア・グラス(大きな姿見鏡)は、1770年から1771年の間にローマで制作され、当時イギリスで最も人気のあった建築家の一人、ロバート・アダムのために作られました。ロンドンのノーサンバーランド・ハウスにある「ガラス張り応接室(Glass Drawing Room)」用に設計されたものです。】イギリス・ギャラリー(1760–1900) の展示風景で、18世紀末から19世紀にかけての「ファッショナブルな暮らし(Fashionable Living)」をテーマにした一角。・中央の肖像画 中年の男性像で、イギリスの富裕層あるいは文化人を描いた肖像画。家具とともに展示され、 邸宅の室内装飾を再現。・左右の小型楕円画(オーバル絵画) 神話または寓意的な場面を描いた小型絵画。肖像と組み合わせて飾られており、当時の邸宅の 壁面装飾の一例を示している。・家具類 中央の金彩のコンソール・テーブル:ロココから新古典主義へ移行期に流行した、壁際に置く 装飾的な半卓。 緑張りの椅子、透かし細工の背もたれ椅子など、デザインの異なる椅子が並べられ、 18世紀後半~19世紀前半の室内様式を比較できるようになっている。・左端の展示物 ガラスケース内にシャンデリア付きの楕円鏡(Irish Mirror with Chandelier, 1780–1790) が見えており、アイルランドのカットグラス産業の発展を示す展示が隣接している。44 IRISH MIRROR WITH CHANDELIER・アイルランド製 鏡付きシャンデリア1780–1790。・楕円形の鏡の前に、カット・グラスで作られたシャンデリアが取り付けられています。・鏡がシャンデリアの光と煌めきを反射し、室内をより豪華に演出する仕組み。・細かくカットされたガラスのプリズムやドロップ(涙型パーツ)が光を乱反射させ、 ダイヤモンドのような輝きを放ちます。・この構造は、18世紀末のアイルランドで発展したガラス工芸の特色をよく表している。「44 IRISH MIRROR WITH CHANDELIER1780–1790In the last twenty years of the 18th century Ireland developed a thriving glass industry,which supplied its own markets as well as those of Britain. Mirrors set with a cut-glasschandelier were an Irish speciality. The Neo-classical style, with its emphasis on glitterand small-scale detail, was particularly suited to the decoration of cut-glass for lighting.Cut glassMade in Ireland, possibly in DublinMuseum no. C.6-1974」 【44 シャンデリア付きアイルランド製鏡1780–1790年18世紀後半の20年間、アイルランドは活発なガラス産業を発展させ、自国市場だけでなく英国市場にも供給していました。カット・グラス製のシャンデリアを組み込んだ鏡は、アイルランド特有の製品でした。きらめきと精緻な細部を強調する新古典主義様式は、照明用のカット・グラス装飾に特に適していました。素材:カット・グラス制作地:アイルランド(おそらくダブリン)】V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)「THE WOLFSON GALLERIES(118)」 の入口部分。・The Wolfson Galleries(ウルフソン・ギャラリー) は、V&Aの中で18世紀から19世紀に かけてのイギリス美術・工芸を集中的に展示しているエリア。・ギャラリー番号 118 は、その中でも「産業革命期の工芸」「新素材・新技術」 「ファッショナブルな暮らし」といったテーマを取り扱う区画の一つです。・入り口横のパネルには「Developments in the Metal Trades 1740–1840(1740〜1840年の 金属産業の発展)」などの展示解説が掲示されており、産業革命期の英国を象徴する工芸品 (シェフィールド・プレート、カット・スティール、ブリタニア・メタルなど)が 紹介されていた。「WHAT WAS NEW?Developments in the Metal Trades 1740–1840Between 1740 and 1840 the metal trades expanded dramatically. New materials were energetically exploited and new techniques of manufacture and marketing were applied.These advances resulted in a wide range of cheaper goods. The search for cheapsubstitutes for silver led to the invention of Sheffield plate, made from copper with a fine layer of silver. Alloys such as Britannia metal and Pakfong, a golden-coloured metal from China, were also used. Japanning imitated lacquer with paint. Brittly goodsandjewellery were decorated with cut steel that sparkled like diamonds.The use of labour-saving machinery meant that goods could easily be made in standard forms. These goods could then be exported and sold throughout the world.」【新しいものは何か?金属産業の発展 1740–18401740年から1840年の間、金属産業は飛躍的に拡大しました。新しい素材が積極的に利用され、製造や販売の新しい技術が導入されました。これらの進歩により、安価な製品が幅広く生産されるようになりました。銀の代用品を求めた結果、シェフィールド・プレートが発明されました。これは銅に薄い銀の層をかぶせたものでした。また、ブリタニア・メタルや、中国から伝わった金色合金の「パクフォン」も使用されました。さらに「ジャパニング(Japanning)」と呼ばれる漆の模倣技法が塗料で施され、鋼を細かくカットした装飾は宝石のように輝き、装飾品やジュエリーを飾りました。労力を節約する機械の利用によって、製品は標準化された形で容易に大量生産されるようになり、輸出され、世界中で販売されました。】 作品名:The Campbell Sisters dancing a Waltz ワルツを踊るキャンベル姉妹作家:Lorenzo Bartolini(1777–1850、イタリア) 。・特徴 ・二人の若い女性・キャンベル姉妹 Emma & Julia の二人が寄り添って歩く姿。 ・衣の表現は古代風のトーガ風で、流れるような薄布の表現はカノーヴァ派の特徴。 ・台座には花綱(ガーランド)が飾られ、祝祭的な雰囲気を添えている。・テーマ ・寓意像(友情 Friendship / 調和 Harmony / 優雅 Grace など) ・あるいは神話の二人の女性人物(ニンフや女神のペア)。 ・新古典主義では、神話的題材を「理想化された女性像のペア」として表現することが多く、 この作品もその系統。「FASHIONABLE LIVINGThe Private Sculpture GalleryMany British collectors developed a taste for classical sculpture during the Grand Tour of the mid-18th through Europe as young men. On their return, the owners createdspecially designed settings for the sculptures they had bought, either in their London or their country houses.Such interiors could often be seen at Holkham Hall in Norfolk, where the Sculpture Gallery was established in the 1750s. At Syon House, Robert Adam designed a sculpture gallery during the 1760s.In the early 19th century, a new interest in contemporary sculpture, in the classical style, developed, aimed at the decoration of fashionable domestic interiors.In Britain, the leading sculptor was Antonio Canova’s pupil, Antonio d’Este, who produced idealised marble sculptures of mythological subjects.」【ファッショナブルな暮らし個人彫刻ギャラリー18世紀中頃、多くのイギリス人コレクターは「グランド・ツアー」(ヨーロッパ大陸への教養旅行)を通じて古典彫刻への嗜好を育みました。若者として大陸で学び、収集した彫刻を持ち帰ると、彼らはそれを展示するための特別な空間を、自宅のロンドン邸宅や地方の館に設けました。そのような室内装飾は、ノーフォークのホルカム・ホール(Holkham Hall、1750年代に彫刻ギャラリーを設置)や、ロバート・アダムが1760年代に設計したサイオン・ハウス(Syon House)の彫刻ギャラリーで見ることができます。19世紀初頭には、新古典主義様式の現代彫刻への関心が高まり、流行の邸宅インテリア装飾に用いられるようになりました。イギリスにおける代表的な彫刻家は、アントニオ・カノーヴァの弟子アントニオ・デステ(Antonio d’Este)であり、彼は神話的主題を理想化した大理石像を制作しました。】 V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の ブリティッシュ・ギャラリーの一室。・中央手前 黒い台座の上に大きな 犬の彫像(セント・バーナード犬のような姿) が置かれています。 白と黒のコントラストがあり、毛並みを強調した写実的な作品。・中央奥 大きなシャンデリアが天井から吊るされ、空間に豪華な雰囲気を与えている。・右手の壁面(黄色) 18世紀後半から19世紀の英国家具・調度品が並んでいる。金装飾の椅子やソファ、 楕円形の額鏡(オーバル・ミラー)、さらに壁面には肖像画や小型絵画が掛けられている。・左手の壁面(紫〜黒) 絵画や漆工芸品(日本や中国からの輸入品も含まれる)が飾られており、英国の室内装飾が 「東洋趣味(シノワズリー)」を取り込んでいた様子を反映している。British Galleries 1500–1900 の「19世紀室内装飾」展示の一部。・このセクションは、19世紀イギリス上流階級の邸宅サロンを再現する構成。・家具・肖像画・鏡・室内装飾を一体的に展示し、当時の「ファッショナブルな暮らし (Fashionable Living)」の様子を伝えています。・背景壁の黄色は、当時流行した室内色彩を意識した演出でもある。中央・楕円形の大きな鏡(オーバル・ミラー) ・豪華な金色の額縁に収められ、上部には羽根飾りのようなクラウン装飾。 ・19世紀初頭、リージェンシー様式やロココ復興の影響を示す華麗な意匠。左側・赤い張り地の寝椅子(カウチ/シェーズロング) ・金のフレームに赤い織物張り。 ・社交空間やサロンで使われた家具。・大型の肖像画(女性像) ・豪華な金のフレームに収められた油彩画。 ・この展示セクションでは、肖像画と家具を組み合わせて「邸宅のインテリア空間」を 再現しています。右側・緑の張り地の肘掛椅子 ・ギリシャ風の脚部装飾があり、ネオクラシカル(新古典主義)の影響を示す。・小型の黒いスタンド(読書台または譜面台のような家具・二枚の肖像画 ・左:白いドレスを着た女性像。 ・右:黒衣をまとった男性像。Spode(スポード窯)のディナーサービス(約1820年)。上段・小型丸皿 ×6・長方形小皿 ×1・中皿(楕円・八角形)×2中段・楕円大皿(ミートディッシュ)×2・中型楕円皿(野菜皿またはサイドディッシュ)×2・丸皿(スープ皿・デザート皿)×2下段(左右の棚も含む)・深鉢(サラダボウル、野菜ボウル)×2・オーバル大鉢 ×1・蓋付きスープチュリーン ×2・ソースボート(片口小鉢)×1最下段・大型のサーヴィングプレート(中央に大花束文)×1「PART OF A DINNER SERVICEAbout 1820; numbers 30–34, 1831This large service is characteristic of the extensive and richly decorated porcelain that was available to an increasingly wide range of buyers during this period. Marketing through London showrooms played an important role in the selling of such ensembles. Massed displays were a familiar sight to the visiting public as in theWedgwood showroom illustrated on the left.PorcelainMade by the Spode Factory, Stoke-on-Trent, Staffordshire」【ディナーサービスの一部約1820年(カタログ番号30–34, 1831年)この大規模なディナーサービスは、19世紀初頭に広く出回った、装飾豊かで華やかな磁器を代表しています。当時、ロンドンのショールームでの販売戦略が重要な役割を果たしました。ウェッジウッドのショールーム展示に見られるように、大規模なディスプレイは訪問客にとっておなじみの光景でした。素材:磁器製造:スポード窯(Spode Factory)、ストーク=オン=トレント(Staffordshire州)】「The Wolfson Galleries(ウォルフソン・ギャラリー)」の一部で、18世紀末〜19世紀初頭の室内装飾と家具 を再現するようなセクション。写真中央には 大きな円形の凸面鏡(Convex Mirror, 約1790年) が掲げられています。鏡は金箔仕上げの松材フレームに収められ、上下にアカンサスの葉飾りや鷲のモチーフが加えられている。これは当時の流行で、家具デザイン集(George Smith, 1808年刊)でも紹介された様式。1.凸面鏡(Convex Mirror, c.1790) ・松材、金箔仕上げ、凸面ガラス。 ・装飾には鷲(eagle)、アカンサスの葉が使われ、クラシカルな権威を象徴。 ・所蔵番号:W.25-1922。2.肖像画(右壁) ・女性の肖像(白いドレス、赤い背景)。 ・男性の肖像(軍服を思わせる装い)。 → いずれも19世紀初頭の貴族・上流階級を描いた作品。鏡と共に飾られることで、 当時の邸宅の「ファッション性」を表現。3.家具(下部) ・赤い張地の寝椅子(シェーズ・ロング)。 ・緑の布座面の椅子(ギリシャ風装飾)。 ・小型テーブル(木製、彫刻装飾)。 → ナポレオン時代からジョージアン期にかけての「新古典主義スタイル」を示す。「19 CONVEX MIRRORAbout 1790Mirror of this type became popular in about 1790. Various examples were illustrated in George Smith's Collection of Designs for Household Furniture and Interior Decoration, published in 1808. This example shows how various details such as the eagle and the acanthus leaf were added to a basic circular mirror.Pinewood, gilded with convex glassMuseum no. W.25-1922」 【19 凸面鏡約1790年この種の鏡は 1790年頃 に流行しました。さまざまな例が、1808年に出版されたジョージ・スミスの 『家庭用家具と室内装飾のデザイン集』 に図示されています。本作は、基本的な円形の鏡に、鷲(イーグル) や アカンサスの葉 などの細部装飾が加えられた様子を示しています。素材: 松材、金箔仕上げ、凸面ガラス所蔵番号: W.25-1922】左側の肖像画・タイトル: Mary Linwood・画家: ジョン・ホップナー(John Hoppner, RA, 1758–1810)・制作時期: 約1800年・技法: 油彩・カンヴァスこの肖像画は、羊毛刺繍による巨匠絵画の模写作品で知られた メアリー・リンウッド(1756–1845) を描いたもの。彼女はレスター・スクエア(ロンドン)でギャラリーを運営し、刺繍芸術を「高級芸術の展示形式」と結びつける先駆者であった。ジョン・ホップナーは当時のイギリスを代表する肖像画家の一人で、リンウッドを優雅な白いドレス姿で描き、彼女の文化的な地位と知的活動を示している。右側の肖像画。・油彩画ではなく、メアリー・リンウッド(Mary Linwood)による毛糸刺繍の ナポレオン・ボナパルト像(19世紀初頭のイギリス肖像画) であろう。・作品:Portrait of Napoleon Bonaparte(刺繍)・作者:Mary Linwood(1756–1845)・年代:18世紀末〜19世紀初頭・技法:クルーエル刺繍(coloured worsteds)・サイズ:およそ 2 ft 7 in × 2 ft 2 in(資料記載) ・所蔵:Victoria and Albert Museum(収蔵番号 1438-1874)「13 MARY LINWOODAbout 1800Mary Linwood (1756–1845) was famous for exhibiting her crewel wool needlework copies of old master paintings in her gallery in Leicester Square, London. Linwood'senterprise was an example of how the luxury goods trades began to use similartechniques of display to those used for high art, attracting customers with public exhibitions.Oil on canvasBy John Hoppner RA (born in 1758, died in 1810)Bequeathed by Miss Ellen MarklandMuseum no. 1439-1874」 【13 メアリー・リンウッド1800年頃メアリー・リンウッド(1756–1845)は、ロンドンのレスター・スクエアにある自身のギャラリーで、オールド・マスター(巨匠画家)の作品を羊毛刺繍(クルーエル刺繍)で再現した作品を展示したことで有名でした。リンウッドの事業は、高級品の取引が「美術作品の展示」で用いられるのと同じような展示手法を取り入れ、公開展示によって顧客を惹きつけるようになった一例です。油彩・カンヴァス画家:ジョン・ホップナー RA(1758年生 – 1810年没)エレン・マークランド嬢の遺贈美術館番号:1439-1874】「TEAPOYThe teapoy became popular in about 1800 as a table with receptacles for tea.This example is close to the design included in Peter and Michael Angelo Nicholson’s Practical Cabinet-maker, published in 1826. A copy is displayed nearby. Such pattern books not only provided designs for cabinet-makers but also influenced popular taste.Carved mahoganyBy an unknown British makerPurchased with the assistance of the Brigadier Clark FundMuseum no. W.16-1973」 【15 ティーポイ(茶卓)1825–1830年ティーポイは、1800年頃にお茶用の容器を収める小卓として人気を博しました。この作品は、ピーターとマイケル・アンジェロ・ニコルソンの著書『実用家具製作者 (Practical Cabinet-maker)』(1826年刊行)に掲載されたデザインに近いものです。その本の一部が近くに展示されています。このような「パターン・ブック」は、家具職人にデザインを提供しただけでなく、大衆の嗜好にも影響を与えました。素材:マホガニー材の彫刻作者:不詳(イギリスの製作者)ブリガディア・クラーク基金の援助により購入所蔵番号:W.16-1973】レディ・アン・ハミルトン・Lady Anne Hamilton (1766–1846)👈️リンク。・レディ・アン・ハミルトン は、王族に仕えた著名な宮廷女性で、特に キャロライン王妃 (ジョージ4世妃)の侍女・側近 として知られています。・彼女は王妃キャロラインがロンドンに帰国した際の「議会審問(離婚裁判のような性質)」に 同席し、その忠誠心から政治的にも注目されました。・絵画では、黒いドレスと大きな帽子(当時の宮廷・社交界での正装) を身につけ、威厳のある 姿で表されています。背後の赤いカーテンや椅子にかけられた毛皮付きマント (アーミン=白テンの毛皮)は、貴族的な地位や儀礼を象徴している。9 TORCHERE or candelabrum・ トーチャー(燭台)またはカンデラブラ「9 TORCHERE or candelabrum1816–1818George Bullock used British woods and British marbles, but he often worked for export.One of his major commissions was for the British Government who furnished the houseon St Helena in which Napoleon was held captive after the Battle of Waterloo.Pollard oak veneer with ebonised and gilt gesso details; light fittings of glass andsilvered metalDesigned by George Bullock (born in 1782 or 1783, died in London, 1818) andmade in his London workshopMuseum nos. W.62A-1887 (torchere), W.62B-1887 (sconce)」 【9 トーチャー(燭台)またはカンデラブラ1816–1818年ジョージ・ブロックはイギリス産の木材や大理石を用いたが、しばしば輸出向けの仕事も行った。彼の主要な仕事のひとつは、ワーテルローの戦い後にナポレオンが幽閉されたセント・ヘレナ島の邸宅を、イギリス政府の依頼で家具調度したことである。素材:斑木(ポラード・オーク)の化粧張り、黒色仕上げと金色ジェッソ装飾、ガラスおよび銀メッキ金属の照明器具デザイン:ジョージ・ブロック(1782年または1783年生、1818年ロンドン没)製作:彼のロンドン工房所蔵番号:W.62A-1887(燭台)、W.62B-1887(ブラケット燭台)】V&A博物館(Victoria and Albert Museum, London)内の「CLORE STUDY AREA(クロア・スタディ・エリア)121室」 の入口。この展示はV&Aの Medieval & Renaissance Galleriesに置かれており、中世美術の実物に囲まれながら「19世紀の中世趣味」を示す重要なコントラスト作品。「The Yatman Cabinet(ヤトマン・キャビネット)」👈️リンク。・このキャビネットは、Charles Francis B. Yatman(1823–1902) の依頼で作られた 豪奢な家具で、彼の名前から「Yatman Cabinet」と呼ばれています。・外観はあたかも中世の聖遺物箱(Reliquary Shrine)のようにデザインされ、宗教画風の パネル装飾やアーチ構造が特徴。・実際には19世紀の「ネオ・ゴシック様式(Gothic Revival)」の産物で、当時のイギリスで 流行した「中世趣味」を反映している。近づいて。キャビネットの扉や引き出しには、寓意的なパネル画がはめ込まれており、テーマは 「知識と文明の発展」 。・左の場面:古代における知識の口伝・写本伝達・中央の場面:学者(もしくは詩人・哲学者)が机に向かって記録・右の場面:印刷機による本の大量生産(グーテンベルクの活版印刷を象徴)つまり、知の継承 → 記録 → 普及 という人類文化の進展を順に表したもの。「Gothic Revival(ゴシック・リヴァイヴァル)」1830–1880 展示コーナーの一部。1.左側の大きな展示布・中世の文様を模した複雑なパターンの織物または壁紙。・「ゴシック・リヴァイヴァル」期のデザイナーたちが、ステンドグラスや古代織物に 基づいて色彩豊かなパターンを創作したことを示す典型例。2.中央〜右側の壁面・壁掛け時計(木製ケース入り):19世紀らしい直線的で重厚なデザイン。・文様図版(3点):ゴシック様式のパターンやアーチ形の装飾デザイン。 建築や家具、織物デザインに用いられたサンプル。・建築画(右端額装):ゴシック風建築の立面図。19世紀に流行した教会・公共建築の 設計案を反映している可能性が高い。3.下部の椅子群・赤い張地に金糸刺繍で「王冠」や「紋章」をあしらった椅子。・おそらく 英国議会のチェア またはそれを模したデザイン。ネオ・ゴシック様式の家具として 権威や伝統を示す役割を持つ。「Gothic Revival(ゴシック・リヴァイヴァル)」 の解説「STYLEGothic Revival 1830–1880Gothic, the dominant style of architecture and decoration in the Middle Ages, becamethe most popular revival style in Britain in the 19th century. The Victorians used it not just for churches but for every type of building, including houses, railway stationsand banks.The characteristic Gothic motifs of pointed arches, spires and turrets were also applied to domestic objects such as clocks and jewel plates. Designers created richly coloured patterns for fabrics and wallpapers based on the complex decoration found inMedieval stained glass and on ancient textiles.To its supporters Gothic was a morally superior style. They saw it as both British andChristian, unlike the foreign and pagan styles of classical Greece and Rome.」【様式ゴシック・リヴァイヴァル1830–1880中世において建築と装飾の主要な様式であったゴシックは、19世紀のイギリスで最も人気のある復興様式となりました。ヴィクトリア朝の人々は、それを教会に限らず、住宅、鉄道駅、銀行などあらゆる建物に用いました。特徴的なゴシックのモチーフ――尖頭アーチ、尖塔、塔など――は、時計や宝飾品の台座といった日用品にも応用されました。デザイナーたちは、中世ステンドグラスや古代の織物に見られる複雑な装飾に基づいて、豊かな色彩の布地や壁紙の模様を創り出しました。支持者たちにとって、ゴシック様式は道徳的に優れた様式と見なされました。彼らはそれを「外国的で異教的な古代ギリシャやローマの様式」とは異なり、「英国的かつキリスト教的」なものと考えたのです。】「Gothic Revival(ゴシック・リヴァイヴァル)」セクション に展示されている 教会祭具・聖具の一式。1.聖体顕示用クロス(大十字架)・左:銀製の大きなクロス(浮彫装飾あり)。典礼用の祭壇十字架。・中央:金色のクロス。下部は釣鐘形の台座に載っており、典礼で視覚的に荘厳さを演出。2.聖杯と典礼器具・中央下:金と銀で装飾された複数の聖杯(chalices)。・右下:装飾写本や典礼書(豪華な装丁)。・左下:銀製のピクシス(聖体容器)やカラフなど、聖体やワインを扱う容器。3.司祭祭服(Chasuble, カズラ)・右:深紅の織物に金糸刺繍が施されたカズラ(ミサ用外衣)。・背面には大きな円形の装飾(オーフリース/orfray)に、十字架や聖体シンボルが刺繍されている。4.背景の装飾布とステンドグラス・上部:赤地に金糸刺繍の祭壇前掛け(antependium)。 中世風の唐草文様とキリスト教シンボルを表現。・右端:小さなステンドグラス断片(キリストの受難を描いた場面の一部)。「Religion in Britain 1800–1900In 1800 the Church of England, the established church, exercised a unique power.Methodists and other Protestants, Roman Catholics, members of other faiths andatheists all faced obstacles to education, professional advancement and public office. The Catholic Emancipation Act of 1829 is the best known of many changes in the lawthat marked the development of religious freedom and led to the gradual removal ofbars to education or employment on religious grounds.Religion in 19th century Britain was fiercely debated and different groups held stronglyopposing views. All religious groups were active in building churches, chapels, meetinghouses or synagogues to provide for the spiritual needs of existing communities and for those that were developing in the expanding cities. Religion also became the spurto many programmes of social care for the poor. Religious observance came to be seen as a mark of respectability and individuals and communities spent large amounts on building and decorating their places of worship.」【イギリスにおける宗教 1800–19001800年当時、イングランド国教会(国教会)は特別な権力を有していました。メソジスト派やその他のプロテスタント、ローマ・カトリック、他宗教の信徒、そして無神論者たちは、教育・職業的昇進・公職就任において数々の障害に直面していました。1829年のカトリック解放法(Catholic Emancipation Act)は、宗教的自由の発展を示す数多くの法改正の中でも最も有名なものであり、宗教を理由とした教育や雇用の制限を徐々に撤廃する道を開きました。19世紀のイギリスにおいて宗教は激しく論争され、各派は強い対立的見解を持っていました。すべての宗教団体は、既存の共同体や拡大しつつある都市の新しい共同体の精神的ニーズに応えるため、教会・礼拝堂・集会所・シナゴーグの建設に力を注ぎました。また宗教は、貧困層への多くの社会福祉プログラムの原動力にもなりました。宗教的な実践は「社会的尊敬性の印」とみなされ、個人も共同体も礼拝所の建設や装飾に多額の資金を投じるようになったのです。】「The Church 1840–1900During the 19th century there was a powerful religious revival in Britain and many churches were built. As new laws increasingly guaranteed religious freedom, all Christian denominations took up the challenge of producing new churches for a population that was growing rapidly, particularly in the cities.Different groups held strongly opposed views on what was appropriate for the architecture and decoration of churches. Roman Catholics and some Anglicans saw rich decoration and furnishings as important elements of worship.Other denominations favoured plainness both in buildings and services.Artists, architects, and in particular A.W.N. Pugin designed both churches and their complete contents. As demand increased, specialist suppliers such as Cox & Sons(established 1837) and Jones & Willis (established 1855) church furnishings could beordered from published catalogues.」 【教会 1840–190019世紀のイギリスでは、力強い宗教復興があり、多くの教会が建設されました。新しい法律が宗教の自由を次第に保障するようになると、すべてのキリスト教宗派は、急速に増加する人口、特に都市部における新しい教会建設の課題に取り組みました。異なる宗派は、教会の建築や装飾において何が適切かについて強く対立した意見を持っていました。ローマ・カトリックや一部の英国国教会信徒は、豊かな装飾や調度品を礼拝の重要な要素と考えました。一方、他の宗派は建築や礼拝において簡素さを好みました。芸術家や建築家、とりわけ A.W.N. ピュージン は、教会そのものとその内部装飾のすべてを設計しました。需要が高まるにつれて、Cox & Sons(1837年創業) や Jones & Willis(1855年創業) などの専門業者が登場し、教会用の家具や調度品を出版されたカタログから注文できるようになりました。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.01
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1










