PR
X
カレンダー
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(3)戦争と平和
(384)対中・対韓関係
(121)医療・衛生
(109)音楽
(386)環境問題
(242)登山・自然・山と野鳥の写真
(694)政治
(1024)ラテンアメリカ・スペイン・スペイン語
(119)食の安全
(19)災害
(217)人類学
(16)経済問題・貧困問題
(111)オリンピック招致問題
(48)橋下知事・橋下市長
(35)外国人の権利
(23)PC・通信・IT関係
(111)鉄道・飛行機他乗り物
(95)その他
(410)テーマ: ◆最近話題のニュース◆(556)
カテゴリ: 環境問題
「環境・自然」のカテゴリを選択
----------------------
最終氷期の末期、地球の気温がいったん急激に温暖化たあと、急激な「寒の戻り」の時期があったことを前回の日記に書きました。「ヤンガードリアス期(新ドリアス期)」です。
ドリアスとは、日本語でチョウノスケソウと呼ばれる高山植物のことです。
チョウノスケソウ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%BD%E3%82%A6
寒冷期にはこの高山植物が北半球の各地で勢力を伸ばしたことから、寒冷期=チョウノスケソウ(ドリアス)が勢力を伸ばした時期、という意味で「ドリアス期」の名があります。
急激な温暖化は今から14700年前、そのあとの再寒冷化は12800年前のことです。この寒冷期は約1200年ほど続き、11700年前頃、再び地球は温暖化して、最終氷期は完全に終わりを迎えたのです。
この間の寒暖の変動は極めて急激なもので、特に、14700年前の最初の温暖化は、わずか3年間のうちに約10度という、とてつもない変動だったようです。
ヤンガードリアス期の再寒冷化は、世界中の地層に記録が残っており、日本でも同時期に北方系の植物が分布を拡大したことが、花粉化石の分析から分かっています。一方、南極の氷床コアの解析からは、この時期の再寒冷化の痕跡はあるものの、その規模はグリーンランドよりも遙かに小さいことが分かっています。
ヤンガードリアス期の終了後、急激な温暖化が収まって以降も、地球の気温はゆるやかに上昇し続けましたが、約1万年前に温暖化のピークに達すると、それ以降は非常に変動の少ない、安定した気候が現在まで続いています。現在までの1万年間が、それ以前と比べていかに天候が安定しているかは、前回紹介したグラフを見れば一目瞭然です。
おおむね1万年前頃に農耕が始まり、それ以来人類の文明が急速に発展してきたことは、この間の気候の安定性とおそらく関係があるはずです。
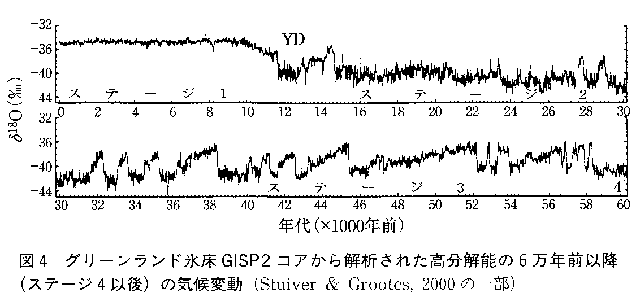
それでも、この安定した気候の1万年でさえ、わずかな気候の変化によって人類の文明は大きな影響を受けてきました。この1万年の中で唯一、グリーンランドの氷床コアに明確な痕跡が刻まれている変動は8200年前の寒冷期です。最終氷期の激しい気候変動に比べれば、このときの気候変動はささやかなものですが、それでもヨーロッパの黎明期の文明には壊滅的な打撃を与えたと見られています。
それ以降、これに匹敵するほどの気候変動はありません。西暦900年頃から1350年頃までを「中世の温暖期」、1350年頃から1850年頃までを「近世の小氷期」と呼ぶことがあります。しかし、グリーンランドの氷床コアからその痕跡はほとんど読みとることはできません。上記グラフの上段左端をよく見れば、確かに左端付近に、それらしき痕跡があると言われればあるなか、という程度です。
この時期の地球の平均気温は、20世紀中頃に比べて、0.5度程度高かったのではないかと推定されています。わずかそれだけの気温の上昇ですが、ヨーロッパでは温暖化の恩恵によって豊作が続いた一方で、北米西部は数百年にも及ぶ長期の干ばつに襲われ、メキシコ南部では繁栄を誇っていたマヤ文明が忽然と滅亡しています。マヤ文明滅亡の真相は明白ではないものの、やはり干ばつが大きく影響しているのではないかと指摘されています。南アメリカでもボリビアのティワナク文明がこの時期に滅亡している。やはり降水量がこの時期に激減していることが分かっています。
一方、近世の小氷期の影響は言うまでもないでしょう。江戸時代の大飢饉はいずれも、この寒冷期における出来事です。
氷床コアにほとんど記録が残らないわずかな気候変動ですらも、人類社会に与える影響はそれほど大きかったのです。まして、最終氷期に見られるような激しく頻繁な気候変動の影響は、想像するに余りあります。おそらく、人類社会は致命的な打撃を受けるでしょう。
さて、ではこのような気候の変動は何が原因で起こるのでしょう。原因が全て解明されているわけではありません。原因は単一ではなく、複数の要素が複雑に絡み合っているからです。
前回書いたように、地球の気候変動には、長期の波、中期の波、短期の波があります。およそ200万年前に始まった第四紀という地質年代は、全体として「氷河時代」と呼ばれます。ただいま現在も、立派に氷河時代です。これが長期の波です。そして、200万年間氷河時代のなかに、数万年から十数万年程度の周期で、比較的暖かい間氷期と、特に寒冷な氷期という中期の波があります。現在は、最終氷期が終わったあと、次の氷期が来るまでの間の間氷期に位置していると考えられます。そして、氷期・間氷期にも激しい気候変動があり、長くても1万年、短ければ数百年の幅で、氷期でもやや暖かい時期と特に寒冷な時期、間氷期でもやや寒冷な時期と特に温暖な時期があります。これを「亜氷期」「亜間氷期」と呼びます。これが、短期の変動です。現在は、亜間氷期に当たります。
そして、長期・中期・短期の変動では、それぞれ原因が異なっていることが推測できます。長期の気候変動の原因についてはここでは触れません。
氷期-間氷期という中期の変動は、ミランコビッチ・サイクルと呼ばれる地球の気道や自転軸の「ゆらぎ」による日射量の変動に主因があるのではないかと考えられています。
謎を解くカギはいくつかあります。例えば、氷床コアの解析からは、氷期の大気中には比較的塵が多かったことが分かっています。塵によって太陽光が遮られれば、気温が下がります。では、塵の発生源は何でしょう。まず、火山の噴火が考えられます。人類の歴史の中でも、巨大火山の噴火によって、世界的な規模で気温低下が引き起こされた事例があります。もう一つ、氷期には世界的に見て、寒冷化と乾燥化によって森林面積が減少した地域が多かったのではないかと推定されています。植生の乏しい裸地が増えた結果、土壌が空気中に舞い上がったのかもしれません。
そして、もう一つ、短期的な気候変動の原因の一つになっているのではないかと考えられているのは、海流の変動です。
ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」は、この海流の変動に主因があったのではないかと考えられています。
最終氷期の最寒冷期には、南極とグリーンランドの他、北欧のスカンジナビアと、アラスカ南部からカナダにかけての地域にも巨大な氷床がありました。これが、ヤンガードリアス期直前の温暖化によって、急激に溶けていきました。北アメリカでは、氷床の南側、現在の五大湖より西に、アガシー湖とい氷河湖を形成したのです。その名残が、現在のウィニペグ湖です。
氷河の溶融が進に連れてアガシー湖はどんどん巨大化し、現在の五大湖よりもはるかに広い湖になりました。そして、あるところで湖岸が決壊し、水が五大湖になだれ込みました。その水が、さらにセントローレンス川を伝って、北大西洋に大量に流れ出したのです。
深海流は、しかし所々で表層の海流と連結しています。そのうちの一つが、北大西洋なのです。大西洋には、メキシコ湾流~北大西洋海流と呼ばれる海流が流れています。メキシコ湾岸の温かな海水をスカンジナビア半島の沖まで運ぶ巨大な暖流です。これが、北大西洋で急激に冷やされて、深海へと沈み込んでいき、深層海流へとつながっているのです。
ところが、そこに、アガシー湖が決壊したことで大量の冷たい淡水が流れ込んできました。この淡水が、北大西洋海流の温暖な海水をせき止め、さらには深海への沈み込みをストップさせたと推測されています。北大西洋海流がせき止められれば、その北側(グリーンランドやヨーロッパ、カナダ)では温かい海水がストップするので寒冷化します。さらに深層海流がストップすることで、世界的規模で、高緯度海域への暖かい水の供給がストップします。
これが、ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」の原因と推定されています。急激な温暖化が、一転して寒冷化の原因となったのです。
前回の日記に、ヴァイツゼッカーの「過去に目を閉ざすものは未来に対しても盲目である」というという一節を引用しました。ヤンガードリアス期の急激な寒の戻りという「過去」に目を閉ざすものは、ひょっとすると未来に対しても盲目であるかも知れません。
以下、更に次回に続きます。
----------------------
最終氷期の末期、地球の気温がいったん急激に温暖化たあと、急激な「寒の戻り」の時期があったことを前回の日記に書きました。「ヤンガードリアス期(新ドリアス期)」です。
ドリアスとは、日本語でチョウノスケソウと呼ばれる高山植物のことです。
チョウノスケソウ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%BD%E3%82%A6
寒冷期にはこの高山植物が北半球の各地で勢力を伸ばしたことから、寒冷期=チョウノスケソウ(ドリアス)が勢力を伸ばした時期、という意味で「ドリアス期」の名があります。
急激な温暖化は今から14700年前、そのあとの再寒冷化は12800年前のことです。この寒冷期は約1200年ほど続き、11700年前頃、再び地球は温暖化して、最終氷期は完全に終わりを迎えたのです。
この間の寒暖の変動は極めて急激なもので、特に、14700年前の最初の温暖化は、わずか3年間のうちに約10度という、とてつもない変動だったようです。
ヤンガードリアス期の再寒冷化は、世界中の地層に記録が残っており、日本でも同時期に北方系の植物が分布を拡大したことが、花粉化石の分析から分かっています。一方、南極の氷床コアの解析からは、この時期の再寒冷化の痕跡はあるものの、その規模はグリーンランドよりも遙かに小さいことが分かっています。
ヤンガードリアス期の終了後、急激な温暖化が収まって以降も、地球の気温はゆるやかに上昇し続けましたが、約1万年前に温暖化のピークに達すると、それ以降は非常に変動の少ない、安定した気候が現在まで続いています。現在までの1万年間が、それ以前と比べていかに天候が安定しているかは、前回紹介したグラフを見れば一目瞭然です。
おおむね1万年前頃に農耕が始まり、それ以来人類の文明が急速に発展してきたことは、この間の気候の安定性とおそらく関係があるはずです。
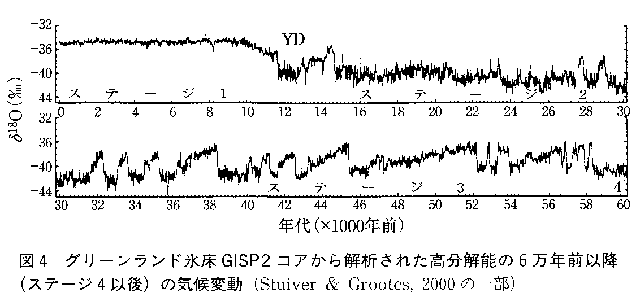
それでも、この安定した気候の1万年でさえ、わずかな気候の変化によって人類の文明は大きな影響を受けてきました。この1万年の中で唯一、グリーンランドの氷床コアに明確な痕跡が刻まれている変動は8200年前の寒冷期です。最終氷期の激しい気候変動に比べれば、このときの気候変動はささやかなものですが、それでもヨーロッパの黎明期の文明には壊滅的な打撃を与えたと見られています。
それ以降、これに匹敵するほどの気候変動はありません。西暦900年頃から1350年頃までを「中世の温暖期」、1350年頃から1850年頃までを「近世の小氷期」と呼ぶことがあります。しかし、グリーンランドの氷床コアからその痕跡はほとんど読みとることはできません。上記グラフの上段左端をよく見れば、確かに左端付近に、それらしき痕跡があると言われればあるなか、という程度です。
この時期の地球の平均気温は、20世紀中頃に比べて、0.5度程度高かったのではないかと推定されています。わずかそれだけの気温の上昇ですが、ヨーロッパでは温暖化の恩恵によって豊作が続いた一方で、北米西部は数百年にも及ぶ長期の干ばつに襲われ、メキシコ南部では繁栄を誇っていたマヤ文明が忽然と滅亡しています。マヤ文明滅亡の真相は明白ではないものの、やはり干ばつが大きく影響しているのではないかと指摘されています。南アメリカでもボリビアのティワナク文明がこの時期に滅亡している。やはり降水量がこの時期に激減していることが分かっています。
一方、近世の小氷期の影響は言うまでもないでしょう。江戸時代の大飢饉はいずれも、この寒冷期における出来事です。
氷床コアにほとんど記録が残らないわずかな気候変動ですらも、人類社会に与える影響はそれほど大きかったのです。まして、最終氷期に見られるような激しく頻繁な気候変動の影響は、想像するに余りあります。おそらく、人類社会は致命的な打撃を受けるでしょう。
さて、ではこのような気候の変動は何が原因で起こるのでしょう。原因が全て解明されているわけではありません。原因は単一ではなく、複数の要素が複雑に絡み合っているからです。
前回書いたように、地球の気候変動には、長期の波、中期の波、短期の波があります。およそ200万年前に始まった第四紀という地質年代は、全体として「氷河時代」と呼ばれます。ただいま現在も、立派に氷河時代です。これが長期の波です。そして、200万年間氷河時代のなかに、数万年から十数万年程度の周期で、比較的暖かい間氷期と、特に寒冷な氷期という中期の波があります。現在は、最終氷期が終わったあと、次の氷期が来るまでの間の間氷期に位置していると考えられます。そして、氷期・間氷期にも激しい気候変動があり、長くても1万年、短ければ数百年の幅で、氷期でもやや暖かい時期と特に寒冷な時期、間氷期でもやや寒冷な時期と特に温暖な時期があります。これを「亜氷期」「亜間氷期」と呼びます。これが、短期の変動です。現在は、亜間氷期に当たります。
そして、長期・中期・短期の変動では、それぞれ原因が異なっていることが推測できます。長期の気候変動の原因についてはここでは触れません。
氷期-間氷期という中期の変動は、ミランコビッチ・サイクルと呼ばれる地球の気道や自転軸の「ゆらぎ」による日射量の変動に主因があるのではないかと考えられています。
謎を解くカギはいくつかあります。例えば、氷床コアの解析からは、氷期の大気中には比較的塵が多かったことが分かっています。塵によって太陽光が遮られれば、気温が下がります。では、塵の発生源は何でしょう。まず、火山の噴火が考えられます。人類の歴史の中でも、巨大火山の噴火によって、世界的な規模で気温低下が引き起こされた事例があります。もう一つ、氷期には世界的に見て、寒冷化と乾燥化によって森林面積が減少した地域が多かったのではないかと推定されています。植生の乏しい裸地が増えた結果、土壌が空気中に舞い上がったのかもしれません。
そして、もう一つ、短期的な気候変動の原因の一つになっているのではないかと考えられているのは、海流の変動です。
ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」は、この海流の変動に主因があったのではないかと考えられています。
最終氷期の最寒冷期には、南極とグリーンランドの他、北欧のスカンジナビアと、アラスカ南部からカナダにかけての地域にも巨大な氷床がありました。これが、ヤンガードリアス期直前の温暖化によって、急激に溶けていきました。北アメリカでは、氷床の南側、現在の五大湖より西に、アガシー湖とい氷河湖を形成したのです。その名残が、現在のウィニペグ湖です。
氷河の溶融が進に連れてアガシー湖はどんどん巨大化し、現在の五大湖よりもはるかに広い湖になりました。そして、あるところで湖岸が決壊し、水が五大湖になだれ込みました。その水が、さらにセントローレンス川を伝って、北大西洋に大量に流れ出したのです。
深海流は、しかし所々で表層の海流と連結しています。そのうちの一つが、北大西洋なのです。大西洋には、メキシコ湾流~北大西洋海流と呼ばれる海流が流れています。メキシコ湾岸の温かな海水をスカンジナビア半島の沖まで運ぶ巨大な暖流です。これが、北大西洋で急激に冷やされて、深海へと沈み込んでいき、深層海流へとつながっているのです。
ところが、そこに、アガシー湖が決壊したことで大量の冷たい淡水が流れ込んできました。この淡水が、北大西洋海流の温暖な海水をせき止め、さらには深海への沈み込みをストップさせたと推測されています。北大西洋海流がせき止められれば、その北側(グリーンランドやヨーロッパ、カナダ)では温かい海水がストップするので寒冷化します。さらに深層海流がストップすることで、世界的規模で、高緯度海域への暖かい水の供給がストップします。
これが、ヤンガードリアス期の急激な「寒の戻り」の原因と推定されています。急激な温暖化が、一転して寒冷化の原因となったのです。
前回の日記に、ヴァイツゼッカーの「過去に目を閉ざすものは未来に対しても盲目である」というという一節を引用しました。ヤンガードリアス期の急激な寒の戻りという「過去」に目を閉ざすものは、ひょっとすると未来に対しても盲目であるかも知れません。
以下、更に次回に続きます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[環境問題] カテゴリの最新記事
-
人間界の流れが変わっただけ 2025.01.24
-
11月になるのにまだ富士山冠雪せず 2024.11.01
-
自粛警察、マスク警察の次は汚染水警察 2024.02.27
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









