2022年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

「1月14日 脱原発みやぎ金曜デモ」 原発に執着する自公政府が日本の壊滅的経済危機を準備している!
「このままでは、最大で100万人の雇用と、15兆円もの貿易黒字が失われることになりかねない」──。東日本大震災から10年を迎えた3月11日、豊田氏は日本自動車工業会(自工会)会長として記者会見に臨み、そんな衝撃的な試算結果を公表した。 こんな「衝撃的な」記述が導入部に記載された記事があった。「出遅れれば雇用も貿易黒字も失う 再エネを使い尽くせ 本腰入れる需要家」という『日経ビジネス』の記事である。 普通に考えれば、「衝撃的」には違いないが、私には「新しい資本主義」などという無内容な頓珍漢ぶりを披露している岸田自公政府(とのその周辺)がほんとうに衝撃をもって受け取っていると思えないのである。 要するに、再生可能エネルギーへの転換が遅れている日本は脱炭素化へと進む世界から孤立するだろうというのである。二酸化炭素排出量をベースにした国際規制の検討が着々と進んでいて「自動車の場合、燃費規制はもちろん、原料の採取から、部品の製造、自動車の生産、廃棄・リサイクルに至るまでが対象となる」ので、脱炭素化が進まない日本の自動車には関税をかける「炭素国境調整措置」の導入が検討されているのだという。そうなれば、貿易黒字も雇用も失われるだろうという記事である。 日本の脱炭素化の遅れ(再生可能エネルギーへの転換の遅れ)の原因ははっきりしていて、次のように書かれている。 「『原発さえまた動き出せば巻き返せる』という甘い見通しに立ち、10年前に再エネの主力電源化を本気で目指さなかったツケが今、回ってきている」。エネルギー政策に詳しい識者は奥歯をかむ。「絶対に安全だ」と長年にわたり国や電力事業者が言い立ててきた原発が未曽有の事故を起こし、国民からの信頼は地に落ちた。もちろん基幹電源を、出力が変動しやすい再エネに置き換えていくことは容易ではない。だが、「原発事故を契機に、エネルギー政策のパラダイムシフトを果たしていれば、世界の脱炭素競争における今の日本の立ち位置は変わっていた」(大手首脳)。そう考える財界関係者は少なくない。 原発に執着した自公政権(と通産官僚)が日本経済の壊滅的危機への道筋を準備してきたのである。国内での新規建設が無理だとわかると、安倍政権はやっきになって原発輸出を試みたが、完璧に失敗した。何も変えることができないこんな無能な政府を国民はいつまで支持し続けるのだろう。 とても面白いことだが、この記事は、自公政府の政策に批判的なメディアではなく、『日経ビジネス』に掲載されているのである。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2022/1/14 18:20~18:39) 風が吹くたび寒さに震えあがる。予報気温はそんなに低くはないのに、風のせいか元鍛冶丁公園はとても寒い。手袋をしていてもカメラを持つ手がかじかんでくる。 30人が集まった集会では、アメリカ合衆国の高速増殖炉開発に日本が技術協力をするというニュースが話題になった。スピーカーは、「もんじゅ」で失敗したのにいまだに高速増殖炉に執着する日本政府を強く批判したが、このニュースは冗談ではないかと思えないこともない。 高速増殖炉の原型炉である「もんじゅ」の運転に完全に失敗したので、日本の高速増殖炉に関する技術は実験炉「常陽」のレベルにとどまっている。原発の開発は、実験炉、原型炉、実証炉、実用(商用)炉と進むので、道半ば以前に失敗しているのである。加えて、廃炉の決まった「もんじゅ」から核燃料を取り出す技術もないことが判明している。高速増殖炉を諦めきれない日本はフランスに泣きついたのだが、そのフランスも高速増殖炉の実証炉ASTRIDの開発から撤退してしまった。 そんな日本が高速増殖炉開発でアメリカに協力できるどんな技術を持っているのか見当もつかない。東芝のように、開発が失敗に終わった時の負債を押し付けられる(尻拭いをさせられる)のがせいぜいではないのか。そうなれば、日本の破滅的経済危機をいっそう加速させることになるだけだろう。一番町。(2022/1/14 18:40~18:45) 仙台の脱原発金曜デモは、2012年から続いているが、デモ開始から半年以上も経ったころデモそのものについて書いたブログがあった。「「2月15日 脱原発みやぎ金曜デモ」 くりかえしくりかえしの〈デモ〉から」 である。 「くりかえしくりかえし」のデモに出ていると、体も心もデモというちょっとした「非日常」に馴染んでくるようだ。デモも終盤にさしかかって青葉通りを歩いているとき、シュプレッヒコールで大口を開けていたらそのまま欠伸に移ってしまった。3,4回続けて欠伸が出たのだ。じつは、寒風吹きすさび、横殴りの雪の中の先週のデモの途中でも何回か欠伸が出ていたのである。 「だらしがない、緊張感がない」と一瞬は思ったのだが、そんなことはないのではないかと思い直した。年をとっても人見知りで、趣味が多くてもすべて一人遊び、そのような私が一人でデモに参加し始めたときは、それなりの心理的な障壁を乗り越える手続きは必要だった。それが今では、デモの最中に欠伸が出るほど、すっかり慣れてしまったのである。 要するに、「くりかえしくりかえし」で、私にとってデモは〈普通〉になったのだ、と思う。つまり、デモはもう日常である。「おはよう」と挨拶するようにデモをする。「お休み」という前にデモをする。思いっきり大げさに、かつキザに表現すれば、「反原発の肉体化」である(「血肉化」の方がいいかな)。肉体化した反原発は、そのまんまで反原発である。もうデモを歩かなくても反原発なのである。 ここまで書いてきて気付いたのだが、これはデモをサボる口実に使えそうな結論にもなっている。いや、サボるつもりは全くないのだが、これが文字通り「両刃の剣」ということか。(2013年2月5日) あの頃はほとんど休むことなくデモに参加していたのである。青葉通り。(2022/1/14 18:50~18:53) 手袋をしたままタッチパネルを操作できる、そんな手袋でそこそこの厚みがあるのに防寒性能が低いのかカメラを持つ手の冷たさが耐え難くなった。 デモが国道4号の大通りを渡るとき、地下道を抜けて先回りをするのが常なのだが、今日は大通りの手前から流れ解散場所に向かうデモの列を後ろから撮影して、そこでデモ参加を終わりとした。 手袋のなかで手を握りしめ、ポケット深く押し込んでの帰路は、当然ながら年齢に似合わない急ぎ足なのだった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)
2022.01.14
コメント(8)
-

「1月7日 脱原発みやぎ金曜デモ」 原発問題は人権問題である、断固として!
年が変わるころに年齢のことを考えるのはごく当たり前のことだろうが、私の場合は誕生日が1月1日ということもあって、暮れの「お年とり」、元日の誕生日と畳みかけられるので多少面倒でもある。 加えて、今年は肉体的にも年齢ということをきつく思い知らされた。その手始めは暮れの障子張りだった。たった障子4枚の軽い作業だと気楽に始めたのだが、障子の細い桟を踏み抜かないように注意しながら、急いで糊を塗り上げるという姿勢が翌日の肉体にかなりこたえたのだった。疲労はたいしたことはないのに、体のあちこちが筋肉痛になったのである。 大晦日は朝から台所に立ちっぱなしで正月料理を作った。年が明ければ、朝一番に起きて餅焼きから仕事が始まる。元旦の夜の誕生祝いの料理も自分で作ったのだが、妻が「それではあんまりだから」といって茶碗蒸しを作ってくれた。わが家では元旦の私の誕生日にはかならず茶碗蒸しが付く。私が育った家では暮れの「お年とり」のごちそうの一つとして母が茶碗蒸しを必ず作っていて、母からそれを聞いた妻がその習慣を「お年とり」から私の誕生日に移してずっと続いているのである。 そんなこんなで正月をぐったりとして過ごした。傍目からはのんびりと過ごす正月に見えただろうが、本人は必至で疲労回復に努めたのである(そんな年齢だというきつい実感に苛まれながら……)。 そして、疲労がなんとか治まった頃、今年最初の脱原発デモである。元鍛冶丁公園から一番町へ。(2022/1/7 18:17~18:40) デモの時間帯の仙台の気温は0℃前後という予報なのだが、あいかわらず何を着ていいのか迷うのである。寒さ対策としてインナーを何にするか決めればいいのだが、たいして選択肢もないのにそこで悩むのである。そういえば、この頃はウールのセーターを着るということはほとんどなくなった。着膨れるのが嫌だということもあるが、寒気の下に長時間いるという行動がまるっきり無くなったということもあるだろう。寒気の中で3時間ほどという金デモは寒さ対策という点では中途半端な時間のように感じるのである。 今日はカメラのフラッシュを放り込んで家を出た。せめてスピーチする人の写真はフラッシュを焚いて撮ろうと思ったのである。フラッシュなしだとどうしても写真が粗くなるのである。 フェイスブックやツイッターなどのSNSに投稿する写真はサイズが小さいのであまり気にならないが、パソコンで写真の一枚一枚を見るとその粗さが嫌でも目に付くのである。 もっとも、フラッシュが役に立つのは距離が短いポートレートのような場合だけで、デモのときの写真にはほとんど役立たないのだが。 この冬は雪降りの日がけっこう多いのだが大雪にはならずにすんでいて、デモには全く支障がない。元鍛冶丁公園には25人ほどが集まっていた。今年最初の金デモということもあってか、次々にスピーチをする人が出てくる。最後に市会議員の猪股由美さんの挨拶もあった。一番町。(2022/1/7 18:44~18:50) 2012年から書き続けている金デモのブログを再読して、抜き書きをいくつかフェイスブックやツイッターに投稿しているのだが、「「11月16日 脱原発みやぎ金曜デモ」。 夜の街を行く、この心身不調」というブログから次のような部分を拾い出した。それを語るであろう人は誰も私達のあとにやって来ない。私達がなさずに置いていたものを、手に取りそして終らせる人は誰もいない。 ヒルデ・ドミーン「誰も私達のあとにやってこない」部分 「後に続くものを信ずる」というのは古典的左翼運動の常套句であった。そう信じなければ前に進めない、という心情を私はけっして否定しない。しかし、振り返ったら誰もいない、ということはしばしば起こる。私のような者にすら、似たような経験はあった。だから、「後に続くものを信ずる」ことによって行為のエネルギーを獲得することは、普遍的に可能なわけではないし、誰かに推奨できるわけのものではない。 「私はこれをやりたい」、「いま、ここ、この私が私の意志を表明する」といった、さながら古典的左翼がプチブルと罵りそうな心情がその古典的左翼の情動を凌駕しうる、と私は思っている。それこそが、古典的左翼が力を失い、反原発運動は括りようのない雑多な市民、組織されていないが多数を形成しつつある市民によって担われ続けている情動としての機制である、と考える。私は誰も代表しない。私は私しか代表していない。そのような〈私〉が集まっているのだと思う。 (2012年11月16日) もう一つは、「「11月30日 脱原発みやぎ金曜デモ」。 あのね、原発はエネルギー問題じゃないんだよ。人権問題なんだよ!」から。 原発をエネルギーや電力の問題、ひいては電力を要する産業の問題として括ろうとする人間がいるが、人命を超えてエネルギー問題を選択することは〈普通の人間〉には許されない。 自分の周囲に放射能被爆で亡くなったり、傷ついたり、病んだりする人がいないことをいいことに、原発を擁護しつつエネルギー問題を論じることを「大所・高所から社会を考えている」と思い込んでいるのは、たいてい田舎政治家である。それを「自分は立派な〈高い〉政治意識を持っているのだ」と自己欺瞞で思い込んでいるので、偉ぶって威張り散らす人間が多い。 彼らは、ただ単に社会全体に対する想像力が劣悪であるに過ぎない。「田舎」というのは、ローカルな周囲を世界の全てと信じているような視野が狭い喩えなので、東京に田舎政治家がたくさんいるのは不思議ではない。代表格は、東京と大阪に一人ずついる。私はそれを「大所・高所シンドローム」と呼んで、精神的(厳密に言えば思想的)な病気の一つに数えている。(2012年11月30日)青葉通り。(2022/1/7 18:54~18:59) 疲労がぶり返すということもなくデモは終わった。寒さも感じないし、着ぶくれて汗をかくということもない。何を着て外出するか悩む必要がなかったと思うのだが、次回もきっと悩むのである。そんなことを繰り返してきたし、これからも繰り返すのである。ほんとうに悩まなくてもいいつまらないことを悩んでいるのである。 こんな年齢になるまで悩むことはそれなりにあったのだが、そのどれも悩まなくてもよかったつまらないことだったのではないか、そんな怖ろしげな思いが頭をよぎって、いそいでそれを打ち消して、そんなふうな帰り道となった。読書や絵画鑑賞のブログかわたれどきの頁繰り(小野寺秀也)日々のささやかなことのブログヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)
2022.01.07
コメント(11)
-
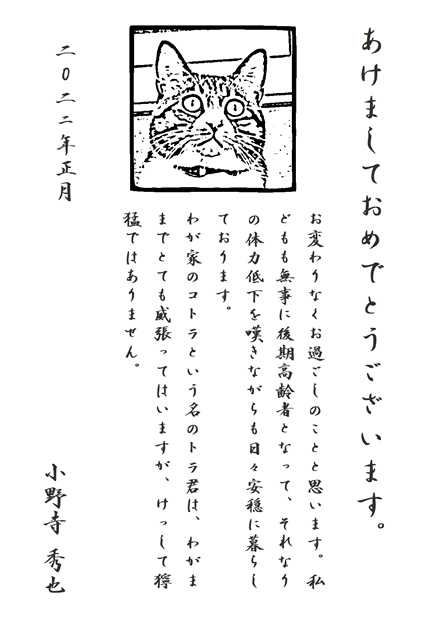
今年もよろしく………
今年もよろしくお願いします。
2022.01.01
コメント(6)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- ちょっと、お出かけ。
- また横浜
- (2025-11-23 11:14:48)
-
-
-

- ☆ルアーフィッシング☆
- 甥っ子君の足となり財布となった日
- (2025-09-21 22:29:02)
-
-
-

- 登山をして、自然や景観に関心を
- 秋の日向山(1,660m)山梨百名山(後編…
- (2025-11-20 06:00:18)
-







