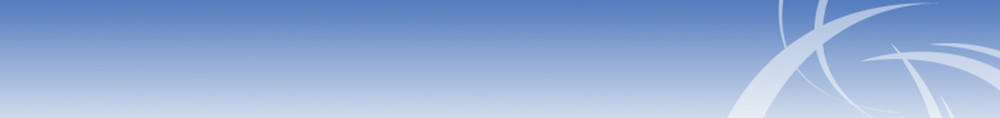2011年08月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
木材腐朽菌
木材腐朽菌とは、 木材(木部細胞の細胞壁)に含まれるセルロース、へミセルロース、リグニンを分解する菌で、 住宅など建物の木部を普及させます。 但し、この微生物がないと木材を土にかえすことができません。【住宅内に見られる木材腐朽菌の分類】 1. 表面で増殖するため、木材を傷めることはない アカカビ、アオカビ 2. 木材の強度に影響ない クワイカビ、アカカビ、ススカビ 3. 水分十分な状態で木材を腐らせる、褐色、青灰色 タマカビ、クロカワ 4. 木材の内部まで腐らせる菌、褐色、成育適温はおおよそ20~35℃ スエヒロタケ、カワラタケ、ヒイロタケ、オオウズラタケ、マツオオジ、キカイガラタケ【関連サイト】 ・ 木材腐朽菌図鑑 (財団法人 日本緑化センター)
2011.08.31
-
露点(露点温度)
露点(露点温度)とは、 湿り空気中の水蒸気が凝縮し始めるときの温度で、その温度より低い温度まで冷やされると 結露が生じます。夏の冷やされたビールが入っているジョッキの外表面に水滴がたくさんついているのは、その表面近くの空気が、温度の低いガラスの表面に接触して露点温度以下に冷やされ、水蒸気が凝縮しているため。
2011.08.30
-
食物アレルギー
食物アレルギーとは、 原因食物を摂取した後に免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状(皮膚、粘膜、消化 器、呼吸器、アナフィラキシーなど)が惹起される現象と定義されています。 (食物アレルギーの診療の手引き2008より) ※免疫学的機序とは、体内に異物が侵入しようとしたときにそれを排除しようというシステムの ことをいいます。食物アレルギーは、食べてから症状が出るまでの時間により以下の2つに分類されます。 ● 即時型反応 食べて2時間以内(ほとんどは15分以内)に、唇が腫れたり、皮膚の発赤・痒み等が起こっ たり、嘔吐などの症状が出ます。この場合、呼吸困難や意識障害、アナフィラキーショック が起こると緊急の治療が必要になります。 ● 非即時型反応 食べてから6~8時間後位に出る遅発型と1~2日後に出る遅延型反応があります。 症状としてはアトピー性皮膚炎や新生児の胃腸管アレルギーなど【主な症状】 ■ 皮膚粘膜症状 皮膚や口の中の粘膜などに出る 皮膚の痒み、じんましん、発赤、アトピー性皮膚炎、湿疹 結膜充血・浮腫、唇の腫れ、 口の中・喉の痒み、舌の違和感・腫張、流涙、眼瞼浮腫 ■ 消化器症状 胃腸など消化器に出る症状 腹痛、嘔吐、下痢、血便 ■ 呼吸器症状 喉の違和感、咳、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、喘鳴、呼吸困難 ■ 全身性症状 アナフィラキシーショックその他、食物アレルギーは赤ちゃんが発症しやすいのですが、成長するにつれてアレルゲンを含む食物を摂取してもアレルギー反応を起こしにくくなる特徴があります。【関連サイト】 ・ セルフケアナビ 食物アレルギー お家でできること (厚生労働科学研究) ・ 食物アレルギー研究会 ・ 食物アレルギー・代替食の作り方教室 (e-ラーニング アレルギー遠隔教育学院) ・ よくわかる食物アレルギー (MCクリエイト株式会社) ・ 食物アレルギーの診療の手引き2008 ・ 食物アレルギーの栄養指導の手引き2008 ・ 新食事療法シリーズ(食物アレルギー) (監修:海老澤 元宏,林 典子(国立病院機構相模原病院臨床研究センター)) ・ ぜん息の発症予防に役立つ!食物アレルギーの正しい知識(すこやかライフNo.33) (独立行政法人 環境再生保全機構) ・ 食物アレルギーによるアナフィラキーショック学校対応マニュアル 小・中学校編 (財団法人 日本学校保健会) ・ 学校生活における救急治療プラン ・ 食物アレルギーねっと (日本ハム中央研究所) ・ 食物アレルギー (キューピー株式会社) ・ 食物アレルギーを持つ親の会
2011.08.29
-
アクロレイン
【別名】 アクリルアルデヒド、アリルアルデヒド、プロペナール 【特性など】 ・常温で黄色または無色の液体 ・刺激臭がある ・常温で揮発性が高い 【主な発生源】 ・加熱した食用油から発生する この場合、発生したアクロレインによって油酔いを引き起こすとされる ・車の排気ガス ・たばこの煙 【主な用途】 ・栄養強化剤 ・飼料添加物 ・医薬品 ・アクリル酸エステル(アクリル繊維などの原料)などの製造原料 ・繊維処理剤 【その他】 ・光化学オキシダントの原因物質の一種 ・大気汚染防止法で、特定物質に指定されている
2011.08.27
-
空気の組成
空気の組成(水蒸気を除いた空気の成分:乾燥空気) 窒素 78.08% 酸素 20.95% アルゴン 0.93% 二酸化炭素 0.03% (その他) ネオン、ヘリウム、メタン、クリプトン、水素、一酸化二窒素、一酸化炭素、キセノン、オゾンなど
2011.08.26
-
フタル酸ビス(2‐エチルヘキシル)
【別名】 フタル酸ジオクチル(DOP)、フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジエチルへキシル 【特徴】 ・常温で無色の液体 ・水に溶けにくい ・特徴的な臭気がある ・合成樹脂を柔らかくする性質を持つ 【主な用途】 ・合成樹脂の可塑剤 壁紙や床材などの建材、電線被覆材などに使われる軟質塩化ビニル製品の製造 【関連サイト】 ・ フタル酸ビス(2‐エチルヘキシル)のリスク管理の現状と今後のあり方 (独立行政法人 製品評価技術基盤機構) ・ フタル酸エステル類の規格基準の取扱いに関するQ&Aについて
2011.08.26
-
青森県
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 青森県 ・ スポーツ健康課 ~ 食育の時間 -学校における食育-
2011.08.25
-
アンモニア
【特性など】 ・刺激臭のある無色の気体 ・空気より軽い ・水に非常に溶けやすい ・水溶液は弱い塩基性を示す 【発生源】 ・糞尿 ・腐敗物 ・コンクリート 【主な用途】 ・化学肥料 ・合成樹脂 【健康影響】 ・目、皮膚、気道への刺激 ・腐食性 ・目の発赤 【その他】 ・悪臭防止法に基づく特定悪臭物質のひとつである
2011.08.25
-
東京都
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 東京都 ・ 東京都福祉衛生局 ~ 食品衛生の窓 ・ 東京都環境局 ・ 足立区 ・ 荒川区 ・ 板橋区 ・ 江戸川区 ・ 大田区 ・ 葛飾区 ・ 北区 ・ 江東区 ・ 品川区 ・ 渋谷区 ・ 新宿区 ・ 杉並区 ・ 墨田区 ・ 世田谷区 ・ 台東区 ・ 中央区 ・ 千代田区 ・ 豊島区 ・ 中野区 ・ 練馬区 ・ 文京区 ・ 港区 ・ 目黒区 ■ 東京都健康安全研究センター ~ 住まいの健康配慮ガイドライン ~ 室内空気中の化学物質 ~ 室内の環境微生物 ~ 化粧品を安全に使うために ■ 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター ~ 高齢者のための熱中症豆知識 ■ 社団法人 東京都歯科医師会 ■ 社団法人 東京薬剤師会 ■ 港区立エコプラザ ■ 東京都薬用植物園
2011.08.24
-
ベイクアウト
ベイクアウトとは、 ストーブ、電気ヒーターなどにより室内温度を35~40℃程度まで上げ、室内の建材の温度を高く することにより、建材から強制的に揮発性有機化合物(VOC)を追い出す方法のことです。これは建材などに含まれるVOCの温度が高くなると放散量が増えるという特性を利用して、建材内部のVOCを追い出すということになります。【基本の手順】 1.加熱 窓を閉め切り、ストーブなどの暖房器具を使い、室内温度を35~40℃程度まで上げる。 2.換気 VOCが建材から室内へと揮発してくるので、時々換気をする。 3、複数回実施 1、2を繰り返す ※その他 ・扇風機で温度を一様にする ・加湿器を併用する【問題点】 ・壁装材等の内装材が剥がれたり、建具が反ることがある。 ・ベイクアウト後に一時的に濃度が上がるリバウンド現象を起こすことがある。 これは表面近くのVOCについては放散されても、内部に含有するVOCは短時間の ベイクアウトでは内部を拡散して建材内部濃度を低減し、放散量を劇的に減少させ るまでには至っていないからと考えられます。 ・放散したVOCが他の建材に吸着し、その後脱着して室内に放散することがある。 ・効果の出る物質は限定的で、処置後の効果の持続性もまばらである。
2011.08.24
-
鹿児島県
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 鹿児島県 ・ 建築課 ~ 住まいの安全と快適性 ~ 住まいの環境を健康に保つ ■ 鹿児島市 ・ 健康福祉総務課 ~ みんなの食育 ■ 県民健康プラザ健康増進センター ■ かごしま環境未来館
2011.08.24
-
宮城県
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 宮城県木材協同組合 ~ シックハウスQ&A
2011.08.24
-
赤外線
可視光線より長い波長の電磁波で、太陽光に含まれます。気温が低くても太陽の光にあたると暖かく感じるのはこの赤外線によるものです。 【特性、特徴など】 ・ヒトの目ではみることができない光 ・波長は0.7μm~1mmに分布され、短いものから近赤外線、中赤外線、遠赤外線に分類 【関連サイト】 ・ 社団法人 遠赤外線協会
2011.08.23
-
ペットボトル症候群
ペットボトル症候群と呼ばれるソフトドリンク(清涼飲料水)・ケトーシスとは、 糖分の多い清涼飲料水を大量に飲み続けていると、急激に血糖値が上がり、糖分の代謝を 促すインスリンの働きが一時的に低下してしまう急性の糖尿病のこと。患者の多くは10~30代の男性ということです。【関連サイト】 ・ 暑い日はペットボトル症候群に注意 (糖尿病ネットワーク) ・ ペットボトル症候群
2011.08.23
-
沖縄県
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 社団法人 沖縄県栄養士会 ■ 沖縄県医師会 ■ 財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団
2011.08.22
-
新潟県
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 新潟市 ・ 食の安全推進課 ~ 家庭でできる食中毒予防--6つのポイント ・ 新潟市保健所 ~ Let's 食育・健康づくり ~ 住まいの衛生 ~ 家庭用品の安全のために ■ 新潟市衛生環境研究所 ~ 食中毒の原因となる微生物について ~ 食品の表示の見方 ■ 財団法人 新潟県環境保全事業団 ■ 新潟県立環境と人間のふれあい館 ~新潟水俣病資料館~
2011.08.21
-
福島県
シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善、化学物質等を中心とした健康や環境などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 福島県 ・生活衛生課 ~ 食品安全のページ ■ 郡山市 ・郡山市保健所 ~ 揮発性有機化合物対策ガイドライン ~ 食の安全 ~ 郡山の食育 ■ 社団法人 福島県建築士事務所協会 県北支部青年部 ~ 20分で分かるシックハウス対策の10のポイント(概要編)
2011.08.21
-
シックスクール問題
シックスクール問題とは、 児童・生徒や教師が体調不良を訴えるというような健康被害が学校施設などに起因すると 考えられる場合、また、化学物質過敏症の児童・生徒への対応を含めた複合的な問題の 総称のこと。NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第一章では、この問題についての対応、課題について言及されているのでこちらに掲載します。 室内の化学物質濃度が厚生労働省の定めるガイドライン値以上となった学校のことで あり、そこにいる多くの児童・生徒さらに先生までもが、目や喉などの粘膜が痛い、嫌 なにおいがする、頭痛がする、倦怠感があるなどの症状を訴えたとき、シックスクール 症候群が起きたことになるのだろう。 ここで問題解決のためにも大切なのは、多くの児童・生徒、教師は問題ないのに、ごく 一部の児童・生徒(時には先生)から上記と同様の症状が訴えられ、なおかつ、それら を訴える人々が化学物質過敏症の体質を獲得しているとの診断を受けている場合は、 化学物質過敏症患者が学校にいたという話で、シックスクール問題ではない考えるべ きである。これはシックハウスの場合は、問題が個人レベルであるが、シックスクール問題は個人だけでなく、父母会対学校といった組織レベルの問題になるためその対策を実施する場合、問題の所在を明らかにする必要があるために明確にする必要があるとも言われています。それは主として建物に問題があるのか、人にあるのかをしっかり見極めることと言えます。その対応については、次のように説明されておられます。 学校の校舎に問題がある「シックスクール症候群」であれば、まず後者の問題のある 箇所を直すのが先決で、これは純粋に建築技術的対応で問題解決に至るはずである。 一方、児童・生徒が化学物質過敏症であるための問題であれば、建物に対して建設 技術的な対策をしても、問題の全面的な解決には必ずしもつながらないであろう。 化学物質過敏症の児童・生徒に対する医学的処置を考えるとともに、そのような児童・ 生徒でも学習できるような場を学校内の一部に確保するといった制度的な対応が現実 的であろう。上記では学校における建物を起因とする室内空気汚染問題を例としての説明でしたが、建物以外(学校の教材など)についても同様で、シックスクールと化学物質過敏症との違いを正確に見据える事が問題の第一歩と言えます。【関連サイト】 ・ 教材から発生する化学物質について
2011.08.21
-
娘核種
放射性核種が放射性崩壊をすることにより新しく生成された核種で放射能を持っているもの。
2011.08.20
-
換気回数
換気量を室内の容積で割った値 単位:回/h換気回数0.5回/hとは、部屋の空気が2時間に1回の割合で入れ換わったことを意味します。
2011.08.19
-
換気量
室内空気が1時間に入れ換わる量 単位:m3/h
2011.08.19
-
環境基本法
この法律は、環境の保全についての基本理念を定め、国や地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とし、従来の公害対策基本法に代わって施行されました。この法律の第二章「環境保全に関する基本的施策」の第一節には、第十四条として環境の保全に関する施策の策定および実施で、次に掲げる事項の確保を旨として行わなければならないとあります。 1.人の健康が保護され、および生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全さ れるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される こと。 2.生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図ら れるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的 条件に応じて体系的に保全されること。 3.人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 さらに、同じく第三節では第十六条として「環境基準」が定められています。 詳しくは「環境基準」の項をご覧ください。この法律は、第五条で 「地球環境保全が人類共通の課題であるとともに、我が国の経済社会は国際的に密接 な相互依存関係の中で営まれている。そこで我が国の能力を生かし、又、国際社会にお いて我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければなら ない」と述べているように、地球規模での環境政策の新たな枠組を示す基本的な法律として定められています。
2011.08.17
-
光化学オキシダント
光化学オキシダントとは、 工場や自動車などから大気中に排出された窒素酸化物(NOx)と炭化水素(HC)が、太陽光線に 含まれる紫外線を受けて光化学反応を起こし生成される酸化性物質のことで、光化学スモッグ の原因になります。大気汚染に係る環境基準では、下記のように定義されています。 「光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)その他の光化 学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するもの に限り、二酸化窒素を除く。)をいう。」 下線部説明 中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するすべての酸化性物質の総称を全オキシダントと いいますが、その全オキシダントの中から二酸化窒素を除いた物質が光化学オキシダントと呼 ばれます。【特徴】 光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化水素が、太陽の強い紫外線を浴びて変質した結果、 二次的に生成されるものであるため、日差しが強くなる春から夏にかけての日中に濃度が高く なる。 したがって、光化学スモッグは、風の弱い晴れた日で、紫外線の強い夏の日中に発生し、紫外 線の弱い冬やあるいは太陽の出ていないは夜間には発生しない。【発生源】 ・工場の排煙 ・自動車排出ガス【健康への影響】 ・目やのどの刺激【その他】 ・大気汚染に係る環境基準において、光化学オキシダントは、1時間値が0.06ppm以下であること と定められています。 ・大気汚染防止法では、 「大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合と して政令で定める場合」において、光化学オキシダントの注意報の発令を規定しています。 この場合の光化学オキシダント濃度は、常時監視の測定データが1時間値100万分の0.12以 上である大気の汚染の状態になった場合(1時間値で0.12ppm)とされています。 「気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な 被害が生ずる場合として政令で定める場合」は、警報の発令を規定しています。 この場合の光化学オキシダントの濃度は、1時間値100万分の0.4以上である大気の汚染の 状態になった場合(1時間値で0.4ppm)とされています。
2011.08.17
-
塩基性
塩基(水溶液中で水酸化物イオンを生じる物質)が示す性質のこと 水に溶けやすい塩基を、特にアルカリと呼ぶ 【主な塩基】 水に可溶性の塩基(アルカリ) ・水酸化ナトリウム ・水酸化カリウム ・水酸化カルシウム ・アンモニア 水に難溶性の塩基 ・水酸化マグネシウム ・水酸化アルミニウム ・水酸化亜鉛 【塩基の性質】 ・しぶい味がする ・赤いリトマス紙を青色に変える ※ その他の各指示薬によって変色は異なる ・高濃度溶液(pH9以上)は皮膚の細胞膜上の脂肪を分解する →皮膚にかかるとやけどを起こす(酸によるやけどよりひどい) ・手につけるとぬるぬるする ・酸と反応してその性質を弱める作用がある(中和反応) 【塩基の強さ】 塩基性の強い塩基を強塩基、弱い塩基を弱塩基と呼び、その物質の電解度の大小で、 塩基の強弱が決まる 【身の回りの塩基】 ・セッケン水 ・石灰 ・木灰 ・アンモニア水(虫に刺された際に使用)
2011.08.09
-
環境基準
環境基準は、環境基本法の第16条に基づいて定められた「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康を保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、 ■ 大気 ・大気汚染に係る環境基準 ■ 騒音 ・騒音に係る環境基準について ・航空機騒音に係る環境基準について ・新幹線鉄道騒音に係る環境基準について ■ 水質 ・水質汚濁に係る環境基準について ・地下水の水質汚濁に係る環境基準について ■ 土壌 ・土壌の汚染に係る環境基準について ■ ダイオキシン類 ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法(1999)を根拠として、大気汚染、 水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている ・ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準についてに 関する環境基準を定めている。【参考】 環境基本法 第16条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につ いて、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望まし い基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域 を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政 府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事 が、それぞれ行うものとする。 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなけ ればならない。 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に 関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保 されるように努めなければならない。
2011.08.09
-
建築材料
【畳】 ・ 畳の規格 ・ 外国産畳表 ・ 畳表の原料 藺草生産時の農薬 ・ 藁畳の防虫加工処理 【塗料】 ・ 塗料の原料
2011.08.08
-
アセトアルデヒド
【特性など】 ・刺激臭がある無色の液体もしくは気体 【主な用途】 ・接着剤 ・防腐剤 ・写真現像用の薬品 ・香水 ・染料 【健康影響】 ・目、皮膚、気道への刺激 ・めまい ・吐き気 ・嘔吐 ・咳 ・皮膚炎 ・中枢神経系への影響 ・変異原性 ・IARC発がん性分類2B(人に対して発がん性を示す可能性がある) 【その他】 ・二日酔いの原因物質の一つ ・ホルムアルデヒドとよく似た化合物で、ホルムアルデヒドの代替物質として用いられている ものと考えられる ホルムアルデヒドの厚生労働省による室内濃度指針値が設定された後、 ホルムアルデヒドの住宅室内濃度がかなり減少したのとは対照的に、 アセトアルデヒドは上昇しているのではないかと懸念されている物質である
2011.08.06
-
生活改善
今まで地球を資源として乱開発をし、産業廃棄物の処理場とする行為をしてきました。その結果、自然生態系・地球生態系を破壊し、このままではいずれ行き詰まりになると考えらるようになってきました。 ※ 当然そこには各国の政治的な考えなど含まれますが、ここではもう少し身近なところから 考えていきます。平行するように昨今、従来問題にならなかった室内の空気質による健康障害であるシックハウス症候群、さらに微量の化学物質にも反応してしまう化学物質過敏症、最近では3人に1人はいるといわれるアレルギーなど様々な問題が表面化してきました。ここで気づくのは我々の生活の便利さや快適さの追及によって環境問題を引き起こし、さらに従来では考えられなった健康障害を引き起こしているということです。では、この現状にどのように対処していくべきでしょうか? まず我々は、地球環境を考えるという傲慢な考えでなく、この地に生をいただき、住まわせていただいていることに感謝し、いかに我々自身が人間として責任を持って生を営んでいけるかということを真剣に考えていく必要があるように感じます。そこで身近なところから我々自身の生活の改善を行なうことが一歩前へ進むことになると思います。 では、今ある生活を見直し、改善していくとは?言葉にするとやさしく感じますが、なかなか実行するとなると難しいものだと痛感します。一歩前へ踏み出すために行なう「改善」という言葉簡単に意味を考えると、悪いところを改めてよくしていくということになります。さらに、この言葉の意味をもう少し思惟してみると、 善 善悪の善で、法則に適っている、世の中の筋道に適っている、正しいという意味合い 改善 悪いところを改めてよくするということで、過去の絶対否定ではないというように理解できます。ようするに、正しい方向に改めていくということになります。では、一体どのように改めていくべきなのでしょうか?世の中、自分自身がよかれと考え行動を起こした場合にも、逆に弊害を起こすということは多々あります。ここで難しいのは自分にとってよいと考え行動するのか、社会や環境にとってよいと考えて行動するのかによっても結果が違ってくるということです。又、よいことも行き過ぎた場合においては弊害を起こすということもあります。その辺りを見極めるには、生きていく姿勢が問われることにもつながると思います。そう考えると、「改善」とは、人間としての根本の物の考え方について深く考え、姿勢を正して前へ進む一歩だといえます。こうして改善という言葉の意味合いを考えると非常に奥深いものがあると感じます。では、根本の物の考え方を正すとともに、具体的にどのように前に進んでいくかを考えてみます。今日我々が存在するこの21世紀は、1世紀からいきなり21世紀になったのでしょうか?そうではありません。世の中は、先人や先達が営んでこられた日々の積み重ねでできている時間的な流れと、この時間の流れの中で人々が共有している社会的空間の交わりによって日々進んでいます。個々の存在は時間的な流れと社会的空間の交わったところに位置していますが、そこで今日の我々が生を営んでいる時や空間における環境において、様々な問題が起きていることに気づきます。環境の問題や従来では考えられなかった健康障害も気づき始めた問題の一部分だといえます。では、この問題が起きているのはすべて過去からの流れで、先人や先達のされたことはすべて否定しないといけないのでしょうか?そうではないと思います。現在、環境問題や従来では考えられなかった健康障害など様々な問題が起きていることは事実です。これは過去の原因が結果として現在の相として現れ、又、未来に対する警告を意味するものとして真摯に受け止める必要があると思います。では、現在の相として現れた過去の原因についてもう少し検証してみます。我々の生活が、食品や電化製品(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなど)、日常生活用品などの安定供給によって多くの恩恵を受けていることは事実で、ここに至るまでに先人の様々な苦労、犠牲が伴ってきたのは間違いのないことだと思います。しかし、その中には人間がよいと考えて行ってきたことが弊害となって現れている面、又、行き過ぎてしまっている面などがあります。衣・食・住は人間が人間としての生活を営む基本といわれていますが、その基本に対して、科学が急速に進み、物質的優位、物質中心の時代になり、生活や製品開発に善という考えを忘れてきた面があり、それが弊害となっていると考えられます。それは使い手側の我々が低価格でデザイン性もよく、より便利で手間が省けるものを要求し、一方で作り手側はそれに応えるように、こうするとより便利で手間が省けるといった提案を行い、止まることのない製品開発及び供給が行なわれてきたということもあります。当然、研究や開発を否定しているわけではありません。昨今では製品開発におかれても環境を含めた広い視野での製品の研究・開発が行なわれており、研究・開発が行われることにより進歩・発展が期待できるというのも事実です。ただそこに行き過ぎてしまうことや人間中心に考える物質的優位、物質中心の表面的相の豊かさだけに目を向けていくのは問題があると思います。さらに、現在における様々な問題をただ単に過去の原因が引き起こした結果としてだけでとらえるのでなく、未来への警告もしくは未来に対する道を教えてくれているととらえる必要があります。過去行なったことが現在の相として現れるといいましたが、現在引き起こされている環境問題や過去には問題にならなかった健康影響(アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など)の原因の一つであると考えられる「衣・食・住」を中心に急激に進んだ製品開発についてもう一度思惟してみます。まず、先人、先輩方は現在の様々な問題が起こることがわかっていてそのような製品や商品を作り続けてこられたのでしょうか?決してそうではないと思います。その時代その時代に応じて、そのときにできる限りの努力をされ、後世に技術や物の豊かさなどを残されたと思います。しかし、色々な人間が生活している中で、見失うものや行き過ぎてしまったこと、考え違いをしてしまったことなどもあり現在における様々な問題が浮上してきているといえます。そこで様々な問題に気づいた者から改めるべき点を正しく見定め、改善できるように考え行動していくことが必要になります。又、ただ単に人や環境に影響を与える可能性があるといわれる化学物質を多用した日常生活用品が我々自身の健康に直接影響を与えるというのみでなく、それらを使用後に破棄した場合、自然環境に与える付加は非常に大きく、いずれはその影響が我々自身にも戻ってくることも考えないといけません。最後にこれまで我々の生活の便利さや快適さの追及によって環境問題や従来では考えられなった健康障害を引き起こしているという点から生活改善について述べてきました。当然その他にも様々な問題が表面化して、社会的に問題視されています。これらの現実を直視し、急務で一人一人が姿勢を正して、根本の物の考え方を改めていく時期が来ていると思います。ここで大事なことは過去を非難するのではなく、歪が出てきた理由を考え、改めていくことだと思います。過去になかった健康障害が表に出始めるというような身近な問題から環境に影響を及ぼすといった大きな問題が起きている中、そこに気付いたときに我々は一旦立ち止まって改善すべきところを見直し、真摯に問題の解決に当たる必要があると思います。そこで先人による努力の結果の恩恵を受けて生活していることに対して感謝し、改めていくところは真摯に受け止めて改善していくということが大切な一歩を踏み出すことになると思います。※ アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など従来では考えられなかった健康影響や環境問題を切り口に生活改善という根本の意味合いについて述べてきました。これら以外にも様々な問題が表面化していますが、改善を施していくという点についての物の考え方は同じだと思います。
2011.08.06
-
シックハウス相談事例 54
【相談者】 男性 37歳 【受付日】 平成22年10月【相談内容】今年の6月にアパートに妻と二人で引っ越しました。引っ越して間もなくしてから痰と咳が止まらず、すでに3カ月経ちます。病院で診てもらったのですが、風邪、インフルエンザや肺炎ではないといわれました。ただ、アレルギーの可能性はあるかもしれないといわれました。その後また別の病院で診てもらったところ、副鼻腔炎(蓄膿症)と診断され、抗生物質を処方してもらったおかげで少しは改善しました。しかし、今でもしばしば痰、咳、鼻づまりは続いています。勝ってな予想ですが、室内のカビが原因ではないかと思っています。その理由は今のアパートはかなり古い建物の上に、日当たりはほとんどなく、湿気がひどい状態だからです。引っ越した当時は風呂場がカビだらけで、今も洗面所などの天井や壁はもカビの汚れでシミになっています。室内の原因が分かればより対応ができると思いますので、一度現地でお話を聞いていただきたいのですが、よろしくお願いします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ NPO法人 シックハウス診断士協会 広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F 東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F 東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F 電話番号 082-961-5271 FAX番号 082-961-5272 ご相談 & お問い合わせメールアドレス takya1123@dolphin.ocn.ne.jp
2011.08.02
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- 活き活き健康講座
- ☆トレーニングスリッパ☆
- (2025-09-22 20:40:58)
-
-
-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…
- 目指せ絶対的健康体 AIに訊いてみた…
- (2025-11-16 05:16:04)
-