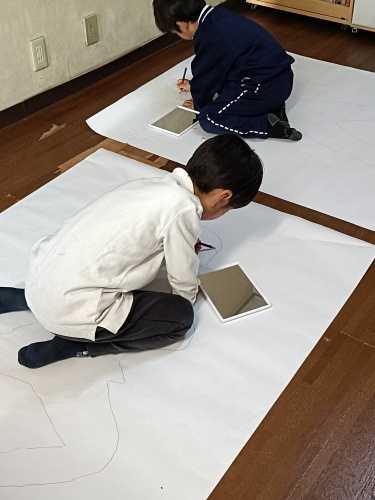2018年10月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

「いろいろな未来のオプションを考えること自体に治療的意味がある」~『心理療法の本質を語る』1
いよいよ、この本を紹介するときがきました。『心理療法の本質を語る ミルトン・エリクソンにはなれないけれど』(森俊夫ブリーフセラピー文庫1)(森俊夫・黒沢幸子、遠見書房、2015,2200円)僕は森俊夫先生の弟子でも何でもありませんが、著書によって大きく影響を受けた一人です。本書を読んだときは、第1章がまるごと、僕の好きな演劇の話だったので、これまた感激しました。かなり詳しく演劇のことが書いてあって、これを機会に寺山修司の芝居DVDをネットで取り寄せて観た、というぐらい、またまた影響を受けました。僕という人間は森俊夫先生に操られているのかもしれません。実際にお会いしたことはないのですけど。今日は、森俊夫先生の遺された「心理療法の本質」から、「これぞ」という1点を紹介したいと思います。それは、「未来」に焦点を当てる、ということです。=============================『心理療法の本質を語る』 1(一応、p134(第4章の終わりまで)より。) ・未来って思ったようになる。(p122)・とりあえず、いろいろな未来のオプションを考えること自体に治療的意味があるかもしれない。・最初はなんで予想課題で患者さんがよくなるのか、よくわからなかった。 でも、予想をすることで未来のオプションをつくっていたのよ。 (p123) ・一直線でもないし、一方向性でもない。全部逆転できるんだよね。(p125) ・何ならできるんですか? 未来は思った通りになりますからね。 思わない未来はできませんからね。 今晩、どんな未来を思うんですか? これが心理療法なんですよ。(p128) =============================過去のことで、思い煩っていませんか?未来は、あなたとイコールです。思わない未来は、こない。思えば、未来は、来るんです。僕の教育実践の中で、「よそうをしよう」というのがあります。予想を考えさせるから、結果がどうなったか、ワクワクしながら学習に参加するようになります。ひとごとでは、ありません。自分事として、自分の未来を、思いましょう。そして、未来の自分にとりもちをつけ、ひっぱられるようにして、未来へ飛んでいってください。ほら、意識を、未来へ!森俊夫先生のことを全くご存じない、という方は、安くて薄いブックレットでめちゃくちゃ面白く読める本がございますので、そちらをまずお読みください。(^^)その紹介は、僕のこのブログの最初期の頃にしています。▼ブリーフ・セラピー(短期療法)は知る価値アリ!!(2006/6の日記)「なんだ、こんなカンタンなことだったんだ!」と笑っている自分、思い浮かびましたか?(^0^)
2018.10.30
コメント(0)
-

「雪が降っても自分の責任」 ~『戦わない経営』
『戦わない経営』という本があります。著者は浜口隆則さん。「幸せをつくっている」会社を経営されています。その本の中の一節。「雪が降っても自分の責任」==========================「雪をいいわけにしても、何も変わらない」「雪が降っても自分の責任」そう、覚悟した。(p77より)==========================どれだけ、自分が、引き受けることができるか。受け入れることができるか。成功のチャンスは、至る所に転がっている。それを、受け入れることができるかどうか、だけですね。『戦わない経営』(浜口隆則、かんき出版、2007、1200円)▼『戦わない経営』【電子書籍】[ 浜口隆則 ]この本は、仕事に向かう、ココロの部分を、考え直すことができます。横書きで、文字量は少なく、すぐ読めます。ただ、すぐ読めるからと言ってすぐに読まず、ゆっくりと、かみしめるように読むのが、本書の場合、いいのかもしれません。
2018.10.29
コメント(0)
-

新しい気づきを与えてくれる『見る見る幸せが見えてくる授業』
来年のゴールデンウイークは10連休だそうです。10連休となれば、やはりどこか旅行に行きたいなあ、と思いました。ずっと行きたかったところに行ってこようと思います。それは、岩手県。宮沢賢治のふるさと。イーハトーブ。宮沢賢治は教師をしていたときもありました。彼は、どんな子ども観を持っていたのでしょう。『見る見る幸せが見えてくる授業』(ひすいこたろう、サンマーク出版)に、宮沢賢治の教師時代のエピソードが書いてあります。========================・宮沢賢治は、作家になる前に高校の先生をしていました。 0点でも、名前だけ書いてあれば 20点をつけてくれたのだそう。 なぜなら、0点の存在など この世界にいないからです。(『見る見る幸せが見えてくる授業』p273より)========================僕の知っている先生の中にも、なかなか点数がとれない子どもたちになんとかマルをつけてあげたいと、名前のひとつひとつにマルをしてあげる先生がいます。そんな先生、すてきですね。『見る見る幸せが見えてくる授業』 [ ひすいこたろう ]『見る見る幸せが見えてくる授業』【電子書籍】[ ひすいこたろう ]僕は宮沢賢治の『やまなし』が好きで、歌も作っています。ついでに、宣伝します。(^^)▼クラムボンはわらったよ(宮澤賢治『やまなし』より「五月」の主題による小品)
2018.10.28
コメント(0)
-

「真剣に遊ぶことだ!」~岡本太郎『原色の呪文』
「芸術は、爆発だ!」で知られる岡本太郎。彼の本もまた、芸術的です。芸術とは何か。あなたはどう生きるべきか。あなたが芸術的に生きるためのヒントが、きっとあります。『原色の呪文』(岡本太郎、講談社文芸文庫)▼【電子書籍版】=============================岡本太郎『原色の呪文』 ・ごま化して功利的に動こうとすると、自分自身に信用がおけなくなる。 かえって無限に己れを弱くしてしまう。(p14)・見るということ自体に、あなた自身が創るというけはいがなければならない。(p131)・「なぜ、あなたがたはうまく描こうとするんですか。」 「うまく描く必要なんかみじんもありません。 かまわないから、どんどん下手に描きなさい。」 「そうです。でたらめなら、なおいいんだ。 でたらめに描いてごらんなさい。」(p137)・おもしろいところで作った芸術でなきゃ、おもしろいはずがない。(p210-211)・大事なことは、功利的でない、無目的な生のよろこびに全身をぶつけ、真剣に遊ぶことだ。 むなしい目的意識や卑小な合理主義にふりまわされてしまわないで。 自分が<何々である>とか<何々が出来る・出来ない>ということよりも、 <こうありたい>、<こうなりたい>ということのほうを中心に置く。(p233)=============================本の中に所収された、書かれた年がそれぞれ違う岡本太郎の著した文章より、その断片をつなぎあわせてみました。そうすることで、年を隔てて見えてくるものが、ある気がします。はっきり言って、それぞれ別々に読んでいたときには、なんだかよく分からなかったです。(笑)今から新しい挑戦をしようとする、すべての芸術家への強烈な檄。やりたいことをやってみようとする元気を、もらいました。爆発的エネルギーを、あなたにも。
2018.10.27
コメント(0)
-
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える・・・つもりです。(^^)
昨日の日記で「勤務市の人権教育研究大会で『読み書き障害』についての発表をすることになりました。」とふれました。その発表原稿の仮原稿が土曜日にできあがったのですが、せっかくなのでその最初の部分をここで紹介したいと思います。まだ直す可能性が大いにありますが、むしろ直す箇所があればご指摘いただければありがたいです。(ここで載せるのは、ほんのさわりだけですけど。)発表自体は11月17日土曜日です。興味のある方がいらっしゃいましたら、別に誰でも参加できる会ですので、ぜひいらしてください。(^^)■読み書きに困難のある子の学習保障~通級指導担当の立場から~===========================1. はじめに このレポートでは主として小学校における読み書きに困難のある子どもたちをとりあげる。教科書の音読がたどたどしかったり、文字を書くことが苦手で自力ではなかなかスムーズに書けなかったりする子どもたちである。こういった子どもたちの中には、「読み書き障害」(ディスレクシア)の診断を医療機関で受けている子どもたちも含まれている。しかし、「読み書き障害」については一般にほとんど知られておらず、本人・保護者・教師に気づかれないまま、他の子どもたちと同じように読み書きができないことを苦痛に感じている子どもたちもいると思われる。「読み書き障害」については少数ながら当事者が手記を出版しているが、「学校では理解してもらえず、読み書きの困難さにより学習意欲が喪失した」と語っていることが多く、教職員の多くにその存在や手立てが知られることに課題があった。今でも教職員の理解には差があると思われ、最も専門的に読み書き障害への対応をおこなっている通級担当が、教職員への情報提供と連携を進め、必要な子どもたちに必要な手立てがとられるようリーダーシップをとる必要が高い。「読み書き障害」の理解啓発が重要である理由は、読み書きの困難さの理由が脳の機能障害にあるからであり、単に量をこなす指導が意味をなさないからである。スムーズに読み書きができる者には理解できないのだが、通常の読み書きを行うための脳の回路が使えない場合、別ルートを代替して文字を読み書きしようとする。例えば字を書く場合、文字の一つ一つについて、形を思い出しながら書くために時間がかかるし、「こんな形だったかな」と苦労しながら、線を付けたし、正しい字形に近づけていくことになる。スムーズに読み書きができる者の「書く」行為とは、全く異なる苦労がある。「読み書き障害」のことを知らなければ、単に文字を読み書きするだけのことにどうしてそんなに苦労してしまうのかがわかず、単に練習が足りないからだと思い込み、とにかく量をこなすことで改善しようとして、よけいに読み書きを嫌いにさせてしまうことも起こりえる。そうではなく、障害を理解し、本人に合ったやり方で読み書きを指導したり、または読み書きを代替する手段(代読や読み上げソフトの利用、音声メモの利用等)を検討したりしていくべきだと思われる。(以下、略)===========================ご意見募集中でーす。
2018.10.21
コメント(0)
-

読み書き障害がテーマのマンガ『ぼくの素晴らしい人生』がおもしろい
勤務市の人権教育研究大会で「読み書き障害」についての発表をすることになりました。そのレポートの「はじめに」に何を書くべきか、悩んでいましたが、あるマンガを読んで、すっきりしました。特別支援教育のメーリングリストで教えていただいた本です。『ぼくの素晴らしい人生』(第1巻) (愛本 みずほ、BE LOVE KC)『ぼくの素晴らしい人生』1巻【電子書籍】物語の主人公は「ディスレクシア(読み書き障害)」です。しかし、自分が「ディスレクシア」であることに気付いていませんでした。彼は、同じくディスレクシアである喫茶店のマスターから、「もしかして、きみ、ディスレクシア?」と言われます。「読み書き障害」の理解啓発が必要である理由を再確認できた本書は、僕が発表の最初に訴えたいことも明確に思い出させてくれました。マンガとしてもとてもおもしろく、まだ1巻だけしか読んでいませんが、思わず笑ってしまったところが何カ所かあります。思わず笑ってしまったところは読んでいただいてからのお楽しみとして・・・「読み書き障害」の理解啓発につながると思った場面を2つ、紹介します。============================= 『ぼくの素晴らしい人生』第1巻 ・「あの文字の書き方が 字を書いてるっていうより 覚えてる「形」を書いてる感じだったから オレと一緒かなって」 (P33より) 喫茶店のマスターから、ディスレクシアではないのかと思った理由を聞かされる場面より。 字を書くときの特徴を、短い表現で的確に表現されていると思いました。 p56以降でも、「読み書き障害」とはどういう障害かということを分かりやすく説明されています。 ・「オレ ずーっと ペーパーテストじゃなくて 口頭で解答させてくれって 思ってたなー」 「問題読むのも書くのも時間かかって・・・ 読んでくれたら 口では答えられたんだ 授業はちゃんと聞いてたから」 (P93より) 2人でディスレクシア「あるある」を話している場面より。 「こんな支援があればよかった」は、支援に携わる人が絶対に聞いておきたい内容です。 =============================読み書き障害の当事者の方が書かれた本は積極的に読んできましたが、マンガで読むと、やはりスッと入ってきますね。登場人物の動きや表情と一緒にセリフにふれられることで、より感情移入できるからだと思います。今まで知りませんでしたが、知ってよかったと思える本。おすすめです!▼公式サイト (第1話の試し読みができます。)P.S.2018/10/23追記メーリングリストで単行本化されていない雑誌掲載内容を読まれた方より教えていただきましたが、「ディスレクシアあるある」は、実はそうではないのだけれど誤解してそう思っている部分もあるようです。ディスレクシア理解の入り口としては第1巻はとてもいいと思うのですが、あまり簡単に言い切れない部分はあるので、個々の違いの部分も含めてよく勉強していかないといけない、と改めて反省しました。補足いたします。
2018.10.21
コメント(0)
-
読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる!
ずっと気になっていた運転免許を取るときの合理的配慮について、福井県の特別支援教育センターの冊子に記述がありました。 福井県運転者教育センターの学科試験問題用紙には、すべての漢字にルビがふってあるそうです。 また、問題集のマルチメディアデイジー図書も提供されているのだとか。 こういう「かゆい所に手が届く」情報がスッキリとまとめられている福井県の冊子、ネットで無料公開されているのがすごい! 特別支援教育関係者全員に読んでほしい情報が満載です。『「読み」や「書き」に困難さがある児童生徒に対するアセスメント・指導・支援パッケージ』 (福井県特別支援教育センター、H30.8-)内容は本当に充実していて、目次を読んでいただければ、その充実具合がわかると思います。以下、目次です。個人的に目立たせたい項目を、太くしたり、でっかくしたりしています。================================== 基本的知識 合理的配慮について 第1部 年齢段階別の指導・支援編 読み書きに困難さがある子どもの育ちと指導・支援の全体像 1 小学1~2年生に対する支援 (1)概説 (2)通常学級の全員を対象としたアセスメントと指導 ① 多層指導モデル MIM を活用した特殊音節の指導 ② T式ひらがな音読支援(旧 鳥取大学方式) (3)個別指導場面や家庭で活用できる教材や指導法 ① ひらがなの基礎的な指導:「キーワード法」を活用した指導 ② ひらがなの基礎的な指導:「 50 音表」を活用したひらがな指導(聴覚法) ③ ひらがなの基礎的な指導:「 50 音表」を手掛かりにした書字指導 ④ ひらがな,カタカナの指導に使えるアプリ紹介 ⑤ 漢字の指導に使えるアプリ紹介 ⑥ 小学校の国語教科書(光村図書)に準拠したアプリ紹介 ⑦ アプリ等を探す際に参考となる web サイト紹介 ⑧ スマイル式プレ漢字プリント(小1~小6) ⑨「ミチムラ式漢字カード」による漢字指導(小1~中3) 【コラム】読み書きの困難さが著しい子どもへの支援 (4)補助代替手段の活用 ① デジタル化された教科書(マルチメディアデイジー教科書)の活用 ②「魔法の定規(リーディングルーラー)」の活用 ③ 「わくわく算数教科書ノート(啓林館) 」の活用 (5)事例紹介 ① 読み書きの指導と課題量の軽減 2 小学3~6年生に対する支援(1)概説(2)個別指導場面や家庭で活用できる教材や指導法 ① スマイル式プレ漢字プリント(小1~小6) ② 「ミチムラ式漢字カード」による漢字指導(小1~中3) 【コラム】漢字はどこまで厳密に採点すればいいの? ③ ローマ字の指導に使えるアプリ等 (3)補助代替手段の活用,合理的配慮の検討 ① 学習者用デジタル教科書(光村図書出版:国語)の活用 ② 読みの困難さへの対応:iPadの「音声読み上げ機能」の活用 ③ 書字の困難さへの対応:iPadの「フリック入力」の活用 ④ 書字の困難さへの対応:デジタルメモ「ポメラ」の活用 ⑤ 総ルビ問題の活用 ⑥ デジタル化された教科書(マルチメディアデイジー教科書)の活用 ⑦ わいわい文庫(マルチメディアデイジー図書)の活用 (4)事例紹介 ① 読み書きの困難さに対して配慮を行った事例(小3) ② 漢字学習における配慮例(小4) ③ 授業やテスト場面での配慮例(小4) ④ 中学校に合理的配慮を引き継いだ事例(小6~中1) 【コラム】通常学級の担任の視点から 【コラム】学習面以外の苦手さも併存するケースについて (5)他の児童・生徒に対する理解・啓発について ① 障害理解授業の実践 ② iPad を教室で使用する前の理解授業 3 中学生・高校生に対する支援 (1)概説 (2)個別指導場面や家庭で活用できる教材や指導法 ① 学習者用デジタル教科書(光村図書出版:国語)の活用 ② anki Pocket(東京書籍)の活用 (3)補助代替手段の活用 ① デジタル化された教科書(マルチメディアデイジー教科書)の活用 ② デジタル化された教科書(AccessReading)の活用 ③ 読みの困難さへの対応:タブレット端末の音声読み上げ機能の活用 ④ 読みの困難さへの対応:iPadアプリ「タッチ&リード」の活用 ⑤ 書字の困難さへの対応 (4)事例紹介 ① テストにおける時間延長の取組(小学校,中学校) ② 事故の後遺症による書字困難への配慮の取組(中学校) ③ 英語の単語テストでの配慮の取組(中学校) ④ テスト問題へのルビ振り,代読等の取組(中学校~高等学校) (5)合理的配慮 ・代読(読み上げ)の実施方法 ・大学入試センター試験で配慮を受けるには? 【コラム】教育以外の場面で合理的配慮は受けられるの? (自動車運転免許取得の際や資格試験等の受験の際に) 【インタビュー】高校生にインタビューしました第2部 アセスメントの紹介 1 集団実施に適する簡易なアセスメント ・MIM-PM,T式ひらがな音読支援の簡易アセスメント ・スマイル・プラネット版 読み書きスキル簡易アセスメント 2 基本のアセスメント ・全般的な知的能力の発達を測定する検査 田中ビネー知能検査Ⅴ ・WISC-Ⅳ ・K-ABCⅡ ・実践ガイドライン ・STRAW-R(改訂版) ・URAWSS-Ⅱ 3 より詳細なアセスメント ・URAWSS-English ・CARD(包括的領域別読み能力検査) ・『見る力』を育てるビジョン・アセスメント「WAVES」 参考図書巻末資料 T式ひらがな音読支援の1年生向け簡易アセスメント 問題用紙,記録用紙一式) ==================================最新情報が整理されているので、10月13日にご紹介した『読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A』と一緒に読めば、完璧ですね。具体例が山ほど紹介されていますので、気になったものは自分でも調べたり、買ったりしています。ネットで無料で利用できるスマイルプラネットのプリントなどは、この冊子の情報から知りました。「魔法の定規(リーディングルーラー)」も、ネットで注文して、買いました。この冊子の総ページ数は172ページ。かなりのページ数になります。目次を参考に、まずは興味があるところだけ、分割ダウンロードで読んでみても、いいと思います。PDFファイルです。
2018.10.17
コメント(0)
-

『斎藤一人 魂力』 ~「ゲームをするように片付けられる」
昨日のブログで『人間力』を紹介したので、次は『魂力』。どちらも、著者の信長さんが斎藤一人さんと対談したものを出版されています。『人間力』が1回目の対談、『魂力』は2回目の対談です。 『斎藤一人 魂力 一人さんと二人で語った一番長い日』(信長、信長出版(サンクチュアリ出版)、2018/2、1400円) この本の中で、楽しく仕事することの極意が出てきます。それは、僕の大好きな「ゲーム」。「ゲームのように」というのは、僕が日頃心掛けていることですが、一人さんも同じようなことを言われていたので、とても心強く感じました。============================= 『斎藤一人 魂力』 ・ゲームに慣れておくことで、自分に起きる問題もゲームをするように片付けられるようになるだろうね。 あと、新しいゲームを創り出せるような人が、新しい商売できるようになるよ。これからは、世の中のすべてのことがゲーム感覚になっていくの。 (P100~101より)本当に、心強い。まるで、僕に言ってくれているんじゃないかと思えるほどです。(^0^) ちょっと前に「エクセルゲームプログラミング講座」というのをやって、そろそろエクセルゲーム以外の、次のゲームを世に出す時が来たと思っているので、背中を押された感じです。(笑) ・もし今、二万部ほど本が売れているとするならば、その次は、「三万部売るゲーム」あたりにして、確実に叶えられる目標にするんだ。そうすると、目標がクリアできるからお祭りができるんだよ。 (P122より)スモールステップでちょっとがんばれば手が届く目標を設定するのは、学習指導の際にもよくやります。自分自身にとっても、そうあるべきですね。そして、目標が達成出来たら、お祝いをする。ごほうびが、動機づけになる。なにしろ人間はすぐにやる気をなくしてしまう生き物ですから・・・。 ・「バンザーイ!」だけがいいの。・そんな簡単なことでいいんだよ。 (P126より) ついついお金がかかるごほうびを思い描いてしまいがちですが、一人さんが言われるように、「バンザーイ!」だけがいい、これが長続きするコツですね。僕はいつもお金がかかるごほうびで、「金でやる気を買う」ことしか考えていないので、もっと純粋な心で、達成できたことを心から喜びたいと思います。今回、久しぶりに、ブログを4日連続で更新しました。バンザーイ!(予約投稿だから実際は4日かけてないけど)============================= 一人さん関連本は、これまでにも多数ご紹介しています。このブログの右サイド欄にある「キーワードサーチ」でブログ内検索をされると、山ほど出てきます。このとき、下の選択肢を、必ず「このブログ内」にしてくださいね。それでは、よければほかの記事も、検索して読んでみてください。
2018.10.16
コメント(0)
-

『斎藤一人 人間力』(信長)
昨日のブログで仕事術の本として齋藤孝さんの本を紹介したので、次は斎藤一人さん。サイトウつながりですね。(^^)一人さんご自身の著書でもいいんですが、ちょうどそこにあったのが信長さんの著書なので、そちらを。信長さんは一人さんファンのカリスマホスト。一人さんと2人で語った対談を、そのまま本にされています。ここでしか聞けない話も、ちらほら。そんな中から、僕が個人的に重要だと思ったところをご紹介します。『斎藤一人 人間力 一人さんと二人で語った480分』【電子書籍】[ 信長 ]『斎藤一人 人間力 一人さんと二人で語った480分』(信長、信長出版(サンクチュアリ出版)、2017、1400円)=============================『斎藤一人 人間力』・最初の被害が少ない時にやらないとダメなの。・最初にちょっと気になることがあるのなら、 即、気がついたときに言っておくの。 (P98)・本当に自信がある人は、いつも謙虚でいられる人だよ。 威張ったりする人は、実際には本当には偉くないから威張っているだけなの。(P113)・全体的に楽しい話が8割で、ためになる話が2割くらいでいい(P188)=============================「威張ってはいけない」「なめられてはいけない」は、一人さん流仕事術の重要キーワード。気がついてときに即、なんてのは、ほんとにそう、そう思います。でも、思っていても、できないときがあるんだよなあ。僕はどうしても、そのときの元気、エネルギーに左右されてしまいます。だから、疲れているときは、余計疲れるようなことになってしまうんだろうなあ。疲れず、楽しく仕事をするには、どうしたらいいのだろうか?その答えを探しに、次回は、2度目の対談を収録した『斎藤一人 魂力』へと、つづきましょう。関連する過去記事▼『斎藤一人 あなたに奇跡が起こる不思議な話』~「本気ですか?」( 2018年10月7日)▼斎藤一人『絶対、よくなる!』( 2016年10月30日)
2018.10.15
コメント(0)
-

齋藤孝『いつも余裕で結果を出す人の複線思考術』
齋藤孝さんの本は、よく読みます。3色ボールペン片手に。(笑)ブログで紹介しようと思って置いていたのは、『複線思考術』。『いつも余裕で結果を出す人の複線思考術』(齋藤孝、講談社、2015、1500円)【電子書籍版(楽天Kobo)1200円】上の商品写真だと帯がないですが、帯がまず秀逸。「自己←→他者」「主観←→客観」「部分←→全体」「直観←→論理」この4つが帯に書かれていて、非常に興味をそそりました。木を見て森も見るみたいな、複眼的思考(複線思考)、大事だと思うんですよね。失敗するときは、たいてい、部分しか見ていない、みたいな。将棋とかだと、てきめん。自分の駒しか見ていないと、負ける。(笑)そういうわけで、おすすめの本です。普通とは違う着眼点で、自分だけでなく、相手も生かすことができます。たとえば、相手がどうでもいいことに力を入れている場合。普通ならこれは、ストレスです。しかし、齋藤孝先生は、これを、ほめます。「エネルギーをかけた行動自体がすごい」とまず誉めるのです。そして、「ここにエネルギーをかけたんだね、それは理解できた。次はここにかけてね」という言い方をする。そうすると、みんなのストレスが減ってくるんだそうです。(p74より)うん、非常に理解できます。(^0^)この本は、タイトルの「複線思考術」がメインではあるのですが、単純に仕事術の本としてもすぐれています。たとえば、「謝罪だけは遅れてはいけません」というようなことが書いてあります。・一番大切なのはスピード・最初の電話は謝罪だけ・「考える余地なし」と決めておく・こまめな連絡は、ストレスを減らしてくれます(すべてp166より)僕は謝罪のことばっかり考えているので、この教えは特に強く印象に残りました。(笑)コインの表裏が両方見えていれば、マイナスをプラスにすることも、できるかもしれません。さあ、あなたもレッツ、複線思考。僕が一番苦手な分野です。
2018.10.14
コメント(0)
-

『読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A』
11月に読み書き障害の子どもの学習保障を中心テーマとした発表を行います。そのこともあって、読み書き障害の子どもへの指導や支援について、ここのところずっと、書籍等で調べてきました。今日は、その中でも、特に「これは!」と思ったものをご紹介します。『読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A』(河野俊寛、読書工房、2012、1800円)素晴らしい本です!読み書き障害に関する基本的な知識から、使えるいろいろな支援の選択肢、はてはLD(学習障害)の登場人物が登場する本や映画のリストまで掲載。類似本を全く読んでいなくても、この本を読んでおけば、ある程度安心、と言ってよい内容です。そのため、読み書き障害の子どもへの支援についての本を初めて買い求める場合には、まさにベストバイと言えるのではないでしょうか。実は、発行が2012年だったので、読む前は「ちょっと古いかな」と思っていたのですが、まだまだ使える知識ばかりでした。しかも、かなり読みやすい。いやあ、いい本です!各学校に配りたいくらい。(笑)具体的な中身については、上の画像から飛んでいるリンク先(楽天ブックスさん)から、少し情報を転載します。ちなみに、楽天ブックスでの口コミ評価は、今現在で 4.50 です!===========================【目次】(「BOOK」データベースより) 0 河野先生と考える読み書き障害を理解するためのはじめの一歩/1 読み書き障害に関する基礎知識(読み書き障害と知的障害は違うのですか?/読むことだけ、あるいは書くことだけに困難な人はいますか? ほか)/2 読み書き障害の検査・評価(読み書き障害であるということは、どうすればわかりますか?/知的能力は、どのようにして確認しますか? ほか)/3 読み書き障害のある子どもへのサポート方法(読み書き障害の子どもへのサポートは、「読めるようにする、書けるようにする」という方針でいいですか?/ひらがなの読み書きを改善する指導方法を教えてください。 ほか)/4 相談を受けてから支援までの具体的な事例(小学1年生の事例/小学3年生の事例 ほか)/5 巻末資料(補助代替ツール/用語解説 ほか)===========================目次を見るだけでも、知りたい情報が見事に整理されている、という印象を受けます。イラストも豊富で、負担なく読めます。保護者にも、先生にも、おすすめ。未読の方で、関心のある方は、ぜひ!なお、この本に書いてあって僕が勉強になったのは、「視覚的な原因から漢字の読みが困難な場合、 漢字にふりがなをつけるという支援は、じつは支援になりません」(p66)というところ。市販のルビうちテストがかなり利用しやすくなってきた現在、漢字が読めない=ルビうちテストの利用、となりそうなのですが、子どもの特性をしっかり理解しておかないと、有効な支援にならないかもしれません。安直な発想でそう思いがちだったので、反省させられました。(ただ、パソコン画面上の漢字にルビを表示させる支援と異なり、ルビうちテストのルビは細字で目立たないようになっていることが多いです。有効か有効でないかは、実は試してみないと分からないのかもしれません。)あと、もう一つ勉強になったのは、「知的障害などの特別支援学級の弾力的運用」について。「校内に特別支援学級がある場合、通級指導教室のように利用すること」(p101)ができるそうです。実は、そういう事例は知ってはいたのですが、校内の運用で特別に行っていると思っていました。こういった本に書いてあるということは、公的に認められているんだな、と驚きました。通級の対象者はあまりにも多くて、通級担当者が全然足りていない現状があるだけに、支援学級を通級のように利用することができれば、それで救われる子もけっこういそうです。このほかにも、具体的な支援ツールの名称を次から次へと知ることができ、本書から芋づる式に情報を参照していくことで、「こんな支援があれば」と思っていたものが、「実はあるんだ!」と歓喜の涙で発見できることも、期待できそうです。そんなわけで、強くおすすめする次第です!!(^0^)
2018.10.13
コメント(0)
-

『斎藤一人 あなたに奇跡が起こる不思議な話』~「本気ですか?」
「これはとてもよかった。ブログで紹介しよう!」と思える本があります。今、かなりたまっています。(笑)今日はその中から、シンプルな教えの一人さんの本をご紹介。一人さん本は今までに何度かご紹介しましたが、かなり久しぶり。書かれたのは一人さんのお弟子さんの柴村恵美子さんです。一人さんの教えがでっかい字で、ばーんと飛び込んできます。おすすめです。『斎藤一人あなたに奇跡が起こる不思議な話』(柴村恵美子、PHP研究所、2018/4、1000円)『斎藤一人 あなたに奇跡が起こる不思議な話』【電子書籍】(柴村恵美子、850円)=============================『斎藤一人 あなたに奇跡が起こる不思議な話』・キーワードは、 「本気ですか?」(P9)・人に威張らない。これだけ気をつければいい(P32)・「自分は困らない」を前提にするんです。 なぜ困らないのか、理由は必要ない。 まず「自分は困らない」と決めつけるんです。(P39)・最終的には、笑顔とやさしさ・ひとりひとり、違う楽器 (P122)・相手を美化して見る、いいほうにデフォルメして見る (P131)・相手が愛を感じるような表現のしかたを、もっとよく、もっとよくしていこうと、自分を磨き続けること(P136)=============================今、健康面でも仕事面でもちょっとした壁にぶち当たっています。壁を乗り越えられるかどうかは、ここに挙げられていた心がけ次第かな、と思っています。本気かどうか。困る必要はない。笑顔とやさしさ。相手のいいところを見る。こういったシンプルな教えを忘れずに、来週顔晴ります!関連する過去記事▼斎藤一人『絶対、よくなる!』( 2016年10月30日)
2018.10.07
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1