2009年01月の記事
全67件 (67件中 1-50件目)
-

日立 CV-W61 掃除機の修理
突然、掃除機が壊れました(T.T) 日立CV-W61型掃除中にモノを詰まらせたようでモーターに負荷がかかりすぎて壊れたみたいです。モーターが焼けた?と思って臭いがしないかを確認してみたのですが、どうやらその気配がありません。ということは、どこかの断線かヒューズ切れと判断しました。早速ネジを外して分解していきます。モーターはガッチリ取り付けられているものと思いこんでいたのですが、意外なことにはめ込まれていただけ(>__
2009/01/29
コメント(1)
-
シールはがしにスクレーパー
100均のダイソーで買ったスクレーパーです。他にも整備ツール販売のショップでも似た形状のものが売られています。車検の時、クルマのステッカー剥がし、コンロの焦げ付きを剥がす時とこれでもなかなか使い道はあるものです。刃の幅が広くて便利なようですが、イマイチ使い勝手は良くないかも。KTCのものは半分くらいの幅なので割と細かな作業も楽に行えますがこれはRの強い曲面部分にはうまく刃が当たらず不向きです。丁寧に何度も刃を立ててやればいいんですけどね(^o^)100均のスライド式は使用時にガタつくので今はツールカンパニー・ストレートの黄色と黒の200円ほどのスクレーパー使ってます。
2009/01/29
コメント(0)
-
簡易タイヤゲージで残り溝測定
ステンレス製の定規でも使い方ひとつで残り溝を簡単に測定が出来ます。適当な薄いプラ製のカード(不要なメンバーズカード等)にカッターで2箇所切り込みを入れて上、下、上と定規を通します。これで完成!カード部分を山に当てて定規を溝に入れて軽くカードを滑らすとOK!ノギスでも測定出来ますが貧乏なので身近なモノを活用してました。
2009/01/29
コメント(0)
-
タイヤゲージ 1
昔、タイヤショップの営業さんから頂いたタイヤゲージ。それまではスレンレス製の定規で残り溝を測っていましたが、これはさすがに専用品! 便利ですね~車検の時に使うくらいですがあれば便利なツールのひとつです。
2009/01/29
コメント(0)
-

新しい玄関周りの3連スイッチ
こちらが交換した新しい玄関周りの3連スイッチです。上側2個は一般的なスイッチで、オン、オフすると即座に電灯が点いたり切れたりします。一番下のスイッチには、タイマー回路が内蔵されておりオフにすると数秒後に電灯が切れます。ホームセンターで偶然入手しましたが、これは便利かも。夜間のお出かけはあまりありませんが、靴をはいて玄関から出てしばらくするとパチンと切れます。また玄関スイッチだけホタルが点灯しますので夜中でもスイッチの場所がよくわかります。狭い玄関ですので、これで真っ暗闇でぶつかる事も解消されました(笑)
2009/01/28
コメント(0)
-

昔懐かしいスイッチです
これまで壁に取り付けられていた壁面の3連スイッチ。横に電線をネジで締め付けてとめる構造です。これにビニールテープをぐるぐると巻いて絶縁してました。壁から外して見ると、長期間の劣化でテープはボロボロになっており、そこに壁の中のゴミやホコリがギッシリと(^^;;;あぶないあぶない。。。
2009/01/28
コメント(0)
-

ナショナルのスイッチ
ごく一般的なナショナルのスイッチの裏面画像です。右端の長細い穴は、マイナスドライバーを奥の方まで押し込んでテコの原理でひねる事で差し込まれた電線を簡単にスポッ!と抜く事が出来るようになってます。すぐ左にある丸い穴が電線を差し込むだけで結線が出来る簡単な構造になっている端子です。電線の被膜を1cmほど剥いて差し込むだけですから電気工事の手間は大幅に軽減されていますね。他のメーカーのものも似たような構造かと思います。単価はひとつが150円程度だったかな?ホタルつきだと500円程度で売られていると思います。
2009/01/28
コメント(0)
-

トイレのスイッチ交換
自宅のトイレの壁スイッチを交換しました。以前ここは古い古いトグルスイッチで、使うたびに「バチン!」という今にも壊れそうな感じのスイッチでした。家族にはスイッチが大きくなって大好評です。操作も大きなスイッチ部分を軽く押すだけですからとっても楽です。夜間は小さなホタル電球がポワッ!と光りますので暗闇の中でも確実にトイレのスイッチを見つけられて便利になりました。これまでは壁を手探りでスイッチを探していましたが、これなら夜間も見ただけですぐにわかります。交換作業は至って簡単で作業時間も10分ほどです。旧型のものとは壁に開いた穴の大きさが多少違うのでノコギリ等で穴を広げる加工をしました。
2009/01/28
コメント(0)
-
carrozzeria DEH-P630 取り付け
以前のSANYO CDF-MP330が音飛びを起こしたりエラーが出るようになってしまいましたのでお小遣いを貯めて買い換えました。ポイントは日本語表示とUSBメモリによるmp3再生だけでした。2万円ちょいでmp3再生時に日本語表示が出るものが買えるのですからいいんじゃないかな?と思いましたが実際は使いにくいです。SANYOのデッキの方が単純な操作で操作ミスもなく選曲が出来て良かったですね。こちらはロータリーボリューム&セレクターという左の丸い部分で音量、選曲、フォルダ移動、設定他をまとめて操作するので少々慣れても使いにくさ抜群です。ロータリーボリューム&セレクターがもっと出っ張っていれば少しは使いやすいかもしれないので何か適当なものを両面テープで・・・音のほうは低音があまりに弱すぎてサブウーファーを買い足したいと思わせるくらいです。とりあえず音質設定で何とかしてますが・・・これは買って失敗だったなぁ・・・orzとりあえず取り付けに20分、あっというまに完了です
2009/01/28
コメント(0)
-
GC8 リビルド オルタネータ交換
10万kmを超えましたのでリビルド品のオルタネータに交換しました。金額は25000円 税別 外したものはリビルドメーカーに送り返します。まずはバッテリーの端子を外します。(これはお約束!)手前のカバーを外し、B端子と配線コネクタを抜き、左側のベルトテンショナーを緩めてオルタネータを固定しているボルトを抜きます。右側のボルトはテンショナーの支点になっているのでこれも抜きます。プーリーにかかっているベルトを外しオルタネータを外します。固着していたのでCRCを吹きましたが案外簡単に外れました。リビルド品を逆の順序で組み込みます。最後にベルトをかけてテンショナーを調整してカバーを元に戻して終了です。チェックが完了したらエンジンをかけて確認します。交換作業は20分ほどで済みました。
2009/01/28
コメント(0)
-

GC8 フジツボ レガリス スーパーR 取り付け
車検に備えてマフラー交換しました。以前の5次元ボーダーファイヤーボールからフジツボレガリススーパーRへ交換したのですが、その際に注文した部品としてスバル純正部品のガスケットを1個使用しました。このガスケット、特徴的なのはテーパー状になっていてフジツボのマフラーにそのテーパー面を、フロントパイプに平面側を向けて取り付けます。ガスケットの定価1090円、部品屋さんで割引して貰い税込みで1034円でした。このガスケット、次回マフラー交換時に固着していたらマイナスドライバーとハンマーで叩きながら壊すしか無いのが不便なところですね。以前装着していた5次元ボーダーファイヤーボールマフラー排気音はJASMA SRなので大きめ・・・(すごく控えめな表現?)早朝や深夜にエンジン始動するのは躊躇しちゃいます。サイレンサーを使うと少々大人しくなりますが、車室内にもやはり水平対向のドコドコ音が響きます。サイレンサー無しだと・・・室内でも爆音です(>__
2009/01/28
コメント(0)
-

ユピテル レーダー探知機 SG290CWの電池交換
ユピテルのレーダー探知機SG290CWの電池がとうとう使い物にならなくなりましたので新しい電池に交換です。2年も使うと充電しなくなってしまうんですね。VARTAというドイツのメーカー製で型番は3/CP300H。(画像はすでに解体済みです。直列になってるんですね。)早速近所の部品屋さんで注文してみましたら「手に入らない」とのお返事(>_
2009/01/28
コメント(0)
-
GC8 ブルーミラー
修理も空しく、結局ブルーミラーは交換しました。表面のミラーコーティングがどんどん剥げてきて後ろが非常に見づらくなってしまいました。部品取り寄せのついでに交換はDラーでやってもらいました。が、冬場の交換で両面テープの暖め方が不足していたのか圧着が足りなかったのか、駐車中に落ちてました。割れはしませんでしたが、走行中に落ちたら後続車が危険!Dラーとはいえ、いい加減な作業はいけませんね。もちろんクレームの連絡を入れてホームセンターで両面テープを購入して貼り直しました。ワイドドアミラー J2717AC010 6400円このミラーって、レガシーと共通だったんですね。後日、反対側のミラーが走行中に脱落しました。運良く割れもせず欠けもせず路上で回収出来ました。Dラーには再度クレームの連絡を入れて自分で貼り直しました。冬場の両面テープでの接着はヒートガンかドライヤーで暖めて行わないとダメですね。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/28
コメント(0)
-
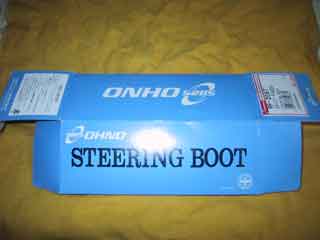
GC8 ステアリングラックブーツの交換
オイル交換の時に見つけたステアリングラックブーツの破れ。ラック&ピニオンブーツとかステアリングブーツとか名前がいくつかあるみたい?これは下に潜らないとなかなか見つからないトラブルですね。車庫入れでハンドルを左右に切り倒すので傷みも激しかったようです。ものの見事に左右ともまん中から裂けてました。純正対応品が1個1000円だそうで、購入して交換しました。大野ゴム製のもので、タイロッドを外しての大がかりな作業になりますが破れたままでは車検に通らないので・・・ドライブシャフトブーツもそろそろ交換せねば危険かも(^^;;;最近は分割式のものが手軽で耐久性もいいみたいですね。破れてから替えるか破れる前に替えるか、財布と相談です。交換したステアリングラックブーツ。すでに汚れてる(笑)右はドライブシャフトのアウター側ブーツ。ハンドルを切るとクネクネ曲がりますので傷みも激しいかと。交換中の画像はありませんが、ラックエンドを外す時に専用のプーラーが無いと厳しいかも。また交換するときにはラックエンドを抜きますので必ず印を入れて元の状態(長さ)へ戻す必要があります。これが出来ないと車が直進しなくなったりします(^^;;;作業が終わったら車検場近くのテスター屋さんで簡単に測定して貰うかショップでアライメントを測定して貰いましょう
2009/01/28
コメント(0)
-
ガラス磨き キイロビン
しばらくガラス掃除をサボっていたら、ガラス表面が物凄いことになってしまいました(^^;;;白いウロコ状の水垢でビッシリと覆われ、指の爪先で軽~くなぞるとカリカリと引っかかり固くなっているのがわかります。ここで画像のものが役立ちました。 キイロビンです。数年前に購入していたものですが、ほとんど出番は無く倉庫の奥で眠っていたのを引っ張り出してきました。付属のスポンジに少量取り、あとは汚れた箇所を前後左右に軽く力を入れて擦り続けます。少し濡れた状態だと汚れが取れた場所だけ水が貼り付いた様に広がるのでよくわかります。撥水ではなく親水になるんです。撥水処理をすると弾いた水玉が水垢の元になるので、私はガラコ等を使っていません。1個300円で安売りしてたので、今後のために1個購入しておきました(笑)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 ステアリング・ロール・コネクター (SRC) 交換 2
新しいSRCを取り付けてボスを取り付け配線をタイラップで軽く止めてあります。テープでグルグル巻きにしても良かったのですが、取り外しのことを考えたらこの方法が一番楽じゃないかと。粘着テープのネバネバはあまり好きではないので(^^;;;今回の断線の原因はSRCの取り付けミスっぽいです。右には軽く回りますが左には1回転ほどしか軽く回らなかった(^^;;;ハンドルとボス交換の時にはここはいじっていないので元々いい加減な取り付けがされていたようです。日産やスバルでここが壊れる事が多いそうなので、製造ラインの問題なのかもしれませんね。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 ステアリング・ロール・コネクター (SRC) 交換
壊れてしまったステアリング・ロール・コネクター (SRC)以前からエアバッグ警告灯が時々点いたり消えたりとおかしな現象があったのですが、突然ホーンが鳴らなくなり焦りました。いろいろとチェックしてみましたが途中の断線ではないようでしたのでここが怪しいと思い調べてみると、やはりこの部品でした。部品番号 98261FC012 金額はナント20900円!ハンドルを外しボスを抜きステアリングコラムカバー下を外し、上は少し浮かせた状態で3本のネジを抜き、SRCと繋がっている配線を外していきます。 他の配線とまとめられているのでタイラップを切断しながら配線を手前に抜いていきます。抜けたら新しいのと逆の手順で取り付けていくのですが黄色い注意書きにあるように右いっぱいまで回しきり、そこから左に2.5回転戻したところで三角の印を合わせます。あとはボスを取り付けハンドルを元にもどして完了です。
2009/01/27
コメント(0)
-
ワイパーゴムの交換
ワイパーゴムの交換特に書く事もありませんが、ひとつだけ注意した方が良いと思う事があります。ワイパーアームからワイパーを外す際には雑巾やウェスをガラス面のワイパーアームが直接当たる場所に置いておく事です。これを忘れると突然、何らかのショックでワイパーアームがガラス面に激しく叩き付けられるため、最悪の場合、ガラスにキズやひび割れが生じてしまいます。 必ず、忘れずに柔らかい物を当てておきましょう。運転席側は525mm、助手席側は450mmのゴムを入手してフロントのゴムを交換します。 ワイパーそのものは無交換でもほぼ大丈夫と思いますが、そのあたりは拭き取りの具合を見て判断します。リアのゴムは助手席側のゴムが使えたりしますのでとりあえず再利用してしまいます(笑) 1cmほど切断した方がいいかも?
2009/01/27
コメント(0)
-

GC8 CUSCO リアタワーバー (アルミシャフト)取り付け
クスコのリアタワーバー(アルミシャフト)です。以前、リアのアンダーバーを取り付けた時に同時に購入予定だったのですが予算の関係上先延ばしになったままでした。これもオークションにて入手しました。TEINのEDFCのステッピングモーターがあるので取り付けには少々手こずりましたが何とか30分程で作業を終えました。最初にシートを外し、この際ですから日干ししておきます。次にシートベルトのロール?を14mmのソケットとエクステンションを使って外します。12mmのディープソケットでサスペンション上部にあるセルフロックナット3個を抜き取るのですが、かなり狭い場所なので苦労しました。後方から見て左側取り付けたブラケットとリアガラスのウオッシャー用のビニルホースと細い配線が同じ穴から通っています。こちら側の作業はそれほど難しくはありませんでした。ただ、仮止めの時になぜかブラケットが5mmほど浮いた状態になり原因は何か?とよく見てみると、防水のコーキングが邪魔してました。そこで、カッターの刃とマイナスのドライバーでブラケットが当たる部分を剥ぎ取り、しっかり密着するように加工が必要でした。配線とビニルホース、EDFCのハーネスがブラケットの下敷きになっていないことを確認してセルフロックナットを本締めします。後方から見て右側取り付けたブラケットとスピーカーへの配線を含む太めの配線がこの穴に通っているのがわかると思います。この配線が邪魔でなかなかブラケットが取り付け出来ませんでした。トランク内で配線を緩める事が出来なかったのでリアシート脇にある配線止めを一旦外して、配線に余裕を持たせ、少し浮いたらブラケットを押し込み、また配線をずらしてブラケットを押し込み、と地味な作業で10分ほど費やしました。配線とブラケット、EDFCのハーネスがブラケットの下敷きになっていないことを確認してセルフロックナットを本締めです。最後にシャフトを左右を繋ぐように14mmのメガネで取り付け完了です。取り付け後、車体が硬くなったのがホントに良くわかりました(^o^)
2009/01/27
コメント(0)
-

GC8 リアブレーキローター交換
ついにリアブレーキが鳴き出しました。さっさと交換してしまいます。APロッキードのスタンダードローター左右1組8250円アクレ スーパーファイター リア用4770円まずはキャリパーを12mmのボルトを外して奥に抜き、落ちないように荷造りロープ等でぶら下げておきます。次に車止めをしてあるのを確認してからサイドブレーキを解除。シフトをバックに入れておいてもいいかも。キャリパーサポートも14mmのボルト2本を外して抜き取ります。ローター外し用のネジ穴にボルトをねじ込んでいきます。「パッキーン!」という音と共にローターが外れます。ローターが外れたら内部をブレーキクリーナーで適当に洗浄。キレイになったら新しいローターを組み付けます。 外したキャリパーサポート。ここに古いパッドがついていますので、そっと外します。画像でわかりにくいかもしれませんが、あと1mmも無くてまさにパッドが終わっていました。古いパッドから鳴き止めのシムを外します。車体外側は1枚、車体内側には2枚のシムがあります。これを新しいパッドにグリスを薄く塗り広げながら組み付けます。組み付けたらローターの外側から被せるように取り付けます。特に問題なく取り付けられると思います。ボルト2本を元通りに締め付けます。次にピストンを押し戻したキャリパーを組み付けます。 ピストンを押し戻す方法は、最初にエンジンルーム内のブレーキ液のタンクの蓋を緩めます。次にテコの原理でピストンを押し戻すか、ウォーターポンププライヤーとウェスでジワジワと戻します。ピストンのゴムパッキンにキズを付けないよう丁寧に行いましょう。面位置まで押し戻したらキャリパーを組み付けます。12mmのボルトをねじ込み完了です。ブレーキフルードのタンクの蓋を締めます。 (これを忘れて走ると大変な事になりますのでご注意を!)ここでブレーキペダルを20回くらい踏み踏みしておきます。サイドブレーキも数回ガチャガチャやっておきましょう(笑)10kmくらいは大人しく走行しながらアタリをつけていきます。しばらくは急ブレーキでも絶対停まりません(^_^;)
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 クーラント交換
クーラント交換しました。この中央白丸部分にあるドレンを指でクリクリと回して外します。数回転させると「ジョロジョロ」と漏れ出てきますのでバケツやオイル受けを下に置き排出させます。ラジエターキャップを外すと元気よく排出される、と思いましたがそうでもなく、時間をかけて抜き取ります。ラジエターホースを揉み揉みしながら気長にやりましょう(^o^)抜けきったら水道水でジャバジャバします。エンジンをかけ循環させ、抜いてジャバジャバを繰り返します。洗浄が終わればドレンを締めて、新しいクーラントを入れます。エア抜きを繰り返し、液面の減りが無くなれば完了です。しばらくは漏れなどが無いか様子を見ながら乗りましょう。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 パワステポンプの交換 2
ユニットはこのプーリー裏側にボルト3本で固定されてます。思ったよりも長いボルトですのでのんびりと作業します。狭いのでうまくレンチが入らない時はラジエターを止めているボルトを緩めて動かすのもいいかもしれません。プーリーを外すのは共回りがあるのでインパクトで一気に。プーリーを固定するものが何かあればそれを使うとベストですね。中心の袋ナットをインパクトで外し、ゴム製ハンマーでプーリーを軽く叩けばすんなり外れました。リビルド品にプーリーを付け替え、元に戻します。配管には新品のガスケットを噛ませて締め込み、オイルを入れてハンドルを左右に切りまくって完成です。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 パワステポンプの交換
交換したパワステポンプ一式。以前から異音はしていましたが長距離を走ったため一気に悪化。エンジン始動で「キキキキキ!」 ハンドルを回すと「キキキキキ!」もうだめぽ ということでリビルド品12000円と交換しました。ガスケットも新品と交換するので純正品140円を注文します。リビルド品はタンクとポンプが一体で届きましたのでOリングは不要でした。ポンプのみの場合には間にOリングを組み込む必要があるのでケースバイケースでしょうね。
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 パワステオイルクーラー
パワステオイルクーラーに細工をしました。この部分にあるU字管をオイルが通り、冷却される・・・はずなのですが、この構造ではそう簡単には冷えません。というわけでホームセンターでアルミ製の針金を購入してきて朝からグリグリと巻いていきました。本当なら銅製がいいのでしょうが、サビますので・・・。結果は、どうなんでしょ?私の乗り方ではあんまり変わりはないような(^_^;)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
mac audio 16cmスピーカ ー
オークションで落札したフロント用スピーカー。新品未使用で市販価格よりも1000円安上がりです。mac audioというメーカーで本体は中国製(^o^)2Wayコアキシャルの16cmでMax130W、充分すぎます(>_<)ツイーターがあるので1Wayでも良かったのですが安さにつられてつい・・・(>_<)以前はスピーカーの後ろに隙間がたっぷりあったので、手持ちの隙間テープでふさぎました。以前のスピーカーを取り外し、新しいのを取り付けるまで1分。内張りはがしにちょっと手間取ったくらいで左右の作業で10分程で完了です。このスピーカー、現在も使用中です 2009/01
2009/01/27
コメント(0)
-
KENWOOD KSC-Z77 3way 1 20W
オークションで手に入れたリアスピーカー。KENWOOD KSC-Z77 3way 120WKENWOODのイルミ付きでスピーカー後方が地味に点灯します。これの新型は上部が点灯するみたいですが、夜間の走行ではリアウインドーに映り込んで邪魔なだけかも・・・。このスピーカー、ちょっとした特徴があって、ウーファーが下側を向いていて、純正スピーカーの取り付け穴からトランクに低音を一度逃がして、トランクをエンクロージャー代わりにして低音を再生するというフリードライブ方式だそうな。純正穴が無い場合、そのまま使うと破損するというのだから、どんなスゴイ音が出るのか?と思えば・・・まぁまぁ普通(爆)現在はKENWOODのイルミもスモールランプから分岐で配線して地味な光が後ろ向きに照らされてます(^o^)2009/01 現在もこのスピーカーを愛用してます(^o^)/
2009/01/27
コメント(0)
-
KENWOOD KSC-440
オークションで落札したリアスピーカー。KENWOOD KSC-440KENWOODのイルミ付きですが、配線は面倒なのでしてません。以前よりきちんとした音になりました。純正とは・・・比べものになりません(^o^)KSC-330と比較してみると、中低音が良く出ています。高音域については、まぁこんなものでしょう。リアは大変良くなったのですが、逆にフロントが負けてます(T.T)気が向いたらフロントのスピーカーも他のものに交換してみようかとは思います。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
最低地上高の確認
先日、ほんの少し車高を落としてみましたので確認の意味で、身近なものを使って最低地上高を測定しました。見てのとおりの3.5インチフロッピーディスクです(笑)今ではCDRやDVD-Rなどしか使わなくなって、処分される一途のフロッピーなのですが、こういう使い方もアリという事でやってみました。画像のように一辺がほぼ9cmあります。車検の際の最低地上高が9cmですから、このフロッピーを縦にして差し込んで、引っかかるようでは不合格というわけです。適当な長さの棒にセロテープで固定して低いと思われる場所にこれを突っ込みます。やってみた結果、余裕でクリアしてました。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
ローター取説
ローターを購入した時に同封されていた説明書です。なんだかわかりにくいけど重要なお約束が書かれています。タイヤを外し、ジャッキで上げてウマを架けて、新しいローターの油分を取って綺麗にして、古いローターを取り外し、ハブを5分ほどかけて綺麗にしてサビを落としたら、新しいローターを取り付けて、対角線で貫通型ロックナットを締めつけたら、回転にムラが無いかをよく確認し、貫通型ロックナットを外して、タイヤを取り付けて、規定のトルクで対角線の順でロックナットを締め付けて、300kmまでは10kg以上の力をペダルにかけないよう優しくブレーキを踏むこと。らしいです(^^;;;***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-

GC8 フロント・ブレーキローターの交換
フロント・ブレーキローターの交換です。パッドは交換してから約1年経ちましたが、まだこれだけ残ってます。ブレーキラインには飛び石から守るため、スパイラルチューブを適当に巻いておきました。気休め程度ですが役には立つと思います(笑)まずは両前輪ともジャッキで上げて馬を噛まして安定させます。次に17mmのレンチでキャリパーを留めているボルトを回します。かなりの力で締め込まれているので覚悟が必要です。ここでは最初にメガネレンチを使います。ある程度緩めばラチェットでサクサクと抜いていきます。上下2本とも抜き取るとキャリパーが宙ぶらりんになるのでブレーキラインに負荷がかからないよう針金ハンガーを適当に曲げてサスのスプリングに引っかけてぶら下げます。 これがキャリパーをぶら下げてキャリパーを外した状態です。ローターは簡単に外れるか、固着していてなかなかすんなりとは外れないかのいずれかです(笑)外れない場合はローターに開いている2カ所のネジ穴にあうボルトをねじ込むと、カパッと外れます。反対側はあっさりと外れたのですが、こちら側は固着していてボルトの出番となりました。1カ所にねじ込めば余程の事が無い限り簡単に外れると思います。工具箱の中にあったボルトの中から合う物を選んでラチェットレンチを使ってサクサクっとねじ込んで行けばオーケーです。 ローターを外した状態です。青く見えるのは針金ハンガーです(笑)かなり汚れていましたのでブレーキクリーナーをたっぷりと吹き付けておきます。異物が噛んでいないかここでよく点検しておきます。私の場合、新聞紙とかビニールの買い物袋の破片?が見つかりましたのでドライバーでホジホジしておきました(笑)新しいローターを入れる際にパッドの隙間を少し広げる必要がありますのでエンジンルーム内のブレーキフルードの蓋を開けておき、静かに隙間を押し広げます。パッドを押し戻すと液面が上がりますので溢れないよう注意します。あとは、新しいローターを組み付けて逆の手順で元に戻します。 同じように両側の作業を行えば完成です。ブレーキの作業ですので、ボルトの締め忘れや締め付け不足などが絶対に無いように注意が必要です。慣れているからと手抜き作業はここでは出来ません(笑)緩めたものは必ず締めておきましょう。ブレーキフルードの黄色い蓋も締め忘れないように!(爆)走り始めてしばらくは、おとなしい上にもおとなしく、速度は出さずに慎重な運転をしましょう。ローターとパッドのアタリが出るまでは無茶は禁物です。しばらくは急な坂道には行かないように・・・マジで止まらないですから。
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 ブルーミラー
購入当初からの親水(?)ブルーミラーです。ディーラー価格で9800円?らしい・・・高っ!(>_<)すでに親水では無いミラーになってます(爆)先日洗車した際に見たらミラーの裏面の上部に金色?というかブルーではない箇所が広がっていて、これは何?と思って純正のノーマルミラーとブルーミラーの隙間にプラ製の棒を差し込みながらコジって剥がしてみました。両面テープで貼り付けてあるだけなので簡単でした。ミラーの裏面の黒色塗装がパリパリになっていて一部が剥がれた状態になっていました。これで反射率に違いが出来て妙な色になって見えたようです。裏面の塗装を剥がせるだけ剥がして、鏡面は可能な限り綺麗な状態にしてから塗装してリペア完成です。ホームセンターで300円くらいの油性塗料で数回塗り重ねたのでたぶん廃車になるまで大丈夫でしょう(^o^)(と思っていましたがそうでもなかった(^^;;;)最後に外装用両面テープで純正ミラーの鏡面に押しつけて完成。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
KENWOOD KSC-330
オークションにて格安に入手したKENWOODの中古リアスピーカー。型番はKSC-330 純正品はすでに寿命を超えて使用していたようでコーン紙が完全に逝っちゃってました。 あれでよく鳴っていたもんです(>_<)純正品を外して、空いた穴を手持ちの材料を使って適当に埋めてトランク側から固定しておきましたので振動で外れる事が無いように注意してあります。定価も安価ですが一応3スピーカーで、音質はまぁまぁです。一応バスレフタイプなので低音もそこそこ出てます。高音はセラミックツィーターとセラミックスーパーツィーターだそうで結構高音は出ているようです。あんまりオーディオに凝っても仕方のないクルマですので、この程度で良しとしましょう(^-^)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
カロッツェリア ドームツィーターの取り付け
以前に中古ドームツィーターを入手していたのですが、なかなか取り付ける機会がなく、今まで放置しておりました。純正でもドアノブ部に一応アゼストのものが取り付けられているのですがいまいち高音が弱いように思いましたので、今回DIYで取り付けを行いました。手順は簡単でドアの内張を外し純正品への配線を新規に取り付けるツィーターに変更、あとは適当に場所を決めて両面テープで固定して元通り内張を戻せば完了です。詳細は他のHPでも紹介されていると思いますので省きますが、この作業は左右で20分程度で終わります。交換してみて、以前より高音が「シャンシャン!」としっかり鳴ってよく聞こえるようになりました。走行中の音が音ですので・・・(>_<) あまり音質にはこだわらないのですが、少しはマシな音が出るようになったと思います。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し 7
穴が適当な大きさになったらゴムのリングをはめ込みます。先に車体にプラグを取り付けてからセンサーをそっとねじ込むように穴に取り付けます。配線に余裕があるので大丈夫だと思いますが、走行中の揺れで断線しないように注意はしておいたほうが良さそうですね。とりあえず、ここまでで作業は完了です。走行してみて、吸気音が少々大きくなった事とエンジンが元気に回るようになった事、純正ブローオフの音が気持ち聞こえる?ということでしょうか。キノコ型エアクリと違って安価に出来るDIYですので時間と手間を惜しまない方ならおすすめでしょう。これでエンジンルームにちょっと隙間が出来たぞ! と・・・(笑)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し 6
プラグ加工後の画像です。右側にあるのは、吸気温度センサーが取り付けられていた場所から外してきたゴムのクッションです。最初はドリルで小さな穴をあけておき、そこから一気に手持ちの一番太いドリルで穴を広げました(^○^)そこに、ニッパーの先端をあてがっておいて手作業でグリグリとねじりながら穴を広げていきます。結構簡単に穴が広がっていきますので、あらかじめ決めておいた大きさになるまでに15分くらい・・・ホールソーとか大きな穴を開けるツールがあれば楽ですね。ちょっと手が疲れました(>_<)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し 5
これはNAインプレッサにはついている吸気口を塞ぐプラグです。キャップとか、カバーとか、そういう名前だと思っていましたが、プラグって言うんですね・・・。部品番号 46059FA000 PLUG って書いてます(>_<)定価は330円。意外に安いというか・・・思っていたよりは安価です。これにドリルでちょいと穴をあけて、吸気温度センサーを取り付けてしまいます。するとSTIバージョン純正位置であるヘッドライト後部にある温度センサーがフェンダーの中の温度を測定するようになります。エンジンやラジエータの熱を測定していたものがフェンダー内の冷えた温度をちゃんと計測してくれるんですね。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し 4
ここに元々はレゾネーターが入っていました。かなりの汚れがありますので、洗剤で濡らしたウェスできれいに拭き取っておきました。ハーネスが見られますが、取り外し作業の際には注意して外すようにしないと断線させるかもしれません。落ち着いて作業すれば問題ありませんが、念には念を入れて。次回は左側に見えるエアクリに繋がる穴に排水管用の部品等を組み合わせてみたいと思います。とりあえずはここまでで、雨の日には乗らないようにします(>_<)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し 3
さて、これが取り外した導風用の部品です。このように部分的にカッターナイフで長方形に切り取ってから適当な目のメッシュを固定しました。金属製だとサビが心配ですが、塗料のスプレーをまんべんなく吹き付けておいたので当分は大丈夫でしょう。アルミの強力なテープで周囲を強引に固定しておきました。前方の穴から見て真正面だと雨水などの浸入が心配されますので、少し上向きに穴をあけてあります。ブレーキに風が行かなくなっても困りますからほどほどの穴にしておきましたm(__)m要は、エンジンルームからよりも冷えた空気が入ってくるようになれば良いのですから。バンパーのフォグの穴にパイピングして導風する方法もありますが、雨水も同時に入ってきますのでこの方法は却下ですね。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し 2
バンパー下部裏側の画像です。奥に見える開口部ですが、ここがブレーキ冷却用の導風口になっています。最初はこの穴の裏側からネットを貼って粗大ゴミを防ごうかと考えたのですが、これがなかなか作業性の悪い場所で、少し悩んだ結果あっさりとあきらめました(^-^)この開口部には樹脂製の筒のようなものが取りつけられていますので、これをまず外しました。3カ所の爪で引っかかっているだけなので簡単に外れます。外したらまずは外側も内側もきれいに洗浄します。これは結構汚れていますね。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 レゾネータ外し (エアチャンバー)
見るからに怪しい形状の部品ですが、これがフロント右側のフェンダー内側に入っています。エアチャンバー、通称レゾネータです。画像手前がエンジンルーム側、画像左が車両前側です。一度空気が左側の穴に入ってどこをどう通るのか不明ですが右側の穴から出て来ます。で、右側の穴がエアクリに繋がっているわけですが・・・8万キロ走行で外して洗浄してみましたが、ほとんど汚れてはいませんでした。内側よりも外側の方が汚れているくらいです。エンジンルーム内の熱気を直接吸い込む事なく冷たい空気がエンジンに入るようにすれば、多少のパワーアップが見込まれるので、ここを工作してみたいと思います。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
トランク内部
これはトランク内部の画像です。100円均一のショップで見つけた滑り止めのシートを底一面に敷き詰めておきました。山道や市街地でも走っていると時々トランクの中のモノが動いてゴツン!とかガシャン!とか聞こえる事ってありますよね?今では、ほとんどトランクにモノを積まないようになりましたが、それまでは置き場所のないカー用品を全部トランクに入れていたので、中はいつも満杯の状態でした(>_<)不要なものは放り出してしまったので現在は必要最小限のものしか積んでいませんが、クロスレンチや車載工具、三角表示板がよく動き回るのでどうしようか考えていました。で、100円均一の中に滑り止めシートがあったのでとりあえず購入してみましたが、これでもかなり効果があるようです。って、もう皆さんこれくらいの事はご存じですよね・・・(>_<)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 ウルトラシリコンパワープラグコード
永井電子のウルトラシリコンパワープラグコードを取り付けてみました。(品番 2335-10 8mm径)純正品のものは無交換ですでに8万キロも走ってますので処分しなければならないでしょう。汚れで真っ黒になってました。ウルトラシリコンパワープラグコードは純正品に比べるととても柔らかいです。これはシリコンゴムだけで、中に銅多芯線が入っているなんて思えないほどフニャフニャしてます。純正品を1本づつ取り外し、長さを合わせて1本づつ取り付けていけばどんなクルマでも問題ないでしょう。取り付けは T 型になった部分に指をかけてまっすぐに押し込みます。案外軽い力で「カチッ!」と入りますので、意外に簡単でした。交換してすぐ走ってみましたが、多少トルクが上がった様な・・・***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 プラグ交換、及びプラグコード交換 2
反対側のプラグ類の交換には少々面倒な作業が必要です。エアクリーナーのボックス類を全部取り外す必要があります。まずはエアクリに繋がっている配線類を取り外します。コネクタを注意して抜き、邪魔にならないように避けておきます。ホース類も動かないように固定されたものを外して自由に動くようにしておきます。最初に、エンジンに繋がってる蛇腹ホースを抜きます。エアクリボックス上側のフタを外しますが、配線やコネクタには注意しましょう。見えない部分にコネクタの取り付けステーがありました。次にエアクリボックス下側を外します。ボルト2本で止められていますが、ラチェットレンチに10cm以上のエクステンションがあると便利です。結構長いボルトで止まっていますので注意しながら抜きます。エアクリボックス下側を外せばプラグにもアプローチ出来ます。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 ウルトラシリコンパワープラグコード 2
これが取り外した純正品のプラグコード先端部分です。ご覧のように、コードの取付けに45度ほどの角度がつけられています。 滅多に見ることのない部分ですね(笑)ウルトラシリコンパワープラグコードは先端の黒い部分も真っ赤なシリコンです。取り外しにはこのコードの根元、T型になった部分に指をかけてまっすぐに引き抜きます。案外強い力で抜かないといけませんので、もし交換される方は充分に注意して作業を行って下さい。少し時計回りにねじりながら抜くといいかもしれません。力任せに引き抜いて、エンジンルーム内側に「ガツン!」なんてことになったら痛いですし、周辺の配線に手が当たって、誤って断線してしまうかもしれません。このあたりが水平対向エンジンの不便なところですね(>_<)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 プラグ交換、及びプラグコード交換
プラグ交換、及びプラグコード交換の際に取り外す必要があるのが、このウオッシャー液のタンクです。詳しいことは他のHPにも紹介されていますので省略しますが、上に見える2個のボルトを外して、配線やホースはそのままで少し反時計回りにねじりながら上に持ち上げます。私の場合1本のホースがスッポ抜けまして、液が漏れてしまいましたが、このあたりは多少の水がかかっても問題ないので、慌てずに持ち上げてから抜けたホースを接続します。配線類にはある程度長さに余裕がありましたので断線の心配はありませんでした。あとは適当にストラットのあたりにでも置いておきます。外したついでに普段は見えない裏側をきれいにしておきました。あとはバッテリーも外してしまえば楽々作業出来ますね。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 プラグ交換
これが走行80000キロで交換したプラグです(>_<)電極が、もう、とんでもないことになってます(>_<)純正品番では、22401AA400NGKの型番ではPFR6Bこれを見ると、エンジンのかかりが悪くなっても仕方がないと純粋に思えますね。新しく交換するプラグは何にしようかと悩んだのですが・・・イリジウムも良かったのですが、あの電極を見たらどうも・・・確かに性能は良いはずですが、2万キロ程度で交換というのも面倒なので、素直に純正と同じモノを手に入れました。滅多に高回転まで回さないのでプラグの番手は7番にはせずに6番のままです。これで次の交換は16万キロって事?(笑)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 車高調の緩み止め 2
これがレンチ&鉄パイプ不要の荒技で締め上げる方法です。皆さんは正しい方法で締め上げて下さいね。クロスレンチの23mm、ここにTEINのレンチがうまく収まるので鉄パイプでの延長など不要のお手軽な方法です(^-^)/手の力だけで大体締め上げておいて、そこからこの方法で約1/8 ~ 1/10回転ほど増し締めしておきました。これを4本とも増し締めしておきましたが、他の3本はほとんど回転しませんでした。元々が滑りやすい材質ですから、反面緩みやすいという事も考えられますが、やっぱり何かおかしいんでしょうね。ネジ山を舐めたわけではありませんので(問題なく回るから)微妙にナットの内径が大きいのか、ナットそのものが滑りやすいのかもしれません。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 車高調の緩み止め
雨の中でしたが、以前から緩んでしまうナットを締める為にジャッキアップしてタイヤを外し、よっこらしょ!っと作業をしました。 もちろんウマはちゃんとかけておきます。うーん、錆びたローターが渋い輝きを・・・(爆)まずはタイヤハウスを綺麗にお掃除・・・放水でざっと流しただけで、出るわ出るわ、泥と砂と小石・・・サスペンションにもたっぷりとこびりついていました。さて問題のナットですが全長調整(フルタップ)用の一番下のものです。これが約500kmも走れば緩んでしまう謎の現象が起きていました。メーカー指定のトルクで締めていても緩むので、それならばそれ以上のトルクでグイ!っと締めてやるわい! (>_<)延長用の適当な鉄パイプを探してみましたが、ホームセンターには売ってない(T.T) 道端にも落ちてない (爆)***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 エアバッグ警告灯キャンセラー自作 3
すみません。 作業途中の画像、撮り忘れてました。流れとしては、まずクルマのバッテリーのマイナス端子を外しておきます。 10分ほど放置していればいいでしょう。次に、ハンドルを六角レンチを使って外します。あとは、ボスの周りにある2個の端子のうち、エアバッグの端子に、上で簡単な工作をしたものをはめ込むだけです。もうひとつの端子はホーンですからすでに何らかの形で接続されているでしょうからすぐにわかると思います。私のクルマの場合、白いコネクタがホーンで、黄色のものがエアバッグの端子でした。抵抗にはプラスもマイナスもありませんから適当な向きに接続しておきました(笑)最後にバッテリーを繋いで、キーをオンにしてみます。エアバッグ警告灯が点灯して・・・5秒ほどで消えたら成功です。たった40円で鬱陶しい赤いランプが消えてくれました。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
-
GC8 エアバッグ警告灯キャンセラー自作 2
さて、これがエーモンの配線コードにハンダ付けしてから「自己融着テープ」(ブチルゴムテープ)で巻いた状態。コードの太さは2sq にしておきました。この自己融着テープ、かなりお役立ちです。巻いておけば、雨で濡れても水分が侵入しません。テープとテープがぴったり貼りつきひとつのゴムの固まりになりますから。フォグランプなどの車外の配線をするときは、私は必ずこのテープを使うようにしています。配線を外す時には何かと面倒ですが、これまで漏電等で困ったことは一度もありません。他には 「熱収縮チューブ」 があれば電装品の取り付けやDIYで便利に絶縁が出来るでしょう。***********************************************************古い記事です。HPからの移動ですm(__)m
2009/01/27
コメント(0)
全67件 (67件中 1-50件目)
-
-

- ξバイク好きの交流所ξ
- 33rd YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW …
- (2025-10-16 20:16:26)
-
-
-

- 自動車・バイクのメンテナンス
- 251117:GSX-R1100:電装トラブル修理…
- (2025-11-17 00:00:12)
-









