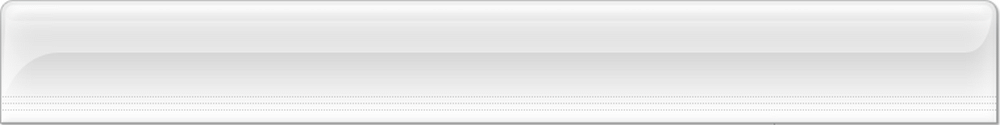2013年11月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
琉球音階で気分はタコライス
今回は短いです。琉球音階のご紹介です。沖縄の音楽で使われている音階(スケール、ドレミファ)です。普段使われているドレミファとの違いを実感しながら弾くのが楽しいです。6弦の7Fと8F、5弦の7Fと8Fと10Fです。この5つの音を適当にふんわりと弾いてみましょう。・・・なんとなく沖縄っぽい音がしませんか?「チャンチャチャンチャ♪」と跳ねるように弾くのがコツです。音階(スケール、ドレミファ)は、「これを使うと雰囲気が変わるな」という実感が大事です。実感→知識の順番だと、すんなりと体に入っていきます。逆だと入ってきにくいんですよね、なんとなく。ここから沖縄の音楽に興味を持って色々勉強すると楽しいです。PS 沖縄の水族館、最高でごんす。サメが平べったくてたまらんです。ギターファースト恵比寿
November 25, 2013
-
リスナーを間違えない
僕が20代の頃、大きなミスから得た教訓の話をします。僕はその頃ポップスのユニットをやっていました。そのユニットを始める時に僕は「音楽をしていない15歳からも共感を得られる曲や詞を書く」と決めました。しかし始めてみると、評価してくれるのはミュージシャンばかり。それも勿論嬉しいのですが、「おかしいな・・・」と首を傾げる日々です。ある日10代の方から感想を聞くチャンスがあり、「難しい」という意見をもらいました。なにがどう難しいかはその方はうまく言葉に出来ないらしく、僕は混乱しました。それというのもわかりやすい曲を書くことをモットーにしていたからです。「曲が好みじゃない」とか「ギターの人の顔が変」という意見ならわかりますが、「難しい」というのは完全に想定外の意見でした。それからユニットが解散するまで、同じような意見を何度か聞きました。その方の言った難しいという言葉の意味を僕が理解したのは数年後でした。ここで突然例を出します。例1僕は洋服が好きですが、すごくおしゃれというわけでもありません。だからファッション誌のショップ店員さんのスナップを見て、「これはちょっとおしゃれ過ぎてついていけないな」と思うことがよくあります。例2僕の友人にとても味覚の優れた人がいます(優秀な料理人です)。彼は「野菜の味が濁る」と言って、サラダに何もかけません。僕はドレッシングやマヨネーズをかけた方が好きです。上記に共通しているのは「知識や経験の豊富な人とそうでない人には捉え方に差がある」ということです。この記事の最初に「音楽をしていない15歳からも共感を得られる曲を書く」と決めたと書きました。当然僕は自分が15歳の頃やその頃の友人を想定していました。しかし当時の僕や友人は楽器を毎日演奏し、音楽の雑誌を月数冊読み、オリコンとビルボードのチャートを毎週チェックし、MTVを録画し、人によっては作曲を始めたり作詞の勉強の為に詩集を図書館で借りたりしていました。どう考えても「音楽をしていない15歳」ではないですね。つまり僕がユニットでやっていた曲の本当のターゲットは「とてもとても音楽に興味があって楽器を演奏している人」になってしまっていたんです。だから好みの近いミュージシャンからはわりと評価され、あまり音楽に詳しくない方からは「難しい」と言われたわけです。たまにCDは買うけど特別音楽に興味がない人として、僕の(さっきとは別の)友人を出します。彼はベースがどういう音か知りません。「ギターに似ていて、すごく低い音が出るらしい」という認識だけです。あきらかに打ち込みのドラムと生ドラムを音で判別することができません。ギタリストの技術の判断が出来ず、「有名かそうじゃないか」「好きなバンドにいるかそうじゃないか」でしか判断できません。今回の記事の結論は、彼のような人にもわかる曲を書こうではありません。「自分の曲や演奏のスタイルがどう認識されているか知ろう」です。ライブやネットなどで誰かに聞いてもらう時、たとえ評価を求めていなくても「周りの自分に対する認識」は知っておいた方が得です。この話の難しいところは、リスナーに直接聞いてもきちんとした返事が返ってきにくいところです。「自分がその曲、フレーズ、アーティストについてどう思うか」をちゃんと論理的にわかりやすく正直に伝えられる人は、ミュージシャンでもそうはいません。だから20代の僕は何年も混乱していたわけですね。誰に向けて演奏しているのか、評価をもらう以前にそれが正しく伝わっているかには気を配りましょう。「そんなの知らないよ、作りたいものを作るだけだよ」でも勿論OKです。その方がいい曲が書けたりするんですよね。どないやねんですね。ギターファースト恵比寿
November 24, 2013
-
「練習してるのに・・・」ギターがうまくならない時に試すべきこと
まずは今、「なにを」→「どのくらい」→「どのように」練習していて上達しないかを考えます。「どのくらい」というのは練習量、「どのように」は練習法などです。どちらも過去記事に色々と書いてありますので、よろしければご覧ください。そこで今回は「なにを」です。何が問題かと言うと、「弾きたいフレーズが弾けない」から困ってしまうわけです。では「別に弾きたくないけど向いているタイプのフレーズ」を練習してみてはいかがでしょうか?当然向いていないフレーズや曲、奏法に比べて上達しやすいはずです。この場合の向いているとは他のギタリストより優れているという意味ではなく、「自分が他のことよりやりやすいと感じていること」です。実例を挙げます。例によって僕です。僕がギターを弾くこと自体に向いていないというのは何度も書きました(毎日4時間練習してFを弾けるまでに1年以上、弦を1本だけ弾くのに半年以上・・・)。毎日「こんなに練習しているのにどうして弾けないんだろう」と涙でアンプを濡らしてビリビリと感電する日々でした。そんなある日、わりとすんなりと出来る奏法に出会います。カッティングです。それでも平均よりは上達は遅かったのでしょうが、自分にとっては「こんなに俺に向いている奏法はない!」でした。当時僕がやりたいと思っていたのは華麗なソロやスピーディなリフでしたので、特にカッティングがやりたかったわけではありません。しかし当時の僕は「別にやりたくないけど、多分これを必死に練習すれば武器になるだろう。別にやりたくないけど」と考えました。この判断は大正解でした。そしてカッティングの練習をするうちに自然と他の奏法の下地も身につき、それ以前に比べて上達のスピードは上がりました。また「得意なことがある」という自信がつき、指も動くようになり、ギターに慣れて緊張も薄れ、モチベーションが上がり練習量が更に増え、最終的には札束の風呂に入れるようにまでなりました。まったく、カッティングちゃん様々だぜ!というわけで、やりたい事は一旦置いておいて、比較的やりやすい事を練習してみませんか?たとえば「CよりDの方がなんとなく押さえやすい」という方なら、無理にCを練習せずにDメジャーセブンスなどのコードに挑戦してみる。「人差し指と中指が他の指より動かしやすい」方ならその二本だけで弾けるタイプのフレーズを探す。「機械をいじるのが好き」という方ならエフェクターやPCのソフトの勉強をしてみる。当然得意なことは伸びるのが早いです。「とりあえず好きなことより得意なことを優先させる」というのは上達のスピードを上げるのに間違いなく効果があると思います。ギターファースト恵比寿
November 23, 2013
-
「だめだ、間に合わない・・・」左手の移動を速くする方法(横移動編)
弦と平行方向の左手の移動をスピードアップさせる方法です。ソロにもバッキングにも必要ですよね。ギターを持っていない状態で適当に左手を素早く動かすことは簡単ですが、ギターを持った途端にこれが出来なくなってしまいます。もっとも大きな要因は「ゴールが決まっているから」です。当たり前ですね。ゴール(次に左手で押さえようとしている弦・フレット)からずれたくないから、どうしてもゆっくりになってしまいます。例えば左手中指で2弦3フレットを押さえている状態から2弦12フレットまで一気に移動させたいとします。“3フレットをスタートした瞬間から加速、6フレットあたりで最高速度、その後ブレーキをゆっくり踏み込んで減速しながらそろそろと12フレットで止まる”といったやり方だと、確かに正確に12フレットに到着はするのですがどうしても遅くなってしまいます。スピードを求めるなら。“12フレットまで全速力でつっこみ、到着したら一気に急ブレーキ!”です。前者は公道での運転が上手な人、後者はレーシングドライバーのイメージですね。ゴール(12フレット)を多少通り過ぎるのは覚悟の上で、最高速度→いきなり急ブレーキを練習してみましょう。手だけでなく手首、前腕、肘も一緒に手前(胴体側)にズバッ!と引きつけましょう。そして見るのは(スライドと同じく)左手ではなくゴールである12フレットです。「スピードが欲しいのならスピードのことだけを考える」です。最初から複数のことを同時に練習するというのは大変です。一番欲しいものがある程度身についてから他の要素を考える、というのがおすすめですよ。※力を入れすぎて怪我をされないよう気をつけてくださいね。ギターファースト恵比寿
November 4, 2013
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-

- オーディオ機器について
- 試作スピーカー32.1(振動系の組み立…
- (2025-11-27 22:12:15)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-