読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20
読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15
読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16
読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5
映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6
[映画 ハンガリー・ルーマニアの監督] カテゴリの記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
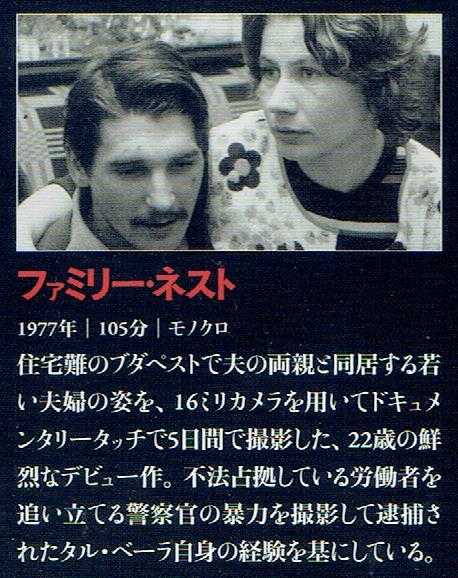
タル・ベーラ「ファミリー・ネスト」元町映画館no113
タル・ベーラ「ファミリー・ネスト」元町映画館 「タル・ベーラ前夜」という企画の二本目でした。1977年の作品で、タル・ベーラ監督のデビュー作だそうです。題名は「ファミリー・ネスト」です。 街角を歩いている女性が電車に乗り、やがて仕事場らしきところにやってきて、白い上着を着て働き始めます。ソーセージを作っている作業場のようです。彼女は夫が徴兵(?)で従軍のあいだ、その実家に幼い娘とともに夫の両親と暮らしているイレン(ラーツ・イレン)という女性です。 映画はイレン、娘、義父(クン・ガーボル)、義母(クン・ガーボルネー)、軍務から帰ってきた夫ラツィ(ホルバート・ラースロー)、そして夫の弟という、同じアパートに住んでいる「家族」の物語でした。 この映画が撮られた当時のハンガリーの首都、ブダペストの住宅難を反映した作品だというチラシの解説がありましたが、ウサギ小屋と揶揄された1960年代から1980年代の日本の住宅事情だって、似たり寄ったりで、その狭い住居の暮らしの様子に違和感はありませんでした。 しかし、映画の始まりのころに映し出される夕食のシーンをみながら、だんだん息苦しいほどの、違和感が広がっていきました。 その日、イレンが連れ帰ってきた職場の同僚である女性が座り、そこに任務を解かれて帰宅した夫が登場する、というシーンです。そこでは普通(?)予想される一家団欒の温かさはかけらも描写されません。延々と続く義父の「暴言」にはじまり、家族たち相互の歯に衣着せぬ発言のあからさまさ、それに加えて次のシーンでは、女性を送って外に出た夫と弟による、妻の友人である初対面の女性に対する異様な暴行シーン。それに続くのがその暴力をふるった男と振るわれた女のなれ合い様子。その後、深夜に帰宅した夫が妻のベッドに入っていくという、チグハグでなにが起こっているのか理解できないようなシーンが次々と映し出されていきます。「いったい、これは、なんなんだ?」 そうつぶやくしかない出来事の連鎖でした。それぞれの人間に、異様な反道徳性が割り振られている印象です。この後も、見ていて理解しきれないことが続くのですが、結果的に「ファミリー」という、本来、一番平和的な社会の単位が、単位個々の心中に充満する憎悪や猜疑心によって、実はすでに壊れているという印象が画面を覆っていきます。 別にそこから「殺人事件の謎を解く」といったようなミステリアスな出来事が起きたりするわけではありません。ただ、何とも言えない息苦しさがあらゆるシーンに漂い、やがて映画は終わりました。 タル・ベーラという映像作家の「人間の実相に対する悪意」 とでもいうべき疑い、不信が、かなり率直に映像化された作品だと思いました。 シマクマ君は「サタン・タンゴ」という長大な作品のわからなさをなんとかしたくて、今回の特集を見始めましたが、「ダムネーション」といい、この「ファミリー・ネスト」といい闇は深まるばかりです。見ていて、どんどん気が重くなっていくのです。 人間の中にある「悪意」や「反道徳性」の芽をデフォルメし、クローズアップすればこのフィルムのようになることに異論はありません。しかし、ほとんどホラー化したその世界を見てどうすればいいのでしょう。 ほんとど最後の頃のシーンですが、義父が酒場で女性を口説くシーンがあります。そのシーンなどは、ホラーを通り越して喜劇的です。しかい、なんだか気が重くて笑う気になりませんでした。 若き日のタル・ベーラの習作というべき作品だと思いますが、ある種、異様な徹底性が記憶に残りました。そこが、タル・ベーラなのかもしれません。 というわけで、「とことん」まで描こうとするタル・ベーラ監督に拍手!なのですが、この年になってみる映画ではないのかもしれないとも思いました。それにしても、やっぱり、疲れました(笑)。監督 タル・ベーラ脚本 タル・ベーラ撮影 パプ・フェレンツ編集 コルニシュ・アンナ音楽 スレーニ・サボルチ トルチュバイ・ラースロー モーリツ・ミハーイキャストラーツ・イレン(イレン)ホルバート・ラースロー(ラツィ)クン・ガーボル(ラツィの父)クン・ガーボルネー(ラツィの母)1977年・105分・モノクロ・ハンガリー原題「Csaladi tuzfeszek」2022・03・09-no32・元町映画館(no113) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2022.03.14
コメント(0)
-

タル・ベーラ「ダムネーション/天罰」元町映画館no112
タル・ベーラ「ダムネーション/天罰」元町映画館 「タル・ベーラ前夜」という企画が元町映画館で始まりました。長い長い「サタン・タンゴ」という映画のわからなさに打ちのめされた監督なのですが、気になってしようがありません。 なにか、わかることがあるんじゃないか! そんな、淡い期待で、ちょっと勢い込んでやって来たのですが、再び打ちのめされてしまいました。見た作品は「ダムネーション 天罰」でした。 リフトというのでしょうか、人を乗せるベンチではなくて、石炭だか鉱石だかを積んでいるらしい荷箱が、延々と向こうまで続いている鉄塔と鉄塔をつなぐワイヤーにぶら下がっていて、向こうに運ばれていきます。それが最初の風景でした。ああ、きっと、これを見ている奴がいるか、場所があるんだよな。 長々と続くカットが切り替わらないシーンをぼんやりと眺めながらそんなことを考え始めると、カメラがだんだんと引いていって、部屋の中から見ているシーンへと変化していき、そこに男がいるようです。 シーンが変わって、建物が映し出され、そこから誰かが出てきて、自動車に乗って、自動車が動き始めるシーンが淡々と続きます。建物は、少し離れたところから撮られています。 「ああ、ここにも人がいて、見ているんだよな」 そう思っていると、カメラが少し引いて、建物の手前、カメラがあると感じていた物陰にさっきから、ずっと男がいたようで、カメラが映し出していたシーンを見ていたらしいことがわかって、やがて、その男が建物に向かって歩き始めて建物のドアに向かいます。 ここまで、ずっと同じカットで、見ているぼくは、なんとなく男と同化していく気がし始めるのですが、次のシーンに打ちのめされました。 チェーンをつけたままの半開きのドアの中から女がにらんでいます。男と続けていた関係を拒絶しているようです。縋りつくように何かいう男をドアの外に残してドアが閉まります。女の拒絶の眼差しが異様にリアルなのですが、なんで、見ているぼくが、こんなにゾワゾワするのか。考える余裕もなくぐったりしてしまいました。 映画はリフトが動き続ける鉱山の町の時間のなかで、この男と女の醜態(?)、いや、愛(?)か、を描いているといっていいのかもしれませんが、何がどうなったのかぼくにはわかりませんでした。だいたい、最初のシーンのドア越しの女が、酒場で歌を歌い、酒を飲みながら男に「町を出ていく」と宣言し、部屋でこの男と情事に及ぶ、それぞれ別のシーンの女と同一人物なのかどうかさえ見ているときにはあやふやで、主人公であるこの男が、かなり後半になってカーレルという名だとわかるのですが、女に何を求めているのか、男が口にする抽象的な「愛」のことばの、具体的に意味していることの見当もつかいないまま見ていましたが、とどのつまりには、瓦礫の中で犬と吠えあっている男の奇妙なリアリティだけ残して終わった映画に、何をいえばいいのでしょう。 雨が降り続き、降り続く雨に濡れていく壁や窓が延々と映し出され、一方に、何故そこにいるのかわからない人々の顔、顔、顔がじっとこちらを眺めている映画でした。 そういえば、タル・ベーラに学んだはずの小田香が「アラガネ」や「セノーテ」で映し出したあの顔とそっくりの顔のです。この何にも言わない顔の迫力って、なんなんですかね。 映像の印象は強烈でした。しかし、物語を納得したがっているぼくの意識は宙ぶらりんのままでした。さて、残り二本、見るかどうか、わけの分からない不安に、またまた、身をさらしにやって来るのかどうか、ああ、悩ましい限りです。 まあ、とりあえず、やっぱり、わけがわからないことを実感させてくれた監督タル・ベーラに拍手!でした。監督 タル・ベーラ共同監督 フラニツキー・アーグネシュ原作 クラスナホルカイ・ラースロー脚本 タル・ベーラ クラスナホルカイ・ラースロー撮影 メドビジ・ガーボル美術 パウエル・ジュラ編集 フラニツキー・アーグネシュ音楽 ビーグ・ミハーイキャストセーケイ・B・ミクローシュ(カーレル)ケレケシュ・バリ(歌手)テメシ・ヘーディ(クロークの女)パウエル・ジュラ(店主)チェルハルミ・ジュルジュ(夫)1988年・121分・モノクロ・ハンガリー原題「Kárhozat」・英題「Damnation」2022・03・07-no30・元町映画館(no112) 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2022.03.08
コメント(0)
-

アレクサンダー・ナナウ「コレクティブ 国家の嘘」シネ・リーブル神戸no126
アレクサンダー・ナナウ「コレクティブ 国家の嘘」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルの予告を見ていて、「ウン?」と思っていると、映画好きの友人たちの評判が聞こえてきて、「そうか、そうか」という気分で出かけてきたシネ・リーブルでした。 映画はルーマニアのアレクサンダー・ナナウというドキュメンタリーの監督の作品で、病院経営者と薬品会社、政治家が結託して、市民の命をもてあそびながら、闇の金儲けに勤しむ世界を、ドキュメント、あからさまにした作品、「コレクティブ」です。 驚いたことが二つあります。 一つは、登場人物たち、新聞記者のトロンタンやその仲間、改革派の若い大臣ボイクレスクという人たちが、まるで俳優のようだったことです。 いつものようにぼんやり見ながら、ドキュメンタリィーではなくて、普通のミステリー映画だと思い込んでしまいそうでした。それは、たぶん、「出来事」を捉えているカメラのある場所のせいだと思います。 新聞記者たちの会話や、大臣の執務室での会話、それぞれ、オフレコに近い会議の内容が直に映し撮られる場所でカメラが回っていて、本当に撮っているのです。で、そこの会話がミステリー映画のセリフのようなのでした。 二つ目は、結末です。政治家や医療関係者のありえない程の腐敗が報じられているさなかに行われた選挙の結果、勝ったのは、なんと汚職まみれの政治家たちだったことです。 ぼくは、2021年秋の衆議院選挙の直後この映画を見ましたが、「日本」という国の選挙結果と、「ルーマニア」という国のこの映画の結末がそっくりだったことに客席から転げ落ちそうな気分になったのでした。 映画監督の森達也さんが、この映画についてこんな発言をしておられるのをネット上に見つけました。 すごい映画を観た。まずはこれに尽きる。誰だってそう思う。次にあなたは思う。なんてひどい国だ。私たちの国はまだましだ。でもならば考えてほしい。 私たちの国は記者会見が一般公開されていない。自分たちの執務をドキュメンタリーで撮られることを了解する大臣もいない。 つまり日本ではこんな映画は作れない。ならば同じことが起きてもわからない。 一人でも多くの人に観てほしい。そして気づいてほしい。権力監視について私たちの国は圧倒的に遅れているのだと。 たとえば、この国には、コロナ騒ぎに乗じて役にも立たないマスクを配った総理大臣がいましたが、そこで動いた何百億だか、何千億だかの公金の行方は闇のかなたという現実があります。 公共(?)テレビ放送は、投票率が上がるのを阻止することが目的のように、選挙戦報道をオミットするかのような、意図的な放送を繰り返し、民放は程度の低さの極限を目指すかのような、インチキな政治家・政治評論家のおしゃべりや、これでもかとを謂わんばかりの、文字どうりバカげた「お笑い」を流し続けています。 森さんは「権力監視について私たちの国は圧倒的に遅れているのだ」とおっしゃっていますが、むしろ、誰が意図しているのかわかりませんが、腐敗権力にとって一番都合のいい「愚民政策」政策を明るく受け入れている「権力崇拝」においては、世界の先頭を走っているのだという方がいいのかもしれませんね。 ハヤリ言葉で言うなら、「自己責任」を弱者に押し付け、無能な「ダメージ・コントロール」能力をさらけ出しながら、自らの責任を糊塗する「リスク・マネージメント」言語を、政治家のみならず、メディアも弄んでいるということなのでしょうが、明るく楽しいディストピアが着々と進行しているのは間違いないようですね。 いやはや、それにしても、この国の医療や福祉の美名の下にも、きっと、この手の腐敗が進行しているに違いないのですが、暴くカメラは出現するのでしょうか。 しかし、この映画に関して言えば、ここまで「奥深く?」カメラを駆使して暴いたアレクサンダー・ナナウ監督に拍手!でした。監督 アレクサンダー・ナナウ脚本 アントアネタ・オプリ アレクサンダー・ナナウ撮影 アレクサンダー・ナナウ編集 アレクサンダー・ナナウ ジョージ・クレイグ ダナ・ブネスク音楽 キャン・バヤニキャストカタリン・トロンタン(新聞記者)カメリア・ロイウテディ・ウルスレァヌブラド・ボイクレスク(新任の保健大臣)ナルチス・ホジャ2019年・109分・G・ルーマニア・ルクセンブルク・ドイツ合作原題「Colectiv」2021・11・09‐no106シネ・リーブル神戸no126
2021.11.16
コメント(0)
-

バルナバーシュ・トート「この世界に残されて」シネリーブル神戸no78
バルナバーシュ・トート「この世界に残されて」2021-no5シネリーブル神戸 何の偶然なのでしょう、新しい年に入って、気難しい孤独癖の中年のオジサンに少女が「恋?」をするという映画を立てつづけて2本見ました。 1本目がどなたでもご存知の名作「レオン・完全版」、2本目がこの映画「この世界に残されて」です。 「レオン」の舞台はニューヨーク、家族皆殺しという惨劇を目撃した少女マチルダが「恋?」をする相手は殺し屋でしたが、この映画では産婦人科の医師でした。 「この世界に残されて」は「初潮」が遅れていることを心配したオバであるらしい女性に付き添われた十代半ばの少女が、婦人科の医師の診察を受ける、診察室のシーンから始まりました。 少女の名前はクララ、医師の名前はアルド。白衣を手繰り上げた医師の左腕には青黒い数字の入れ墨が見えます。彼女を連れてきた女性は大叔母のオルギで、身寄りのないクララの世話をしています。 今日の診察がはじめてではないことが、オルギの言葉からわかりますが、医師は少女の体のどこも悪くないことを静かに告げるだけです。 少女が診察を受けているこの病院のある場所は、はっきりしたことはわかりませんが、東欧の国、ハンガリーのブダペストでしょうか。 時代は、最後まで見ればようやくわかりますが、あの「密告」と「粛清」の独裁者スターリンが死んだ1953年に至る1950年代の初頭です。 数日後、クララは一人で医師の自宅を訪ね、「初潮」があったこと、そして、その経験が、身体的にも精神的にも、いかに不快であったかを訴えかけます。オルガが自分に対していかに無理解で、学校がいかにくだらない場所であるか、・・・。 アルドは貴重品の砂糖をたっぷりと入れた、暖かく、甘いホット・レモンを少女に与えながら、静かに話を聞きます。そして、なんと、その日から、二人は同じ部屋で暮らし始めます。 美しく、利かん気で、大人の扉の前に立ったことにいら立っている少女クララと、彼女の言葉に耳を傾け、静かに微笑み、穏やかな忠告を口にする、一人暮らしの医師アルドの生活が始まりました。 少女は何故、この医師の部屋から帰ろうとしないのでしょうか。医師は何故、少女を追いかえそうとしないのでしょうか。そして、それを、この映画はどのように語ろうとしているのでしょうか。 驚くべきことに、ここからラストシーンに至るまでの60分余り、この映画はナチスの収容所の悲惨なありさまや、戦災孤児を集めた孤児院の暮らしの苛酷な様子について、言葉としても映像としても、一切、語らないのです。 ただ、一度だけ、オルガの言葉によって、孤児院から拾われてきたという少女クララの過去を知ったアルドが数冊の写真帳を差しだしてこう言うシーンがあるだけでした。「ぼくにはこれを見る勇気はないが、あなたとぼくとの間で公平を期すために、あなたはこれを見てもいい。ただし、ぼくがいないところで。」 アルドの留守にその写真帖を見はじめたクララが、やがて号泣するシーンを映し出しながら、画面は暗転します。そこに写っていたのは幼い二人の息子と美しい妻、そして笑っているアルドの姿でした。 なぜ、クララは号泣し、なぜ、アルドはその写真帳を見ることができないのか。「この世界」に取り残された二人が、いま巡り合っていること がひしひしと伝わってきます。 それ以外は、ただ、ただ、淡々と、大人になりかかっている少女と独身の中年医師の危なっかしい「同棲」生活と、それをスキャンダラスに噂し始める「密告社会」の小さな「不安」が、少しづつ膨れ上がっていく「兆し」を描くだけです。 スターリンの死が報じられた当日、再婚したアルドの誕生日を、新しい妻、結婚したらしいクララ夫婦、伯母(確か、彼女もいたと思のですが、確かではありません)、アルドの職場の寡黙な看護師の6人で祝い合う美しいシーンが、この映画で、初めて差し込んできた明るい日射しのような印象を残して映画は終わります。 もちろん、その後のハンガリーの歴史を知る人間であれば、この穏やかなシーンが束の間の小春日和であることはすぐに気づくことなのですが、「この世界に残された」二人が、それぞれ、抱きしめ合うことができる「他者」と巡り合ったことを知らせるこのシーンは、ぼくにとって心からホッとするシーンでした。 それにしても、これほどまで寡黙に、そして、あたたかく「この世界」に取り残された人々の「愛」の姿を描いた作品はほかにあるでしょうか。 1940年代に、主人公たちが経験したに違いない壮絶な過去を、その未来に起こるハンガリー動乱の悲惨同様、描かないことで、「この世界」の悲しい姿と「人間」の「愛」の美しさとを描き切ってみせたバルナバーシュ・トートという監督はただ者ではありませんね。 「レオン」という映画の中でマチルダとレオンがニューヨークの街を歩くシーンが印象深く記憶に残っています。この映画でも、クララとアルドがブダペストの街を歩く美しいシーンがあります。ぼくにとっては、長く記憶に残るシーンになりそうです。 「レオン」の感想はここをクリックしてください。監督 バルナバーシュ・トート製作 モニカ・メーチ エルヌー・メシュテルハーズィ原作 ジュジャ・F・バールコニ脚本 バルナバーシュ・トート クラーラ・ムヒ撮影 ガーボル・マロシ音楽 ラースロ・ピリシキャストカーロイ・ハイデュク(アルダール・ケルネル通称アルド)アビゲール・セーケ(クララ)マリ・ナジ(オルギ・大叔母)カタリン・シムコー(エルジ)バルナバーシュ・ホルカイ(ペペ・クララの恋人)2019年・88分・G・ハンガリー原題「Akik maradtak」2021・01・19・シネリーブル神戸no78 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
2021.01.22
コメント(0)
-

タル・ベーラ「サタンタンゴ」(その1)元町映画館
タル・ベーラ「サタンタンゴ」元町映画館 観ようかな、やめようかな? ひいきの元町映画館の2019年秋の大型企画、ハンガリーの巨匠(?)、タル・ベーラ監督の「サタンタンゴ」です。7時間を超える、ブットンダ映画です。今回見逃せば、二度と観ないことは間違いないでしょう。「あ、今日、映画行ってくるわ。」「いうてた長いやつ?行く決心ついたん?何時になるの?」「お昼前からやから、8時には帰ってくると思うけど。」「阪神勝つかなあ?」「帰ってくる頃には負けてんのとちゃうか。」2019年午前10時46分。元町映画館到着です。 特別料金3900円。いつもは入場整理券で10分前開場ですが、今日は、そのままご入場でした。 館内が暗くなり、画面は薄暗いまま映画が始まりました。一人で三席確保の贅沢鑑賞開始です。 遠くに建物が見えます。かなり大きな建物で、手前はぬかるんでいるようです。右寄りの戸口から牛が現れて、次々と増えていきます。ぬかるんでいるのも気にする様子はなく、交尾をせがむ雄牛と、それを振り落とす雌牛が画面こちらの方まで迫ってきます。大きな建物は牛舎のようです。7時間18分が始まりました。 東ヨーロッパの平原なのでしょうね、何処まで行ったら木立があるのでしょう。道が向こう向きにうつっていて、人が歩いて進んでいくと、その姿が消えるまで追い続けるように映り続けます。もう誰も映っていない平原が映っている画面は薄暗いモノクロです。のべつ幕なしに雨が降っています。風は後姿を追い立てるように吹いています。 二つ離れた席では、大いびきで同年配のおやじが寝ています。まるで、風の音のようです。 最初の休憩時間がやって来ました。何が起こっているのか、全くわからないまま、タバコを喫いに外に出ました。昼を過ぎていて、日射しが少し暑い。午後1時30分。 相変わらずいびきは聞こえていますが、映画が輪郭を持ちはじめたように感じ始めました。相変わらず雨は降り続けていて、画面は暗いままです。ただ、何となく、ジグソーパズルの破片が埋まり始めて、全体を予感させてきました。 二度目の休憩がやって来ました。タバコを喫いに外に出て時計を見ると午後4時でした。明るい日射しのままです。 飲んだくれのドクターと呼ばれていた男が、鐘の音が鳴り響き続けている長い道を教会の鐘の塔に向かって歩いています。 塔では「トルコ軍がやって来た」 と繰り返し呪文のように唱えながら、男が鐘を撞いていました。風景を横に映してゆく、長い長いショットが続くのですが、いつまでたっても、あるはずの牛舎も、その近くにあった、横にうねうねと続くみすぼらしい民家の影も映りません。 風景を眺めていたのはドクターですが、彼の眼前から人びと住んでいた「村」が消えているのです。自宅に帰ったドクターが、窓に板を打ち付け始めます。薄暗い画面が真っ暗になり、ドクターのメモが読み上げられました。「フタキは鐘の音を聞いて目を覚ました。一番近い礼拝堂は8キロ離れているが、そこには鐘がなかった。」 画面が消えて場内が明るくなりました。午後7時でした。映画館を出て、商店街から南の海岸通りに向かう路地に方向を変え、煙草に火をつけると、雨がポツポツと顔にあたりました。「しまった、雨が降り始めた。世界が滅ぶぞ。」 そう呟いて、中央郵便局の交差点の赤信号で立ち止まり正面のビルを見上げました。古い外観だけ残したリニューアルビルの改築工事の現場です。古いビルの内部が明るく照らされている不思議な光景を見ていると、納得が渦を巻くようにやって来ました。「そうか、そうだったのか。あれは滅びの鐘だったんだ。これはすごい。現代の黙示録なんだ。あの、飲んだくれは、飲んだくれている間に世界が滅んだことに、最後に気付いたんだ。 ネタバレの考察は(その2)で書きます。 監督 タル・ベーラ 共同監督 フラニツキー・アーグネシュ 原作 クラスナホルカイ・ラースロー 脚本 クラスナホルカイ・ラースロー タル・ベーラ 撮影 メドビジ・ガーボル 編集 フラニツキー・アーグネシュ 音楽 ヴィーグ・ミハーイ キャスト ヴィーグ・ミハーイ (イリミアーシュ) ホルバート・プチ (ペトリナ) デルジ・ヤーノシュ (クラーネル) セーケイ・B・ミクローシュ (フタキ) ボーク・エリカ (少女エシュティケ) ペーター・ベルリング(医師) 1994年 438分 ハンガリー・ドイツ・スイス合作 原題「Satantango」 2019・10・07・元町映画館no21追記2023・12・27 ネタバレとやらの感想は、とうとう書かれませんでした。この映画の筋書きに沿って感想を書くなんて、ボクには無理なことだったようです。で、5年経ちました。暗い道を歩いていく男たちの姿は浮かびますが、さて、どんなお話だったか、さっぱり覚えていません。機会があれば、また、挑戦するしかないですね(笑)ボタン押してね!
2019.10.09
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1










