読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20
読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15
読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16
読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5
映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6
[読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」] カテゴリの記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

週刊 読書案内 川上弘美『神様』中央公論新社
100days100bookcovers no77 77日目川上弘美『神様』中央公論新社 遅くなりました。申し訳ありません。SODEOKAさんの都合で、77日目が回ってきた。YMAMOTOさんの採り上げた、田中小実昌『ポロポロ』からどうつなごうかと思っていろいろ考えて見たが、なかなか思いつかない。 試しにWikiで田中小実昌を当たってみると、『ポロポロ』が谷崎潤一郎賞を受賞していることがわかる。それで、これまでの谷崎賞の受賞作家、受賞作品をつらつら眺めていたら、川上弘美の『センセイの鞄』(2001年)が目についた。以前、採り上げた堀江敏幸『雪沼とその周辺』も2004年受賞作だった。ああ、じゃ『センセイの鞄』にしようかと思ったが、作品が結構長いことに思い当たる。このところ何やかやであまり時間が取れない状況になってきているので断念。川上弘美はいくつか読んでいるので、他になかったかなと思って最初に思い当たったのが、 『神様』川上弘美 中央公論新社 だった。これなら連作的な短編が都合9作で、200ページ足らず。全部読めなくても何とかなりそうだ。そもそも最初に置かれた表題作とその続編で最後に置かれた「草上の昼食」にはかなりいい印象が残っていた。 かつ、これに決めてから気がついたのだけれど、タイトルの「神様」は、田中小実昌の『アメン父』にも通じる。 いくつか読んだ川上弘美の作品で最初がこの作品かどうかは定かでないのだが、印象深い作品であるのは間違いない。 結局、改めて全部読み直した。 9作の「連作」の基本的な共通項は、語り手「わたし」が暮らす集合住宅の住人、あるいは友人・知人等々との交流の中で生まれる「物語」であり、大体が「非日常のもの」あるいは「異世界」がテーマだということ。 それは場合によっては、おそらく「わたし」自身の中にあるものの投影でもある。 表題作「神様」は作家のデビュー作で、パスカル短篇文学新人賞受賞作。だが、1998年に出たこの作品集は刊行順では4冊目になるようだ。 付け加えておくと、その表題作「神様」は、2011年の震災および原発事故の後、同年9月に『神様2011』としてリライトされてオリジナルの「神様」と併せて50ページの本になる。私もたぶん雑誌掲載時に「神様2011」を読んだ覚えがあるので、その雑誌を探したのだが見つからなかった。もしかしたら立ち読みしただけかもしれない。 9編もそれぞれにテイストが異なり、民俗伝承譚的なもの、ユーモラスでコミカルなもの、児童文学風なもの、心理的ホラー等々も交じってヴァラエティーに富む。 共通項を持ちつつも同じような話というのはない。 一つだけ、普通の小学生くらいの男の子との交流が描かれるものもあるが、それ以外は、架空のものも含め生物か、あるいは死者・幽霊が登場する。 皆、それぞれおもしろいが、冒頭の「神様」と最後の「草上の昼食」は改めてよかった。 簡単に紹介する。引用を「>」記号以下に、また一部引用の場合は「」で示す。 前者の冒頭は、>くまにさそわれて散歩に出る。川原に行くのである。 「三つ隣の305号室に、つい最近越してき」て、「引っ越し蕎麦を同じ階の住人にふるまい、葉書を十枚づつ渡してまわっていた」昔気質らしいくまと散歩に川原に行くところから始まる。 魅力的な書出しだ。 川原で家族連れと出会ったり、くまが川で魚を取って、上手に開いて干物を作ったり、持参してきた弁当を食べたりして過ごす。 くまは、魚を捕る際なんかで、時折「くま」らしいところもみせるが、概ね穏やかで気配りにすぐれている。 そんな散歩のようなハイキングの後、部屋の前まで戻り、305号室の前で別れ際にくまは恥ずかしそうに言う。「あの」「抱擁を交わしていただけますか」「親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」。 承知した「わたし」とくまは抱擁を交わす。>くまの匂いがする。(略)思ったよりもくまの体は冷たかった。 くまは言う。「熊の神様のお恵みがあなたの上にも降り注ぎますように」。 わたしは思う。「熊の神とはどのようなものか、想像してみたが、見当がつかなかった」。 「悪くない一日だった」とこの一編は閉じられる。 その続編とも言うべき『草上の昼食』がこの短編集の最後に置かれる。>くまにさそわれて、ひさしぶりに散歩に出る。 少し太ったり、息が以前より荒くなったりして成長したようにも見えるくまは「わたし」に、先日北の方へ「ともだちに譲ってもらったセコハン」の車で里帰りしたことを話す。 二人は「穴場」の草原に入っていく。バスケットから敷物を出して敷き、食べ物を並べる。くまが作った料理の数々。赤ワインも。でもくま自身は「酒はたしなみません」。 くまの料理は自己流。「学校に入るのも難しいですし」。「くまであるのならなるほど学校には入りにくかったかもしれない。学校ばかりではない、難儀なことは多かろう」。 料理の話や鍼の話をしながら食事をしているいうちに「わたし」は眠気にさそわれ、くまに寄りかかってうとうととする。 目覚めたわたしにくまが切り出す。「あの。今日はお別れを言いに」「故郷に帰ることにしました」「明後日には発ちます」「しおどき、というんでしょうか」。 びっくりしていろいろ問いかける「わたし」にくまは答える。 ずっと、帰っちゃうの。「ずっとです」こちらには、もう。「来ません。故郷に落ち着くつもりです」遊びにも、来ないの。「たぶん」。 たぶん、と言ってから、くまはわたしの肩を軽く叩いた。「そんなお顔なさらないでください」。 そんな顔、と言われ、自分の口が開かれ眉が寄せられていることを知った。「でも、どうして」と問う「わたし」に、「結局馴染みきれなかったんでしょう」と目を細めて、くまは答える。 わたしも馴染まないところがある。そう思ったが、それも言えなかった。やがて雨がやって来る。かみなりも鳴り始める。いなびかりから雷鳴までの時間がせばまってくる。 くまは傘を地面に放り、体でわたしを包みこむようにして地面にうずくまった。 雷鳴はますます大きくなる。次の瞬間、いなびかりと雷鳴はまったく同時で、からだ全体にどん、という衝撃が走った。くまごしに、大きな衝撃が走った。 くまは衝撃が走ると同時にわたしから身を離し、大きな声で吠えた。おおおおお、と吠えた。どんな雷鳴より大きな声で、くまは直立して空に向かって吠えていた。 くまは何回でも、腹の底から吠えた。こわい、とわたしは思った。かみなりも、くまも、こわかった。くまはわたしのいることをすっかり忘れたように、神々しいような様子で、獣の声をあげつづけた。かみなりがおさまり、雨が止んだ。「熊の神様って、どんな神様なの」わたしは聞いた。 「熊の神様はね。熊に似たものですよ」くまは少しずつ目を閉じながら答えた。 「人の神様は人に似たものでしょう」。 そうね。 「人と熊とは違うものなんですね」目を閉じ切ると、くまはそっと言った。 「故郷に帰ったら、手紙書きます」くまはやわらかく目を閉じたまま、わたしの背をぽんぽんと叩いた。 帰っちゃうのね。彼方を向いたまま言うと、「さようなら」くまも彼方を向いたまま言った。 さよなら。今日はおいしかった。くまの世界で一番の料理上手だと思う。手紙、待ってるからね。 くまはこのたびは抱擁しなかった。わずかに離れて並んだまま、くまとわたしはずっと夕陽を眺めていた。 この「抱擁しなかった」理由も、もしかしたらくまの「気遣い」だと思うとなかなか切ない。 その後、くまから差出人とその住所の書かれていない手紙が届く。 その手紙をわたしは三回読む。泣きそうになったが泣かなかった。でも寝床に入って少し泣いた。そして返事を書く。 そして、宛先が空白の封筒に入れ、切手を貼り、裏に自分の住所と名前を書いて机の奥にしまった。「寝床で、眠りに入る前に熊の神様にお祈りした。ずっと机の奥にしまわれているだろうくま宛の手紙のことを思いながら、深い眠りに入っていった」と結ばれる。 9編の中でも比較的叙情性の勝った、感情移入のしやすい作品だと思う。 ただ、ここでも穏やかではあるが、「他者」「異物」として「くま」が描かれている。 くまは人とは違う。くまは野生を保持し、人は野生をほとんど捨てた。だからくまは「故郷」に帰った。帰ることができた。でも人間は「故郷」を忘れて、ただ途方に暮れるばかりだ。 あるいは「人間」とは、少なくとも近代以降の人間は、「故郷」を捨て忘れることによって「成立」しているのかもしれない。 そして「故郷」は、この作品での「神様」と重なるところがある。 先述したようにこの2編に限らず、ここに収められた9編に共通しているは「異界」や「異物」であり、それはいわば「他者」でもある。 自身の中の他者性をも含めた他者性。場合によっては、かつての自身だったり、あるいは祖先の姿であるかもしれない「他者」。 それについて、この2編より、もっと象徴的な話になっているのが「離さない」かもしれない。 何を感じたかは違えど、「離さない」を最も印象深く感じた読者も少なくないのではないか。これも当初紹介するつもりだったのだが、長くなるので、簡単にだけ。「わたし」と同じ集合住宅住む「エノモトさん」が、彼が旅先から連れ帰ってきた「人魚」に「魅入られる」話である。「魅入られて」人魚から離れられなくなる。そこで人魚を海に帰すのだが。ここには、他者に対する、ある種の怖れと執着が象徴的に描かれる。そして他者は自己自身でもある。人魚が2度発する決定的な一言は、本来、こちらの人間が口にするべき言葉である。ここに逆転と混交が生じる。 民俗伝承的な体裁の心理的スリラーとして秀逸だと思う。 人間の欲望とは、他者の欲望であると言ったラカンの言葉を思い浮かべたりもする。 最後に。食べ物の話題が多いのも一つの特徴かもしれない。 手許にある2003年8/1発行の「文藝」秋号の「特集 川上弘美」掲載の、榎本正樹による作家へのインタビューで、榎本は、作家の作品では「食と性と死がボーダーレスにつながっている」 という指摘をしているが、この9編でも濃淡の違いこそあれ、それらは全体を覆っているように思える。 ただ、こうして作品について書いてきても実際に作品を読んだときの何だか不可思議な感覚を表現できているように思えないのは、同じ雑誌で「あらゆる意味で最も批評しにくい作家」とか「批評を禁じるところがある」(斎藤美奈子)とか言われていることと重なっているのかもしれない。 何だか、一般化してしまうとどうしてもこぼれ落ちてしまうものがある。それはおそらくごくごく個人的な、プライベートな何かに触れる感触とでも言えばいいか。読者が各々持っている生(なま)の「個人性」「私性」みたいなものだが、こう書いてしまうとまたちょっと違うかという気になる。いや何と言ったらいいのか、というより、私自身が自分がどう感じたかがわかっていないのだろう。でも感じるものはあるのだ。きっと。 それが優れた文学であり優れた小説なのだと言われれば、そのとおりなのだろうけれど。 では、次回、DEGUTIさん、よろしくお願いします。2021・10・21・T・KOBAYASI追記2024・04・27 100days100bookcoversChallengeの投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目)という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。
2022.07.20
コメント(0)
-
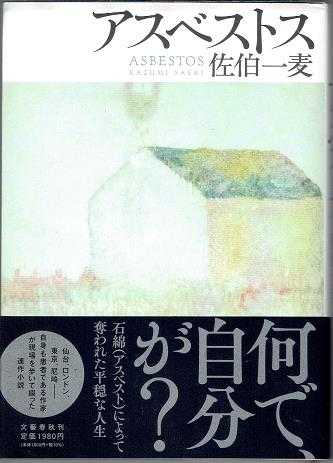
週刊 読書案内 佐伯一麦「アスベストス」(文藝春秋)
佐伯一麦「アスベストス」(文藝春秋) いつの間にか、大家になってしまった佐伯一麦の2021年秋の新刊、「アスベストス」(文藝春秋社)という短編(?)集を読みました。目次せきらしゃかきぐさあまもりうなぎや 全てひらがなで題がつけられている作品集でした。この作品集には「アスベスト」を主題にした4作の短編が収められています。佐伯一麦による「アスベスト作品集」、つまりは「アスベストス」というわけです。 目次の次のページにはこんな文章が載っています。アスベストス(asbestos)石綿、アスベスト。天然に産する繊維状鉱物の総称。主成分が珪酸マグネシウムからなる蛇紋岩系のクリソタイルと角閃石系のクロシドライト、アモサイトなどがある。アスベストの語源はギリシア語で、直訳すれば「消滅することのない」、つまり永久不滅の物質という意味である。 佐伯一麦を最初に読んだのは、もう30年以上も昔です。「ア・ルース・ボーイ」(新潮文庫)という、高校を中退して、なんだかイガイガした少年の話にはまりました。惹かれついでに、なんだかんだ読み続けて到達したのがこの「アスベストス」でした。 「平成の私小説」と勝手にジャンル化していますが、すべて(?)の作品の登場人物が、いつも咳をしている小説群でした。たとえば「ショート・サーキット」(福武文庫・講談社文芸文庫)という、最初期の作品では電気工の仕事をしている青年が登場しますが、彼はすでに発作的に起こる咳に苦しめられていたはずです。 目次の二作目「らしゃかきぐさ」が、もっとも心に残りました。その中にこんな一節があります。その寝台のベッドカバーの上に、ちょこんと載せられてあるものを見て、あ、やっぱりあった。と彼は気が弾むのを覚えた。それは、去年も目にした、精巧な針金細工のような、とても変わった形をした花穂のドライフラワーだった。咲き終わった花序の小苞の先端が鋭い鉤状に曲がっていて、その根元の周りを総苞が美しい曲線を描いて数本取り巻いている。それも鋭く長い棘をしている。 それに会うために、彼はこの場所を再び訪れたのだ。 ― チーゼル。 一年前、本を読みながら、部屋の隅に座っていた若い女性の案内人が、そうおしえた。(P40) イギリス旅行中の著者が夏目漱石ゆかりの「カーライルの家」を訪ねた場面です。英名チーゼル、和名はらしゃかきぐさとの出会いが書かれている短編ですが、ネットで調べてみるとこんな植物でした。 「宿痾」という言葉があります。辞書によれば「長い間治らない病気」。「持病」ということになりますが、佐伯一麦にとってはアスベストによる肋膜炎と喘息は、まさに「宿痾」と呼ぶべき病で、彼の文学とは切り離すことが出来ない病であるともいえるかもしれません。 この短編集の、著者インタビューだったと思いますが、こんなふうにも言っています。「あ、アスベスト君」 そう呼ぶような仲間意識がアスベスト(石綿)にはある。 すべてが棘でできているチーゼルのドラフラワーに心惹かれるれる様子が、淡々と描かれる穏やかな作品ですが、病を抱えて書き続けてきた作家の「書く」ことの深層を思わせる佳作だと思いました。追記2022・05・24 ブクログというサイトに感想を書きました。ついでなので貼っておきます。 佐伯一麦という作家の作品と出会ったのは、新潮文庫の新刊「ア・ルース・ボーイ」でした。1994年の出版ですから、今から30年前です。「あっ、こんな作家がいるんだ!」と思いました。「ショート・サーキット」(福武文庫)、「雛の棲家」(福武書店)と読み継いでファンになりました。 作品の底には、どの作品にもイガイガとした現実との接触感に対するいら立ちがながれていて、それは苦悩とか自己嫌悪とか言う、主観的な判断ではない直接的な痛みでした。勝手な言い草ですが、このイガイガ感に惹かれて読み続けてきました。 作家の肉体を苦しめ続けるイガイガがこの作家の文学を支えているというのがぼくの思い込みです。 その佐伯一麦がイガイガを直接作品化したのが本書でした。読み終えて感無量ですね。ここの作品のよしあし以前に、30年、書き続けてきた作家の今を思い浮かべました。 「やあ、アスベスト君」 作家の、そんな呼びかけが木霊している作品集でした。
2022.05.09
コメント(0)
-

週刊 読書案内 川上弘美「三度目の恋」(中央公論新社)
週刊 読書案内 川上弘美「三度目の恋」(中央公論新社) 川上弘美の最新作(?)です。彼女はこの作品に先立つ2016年、「伊勢物語」の現代語訳を、池澤夏樹が編集して評判をとった河出書房の「日本文学全集」で、上辞しています。本を見たことはありますが、内容は知りません。 で、その仕事と、今回の「三度目の恋」(中央公論新社)という作品との関係について、本書の「あとがき」でこんなふうに書いています。 実は伊勢物語を訳しながら、どうにもすっきりしない感じを覚えていたのです。業平という男が、つかめなかった。光源氏の造形に影響を与えているだけあって、数々のまつわる恋物語もあれば、仕事人としての業平も描かれていれば、男どうしの友情も描かれている。光源氏よりも人間くさい男ではある。それにしても、女たちはなぜ、この業平という男にこれほどまでにとらわれるのだろう。そのことがどうにも解せなかったのです。(「三度目の恋」P387) ようするに、伊勢物語を精読した川上弘美は「どうして業平はもてるのか?」ということが「解せなかった」というわけで、ちょっと、自分なりに謎解きしてみましょうとこの作品を描いたということのようです。 で、現代の女性である主人公の「梨子(りこ)」さん。その梨子さんがほんの幼い頃から「ナーちゃん」と呼んで恋い慕う男「原田生矢(なるや)」さん。梨子さんが小学校の用務員室で出会う、実になぞめいた「高丘(たかおか)さん」という三人の登場人物を設定して、小説は始まります。 お話は現代っ子である「梨子さん」が「時をかける少女」よろしく、「昔」、「昔々」、「今」、と章立てされた時空を飛び交います。 ちょっとエキセントリックな少女であった梨子さんの「愛」と「恋」を巡る遍歴を経た成長譚ともいえます。江戸の遊郭とか平安貴族のお屋敷とか、結構、とんでもない世界に飛び込んでいく冒険譚でもあります。 ちょっと、ネタバレしますと、時空を超えるのですから、作品世界がハチャメチャにならないための仕掛け、まあ、ドラえもんでいえば「どこでもドア」として使われるのは、この作品では「夢」ですね。「時をかける小学生」だった梨子さんが、「夢見る子育てママ」に成長して、「三度目の恋」を夢みるというのが、まあ。ぼくなりの要約です。 川上弘美も「蛇を踏む」(文春文庫)で芥川賞を取って25年になるのですね。この作品には、彼女らしさというのでしょうか、「におい」や「気配」を描いたシーンも満載で、お好きな人にはたまらないでしょうね。 面白かったのは、あの澁澤龍彦の遺作、「高丘親王航海記」(文春文庫)を巡る展開が挿入されていることでした。作家自身も、先述の「あとがき」でその作品に対するオマージュだと書いています。 澁澤龍彦の小説は、最近では近藤ようこによって漫画化されていて、そっちの方が有名かもしれませんが、在原業平との関係で言えば、高丘親王というのは、平城帝の息子で、業平の父、阿保親王の弟ですね。業平にとっては叔父さんなのですが、在原業平を描くときに必ず登場する人物なのかどうか、「語りたいこと」と「語る人」によっては、ほぼ、登場することのない人物だと思います。 ところが、この作品では小学生の梨子ちゃんが、いきなり高丘さんという謎の人物に出会うのです。読む人によっては、「高丘・・・?聞いたことある名前なんですが!」とか、何とか、まあ、気付く人もいる名前で、その後、かなり読みすすめていくと、澁澤龍彦の作品名まで出てくると「やっぱり!」と納得するのですが、だからといって、なぜ高丘さんが登場するのかわかるわけではないのです。なんだか何を言いたいのかわからない紹介になっていますね。 おそらく、この作品に登場する高丘さんという人物と高丘親王とが、どう繋げられているのかというのは、ひょっとしたら、こちらがメインなのかもしれないという感じで、この作品の肝の一つなのはわかるのですが、まあ、何が語りたいのか、結局よくわからないのです。 作品のディテールは「婦人公論」(中央公論新社)に連載しただけのことはあって、セクシャルでスキャンダラスなシーン満載なのです。偶然、聞くことができたのですが、読み終えた数人のお知り合い(みなさん女性でした)の評価は◎と×とで真っ二つでした。 ぼく自身は、何処か、還暦を超えたおばさまがお書きになった「通俗小説」という印象で△でしたが、評価が割れるのも納得という感じでした。「伊勢物語」なんかに興味をお持ちの方にはいいかもしれません。なんといっても、有名な「芥川」のシーンの前後が実録「性愛小説」化されていますからね。 「高丘親王航海記」(文春文庫) 近藤ようこ版
2021.10.31
コメント(0)
-
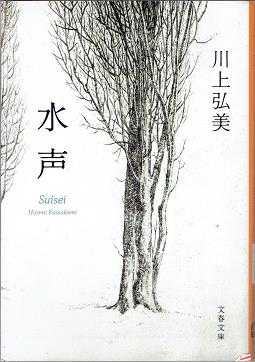
週刊 読書案内 川上弘美「水声」(文春文庫)
川上弘美「水声」(文春文庫) 久しぶりに川上弘美を読みました。「水声」(文春文庫)です。 Suiseiと表紙にルビがあります。「すいせい」と読めばいいようです。2015年の読売文学賞受賞作です。 ページを繰って最初に目に入るのは目次です。1969年/1996年ねえやたちママの死パパとママ/奈穂子家 ― 現在夢女たち父たち1986年前後1986年2013年/2014年 こんな感じです。 書き出しはこんなふうです。夏の夜には鳥が鳴いた。短く、太く、鳴く鳥だった。雨戸はたてず、網戸だけひいて横たわれば、そのうちに体は冷えてくるはずだったのに、その夏はいつまでも体が熱を持ったままだった。 「その夏」のことが語りだされているのですが、その夏とはいったい、いつの夏なのでしょう、という謎でこの小説は始まります。作中の語り手は「都」という女性で、語っているのは2014年、この作品が発表されたのは2013年から2014年の「文学界」という文芸雑誌ですから、作家が書き始めたのは2013年、ないしは2012年の暮れあたりかもしれませんが、作中人物でもある「都」が語るのは2014年でないと、結末との辻褄が合いません。 小説って、面白いですね。そういうこともできるわけです。 「都」は1969年に11歳の少女だった女性で、2014年に存命ですから、この冒頭を書いたとき(語った時(?))には55歳か56歳です。 ちなみに川上弘美は1958年生まれですから、「都」と同じ年、その事実が「作品」が描いていること、まあ、たとえば自伝小説であるというふうに関係があるかといえば、この作品では、それはありません。ただ、作家と同じ時代を生きてる登場人物という意味ではかなり大切な要素素だと、ぼくは思いました。 「その夏」という謎でページを繰り始めると、すぐ次のページにこんな描写があります。 匂いは記憶を呼びます。 アスファルトを平らにならす熱いにおいをかぐといつも、セブンアップをやたらに飲んだ1969年の夏を思い出す。 あの夏私は十一歳で、陵は十歳だった。 この引用部に出てくる「あの夏」と冒頭の「その夏」は違うようです。小説が、いや、55歳だかの作中人物「都」が、今、語っているのは「その夏」であって「あの夏」ではないからです。 ついでですから、補足すれば、「陵」というのは「都」の弟です。この小説の登場人物は目次にある「ねえや」、「ママ」、「パパ」、ママの幼なじみの娘で二人にとっても幼なじみである「奈穂子」、と、この「姉弟」で、ほぼ、すべてです。 もう一つ、ついでですが、この引用部の「匂いは記憶を呼びます。」というような描写は、「これが川上弘美です!」 とでもいうテイストですね。彼女の作品は、ストーリー云々にこだわるよりも、こういう「感覚的」表現を面白がる方がスリリングかもしれませんよ。 ともあれ、「都」が語り始めた「その夏」とはいつの夏のことで、「その夏」、語るべき、何があったのか、それがこの作品の「愛と人生の謎(裏表紙の宣伝文句)」というわけでした。 そのあたりは、まあ、ご自分で読んでいただくほかないわけですが、実はこの作品にはもう一つ「謎」があると、ぼくは思いました。 それは題名です。「水声」って何だ? ということです。申し訳ありませんが、ここで禁じ手を使います。 ふいに、水の音が聞こえた。遠い世界の涯(はて)にある、こころもとなくて、ささやかな流れの。 わたしと陵はまだその涯まで行っていない。誰もそこに行きつくことはできないのかもしれない。ママも、パパも、そこに行きたいと願ったのだろうか。 水鳥が、一羽だけ、暗い水の面にうかんでいたの。奈穂子は言っていた。一羽だけなんだけれど、ちっともさみしくなさそうだった。雪にうずもれるようにして、静かにうかんでいた。あなたたちのママは、あの水鳥みたいだったわね。 東京に戻ると、もう家はきれいに壊され、ただ平らな土地だけがあった。思っていたよりもすっと狭かった。ママが好きだったゆすらうめも、あじさいもなくなっていた。 また夏が来る。鳥は、太く、短く鳴くことだろう。陵の部屋を、今日はわたしから訪ねようと思う。 ご自分でお読みくださいなどと言いながら、小説の結末を引用するとは何事だというわけで、ちょっと反則なのは承知です。しかし、この最後の描写は小説の謎を、相変わらず暗示はしていますが、解いているわけではありません。 むしろ、「また夏が来る。」という最後の一文が冒頭の「夏の夜には鳥が鳴いた。」という一文と呼応して、語りの一貫性を、同じ人物の同一の語りであること示していると考えられる結末です。 マア、そのあたりを理由にご容赦願いたいのですが、注目していただきたいのは、ここにきて、がぜん浮かび上がってきた「水」についてです。 「水」と「廃墟」をめぐる「都」の身辺の出来事に、重ねられている奈穂子のことばが、この小説全体の読み直しを求めているように、ぼくには感じられたのです。 「時間」の往還の中で浮かび上がる「昭和」から「平成」という時代の記憶。「身体」として感受する「他者」と「孤独」。 「都」と「陵」という姉弟の「出生と愛の秘密」。 読みどころは満載ですが、もう一つ、2011の震災の「災後小説」という視点から読み解くことを、物語の終わりに暗示しているのを見落とすわけにはいかないのではないでしょうか。 小説の底に流れている「水」の声に耳を澄ませることで浮かんでくる世界があるのではないか、そして、その世界が川上弘美という作家の「現在」を暗示するのではないか、そんなふうに思うのですが、なかなかピントがあいませんね。 どうですか、一度「水の声」に目を凝らしてみませんか?
2021.04.30
コメント(0)
-
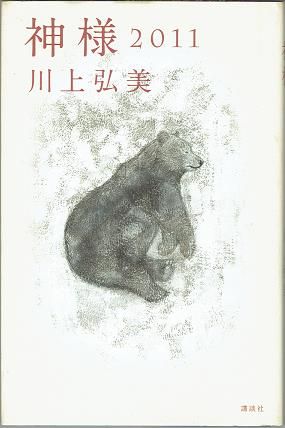
週刊 読書案内 川上弘美「神様」・「神様2011」(講談社)
週刊読書案内 川上弘美「神様」・「神様2011」(講談社) 高橋源一郎の「非常時のことば」(朝日文庫)という評論を読んで感想を書きました。その本の二つ目の評論というか、「非常時のことば」が第一章だとすると、第二章は「ことばを探して」というタイトルの評論なのですが、その章で川上弘美の「神様」と「神様2011」という作品が丁寧に読み返されています。 「神様」という作品は1996年に芥川賞をとった「蛇を踏む」より、二年早く書かれた、彼女のデビュー作ともいうべき作品ですが、お読みになったことがある方はご存知のように、「くま」がアパートの三つ隣に引っ越してきて、まあ、いろいろ丁寧な挨拶があって、ある日、誘われて河原までお弁当を持って散歩に出かけてお昼寝をして帰ってくるというお話しです。 2011年に東北の震災がありましたが、川上弘美はその年に、この作品を書き直して「神様2011」として、同じ講談社から再刊しています。この本には「神様」と「神様2011」が両方とも入っていてお買い得ですが、ともに、とても短い作品です。 この、一冊の小さな本で読み比べることのできる、二つの「神様」という小説は、ぼくのような、粗雑な読者には「地震があった後の世界」と、「地震のことなど夢にも想像しなかった世界」という二つの世界が描かれていることくらいまでは理解できるのですが、その二つの世界に、同じように登場する、この「くま」って、いったい何なんだという訳のわからなさを増幅させただけで終ってしまいかねない作品でした。 その「神様」を高橋源一郎は見事に読み解いていました。 久しぶりに出現した「神様」は、黙って、自分を必要としなくなった国を歩き、おそらく、数少ない信仰の持ち主である「わたし」を抱擁するのである。そういえば、ドストエフスキーの大審問官に対しても、最後に、場違いのように出現したキリストは、その唇に口づけをして、何処ともなく去ってゆくのだった。 「神様」の世界は。守がない世界を生きているぼくたちの悲しみを、そっと静かに、救い上げたような小説だった。(1994年版「神様」評) だが、「あのこと」が起こった。 「くま」とは神なき時代に出現した神なのですね。ここで「大審問官」の例を引っ張り出してくる、その読みの卓抜さに、まず、うなりましたが、「あのこと」が起こった結果「神様2011」として、川上弘美によって書き直された本文について高橋源一郎の結論は以下のようなものでした。「親しい人と別れる時の故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」 わたしは承知した。(くまはあまり風呂に入らないはずだから、たぶん体表の放射線量はいくらか高いだろう。けれど、この地域に住みつづけることを選んだのだから、そんなことを気にするつもりなど最初からない) くまは一歩前に出ると、両腕を大きく広げ、その腕をわたしの肩にまわし、頬をわたしの頬にこすりつけた。くまの匂いがする。反対の頬も同じようにこすりつけると、もう一度腕に力を入れてわたしの肩を抱いた。思ったよりもくまの体は冷たかった。(「神様2011」) ここで「わたし」は、「この地域に住みつづけることを選んだ」と「神様」の前で告白している。この部分こそ、「神様2011」の白眉の個所ではないだろうか。なぜ、「あのこと」が起きたのか。それは、人々が、「神様」を信じなくなったからだ 一つの世界だけを見ていながら、同時に、その世界に重なるように、震えて、かすかに存在している、もう一つの世界。そんな、においや気配しか存在しないような世界を感じとること。それこそが、なにかを「読む」ことなのだ。 二つの作品をお読みになったことがあれば、これで十分納得していただけるのではないでしょうか。 少しだけ補足すれば、高橋の引用は「神様2011」のお別れの抱擁のシーンですが、1994版「神様」ではこうなっています。 「抱擁を交わしていただけますか」くまは言った。「親しい人と別れる時の故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」わたしは承知した。くまは一歩前に出ると、両腕を大きく広げ、その腕をわたしの肩にまわし、頬をわたしの頬にこすりつけた。くまの匂いがする。反対の頬も同じようにこすりつけると、もう一度腕に力を入れてわたしの肩を抱いた。思ったよりもくまの体は冷たかった。(1994年版川上弘美「神様」) 上記の引用の太字の部分が2011年版で加えられた記述ですね。高橋はその追記部分を問題にしています。それにしても、高橋源一郎の「読み」の定義は、素晴らしいですね。詳しくは川上弘美「神様2011」(講談社)・高橋源一郎「非常時のことば」(朝日文庫)をお読みください。追記2010・02・14 高橋源一郎「非常時のことば」の感想はここをクリックしてみてください。ボタン押してね!ボタン押してね!カラマーゾフの兄弟(1) (光文社古典新訳文庫) [ フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフス ]
2020.02.14
コメント(0)
-
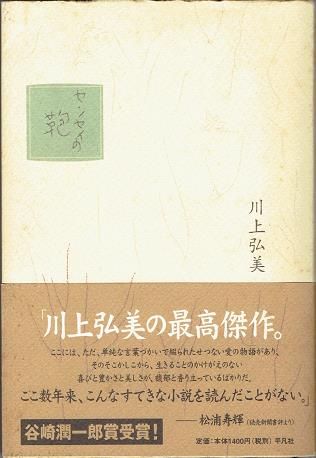
週刊 読書案内 川上弘美「センセイの鞄」(文春文庫)「2004年《書物》の旅 その3」
川上弘美「センセイの鞄」(文春文庫) これも「2004年《書物》の旅」と銘打って案内している、過去の案内のリニューアルです。15年前に「今」だった人たち。みんな偉くなった、そんな感じもしますね。今回は川上弘美さん。彼女は、この作品でメジャーになったと記憶しています。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 小川洋子さんの「博士の愛した数式」(新潮文庫)の主人公が、老数学者だったことを案内しながら、そういえば、川上弘美「センセイの鞄」(平凡社)も登場人物の一人は老人だったことを思い出しました。 三十過ぎ(?)の女性と、退職して七十歳を越えた老教師の恋愛を描いて評判になった小説ですね。 主人公の老教師が亡くなって、残された空っぽの鞄から一人の人間の一生分の思い出の「におい」が立ちのぼってくるような結末の小説というのが、ぼく風のまとめですね。それは、むせるような強烈な「生」を感じさせるものではなくて、古い骨董のようなにおいなんです。 老人の死と残された人間のつながりに「におい」を持ってきたところが俊逸だと思いましたね。 残された「カバン」が描かれる一方で、二人が出会い、一緒に通った居酒屋のメニューとカウンターの向こうから立ち昇るにおいがとてもいい小説なんですが、この辺りは高校生にはわかり辛いかもしれません。 でも、この作者はきっと食いしん坊に違いないということは、ほのかな共感と一緒に感じるくらいはできるでしょう。 ともあれ、小説の中に、生きている世界の「におい」と死んでしまった世界の「におい」をあざやかに描き分けた、この作家の力量は、ちょっと目を瞠るものがあると思いますよ。人は死んでしまったからといって、いなくなってしまうというわけではないのかもしれませんよ。 初稿2004・9・23改稿2019・10・25「2004年《書物》の旅」(その4)はこちらからどうぞ。追記2019・10・25 この作品を、お読みになった方は気づかれていると思いますが、「センセイ」の生前にも、死後にも、この小説の中に「匂い」に関する記述は、実はありません。 川上弘美という作家は、「蛇を踏む」という作品で芥川賞を受賞して知られるようになった人です。その後、「神様」という本当のデビュー作が単行本化され、東北の震災の後、「神様2011」として、改稿されたりしました。「蛇を踏む」は蛇をたしかに踏んづけてしまった、足の裏、いやからだ全体に残る、独特の「感触」が20年たっても消えませんし、二つの「神様」は、神様が作品の世界を抜け出して「そこにいる」という「気配」だけは残ります。三作とも何が書かれていたかはほとんど記憶していないにもかかわらずです。 「センセイの鞄」も、「におい」の記述なんてどこにもないにもかかわらず、残された鞄を開けて覗き込む最後のシーンで立ち上ってくる「におい」が、作品全体を包み込むような印象が鮮やかに残っっている作品です。 彼女も今や芥川賞の選者の一人ですが、彼女の独特な感性に判定される候補作は大変だろうと、つくづく思います。追記2019・10・30あの、ちょっとお断りしますが、「センセイの鞄」は2004年の作品ではありません。2001年に出版されたと思います。10万部を超えるヒット作。でも、昨今は100万部を超えるそうですから、ホント、どうかしてますね。もちろん「昨今」がですが。 この作品は、テレビドラマにはなりましたが、たぶん、映画にはなっていません。川上弘美の世界には「絵」がないからでしょうか。いや、そんなことはないか。 追記2020・10・15「神様」の感想を書きました。こちらからどうぞ。追記2024・08・31 ブログのカテゴリーとかに「読書案内 川上弘美・小川洋子・他」を追加しました。いつの間にか、お二人とも還暦とかを通過されていて、文学賞では選者の側で、それも、そろそろ引退かというお年であることにふと気づいたからですが、大した意図はありません。 もう少し、案内する本が残っているなあというわけで、自分を励ます気分です(笑)。にほんブログ村にほんブログ村大きな鳥にさらわれないよう (講談社文庫) [ 川上 弘美 ]ざらざら (新潮文庫) [ 川上弘美 ]
2019.10.30
コメント(0)
-

週刊 読書案内 小川洋子「博士の愛した数式」(新潮文庫):「2004年《小説》の旅 その2」
2004年《本》の旅 小川洋子「博士の愛した数式」(新潮文庫) 二学期が始まったというのに、夏休みの課題図書の話からスタートします。ええーっと、読書感想文コンクールというのが毎年あって、どこかの団体が、(えらい無責任な言い草で申し訳ないけれど、多分、学校図書館協議会とか、そんな所だったと思います。)何冊か課題図書というのを選定しているわけですね。。小学校から高校までありますが、最近は大学生にも必要なんじゃないか、ナンチャッテ。 でも、へそ曲がりから見ると「子どもに読ませたい」という根性が透けて見える選定の本が多いコトも事実。不良少年は、買いそうも、読みそうもない「イイ」本のイメージもありますね。みんないい子になってほしいわけ。まあ、本なんか読んでいい子になんてなるわけないのにね。 もっとも、今年の課題図書の中の1冊。小川洋子「博士の愛した数式」(新潮社)なんて本は誰かれなしにとてもよく読まれているそうだから、そんな話にはならないでしょうね。 内容は時間限定の老数学者と少年の話。どの辺まで説明してイイのか難しい話だけれど、パズルマニアのように数学の難問を解くことだけで生きている数学者がいて、一定時間がすぎると記憶を失うという人物。ようするに、数時間毎に頭がリセットされる人物として設定されている。だから普通の生活は出来ない。 これだけ聞くと現実離れしていて読む気を失うかもしれないけれど、どこにでもいる記憶がまだらで、頑固なだけのボケ老人というと、もっと読む気を失うでしょ。だから、もうはじめから特異な人物のほうが腹が立たなくていいというわけです。 その人物とホームヘルパーの女性。この女性の生き方もかなり変わっているのだけれど、それは読んでのお楽しみ。 それから、その女性の息子の小学生が、いわばもう一人の主人公ですね。この子はプロ野球に憧れている「子どもらしい子ども」で、そういう意味でやっぱり、いまどきの子どもではないかもしれません。 ここまで書くと「浮世ばなれのファンタジーか」と思う人もいるでしょう。そういえばそうなんですけれど、そうでもないわけです。ある意味「老人介護小説」ともいえるリアリティーが、僕にはありました。ついでに阪神タイガースの歴史に詳しくなれて、「フェルマーの定理」とかともお知りあいになれる。案外お読み得かもしれません。 少々、遅ればせな、夏休みの課題処理はいかがでしょうか。(S)初出2004・9・23改稿2019・10・26追記2019・10・25 これも「2004年《本》の旅」と銘打って案内している(その3は川上弘美さん、ここをクリックしてくださいね)、過去の案内のリニューアル。15年前に「今」だった人たちの一人小川洋子さん。 15年の歳月の間に、忘れられた作品も多いですが、小川さんの、この作品は映画にもなり、誰でも知っているスタンダードになりました。1990年、「妊娠カレンダー」(文春文庫)で芥川賞をとって登場した小川洋子さんも、今では芥川賞の選考委員というわけです。 新しい作品がでれば読むのですが、阪神ファンで芦屋にお住まいだということ以外思い浮かばないぼくは、実に失礼な奴だとと思う今日この頃です。ボタン押してね!にほんブログ村言葉の誕生を科学する (河出文庫) [ 小川洋子(小説家) ]洋子さんの本棚【電子書籍】[ 小川洋子 ]
2019.10.26
コメント(0)
-

週刊 読書案内 佐伯一麦 「空にみずうみ」(中央公論新社)
佐伯一麦 「空にみずうみ」(中央公論新社) 佐伯一麦の新しい小説「空にみずうみ」(中央公論新社)を読み終えました。新しいといっても2015年に出版されているわけで、すでに文庫になっているようですし、「麦主義者の小説論」(岩波書店)とかと出版は同じ時期、2014年から15年にかけて読売新聞の夕刊に連載された小説のようです。もう五年ほどたっていますね。 本のカバーの絵が面白いのですが、樋口たつのさんという絵描きさんの絵で、新聞の挿絵は同じ人だったようです。単行本には、挿絵はありません。 食卓のテーブルで夜中の二時くらいに読み終えて、しばらく座ったままボンヤリしました。 「空にみずうみ」という作品の題名が、最初から、小説の構想のシンボルとして書きだされていたことが最後になってわかりますが、ここでは詳しく書きません。「登場人物たちは、いったい、どこで空にみずうみを見るのだろう?」 読み進めながら、ずっと考え続けていた疑問です。読み終えてみると、その題名にこそ、しばらく立ち上がれなかった理由があったと、今、感じています。どうぞ、お読みになって気づいていただきたいと思います。 小説を書いている早瀬と、草木染の作家で、編み物をしている柚子という、もう中年とはいえない夫婦の日常が、春先から、次の年の三月まで綴られています。 早瀬の名前は、「コウジ」だったか、一度どこかで出てきたように思いますが、思い出せません。廸子の旧姓は輿水といい、東京育ちです。 日々の暮らしに大きな事件は何も起きません。二人が出会う人たちが、その他の登場人物ですが、恐ろしげな人は一人も出てきません。鳥の声を聞き、日々の食卓があつらえられ、ちょっとした事件や、困りごとが季節のめぐりとともに描かれているわけで、読んでいてなにが面白いのかと言われれば、「さあ、なんでしょうね。」 と答えるよりほかにないのかもしれません。 青葉木菟(アオバズク)、画眉鳥、鶯、時鳥、トラヅグミ、雀、ジョウビタキ、カモシカ、タヌキ、蛇、クサガメ、ゾウムシ、青虫、チョッキリ、水琴窟、御衣黄、枝垂れ桜、上溝桜、山法師、欅、小楢、筍、かなかな、ニイニイ蝉、なめくじ、エダナナフシ、アメリカシロヒトリ、アシナガバチ、ミヤマカミキリムシ、紙魚、ヒメシャガ、半夏生、藍、臭木、鉢植え椿、栃、シオジ、ハンカチの木、合歓の木 冷や奴、赤かぶの酢漬け、きゅうりの辛子漬け、さやいんげんのおかか和え、自家製梅干し、無花果の甘露煮、カレーうどん、冷やしきつねうどん、麩まんじゅう、鰹のたたき、スイカ、鳥ソバ、はらこ飯、栃餅、参鶏湯ふうスープうどん、しおむすび、千切り大根の梅漬、七草粥 一年の季節を巡る中で、出てきた鳥や、虫、樹木や花を上にあげてみました。今、思いだせるものを並べたのですが、知らないものはチョッキリくらいです。その次に食楽に並んだり、客をもてなしたりする料理で、食べてみたいと思ったものを上げました。 普通の生活ですね。この普通の生活を描写するに際して、書き手である佐伯一麦はいくつかの工夫をしています。 一つは、視点人物の複数化とでもいうのでしょうか。 「私小説」の手法では視点人物は、普通、一人です。作中の主人公が作家として語るというのがよくあるパターンです。三人称で書かれている場合もありますが、事情は変わりません。ところがこの小説には視点人物が二人いるのです。佐伯と等身大の人物である早瀬以外に廸子も語るのです。 二人の家庭を、立体的に構造化するために使った手法なのかもしれませんが、今まで読んだ佐伯作品にはなかった書き方で、現実に暮らしている、別の人間に語らせるわけですから、かなりスリリングです。 読み手にすれば、二人が同時に登場する場面で、例えば、「あたたかかった」というような言葉が主語なしで使われると、「えっ?」という疑問と、その場が「ことば」を生みだしているような不思議な錯覚を生みます。 それにしても、佐伯一麦が、「私小説」世界から離陸し始めている印象は、なかなか興味深いのです。 二つめは、新聞小説という執筆の条件を、作品の中に取り込むことによって、読み手の読書の印象を重層化するとでもいえばいいのでしょうか。 小説の後半に前半で読み終わった部分を書いている作家が登場します。時間をずらしたトートロジーの世界で、読み手は不思議な臨場感を味わうのです。作家が、書いている自分自身を書く。読者は、今、書いている時間を読むわけですから、現場に立ち会っていると錯覚する、そんな感じですね。 三つめは複数の時間を、同時に書き込んでいるということです。 カモシカ騒ぎの話の中で、早瀬は誰も来ない高台でひとりの少年と出会います。さびれた山中の出会いを不思議に思った早瀬が少年に声をかけます。少年は噂になっていて、一度出会ったことのあるカモシカに出会いに来たことを告げます。 「また、シカサブロウがいないかと思って」「シカサブロウ?」「カモシカ。前にこのへんで見つけたの」「えっ、カモシカみたんだ」 早瀬が驚くと、、男の子は得意気にうなずいた。「一緒に見つけた大人の人が、たぶんまだ子供のカモシカだろうって。一頭しかいないから、親からはぐれてしまったみたい。それで、ぼく、シカサブロウって呼んでいるの」 シカサブロウは、漢字で書くなら鹿三郎だな、と早瀬は思った。「でもどうして鹿太郎や、鹿二郎じゃないんだ」「ぼく次男だから、弟がほしくて」 ― 略 ―「あ、キビタキの声だ」相変わらず囀っているのを聞いてシン二郎君が言い、あたりを見回した。「そうだね。よくわかったね」「だって、ぼく、前にいた県の鳥だから知ってる」 この少年が、ここで、一人、はぐれたカモシカを、弟を慕うように探している姿の中に、この小説の2014年という現実の時間の底に流れている、もう一つの時間が顔を見せています。東北の震災から三年という大きな時間の流れです。 早瀬には早瀬の三年の時間が流れたのですが、この少年の過ごした三年の時間、具体的な境遇や友達について、読者が言葉にして聞くことは、つまり作家が小説として書くことはできません。しかし、この少年が、なぜここにいたかということこそが、この作品が描こうとしていることじゃないかという印象が浮かび上がってきます。 作品は最後にこんな詩を引用して幕を閉じます。息子はどこかの墓に眠っているでもわたしにはどこだかわからない母親が息子をみつけられないでいるのだから神の小鳥たち、どうか息子のためにさえずってあげて母親が息子を見つけられないでいるのだ から 小説の中で、小鳥が囀り続け、二人の男女は耳を澄まし、木々や花々、小さな虫やドングリや栃の実に、コンクリートの壁から聞こえてくる騒音や、喘息の発作や手首の痛みに一喜一憂しながら、静かに暮らしています。 作家は神の小鳥や花々を描きたかったのではないでしょうか。 ともあれ、佐伯一麦という作家が新しい書き方に挑みながら、震災後の文学として、鎮魂の結晶化! を、見事に成功させた作品だと思います。どうぞお読みください。(S)追記2019・11・24 佐伯一麦はこの作品とほぼ同じ時期に「渡良瀬」という作品を完成させています。感想はこちらをクリックしてくださいね。「渡良瀬」追記2022・03・26 最近、佐伯一麦の「アスベストス」(文藝春秋社)という、新しい作品を読みました。その感想を書きあぐねて、昔の作品のことを考えています。もう少ししたら感想をアップしますが、やはり胸に迫る作品でした。ボタン押してね!にほんブログ村にほんブログ村
2019.04.25
コメント(0)
-
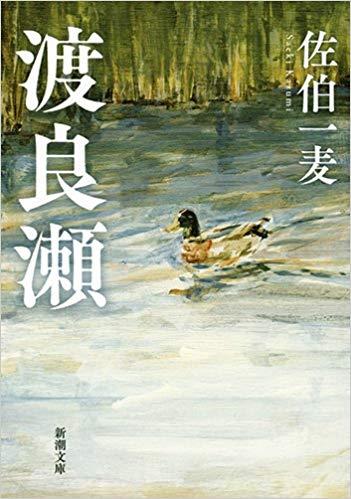
週刊 読書案内 佐伯一麦 「渡良瀬」 (新潮文庫)
佐伯一麦 「渡良瀬」 (新潮文庫) 佐伯一麦という作家のエッセイ集「とりどりの円を描く」(日経新聞社)を読み終えた。 本の紹介を集めた本だが、書評というには短い、新聞を読む読者に向けて小さなエピソードと、作家の考えが過不足なくつづられていて読みやすい。いつから、こんなふうに穏やかで落ち着いた文章を書くようになったのか。老成した作家然としている落ち着きように少しいやみだと感じないわけでもない。 「ショート・サーキット」(当時、福武文庫・現在、講談社文芸文庫)が初めての出会いだった。続けて読んだ「ア・ルースボーイ」(新潮文庫)でハマった。たしか、野間文芸賞新人賞、三島由紀夫賞をそれぞれとったはずだ。 印刷用紙を触っていて手を切ったりすることがある。たいして切れているわけではいないのに、じわじわ痛い。数日すると細く長いかさぶたができる。そんな小説だった。 2005年くらいまで、新しい作品が出ると、しようがないような気分で買いこんで読んでいた。この春に書棚の整理をしていると、大きめの判型の「鉄塔家族」(日本経済新聞社)が、妙に邪魔になる感じで座っていた。ところどころに付箋が貼ってあるから、読んだことは確かだ。たしか、これを読んだのを最後に、この人の小説を読むのを一旦やめた。 家族との不和、仕事の現場で被災したアスベストによる喘息、ずっと、ルースボーイのままで、職場や家庭はいつまでもショートサーキットしている主人公のありさま、読み終わると、切れないカミソリきずのようなひりひり感、大作の「鉄塔家族」を読み終えて、つくづく、この人の作品は疲れると思ったはずだ。 あれから十年余り、とっている新聞の書評欄に佐伯一麦が書評を書き始めた。地に足が着いたというか、穏やかな物言いで作品をほめている文章に、はてなと思った。「この人、何か変わったかな。」 何が変わったのかは、よくわからない。知り合いが勤めている大阪にある大学の文芸科で先生をしていると聞いたのもこのころだった。 新潮文庫の新刊のラインナップにあった「渡良瀬」(新潮文庫)という小説を久しぶりに読んだ。 読み終えて、 最後のシーンが引っ掛かった。しかし、全体の印象は化けた! という感じだった。以前のイメージが、小枝にとまって囀り続ける小鳥だったのに対して、かなり大きな鳥が大きく羽ばたいて、空をゆく感じがした。 主人公を取り巻く家族や、職場の状況が大きく変わっているわけではないし、主人公の描写も年齢を重ねた様子が違うだけのようだが、読んでいると読者まで傷つけるような、錆をなめたような不快感が消えていた。 あわてて、なんであわてなきゃあいけないのかわからないが、気分はあわてて「還れぬ家」(新潮文庫)を読んだ。家族も仕事も変わっていた。40年前に飛び出したはずの仙台が舞台だった。東北の大地震を被災したふるさとの町に主人公は帰っていた。 微妙なニュアンスは、以前の味わいを残しているが、この作品も「渡良瀬」に近い印象だった。 「渡良瀬」は「鉄塔家族」と描かれている時期が重なっているように感じたが、何かが変わっている。小説世界は1980年ころの作家の生活、子どもがいて、小説を書きたがる主人公がいて、それを嫌がる妻がいる。街の電気工事ではなく、配電盤製作工場の勤め人をしている。 今、手元にないのであやふやな記憶で書くが、小説の中で、時々訪ねる遊水池の野焼きのシーンが、日々の配電盤の製作のシーンと対照的なイメージで描写されており、ここに妻や子供たちを連れて来たいと思う気持ちを生活のなかでは素直に表すことができない主人公の哀切な心情の穏やかな深さがこれまでの作品にはなかった印象だった。しかし、最後にもう一度描かれた、この「遊水池」のシーンに引っかかった。 何故このシーンがもう一度ここで描かれるのか、そこまで書かれてきた電気工の主人公の描写と、このシーンがどうつながるのか。 ここで湧きあがった 自分なりの疑問に答えを出したいからというより、「還れぬ家」(新潮文庫)を読んだあと、再び自分のなかでブームになっていて、図書館という強い味方を得たこともあり、今まで読まなかった小説論やエッセイ集にも手を出しはじめた。 「とりどりの円を描く」の次に手にとった一冊は「麦の日記帳」(プレスアート)という佐伯の最新の著書だ。そのなかに「渡良瀬遊水池ふたたび」と題したこんな文章があった。 はるか上流の足尾銅山の鉱毒によって渡良瀬川は汚染され、流域の農地にまで及んでいった。日本における郊外に始まりととされる足尾鉱毒事件。そのために、時の明治政府によって、洪水調整の名目で、もともとは肥沃な農地で流れている川には魚影も濃かったこの土地は、遊水池として強制的に水没させられ作り替えられたのだった。 そして今、上流の足尾山地や赤城山一帯は、放射能の汚染地帯が広がっており、大雨のたびにセシウムを含んだ大量の土砂が、遊水池へ運ばれてくる。震災によって三年ぶりにおこなわれた野焼きは、放射能の悲惨を懸念する声を配慮して、焼く葦原の面積を例年の四〇%にとどめたという。百年を経て歴史が繰り返されている思いが湧く。 「あっ、そうか、ここが『谷中村』の水没地点だったんだ。」 さすがのぼくでも、渡良瀬川が足尾銅山の鉱毒が垂れ流された川だということくらいは知って読んでいた。 しかし、主人公が自転車に乗ってやってくるこの場所の水底には100年前に沈められた村が一つある事には気づかなかった。 気づいてみると、この場所を小説の中に描こうとしていた作家の意図のようなものが浮かび上がってくる。作家は、人が生きている、小さな「とりどりの円」を描きながら、癒しの風景としての自然としてこの場所を描いていると読んでいたのだが、そうではなかった。この風景もまた100年を超える時間をたたえた「とりどりの円」の一つだったのだ。 日々のうたかたのような人の暮らしを描く小説の最後に、この風景を描くことで、人の命や生活を越えた時間が小説世界に流れ込んでくると作家は考えたに違いない。それがぼくの納得だった。 この日記は2013年の春に書かれていて、「渡良瀬」(岩波書店)が単行本として出版されたのはその年の暮れだ。小説は20年以上も昔の生活を描いているわけで、震災も放射能汚染も想像すら出来ない主人公の暮らしが描かれている。しかし、作家のなかには100年を超える時間の流れが意識されていたことは間違いなさそうだ。 引っかかっていたとげのような読後感はこうして解消し、小説「渡良瀬」の大きさ を、あらためて実感した。2018/12/30 追記2019・04・19佐伯さんの新作「山海記」(講談社)が出ましたね。楽しみです。朝日の書評委員を退かれたのは、とても残念ですが。追記2019・11・24「山海記」を読みました。ぼくの中では2019年のベスト3に入る作品でした。感想はいずれ書きますが、ほかにも「空にみずうみ」の感想を書いています。表題をクリックしてくださいね。 ついでというわけですが、黒川創「鴎外と漱石のあいだで」(河出書房新社)という評論で、「渡良瀬川の遊水池」をめぐって田中正造と吉屋信子の父の出会いのエピソードが書かれています。で、それについて感想を書いています。表題をクリックしてみてくださいね。追記2022・09・29 「山海記」の感想は書けないまま3年経ちました。難しいものですね。自分の家のどこかにあるはずなのですが、読み終えたその本がどこにあるのかもわからない状態です。黒川創の作品の感想も書きたいと思いながらうまく書けないのでほったらかしです。「読んだ本はどこに行った?」と、自問したのは晩年の鶴見俊輔だったと思いますが、とりあえず「ああ、ここにあった」にたどり着きたい今日この頃です(笑)。 にほんブログ村(ボタン押してね!)にほんブログ村(ボタン押してね!)
2019.04.19
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










