2006年12月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
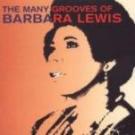
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.073)
レディソウル。とても好きな作品です。これで今年のアルバム紹介は締めの予定。みなさん、よいお年をお迎え下さい。来年もよろしくお願いします。【No.73】 ・Barbara Lewis:The Many Grooves Of Barbara Lewis (Rec.1969,70 CD化:1992)70年代前後のキャッチーでグルーヴィーなレディソウルというのは、私のツボなんですが、本作はまさにそういう作品です。録音年と場所、タイトルに魅かれて買いました。このアルバムは、69年のアルバムにボーナストラックを3曲追加した編集盤です。この人は60年初期から中期の「Hello Stranger」「Baby, I'm Yours」 といったヒット曲で有名なソウルシンガーで、その頃の作品はよく紹介されてます。本作に関して、どういう評価がされているのか私には分かりませんが凄く良い作品です。前に紹介したマキシン・ブラウンやアリス・クラークのアルバムが好きな人に気に入ってもらえそうな作品と言えば分かりやすいでしょうか?先の人達と比べると、バーバラ・ルイスのヴォーカルは少し大人な感じですね。本作のポイントは、やはりシカゴ録音(ソウル)というところだと思ってます。前に紹介したアーティスティックスもそうですが、シカゴソウルはメロディーとグルーヴ感のバランスが絶妙な作品が多いですね。日本盤も出てませんし、本CDが人気作という話も聞かないので、廃盤になる前に買っておいた方がいいと思います。ボーナストラックも全て良い出来です。捨て曲がなく爽やかな作風で凄くオススメです。サウンドも70年前後の暖かい雰囲気で最高。幸せ感(?)が高いです。大手のサイトで試聴可能です。ジャケが変わっているものがありますが、内容は同じです。是非リマスターして日本盤で出して欲しい作品です。ちなみにamazonは在庫ありでしたよ。
2006.12.31
-
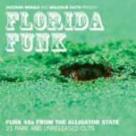
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.072)
Jazzmanディープファンクコンピの最新作を紹介。ちょっと遅くなりましたが。【No.72】 ・V.A.:Florida Funk (2006)私の好きなレーベルであるJazzmanの最新ディープファンクコンピ。今はノーザンソウルだ!と言いつつ、やはりファンクも好きなんですよね。このファンクコンピシリーズは、「Texas Funk」「Midwest Funk」に続く3作目。間にQuanticによるファンクコンピがありましたが、あれは企画ものだと思ってます。ディープファンクのレーベルとしては、Stones Throwも非常に良いものを出していますが、選曲という点でJazzmanの方が私好みですね。内容は、既に他のコンピに収録された曲や雑誌等で紹介されている有名どころ(と言ってもマニアの間で)も含まれますが、全く知らないグループが大半です。前者では、Third Guitarの「Baby Don't Cry」やPearl Dowdellの「Good Thing」、BlowflyやCokeあたりがそうですね。私にとっての聴き所は、The Outlaw Gangの「Funky Fast Bump」、The Universalsの「New Generation」、Cokeの「Na Na」あたりでした。特にThe Outlaw Gangは必聴ですね。キラーチューンなんでしょうけど、私は聴いたことがなかったので、凄く気に入ってます。Cokeの「Na Na」も非常にカッコいいファンク。とにかく、この3曲は凄くオススメです。James Knight & the Butlers、Oceanlinersも好きですね。コンピ全体としては、前2作と比べ、ポテンシャルが非常に高くなっていると感じました。具体的に言うと、マイナーながら一定のレベルを保った作品が殆どで捨て曲が少なくなってます。ライナーも充実してます。ディープファンクが好きな人は買って損のないアルバムです(というか殆どの人が買ってると思いますけど)。
2006.12.30
-
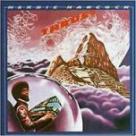
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.071)
ジャズファンク。ハービー・ハンコックのファンク時代ではライヴ盤を除くと最も好きな作品。【No.71】 ・Herbie Hancock:Thrust (1974)超がつくほどのジャズファンク、レアグルーヴ定番なんで、軽く読み飛ばして下さい。今更な感はかなりありますが、思い入れのあるアルバムですし内容も最高なんで、日記に書くことにしました。「Head Hunters」以降のファンキーな作品群の中では、ライヴ盤を除くと、間違いなく本作が最高傑作だと思います。ジャズファンクと呼ばれる色んな作品を聴いてきましたが、本作に匹敵する作品はそう多くはありません。ファンクのグルーヴとジャズのインプロが見事に融合した作品で、ハービーはもちろんですが、特にポール・ジャクソンのベースと、マイク・クラークのドラムによるグルーヴ、スリリングなプレイには圧倒されます。この3人のコンピネーションは、数多いジャズファンク、クロスオーバーものの中でも最高の一つだと思います。本作は全4曲で、凄い演奏が聴ける「Actual Proof」、名曲「Butterfly」、ファンキーな「Parlm Grease」「Spank-A-Lee」を収録。個人的には、「Actual Proof」「Spank-A-Lee」が大好きです。何回聴いたか分かりません。ご存知の方も多いと思いますが、ライヴアルバム「洪水」での「Actual Proof」は更に強力なので、そちらもオススメです。本作を聴かずに、レアグルーヴのマイナーものばかり掘っている人がいるとしたら、それは凄く損をしていると言えます。本物を聴かずにどうする?って感じがします(またしても余計なお世話ですね)。とにかく、生音が生み出すグルーヴの素晴らしさが、分かっていただける作品です。ジャケがイマイチですけど。実は私の父も聴いていた作品です。影響されたのかもしれませんね。楽天booksリンクはこちら↓スラスト(突撃)
2006.12.29
-
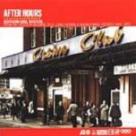
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.070)
ノーザンソウル(英国のシーン)のコンピ紹介。第三弾。ノーザンソウルは、真面目な話、今のストレス社会にピッタリだと思います。気分転換に最適。年末年始は10連休の人も多いのではないでしょうか?私は今日から休みですが、5日出社で8連休。【No.70】 ・V.A.:After Hours Northern Soul Masters (2002)After Hoursのノーザンコンピは、現在Vol.3まで出ています。これは1作目。前の日記を読んでいた方は、お分かりだと思いますが、Alice Clarkつながりという単純な動機です。Alice Clarkのアルバム未収録曲を1曲目にもってくるあたり、この人の人気の高さが感じられますね。この曲は1968年録音で、アルバムとは趣の異なる見事なノーザンサウンド。良いです。本コンピは、ワーナーから出ており、1965年から73年の曲が収録されています(ズバリ私好みの年代)。収録アーティストはメジャーからマイナーまで幅広く、またアルバム未収録や初CD化の曲が多いです。キャッチーかつグルーヴィー、ノーザンソウルならではの躍動感が感じられる好アルバム。コンピ全体のポテンシャルも高いと思います。これからノーザンソウルのコンピを買おうと思っている人は、KentやGoldmineのコンピを適当に選ぶより、本シリーズを買ってみる方がいいかもしれません。本作は24曲収録。価格もそう高くないですし、入手もしやすいです(輸入盤ですが大手のショップでは容易に入手できます)。店頭にも置いてあることも多いですよ。前に紹介した2作品と共に、ノーザンソウルの良さが気軽に楽しめる一枚でオススメです。今後も、ノーザンコンピ紹介シリーズ(?)は続けていきます。
2006.12.28
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.069)
フリーソウルでも注目されたレアグルーヴの傑作。最近、輸入盤や入手が難しいものが多かったので、入手しやすいアルバムを紹介。【No.69】 ・Alice Clark:Alice Clark (1970)アリス・クラークは、フリーソウルで有名になったと思われている人もいるかもしれませんが、レアグルーヴの初期から注目されていたアーティストです。これは唯一のアルバム(のはずです)。グルーヴィーなサウンド、アリス・クラークのちょっとハスキーで力んだ感じのヴォーカルが素晴らしいです。ドラムもカッコいいですよ。特に「Don't You Care」「Never Did I Stop Loving You」が定番として知られますが、他にも良い曲が多く捨て曲がないアルバムです。レアグルーヴで話題になるアルバムは、キラー・チューンと言われる曲だけは良いけど、後が今ひとつという作品が非常に多いので、本作のようなアルバムは凄く印象に残りますね。クレジットが全くないので、詳細が不明なのが残念。解説も推測で終わってますしね(もっと詳しい人に書いてほしいですね)。レアグルーヴの名盤であるジャクソン・シスターズと同様に、一般の洋楽ファンにもオススメできるアルバムです。ちなみに、ノーザンソウルのコンピ「After Hours」のVol.1で、本アルバムに未収録の曲が聴けます(さすがUK。ソウル・ファンク好き)。本作でファンになった方は、聴いてみて下さい。後、リンクはってありますが、楽天booksの紹介文は笑えます(他の楽天ショップも同じ)。やはり音楽に関しては、大手の音楽サイトと比較して、レベルの低さ・アンテナの狭さを感じますね。ショップのコメントとは思えないです。私もレビュー書いてますので、こちらも笑ってやって下さい。★12/28追記:本作は1970年の作品でした。「After Hours」の解説より。また、同アルバムの本作未収録曲は1968年の作品。詳しくない日本盤の解説よりは、英語でもUKのコンピが役に立ちます。
2006.12.25
-
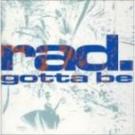
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.068)
アシッドジャズ後期に発売されたジャジーなファンク作品。ラッド。今も活動しているようです。アルバム紹介はクリスマスとは関係なし。ケーキはもう食べました。甘いもの好きなんですよね。【No.68】 ・rad.:Gotta Be (1994)アシッドジャズ・レアグルーヴに、一番はまっていた頃に買ったアルバム。ラッド(キーボードとヴォーカル)は、当時Soulcietyというドイツのマイナーレーベルからアルバムを発売していた女性ミュージシャン。ちなみに、このレーベルには、Poets Of Rhythmもいましたね。ラッドで私が購入して聴いたのは、本作と「radified」、「Higher Plane」の計3作品です。本作と「radified」は今も持ってます。「Higher Plane」が好きになれず以降買ってませんが、最新作は試聴した感じでは良さそうでした。本作「Gotta Be」は彼女の代表作。参加メンバーで特筆すべきは、タワー・オブ・パワーのドラマーであるデヴィッド・ガリバルディでしょう。らしいプレイを聴かせてくれます。凄くカッコイイですよ。あと、同じくタワー・オブ・パワーのホーンセクションが参加しているのも見逃せません。もちろんラッドも素晴らしいミュージシャン。彼女のオリジナル曲も(特にタイトル曲は最高)良い出来ですし、ヴォーカルも中々で特徴もあって好きですね。キーボード(ピアノ、オルガン、エレピ)も上手いです。ボビー・バードの賛辞がのってるんですが、聴いていただければ納得できます。でなければ、これだけのメンツは集まらないでしょう。アルバムの方は、UKソウル・アシッドジャズの影響があるものの、よりファンク色が濃いサウンドになってます。当時は好きでよく聴いた作品ですが、日本盤は廃盤かもしれません。ただ中古やオークションで安く入手はできると思います。このアルバムに限らず、この頃の結構いい作品でも入手困難になっているのが現実。悲しいもんです。今のクラブ系ミュージックも同様の道をたどるでしょう。ただCDが廃盤でも、どこかからダウンロードできる形で音楽は残りそうですが。一応、楽天内のリンクを貼っておきます。ラッド/ゴッタ・ビーゴッタ・ビー / ラッド
2006.12.24
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.067)
デヴィッド・T.ウォーカーの4thアルバム。祝再発!【No.67】 ・David T. Walker:David T. Walker (1971)デヴィッド・T.ウォーカー。今やソウル、ジャズファンやギターファンでなくても、彼のギターをどこかで聴いていると言ってもよいほど、数々の名盤に参加し、独特の輝くようなプレイで知られるギタリスト。吉田美和のソロに参加していた人と言えば、洋楽ファンでなくても分かるのではないでしょうか。とにかく、一聴しただけで、この人のギターだと直ぐに分かりますから凄いです。特にバッキングが最高ですよね。これはOdeレーベルからのアルバムで通算4作目のソロ作品です。初期作品は、CD化もされていましたが、この時代のアルバムがリイシューされず、やっと12月に発売されました。私がこの人のギターを初めて聴いたのは、おそらく90年代で、マリーナ・ショウのアルバムだったと思います。以来、ファンな訳で、今回のOdeレーベル時代のリイシューは凄く嬉しかったです。解説や色んなレビューをみると、次作「Press On」が最高傑作とされているようです。ギターソロプレイの密度という点では、そういう気もしますが、アルバム全体のサウンド・構成は、本作(「通称:The Real T.」)の方が好きですね。デヴィッドのギターが好きといっても、それだけを聴くわけではないですし、メンバーもベースのウィルトン・フィルダー、ドラムのポール・ハンフリーなど、こちらの方が好きな人が揃ってます。まず、ジャクソン・ファイヴの名カバー「Never Can Say Good Bye」が素晴らしい出来です。そして続く「Loving You Sweeter Than Ever」も明るくグルーヴィーで最高。ミドルテンポのナンバーが殆どの「Press On」に比べ、選曲にメリハリがあり、アップテンポでカッコいい曲からメロウな曲まで多彩。ウィルトン・フィルダーとポール・ハンフリーによるファンキーなグルーヴが私的にはポイントが高いです。まあ、どちらも素晴らしいアルバムですので、両方買ってもよいと思います。
2006.12.23
-
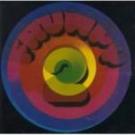
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.066)
70'sジャーマンハードロックの傑作。ハードロック好きな人は要チェックです。【No.66】 ・Frumpy:2 (1976)ジャーマンロックというと訳が分からないイメージがしませんか?特にプログレッシヴロックとかは、イタリアやフランスとも違う多種多様な音楽が多いです。今回紹介するのは、そういうのではなく、オーセンティックなジャーマンハードロックバンド:フランピーの2ndアルバムです。本作はハードロックが凄く好きな人の間では知られた存在で、フランピーの最高傑作であると共に、ジャーマンハードロックの名盤です。特にヴォーカルのInga Rumpfはジャーマンハードロックを代表する女性ヴォーカリストとして有名です。後に結成するAtlantisというバンドも素晴らしく、1stアルバムは傑作だと思います(機会があれば紹介します)。ここ数年は、Atlantisの1stやライヴの方を聴くことの方が多いですが、たまには懐かしいハードロックを紹介するのもいいかと思いました。私が大学生の頃よく聴いた作品です。1stもまあ良いのですが、この2ndではハードロックバンドとして大きくスケールアップしており、全4曲素晴らしいものになってます。オルガンもカッコいいですし、泣きのメロディーもちゃんとあります。もちろん、Inga Rumpfのソウルフルなヴォーカルも素晴らしいです。70'sハードロックファンは必聴盤です。確かにブリティッシュハードロックのA級(?)バンドの凄さは認めますが、レベルの低いマイナーグループを聴くよりは、フランピーなど他国のバンドを聴くのもいいと思います(経験上)。いいバンドが沢山ありますから。また、スコーピオンズだけが、ジャーマンハードロックではないということが、本作を聴けば分かると思います。特にオルガンが好きな人にはオススメです。名作。輸入盤で出ていましたが、現在入手可能かどうか不明(こればっかりですみません)。
2006.12.20
-
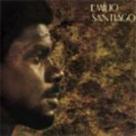
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.065)
ブラジリアン・メロウグルーヴの名盤。定番です。【No.65】 ・Emilio Santiago:Emilio Santiago (1975)エミリオ・サンチアゴの作品では本作(1st)が一番好きです。ブラジルのメロウ・レアグルーヴものの中でも、この作品は非常に有名ですよね。タイトなドラムが印象的な定番曲「バナネイラ」を収録していることで知られていますが、アルバムの出来がとにかく素晴らしいです。2003年にwhatmusic.comからリイシューされた時は凄く嬉しかったですね。捨て曲なしのアルバムとは、まさに本作のこと。選曲、エミリオ・サンチアゴのヴォーカル、バックのサウンド・アレンジ全て文句なし。私の好きなエレピも絶妙ですし、グルーヴィーな曲からメロウな曲まで、どれも最高の仕上がりです。バックのメンバーも超豪華(ジョアン・ドナート、ジルソン・ペランゼッタ、アジムス等、有名な人が多すぎて書ききれません)。ブラジルの男性ヴォーカルを紹介する上でも、この人は絶対外せませんね。とにかく声がいいです。何作品か国内でもCD化されてますが、本作が最高傑作だと思います(多分多くの人がそう思っていると思います)。一時期、輸入盤に解説と帯をつけた日本盤が出ていたと思いますが、現在は輸入盤でのみ入手可能と思われます。何の予備知識なく買っても損はしない作品。是非聴いていただきたいアルバムです。
2006.12.19
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.064)
Prestigeジャズファンクの傑作。CDのジャケは最悪だけど、バーナード・パーディーのドラムで買いの一枚。明日は会社に行けそうです。【No.64】 ・Johnny Hammond Smith:Legends of Acid Jazz(Rec.1969 CD化1996)これは10年近く前に買った懐かしいアルバム。Legends of Acid Jazzは、Prestigeレーベルの70年前後のコテコテジャズファンクをリイシューしていたシリーズですが、中でも本作は最も聴いたCDの一つです。「Soul Talk」「Black Feeling!」の2作品を収録。メンバーはいつもの顔ぶれ(バーナード・パーディー、ジミー・ルイス、ラスティー・ブライアント等)。聴き所は、名手バーナード・パーディーの素晴らしいドラミングとジミー・ルイスのベースによる骨太でファンキーなグルーヴです。この時期にパーディーが参加したジャズファンク系のアルバムでは(あくまで私が持っているCDの中で)、ベストと言っていいプレイが聴けます。今回ブログを書くに際して聴きなおしましたが、ドラムの切れが半端ではありません。特に「Soul Talk」「Dig On It」は必聴の名演。まさにグルーヴマスター!大音量で聴くと鳥肌ものです。「Black Feeling」「Johnny Hammond Boogaloo」「Soul Talk-70」もグルーヴィーで好きです。70年代にはミゼル兄弟によって、洗練されたジャズファンクアルバム:「Gears」といった名作を残すジョニー・ハモンドですが、この頃が一番好きです。レアなファンク、ジャズファンクを聴く前に、本作で聴けるようなグルーヴを聴いておいて損はないと思います。濃すぎて(殆ど演歌?)馴染めない曲もありますが、先にあげた曲を聴けるだけでも本CDを買ってよかったと思います。洗練された欧州のジャズロック・ファンク系が好きな人にはオススメできないですが、ドラムが好きな人(あるいはドラムをやっている人)は名ドラマーであるバーナード・パーディーの豪快かつ切れのあるプレイを聴けるというだけで買う価値があります。リンクはってますが、今は輸入盤でのみ入手可能だと思います。
2006.12.18
-
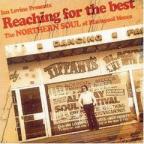
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.063)
ノーザンソウル(英国のシーン)のコンピ紹介。第二弾。DJ Ian Levineによるコンピ。ノーザンソウルって元気が出るというか、平日でもテンションを上げてくれますよね。といいつつ、熱と体調不良で今日は会社を休んでしまいました。【No.63】 ・V.A.:Reaching For The Best・Blackpool Mecca Story(2004)これはノーザンソウルDJとして非常に有名なIan Levineによるものです。この人のコンピだけでも結構多いのですが、本作は現在でも入手しやすいCDです。特徴としては70年代の曲が殆どであるという点でしょうか。2CDで50曲!収録してます。ちなみに、Blackpool Meccaはノーザンソウルの有名なクラブの名前です。正直カバー範囲が広すぎる(ディスコ調の曲まで何曲か収録されてる)感がありますが、さすがIan Levineと思わせるグルーヴィーで凄く良いノーザンが非常に多く収録されてますので買って損はないと思います。私的には、平均点の曲が多いCDより、凄く良い曲があるCDの方が、コンピでは特にポイントが高いです。DJらしく踊ることを重視した選曲がされていると思います。ドラムがカッコいい曲も多いですね。アーティストは、比較的メジャー(Gil Scott HeronやVoices of East Harlem)からマイナーまで色々です。DISC1の1曲目:The Carstairsの「It Really Hurts Me Girl」からカッコ良すぎです。特に、この曲は大好きでよく聴きます。ディープファンクも同じですが、完璧なコンピは少ないですから、色んなコンピから自分の気に入った曲を集めるのがいいでしょうね。ただ沢山買うと、既に持っている曲の割合が高くなってくるのが難点ですね...だからといってレアものを買っても、レアなだけで内容が×なCDもありますし。困ったもんです。ノーザンソウルについては、また間をおいて紹介していきたいと思います。
2006.12.18
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.062)
ノーザンソウル(英国のシーン)のコンピ紹介。第一弾。【No.62】 ・V.A./Northern Soul Scene (1998)ノーザンソウル(英国のシーン)は凄く好きです。昔はディープファンクに凄く興味があったんですが、今は断然ノーザンソウルです。明るくてキャッチーでグルーヴィー。最高ですね。このアルバム以外にも非常に多くのコンピがKentやGoldmine等から発売されてますし、内容もピンからキリまであって、何を買っていいのか分からないような状態ですね(ディープファンクもそうですが)。もちろん、このアルバム以外にも傑作コンピはありますので、今後紹介していくつもりです。ディープファンクと同様にシングル主体のシーンですから、どうしてもコンピに頼ってしまいますね。本作はDeccaからリリースされたコンピで、比較的安く、内容も良いですし、入手しやすいので選びました。25曲収録です。このシリーズでは「Mod Scene」が結構売れていたように思います。私が持っている他のノーザンソウルコンピと比べると、白人のグループが多いのが特徴ですね。正直、本当にノーザンソウル?って感じる曲も多いですが。まあ曲がよければ気にしないです。「I'll Hold You」「Nothing But A Heartache」「Name It You Got It」「Picture Me Gone」とかが特にお気に入り。グルーヴィーさという点では、他のコンピの方が上だと思いますが、良い曲が多いのと、日頃ソウルを聴かない音楽ファンに対して、敷居が低いのが良いところでしょう。色んなグループの曲を集めているにしては、当時らしい統一感も十分感じられます。オススメです。
2006.12.17
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.061)
Roy Ayersのライヴ。テンションの高い傑作。懐かしいアルバムで、久々に聴き返してみました。UPのペースが早いのは分かってるんだけど、PCに向かうと書いてしまうんです。現在、私自身はソウルばかり聴いているので、後々他のジャンルについてはネタに困りそうです。【No.61】 ・Roy Ayers Ubiquity:Live At The Montreux Jazz Festival (1972)ジャズファンクが好きな人なら一度はこの人の作品をどれかは耳にしているはず。有名ですからね。私はRoy Ayersの凄いファンというわけではないので、あまりCDは持ってませんが、このアルバムは凄く聴いたアルバムです。72年ですが洗練された音です。今聴いても古さは感じませんね。アルバム全体のテンションが非常に高く傑作ライヴだと思います。このCDは、当時日本でのみ発売されたLPに未発表作品を加えたもので、96年に発売されました(もう10年もたつんですね)。私が丁度、ジャズファンクにはまっていた時期に購入したものです。Roy Ayersのプレイ、そして毎度のことながらドラム・ベースがカッコいいですし、Harry Whitakerのエレピもgoodです。グルーヴィーな「Daddy Bag」「Move To Groove」「Sketches in Red,Yellow,Brown,Black, and White」、Roy Ayersの緊張感のあるプレイが聴きものの「Your Cup of Tea」が気に入ってます。オススメです。現在輸入盤で扱われているのか分かりませんが、機会があれば是非聴いてみて下さい。
2006.12.16
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.060)
日本のイージーリスニング系ジャズヴォーカルアルバム。岡崎広志さんの作品。オススメです。【No.60】 ・岡崎広志:Living Jazz (1971,CD化2003)岡崎広志は、伊集加代と共に「11PM」のオープニングテーマが有名です。本作は、国産のイージーリスニング系ジャズやボサ・ノヴァを紹介するLiving...シリーズでリイシューされた71年発表の作品。当時のアルバム名は解説によると「驚異のエイト・トラック・サウンド~Easy Listening Special」。タイトルが時代を感じさせます。曲も有名なスタンダード(ジャズやロックなど)ばかりで、いかにも当時ありそうな企画。これだけ読むと聴く気がなくなりそうですが、実は非常に素晴らしい作品。スタンダード曲も岡崎広志のヴェルヴェッド・ヴォイス(帯に書いてました)と、当時の日本の実力派ミュージシャンによる洗練されたサウンドで凄く良い仕上がりになってます。日本人が歌うジャズも独特の味があって私は好きです。本作は岡崎広志とスターゲイザーズ名義でレコーディングされてますが、このメンバーがまた凄いんですよね。例えばドラムは石川晶、ピアノは大野雄二(ルパンやソニア・ローザのアルバムで有名)、ギターは杉本喜代志(カウントバッファローズにもいました)。これを知ると聴きたくなりませんか?グルーヴィーな曲ももちろんありますが、全体的に心地よい作品で聴いていて和みます。たまに引っ張り出して聴くアルバム。このシリーズは今も続いているようですが、何作品出てるのか最近チェックしてないんで分かりません。ちなみに、スキャットで有名な伊集加代のアルバムが結構このシリーズで出てますので、要チェックです。私もタイトル忘れましたが持ってます。こういうシリーズは、知らない間に廃盤というケースがよくありますので注意です。ジャケもいいです。
2006.12.15
-
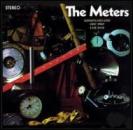
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.058,059)
ニューオリンズファンク。基本です。新鮮味はないですが読んでやって下さい。今日は忘年会でしたが仕事があって欠席。まあいいんですがね。【No.58,59】 ・The Meters:Meters (1969)/Look-Ka Py Py (1970)何を選ぶか迷ったのですが、一枚には選べず有名な1stと私の好きな2ndを選びました。雑誌等でよくとりあげられる作品なんで、既に持っている方は読む必要はないかと。Josieレーべルの1st~3rdは凄く好きです。ファンクインストを語る上で外せない作品群。ただ1stは正直聴きすぎて最近は殆ど聴いてません。2nd「Look-Ka Py Py」の方をここ数年は聴きますね。1stに劣らない素晴らしいアルバムだと思います(ジャケは地味ですが)。Metersは、なんといってもJoseph 'Zigaboo' Modelisteのドラムが最高です。ドラムが好きな人で、この人を知らない人は是非聴きましょう。ジャズロックとかのドラマーは手数が多く空間を埋め尽くすタイプが多いんですが(それはそれで好きですけど)、この人の場合は空間をうまく使った力強いドラミングが見事です。文句なしの演奏。この間の上手さに関しては、この頃のMetersの音楽についても言えます。習字なんかでも余白が大事だと思いますが、音楽でも同じですよね。それでいてスカスカな感じがしないのは流石です。サウンドも乾いた感じが非常に好きです。マイナーファンクやディープファンクを聴く前に、Metersはおさえておくべきグループですね(J.B.はもちろんですけど)。実際カバーも非常に多いですからね。日本盤は、ようやく2006年にCD化されてます(楽天にはないようですが大手に行けばあります)。どう考えても遅すぎますよね~。私が買ったのは99年の輸入盤。ここちらの方が安いのでオススメです(収録曲は変わらず。共に未発表曲を2曲収録)。3rdも良作ですので、気に入った方は聴いてみて下さい。写真は1stです。
2006.12.14
-
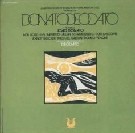
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.057)
ブラジリアンフュージョンの傑作。【No.57】 ・Joao Donato:DONATODEODATO (1973)これは、ジョアン・ドナートがデオダートと組んでMUSEから発表したブラジリアンフュージョンアルバム。結構前に日本盤でCD化されました。ジョアン・ドナートのグルーヴィーな作品と言えば「Bad Donato」(そろそろ日本盤が出る予定だったような気がします。輸入盤ではCD化済み)が有名ですが、それと比べると、この作品は、より洗練されていて、心地よいメロディーとグルーヴが特徴です。アルバムの内容で言えば甲乙つけがたい出来だと思いますが、聴いた回数で言えば、私の場合、こちらの方が圧倒的に多いです。フュージョンといっても、ジャズフュージョン作品の駄作で聴かれるようなチープさは全くありません。何といってもドナートによるオリジナル曲のメロディーが素晴らしいですし、デオダートのアレンジも冴えてます。もちろんドナートのエレピも絶妙です。メンバーも、ランディー・ブレッカー、アイアート・モレイラなど豪華ですが、私的には、アラン・シュワルツバーグ(でいいのかな?)の凄くファンキーで躍動感のあるドラミングが気に入ってます。特に1曲目の「Whistle Stop」はレアグルーヴとしてもオススメの一曲。本作を聴くたびに、アメリカのジャズミュージシャンが出すブラジルっぽいフュージョンアルバムとは全然違うな~と感じますね。ありそうで無いサウンドだと思います。穏やかなブラジリアングルーヴを楽しみたい方にはオススメのアルバムです。楽天booksにありましたが在庫切れでしたのでリンクはってません。
2006.12.13
-
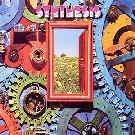
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.056)
フランスのジャズクロスオーバーもの。レアグルーヴ。お気に入りです。今日は余裕がなくて、アルバム紹介が短くなってしましました。【No.56】 ・Synthesis:Synthesis (1976)フランスのクロスオーバーなジャズファンク・ロック系グループ。日本盤で発売されたコンピに収録されたこともありましたね。ジャズロックファンにはお馴染みのフランスの実力ミュージシャン(フランソワ・ジャノー、アンドレ・チェッカレリ、ディディエ・ロックウッド等)が参加したグループ。2002年に輸入盤でCD化されましたが、現在入手可能かどうか不明。フュージョン一歩手前(ここがポイントなんです)って感じで、緊張感と心地よさが同居したサウンドは絶妙です。ブラスセクションを加えたビッグバンド編成も豪華で良いです。非常に完成度の高いアルバムと言えます。アンドレ・チェッカレリ(Dr)の切れのよさ、女性ヴォーカル、エレピの使い方などレアグルーヴファンには、たまりませんね。フランスは元々ジャズロック(MAGMA、ZAOなど)の下地があるんで、レベルが高いのも納得できます。オススメです。
2006.12.12
-
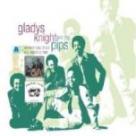
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.054,055)
ソウル。グラディス・ナイトのモータウン後期の傑作。【No.54,55】 ・Gladys Knight and The Pips:Neither One Of Us/All I Need Is Love (1973)グラディス・ナイトも凄く好きなシンガーです(ソウルは好きなシンガーが多すぎ)。これまでは、モータウン時代の彼女の曲は編集盤やベスト盤という形でリリースされることが多かったように思いますが、11月に輸入盤ですが、スタジオ盤8作品が2in1という形で計4枚リイシューされました。ジャケがオリジナルを再現していないのが残念ですが、ファンにとっては嬉しいリリースです。全部買うほどお金はないですが、何枚か代表的なものは買うつもりです。今回取り上げたのはモータウン後期の7作目と8作目です。理由は、サウンドの完成度が高いのと、両作品共に好きなギタリストであるDavid T.Walkerが参加しているということです(もう少し音が大きいと嬉しいんですけどね)。この2作品は73年ということもあり、エレピが結構使われているのが個人的には好きなポイントで、ヒットした「Neither One Of Us」は代表的な例です(もちろん名曲)。また続く「It's Gotta Be That Way」も素晴らしい名曲。David T.Walkerがいい味だしてます。これは、ジャクソン・シスターズでもお馴染みのジョニー・ブリストルの曲。この人は、本当にいい曲かきますね。「All I Need Is Love」収録曲では同じくブリストルの「I'll Be Here」や「The Only Time You Love Me Is When You're Losing Me」が素晴らしいです。アルバムとしては、どちらもミディアムテンポのナンバーが多いのですが、ファンキーな曲からバラードまで色々楽しめますし、グラディス・ナイトのヴォーカルはもちろん、曲とサウンド・アレンジも抜群に良いので退屈することはありません。ボーナストラックも3曲収録。特に私の好きな曲である「I'm Gonna Make You Love Me」が収録されているのが嬉しい。ソウルをこれから聴こうという人にはオススメなCDです。
2006.12.11
-
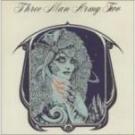
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.053)
ブリティッシュハードロックの名盤。ロック強化中です。なぜかCD化に恵まれない一枚。【No.53】 ・Three Man Army:Two (1974)ブリティッシュハードロックファンの間では有名なグループ。これは3rdアルバムで、個人的には彼らの最高傑作だと思います。一般的にも評価が高い一枚。Gurvitz兄弟のドライブ感満点のギター、ブリティッシュな抒情性のある旋律、曲の良さ、グルーヴ感など、全てを兼ね備えた名盤。おそらく、日本人が好む(勝手に決めつけてます。すみません)70'sブリティッシュハードロックの要素が、このアルバムには全て詰まっていると言っていいと思います。特にこのアルバムでは、元Jeff BeckグループのTony Newmanが素晴らしいドラミングを聴かせてくれます。疾走感溢れる「Polecat Woman」や「Burning Angel」「Irwing」、名曲「Space Is The Place」など何回聴いたか分かりません。というのも、私がこの作品を初めて聴いたのはLPで、もう15年ぐらい前になると思いますから。この作品は、輸入盤で93年にCD化され、その後、本グループの編集盤が出た際にCD化されてますが、日本では私の知る限り未CD化。輸入盤も現在では新品での入手は難しいように思います。なぜなのか不思議ですね。ハードロックのリイシューものとしては、絶対売れると思うんですが。ZEP、パープル、ユーライア・ヒープ、Queen、ブラックサバスなど大物グループだけではない、ブリティッシュハードロックの奥深さを痛感させられるアルバム。見つけたら買って聴いてみて下さい。
2006.12.10
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.052)
ブリティッシュロックの傑作。大好きなグループ。カテゴリ別に分けたらロックが少なかったので追加。色々聴いてますが、私の出発点はロックだし今も好きなんで。【No.52】 ・Wishbone Ash:Pilgrimage (1971)ブリティッシュロックグループであるウィッシュボーン・アッシュの2ndアルバム。一般には3rdアルバムである「百眼の巨人アーガス」(→日記には書かないアルバム紹介のページ参照)が最高傑作とされてます。彼らを初めて聴いたのは中学生の頃ですから、これも付き合いの長いグループです。先ほどの3rdはもちろん傑作ですが、忘れてはならないのが本作:2ndアルバムです。両方とも大学生の頃LPで聴いていたのですが、その後CDでも購入しました。1st~3rdまでは統一された独特な世界観があり、どれも外せないアルバムですが、特に2nd、3rdは必聴です。彼らの場合、いかにもブリティッシュといった抒情的な旋律とサウンド、ツインリードが一般に強調されがちですが、各メンバーの技量ももっと評価されるべきかと思います(特に初期はインストパートで聴かせるバンドでしたから当然です)。特に、この2ndアルバムを聴くと、ギター(もちろん上手いです)だけでなくタイトなドラム・ベースがあってこそのバンドであったことが分かります。また、音楽的な幅の広さにおいても2ndアルバムは注目されるべき内容で、トラッド、ブルースはもちろんジャズ的な要素までも取り込んだサウンドが楽しめます。特徴のある独特なコーラスも気に入ってます。冒頭の「Vas Dis」からオリジナリティーのあるジャズロック(こういうサウンドは他にはちょっとないですね)でカッコいいです。もちろん、本グループならではの美しい曲「Lullaby」、「Valediction」も素晴らしいですし、ラストのブルースも最高。70年代のロックファンにはオススメですね。巡礼の旅[+1]
2006.12.09
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.051)
日本の70年代ロック名盤。レアグルーヴでもあります。いつものように土曜は早起きです。【No.51】 ・鈴木 茂:バンドワゴン (1975)ティン・パン・アレーのギタリストである鈴木茂の1stソロ。ご存知な方も多いと思います。70年代の日本のロックを代表する名盤です。「砂の女」「微熱少年」など名曲揃い。こんなにグルーヴィーな日本のロックがあったのかと驚きます。20代の人にこれを聴いてもらうと、殆どの人がホントに70年代?という反応を返してきます。もちろん気に入ってもらえます。歌詞(日本語)の古さを感じる部分はありますが、サウンドに関して言えば、今聴いても全く古さを感じません。曲もインスト含めて良い出来で、とくに前述の2曲は必聴でしょう。アルバム全体に渡って、鈴木茂のメロディーセンスが光ってます。また、特筆すべきは、現地(LA)のミュージシャンで固めたバックのファンキーなグルーヴ(ベースとドラムが最高です)、鈴木茂のギタープレイ(スライド、音色、バッキング等)、アレンジの素晴らしさでしょう。現在の若手ミュージシャンが影響を受けたアーティストにあげるのも当然(音を聴けば納得できますよ)。非常に極端な表現ですが、渋谷系以降の日本のグルーヴ感を重視した音楽を75年にやっていたと思ってもらえれば分かりやすいかもしれません。洋楽ファンにもオススメですよ。大手のサイトで試聴可能。本作とは方向性が異なりますが、ゆったりとした2ndアルバム「Lagoon」もオススメで、エレピがいい感じですし、いい曲が揃ってます。
2006.12.09
-
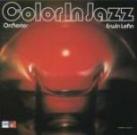
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.050)
MPSレーベルの傑作。ジャズオーケストラもの。レアグルーヴの定番曲も入ってます。金曜日というのに仕事ばかりです...悲しい。【No.50】 ・Orchester Erwin Lehn:Color In Jazz (1973)前にも書いてますが、MPSは好きなレーベルです。元々欧州ジャズが好きなこともありますし、ジャズを基本としながらも、その音楽性の幅広さは凄いですからね。それに加えて私はジャズオーケストラものが好きなんで、当然この作品は好きなアルバムなわけです。グルーヴィーなナンバーも収録されてますしね。ちなみに、この作品の一部の作品は、かなり前に紹介した傑作コンピ「Snow Flakes」にも収録されてますし、MPSのクラブジャズ系傑作コンピである「Between or Beyond The Black Forest」にも収録されてます。レアグルーヴでは「カラー」、「ファイヴ・トゥ・フォー」あたりが有名ですが、個人的には冒頭の「アルフレッド」が一番好きですね。ビッグバンドのカッコよさが出ているし、とにかく楽しい曲です。演奏も切れがあって先にあげた曲より断然テンション上がりますね。続く「バージス」や「エル・クェルヴォ・ヌエヴォ」もいいメロディーをもった良い曲です。このアルバムが日本盤でリイシューされた頃は、沢山のMPSレーベルのアルバムがリイシューされましたが、中でもこのアルバムは大好きでした。捨て曲がありませんし、クラブジャズとかレアグルーヴとか関係なく良いアルバムです。日本盤で出てましたが、現在入手できるかは分かりません。最近はClarke-Boland Big Bandの作品も容易に輸入盤で入手できますし、いい時代になりましたね。楽天booksリンクはこちら↓カラー・イン・ジャズ
2006.12.08
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.049)
シカゴソウルの傑作。ソウルファンには定番ですね。雨に降られるし、仕事で疲れてるし今日はテンション低めです。こういう時は、元気のいいノーザンソウルを聴くことが多いです。【No.49】 ・Tyrone Davis:Turn Back The Hands Of Time (1970)Brunswickレーベル70年代の人気作で、タイロン・デイヴィスのセカンドアルバム。と言っても私は、この人のアルバムはコレしか持ってないんで、この人については多くを語ることができません。私はサザンソウルもノーザンソウル(英国のシーンも含めて)も好きですが、実際初めてソウルを聴く人が、名盤というだけでサザンソウルのディープなものを聴くと抵抗があるかもしれません。ソウルは時代・場所・レーベル・アーティスト等でかなり違うんで、最初にどれを聴くかがポイントになるジャンルだと思います。例えば、私が日記で紹介しているソウルだと、アーティスティックスとかマキシン・ブラウンあたりは、ノーザンテイストで明るく聴きやすいアルバムですし、ウィリー・ハイタワーやキャンディ・ステイトンは少しディープですが、比較的抵抗なく聴ける作品(内容が抜群だから)だと思います。話がそれましたが、本作もそういったソウルファン以外の人が入りやすい作品で、完成度の高いアレンジ・タイトなグルーヴと、タイロン・デイヴィスのヴォーカルとが絶妙にバランスされた傑作です。解説によると、タイロン・デイヴィス自身は元々サザン的なディープシンガーらしいですが、そこに上手くノーザンテイストが盛り込まれているのがこの作品を特別なものにしていると思います。タイロン・デイヴィスが全体の曲のバランスを考えて、軽快に歌っているように聴こえますね。もちろん曲も良いです(当時かなりヒットしたアルバムですから)。ファンキーなグルーヴも気に入ってます。オススメです。楽天booksリンクはこちら↓ターン・バック・ザ・ハンズ・オブ・タイム
2006.12.07
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.048)
クラシックピアノの大好きな作品。ソウル、ファンク、ジャズもいいけど、たまには、クラシックもいいですね。今もショパンのワルツを聴きながら書いてます。クラシックはそう詳しくないんで、ほんの参考程度に読んでいただければよいかと思います。【No.48】 ・Daniel Barenboim:Mendelssohn/Songs Without Words (1974)メンデルスゾーンの無言歌集を全曲収録。無言歌集は有名ですが、全48曲収録されているCDは少なく、これはその中でも代表的な作品だと思います。2CDです。メンデルスゾーンの無言歌集の特徴は、とにかくメロディーが素晴らしい点です(美旋律の宝庫です)。また旋律も親しみやすいものが多く、ポピュラーミュージックを聴いている人でも、すんなり入っていける作品と言えます。クラシックを聴いてない人には、op.30の「瞑想」がオススメですね。凄く良いですよ。クラシックピアノに何を期待するのかで、このアルバムに対する個人の評価は変わるとは思いますが、リリカルな旋律の素晴らしさを期待するのであれば、文句なしにオススメできるアルバムです。まさにSongs Without Wordsの名どおりの作品。バレンボイムの演奏もいいですし、録音も良いです。無言歌集の他には、「子供のための小品」「ヴェネツィアの舟歌」「2つの小品」「アルバムの綴り」を収録しています。最近はジャズピアノでもメロディーが美しいものが売れていますが、そういうのが好きな人には是非聴いて欲しい作品。意外に求めているものがクラシックの世界にあったりしますよ。
2006.12.06
-
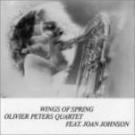
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.047)
欧州ジャズ・フュージョン(クロスオーバー)の傑作。【No.47】 ・Olivier Peters Quartet:Wings of Spring (1980)私がこの人を知ったのは、多くの人と同じく「The Spinning Wheel of Jazz」というジャズレアグルーヴのコンピでした。このコンピが再発されていた頃は、ヨーロッパや日本の昔のジャズ、フュージョン(私はクロスオーバーという呼び方の方が好きです)、プログレが、メジャー・マイナー含めて再注目されていた時期で、数々のコンピがリリースされていたように思います。その後、日本のCelesteレーベルから2001年に本作がリイシューされ購入しました(まだ入手可能なはず)。同時期に、Celesteレーベルからリイシューされた同傾向のものも、いくつか購入しましたが、その中では断トツでこのアルバムが良かった記憶があります。フュージョンというカテゴリーで紹介されることも多いですが、一般に想像されるような軽いフュージョンでは決してなく、欧州らしく透明感があり、80年代の作品ですが非常に音は硬質です。ジャズと言った方がいいと思います。演奏もダイナミックでカッコイイです。その辺が好きな理由ではありますが、ブラジリアンなフィーリングが随所に見えるところも、この作品の良いところです。隠れた傑作ですね。Olivier PetersはSax,fluteを担当してますが、ジャンルを超えた活動をしているようで、そういう背景がこういったサウンドにつながっているように思います。クラブジャズ的には、女性VoのJoan Johnsonのスキャットや歌がやたらと注目されてましたが、各演奏者のプレイも良く、アルバム全体がスリリングでタイトです。冒頭の「Wings of Spring」や「Full Moon」が特に好きですね。こういうのを掘り出してリイシューする人たちに感謝です。最近のCelesteって全くチェックしてないのですが、まだ続いているのでしょうか。楽天では売ってないようです。大手で購入されることをオススメします。ジャケの雰囲気どおりの作品です。
2006.12.05
-
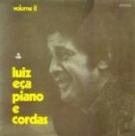
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.046)
タンバ・トリオのピアニスト:ルイス・エサの傑作ソロアルバム。思ったより早く帰れましたんで一枚紹介。【No.46】 ・Luiz Eca:Piano E Cordas (1970)タンバ・トリオは私がジャズ・ボッサを好きになるきっかけとなった思い入れのあるグループです。本作はタンバ・トリオの名ピアニストであるルイス・エサのソロアルバムで、CD化をずっと待っていた一枚です。10月に発売されていたのを最近知って即購入しました。またまたBOMBAレコードからのリイシュー(BOMBAさん感謝です)。同時期のソロアルバムである「ブラジル70」も同じシリーズでリイシューされてますが、内容は圧倒的にこちらが上です。とにかくピアノとストリングスのアレンジが絶妙!(この組み合わせは凄く好きなんですよ)。ため息がでるほど美しいアルバムです。ボサ・ノヴァスタンダードやルイス・エサのオリジナル曲を収録してるのですが、スタンダードの選曲も抜群です。ルイス・エサはタンバ・トリオの作品でも分かるようにクラシックなど音楽的な素養が豊かで、ピアノ演奏・アレンジ共に上手い人ですから、よく聴いたスタンダードも凄く新鮮に聴こえますし、ブラジル音楽のメロディーの素晴らしさ・奥深さを再認識させられます。間違いなくボサノヴァ・インストの名盤です。唯一残念なのは収録時間が短いことでしょうか。どの曲も、もっと長く聴いていたい気がします。ちなみにCDは限定盤なんで、ブラジル音楽ファンは早めに購入されることをオススメします。買って損はありません。こういうの聴くと、またブラジル熱が再発しそうになります。今年発売されたリイシューものではベスト10に入る作品。楽天内で販売されていました。リンクは↓(07/1/21追記)。ルイス・エサ/ピアノ・イ・コルダス(紙ジャケット仕様)
2006.12.04
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.045)
サザンソウルの名女性シンガー。定番ですが大好きなんで紹介。明日書けないかもしれないんで、今書いときます。【No.45】 ・Candi Staton:Candi Staton (2004)邦題は「ベスト・オブ・キャンディ・ステイトン」。色んなジャンルを聴いてきましたが、もし好きな女性シンガーは?と問われたら(実際は問われたことないですけど)、キャンディ・ステイトンは間違いなく、その答えのベスト5に入ります。上手い人は特にソウルでは多いですが、この人の場合、上手いのは当然として、とにかくカッコイイ。彼女をNo.1の女性ソウルシンガーにあげる人がいるのも納得です。実はしばらくソウルから離れていた時期があったのですが、再びソウルの良さを再認識させてくれた思い入れのある一枚でもあります。ゴスペルをルーツとしながらも、他のソウルシンガーとは一味違う凄さを感じます。鳥肌ものですね。声も好みです。本作はベスト盤で、Fame時代(70年前後)の1stと傑作2ndアルバムが全曲収録され、同3rdの一部とシングルB面などが収録されています。この内容と26曲収録でこの値段は安いです。好きな曲も「I'm Just A Prisoner」「Heart On A String」「Stand By Your Man」「How Can I Put Out The Flame」「In The Ghetto」「Get It When I Want」等あげるときりがないです。バックのサウンドもグルーヴ感に富んでますし、サザンソウルらしい乾いた感じが良いです。もちろんオススメです。買うならブックレットが付いている日本盤。大手のサイトで簡単に試聴できますよ。楽天booksリンクはこちら↓ベスト・オブ・キャンディ・ステイトン
2006.12.03
-

今日の一枚 (Groove Finderブログ No.044)
ジャズファンク。ジャムバンドが注目された頃のマイナー作品を紹介。【No.44】 ・On The Corner With Fuzz:B'Gock! (1999)ジャムバンドシーンは90年代後半から注目されたアメリカのムーヴメントですが、サウンドは、極端に言えばアメリカ版アシッド・ジャズとも言えます(ムーヴメントとしては全く違いますけど)。ジャズファンクが基本にあるグループが多いです。ギャラクティックやそのバンドのドラマーであるスタントン・ムーアが、日本では有名ですよね。今回紹介するのは、Deep Banana BlackoutというバンドのギタリストであるFuzzのソロアルバム。ちなみに、このバンドは日本でこそ知名度が低いですが、メンバーがジョン・スコフィールドのアルバム(Bump)に参加する程、実力のあるバンドです。私はライヴ:「Rowdy Duty」しかもってませんが、こちらも良い作品。ただVoが好みではなく日記で紹介はしません。本作は、トリオが基本なんですが、曲によってオルガン、エレピ、ホーンセクション、DJ Logicが加わり多彩なジャズファンクを聴かせてくれます。グルーヴィーなのは言うまでもありません。この人は、ギターが上手いのはもちろんですが、ホーンアレンジも手がけ、曲も大半がオリジナルという多才ぶり。カバーもウェスの「Four On Six」があったり中々楽しめます。「Too Bad」とか凄く好きでよく聴きました。ジョン・スコフィールドがジャムバンドに影響されて2作ほどファンキーな作品を出してましたが、このアルバムの方が断然好きですね。現在廃盤。このあたりのCDは内容が良くても、マイナーなレーベルから出ているものが多いだけに、すぐに入手困難になってしまうのが悲しいですね。Deep Banana Blackoutが日本で売れていれば注目もされていたとは思いますが...
2006.12.03
-
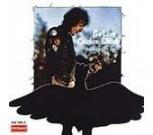
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.043)
ブルースロック。スタン・ウェブは最高です。今日も早く起きてしまった(土曜はいつもです)。【No.43】 ・Chicken Shack:Goodbye Chicken Shack (Rec.1973 1976発売)英国三大(ほんとか?)ブルースバンドの一つですが、中でも一番好きなのなチキン・シャックです。というよりもVo,Gのスタン・ウェブが好きといった方が正しいかもしれません。日本では、ここ数年、初期作品がCD化されたり再評価なんでしょうか。私は「Imagination Lady」や本アルバムの頃が最も好きです。ただ「Imagination Lady」は昔から有名で、ハードなブルースロックの傑作としてブリティッシュロックファンでは知られた存在ですんで、今日は新鮮味を考えて本ライヴを紹介。これは当時ドイツと日本のみで発売されたLP(当時のタイトルはGoodbye Chicken Shack)をCD化したもの。実際はCD化に際して「Go Live!」というタイトルに変更されてますが、あえて昔のタイトルにしました。LP(ダブルジャケット)は持ってましたがCDで買いなおしましたね。この後バンドは解散しますが、また復活し良い作品をいくつか残してます。この人は、ヴォーカルが凄く魅力的で、その風貌やギタープレイも含めてカリスマ性があると思います(クラプトンより好きな部分も多いですね)。また時に非常に美しい曲を作るのも見逃せないところ。ギターもアグレッシヴな面、泣き共にいい感じ。ワウを多用するのも特徴ですね。「Imagination Lady」はドラムのバタバタ感が少し気になるのですが、本作はバンドサウンドとしても、まとまっているように思います(ドラムも良いです)。ハードロック、ブルース、バラード、ブギありのベスト的なライヴアルバムです。例によってスタンダード「Everyday I Have The Blues」からスタートするのですが、これが最高ですね。全体の構成、曲自体の抑揚がきいたアレンジも良くて、一気に聴かせてくれます。本CDは廃盤だと思いますが、現在は輸入盤「Poor Boy: In Concert 1973 & 1981」で聴くことができます(ジャケが全然ダメですが81年のライヴがついてます)。
2006.12.02
-
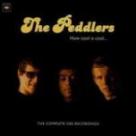
今日の一枚 (Groove Finderブログ No.042)
Peddlers。最高ですよね。このCDが出た時は、どれほど嬉しかったか。【No.42】 ・The Peddlers:How Cool Is Cool...Complete CBS Recordings (2002)モッドジャズ(?)トリオであるPeddlers。60年代から70年代初期にイギリスで活躍したグループ。これは、「Freewheeler」(1967)「Three In A Cell」(1968)「Birthday」(1969)というCBS時代のアルバムを収録し、かつシングルと未発表曲を加えた編集盤。現在までに、ロンドンフィルと共演した「Suite London」(入手可能)、「Live At The Pickwick!」と「Three For All」を2CDでリイシューしたもの(現在はたぶん廃盤)がありましたが、本CDがベストだと思います。全て輸入盤です。ジャズ・ブルース・ポップスなどの幅広い音楽を、オルガンを中心として、時にはストリングスを加えながら、ジャジーかつブルージーなサウンドに仕上げてます。この頃のPeddlersは、オルガンが凄く良い(音も演奏も)ですし、モッドらしいグルーヴ感が最も出ている時期。ヴォーカルも渋くてカッコいいです。日本での知名度がどの程度か分かりませんが、是非聴いていただきたいグループ。コンピにも取り上げられたりしてますが、まだまだ過小評価だと思います。特に「On A Clear Day You Can See Forever」、ちょっと前にカバーヒットとなった定番曲「Smile」、美しい「Prime Of My Life」などがオススメです。グルーヴィーな曲からバラードまで聴き所が多いアルバム(但し、ベストではないので全曲最高とはいえないですけど)。レアグルーヴファンの間では比較的有名ですが、ロック、ソウル、ブルースなど幅広い音楽ファンにも受け入れられる可能性のあるグループです。実際に聴いていただかないと、このグループの良さを表現するのは難しいですね。私は大好きです。ブックマークに関連ページへのリンクはってます。興味のある方は見て下さい(英語ですが)
2006.12.01
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- ラテンキューバン音楽
- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…
- (2025-10-16 12:29:53)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- 26周年💚&新作♪スエード調 巾着バ…
- (2025-11-03 00:00:11)
-







