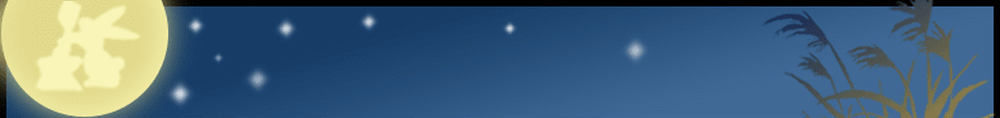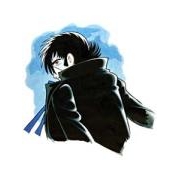PR
X
--< ふつうの歩道に…
 New!
いわどん0193さん
New!
いわどん0193さん
第145回目広報勉強会… ビューティラボさん
全国高段者大会 seikotsuinさん
ようこそ!ぶーたの… momoka1583さん
もぐらのランプ Mol… むぐむぐもぐらさん
 New!
いわどん0193さん
New!
いわどん0193さん第145回目広報勉強会… ビューティラボさん
全国高段者大会 seikotsuinさん
ようこそ!ぶーたの… momoka1583さん
もぐらのランプ Mol… むぐむぐもぐらさん
カテゴリ
カテゴリ未分類
(43)プロ受験生
(158)臥薪嘗胆
(79)追憶
(47)TO LUCKY
(130)幸せの掴み方
(18)かむ太郎の法則
(31)MY TOOL
(82)The Road to Doctor ~医師への道
(145)勉強
(158)センター試験/共通テスト
(105)作戦
(88)エネルギー源
(130)受験生心得
(1)春夏秋冬
(170)闘病と肉体改造・・・明日のために
(121)堅気(かたぎ)への道 ヽ(゚◇゚ )ノ
(247)本日の講義
(25)文学やら音楽やら美術やら・・・
(41)自称「ぐるめ」
(123)マンガ・漫画・・・アニメ?
(36)阪神タイガース
(22)お~まいがぁっ!
(57)犬と猫と花や木たち
(55)時代が俺様を求めてる・・・のか?
(12)最近読んだ本
(21)深夜のアルバイト先から・・・
(87)キリ番
(51)我、日々三省す。
(48)風景
(12)分岐点
(5)日本一周放浪記・・・勿論貧乏漫遊記(TへT)
(6)北の大地・・・貧乏漫遊記
(12)Debian GNU/Linux Sarge
(11)誘惑
(7)ミッション遂行
(24)はじめにお読み下さい・・・Read Me 携帯用
(0)事務長日記
(18)MISSION 4000
(3)保育士
(14)腹膜透析の記録
(31)キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ: 自称「ぐるめ」
「かむかむ軍団」
というタイトルを見つけました。
「かむかむ」シリーズが勢ぞろいです。
かむかむヨーグルト(ラブラブの甘さ)
かむかむグレープ (恋多き女の甘さ)
かむかむパイン (セカンドラブの甘酸っぱさ)
かむかむ梅 (大人の渋さと甘さ)
かむかむキウイ (忘れられない恋の甘酸っぱさ)
かむかむレモン (初恋の甘酸っぱさ)
コメントを見ただけで、胸躍ってしまう私です。
今日から12月です。
睦月、如月、弥生、卯月、皐月、水無月、
文月、葉月、長月、神無月、霜月
・・・と来て「師走」です。
3月と12月だけ「月」が無いんですねぇ。
<豆知識>
旧暦 3月 を弥生(やよい)と呼び、現在は新暦3月の別名としても用いる。
弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月
「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって
「やよひ」となったという説が有力。
他に、花月(かげつ)、嘉月(かげつ)、花見月 (はなみづき)、
夢見月(ゆめみつき)、桜月(さくらづき)、暮春(ぼしゅん)等の別名もある。
「師走」の由来には諸説ある。
一般には、 12月 は年末で皆忙しく、普段は走らない師匠さえも
趨走(すうそう)することから「師趨(しすう)」と呼び、
これが「師走(しはす)」になったとされている。
師は法師(お坊さん)であるとし、法師が各家で経を読むために
馳せ走る「師馳月(しはせつき)」であるとする説も一般的である。
また、「年果つる月(としはつるつき)」「為果つ月(しはつつき)」
が「しはす」となったもので、「師走」は宛字とする説もある。
「三冬月(みふゆつき)」などの別名もある。
旧暦 1月 を睦月(むつき)と呼び、現在では新暦1月の別名としても用いる。
睦月という名前の由来には諸説ある。最も有力なのは、
親族一同集って宴をする「睦び月(むつびつき)」の意である
とするものである。
他に、「元つ月(もとつつき)」「萌月(もゆつき)」
「生月(うむつき)」などの説がある。
旧暦 2月 を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)
と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。
「如月」は中国での二月の異称をそのまま使ったもので、
日本の「きさらぎ」という名称とは関係がない。
「きさらぎ」という名前の由来には諸説ある。
旧暦 4月 を卯月(うづき)と呼び、現在では新暦4月の別名としても用いる。
卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」
を略したものというのが定説となっている。
しかし、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花
と呼ぶのだとする説もある。「卯の花月」以外の説には、
十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、
稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」
「田植苗月(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」
であるとする説などがある。
他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。
旧暦 5月 を皐月(さつき)と呼び、現在では新暦5月の別名としても用いる。
「さつき」は、この月は田植をする月であることから
「早苗月(さなへつき)」と言っていたのが短かくなったものである。
また、「サ」という言葉自体に田植の意味があるので、「さつき」だけで
「田植の月」になるとする説もある。日本書紀などでは「五月」と書いて
「さつき」と読ませており、皐月と書くようになったのは後のことである。
また「皐月」は花の名前となっている。
また、「菖蒲月(あやめづき)」の別名もある。
旧暦 6月 を水無月(みなづき)と呼び、現在では新暦6月の別名としても用いる。
水無月の由来には諸説ある。
文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いが、
逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みづはりづき)」
「水月(みなづき)」であるとする説も有力である。
他に、田植という大仕事を仕終えた月「皆仕尽(みなしつき)」であるとする説、
水無月の「無」は「の」という意味の連体助詞「な」であり「水の月」
であるとする説などがある。
梅雨時の新暦6月の異称として用いられるようになってからは、
「梅雨で天の水がなくなる月」「田植で水が必要になる月」といった解釈も
行われるようになった。
旧暦 7月 を文月(ふみづき、ふづき)と呼び、
現在では新暦7月の別名としても用いる。
文月の由来は、7月7日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝す風習が
あるからというのが定説となっている。
しかし、七夕の行事は奈良時代に中国から伝わったもので、
元々日本にはないものである。
そこで、稲の穂が含む月であることから「含み月」「穂含み月」
の意であるとする説もある。
また、「秋初月(あきはづき)」、「七夜月(ななよづき)」の別名もある。
旧暦 8月 を葉月(はづき)と呼び、現在では新暦8月の別名としても用いる。
葉月の由来は諸説ある。木の葉が紅葉して落ちる月「葉落ち月」「葉月」
であるという説が有名である。
他には、稲の穂が張る「穂張り月(ほはりづき)」という説や、
雁が初めて来る「初来月(はつきづき)」という説、
南方からの台風が多く来る「南風月(はえづき)」という説などがある。
また、「月見月(つきみづき)」の別名もある。
旧暦 9月 を長月(ながつき)と呼び、現在では新暦9月の別名としても用いる。
長月の由来は、「夜長月(よながつき)」の略であるとする説が最も有力である。
他に、「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」
となったという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が略されたものという説がある。
また、「寝覚月(ねざめつき)」の別名もある。
旧暦 10月 を神無月(かんなづき、かみなしづき)と呼び、
現在では新暦10月の別名としても用いる。
「神無月」の語源として以下のような説があるが、
いずれにしても「神無」は宛字としている。
醸成月(かみなんづき): 新穀で新酒を醸す月
神嘗月(かんなめづき): 新嘗(にいなめ)の準備をする月
神な月(かみなづき):「神の月」の意
雷無月(かみなしづき):雷のない月
一般には、出雲の出雲大社に全国の神様が集まって一年の事を話し合うため、
出雲以外には神様が居なくなる月の意味と言われており
(実際にいなくなるのは大国主系の国津神だけであり、天孫系の神々などは
出雲に参集しないため居なくならない。あるいは全ての神が出雲に集るが
「留守神」だけは留守番として残る、など諸説ある)、
出雲では 神在月(かみありづき) と呼ばれる。
ただしこれは中世以降、出雲大社の御師が全国に広めた説であり、
「神無」の宛字から生まれた附会である。
旧暦 11月 を霜月(しもつき)と呼び、現在では新暦11月の別名としても用いる。
「霜月」は文字通り霜が降る月の意味である。
他に、「食物月(おしものづき)」の略であるとする説や、
「凋む月(しぼむつき)」「末つ月(すえつつき)」が訛ったものとする説もある。
また、「神楽月(かぐらづき)」、「子月(ねづき)」の別名もある。
10月の、出雲大社の話は、如何にも日本人らしい発想です。
実際に、出雲の方では、今でも「神在月(かみありづき)」
と言っているのでしょうか?
日本だけでなく、ローマ時代から、 「暦(こよみ)」の逸話 は
いろいろと面白いものが有ります。
「かむかむ」シリーズが勢ぞろいです。
かむかむヨーグルト(ラブラブの甘さ)
かむかむグレープ (恋多き女の甘さ)
かむかむパイン (セカンドラブの甘酸っぱさ)
かむかむ梅 (大人の渋さと甘さ)
かむかむキウイ (忘れられない恋の甘酸っぱさ)
かむかむレモン (初恋の甘酸っぱさ)
コメントを見ただけで、胸躍ってしまう私です。
今日から12月です。
睦月、如月、弥生、卯月、皐月、水無月、
文月、葉月、長月、神無月、霜月
・・・と来て「師走」です。
3月と12月だけ「月」が無いんですねぇ。
<豆知識>
旧暦 3月 を弥生(やよい)と呼び、現在は新暦3月の別名としても用いる。
弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月
「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって
「やよひ」となったという説が有力。
他に、花月(かげつ)、嘉月(かげつ)、花見月 (はなみづき)、
夢見月(ゆめみつき)、桜月(さくらづき)、暮春(ぼしゅん)等の別名もある。
「師走」の由来には諸説ある。
一般には、 12月 は年末で皆忙しく、普段は走らない師匠さえも
趨走(すうそう)することから「師趨(しすう)」と呼び、
これが「師走(しはす)」になったとされている。
師は法師(お坊さん)であるとし、法師が各家で経を読むために
馳せ走る「師馳月(しはせつき)」であるとする説も一般的である。
また、「年果つる月(としはつるつき)」「為果つ月(しはつつき)」
が「しはす」となったもので、「師走」は宛字とする説もある。
「三冬月(みふゆつき)」などの別名もある。
旧暦 1月 を睦月(むつき)と呼び、現在では新暦1月の別名としても用いる。
睦月という名前の由来には諸説ある。最も有力なのは、
親族一同集って宴をする「睦び月(むつびつき)」の意である
とするものである。
他に、「元つ月(もとつつき)」「萌月(もゆつき)」
「生月(うむつき)」などの説がある。
旧暦 2月 を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)
と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。
「如月」は中国での二月の異称をそのまま使ったもので、
日本の「きさらぎ」という名称とは関係がない。
「きさらぎ」という名前の由来には諸説ある。
旧暦 4月 を卯月(うづき)と呼び、現在では新暦4月の別名としても用いる。
卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」
を略したものというのが定説となっている。
しかし、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花
と呼ぶのだとする説もある。「卯の花月」以外の説には、
十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、
稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」
「田植苗月(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」
であるとする説などがある。
他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。
旧暦 5月 を皐月(さつき)と呼び、現在では新暦5月の別名としても用いる。
「さつき」は、この月は田植をする月であることから
「早苗月(さなへつき)」と言っていたのが短かくなったものである。
また、「サ」という言葉自体に田植の意味があるので、「さつき」だけで
「田植の月」になるとする説もある。日本書紀などでは「五月」と書いて
「さつき」と読ませており、皐月と書くようになったのは後のことである。
また「皐月」は花の名前となっている。
また、「菖蒲月(あやめづき)」の別名もある。
旧暦 6月 を水無月(みなづき)と呼び、現在では新暦6月の別名としても用いる。
水無月の由来には諸説ある。
文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いが、
逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みづはりづき)」
「水月(みなづき)」であるとする説も有力である。
他に、田植という大仕事を仕終えた月「皆仕尽(みなしつき)」であるとする説、
水無月の「無」は「の」という意味の連体助詞「な」であり「水の月」
であるとする説などがある。
梅雨時の新暦6月の異称として用いられるようになってからは、
「梅雨で天の水がなくなる月」「田植で水が必要になる月」といった解釈も
行われるようになった。
旧暦 7月 を文月(ふみづき、ふづき)と呼び、
現在では新暦7月の別名としても用いる。
文月の由来は、7月7日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風に曝す風習が
あるからというのが定説となっている。
しかし、七夕の行事は奈良時代に中国から伝わったもので、
元々日本にはないものである。
そこで、稲の穂が含む月であることから「含み月」「穂含み月」
の意であるとする説もある。
また、「秋初月(あきはづき)」、「七夜月(ななよづき)」の別名もある。
旧暦 8月 を葉月(はづき)と呼び、現在では新暦8月の別名としても用いる。
葉月の由来は諸説ある。木の葉が紅葉して落ちる月「葉落ち月」「葉月」
であるという説が有名である。
他には、稲の穂が張る「穂張り月(ほはりづき)」という説や、
雁が初めて来る「初来月(はつきづき)」という説、
南方からの台風が多く来る「南風月(はえづき)」という説などがある。
また、「月見月(つきみづき)」の別名もある。
旧暦 9月 を長月(ながつき)と呼び、現在では新暦9月の別名としても用いる。
長月の由来は、「夜長月(よながつき)」の略であるとする説が最も有力である。
他に、「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」
となったという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が略されたものという説がある。
また、「寝覚月(ねざめつき)」の別名もある。
旧暦 10月 を神無月(かんなづき、かみなしづき)と呼び、
現在では新暦10月の別名としても用いる。
「神無月」の語源として以下のような説があるが、
いずれにしても「神無」は宛字としている。
醸成月(かみなんづき): 新穀で新酒を醸す月
神嘗月(かんなめづき): 新嘗(にいなめ)の準備をする月
神な月(かみなづき):「神の月」の意
雷無月(かみなしづき):雷のない月
一般には、出雲の出雲大社に全国の神様が集まって一年の事を話し合うため、
出雲以外には神様が居なくなる月の意味と言われており
(実際にいなくなるのは大国主系の国津神だけであり、天孫系の神々などは
出雲に参集しないため居なくならない。あるいは全ての神が出雲に集るが
「留守神」だけは留守番として残る、など諸説ある)、
出雲では 神在月(かみありづき) と呼ばれる。
ただしこれは中世以降、出雲大社の御師が全国に広めた説であり、
「神無」の宛字から生まれた附会である。
旧暦 11月 を霜月(しもつき)と呼び、現在では新暦11月の別名としても用いる。
「霜月」は文字通り霜が降る月の意味である。
他に、「食物月(おしものづき)」の略であるとする説や、
「凋む月(しぼむつき)」「末つ月(すえつつき)」が訛ったものとする説もある。
また、「神楽月(かぐらづき)」、「子月(ねづき)」の別名もある。
10月の、出雲大社の話は、如何にも日本人らしい発想です。
実際に、出雲の方では、今でも「神在月(かみありづき)」
と言っているのでしょうか?
日本だけでなく、ローマ時代から、 「暦(こよみ)」の逸話 は
いろいろと面白いものが有ります。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年12月01日 13時05分27秒
[自称「ぐるめ」] カテゴリの最新記事
-
コーヒーも「マイ・ソムリエ」にお任せ 2018年07月01日
-
まんじゅう怖い 2018年04月19日
-
自称「美食家」です。 2017年11月05日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.