2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年06月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
友情とは
悩んでいるとき、困ったとき、疲れ果てたとき、寂しいとき友達っていいなあと思う。温かくなる、勇気が湧いてくる、知恵が生まれる、気づく、自信が湧いてくる。真の友情の見極め方はその人といるとどんどん自分が好きになってくると言う人また逢いたくなる怖れが無い逢っていると時間を忘れる互いを思いやっている相手中心のお付き合い感謝で一杯になる足をむけて眠れない人偽の友情はなんだか、話したあとの後味が悪い疲れる怖れが生まれるこのままじゃだめだと思うありのままの自分を出せない肩がこるその人といるときの自分が好きではない誰が正しいとか間違っているとかではなくて気が合うこと大切気が合うとエネルギーが高まる大切にしていることとどうでもいいことが同じそんな友達がみんな、みんな必要出会いにありがとう!今日ルーマニアに旅立つ女性がいた言葉は互いに理解できなかったけれど大切にしていることが同じだったから遠くに離れても心が近くにいてくれる気がする通じ合えるものがあった分かり合える笑顔があった笑うところが同じ泣くところが同じ黙るところが同じ耐える所が同じ最後に手紙をくれた誰かに頼んで日本語で書いてあった「まゆみの全てが好き、まゆみの愛を全身しみ込ませたから、まゆみの愛と一緒に旅立ちます。」ありがとう、ありがとう、ありがとう!私の愛を分ってくれた事が本当に嬉しかった(*^_^*)
2008.06.30
コメント(0)
-
一途に!
一途に、信念を抱いて貫いている人とても素敵ですね(^。^)迷いが無い動じない訳は自分を信じているから愛を信じているから「もしこうなったら・・・。」という思考は無く「たとえそうなったとしても・・・。」という思考が在る今日は一日、一途な人にばかり逢った。求めると叶う不思議な出会いの数々でした。笑いと感動と涙の一日と沢山の出会いにありがとう!私も一途に歩みます(^^)v
2008.06.29
コメント(0)
-
今日の感謝
傘を持たずに出かけたら雨になりました。でも用が終わって帰る頃には止んでいました。助かりました!保育園に帰ると職員全員が楽しそうに運動会の準備をしていました。仲良く楽しそうにしている姿には癒されました。保護者の方がそんな職員に差し入れを届けてくださいました。シュークリーム、プリン、ケーキなどなど。有難いですね!それらを職員達が嬉しそうに選んで決めては、「ありがとうございます!」とお礼を言いに来たときの笑顔がとても輝いていて可愛かったです。そして、その保護者が「長野さん、小学校創ってください!」と提案してくださいました。求めることよりも求められることの幸せを知ることができたこの人生に感謝です。茜がメールをくれた、とても上手な文で届いたので驚きました。夫と夕食を食べることができました。やっぱり家族と食べる食事は美味しいです!仁未が日に日に柔和になり女性らしく成長しています。花嫁姿が楽しみです!今日も力いっぱい生きたから、よくやった自分に感謝です!一つの山を乗り越えたら、また見えてくる景色が楽しみです。来年の今頃の自分は、今の自分をどう思い出すのかしら。どうか、明日も楽しく過ごすことができますように!温かな家族の他に、家族同様な仲間に囲まれて生きていることに、感謝いたします!両家の両親が明日も元気で豊かな老後を過ごしてくれますように!子ども達の輝く笑顔のために出来ることを教えて下さい!
2008.06.26
コメント(0)
-
低体温のお子さんが多いですね
最近気になることのひとつに、平熱が35,4度といった、低体温のお子さんが目立ちます。私が、30年前保育士になったころは、子ども達は36.5度から37.0度くらいの平熱でした。要するに、体が冷えているのです。昔から冷えは万病のもとといいます。この、低体温は本当に改善してあげたいものです。低体温が子ども達の健康や発育に与える影響について勉強してきました。いろんな環境の変化が関係しているとのこと。私達には容易に改善できない状況も沢山ありました。要するに、生きることに不可欠な水・空気・栄養の全てが昔とは違う状態になっているとのこと。また、脳も内臓でありもっともエネルギーを必要としている。環境の変化による、脳の栄養不足は「だるい、覚えがわるい、きれやすい」などの原因になる可能性は高いとのことでした。私達にでもすぐにできること。それは、食事の改善でしょうか。田や畑の土壌の変化、雨風の中の汚染などによる作物の栄養価の変化その上、野菜不足の食卓、欧米化しすぎた食事の内容もっと野菜を!もっと和食を!とかかれた記事も目に付きます。野菜をコンセントレーションで補給する提案もよく聞かれます。茜の通う小学校でも、野菜中心の食事をという勧めがあります。校長先生は、「児童の資質と食事の関係」について熱心に説明してくださいました。食事を改善すると本当にいろんなことが解決してくるのかもしれませんね。私が小学生のころ、コンビニエンスストアはありませんでした。お店はみな6:00ごろには閉まってしまいました。また道に自動販売機はありませんでした。携帯電話も宅配ピザもハンバーガーもありませんでした。今の子達は生まれたときから、便利なもの、欧米化された食卓の中で生きています。この子達が50歳になるころ、どんな体調でいきるのでしょう。少なくとも今より環境が悪くなっているとしたら。今50歳の私達より丈夫であって欲しいと願います。一人で出来ることの中で野菜を食べる!和食を選択する!添加物のあるものを避けることできっとスーパーに並ぶものも変わっていくことでしょう。子ども達の輝く未来のために今日本中の大人たちが、食卓を見直し子ども達の50年後のために買い物の選択をすることができますように!最近近くのスーパーでも「無農薬有機」と書かれたバナナや「国産有機大豆使用」と書かれた豆腐や納豆の方が棚を占めてきています。この地域の方々の賢い買い物の選択に感謝いたします。子ども達が50歳になるころ90歳近くなった私達に「本気で僕達の未来のために環境を守ってくれてありがとう!」といってもらえますように小さな事でいいので、出来ることを教えてください!
2008.06.26
コメント(2)
-
パパは家庭の経営者!
私はよく、普通の主婦がたった一人で保育園を立ち上げてどんどん大きくしていってる。生まれつきの経営のセンスがあるんですねと言われます。とんでもないです(^^ゞたったひとりではなく、夫がいてくれたから今があるんです。経営センスもほとんど夫や専門家の皆さんのお導きです。夫に経営について相談すると必ず言う名言があります。「願ってもいないことを口に出すんじゃない!」私が弱音を吐いて、保育園を締めようとしたときや新しい保育園の構想を諦めようとしたときいつもそういって励ましてくれました。どのご家庭でも、パパはその収支の経営者!パパに、相談してパパの意見を仰ぐことが日本の文化でした。パパが決裁権を持ち、ビジョンを開く。それを見て子ども達は、父を敬い父が慕う母を同じように大切にする。我が家もずっと共稼ぎでした。私の年収の方が高い時もありました。でも、夫はそんな額面の違いなどに遠慮しないでずっと家庭の決済を担ってくれたことに感謝しています。5000円以上のものを買うときは夫に相談する。初めてマンションを買うと夫が言ったときも「まだ早いんじゃない?もっと貯金してからがいいんじゃない?」と私は言いましたが夫は「俺は買う!」と言って買いました。お陰で後にそのマンションを売って、今の大きな家を手に入れることができました。茜の小学校を決めるときにも幾つも調べて幾つも見に行って、夫が決めました。そんな習慣の中で「パパが良いって言うんだから、きっと大丈夫だね!」という合言葉が私と娘二人の間にうまれました。私は離婚をして母子家庭で生きたので夫の有難さが誰よりもわかります。女性の脳の構造と男性の脳の構造の違いひしひしと感じて再婚するまでも大きなお話を決めるときには必ず信頼できる男性に相談をしていました。変わりにママの特権は子どもの心の小さな変化に気づくこと。これはパパより優れているんですよ(^^)v男と女本当の意味で平等であるために無理をしないで、互いの特技を活かす。女の子女の子らしく男の子は男の子らしく育むことも幸せな家族を創るために検討してみる価値はありそうですね(^。^)どうか、日本中の家族がパパを尊敬して大きな事の決定を委ねパパ中心に家族が安定した経済を保つことができますように!もしこの世に経済を委ねることはできないと言うほどの破壊的な考え方のパパがいたとしたらどうかそのパパが一日も早く悔い改め子ども達のために、健康で正しい考え方をもち家族を守っていく自分の使命に気づいてくれますように!またパパが、そのように成長するために家族全員が、「パパに聞く」というルールをもち敬う姿勢でパパを支えることが出来ますように!子ども達の輝く笑顔のために出来ることを教えてください。
2008.06.24
コメント(0)
-
茜の小学校の両親学級での学び
茜の小学校は土曜日も授業があります。礼拝のあと子ども達と保護者で分れて学びます。昨日の土曜日は、夫が両親学級に参加しました。テーマは「子ども達の体験不足」でした。いつからか、小学校で糸電話ややじろべいを使って学ばなくなっている。結果中学校になって音の振動やてこの原理を学んだときに知識と体験が重ならなくて理解が深まらないことがあるのではないかというお話だったそうです。それを夫に聞いて、夫婦で話し合いました。「そしたら、公園にも危ないという理由でシーソーがなくなってきているの。それもてこの原理や重力の比較に役立っていたのよね。」「回旋塔は、遠心力を身をもって学んでいたね。」そんなことを車の中で話し合いながら、家族4人は教会に到着牧師であり心理学教授であり自閉症やLDの研究者である先生と礼拝のあとお茶会「先生、子ども達の体験不足について夫婦で話していたんですよ。」「うん、僕は小学校のとき、コマを回して手のひらに乗せて回っている間走れるおにごっこをよくやっていたんだよ。大人になって判ったんだけど、その同時にいろんな神経を使う動きが脳の活性にとても役立っていたんだよ。もしぼくがその鬼ごっこを繰り返しやっていなかったら今頃教授にはなっていないし、牧師にもなれていないかもね。」そういって、牧師先生は、縄跳びを出してこられました。「僕が考えた、今の子どもたちにも出来る脳を活性化する飛び方。これを続けると子ども達の学習状況が変化すると思うんだよね」といってとても軽やかにとても複雑なまわし方で縄跳びを披露してくださいました。「??????、せ、先生みてもすごいんですけど、私には真似ができません・・。」夫が少し挑戦しました。「いやあ、まねできないですね。」「でもこれ、地域の子ども達ならすぐできそうね!教えたいなあ。」「こんど、運動神経が良い職員に教会にきてもらって覚えてもらおう!」「縄跳びを学ぶために教会に行かない。って誘うのもあなたらしいわね!」牧師さんは、おだやかに微笑んでおられました。私の教会は聖書に基いて、愛や思いやりについて学べる他にこんな研究結果のホットな情報もいただける本当にありがたいところです!どうか、先生が考えた難しい飛び方を誰かが把握して、地域の子ども達にはやらせてくれますように!簡単そうに見えるのですが、曲芸のように複雑ででも出来たらすごくリズミカルでたのしく、はやりそうです!その動きの中に遠心力、てこの原理などの算数にとって大切な要素が、体感で含まれています。
2008.06.22
コメント(0)
-
今日は母の70歳の誕生日!
育ててくれた母が70歳になりました。戦争に始まり、高度成長時代、バブル、バブル崩壊、情報化社会、なんと波乱万丈な70年だったことでしょう。兄弟4人とその連れ合いと子ども達が集まってささやかなお誕生日会ができました。何年かぶりに全員が集まりました。みんなそれぞれ、成長しそれぞれの課題に取り組んでいました。兄弟の話題は、老後の話年金は月額12万円ほどになりそうだ。退職金も年々減っている両親が90歳代になるころ自分達も70歳近いなどなど兄弟も年をとりました。「きっと大丈夫!」と考える前向きな考えと「もしこうなったら!」という構えのバランスが大切だねと行って話しは終わりました。年金が減り、消費税が上がり、医療費個人負担が増えたとしても豊かな老後を送ることが出来ますように!経済的な問題だけではなく健康で、孤独感がなく、友達が一杯で楽しい老後でありますように今から出来ることを教えてください!どんなことがあっても、夫の両親と自分の両親を支える力を与えてください!沢山の知恵と力を与えてください!
2008.06.21
コメント(2)
-
ゴシップの管理
陰口、悪口とうものは、組織を破壊していくと教えてくれた友人がいた。そこにいない人の話をすることを陰口をいいます。ゴシップはそこで解決できないことを話題にして語り合っていることだそうです。でも私達は、職員会議でそこにいない子ども達や保護者の方々の状況を相談して計画を検討していきます。ある職員がききました。「職員会議が、いつしかゴシップに変わるときってありそうで怖いですね」といいました。そこで私は職員会議にルールを創りました。「万が一、その壁の向こうにその方が立っておられたとしても、感謝してそっと帰っていかれるようなイメージを忘れないで話し合いましょう」会議の時間が遅いので、それぞれの方の参加していただいて相談することはできない。だとしたら、その人もそこにいるんだというイメージで言葉を選んで話し合っていくことができますように。茜の新しい学校の教育方針は「自分がして欲しいと思うことをまずあなたが相手にしてあげなさい」もし、自分が自分のいないところで誰かが私の話をするとしたらどんなことに配慮して、どんな風に話し合って欲しいかを考え実践することができますようにたとえ、それが事実だとしてもその人を否定する表現を決して使うことがないように考慮して言葉を発することができますように。そして、問題に焦点をあてず温かな人間関係に焦点をあてて正しさよりも愛を選んでいくことができますようにそのためにいつも焦らず、待つことを嫌がらず小さな配慮を積み重ねることによって信頼と心の豊かさを手に入れることが出来ますようにいつも導いていてください!
2008.06.20
コメント(0)
-
今日の感謝
・茜が、だんだん早起きに慣れてきてくれた。・夫が毎朝、茜親身に通学路を教えてくれている。・ひとみと二人で昼食の時間を持つことができた。・今日も風邪一つ引かず健康でいられた。・二人の人に大切なこと伝えきることができた。・夜遅くまで、保護者の方が私達職員の話を聴いてくださりアドバイスを沢山くださった。・新しいアルバイトさんが、「長野さんの毎日の笑顔と感謝の姿に感動しています」と言ってくださった。・来年入学する子のお母さんが、私の意見を熱心に聴いてくださった・誰かを許すことが、上手になってきた。・自分を許すこともできるようになってきた。・どちらでもいいと思えることが増えてきた。・今日も沢山の方々の笑顔を見ることができた。・今日も沢山の子ども達の可愛い仕草や反応を見ることができた。・深呼吸をしたら、ほっとした。・明日も、沢山の人に逢える・今日も家族がみんな元気で無事に眠った今このままで、沢山恵みがあることを忘れないでいつも感謝して、いつも喜んで、いつも祈りながらその上で更に良くなっていくために、よく考えて、いろんな人に相談をしてしっかり判断してどんな時にも、愛だけを選んでいくことが出来ますように。
2008.06.18
コメント(0)
-
長野さんあのね!
私は、保育園の園長をしています。私の保育園では、保護者の方とご一緒に食事をすることを大変大切に考えています。保育園の入り口に「先生あのね!」というカードがあって私だけではなくどの職員とでも、プライベートでランチや夕食をご一緒させていただくことができる申し込み用紙となっています。食事を共にすることは大変有意義です。本当にお一人お一人と愛所属が満たされて絆が深まっていきます。お話の内容は、子育てのことから、世間話まで様々です。時には私の方からお誘いするときもあります。今日は二人のお母様を私の自宅に招いて、学校から帰ってきた茜と4人で夕食を食べました。無条件に温かく、無条件に楽しい一時です。最高に幸せな瞬間です(*^_^*)どうか!沢山の保護者の方々とこれからもお食事を共にすることができお子さんを囲んで、無条件に温かな一時を過ごすことができますように!
2008.06.17
コメント(2)
-
セカンドステップとの連携
茜は、今日無事に新しい小学校から帰って来ました。お友達も出来たみたいでした。茜の新しい小学校には「道徳みたいな道徳ではない時間」というのがあるそうです。スクールカウンセラーの方による、セカンドステップという学びです。セカンドステップについて「セカンドステップ」プログラムは、米国ワシントン州にあるNPO法人Committee for Children (1978年設立)によって、「子どもが加害者にならないためのプログラム」として開発されました。「キレない子どもを育てよう」を合言葉に、子どもが幼児期に集団の中で社会的スキルを身につけ、さまざま場面で自分の感情を言葉で表現し、対人関係や問題を解決する能力と怒りや衝動をコントロールできるようレッスンが計画されています。アメリカでは数年間にわたり幾度もプログラム調査が行われ、以下の結果が理解されました。 「セカンドステップ」を学んだ子どもは、言動に攻撃性が減少し、より良い人間関係を持つようになった。 「セカンドステップ」を学んでいない子どもは、時がたつにつれて言動の攻撃性がさらに増加し、社会的行動にも進歩がみられなかった。 また、全米百数十の防止教育プログラムの中から、「もっとも効果的なプログラム」として米国教育省(日本では文部科学省にあたる)より表彰を受けています。 レッスンは、4歳から8歳を対象に1週間に1回約20分、計28回行います。ぬいぐるみやカードを使い、ある状況におかれた登場人物の気持ちをそれぞれ想像し、子ども達に自由に発言してもらい、みんなで話し合いながら、問題を解決していきます。米国の「セカンドステップ」は、未就学児向け・小学生低学年向け・高学年向け・中学生向け、及びその保護者向けのプログラムがあります。日本の「セカンドステップ」は、学年別ではなく、年齢別のコースに分類する方向で改訂を進めています。現在は、4歳から8歳を対象とした「セカンドステップコース1」のプログラムを提供しております。 第1章 相互の理解自分の気持ちを表現し、相手の気持ちに共感して、お互いに理解し合い、思いやりのある関係をつくること。第2章 問題の解決困難な状況に前向きに取り組み、問題を解決する力を養って、円滑な関係をつくること。第3章 怒りの扱い 怒りの感情を自覚し、自分でコントロールする力を養い、建設的に解決する関係をつくること。 これまで導入してきた選択理論心理学により人の行動と脳の働きを知った上で、さらにこのセカンドステッププログラムを学ぶことにより、保護者と子ども達が成長して各学校でも、先生方にストレスを与えないようになれば先生と子ども達との関係も今よりもっとよくなり安心して楽しい学校が実現することでしょう。そして、可能なら幼児教育にも取り入れることにより茜が望んだ「どんな状況でも動じないで学べる」自己コントロールスキルを親子で身につけて就学前を過ごせれば社会がどのように変化していっても、建設的に解決できる状況が実現するのではないかと思います。品川区では、全小学校に導入して、成果が見られているとの報告があったそうです。一筋の光に感謝いたします。どうか、このセカンドステップを学び今後の展開を共に検証してくださる仲間を沢山与えてください。
2008.06.16
コメント(2)
-
茜の初登校!
今日から、茜は朝5:30に起きて新しい小学校に登校しました。私は4:50に起きて朝食とお弁当を作りました。仕事で、茜と関わる時間が短いのであと3年毎朝お弁当をつくってやることができるのは本当に感謝です。「手塩にかけて育てる」という言葉を、思い出しながらお弁当をつくっていました。真っ白なセーラー服にチェックのプリーツスカートとそして帽子、黒のランドセル、紺の靴下黒の革靴。全て学校で決められていて例外がありません。筆箱も下敷きも鉛筆も決められています。自由の中で、茜は悩み苦しみ「誰のすることが正しいのか判らない」といって不登校になりました。児童の言動にも、教師の言動にも、保護者の言動にも、一貫性がなくそれぞれが思いのままに出来ることの最善を尽くしていました。でも、結果的に声高な人、パフォーマンスがいい人、争いさえも気にしない人の自由が優先され、おとなしい人、争いを望まない人が我慢する環境が出来上がっていたのです。自由が大好きな茜でしたが、それは本当の自由ではなく、不満を生み出し、不安と怖れが芽生え、怒り、悲しみ、脅し、互いを責め合う結果を生み出すことを学んだのです。そして茜は逃げ出したくなる衝動にかられたのでした。そして、色んな小学校を見学し、とうとう「互いの尊重のための規律」に出会いました。優しく上品に制服や文具の説明をされる先生に対して、素直に凛々しく「はい」と答えたのです。今茜は、自ら進んで規律のすがすがしさに浸っています明確なルールに従い、創り上げていく規律ある学校生活には、心の平安とそこにいる全ての人達の幸福と言う名の真の自由がありました。それは子ども達の言葉で表現すると「安心して楽しく学びたい」という願いの実現です。でも、これで良かったのと思っています。茜がもし、不登校を選ぶまでの経験がないままにこの学校に出会っていたとしたら。ここまで規律の大切さを受け入れることはなかったと思います。人生は、本当に良く出来たシナリオです。家庭においても、マナー、常識についてそのつどはっきり教えてあげることにより、マナーも知らないと社会に出てばかにされることもなく「本当の自信」をもち大人になっていくことが出来るのでしょう。但しそれを教える親や教師がまずそのことが出来ていることが前提だと思います。そしてやってはいけない事を教える方法がやってはいけない方法だったりしていることが良くあります。何が正しく、間違っているかがわからなくなったときには、とても良い判断基準があります。温かな人間関係を築けるなら、その方法は正しくて破壊的な方向に向かうのであれば、それは間違っているのです。この世を去る最後の一瞬まで前向きに、愛と感謝と希望をもって生きることができますように!そのために、互いに許しあい、助け合い、励ましあってルールを守っていくことが出来る沢山の仲間を与えてください。私達を、「あたりまえの事を特別熱心にできる人」とならせてください。やるべき事はやるそれは成果結果の問題ではなく温かな人間関係を築くことそれこそが、親となって「やるべき事」の最重要課題だと思います。日々の言葉の選択の延長線に虐めがあり虐待があり、離婚があり、自殺があり、戦争があることをマザーテレサが、語っていました。明日を悩み、将来を恐れるエネルギーがあるなら今日この瞬間瞬間自分の言動を愛(温かな人間関係)に向かうよう責任をもって言動を選択していくことができまように!どんな素晴らしいプランも成果も破壊的な人間関係の中では、決して幸福感を得るものにはならない、次の不安を手に入れるだけのことです。孤独と怖れの中、ストレスを選び続けなければならなくなるのです。幸福であれば、どんな逆境の中でも正しい判断をすることができ、仲間と力をあわせて乗り越えることも出来ます。今日も、私を含む福祉、教育で働く人たちが笑顔で、正しい言動を選び温かな人間関係の中、幸せに生きることが出来ますように!規律に返り、職員がまず児童にしてはならないことを避け、規律に従うことのほうが遥かに自由なのだということを肝に命じて日々大切な子ども達に関わることが出来ますように。
2008.06.16
コメント(2)
-
躾の原則
親になって、一番悩むことが「どこまで躾けて、どこまで許して、どこまで可愛がったら良いかわからない。」というところでしょうか。私も日々悩むところです。ただ、今考えているのは「社会に出たときにどんな大人であって欲しいか。」とご夫婦で話し合い明確にしておくことは有意義です。そして「我が家の教育方針」というものを、掲げておくのも動じないために効果的かと思います。そして、「こうなって欲しい」が出来るだけ具体的であることどんな体格でどんな言葉を使いどんな知識をもちどのように暮らしどんな家庭を築いてほしいかそしてそのように、両親が生きることが不可欠だということをしっていることも大切ですね親や教師が暴言を吐きながら、「礼儀正しく挨拶しなさい」といっても言うことを聞くのは小学生までが限界です。だんだん、尊敬の定義が変わっていくので言行一致は、とても大切なことですね。私も日々反省そして今日からここから子どもを授かったら、子どもと共に成長する子どもと共に学び、教え、そして子どもにも教えられる子育てに取り組むことが出来たことに感謝いたします。どうか、私がまず!娘のあるべき姿を生きることが出来ますように。そして言い訳しないで、自分の至らない所を良くしていくことを楽しむことができますように。沢山の子育て中のお父様、お母様たちと共に励ましあい支えあって、成長することが出来る環境をつくるために沢山の知恵と勇気を与えてください。
2008.06.12
コメント(0)
-
長野家のニュースです!
茜が横浜三育小学校の編入試験に合格いたしました。今週一杯で公立小学校を転校いたします。思い出一杯の公立とインターナショナルスクールに感謝のご挨拶に行って来週から新しい小学校に登下校いたします。学級崩壊、虐め、友達の転校、不登校、インターナショナルとの出会い教育委員会との相談、本意が学校に伝わらない日々、親父の会の発足長い長い一年でした。でもその出来事があったお陰で、今までにないほどに家族が話し合い、支えあい、意見を交換しあうことができ家族の絆が深まりました。茜の制服姿に涙が溢れます。人生には暗闇の日々があるからこそ、光が見える。悲しみがあるからこそ感謝がわかる。多くの方々が茜の不登校状態に対して、沢山の情報提供をしてくださったことに感謝です。また最後まで家族が争わず、愛を選び続けることができたことにも感謝です。知、徳、体3つを育むから3育これから初心に帰って入学し親子で学んでいくことができますように。保護者会もほとんど夫婦参加とのことお父さんのご協力が大きいとのこと保護者の方々に出会えることもとても楽しみです。これからの日本の教育にとって何が一番大切なのかをしっかりと家族で学ぶことが出来ますように。三育の卒業生であり、教員を務めた校長先生。自然体で温厚でありながら、強い情熱を抱き、豊かな知識、技術そして信念をもって子どもたちへの愛を語る校長先生を尊敬いたします。学んだことを地域に持ち帰り、沢山の情報提供ができますように!教育委員会に対して、私が本当に伝えたかったことが伝わる自分になるためにもっと学んでもっと成長します。そして、改めてもう一度教育委員会にお話しに行きます。茜は、「学校にも先生にも変わって欲しいとはおもっていない。どんな状況の中でも、動じないで学ぶことが出来る自分に成長したい。」と作文に書いていました。
2008.06.10
コメント(11)
-
就学前に子ども達に与えたいもの
最近、就学前に何を身につけておけば良いのかということを考えます。今日は、そのことについて夫とマネージャーと夜更けまで語り合いました。そして、私達が子ども達に就学までに与えたいものは、「ゆるがない家族愛」だというところで三人は一致いたしました。家族愛さえあれば、どんなことでも乗り越えていける。私達はそう考えています。その「家族愛」を育むことこそが、私達の目的だね!と話し合いました。子ども達の輝く笑顔のために家族愛を育むことが出来る人として成長させてください。家庭は子ども達のベースキャンプ!安全地帯!願わくば家族愛に満ち溢れた家族同士が家族ぐるみでお付き合いができますように。末永く、絆を深めて助け合い、励ましあって支えあう地域愛を育む拠点となることができますように!
2008.06.09
コメント(0)
-
人生に理念や目的がありますか?
ある、カウンセラーの方が行き詰まって、師に相談をしたところこんな答えが帰って来たそうです。「それは、貴方の人生哲学で判断してください。」人生哲学で判断する・・・。人と関わる仕事を持つと、必ず行き詰まるときが来ます。「どちらの言うことが正しいの?私はどちらと共に歩めばいいの?」こちらを立てればあちらが立たずといった出来事に出会います。そんな時自分独自の人生理念、人生哲学が必要であるというお話でした。私の人生理念は、単語でいうと「愛、感謝、誠実、希望、感動」ビジョンでいうと「子ども達が輝く笑顔で安心して成長できる社会」人生の目的(意図)は「温かで安らぐ家庭を気づき、与えられた幼児教育の賜物を活かし地域の子ども達の幸せのために貢献すること」行き詰まったら、ここに帰る「私は何を求めているのだろう、私が本当に求めているものはなんなのだろう。今していることや考えていることは、求めていることを得るために本当に効果的だろうか?」私が今求めているものは「みーんな仲良し!」な状況です。みーんな仲良しに繋がらない言動や考えは、私の人生理念、哲学に反するので疲れてきます。でも、本当に仲良くあるためには私も職員も保護者も児童達も互いに対等であることが不可欠です。互いに尊敬し合い、許しあい助け合い励ましあっている状況が「仲良し」という状況です。家族も同じです。全員が対等であることが大切です。どうか、私と私が関わる全ての方々とがいつも対等な関係になるよう私自身が、誰に対しても尊敬の念をもって接することができますように。そのために誰よりも自分自身に対して、いつも尊敬の念を抱き日々自信をもって判断、選択し結果に責任を持つ人でありますように!
2008.06.08
コメント(0)
-
リーダーシップに必要なこと
リーダーシップについて、書いてある本があった。有能なリーダーにとって必要なこと1、ビジョン(どうなりたいかが明確)2、高いコミュニケーションスキル(どんな人とも調和できる)3、人を動かす、または巻き込む力4、実力5、イエスはイエス、ノーはノーと言える高潔は人格6、万人のしもべとなる態度7、深い愛情を持ち備えている子ども達の中にリーダーシップを取りたいと考える子が年々減っているとの事。きっと、憧れのリーダーと身近に出会う機会が少ないのだと思います。この日本には、素晴らしいリーダーが沢山います。スポーツの世界にも、芸術の世界にも、経済界にも。私達保育に携わる者たちもどうか、子ども達にとって、「かっこいい先生」であることが出来ますように。私もこの年からでも、自分の欠点を一つずつ改善していくことが出来ますように!欠点はほとんど習慣です。悪い習慣は、トレーニングで改善できます。考え方も習慣です。より良い考え方を選んでいけるトレーニングが必要です。私も一歩ずつでいいから、良きリーダーに近づいていくことができますように!一つずつ、期間を決めて、計画通りにトレーニングしています。
2008.06.07
コメント(0)
-
お手伝いの大切さ
子どもに家事のお手伝いをしてもらうことは、本当に大切だそうです。3歳くらいからお願いすると良いそうです。「自分も家族の一員として機能している!」という実感が、いろんな事に取り組む意欲と自信に繋がるそうです。自信はやはり、根気強く練習した事柄に対して、持つことができるそうです。子ども達が沢山お手伝いして、家族にありがとうと言ってもらい自信一杯で大きくなって行けますように!日本中のパパママ、お手伝いを教えてあげてくれますように!
2008.06.05
コメント(0)
-
保育園園長という仕事
園長の仕事に就いて、早や10年目になります。園長の仕事とは、と考えます。1、園全体の総監督2、利用者の意向と職員の意向の調整3、財源の確保、経営全般4、採用、職員育成5、他機関との連携のための交流6、園の事業計画作成と実践のための計画作り7、時代の流れによって変化していく児童や保護者のニーズを把握する8、社会状況を把握し合法に運営するための環境整備9、職員のモチベーションを保つための援助10、児童を取り巻く、家庭や地域の環境の改善のための取り組みまだまだあります。でも、一番大切なことは職員と保護者にとって安心してどんなことでも相談できる人格を保つための自己の研鑽です。常に学び、成長し続けていること多くの人たちに、夢と希望という光を与えることができるよう自分自身が、いつも夢と希望に満ち溢れ有言実行、誠実、寛容、堅実であること。自分の理想の園長像が100点だとした今は、まだまだ20点というところでしょうか。憧れの園長先生や校長先生がおられます。「あんな人になりたい!」50歳になるというのに、そんな憧れをもち生きていられることに感謝です。どうか、出来るだけ多くの方々に夢と希望を与えることができる園長に成長できますように。そして、後継者を沢山育み、若い職員に全てを委ねていつもやさしく、おだやかに、にこやかに見守って職員たちの良いところを誰よりも沢山見出し職員たちに感謝して賞賛し続けることができますように。保護者と子ども達にとっては、「園長先生に出会って、自分のことが大好きになった」いつか、思い出して語り合ってもらえますように。沢山の知恵と勇気と愛を与えてください。
2008.06.04
コメント(0)
-
素晴らしい小学校
今日の午前中、再度横浜三育小学校に行ってきました。今日は、職員室で1時間ほど校長先生をお待ちすることになりました。その間に2年生くらいから6年生くらいの生徒さんが4回ほど職員室に来られました。どの生徒さんも「失礼いたします!」と元気に明るくかつ美しい敬語で挨拶をされました。「○○先生おられますか?」「○○先生はおられませんが、どんな御用ですか?」と先生の対応する言葉も表情も自然体でとても美しいのです。「○○を取りに来たのですが」「それでは、そのことを先生にお伝えしおきましょう。」「はい、ありがとうございます。」ニコニコと無邪気な表情なのに言葉がとても綺麗だったのが印象的でした。幼児期、小学校時期に身につけておかなければならないことそれは、知識のほかに、礼儀作法、労作(働いて共に過ごす人の役に立つこと)忍耐、体力などであることを実践して、見事な結果を出しておられました。私自身がこの小学校で学びなおしたいと思いました。正しい敬語、美しい言葉、挨拶、そして掃除、洗濯、料理を喜んで手伝える子それは、女の子なら素晴らしいお母さんへの道であり、男の子ならかっこいいお父さんへの道また、結婚しなかったとしても社会で多くの人の役に立つ人格への道です。今日の学びが、私の人生に活かされますように!
2008.06.03
コメント(0)
-
アフリカフェアー
今日は、知り合いが出展しているということで。横浜パシフィコで開催されていた「アフリカフェアー」に行ってきました。すごいエネルギーを感じました。ステージも熱く、歌演奏踊り全て、元気を沢山もらいました。文字が読めない子4人に一人、学校に行けない子3人に一人、7歳までに病気で死んでしまう子もまだまだ沢山いるという国もありました。この豊かな日本で、何かに悩んだりくよくよしていたら恥ずかしいですね。クラッカー4枚もらうために家族で2時間歩いて並ぶひともいるそうです。自由に使える水が沢山あって、食料に困ることなく、病気してもすぐに治療でき、暑さ寒さもエアコンがまもってくれる。そんな当たり前のことが、とても贅沢なことなのだと思いました。我これに足るるを知る也何がどうでも、感謝です。生きることに精一杯なら、悩むことも少ないですね。いろんな事考えて、悩むことが出来るほど自分の置かれている環境が豊かなのでしょう。明日から一週間小さなことにも感謝して、毎日を過ごすことが出来ますように。子ども達と職員たちの温かな笑顔に囲まれて、毎日過ごせる自分の仕事に心から感謝いたします。
2008.06.01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-21 16:48:55)
-
-
-

- 政治について
- 【速報】高市首相が記者団にコメント…
- (2025-11-22 03:40:16)
-
-
-
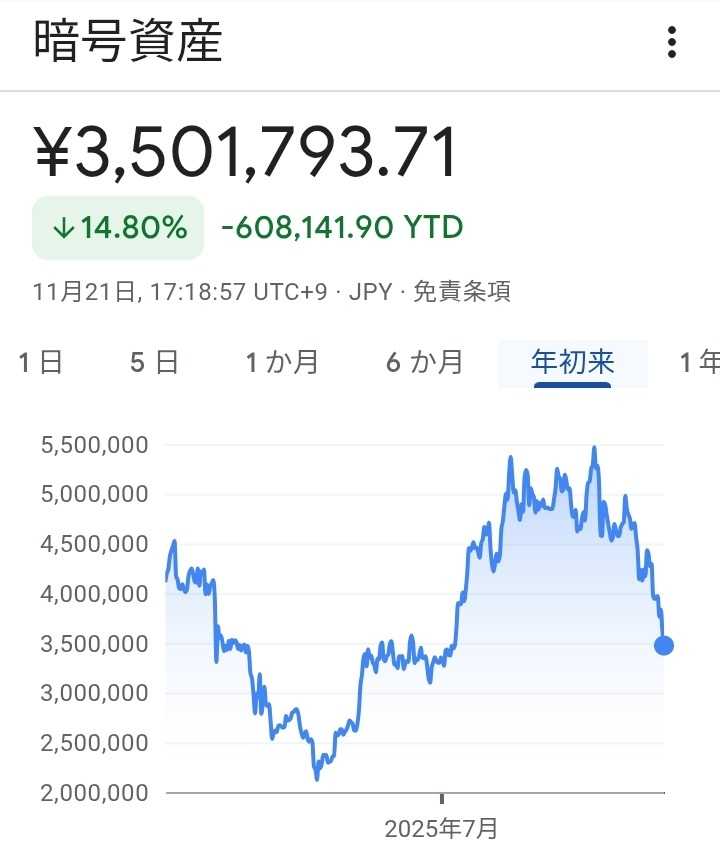
- 株式投資日記
- 久しぶりに日本株資産が増加したが、…
- (2025-11-21 19:50:51)
-







