ボストン大学の研究者チームが致死率80%というSARS-CoV-2(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2、いわゆるSARS2)の変異種を作り上げた という。SARS2は2002年から03年にかけて南部中国に出現したSARS(いわゆるSARS1)と同じで、人工的に作られたと考える人は少なくない。ありふれたコロナウイルスから致死性の高い病原体が作られたというわけで、倫理的にどうかはともかく、今回のようなことが行われても不思議ではない。その一方、SARS2の幻影も作り上げたということである。
例えば、 医学雑誌「ランセット」のCOVID-19担当委員長を務めたジェフリー・サックスは5月19日、SARS-CoV-2は人工的に作られたと指摘 し、独立した透明性のある調査を行う必要性を訴えている。 6月にはスペインのシンクタンク、GATEセンターで彼はアメリカの研究施設から病原体が漏れ出た可能性を指摘 した。
2014年2月にバラク・オバマ政権はウクライナでネオ・ナチを使い、クーデターを仕掛けてビクトル・ヤヌコビッチ政権を倒した。アメリカを支配する私的権力は昔から自分たちの利権にとって邪魔な政権や体制を破壊してきたので、珍しいことではない。
クーデターを拒否する国民も少なくなかったが、特にヤヌコビッチの支持基盤だった東部や南部では反発が強く、ドンバス(ドネツクやルガンスク)では内乱になった。その反クーデター派を潰すためにアメリカ/NATOは兵器を供給、戦闘員を訓練、自国の特殊部隊員や傭兵会社の戦闘員を送り込んできた。そして2月24日のロシア軍による軍事作戦につながるわけだ。
ロシア軍はまずミサイルや航空兵力を利用してウクライナの軍事施設や生物化学兵器の研究開発施設を破壊、重要文書を回収している。3月7日にはロシア軍の核生物化学防護部隊を率いるイゴール・キリロフ中将がウクライナの研究施設で回収した文書について発表、ウクライナにはアメリカのDTRA(国防脅威削減局)にコントロールされた研究施設が30カ所あると発表した。
そうした研究施設があることは知られていたが、ロシア国防省によると、ウクライナの研究施設で鳥、コウモリ、爬虫類の病原体を扱う予定があり、ロシアやウクライナを含む地域を移動する鳥を利用して病原体を広める研究もしていたという。
3月8日にはアメリカの上院外交委員会で ビクトリア・ヌランド国務次官 が宣誓の上で証言している。その中でマルコ・ルビオ議員はウクライナにおける生物化学兵器について質問、ヌランドはアメリカの研究施設には兵器になるほど危険な病原体の資料やサンプルが存在、それがロシア側へ渡ることを懸念すると述べた。
こうした研究では遺伝子操作の技術が使われるが、世界的な大手化学会社である バイエルで重役を務めるステファン・ウールレヒは2021年10月、「WHS(世界健康サミット)」の集まりでmRNA技術を使って製造する「ワクチン」は「遺伝子治療」の薬だと語っている 。要するに遺伝子操作を行う「新薬」だということだ。
この新薬に「ワクチン」というタグをつけた理由のひとつは、安全性を確認するために定められた正規の手順を経ずに緊急使用を認めさせるためだが、別の理由もあるようだ。ウールレヒによると、遺伝子操作だと告げると95%の人が拒絶するというのだ。当然だが、タグを取り替えるだけで大多数の人は未知の新薬を体に入れた。
mRNAを利用した「COVID-19ワクチン」を製造している会社はBioNTech/ファイザーとモデルナだが、モデルナの説明を読むと、彼らはmRNA技術を使い、コンピュータのオペレーティング・システムと同じようなプラットフォームを作るつもりだ。
同社の最高医療責任者のタル・ザクスが2017年12月にで行った講演 の中で、癌を治療するために遺伝子を書き換える技術について説明したが、これがmRNA技術。つまり遺伝子操作の技術である。
ジョー・バイデン大統領は今年9月12日、バイオ技術の導入を促進するための行政命令に署名した。それを正当化する理由として「COVID-19パンデミック」でバイオ技術が使われたことが挙げられているのだが、この経験は人類にとってバイオ技術は危険だということを再確認させただけである。そうした危険な遺伝子操作をWHO(世界保健機関)は強行するべきだとする報告書を2021年に出している。
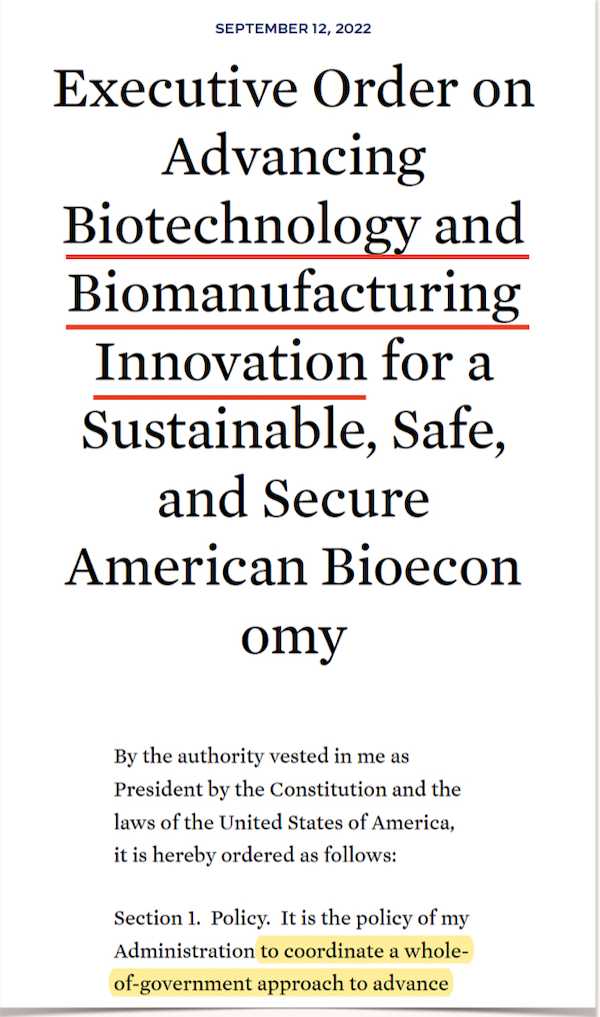

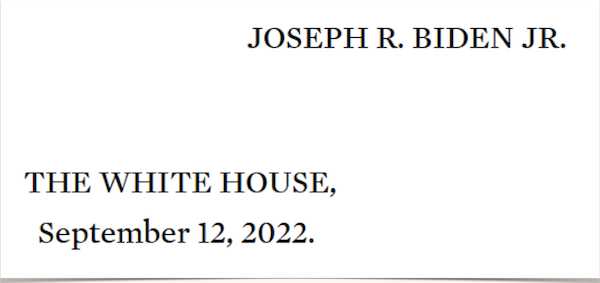
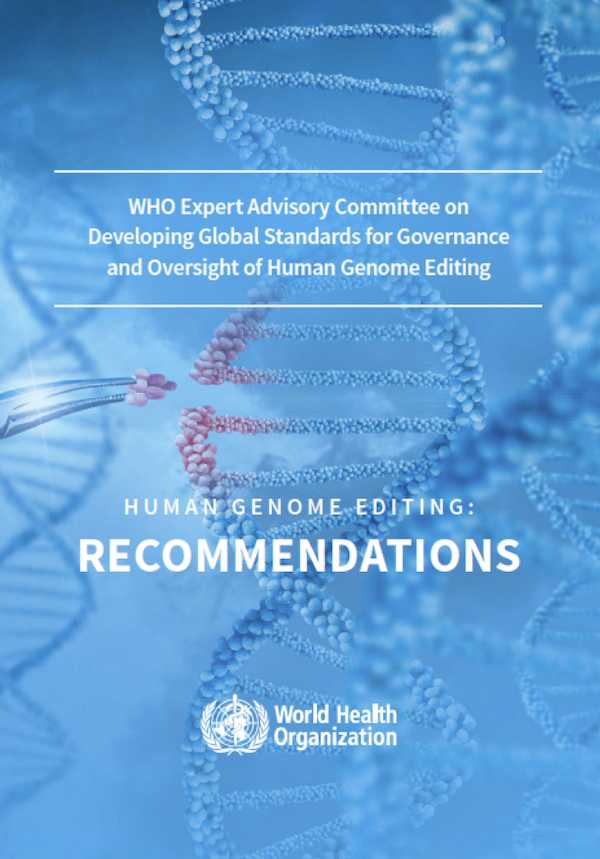
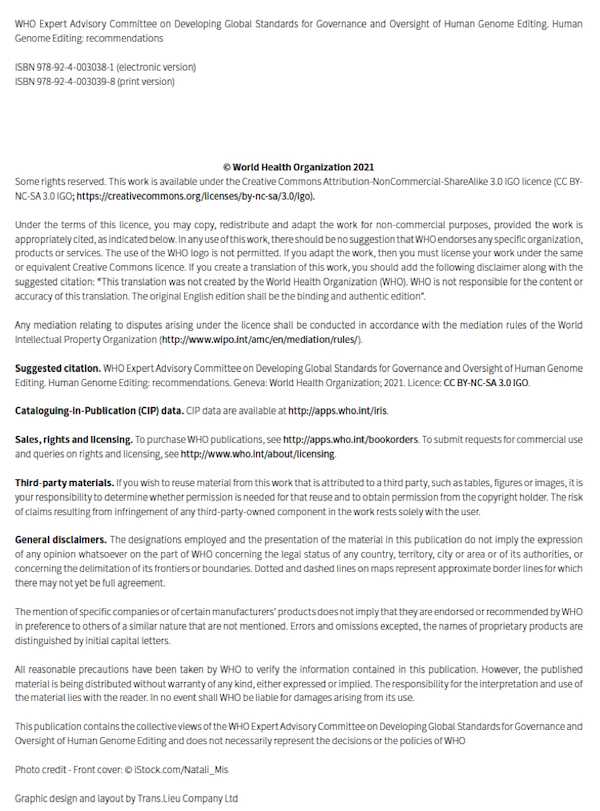

本ブログでは繰り返し書いてきたが、ナチスが政策に取り入れた優生学は19世紀にイギリスで始まり、支配層の中に広まった。その思想はアメリカへ伝わって政策に取り入れられ、それに魅了されたのがアドルフ・ヒトラーであり、ナチズムと結びつく。優生学の祖はチャールズ・ダーウィンの従兄弟であるフランシス・ゴルトンだとされている。アメリカで優生学を支えたのはカーネギー財団、ロックフェラー財団、そしてマリー・ハリマンらで、優生学に基づく法律も作られた。
19世紀のイギリスを動かしていた大物として、セシル・ローズ、ネイサン・ロスチャイルド、ウィリアム・ステッド、レジナルド・ブレット(エシャー卿)、アルフレッド・ミルナー(ミルナー卿)らが知られている。
前にも書いたことだが、その中でも特に重要な役割を果たしたといえる人物がローズ。彼はロスチャイルドをスポンサーとし、南部アフリカ侵略で巨万の富を築いた人物だが、1877年6月にフリーメーソンへ入会、その直後に書いた『信仰告白』は興味深い。そこにイギリス支配層の思想が反映されている。
ローズはアングロ・サクソンを最も優秀な人種だと位置づけ、その居住地(支配地)が広がれば広がるほど人類にとって良いのだと主張している。領土を拡大して大英帝国を繁栄させることは自分たちの義務だというのだ。アメリカの先住民、いわゆる「アメリカ・インディアン」を虐殺して土地や資源を奪うことを彼らは当然だと考えていたが、優生学はそれを正当化する根拠になっている。
先住民の虐殺は徹底したもので、1864年には講和を結ぶためにコロラドのフォート・リオンへ向かう途中のシャイエン族約700名がサンド・クリークで約750名のアメリカ兵に襲撃され、老若男女を問わず、全体の6割から7割が虐殺されている。この出来事に基づいて「ソルジャー・ブルー」というタイトルの映画が1969年に制作されている。
1890年12月にはサウスダコタのウンデッド・ニー・クリークにいたスー族をアメリカの騎兵隊が襲撃し、150名から300名が虐殺された。虐殺を正当化するため、ある種の人びとは先住の民は悪魔の創造物だと主張、ある種の人びとは劣等な種だと主張している。
1904年にアメリカのセントルイスでオリンピックが開催されているが、その際、並行して「万国博覧会」も開かれた。1903年までアメリカの民族学局に所属していたウィリアム・マギーは「特別オリンピック」を企画、人種の序列を示している。トップは北ヨーロッパの人びとで、最下位はアメリカ・インディアンだ。アパッチ族のジェロにもが「展示」されたのもその時である。(Alfred W. McCoy, “To Govern The Globe,” Haymarket Books, 2021)
優生学の背後には自分たちが神に選ばれた人間だという考えがあるのだろう。そのカルト的な考え方を正当化する「科学的」な根拠が優生学だ。優生学の信奉者は「優れた種」をアングロ・サクソンに限定せず、ドイツ系、北方系人種が優秀だと主張、劣等な種を「淘汰」するべきだと考える。ウクライナのネオ・ナチもその神話を信奉している。
優生学的な信仰は「劣等な種」を家畜化する、あるいは絶滅させるという考えだけでなく、遺伝子操作を利用して「超人」を作り出すという考え方につながる。








