全53件 (53件中 1-50件目)
-

最近何も書いていないなあ
トリプルA価格:1,785円(税込、送料別)☆ これは楽天経由で買っていないのだけど,まあそこそこ面白かった。初出が東京スポーツだったのは驚いたが,艶話はほかの人が書くから東スポに乗せても一切手抜きしないところが彼らしくて良い。☆ ある意味,ここ25年程度の金融クロニクル的な話ではある。プロローグも元ネタはあるのだが(ちゃんと原著の出典もある)このシーンを描く方法としてはこれで良いのだろうなと思う。☆ これは作家の性格なのかもしれないが,彼の作品の中には「嫌な奴」はたくさん出てくるが徹頭徹尾悪人というキャラクターがいない。清水一行や高杉良らとの差はそこにあることは以前から指摘してきたが,反面で登場人物の性格の掘り下げが甘くなるきらいもある。真の悪人を描き切れない限り,黒木の作品はいつか飽きられてしまうのではないかと懸念している。トリプルA価格:1,785円(税込、送料別)
Jul 3, 2010
-
GW中まとめてアップ予定
☆ かなり貯まっていますのでまとめて書きます。
Apr 25, 2010
-
ギフト・パック(DVD付)シンプル・マインズ [DVD付CD]
投稿日:2010年02月11日 ショップ: Felista=みんなのレビュー投稿内容= ☆ よく知られた話だが「Don't You」のオファーは,最初ブライアン・フェリーのところに来ていた。彼が断り,ジム・カーのところに来たらこれが全米No.1になった。フェリーは後日この事を訊かれて「ジム・カーは良くやったと思う」とほめてるのか皮肉を言ってるのか分からないようなコメントを残している。もっとも『サンズ・アンド・ファッシネイション』あたりからシンプル・マインズを聴いていたファンなら,彼等のオリジナルの音で上手く仕上げたこの曲のヒットは自慢しても良いだろう。☆ シンプル・マインズがマガジンの影響下にあったこともよく知られた話で,当初は数あるエレクトロ・ポップ・バンドの一つに過ぎなかった。このデジパンク盤ならDisc1の終わりの方に入っているZoomレーベル時代の曲を聴くと分かる。皮肉なことにジョン・マクガフの脱退をきっかけにマガジンが空中分解するかのように解散した直後,ヴァージン・レーベルに迎えられたシンプル・マインズは,代表作となる『New Gold Dream』『Sparkle In The Rain』『Once Upon A Time』と進むにつれ,どんどん骨太のバンドに成長していった。その初期のリリカルなスタイルからの変化の軌跡は,U2と並べ評しても悪くない。ただU2が『ジョシュア・ツリー』の世界的ヒットでワールドワイドなバンドに成長していったのとは対照的にシンプル・マインズは英国を代表するバンドへ成長していった。比喩として的確ではないことを覚悟して言えばストーンズとキンクスのような差があると思う。☆ 実はこの盤。CDのみの洋盤を入手したばかりであったが,限定盤でCD+DVDの国内盤があると知り,入手し直したもの。洋盤ではバラバラに入手しなければならないCDとDVDがパックされていること自体,入門編としては最適と思う(ただし紙製のデジパックはパッケージのせいで隅っこがよれてしまっていて(これはお店の責任ではなくメーカーの問題)その点だけが残念だ。=以下追加=☆『Sons And Fascination』のLP(初版当時)のレビュアーは「The American」をマガジンの「A Song From Under The Floorboards」そっくりだと書いていた。そっくりとは思わないが,シンプル・マインズのマイケル・マクニール(キーボード)は,確かにマガジンのデイブ・フォーミュラを意識していたかもしれない。ただ『New Gold Dream』はマガジン(特に『Real Life』)やニューロマンティックスに至る前のエレクトロ・ポップ(例えばヒューマン・リーグなら『Travelogue』)の色彩が強い。☆ 「Someday,Somewhere in Summertime」は,当時サントリーのCMで使われたため,このバンドの曲ではかなり認知度の高い作品(サントリーとホンダは本当に選曲センスが良く,ジョン・フォックスやピッグ・バッグなどCMが無ければもっと知られていなかったと思う)。日本選曲でもないこのベスト盤に選曲されたのはちょっと意外(ただ日本盤のレビューの記録以上に全英でヒットした気がするのだが)。☆ 「I Travel」はまるでジョルジオ・モロダーといっては何だが(笑)ドイツ系のエレクトロ・ポップの系譜の音に感じた。
Feb 13, 2010
-

1Q84 (8)
☆ 用賀から渋谷まで混んでいなければあっという間であるが,この時代でも渋滞は日常茶飯事だった(駒形ほどじゃないが)。そこから少しずつ現実が離れていくのだが,この現実から離れていく感覚の違いが,時間経過の違いとなって現れているのかもしれない。村上龍はパラレル・ワールドを題材に『5分後の世界』を書いたが,第1章の経過の中で「その5分間」が追いついていくような感覚がある。ヤナーチェックは,その5分間を呼び寄せる「カタリスト(触媒)」の役割であるかのようだ。【古本】五分後の世界/村上龍1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 28, 2009
-
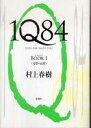
1Q84 (7)
☆ 第1章は青豆という主人公の一人が「仕事」のため,タクシーに乗って首都高速4号線の渋滞に巻き込まれるところから始まっている。幾つかのそそっかしい書評や紹介記事には主人公の職業がこれだと書いているものがあるが違う。ここで事情は明かされてはいないが,あくまでも表面の職業は違うし,そうでなければ片手落ちというものだ。☆ 少し前に絡んで見せたように(笑)その時間にそういうレコード(もしくはライブ録音)を紹介するような番組は,森田美由紀氏がアルバイトをしていた放送局を含む全国のあらゆるFM放送(AM放送は既に前提から排除されている)にはなかった。当たり前である。それが一番最初の「企て」であるのだから。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 27, 2009
-
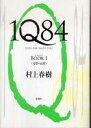
1Q84 (6)
☆ 最初の数章を読んでいて気付くのは,二人の登場人物が並行的に描かれているのに,互いの時間の流れ方に位相差があるということだ。作家にとって「二つの場面の設定が交互に出て来る手法は同じ新潮社から出した『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』で一度使っている。それとの差異がここに見られる。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 26, 2009
-
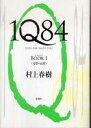
1Q84 (5)
☆ この段階で拘る話でもないが,各章のタイトルは最初ばらばらに提示され,話が進行していくにつれて,関係性を持ち始めるように思える。勿論,話を読む前に不用意に各章のタイトルだけを読んではならない。それは作者の用意していなかった「企て」に自分から引っ掛かるようなものだから。☆ 最初にFM番組のことをあれこれ穿(ほじ)っているのは,その空間が既に作者の「企て」であるのかどうか一読目では解らなかったからだ。ただ,その空間が始まる前から既に物語は始まっており(それは読み進むうちに倒叙される),読み手は最初のページから既に時間と空間を複数持っていることになる(無意識でしかないが)。これは物語であれば当然のことで,作者と読者の位相差のことを話しているに過ぎない。ただそれにしても,映画的にこの空間を受け容れることでしか物語の幕は開かないのだから,開幕ベルが鳴れば,読者は目を凝らして自分の視線の先のことを追うしかなす術は無いのである。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 25, 2009
-

1Q84 (4)
☆ 賢明な読者諸氏はお気付きのことと思われるが,このレビューは「アストロ球団的展開」を示す可能性が極めて高い(爆)。さらに最初に自分で触れていながら極めて枝葉末節の周囲をウロウロすることになる。それはわたしなりの「敬意」の表し方であるのでどうしようもない。アストロ球団(第1巻(ブラック球団編))☆ 東名高速から用賀を経て首都高に入り渋谷に向かう途中で覚えている看板は「新日本プロレス」と「日本航空電子工業」だ。当然その途中に階段があったかどうかなど覚えていない。階段といえばこんな映画があったが題名からして「この世界」とは遠く離れている。女が階段を上る時(DVD) ◆20%OFF!☆ 更に言えば登場人物と科白の組み合わせが各章の見出しになっていることも興味深い。チャンドラーだったら番号をふるだけだろうし,まるで最近のNHKの連続ドラマ(各週毎に「見出し」がついている)のようだ。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 24, 2009
-
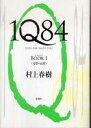
1Q84 (3)
☆ 目に見える「企て」ばかりを追いかけても,作家が無意識に提示する本質には辿り着けない。これは逆も真なりで,本質を掴んだかどうかは提示しているはずの作家にとっても確信があることとは言えないので,判ったつもりが「知ったか(ぶり)クン」になりかねない。いわば「諸刃の剣」のようなものだ。それを前提としながらも枝葉末節に踏み込んでみたくなるのが人情というものだ(笑)1Q84 book 1(4月ー6月)☆ 1984年のFM放送についてウィキペディアでも十分な情報はなかった(今更「ファン」「週刊」「レコパル」「ステーション」の古本を漁る気もしない=笑=)。ただ覚えていることを言えば,NHK-FMで夕方にクラシックの放送がある可能性は低かった。唯一ありうるのは「オペラアワー」がまだ頑張っていた日曜日であろうが,月~金は「軽音楽をあなたに」で土曜日は「リクエストコーナー(だったと思う。NHK-FMの放送局別プログラムで,おそらく森田美由紀氏がNHKに入局するきっかけの一つではないかと思う。)」だと思われたからだ。☆ 全てのスタートがおそらく「虚構」であるという仕掛けをこの中に見る。もとより小説家は物語の中に「企み」を数多く残していくのが仕事であり,これは虚実の中にこそ「物語」の力があるという考察に繋がるものでもある。それにしてもまた東芝EMIか,日経新聞で読んでいたけど。。。EMI CLASSICS 決定盤 1300 381::ヤナーチェック:シンフォニエッタ 狂詩曲「タラス・ブーリバ」☆ ちなみにその日本経済新聞の朝の連載小説は後に宝塚を退団した黒木瞳の衝撃のデビュー作となる「化身」だったはず。【古本】化身 上/渡辺淳一【古本】化身 下/渡辺淳一
Jul 23, 2009
-
メッサ疲れますた
☆ 今日はお休みです。
Jul 22, 2009
-

1Q84 (2)
☆ 『1984』は映画になってユーリズミックス(その頃はまだ存在していたのでは?)がサントラを担当した。その映画は見に行っていない。ちなみに前日の話に戻るが,おそらく高校の先生達はこの本はテキストには絶対しなかっただろう。これをテキストにしたら生徒(特に出来の悪い者達)は "Newspeak" ばかり覚えてしまうのは間違いなさそうだから(しかし,そんな集団の中から上場企業の起業社長が出るとは先生方も予想不可能だったに違いない。だから人生は興味深いのだ)。NINETEEN EIGHTY-FOUR/サントラ 洋画オリジナル1Q84 book 1(4月ー6月)☆ ところで余談ばかり書いているのだが,昨晩ようやく一度目の読了をした。実に目出度いのだが,いろんなことを考えては考えがまとまらない。どうやって書いたらいいか考えている。1Q84 book 2(7月ー9月)☆ ガイド本,こう読め本には寄り付かない方が良い。当たり前だが「自分の頭で考えながら読む」ことによってしか「企み」は味わえない。もっとも作家の方も心得たもので,明らかにミエミエの「企み」を仕掛けておいて,最後の最後(小説の本文が終わった後)にこっそり「引っ掛け」のコメントを書いている。最後まで読み切らずに「重箱の隅をつついて鬼の首を取ったようなことをブログ等に簡単に書いてしまう」と後で大恥をかくことになるかもしれない(苦笑)。
Jul 21, 2009
-
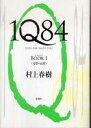
1Q84 (1.1)
☆ 『1984年』の作者であるジョージ・オーウェルの作品との出会いは,高校時代の英語のサブテキストで読まされた『動物農場』だった。高校(の英語の先生)側が『動物農場』を選んだ理由は,オーウェルの文体が比較的平易であることもあったろう(翌年はサマセット・モームだったのだから)。しかし多感な「リア工(坊)」の目には,遠まわしの「赤のぼせへの警告」であるように感じられた。まあそれはいい。我々は何とか文庫版の『動物農場』を手に入れ,それから授業は楽になった。☆ 反面,スターリンとトロツキーの相克とコミンテルンの「覇権」を戯画化した内容には衝撃というより興味を覚えた。ある意味この本と出会ったことが,私を「非政治的」政治的観察者みたいないい加減な存在にした原因だったかもしれない。☆ そういえばあの時代,ソ連を「覇権主義」と呼び,「非林非孔」を喧伝していたのは北京放送局だった。(※中華人民共和国の副主席?だった林彪は,後年の「四人組」中でも江青との権力闘争に敗れソ連に脱出途中に撃墜され死亡。そしてなぜか四人組は攻撃の矛先を「孔子」に向け,この時代「非林非孔」なる運動を展開していた)を戯画的に描いた物語は,共産主義への疑念を抱くには十分に説得力があった。そのオーウェルは『1984』という作品で全体主義化した「社会」を描いているというのを知ってその本を探しまくったのだが,なぜか見つからなかった。☆ それは探し方が悪かった。まさか知らなかったのだが,ジャンルが違っていたのだ。『1984年』は未来の話だったため早川SF文庫に所収されていたのだ。知らないとはつまりこういうことで,その頃かじり始めたロックの歴史に輝く悲劇の星のひとりジャニス・ジョップリンが属していたバンド名 "Big Brother and the Holding Company" こそがこの小説から取られていたものだということも後から知った。もちろんいまだに『1984』さながらのアナクロな地域がこの近くに存在していることも。。。☆ オーウェルについての興味深いエピソードは,ある時彼が「大衆というものは当てにならないものだ」と漏らしたことがあるという話だ。権力という一種の「システム」に対して大衆は反抗すべしと教条的に語られることの多いオーウェル(英国の植民地に支配する側の人間の家族として幼少期を送っている。この辺はクラッシュのジョー・ストラマーにも近く,時代が違えば表現方法が変わるとはいえ,本質的な部分が似ている点も更に興味深い)だが,チャーチル同様「大衆民主主義」の限界も十分に理解していたのだと思う。この話を知って,わたしはジョージ・オーウェルという作家にとても共感を抱けるようになった。ずいぶん昔の話だ。1Q84 book 1(4月ー6月)1Q84 book 2(7月ー9月)
Jul 20, 2009
-

仮構の「やつら」と「システム」との間
☆ 「ドント・トラスト・オーヴァー30」と粋がっていた筈の元ヤングのオッサン達が,それより倍以上年齢をとってみると,あんたそういうのを「馬齢」と言うんじゃないの的な「残骸」になっていて,当然のように失望させられる。☆ では「かつての "やつら" ども」は,何処に隠れてしまったのか?おそらくこれを解く言葉が「システム」ではなかろうか?村上春樹を「ミニマリズムの作家」と斬り捨て,人畜無害な存在だと軽く見た側こそが「システム」の側に隠れている「やつら」であり,かつては反対側にいた筈の「やつらの後継者共」である。何のことはない。皆さんイイオトナになりましたねえ~的な皮肉しか浮かんでこないのだ。まるで30年ほど前のスティーリー・ダンの歌のように「彼らは人間(おとな)社会に逆戻りした」。【Aポイント+メール便送料無料】スティーリー・ダン Steely Dan / Royal Scam (輸入盤CD)☆ 村上春樹の小説はミニマリズムの系譜にはあるかもしれない。しかし,それは内部にさまざまな要素を孕んでいる。「クローズアップ現代」的なステロタイプな分析には与(くみ)することは出来ない。わたしの村上作品歴は『ダンス・ダンス・ダンス』で止まっている。呆れたことに『ねじまき鳥クロニクル』以降の全作品で完読した作品は,ジャズのこととウイスキーのことと走ることに関するエッセイである。☆ だから「そこまでの持ち駒」と実際に知っている1984年の記憶だけで勝負したい。1Q84 book 1(4月ー6月)1Q84 book 2(7月ー9月)
Jul 19, 2009
-
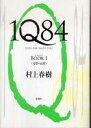
続4 ちょっと違うような気がする~小説という企み(12)
☆ このように書いていくと,村上春樹が指摘したのは単純にイェルサレムの統治者(イスラエル及びその軍隊,諜報機関,治安警察)のことではないことに気付くかもしれない。イェルサレムに係わる三つの宗教(ユダヤ・キリスト・イスラム)であり,それらに仏教や道教などから「喪黒福造的新・新興宗教」を含んだ宗教全てでもあり,更に一般化できるなら(これはかえって危険なことでもあるが)社会あるいは人間の集団(それがゲマインシャフトであろうとゲゼルシャフトであろうと個々人の生命を超越した集団)に対する「個々の個人(重畳的表現を敢えて使っている)」が何を武器に対抗出来るのかという問題である可能性を感ぜずにはいられない。☆ 言葉が発せられた場所には確かに意味があるのだが,(意識していたかどうかは別にして)作家の企みはもっと本質を突いているのではないか。それが「違和感の最大の理由」である。☆ 長くなったが(というか今頃番組に立ち戻るのか?),内容は悪くなかった。ただ,どちらかと言えば主体的に村上作品と向き合ってきたか,村上春樹と係わりが多少なりともあったか(といっても,どこかのマラソンで偶然,彼の隣を一緒に走っていたような人の意見はなかったが)という人達の発言が多かった。最後に絶対触れておくべきなので書き添えておくが(苦笑)栗山千明の朗読姿はとても魅力的だった。役者稼業に飽きてもあれだけで十分に食っていけるだろう(自爆)。1Q84 book 1(4月ー6月)1Q84 book 2(7月ー9月)
Jul 18, 2009
-

続3 ちょっと違うような気がする~小説という企み(11)
☆ 宗教が「オピウム(カール・マルクス)」である理由は「信仰というベクトル」の力にある。帰依さえしていれば幸せであるなら,これに越したことはない。だがしかし,自分が帰依することと(特殊用語はあえて使わないが)それに「興味関心もない他人」を帰依「させる」こととは本質が異なる。もし宗教の力が限界的で更に内部調和的であったとすれば,ごく少数の者の間で固い紐帯に結ばれた集団となる(「隠れキリシタン」のように)。☆ しかしマルクスの指摘する「(宗教の)オピウム性」は,これが他の社会集団同様,最終的に自己目的化しながら拡大再生産をするという「社会性」にある。従ってそこには異教だけでは飽き足らず「正統と異端」のような内ゲバに発展する(キリスト教,イスラム教,仏教の歴史を目をかっぽじって良く見てみるがいい!)。それは宗教の別によらず悲しいほど似ている。まさに織田信長が喝破したように「神仏は人の作りしもの」である何よりの証拠ではないか!☆ しかし,そうした本質にも拘らず「喪黒福造」的「新・新興宗教」は,やがて巨大な犯罪集団に成長する。それは少なくとも「その信仰の彼岸」である我々の認識であり,此岸にいる彼らには「理解し難い,受け容れ難いこと」である。【古本】アフターダーク/村上春樹
Jul 17, 2009
-

続2 ちょっと違うような気がする~小説という企み(10)
☆ 誰がどのようにズッこけたかはウィキペディアの「湾岸戦争」の項目(改竄されていなければ)を見れば解かるが,そのことを以って文学者達を非難する権利は誰も持ち合わせてはいない。逆に言えばブンガクが「それだけのこと」と化した瞬間でもあった。☆ それでもまだ90年代前半は「どうにかしなければならない政治状況」が存在し,何人かの作家はそれに向けて行動する姿勢(まさに彼らの好んだスポーツで言えば「ファイティング・ポーズ」)を示していたが,いつの間にか(おそらく「日本の政治状況に嫌気が差して」)止めてしまった。残ったのは本当に職業政治家になった数名だけで,ある者は虚飾が剥がれて失墜し,別の者はポーズだけは続けている。☆ 文学者は(恐らく音楽家も)こうして彼等がかつて味わった「スチューデント・アパシー」に再び直面し,基本的に「地下潜行した(They went undeground.)」。その間隙を縫って新・新興宗教が登場する。まるで喪黒福造のように「どこにも行けない」「居場所がなかった」若者達のココロの隙間に,「人格改造セミナー的入念さ」と「似非科学的な魅力」とを持って。全巻セット!ご購入は当店で!期間延長!全商品 送料無料です!【漫画】笑ゥせぇるすまん [文庫版] (1-5巻 全巻)
Jul 16, 2009
-

続 ちょっと違うような気がする~小説という企み(9)
☆ 「物語」の力によってシステムに対抗するという村上春樹の意思表明は非常に意義深いと思う。これについては番組の中でもコメンテイターがずばり指摘していたが,1991年に湾岸戦争が勃発した時,日本の作家達は四分五裂した(かのようだった)。この時,東西冷戦の終結という「邯鄲の夢」が終わり,平和の配当を享受する筈だった西側諸国はどうしたことか「キリストとイスラム」という中世の課題を再び突きつけられてしまう。☆ 中世において「極東のジパング」に過ぎなかったこの国は,図体(経済的な規模)だけは大きく,内実はコドモ(人間を幸福にしない日本というシステム)の「不思議な存在」になっていった。そうだな。「ホモンクルス」とでも呼んだ方が良いかもしれない。そして作家達もまた自らがその「ホモンクルス」の更に一部分に過ぎないことを見せつけられる。テレビゲームのような「(自称)ハイテク攻撃」の白黒の図柄には,その標的が戦闘目標として正しいのかそれとも誤爆なのかすら考えさせない「ディジタルなリアル記号」としか写らない。そんな「現実」の前にことばによる「企み」は強風の前に揺らめく蝋燭(ろうそく)の灯(ともしび)よりも無力であった。☆ 作家達はディジタルによって非常に強いトラウマを植えつけられた(もっと直截な表現があるが,使いたくないから使わない)。それは「唯一の被爆国」ですらただの「お題目」ではなかったのかと80年代後半にに浜田省吾が続けて鋭く問うたことでもあったのだが。《送料無料》浜田省吾/J.BOY(アルバム)(CD)《送料無料》浜田省吾/FATHER’S SON(CD)【CD】浜田省吾 /誰がために鐘は鳴る <1999/9/29>
Jul 15, 2009
-
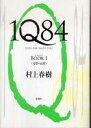
ちょっと違うような気がする~小説という企み(8)
初出http://deaconblueatnetmile.blog.so-net.ne.jp/2009-07-14☆ NHK総合「クローズアップ現代 「村上春樹 “物語”の力」 」を見た感想。> 新作『1Q84』が大ヒット中の作家・村上春樹氏。「個人の魂の尊厳を浮かび上がらせる」と宣言した村上氏が、読者に向けて発したメッセージとは何なのかを読み解く。☆ 上手く言えないのだが,90年代半ば頃に時ならぬ「ビーチボーイズの『ペット・サウンズ』~『スマイル』の再発掘みたいな変なムーブメントがあって,山下達郎が凄い違和感を感じるという趣旨の発言を自身の番組の中で言っていた。『1Q84』から始まる物語,その物語の磁力の強さに「トレンド的評価」を下すことは,まったく「システム」の中に囚われている "消費者" のような感覚を持つ。何だろう。この感覚は例えばイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」の結論みたく,システムの側はいつでも捉まえることは出来るが(いつでもチェックアウトできるが),捉まえられた方はそのことすら気付かない(決してここを離れられない)という様相に似ている。☆ こんだけ書いたら「読書室」で続きを書くべきなんだろうな(笑)。1Q84 book 1(4月ー6月)1Q84 book 2(7月ー9月)
Jul 14, 2009
-
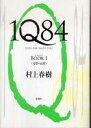
小説という企み(一時休止2)
☆ 明日「クローズアップ現代」で村上春樹『1Q84』が取り上げられるらしい。この番組ならまだマトモな気がするが,一体どうなるのだろうか?1Q84 book 1(4月ー6月)1Q84 book 2(7月ー9月)
Jul 13, 2009
-
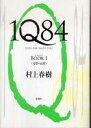
小説という企み(7)
☆ 反面,これとは逆に「自分の恥部と思われるもの」を露出しているのではないかと疑いを持たれるような小説を書く人もいる。どこかの公演で裸になった上に大声を出して捕まるより性質(たち)が悪いことかもしれないのだが,それでも小説であることに間違いはない。このような「露悪趣味」ギリギリの線をなぜ作家は選ぶのか?☆ どこまで「迫真のもの」を描けるかという点で作者に「企み」は確かにある。自分の体験をのんべんだらりと書くだけなら(かつてそれをされたであろうご婦人方には恐縮ながら)「読者の体験手記」レベルに留まる。それはそれで「(自分には追体験不可能な)個人の体験記録」として興味関心の範疇に入るかもしれないが,小説家はそのレベルで「あってはならない」。☆ やはり虚実の綾を見せながら読者に対して自らを「台」としながら読者に対して物語の中へ引きずり込む「企み」がなければ,それは小説ではなく「体験手記」に過ぎないのである。だから,自然主義のドロドロ小説は,ただドロドロなままではもはや「小説たりえない」。そこにどんな「物語」を提示しうるか,それこそが自然主義作家達に課せられた使命であったと思う。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 10, 2009
-
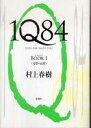
小説という企み(6)
☆ 小説が(模倣や剽窃[ひょうせつ]でない限り)作者の創造物であることは疑うまでもない。だとすれば,作者に課せられている使命はおそらく「小説の中にある "物語" を詳(つまび)らかにする」ということであろう。だが作家の中にはそのことをまるで「見せたくもない自分の恥部を他人に曝(さら)け出す」ことのように嫌がっているとしか思えない人がいて,「この人は何のためにこの小説を書いているのか」と思わせることがある。☆ 強引に結論付けてしまえば,彼が言葉によって紡(つむ)ぎ出す「迷宮」そのものが「彼の企み」の全てであり,そこには元から虚構であるはずの「物語」そのものが「正体の見えないもの」として存在しているということも出来る。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 9, 2009
-
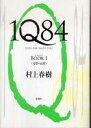
小説という企み(5)
☆ 小説における作者の「企み」の最大のものは「物語」を通じて読者をその世界の中に引きずり込むことである。これはポルノグラフィーの持つ「猥褻(わいせつ)性」に特徴的だ。昭和40年代後半(1970年代半ば)以降,暫くの間「わいせつか芸術か」という不毛な論争が法廷を占拠した時代がある。猥褻は統治者の恣意的な判断によるものだという根底意識から,反体制的な無意識に支配される「猥褻の何が悪い」サイドと猥褻とは風紀を紊(びん)乱し,(性犯罪の激増を通じた)国家体制を揺るがすきっかけ(いまどきの「危機管理用語」なら「モラル・ハザード」とでも言うべきだろう)になりかねないという警察官僚の意思が真正面から衝突した時代である。☆ 「これ」については,統治論で述べたほうが良いから,ここでは深入りしないが,基本的に「猥褻」と認識される可能性のある引力は,性衝動という本能(別名「官能」)に作用することで,作者の「企み」を如実にする分,わかりやすいとは言える。いずれにせよ,作家にとって最も原初的な「企み」は,「読者を物語の中に引きずり込むこと」であることは疑いない。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 8, 2009
-
小説という企み(一時休止)
☆ 七夕の歌の正式な題名が「たなばたさま」であることを当日に知った(笑)。もちろんポイントサイトのクイズ問題に出題されていたのでポイント付き検索で調べて分かったという,どうにも情けない話である(爆)。昔,山下達郎がまだ土曜日の放送だった頃の「ソングブック」で音楽との係わりについて話していたのを聞いたことがあって,彼曰く,小学校低学年の時に,この「たなばたさま」を歌うのにボーイソプラノのキーが届かず,「ささのは」の後の「さ~らさら」を一オクターブ落として歌ったら教師から「ふざけるのはやめなさい!」と怒られ,一時期音楽嫌いになったという。それが高学年になってマーチングバンドに入ったことがきっかけでプロのミュージシャンになり,(ポピュラー)邦楽界の第一人者の一人として,40年近く第一線で活躍することになるとは,人生何がきっかけになるか判らないものだ。☆ と本日は完全に脱線しました(自爆)。月曜の続きはまた明日(^^)v。=検索能力低いね(苦笑)=
Jul 7, 2009
-
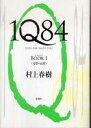
小説という企み(4)
☆ 全ての「物語」が「小説」であるのに係らず,「小説」の中に「物語」があるとはどういうことか?運悪くこの駄文を(1)から目にしてしまった人は当然疑問に感じることだろう。それはひとえに作者か読み手のいずれかの技量の問題だといってしまえばそれまでである。あまりにも面白くわくわくしながら一気に最後まで読み終えたと言えば,それは小説の持つ「物語性」自身が作者にとっての「企み」であったかもしれない。読み手に対してローラーコースターに乗ったかのような感覚を与え,興味関心を最後まで失わせず,一気に終結まで導いてあげるというのは,これもまた作家の技量そのものである(反面,読み手の技量に依存するところもある。なぜなら小説という「企み」は,作家と読み手の間に相互依存関係を作り出す仮想空間でもあるからだ)。☆ この関係性における技量を最も強く求められるのが新聞小説である。他の連載小説よりも遥かに少ない字数で,読み手の関心を引き続けなければならないからだ。だから新聞小説が書けるということは作家としての技量をある程度認められているという証左でもある。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 6, 2009
-
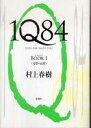
小説という企み(3)
☆ 物語は存在そのものであり,小説は「企み」のある物語である。だからイソップ童話は全て物語ではなく小説であり,古事記や聖書,コーランも全てこの点についてのみ同様(気をつけて欲しいのは,あくまで「この点について」であり,聖典の「聖性」とこのこととは「何ら関係がない」こと)である。☆ つまり「物語」は,小説の本質もしくは「核(コア)」そのものを指し,既に作家(もしくは著述者もしくは口述者)の中にあるものを表出する時,物語に「企み」が混じりだすのである。企みのない純粋な「物語」はこれらの人間の心もしくは頭の中でのみ存在し,外に出ることはない。物語が外に出るとは,企みのフィルターを通り抜けていくことでもあるのだ。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 3, 2009
-
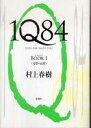
小説という企み(2)
初出http://ameblo.jp/definitivegaze/entry-10290658562.html☆ 小説と物語の違いは前日書いた通りだが,読者として小説と対峙した時,作者の「企み」とどのように付き合うのかという問題がある。全く付き合う必要もないのであれば,企みのない「物語」として一気にゴールまで読み流せばよい。そこには一冊(もしくは一巻)読んだという量的な満足感があるかもしれないが,それは「数をこなす」という徒労感というか虚脱感も併せ持つものと言えるだろう。☆ 「企み」がコンセプトになっている小説は「推理・ミステリ」の類である。そこで作者は自らの企みを隠すことなく読者に提示し,読者はその「企み」を読み込むことで物語の渦中に投ぜられることになる。これは方法論としては簡単に見えるが,あまりに知られたやり方であるため,かえって作者の技量が問われる結果となる。結構むずかしいものなのだ。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 2, 2009
-
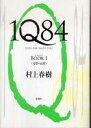
小説という企み(1)
初出http://ameblo.jp/definitivegaze/entry-10290136327.html☆ 小説が物語と異なる理由は,そのテクストの中に作者の企みを孕んでいるところである。企みを孕んでいない物語は,その名の通りただの「物語」に過ぎない。小説の小説たる所以(あるいは物語と分かたれているところ)は,テクストの行間に作者の企みが潜んでいるか否かによる。☆ だから物語はあるがままの「物語」として筋を辿って行くだけで良い。他方,小説は最初は「物語」として筋を辿り,二度目に作者の企みを探し,三度目に作者の企みを自分のものとして味わえる。せっかちな人は最初からこの「行間」を穿(ほじく)り出そうとするが,この手の拙速な鑑賞はあらかた失敗に終わる。もしそれで図星を指されるなら,テクストたる小説あるいはその企みが未熟なのである。1Q84 book 1(4月ー6月)
Jul 1, 2009
-

昭和のエートス (2)
昭和のエートス☆ エートス(Ethos)とは,(ある文化の根本的)精神とか(社会・集団の)気風などを指す。ただ,内田の指す「昭和」とは,敗戦によってアイデンティティに分断を受けた層に限定されている。そこでは例えば「特殊近代的」「進歩的」自我が,民俗(民族ではない)精神の逆襲を受けるさまを戦前の「転向」と6~70年代「安保闘争」によって自壊するのを明示しており,この指摘は興味深い。☆ 読み進めていくうちに内田の「エートス」には「三丁目の夕日」的なノスタルジイが峻別されていることに気付く。これについては内田自身も別の所で述べている。=続く=
May 10, 2009
-

昭和のエートス (1)
昭和のエートス☆ 内田樹(うちだたつる)の「昭和」は,筆者には遠い「昭和」である。著者と筆者は殆どひと回りの差があり,その差は著者によらずとも「決定的な意味」を持っている気がする。ただ,第1章「昭和のエートス」の中で内田が縷々述べている事に筆者は不思議と反発は感じなかった(もっと反発するのかと事前に思っていたのだが)。=続く=
May 9, 2009
-
ONLY YESTERDAY (6)
☆ 昭和軽薄体とはいったいなんだったのか。それは確かに「文体(テキスト)」であり,その背景に「視線」があった。当時の表現で言えば「ドクダミ光線」とか(笑)。ただ「軽薄体」に隠れた視点があったとすれば「恥ずかしい」モノ「いい加減な」モノ「胡散臭い」モノへの疑問であり,批判であった。☆ だから「国分寺書店のオババ」は天敵(ライヴァル)であっても「ドクダミ光線」の対象ではない。「ニッポンの異様な結婚式」は「ワシは恥ずかしくて願い下げ」だが「どうしてこんなものになってしまったのか」という好奇心が貫かれている。☆ そう考えると「スーパーエッセイ系」と括る中でも村松具視の「プロレス三部作」は,専ら「プロレス」を見る者の視点が定まっている(=「プロレス者(もの))し,クマさんこと篠原勝之にはゲージツ家と豪快に笑い飛ばしながらも繊細な完成が透けてみえる。いちばん「スーパー」だったのは,椎名さん,嵐山さん,南さんだったのかなと思う。=続く=
Mar 8, 2009
-
ONLY YESTERDAY (5)
☆ スーパーエッセイについて当時椎名さんは「スーパーマーケットのように身の回りのことを書いた」という言い方をしていた。あるいは半径何mのエッセイだと。☆ これを青二才盛りだった筆者は一種の反権威として捉えていたし,賞賛というかシンパシィを感じていた。ただやがて自分自身が気付くのだが「反権威は権威を目指す」。つまりサル山のボス猿と若いオスのようなものだ。これは単純に「世代交代」と言っても良いのかもしれない。☆ 椎名さんは直感的にそういうことに気付いていたようで,いまだに決して権威の方向に足を踏み入れてはいないように見える。同じことは未だに文芸評論家:北上次郎であり続ける目黒さんにもいえる。☆ だがこれは別に権威化しつつある林真理子を批判しているわけでもない。本格的な小説家になってからの彼女は昔の彼女のように物欲しげではなく,むしろ堂々とまっすぐな良い仕事をしていると思うからだ。=続く=
Mar 1, 2009
-
ONLY YESTERDAY (4)
☆ そういえば当時会社の同期だったK氏が,とある土曜日O田急本線の車内で林真理子をたまたま見掛けたことがあったと話していた。その頃はまだ単なる「売れ始めた物書き兼売れっ子コピーライター」だった彼女はマネジャーかスタッフか鞄持ちかよく判らない男性と車両の中を移動していったとのことである(念のために書き添えると,急行だったそうな)。☆ 椎名さんのコラボではNHK-FMでスーパーエッセイを2編もやったのを思い出す。勿論ナレーターは伊武雅刀氏で,これが面白くないわけはなく,毎晩抱腹絶倒。真夜中近く(まだあの頃のNHK-FMは24時の時報のあと「君が代」が毎日のように流れていた)で多少親の不況を買ったが(爆)それは確かに面白かった。☆ 第一弾が「さらば国分寺書店のオババ」で,第二弾は「ニッポンの異様な結婚式について(『気分はだぼだぼソース』収録)」だった。後者の最終日に伊武さんと椎名さんの対談みたいな「おまけ」があって,これも面白かった。NHKは持ってるならこのCDを出して欲しい(再爆)。=続く=
Feb 15, 2009
-
ONLY YESTERDAY (3)
☆ 林真理子の第二作は『花より結婚 キビダンゴ』だったと思うが,今で言えば西原理恵子とか上大岡トメとか,あの線に近い気がする。だとすれば,林がライトエッセイの主峰たる「本の雑誌(=昭和軽薄体)」に「混ぜてほしい」と思っても不思議はない。椎名さんや目黒さんがそれを体よく断ったのかどうかは知らないが,波長が合わなかっただけだろう。☆ 当時の「本の雑誌」のことは『本の雑誌 血風録』とか『別人群ようこのできるまで』とか当事者が書いた本のほうが面白いし,それ以上のことは書きようもない。でも当時の「本の雑誌」の奥付に「木原ひろみ」が書いていた後記と沢野ひとしの挿画イラストを「真に受けた純情ハートの」読者があとで異議申し立てをすることには道理があると思う(爆)。=続く=
Feb 14, 2009
-
ONLY YESTERDAY (2)
☆ 同じ頃,主婦の友社から『ルンルンを買っておうちに帰ろう』でデビューした林真理子はこのグループに入れて貰えなかったことを悔しがって「あの人達は一種のギルドだから...」とどこかに書いていた。ただ「本の雑誌」の女性投稿者は,やがて独り立ちする群ようこを除けば佐野洋子さんくらいしかいなかったような気がしている(1981~3年頃)。☆ 70年代半ばにマスコミでもミニコミでもない概念として「ミディコミ」という言葉があった。ある程度の「立場(販路など)」を獲得した雑誌がこれに相当し,前回書いた音楽系の二誌や「本の雑誌」「広告批評」(島森さんもいたけどまだ天野さんの時代だった)などが「ミディコミ」と思われていた。「本の雑誌」の人達(目黒さん,椎名さん)は認めていなかったが,情報誌としての「ぴあ」もここに入っていたと思う。☆ 「ミディコミ」の流れは,たぶん米国60年代のカウンターカルチャー(例えば「Rolling Stone」など)が形を変えて日本に定着してきたものだと考えられる。これはやがて「サブカルチャー」に変化していくが,表現方法としてのサブカルチャーが最も意識的に行われていたのはインディーズ/オータナティブという形で作品を発表する場を得ていったロック音楽だったのだろうと思う。☆ 出版という世界は,音楽業界に比べると既成の秩序が強いイメージがある。放送などのように,ギョーカイを売り物にする割には保守的で一種「せこい」カルチャーが大手を振るのならと,海賊放送事件などを経てコミュニティーFM局が認可されるようになる。そんな流れの中でIT革命が起こりポッドキャスティングや動画投稿全盛時代になっていくのだが,これら(見てくれよりもずっと保守的な放送業界をも最終的に巻き込む形で進んでいった)のサブカルチャーのメーンストリーム化の原動力は,やはりこの辺りにあったんじゃないかという思いは強い。と今日も脱線したまま話が終わってしまうのであった。。。=続く=
Feb 13, 2009
-
ONLY YESTERDAY (1) はじめり
☆ だから1980年頃の話だったと思う。その頃RCサクセションが『RHAPSODY』を引っ提げてシーンに復帰してきた(『RHAPSODY...NAKED』を聴き,解説を読むとこのアルバムはロキシー・ミュージックの『VIVA!』の手法に近い。ライブ音源をベーストラックにミックスダウンを重ねた擬似ライブ・・・しかし正真正銘のライブ盤だった)。☆ そのRCのコンサートを見に行ってレポートらしき文章を書いた上に執筆依頼をしたのが当時はまだ「本の雑誌」編集長だけだった椎名誠だった。この辺はシンクロしている部分があって,彼もまた「昭和軽薄体」を駆使した「スーパーエッセイ」を情報センター出版局から上梓したばかりだった。☆ たぶん順番は「朝日新聞」あたりに載っていた情報センター出版局の広告になにやら怪しげなタイトルの本が並んでいて(『さらば国分寺書店のオババ』とか『気分はだぼだぼソース』とか『かつおぶしの時代なのだ』とか)「何これ?」と思って大学生協で買ったのがはじめじゃなかったのかなあと思う。☆ そうすると当然「本の雑誌」という雑誌にも興味を持つ訳で,そのとき運良く大学生協には「本の雑誌」とか「広告批評」などが並んでいたから(当時は一般書店ではまず手に入らなかった。せいぜい「ロッキング・オン」とか「ニュー・ミュージック・マガジン(当時)」あたりが限界だった)運良くそれらの雑誌と出会うことが出来た。=続く=
Feb 8, 2009
-
ONLY YESTERDAY
http://item.rakuten.co.jp/book/584766/☆ ↑な事してもアフィリエイトにはならないそうだ。☆ アレンの本が描くのは,大恐慌後のアメリカで「あの時代(ローリング20's)とは何だったのか」ということだ。どうせならこっちも読んでおくと面白い。http://item.rakuten.co.jp/book/256566/☆ しかしこの本も『マフィア経由アメリカ行』も「品切」だってさ!今日も憤慨し始めたので本来の話に入れない
Feb 7, 2009
-
うわひでえ
☆ テーマを後から選択したらそれまで書いていた駄文が全部消えちまった。全部まとめてやり直し
Feb 6, 2009
-

戦後最大のベストセラー「冠婚葬祭入門」の意義
冠婚葬祭入門☆ この書名を見てピンと来た人は40代後半より年上ということになるだろうか。単なるベストセラーを超えている意義があると思う。(1)ノウハウ本ブームに先鞭を付けた(2)同様に新書型の本の一大ブームを巻き起こすきっかけとなった(3)核家族化を背景に人伝えにしてきたものをノウハウという形に変えた(4)言い換えれば公団サイズの団地族があって初めて成立した本である(5)このようにこの本は戦後日本の転換点を見事に指し示した本である以上の理由による。☆ ちなみに戦後最悪のベストセラーは,中世に生きたあるフランス人が自らの生きた戦乱と疫病の時代を別の世代に仮託して描いた叙事詩を勝手に解釈したオカルト本である。
Feb 2, 2009
-

『バブル』 (田中森一×夏原武) =3=
バブル☆ この本を読んでいると,米オバマ政権がなぜ「アフガニスタン」に拘っているのか気付かされる部分がある。また昨年あたりから急にクローズアップさせられている観のある「大麻問題」が同じ根っ子を持っていることにも気付かされる。こうした薬物は昔から知られていた。覚醒剤(終戦直後の「ヒロポン」も同じ)が「シャブ」という隠語で呼ばれる理由は「骨までしゃぶる(=覚醒剤中毒で死んだ人間を火葬したら,骨がボロボロの粉になってしまったこと)」に由来する。そうしたブツの一大供給源が,かつてクン・サが支配した「黄金の三角地帯」からアフガンの奥地に移ってきたからだろう。☆ そういえば「ミャンマー」と名乗っている国もこの「三角地帯」の一角にあることを忘れてはいけない。これらの国が米欧諸国から非難される一因がここにあることは事実と言ってよいだろう。。。なんだか肝心の本の話からすっかり離れてしまった。でもここで紹介するより実際に読んでみれば判る。面白いのは人の心であり,それぞれの立ち位置といってもよい。新クロサギ(1)
Jan 30, 2009
-

『バブル』 (田中森一×夏原武) =2=
バブル☆ 『バブル』という本を読んでいて痛感するのは,今日時点の50代と30代との間には決定的な「断層」があるということだ。1980年代バブル(以下「平成バブル」と表記)の崩壊は,昭和という元号の終わりとも相まって,決定的な「何か」を日本人に与えたような気がする。勿論それは,バブルが崩壊した瞬間に衝撃として発生したというよりは,バブル(の破裂)によって決定的に崩壊した旧秩序と冷戦構造の崩壊,IT革命とが「たまたま同じ90年代初頭~前半」に発生したせいだと言う方が何となくスッキリする感じはするが,どうもそれだけではない。日本人の精神構造が世代・社会・体制(直接の関係はないように見えるだろうが,(旧)社会主義陣営,なかんずく中国との関係を通じて明らかに影響を及ぼされている)の変化と相互に作用して「変わってしまった」。そして,この「変わってしまった」という感覚は田中・夏原の二人が進める会話のあちこちから感じられるのだ。☆ だから二人が「平成バブル」とライブドア騒動などに見られた「投資銀行バブル(=「サブプライム問題」まで通底する「ITバブル(1998~2000年)」以降に成長し,2007年に破裂し始めるバブル)」に対して違和感を感じるのは,ただ「世代の差」という言葉で片付けられない「深み」があるように思う。バブルは人間の所為であるから本質的に人間臭いものである。それが金融工学に裏打ちされていようが,システム的に執行されようが,どのようにやっても「人間の欲望」はコントロールできない。この制御できない過程(貪欲の僕=しもべ=)が「バブル」の本質であり,それは資本市場に限らず人間の所為のあらゆる部分に姿を現す。権力欲から支配欲に至る全ての煩悩は間違いなく「バブル」であり,それは同時に「バブルの似姿」でもある。☆ 良く言われるように「金は使っても,金に使われるな(この言葉,実に「酒は飲んでも,酒に呑まれるな」に似ている)」。お金は自分を実現する手段であり,お金自体(を貯めこむこと=それによって自分の財力や自分の蓄財の才能をを誇示すること)を目的とするな。ここにバブルの裏側が透けて見える。繰り返すが「バブル」とはどんな目的手段があろう(飾り立てよう)とも,人間の持つ貪欲・煩悩そのものであり,(バブル的な方法で貯まった)お金はその欲望の似姿に過ぎない。=続く=
Jan 28, 2009
-

『バブル』 (田中森一×夏原武) =1=
バブル☆ 読書日記は書きにくい。読んでいる時には書き辛く,読み終わってから書こうと思うのだが,その頃には他のことに時間を取られ過ぎる。上手く書こうと思えば,一気に読んで一気に書くしかない。これは自分の性であるから仕方がない。
Jan 24, 2009
-

大暴落 1929 (ジョン・K・ガルブレイズ)=1=
大暴落1929☆ 奥付きを見ると今回(というかこのヴァージョン)の初版は2008年9月29日になっている。それはそれで悪くないタイミングだし,実際良く売れた。しかし,いくら著者の「最新のまえがき」が1997年版だったからといって(かつ,もう二度とこれより新しい「前書き」が書かれないと分かっていても)この値段は阿漕だろう。。。☆ ガルブレイズと言えばもう一冊『バブルの物語』という好著がある。これも薄い本なのにハードカバーで結構なお値段だったが,どうなるものやら。。。バブルの物語新版=続く=
Jan 4, 2009
-

ご老公キレる
> マスコミに報復してやろうか=厚労行革懇の会合で-奥田座長 11月12日21時30分配信 時事通信> 政府の「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」の奥田碩座長(トヨタ自動車相談役)は12日に首相官邸で開かれた会合で、厚労省に関するテレビなどの報道について、「朝から晩まで年金や保険のことで厚労省たたきをやっている。あれだけたたかれるのは異常な話。正直言ってマスコミに報復してやろうか。スポンサーでも降りてやろうかと」と発言した。> 奥田座長は「ああいう番組に出てくるスポンサーは大きな会社ではない。地方の中小とかパチンコとか」とも述べた。> これに対して、委員の1人である浅野史郎前宮城県知事は「スポンサーを降りるぞとか言うのは言い過ぎ」ととりなした。☆ 日本経済新聞がご丁寧にも上記でぼかした「地方の中小云々」を「パチンコ屋とかサウナとかうどん屋とかとまくし立てた」と発言を微に入り細に入り紹介しているが,こりゃ絶対悪意あるな(爆)。☆ 奥田氏が強面なのは知っている人には周知の話で,この『エネルギー』下巻にも出てくる。言うまでもなくトーニチはトーメンのことで,トーメンが豊田通商に吸収されたので,豊田通商の穀物取扱高はグッと増えた。昨年NHKスペシャルでメタノール生産に走る米国のトウモロコシ農家相手に手こずる豊田通商マンの姿を紹介していたが,彼もトーメン直系のヒトなのかもしれない。
Nov 13, 2008
-

エネルギー(雑事)
☆ この小説は非常に興味深い内容で一気に読ませてくれるのだが,何箇所か「えっ?!」と思うような誤植がある。探してみるとわかるが,たとえば上巻なら国名と首都が反対に書いてあるとか「征服」が「制服」になっている(爆笑した)とかその手のヤツを見つけた。ただしこれ初版第一刷なので見つからなかったとすれば改版か訂正されたのだろう(^^)。
Nov 9, 2008
-

秋霜烈日
☆ 筆者は検事ではないが(そんなに優秀だったら。。。まあいいか),秋霜烈日という言葉の持つニュアンスが好きだ。朝は霜が降りるほど寒く,昼間は汗をかくほど気温が上がる。気温の日較差というがそういう時節になった。☆ 楽天のサービス全体を9月から再び使い始めたのだが,18ヶ月もあいだが開くとかなり「進歩」していて,逆に言えばこちらは取り残されてしまっている。おそらく「進歩」の過程を知っている人にとっては自明で使いやすい機能も遅れてきた者にとっては,へたに昔のシンプルな機能を知っているだけにかえって使い辛いところがある。☆ そうした無知やある種の「デヴァイド」につけ込んで,下らないスパムを撒き散らす害虫の被害に遭っていることに気付いた。何しろこっちは「玉手箱」を開けた直後の浦島太郎状態だから,気を長く持ちながら(ジジイにはこれが肝要なのだ)ヘルプで粘り強く検索して,ようやく排除することに成功した。リアルな世界なら防虫スプレーをひと吹き擦ればいいのだろうが,こういう時が苦労する(苦笑)。☆ そういう訳で,コメントやBBSの管理が億劫なので勝手なことを書き散らすだけの詰まらないブログのひとつになってしまっているのだが,前回まで紹介してきた本の著者は,今後マスコミへの露出が増えてくるかもしれない(本人かそのマネージメントが望めばだが)。あまり長く本の内容を書いていると都合が悪いし,だいたい読みやすい新書でもあるので,良かったら一度手にとって見て欲しい。すべての経済はバブルに通じる
Nov 8, 2008
-

すべての経済はバブルに通じる (3)
すべての経済はバブルに通じる☆ 著者は証券化の本質を「商品化」であると指摘するが,「商品化」とはどういうことか。> 金融市場に対してもっとも大きな影響を与えた現象としての証券化の本質とは,資産が証券化されると同時に「商品化」され,価格が付くということなのだ。価格が付くとは,単に鑑定評価額などの理論的な価値が決まるのではなく,「市場価格」が付くという意味だ。そして,これが本質的な変化をもたらすのである。☆ 注目すべきは「市場価格」が理論的な価値から遊離したものになることを示唆しているところである。バブルという現象の本質は "あるものの価値がその実態価値から遊離し過大に評価される過程ならびにそのようにして「作られた」価値 " のことであるとすれば,1980年代末にこともあろうに「トービンのq」をバブル化した「qレシオ」なる妖怪が登場したのと同じ過程が「証券化」という一見合理的なプロセスの中に紛れ込んでいたと指摘しているように思う。☆ このような「商品化」がもたらした影響について著者の指摘は明快である。> では商品とは何であろうか。一般的には,商品とは,店などで売られているモノであり,そのモノは,広く潜在的な買い手を想定して作られていたり,ディスプレイされていたりする。証券化商品も同じである。様々な投資家が買う状況を想定して作られ,売り出され,宣伝されているのが,証券化された投資商品なのだ。> 投資商品は,たとえば,ハイリスクハイリターンとかミドルリスクミドルリターンという大まかな分類で,投資家に提示される。つまり,リスクとリターンの2つの軸で標準化されているのだ。どんなに複雑な証券化商品も,結局は,リスクとリターンの2つの軸で,投資家に対して提示される。そして,その組み合わせに対して,投資家は自己のリスク許容度,リターン追求度など,自己の嗜好に合わせて投資商品を選ぶことになるのである。☆ 投資におけるリスクとリターンは,投資する金額(元本)に対する「期待収益率とその振れ幅」という形で整理される。ところで著者の記述にもあるように,投資信託の説明書を典型とした投資商品においては,一般的なリスク・マネジメントで使われる「リスク・マップ」が用いられることが多い。これは,発生しうるリスクについてその影響の大きさを縦軸,発生頻度を横軸として表わすものだ。☆ 本来的「投資リスク・マネジメント」で,リスク・マップは標準偏差で使われる「釣鐘状の分布グラフ」で表されるべきであろう。T字を逆さまにして,真ん中をゼロとして,左側が損失,右側が収益となるあの図である。☆ 同じ「リスク・マップ」でも両者の意味するところは全く異なる。後者のリスク・マップは損失の発生機会を意識させるが,前者にはそれはない。一般的な用語,企業などで使われるリスク・マネジメント同様,発生の頻度と影響の大きさは理解されるが,その「影響」が損失に繋がるという印象は与えない。☆ 投資について経験と理解がある人間なら,後者のリスク・マップで前者のリスク・マップのイメージも理解されるかもしれない。しかし大多数の投資家にとっては不十分と言ってよいだろう。そして「投資商品」の売り手にとってはその(買い手側の)意識の「ギャップ」もまた無意識的「裁定機会」と言えなくもないのである。=続く=
Nov 1, 2008
-

すべての経済はバブルに通じる (2)
すべての経済はバブルに通じる☆ 証券化の本質について,著者の考察は次のように分かれている。(1)リスクの小口化(2)リスクを除去するプロセス(3)リスクを純化するプロセスそしてこの三つのプロセスを経ても「これまで述べた手法は,全てリスクを移転しているだけであり,経済全体のリスクが減ったり,なくなったりしているわけではないから」「この証券化によっては,実質的には何も生み出されていない」。☆ まえがきに戻ろう。資本主義(なかんずく金融資本主義)とは「ねずみ講」であるという著者の前提が一貫していることに気付くべきであろう。証券化の本質は「信用創造」の「手法的な新しさ」にあり,その特徴はリスク移転,悪く言えば「リスクの曖昧化」にあった。これは時間の観念を忘れてアキレスと亀の位置関係を追っているようなものである。今のマーケットを見ていると「客観的な指標」なるものが全て「砂上の楼閣」のように見えてくる。実際は「恐怖の大王」の正体もこの辺りに靡(なび)いている「枯れ尾花」のようなものであるのかもしれないが,それは言い換えれば我々が調子に乗って作り上げたヴァーチャルなバブルの塔が3Dドルビーシステム的に音を立てながら崩壊しているのを目前にしているからかもしれない。☆ しかしこの若い著者の本領は,このあたりから巷間に溢れる「と本」と一線を画する。それが「リスクを変質させるメカニズム」としての「商品化」についての指摘である。=続く=
Oct 26, 2008
-

すべての経済はバブルに通じる (1)
すべての経済はバブルに通じる☆ 金曜日の日本経済新聞(第44095号)の3面下に,やけに自信に満ち溢れた著者の近影と共に広告が出ていた。新書で手軽だったことと最近アンケート・サイトから謝礼として送って来た図書カードがあったので,仕事帰りに丸善に寄って地下鉄の中で読み始めたが,これが結構な拾い物だった。☆ まえがきの冒頭で著者は資本主義の本質は「ねずみ講」であるという。これは一歩間違うとその辺に満ち溢れている「と本」の類と間違えられてしまう記述だが,著者の本領はその後発揮される。このあたりの面白さは実際に読んでみると解る。資本主義,なかんずく「金融資本主義」の本質は著者の指摘するように「信用創造」であり,マネタリズムがケインズ資本主義を横に置いたこの四半世紀あまりの世界経済を見ても,それは事実として現れている。残念ながら社会科学たる「経済学」は物理学のように実証する術は「事実=歴史的考察」しかないので,より科学的という訳にはいかないが,「円の支配者」的な「と本(であることはいずれこの欄で紹介する)」よりもコンパクトに本質を突いているところが実写の若さを感じるところでもある。=続く=円の支配者
Oct 25, 2008
-

アジアの隼 (5)
☆ 『アジアの隼』の背景を読んでいくと1990年代アジアで進められた「開発」の問題に突き当たる。ひとつは最終場面まで描かれてはいないが,インドネシアのクローニィ・キャピタリズムの実態であり,もうひとつは小説の出だしと終盤に重要な役割を果たすパキスタンの内政問題である。エマージング・カントリーの仲間入りを果たそうとするヴェトナムを巡る主人公の奮闘と香港から飛び立った「アジアの隼」ペレグリンの栄華盛衰の物話を縦糸とするなら,ここに絶妙の配役をされたボート・ピープル出身のヴェトナム人と韓国系の投資銀行家の二人を絡めた物語を横糸としている。☆ そこに描かれた個人の物語は,前回も指摘したように正は正,邪は邪と描けば主人公だけに光の当たる「サラリーマン物」になっただろうところを,そのような単純な善悪二元論を慎重に避け,正邪の入り乱れた複雑な姿を描いている。邪(よこしま)を多く描き,それがゆえに物語の最後に身を滅ぼす男ですら,その生い立ちとボート・ピープルとして生き抜いた壮絶なエピソードを描くことで,なぜこの男がここまで力(汚職に支えられた金の力)を頼りに生き抜こうとしているかをキチンと描いてみせる。だから物語に奥行きができ,その対比としての主人公の正しさが時に脆さに変わることを示唆しているのである。☆ しかし『アジアの隼』から10年経って,これらの国々にインドを含んだ東~南アジア諸国の興隆は目を見張るものがある。小説に描かれた時代には知ることもなかったこれらの国の市場に専ら投資信託という形で本邦からも個人投資家の資金がかなりの量投入されていることは興味深い。また,その反面,リスク(この場合は専ら「流動性リスク」を蔑ろにした「営業姿勢」が一部の投信会社に見られることは眉をひそめるべき事だろう。具体的な銘柄や投信会社は名指ししないが,募集時には「慎重な投資」を約束していた某国市場に結局なし崩し的に資金を投入し,世界金融恐慌の混乱でその市場が閉鎖に近い状況になると「解約受付を停止した」と「日経ヴェリタス」に報道されていた某投信などはその悪しき見本といって良いだろう。結局,米国流の投資銀行モデルの猿真似で手数料欲しさのビジネスをやっているから投資家の資金を傷つけるのではないかと思わざるを得ない。というのも,この投資信託の説明会なるものに顔を出した時,説明者である投信会社の幹部の説明に疑問を持ち「ベンチマーク」について具体的な質問をしたが,満足な回答を得られなかったという実体験があるからだ。☆ このように「投資銀行モデル」の脆弱さは個別の商品レベルでは如実に出てくるのだが,それを意識的に突き進んでいくことにおいて,ペレグリンの「墜落」と今回の金融恐慌との相似形は示唆深いものがあると思う。そして小説ではサイドストーリーとして描かれたパキスタンという国の国情を思い,さらにかの「投信」の行く末をも考える時,なかなか複雑な思いを抱いてしまうのである。=了=
Oct 21, 2008
-

アジアの隼 (4)
アジアの隼(下)☆ 黒木亮の小説の特徴は「イヤな奴はいるが,ワルい奴はあまりいない」というところかなと思う。例えば清水一行であれば「集団」シリーズの初期の作品のように,ワルい奴は徹底的に悪く描く。そこに悪の「凄み」をもたせるためであろう。清水が小説を書かなくなってきたのは,彼が描きたいような「凄み」を持ったキャラクターがいなくなってきたからで,堀江(貴文)とか村上(世彰)では「小物過ぎる」ということだろう。☆ だからこのタイプの小説を書かせれば,やはり高杉良ということになるが,高杉だったら悪役はもっと露骨に書くだろう。昔からそうなのだが高杉という人は正邪に拘る。それは彼の小説のバックボーンであり,戦うミドルを描かせて彼の右に出る小説家はいなかったし,これからも出ないだろう。清水や高杉より前の世代の小説家,例えば城山三郎や小島直記は,経済人つまり人そのものを描いていった。しかし清水が『兜町』で描いたものは勿論人でもあるが,それ以上に市場という「人の群れ」だった。ここに業界から財界までの「人の群れ」を描く「経済小説」のジャンルが確立し,後は人を中心に描くのか,事件を中心に描くのかという分け方になっていった。☆ 高杉良が描くのは勿論「人」とその集団としての「カイシャ」であった。彼にとってカイシャは人が生き生きと戦う戦場であり,同時に悪役が権謀術数を巡らす舞台でもあった。そういえ描き方をして高杉は清水を超えていったのだが,黒木亮は高杉的な正邪二元論を慎重に避けているように思える。
Oct 20, 2008
全53件 (53件中 1-50件目)











