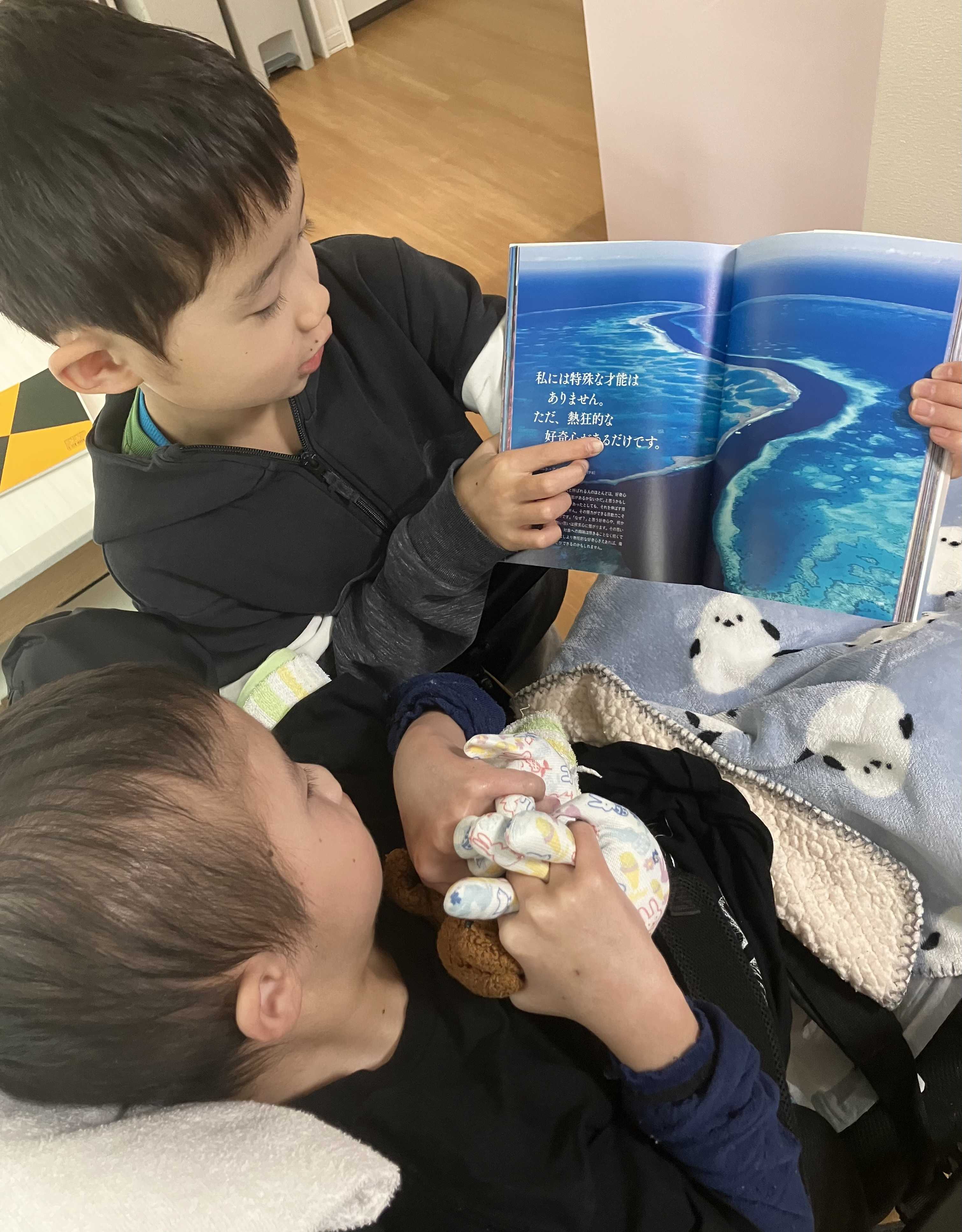2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

読了:「ウチのシステムはなぜ使えない」
いつもご訪問頂き、ありがとうございます。今日も長い通勤時間を利用し、一日で読み切ってしまった書籍の紹介です。タイトルは「ウチのシステムはなぜ使えない」で、システム屋としては気になる一冊です。この本は企業のITシステムに関し、なかなか思うように導入できない現状を指摘しています。「高いお金を払ったのに使いにくい」「少し変更したいだけなのにお金がかかる」「システムが動くまでに時間がかかる」といった不満を、働く人の視点から説明しています。ITシステムを開発しするのはSE(システム・エンジニア)と呼ばれる人たち。それを導入する(買う)側はユーザと呼ばれる、(概して)コンピュータに詳しくない人たち。コンピュータやITシステムというと、かっこいい印象があるかもしれません。ですが、実際に作っているのは紛れもなく生身の人間。人と人とが、どんなシステムにしたいか打合せをしながら作っていくものです。打合せをしていると、自然に人間関係や交渉などの機会が増えていくもの。その中から、会社の中でも政治的な動きがあり、うやむやに進んでいくことも。「なぜこんな機能が?」などと疑問に思うこともよくありますね。本のサブタイトルに「SEとユーザの失敗学」とある通り、こうした人間関係からシステム導入が“いかに失敗していくか”を小気味良く描ききっています。正直、一般的なシステム開発側の人間から見ると頭に来ることが多いかもしれません。ですが、私の場合は本当の意味での「顧客第一主義」を最優先に考えています。もちろん元SEという立場上、業界の裏側もよくわかっており、うなずけることは多いです。ですので、私は頭に来るというよりは、甚く共感しました。できれば、今までにシステム導入で失敗したことがあるような企業様、失敗したことはないけれども、大きな投資をしようとしている企業様には読んで欲しい一冊です。システム業界に造詣がなければ、是非とも事前対策として、お奨めできる一冊です。今後「使えないシステム」が少しでも減るよう、私も微力ながら尽くしたいと思っています。応援クリックは励みになります!ではでは~。---「ウチのシステムはなぜ使えない」です。
October 31, 2008
コメント(3)
-

生産性分析の基礎(2) - 財務・会計の問題
おはようございます。いつもご覧頂き、ありがとうございます。昨日に続き、中小企業診断士の財務・会計分野から生産性分析についてです。今日は生産性分析のいくつかの指標を紹介します。(参考:06年度1次試験 第9問)労働による付加価値は、労働力の生産性として労働生産性と呼ばれる指標で示されます。労働生産性は付加価値生産性とも呼び、企業における従業員1人あたりの付加価値額のことを表します。労働生産性 = 付加価値額 / 従業員数この労働生産性は、3つの観点から計算式を分解して求めることが出来ます。[1]売上高による分解 労働生産性 = 売上高/従業員数 × 付加価値額/売上高 (付加価値額/売上高 は、付加価値率と言います。)[2]有形固定資産による分解 労働生産性 = 有形固定資産/従業員数 × 付加価値額/有形固定資産 (有形固定資産/従業員数 は、資本装備率(労働装備率)と言い、 付加価値額/有形固定資産 は、資本生産性(設備生産性)と言います。)[3]人件費による分解 労働生産性 = 人件費/従業員数 ÷ 人件費/付加価値額 (人件費/付加価値額 は、労働分配率と言います。)付加価値率や、労働分配率といった指標も基本的な公式になっています。掛け算や割り算が入り混じっていますが、こういった公式の理解も必要ですね。日々、一歩一歩勉強です。応援クリックは励みになります!ではでは~。---うちの娘の大好物ですが、さすがにこれは持ってません。。。
October 30, 2008
コメント(2)
-

生産性分析の基礎(1) - 財務・会計の問題
おはようございます。いつもご覧頂き、ありがとうございます。今日は中小企業診断士の財務・会計分野から生産性分析についてです。まずは生産性分析の付加価値について紹介します。(参考:06年度1次試験 第9問)生産性とは、いかに効率よく価値を生み出すかという効率を表す指標です。ここでの「価値」を金額に換算したものが、付加価値額です。付加価値額の定義には色々ありますが、日銀方式が代表的なものです。その定義は、以下のようなものです。付加価値額 =税引き後経常利益+人件費+賃借料+他人資本利子+租税公課+減価償却費租税公課には、固定資産税などがあります。人件費には、福利厚生費などがあります。賃借料には、不動産賃借料などがあります。過去問では、「付加価値に含まれるものを選択せよ」と問われました。この辺りを理解していれば、簡単に解けるはずの基本的な問題でした。簡単ですが、今日はこの辺で。明日は生産性分析の具体的な指標をいくつか紹介します。応援クリックは励みになります!ではでは~。---最近は仕事で肩や腰の凝りが激しく・・・血流を良くしたいものです。
October 29, 2008
コメント(0)
-

読了:「運命を拓く」
いつもご訪問頂き、ありがとうございます。最近は客先への電車通勤の時間が4時間近く(往復)になり、読書量が増えました。その中から、今日は「運命を拓く」の紹介です。まず著者の中村天風(てんぷう)ですが、私はこの本を読むまで全く知りませんでした。40年も前に92歳で亡くなっているのですが、私の生まれる前なので尚更かもしれません。でも、意外と言っては失礼ですが、かなり有名だったのですね。そんな著者は日露戦争時代に活躍し、死刑寸前や不治の病から生還しました。その時の“悟り”を世に広く教え、伝えるための本が「運命を拓く」です。最初は単なる精神論かとも思っていましたが、良い意味で期待を裏切られました。人生を生きる目的や病に対する心構え、“理想”とは何か、などを見事に説明し切ります。個人的には、この本を読めば拝金主義的な心の狭さから解放され、前向きに生きるための哲学を得ることができると思っています。満員電車の混雑や仕事でのストレス、小さいことですぐ怒るようなこと、損したことを他人のせいにすること、そういったことのマイナス面から解放されます。私も通勤電車で読んでいて、思わず自分が恥ずかしくなりました。少し前までは仕事がうまくいかないと、何かしらの理由をつけて、他人のせいにしていましたが、今は全く考え方が変わりました。「早く帰りたい」「きつい」「苦しい」「嫌だ」「やりたくない」「お前が悪い」「景気が悪いせいだ」などの言葉は、聞いている他人の心に悪影響を及ぼします。ネガティブ発言は、他人を不幸にする犯罪のようなものです。そんなことも、本を読めば心に刻まれていくはずです。少し昔の言葉なので、読みにくい箇所があるかもしれません。ですが、それでも心に深く感じる“何か”があるはずです。個人的には手放したくない一冊です。クリック応援はとても励みになります!ではでは~。---「運命を拓く」です。
October 28, 2008
コメント(2)
-

原価計算制度の基礎(3) - 財務・会計の問題
おはようございます。今日もご訪問頂き、ありがとうございます。昨日に引き続き、中小企業診断士の財務・会計分野から原価計算制度についてです。今日は総合原価計算の少し詳しい内容です。(参考:06年度1次試験 第8問)総合原価計算では、発生原価を直接材料費と加工費とに分けて計算します。直接材料費は一昨日の日記の通り。加工費とは、一昨日の日記で直接材料費以外の5つ(間接材料費、直接労務費、間接労務費、直接経費、間接経費)のことを言います。実際のケースとしてはいくつか存在するのですが、過去問で出たのは次のようなものです。・前月に生産を開始した製品が、前月中にすべては完成せずに仕掛品(中間製品)として 当月に繰り越され、かつ当月に生産を開始した製品の一部も仕掛品として残った場合詳しい事例は割愛しますが、期首仕掛品が存在する場合、期首仕掛品の原価と当期の総製造費用を、完成品と期末の仕掛品に配分する必要があります。その配分方法には、以下の3種類があります。(1)先入先出法 期首の仕掛品を優先的に完成させ、その後に当期の生産開始品(の一部)を完成させる方法(2)後入先出法 当期の生産開始品を優先的に完成させ、その後に期首の仕掛品(の一部)を完成させる方法(3)平均法 期首の仕掛品と当期の生産開始品を、平均的に完成させていく方法難しいようですが、実例を挙げられるともう少しわかりやすいかもしれませんね。が、そこまで行くとさすがに日記が難しくなり過ぎるので、控えておきます。(笑)応援クリックは励みになります!ではでは~。---発酵食品は健康に良いと聞きます。私も最近はずっと継続しています。
October 27, 2008
コメント(2)
-

原価計算制度の基礎(2) - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もありがとうございます。昨日に引き続き、中小企業診断士の財務・会計分野から原価計算制度についてです。まずは、今日は原価計算の種類についてです。(参考:06年度1次試験 第8問)原価計算は、3つの切り口でそれぞれ二種類に分類できます。[1]個別生産か、一括大量生産かという切り口による分類 (1)個別原価計算 受注生産(個別生産)の形態で採用される製品原価の計算方法 (2)総合原価計算 一括大量生産の形態で採用される製品原価の計算方法[2]製品の製造前か、製造後という切り口による分類 (1)実際原価計算 製品製造のための原価を、製品の製造後に把握する原価計算の方法 (2)標準原価計算 製品原価を製造前に標準的な原価として設定し、実際の原価と比較し改善していく方法[3]どのように営業利益を計算するか、という切り口による分類 (1)全部原価計算 製品が販売された期間の売上・販売費・一般管理費と、製品全体の原価から 販売量に該当する製品原価を計算し、これらを計算することで営業利益を算出する方法 (2)直接原価計算 原価を変動費と固定費に分類し、以下の計算から営業利益を算出する方法 貢献利益 = 売上高 - 変動費 営業利益 = 貢献利益 - 固定費ひとくちに原価計算と言っても、色々な切り口から呼び方があるんですね。明日は、過去問で出題された総合原価計算について、少し詳しく紹介します。応援クリックは励みになります!ではでは~。---ちょっと前から欲しい一品。誰かにプレゼントしてもらいたいです。
October 26, 2008
コメント(0)
-

原価計算制度の基礎(1) - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もご訪問頂き、誠にありがとうございます。今日は中小企業診断士の財務・会計分野から原価計算制度についてです。まずは基本的な内容として、原価の種類と構成についてです。(参考:06年度1次試験 第7問)原価計算とは、企業活動における原価などを、経営者に対して説明(明らかに)したり、関係者に対して情報を開示するための理論や方法のこと、です。法律的には、制度会計と共に、利害関係者のために製造原価の明細を開示するための制度が決められており、これを原価計算制度と言います。原価の分類として、以下の三つの観点から分類されます。ここで原価とは、「事業活動で消費された経済的資源をお金に換算し測定したもの」です。[1]原価の職能による分類 原価は、職能(事業活動への使われ方)によって、以下の三つに分類されます。 (1)製造原価・・・製品の製造活動(材料、労務など)に要した原価 (2)販売費・・・販売活動(販売員活動、広告宣伝など)に要した原価 (3)一般管理費・・・一般管理活動(減価償却など)に要した原価 また、(1)~(3)の合計金額を「総原価」と言います。 総原価 = 製造原価 + 販売費 + 一般管理費[2]製造原価の、形態による分類 製品を製造する際の形態(種類)によって、上記(1)の製造原価は以下のように分類されます。 {1}材料費・・・製造に使用する材料、部品などの費用(原材料費、部品費など) {2}労務費・・・労働者への費用(工員の賃金・福利厚生費など) {3}経費・・・{1}{2}以外の費用(工場建物の減価償却費や水道光熱費など)[3]製造原価の、製品との関連による分類 個々の製品に直接関連しているかどうかにより、製造原価は以下のように分類されます。 {1}製造直接費・・・材料費など、製品との関係が明白なもの(車ならタイヤ4個) {2}製造間接費・・・複数の製品で共通に消費されるもの(工具、減価償却費など)なお、[1]と[2]の掛け合わせにより、製造原価は以下のように分類されます。 a) 直接材料費・・・材料費 × 製造直接費 b) 間接材料費・・・材料費 × 製造間接費 c) 直接労務費・・・労務費 × 製造直接費 d) 間接労務費・・・労務費 × 製造間接費 e) 直接経費・・・ 経 費 × 製造直接費 f) 間接経費・・・ 経 費 × 製造間接費原価の分類だけでも、これだけ覚えることがあるんですね。製造業の企業ではここまで考えなければいけません。う~ん、奥が深い。明日は原価計算の種類の基本事項を紹介します。応援して頂けるとうれしいです!ではでは~。---楽天さんも色々なサービスがあるんですね。
October 25, 2008
コメント(9)
-

税効果会計の基礎(2) - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もご訪問頂き、ありがとうございます!昨日に引き続き、中小企業診断士の財務・会計分野から税効果会計についてです。今日は基本的な内容(2)です。(参考:06年度1次試験 第7問)税効果会計においては、税効果会計を適用するか否かにより差異を以下の2つに分類します。差異とは、企業会計上の「収益・費用」と法人税法上の「益金・損金」との、認識時点の相違などによって生じた、企業会計上の「資産・負債」の金額と法人税法上の「資産・負債」の金額との差額のことです。(1)一時差異 差異が生じている「資産・負債」が将来、売却や決済されることにより、解消されます。 税効果会計を適用し、法人税等を適切に期間配分します。 (例:繰延税金資産) ・棚卸資産評価損の損金不算入額 ・引当金の繰入限度超過額の損金不算入額 ・減価償却費の償却限度超過額の損金不算入額 ・その他有価証券評価損の損金不算入額など (例:繰延税金負債) ・(利益処分方式による)圧縮記帳の損金算入額など 法人税等を繰り延べる(前払い)か、見越計上する(先送り)かにより、以下の2つに分類されます。 (1)-1:将来減算一時差異 一時差異が解消するときに(将来)、その期の課税所得を減算する効果を持つものです。 一時差異の発生時には、法人税等を繰り延べることで、その期の課税所得が加算されます。 (1)-2:将来加算一時差異 一時差異が解消するときに(将来)、その期の課税所得を加算する効果を持つものです。 一時差異の発生時には、法人税等を見越計上することで、その期の課税所得が減算されます。(2)永久差異 差異が永久に解消されないもので、税効果会計を適用しません。 (例) ・受取配当金の益金不算入額 ・交際費の損金不算入額 ・寄付金の損金不算入額 ・罰科金の損金不算入額色々な難しい言葉が出てきましたが、毎日少しずつ覚えていくと良いですね。日々、少しずつ頑張りましょう。よろしければクリックを!ではでは~。---電車の社内広告で見て、欲しくなりました。歩くだけで痩せるのは良いですね。
October 24, 2008
コメント(0)
-

税効果会計の基礎(1) - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もご覧頂き、ありがとうございます!今日は中小企業診断士の財務・会計分野から税効果会計についてです。まずは基本的な内容です。(参考:06年度1次試験 第7問)税効果会計とは、『会計上の収益/費用と、税法上の益金/損金の認識時点の相違などがある場合に、「法人税、住民税及び事業税」の額を適切に期間配分することにより、これらの税額を税引前当期純利益に対応させる手段のこと』を言います。何だか難しいですが、要は「税金を前払い/先送りできる」場合があるということです。税効果会計では、基本的に以下の3つの勘定科目を使用します。(1)繰延税金資産 これは聞いたことがあるかもしれませんね。 法人税等を繰り述べる(前払いする)場合に計上される借方科目(資産勘定)です。(2)繰延税金負債 (1)の逆で、法人税等を見越計上(先送り)する場合に計上される貸方科目(負債勘定)です。(3)法人税等調整額 法人税等を繰り述べる/見越計上する場合に計上される科目です。 (1)や(2)に対応する形で、貸方/借方に計上し、法人税等から控除/加算します。「借方」や「貸方」というのは仕訳における処理のことですね。簿記で右や左に勘定科目と金額を記載し、取引を処理していくようなものです。明日は税効果会計における「差異」の考え方を紹介します。よろしければクリックを!ではでは~。---オフィスの必需品。眠い時は助かりますね。
October 23, 2008
コメント(3)
-

キャッシュフロー計算書とその種類 - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もご訪問頂き、ありがとうございます!今日も昨日に引き続きで、営業活動によるキャッシュフローの簡単な紹介です。(参考:06年度1次試験 第6問)キャッシュフロー計算書の作成方法には、直接法と間接法があります。何が違うかと言うと、営業活動によるキャッシュフローの書き方が違います。二つの記述法は、具体的に下記のようになっています。(+,-は健全な会社の場合)I.営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) 営業収入(+) 原材料又は商品の仕入れによる支出(-) 人件費の支出(-) その他の営業支出(-) 小 計(+) 利息及び配当金の受取額(+) 利息の支払額(-) 法人税等の支払額(-) 営業活動によるキャッシュ・フロー(合計)(+)II.営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) 税引前当期純利益/損失(+) 減価償却費(+) 減損損失(+) 貸倒引当金の増加額(+) 受取利息及び受取配当金(-)(*1) 支払利息(+) 為替差損(+) 有形固定資産売却益(-) 損害賠償損失(+) 売上債権の増加額(-) たな卸資産の減少額(+) 仕入債務の減少額(-) 小 計(+) 利息及び配当金の受取額(+)(*2) 利息の支払額(-) 法人税等の支払額(-) 営業活動によるキャッシュ・フロー(合計)(+)表記法は異なりますが、最終的な値(合計値)は同じ値になります。一見すると間接法の方が、項目が多くて難しいように見えますが、日本企業では間接法を採用している場合が多いようです。なぜなら、直接法の場合は決算時に様々な値を集計する必要があり、逆に手間がかかるからです。ここで注意したいのが、間接法における*1と*2です。名称も指しているものもすごく似てますね。過去問の出題もここからでした。ですが、プラス/マイナスが逆ですし、もちろん値(絶対値)も変わります。(詳細略)個人的に苦手なこの領域ですが、少しずつ勉強していっているところです。よろしければクリックを!ではでは~。---まさかとは思いましたが、こんなものも買えてしまうんですね。。。
October 22, 2008
コメント(2)
-

キャッシュフロー計算書とその種類 - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もご訪問頂き、ありがとうございます!今日は中小企業診断士の財務・会計分野からキャッシュフロー計算書についてです。まずは基本的な内容です。(参考:06年度1次試験 第6問)日本では、2000年3月期からキャッシュフロー計算書というものが財務諸表に追加されました。それまでは貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)が「財務二表」と呼ばれていました。キャッシュフロー計算書の定義は以下のようなものです。「2期の現金及び現金同等物(キャッシュ)の増減(フロー)の明細を、2期の貸借対照表の 各勘定科目の差額と、損益計算書の数値から明らかにしたもの。」現金及び現金同等物とは、現金、預金、3ヶ月以内の定期預金などのことです。このキャッシュフロー計算書には以下の三種類があります。健全な企業は、(1)がプラス、(2)(3)がマイナスで、合計がプラスだと言われています。(1)営業活動によるキャッシュフロー 営業損益計算の対象となった取引や、投資活動・財務活動以外の取引による キャッシュフローを記載したものです。企業の本業なので、プラスの方が良いですね。(2)投資活動によるキャッシュフロー 固定資産の取得・購入、現金同等物に含まれない短期投資の取得・売却による キャッシュフローを記載したものです。将来に向けての投資なので、マイナスの方が良いですね。 投資を行っていないと、将来の営業キャッシュフローが悪くなってしまいます。(3)財務活動によるキャッシュフロー 資金の調達および返済によるキャッシュフローを記載したものです。 この値がプラスということは、借金の返済よりも借り入れが多いことと同じような意味になる ため、マイナスの方が良いですね。昨日の日記で紹介した『「1秒!」で財務諸表を読む方法』にもキャッシュフロー計算書を読むポイントが書かれています。短時間でポイントだけ押さえたい人にはお奨めです。明日は営業活動によるキャッシュフローについて、少し詳しく見てみましょう。よろしければクリックを!ではでは~。---我が家では寒くなってくるとシーズンに何度か食べています。山梨にも出かけたりします。
October 21, 2008
コメント(2)
-

いつかは乗りたいBMW
こんにちは。いつもご訪問頂き、ありがとうございます。今日はいつもの難しい話から少し外れて、個人的な興味から、です。我が家は子供のいる3人家族。(もうすぐ4人目も。)家も車庫も狭く、今は国産7人乗りの四角い小型車に乗っています。でも、個人的には学生時代からドライブ好きです。今夏も 500km を12時間かけて、のんびり5箇所の「道の駅」を回ってきたり。ガソリンが値上げしても、特に「車での外出を控える」ようなこともありませんでした。そんな私の個人的な夢は、やはりいつかは外車で気持ちよくドライブしたい。外車といっても色々ありますが、BMWが好きですね。BMWは実走したことがないのですが「コーナリングがスムーズ」と良く聞きます。コーナーを曲がる時の、国産車で感じる遠心力をあまり感じないようですね。今乗っている車は、車高が高いので遠心力も強いのです。家族で乗る時は、乗り降りしやすくてとても良いです。が、やはり将来的にドライブを楽しむ時は BMW のような車が良いですね。これまで BMW と言うと価格が気にはなっていましたが、かなりお得になっているとのこと。(16,800円/月~の残価設定型もあるようです。最安で 60万円/3年 程度。)しかも、24時間の試乗(貸し出し)もあるとか。週末で1泊2日借りることもできるようです。さらに、オイル交換が 25,000km に 1回で良いというのも、何とも魅力的ですね。参考サイト:今、BMWに乗る理由あとは、スピード違反にさえ気をつければ、というところですね。(笑)すぐには無理にしても、子育てが一段落したらチャレンジしてみたいです。こういった具体的な目標を持つと、仕事にも力が入りますね。よろしければクリックを!ではでは~。---外観もカッコいいですね。
October 20, 2008
コメント(6)
-

読了:『「1秒!」で財務諸表を読む方法』
毎度のご訪問、とてもうれしいです。今日は最近読んだ『「1秒!」で財務諸表を読む方法』小宮一慶著の紹介です。日本企業の財務・会計の分野では、財務諸表というものがとても大事です。この本は、企業活動の結果である財務諸表の読むポイントを簡潔に説明したものです。本の冒頭から、この本のポイントである「1秒で読む方法」が説明されています。それはズバリ!・・・ってそれをここで書いてしまったら意味がないですね。簡単にヒントだけ言うと、短期的に会社が潰れないこと、を1秒で確認できます。(会計に関する知識が多少でもあれば、答えは簡単ですね。)あとは、ROE、ROA、自己資本比率などの聞き慣れた用語もわかりやすく説明されます。個人的に初耳だったのがWACC=加重平均資本調達コストです。一般的に、銀行から借金するよりも出資者に株式を発行する方が支払う利息が多くなります。(もちろん、株式に対する利息とは、配当金などを指します。)なぜなら、出資者は企業に出資するよりも銀行に預けた方が利息が高いのであれば、そんな企業には出資せず、銀行に預けるからです。企業は当然、銀行利息よりも高い配当金を払わなければ、出資者がお金を出してくれません。この借金と出資金の利息(調達コストと言います)の加重平均がWACCです。詳しくは割愛しますが、WACC≦ROA とならなければなりません。あとは、航空会社や携帯電話、自動車、液晶テレビなどの例を用い、会計的な観点からの各企業の動向をわかりやすく説明しています。財務・会計が苦手な私にも、とてもわかりやすい1冊でした。よろしければクリックを!ではでは~。---『「1秒!」で財務諸表を読む方法』です。
October 19, 2008
コメント(4)
-

特殊商品売買の形態 - 財務・会計の問題
こんにちは。いつも応援頂きありがとうございます!今日も昨日に引き続き、中小企業診断士の財務・会計の問題です。(参考:06年度1次試験 第3問)本屋さんや携帯電話など、特殊商品の販売方法にはいくつかの種類があります。最近は携帯電話の「割賦販売」が有名ですが、整理してみましょう。(1)委託販売 商品の販売を代理店などに委託し、手数料を払って商品を販売する形態です。 原則として販売基準により受託者が委託品を販売した日に売上収益を計上します。 例外的に、仕切清算書(売上計算書)が都度送付されている場合は、仕切清算書の到達日に 売上収益を計上することも出来ます。(2)割賦販売 商品を引き渡した後、月賦などの方法により売上代金を数回に分割して回収する販売形態です。 原則として販売基準に基づき、商品を引き渡した時に売上収益を計上します。 例外的に、割賦金の入金(回収)日に売上収入を計上する回収基準や、割賦金の回収期限 到来の日に売上収入を計上する回収期限到来基準に基づく認識基準もあります。 私の au の携帯電話はこの割賦販売になっています。(3)試用販売 取引先に商品を発送し、一定の期間使用してもらい、取引先が買取りの意思表示をした時に はじめて売買契約が成立する販売形態です。 商品の発送時点ではなく、販売基準で取引先が買取りの意思表示をした時に売上収入を計上します。(4)予約販売 代金を前もって予約金として受け取り、後から商品の引渡しを行う販売形態です。 予約金を受け取った時点ではなく、商品を発送または受け渡した時点で売上収益を計上します。 これも販売基準となります。昨日の日記に書きましたが、これらは全て販売基準=実現主義ですね。それにしても、世の中には色々な販売形態があるものですね。よろしければクリックを!ではでは~。---私も時々飲んでます。血流を良くしたいのと、目の健康のために。
October 18, 2008
コメント(4)
-

収益と費用の認識の基準 - 財務・会計の問題
こんにちは。今日もありがとうございます!今日から中小企業診断士の問題も、財務・会計分野になります。(私の苦手領域です。)(参考:06年度1次試験 第3問)企業会計においては、取引の結果をどの時点で計上するかに応じていくつかの形態があります。(1)現金主義 収益を現金収入があった時に、費用は現金支出があった時に計上する考え方です。 基本的に最近の企業では、現金主義会計では期間損益を正確に把握できなくなっています。 営業債権という、納品とお金の流れの時間にタイムラグが生じているからですね。(2)実現主義 モノを提供し、その対価を受け取る/受け取りが確実になった時点で収益を計上する考え方です。 一般的には販売の時点で収益が計上されるため、「販売基準」と呼ばれています。(3)発生主義 現金の受け払いとは関係なく、収益または費用をその「発生を意味する経済的事実」に 基づいて、発生した金額だけを計上する考え方です。 今日の会計は原則的にこれを採用していますが、現実的には(2)実現主義を採ることが多いです。ちょっと(2)と(3)の区別が難しいですね。(3)は、発生時に客観的な測定が不可能なため、(2)を採用することがほとんどのようです。個人的には、(1)と(3)(=(2))を覚えておけば良いのかと思っています。よろしければクリックを!ではでは~。---個人的にはうなぎよりこちらの方が好きです。
October 17, 2008
コメント(2)
-

IT関係の仕事に役立つWebシステムの全体像
おはようございます。いつも応援頂きありがとうございます!今日は「意外と知らないWebツールの全体像」というコラムからです。http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080627/309636/IT関係の仕事をしていると、インターネットには仕事に役立つ情報やツールが多くあります。例えば、個人で使う電子メールやスケジュール/タスク管理のツールなど。情報収集や発信のためにはブログ、RSSリーダー、ソーシャル・ブックマークなどがあります。これらは、IT関係に限らず、色々な用途に使えますね。無料で使えるWebメールとしては、GmailやYahooメールなどがありますね。ブログというのは、まさに今使っているものですね。ブログを対象とした検索を「ブログ検索」と言ったりしますが、楽天ブログにもありますね。(私のブログの場合、トップページの左側にある「Keyword Search」というものが該当します。)ここからブログを検索すると、好みの似たブログを発見できるはずです。RSSリーダーというのは、色々なWebサイトから情報を集めて表示してくれるツールです。楽天日記からも、こちらのRSSリーダーが提供されています。好きなWebサイトに関し、最初の1度だけは登録しておく必要があるので、少し手間はかかります。ソーシャル・ブックマークとは、ブラウザの「お気に入り」と同じような情報をWebサイト(インターネット)上に保存するものです。外出先からもいつもと同じお気に入りを参照することが出来ますね。また、他の人のお気に入り情報を参照できたり、集計されてトレンドがわかったりします。覚えるのが大変かもしれませんが、色々と試してみると発見がありそうですね。よろしければクリックを!ではでは~。---個人的に腕時計は大好きで、スケルトンの機械式↓も持っています。
October 16, 2008
コメント(3)
-

情報の非対称性 - 経済学・経済政策の問題
こんにちは。いつも応援頂きありがとうございます!今日も中小企業診断士の経済学・経済政策に関する問題からです。(参考:06年度1次試験 第14問)経済用語に「情報の非対称性」というものがあります。これは、「市場における各取引主体が保有する情報に差があるとき、その不均等な情報構造のことを指す」ものです。(All Aboutから引用。)情報の非対称性には、大きく2種類あります。・逆選択(逆淘汰):契約(取引)前に、既に情報の非対称性が存在している状況・モラルハザード:契約(取引)後に、情報の非対称性が発生する状況前者には、中古車の流通や保険会社の加入者などの例があります。例えば中古車の質は、売り手は知っていますが、買い手にはわからない事が多いです。そのため、質の悪い中古車のせいで中古車全体の価格が下がり、質の良い中古車が市場に出回らなくなるようなことがおきます。これを逆選択と言います。後者には、会社への出資者と出資された会社の経営者のような例があります。例えば、会社の経営が悪くなると、出資者は会社のことを助けるために債権放棄(という取引)を行ってあげます。しかし、経営者はそれに乗じて経営努力をしなくなることがあります。ただ、出資者からは経営努力の状況がわかりません。これをモラルハザードと言います。同じ「情報の非対称性」でも、契約(取引)前と後では呼び方が違うんですね。ややこしいものです。よろしければクリックを!ではでは~。---お腹がすくと、甘いものを食べたくなるのは「食欲の秋」のせい?
October 15, 2008
コメント(4)
-

読了:「呼吸入門」
いつも応援頂き、誠にありがとうございます。今日は最近読んだ「呼吸入門」齋藤孝著の感想です。出身大学の教授でもあり(直接関わりはありませんでしたが)、齋藤先生は大好きです。齋藤先生は若き頃から「呼吸学」を研究していたとてもユニークな方です。この本では、日本の文化と呼吸方法を結び付け、日本人の私には心から共感できました。具体的には「3秒吸って2秒止め、15秒で吐く」これを6セット=2分。それだけで集中力が高まり、それが持続できる。誰でも簡単に出来て、極めて安全なもの。私も試してみました。通勤電車の中で試すと、心も落ち着き、混雑した車内でも冷静にいられたりします。もちろん集中力が高まるので、眠くなることも少なく、勉強や読書に没頭できます。「誰でも簡単、安全に」というのが良いですね。いつでもどこでも試せます。ただ、最初は難しいかもしれません。特に「15秒で吐く」ということが。齋藤先生も書いていますが、息の長いことは誇るべきことですが、現代人には難しいですね。浅く短い口呼吸が増えてきた現代人は、鼻から息を吸ったり吐くことも減ってきた、と。もう一つ、リラックス法というのに着目しました。気持ちがこもっていたり、集中力が持続できなくなってきた時に効果的です。「体を揺さぶり、息をハッハッとどんどん吐く方法」というものが紹介されています。自分の中から吐き出すものをどんどん吐き、体の中を入れ替える感覚でやってみましょう。実際にやってみると、確かに頭の中がスッキリし、目の前のやるべき事に集中できます。これは、早朝に軽い運動を行って目を覚ますのと同じようなものかもしれませんね。一通り読み終える頃には、すっかり呼吸人間になっていると思いますよ。ストレス社会の今日ですが、意外と簡単なことでストレス解消できそうです。よろしければクリックを!ではでは~。---もちろん、今日は「呼吸入門」です。文庫なので1,2日で読めますよ!
October 14, 2008
コメント(6)
-

規模の経済性、範囲の経済性 - 経済学・経済政策の問題
こんにちは。いつも応援頂きありがとうございます!今日も中小企業診断士の経済学・経済政策に関する問題からです。(参考:06年度1次試験 第11問)企業において製品を生産する際に「たくさん作ると安くできる」というのは何となくわかると思います。これを経済学の用語として「規模の経済性」や「範囲の経済性」と言います。規模の経済性とは、製品1個あたりのコストが、生産する数を増やすことによって減少していくことを指します。まさに、たくさん作ると安くなる、ということです。一方、範囲の経済性とは、異なる製品を併せて作った時に、それぞれの製品だけを作る場合より1個あたりのコストが安くなる、ということを指します。例えばパンとピザを作るとき、パンだけを作ったりピザだけを作るとそれなりのコストがかかりますが、両方とも併せて作れば合計のコストは安くなる、というものです。個人的には「範囲の経済性」を誤解していました。まだまだ勉強が足りないですね。今日は簡単ですが、ここまでです。よろしければクリックを!ではでは~。---太らずあっさり血液循環もよく、よく飲んでます。杜仲茶。
October 13, 2008
コメント(9)
-

ミーティングや会議では、コンフリクトを想定して事前準備しよう。
こんにちは。いつもご訪問頂きありがとうございます!今日は会議や打合せに関する「半歩先を行って先手を打とう!」というコラムから。http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080613/308036/以前もブログで書きましたが、仕事はやはり事前準備が大事ですよね。以前はインタビューやヒアリングについて書きましたが、今日は会議/打合せについてです。会議/打合せには主催者がいて、参加者を招集することがほとんどだと思います。少なくとも、その主催者はアジェンダ(プログラム)は事前に用意すべきですよね。次に考えるのが、会議/打合せでの席順。どのような机・椅子のレイアウトで、誰がどこに座るか。お客様や上司・部下、同僚やライバルなど、立場や心理面を考慮して座る必要がありますね。対立しやすい人が正面に座ると、場の空気が重くなりがちです。さらに、人間関係にも気をつける必要があります。議論が白熱してくると、利害関係の対立からつい感情的な罵り合いになることがあります。こんな時は、事前のアジェンダから外れても、まずは人間関係の修復に注力する必要があります。最後に、意見のコンフリクト(衝突)が生じても、結論をまとめる必要があります。この場合は意見の食い違う点を明確にし、お互いの根拠を確認し、参加者でアイデアを出し合い、全員が合意できる結論を導かなければなりません。とりあえず結論を先送りする手段もありますが、いつまでもそうはできないですよね。こんなことを頭に入れて事前準備を進めれば、きっと会議はうまく行きますね。改めて考え直してみると勉強になります。よろしければクリックを!ではでは~。---昨日は朝から腹痛が…季節の変わり目だからか、仕事が忙しいせいか。常備薬にしたいものです。
October 12, 2008
コメント(7)
-

国際貿易に関する地域経済統合のパターン - 経済学・経済政策の問題
こんにちは。今日もご覧頂きありがとうございます!定番となりつつある、中小企業診断士の経済学・経済政策に関する問題からです。(参考:06年度1次試験 第10問)国際貿易においては、欧米やアジアで地域経済統合が進んでいます。代表的なものに、EU(欧州)、NAFTA(北米)、AFTA(東南アジア)などがあります。ニュースなどで名前くらいは聞いたことがあるでしょうか。この地域経済統合について、B.バラッサ(経済学者)はいくつかの段階分けをしています。それは、統合の強さに応じて、レベルが緩い順に以下のようなものです。(1)自由貿易地域(協定):FTA 域内貿易の自由化を推進する一方で、域外に対しては加盟国が独自の貿易政策を発動する(2)関税同盟 域内貿易の自由化を推進し、域外に対しては加盟国が共同で貿易政策を発動する(3)共同市場 関税同盟(2)を基盤として、労働や資本など生産要素の域内自由移動を認める(4)経済同盟 共同市場(3)を基盤として、マクロ経済政策の強調を図る(5)完全な経済統合 経済同盟(4)を基盤として、政治的統合をも含むだんだん結合がきつくなる(統合されていく)様子がわかりますね。自由貿易協定(FTA)というのは、割とメジャーなので聞いたことがあると思います。中小企業診断士としては、こういった貿易に関する知識も必要なのですね。よろしければクリックを!ではでは~。---寒い夜は少しアルコールで暖まらないと。個人的に大好きなワインです。
October 11, 2008
コメント(4)
-

世界に一つだけの花と分業制
いつもご訪問頂き、誠にありがとうございます!先日、ラジオを聞いていたら「世界に一つだけの花」が流れていました。2003年のSMAPの歌で、たった5年なのにかなり懐かしく感じました。ご存知の通り「No.1ではなくて、オンリー1でいいじゃないか」という歌です。(そんな内容だったと思っていますが、あってますよね?)その歌を聴いていて、「分業の進んだ世の中、自分の役割を全うしよう」と思いました。今の社会は極めて分業が進んでいます。経営・企画・開発・生産・営業・保守という会社の中での役割分担であったり、農業、漁業、小売業、卸業、製造業、サービス業という業種の分担であったり。家庭内でも主婦(家事・子育て)と亭主(金稼ぎ)であったり。個人的には知的好奇心と言いますか、色々なことに興味があります。経営・税務・営業・法務・システム開発・コンサルティングなどの仕事面から投資・子育て・掃除・リフォーム・スポーツ・ドライブなどプライベート・趣味に至るまで。でも、限られた時間で全てを極める(納得するまで突き詰める)ことは非常に難しいです。で、世界に一つだけの花ではありませんが「♪一人一人違う種を持つ~」ので、自分の得意とする/好きな分野に集中し、「♪その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい」のかな、と考えさせられました。やりたいことはたくさんあっても、今はやるべきではない。(それだけで生活が成り立てば別ですが。)それよりも、自分の役割を極められるよう、一生懸命に進もう。そんなことを考えさせられました。よろしければクリックを!ではでは~。---これで「血液サラサラ」になるかな?
October 10, 2008
コメント(2)
-

日本の財政状況(06年時点) - 経済学・経済政策の基礎問題
おはようございます。本日のご訪問、誠に感謝致します。今日も中小企業診断士の経済学・経済政策に関する問題からです。(参考:06年度1次試験 第6問)近年(06年当時)の日本の財政状況について、いくつかまとめました。□最近はあまり聞かなくなりましたが、「三位一体改革」をご存知でしょうか?(1)国から地方への補助金を削減する(2)国から地方へ税源を委譲する(3)地方交付税を見直すこの3点を同時に行うことです。同時なので「三位一体」なのですね。□直接税と間接税ってご存知でしょうか?納める人が直接納めるのが直接税、間接税は消費税のように払う人と納める人が違うものです。日本では消費税導入後、国税に占める間接税の割合が上昇しています。□「国民負担率」ってご存知でしょうか? 以下の(1)と(2)の合計値のことです。(1)租税負担率=租税負担額/国民所得(2)社会保障負担率=社会保障負担額/国民所得日本では国民負担率が上昇傾向にあります。□「プライマリーバランス」をご存知でしょうか?これは、国債発行を除く歳入と、借金に対する元利支払いを除く歳出との差額のことです。日本ではプライマリーバランスが赤字状態ですが、政府はこれを2011年に黒字化すると言っています。中小企業診断士の問題としては、上記のような内容の一部を誤って記載し、「どれが間違えているでしょうか?」というようなものでした。基本的な内容とはいえ、なかなか全てを覚えているわけでもないので、難しいですね。。。よろしければクリックを!ではでは~。---UFO?のようにも見えますね。きれい好きな私はどうしても欲しい逸品です!
October 9, 2008
コメント(4)
-

あとはタイミングを見極めて参戦するのみ!
こんにちは。いつもありがとうございます!昨日、ついに日経平均が(一時的に)1万円を割り込みましたね。この状況はいつまで続くのでしょう・・・少し不安ですね。私も少々、証券会社にお金を預け、株式投資を嗜んではおります。が、昨今の右肩下がりの状況から、持ち株の評価も思い切りマイナスです。。。長期にわたり、塩漬けするしかなさそうです。日本ではバブルやITバブルの崩壊というものを経験しておりますが、今回は世界規模の金融バブル崩壊のような感じですね。(「バブル」と言うと金融の領域なので「金融バブル」という言い方は正しくないかも。)とは言いながら、いずれはこの危機的な状況も収まり、成長に向けて舵を切るはずです。何年か前から顕著になってきましたが、自分の資産は自分で守り、育てるしかありません。今は間違いなく「下り坂」の状況ですが、いずれは「上り坂」になるはず。そう信じて、タイミングを見極めたいですね。よろしければクリックを!ではでは~。---こちらのキャンペーンにも参加しています。
October 8, 2008
コメント(6)
-

近年の日本銀行による金融政策 - 経済学・経済政策の基礎問題
いつもちょっと難しいかもしれないブログを読んで頂き、ありがとうございます。今日は中小企業診断士の経済学・経済政策に関する問題からです。(参考:06年度1次試験 第5問)近年の日銀の金融政策についてですが、「公定歩合」ってご存知ですか?日本銀行が市中銀行(我々が目にする銀行)などにお金を貸す際の基準金利のことです。日銀は、95年頃から公定歩合を 0.5%以下 とすることで、景気を下支えしようとしました。(現在の公定歩合は 07年2月に引き上げられ、0.75%)ところが市中銀行が銀行間でお金を貸し借りできるようになり、公定歩合よりも「無担保コール翌日物金利(短期金利)」というものが重要になってきました。日銀もこの「短期金利」に目をつけ、99年頃から 0.1% 未満という金利が設定されました。これがいわゆるゼロ金利政策、というものです。しかし、これも景気の下支えにはならず、次に日銀が目標とした指標が「日銀当座預金残高」です。日銀当座預金残高とは、市中銀行などの日本銀行に対する預金のことです。市中銀行は持っている預金総額の一定割合を日銀に預ける義務があります。日銀は「買いオペ」と言われる、市中銀行の持つ手形や債権の買い取りを行いました。すると、市中銀行の預金は増え、必然的に日銀当座預金残高も増えるというわけです。こうして今では目標を達成しつつ、一般に流通するお金の量を増やし、景気を支えようとしています。参考URL:http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ko/koteibuai.htmlhttp://fp.st23.arena.ne.jp/interest.htmhttp://kw.allabout.co.jp/words/w000086/%E5%85%AC%E5%AE%9A%E6%AD%A9%E5%90%88/http://manabow.com/qa/nichigintouzayokin.htmlすごく難しいようですが、これも経済政策の一般知識なのですね。よろしければクリックを!ではでは~。---実家から送ってきた新米を食べました。やっぱりいいですね。(^o^)
October 7, 2008
コメント(2)
-

モノを安く買えるのは喜ばしいこと!?
いつもご覧頂き、ありがとうございます!さてさて、今日は「モノを安く買えるのは喜ばしいこと」と題して考えてみました。巷では100/99円ショップや激安のお店が流行ってますよね。私もよく利用させてもらっています。本当に安いので懐には大助かりです。でも「安い」ということは、よほど大量に売れないと、ビジネス上は苦しいですよね。特にシステム(ソフト)開発などですと、原価のほとんどが人件費。安く買えるということは、それだけ原価が抑えられているということ。小売業でも同じですよね、最後は人件費が抑えられてしまう。某ファーストフードの「名ばかり管理職」による残業代不支払問題、のように。消費者の視点で考えると、同じモノなら安いほうが良いのですが、生産者(提供者)の視点で見ると、安く売ってしまうと従業員が苦しむことになります。自分はどちらの立場でしょう?自分の身内はどちらの立場でしょう?例えば、主婦の方が安く買えて喜んでも働いている旦那さんの給料は上がらない、のような。モノを安く買えて喜んで良いのやら、結果として給料が上がらないことで悲しむことなのか。モノを買う(消費する)ことで会社が潤い、世帯の給料が増えてまた消費に使われる、こういった流れを「経済は循環する」と言ったりするのですね。まぁ世界規模での分業が進んだ今では、経済の構図はそれほど単純ではないですが。いつも消費者の立場で安売りを喜んでいますが、自分で事業をすると厳しいものです。などと考えてしまった今日この頃でした。よろしければクリックを!ではでは~。---キャンペーンに協力しています!私も何度かこれで旅行に行きました。お得ですね。
October 6, 2008
コメント(3)
-

スパム・ブログにもイロイロ
いつもご覧頂き、ありがとうございます!今日は「スパム・ブログ」についてです。以前もブログで書いたような気がしますが、今日はスパム・ブログの種類についてです。そもそも、「スパム・ブログ」とは広告収入や営利/悪意目的のサイトへの誘導を目的としたブログです。機械的に生成されることが多いのですが、以下のような種類があります。○アフィリエイト・スパム 商品写真とアフィリエイトのリンクだけを書いたブログ。 機械で自動的に作られるため、感想や口コミはほとんど書いていません。○引用スパム 他のブログやコラム、ニュース記事などをそのままコピーしただけのブログ。 これも専用のツールがあり、機械的にブログを書き込むことができるようです。○自動マルチポスト 同じ内容の記事を、複数のブログに、大量に投稿することです。 これも専用のツールがあるらしいです。(私は使ったことありませんが。) 怪しいと思ったら、記事のキーワードで Google などから検索すると、 複数のブログがヒットすることもありますね。「スパム・ブログ」という言葉は知っていましたが、色々な種類があるんですね。より詳しくはこちらのサイトを。(クイズ形式です。)http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080617/308512/スパム・ブログで浪費しないようにしましょうね。お金も時間も。# 私のブログは毎日ちゃんと自分で書いてますよ、念の為(笑)。よろしければクリックを!ではでは~。---密かに応援している会社の商品です。
October 5, 2008
コメント(8)
-

GDPとGNP - 経済学・経済政策の基礎問題
毎度のご訪問、誠にありがとうございます。今日は中小企業診断士の経済学・経済政策に関する問題から。(参考:06年度1次試験 第1問)GNP(国民総生産)とGDP(国内総生産)という言葉をご存知でしょうか?中学生くらいのときに社会の勉強で習ったような・・・という感じでしょうか。GNPというのは簡単に言うと、日本人による総生産を表しています。GDPというのは簡単に言うと、(地理的に)日本の中での総生産を表しています。読んで字のごとく、という感じですね。(いずれも日本の場合)GDPに関しては、他にも大事なこんな用語があります。実質GDP:物価の変動の影響を取り除き、一年で生産された財(*)の本当の価値を算出したもの名目GDP:一年の経済活動の水準を算出したもの。全ての財の生産数量×市場価格の合計値GDPデフレータ-:物価動向を把握するための指数の一つ。GDPの計算をする上で使う物価指数(野村證券の証券用語解説集より)(*)財とは、簡単に言うと製商品などによる価値のこと。物価の動きに関係なく、絶対的な金額を表したようなものが名目GDP、物価の動きを考慮し、本当の意味での経済規模を表したのが実質GDP、なんですね。また、経済学の中では「名目○○=実質○○×物価水準」というあるルール(公式)のようなものがあります。それに当てはめると、「名目GDP=実質GDP×GDPデフレータ-」となります。何だか難しそうな話ですが、経済学の世界では極めて基本的な内容です。これからも時々中小企業診断士関係の日記を書きますので、一緒に勉強しましょう!よろしければクリックを!ではでは~。---寒くなってくると越前のが気になります・・・
October 4, 2008
コメント(10)
-

携帯で絵文字チャット!
いつも日記を見て頂き、ありがとうございます!最近、仕事の関係で携帯電話の「絵文字」を扱う機会がありました。携帯電話で気軽に使っている絵文字ですが、システム側では意外と取り扱いが大変です。色々と調べていると、非常に有益なPHPのライブラリを発見!MobilePictogramConverterhttp://php-develop.org/MobilePictogramConverter/開発を個人で進められているようですが、とても助かります。さて、これを使って(仕事とは別に)「絵文字チャット」というものを作ってみました。それがこちら→絵文字チャット(α版)http://pc.matrix.jp/trial/e_chat/chat.phpテストメッセージが残っていますが(笑)、絵文字の入った言葉を登録できると思います。手元に au の機種しかなかったので、とりあえずそれで試してみました。DoCoMo や SoftBank にも対応できていると思います。また、登録した内容をメールで送ることもできます。メールの宛先が、パソコンや他のキャリアの携帯でも絵文字が見れます!(のはず)匿名でのメールとなってしまうため、悪用しないで下さいね。迷惑メールの温床にでもなりそうでしたら、サービスを停止することがあります。(苦笑)また、悪質な書き込みも無条件に削除させて頂く事があります。(連続書込み防止や、認証のためのメールアドレス入力などの機能を設けるかもしれません。)今は誰でも匿名で書き込むことが出来ます。将来的には、あるグループで秘密のチャットルームを作れるようにしようと思っています。乞うご期待!よろしければクリックを!ではでは~。---急に寒くなってきたせいか、朝から頭痛が・・・
October 3, 2008
コメント(6)
-

インタビュースキルを上げよう!(その2)
今日もご訪問、ありがとうございます!いきなりですが、訂正です。昨日の日記で『明日は「ヒアリング」について』と書いていましたが、「インタビュー」について、の間違いです。自分でも混同していたかもしれません。(笑)それでは本編です。インタビューとは、相手の潜在的な考えを含めて聞き出すことです。では具体的にどのように進めればよいのか?答えは、簡単に言うと、「準備をしっかりすること」です。それだけです。具体的な準備の方法としては、以下のようなものがあります。・インタビューシートを用意すること(目的、進め方、質問内容、期待する/しないことなど)・内容をあらかじめ伝えておくこと(インタビューシートや添付資料など)・インタビュー相手について、事前に調べておくこと(年代、性別、役職、目的意識など)また、インタビュー開始時には以下のような重要点があります。・アイスブレーク(硬い雰囲気やお互いの緊張を解きほぐすこと)・ラポール(相手との心と心のつながり)を築くこと・インタビューの目的や流れを確認することここまでくれば、あとはオープン質問で深掘りしていくだけですね。(って、それも難しかったりするのですが。。。)もっと詳細を知りたい方はこちらのコラムを。相手から考えや要望を引き出すインタビュー・スキル一口にインタビューとは言っても、奥が深いですね。私も今後の仕事で参考にできそうです。よろしければクリックを!ではでは~。---昨日に続き、今日は「鍋」特集
October 2, 2008
コメント(6)
-

インタビュースキルを上げよう!(その1)
今日も私のページにアクセス頂き、感謝致します。さて、今日はインタビュースキルを上げよう!ということで、その第一回です。第二回は明日のブログにする予定です。普段の仕事などでインタビューを行う機会はどのくらいあるでしょうか?インタビューは、相手から考えや要望、情報などを聞き出すコミュニケーション手段です。そこでは、明確になっていない(潜在的な)考えを引き出す必要もあります。私の場合、仕事の際にお客様やチームメンバーにインタビューし、考えている内容、想い、状況などを逐次聞き出す必要があります。ところで、仕事では「ヒアリング」と言ったり「インタビュー」と言ったりすることがありませんか?今日はこの違いを考えてみました。インタビューは、相手の考えを(見えない部分も含めて)聞き出すこと。一方のヒアリングとは、相手からの説明をほぼ一方的に聞くこと。個人的にはそう思っています。我々ですと、「ヒアリング」は現行システムや業務の内容を聞く時、またはお客様のRFP(提案依頼)の内容を聞く時など、お客様が明確に説明したい内容を持っている際に使います。一方、「インタビュー」はこちらから要求を深掘りしたい時などに使います。普段、仕事の場では何気なく使っていた言葉ですが、定義を曖昧にすると混乱を招きそうですね。よろしければクリックを!明日は具体的な「ヒアリング」の進め方やうまく行うためのポイントを紹介します。ではでは~。---関東は急に寒くなり、恋しくなってきました。
October 1, 2008
コメント(8)
全31件 (31件中 1-31件目)
1