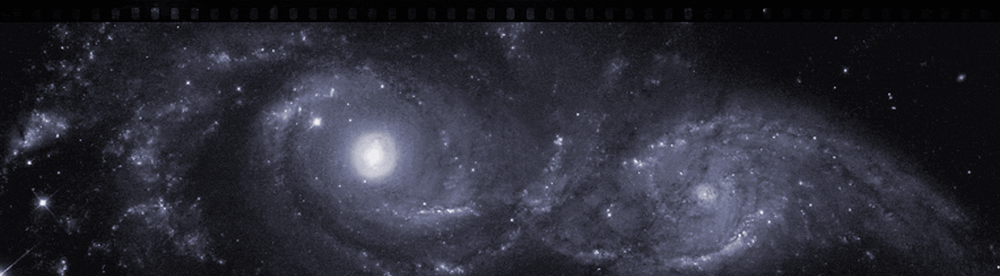2008年03月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
九つの物語 J・D・サリンジャー
一時間かけて書いた文が消えた・・・・。もう一回あの量を書くのはきついから少なめにしよう・・・しかし内容が難解だった。正直いって全く意味のわからない短編もあるし。あらすじついでにちょっと感想バナナフィッシュに最適の日フラニーとゾーイーに名前だけ出てきたシーモア最後の日。解説では人間心理がよく書けているとあるが、まあ確かにそうだがそんな事をいったら全作品を通してサリンジャーの人間心理は凄いものがあるわけで、やはり何故こんなことになってしまったかだけれども、これもどう考えてもフラニーとゾーイーのバディの話と全く同じ事がシーモアにもわかったと考えるほかないと思う。コネチカットのよろめき叔父さんまったく意味がわからん対エスキモー戦まぢかまったく意味わからん笑い男攻殻機動隊にも出てきた単語、笑い男。原因と結果はわかるけれども、原因と結果の中で何が起こったのか全く理解できない作品。小舟のところで子供の心理というかなんというか考え方?みたいなのが凄いと思う。エズメのために戦場で傷ついた男の傷を少女の手紙が癒すというただそれだけの話なんだが、なんかしらんが滅茶苦茶泣いた。超泣いた。自分でもびっくり愛しき口もとはみどり皮肉なジョークがきいた精神異常者の怖さを書いた短編だとおもったが違うかもしれない。ド・ドーミエ=スミスの青の時代痛い中二病患者が慌てふためくさまを読んで楽しみ小説だと思った例によって違うかもしれないテディーやたらと頭のいい少年が、仏教的なモノノ考え方で大人をやりこめる話?しかしやけに印象に残る話だった。何はともあれ大人になるにつれて誰しもくだらない人間になっていくというのは全くわかる話であるし。やはりサリンジャーの凄いところといえば、これもまた勝手に思っているだけだが意味はよくわからないけれど、凄いという事だけはわかるというところだろうか。あるいは意味わからないけれども、重大な意図が隠れているように思わせる能力か(本当に隠れているんだが)村上春樹もそんな感じ・・・。九つのうちそのどれもが、丁寧な描写に彩られたとても面白い小説であったのはいうまでもない。まったく意味がわからなかったと書いたコネチカットのよろめき叔父さん、対エスキモー戦まぢかにおいてもそれは同様である。 何かとっかかりを与えてくれるような作品なのだ。---------------------------ネタバレ有----------------------------------------バナナフィッシュに最適の日これはやっぱりシーモアが死んだのは少女と出会って、天啓を得たからとしか考えられん。それ以外の考え方が何かあるとしたらなんだろうなぁ。現時点ではこれぐらいしかおもいつかん・・・。笑い男どう考えても男の最後のストーリーが悲惨な話になってしまったのは女の人と関係してるっていうのはわかる。わかるが、その内容にどんな暗示的な内容が含まれているのかまでは全くわからんな。いったい何が彼をそんなにやさぐれた気分にさせてしまったんだろうと想像するほかない。単純にフラれた、とかそんな話じゃなさそうだが・・・。このトラウマを植え付けられた子供たちがはたしてどうなるのか・・・全く想像もつかん。エズメのために────愛と惨めさをこめて少し大人びたエズメの優しさ?愛?しか感じられないぜ・・・。まぁしかし、明らかに狙って感動させようとしたシーンでもあるので泣いてしまったのは少々不覚というか悔しいという気がしないでもないが・・・。主人公の名前が伏字になっていて、ほとんどのものはそれが誰かわからないだろうと書いてあるがきっとそれは照れ隠しのようなものであって、実際にはすぐにそれが誰だかわかる・・・と思う。手紙はやばい。手紙は反則だって・・。精神を病んだX軍曹殿が救われる描写には胸が表れるようだ。できる事なら全部書きたいがそんな事をしても無駄だ。全部書けないなら一部分だって書く意味はないというそれぐらい完成された文だった。そのあとの部分を引用するXはこの手紙をすぐには脇に置く気にならず、むろんエズメの父の腕時計を箱から取り出そうとも思わなかった。やっと腕時計を手に取ったとき、ガラスが郵送中に壊れたのに気づいた。他の所もダメになりはしなかったろうかと思ったが、ネジを巻いて試してみる勇気はなかった。彼はただその時計を手に持ってまたしても長い間じっと座っていた。やがて不意にうっとりとした気持ちになり、眠くなった。 エズメよ、彼は本当に眠たくなったのだよ。本当に眠たくなって眠れば、彼はそのうちに精神と体のあらゆる能力が無事な人間に戻ることができるのだよ。眠りって大切だなぁー。愛らしき口もとはみどり二人で寝てる男女の元に、男の友人から妻が帰ってこないどうしようと電話がかかってくる話なのだが、最後の反応を見るとどうも男の隣で寝てるのが友人の妻なんだよなぁ?それで妻が帰ってきたーと男の友人がいってるのはそれは気がくるって幻覚でもみてるって事だと思ったんだが・・・違うかもしれないな・・・。ド・ドーミエ=スミスの青の時代痛すぎる・・・・。設定年齢は19歳ということだが、サリンジャーがこれを書いた時代を考えるとまだ寿命も短くて19歳でも十分立派な大人としてものの見方が出来るようになってて当然の年齢だと思うんだが・・・・今の19歳ならまだわからないが。メールの語尾にハートマークがついてるからこの子は俺の事を好きだと勘違いしちゃう男の子ぐらい痛いぞ・・・テディー「ぼくたちを絶えず少しずつ変えることができなければ、ぼくたちを愛することは出来そうもないんだ。両親はぼくたちを愛すると同じ程度に、ぼくたちを愛する理由を愛している。ほとんど理由の方を愛しているといってもいいくらいだ。そういうのはよくない」これはようするに、女の人があの人形かわいいーっていっている自分を愛しているのと同じような話か。親も自分の理想とする子供に子供をしたくてそれに近づけようと頑張っていると。ありのままの子供を愛そうとする親は思いのほか少ないのかもしれない。自分の個人的見解から言わせてもらえば、親が子供の才能を潰すことはたくさんあっても、親が子供の才能を伸ばすことはない。「万物が神だということが分かって、髪が逆立ったりしたのは六歳の時だった。今でも覚えているけど、あれは日曜日だった。妹は本の赤ん坊で、まだミルクを飲んでいた。ところが突如として、妹が神で、ミルクも神だってことがわかったんだ。つまり、妹がしていたことは、神の中に神を注ぎ込みことにほかならない。ぼくのいうことがわかるかな?」六歳にしてシッダールタが厳しい修行のすえにつかんだ真理に到達するとは末恐ろしい子供よ!テディーがいいたいのはとどのつまり、この世のものはすべて何でもありだということだろう。というか、考えるだけ無駄ということか。考えるという行為自体がそもそも間違っているというような、いや違うか。感情とか、物が長いとか高いとか安いとかうるさいとかそういったものが全部個人の価値観から来たものである以上それに意味なんてないとかそういった感じである「良心やいろんな人が教えた事をすっかり取り出して子どもたちの頭をからっぽにしてやる。もし両親から象は大きいと教えられていたら、そいつを追い出して頭を空にしてやる。象が大きいのは、他のものと──たとえば犬だの女の人だのと──比べた時だけなのだから」「色は名称にすぎないから、草が緑だと教えれば、子供たちはあるひとつの見方で──教えた人の見方で──草を見るようになってしまい、同じくらいまともな別の見方、いやたぶんもっといい見方でみなくなる・・・・・」大人になるにつれて何もかもダメになっていくんだ・・・・という気分にさせられてしまうよ。この理論からいったら、生まれた瞬間何の先入観もなしにすべてを自分解釈していかなきゃいけないんだから。これはこれであれだな。この考え方は、何よりも大事なものだと思うよ。まだ色々書きたい事はあるけれども、さすがに疲れてしまった。おしまい
2008.03.29
コメント(0)
-
フラニーとゾーイー J.D.サリンジャー
サリンジャーなめてたな。あらすじヒステリックになって喚き散らし、苦悩の果てに大学にも行かずひきこもるフラニー。そしてそれを説得しようとするゾーイー。感想 ネタバレ無自分でもよくわからなくなってきたのだけれども、あらすじって必要なのだろうか。いや、もちろん自分が読み返す時にあれ、どんな話だったっけ・・・という時にあらすじがあったら連鎖反応式に思い出せそうだという微妙な打算あってのあらすじ、なのだけれども。そんな事は置いておいて、おいておいてって何か面白いな。いやどうでもいいんだ。作品の中でやってる事は別になんてことない事、といえるだろう。現にこんな感じの茶番をやってる人たちは、時代を問わずいただろうから。問題はそれを書くのがサリンジャーだった、という事だ。正直に言って、読んでいる最中に異様な感動を覚えていた。読んでいる最中にヤバイヤバイこの作品おもしろすぎる・・・。という感動を覚えた事は、片手で数えられるぐらいあった(この表現おかしい)けれども、それともちょっと違う。なんというか、展開にひきこまれたら上のような感動を覚えると思う。または書いてある事が人を感動させるようなセリフであったら、感動するだろう。どうでもいいけれど人を感動させるというのはかなり簡単な事だと、思う。正直いって、その簡単な方法で人を感動させようとする作品は、嫌いだ。だから、何に感動したのかというと、こんな表現があったのか・・という感動である。何も比喩が優れているとか、そういう話じゃない。文章の隅々に状況をにおわせる描写が隠れていて、わかりやすいのに膨大な情報量を持っているというのが、率直な感想。つまんない事を説明するのに長々と文章を書くのはもうこりごりだな。世界とズレている感覚という、なんとも表現しがたいものを生々しいものを表現されていたと、そう思う。なんとも書きづらいものではあるのだが、そう思ったのだからそう書いておこう。一見フラニーは青春期にありがちな悩みをもった若者、という感じに見えるが、自分は早く大人になりすぎたがゆえに生じるズレ、というものを感じた。要するにすでに若者ではないということだ。才能が一つ多い方が、才能が一つ少ないよりも危険である。──ニーチェというように、フラニーの苦悩は才能が一つ多いが故の苦悩ではないかと。多くのことを中途半端に知るよりは何も知らないほうがいい。他人の見解に便乗して賢者になるくらいなら、むしろ自力だけに頼る愚者であるほうがましだ。 ──ニーチェ ―「ツァラトゥストラかく語りき」―まさかのニーチェ二連続!しかしこの本から感じるのは、ニーチェ的な思想なのであった。フラニーは自力だけの愚者であろうとして、そうなりきれなかったのだと感想を吐かせてもらう。----------------------ネタバレ有-----------------------聡明に思えるフラニーが、どうしてレーンみたいな人間を愛しているのかがさっぱり理解出来ないが、それが理解出来たといったらそれは愛が理解出来たという事になるのだろうか。つまりこの場合は理解できない方が正解、だといいのう。フラニーが、世の中全ての事に我慢出来ない、といった感じで世間のつまらないところについてぶったぎっていく。「それもたまんないことの一つなの。つまり、あの人たちは本当の詩人じゃないってこと。あの人たちはジャンジャン出版されたりアンソロジーに入ったりする詩を書いてる人っていうだけのことよ。でも詩人じゃないわ」「なんていうかなあ、詩人ならばね、何かきれいなものがあると思うの。つまりね、読み終わったりなんかしたあとに、何かきれいなものが残るはずだと思うの。あなたの言う人たちは、きれいなものなんか、ひとつも、これっぽちも残しやしないわ。ちょっとましな場合だって、こう、相手の頭の中に入り込んで、底に何かを残すというのがせいぜいじゃない? でも、だからといって、何かを残すすべを心得ているからと言って、それが詩だとは限らない。そうでしょ? なんか、すごく魅力的な文体で書かれた排泄物──と言うと下品だけど、そういうものにすぎないかもわかんない。マンリウスとか、エスポジトとか、ああいったご連中みたいに」日本の作家で、私の書くものは私の排泄物でしかないといった人がいたが、果たしてだれだったかな・・・。いや、この場合いってることに微妙に相違があるのはわかっているけれどもね。それに微妙に表現が違ったかもしれないし、私が消化した消火物でしかない、といっていたかもしれない。その場合自分の中でいっかい咀嚼して変化させたということで、その意味合いは全く違ったものになるだろうけれども、これを言った人はおそらくサリンジャー的な意味でいったのではないかと思う。この場合のキレイなもの、というのが何かはわからないがすべてのものは劣化コピーだといいたいのかもしれない。詩人であれ作家であれ、何かを創造するときにその元となるものがあるはずなのだ。昔読んだあれがすごかった、とかそういう感情の元に生み出されたものは、それはやはり元の劣化でしかないとそういう考え方なのかもしれない。フラニーの苦悩の根源といってもいいかもしれない「エゴ、エゴ、エゴで、もううんざり。わたしのエゴもみんなのエゴも。誰も彼も、何でもいいからものになりたい、人目に立つようなことなんかをやりたい、人から興味を持たれるような人間になりたいって、そればっかしなんだもの、わたしはうんざり。いやらしいわ──ほんとに、ほんとなんだから。人がなんと言おうと、わたしは平気」誰だって人に褒められたいと思っているし、男だったら女の子の前だったらいつだってかっこつけたくてそっけないふりをするし、とにかくいつだって誰だって、自分のことを認めてもらいたいんだ、というそんな単純な人間の心理が全部嫌になってしまって、さらに自分すらもそう考えている事がたまらなく嫌だという。だったら山にでもこもって誰ともかかわらない生活を送ればいいという話だけれども、それが出来ない自分が嫌いなんだと、そういっているわけだ。そんな事目の前にいる人間にいわれたら、じゃあもう勝手にしてくれ、ばいばいってなりそうだが耐えて聞き続けているレーンは凄いと思うよ。一番最初にどうしてレーンみたいな、なんてことを書いたけれども、まぁいいやつだなぁとは、思う。場面かわってバディからゾーイーにあてた手紙の中から重要と思われる話があったので書く。バディが肉の売り場にいたら、4歳ぐらいの少女がバディの事をじっと見上げる、バディはあなたは今日私が見た中でまず一番きれいな女の子だと言ってやった。このロリコンめ!と思わず心の中で叫んだがそれはまあどうでもいいんだ。バディは彼女にボーイフレンドがいっぱいいると考え、聞くと頷く、そして何人かと訊くと こっから引用彼女は指を二本差しだした。「二人!」と僕は言ったね「そりゃまたずいぶんたくさんですねえ。その人たちのお名前は何ていうの、お嬢ちゃん」すると、彼女は、つんざくような声で言ったんだ「ボビーとドロシー」ってね。僕は羊の肉をひっつかむと一散に駈け出したね。 しかし、この手紙を書かしたのは、まさにこの出来事なんだ~中略~今日の午後、あの子が自分ノボーイ・フレンドの名前を、ボビーとドロシーだって、そう僕に言ったあの瞬間、僕は完全に伝達可能な真理(ラム・チョップ的イメージ)を掴んだことは間違いないんだ。この後にシーモアがいったこととして宗教をつきつめて考えると熱いとか寒いとか男とか女とか、見かけだけの相違にとらえられなくなるといっている。何故ここを長々と書いたかというと、ナインストーリーズに書かれているシーモアの最後と符合することがあまりにも多いという事か。シーモアの自殺する直前に、シーモアも少女とあっている、その時に描写はなかったが、自分はバディと同じように完全に伝達可能な心理を得たのではないかと、そう考えている。もっとも物凄い素人意見なので、もうどこかで解釈みたいなのが出ているかもしれないが、それだともう完全にこれは恥ずかしい的外れの意見なのだろうけれども(実際そういう事ばっかりだ)こればっかりは譲ることのできない直観的インスピレーションというやつだ。少女の純真さとか、こう、うまく書けないのだけれども、子供を通して真理を得るというのは全く理解できない話ではない。さらにシーモアは男と女の見かけだけの相違のように生と死の相違も関係なくなってしまったのではないかと。生きてるのも死んでるのも、一緒のことだ、とかなんとかとんでも理論を生み出してすぐに自殺してしまったのじゃないかなぁ。バディはゾーイーに向かって手紙で、母さんには優しくしてやれよ、と書いてあるけれど、そのすぐあとに出てくる母親との会話はとても優しくしてやっている雰囲気ではない。しかしその奥底に流れている愛情というのが、わかるようになっているあたりが、サリンジャーの凄いところだろう。同様なことはフラニーとゾーイーの会話でもいえる。鬱鬱としている人間にむかって、お前がそんな状態だとみんな困るんだよ、ていうかうざいんだよ。そんな風になっているんだったら家にいないで学校でやれよ、とか散々ひどい事を言っている中に愛情が流れているなんて、とてもじゃないがいえないが、それを言っても大丈夫だと信じているその土台のところが愛情なのだ、とそういえるだろう。または絆、か。「俳優の心掛けることはただひとつなんだ。観客のことなんかについて考える権利はきみにはないんだよ。絶対に。とにかく、本当の意味では、ないんだ。分かるだろ、僕のいう意味?」いい小説だったと心から言えるだろう。
2008.03.17
コメント(0)
-
不気味で素朴な囲われた世界 西尾維新
あらすじ平和な学園で殺人事件が起こる!(思いつかんかった!)感想 ネタバレ無さすがにもうまともなミステリーを書く気は無いとみた。いや、もうって言ったら最初はまともなミステリーを書いていたみたいだな・・・・。頑張って推理してみようかと思ったけど無駄だ!わからん!しかしいつもどおりの作風だな。一冊気に入れば他の作品もすべて読めるっていうのは魅力だが、たまにはドシリアスな話でも書いてみてほしいものだ。言葉遊びとか抜きにして・・・。西尾維新の言葉遊びはとどまる事を知らない。何でこんなに色々考えつくのか不思議だ。ていうか、ミステリーで推理して論理的に犯人を導いた事がないんだけど、ミステリーの楽しみ方間違ってるかも知れんな・・・。それとも本格ミステリとかじゃないと普通はわかるようにできてないのかなぁ。わかるようにできているのか、できてないのかすらわからないんだが。それからどのタイミングから推理すればいいのかわからんな。本格ミステリだったらそういうのわかるようになってた気がするんだが。まぁしかしこの作品に関しては推理とは遠いところにあるだろうというのは、わかる。それから、もんだい編。大もんだい編。 みかいけつ編。 えんでぃんぐ。とわかれているが、そのたびにちょっとした漫画が入っていて、それが盛大にネタバレ。簡便してくれ・・・・驚きが減るじゃないか・・・・しかし今回は、徹底的にミステリーという考え?枠組み?を手のひらで転がし続けたな、というのが印象。ミステリーの暗黙のルールをそりゃーないだろ、常識的に考えて、と否定していくミステリーである。 よく漫画や小説の中で、漫画じゃあるまいし・・・というセリフを見るとついつい突っ込みたくなるような、なんかもやもやした気分になるが、読んでいる間ずっとそんな気分だった。表紙が学ランの女の子だが、学ランにはピンと来ない自分であった。-------------------------ネタバレ有--------------------------------思わず笑ってしまった場面 主人公串中弔士とその姉串中小串の会話。「それとも弔士くん、UFO研入る?」「入りませんよ」そこでどんな運動をするのだ。「んー? 前に教えてあげたじゃない。 こうやてねえ。みんなでおててを繋いで、『ジェントラージェントラー、スペースピープル』って言って宇宙人を呼ぶんだよ」「紳士的な宇宙人が来そうですね・・・」や、やべえ読んでた時は面白かったけど冷静に考えるとあんまり面白くないかな・・・という現象かもしれない・・・。あんまり面白く感じないぞ・・・。2個目「つまりねー、弔士くんはなんだかんだ言って、大人になりたくないだけなんだよ。小理屈こね回してそれっぽいこと言っちゃって、ただ単に、小学校から、中学校に上がって、情緒不安定になってるだけなんだよ」「大人になりたくない・・・・ですか」「そう。ピーターパン将軍だね」「強そうですね・・・・」いやいやいやこれもどうだろう。うーむ、その場のノリって怖いな。きみとぼくの方は妹を溺愛していたがこっちは姉か・・・まぁ溺愛っていうわけではないが。串中弔士という名前は縦で読むと一本筋が通っているが、それだけでつけた名前なんだろうか・・・。しかし一番最初に死ぬのが、串中小串だとは、これは全く予想していなかった。どう考えてもふや子さんが死亡フラグだったのに、どういうことだこれは!作中に、時計の針を戻すことはできない、だが進めることはできるという台詞が、有名なアニメにあるのですけれど とあったが何のアニメかなーと思って調べてみたらエヴァンゲリオンの碇ゲンドウの台詞だった。「進んだ時計の針を戻すことはできないが、自らの手で進めることはできる」しかしトリックをイラストで説明したり、するというのもまぁミステリーには無かったものだろうか。それも含めてミステリーというルールで遊ぶという考えのほかに出てきているものといえば、普通の大人だったら実際の殺人にはトリックなんか使わないだろうという誰もが考えている事、だったりほとんどのミステリーのように完璧な犯罪を犯す人間なんてそんなにいないだろう、という事だったり、ミステリーファンのいうところの、アリバイなどという単語を一般人は知らないんじゃないか? 知らない人間が犯罪をおかしたらどうなるのか? それから人は人の事をそう簡単に殺さない。などなど。まぁ誰でも考えることだが、明らかにトリックなどに使うエネルギーは無駄だという事だな。普通に考えりゃ夜道で後ろから殴って見つからないところにやっとけばあっというまに完全犯罪の出来上がりだし。そもそも人は人の事をそう簡単に殺さないよね、というのももうそのままだろう。少年犯罪の増加みたいに書かれているが、日本に限って言えば殺人の件数は年々下がっているわけですし。だからそれを踏まえた上での話の構成、という事になっている。人が人をそう簡単に殺さないのは、主人公の操作ということで説明がつくし、普通に分別のつく大人がトリックなんて使わない、というところは思いつきで行動してしまう中学生だから、という事だし、犯人だってミスは犯す。現実的じゃない世界の中で現実的な考えを持って行動するキャラクター達だからこそ、漫画や小説の中で、漫画じゃあるまいし・・・という台詞を言ってもそれ程の違和感もなく受け入れられた。「考えてみれば、ミステリー小説ファンの傲慢って言いますかね。誰もがミステリー用語を知っているわけじゃないです──アリバイ、密室、物理トリック、入れ替わり。そんな言葉は普通使わないし、知りもしない。それを失念していました。アリバイという概念を知らない以上、そもそもアリバイ工作がするわけなどない──」どうでもいいけどアリバイ工作がするわけなどないって完全に誤植だよね。しかしまぁそれでも高校生にもなれば、詳しくは知らないまでもアリバイ──の意味ぐらいは知っているだろう。だからこその中学生設定だったのかもしれない。いやまぁ知らないのだけれども、ていうかアリバイの意味を知らない人が中学生にもいるのかと今でも疑問だけれども。スタンガンで何時間も失神していたーみたいな話のところはスタンガンってそんなに何時間も失神してるもんなのか・・・?と心底疑問だったのだが、気を取り戻しそうになるたびにスタンガンを押し当てていた、が正解だとは、さすがにわからなかった・・・。常識じゃ測れないぜ・・・。最後の最後に、病院坂黒猫がやってきて今回のネタバラシ。まるでクビキリサイクルの赤い人みたいだ。ここで全ては串中弔士くんの操作の仕業だったと判明したわけですが、ここで自分を将棋で例えると王将、といったことの真の意味というわけか。自分はほとんど動かずに、周りの駒を動かして勝利を得る、そういう意味で自分を王将とたとえたのだろう。なかなか面白い伏線だった。主人公が周りを操作して小串を殺すかもしれない状況に動かしたことの動機は、二段ベッドの上の段を使いたかったから、というものだが、なんかこのしょうもない動機から砂糖菓子の弾丸は打ち抜けないでも出てきた、あの有名な犯罪心理学の話を思い出したな。夫が死んで、葬式に行ったあと夫の同僚と会い、次に子供が死んだ。母親が犯人だったのだが、何故夫と子供を殺したのか、という問題。正解は夫の同僚に会いたかったから、なのだがそういった他の人には理解できない──ような動機を作りたかったのかもしれない。しかし病院坂迷路、小物すぎて笑ったなぁ。あっさり殺されてしまうなんて・・・。病院坂黒猫が特別だったという事か。
2008.03.14
コメント(0)
-
故郷から10000光年 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア
光年は時間じゃない・・・!距離だ・・・!あらすじ短編が 15個も 入ってる!感想 ネタバレ無前回読んだ老いたる霊長類の星への賛歌、は正直いって読みづらかった作品であったが、こっちは短いものが多い事と、わかりやすい作品が多い事もあって楽であった。ちなみに老いたる霊長類の星への賛歌が読みづらかった理由として、基本的に異世界の話であるから、体が人間とは違う描写が多いんだが、いろんな星系のいろんな登場人物が出てくるから、なんかもう名前とイメージが全く一致しない。さらに新しい用語がぽんぽん出てきて、それの役割を把握するのが非常に困難であった。例をあげるとすると、惑星連合艦隊司令とかわかりやすいのならばいいのだが、転送する際の問題を処理する人間とか、動物レースのルール監視員とか、なんか架空の存在が多すぎて把握するのに時間がかかるのだった。って、この例に出てきたものが出てくるのは故郷から10000光年の方なのだが。今回は主に、故郷に関する短編が集められている。故郷に対する深い思いというのは、言われるまでもなく強いものだろうというのは容易に想像出来る。なんか、うまく書けないのだけれども、故郷が誰にとってもかけがいの無いものであるという事はみんな感じる事が出来ると、思う。生まれた場所であり、帰る場所であるはずなのだ。そういえばいつだって故郷は帰る場所として、書かれている気がする。いや、この短編集の話じゃなくて、世間一般論として。今回はちょっと長丁場になりそうだな・・・。7000文字も書くはめにならないといいんだが・・。さきに気に入った短編をいくつかあげておくと、故郷へ歩いた男。 ハドソン・ベイ毛布よ永遠に。スイミング・プールが干上がるころ待ってるぜ。ビームしておくれ、ふるさとへ。いうまでもなく他の作品も、素晴らしいものであるのだが、自分の中ではこれが面白かった、という事だ。というか、非常に残念な事にあまり集中出来ていなかったのかしらないが、というか十中八九そうなのだけれども最初のいくつかの短編は印象に残っていない。--------------------------ネタバレ有---------------------------マザー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズだが、悲しい事に全く・・・わからなかった・・と言ってしまったら敗北宣言みたいで悔しいけれど、全くその通りだった。読んでる最中は自分の読解力が足りないからわからないのか、それとも最初っからわからないように書かれているのか、それすらもわからなかったが、結局最後までよくわからなかった事を考えるとどうも読解力が足りなかったのだろう。どんな話だったのか、という事がわからなかったのではない、どんな意味があるのかがわからなかった、という事だ。なんか、ラグナロクが巨大なエネルギーをもった物体だということもわかるし、何かから逃げているのもわかるけれど、宇宙シャベルとか石ころ雲をがっちり掘り進んで、トロイ岩にぶつかって爆発した可能性はある。そうすれば、ちょっとした太陽ができる。 とか 正直意味がわからない。石ころ雲・・・?トロイ岩・・・?われらなりに、テラよ、奉じるはきみだけ銀河系規模で、生物にレースをさせようという試み。壮大な話だなぁ。壮大な話は好きだ。ジャンルごとにレースがスタートするわけだが(蜘蛛同士とか恐竜同士とか)そんな都合よく蜘蛛と同じような生物がいたり恐竜がいたりするか・・・・?と思うわけである。他の星にもし知的生命体がいたとしても、それが人間と同じ形をしているということは絶対にありえないというのはもう定説だが、それなら他の動物にだってそういう事がいえるんじゃないかなぁ~とは思うが、よく考えたら知的生命体に限った話だったのかな。まぁそんな重箱の隅をつつくような追及をするのはハードSFだけにしておけっていう話であるが。テラを失った人々が、テラをなつかしがる場面 以下引用。「われらがドームよ、安けきふるさと、みどりのテラいまはなく……」彼はもちろんのこと、十五代前の祖先だってみどりのテラなど知らないし、ドームにさえ住んだことはない。だが心象は深く刻まれていた……地球へ・・・を思い出したなぁ。あれも見たことのない地球に思いこがれて果てしない距離を故郷に向けて旅をする話だった(ちょっと違う)どんなに離れていても、見たことがなくても、その血に記憶が刷り込まれていくのだろうかとそんな感傷にひたることが、出来る場面であった。「われわれの銀河では、母星を失った生物は長く存続しない」「ここでも同じです」クリスマスは重い口調でいった。それは事実だった。みなしご種族はみんな死に絶えてしまうのだ。理由は誰にもわからない……いや、それより、この痛みがなぜ消えないかだ。痛みに耐えて生きてゆくか、あるいは痛みを忘れ、そのうちいなくなってしまうかなのだ。故郷を失うというのは想像も出来ないが何か心の一部がかけてしまうようなものだとは、考える事が出来る。というかこれもうまく書けないなぁ・・・。故郷に関するこのもやもやとした感じが、とても文章に出来そうにない。故郷へ歩いた男故郷へ歩いた男、というタイトルだけでなんかくるものがある自分はきっと故郷オタク(なんだそれ)どうでもいいけれども、こいつが戻ってくる事によって過去で大爆発が起こったならば、こいつはその時点で存在しているんじゃないのか?という事なんだが違うんだろうか。 タイム・パラドックスだ!雷電!いやなんでもないあれかな、こいつが戻ってくる事によって起こった大爆発で死んでしまったのか。そう考えるのが自然だな。一年が彼には二分の一秒ってこんな設定どっかで見たなーと思ったら古橋秀之の短編集でこんなネタがあったな。あっちはあっちで秀逸な短編だった。われわれの過去は彼の未来であり、われわれの未来は彼の過去である。というのは非常になんというか、状況を的確に表していていいなぁと思った。唯一正しい道の周囲はすべて誤りでしかなく、彼の心臓が、血液が、あらゆる細胞がその原子の深みから求めるのは、故郷、故郷!そう、故郷について何がいいたいのかというと、心の奥底から求めるものであるというこの感覚なのだけれども、それがうまく書けなかったのだ・・・。要するに生まれた地に愛着を示すのは精神の本質なんじゃないかと。まぁ規模にもよるけれども。日本に生まれたから日本を故郷と思うのか、地球に生まれたから地球を故郷と思うのか、それとも東京都に生まれたから(ryそこんところもよくわからんよなーハドソン・ベイ毛布よ永遠にこれは地味に一番好きな話だったなー。割とストーリーの内容はありふれている?と言ってもいいぐらいの話なんだが・・・。タイム・トラベル出来る機械がほんとうにごく少数だがある世界の話。たとえばその機械を使って、20年後に行ったら20年後の自分と今の自分の精神が入れ替わって活動できるというもの。もし未来の自分が死んでいたらそれはキャンセルされるだけで特に何も起きない。ここではその機械のことをジャンパーと読んでいるが、先日同名の映画を見に行ったがかなり面白かった って、この話全く関係ないな。ちうか、最高に面白いんだけれどもどこか一場面だけ抜き出して記憶にとどめておくってことができないんだよなーこの話の場合。もし思い返したい場合全部読み返さなきゃならん。ってことで終了。スイミング・プールが干上がるころ待ってるぜこれも非常に面白いんだけれども、またしても一場面だけ抜き出してどうこうっていうのはきつい話だ。 たとえるならば、ドラゴンボールなら、フリーザと闘ってるところは最高に燃えたよな、とか言えるけれど、・・・ってここまで書いたけどいい案が思い浮かばなかった 投げっぱなしジャーマン。ビームしておくれ、ふるさとへ国家は歴史から何一つ学ばないという古言とは裏腹に、アメリカは、ベトナムでの長い苦闘から学び取った証拠を見せた。アメリカが学んだのは、こういうことだった。人民投票、軍事顧問、訓練プログラムなどにかまけて時間をくわれるな。すぐ動け。そして叩きのめせ。なんだか、実際にCIAに勤めていたティプトリーから出てきた言葉だと思うと全く笑えないな。というかこの作品とハドソン・ベイ毛布よ永遠にが個人的には二強であった。特にこの作品は最後のシーンは鳥肌ものだった。死に向かって行く時の様子がおだやかなものなんかじゃなくて、燃え盛るように突っ走っていくものだったり、その燃え盛るような情熱のまま、目的を到達するあたり、というかこれは目的を到達した時に死んだんじゃないかと思うんだがどうだろうなぁ・・・。まぁ十中八九死んじゃいないんだろうが・・・。なんというか、これまた説明できないんだが、命をかけて、最後の最後に目的を達成し、笑ってしんだ。という表現がこの場合一番適切だと思うんだよなぁ。「心配しなくてよい」声が聞こえてきた。声は、キャプテンのコンソールのわきにある球から流れてくるように思われた。「きみがいまどこにいるか教えよう」「わかっています」ホビーはささやき声でいい。泣きながら息を吸い込んだ。「帰ったんだ!」そう叫び、気を失った。
2008.03.12
コメント(0)
-
連射王 上下 川上稔
終わりのクロニクルで有名な川上稔のハードカバー本あらすじ何事に対しても本気になれない主人公は自分が何かに対して本気になれるのかを疑問に思っていた。しかしとある人物との出会いから、方向づけがなされる。その方向とは、シューティングゲームであった。感想 ネタバレ無まぁよくも悪くも川上稔だったかなと。しかしどう考えても最初の方の文章はひどい・・・・。まぁ、何事にも本気になれない主人公が本気になれるものがシューティングゲームだったーやってやるぜーって感じなんだけれども、話がなんだかシューティングゲームを相手にしているにしては、人生の巨大な敵を相手にするかのような書かれ方でそれはそれで結構面白い。ただ、やはり本音を言えばゲームごときに何をマジになっているんだ・・・こいつらは・・・という感じか。しかしそこはやはり必然といえば必然だったのだろう。ただのゲームごとき・・・というままでこの小説を書いたらいったいなんなのかわからなくなってしまう。シューティングゲームを主軸にすえて書こうとした以上、多少大袈裟な表現ばかりになってしまうのもしょうがないのかもしれない。内容に少しふれると、ところどころにシューティングゲームの解説が入る。シューティングゲームの事はちょっとかじっただけでほとんど素人と言っていい自分が知っている事しか書かれていなかったので、本当の中の本当の初心者のみを対象にした解説なのだろう。正直に言って、死ぬほど邪魔だった。というか、正直に言ってしまえば、不覚にも全部読んでしまったがあまり面白いものではなかったな。しかしあえて面白いところをさがそう。さすがにないわけがない。確かに面白い点もなくはないが、というかあるが、それでもそれに負けないだけのいい点も、確かにそんなにあるわけではないけれども、まぁないわけではないわけで。まず解説がついているから、シューティングゲームのことを全く知らない人が読んだら、感謝するだろう。新設設計だ。絵で説明してくれたりするし、さらには巻末にシューティングゲームの歴史まで書いてある。それから真剣に本気になれない・・・と悩んでる人がいたとしたら、自己を肯定してくれような物語に救われる事だろう。それから構成自体は、悪くない。物語作りは、きっとうまいんだろう。それから、青春物語としても成立している。---------------------ネタバレ有---------------------------俺が衝撃を受けた文章以下引用広い、白い空間が有る。長いカウンターと、テーブルが幾つも並ぶ場所。食堂だ。テーブルと椅子にはどれも学生服姿が着いており、壁の時計は十二時五十分を指している。ここは昼休みの学食だ。ソシテカウンターに近いテーブルに、紺色の学生服が一人いる。高村だ。 アwwwwwホwwwwwかwwwwww読んでる時ギャグでやってるのかと思ったわ・・・・。ほとんどの作品を許容してきたものの、これにはさすがに付き合いきれん。まぁさすがにここまで酷いのはここだけだった。もう一回出てきたらさすがに読むのをやめていただろうな。どうでもいいけど、作品中の高校だと授業がある時にゲームセンターに行っていたというそれだけで2週間の停学だとか。なかなか酷い話だ。厳しいなぁ。しかも受験間近の3年生に・・・ちょっとぐらい考えてやってもいいだろうに。しかしそれだけでストレスで吐くとかどんだけ精神的に弱いんだろうという気がしないでもない。下巻の帯の文も地味にひどい。あらゆるゲームの中で難度の高いシューティングゲームを縦横にプレイ出来るものだけが持てる最高の攻撃手の称号であり、そしてゲームが出来ない人々を絶対に楽しませることが可能な、・・・・・ゲームセンター最強の守り手の呼び名。連射王。──と、そういうべきかしら(本文より抜粋)冷静に考えるまでもなくありえないだろ・・・・。ゲームセンター最強の守り手ってなんだよ・・・。いったい何の存在からゲームセンターを守ってんだよ・・・・。まだまだあり得ないことへの突っ込みは終わらないぜ。ゲームセンターで遊んでいるゲームが、うまくできなくてクソっと叩いた人に向かって全力で何しとんねんと全力で鉄拳制裁をするようなゲームセンター狂が作品中で最も信頼されている人だとか大切な人には嘘をついちゃいけないのにおれは嘘をついてしまった・・・!とかいう滅茶苦茶な理論で落ち込みまくる主人公とか、嘘をついたぐらいで見損なったわ・・・とかいうクソヒロインとか色々あるけれども、まぁ全部ひっくるめたら相当に面白くない作品になってしまうんだけれども。大体嘘をつかないとか不可能だろ・・・・私には嘘つかないで・・・!なんていわれたら百年の恋も冷めるわ。そもそも何事に対しても本気になれないとかいうわけのわからない事を悩んだ事が無いから全く主人公が考えている事がわからなかったぜ・・・。考えれば考えるほどつまらない作品に思えてきたからここらでやめようと思う。愚痴にしかならんわ・・・。追記やはりただの愚痴だとつまらん穴が多いな。つまらなかったと書く方が簡単で、たくさん書けるがその分浅いわさ。自分で自分の意見に反論してみよう。自分の作品を滅茶苦茶にけなすとかいう自虐をやった作家が居たような気がするがそれの日記版だな・・・。筒井康隆だったかな。嘘をつくつかないのくだりは、高校生だからという理由もあるだろうなと思った。要するに、若くて純粋な恋愛だなぁという目で見るべきだったのだ。ひねくれてしまった。本気になるならないというのも、思春期特有の問題だろうと思う。要するに青春物語であると、自分で理解しているかのように書いたのにそれを理解してなかったことから前提が間違っていたということだろう。停学などのもろもろのストレスで吐く、という描写も、本人にとってそれがどれだけ重大な出来事だったのかを表す指標だろうか。ゲームセンターで台を叩いたぐらいで本気でぶん殴る男も、本気の表れとしてみることができるかもしれない。たかがゲーム、されどゲームというところだろうか。正直いって、何をゲームにマジになっちゃってるの?という読み方をしたら全く楽しくないだろうが、なるほど、そういう考えもあるのかという読み方なら面白かった・・・・と思う。惜しい事をした。考えが足りなかったか・・・。しかしまぁ文章がきついのは無理。 あとゲームセンター最強の守り手も無理。
2008.03.11
コメント(0)
-
零崎曲識の人間人間 西尾維新
零崎を始めるのも悪くない。あらすじ戯言シリーズではあまり語られることのなかった零崎一族の主要人物について語られる零崎一族シリーズ。今回は3巻目、零崎曲識の話である。感想 ネタバレ無西尾維新の本領発揮というところか。刀語を通して何か引っ張られるんじゃないかという危惧があったが、そんなの全く気にせずに完成させてくれたと、書くべきだろう。やはり、自分の中に確固たる考えがある人だな、という事を感じる。自分で考えられる人なんだなという事だが。何の考えも無しに、人気があるからという理由で小説を動かすような、そんな人ではないだろう。まぁ、最近のライトノベルに対する批判か。伏線の妙や、セオリーを知りながら、それを読む人間の考えまで逆手にとって物語を構築していくやり方は、どこか伊坂幸太郎に通じるものがあると思う。しかしこの人間人間というタイトルの意味がわからんな。人間試験は意味がわかったし、人間ノックもまぁ、わからんでもないけれど・・・。人間人間??本編では、今までほとんど話にかかわってこなかった零崎曲識がいったいどんな人間だったのか、どうやって生きたのかが語られるわけだが(当たり前)まぁしかし、徹底して脇役だな。最後の方は読み終わるのが嫌になるぐらいには気に入った。死で終わる事が決定づけられている話ほど悲しいものはないな、と思う。読み進めたら死んでしまうのだから、読み進めたくなくなるのが人情っていうもんだろうが。おかげで最後の方は読まずにちょっととっておいたぐらいだ。こういうのはやはり、結末を知っているからこその症状だろう。最後が死で終わるとあらかじめ知っている話はだから嫌いなんだ。最近だとFate/zeroも途中で読みたくなくなってしまった。どうでもいいが、おまけのカードは全くもっていらないんだが・・・。何でこんなカードがついてるんだ・・・。しかしまあ、凄く面白かったよ、という事です。----------------------ネタバレ有------------------------------由比ヶ浜ぷに子の絵が刀語に出てきたロボの絵にしか見えない。日和号だったか。しかし、あれだな、こいつも無意味にメイドの格好をしているな。メイド好きだな西尾維新・・・。だが、確か戯言シリーズのほうだったと思うが、メイド服を着ていなくてもそのメイドという魂がいいのだという考えには全くもって同意できないな。メイドという魂をもってなおかつメイド服を着てこそ完全なる全体、メイドになりうるのだ!とそこだけは譲れないところだな。メイド服だけでもメイドじゃないしメイド魂だけでもメイドではないのだ・・・!まったく本筋に関係がないぜ。人間人間のタイトルの意味だが、人間試験が、人間の試験で人間ノックが人間をノックする事だと考えると曲識の場合は人間を操るから人間人間なのだろう。人間を人間するとでも書けばわけがわからないだろうがわかった気にはなれるのじゃないだろうか。ようするに武器に由来するわけかな。しかし人識の出番多かったなぁ。伊織とのセットが多かったが・・・。伊織もかわいすぎるキャラだぜ・・・・。こいつ死ぬんだったっかなぁ、忘れてしまった・・・いや、結末は書かれてなかったかな。ということは零崎一族シリーズ最後の一巻で語られるんだろうか。こっから先は未知の領域だぜい。終わるのは悲しいシリーズだが・・・。零崎一族シリーズだけの終りではなくて、戯言シリーズの世界の完結でもあるのだからな、この先まだ何か起こる事も否定できないが・・・。しかし逃げの曲識、いったいどういったキャラなのかと思ったら、なかなか熱いキャラじゃないか。臆病キャラかと思いきや以外だ。格好いい。「──しかし、『逃げの曲識』くんらしくないと言えば、らしくないですね」「僕らしさというのは、家族が皆殺しにされてもまるで動じず、暢気にピアノを弾き続けていることだろうか?」 曲識はそっと──トランクの中のマラカスに手を伸ばした。「だったら、そんな僕らしさはいらない。らしくないことを、してやるまでさ」予想に反して、熱いキャラだぜ。曲識・・・。意外や意外。零崎一族の中で一番気に入ったキャラになってしまったな。それはもう、かわいいのは抜きにして伊織よりも人識よりも一族史上もっとも長生きした男零崎軋識よりも。武器が楽器というところもいいしな。必然、戦いが精神との、自己との戦いになってくる。そういう所が好みだとも、言えよう。名シーンがたくさんあるんだよなー。こんなに短い話なのに。不思議だ。少女しか殺さなくなった動機の場面とか、初めて自分に合った武器を手にした場面とか、強さについて語り合う人識と出夢や、曲識の最後とか。いやはや、まったく満足ですよ。しかし、重要な場面にことごとく現れる哀川潤はまるで森博嗣の四季のようだなぁ・・・と。おいしいところにタイミングよく現れるところが、もって生まれた才能であり天才というところか。曲識にとってのキーワードが哀川潤だったように、橙にとってのキーワードが戯言だったように、狐さんのキーワードが加速だったように、誰にだって譲れない絶対に譲れないキーワードがあるんだろうな、とそんな事を考えさせられる。曲識にとってのキーワードは。考えるまでもなく──哀川潤だったのだ。零崎一族、『少女趣味』、零崎曲識。死の間際にして──彼の望みは叶った。せめて人間らしく──笑って死んだ。輝ける最後の瞬間、彼は本懐を遂げたのだ。それは確かに、彼が主役であれた瞬間だった。彼が最後に演奏した曲の作品Noは唯一の欠番──十年前、赤い少女に出会った直後に作詞作曲した、入魂の一策タイトルは『ままごと』。けれどそれは誰の目にも明らかな、初恋だった。主人公の死で終わる作品は悪くない。いつだってそれは何か考えさせてくれるから。
2008.03.09
コメント(0)
-
老いたる霊長類の星への賛歌 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア
あらすじたんぺんが 7つ 入ってる汝が半数染色体の心。 エトセトラ、エトセトラ。煙は永遠にたちのぼって。一瞬のいのちの味わい。ヒューストン、ヒューストン、聞こえるか?。ネズミに残酷なことのできない心理学者。 すべてのひとふたたび生まるるを待つ。感想 ネタバレ無どうでもいいけど解説がどの本を読んでも、ティプトリーが女であった事を明かされた事が衝撃的だ!という話しかしなくてイライラさせられる。どの本を読んでも解説といえばそのことだ。もうちょっとましなことかけ、と思わざるをえない。まぁ、それだけの衝撃だったのだろうと推測するだけだが・・・。ちゃんと解説してほしいものだな。しかしこの本も文庫が発行されたのは、1989年か・・・。ずいぶんと昔だなぁ。まだティプトリーの作品で、翻訳されていないものがあるので、そちらも頑張ってもらいたいものだ。短編集って、基本的にその中にはいっているもののなかから、ひとつだけ代表作をとってタイトルにするのが普通だとおもってたけれども、これは違うみたいだ。短編集自体に名前がついている例か。日本の作品だと珍しくない・・かな。内容は染色体XYのに関係する性の話題から、実験動物に対する矛盾などなど。ほとんどすべての作品に共通するテーマのようなものは、生と死 だと思った。最後の短編はそれしか表していない。これを最後にもってきた編集の気持ちもわかるきがする。訳のせいか知らないが、ひどく読みにくかったような気がする。浅倉久志氏のほうが、よかったなぁと思わないでもない。分量も、まぁ翻訳という作業ゆえ仕方ないことであるのだが、ちょっと多い。普通翻訳するとページ数は増えてしまうのだが、それにしても増えすぎでは、という気もする。序文の人は割と好きだ。あえて解説などは不要なものであるといっているティプトリー本人のセリフを持ってきたりして、自虐である。序文でまでもティプトリーショックについて述べているのは本当にもうどうしようもないことだが・・・・。--------------------------------ネタバレ有------------------------------短編も7つしかないから一つずつ書いていくか。汝が半数染色体の心。半数ずつ染色体をもったものが、交互に世代交代をしていく話。非常に説明しづらいが、病気をしない人間のようなものがいて、しかしそれの子供はみすぼらしい存在が生まれてくる。しかしそのみすぼらしい存在から生まれてくるのは病気をしない人間のようなものである。そして当然劣っているものはより優れているものから迫害を受ける。自分達だってありえたかもしれない世界の話でもある。遺伝子という考えのなんと奥深くて精密で危険なものよ。どこかの遺伝子配列が少しでも違っただけで全く違ったものが生まれてくるというそんな恐ろしさを書いたものでもあった。エトセトラ、エトセトラショートショートと言っていいぐらいの長さ。7ページしかない。宇宙をすべて探索しつくしてしまった人たちの話。この先には取り返すことのできない、長い衰退の道があるだけだ。始めてわれわれは、行く手に何もないことを知ったんだとあるけれど、衰退なんて生まれた瞬間に始まっていると思う。限界に達したから衰退をはじめるなんてそんなことあるだろうか。限界なんていう概念がそもそもおかしいし。誰だって生まれた瞬間が一番すぐれている状態で、その瞬間から衰退が始まっていると思う。もちろん、種としても。人間が生まれた瞬間なんてものがあるのかしらないけれど、もしあるとすればそこからすでに衰退ははじまっているとしか思えない。煙は永遠にたちのぼってなんかよんだけどまったく印象にのこってない。変な狂ったやつがなんかしてたようなきがする。スルーで。一瞬のいのちの味わいこれもなんだかものすごい規模の話だったな。一番最初から最後にはあんな話になるなんて全く想像もつかなかった。ちょっと最初から読み返してみたら、一番最初のところに最終的な結論を示している部分があった。ううむ。しかしこれはすでに短編っていう文章量じゃないな。ほとんど中編だぞ。それでいて前半のたらたらとして進まない展開はいらいらさせられたが・・・。地球人が、精子だったという話だ。まとめてしまうとそういう話だったが、それだけだとあまりにも短いな。地球に人間が生まれたのは、いつかどこかにある卵子に飛び込んでいくためだとか凄い発想だなと思った。そのために人は成長して、宇宙に飛び出して、他のものを探し求めていたのだと、・・・・・荒れ野のなかの泉より掬し味わう一瞬のいのち ──ハイヤームつまりこの文が一瞬のいのちの味わいなんだろうな。本編にはあまりそういった描写はないが・・・・。自分たちが人生だとおもっているこの時間は、自分たちより上位のものからしてみれば一瞬の人生なのかもしれないとか、そういうことだろうか。ぜってーちげー ちょっとわかりづらいです。ヒューストン、ヒューストン、聞こえるか?うろうろ宇宙をさまよっていたらいつのまにかタイムジャンプしてて気づいたら200年後で、女しかいない世界にきていた、と。女性と男性を書きたかったんだろうなぁということがわかるぐらいである。ストーリーとしてひかれるところはあまりなかった。ネズミに残酷なことのできない心理学者実験動物として無残にも殺されていくネズミに愛情をもって接してしまう心理学者の話。なんというか、一般人の矛盾をついた作品でもあったと思う。毎日保健所で何千もの動物が死んでいくのに、そこには誰もつっこまないで、身近なところでの動物の死にいつまでも注目するその矛盾。動物園の動物に石を投げる人間に対する批難をしても、動物を檻に閉じ込めて自由を束縛する動物園側に対する批難をしないその矛盾。無残な虐待をかわいそうというくせに実験動物がどんなむごたらしい実験をされても、それは実験だからといって許容するその矛盾。そういう事を書いていた。もっとも、主人公はただのネズミ馬鹿といった感じだったが。しかも最終的にそういった感情をネズミの王に持ってかれて残虐なネズミ殺し野郎に・・・・。すべてのひとふたたび生まるるを待つ生と死の物語。見ただけで相手を殺すとかいう魔眼をもった幼女とかまるでライトノベルみたいな設定の話だが、実際はかなりグロテスクな話でもある。今までの歴史が全て生と死の歴史であったことをのべて、死が生を成長させ、生が死を成長させてきたと。そして最終的に生が死を飲み込み、完全なるものが生まれる。これがあの有名な人がいってた男と女が一体になった完全なる全体というものだろうな。そしてそれが世界で唯一の人間となって、人間性の最終的な形となる。
2008.03.03
コメント(0)
-
四季 冬 森博嗣
うわー。やばい面白いです。あらすじ天才、真賀田四季はどこにも行かない。感想 ネタバレ無つなげすぎじゃないかな?とは思うものの、やはり面白い。天才を登場させるだけではなくて、天才を書こうとしたところが素直に凄いと感じられる。総括としての感想としては、S&MシリーズとVシリーズを読んでいて、なおかつ百年シリーズも読んでいたらさらに面白いという事だろうか。 Gシリーズは読んだことがないからわからないが・・・・。たぶん読んでいた方がよかったんだろうな。春、夏、秋、冬。どれもこれも違った雰囲気を持っていてとても楽しめた。天才が書けているかどうか には全く興味がない。天才って何?っていう事からわからない。どうでもいいけど、ノベルス版の冬の文字が凄く格好いい。惚れた。冬のタイトルの下にBlack Winterと書いてあるけれど、よく意味がわからないな。何か意味があるんだろうか。直訳で黒い冬っていう意味なのだろうか。まぁ黒い冬って言われれば内容的に納得出来なくもないが・・・。------------------------ネタバレ有---------------------------まさかウォーカロンが出てくるとは思わなかった、つまり百年シリーズとつながっているとは、まったく思わなかった。さすがにこれを先に予測するのはきついものがある。壮大な時間の流れの中の一部といえる事だろう。というか、四季の能力がまるっきりラギッド・ガールに出てきた直感像的全身感覚と同じだなぁと思いつつ読んでいた。そしてやはり人の科学の行き着く先は、自分のコピーを作る事に行きつくんだろうかと思った。未来に世界が移行する、自分がトップレベルだと認識している作家の想像力が必ずそこに行きつくからだけれども。あ、コピーじゃなかったな。つまるところ、肉体を捨てる方向への考え方か。やはり肉体は精神をしばる邪魔なものでしかないという事か。すべてが肉体に縛られている。時間の流れには逆らえないと諦めている非力。何もしないことが安全だと信じている軟弱。時間に逆らえないのは、単に躰だけのこと。物体でできているゆえに、質量を有するゆえに、時空を超えることができない。けれど、思考は、もっと自由なのだ。飛躍できる。いろいろ書きたい事があるけれど、順序だてて書いていかないとこんがらがって書洩らしが出てきてしまう。それが不自由だ。頭の中に浮かんでくる言葉はいくらでもあるのに、それを打つ手が遅い。キーボードがあることによってかなり速くなったけれども、それでも打ち続けても1時間かけて8000文字しか書けない。遅い。考えたことがそのまま何か理解できるものに変わればいいのに・・・。文字じゃだめだ。文字じゃ遅すぎる。もっと瞬間的に理解出来るものが欲しい・・・。頭の中に思い描ける形が確かならば、それはその世界に存在しているのに等しい。物体としてこの世に存在するものと、脆弱さは大して違わない。という文があったけれども、頭の中に思い描ける形が~のくだりはどっかの哲学者が言っていたけれども、(哲学者じゃなかったかも)脆弱さは大して違わない、というのもその通りだなと思った。もともと存在しているものと等しいならその脆弱さも変わらないだろう。そうなると現実なんて途端にむなしくなってしまうだけだけれども・・・・。大体頭の中のものもこの世のものも大してかわらないんだったら、どっちに生きていたって同じだって事になってしまうじゃないか真賀田四季が何なのか、についても考えてみよう。正直いって、特異な能力を持ったただの人、としか思えない。それはつまり、思考能力の早さと直感像的全身感覚を併用している、ただの人間であると。ラストで四季が自分と犀川とパソコンにたとえて比較しているけれど、その通りだろう。神とかそういったものじゃなくて、ただ単にその時代には通常なかったはずのハイスペックなパソコンというだけだろう。あれ、そういうのを神というのかね。ただの、人である。とはいうものの人は誰だって複数の考え、相反する疑問を持って生きている。真賀田四季は極めてそれが薄いと感じる。ただの人であるけれど、特別な事であることにかわりはない。何にも干渉せず、何にも触れずに、自分だけの中で生きて行っているのではないか。干渉しているのは、殺人という動機で干渉したのは、自分を生み出した母親と父親だ。それから、自分の体か。そもそも、自分の体を失くして生きていったとして、はたしてそれは体を持っていた時の自分という存在と等しいものなのだろうかという疑問がある。体と心が同じ場所にあってこその自分じゃないのか。体がなくなったらそれは半身を失くしたのと同じ事。ああだめだまとまってないな。人と人が、別れられるように。人とこの世が、別れられるように。人とこのときが、別れられるように。切り離して見せよう。「貴方は、貴方から生まれた」彼は言った。私は私を殺して、私は私になった。私は私を生かして、私は私を棄てた。私と私が別れられるように。私とこの世が別れられるように。私とこのときが、別れられるように。すべてを、切り離して見せよう。「貴方は貴方だ。そして、どこへも行かない」私が私であるためには、どこからも、いつからも、私が遠ざかる必要があった。空間と時間からの決別こそ、自己存在の確定。浮いて見せよう。何物にも触れず。何物からも受けず、何物へも与えず。すなわち、私がすべてになる。これがつまり、肉体との別離を露わしていて、なにものにも触れず、のくだりはすべての世間からの乖離を露わしているのではないか。そして誰からも理解されず誰のことも誰も本当の意味で彼女に近づけないという、孤独だ。全てにおいて、真賀田四季は孤独だったのだ、と言えるだろう。どんな存在かと問われれば、誰よりも普遍的で、誰よりも孤独であったということだろうか。誰よりも孤独であるがゆえに、誰としても存在できるのではないか。「神様にも、わからないことがありますか?」「ありますよ。わからないことがあるから、人は優しくなれるのです」神様がこの世界を作ろうと試してみなかったら、この世界はなかっただろう、つまり神にもわからないことがあるのだ、という理屈? 結構面白い。「私たちは、どこへ行くと思います?」「どこへ?」「どこから来た? 私は誰? どこへ行く?」「貴方は、貴方から生まれ、貴方は、貴方です。そして、どこへも行かない」この問いは何だか、萩尾望都の半神のオマージュじゃないかなと思った。似たようなセリフがあった。・・・・・・死 どこへいった? 遠い旅へ もう会えない? いない なぜ? 天使になった そう・・・・・・? 萩尾望都 半神肉体が死んでも、、生きることができるはず。それを受け入れることさえできれば。そのとき、初めて、人は真の自己を認識するだろう。肉体がないことを、受け入れることなんてできるだろうか。たとえば突然鏡を見せられて、脳みそと目玉だけになったものをあなただといわれて、それを新しい自分として定義できるだろうか。普通の人には、無理だと思うんだけどなぁ。4章の最後で百年が過ぎた、と言って四季が誰かと話しているシーンで終わるんのだけれども、これは本当に百年が過ぎて、それで何故か犀川も生きていて邂逅したということなのだろうか?それとも別の誰か? それか、最後に四季はそこでスイッチを切った、とあるからそれはただの未来予測みたいなものなのだろうか・・・ もしくは、実際に百年たった後に、もし犀川がいたら、という過程の元で組み立てた仮説?謎は深い。
2008.03.01
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- スポーツチームの経営・収入獲得マニ…
- (2025-11-21 02:46:52)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月7日分)
- (2025-11-21 01:15:56)
-
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その4
- (2025-11-20 12:25:59)
-