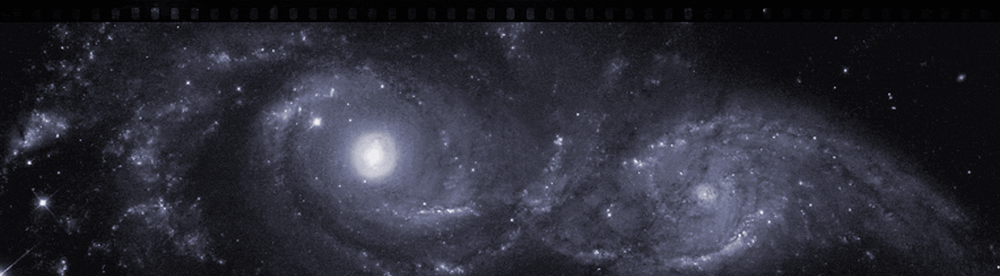2008年09月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
さらば
200件記事が突破してキリがいいので楽天とおさらばします。リンクしてくれている方を二、三名知っています故に全く心苦しい事ですがリンク廃棄してくださいとしか言えないです。主な理由としては1.過去ログが検索できない(ひょっとしたらできるかも)2.文字数一万文字制限が邪魔で記事が二分割される事がある。3.業者コメント、トラックバックが巧妙になってきて邪魔。というところです。さらば。日記の書きやすさは一級品でした。これからはhttp://d.hatena.ne.jp/huyukiitoichi/での更新となります。一応ここはこのまま残しておきます。というか消す方法を知りません。
2008.09.03
コメント(24)
-
餓狼伝2 修羅の道/夢枕獏
感想 ネタバレ有二巻である。やっていることは一巻とまったくかわっていない。男と男が格闘するのみである。ここにきて夢枕獏、さらに新キャラを出してきた、それも主人公を食いかねないほどのキャラクターである。もはや三巻で終わらせるつもりなんてさらさらない。本人もあとがきで4巻になりそうだ、なんてアホなことをいっているが、三巻を読んだ時点でその約束が守られるのはなさそうだ、と思うだろう。何を思ったのかトーナメントを開催したのである。それはジャンプのお約束だろう、と突っ込みたくなったが確かにこういう単純な話である、というか格闘においてトーナメント方式のバトルというのは何よりもやりやすい方式なのではないか。何しろ闘う舞台と、理由をわざわざ作る描写を省く事が出来るのである。今まではいちいち主人公である丹波に四国に移動させたり横浜に移動させたりと割と忙しい活動をさせながら、敵とわざわざ待ち合わせをしたり待ち伏せをしたりと、闘うのにもそれはもうたくさんの苦労をしてきたのである。それに丹波、確実に無職である。こいつが金を持っている筈はない。どうやって四国まで移動したの?と心底疑問である。まぁこいつなら走って移動しそうな気配はあるのだが。それをトーナメントは恐ろしいほどに簡単に解決してくれる。場所はでかいところを用意してくれるし、敵は勝手に集まってきてくれるし、闘う理由はいわずもがな、全員共通の目的に向かって突き進むことになる。単純に闘うことのみを求めたこの小説にとってこれ以上便利なものはない、と言い切れるぐらい便利な存在がこのトーナメントなのである。これでお金のない丹波はわざわざあっちにいったりこっちにいったりしないで済むし、相手もわざわざ丹波を狙ってあっちに行ったりこっちにいったりしなくていいのである。そしてトーナメントというのは大体漫画でも引き伸ばしに使われる代名詞というぐらいのレベルであって、それはもう時間をかけようと思えばいくらでもかけられる存在なのである。これが四巻で終わるはずがない、とトーナメントが開催される気配を感じた時に思った。バキも、トーナメントをやっていた。あれは面白かったなぁ。渋川先生とか愚地とかもあの頃はまだ第一線で頑張っていたというのにいつからあの二人はかませ犬的な存在になってしまったというのか。なんなんだよピクルって。そう、つまり格闘といえばトーナメントなのである。トーナメントなくして格闘なしだ。藤巻との戦いはまたしても途中で中断である。一巻の終わりも梶原との一騎打ちは中断で終わった。なんだこれは、生殺しなのだろうか? 何故最高の戦いを二回も続けて中断されなければならないのか。さすがに次では何らかの決着をつけてもらえるとは思うのだが。梶原との一騎打ち、かなり中途半端に終わったように思えるのだが丹波が完全に納得してしまっている。理由がよくわからない。あれだけ執着していたのに、どちらかが倒れるまでやらなくていいのだろうか。それにしても、である。凄いのは文章だけじゃなかった。いや、文章が凄いのはその通りなのだが、読んでいてその感覚まで伝わってくる。たとえば筋肉の描写である。首が太くて、腕が太くて体全体のバランスがしっかりととれている、というだけの描写なのに、いったいそれがどういう状況なのかまるで自分のことのように伝わってくるのだ。きっと自分に筋肉がついていたらこんな感じなのだろうなぁ、と想像力を喚起させる。こんな事はあまりない。第一章でカマセ犬的存在が次々と1ページぐらいの描写でやられているのはなんか笑ってしまった。かませという言葉がこれほど相応しい奴らもいるまい。どんどん強いやつが集まってきてどんどんどんどん面白くなっていく。ついに松尾象山が少しだけ闘ったし、川辺も長田も姫川もその実力を表していないし、グレート巽にいたっては名前だけしか出てきていない。こいつらが一体このあとどんな死闘をくりひろげるのか・・・。
2008.09.03
コメント(0)
-
餓狼伝1 虚空死闘記/夢枕獏
あらすじひたすら格闘。感想 ネタバレ無非常にシンプルな話である。男が強さとは何なのかと考えながら敵と戦い続ける話である。内容なんてほとんど無いと言っていい。闘いの描写と、そこに至る過程が繰り返し繰り返し描写され続けるだけだ。非常にシンプルである。闘いを手段として使う小説は多々あれどただ単に戦いたいがために闘う、という話は確かに読んだ事が無かった。それにしてもこれが書かれていた当時、まだ夢枕獏は新人と書かれていたのだ。時の流れを感じさせる物の、文章に劣化した印象はない。本当に内容が無いと言ってもいいので正直書かなくてもいいぐらいなのだが、それでも面白かった、ならば書かないわけにはいくまい。せめてどこがどう面白かったかぐらいは書かなくては、忘れてしまっては何の意味もない。シンプルな話だからこそ深いともいえる。考えてみれば世の中単純なものほど複雑だということが多々ある。考えてみれば結構あるはず。考えるのがめんどうくさいので一個も具体例を挙げる事は出来ない。ただなんとなくそんな感じはする。あぁ、そういえばサザエさんとか、ちびまる子ちゃん、アンパンマン、ドラエもんなどの国民的アニメでいいか。あれも、シンプルながら深い、といえないだろうか。だからこそ、あれだけ長く続いているともいえる。変に方向性が定まっていないからこそどこにでもいける。餓狼伝でいえば単純に強い敵と戦う、というか相手と闘う、というそれだけを求めているのだから、闘い続けれいれば多分サザエさん並に続く事が出来るはずなのである。その証拠に一巻の時点で、三巻で完結といっているのに、実際に2008年現在すでに10巻を超える巻数を出している。終わる気配がない。いや、ひょっとしたら終わっているのかもしれないが、新・餓狼伝などというものを出しているから違うのだろう。いやひょっとしたらこの新・餓狼伝がただの新装版という可能性もなきにしもあらずなのだが。面白い点の一つとして、描写が物凄く想像しやすいのだ。格闘といってまず一番に思い浮かぶ問題点が、描写がわかりやすいか否かだった。わかりにくい描写、想像しにくい描写で延々と格闘描写を書かれても困るのである。その点驚くほど想像しやすい。何の苦労もなく研ぎたての包丁で大根を切るみたいにスラっと頭の中に切り込んでくる。関節技までもがわかりやすく書かれているというのは凄い事だ。関節技というのは現実に見ているとあまりに地味で、プライドなどを見ていても、正直素人目にはあまり面白くない(あくまで個人的に)だがそれが小説や漫画になると魅力的な動作に見える。エアマスターの関節技はどれをとっても面白いし、何しろ自分、エアマスターの中で一番好きなキャラクターは関節技使いの小西なのだ。関節技が面白いのはこの小説の中でも同じだ。何故だろうか。純粋に痛みとか、どれだけきいているのか、というのがわかりやすいからではないだろうか。描写すればいいだけなのだから。テレビでみているだけだと関節技が決まっているのか決まっていないのか、今は痛いのか痛くないのか見ているだけじゃわからないというところはあると思う。過去に板垣版餓狼伝は読んでいたのだが、内容をほとんど覚えていない。というか、つい最近まで餓狼伝は板垣氏が原作だと思っていたぐらいだ。それから面白いのは、この時点ですでに異種格闘技という視点で書き始めていた点である。確かこのころはまだ、一般的に異種格闘技という目線では格闘技は行われていなかったのではないかと思う。最近になってプライドやK-1の人気の甲斐もあって、異種格闘技が盛り上がってきた、喧嘩商売なんていうまさに現代版餓狼伝みたいなものもはじまっているし。はじまっているっていうか結構前からだが、それにプライドもK-1も、もうかなり下火に入っている感がある。プライドがテレビ放映されていた頃はまだ話題だったように思うのだがネタバレ有丹波いったいどうやって金稼いでるんだ? まさかスリじゃあるまい。しかしいい感じにエロとバイオレンスである。このまま何も変わらずに延々と続けばいいのに、と思わせるような心地よい文章である。せめてグレート巽と松尾象山と闘う場面ぐらいまでは読もう。プロレスは実際には強いんだよ! という主張が強い。最近になってはもうプロレスが実際に強いとか弱いとかいう以前に、プロレスなんて一回も見た事が無い、という人の方が多くなってきたように思う。まだこのころは、プロレスにもまだ注目は残っていて、それでこその強い弱い論争があったのじゃないかと勝手に想像している。強い弱い論争さえなくなってしまった今のプロレスは本当に存在が怪しい。こうして考えてみると弱いと言われようがまだ注目されているうちはよかったなぁという感じである。誰からもわすられてしまったら弱いとか強いとかも何もなくなってしまう。まるで死んでしまったかのようにプロレスは消えていくのだろうか。ワンピースのドクターヒルルクの言葉が思い出される。人は──いつ死ぬと思う? 人に忘れられた時さ! プロレスはいつ死ぬと思う? ひとに忘れられた時さ! ふむ。まだ本当に書き始められたばかりだからかもしれないが、格闘描写は新・餓狼伝の方が面白かったように思う。新・餓狼伝もほんの20ページほど読んだに過ぎないのだがそれでもわかるぐらいには進歩しているという事か。あるいはいつもの思い違いかもしれない。梶原と丹波の戦いは尋常じゃないな。風景はほっとんどイメージできないのだが二人の立会だけは明確にイメージできる。もはやアニメ化不要というレベルである。プロレスバカにしちゃあかんなぁ。はっとするような文章でもないのだが、それでも確実に読ませる文章である。
2008.09.03
コメント(0)
-
偽物語 上/西尾維新
あらすじ妹がなんやかんや感想 ネタバレ無予想していたよりもずっと面白くてなんかもう最高だわさ。この場合の予想というのは傷物語と比較しての話である。せいぜい傷物語程度の面白さであればいい、と考えていたのである。いやはや、恐れいった。ギャグパートはこれ以上ないほど面白かった。シリアスパートは、何か言葉に出来ないような違和感をもったものの傷物語よりは格段に楽しませて貰った。これはひとえにキャラ小説ゆえの障害というかなんというか、傷物語のヒロイン的立場にたっていた吸血鬼と羽川にほとんど何の関心も持っていなかった事もあげられる。アホをやっているキャラクターがシリアスパートになると急にまじめになる、という展開が大嫌いなのだが。特に銀魂とクレヨンしんちゃんはその最たるものだろう。どこがどう嫌いって、今まで普通にバカやっていたキャラがある一時だけまじめになる、というのが理解できないだけだ。正直な話、このシリーズにシリアスな場面をほとんど期待していないのである。これが小説ではなく漫画だったら読み飛ばしているレベルだ。そういえば漫画だと平気で読み飛ばしという行為をする自分であるが、何故か小説に対してそれをやる事はひどくためらわれる。だが少しだけちゃんと考えてみるに、読み飛ばしという行為が起きるのは週刊連載の漫画だけであって単行本を買ったらいくらなんでも全部読む。金を払っているかどうかという問題ではない、週刊連載の漫画だって金を払っている。なんというか、せっかくあるのだから読もうという精神だろうか、それだったら何で週刊連載の漫画は全部読まないのだろうか。小説より漫画を読み始めた方が速いからだろうか、つまりそれだけなれたという事だろうかいやいやそんな事はないだろう、考えてみるに小説という媒体をページ単位で読み飛ばすという行為をしているという話を過分にしてきいたことがない。過分にしてって適当に使ったけれど実際意味はわかっていないのである。それにしても最近考える力が落ちている、と実感している。何か変だな、と思う事があってもそれが何故変なのかというところまで問い詰める気力がない。ちょっと前はそれが自然に出来たのだが今は何故か出来ていないような気がするこれはおかしい。まぁ何か原因があるようにも思えないのでほっておけばまた元に戻るかあるいはこのままなのかはわからないがこのままならそれはしょうがないことなのである。それにしてもと書いておいてなんだが、少し前、文章を書いていたらそれにしてもと一つの記事の中でなんと6回か7回も使用していたことに気づいた。とりあえず話を繰り出す時にそれにしても、といって前おきのようにして繰り出していたのだ。それに気づいて以来それにしても、というのを出来るだけ使わないようにしているのだがそこはそれ、クセというものがなかなか治せないように(ギャンブルを読んでもわかる)結構大変なのだ。少しでも気を抜くとそれにしても、とタイピングをしている自分がいるのである。何しろ自分タイピングをするのが結構速いものであっと気づいた時には自分の目の前にはそれにしてもという文字がすでに打たれているのである。これは恐怖でありますぞ。クセを消すには新しいクセをつければいいのであるからしてそれならばとそれにしてもに変わる言葉をしようとしているのであるがそれがしかしであったりなにか別のものであったりしているのであるがってこれ正直偽物語に全く関係ない話なのである。ただいったん書きだすと止まらないうねりというか流れというものがあるからしてこうやって自動記述ではないがだらだらだらだらと文章を書き続けているのである。本質的に無意味な行動であるがこれが普段の思考の流れなのだと考えて読みなおせばまたこれにも価値が生まれてくるのかもしれない。何も練られていないただの文章というのは練られていないがゆえの価値というものが存在するのだろうか、当然時間をかけていない脊髄反射的文章なので支離滅裂もいいところでそういった方面での魅力は皆無であるが、脊髄反射的文章であるがゆえのいいところといえば、はてそんなもの存在するのかどうか。なにごともなかったかのようにギャグパートとシリアスパートの話に戻ろう。前半150ページは、ほとんど本筋と全く関係のない、登場人物と主人公の絡みというだけの恐ろしい紙の無駄遣いというやつであった。それからの本筋、いわゆるシリアスパート、絶賛といえるほどではないが、ふむ、面白いか。ただ何かがひっかかるのだけが、気になってしょうがないのである。それが何なのかがわからないだけに困惑するほかない。確かに笑えるのだが、どこか笑いきれない違和感とでもいうのだろうか。何故かはよくわからない。ただ面白かったのは確かだ。傷物語の時は、シリアスパートに比重がかけられすぎていたように思う。戦闘描写ばかりで、それが読みたいわけじゃない・・・という気分であった。ただこうして、本編の半分が本編と関係のないただのじゃれあい、というのも結構大変なものだなと思いなおした。まだストーリーをおった話をやっていた方が楽だ。今回は最大の欠点だと勝手に自分で思っていた戦闘描写もほとんどなく、純粋に面白い。どんどんその阿良々木ハーレムを拡げていく。まるでときメモか何かをやっているかのようだった。携帯アプリでやったときメモは、少しでもケアを怠るとものすごい勢いで好感度がどんどん下がっていくという恐ろしいゲームだった。しかも何人もいるのだ。きっと主人公はてんてこまいだっただろう。偽物語を読んでいてずっとそんなことを考えていた。フラグを立てるだけではだめなのだ、維持するのがこれほど困難だとは。前半150Pが語りのための語りというべきか、本当にただ何の意味もなく女の子のまわりをまわってまわって喋っていただけであるそれにしても本当により取り見取り。まったく素晴らしいのは上巻と銘打っておきながらこれ一冊で完結している点である。ダンシング・ヴァニティを読んですぐだからこう思うのだろうが、繰り返しの表現が目立つ。そういえばこれには確かれっきとした現象名がつけられていたように思う。たとえば新しい単語を知った時に、新聞などをちらっとめくるとやけにその単語がよく目につく、というような具合に。今まで意識していなかった、というだけでそういった現象はあふれているのかもしれない。というか反復の話だが、繰り返しネタである。意外と反復という表現は小説でも日常的に使われている表現だったのだろうか。今まで反復があるというのは知っていてもそれを全く意識していなかった。意識していないということは、存在しないも同じ事である。こうやって自然にスルーしてしまっている作者の意図みたいなものがたくさんあるような気がする。ネタバレ有ついに妹まで惚れさせてしまったか。なんというハーレム・・・。火憐の口調がどう読んでも戯言シリーズの零崎人識だったように思う。少なくとも記憶の中の零崎人識はこんな口調だった。まあ概して記憶と現実は違うものであるから、実際全然違うという事もまったくありえるのだけれども。さて、これで残されたキャラはもう一人の妹の月火だけである。あと一人終われば全員攻略ということに相成る。もう新キャラも出てこないだろうし、これではれて、やっと、このシリーズ完結となるのだろう。面白いシリーズというのはそれはもちろん結構な話だが、まだ続いているというのは意外と不安なものだ。ひょっとしたら面白くなくなるのではないか、という不安がある。出るたびに面白かったとしても、期待が膨れ上がればそれに応じて求めるもののレベルも高くなる。完結してくれればその心配もない。反復の話だが、なんといっても八九寺と主人公のかけあいだろう。なんというかこの二人のやりとりははじめから終りまでもはやテンプレート化している感がある。 「なるほど、修羅々木さん」 「ものすげー格好いいからむしろそっちの名前に改名したいくらいだが、しかし八九寺、何度も何度も繰り返して言うように、僕の名前は阿良々木だ」 「失礼。噛みました」 「違う、わざとだ・・・・」 「噛みまみた」 「わざとじゃないっ!?」 「ファミマ見た?」 「そんな気軽にコンビニの場所を確認されても!」ただやはり化物語での神はいた、ほどのインパクトはない。以下笑ったところ。 「そうなんだ。病院のベッドで眼を覚まして、お前はすぐに言ったものだよ」 「『ここはどこ、わたしは誰?』と」 「いや、『高校はどこ、わたくしりつ?』と」 「記憶を失ってなお学歴社会の虜です!」 「暑いんなら、そこの壁に据え付けられているエアコンを入れればいいんじゃ・・・」 「だ、駄目だよっ! 暦お兄ちゃんはこの地球がどうなってもいいの!?」 地球が人質に取られた。 なんて壮大な人質だ。 「何がボランティアだ、得意げに横文字使ってんじゃねえよ、馬鹿。この間、ディフィカルトと言おうとしてデカルトって言っちまったような中学生がインテリぶるな」 「いいじゃねーか。デカルトの言ってることって大抵ディフィカルトだし」 「口の利き方に気をつけることね。さもないと凶悪犯罪に手を染めた挙句、阿良々木くんが好きな漫画に影響されて犯行に及んだと供述するわよ」 「お前、漫画化の先生を人質に取るの!?」ここまでだらだらだらだらだらとだらを五回も書いてしまうぐらい長々と書いてきたが、そのどれもが過去の繰り返しである。ギャグパートの個人間のやりとりは完全にすべてテンプレート化してしまっている。何回か会話のキャッチボールを交わして流れにのってどっちかが突っ込むパターンと、地の文で突っ込むパターンが主なパターンで、他に読み間違えネタ、似ている漢字ネタ、人質ネタ、大別して、ネタの種類がそんなにあるわけではないがパターンが豊富なのだ。いや、内容が豊富か? とにかくよくそんなに考えつくものだと感嘆するしかない。またしても正義言葉をなんか色々やっていたようにも思う。正直真面目な部分をあまりまじめによんでいないのだ。ギャグパートを真面目によんでシリアスパートを真面目に読まないというのは一貫性というか法則性という意味では割と整っているがはたしてそれはいったいどうなのだろうか、と疑問に思わざるを得ないが。世の中案外そんなものなのかもしれない、という言葉でしめれば世の中案外そんなものだよな、というような気がしてくるから不思議なものだ。貝木のいっていることがまるっきりストレイト・クーガーでちょっと面白いと思ったが、読んでいる最中はそんなこと全く思わなかった。時間をかければ誰でも名作小説が書けるっていうクーガーのセリフはどうかと思ったが時間をかければ誰でも同じ事が出来るっていうのを将棋のたとえでもって説明するのはふんふんとうなった。確かにパソコンは今はまだ将棋のプロに勝てないけれど、時間をかければ最適の手を導き出せるものな。いや、どうなんだろう。先の先を見据えた手はうてないかな?せめて盤面が終盤まで行けば話は別だろうが。初手からすべてを計算するのは不可能なわけだし。 「あまり考えすぎるな。俺から見れば、己の考えに没頭している奴は、考えなしの奴と同じくらいに騙しやすい。適度に思考し──適度に行動しろ。それが──今回の件からお前達が得るべき教訓だ」
2008.09.02
コメント(0)
-
ダンシング・ヴァニティ/筒井康隆
あらすじなんか繰り返しちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりして。感想 ネタバレ有び、びっくりした。まさか前半部のあの滅茶苦茶からあのラストが生まれてくるとは予想だにしなかった。後半に行くにつれて加速度的に評価があがってきてラスト何ページかの、あの死を迎えるシーンはもう何も考えられなくなるぐらいびっくりした。本当に凄い。老いたから書ける文章があるとすればあのラスト何ページかのことではないのか。ジェイムズティプトリージュニアの書いた、輝くもの天より堕ちを読んだときと同等ぐらいの衝撃を受けた。しかもその凄いところは、それをこんな実験小説でやってのけた事だ。ストーリーでもなくキャラでもなく、純粋に文体というか語りを楽しませて貰った。素晴らしい。ビアンカ・オーバースタディを読む前にダンシング・ヴァニティを読んだ方がいいというような話をどこかで読んだ気がするが、その理由がわかった。ビアンカ・オーバースタディも反復を基調にした話なのだ。しかしダンシング・ヴァニティの繰り返しとはまた違い、同じ時間軸というよりもはっきりと別の時間にうつっているにも関わらずの、繰り返しなのだ。これを読んだ事によってビアンカ・オーバースタディへの期待が高まる。何かの企画で、色々な作家に、自分が死ぬ時はどんな風に死ぬと思いますか、という質問があった。その中で、普通は家族にみとられて、などと書くものが多いのだが、実際に作家でもそういう事を書いている人が多かったように思う。筒井康隆は、確か近所の悪ガキをステッキか何かでたたこうとして逆に殺される、と答えていたのが非常に印象的だ。細部は違うかもしれないが、だいたいはあっているはず。まさに、家の前でうるさくしているヤクザを注意して殺された、ダンシング・ヴァニティの主人公ではないか。いや、これをすでに書いていたから、そんな事を言ったのかもしれないが。それにしてもダンシング・ヴァニティの主人公と筒井康隆のイメージが、どうしてもかぶってしまう。その生きざま、というかなんというか。作品の中にも、これ現実に居そうな人だなぁというようなキャラクターが何人もいた。出版社で何度もくだらないミスをする人とか。ってほかにはいなかった。何人もいた、なんてノリだけで書いたけれども完全にオーバーリアクションであるどんな風にでも解釈出来る、という作品であったように感じる。それだけ深い作品ということだろうか。宮崎駿みたいに。例えば虚構も現実であるという風に、世の中に本当の事なんて何一つ無いということは世の中はすべてが本当のことなのだ、という詭弁も成り立つ。そんな事が言いたかったのだと単純に言えることでもないだろう。というか自分、この作品を恐らく理解できてはおるまい。この同じ事が何度も繰り返されるのが現実か、夢かなんて恐らくあまり意味はないのだろう。読もうと思えば、死ぬ最期の瞬間だけが本当の現実で、今までのは全部意味のわからない夢だった、ともとれる。自分が理解出来ていない多くの事柄の一つとして、例えば最期に出てきたフクロウはいったい何を表していたのかが自分にはわからない。フクロウが涙を流していたのは何故なのか。Wikipediaで調べたところによると日本ではフクロウは死の象徴であるともいう。または知恵の象徴でもあると。ただこの象徴なんていうのは割と地域差があるもので、あまりあてにしていいものではないが少なくとも日本における死の象徴と、死の瞬間に現れるフクロウというのは完全に意味は合致している。ただ、片方の目から涙を流した、というのは何の意味だろうか。単純に死という概念にすら涙を落とさせる程惜しい存在だったという事だろうか。片方というのにも何か意味はあるのであろうか。コロス、というのも読んでいる間はわからなかった。読み終えて、Wikipediaで調べて初めて観客の望んでいる反応をする存在の事をコロスという事を知った。確かにコロスに与えられている役目はそのまんま、普通の反応だった。フロイト的な夢診断の要素が入ってくるとこれはもう完全にお手上げである。精神分析入門を読んだが、象徴するものの種類が多すぎて把握しきれない。この作品が多分色々な要素を含んでいることは巻末の参考資料を見ればわかる。前半部を少し読んだ時点では、何でこんな小説にこんなにたくさんの参考資料が必要なんだろう? と疑問に思ったものだ。たとえば時空は踊る─関係としての世界、なんていったいどこに関わっているのかさっぱりわからないのである。いや、ループ関係のところで使われているのは当然だろうが。「考える身体」はひょっとして主人公が匍匐前進! と叫んで人が即座に反応するのと関係しているのだろうか、と想像するのが楽しい。いっけんわからなくても多くの要素がこの小説の中に含まれているのは確実のように思う。何でもないただの反復の中にいろいろな意図が含まれているのかもしれない。まぁ気づけないのだから、意味はないのだが。きづけていないにもかかわらず面白いのだからなおさらどうでもいいことなのかもしれない。読んでいる最中に反復ゆえの欠点というか、単純に自分がしっかりと読んでいないというか覚えていないからなのだが、ちょっとトイレ、とかいって読むのを中断して再び読み始めると、自分がいったいどこまで読んだのかわからなくなってしまうことがあった。あれはこんな小説特有の欠点だったな。老いぼれて、体も声も昔のように動かなくなって、昔の反則ともいえるような「匍匐前進」も声がかすれて使えなくなり、ぼこぼこにされる描写が悲しすぎる。どうしようもない老いというものが存在する事を明確に意識させられる。今までの回想が入り乱れて次々と襲ってくる場面、また一番最初の繰り返しポイントに戻るもののやっぱりこんなものはダメだ、と病室に戻ってくる場面、どれ一つとっても素晴らしい。何がどう素晴らしいのかというとうまくかけないのだ。だから素晴らしいと書いているのだ。何が素晴らしいってやはりこの文章だろうか。いや、内容が素晴らしいというのはわかっているのだ。何がどう素晴らしいのか説明できないのだ。非常に難しい。このまま投げっぱなしでいいのだろうか。今のこの気持ちを書いておくべきなのではないだろうか、うまく書けなくても。死に向かっていくというのが明確に意識させられる。そのタイミングというか、文章の呼吸というかそういったものが何一つ欠けていないというか、本当にぴったりあてはまった文章がそこにあるというか概念がそこにあるというか非常に書きがたいのは重々承知なのだ。もう意味がわからないが。何より感じ入ったのが、終わり方が老いで終わるということだ。何を書いているのかはよくわからないがこの老いで終わるということに感動したのは確かだ。やっさんに殴られて死んだのは確かだが、やっさんに殺される原因は老いだ。こんな事書くと何をわかりきった、というような感じになるので本当に厭なのだが、人は誰でも老いていって、人は誰でも死ぬのだ、という非常に単純な文学の基本的なテーマともいえる事を突き詰めた小説であったように思う。 この時代には戻りたくないなあと思う。しかしいったん戻った時はその時でおれはまたいくつかの分岐点において前回とは違う別の選択肢を選ぶのかもしれない。しかしどの選択肢を選ぼうがまたこの病室へ、つまりは自身の死へと戻ってくるのは確かなことだ。だとすればリセットしてもつまらない。生が一回限りでないとすればただの人生ゲームじゃないか。もしリセットを選べと言われたらおれは拒否するかもしれないぞ。よほど死を恐れていない限り誰でもそうするんじゃなかろうか。そんな生であればなんの意味もなくなってしまうからな。実に基本的な事を言っているように思う。死を意識することによってはじめて生きるという事を意識できるのだ、不自由があってはじめて自由が生まれるように、死が無い限り生きるという事にも何の意味もない。誰だってそうするだろう。 頸城氏がそこまで言ったとき、正面のドアを開けて功力さんがあらわれた。今度は何も持たず、ひたすら緊張した生真面目な表情で無言のまま、ひたと真正面を見据えておれの前まできて立ち止まった。そして彼女は突然、両腕を拡げ、おれの頭上へとななめ前方に突き出した。その勢いに気圧されて、おれも思わず立ちあがり、ななめ前方へ勢いよく両腕を拡げて突き出した。これを始めて読んだ時は意味がわからなさすぎてわらったものだったが、読み終わった今も全くこの行為に何の意味があるのかわからない。他にも川崎が突然壁に激突する行為など、意味のわからないことはたくさんあった。最期に、頸城氏がやってきてこのポーズをとったが、体が動かなくてそのポーズの真似できない、というような場面を読んで悲しくなる。 みんな美しかった。みんな可愛かった。会いたい。もう一度会いたい。しかしおれはもう眼が見えない。体力も残っていない。見ろ。手をあげようとしてもまったく動かないではないか。指先さえ動かない。ぴくりとも動かない。でも気配だけは感じられる。コロスが病室にいる。自分の立ち位置を心得盡している舞台上の役者たちのように理想的な配置で病室内に立っておれを見守っている。ゆっくりと静かに彼女たちは「グットナイト・スイートハート」を歌い出す。おれは眼を見開いて彼女たちの姿を見ようとする。だがコロスは見えず、ぼんやりとだが枕辺で白い顔のフクロウがおれの顔を覗きこんでいるのが見えた。その片方の眼がしらに一滴、涙が光っている。泣ける。これほどまでに死に際というものを書けるとは。結構死ぬシーンにはうるさいと自分では勝手に思っているが、それでも満足させてもらえるものだった。今まで片手で数えられるほどしか満足した場面はない。この小説、実験小説でありながら小説としての面白さを失っていない、と思った。虚人たちは実験小説としては面白かったけれども小説としての面白さを感じられなかった。いや、というかこれは実験小説とひとくくりにしてしまうからであって、単純に実験の内容によるのかもしれない。今回の反復という実験がたまたま小説としての面白さがあるまま読ませてくれるものだったのだろうか。繰り返されるものに人は安心感を覚えるものだと思う、
2008.09.02
コメント(0)
-
三国志 九の巻 軍市の星/北方謙三
ネタバレ有帯でネタバレいい加減にしろばかやろ。なにが心の中で蘇る死もある。さらば、関羽雲長よ! だ。関羽死ぬのが1秒で認識出来てしまったじゃないか。しかもいざ読み始めたらいつ死ぬのかが気になって内容が全く頭の中に入ってこなかった。結局死んだのはラスト1ページ。自分だけかもしれないが、関羽の影が非常に薄かった。もちろん、曹操の元にいたところから、敵将の首を取って劉備のところへ帰還するシーンなどはなくちゃならない場面でもあるし、関羽の存在感もでていたけれど、やはり張飛との対比がちょっと弱いような気がした。張飛が劉備の足りないところを補っているように関羽ももっと単純なわかりやすい補い方があればよかったのだが。悩む関羽、というのも新鮮だ。今まで読んだ三国志関羽の死にざまに至る過程といえば、あまり描写されていなかったものだ。それが荊州で一人とりのこされ、いつか劉備と張飛と肩を並べて闘う日を願う描写が入っている分、重たく感じる。関羽の死が。単純に話に深みが加わったという話ではなく、想像の余地が生まれたというか、いやそれが話に深みが加わったということなのだろうか?いまいちわからないが。ラスト何十ページか、曹操が、孫権が、関羽を殺す算段を立てている描写なんてほとんど読んでいなかった。何故関羽が殺される計画をねっているところを殺されるのを嫌がっている自分が読まねばならないのか。水滸伝を連載しているときに、作者に助命嘆願がいったというが初めてその気持ちが理解できた。何故関羽が殺されなければならないのか。しかしそうはいってもいられない。もうみんな歳だ。正直、寿命で死んでもおかしくない歳の武将ばかりになってきた。寿命で死ぬよりは、こんな終わり方の方がよほど軍人らしい。関羽が布団の上で死ぬところなんて、想像できない。しかし、関羽、六十五になっても戦場に立つつもりでいたのだ。自分もへたれちゃいられんなぁと思う。六十五なんてまだまだ先だが、五十五になって、十年後、闘い続けている自分を想像できるだろうか。もうどこかに落ち着いて、余生をじっくり暮らそうと考えているような気がする。というか、今この時点ですでにそう考えているのだからもはやどうしようもない。 劉備とともに、闘うことができなかった。張飛と、轡を並べることができなかった。趙雲とも、会えなかった。しかしそれは、特別口惜しいということでもなかった。 みんな、益州から自分が闘うのを見ていたはずだ。ともに、闘ったのだ。心の中では、ともに戦場にいた。長い、実に長い歳月、ともに闘ってきたのではないか。ぐおおお。関羽おまえ・・・。なんという漢。やってくれる。ドッカンドッカンきた。ドッカンドッカン。 膝を叩いて腕立てを五十回ぐらい息継ぎ無しでやり続けられるぐらいの興奮を与えてもらった。 「郭真、旗をあげよ。関羽雲長の旗を」 「はい」 「城を出る。私は、最後まで諦めぬ。男は、最後の最後まで闘うものぞ。これより、全軍で益州の殿のもとへ帰還する」 十名、それが全軍だった。十名、それが全軍だった、で鳥肌が。一度曹操にくだったときも、死ぬほど悔しがっていたからな、これほど一貫して変わらなかった漢というのも珍しい。十名しかいないのに、まるっきり諦めていないところがすげぇ。さすがに曹操も今度は助けを出さない。老いたのだろうか、屈服させようという気力がなくなったのか。曹操が、あきらめを知ったか。馬の名前が、赤兎の子供なのに、赤兎と読んでいるのはどういうことなんだろうか。新しく名前をつけてやらないのか? それともやっぱり赤兎ってのは種類名なのだろうか。この赤兎の名前はちょっとした謎だわさ。 「関羽雲長、帰還できず」 呟いた。 次第に、視界が暗くなった。帰還しろばかやろおおおお。この最後のセリフ、今までと違い、ちょっと浮いてるような気がしたがどうなのだろう。印象に残るフレーズだが、どうにも違和感がぬぐえない。まぁいいさ、関羽だ。関羽雲長の死のシーンだ。そこに何かケチをつけるつもりはない。この巻は、この場面以外求めていないのだ。死ぬ事によってその存在をアピールしたのかもしれない、と考えた。いなくなってはじめてわかる、その存在のでかさだ。
2008.09.01
コメント(0)
-
三国志 八の巻水府の星/北方謙三
感想 ネタバレ有周瑜の死がついに訪れた。ここまで死亡をにおわせる描写だらけだったから当然かもしれぬ。それにしても呉軍の武将は早死にである。ただ、孫権は長生きするはずである。少なくとも劉備よりは。ここまで周瑜の存在が大きなものになるとは、読み始めた当初は思いもよらなかった。北方三国志内部だけでいえば、周瑜は水軍を強化し、孔明に張り合うほどの軍略を見せ、世紀の大決戦である赤壁の戦いで曹操軍を破った。まさに三国志の豪傑に相応しい男として書かれた。素晴らしい。拍手を送りたいぐらいだ。108人もいた水滸伝とは違って、充分な描写を与えられての死となった。この巻の前半部はほぼすべて周瑜一人のためにあったといっても過言ではない。108人のうち7割を殺す宿命を背負っていた水滸伝では出来ないやり方といえよう。それだけに一つの死が重い。周瑜が死ぬシーンは全く涙が止まらない。比較的、泣くっていう感情は起こりやすい部類だろうが、その中でも漢泣きといっていいぐらいのいい泣き方だった。肝心の死ぬ場面だが、三国志を共通して言えることとして、やたらとかっこいいというか、魅せ方がちゃんとしているというか、まるで劇か映画がそこで終わるかのような、幕引きを思わせる場面や、セリフを残して死ぬ事が多い。ようするにかっこつけすぎじゃね? と後で思い返すようなセリフか。だが面白い。 「人は、いつか死ぬ。それは、誰もが知っている。いま、自分に、ということが信じられないだけだ。魂を売っても、生き延びたいという思いがある。いま、自分に、死が訪れようとしているのなら、雄々しくそれを迎えようという思いもある。不思議だな、口惜しくはない」これから益州攻略へと向かう途中だ。もしこのまま死なずに益州にむかっていたらかなり劉備軍はきついことになっていたはずだが、孔明はその場合どうするつもりだったのだろうか。当然、策は考えてあるはずだと思うのだが。作中で周瑜が向かっていたら打つ手がないみたいなことをいってたが、まさかそこで終わる孔明ではあるまい。 ざわめきが近づいてくる。軍勢だった。敵ではない、と周瑜は思った。しかし、味方でもない。顔のない軍勢だった。闘う相手を、捜しているように見える。 戦が、人生だった。その軍勢にむかって、周瑜は声をあげた。戦に生きた。いまだ、敗北を知らない。語る言葉がないな、これは・・・。周瑜が一番好きかも知れない。キャラ萌えの観点から見れば。何を書いてもウソっぽく見えてしまう事がある。あえて書くならばこの曹操のセリフだろうか。 「華であったな、大輪の。しかし、咲いたら散り、枯れゆく華だったのだろう。冬に散り、春に芽を出す。それができないからこそ、見事な華だったのかもしれん」 まさに一代の豪傑。周循にその資質は受け継がれていないのだろうか。それができないといいきっているのならば、周循はダメなのかもしれぬが。そもそも解釈が違うのかもしれない。別に冬に散り、春に芽を出すっていうのが世代交代を指しているわけではないのかもしれない。ただ考えても仕方ないことではある。孫権だけで呉を制御していくのは難しい。後年孫権が横暴な存在になって呉を滅ぼすのも周瑜がいればそうはならなかったかもしれぬと考えると面白い。
2008.09.01
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(浅暮三文)・・その百六十
- (2025-11-19 20:55:43)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『おしかけ婚~エリート御曹司さま、…
- (2025-11-21 00:00:19)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-