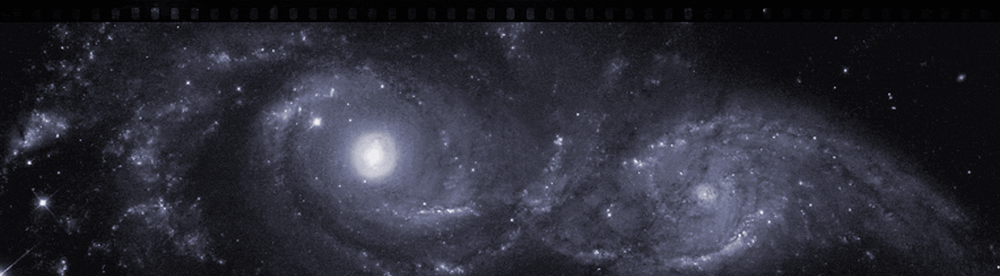2008年07月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
水滸伝 五/北方謙三
感想 ネタバレ有さぁさぁついにやってきました五巻。なんといっても注目は楊志の最期か。死亡フラグ立てまくってたので死ぬのはわかりきっていた事だが、ここまで壮絶な最期を持ってくるとは思わなかった、というか想像をはるかに超えて「圧倒的」な最期だった。ここまで読んできた人間を圧倒するかのその描写。もし仮にだが、北方謙三のキャラクター造型に疑問を持つ人間が読んだとしても、唸らざるを得ない場面であった。自分自身そういう経験があるからわかるのだが、自分の嫌いな設定、展開、キャラクターであるにも関わらず、それでもなお面白いと認めざるを得ない作品がある。たとえばゲーム「マブラブオルタネイティブ」だが、キャラクターはあまりにもシンプルなうえに、主人公に全く魅力がないわ、ストーリーがあまりにも王道すぎる、本当に、ひとつも好きなところがない作品だったが、中身をみて見直した。なんというかうまく説明出来ないのだが、説明出来ないからこそ、みんなパワーに圧倒されたとか曖昧な言葉で逃げているのかもしれない。物語の面白さというものに、キャラクターの魅力、ストーリー、テーマ、の他にもまた違った要素があるのかもしれない。同じ事が北方謙三の作品でもいえるかもしれない。こんな漢と書いてオトコと読むようなヤツらしか出てこないというのはある意味お約束でありながら、それを毛嫌いする人間も当然、いるだろう。現に解説でもそういう事を書いている人はいる。ただ、例外なくパワーに圧倒されたと言っている。水滸伝で、これから先死んでいく仲間が死んでいくさまは本当にどのシーンも格好いいものだが、果たして楊志を超えるものは現れるものか。これほどの存在感のあるキャラクターの五巻での退場というのは、銀河英雄伝説の二巻で死んでしまったキルヒアイスを思い出させる。楊志の事しか書いていないが、ここではもうそれだけでいいだろう。特に楊志の最期の戦闘の描写はまるで井上雄彦のバガボンド27巻、吉岡一門70名以上を相手に戦った時の絵を彷彿とさせた。それほどの衝撃だった。これほどの戦闘描写が書けるのか、と唖然としたのを覚えている。 ふり返る。楊令。済仁美に庇われるようにしながら、顔だけこちらにむけていた。眼が合った。笑いかけようと思った。笑えたかどうかは、よくわからない。父を見ておけ。その眼に、刻みつけておけ。格好いいと、もう何回書いたかも思い出せないが何回でも書こう。格好いいぞおおおおおどいつもこいつもかっこいいぞおおおお。しかも信じられないぐらいに。一人一人が、かっこいい。こんなのが108人もいるんだから恐ろしい話だ。この話の中では、闘う相手にも家族がいるんだ、とか戦争はいけない事だ、とかいうそういう偽善的な話は、一切出てこない。どれもこれも志を胸に、誇りを胸に闘うだけだ。その一貫した姿勢が、心地良い。 「われらは、この山寨を死守する。それが、総隊長へのはなむけではないか。総隊長に鍛えられたわれらが、ここを守らずして何とする。耐えろ。耐えて、耐えて、桃花山の土になれ。ひとりひとりが、その気持ちを失わずに、ここで耐えるのだ。俺を、信じろ。俺を信じて、『替天行道』の旗のもとで、懸命に闘え。じっと耐えるのも、敵と斬り合うのも、同じ闘いだ。斬り合うときは、俺が命令を出す。わかったな」 叫び声に近かった。涙は、まだ溢れ続けている。兵たちがどよめき、声をあげはじめた。それを手で制し、周通はさらに大声をあげた。 「われらは、梁山泊の一党。義によって、官軍と闘うために立った。その時から、命は捨てている。いいな。どれほど苦しくても、梁山泊の誇りを忘れるな」
2008.07.30
コメント(0)
-
水滸伝 四/北方謙三
水滸伝が 面白すぎて 読むペースと感想を書くペースの釣り合いが取れていない件について。感想 ネタバレ有そろそろキャラが多くなってきて、どれがどの勢力だかわかりづらくなってきた。しかし、一瞬わからなくなるだけで、少しでも読めば、ああ、あそこにでてきたあの人か、と思いだせるような書き方になっている。さりげない心づかいがうれしい。というか面白い。やばいこれ。ナニコレヤバイデスワヨ。激動の展開の5巻に向けての、準備の巻だったという印象が強い。まぁこれほど長い物語だ、そういう巻もあるだろう。ただその分しっかりと「志」各人が闘う理由が書かれていたり、さらに新しい人間が追加されたりしている。それにしても王進システムが人間リサイクル機関ならば、宋江の旅は人材発掘隊だな。旅に出る理由は苦しい気がするが、どう考えても108人の人材を都合よく発掘させるための旅だろう。読んでいて気付いたが、次の巻で壮絶に活躍するやつは前の巻から念入りに伏線が張られているか、大量に描写が入る。楊志しかり、林冲しかり。ただこれに気づいたのがいい事だったのかはたしてネタバレ並にひどいのかは少しわからないが。もう何度も書いたが、本当に一人一人が格好いいのである。もうこれでもかっていうぐらい。雷横とかいう脇キャラがこんなに格好いいなんて思わなかった。雷横が部下と一緒に逃げて、部下との深いつながりを示したシーンはボロボロ泣いたような気がする。(おい) 今ぱっと読み返してみても、あまり感動はしないが、流れで読んでいったときに雷横と部下との関係がキレイすぎる。汚いものなどなにもない。そういえば北方水滸伝の、梁山泊108人、誰ひとりとしてつまらない人間がいない。現実ならば、割と性根の腐った人間もいそうなものだが、一人一人が圧倒的なまでの信念を持ってる。命乞いをするような人間が、一人もいない。そういった弱さ、というものを完全に排除しているのか。 「老いとは、孤独なものなのですよ、宋江殿。出来のいい息子がいようが、やさしい娘がいようが、同じことです。ひとりで土に還る時を、待つ日々なのですから、その時、癒してくれるものを持つのは、その人の人生が豊かという事にならないでしょうか」ふーんとおもったけど自分老いた経験がねえからわかんねえ!あと40年ぐらいしたらわかるかな?でも確かに、60や70になって、死が射程距離に入ったら、本当に孤独な気がする。異邦人でムルソーが、死刑宣告された時に来た救いを説く神父に怒りをぶちまけたみたいに、死のうとしている人間に救いなんて何の意味もないのかもしれない。本質的に孤独っていうのはそういう事か。その時に死の恐怖をやわらげてくれる何かがあったら確かに人生は豊かといえるかもしれない。 「自ら死のうなどという気はない。しかし、志のために私は命をいとうべきでもない」宋江のセリフ。今のところまだ死んでいないが、いつか死ぬのは確実に思う。林冲が死ぬのを望んているような描写が大量に入るが、宋江も負けてない気がする。周りの人間が囃したてないだけであって。ただ確実に立派な最期を遂げるだろうという事がこのセリフから伝わってくるだけだ。それだけはわかる。きっとそういう誰もが期待して、当然そうなるだろうという王道をどうどうと突っ切ってくれるから最高に面白いのだろう。次への準備の巻という印象が強いが、主役をあげるとするならば間違いなく穆春と李俊だろう。この二人の見せ場は異常にかっくいい。 「おまえらの命、この李俊が預かった」 山寨に、百名のあげる声が谺した。嫌が応にも燃える。かっけええええとがっつぽーずしたまま壁にぶつかっていきそうな気分だ。この巻あたりから、死ねば土に還るだけ、というフレーズが増えてきている。後々重要になりそうな感じである。良く覚えておこう。
2008.07.28
コメント(0)
-
水滸伝 三/北方謙三
感想 ネタバレ有もうネタバレ無で書くような事が無くなってしまった。というか、特にここでもふれることはないのだが。でも書く。というか面白すぎてどんどん先に進むものの、こっちを書かないでいると内容が全く思い出せない。今読んでるところならわかるんだけれども・・・。三巻はどういう内容だったっけ?そういえば三巻の最初は、役人が腐っていた。という一文から始まるのだった。まだ読み始める前に、何故か三巻だけ、ちょっと読んでみたのだが、役人が腐っていた。という簡潔な単純明快なはじまり方に惚れたのだった。それから帯があまりにも格好よかったのもある。7巻だか8巻だかの帯のセリフ、死ねば土に還るだけ。どこからでもいいぞ、かかってこい。とか死ぬほど格好いいじゃないですか・・・ていうかそんなセリフまで到達したら泣く。ちょっと先まで読んだからわかるのだが、何気なく起こる、イベントが一つ一つ、あとになって重要な意味を帯びてくる。いったいどれほどの考えを巡らせて、どれほどの筋道を考えて、矛盾がないように行動を一つ一つ選択させているのかと想像すると絶句しそうになる。とにかく無駄というものがない。だから読んでいて楽しい。そういうものだ。たとえば石秀の一つ一つの行動であったりさりげないセリフが未来に起こる事の伏線だったりだ。晁蓋と呉用の会話が格好いい。「酒なら、これからも付き合おう。お前の夜だけが、長いわけではない」二人の思い出話ががががが。晁蓋はこういう男だ、というのがさすがに三巻ともなると味が出てくるというかなんというか。なるほどこういう男か、という納得がやっと出来るようになってくる。長い付き合いになるのだから把握も頑張らないといけない。宋江と晁蓋、いっけん相反する二人というところが、組織というものでは重要なのだろうと思わせてくれる。ガンダムを作った富野さんも、ガンダムを作った主要メンバー3人は仲がわるかったからうまくできた、といっていることだし。といっても水滸伝の二人は仲がいいが、中身が正反対という意味ではある意味あたっているであろう。王進と史進の関係性が最高すぎる。どれだけ慢心して、強さにおぼれても王進だけには素直な史進を読んでいて感動すら覚える。二人の絆の強さが見えるシーンだった。二人が再び出会うシーンは。「棒術の強さなど、人間の強さの中では小さなものだ。それをすべてと考えているから、おまえは幅の狭い男になった。なにが真実なのか見えぬ、濁った眼しか持たぬ男になった。おまえに、もうひとつだけ教えておけばよかったと思ったのは、強さがすべてではないということだ。棒術の強さがすべてというなら、世の人はみな棒を持っていなければならぬ。現実には武松のように拳を武器にしている者もいれば、魯智深殿のように懐の深さを武器にしている、棒では打倒せない男もいる」かっこいい男だ、王進。この男が無様に命乞いをしている姿を全く想像できない。またしても、ここで修行を積むことになった史進だが、きっと戻ってきた時は想像を絶する深みと強さをかねそろえた陽志のような男になっているであろう。それにしても王進システムがまるでポケモン育て屋さんみたいで少し笑ってしまった。 「所詮、強いやつに弱い者の思いなど、わかるわけがない」 「俺も、弱い」 「それでか。棒を、拳で打ち砕いてしまい様な男でさえか」 「そうだ。弱い」 「では、私は弱くさえもない。この山寨に入ったとき、強いものがいて、その下で闘えばいいのだと思っていた。ところが、私が一番強かったのだ。わかるか、その時の驚きと恐怖が。私は、さまざまなことを考え続けてきたが、闘えばみんなを死なせる、というところにしか行き着かなかった。闘いで人が死ぬのは当たり前としても、むなしく死なせたいとは思わなかったのだ」私は弱くさえもない。ずしんと来た。対して重要じゃないこんなキャラのセリフでずしんと来た。人は誰でも弱いと自覚した時にまた一つ成長するというが、無知の知というやつか。しかし弱くさえもない、というセリフを読んだ時の衝撃は本当に忘れがたい。しばらく頭の中でセリフが反芻されていた。それほどの衝撃だった。大したことがないように、あとから読み返したら思うかもしれないが、何故これ程、衝撃をうけたのか・・・。武松が自分の事を弱い、と断言して憚らないのにまず感心して、それを即座に受けて弱くさえも無いと自分の存在をすぐに認められることのできるというそこに感動したのかもしれない。はじめから勉強ができたやつに、勉強が出来ないやつの気持ちはわからないという話があるが、強い、弱いという次元での話ならば、最初から強かった奴なんていないだろう。宋江の嫁と宋清の嫁が死んでしまうが、あまりにも自然に受け入れてしまうというのが、宋江の志、覚悟を表しているのか。晁蓋といい宋江といい、度量の広さを見せつける描写である。この二人が今後どうなっていくのか目が離せない。
2008.07.27
コメント(0)
-
水滸伝 二/北方謙三
感想 ネタバレ無相変わらずぶっ飛んでる北方水滸伝。途中で読むのをやめるという事が出来ない。とにかくぶっ飛んでいる。面白さ限界突破という感じ。というか、別に巻ごとに、特に大きな区切りが無いわけだから、読むのをやめるわけにはいかない。読み終わるまで進み続けるだけである。巻が変わっても変わらぬ世界がそこにあるというのは新鮮な喜びだ。やはりこの巻でも数々の名場面がああ。やばいやばい。鳥肌物。この巻で陽志が出てきて、物語も少し、動きだす。梁山泊の主力メンバーも次第に集まってくる。さらに王進システム。というかこのシステム、なんか真面目にアホな事やっているような面白さがあって笑ってしまうのだがどうもおかしいような気がする。読み方間違ったかなぁ。でも王進の凄さが、巻が進むごとにだんだんわかってくる。最初から凄い凄いとは書かれていたけれど、あぁなるほど、というように吸収されていく。話の流れとしては、梁山泊を手に入れるための数々の行動というところか。もちろんそれだけではないのだが、何分一巻ごとに語るような本ではないような気がする。全部読み終わってから総括、という風にすればよかったのかもしれぬが、忘れてしまうというのはどうしても避けたい。ネタバレ有白勝が林冲と安道全に感謝するシーンは号泣物。ていうか、こんな小物の盗人一人にさえ確かな志が根付いているというその一事をもってしてすでに号泣出来る。 「あの二人がいなけりゃ、俺は死んでた。いや、一遍死んじまったんだ。手癖のわるいところなんか、きれいに治っちまったもんな」 「わかったよ、白勝さん」 「いや、孔亮、おまえにゃわかってねえ。俺は滄州でしばらく動け無くて、その間に、安道全も林冲も行っちまった、追ってみたが、山寨の中だってよ。安道全は、兄弟以上なんだ。林冲は、血を通い合わせた友だちなんだ。山寨にいるなら、俺も山寨に入りたい。そのために、みんなに信用される仕事をしなけりゃならなねえんだ。志なんか、くそ食らえなんだよ。それが恥ずかしいとも、俺は思っちゃいねえ」白勝は自分には、志がないといっているが冗談じゃねえ、これが志じゃなくていったい何が志だ。格好良すぎる。2巻一番の名場面といってもいい。晁蓋と宋江の二人共、タイプは違えど担ぎあげられるだけの強さが存分に書かれている。1巻で、林冲一人信じられないで何が志だ、と言って拷問にかけられている林冲が秘密をばらすと全く思っていないその胆力に圧倒された。 「会いたいと思った。思ったら、林冲は必ず来るという気がした。だから、夜明けに家を出て、ここで待っていた。おまえは、私に待たせる資格がある、数少ない男のひとりだ。会いたいと思って待っていれば、必ず会えるのだと、おまえが駆けてくるのを見て、本気で思ったぞ」ここで突っ込むべきなのは、来ると思ったから待ってるって、お前エスパーか何かかよっという野暮な突っ込みではない。自分勝手に解釈して、宋江を格好いい男に仕立て上げるのが本当のやり方じゃ。つまり宋江はたまたま今回だけ立っていたわけじゃなくて、会いたいと思った時は毎回立ってたんだよ!つまり今まで何回も不発させておきながら、それをみじんも感じさせない宋江超格好いい。この二人の絆には何物も阻めねええ。1巻の時点で林冲は何故こんなひどい拷問にあわせられながらも、何もしゃべらないのだろうと疑問に思ったが疑問は愚問であった、信じられる強い絆ってのをまざまざと見せつけられた気がする。どう考えても最強なのはこの二つの場面だが、さらに上げるとすれば王倫を殺したシーンか。あれはやばかった。まぁなんだかんだいって、このストーリーに出てくる登場人物は敵であれ味方であれ小物であれ全員格好いいという事を再認識した2巻となった。
2008.07.25
コメント(0)
-
水滸伝 一/北方謙三
あらすじ十二世紀の中国、北宋末期。政治は腐敗し、民は苦しんでいた。腐敗した政治を倒そうと、志を胸に漢達が立ち上がった。感想 ネタバレ無お、面白すぎる。20巻もあるというのに(文庫で)1巻だから、まぁまずは各キャラクターの顔見せとかかな、なんていう軽いジャブじゃない。ド真ん中ストレートで1巻目から最強に面白い。死ぬ前に読めて良かった。20巻てよく考えてみればラノベでもそうそう20巻続いてる作品なんて無い。しかもそのあとにもまだ話が続いているという。というかそもそも水滸伝という話を、ジャイアントロボでしか知らない、ていうかまったく知らない状態で読み始めたのだがまさかこれほど楽しめるとは思わなんだ。読む手が止まらない。というか巻が変わっても止まらない。ぐいぐい引き込まれる。これからこのブログは北方水滸伝に埋め尽くされるであろう。これから20巻も、北方水滸伝の世界に浸っていられるのかと思うと心が躍るわ。すでに手元には20巻分の北方水滸伝がある。あるいは途中で止まるかもしれないが、読むのが楽しみである。しかしただひとつ重大な欠点があるとすれば、7巻だか8巻の帯で壮大なネタバレを喰らった事だ。恨んでも恨み切れない。なんというネタバレ・・・。たいていのネタバレは笑って許せるが、許せないネタバレというのもこの世界には存在するのだ。しかも帯に書くとか・・・。さきに帯を読んでしまった自分が悪いのか。内容的には、やはり一巻だけあって、まだ大きな物語の断片が語られたにすぎない。林冲や魯智深、史進など、のちのち活躍していく人間の運動の始まりが多少語られているにすぎない。ただ一巻の時点でほぼ50人近くの人間が登場している。やはり重要な巻なのだろう。何より凄いのはどの人物をとってもつまらない人間がいないということだ。どの人間の視点になっても面白くて仕方がない。人間が増えれば最終的に100人を超す事になるが、それによる不安が全く湧いてこない。素晴らしい実力で書いていると感じる。というかそのすさまじさに声も出ない。読んでいて、あまりの凄さに芯から何かが込み上げてきた(言いすぎ)むやみやたらにほめても凄いとしか書きようがないのでポイントを押さえてみようか。まず第一に、数多くの人間が出てきているのに、つまらない人間がいない事が凄い。どの個人も機能的に生きている。作品の中で。というかみんな格好よすぎる・・・。思わず、か・・・かっこええと独り言を言うぐらい格好いい。第二に、戦闘描写が思わずみいってしまうほどわかりやすく、伝わってくる。みいるというのは誤字ではない。本当に情景が頭の中に浮かぶだけじゃなく、間というものまでも伝わってくる。つまらない戦闘しか書けない人間が書いたものを読むと、経過はいいからもう結果だけ書いてくれればいいのに・・・といつも思うのだがむしろ結果はいいからずっと闘っていてくれればいいのに・・・という感じである。第三に、単純ながらも魅せ方がうまい。強さを示すためにわざと弱いやつと闘わせたり、人間性をみせるためのイベントを設置したりと単純だが、だからか普通に響く。第四に、リズムが崩れない。20巻もの長大な物語を書くというのに、そのリズムが一定してみだれない。あいにくまだ全部読んだわけではないので20巻最後まで全くリズムが乱れていないのかどうかはわからないが、3巻まで読んだ感触だとこの先もリズムは乱れないのだろうと思う。あるべき結末に向けて着々と進んでいる印象を受けたあげればきりがないのでこれぐらいで。凄まじい小説だという事は繰り返し述べていきたい。ネタバレ有王進の漢っぷりに泣いた。内へ内へ向かうというのも別にわかるわけではないが、きっとこういうものだろうというのも、想像出来る話だ。親を大事にしている登場人物ばかりで心が痛かったりもする。それにしてもここで目指している民が普通に笑っていられる世界っていうのは、今まさに日本の事だろうなぁと思うと少ししんみりだ。シュルレアリスムとは何か、で理想郷とはそのまま日本の事だ、という言葉があったが言われてみればそういう気もする。今の日本を目指しているわけではないだろう。もちろん。ただこの状況を脱した後に待っているのも、日本のような状況だと考えると少し悲しくなってくるものがある。王進と史進も最初の対決は本当に良かったなぁ。格好いいという他ないし、王進の強さが存分に書かれていた。個人個人も水滸伝の大きな魅力かもしれないが、その実、一番の魅力は登場人物の多さによる、関係性の多さかもしれないと読んでいて思った。王進と史進。史進と盗賊3人衆。安道全と白勝と林冲。その他いろいろな関係性がある。そしてそのどれもがどうしようもないほど格好いい。これほど関係性というものを意識したことはなかった。それはやはりこういった多数の人間が入り乱れる小説でしか生まれてこないものだろうか。ともおもったがどこを重視するかによるのだろう。王進システムはいいなぁ。もはやシステムになってしまっている。それから、どの場面のどのセリフをとってもほとんど無駄なセリフというのがないせいか、どこを読んでも、みんな志というものを持っているのだなと意識させられる。書いている意味がわからないが・・・。なんというか芯というか、筋というか、キャラクターの中に存在する真中のものが設定されている、と読んでいてわかる。作者がそういう風に考えて書いていないと、伝わってこないだろうし、そもそもかけないだろう。好きなシーン史進と王進の別れのシーン。お前と私が別れても、お前の心の中に私は生きている、とか王進じゃなきゃ言えないぜ・・。鮑旭が、王進と王進の母に人間のように扱ってもらえて、うれしくてやべぇ!となっているところ。ほんと王進格好いいな。それから、安道全が白勝と林冲のことを友と認めて、死にそうになっている白勝をなんとしてでも助けようとして雪の中手術するところとか、というかその一連の流れ全部だ!やばすぎる。面白すぎる。こんな感想書いている暇も惜しい。さらばだ
2008.07.24
コメント(0)
-
ゾウの時間ネズミの時間/本川達雄
感想 ネタバレ有む、難しいぞおおおお。サイズの生物学、ということで単純に時間だけをとりあつかったものではなかった。純粋に、大きい動物でも小さい動物でも一生の心拍数は同じなんだぜ、へへんっていう小賢しい知識の補強でもしようかと思い(純粋じゃない)読み始めたのだが、読み終わった今、自分の中に何か知識が残っているかといえば怪しいものだ。ちょっと思いつく限りにあげてみよう。ヒトデとかはなんか切り離せる自切とよばれる組織がある。ナマコとかは肺を吐き出して新しい肺を作る事が出来る(気持ち悪い)サイズの大きい動物は、大きいだけに安定度を失っている。逆に小さい動物は安定度が強い。だから高い所から落とされてもなんともない(100g以下限定)本来、大きい動物も小さい動物も、外敵から身を守るために仕方なく変化した形である。よってもし外敵がいない場所で暮らしていけるならば、進化の過程でだんだんどちらの動物も中庸の大きさの動物に変化していく。昆虫はなんかよくわからんが凄い人間はほかの動物と空間にしめるエネルギーとか身体の大きさから占めるエネルギー量をやばい程オーバーしている。これだけかな。思いのほか残っているじゃないか。一週間後まで残っているかどうかはわからんが。だからこそこうして書き遺しておこう・・。あと面白いな、と思ったのはこの上で書いたような、大きい動物も小さい動物も外敵から身を守るために仕方なく変化した形というところだ。これを島の規則といっており、日本とアメリカもこれで説明するとよくわかるという。 島国という環境ではエリートのサイズは小さくなり、ずばぬけた巨人と呼び得る人物は出てきにくい。逆に小さい方、つまり庶民のスケールは大きくなり、知的レベルはきわめて高い。「島の規則」は人間にもあてはまりそうだ。何も日本の過去の大人物たちをけなしているわけではない。ただ、傾向としてこういう事があるというだけだ。カラオケなども、日本はプロは別にうまくないが、一般人がみんな歌が上手いという(関係あるのか?) 大陸に住んでいれば、とてつもないことを考えたり、常識はずれのことをやることも可能だろう。まわりから白い目でみられたら、よそに逃げていけばいいのだから。島ではそうはいかない。出る釘は、ほんのちょっと出ても、打たれてしまう。だから大陸ではとんでもない思想が生まれ、また、それらに負けない強靭な大思想が育っていく。獰猛な捕食者に比せられるさまざまな思想と闘い、鍛え抜かれた大思想を大陸の人々は生み出してきたのである。これは偉大な事として畏敬したい。しかし、これらの大思想はゾウのようなものではないか? これらの思想は人間が取り組んで幸福に感じる思考の範囲をはるかにこえて、巨大なサイズになってしまっているのではないのか?人間にも適切なサイズの思想があるというのは非常に興味深い話である。利己的な遺伝子でもいっていたがミームともつながってくるような気がする。情報や思想というのも生き残りをかけて、少しでも長く生き残ろうとするのだ。それが、大陸のような広い場所だと競争相手が多数おり、生き残るために強靭な思想にならざるを得ず、それ故に大陸の思想は太く死にづらくなっていくのではないか。読んでいて思ったのはほかに、昆虫って凄いな、という話だ。まず飛べるのが凄い。あいつらおんな硬い殻に覆われていながら空を飛ぶ事が出来る。恐ろしい奴らだ。しかもやつら葉っぱを食う。誰もそんなものくわないのに。しかもあいつらなんか変身する。蝶とかに。やばい。なんだか虫に惹かれる人たちの気持ちが少しだけわかったような気がする。大嫌いだけど。
2008.07.23
コメント(0)
-
ブラック・ラグーン シェイターネ・バーディ/虚淵玄
あらすじなんか忍者出た。感想 ネタバレ無最初の20ページぐらい、微妙な違和感を覚えていたがそれ以降は、ちゃんとしたブラックラグーンとして読む事が出来た。多分最初の20ページで違和感に感じたのは単純に、媒体が変わったことによるズレの修正にかかったページ数というだけだろう。とりあえず何が言いたいかというと忍者が出てきた忍者が。しかも滅茶苦茶おいしいキャラだった。ただひとつ残念な事があるとすれば、ひょっとしたら小説版で忍者を出してしまったばっかりに、広江さんが本編で忍者を出せなくなってしまうのではないかという事だけだ。あるいは小説版のキャラを登場させるという選択肢もあるかもしれないが、広江さんが自分で考えだした忍者をブラックラグーンの世界に登場させてほしかった。何しろ自分、小さい頃は忍者が好きで好きで将来は忍者になろうとおもっていたぐらいだ。戦隊物の忍者のやつをみたせいでもあるし、ピザを食う亀にはまったからでもあるのだけれども。NARUTOも始まった当初は興奮したものだが最近は何だかよくわからなくなってしまった。忍者が出てきたというその一事だけでこの小説の評価は自分の中で2階級特進である。しかもカマセではない。ネタバレだが。それから単純に話は面白かった。小説版、ブラックラグーンの体裁を完全にまっとうしている。シーンの格好良さだけじゃなく、微妙な人間ドラマまで魅せてもらえるとはおもわなんだ。それから信じられないネタキャラが忍者のほかにもう一人いた。笑わせてもらったな。こうして考え直してみれば笑って、漢泣きして、およそ自分がライトノベルに求めているものを完璧に満たしてくれたような気がする。ほめすぎだろうか。ただ色々やってみせたせいか、全体的にあっさり感が漂っているのは仕方のないことなのだろうか。どれもこれも中途半端とはもちろん言わないが、どこか一点に絞って書いてみてもよかったのではないかと勝手な事を書いてみる。いろんな展開がいちいちあっさりなのだ。ネタバレ有スタニスラフの最期 「なら、故郷から北風だ・・・・・アカマツの・・・・匂いが、する・・・」風を読むことで生きてきた男の最期が、滅茶苦茶格好いい。思えば昔から人の最期は自分の故郷を思い出すというパターンが多い。このラストシーンは映画、ブラッドダイヤモンドを連想させた。死ぬ時に思い出す故郷がない人間は、悲しいだろうか。でもよく考えたら故郷というのは、何も土地だけじゃないものな。母親だって恋人だって自分が一日しか滞在してない土地だって、自分が故郷だと思えば故郷か。それにしてもスタニスラフは本当にいいキャラだったなぁ。面白いだけなら忍者にアルティメットクールさんがいるからいいとして。最初のあのへろへろのひでぇ状態から、あそこまで株を持ち直すとは思わなかった。 「こんな私が柄にもなく、あの素晴らしい夕陽をもう少し眺めていようと思ったのさ。それほどに嬉しかった。心に祝杯を掲げたよ。何せ彼は来なかったのだから」 「彼は屈服による安寧よりも、闘争の継続を選んだ。地獄の底の袋小路で、なおも不屈という在り方を貫いた。彼は紛れもなく我が同胞だ。今なお我々と同じ魂で、血染めの夢を見続けている。・・・・ ああ、今ようやく私は再会の喜びを噛み締めているんだよ。彼とはしばし道を違えて、互いの立場に齟齬が出た。ただそれだけのことでしかない。我々は今また同じ夢を見て、同じ道に殉じようとしている」 「だから、譲らん。彼の望みも、彼の渇きも、私が満たす。私が彼を祝福し、彼の夢を埋葬する。──なあ張、最低の腐肉と貴様はいうがな。我らにとってはこれが極上の晩餐だ。私も、今ここに理想を遂げんとしている。戦い抜いて果てるという意地を」格好よすぎるだろ・・・。村上春樹の羊をめぐる冒険のねずみのセリフを思い出した。僕は僕の弱さが好きなんだ、誰にも渡すつもりはない、みたいなセリフだったんだが・・・。それがこの、中身の良さとかは関係無しにただ格好いいというスタイルが完全にブラックラグーンだな、と感じる。それからバラライカが我が遊撃隊にはたった一人の裏切り者も絶対にあり得ないと断言して、だからお前が犯人だと突き付けるシーンは漫画にしてもアニメにしても最高に格好いいだろうなと思った。もちろん小説でも。それにしても忍者だ。忍者の容姿が、日本人っぽいスラっとした細身で俊敏な動きが可能そうな忍者を予想していたのだが、イラストは滅茶苦茶ごついわ顔も異常にごついわでなんだか無性に悲しくなってしまった。それにしても忍者、おいしすぎるのである。神出鬼没だわ強いわ生き残るわ。これはもう再登場を期待するしかないのである。漫画か、あるいはノベライズ第二弾か・・・。しかしノベライズを虚淵玄に任せたのは全く最高の判断だったと、読み終わる前から思っていたし、読み終わった後もその気持ちにみじんの揺らぎもない。Fate/zeroといいブラックラグーンといい、ノベライズしか出していないのが気になるが、それ故にノベライズ特有のやり方、空気というのもわかっているのが虚淵玄なのであろう。全くいい作品であった。2008/7/20
2008.07.21
コメント(0)
-
嘘つき男と泣き虫女/アラン・ピーズ&バーバラ・ピーズ
感想 ネタバレ有無いわー。確かにいろいろな所から情報を集めたのは確かなのだろうが、その集めた情報を自分の都合のいいところで自分の都合のいいように出してあるべき結論に持っていこうとするような論調にしか感じられなかった。まぁよく考えたらそうやるのが普通にどんな場合でも、常套手段というか普通のことだったのだが。それでも男は~~~風に考えるものなのです!と断定口調に書かれている事のほとんどすべての事が自分に当てはまらないのはどうかと思った。むしろ女の特徴にあてはまるぐらい。中には例外もいるよ、ってことなのか?男は車の運転が得意だとかいうけど、自分なんて車の免許が取れた事が奇跡的なぐらい運転が下手だし....およそ男に関する情報が自分と全く当てはまらないので、同様に女性に対する情報も全く信用できなかった。確かに世間一般にいる人間を一列に並べて、平均化したらここで書かれているような女性が浮かび上がってくるだろうが、いったいそれに何の意味があるんだ?また各章ごとに、問題とその解決策が提示されているが、言われなくてもそれぐらいわかるわ! と怒鳴りたくなるようなチンケな解決策ばっかりだ。しかも世の中の男は、みんなそんな解決策ぐらい知っているうえで、その解決策をとれないから悩んでいると思うのに・・。男はチャンネルを変えるとかいう、局部的な話もわからんしな。チャンネルなんか変えないわ・・・。むしろ変える人間をみると、何でそんなにチャンネルを変えるんだろうという気分になる。ことあるごとに、男は昔狩りをしていたから脳が~とかいうが一体どれほどの核心があってそんなこといっているんだ?チャンネルを変える男に対する対応策 チャンネルをしょっちゅう変える男には、いらいらするからやめてくれと冷静な口調で話をする。それでも効果がなかったら、リモコンを隠すか、自分専用のリモコンを持つか、テレビをもう一台買う。それができねーから困ってるんだろうがバカ野郎。それぐらい誰だってわかっとるわ・・・!男は道に迷っても素直に尋ねられないという話があったが、少なくとも自分の周りに居る人間にそんな男は居ない。あるいはこれは日本では全く受け入れられない話なのだろうか?でも前作の地図が読めない女とかいう本は日本でもうれていたみたいだから、日本でも受け入れられているのだろうか。本能的に厭な行為を、あなたのずっと昔の先祖から続いてきた本能的な嫌悪感です、原因はあなたの脳ですと説明されても、だからなんなの?という。この本を読んで男と女が理解できたっていう人間は多分全然理解出来ていないと思う。知識と知恵の違いを例にあげるまでもなく。普通にいろんな人間と付き合っていく中でわかる事ばかりだ。ただ、だからといって全く面白くないわけではなかった。最初の方は確かに楽しめて読めていたような気がする。後に行くほどくどくなり、同じ事を同じ方法で繰り返すので飽きてきて最後の最後はもう何の意味もない文章だからと読むのをやめてしまう。ジョークは面白いし、男と女の脳の違いによる判断の違いを説明されるのも、まるで無意味ながら少しは面白かった。何しろここに書かれている脳の違いというのは、勉強が嫌だと言っている人間に向かってそれはあなたの脳のせいだ、といっているようなものだ。そんな事言われたってどうしようもない。 今朝、妻の母親がうちに来たんだよ。と愚痴のところで「しばらくここにいせてもらえる?」と聞くものだから、「もちろんですよ、お義母さん」と答えてドアを閉めたよ。
2008.07.20
コメント(1)
-
AURA ~魔竜院光牙最後の闘い~/田中ロミオ
あらすじ喰らえー!ひっさつ魔剣七式ー! ちゅどーん!感想 ネタバレ無思いのほか面白くてびっくりした。タイトルを見ても絵を見てもプロローグを読んでも全く期待できなかったのに!最初っから最後まで混沌とした内容を貫きながら最後は最後でやってくれる。内容があれなのに、現代版文学というか、ライトノベル版文学的テーマの追及みたいなひどい有様。しかし面白かったぞー!穴があったら叫びたいものだ。またしても脇役の姉貴が一番好きなキャラだ。何だか自分の好きになるキャラクターの傾向が分かってきた気がする。最後はうまくまとまったかと思いきや最後の最後まで混沌としていた。もう全く混沌としていた。中盤までは笑わせてもらった。何だか、オチがうまくついて笑うというよりも、全体的に蔓延した笑いの空気にやられた。にやにやしながら読んでいたような気がする。これを本人が言うように学園ラブコメとして売りだしたらいろんな人が怒りそうな気がする。厨二病と言われる設定を逆手にとってネタにしてしまうとは・・。しかもそれで一本長編を書きあげるんだから凄いという他ないな。タイトルからしてすでに痛々しすぎる。これはひどい。思わず買うのをためらってしまうレベル。ただそこを乗り切れば何か別のものが待っている・・!はず。ネタバレ有異常にテンションの高い自称戦士達が、普通人たちによっておかしいことを指摘されているところは全く胸が痛い。普段元気のに突然しょげてるのが痛い・・・心に突き刺さるぜ・・。 黒歴史と呼ばれるようなものは意外や意外、もっていないがあるいは今現在黒歴史進行中なのかもしれないがえてしてそういうのは進行中の時は気がつかないものである。実際そんな人間がいたら、事実を突き付けていう方が一番つらい気もするが。現実にこのクラスにいるような人間がいるはずもないが、まぁ事実は小説とは奇なりというぐらいだし、案外いるのかもしれないな。自分が通っていた学校には一人もいなかったが。イジメも無い学校だったので全く平和な学校であった。もちろん感知していないところでイジメぐらいあったのかもしれぬが。最後クラスのほぼ全員が厨二病に感染するのも、なんだかノリのいい昔の学園モノのノリみたいで楽しかった。頭の片方でねーよ!と思いながらもそれもあるあると思うようなそんな絶妙の間。小説を読むと、批判される場合どこが批判されるかがなんとなくわかるのだが、この作品だとわからんな。全部批判する人か全く批判しない人の二極化になりそうだと勝手に思った。この普通になりたくなくて、社会に適応できない人間はどこで生きていけばいいのか、人の輪の中に入っていけない人間はどこに逃げればいいのか、みたいな問いはずーっと繰り返されてきたテーマだよなぁ。人間失格とかもそうだし。田中ロミオ版人間失格なんていったら噴飯ものだが。 「わかるよ。くっだらねーよなぁ。学校とかほんとくだらねーわ。いいこともあるけど・・・・・・悪い事はその数倍もあるよ。けど考えてみろよ。この魔法も植物もいない世界には、敵だけはいてくれる。闘い放題だろ。・・・・・まあ、見えない敵ばっかりだけどな」この答もまた色々な作品で言われセリフをかえ中身をかえ状況を変え本当にいろんな場面で言われてきた答えだよなぁ。考えてみればこういう、答えの出ない問いみたいなのに対する答えなんて、がむしゃらに前に進め、しかないわけであって。ただこんなやり方でそれを見せてくれる、っていうところがやっぱり面白いわけで。
2008.07.19
コメント(0)
-
小生物語/乙一
あらすじ乙一の日記感想 ネタバレ有はげわろた。まさか日記ごときにこれほど笑わされるとは思わなんだ。読み始めた時は、っは なにくだらないことを書いていやがる、ぐらいの心持ちで臨んだのに3分もしたらその決心は砕け散っていた。それにしても読み始めてから少しの間、これがうそ日記だという事に気付かなかった。特に最初の第一部、愛知編に出てきたA君の存在がウソだったというのは、読んでいた自分を戦慄させた。特にウソをつく必要のない場面でウソをつくのは卑怯である。まったくもって疑う事が出来ない。CDショップから流れる音楽があまりにもうるさいのでCDを取り換えたという話も明らかにウソだが面白い。というか、自分はこうやって面白かったところを一つひとつ取り上げていって、このエピソードが面白かった、あのエピソードが面白かったと延々と語りつづけるつもりなのだろうか? それは避けたいところである。最初は面白いと思ったところを折っていたのだが、20ページを超えそうになったところであきらめた。こんなに引用ばっかりしていたらいくら個人ブログといえど非難GOGOである。一つ一つの話にオチがついていて、よくこれだけ考えつくなという感心。いやしかしこれは読まないとわからないな。あまりにも影響力が強すぎて、自分もうそ日記を始めたくなることうけあいだ。しかしもちろん、これほど面白く書けるはずもないので書いているうちに、自分の力量の低さに恥ずかしくなって途中であきらめることもうけあいだ。でもこの日記冷静になって読むと相当恥ずかしいかもしれない。それにしてもよく出版されたものである。本当に書く事がない。面白かったなぁーあははわらったわらった。としか書けない。まぁよく考えたらそれも当然なのだが。何しろ内容と言ったら全部ウソなので論議するようなことでもないし。面白かった所を一つ一つあげていったら日が暮れてしまう。結果何にも触れずにそっとしておくのが正しい選択肢なのだ。ひょっとしたらこれ、今まで書いた中で一番短い記事かも。さようなら2008/7/18 読了
2008.07.18
コメント(0)
-
ゴールデンスランバー/伊坂幸太郎
あらすじ逃げろ!オズワルドにされるぞ!感想 ネタバレ無間違いなく面白い。全く無駄のない数々の描写に、圧倒された。これは伊坂だからという点もある。少しでも不思議な点、不自然な点があると期待してしまう。伊坂ならやってくれる──そのせいでさりげない描写でも伏線として機能して、のちのち生きてくる。あとやっぱりなんといっても会話が最高。こんな会話、伊坂にしか書けねえ。逃げろ!オズワルドにされるぞ でしびれた。何故か泣けた。帯に、現時点での集大成と書いてあるように、確かに伏線、会話、ストーリーとどれをとっても完成度の高さはほかの作品を圧倒しているように思えた。しかし作品自体の面白さが、他の作品よりも飛びぬけているかというかと、少し疑問に思ってしまうのが小説の難しいところか。ラストの終わり方に納得のいかない人も多いのではないかと想像する。それにしてもマスコミは酷い言われようだな。まぁそれだけの事をしているのであるが。序盤はスロースタートで、中盤から駆け足かな。加速していく。話がでかくなればでかくなるほど、ほころびもでかくなる。そのほころびを悟らせないようにするのが、作者の力量だと思う。そろそろさすがに、伊坂幸太郎がいつもあとがきでいっている現実とはかけ離れた部分が多い、という部分を読者に納得させられなくなってきたのではないか。ここがギリギリ限界点といった感じがする。正直いってラストああくるとは全く予想してなかった。やられた!っと言う感じだ。読み終わった後は誰かれ構わず、これを読め!とつきつけたい衝動に駆られた。そういえば伊坂幸太郎を好きだという人間はよく聞くけれども、嫌いだという人間をあまり聞いた事がない。何故こんなに伊坂が一般人に受け入れられるのか、感覚としてはわかるのだがうまく言葉に出来ない。信頼、というもののなんと美しい事よ。感想 ネタバレ有七美が最高すぎる。まさかラストも七美が持って行くとは。まさか真の主役は七美ではないか?ゴールデンスランバーの格ゲーが出たら間違いなく隠しキャラだな。間違いない。それにしてもドラマにしたらおもしろそうな話だ。何しろ派手なのがいい。ただ過去と現在が入り混じるのはわかりずらいから変えた方がいいか。それからラストで助けたアイドルが出てくるところ。今まで散々アイドルを助けたアイドルを助けた、って強調していたのも、やはり伏線だったのか。やはりラストは予想外な出来事で締めくくりたいよね。しかしテレビで散々犯罪者だ!と騒ぎたてられているのに、それでも犯人じゃないと信じてくれる人たちがいるっていうのは、なんて心強い事なんだろうと読んでいて思った。もちろん現実じゃそううまく行くはずもなく、息子はやっていないなんて主張をするオヤジがテレビで放映されたなんて話とんと聞いた事がないからな。あるいは、いたとしても映っていないだけか。人を信じる事が出来る奴は、人から信じられる事が出来るのかもしれない。 「俺なんて、ドストエフスキーのこと昔、刃物を持ったエスキモーだと思ってましたけどね。ドスとエスキモー」笑った。いったいどこからこんな発想が出てくるんだ。だいたいドスって日本語じゃねーか。 「すぐに返信しないタイプの子かもしれないっすよ。受信がうまくできなかった、とか。センター呼び出し、してみました?」 「俺がセンターだったら、激怒するくらい、呼び出したよ。メールはありません、って。こっちだってそんなの重々分かってるっての」アホすぎる。激怒するくらい呼び出したよってとこが滅茶苦茶面白いな。普通ここにこうやって改めて書くと全然面白くないような気がしてくるんだが、ドスとエスキモーも激怒するくらい呼び出したも全く色あせずに面白い。それにしても三浦のキャラがよくわからん。何の面白みもないキャラだったような気がする。確かにかなり役に立った事はたったのだが、印象が弱い。死んでしまったし。俺は犯人じゃない、と書いて車のサンバイザーに挟んでおいて、しばらくたって戻ったら、だと思った、って書いてあったとかいうところを読んだとき不覚にも泣いた。卑怯じゃろ・・・。 「名乗らない、正義の味方のおまえたち、本当に雅春が犯人だと信じているのなら、賭けてみろ。金じゃねえぞ、何か自分の人生にとって大事なものを賭けろ。おまえたちは今、それだけのことをやっているんだ。俺たちの人生を、勢いだけで潰す気だ。いいか、これがおまえたちの仕事だということは認める。仕事というのはそういうものだ。ただな、自分の仕事が他人の人生を台無しにするかもしれねえんだったら、覚悟はいるんだよ。バスの運転手も、ビルの設計士も、料理人もな、みんな最善の注意を払ってやってんだよ。なぜなら、他人の人生を背負ってるからだ。覚悟を持てよ」覚悟を持てよ──間違いなくこの本の中での1,2を争う名シーンだ。いったいこの文章を完成させるのにどれぐらいの時間をかけたのか。よく練り込まれていると感じる。名乗らない、正義の味方のおまえたちって格好良すぎるだろ・・・。大絶滅の感想でも書いたけれど、人を告発する事は誰だってできる。わかりやすい悪に向かって悪口をいい、正義の味方になることは誰にだってできる。それが問題なのだろう。まったくかっこいいぜオヤジ。それから最後のたいへんよくできました、か。やばいなぁ。白ヤギさんとかの話も伏線だと思ってたんだが大したこと無かったな。なんかまだ書いてない事があるような気がするけれどこのへんで。2008/7/16 読了
2008.07.17
コメント(0)
-
人間失格/太宰治
読書熱沸騰中、果たして何日続くものやら。あらすじ人間失格感想 ネタバレ無暗っこの話暗っ遮光カーテンとかで真っ暗にした部屋ぐらい暗いっ。読んで中断し、人と話してる間も何だか他人が乗り移ったかのように憂鬱な気分だった。人を憂鬱な気分にさせるとは恐るべき小説だ。しかし全く有用ではないな。ある意味こういった本を呪の本というのだろう。まったくひどい話だ。訴えたら勝てそうだぞ。勝てないけどよく本気は人に伝わるというけれどこういう負のエネルギーも本気と同じぐらい伝わるのではないだろうか。なんか死にてー死にてー言っているようなそんな負のオーラが近寄ってくる。まぁこれを書いたあとに太宰治が死んだからそう思うだけなんだけどね・・・。面白かったか?と聞かれたら多分暗かったと答えるだろう。多分聞いた方は怒るだろう。面白いかつまらないか聞いてるのに暗かったと答えられたら当然だ。まぁなんか面白いかつまらないかとかよくわからないけれどそういった方向の話じゃなくてなんか暗かったという印象しか残らなかった。斜陽と比べたら断然斜陽の方が面白かったが、どちらがより凄かったかと聞かれたらどちらか迷う。なんてひどい感想。何でこんなにこの主人公は暗いんだろう?と疑問に思う事が出来たらその人は恵まれているのだろう。ってことは自分、恵まれている。やったね!しかしもっと自伝的に書かれているのかと思っていたんだが、意外とそんなことなかった。むしろ普通に小説じゃないか。太宰の生涯を知らないと理解できないのかと思ったが、そんな事ないな。個人的にはストーリーというよりも、ところどころにある印象的なセリフを拾い読みするだけでも十分に楽しめる作品だ。もし仮に深く読みこんだとしても、太宰自身の生涯を考える事にしかならず、もう死んでしまった人間について考えるのも少々バカらしいものがある。それだったら上辺だけ読んであははーこの作品暗いねーとアホみたいに笑って読みたいものである。ネタバレ有 自分の幸福の観念と、世のすべての人たちの幸福の観念とが、まるで食いちがっているような不安、自分はその不安のために夜々、転転し、伸吟し、発狂しかけた事さえあります。天才は早死にだ。少なくとも30代手前で死ななくては天才ではないのではないかという勝手な持論を自分は持っている。もちろん根拠はない。なんとなくそう思っただけだ。アインシュタインだって長生きだしフェルマーだってニュートンだってみんなみんな長生きだ。考えすぎだ!多分伊坂の小説に影響を受けたんだな。確か登場人物がそう言ってた気がする。その時30手前で死んだ人間の例としてビートルズかなんかのバンドマンをあげていたな。そうか、芸術方面の天才か。なるほどなるほど。数学方面の天才しか考えてなかったぞ。うむむ。なんかいたかな、芸術方面。ピカソは長生きだしダヴィンチも長生きだ!なんてこった!もう知らんわ 女があんなに急に泣き出したりした場合、何か甘いものを手渡してやると、それを食べて機嫌を直すという事だけは、幼い時から、自分の経験に依って知っていました。実はこの人間失格友人に借りたのだが、この部分に入念に線が引いてあって思わず笑ってしまった。そうかそうか・・・そんなにここが重要だったか・・。今度からそうしよう・・・。 用をいいつけるというのは、決して女をしょげさせることではなく、かえって女は、男に用事をたのまれると喜ぶものだという事も、自分はちゃんと知っているのでした。ここにも線が・・・。勉強になります。太宰先生。まったく太宰先生の時代から女も男も進歩していないであります。それにしても本当に女によくもてる。何だか色々な感情が湧きあがってくるなぁこういうものを読んでいると。もやもやっと。何でそんなにもてるねん、みたいな。 ああ、人間は、お互い何も相手をわからない、まるっきり間違ってみていながら、無二の親友のつもりでいて、一生それに気付かず、相手が死ねば、泣いて弔詞なんかを読んでいるのではないでしょうか。それはそれで悲しいが、それがどうしたの?という感情が湧きおこる。死んだ本人が墓場まで持っていけば、その状態に何の問題も起こらない。むしろ自然な事だ。そんな事に一々矛盾を感じてしまうから、もちろん人間失格ということなのだろう。矛盾を矛盾として肯定できないと、矛盾だらけのこの世界で生きていく事は出来ないのだろう。それにしてもこの小説は、あとがきまで小説の一部なんだなぁ。あ、そういえば内容についてほとんど語っとりゃせんがな。こりゃまいった。なんか1年後には完全に内容を忘れてそうだからここに書いておかないと・・・。自殺に何度も失敗した人間の心理状態っていうのは、一体どういうものなのだろうか。いつだって死んでやる、というような心理状態っていうのは意外と何でもやれるのではないか、なんて当たり前の論理じゃなくて、自傷行為によって死ぬような気配だけを装って満足するとかいう底の浅い話じゃなくて、本気で死のうとして何度も助かるとしたらそれはいったい何がたまっていくのだろう。まぁ太宰が本気で死のうとしてたかしてないかなんて知らないし興味もないのだが。4回だか3回だか失敗しておいて、何を思うのか。意外と、次はうまくやるぞ!っていう前向きな意気込みだったりして、死ぬのに前向きってのもおかしな話だが。目標自体が後ろ向きなのに意気込みだけは前向きか、ちょっと面白いな。Funnyだ。2008/7/15
2008.07.16
コメント(0)
-
疾走/重松清
まさに「疾走」オーバードライブ!感想 ネタバレ無ラストまで駆け抜けた。なるほど、読むのが止まらないというのはこういう事を云うのだ、と読み終わってからしみじみと思った。今までも、よむのが止まらないという作品には何作も出会ってきた。その作品は面白かったから読むのが止まらなかったり、先が気になるから読むのが止まらなかったり、要するに理由があったような気がする。ただ、この作品の場合、作者の意図するままに操られて疾走させられたと、そんな気分だった。もちろん面白い、それに先が気になる。というかそれは凄い作品の必須条件であるように感じるが、それだけじゃなかった。面白い作品を書いたから結果的にそうなったのではなく、最初からそれを目指したら結果的に面白い小説になった、というのが正しい。うまく説明出来ない。最初の数ページでひきこまれ、ラストまで同じテンションを持続させ続けて読み切った。同じテンションでいられたのは特異な語り口のせいだろうか。常に同じテンションで、ペースで語られる故そのペースに、マラソンのペースメイカーのようにぴったりと歩調をあわせられるその感覚。ベルカ、吠えないのかの神視点を彷彿とさせる。素晴らしい。特に上巻の終盤あたりから最後までは、ほとんど休憩を挟まずに読み続けた。ラスト付近は涙無しには読めないだろう。もしくは、何かを感じたはずだ。あるいは嫌悪感かもしれないけれど。最後まで救いのない物語だった。あるいは人によっては、最後は救いや希望だと感じたのかもしれない。全編を通して聖書の言葉が引用されている。幸福とは何か、なんて面白くもない事を考えさせられてしまうぐらいには暗い話だった。それにしても、色々考えさせられる。はたして色々考えさせられる物語が、良い物語なのかどうかというのは、よくわからない。読む目的にもよるか。ただうまく説明出来ないのだけれど、言葉では説明できない何かなんて言うと一気に陳腐というかキザというか、基本的に物事は何だって言葉では説明できないとかいう屁理屈を置いておいて、概念をぶつけられたというか、難しいなぁ。いろいろなところに、性的な描写がある。どういう意図のものかは考えてみる価値があるだろうか。ないかな?それにしても下巻の中盤辺りまでは本当につらい。自分は上巻を読んだ勢いでそのまま突っ走ったからよかったけれど、いったん中断していたらどうなっていたことやら。自転車でいうならば上巻を読みぬけた慣性でそのままいったわけだ。しかもその先に報われる結末が用意されているとは到底思えなかった。ネタバレ有シュウジはどこまでもツイてない男だった。兄は放火をし精神崩壊を起こし、父は金持って逃げ、母親も借金まみれになってどこかえ消え、自分も逃げた先で人を殺してしまう。およそいい事なんて何一つ無い。もちろんイジメもあった。マイナスしかない。ここから這い上がる事なんて、出来るのか?精神崩壊した兄が復活し、父が金を持って戻ってきて、母親も戻ってきて殺しもなかったことになる、そんな幸せな未来が来るはずがないのだ。こんな状態で生きていたいと思えるはずが、無いだろう。知り合いと、生きていく時に、大事な事は何かというのを話し合った事がある。知り合いは、現状に満足して、いつだって「今」が幸せな状態だと認識することが生きていく上で大事なことであるといった。身の回りにあることで幸せを追求するのだと。反論した。仕事をして、かえって寝るだけの人間にお前はそれを言って、仕事に幸せを見つけ出せというのか、と。そうだと答えた。はたしてシュウジに同じ事が言えるだろうか。家庭が崩壊して家もなくなって殺しをしてしまってそれでも、そんな状態の人間に、お前は今幸せなのだと、紛争地帯に居る人間や、ゴハンにありつけないで死んでいく人間よりお前は幸せだと言えるのだろうか?誰が死にたいと思ったシュウジを責められるだろうか。殺してくれと頼んだエリを責められる? 死にたいと思う事は悪いことなのだろうか。からっぽな目だと作中で何度も言っている。まるで穴ぼこだと。希望も何もない状態だとそうなるのだろうか。またシュウジは誰にも期待しなくなる。人に期待しないというのは、怒りとかそういった感情からも切り離される事だ。他人が何をしようが、それはその人が勝手にしたことで自分とは全く関係がない事だと認識する事だ。悲しい事だとは思うけれど、そこまで悪い事だとは思わない。ただまだ15歳なのに、人に期待するのをやめてしまった事は悪い事だろう。大人になるまで生き延びられたら、死ぬ事もなかったのに。大人になるまで生き延びる事ができなかった。戦争から帰ってきた人間は、まわりの人間があまりにも普通に過ごしているのを見て、精神の均衡が崩れるという。 どこまでも不幸だったシュウジは周りと自分を比較して、精神の均衡が崩れないはずがあるか。まわりが幸せな中の不幸は周りが不幸な中の不幸よりよっぽどつらいんじゃないだろうか。ある意味これは聖書か?人々の罪を背負ってしんだキリストが、シュウジなのか?シュウジは復活はしないが。それにシュウジは「ひとり」を背負った。 神視点だと思っていたが、神父視点だったのには訳があるのか。 罪を犯そうとするひとを止められるのは、そのひとの丸ごとすべてを信じている相手だけなのです──普通、それをやるのは両親の仕事だ。もし死んでいたとしても、信じられていたという過去の経験がその人を支える。あるいは過去の信じられていた頃にされた自分の行動が。誰が悪いかっていったら全ての元凶は両親だろう。何がというまでもなく、全てがダメな親だった。ある意味こういった親を痛烈に批判している。一見するといい親にうつるのにその実情ときたら・・。いかん、いらついてきた。 仲間が欲しいのに誰もいない「ひとり」が「孤立」。 「ひとり」でいるのが寂しい「ひとり」が「孤独」。 誇りのある「ひとり」が「孤高」。なるほどなぁー。誇りのあるひとりってのがどうにも想像できないけれどな。エリみたいなのっていわれたらそれまでなんだが・・。どうにもしっくりこない。 聖書の時代から、どうしてひとは物語を紡ぎつづけ、語りつづけるのか、おまえたちは知っているか? ひとは、同じあやまちを繰り返してしまうものだから──だ。ここでいうおまえたちとはエリとシュウジの事。しかしどうもこういうセリフを読んでいると、どうしても神父というより、神の事を意識しなくてはならない。断定口調だ。ひとは、と全てをひとくくりにしている。それを断定口調で言えるのは、神しかいないのでは?あるいは神父という身体を持っているけれど、魂は神という見方も出来る。シュウジの事について、これほど綿密に語れるのはやはり神しかいない。神父が語り手だけれど、神父は神なのだ、と自分の中では結論を出してみる。それにしては神父に弟がいたりとそう考えると微妙な結論だがまぁいいだろう。誰に迷惑をかけるでもないし。2008/7/12 読了
2008.07.15
コメント(0)
-
永遠の出口/森絵都
あらすじいろいろなものをあきらめた末、ようやく辿りついた永遠の出口。私は日々の小さな出来事に一喜一憂し、悩んだりま迷ったりをくりかえしながら世界の大きさを知って、もしかしたら大人への入口に通じているかもしれないその出口へと一歩一歩、近づいていった。時には一人で。時には誰かと。感想 ネタバレ無それにしても森絵都の本はまだ、カラフルとこの永遠の出口しか読んだ事がないけれど、青春小説というジャンルに限って言えばこれ程洗練されている書き手もいないのではないか。女子の世界のイジメについても書かれている。色んな女子のイジメの事を書いた小説を読んできたが、読んでいて微妙な気分になる。自分が過ごしてきた世界の反対ではこんなイジメがあったのかと。自伝か?と疑ってしまうほどの完成度の高さ。それが常に褒め言葉になるとは思わないけれども、この作品に限って言えばこのリアリティあふれる世界というのは非常に心地がよい。もしくは心地が悪い。感情移入させられる。実話的でありながら、フィクションとしての面白さが全く損なわれていない。普通を普通として書けて、しかもそれを面白く書けるというなかなか難しそうな事が出来る稀有な作家ではないか。まるで丸戸氏のように。また、「特別」を作らないようにどのキャラクターにも深く立ち入らないような構成になっていたように思う。誰か特定の人間の描写だけが深い、ということはなく、どの登場人物も実際の人生がそうであるようにだれもかれもが行きずりのキャラクターだ。またいったん離れ離れになっても、ひょんなことからまた道が重なる事もある。家族についても同様の扱いだったかな。そこまで深く触られていない。あらすじに書いたのは本文の中の文だが、そこにあるように流れゆくときの中で時には一人で、時には誰かと歩んでいく様子が書かれていた。読み終わった時にまるで、自分の人生を思い返しているようなそんな感慨深い思いにとらわれる。ネタバレ有一番好きなキャラクターはお姉ちゃん。だけど特別なエピソードが語られるわけではなくあまりにもサラっと流されてしまった。悲しい。いじわるながらも優しいというツンデレの典型を踏まえながら、一見すると強いもののその中に色々な葛藤を抱えているっていう設定のキャラに弱いのかもしれない。これからはちょっと意識して読んでみるか。恋愛の話題もたくさん出る。失恋した時の話が割と印象的。常に相手の事を考えていて、失恋によってそれが無くなってしまった時に考えていた時間が、部分が無くなってしまってその喪失感で悲しくなるのだ。自殺の原因に、失恋という理由が以外に多いのも上のような理由だろう。自制できるようになればいいけれども、自制出来ないうちは際限なく考えてしまって、その重さに耐えきれなくなって辛い思いをするのだ。 それから長い年月が流れて、私たちがもっと大きくなり、分刻みにころころと変わる自分たちの機嫌にふりまわされることもなくなった頃、別れとはこんなにもさびしいだけじゃなく、もっと抑制のきいた、加工された虚しさや切なさにすりかわっていた。どんなにつらい別れでもいつかは乗りきれるとわかっている虚しさ。決して忘れないと約束した相手もいつかは忘れると知っている切なさ。多くの別離を経るごとに、人はその瞬間よりもむしろ遠い未来を見据えて別れを痛むようになる。成長するってのも考え物だな。経験をつむのも考え物だ。 友達の一人はデートの前に逃げ出したいほど緊張し、実際、なぜか銚子の犬吠埼まで逃げ出してしまい、デートをすっぽかされた相手から絶縁宣言をされて、独りで銚子へ行くほどのバイタリティがあったならなぜ彼と向き合えなかったのかと泣いていた。笑った。あまりにも途方もない話すぎてこれはむしろ実話なのではないかと疑ってしまったぐらい。ていうかこれ舞台どこなんだっけ?知らない地名出されると全く記憶に残らないので困る。地名書いてあったかなぁ。というか読むペースが割とはやいせいか、そういう記憶に残しても残さなくても物語の本質にあまり関わらない話、みたいなのは割とスルーしてしまう癖がついているように感じる。いかんなぁ。ていうか表紙の皿にのってる黄色い物体は何だ?黄金か?砂金か?オムライスか?そんな描写あったか?ていうか女の子が泣いてるようにみえるのだが何故だ?オムライスが嫌いなのか? レモンシロップがかかったかき氷のようにもみえる。適当な事書きすぎだが。しかしいい感じに青春小説だった。青春小説でお勧め無い?ってきかれたら真っ先にこれと答えるかもしれない。違うかもしれない。表現がよくわからないが、むき出しの青春という感じがした。 2008/7/12
2008.07.14
コメント(0)
-
オイレンシュピーゲル4/冲方丁
あらすじ書こうと思ったけど面倒くさいと思ったけどやっぱりこうやってあらすじとして本の中身を要約するのは、何かの能力アップにつながるのではないかという姑息な打算を胸に秘めあらすじを書こう。空港で旅客機が占拠された。さらに中国から戦闘機で亡命を希望する人物が。さらに中国組織がその人物を狙い空港に攻め入りさらにさらにテロ組織まで入り乱れ空前絶無の三つ巴の乱戦が幕を開けるのであった。さらにその事件は二つで一つの事件で──!?とかなんとか書いて見ちゃったりしてー。感想 ネタバレ無どっちかというとスプライトの方が面白かったかな。っていうか向こうが基点になっているような感じがした。オイレンは向こうに合わせて動いているような。といっても厚さが違うからしょうがないかな。おもしろさの密度が違うのは。あっちは小話も入っていたし。ここでついに二つの物語が多少入り混じるわけですが、入り混じって初めて分かったのだが、たくさん入り混じらせると内容がほとんど同じにならねえ!?って事で。そんな当たり前の事実に4巻まで気がつかなかった自分に愕然としつつオイレンの方を読んでいた。これから先、どちらを先に読むか、というのが最大の問題点になりそうである。多分、先に読んだ方を面白いと感じる、はずだ。5巻と6巻が出て完結だという。5巻はオイレンで6巻はスプライトから読もう、とかそういう適当な読み方でいこうかしらん。また、今までもちょくちょく触れてきたレベル3というものの謎が、やっぱりこれまたじょじょに明らかになっていくわけで。しかしレベル3っていうのはあれだな、もう通常のレベルを超えてスーパーサイヤ人とかそういうレベルの戦いになってきてるな。このままスーパーサイヤ人5ぐらいまでいったように、気合いと根性で「うぉぉぉぉレベル10だああ」「なにぃぃぃ、まさかレベル10を使いこなすやからがいたとはああ」どがーんばきーんとかそういう展開になったら凄い面白いのだけれども、絶対にそういう展開にはならないよね・・・。大体転送っていうシステムがあるし・・・。しかしなんでこいつらみんな髪に猫耳みたいなのつけてるんだ?い、いったいどういう意味があるんでせうか?あと表紙で陽炎が持っているライフルが、コンパスに見えて思わず笑ってしまった。ていうかなんかイラストが気に喰わない。自分にイラストが書けるのならば、技術論的に難癖つけられるのかもしれないが、まったくの無知であるからしてなんとなく気に喰わないとしか書けない。つまるところ、自分に出来ない事をやっている人間の作品をけなすな、というさも常識論ぶった反論は上のような理由から来ているのだろうか。知らない、出来ない以上、感情論的に気に喰わないというしかない、だから出来ない事を批判するのをむかつく、と考える人間がいるのだろうか。まぁそんなこといったら漫画が面白くないなんて言えなくなてしまって、それこそ何にも面白くなくなってしまう。やはり気の向くまま毒を吐く人間も必要なんじゃないだろうか。ってそんな事はどうでもよくて。やっぱりというかなんというかスプライトと対照的に、やはり地を這う部隊だけにどこまでも血なまぐさい話だ。どちらかというと個人にピントを合わせて書いている感じがする。陽炎とミハエル隊長の話しかり、夕霧と白露しかりどちらもスプライトの3人組みのリーダー以外の2人よりはしっかりを書かれている。じゃあスプライトは3人のチームという観点で書かれているのだろうか?問題としてはオイレンの方にはない微妙なチームの連帯感がある。それを考えるとチームという観点で考えられているといってもいいんじゃないだろうか。って同じ事を過去のエントリで書いたような気がする。学習しないやつだ。というか前に進めないやつだな。同じ事を何回も考えている。またレベル3の話がたくさん出てきた。それもまた興味深い。ネタバレ有こいつらのレベル3時のユニフォーム全員下乳が見えるんだけど何なの・・・?相手を誘惑でもしようとしてるの・・・?そんな描写あったっけ。ていうかやたらとエロいな・・・。悟空が本気だすと上半身裸になっちゃうのと一緒か・・?陽炎の武器がライフルからファンネルになっちゃうしちょっと悲しい・・・。夕霧がどこからどうやってワイヤーを射出しているのかうまく想像できなかった。しかしこいつら本当に血みどろになりながら戦っているな。陽炎は体中触られるは、涼月はどれだけ体吹っ飛ばされたかわからんし、夕霧なんか死ぬ一歩手前とか。確かスプライトの方の損害は最後まで全員元気だったのになんという差・・。基本的にいつもオイレン3人組みの方がひどい目にあっている。まぁ空を飛びながら戦うのと地面駆けずり回って戦うのとじゃ、また全然違うか。だから同時に読むとスプライトの方がぬるま湯につかっているように感じてしまう。ただ空を飛ぶ能力を得た代わりに味覚障害が起きているからそれを考えれば・・・どっこいどっこい?今回の事件でお互いの部下がお互いの隊長に好意を持たせるような描写が交換されたが、これはついに次の巻で完全に部下チェンジ的な展開になるとみていいのだろうか。夕霧だけどっちとも接触していないけどな。 「自分のふがいなさを他人のせいにするな。人生はこんなものだと決めつけるな。心に抱いたものを信じて前へ進み続けろ。どれほどの挫折の中でも──真っ直ぐ前へ。お前が誰よりも胸を張って自慢できる、その大人顔負けのガッツがあれば可能なことだ」今まで充分に猪突猛進で、前にしか進んでこなかったように見える涼月だが、この言葉でさらに前にしか進まなくなったのではないか。ていうかこれ以上猪突猛進にするよりも、もうちょっと横に動くとかいう動きを教えた方がいいんじゃないかと思うのだが・・・。どうみても香車です、ありがとうございました。羽生善治が、コンピュータが将棋でプロに勝つようになったら香車を横に動けるようにすればいい、と一言言っていたというが、うむ、横にも動けるといいね、という感じである。なんだか涼月が異常に精神的に強くなってしまいそうな予感がある。冬木?だっけ? にあなたの心は僕が守ります、なんていわれちゃって本当に異常に精神的に強くなってしまったんじゃないだろうか。特に、握れ──といいながら、レベル3になっても正気を失わずに自分の心を握り続けて戦うシーンは鳥肌物。鳳との対比としては、どう考えても涼月の方が強くなりすぎ、という感じがするのだがこの釣り合いはどうやって取るのだろうか。5巻が待ち望まれる。2008 7/11 読了
2008.07.13
コメント(0)
-
決断力/羽生善治
あらすじ決断力感想 ネタバレ有聖の青春を読んでいてもたってもいられなくなり、決断力を読んでみる。読んでいる最中は面白くて、久しぶりに集中して本を読んだ。といっても羽生程の集中力があるはずもなく、まわりの音が聞こえなくなるほど集中して本を読むことなど出来ないのだが。訓練すれば出来るようになるというものでもないのだろうか。だが擬似的にそういう状態に持っていくためによく、風呂に入り耳までお湯につけて本を読む。そうするとまわりの音が聞こえない状態になって集中出来る。そうでもしないと集中して本が読めない。やたら本の中で、加藤一二三を絶賛していたが、そんなに凄かったのか・・・いや、もちろん凄い事は知っていたのだがそれにしても奇行ばかり目についてその実力というかそういったものを知らなかったなぁ。相当面白かった。なんというか、本で読んだ事を書いているというか、人の話を流用しているという感じが全くしない。全部自分がその棋士としての人生の中で、「経験」としてたくわえてきた中から、感じ取ってきたことなのだろうと思う。なにしろ内容がなんというかあやふやで、自分でも説明出来ない事を必死に文章にしようとしている印象を受けた。ただの直感だが。だが羽生善治によると直感の7割は正しいらしいし、って同じ土俵で語っても仕方がないことだが。加藤一二三は直観の95は正しいといっていたが加藤一二三のいうことなので全く信用できない。面白かったので友人に「そういえば決断力って本を読んでさ」「あ、俺もそれ読んだ」「あれ最高に面白い!」「あれ最高につまらなかったな」「・・・・」「・・・・」確かに言っている事は当たり前というかなんというか、下手したらつまらないといわれてもしょうがない事なのかもしれないと冷静になって考えたみたがやっぱり面白いものは面白い。というか、羽生善治の事を神格視しすぎて本の内容を全肯定しかねない勢いなので、あくまで冷静な読み方をしたか、というと全く自信がないのだが。羽生善治は凄い人だ!→書く本が面白くないはずがない!→面白い!の単純な構造になっている可能性も否定できない。だがやっぱり面白いな。何が面白いって、将棋界最強と言われている人間が、いったいどういう決断のプロセスを持って将棋をさしているのかっていうのがまず面白いし、というか書く事一つ一つが格好いい。また、自分で考えて自分で出した結論というか、理論みたいなものを惜しげもなく書いてくれているのがいい。本で読んだ知識などではなく、自分自身で気づいたことというのが、その出来事を理解する時に一番の近道なのだという事がよく分かる。例えば本などで、成程確かにそう思う、というような真理や名言などを読んだとしても、それを自分で、自分の経験から導き出した人と、ただ読んだ人の間には多大な壁がある。羽生善治が、自分の経験から導き出した結論がたくさん入っている。よくよく内容を吟味してみると、もしくは吟味するまでもなく、当たり前の事を言っているだけなのだ。それをああ、当たり前の事を言っているな、といってスルーしてしまうと全く楽しめないと思う。何が楽しめるのかというと、その当たり前の結論に行きつくまでの「過程」だと思う。それがここにはある。棋士で驚くのは、若い頃から恐ろしいほどブレていない。早くから勝負の世界に入ることで、普通よりも早く大人になっているのだろうか。 将棋は自分との孤独な戦いである。追い込まれた状況からいかに抜け出すか。 追い込まれるということはどういうことか、でも、人間は本当に追い詰められた経験をしなければダメだということもわかった。逆にいうと、追い詰められた場所にこそ、大きな飛躍があるのだ。追い詰められた経験をしなければダメだということも「わかった」やはり全てを経験から導き出していると感じる。そうでなかったら、断定口調で追い詰められた経験をしなければダメだ。で終わるのではないか。いまだ自分はその意味はわからない。本当に追い詰められた事がないから。追い詰められるという事はどういうことなのだろうか。仕事がなくなったら?金がなくなったら?周りの人がみんないなくなってしまったら? ただ、将棋の世界なら単純にそれは追い詰められた状況というのは想像しやすいように思う。 現状に満足してしまうと、進歩はない。 物事を進めようとする時に、「まだその時期じゃない」「環境が整っていない」とリスクばかりを強調する人がいるが、環境が整っていない事は、逆説的にいえば非常にいい環境だといえる。リスクを強調すると、新しい事に挑戦することに尻込みをしてしまう。リスクの大きさはその価値を表しているのだと思えば、それだけやりがいが大きい。 積極的にリスクを負うことは未来のリスクを最小限にすると、いつも自分に言い聞かせている。現状に満足してしまうと、進歩はないというのは全くその通りで、自分の仕事に誇りを持つのはいいが、それで完璧だ、と思ってしまうのはほとんど死んだのと同じ事だ。物事は基本的に劣化していくのだから、それを維持するためには必然的に進歩し続けなければならない。 ただ環境が整っていない事は非常にいい環境だといえるというのには、全面的に同意は出来ない気がする。根が臆病者だからだろうか。そんなにリスクの高いものに挑戦する気がおきないのは。恐らく決断力という意味では自分はかなり低いだろうなとこれを読んでいて思った。リスクばかり気になって先に進むことができない。話はそれるが今の将棋は、本当に昔とは全く別物になってしまったな。そして古い世代の棋士が勝つためにも、今流のやり方を取り入れなければいけない。ってことは今も闘っている50代ぐらいの棋士は、みんな昔のやり方を捨てて今風にやり方に変えたのだろう。良く簡単に今までのやり方を捨てられたという感想。ただ良く考えたら、やり方を変えられた人間だけが残り、変えられなかった大多数の人間はやめていったのかもしれない。人数の把握なんてしているはずもないから、どれぐらいの人間がやめたのかはわからないが、それにしても今残っている人間は、みんな変えたのだ、というのは凄いことに感じる。 基本は、自分の力で一から考え、自分で結論を出す。それが必要不可欠であり、前に進力もそこからしか生まれないと、私は考えている。本ばっかり読んで他人の意見をさも自分が考えたかのように言っている自分には全く頭が痛い話だ。確かにいざというときに、というのもせっぱつまった時に出てくるのは本で語られている内容などではなく、本質的な自分の言葉だけだ。それは常日頃から考えていないと、出せない。
2008.07.12
コメント(0)
-
きみとぼくが壊した世界/西尾維新
ネタバレ無読めば分かると思うのだが、非常に特殊な小説である。タイトルを見てなるほどなぁーと思った。というか半分読んだ時点でそういう方向性で行くのだとほとんどの人は気づいたのではないか。こういうのもありだよねーっていう感じではあるが、それでもやっぱり長編を読んでいるというよりも短編集を読んでいるような気分になってしまった。いろいろな内容が終結して最後にはちゃんと終わってくれるから、長編が好きなのに・・・。もちろん短編も好きだが、読み方っていうもんがあるだろう、もしくは読む前の心構え?これからどちらを読もうとしているのか?そういうのを見事に裏切られたような気がするよね、まったく。それに最初の方は確かにえぇぇぇぇというふうにいい感じにびっくり出来たけれど乱用はいかがなものか、いや、なんだか文句ばっかり書いているような気がするが面白かったのだけれども。ただ雰囲気としては同じシリーズである、前二つとは雰囲気は完全に異なっていたなっていう。雰囲気は異なっていたがやっていることは一貫としている。それはつまりお約束の破壊、だろうか。タブーの破壊というか。ミステリーのお約束を次から次へと破って行く。そういう一貫した姿勢が感じ取れる。そういう一貫したところがあるから西尾維新作品が好きなのだが。作中作が昔は確かにはやったけれどもこういう使われ方は多分誰もしてないんじゃないかなぁ。知らないけれども。ていうか作中作って夢落ちと同レベルの話のような気がするのだが。まぁそんな事は置いておいて。非常に語るに難しい内容になってしまっている。むむむさてどこが面白かったというとそれはもうまるっきり話の核心にこれでもかというほど切り込んでいってしまうことになってしまうわけであって、ここでいったんCM入ります。ネタバレ有きみとぼくが壊した世界ってそういう意味だったのね。きみとぼくで小説の中にある世界を崩壊させたと、作中作の乱用によって。ただ、最終的にそれを書いていたのは笛吹さんだっていうことはきみとぼくじゃなくて笛吹さんだけが壊した世界って事になってしまうんじゃないか?っていうのがただひとつ心残りだったのだが、そういうわけでもないのかな。それにしても最初に作中作だということが明かされた時はびっくりしたなぁ。最初の章が語り手は病院坂だしトリックはポカーンとしてしまうようなものだしで、ひでえ出来だとおもっていたところだ。やっと本領発揮かとおもった第二章も微妙なトリックだと思ったら案の定それも作中作だし。それできみとぼくが壊した世界っていうタイトルなんだから絶対にこのあとも作中作が続くな、と誰だって気づくから驚きが減ってしまうのはしょうがないことなんだろうが。病院坂が死んだところも、全くはらはらどきどきという感じではないしな。それにしても結局事件は何も起こらなかった、っていうのはこれがなかなかミステリーのくせに平和的解決でいいね。それでいて作品の中じゃいくつも事件を解決しているのに、血なまぐさいところが全くない。どの推理も事件から逆算してこれしかありません!みたいなむちゃくちゃな推理ばっかりだったけれどな。
2008.07.09
コメント(0)
-
聖の青春/大崎善生
あらすじ29歳で夭折した、村山聖棋士の一生。感想 ネタバレ有滅茶苦茶面白いわ!しかしあれだけ鮮烈な印象を残した羽生善治に、こんなライバルがいた事を知っていた人間がどれだけいるだろうか。羽生の影響力は当時を思い出してみるに凄かったと記憶している。だれもが羽生の7冠をたたえて、それがどういう意味なのか、どのぐらい凄いことなのかを誰も理解せずに、なんとなく凄いことなのだろうという、ただ漠然とした思いだけでみんな騒いでいたのだろう。だがわからずとも騒がせるほどの凄さがそこにはあったということだ。その羽生に匹敵する人間がここにもいたのだ。棋士という職業の特殊性が、必然的に表れている。どう考えてもまっとうな職業ではない。幼い頃から将棋漬けの毎日を送って、時間との戦いでプロにあがってそれからも闘いの日々だ。そんな環境に居る人間が、一般の物差しで測れるものではない。そういう事を読んでいて強く思った。変わり者の多さという意味では、将棋界が一番ではないのか。芸術の方面も結構いい線までいきそうだが・・・・。加藤一二三とかを考えるに、全員がどこかしらおかしい、という話だとどっこいどっこいかもしれぬ。天才、などと言われているがその努力のあとを見たらその一言で片づけるのは軽いというものだろう。もちろん何度も書かれているように、天性の勘のような、勝負強さのようなものは当然持っていたのだろうがしかしあのレベルになるとそういった努力では到達できない高みというのが勝負を左右する分かれ目になってくるのではないか。だとしたら元々の才能がある事は必須条件であるともいえる。ただ、村山聖も髪を切らないわ爪は切らないわで変なやつだが、その師匠の森も相当変なやつだ。およそまともとはいいがたいがあるいは将棋界ではまともな方がおかしいのだろうか? この二人の関係には本当に泣かされた。月下の棋士に出てくる、村山聖をモデルにしたキャラクターの名前が村森聖は明らかに師匠の森さんから、名前をとっているのだろう。聖の青春を読めば森の存在がどれだけ聖に影響を与えたのかが痛いほどにわかる。しかし将棋というやつはこれがまたひとを魅了するのに十分すぎる魅力を持っているゲームで。決して死んでも自分でのめり込みたいとは思わないものの、のめり込んでいる人間を心底尊敬し、強い人間は本当に神のような存在であると思っている。格闘技やら何やらよりよほどすっぱりと決着がつく。将棋の何が、見ている人間を興奮させるかといったらやはりその、すっぱりと決着がつくというところだろう。またその過程が、恐ろしいほどの綿密な計算と感覚によって裏打ちされているというその事実がまた見ている人間を圧倒させる。強いやつは強いし、弱いやつは弱いという単純な論理がまかり通る世界だ。聖がつけていた日記というのが、小学生の頃の日記なのに相当しっかりとしている。自分自身小学生の頃につけていた日記を、読み返した事があるのだがひどいという他ない。あったことの羅列すら満足に出来ていないあの日記に比べれば、ちゃんと出来事をかけているだけで凄いという他ない。それにありがちな内容のぶれがない。一貫して日記というものを書こうとしないとこうは書けないだろうと思う。 小さいころから集中してやる、やることをやる、という根元みたいなのがしっかりしていたのではないか。小学生から将棋にのめり込む人というのは、いったいどういう人間なのだろうか。他にやる事がないから将棋にのめり込んだ、というものでもないだろう。現に村山聖だって、将棋だけしかなかったわけではない。数々の娯楽の中から何故将棋を選びとったのか。同時多発的に強い棋士が将棋の世界に入っていったのは何故なのか。ちょっとオカルト的な考えに行ってしまいそうな話である。この村山聖という存在の生き方は、ただ個人のためだけにあったわけではないと思う。挫折して、死と隣合わせに生きながら、這ってでも目標に向かっていき、さらにそれを諦めないで最後まで生きる事が出来た、というのはほかの人間にとって大いなる希望のはずなのだ。ひとりの人間にそれができたとすれば、たぶん他の人間にもできるだろう。人間にはそういったことが出来ると、村山聖は証明してみせた。村山聖という実例のおかげで、病気で苦しんでいる人間はあきらめない事を学ぶだろうし、他の理由で苦しんでいる人間も前に向かう事が出来るという実感を得るだろう。 「村山さんはいつも全力をつくして、いい将棋を指したと思います。言葉だけじゃなく、ほんとうに命がけで将棋を指しているといつも感じていました。」と羽生は言う。それにしてもやはり森と村山の関係がすごすぎる。森さんのエピソードで泣かないはずがねぇ・・・。いつか聖が年をとってランクを落としてきた時に、森がまだ踏ん張って二人で将棋を指す。あぁ、男の友情ってのはそういうものだったっけ。師弟愛か?まぁ何にせよこれは男にしかわからない感覚だよ。絶対に。ああ格好いい。2008 7/9 読了
2008.07.09
コメント(0)
-
手紙/東野圭吾
あらすじ犯罪者と、その親類がその後どのような扱いを受けるのか。感想 ネタバレ無東野圭吾は、白夜光とエッセイしか読んだ事はないが、印象が変わった。これは東野圭吾版デッドアイ・ディックだ。もしくは日本版というべきか。デッドアイ・ディックがアメリカ的な、人生だったのに対してあくまでも手紙は日本版だろう。デッドアイ・ディックが深刻な話をあくまでもエンターテイメントとして、笑いを取り入れていたのに対してこちらは暗い。暗すぎる。そして何よりも、伝えたい事ありきで書いたのか知らないが、イベントの配置が思わせぶりすぎるのではないか。こういう事もあるよ、こんな事もあるよ、とそれはわかるのだが、また登場人物にひどい状況を味あわせて、それを乗り越えさせるのが小説というものだというのも、わかる。だがあまりにもあからさますぎるというかなんというか。自然な流れというものを全く無視していると感じられた。ただ、作品の質を落とすようなものでは決してない。伝えたい事は痛いほどに伝わってきた。また解説が秀逸である。ジョン・レノンの例は思わず感心してしまった。タイトルにある通り、手紙が重要な要素となっている。思い返せば、手紙というのは感動させる要素の一つだよな。遺言がメールだったら締まらない。思えば手紙にはいつも泣かされてきた気がする。現実に手紙なんてめったに来る事なんて無いのだが・・・。手紙で泣かされた例といえばLAST KISSだろうか、あれもあまりにもテンプレートすぎる話だったが、それ故に泣いてしまった。あれを読んだ時に、人間を泣かせるってのは簡単なんだなと思ったのだ。つまり死んでしまった人が今までの感謝を手紙で伝える、とか、罪を告白する、みたいなのは泣くテンプレートみたいなものではないだろうか。死んでしまった人のパソコンを見ていたら感謝の文があったーなんていうパターンもあったが、パソコンよりも断然手紙の方が破壊力は上だった。何故だろうか。やはり手で書く、というのが大きいのかもしれないな。ラストシーンは良かった。思わず泣いてしまった。言っている事は全く本当にバカだなぁという内容なのに、シュチュエーション的にここは泣かないと嘘だろ!と頭の中で勝手に考えて泣いてしまった。あれは卑怯だな。泣かせるのは簡単だと何度も書いたが、どんな感情が一番湧かせづらいだろうか。怒り?悲しみ?喜び? 悲しみは結局泣く方と同じベクトルだろうか。微妙に違うような気もするが・・。喜びっていうのは、登場人物が何かを達成したりする時に普通に湧き上がってくるような気もする。そう考えると怒りが湧いてくる小説というのは、非常に少ないのではないか。嫌悪感を与えるようなキャラクターはそれだけよく練り込まれている、というような話があるが、怒りも似たようなものかな?怒りで変換しようとするとなぜか最初に碇になるので碇シンジについて考えてみよう。最初エヴァンゲリオンを見た時にあまりに碇シンジがへたれすぎて怒りが湧いて来た記憶がある。そう考えるとやはりエヴァンゲリオンは凄いというべきか。ただ改めてエヴァンゲリオンを見返してみた時に、あまりにも碇シンジの置かれた状況がひどすぎて同情的になってしまったのは少しショックだ。もう全く怒りなんて湧いてこない。ただのかわいそうな運のない少年だ。ネタバレ有手紙では決して、差別や偏見がいけないことという事を書いたわけではない。作者の意見を反映しているのはあからさまに社長だろう。というかある種どうとでもとれるセリフというべきか。差別や偏見があるのは当然だという前提の上で、ならばどう生きるのかというのがこの作品の一歩進んだところだ。それにしても、社長が言う絆の数、結局由美子の分しか増えてないんだけどこのあと増える予定、あるんですかね。正直いって主人公のとった道は、間違ってはいないが、正しくもない、という感想しか持てないのですが。まぁそれが社長のいっていたことなのだが。ならばどう生きるかに正解も間違いもない。だから正直にいえば、何もかも話してあけっぴろげに生きていくのもありだ。ただそれは、最終的にやっている事は剛志と同じだ。自分はこういう人間だ、本当に自分はだめなやつだ。本当にすまない。確かにそれを言えば、言った方はどれだけ満足か。だが言われた方はどうだろうか?そんな事言われたって、迷惑だと思うかもしれない。あるいは思わないかもしれないが、それによって何かが変わる事は確かだ。勝手に話して勝手に満足して、それで全部解決っていうわけには何事もいかないのだ。相手にそれを押し付ける行為だというのを理解しなくてはいけない。私の兄は強盗殺人をおかしました、と正々堂々と言って回るのもいいだろうがそれは上のような事を覚悟していかなきゃいけないのではないか。それによって避けられたり、ありとあらゆる事が起こるだろうがそれは全部受け入れていかなきゃいけない。できなかったら直貴がやったように逃げるしかない。 「差別や偏見のない世界。そんなものは想像の産物でしかない。人間というのは、そういうものとも付き合っていかなきゃならない生き物なんだ」上で書いた事だけれども、なんだかわざわざ直貴にバンドさせて挫折させたり、わざわざ頑固な親を持つ娘と交際させて破局させたり、あまりにもわざとらしすぎるイベントの配置が多少気に障った。もっと集中というか、違和感なくやってくれればよかったのだが。何故違和感を感じたのかはよくわからぬ。直貴の苦しみがよく伝わってくる凄い文章だったと思う。剛志は何も悪くないのだ、少なくとも直貴に対しては。直貴の学費を稼ぐために毎日身体を壊すまで働いて、働けなくなり、最終的に強盗に入り殺人を犯してしまう。直貴がそれに対して、どうこう言えるはずもない。手紙も直貴に対して優しい事ばかりが書かれている。愛に満ち溢れている。それに遠慮して、強く書く事ができなかったのは直貴の罪だろうか、自分たち家族を守るためと今まであったことを全部書き記して、相手に贖罪を迫るのはいったい正しいのか間違っているのか。いやもちろん正しくもないし、間違ってもいないのだろうが。ただそれってやってる事は剛志と同じじゃない?と読んでるときは思ったものだったが、読み終わるとそうもいえないっていうか優柔不断ですからぐだぐだしてしまうんですがね。 解説より ほとんどの人は自分は差別などとは無縁だと考えている。世の中に存在する差別に対して怒りを覚え、嫌悪を感じることはあっても、自分が差別する側に立つ事は断じてないと信じている。 この小説は、そんな我々に問いかける。 では、この鏡に映っているのは、いったい誰なのだ、と。知らず知らず差別しているのだ、と。そんな事言われなくてもわかっとるわぼけぇといいたいところだがそうも言えないな。ただ少なくとも、たとえ相手の家族が何をしていようが、それによって相手を差別したくはないと常に考えている。だが多分そうやって意識する事が、すでにその相手を差別している事と同じなのではないか。でもそんな事言いだしたら家族が犯罪をおかしたら、その親類は一生差別に悩まされるという事になる。否定したいが、ここで書かれているのはそのまま、そういうことなのだ。
2008.07.08
コメント(0)
-
流星ワゴン/重松清
初重松。のような気がしてたけどロストオデッセイで読んでいたのだった。あらすじ死にたいと思ったら突然おっさんとその息子のワゴンに乗せられて過去をめぐらされる。感想 ネタバレ無な、ないてしもうた。しかもなんて事ない、泣かせのテンプレートみたいな話なのに。いやでも泣かせる話は結構簡単だっていうしな。とはいうもののやっぱり面白いよ!ロストオデッセイの方の話と、この小説しか読んでないけれども、雰囲気が同じような気がする。似ているというわけではなくて、じんわりと染み入ってくるような文章が心地よい。本当に、展開で泣かされた部分もあるけれど、この単純な、純粋に思いを伝えてくるような一人称の文章にやられた。家族の話である。家族の話を読むといつも複雑な気持ちにさせられる。大抵その話の落ち着くところは、家族とは切っても切れないもので、どんなに喧嘩しても結局は繋がっているんだよ、というようなものだ。そんなわけないだろ、というような気持ちに、読み終わった時になる。家族だといっても、他人なのだ。遺伝子でいえば自分とは50パーセントしか自分と同じではない。人間として尊敬できない時だってあるし、家族だから無条件に何でも許される、愛され愛する事が出来るというのはおかしなことだ。だが、読んでいるときはそれでいいのだ、としか思っていない。そういった都合のいい事が出来る自分が好きだったりする。流星ワゴンはその典型のような話だ。家族っていうのはそういうものなんだよというような。それはきれいなものだし、だからこそ読んでいて面白いのだろうか。家族というのに血のつながり以外に重要なものがあるとすれば、それは一緒に居た時間の長さだろう。って何が書きたいのかわからなくなってしまった。何が言いたかったんだっけな・・。利己的な遺伝子を読んでから家族というものの持つ意味がわからなくなってしまった。家族という意味というか意義というかそんなものが。家族の話というのは、泣かせるのにはもってこいだなと思う。何故ならどんな題材よりも、読者にとって身近だから。家族がいない人はいないから。生まれた時から孤児だという人だって、この世のどこかには父親と母親がいたはずだ。どんな立場のどんな人間だって、家族ネタなら身近に感じられるはずだ。現実を受け入れて、今まで見過ごしてきた自分の間違いに気づいて。それを成長の糧にしていくという王道ともいえる話だ。だが重松清の、言い知れない文章も相まって特別なものになっている。恐らくどの作品を読んでも、さすが重松清といえるような出来になっているのではないか、とこの作品を読んでいて思った。こういうのを文章のプロといえるのだろうか。恐ろしくレベルの高い作品を平均的に出し続けることのできるもの、といったような感じで。きっとほかのどの作品を読んでも、がっかりすることはないように思える。最近の作品どころか過去の作品も全く知らないが。だからいうなればこれはただの妄想だ。ネタバレ有子育っていうのは何にも増して思い通りにいかないものだな、と思った。父親にもなっていない自分がこんな事を書くのはおかしいだろうか?こういった子供になってほしいと願えば、その通りになるというものでもない。才能を伸ばしてやりたいと思ったからといって、その通りにできるものでもない。じゃあ子供の自主性に任せようとして、何もかも子供の好きなようにやらせたからといってうまくいくものでもない。最低限自分で考えて、行動できるだけの常識をつけさせてやらねばならないのか。子どもとたくさん触れあって、たくさん遊んであげるのがいいのか。もし自分が親になったら、という仮定の元で考えるとこれほど難しい事もない。全部正しいような気もするし、全部間違っているような気もする。ただ幸せになってほしいとは思うだろう。それならば、それに従って行動するだけだ。すべては臨機応変に。 「いいこと教えてあげるよ、健太くんに。あのな、息子は親父を捨てていかなきゃいけないんだ。いつまでも親父さんにべたべたしてちゃだめなんだよ。嫌ってもいいし、憎んだってかまわない。親の世界から出ていかないと、子どもはどこにも行けなくなっちゃうんだから」神林長平のあの名言。子供は親に反乱した時に、初めて大人になるのだ。を彷彿させるこのセリフ。まだ実感として理解できないけれども、それでも大切な言葉だという事はわかる。捨てる=反乱ではないけれど、本質的な意味は同じだ。いつまでも親の世界にとらわれているだけではだめだという意味。それにしても、広樹の挙動だったり、主人公の葛藤だったりどれも身近なものばかりだ。自分が感じたものをそのまま文章にしたらこんな風になるだろうなというような。簡単そうに見えてかなり難しいのだが、それを実際にやっていて、それがさらにくどくなく非常にシンプルになっているところが凄い。広樹がペットボトルに嫌なやつの名前を書いてパチンコで撃ったり、親に相談できなかったり、主人公が日々の忙しさに追われて色々な事に気づくことができなかったり、そういった身近な事がいちいち丁寧だ。 「逃げてもいいんだよ。逃げられる場所のあるうちは、いくらでも逃げていいんだ」「負けてもいいんだ。ずうっと勝ちっぱなしの奴なんて、世界中どこにもいないんだから。みんな、勝ったり負けたりを繰り返してるんだ」全く同じセリフを西の魔女で聞いた時は、まったく同意できなかった。今回は、まったく同じ状況にもかかわらず同意出来る。二人とも、イジメから逃げる、というような共通の理由を持っているのに何故片方は同意出来て、片方は出来ないのか?わからんなぁ。西の魔女の方は、あまりにも、無条件に全肯定すぎたからだろうか。詳しい事情も知らずに、何も確かめずに、逃げていいのだ、とそれだけ伝えるのがはたして正しいのかどうかという事が気になったのかもしれない。いつまでも逃げ続ける事は出来ない、というような意見が自分の中にあるからかもしれない。あまり意識したことはないけれど。でもだったら何で、流星ワゴンの方は同意出来るのか。頑張ったからかもしれない。広樹は受験するために頑張ったし、その過程でいろいろまずいことがあってイジメられる事になってしまうけれども、それは頑張った事の結果なのだ。努力の結果だ。そういった人間は救われるべきではないのか。はじめの一歩のあの名言がよみがえる。 努力したものが必ず報われるとは限らないが 成功したものはみなすべからく努力している。ただ、努力した人には少しでも多く救われてほしいと思っている自分がいるから、広樹に同情的になったのだろうか。西の魔女が死んだの主人公は、自分から努力したとは思えない。どんな名言も、立場や視点の違いによって同意出来たりできなくなったりするといういい例だろうか。それにしても~だろうか、とかそういう推測的な言葉でしか書けなくて面白くない。自分の事なのに全くわからないとは。 学校に行けなくなってしまった一人息子と、家に帰らない夜もある妻。そして、職を失った父親。サイテーの現実が待っている我が家に、僕は戻る。胸を張れよ、と自分に命じた。まっすぐに歩け、と言い聞かせた。 もう魔法は解けてしまったのだ。あまりにも問題が山積みの、まさに最低の現実だ。この深刻な問題を一気に解決するのは、到底無理な話だろう。だったら受け入れるしかない。人間諦めが肝心というが、こういうときに適用されるべきであろう。いくつも解決しようとして結局何も解決しないよりも、いくつか諦めてしまって、他のものは受け入れるしかない。ってこんな事がいいたかったわけじゃないだろうな。いろんなつらいことが待っている現実でも、それが現実なのだと受け入れて生きていくのが人生というものだと綺麗に閉めたところで読了2008/7/6 読了
2008.07.06
コメント(0)
-
スプライトシュピーゲル4 テンペスト/冲方 丁
あらすじ七人の証人を守ろうとする話。感想 ネタバレ無相変わらず面白い。やたらとこういった政治的な話とか、国ごとの関係みたいな話について真に迫っているのは、子供の頃シンガポールやネパールで暮らした経験故だろうか。特に民族紛争の話など、ネパールで暮らしていたら意識することしかりだろう。そういえば昔マルドゥック・スクランブルをアニメ化するとかいっていてうれしく思ったな、という事を思い出して調べた見たら、アニメ化中止していた。こんなことあるんだな・・・。今までこの文体、ひょっとして作者が楽をしたいだけなんじゃ・・なんて邪推したりもしたが、4巻を読んでいてやっと、この文体の方がいいかもしれないと思うようになった。明確な理由はよくわからないけど。というか、この=とか/とかを使ったほとんど箇条書きみたいな書き方は、果たして普通に書くのと比べて楽なのか、それとも大変なのか、というのはよくわからんところだな。今回みたいに次から次へと状況が入り乱れる場合だとこの文体のありがたさがわかるな。というか、別にこの作品に限って言えば今回だけがこんな状況だったわけじゃないが。しかしマルドゥックからこの作品までずっとこの文体でやってきているわけだけど、この先普通に文章が書けるのかどうかっていうあれ。あとやっぱり関心させられてしまうのは、二作品がほぼ同じ内容量で、同じ満足度を提供し続けるところか。よくそんだけあわせられるものだな。これだけは今まで培ってきた経験というやつか。多才ぶりというか、色々こなすよなぁ。いっそのこともう小説家なんてやめて他の仕事やればいいのにと思うぐらい。いや、面白いから書いてほしいけど。この二作品を別々の出版社でやるっていうのも色々面倒くさい事が多そうだ。ページ数は極力同じにしなくちゃいけないし、片方だけたくさん宣伝するわけにもいかないわで。それをあえてやっているのだから、あとがきの最初の引用。「俺はいわば赤信号だ。めちゃくちゃやることで、人々にこれが限度だと警告する」 ──映画『フィッシャー・キング』が、まさに冲方 丁という感じなのだよな。ただやはり格好つけすぎかな、とも思うが。フロムディスタンスという冬真と鳳の話と、テンペスト七人の守る話でわかれているが、テンペストが濃すぎてフロムディスタンスがついていた意味をあまり感じないな。これから先、5巻6巻で終了とあるからおそらく次で何かでかい事件が起こって、二つの話が入り混じるようにして終わりに向かうのだろうから、冬真とのエピソードをはさめるのはこれが最後だったのかもしれぬ。テンペストはちょっと中だるみした感があるが、それでもやはり最後はきちっとしめてきて文句ない出来。まったく関係ないけど、マルドゥックのカジノを思い出させるようなところがあって面白かった。実際どこが似ているってことはないんだけど、勝手に似ていると思っただけである。特にラストの方は、やっと二作品が本格的にクロスしはじめたか、という気持ちがそのままワクワクに直結して大変面白かった。5巻にも期待がかかる。その前にオイレンの4を読まないとな。ネタバレ有フロム・ディスタンスの方じゃ、冬真と鳳の距離が一気に縮まったのはどうでもいいとして、雛と水無月はどうなるのいうのか。日向と乙も。ていうか日向そのままじゃ完全にロリコンのごとき人間になってしまうのではないでしょうか。ここでやっと両者がお互いをちゃんと認識して話し合うという一歩も二歩も進んだ展開になるのだが、戦力を考えてみた時にオイレン勢の方がよほど強そうに思える。絵のせいかとも思っていたがなんだか実際にもオイレン勢の方が強そうだ。まぁスプライト勢は単純な強さというよりも、「飛べる」というほうに価値があるのかもしれないが。スプライト勢とオイレン勢の単純な火力が比例していたら、空を飛べないオイレン勢は弱くなってしまうから当然のあれか?でも瞬間的な火力だったら明らかにスプライト勢の方が高いんだよな。爆弾ばらまいたり機関銃掃射したり出来るんだから。しかも理屈はよくわからんが転送を開封──とかいってりゃ弾も武器もどんどん転送されてくるんだから、冷静に考えたら圧倒的にスプライト勢の方が強くなると思うのだが、描写を見るにオイレン勢強いな。まぁどうでもいいのだけれども。マルドゥック・スクランブルのカジノのシーンを彷彿させたと書いたけれども、描写が似ているとか魅せ方が似ているとかいうよりも、そのどちらも違うのだけれどもわき起こる感情が似ている。何が起こるかわからないドキドキ、といってしまったら単純化しすぎだけれども、感覚としては似たようなものか。そのシーンというのも、世界統一ゲームを遊ぶシーンなのだが。ていうかこれ、目的が違うだけで完全にCivilizationだよな。細かい違いをあげればキリがないけれどほとんど同じだ。しかしここでのミッターマイヤーの存在感が強すぎて、のちにあっさりと、本当にあっさりと殺されてしまったから、思わず黒幕だと疑ってしまった。キャラが強すぎるというのも考え物だな。逆にほとんど目立たなかったおじさんが黒幕だったとわ・・・。 「旧ユーゴでの虐殺を止めるため安保理の決議なしで空爆が実行されたのさ。そして決議1244において、その行為ではなく''結果''が承認された。そしてコソボ独立委員会は、今なお政界の出ていない、ある結論を発表した。あの空爆は決して国際法上''合法ではなかった''──だがしかし''正当であった''と」ミッターマイヤーのセリフ。名前もあいまって格好よすぎる。同じシーンの中で、最終的に全世界が水不足に陥り、ただ一国だけ真水を作る技術を持っていた雛国が、全世界のために水を作る技術を売った時に、自国の利益を損なったとしてクーデターが起き、暗殺されてしまうというくだりがあったが、正しい事をやったとしても死ななくてはいけないという現実を見たような気がしてちょっと泣いた。それにしても、結局証人がほとんど死亡してしまうなんて、任務としては大大大失敗だなぁ。しかもその後が全く書かれていなくて、事件終了しただけだからこのあとの事を5巻でやるのかやらないのか・・・。読んでいてずっと思っていたのだが、この大量のルビをふるのはなかなか大変そうだなぁという事だ。まぁそんなのは当然のことなのだが。2008/7/5読了
2008.07.05
コメント(0)
-
異邦人/カミュ
あらすじきょう、ママンが死んだ。感想 ネタバレ無ラスト4ページは本当に鳥肌もの。主人公の狂気が乗り移ったような感覚で読み切った。読後感でいえばこれほどのものもそうあるまい。不条理小説だとか、実存主義だとか意味のわからない事が解説に書いてあったが、そんな事抜きにして楽しめる小説だ。むしろそんなわけのわからない理屈なしで読んだほうが余程楽しめるのではないか。単純に生きるという事は何なのかという問題に、正直に、嘘偽りなくこたえようとしたのがこの小説であったと考えている。現に、主人公であるムルソーは、いついかなる時も自分の気持ちに正直であった。普通、ボールが自分に向かって飛んできたら、速度や軌道を自分に当たるかどうか計算して、避けるかどうか決定する。だがそれは無意識的な物だ。頭の中で数式を展開して答えを出しているわけではない。それと同じように、みんな日常生活の中で、対人関係の中で似たような事をしている。無意識的に計算を行って、本心とは別の理由づけを作りだして、自分さえもだます。そういった事を全部排除して、感じたものを感じたまま、素直に表現したのがムルソーであると、考える。それは他の人間から見れば異端であり、ムルソーは異邦人であった。タイトルの意味は、そういう意味だとカミュ自身が書いている。こんな人間は現実にはいないからこそ心地よい。太宰治の斜陽にもこんな文があった。わたしが乱暴者を装えばみんなはわたしを乱暴者だといい、違う自分を演じればみんなは自分を違う自分だといい、本当の私など誰も見ていない。ようするに世の中というのはそういうものであるという話だ。また間違いなくラスト4ページは記憶に残る、物凄い質量を伴った結末であったと自信を持って言える。そしてこの死生観だ。この正直な男が死と向き合って何を考えるのか、というのは最大の関心事でありまた十分満足させられる内容であった。裁判制度について、死刑制度についてももう一度考え直すきっかけを与えてくれるだろう。ネタバレ有 きょう、ママンが死んだ。で始まるのは単純にインパクトの点で凄い。単純にきょう、ママが死んだ、じゃないところもおや?っと思わせるだろう。冒頭に衝撃的な文を持ってくるというのは、なんだか常識のようになってしまっているがこの微妙なアクセントのついた始まり方は訳者のおかげというかなんというか。しかし上の文章は膚の下の、きょう、サンクが死んだ、という文を思い出して非常に泣ける最初はいったいこれからどういう展開になるのか、まったく予想もできなかったがまさか裁判にかけられて、母親の葬式で泣かなかったという事を執拗に攻められ、なんでもない事件を死刑にまでもっていって死生観を問い、裁判制度を問い、世の中の人がいかに人の上辺だけしか見ていないか、声の大きな人間に惑わされるのか、というような事を問いかけるような内容になっていくとは予想だにしなかった。確かに不条理小説といえば不条理小説だが、不条理小説と一言で片づけるにはあまりに重い。単に一言で表せるのは便利だが、あまりに単純化しすぎると本質を失うのではないか。不条理というのはつまり、常識外という事だ。その常識外が、世間であって、ムルソーの状況を不条理だ不条理だと考えながら読む事は、世間を常識外だと糾弾しながら読むことではないのか。ただ、不条理だ不条理だと騒いで、社会が悪い世間が悪いと勝手に読んで、勝手に想像して、人類を告発したような気分になるようではダメじゃないかと思うのだ。何故なら現実に居る自分もその世間の一員になっている可能性があるのだから。単に不条理小説と割り切って読めないのはこういう無意味で複雑な思いがあるからだが、なんか格好いい事を書きたかっただけという説もある。何故、殺したかについて 「太陽のせい」と答えたというこの文は非常に有名だが、これもウソをつかないように、正確にその時の自分の気持ちを表現した結果だ。意外と人を殺すなんていう事にも、それぐらいの理由しかないのかもしれない。あるいは人を殺すのに本当は理由なんて必要ないのかも。聞かれたから、無理に答えただけで本当は理由なんて複雑に絡み合っていて、いろんな要素があって簡単に説明できるような、理解できるような事ではないのかもしれない。理由の目立つ犯罪ばかり、世間にはあらわれるけれどその影でこういった殺人も起きているのだろうか?しかしどう考えても死刑になるような罪じゃないと思ったんだが、よく考えたら日本の法律ベースで考えていたからなぁ。死刑とかいう単語が出てきたとき眼を疑った。死刑を受けるものにもチャンスが必要だと、作中で主人公が言っていたがその辺はどうなのかよく理解できない。10回に1回助かるような仕様にしたからといって、それに何か意味があるのだろうか。いや、もちろん当事者からしたら凄く意味のある事だろう。何しろ単純に死ぬだけじゃなくて、低すぎる確率だとしても希望が生まれるのだから。あるいはここで言っている事は、どんな時でも、チャンスは必要だ、ということなのだろうか。そんな事するぐらいなら最初っから死刑制度なんて廃止にしたほうがいいのだと思うが・・。人は誰だって平等にチャンスが巡ってくるわけじゃない、それなのに死刑囚にのみチャンスを認めるというのはおかしいんじゃ?ちなみに日本の死刑制度については反対でも賛成でもない、念のため。この世界の事はほとんど意味がないが、自分が楽しいと感じる事、うれしいと感じる事には意味があるという単純な理屈が世の中のほとんどの人には理解できないらしい。最後、ムルソーはしきりに神を信じろ、あなたのために祈ろう、と言ってくる神父に向かって猛烈に怒る。それがあまりにも・・・なんていうのかなぁ、真に迫りすぎているというか、激情がこっちにまで伝播してくるようなそんな演出?なんていうのかな、怒りが伝わってきた。これから死刑されようとしているのに、神の救いなんてものを持ってこられても迷惑なのだと今まさに、死とこんにちはしているのに今さら目にも見えない毒にも薬にもならない、実際の助けには何の役にも立たない神なんてものを持ってこられても何の意味もない、とムルソーが怒るのが心情的に近いから、より理解できるのだろう。あるいはこれは無宗教の日本人故か? 私はかつて正しかったし、今もなお正しい。いつも、私は正しいのだ。いつだって自分の感じるままに行動してきて、自分に出来る事をやってきたムルソーだからこそ言える言葉だろうか?たとえ行動が、ひどい結果を招いたとしてもそれを選んだその人の決断は、誰だって間違っていないと自分は思う。もし自分のとった行動によって、悪い方向に行ってしまったとしたら、その人は多分自分のとった行動が間違いだったと悔やむだろう。だけど、それはその時取り得る最善の行動だったはずで、だからこそその行動を選択したわけであって、間違いなどではあり得ないのではないか。この言葉はムルソーにだけ当てはまる言葉ではなく、全員に適用されるべし言葉だと思う。上でも書いたように、やはり世間というくくりでくくられる人々は声の大きな人に従い、人の上辺だけを見て人を判断し、異端を排除し、理解出来ないものを排除し、およそ真理、本質、そういったものを全く見ようとしないのだろうか。ここではそのテーマ性ゆえに強調されて書かれていただけで、実際はちゃんと理解してくれる、本質を見る事が出来る人もたくさん、いるんじゃないか。さっきこんな人間は現実にはいないと書いたが、実際には、ムルソーの一部を体現しているような人間はそこらじゅうに居る、というか、多かれ少なかれ人はムルソーに共感するのではないかと思う。同情とは違う。同情なら誰だってするだろう。そうするように書かれているのだから。2008/7/2 読了
2008.07.02
コメント(0)
-
ティファニーで朝食を/カポーティ
あらすじ中短編集感想 ネタバレ無んーちょっと合わなかったかな。単に相性の問題だと思うが。全体的に、だからなんなんだろう・・・と読み終わった時に疑問に思うような作品が多かったような・・。恋愛小説としてみれば、ティファニーで朝食を、はどうなんだろうかなあ。こんな終わり方も、もちろんありだけど。映画だともろハリウッド的な終わり方にされていると聞いて悲しくなった。ティファニーに出てくるヒロインなんて、まるっきり涼宮ハルヒと相違ないツンデレ具合だと思った。というか単純に自分に素直というか、わがままに生きているだけだ。それにしてもどうにも読みにくいと感じるのは何故だろうか。なんというか、突然始まって、人物紹介も何もないまま進むので、まったく意味がわからないまま何ページも読み進んだのが原因のような気がする。結局人物の相関図が頭にぼんやりと浮かぶようになったのは160ページある本編を半分読み終わった時だった。遅いっあるいは訳のせいかもしれない。あるいは読み方の問題かもしれない。あまりにも文章に遊びというか、無駄がなくて、ちょっとでも読み飛ばすと前後のつながりがわからなくなる。数学は、ちゃんと毎日勉強しないとわからなくなるけどそれと似たような感じで。ただ、アマゾンのレビューを見る限りでは、やはりこの龍口直太郎氏の訳が読みづらいといっている人間も、多くいるようだ。鈍感なので、文章が下手だなと思うよりも、なんとなく読みづらいな、と思うぐらいのことでしかないのだが、読みづらいのは確かだと思われる。あと無駄な訳注が多すぎるように感じた。そんなに訳注入れなくていいから・・・。自分で解釈させてくれよ・・・。1Pに3つも訳注があるってどういうことだよわが家は花ざかり田舎娘が田舎の男とくっつく話これこそ本当に意味がわからない。最初っから最後まで予定調和の中で仕組まれたお遊戯といったようなとにかく問題も何もない。ただ普通に日常が過ぎて行って、嫌な事があったりするけど結局くっつくっていうなんの変哲もない話だったとしか・・・。ティファニーのほうでもそうなのだが、冷静に考えてみると事件は起きている、それがあまりにも普通に書かれるので大したことのように感じない。結果的に特に何の展開もなくハッピーエンド、はいよかったね、という感じで終わってしまうのではないか。多分自分だけ。ダイヤのギターこれを読んで思ったのだが、ひょっとして自分は恋愛小説大嫌いなんじゃないかという事だ。何故ならこれは面白かった、そして恋愛小説ではない。今までほとんど意識していなかったが、恋愛小説というのをほとんど読んだ事がない。あまりにも無意識的に避けていたので、気づかなかった。そうだ、恋愛小説嫌いだったのか・・・。この本だって、自分から読み始めたわけではなく、読む必要が生じたから読み始めただけだ。そう考えるといかに恋愛小説に向いていないかわかる。恋空なんて読んだら死んでしまうのではないか?短い話だが、微妙にせつない気分にさせてくれた。クリスマスの思い出おばあちゃんと、孫の仲の良かった話これもそこそこ面白かった。ただ、おばあちゃんものとしてはあまりにも普通すぎる・・。安易な方法で人を感動させようとする意思を感じてしまうのはひねくれものだからか。なんというかあまりにもテンプレートすぎる。なんていうのも西の魔女が死んだを読んだせいかもしれないが。内容的にはほとんど大差ない(そんな事はない)ネタバレ有ティファニーで朝食を滅茶苦茶わがままな女だなぁ。ティファニーで朝食をって、ティファニーは宝石店であってカフェではない。念のため。ティファニーで朝食を食べるようになっても、自我だけは失いたくないといっているが、まったく意味がわからん・・・。なんで金持ちになっても、自我を失いたくないっていう話が、ティファニーで朝食を食べる話になってしまってるんだ?宝石屋ってのが、金持ちの象徴で朝食が気軽さの象徴だとしたら、金持ちになって朝食でも食べる気分でティファニーに向かうようになったとしても、自我だけは失いたくないということなのか?それともこれは難しく考えすぎだろうか。 もしあんたがあたしのところへやってきて、軍艦と結婚したい、といったら、あたしあんたを見直すわな、なんだこの女・・・やっぱり意味がわからん・・。というか涼宮ハルヒをもう少し現実的にしただけだ。時代の先取りという意味ではこれ以上ないほどだがそんな事いったら古典のほうがよっぽど凄いという事になるわな。結局読んでいたけど、一人称の小説家の名前を覚えられなかった。というか、出てきたかなぁ、本名。何回か出てきたような気もするんだが。そんでもって、やっぱり小説家はホリーに惚れてたのかな?そんな描写があったような気もなかったような気も・・ いや、確実に惚れてはいたんだろうが、それがどの程度かってのがよくわからんよなぁ。簡単にあきらめられるぐらいの惚れ方だったのか否か・・・。結局ホリーは警察から逃げてブラジルにいってアフリカに行くんだから、もうこれは全く意味がわからんよね。ただ、こんな終わり方も、楽しくていいよね。わが家は花ざかりいつもご都合主義にはなれているはずなんだが・・・。主人公がピンチの時に都合よく仲間が助けに来るとか。ただ、なんとなくこの作品の場合は許容できなかった。多分あくまでリアリティがあるように書かれていたからだろうか。ようするに漫画だったら明らかに漫画世界!って感じで何があってもあーはいはいっというようにスルー出来るのだが、文学みたいに現実感を追及したような作品だと、あまりにもご都合主義が際立ってそこだけ目立ってしまうように思う。何で、ちょうどよく縛られた日に限って、元同僚の二人が尋ねてくるのか、というのがその許容できない部分なのだが。もう出て行って何日も過ぎたのに、何故ちょうどよくその日に来るんだよ!と突っ込まざるを得ないわけで。ダイヤのギター最終的に、ギターで奏でる音が自由の天地に触れるのである、という一文で終わるのだが、どういう意味だろうか。音楽こそが自由の天地なのだ、というそんなありきたりな主張か?よくわからんな。それにしてもシェファーさん、逃げだしたのにおっかけたと勘違いされるなんて、やっぱり日頃の行いって大事だなというのがこの短編を読んで一番強く感じた事だ。また、刑務所の雰囲気というか、全体の雰囲気が非常によく伝わってくる短編だった。みんながシェファーさんを頼りにしているところとか、シェファーさんの人柄のよさとか、そういったものが少ない描写の中からたくさん伝わってくる。クリスマスの思い出おばあちゃんの人物描写 顔立ちもなかなか個性的で、風にさらされたり日焼けしたりして肉のそげたところなど、ちょっとリンカーンに似ていますが、それでいて、やはり女らしい、上品な顔をしています。っておかしーだろ!リンカーンに似ていたら女らしくねーと思うんだけど・・・?それとも世間一般の人からしたら、リンカーンは女らしい顔なのだろうか?こればっかりは誰かに教えてもらいたいものだ。この文を読んでから自分の中で完全におばあちゃんがネタキャラになってしもーた・・・。まぁそのあとは普通に、おばあちゃんと孫のほのぼのとした絆が描かれて、結局やっぱりそういうことなので、最後はおばあちゃんなんで死んでしまうん・・・?なのだがまぁなんというか悲しいわね。典型的すぎるけど。これでおしまい
2008.07.01
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 210
- (2025-11-20 22:08:18)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『おしかけ婚~エリート御曹司さま、…
- (2025-11-21 00:00:19)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-