全89件 (89件中 1-50件目)
-

愛想の良さ、もう信用しないことにした
はい、マモ〜です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「愛想の良さはアテにならない」というテーマで話していきます。完全に個人的な話になるんですけど、今年カフェ会とか読書会とか、初めての人と会って話す系の会に5回ほど参加しました。目的は最初、コーチングの顧客になり得る人を探すためだったんですが、「目的を隠して人に会うのは違うよな」と思い直して、2回目以降は「友達ができたらいいな」という気持ちで参加していました。気軽にご飯や飲みに行ける友達が欲しくて。そのカフェ会/読書会で、その後個別に会った人は4人。そのうち2人が思いっきりネットワークビジネスの勧誘で(笑)。残りの2人のうち1人は読書会で出会って、今では飲み友達。いい人です。ただ、残るもう1人は直接勧誘はなかったけど「匂う」感じはありました。つまり、実質4人中3人はネットワークビジネス系だった、というオチ。で、この「2人+その背後にいた師匠筋の人」みんなに共通していたのが愛想の良さなんですよね。笑顔が素敵で、話しやすくて、親しみやすい。しかも聞き上手で、こちらの話をどんどん引き出してくれる。その場ではこっちも気分がよくなる。今思えば典型的な勧誘手法なのかもしれませんが、第一印象は全員よかった。でも、ふたを開ければ勧誘。そこで「第一印象としての愛想の良さって、当てにならないんだな」と感じたんです。この実感を後押しするようなデータがあって。組織心理学者アダム・グラントさんの著書である『GIVE & TAKE』にこういう話がありました。GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代 [ アダム・グラント ]・愛想の良さの少なくとも1/3、ひょっとすると半分以上は遺伝による・テイカー(与えるふりをして最終的には受け取る側)の特徴に、第一印象が良く親しみやすいという傾向があるつまり「愛想の良さ=その人の誠実さ」ではまったくないし、むしろテイカーが最初に好印象を取りに来るのは合理的とも言える。これを踏まえると、人付き合いを考えるときに「愛想の良さ」を判断材料に入れすぎるのは危険だな、と。むしろ外した方がいい要素かもしれません。で、これ自分にはちょっと救いでもあって。私、愛想が良くないんですよね(笑)。言われるし、自覚もあります。第一印象はそんなに褒められないけど、ある程度付き合ってから評価されるタイプというか。だと思っている・・・だから、「第一印象に頼らない」「一定期間・一定回数付き合ってから判断する」という姿勢は、自分の救いにもなるし、実体験と研究結果の両方からも合理的だなと感じています。ということで、今後は初対面の印象は一回疑う。いい印象でも「本当にそうか?」、悪い印象でも「本当にそうか?」と。短期では判断しない。それでいこうと思っています。最後までお読みいただきありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください。
2025.10.30
コメント(0)
-
受験で成果を出した学生講師にインタビューして感じたこと
マモ〜です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「学生講師にインタビューをしてみた」というテーマで話をしていきます。私は今、学習塾に勤めておりまして、科目を指導する先生は基本、学生の先生になります。採用基準がかなり厳しいので、本当に人柄も良くて、かつ受験で高い偏差値の大学に行った先生しかほとんど雇っておりません。お願いすらしていません。今回インタビューをしようと思ったのは、受験で成果を上げるかどうかは「学習のスタンス」によるところが本当に大きいと思っていて、実際に成果を上げた人に話を聞けば、共通項が見えるんじゃないかと考えたからです。具体的には、小中高でどう勉強と向き合ってきたのか。どういう日々を過ごしてきたのか。そこを聞くことで、成果が出る人の共通項を見出せるのでは、と思い今回始めました。今後、最低でもあと5人ぐらいは続けていくつもりです。前置きが長くなりましたが、早速、1人目の先生と1時間ほど話をすることができたので、その内容をざっと話していきます。この方はもちろん大学受験で秀でた成果を出された方です。小中は公立、中高は県内トップレベルの公立高校。その後は本当にレベルの高い大学に進学されています。驚くことに、この方は一度も塾に行っていません。どうしていたかというと、わからない問題が出たら学校の先生を捕まえて聞きに行く。あるいは、その科目ができる友達に聞いていたそうです。特に、何人かの先生をすごく慕っていて、「この先生は本当にわかりやすい」と思える存在がいた。だからその先生方に積極的に聞きに行っていたと。勉強において「聞く」時のこの方のポイントとしては 、「ロジックがないと絶対にダメ」と言っていました。なぜその解き方なのか。根拠がないと理解も納得もできない。徹底的に、なぜこうなるのかを考えながら教材と向き合っていたそうです。そして、パズルのように点と点がつながる感覚がすごく面白い、と。これ、よく聞きますよね。数学でも英語でも、「だからこうなるのか」と、過去に学んだ知識と今の学びがつながる感覚。それが快感だとおっしゃっていました。さらに「面白い」。これが一番大きいと思います。なんだかんだ、勉強をしていて「面白い・楽しい」と思える人じゃないと、ぶっちゃけ成果は出ない。ここが一番難しいんですけどね。特に歴史は面白かったし、高校に入ってから数学も面白くなってきた。英語も同じ。ただ国語は最後まで面白くなかったと(笑)。成果を出す人でも全科目が面白いわけではない。でも「特定の科目が面白い・好き」はだいたいある。全部を好きになる必要はなくて、一つ二つ好きでいられる科目を作るのは大事だなと聞いていて思いました。ここまでが「その方の勉強観」。ここからは「どういう生活・背景があったか」です。特徴的なのは幼い頃から読書習慣があったこと。これ、元も子もないですが、やっぱり好奇心旺盛だったようで、いろんなことを知りたい欲求が強かった。お母さんが読書好きで、その影響もあり、幼稚園時代から公共図書館でいろんなジャンルの本を読む習慣がついていたそうです。昔から「文字に触れている」か「図鑑などのビジュアルに触れている」かは大きい。背景には「身近な大人が本を読んでいた」という環境がある。これはやはり大きい。さらに、本人の好奇心を否定せずフォローした親御さんのスタンス。興味関心をそのまま突き詰めさせることを許容していた。ここも大きい。続いて家庭内の会話。量が多いかはわからないが、何より大事なのは “役割” が逆転してないこと。つまり「本人が話し手・親が聞き手」。これが逆だとよくない。学校であったことを気軽に話せる環境があり、親御さんは否定せず尊重して聞いてくれていた。このスタンスができていないと、その状態にはならないので、やはりここも親御さんの姿勢が大きい。生活の面で「勉強の成果につながっているな」と思えるのは、この2つ ① 読書習慣 ② 家庭内会話(本人が話し手・親が聞き手)これはかなり大きいと感じました。勉強そのものについては、昔からできていたようです。小学校の頃はだいたい 90〜100 点。ただその時点では「自分が勉強できる」とは思っていなかった。中学に入って定期テストで順位が出るようになって、「もしかして、自分は周りよりできるのかも」くらいに思い始めたとのこと。その頃から親御さんに「〇〇高校がいいよ」「〇〇大学がいいよ」と言われるようになり、「あ、そうなのか」と自然とそこを目指すようになった。大きな反抗期も特になく、すくすく育ったそうです。これ、親御さんがあれだけ寛大で「聞き手」をしてくれたら、反抗しようがないよなとも思いますが…本当に素晴らしい。勉強はどうしていたか。親御さんと会話をしながら、ちょくちょくやっていた。親御さんが一方的に教え込むのではなく、理解を促すような問いかけやサポートをしていた。本人の興味・好奇心が高まる接し方だった。だから本人は「面白い」と思えるものを徹底的に突き詰められるし、そうでなくても親のサポートがあって理解につながる。ぶっちゃけここが大事で、塾だけに行っても、この土台がないと成果は上がりにくい。これは本当にそう。他の成果を出している人の話を聞いても「読書習慣」「家庭内の対話(親が聞き手)」はやっぱり共通している。ここは改めて強く感じました。さらに勉強法の話。ただ暗記するのはナンセンス。ロジック(理屈)がないと前に進めない。そして「これまで学んだこと」と「今の学び」がつながる感覚を面白いと思えるか。ここが成果を左右する大事な要素。また、全科目を好きになる必要はなくて、特定の科目がめちゃ好き・得意という「武器」を作るのが大事。この方の場合は数学・英語・歴史を高3になる前にほぼ仕上げてしまった。そうすると高3では残りの科目に集中できる。つまり「先に仕上げておく」という戦略。実際、高2の春はほぼ数学しかしていなかったと言っていました。これは私自身も勉強になりました。最後に「授業」の意味についても聞きました。「授業って意味ありますか?」と率直に聞いたところ、「意味がないことはないけれど、問題の解説よりもいかにモチベーションを上げるかの方がはるかに大事」と。これは本当にその通りで、やる気のない生徒に解説だけしても意味がない。むしろ授業内容をすっ飛ばしてでもどう“その気”にさせるか、対話するか、にフォーカスした方が成果は出やすい。結局、本人が「やろう」と思えるかどうかで決まる。覚悟とモチベーションがあれば、自学で進められる。つまり授業の役割とは何か、改めて考えさせられたし、成果を出した人はやはり生活環境・スタンスに共通項がある。そう再認識させられたインタビューでした。今後も別の先生にもインタビューをして、同じようにアウトプットしていきたいと思います。共通項が見えてきたら、それを今の生徒にどう反映するかまで考えたい。そんな話でした。最後にお知らせです。受験で成果を出した人の背景を聞けば聞くほど、「家でこれをゼロからやるのは正直めちゃくちゃ難しい」とも思います。忙しいし、時間ないし、感情もぶつかるし、家庭で土台を整えるのは言うほど簡単じゃない。そこで私は、勉強に向かうための“土台づくり”だけに特化した伴走サービスをココナラでやっています。ボトルネックの特定から、改善の具体策、定着まで一緒に伴走するサービスです。興味ある方はここからどうぞ最後までお読みいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。
2025.10.27
コメント(0)
-

満たされない時代に、「足るを知る」を考えてみた
マモ〜です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「足るを知るには」というテーマで話していきます。これまで私自身も、「足るを知る」ということをかなり意識して生きてきました。……といっても、実際に意識しはじめたのは最近かもしれません。きっかけは『サイコロジー・オブ・マネー』という、お金と心理学をテーマにした本でした。サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセット [ モーガン・ハウセル ]この本では、「最終的にお金に恵まれる人はどんな人か」ということを、いろんなエビデンスや事例をもとに論じています。その中で出てくるのが、結局、「足るを知る」という話なんですよね。人間の欲望ってキリがない。足るを知らないと、いつまでたってもお金は貯まらないし、投資もできない。どれだけ高収入でも、それ以上に欲望にまみれて出費してしまえば、結局は破産してしまう。そんな内容でした。本の中に「収入 − エゴ = 貯金(資産)」という式が出てくるんですが、これが本当に腑に落ちたんです。それ以来、日々の生活の中でもよく思い出しています。とはいえ、「足るを知る」って、具体的にどうすればいいんだろう?そうも思っていました。結局、一度は自分の“欲望のコップ”を満たしてみないと、どのあたりで「足りる」と感じるかが分からない。でも、それをやりすぎると破産しかねない。そんなジレンマもありますよね。そこで最近読んだ本が、楠木建さん(経営思想家・経営学者)の『楠木建の頭の中 仕事と生活についての雑記 [ 楠木 建 ]』。この本の冒頭にも「足るを知る」関連のテーマが出てきます。楠木さんも同じように、「足るを知ることは大事。でも、どうすればそれを実感できるのか?」という問いを立てています。そして、ひとつの答えとして挙げていたのが、「羨ましいものを見たときに、“そんなにいいか?”と自分に問う」という考え方。例えば、道を走るフェラーリやランボルギーニを見て「いいなぁ」と思ったとき。その直後に、「でもそんなにいいか?」と自分に聞いてみる。そして「いや、別にそうでもないな」と思えたら、それは自分にとって“足りている領域”なんですよね。逆に「やっぱりいいよな」と思うなら、それは自分にとって必要なもの。この発想、実は自分も無意識にやっていたなと思います。たとえば、妹夫婦の結婚式のとき。自分の両親と妹夫婦でディズニーのオフィシャルホテルのスイートルームに泊まっていたんです。確か・・一泊十数万円、ベッドが4つもあって広い部屋。でもそのとき、不思議と羨ましさが全くなくて。むしろ「このスペースもったいないな」とか、「お金の使い道、他にあるよな」と思ってしまったんです。だから自分は旅行でもホテルの広さとかラグジュアリーさにはこだわらない。正直、「風呂入って寝られればいいよね」くらいの感覚です。車も同じ。もともと運転が好きじゃないし、できれば一生運転せずに済ませたい。乗るなら軽自動車で十分。高級車には1ミリも興味がありません。不動産もそう。所有するってかっこいいけど、失う恐怖や管理の手間を考えると、まったく憧れがない。「羨ましい」と思ったことがないんですよね。家も同様です。テレビで「広い家に住んでます!」っていう特集を見ても、全然羨ましくない。広いスペースって、結局“余計なもの”で埋まっていくんですよ。掃除も管理も大変だし。だから「2LDKくらいで十分」と本気で思っています。アクセサリーや時計、ブランドバッグにも興味なし。一時期腕時計をつけてみたけど、最終的に「邪魔」でやめました。今は結婚指輪すらつけていません。シンプルが一番。ユニクロ最高。GUも最高。ただ、「いいよね」と思うものがまったくないわけじゃない。たまに心から惹かれるものもあります。そういうものにだけお金を使えばいいと思っています。唯一といっていいほど、自分が「いいな」と思うのは本です。本に囲まれて暮らす人を見ると、ちょっと憧れます。快適な椅子に座って、1日中読書できる時間。それは本当に欲しい。食も似ています。高級料理を一人で食べたいとは思わない。高級寿司に行くなら妻や娘と一緒に行きたい。一人ならカレーとかラーメンとか、千円くらいの定食で十分です。以前、一人でちょっと高めの海鮮丼を食べに行ったことがあって。美味しかったけど、なんだか“もて余した感じ”があったんですよね。「美味しいものって、誰かと分かち合ってこそだな」と思いました。そんなふうに、「足るを知る」って結局、「自分にとって本当にいいのか?」「自分の価値観に合っているのか?」。そうやって一度立ち止まって考えることなのかなと思います。それがわかれば、「足りているもの」と「そうでないもの」が自然と見えてくる。そんな気がしています。まとまりのない話でしたが、何かの参考になれば嬉しいです。最後まで読んでくださって、ありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください。
2025.10.16
コメント(0)
-
AI時代にこそ必要なのは“言語化力”というスキル
こんにちは、マモ~です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「言語化能力を鍛えておこう」というテーマでお話しします。言語化の大切さを感じる現場から私は学習塾に勤めており、これまで200組以上のご家庭・生徒さんの受験サポートをしてきました。それに加えて、最近は「ココナラ」というサービスで、推薦入試のフォローサポートも行っています。具体的には、・面接対策(壁打ち)・志望理由書の添削・一緒に内容を考えるセッションなどをしています。ココナラ以外でも、個人的にサポートしている方もいらっしゃいます。もちろん、塾の方でも担任として、推薦入試を受ける生徒の面接練習や志望理由書の添削をしています。そうして多くの生徒と関わる中で感じるのは、「自分の考えや感情を言葉にすることに慣れていない人が多い」ということです。なぜ言葉にするのが難しいのかこれは当たり前のことでもあります。学校の授業って、基本的に先生が話して、生徒はノートを取るスタイルですよね。生徒同士の会話でも、自分のことを深く話す機会って意外と少ない。最近見た映画やアニメの話、誰かの噂話はしても、「あなたはどう感じた?」「なぜそう思ったの?」という問いに答える機会はほとんどないと思います。だから、「なんでこの大学を志望したの?」「どう思ったの?」と聞かれても、言葉が出てこないんですよね。しかも「なぜそう思ったのか」と問われると、ますます難しい。日頃から“なぜ”を考えて自分を振り返る習慣がないからです。学力が高い生徒でも、最初はうまく言葉にできません。でも、練習を重ねるうちに、少しずつ形になっていきます。最初はみんなつまずくものなんです。言語化が得意な人の共通点一部の例外的に上手な子たちは、日頃から“振り返り”をしています。たとえばスポーツ系の部活をしていて、自分の反省を言葉にしている子。そういう生徒は最初からスムーズに言語化できている印象があります。でも、そうでない人が大多数。だからこそ、これからの時代を考えると、「言語化能力」は意識的に鍛えておいたほうがいいと強く思います。推薦入試でも求められる力理由の一つは、推薦入試の割合が高まっていることです。大学によっては、総合型選抜や指定校推薦で半分以上の生徒を取るところもあります。つまり、ペーパーテストだけでは測れない「意欲」や「考え方」がより重視されているということ。その中で必要になるのが、志望理由書や面接。どちらも“言葉で伝える力”が問われます。3ヶ月で面接対策を詰め込むのと、3年間かけて自分の考えを言葉にしてきた人、どちらが有利かは明らかですよね。だからこそ、今のうちから訓練しておくのが大事なんです。言語化とEQ(感情の知能指数)言語化能力は、EQ(心の知能指数)とも深く関係しています。EQが高い人ほど、キャリア・人間関係・幸福度が高いことが分かっています。そしてEQを高めるには、「自分と向き合うこと」が不可欠です。たとえばジャーナリングや内省、内観日記など。どれも「自分の感情や思考を言葉にする」行為なんですよね。つまり、言語化能力という土台がないと、EQも鍛えられません。AI時代こそ、言語化能力が武器になる最近よく言われるのが、「AIが進化しても残るのはコミュニケーションの力」だということ。AIがスキルを代替しても、人と人との関係はなくなりません。その根底にあるのが、やはり「言葉」です。もちろん、非言語の要素(表情や雰囲気など)も大切です。でも、最終的に人とAI、自分とAIが対話する時代になってきた今、自然言語で正確に指示を出す=言語化能力が必須になっています。私自身も言語化が苦手だったこんな偉そうに話していますが、私も昔は全然できませんでした。社会人になってもプレゼンの練習で言葉が出てこず、先輩に笑われたこともあります。だからこそ、今の生徒たちには「早めに言語化を鍛えておこう」と伝えたいんです。最後に:学びを深めたい方へ「言語化能力をどう鍛えればいいのか?」「EQを高めるには何をしたらいいのか?」そんな方に向けて、noteで有料記事を書きました。この記事を読めば、・EQを高める具体的な方法・言語化能力を伸ばすステップ・推薦入試に向けた準備の考え方が分かる内容になっています。ぜひチェックしてみてください。言語化力を鍛えるための具体的ステップ(note)また、ココナラでも「推薦入試」や「言語化トレーニング」のオンラインサポートをしています。興味があれば、こちらもご覧ください。推薦入試・言語化トレーニングサポート(ココナラ)最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください。
2025.10.08
コメント(0)
-
頑固とこだわりは紙一重!成績が伸びる子、伸びない子の違い
マモ〜です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「頑固とこだわりは紙一重」というテーマで話していきます。学習塾で見てきた「頑固な子」私は学習塾に勤めていて、これまで200組以上のご家庭・生徒と接してきました。受験マネージャー、担任としての経験から言えるのは、すごく頑張っているのに成績が伸びきらない子が一定数いるということです。そういう子の特徴として、「頑固さ」があると思っています。頑固とは、自分の価値観や考え方、やり方を貫き通すこと。良い面もありますが、受験においてはそれが命取りになることも多いんです。頑固さが邪魔をして柔軟になれず、結果として成績が伸びない。そんなケースをたくさん見てきました。「こだわり」との違い似た言葉に「こだわり」がありますよね。こだわりと聞くと、なんだかポジティブなイメージがあります。例えばコーヒー屋さんを思い浮かべてください。店主が「こだわりの自家焙煎コーヒー」を出していたら、ちょっと美味しそうだな、飲んでみたいなと思いますよね。このこだわりと頑固の違いは、望む結果を生んでいるかどうかだと私は考えています。こだわり:本人も周囲も納得している、喜んでいる頑固:本人は満足しているが、周囲からは評価されず調和できていない要は、周囲との関係や結果の出方で呼び方が変わる、ということです。受験では「素直さ」が武器になる受験の世界はある意味、正解がある程度決まっている世界なんですね。長年携わっている先生や先輩のアドバイスに素直に従った方が、たいていうまくいきます。ビジネスなら、やり方が数年後には古くなることもありますし、AIのように常識が短期間でひっくり返る世界です。でも勉強においては、やり方や根本はほとんど変わりません。それでも「自分のやり方」に固執してしまう子はいます。結果、成績が伸びず志望校に落ちてしまう。そういう例を何度も見てきました。だからこそ、受験においては頑固さや不要なこだわりは手放し、素直に先生の言うことを聞くのが一番の近道だと思います。マインドセットが未来を変える頑固さは、ある意味マインドセットの一種です。その反対にあるのが「素直さ」。どんなマインドセットを持つかで、成績向上も志望校合格も本当に変わります。実際、私はマインドセット次第で結果が激変する瞬間を何度も見てきました。このテーマについて、さらに深掘りした記事をnoteに書きました。具体的な生徒の事例や、望ましいマインドセットを手に入れる方法も解説しています。良かったらチェックしてみてくださいませ。マインドセットの記事はこちら具体例や望ましい考え方の身につけ方を詳しく解説しています。最後までお読みいただきありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください!
2025.09.29
コメント(0)
-
ペーパーテストより大事な力─AI時代に必須のスキルとは?
マモ〜です。今回は「AI時代も言語化能力は必要だよね」という話をしていきます。ペーパーテストの価値は下がっている?AIが台頭してきて、これまでの当たり前がどんどん覆ってきています。私は学習塾で働いているので、教育という観点からこの変化をよく考えます。その結果として一つ言えるのは、いまのペーパーテストみたいに「与えられた問題をいち早く正確に解く能力」は、あまり必要とされなくなるんじゃないか、ということ。むしろAIの方がその能力は圧倒的に強いですよね。実際、アメリカではAIが医師国家試験に合格するレベルに達している。しかもこれは少し前のニュースなので、今はもうそれ以上の知能を持っているはずです。医師国家試験を受けるのは、その国でもトップレベルの知能を持つ人たち。日本で言えば、医学部に合格するような“本当に勉強ができる子”たちです。そのレベルにもAIが到達していると考えると、「ペーパーテストの点を取る力」をいくら鍛えてもAIにはかなわない。でも、実際の教育現場では何が起きているかというと、さらに詰め込み教育が進んでいます。私の勤めている塾は富裕層向けで、生徒の多くは私立の中高一貫校に通っていますが、話を聞くと「ひたすら先取り学習」「とにかく問題を解かせる」スタイル。従来と何も変わっていないんですよね。それでも「言語化能力」は重要とはいえ、ペーパーテストの能力そのものが完全に不要になるわけではありません。ただ、それ以上に大事になってくる力があります。それが「言語化能力」です。つまり、自分の思考や感情を言葉にして、相手に伝える力。意外と、ペーパーテストができる子でも、これが苦手な子は多い。勉強はできるけれど、自分の考えを人に分かるように伝えるのが苦手。これは結構危ういなと感じます。言語化能力の先にあるのがコミュニケーション能力。これは時代が変わっても絶対に必要です。コミュニケーションは「自分」「他者」「AI」との対話まずは自分とのコミュニケーション。人は意識していないだけで、1分間に300〜1,000語くらい、自分に語りかけていると言われています。例えば、道端で綺麗な人を見かけたら、頭の中で「あの人、綺麗だな」とつぶやく。(……例えが微妙かもしれませんが、イメージは伝わりますよね笑)これも立派な「自分との会話」です。次に他者とのコミュニケーション。自分の考えを相手にわかるように伝える。ここでも言語化能力が試されます。そして、今の時代は「AIとの対話」も重要になっています。AIにタスクをしてもらうには、言葉で正確に指示を出さなければなりません。伝え方が悪いと、ちょっとズレたアウトプットになってしまう。これからはAIを活用する前提で生きていくことになるので、「AIに正しく伝える力=言語化能力」はますます重要になっていきます。まとめペーパーテストで測れる力の価値は下がってきています。一方で、言語化能力の価値はますます高まっている。そんなことを感じたので、今回はこのテーマでお話しました。お知らせ私自身、言語化能力をどう高めるかを常に考えていて、実際の現場でもいろいろ試しています。それをココナラでも展開しているので、興味があれば見てもらえると嬉しいです。言語化能力の向上サポート依頼はこちら最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください!
2025.09.26
コメント(0)
-
塾の担任なのに娘は塾に行かせない理由
マモ~です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「塾の担任が自分の娘には絶対にしないこと」というテーマでお話しします。自分の立場と娘への思い私は学習塾に勤めていて、担任、あるいは受験マネージャーとして働いています。プライベートでは、6歳・年長の娘の父親。日々、家族と一緒に過ごしています。そんな私が「娘には絶対にしない」と思っていること。それは、学習塾に行かせることです。もちろん、娘に何かを無理やりさせる発想は、極力持たないようにしています。スポーツはやってほしいな、と思ったりはするので、もしかしたらそっちに誘導する可能性はあります。でも「塾に通わせる」は、絶対にしないかなと思っています。教育への違和感塾に勤めて、いろんな家庭や生徒と接している一方で、自分の娘には塾に行かせたくない。この矛盾や葛藤はずっと抱えています。理由の一つは、「今の教育、大丈夫かな?」という感覚です。特にわかりやすいのが中学受験。中学受験って、公立小学校の学習内容を理解している前提で、さらに多くのことを勉強させますよね。そして試験に出して、点数で合否を決める。ここにまず違和感を覚えます。受験生の日常と負担中学受験生の日々を見ていると、・朝から夕方前まで学校・休憩して、または休憩もせず塾や家で勉強・夜は21時半〜22時まで勉強ほとんど休みがない。学校から直行で塾、授業を受け、自習して帰る。さらに個別指導塾にも通う子もいて、本当にいつ休んでいるのか……と心配になります。そして受験が終わっても、私立の中高一貫校は授業進度が速い。トップ層はついていけても、他の子はついていけず、結局また塾通いが続く。部活をやりながら、学校の勉強・受験勉強を続ける。そんな生活がずっと続くわけです。逆に勉強をやめて遊びに走る子は、学力が下位になり、受験時に苦労する。この構造自体が歪んでいるなと感じます。さらに、6年生の秋ごろになると、公立小学校のクラスの半分が休んで受験勉強している、なんてことも。これもう、公立教育として成り立ってないですよね。経済的負担と教育コスト親目線で見ると、塾代も大きな問題です。・集団塾で月4〜5万円・夏期講習でさらに数十万円・教材費も追加・個別指導も加えるとさらに高額私が勤めている塾は富裕層向けなので、払える家庭が多いですが、普通の家庭にはかなりの負担。正直、ウチは出せません。仮にお金があったとしても、そこまで塾にお金をかける気はないです。AI時代と教育の意味最近はAIも出てきて、与えられた問題に正確に早く答えるだけの訓練って、もうAIに勝てないんですよね。AIの下位互換を育てるための教育になっている気がして、ますます疑問を感じます。だから私は「もっと遊んでいい」「勉強ばっかりするな」と思います。推薦入試への評価入試制度そのものも考え直したほうがいいと思いますが、推薦入試だけはわりと良い仕組みだと感じます。・志望理由書、面接、小論文・基礎学力を測るペーパーテストこれらを通して、言語化能力や自己理解、コミュ力が鍛えられる。面接では「なぜその大学か」「将来どうしたいか」を語る必要があり、自分と向き合う訓練になります。推薦入試は就職活動や転職活動にも通じる経験。生徒が成長していくのを見ていて、私自身も楽しいです。これからの塾のあり方今の塾のように、ただ科目を教えるだけなら不要だと思います。学校の授業をもっと工夫すれば十分対応できるはず。塾がやるべきなのは、・言語化能力を伸ばす・自己理解を深める・面接対策や志望理由書のサポートそんなサービスだと思います。私は今、ココナラでこうしたサービスを提供しています。志望理由書の添削、面接対策、親子の教育相談など、興味があれば見てもらえると嬉しいです。志望理由書の添削・面接対策の依頼はこちら最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。
2025.09.21
コメント(0)
-
言葉にできないからこそ美しい─言語化の落とし穴
はい、マモ~です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「言語化の落とし穴」というテーマでお話しします。言語化の重要性と私の経験これまで、学習塾の担任、受験マネージャー、教育コンサルといった立場で、生徒の「言語化能力の向上」をサポートしてきました。具体的には、日々の面談で生徒が自分の考えを言葉にできるようにサポートしたり、日頃の行動を振り返るための問いかけをしたり。推薦入試にむけて志望理由書の添削や面接対策も行ってきました。いずれにせよ、勉強や入試では「言語化」が求められます。授業で先生の話を理解するのも、質問をするのも、自分の考えを伝えるのも、全部「言語化能力」が関わっています。成績を伸ばすにも、推薦入試で合格するにも、言語化は本当に大事だと感じています。私自身も、これまで3度の異業種転職を経験しましたが、言語化=コミュニケーション能力のおかげでなんとかやってこれたと思っています。言語化の限界ただし、言語化は万能ではありません。たとえば「好き嫌い」を言語化するのって難しいですよね。「なんとなく好き」「なんとなく嫌い」としか言えないとき、理由を聞かれても答えられないことがあります。直感で動くこともあるし、説明できないけど確かに感じている、という状態も普通にあります。絶景を見たときや、映画で感動して涙が出たとき、「なぜ涙が出たのか」「なぜ心が動いたのか」を言葉にするのは難しい。でも感動している自分は確かにいるし、それが美しいとも思うんです。言語化できないからこそ価値がある、そんな領域もありますよね。AI時代の言語化最近はAIが発達して、文章を整える力はもう勝てる気がしません。私自身も、思いついたことをバーッとテキストや音声で入力して、AIに整えてもらっています。とはいえ、言語化能力やコミュニケーション能力は不可欠です。ただし、やはり万能ではない。EQ(感情知能)を高めるには言語化は欠かせないけど、それがすべてではないと思っています。言語化できる領域と、直感や感覚の領域、どちらも大事。そこをうまくバランスとることが大切だと感じます。お知らせ最後にお知らせです。推薦入試を受ける人は、面接や志望理由書で「自分の言葉で語る力」が必要です。言語化能力を高めたい方、特に中高生向けに、ココナラでサービスを提供しています。興味があればぜひチェックしてみてください。推薦入試のサポート依頼はこちら最後までお読みいただきありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください。
2025.09.19
コメント(0)
-

お金をかけずにゆるっと英語学習を再開してみた
どうも、マモ~です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「最近の英語勉強の仕方」についてお話ししてみようと思います。英語学習を再開した理由最近また英語の勉強を始めました。理由はシンプルで、時間ができたからです。毎日ほんの少しでも英語に触れてみようかな、という軽い気持ちで再開しました。2年ほど前まではかなり真剣に取り組んでいて、テキストを使った英文法や長文読解、オンライン英会話などもしっかりやっていました。ただある日パタッとやめてしまって…。それでも一応、文法の基礎は頭に残っている状態です。ブランクはあるけれど、土台はある。じゃあ今はどう勉強しているのか?をシェアします。使っている教材:英文法の本まずは英文法。最近は「英文法の教科書」という1冊だけを読んでいます。一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 [ 牧野智一 ]これがすごく面白いんですよ。中高6年間で習う英文法を、ストーリー仕立てで学べる本。ピンク色の表紙で、本屋さんの社会人向け英語学習コーナーに必ず並んでいるくらい有名なやつです。もちろん社会人にもおすすめですが、学生さんにも良いと思います。英語の成り立ちや「なぜこの表現を使うのか」を学べるので、単なる暗記ゲームで終わらない。例えば「受け身は主語をぼかすために使う」みたいな、使いどころが分かる説明があるんです。学校の授業って「とりあえず覚えとけ」になりがちで、それが原因で英語を嫌いになる人、多いと思うんですよね。でもこの本なら読み物として面白いし、英語の本質に触れられる。「ちょっと英語やってみようかな」という人にすごくおすすめです。生成AIを活用次に使っているのがChatGPT。自分は無料プランですが、これがめちゃくちゃ便利。基本動詞の使い方を例文と一緒に教えてもらったり、文型とセットで確認しながら自分で文を作ったり。音声モードで会話練習もできるので、ライティングもスピーキングもカバーできます。気になることがあれば文法もすぐ聞けるし、ほんと「AIさまさま」です。しばらくはこれを活用していこうと思っています。ポッドキャストでリスニング最後にリスニング。SpotifyでBBCラジオなど、英語学習向けのチャンネルを聞いています。ネイティブの方が「食べ物」「仕事」「家族」といった身近なテーマで会話する番組があって、これがいいんですよ。シンプルな英語だから聞き取りやすいし、「あ、自分でもいけるかも」と思わせてくれる。ただ、広告が多いのがちょっとネック…。まとめ今やっていることは、この3つです。・読み物として楽しめる英文法の本・ChatGPT(生成AI)・英語学習向けポッドキャスト本は買う必要がありますが、それ以外は基本無料。「モチベーションはそこまで高くないけど、できればお金はかけたくない」という人には、なかなかいい方法かなと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。最後まで読んでいただきありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください!
2025.09.13
コメント(0)
-
塾に通えば成績が上がる?200組以上を見てきて分かった答え
マモ~です。いかがお過ごしでしょうか。今回は「塾に行った方がいい人」というテーマでお話ししていきます。塾に行けば成果が出る、わけじゃないこれまで学習塾で担任、いわゆる教育マネージャーや受験コンサル的なことをしてきました。関わったご家庭・生徒さんは200組以上になります。その経験から言えるのは、塾に通ったからといって、必ずしも成果が出るわけではない、ということです。成果が出た人でも、早くて3ヶ月、普通は半年から1年くらいのスパンで見ないと厳しい。しかも、本当に「塾に行った方がいい人」って、そんなに多くないんですよね。自学習慣がないと厳しいまず大前提。自学習慣がない子が塾に行っても、あまり意味がありません。もちろん、塾に通うことで少しずつ自学習慣をつけられれば成果は出ます。ただ、それでも最低半年はかかります。逆に、自学習慣が身につかないまま授業を受け続けても、成果は出ません。「そういう子を成果に結びつけるのがお前の仕事だろ」と言われればそれまでですが……正直、親に言われるまま仕方なく通っている子や、「なんでこんな勉強せなあかんの」と思っている子を変えるのは、かなり厳しいです。結局は本人に課題意識があるかどうか。「これを達成したい。そのために勉強が必要だ。だから変わりたい」そういう状態になっていないと難しいんですよね。コーチングですら難しいコーチングってありますよね。あれは「本人が変わりたい」と思って受けるものです。でも、知り合いが有名どころのコーチングを数ヶ月受けても、「あんまり効果なかったな」と言ってました。そのくらい、人を対話だけで変えるのは難しい。だから、本人が困っていない・変わろうとしていない人を動かすのは至難の業だと思います。まあ、それゆえにやりがいがあるとも言えるんですが。……とはいえ、ここまで話してきたことって、もしかすると私自身の「無力さ」とか「雑魚さ」を正当化しているだけかもしれません(笑)。でも、それも含めて正直にお伝えしたいんですよね。じゃあ話を戻して、実際に「どんな人が塾に向いているのか?」という話に移ります。じゃあ、塾に行った方がいい人は?ここからが本題です。私の考える「塾に通うと良い人」の条件を挙げます。①自学習慣がある勉強を日常的にこなせること。ここがスタートライン。もしそうでない場合は、授業よりもまず「習慣をつくるサポート」を受ける方が先決です。私自身もココナラで伴走型のサポートを提供しています。伴走型サポート(ココナラ)②マインドセットが整っている思考や行動のスタイルが前向きでないと成果は出ません。どんなマインドセットが良いか、どう直せばいいかについては、私の電子書籍『塾通いの落とし穴』にまとめています。電子書籍『塾通いの落とし穴』③目的意識が明確「なぜ塾に通うのか」を自分の言葉で言えること。例えば、・自学で分からない問題を解説してほしいから個別指導塾へ・量はこなしているけど成果が出ないから、原因を分析してほしいこういう具体的な目的があると、塾はとても有効です。④より高いレベルを目指したい人学校の勉強が物足りなくて、もっと難しいことをやりたい人。好奇心が強い子には、塾は最高の環境になります。まとめ塾に通えば誰でも伸びる、というわけではありません。むしろ伸びる人は少数派です。ただし、以下の条件が揃っていれば、塾は効果的な場所になります。・自学習慣がある・勉強量をこなせる・マインドセットが整っている・目的意識が明確・さらに高みを目指したい意欲や好奇心があるこの条件が揃ったとき、初めて「塾に行った方がいい人」になるのだと思います。参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただきありがとうございました。どうぞ良い一日を!
2025.09.11
コメント(0)
-

お金より大事?『時間資本』の使い方を見直してみた
今回は「時間資本の使い方を見直す」というテーマでお話しします。この「時間資本」という考え方、どこから来たのかというと――自分が大好きな著者である独立研究者・山口周さんの本 「人生の経営戦略」です。人生の経営戦略 自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 [ 山口 周 ]もうベストセラーと言っていいくらい売れていて、本屋のビジネス書コーナーに行くと表紙陳列されているぐらい、今ホットな本だと感じています。今年の1月ごろ出版されて、僕もすぐに買いました。前から発売が決まっていた時点で「これは絶対買おう」と思っていて、博多・天神の大きな本屋で見つけてすぐ手に取った記憶があります。時間資本とは何か?山口さんによれば、人生というのは「時間資本を、人的資本・社会資本・金融資本に変えていくゲーム」だということです。時間資本:自分でコントロールできる唯一の資源。つまり時間の使い方。人的資本:知識・スキル・経験。社会資本:信用・ネットワーク・人とのつながり。金融資本:現金・株式・不動産などお金に換算できるもの。この時間資本をどう振り分けるかがポイントなんですね。注意点としては、いくら知識やスキルを積み重ねても、それが直接お金(金融資本)にはならないということ。人的資本を高めたうえで、社会資本を築いて、初めて金融資本に変わっていく。――本を読んで、「確かにそうだな」と腑に落ちました。僕自身、資格を2〜3個とったことはありますが、それが直接お金になったことは正直ないんですよね。自分の時間資本の使い道では、自分は今どこに時間資本を投じているのか。仕事柄、午後から夜は働いていて、家に帰るのは11時過ぎ。そこからは風呂入って、歯磨いて、ちょっと休んで寝るだけ。だから、平日の午前中の3時間が勝負の時間なんです。この時間をどう使うかで、自分の未来が変わると思っています。1. 発信活動このポッドキャストのような発信ですね。シンプルに「好き」というのと、トーク力を磨きたい、副業につなげたい。人的資本・社会資本・金融資本すべてにつながる取り組みだと考えています。2. 運動ランニングや筋トレ、体操を30〜45分ほど。これは人的資本の「健康」の部分。健康がなければ人的資本も社会資本も築けない。だから一番大事な投資かもしれません。3. 英語正直、今は使う場面はないです。これまで2〜3回チャレンジしてはやめてきました。でも、海外旅行や外国の方との交流で役立つし、単純に楽しいので少しずつ続けようと思っています。4. 副業関連の勉強教育系の本を読んだり、アウトプットしたり。こちらは将来的に金融資本にもつながる部分ですね。ざっくりまとめると、僕の時間資本の使い道は発信・運動・英語・読書。副業を本格的にやるときは、発信と運動に絞り込む形になると思います。あなたの時間資本の使い方は?僕自身、最近改めて「自分はどのくらい時間を持っていて、それを何に投じるのか」を考えるようになりました。SNSをただ眺めるだけでいいのか? それとも、未来の資本につながることに時間を使うのか?この記事を読んでくださったあなたにも、一度「時間の使い方」を見直すきっかけになれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください。
2025.08.28
コメント(0)
-

型破りでもいい。「成功の再現性」を問う一冊『ダークホース』を読んで
こんにちは。今回は「これまでの成功ノウハウに縛られない」というテーマでお話していきます。「成功」とは何か?を問い直す本との出会い先日、個人的にとても面白い本に出会いました。その名も『ダークホース』。アメリカで2018年に出版された本で、日本語訳も出ています。この本では、従来の「成功の型」に当てはまらない人々のエピソードが紹介されています。いわゆる「成功の王道」——目的を定め、情熱を燃やし、決められたルートを進む——といった考え方に一石を投じる内容です。「情熱」ではなく「小さなモチベーション」に従うたとえば、学者として成功するには、大学に入り、専門性を磨き、徐々に職位を高めていく。音楽業界なら、インターンからスタートして、業界内で人脈を築く…そんな「成功のルート」があるように思われがちですよね。しかし、『ダークホース』に登場する人たちは、そうしたルートから大きく外れています。一見すると型破り。でも著者は、それを「たまたまの成功」だとは言っていません。再現性があると主張しています。その鍵となるのが、・自分の“違和感”を大切にする・情熱よりも“小さなモチベーション”に従う・自らの“感情”や“直感”に従って行動するという姿勢です。彼らは「成功しよう」と意気込んで成功したわけではなく、「なんか面白そう」「ちょっとやってみたい」という気持ちに従って動いた結果、気づけば成功していたという共通点があります。順風満帆じゃないからこそ、価値がある登場人物たちは、決して順風満帆な人生を歩んできたわけではありません。むしろ、若い頃は「成功」とは無縁だった人も多く、30代、40代、50代になってようやく「成功した」と言われるようになった方々ばかり。共通していたのは「自分の違和感を見逃さなかったこと」。そして「日々、小さなモチベーションに従って試行錯誤を繰り返していたこと」でした。「好きなことだけで生きていける時代」——どこかで聞いたようなこのサブタイトルに、最初は若干の時代錯誤を感じました。でも読み進めるうちに、今の時代にこそ必要な価値観なのかもしれない、と思うようになりました。本との「出会い方」で読み方は変わるちなみにこの『ダークホース』、実は3〜4年前にも一度出会っていました。手に取ったてパラっと読んだのですが、全く響かず、買うこともせずにスルー。ところが、先日たまたま書店で再会し、パラっと読み返してみたところ「なんか面白そう」と感じて、そのまま購入。そして今回はちゃんと読了して、「読んでよかった」と思えたんです。この経験から強く感じたのは、「同じ本でも出会う文脈によって感じ方は変わる」ということ。一度ピンと来なかったからといって、もう自分には必要ないと決めつけるのはもったいないですね。違和感と小さなモチベーションを大事にこの本を通して改めて感じたのは、「日々の違和感」や「ちょっとやってみたい」という気持ちをもっと大切にしたいということ。そして、失敗前提でいいから、面白そうと思ったことには素直に手を伸ばしてみる。行動のきっかけは、情熱じゃなくてもいい。むしろ、小さなモチベーションのほうが、結果として長く続くのかもしれないなと感じさせられました。最後にもし今、何かに行き詰まりを感じていたり、これからどう生きていこうか悩んでいる方がいたら、『ダークホース』を手に取ってみてほしいと思います。型破りな生き方にも、ちゃんと再現性はある。そんな勇気をもらえる一冊です。Dark Horse(ダークホース) 好きなことだけで生きる人が成功する時代 (単行本)最後までお読みいただき、ありがとうございました。どうぞ、良い一日をお過ごしください。
2025.06.06
コメント(0)
-
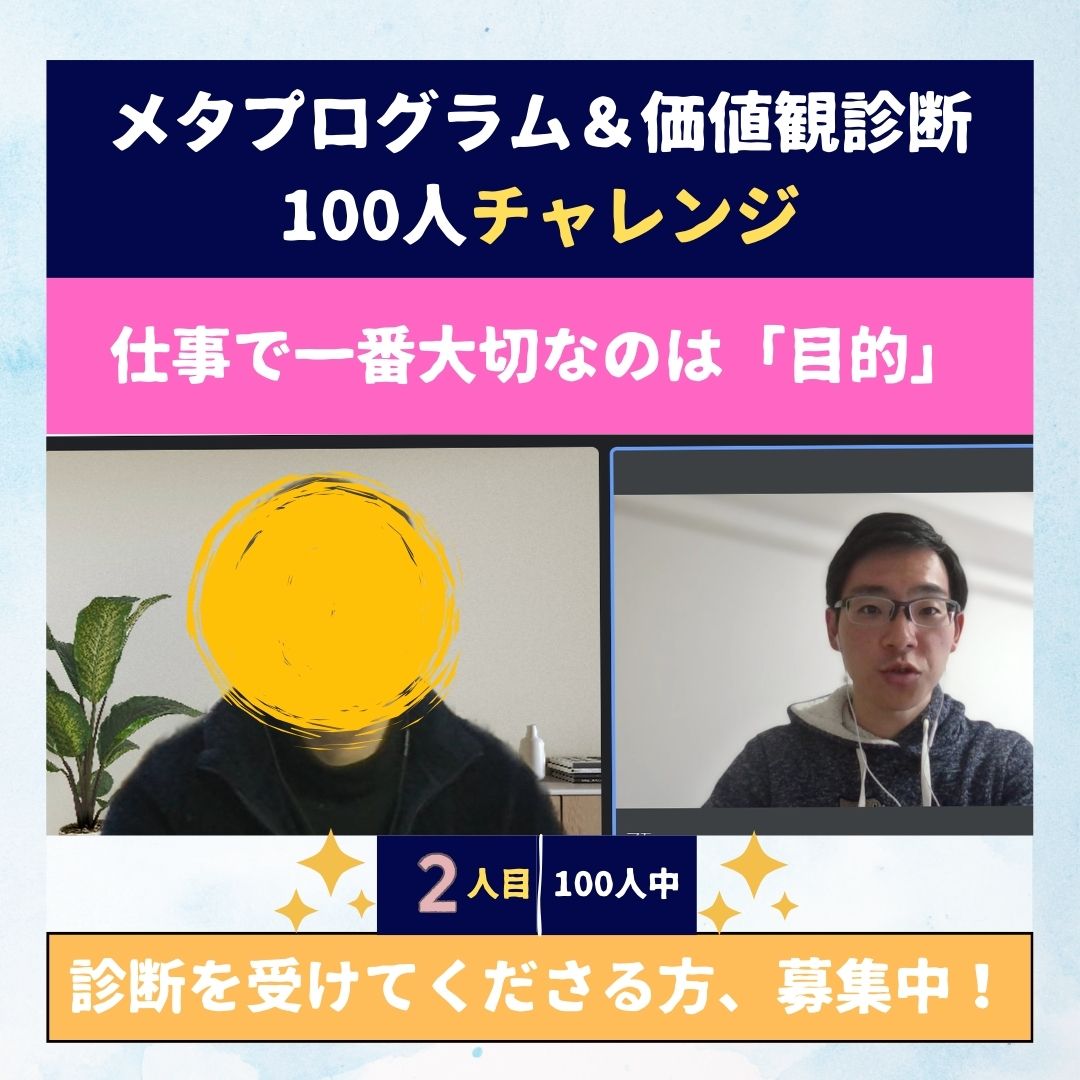
「そうです、だから私はこうなのか!」 メタプログラム診断で自己理解が深まる瞬間
📢 100人チャレンジ、2人の目の診断を実施しました!先日、メタプログラム診断を2人目の方に実施しました!メタプログラムの話をしたところ、「それ、面白いそう!」と興味を持って拝見し、診断を受けることに。診断を進める中で、「なるほど、だから私はこうなのか!」「そうか、これが私の考え方のクセなんだ!」と、自分の思考や行動のパターンに深く納得されていました。さらに、「これは◯◯さんのタイプだな」「だからあの人はああいう行動をするのか!」と、他者理解も進んでいく様子がとても印象的でした。診断後には、「これは面白い!もっと多くの人に知ってほしい!」と興奮気味に話をして見守って、この診断の価値を認識しました😊この診断を受けると、✅自分の思考パターンを言語化できる✅ 他人との違いがわかり、人間関係がスムーズになる✅仕事や環境選びのヒントが得られるというメリットがあります!現在、100人チャレンジを継続中!興味のある方は、ぜひ無料診断を受けてみてくださいね✨📌詳しくはこちら!無料セッションのご案内100人チャレンジモニター募集中!
2025.02.28
コメント(0)
-
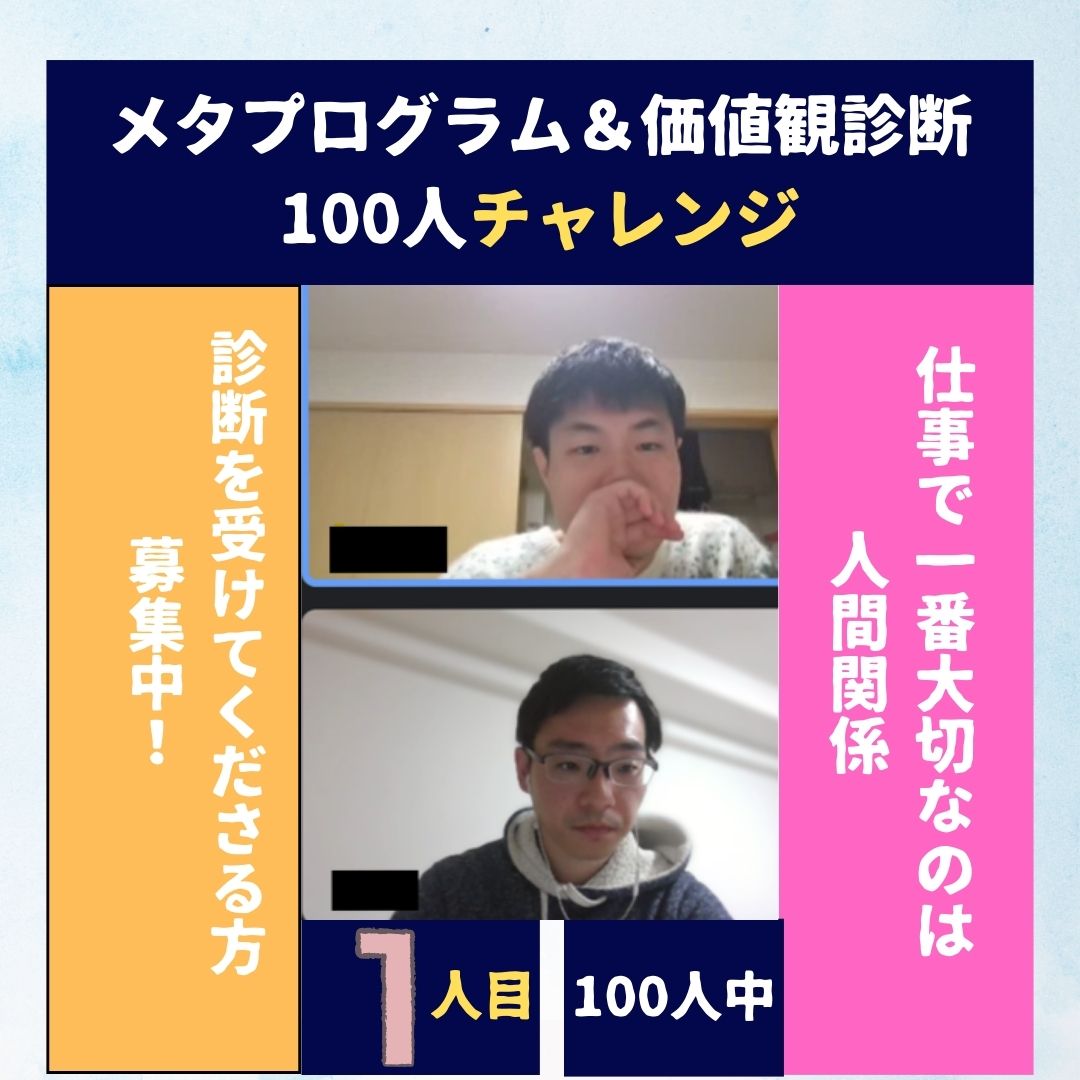
メタプログラム診断で「自分の思考パターン」を発見しよう
✔ 「なんとなくモヤモヤする…」✔ 「今の働き方や生き方、このままでいいの?」✔ 「本当に自分に合った選択をしたい!」こんな風に感じたことはありませんか?実は私自身、かつては「自分が何を大切にしたいのか」すら知らずに、迷っていました。でも、ある診断を受けたことで、自分の価値観や思考のクセを知り、納得のいく選択ができるようになったんです。そこで今回、100人限定でメタプログラム診断を提供することにしました!最初の診断を受けてくださった方からは、✅ 「これは面白い!」✅ 「人間関係の向上に役立ちそう!」といった嬉しい感想をいただきました。📌詳しい概要はこちら(note記事)無料セッションのご案内100人チャレンジモニター募集!メタプログラム診断とは?「人にはそれぞれ、無意識の思考や行動のパターンがある」と言われています。この診断では、あなたが普段どんな考え方や行動のクセを持っているのかを知ることができます。診断を受けるメリット✅無意識の思考や行動のクセが明確になる✅仕事でのモチベーションの上方や向いている仕事のほうが見えてくる✅他人のパターンを知ることで、人間関係が良好になる現在、100人チャレンジを進行中!無料で診断を受けられるこの機会に、ぜひ試してみませんか?興味のある方は、お気軽にDMまたはコメントください!
2025.02.25
コメント(0)
-
「勉強なんて面白くない」が正解。学校の勉強が役立つ本当の理由
こんにちは。今回は「何で学校の勉強をするのか」という疑問について、綺麗事ではない現実的な答えをお話しします。「将来役立つから」は子どもには響かないよく「何で勉強するの?」という問いに対する定番の答えといえば:「将来役に立つからやるんだよ」「勉強することは本来面白いものなんだ」でも、正直、全然ピンときませんよね。子どもたちに「将来役に立つから」と言っても、そんな先のことなんか見通せません。今を生きるのに精一杯な子どもにとって、全く納得感がないんです。私自身の学生時代を振り返っても、勉強が面白いと思ったことなんてありませんでした。よくわからないことをひたすら覚えさせられて、テストで評価される。良い印象がまったくなかったんですよ。そんな綺麗事を言われても、当時の自分も今の子どもたちも納得しないと思います。学校の勉強の本当の意義個人的には、学校の勉強をする意義はこうだと思います:「好きでも面白くもない物事を継続して、一定の成果を出す訓練をしている」または、「面白くないものに対しても、少しでも楽しみを見出す技術を学んでいる」ぶっちゃけ、学校の勉強は面白くないです。好きになれたらラッキー、面白いと思えたらラッキーですよ。でも、多くの人はそうは思えない。それでも継続して成果を出す訓練、つまり成績を上げたり、偏差値の高い高校や大学に行くための過程に意味があるんです。これが仕事に役立つ理由では、こんな訓練が何の役に立つのか?それは「仕事」です。仕事って、特に最初は全然うまくいかなくて、楽しくないし、つまらない状態からスタートするものです。中には最初から楽しいという人もいるかもしれませんが、大抵は面白くありません。ある程度の知識や経験を積んでようやく「ちょっと面白くなってきたかな」というレベルです。なのに「仕事も勉強も楽しいものだ」という前提で入ると、現実とのギャップに必ずやられます。過去の私がまさにそうでした。「天職がある」「好きを仕事にするべき」と思っていましたが、実際の仕事はそんなことなく、面白くなかった。そして、マインドセットの問題もあって、すぐに投げ出してしまいました。「好きを仕事に」の現実「好きを仕事にする」という考えに対する反論も。確かに好きな仕事をしている人はいます。YouTuberなどが代表例かもしれません。でも、彼らも最初からそれが仕事になっていたわけではありません。何年も無名の日々を過ごして、ようやく花開いたんです。その間はお金をもらっていないから「仕事」ではなかった。好きなことを続けた結果、価値提供できるようになって、それがお金につながった流れなんです。「好きを仕事に」は聞こえが良いですが、実際にはすぐにそうはならず、何年も、あるいは10年以上かかるケースがザラにあります。それに、ある程度の貯蓄や他の収入源がないと厳しい現実があります。仕事の本質多くの人(私も含めて)は、最初は基本的につまらない、面白くない、楽しくないことを仕事にしています。仕事の本質として、誰もがやりたがらないことをやっているからこそ、他者への価値提供につながるという側面もあります。みんながやりたいことなら、わざわざ誰かに頼む必要はないですよね。やりたくないからこそ他人に頼み、その分自分は別のことをする。それが仕事の一側面でもあるので、「つまらない、楽しくない、やりたくない」という前提があるんだと思います。学生時代に培うべきスキルそういった「面白くないこと」を耐え抜く力、乗り越える力、成果を出すためのスキルを、学生時代に勉強を通して培うほうがリアルだと思います。だから子どもたちに「なぜ勉強しなきゃいけないの?」と聞かれたら、綺麗事ではなく、こう答えます:「好きでも面白くもない物事を継続して成果を出す訓練を今しているんだよ。」「面白くない、楽しくないものに対しても、少しでも楽しみを見出す技術を学ぶためにやっているんだよ。」これは間違いなく仕事に役立ちます。例外はいる例外中の例外として、ビジネスそのものが好きな人、お金を稼ぐこと自体が好きな人(ホリエモンさんなど)には、この話は全く響かないでしょう。「何言ってんだ」と思うはずです。ただ、そういった人は少数派だと思います。起業家などはそうかもしれませんが、多くの人(私を含む)はそうではないはず。そういった大多数には、この考え方は響くのではないでしょうか。最後に何かの参考になれば嬉しいです。綺麗事ではなく、現実的な視点から学校の勉強の意義を考えることで、もっと納得感のある動機づけができるかもしれません。それでは、良い一日を。この記事を読んでくださった方へ私のことをもっと知っていただけたら嬉しいです。こちらの記事に詳しいプロフィールを公開しているので、覗いていただけると嬉しいです。これからも皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思います。プロフィール
2025.02.21
コメント(0)
-
国語ができない子の特徴。読書量や語彙力の問題じゃない?
今回は「国語ができない子の特徴」というテーマでお話しします。これまで学習塾で100組以上のご家庭・生徒を見てきた中で、国語ができない子には典型的なパターンがあることに気づきました。そこで、その特徴についてお話ししていきます。よく言われるのが「語彙力がない」「本を読んでこなかった」などですが、これは一理あるものの、例外も普通にあります。語彙力が豊富でも国語が苦手な子はいますし、たくさん本を読んできてもできない子もいるんです。もちろん、読書習慣があるに越したことはないし、言葉を知っていることもプラスですが、国語ができない根本の問題はそこではありません。では、何が問題なのか。それは「マインドセット」です。 具体的に言うと、「頑固」「柔軟性がない」「主観が強い」この3つが揃うと、国語ができなくなる傾向があるのです。これは、かつての私自身にも当てはまります。私は昔、頑固で柔軟性がなく、主観が強かったため、国語が全くできませんでした。今になって振り返ると、できなくて当然だったなと思います。そして、塾の先生として生徒を見てきた中でも、この3つの要素を持っている子は、国語が伸びにくいと感じています。国語の授業を受け続けても、なかなか成績が上がらない。先生は熱心に指導し、生徒も頑張っているのに成果が出ない。これは、この「マインドセット」の部分が解決されていないからです。例えば、「頑固さ」がどのように国語の学習に悪影響を及ぼすかを考えてみましょう。国語の評論文や論説文では、さまざまな著者の考えに触れます。文章を正しく理解する上で最も大切なのは、「受け入れること」です。自分の意見は関係なく、「この著者は何を言いたいのか?」を理解することが重要です。しかし、頑固な子はそれができません。そこで「主観」が出てしまい、「私はこう思う」と考えてしまうのです。けれども、問題は「あなたがどう思うか」ではなく、「著者が何を言いたいのか」です。主観が強い子は、この部分をうまく捉えられず、本文の要点を見失ってしまいます。また、小説問題でも同じことが言えます。小説の読解では、登場人物の心情を理解することが求められます。人間の本質的な感情や行動パターンに基づき、「こういう状況では、人はこういう気持ちになり、こういう行動をとる」という流れを掴むのが重要です。しかし、主観が強いと、「自分はこう思うから、この登場人物もこう考えているはずだ」と思い込んでしまい、適切に読解できません。要するに、「自分の考え」に縛られてしまうのです。一方、国語ができる子はどうでしょうか?彼ら彼女らには、以下の特徴があります。・柔軟性が高い ・いろんな考えを受け入れられる ・主観が弱い(自分の考えに固執しない) ・相手目線で考えられるこうした子は、たとえ本をあまり読んでいなくても、語彙力がそれほど豊富でなくても、国語の点数を安定して取れるのです。ですから、国語力を上げたいのであれば、単に教材をやる、授業を受けるだけではなく、「頑固さをなくす」「素直にいろんな考えを受け入れる」ことが大切です。また、「主観を抑える」ことも重要です。 「自分はこう思う」ではなく、「この著者は何を言いたいのか?」「この登場人物はどう感じているのか?」と視点を変えることが、読解力を高めるポイントになります。さらに、自分の考えに縛られないことも大切です。ここでポイントとなるのが、「アイデンティティ」と「考え」を切り離すこと。「自分の考えを受け入れなかったら、自分の存在を否定されたように感じる」という思い込みをなくすことが、国語力向上の鍵になります。最後に、考えてほしいことがあります。「なぜ、そこまで自分の考えに縛られてしまうのか?」 「なぜ、他の考えを受け入れられないのか?」これを自問自答してみてください。まとめると、国語ができない子の特徴は、 ・頑固 ・柔軟性がない ・主観が強い国語力を高めるには、これらを改善することが大切です。具体的にどう改善していくかについては、また別の機会にお話ししたいと思います。私自身も、どうすれば柔軟性を高め、主観を抑え、素直さを獲得できるのかを探求中です。その結果をまたアウトプットできればと思っています。最後までお読みいただき、ありがとうございました。 それでは、良い一日をお過ごしください!この記事を読んでくださった方へ私のことをもっと知っていただけたら嬉しいです。noteで詳しいプロフィールを公開しているので、覗いていただけると嬉しいです。これからも皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思います。プロフィール
2025.02.20
コメント(0)
-
子供に「どうしたい?」と聞く罠
今回は、「子供に『どうしたいの?』と聞く罠」についてお話しします。これは、私自身が娘を育てる中で気づいた、自分への戒めでもあります。この話を特に読んでほしいのは、小中学生、あるいはもっと幼いお子さんを持つ親御さんです。「どうしたい?」と聞くことのメリットと落とし穴子供に「どうする?」「どうしたい?」と聞くことは、例えばどこかに出かけようと考えている時や、時間を持て余して何をしようか迷っている時など、日常の中でよくあることですよね。このように子供の自主性を尊重することは、とても良いことですし、私自身も娘によく「どうする?」とか「どうしたい?」と聞くようにしています。一方的に指示や命令をするよりは、はるかに良いと思います。しかし、ここに一つ落とし穴があります。それは、子供の世界観が広がらないということです。子供は知っていることしか選べない常に「どうしたい?」と聞かれると、子供は(大人も同じですが)、これまでの経験や知識の中からしか選ぶことができません。つまり、知らないことは選択肢に入らないんです。その結果、いつも同じ選択肢の中で決めることになり、新しい体験が自然と減ってしまう。例えば、我が家では、娘に「今日はどこに行きたい?」と聞くと、決まって「ショッピングモール」か「いつもの公園」という答えが返ってきます。それはそれで楽しいですが、気づけば毎回同じ場所に行ってしまう。そして、それ以外の選択肢を考えることすらなくなってしまう。親が新しい選択肢を提示することが大切親の方が多くの知識や経験を持っています。だからこそ、子供の世界観を広げるためには、親が主体的に動いて、新しい世界を見せたり、聞かせたり、感じさせたりすることが重要だと感じました。もし「なるほど」と思った方は、ぜひいいねやコメントをしてくれると嬉しいです!この記事を読んでくださった方へこちらの記事に詳しいプロフィールを公開しているので、覗いていただけると嬉しいです。これからも皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思います。プロフィール
2025.02.12
コメント(0)
-
目標設定が苦手なあなたへ──問題から考えるアプローチ
目標設定って、難しくないですか?「目標を決めろ!」と言われても、そもそも何を目指せばいいのか分からない。そんな経験はありませんか?実は、私も目標設定が苦手でした。目標を立ててもピンとこないし、やる気も続かない。そんなときに試してみたのが、「問題から考える」目標設定の方法です。いきなり目標を決めるのはハードルが高い目標を設定する際、多くの人は「自分がどうなりたいか」「何を達成したいか」から考えようとします。でも、これが意外と難しい。そもそも、自分が何を求めているのかが分からないことも多いからです。そんなときは、「今、困っていること」や「解決したい問題」に目を向けるのが効果的です。私自身、目標を考えようとしてもうまくいかないことがありましたが、「今の問題を解決すること」を目標にすると、自然とやるべきことが明確になったんです。具体例:スマホの使いすぎをやめたい例えば、「スマホをついついいじってしまい、目の前のタスクに集中できない」という悩みがあったとします。この場合、いきなり「仕事や勉強に集中する!」と目標を立てるのではなく、まずは「スマホをいじる時間を減らすにはどうすればいいか?」を考えます。次に、「やめたいこと」「避けたいこと」を具体的に考えます。目的なくスマホをいじるのをやめたいSNSをダラダラ見る時間を減らしたい寝る前のスマホをやめたいこうして問題を明確にしたら、次に「その正反対の状態」を目標として設定します。スマホをいじらずに目の前のタスクに集中するSNSを使う時間を決める寝る前は読書やストレッチをするこのように、「問題」から「理想の状態」を逆算することで、現実的で実行しやすい目標が立てられるようになります。目標設定のカギは「自分の特性を知ること」人によって、目標にフォーカスすることでモチベーションが上がる人と、解決したい問題に目を向けることでやる気が出る人がいます。私自身、前者の「目標達成型」ではなく、後者の「問題解決型」です。「目標を立てて頑張ろう!」と言われても、あまりピンとこない。でも、「この悩みを解決しよう!」と考えると、行動がスムーズになるんですよね。あなたはどちらのタイプでしょうか?もし、「目標を決めても続かない」「そもそも何を目標にすればいいのか分からない」と感じるなら、まずは自分の抱えている問題に目を向けてみてください。まとめ:目標が決まらないなら「問題」から考えよういきなり目標を決めるのではなく、今抱えている問題を整理する「やめたいこと」「避けたいこと」をリストアップするその正反対の状態を目標にするこの方法なら、目標が決まらずに迷子になることもなく、自然とやるべきことが見えてくるはずです。参考になれば嬉しいです!最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください!この記事を読んでくださった方へ私のことをもっと知っていただけたら嬉しいです。noteで記事にで詳しいプロフィールを公開しているので、覗いていただけると嬉しいです。これからも皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思います。プロフィール記事
2025.02.10
コメント(0)
-
仕事の効率が劇的に変わる!自分に合った環境の見つけ方
こんな悩み、ありませんか?会社のオフィスだと集中できないけど、リモートワークでもなぜかうまくいかない…一人で黙々と作業するのは苦手。でも、チームワークが多すぎると疲れる…自分に合った働き方がわからず、仕事の効率が上がらない…実は、人によって「最も生産性が上がる環境」は違います。 あなたに合った環境を見つけることで、仕事のパフォーマンスが劇的に向上するかもしれません。この記事では、あなたに最適な働き方のタイプを知り、より快適に仕事を進めるヒントをお伝えします!あなたに合った働き方とは?人それぞれ、どんな環境で仕事をするのが一番効率が良いかは異なります。では、あなたにとって望ましい環境とはどんなものか、一緒に考えてみましょう。大きく分けて3つのタイプがあります。1. 個人型個人型は、一人で集中して作業することを好むタイプです。自分のペースで仕事を進めたい余計な会議や雑談が苦手成果が自分に直接反映される仕事が好きこのタイプの人は、フリーランスや専門職(ライター、プログラマー、デザイナーなど)に向いている傾向があります。例: コロナ禍でリモートワークに移行した途端、仕事の生産性が大幅に向上した人は、このタイプの可能性が高いです。2. 管理型管理型は、チームの中で明確な役割を持ちながら働くことを好むタイプです。仕事の範囲や役割が明確であることが重要他人と協力しながらも、自分の担当部分はしっかり管理したい誰が何をするのか、ルールが決まっている環境が快適このタイプの人は、プロジェクトマネージャーやチームリーダーなどに向いています。例: オフィスでは生産性が高かったのに、リモートワークになった途端、やるべきことが曖昧になりパフォーマンスが落ちた人は、管理型の可能性が高いです。3. チーム型チーム型は、他の人と一緒に働くことでモチベーションが上がるタイプです。みんなで協力しながら仕事を進めるのが好きチームの成果を共有できることに喜びを感じる一人で仕事をするとやる気が出にくいこのタイプの人は、営業職やイベントプランナー、カスタマーサポートなどに向いています。例: コロナ禍でリモートワークが導入され、在宅で一人で仕事をするようになった途端、生産性が大幅に下がった人は、このタイプかもしれません。どのタイプにも適応できる可能性どのタイプの働き方も、ある程度は演じることが可能です。例えば、普段は個人型の人でも、管理型やチーム型の特性を発揮することができます。これは状況に応じて適応する力とも言えます。同じ職場の同僚、上司、部下が全員同じタイプとは限りません。 むしろ、それぞれ異なるタイプであることの方が一般的です。だからこそ、相手がどのタイプなのかを考えながら仕事をすることで、適切な仕事環境を整えたり、自分に合った働き方を見つけることができるでしょう。例えば…「この人は連携プレイが苦手だな」 → その人は個人型かも?「オフィスでは優秀だったのに、リモートワークになって生産性が落ちた」 → その人はチーム型の可能性大!まとめ人それぞれ、望む働き方や適した環境は異なります。もし、「自分がどのタイプに当てはまるのかわからない」という方がいれば、診断ツールもありますので、お気軽にご連絡ください!オンラインでお話ししながら、あなたに最適な働き方を特定するお手伝いができます。最後までお読みいただき、ありがとうございました。では、今日も良い一日を!
2025.02.08
コメント(0)
-

心の知能指数を磨くための入門書『ゾーンに入る』レビュー
📖 「ゾーンに入る」—— EQを学ぶ入門書として◎「EQ こころの知能指数」の著者、ダニエル・ゴールマン氏の最新作を読みました! タイトルの「ゾーンに入る」にはちょっと惑わされましたが(笑)、内容はまさにEQの基礎を学ぶのにぴったりな一冊。この本では、✔ EQ(感情知能)とは何か?✔ EQが高いとどんなメリットがあるのか?✔ EQをどうやって鍛えられるのか?といった疑問に、具体的な例を交えながら解説されています。さらに、これまで学んできたGRIT、マインドセット、思考柔軟性(メンタルフィットネス)ともつながる内容で、改めて理解を深めることができました。そしてやっぱり、マインドフルネスの重要性! 本書でもその大切さが強調されていました。どんな分野でも、自分の心と向き合う力って不可欠ですね✨ゾーンに入る EQが導く最高パフォーマンス [ ダニエル・ゴールマン ]
2025.02.06
コメント(0)
-

時間資本を最大化する人生戦略
📖『人生の経営戦略』山口周「正しい目標がなければ戦略に意味はない。」これは胸に響く一文でした。私たちが唯一コントロールできる資本は「時間」。時間の使い方次第で、人的資本、社会資本、金融資本が変わってくる。だからこそ、成長・発展している領域に時間を投下することが大切。「仕事をしすぎて友人関係を疎かにしたことを後悔する」人生の有限な時間を、実現したいこと、大事にしたいことに投じられているだろうか?短期や部分的に見れば不合理でも、長期や全体では合理的な選択をする。「市場が爆発するのは一瞬」だからこそ、変化率に着目し、自分の居場所を論理的に見通す。結局、楽しめることがパフォーマンスを上げ、長く続けられることが大事。「ただ好きだから」で続けてきたものが、唯一無二の価値になる。打率より打席。時間資本の投資先、意識的に選んでいきたいですね。📷 画像はこの本!人生の経営戦略 自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 [ 山口 周 ]
2025.02.06
コメント(0)
-
あなたの"やる気スイッチ"、実は逆向きかもしれない
みなさん、こんにちは。今日はちょっと面白い話をしたいと思います。人のやる気って、不思議なものだと思いませんか?同じ状況なのに、ある人はめちゃくちゃやる気になって、ある人はまったくピンとこない。よくある話ですよね。なぜ、同じ声かけなのに、やる気の出方が違うのか例えば、こんな場面。会社の会議で上司が「今月は売上1000万を達成するぞ!」と声をかけます。すると...「よっしゃ、何とか達成してやるぞ!」と目を輝かせる人もいれば、「うーん、なんかピンとこないなぁ」と微妙な表情を浮かべる人も。実はこれ、おかしなことでも何でもないんです。やる気スイッチには、実は「向き」がある人によって、やる気が出るシチュエーションって全然違うんです。- 目標達成に向かって頑張れる人- 問題を解決しようとするときに燃える人- 周りの評価や報酬でやる気が出る人- 自分の価値観が満たされるとやる気になる人私自身、長年「なんで目標達成でやる気が出ないんだろう?」と悩んでいました。でも実は、私は「問題解決型」だったんです。つまり、「目標を達成するぞ!」と言われても、あまりピンとこない。でも「この問題を何とかしないと...」という状況だと、むしろやる気が出てくる。出世とかお金の話より、自分の価値観に合っているかどうかの方が、ずっとモチベーションに影響するんです。これって単なる「癖」なんですこれは性格の良し悪しの問題ではありません。その人が持っている思考や行動の「癖」なんです。心理学では、こういった無意識の思考・行動のパターンを「メタプログラム」と呼びます。人それぞれが持っている「フィルター」や「思考の枠組み」が違うんですね。なぜ、これを知ることが大切なの?自分のやる気の「向き」を知ることで、実はいいことがたくさんあるんです:- 仕事や人間関係でモチベーションを上げやすくなる- メタ認知能力が育つ- 人を色眼鏡で見なくなる- 「なんでこの人はこうなんだろう」と悩むことが減る自分のタイプを知りたい方へ現在、私は無料でメタプログラム診断を行っています。自分の経験を積むために無料で行っているので、怪しく思われるかもしれませんが(笑)、興味のある方は、コメントやDMでご連絡ください。きっと、あなたに合ったやる気の上げ方が見つかるはずです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2025.02.05
コメント(0)
-
受験もキャリアも、結局マインドセットで決まる説
勉強法や参考書選びも大事。でも、それ以上に大切なのは、もしかしたらマインドセットかもしれない。マインドセットって何?🤔マインドセットは、単なる「考え方」以上のもの。人の思考様式や心理状態を指し、個人の価値観や信念、経験に基づいて形成される概念です。我々の思考や行動を形作る枠組み全体とも言えます。なぜマインドセットに注目するのか富裕層向け学習塾で100組以上の家庭・生徒を見てきた経験から、ある結論に至りました:受験の結果や成績向上の分かれ道は、マインドセットで決まる!よくある残念なマインドセットパターン😅一生懸命勉強しているのに成績が伸びない、志望校に合格できない。その背景には、以下のようなマインドセットが隠れています:1. **先生のアドバイスを無視する自己流タイプ** - 指導教師からのアドバイスを受け入れず - 最後まで自分のやり方を貫く2. **現実逃避タイプ** - 悪い成績という現実から目を背ける - 改善策を考えようとしない3. **他責タイプ** - 成績不振を環境のせいにする - 親や先生のせいにする - 自分の責任と向き合わない4. **近視眼的タイプ** - 目先の結果だけを見る - 受験までの中長期的な戦略を立てられない私自身のマインドセット失敗談🙈実は私も、かつては「望まない結果を生むマインドセット」の持ち主でした:- 仕事がまったくうまくいかない時期があった- ダメダメな状態が続いていたでも、変われました- マインドセットを徐々に改善- その結果、「今は」割とうまくいっている- 最大の転換点は「マインドセット」だったなぜマインドセットは重要なのか?1. **受験だけの問題ではない** - 志望校合格 - 成績向上 - その先のキャリア2. **思考の枠組み自体を変える** - 結果を生む考え方が身につく - 長期的な成功につながるまとめマインドセットは、受験やキャリアの成功を左右する重要な要素です。正しいマインドセットを持つことで、望む結果への道が開けます。私自身の経験からも、マインドセットの改善が人生の転換点になることを実感しています。まずは自分のマインドセットを見つめ直してみませんか?具体的なマインドセットの改善方法や、望ましいマインドセットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。塾通いの落とし穴、成績が伸びない本当の理由#受験 #マインドセット #成功哲学 #キャリア #自己啓発
2024.10.25
コメント(0)
-
早めの専門特化は失敗のもと
「大学で学んだことをそのまま仕事に生かしたい」という思いを持つ高校生は少なくありません。学習塾講師として多くの高校生と接する中で、そんな生徒をよく見かけます。しかし、研究結果は意外な事実を示していました。専門を早く決めることのデメリットキャリアに関する研究によると、早めに専門を絞り込んだ人は、大学卒業後しばらくは高収入を得られるものの、時間の経過とともにゆっくり専門を決めた人に追い抜かれていくことがわかりました。これは、ゆっくりと時間をかけた人の方が、自分のスキルや性質により合った仕事を見つけられるためです。イノベーションを生む多様な経験テクノロジー開発の分野では、さらに興味深い発見がありました。様々な分野で経験を積んだ人の方が、一つの分野を極めた人よりも革新的な発明を生み出しやすいのです。これは、一見関係のない知識や経験を結びつけることで、新しいアイディアが生まれやすいからだと考えられています。若いうちは自分に合う分野がわからない高校生や大学生の多くは、勉強、部活動、アルバイトという限られた経験しか持ち合わせていません。そんな状態で、受験時に興味を持った分野が本当に自分に合っているかを判断するのは難しいでしょう。まずは様々な分野に触れることから始めるべきです。音楽家の研究から見える意外な事実音楽の分野でも、興味深い研究結果が報告されています。優秀な音楽家ほど、複数の楽器を演奏できる傾向にあるのです。具体的には3つ以上、半数以上の人が4~5つの楽器を扱えるそうです。幼い頃から一つの楽器に特化すべきという一般的なイメージとは、大きく異なる結果でした。理想的な専門分野の見つけ方専門分野は、多様な経験を積む中で自然と見えてくるものです。様々なことにチャレンジし、その過程で自分の興味や適性を発見していく。そして徐々に専門分野を絞り込んでいく。これが最も理想的なアプローチだと考えられます。世間では早めの専門特化が良いとされがちですが、研究結果はそれとは異なる示唆を与えています。芸術分野でさえ、多様な経験が良い結果につながるというデータが存在します。焦って専門を決めるのではなく、様々なことにチャレンジしながら、じっくりと自分の道を見つけていくことをお勧めします。皆さんも焦らず、自分のペースで進んでいってください。
2024.10.24
コメント(0)
-
幸せを追求しない方が幸せになれる説
皆さん、こんにちは。マモ~です。今日は幸福についての逆説的な考え方をお話しします。結論から話すと幸せを重視しすぎない方がいい、というのが私の結論です。さらに、自分が今幸せかどうかをあまり考えすぎない方がよい、とも思っています。心理学研究が示す興味深い事実ある心理学研究によると、人は幸せを重視すればするほど、今の生活に不満を感じやすくなるそうです。この傾向は、日頃から幸せを重視している人たちだけでなく、無作為に選ばれて「幸せの重要性」について考えさせられた人たちにも同様に見られました。さらに興味深いことに、幸福を最重要視する人ほど、うつ病になりやすい傾向があることも明らかになっています。哲学者ミルが見抜いていた真実この研究結果が出る前から、哲学者のJ.S.ミルは重要な洞察を残していました。彼は著作の中でこう述べています。「幸福以外の何か他の目的に心を傾けているものだけが幸せだと感じるのだ。例えば他人の幸せ、人類の発展、ある種の芸術や趣味などを手段とするのではなく、それ自体に理想の目的として情熱を向ける。幸せは目標として追求するものではなく、目標に向かう道のりの中で自然と見つかるもの」まさにその通りだと私も感じています。日常生活の中での幸せ私たちは普段、仕事をしたり、友人と交流したり、家族と触れ合ったり、趣味に没頭したりしています。これらの活動は、幸せになるための手段ではなく、それ自体が目的となっているのです。実は、その時は特別な感情を感じていなくても、後から振り返ってみると「あの時は幸せだったな」と感じることが多いものです。自己目的的活動の大切さ幸せを直接の目的とするのではなく、その行動自体に意味を見出す。これが自己目的的活動です。活動している最中は特別な感情がなくても、後から振り返った時に「あの時幸せだったな」と感じられる。これこそが理想的な形なのではないでしょうか。最後に幸せになりたいという気持ちは当然のことです。しかし、日常生活の中でそれを意識しすぎることは、かえって逆効果かもしれません。自分が幸せかどうかを考えすぎるのではなく、今している活動に没頭することで、結果として幸せが訪れる。これが、私の考える幸せへの近道なのかもしれません。この考え方は一見矛盾しているように思えますが、実は深い理にかなっているのではないでしょうか。皆さんも、あまり幸せを意識しすぎず、今している活動に没頭してみてはいかがでしょうか。
2024.10.23
コメント(0)
-
勉強が苦手な子の記憶力アップ3つの秘訣
こんにちは!学習塾で講師をしているマモ~です。私のもとには、「うちの子、なかなか勉強を覚えられなくて...」という親御さんの相談が多く寄せられます。そこで今回は、私が実践している記憶力アップの秘訣をお話ししたいと思います。1. 感想を言葉にする「実況中継法」人間の記憶の仕組みについて、皆さんご存知でしょうか。実は、私たちの記憶は「非陳述記憶」と「陳述記憶」という2種類に分かれています。さらに、陳述記憶は「意味記憶」と「エピソード記憶」に分類されます。勉強で覚える内容のほとんどは「意味記憶」に該当します。これは言葉の意味を表す知識や記憶のことですが、残念ながら記憶に残りにくい特徴があります。一方で、経験したことについての記憶である「エピソード記憶」は、とても記憶に残りやすいのです。そこでおすすめなのが、新しい知識に出会ったときに、すぐに感想を声に出す方法です。例えば、理科の人体の授業で「人の体って複雑だなぁ」と呟いたり、社会の授業でフランシスコ・ザビエルの肖像画を見て「この人ハゲてるやん」と言ってみたり。一見つまらない感想でも構いません。大切なのは、勉強内容に感情を乗せることで、意味記憶をエピソード記憶に変換することなのです。2. 五感フル活用法私が特に英単語学習で効果を実感している方法をご紹介します。単語を目で見て、ノートに書き出し、声に出して読む。そこまでは一般的かもしれません。しかし、ここからが重要です。家の中を歩き回りながら暗唱することで、体の動きと記憶が結びつき、より強く脳に定着するのです。じっと座って見るだけの学習より、体を動かしながらの方が圧倒的に覚えやすいことを、私自身の経験からも確信しています。3. 復習の黄金法則最後に、もっとも重要な「復習」についてお話しします。とある実験では、1回だけ学習した場合と、学習後に3回復習した場合では、記憶の定着率が3〜4倍も違うという結果が出ています。これは、短期間に同じ内容を複数回インプットすることで、情報が長期記憶に転換されやすくなるためです。復習をしないということは、せっかく費やした時間が無駄になってしまうということです。塾に通っている場合は、授業料も無駄になってしまいます。だからこそ、復習は学習の要となるのです。まとめこれら3つの方法は、私自身の経験からも効果が実証されています。特に「実況中継法」は、子どもたちに大人気です。楽しみながら記憶力を高められる方法なので、ぜひ試してみてください。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が皆さんの学習に少しでもお役に立てれば嬉しいです。良い一日をお過ごしください。【コンテンツのご案内】 受験成功の隠れた鍵:マインドセットが全てを変える!なぜ塾に通っても成績が上がらないのか? その答えが、ここにあります。 100組以上の家庭を導いた共育マネージャーが贈る、 画期的な受験対策ガイド。 ✅ 成功するマインドセットを身につける✅ 親子関係を深めながら志望校合格を目指す✅ 受験だけでなく、幸せな人生の基礎を築く 受験に悩む全ての親子におすすめの内容です。 詳細はこちら↓塾通いの落とし穴、成績が伸びない本当の理由
2024.10.22
コメント(0)
-
勉強ができる子の6つの秘訣:頭の良さよりも大切なこと
こんにちは。今回は、勉強ができるかどうかは実は態度で決まるという、ちょっと意外なお話をしていきます。富裕層向け学習塾での経験私は富裕層向けの学習塾に勤めていて、これまで少なくとも100人以上の生徒を担任として見てきました。その中で気づいたのは、地頭はものすごくいいけれども、あまり成績が良くない子が多くいるんです。一方で、正直に言って地頭の良さをあまり感じさせないけれども、勉強ができる子、つまり成績の良い子もいるんです。この経験から、私はずっと「地頭が良いに越したことはないけれど、それ以上に大事なのは、そもそも勉強に向かうスタンスなんじゃないか」と思っていました。科学的な裏付け実は、この考えには科学的な裏付けがあるんです。カリフォルニア州立大学名誉教授のアーサー・コスタ博士による調査結果が、私の考えと一致していたんです。勉強ができる子の6つの資質コスタ博士の調査によると、勉強ができる子に共通する資質が6つあるそうです:1. 諦めない2. 自制心がある3. 人の話を聞ける4. 柔軟に思考できる5. 正確さを追求する6. チャレンジを恐れない驚くべきことに、これらの資質は知的な才能というよりも、学習態度に関するものなんです。誤解を解く「頭が良くないから、うちの子は勉強ができない」というのは、実は大きな誤解なんです。むしろ、上記のような態度を持っているかどうかが重要なんです。例えば、「うちの子は本当に人の話を聞けるのか」「柔軟に思考できるのか」「諦めないか」「自制心があるか」といったことを見ていく必要があります。これ、マジで重要だと思います。受験失敗の主な原因私の経験では、受験でうまくいかない子の多くは、自制心が欠けていて、目の前の楽しい誘惑に流されてしまうケースが多いんです。まとめ結局のところ、どのようにして良い学習態度を身につけるかは日々の試行錯誤になると思います。でも、頭がいいとか記憶力がいいから勉強ができるというわけではない、ということだけは覚えておいてほしいんです。この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください!【コンテンツのご案内】受験成功の隠れた鍵:マインドセットが全てを変えるなぜ塾に通っても成績が上がらないのか?その答えが、ここにあります。100組以上の家庭を導いた共育マネージャーが贈る、画期的な受験対策ガイド。✅ 成功するマインドセットを身につける✅ 親子関係を深めながら志望校合格を目指す✅ 受験だけでなく、幸せな人生の基礎を築く受験に悩む全ての親子におすすめの内容です。詳細はこちら↓塾通いの落とし穴、成績が伸びない本当の理由
2024.10.21
コメント(0)
-
志望校決め、遅くてもいいんじゃない?
こんにちは。富裕層向け学習塾で講師をしているマモ~です。今回は、ある生徒の体験から、志望校選びについて考えてみたいと思います。突然の進路変更私の塾に通う高校3年生の生徒が、共通テストまであと3ヶ月というタイミングで、突然進路変更を申し出てきました。「先生、やっぱり建築じゃなくて、経営学部か商学部に行きたいんです」それまで建築系の学部・学科を目指して勉強してきた彼が、突如として理系から文系への転向を決意したのです。「今までの勉強は…?」正直、この報告を聞いた時は驚きました。今まで理系科目を中心に指導してきたのに、突然文系科目が必要になるなんて。「今までの授業は何だったの?」という気持ちが頭をよぎりました。しかし、よくよく考えてみると、これはこれで良かったのかもしれません。納得感のある選択彼の話を聞くと、建築系を目指すと言いながらも、ずっと疑問を抱えていたそうです。「本当に自分がやりたいことなのか?」という思いを抱えながら日々勉強していたのです。そして、じっくり考えた末に、自分が本当に学びたいのは経営や商学だと気づいたのです。早期決定vs納得感確かに、志望校を早く決めれば勉強の方向性も定まり、受験対策もしやすくなります。でも、それ以上に大切なのは、「本当にこれを学びたい」と自信を持って言えることではないでしょうか。大学に行く目的は、単に就職に有利だからではありません。学びたいことを学ぶこと。それが一番の目的のはずです。経験不足の中学生・高校生中高生にとって、将来の進路を決めるのは本当に難しいことです。学校の勉強と部活動、アルバイトくらいしか経験がない中で、自分の人生の方向性を決めるのは至難の業です。だからこそ、多くの経験を積み、人と接する中で、自分が本当に学びたいことを見つけていく過程が大切なのです。遅くても、納得できる選択を中学や高校の早い段階で志望校を決めてしまうより、時間をかけてじっくり考え、納得のいく選択をする方が自然だと私は考えています。たとえ浪人することになっても、本当に納得できる進路を選ぶ方が、長い目で見ればいいのではないでしょうか。まとめ志望校選びに正解はありません。早く決めることも大切ですが、それ以上に自分が本当に学びたいことを見つけることが重要です。みなさんも、焦らず、じっくりと自分の進路について考えてみてはいかがでしょうか。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が少しでも参考になれば幸いです。良い一日を!
2024.10.18
コメント(0)
-
宿題をやらない子どもとの向き合い方
こんにちは。富裕層向け学習塾で働いているマモ~です。今回は、多くの親御さんが悩んでいる「宿題をやらない子ども」との向き合い方についてお話しします。現実の厳しい状況私の勤める塾では、宿題をやってくる子の割合は半分にも満たないのが現実です。この状況は多くの親御さんを悩ませていることでしょう。私の基本的な考え方個人的な意見を述べると、宿題をやるかやらないかは本人の自由だと考えています。これはアドラー心理学でいう「課題の分離」という考え方に基づいています。宿題をやらなかった結果の責任を負うのは子ども自身であり、親や周囲の大人ではありません。しかし、親御さんの立場からすれば、そう簡単には割り切れないでしょう。そこで、具体的な向き合い方をお伝えします。宿題の目的を考えるまず大切なのは、なぜ宿題が出されるのかを子どもと一緒に考えることです。主な目的としては、授業内容の定着があります。また、自学時間の使い方を示すという役割もあります。さらに、学校では成績評価の材料として使われることもあります。未来を想像させる次に、宿題をやった場合とやらなかった場合の未来を想像させることが効果的です。例えば、宿題をやれば、テストで良い点が取れたり、大人に認められたりするかもしれません。一方、やらなければ、授業内容が定着せず、点数が下がったり、志望校合格が遠のいたりするかもしれません。このように考えることで、子ども自身が宿題の意義を理解し、取り組む動機づけになります。宿題の取捨選択ここが重要なポイントです。全ての宿題が意味があるわけではありません。例えば、公立小学校でよくある「同じ漢字を10回書く」ような宿題は、中学受験を目指す場合はあまり意味がないかもしれません。親御さんも一緒に、「この宿題をやる意味はあるのか?」を考えてみてください。場合によっては、勇気を持って宿題を「切る」という選択肢もあるのです。まとめ宿題との向き合い方は、単に「やらせる」だけではありません。子どもと一緒に目的を考え、意味のある宿題を選び、取り組む姿勢を育てることが大切です。時には、親が「この宿題はやらなくていい」と判断することも必要です。これらの方法で、宿題を通じて子どもの自主性や判断力を育てていけるのではないでしょうか。宿題は単なる課題ではなく、子どもの成長を促す機会として捉えることができます。最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。良い一日をお過ごしください。
2024.10.17
コメント(0)
-
目標は高く設定せよ!達成への近道と落とし穴
こんにちは。今回は「目標設定」について、私なりの考えと経験をお話しします。なぜ目標は高く設定すべきか人間は基本的に怠け者です。これは私自身、日々の生活で痛感していることです。隙あらば楽をしたい、怠けたいという気持ちがドクドク湧いてきます。だからこそ、目標は高く設定する必要があるんです。低い目標なら簡単に達成できますが、それ以上のことはしません。高い目標を設定することで、自分を奮い立たせ、より大きな成果を得ることができるのです。ただし、注意点があります。高すぎる目標は逆効果です。無謀すぎると感じてしまうと、やる気が起きません。理想的なのは、「難しいけれども頑張ったら達成できるかな」というレベルの目標です。研究結果が裏付ける高い目標の効果これは単なる私の思い込みではありません。様々な研究結果が、難しい目標を設定することの効果を示しています。特筆すべきは、達成感の違いです。簡単な目標を達成しても、得られる達成感は薄いものです。一方、「頑張ればできるかな?でも、どうだろう?」と思えるような難しい目標を達成したときの喜びは格別です。具体的な目標設定のコツ目標を設定する際は、具体的であることが重要です。例えば、ダイエットの場合。「痩せる」という漠然とした目標ではなく、「2週間で5キロ減量する」のように、具体的で測定可能な目標を立てましょう。目標達成に向けての心構え1. ポジティブに取り組む2. 甘く考えない3. 「楽勝」と思わない目標は達成できると信じつつも、簡単には達成できないと考えることが大切です。「楽勝だよ」と思ってしまうと、かえって達成確率は下がってしまいます。モチベーション維持のコツ目標達成に向けて頑張っているときに、「もう嫌だな」「やる気が下がったな」と感じることはよくあります。そんなときは、次の2つを考えてみましょう。1. 目標達成で得られるメリット2. 乗り越えなければならない壁この2軸を意識することで、モチベーションを高めることができます。さらに、目標を達成できなかった場合に起こりうる問題も考えてみると、より一層やる気が湧いてくるものです。最後にここでお話しした目標設定と達成のポイントは、受験勉強だけでなく、仕事にも十分活かせると思います。皆さんの目標達成の助けになれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください!
2024.10.16
コメント(0)
-

「たかが受験」と思うことで受験ストレスを軽減できる?
こんにちは。今回は受験ストレスとの上手な付き合い方について、ちょっと意外な視点からお話しします。意外な結論:「たかが受験」と思おう結論から言うと、子供というよりは親御さんが「たかが受験」と思っておくことをおすすめします。「え?そんな無責任なこと言っていいの?」と思われるかもしれません。確かに、一生懸命取り組んでいる受験に対して「たかが受験」なんて言うのはないだろう、と思う方も多いでしょう。でも、ちょっと聞いてください。富裕層向け学習塾での経験から私は富裕層向けの学習塾で働いていて、様々な家庭を見てきました。その中には、「この中学や大学に受からないと人生終わり」と思い詰めている生徒や親御さんがいたんです。レアケースですが、たまにいました。そういった家庭こそ、どこかで「たかが受験」と思ってほしいんです。そう思わないと、家族みんなでメンタルがやられてしまうんじゃないかと心配になります。「たかが受験」の使い方に注意ただし注意点があります。受験勉強に真面目に取り組んでいない人が「たかが受験」と言うのは、ちょっと違います。一生懸命やりすぎて思い詰めてしまい、メンタルがヤバそうな人たちが「たかが受験」と思うことに意味があるんです。それで冷静に我に返ることができるんですね。サッカー漫画「アオアシ」からのヒントこの考え方のヒントになったのが、「アオアシ」というサッカー漫画です。【中古】アオアシ <1−36巻セット> / 小林有吾(コミックセット)主人公の青井葦人がサッカーのことで思い詰めている時、ヒロインの一条花が「たかがサッカーだろ」と言うシーンがあります。この一言で葦人は冷静さを取り戻し、改めてサッカーと向き合うんです。もしこの言葉がなかったら、葦人は本当に追い詰められていたかもしれません。「たかが受験」の真の意味それだけ物事に熱中して思い詰めてしまう。そんな状態の時にこの「たかが受験」という言葉を思い出してほしいんです。どこかで「たかが受験」と思っておくことで、変に思い詰める必要もないし、過度なストレスもかからないんじゃないでしょうか。もちろん、受験を軽視しろという意味ではありません。でも、人生には受験以外にもたくさんの大切なことがあります。そのバランスを取るための、ちょっとした心の余裕として「たかが受験」という言葉を使ってみてはどうでしょうか。この記事が、受験に向き合う皆さんの心の支えになれば嬉しいです。がんばりすぎず、でも諦めず、自分のペースで頑張ってくださいね。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
2024.10.15
コメント(0)
-
親の期待、「What」より「How」で伝えよう
こんにちは。今回は、親の子に対する期待のかけ方というテーマでお話しします。結論から言うと、WhatではなくHowが大切なんです。理想は期待しないこと実は一番いいのは期待しないことなんです。子供のありのままをただ受け入れて、存在そのものを肯定して愛する。これが理想的だと思うんですよね。ただ、正直これができるのは、おそらく人生3周ぐらいしてないと無理だと思います。私も5歳の娘を育てながら、いろんな子育ての本やネット記事を読んで実践しています。日々試行錯誤して、間違ってるなぁと思うことは改善していってるんですけど、完璧な親になるのは無理だろうなぁと思っています。でも、それに近づけるように日々自分を成長させていきたいなと思っているんです。「What」の期待の問題点「What」の具体例を挙げると、例えば「子供に医者になってほしい」とか「弁護士になってほしい」、あるいは「〇〇大学に行ってほしい」とかですね。就職先も「この会社に入ってほしい」というのも「What」です。実は、私は富裕層向けの学習塾に勤めているんです。そこでは医師家系の子どもが多くて、自然と医者になる道を歩まざるを得ない状況をよく目にします。正直、見ていて苦しそうだなと感じることが多いんです。確かにお金は世間的な家庭からするとめちゃくちゃあって羨ましいんですけど、その子供たちは進路を狭められているんですよね。中には医師以外の道がないみたいな感じの子もいて、「What」に関する期待のかけ方ってかなり辛いものがあるなと思います。「How」の期待のメリット一方で「How」は違うんです。これって正解が無数にあるんですよね。例えば私の場合、娘への唯一の期待は「How」なんです。その内容は「自分が信じた道をとことん突き進んでほしい」というもの。周りが何と言おうとも、自分がこれだと思うものに突き進んでほしい。これって無数の正解がありますよね。正直、親としては本人が納得いっていればそれでいいという感じなので、選択肢はいくらでもあるんです。こういった期待のかけ方の方が個人的にはいいんじゃないかなって思っています。まとめもちろん、そのうち「What」的な期待が出てくるかもしれません。でも、そういう親のエゴをどう抑えていくかが自分の課題だと考えています。今日お話ししたのは、親の子に対する期待のかけ方。大事なのは「What」ではなく「How」だということです。皆さんの子育ての参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください!
2024.10.14
コメント(0)
-
子どもの「なぜ?」を育む、面倒くさくない答え方
こんにちは。今回は、子育て中の親御さんにとって身近な話題、「子どものなぜへの答え方」についてお話しします。子どもの好奇心、どう受け止める?子どもって本当に好奇心旺盛ですよね。「なんで、これはこうなるの?」と、次から次へと疑問を投げかけてきます。我が家の5歳の娘も例外ではありません。正直なところ、親として「いいことだな」と思う反面、忙しい時には「ちょっと面倒くさいな」と感じることもあります。皆さんも同じような経験ありませんか?NGな答え方とその影響ここで注意したいのが、子どもの「なぜ?」に対する答え方です。❌ NGな例:「そんなこと考えないでいいから○○しなさいこういった答え方は、子どもの疑問を封じ込めてしまいます。結果として、好奇心が徐々に失われていくんです。好奇心のない人生って、ぶっちゃけ面白くないですよね。富裕層向け学習塾での観察私は富裕層向けの学習塾で働いていますが、そこでの経験からも好奇心の重要性を実感しています。「ただやるべきことをやれ」「いいからやれ」と親に言われて勉強している子どもたちの目は、どこか死んでいるんです。一方で、自ら学びたいと思って勉強している子どもたちは目が輝いていて、「めっちゃ楽しかったです」と授業後に言ってくるんです。そして、そういう子たちは結果も伸びていくんですよ。好奇心旺盛な受験生の例去年、ある中学受験生の男の子が印象に残っています。多くの子が不安を抱える受験期に、彼は「めっちゃ楽しみです」と目を輝かせていたんです。日々の授業でも積極的に質問し、新しい発見を楽しんでいました。そんな彼のお母さんとお話する機会があったのですが、驚いたのは母親の接し方でした。好奇心を育む親の対応このお母さん、自分の考えを押し付けるのではなく、子どもの疑問に寄り添う姿勢でした。「何でやろうね」と一緒に考え、子どもが仮説を立てると「そうかもね」と受け止める。まさに理想的だなと思いました。おすすめの答え方そこで、私がおすすめする答え方です。✅ 好奇心を育む答え方「何でやろうね」「何でだと思う?」この方法なら、親も面倒くさくないですし、子どもの好奇心も育めます。子どもは自然と考え、仮説を立てるようになります。まとめ子どもの「なぜ?」に対して、「何でやろうね」「何でだと思う?」と返すことで、好奇心を殺さず、探究心を高められるのではないでしょうか。私自身、娘にはこんな風に接する父親になりたいと思っています。皆さんの子育ての参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
2024.10.12
コメント(0)
-
受験勉強の計画は「何を」だけじゃダメ
こんにちは。富裕層向けの学習塾で働いているマモ~です。今回は、受験勉強における効果的な計画の立て方についてお話しします。なぜ「何を」だけの計画では不十分なのかこれまで多くの生徒さんと接してきた中で、よく勉強計画の話になります。そんな時、ほとんどの生徒さんが「何を」するかしか考えていないことに気づきました。例えば、「理科の問題集を2時間解く」というような計画です。一見悪くないように思えますが、これだけでは不十分なんです。なぜかというと、「何を」だけを決めても、実行レベルのクオリティが下がってしまうんですね。つまり、計画を実行する確率も低くなってしまうわけです。これでは効果的な勉強ができません。効果的な計画立ての3つのポイントでは、どうすれば良いのでしょうか?私がお勧めするのは、「何を」に加えて「いつ」「どこで」「どのように」を具体的に決めることです。これらを明確にすることで、計画の実行力が格段に上がります。「いつ」を決めるまず「いつ」を決める際は、単に時間を決めるだけでなく、日常のルーティーンに組み込むのがおすすめです。例えば、「風呂上がりにすぐ勉強する」とか「歯磨き後に30分勉強する」といった具合です。毎日必ず行う行動の後に勉強を組み込むと、習慣化しやすくなるんです。「どこで」を具体的に次に「どこで」ですが、これも具体的に決めることが大切です。「家で勉強する」では曖昧すぎます。「自分の部屋の机で」や「リビングのソファで」というように、具体的な場所を決めましょう。場所を決めることで、その場所=勉強という連想が生まれ、集中しやすくなります。「どのように」を言語化する最後に「どのように」を言語化することが重要です。ここが多くの生徒さんが躓くポイントなんです。「問題を解く」では不十分で、もっと具体的にステップを言語化する必要があります。例えば、「先週の授業で解説された数学の問題10問を自分で解く。次に関連問題を20問解く。その後、丸付けをして理解度を確認する。間違った問題はやり直し、全ての問題を人に説明できるレベルまで理解を深める」というように、具体的なステップを決めるんです。実践例:2時間の勉強計画こうすることで、何をすべきかが明確になり、勉強の効率も上がります。実際に2時間の勉強計画を立てるなら、「風呂上がりにすぐ、自分の部屋の机で勉強を始める。2時間で教科書6ページ分の問題を解く。まず一通り全ての問題を解いてみて、わからない問題は印をつけておく。全て解き終わったら、印をつけた問題の解説を見て理解し、もう一度その問題を解き直す」といった具合です。最後にこの方法を実践すれば、計画通りに勉強を進めやすくなります。もちろん、多少の時間のズレは出るかもしれません。しかし、「何を」だけでなく「いつ」「どこで」「どのように」まで具体的に計画を立てることで、実行力は格段に上がるはずです。みなさんの受験勉強の成功を心から願っています。この記事が少しでも参考になれば幸いです。それでは、良い一日を!
2024.10.11
コメント(0)
-
本を買わないことが、読書の質を高める
こんにちは。今回は、私の本の買い方についてお話しします。これまで1000冊以上の本を読み、400冊ほど購入してきた経験から得た考えをシェアしたいと思います。本を買うときの新しいアプローチ私の本の買い方で一番のポイントは、欲しい本があってもすぐに買わないということです。これは最近始めた方法で、以前はまったく逆のことをしていました。2、3年前までは、直感でいいと思った本はすぐに購入していました。その結果、買ってよかったと思える本や何度も読み返したい本にも出会えました。しかし、多くの本は「とりあえず読んだ」だけで終わり、身にならない、血肉にならないと感じることが多かったです。結局、購入した本の半分以上をブックオフなどで売却してしまいました。この買い方に問題を感じ、新しいアプローチを試し始めました。新しい方法では、本屋で気になる本を見つけたら、その場でパラパラと読みます。いい感じだと思っても、すぐには買いません。この作業を2、3回繰り返します。2ヶ月後、3ヶ月後にまた同じ本を見て、「いいな」と思っても、もう一度待ちます。ようやく3回目くらいで、「今、この時期に読むべき本だ」と感じたら購入します。この方法を実践してみると、本当に良かったと思える本に出会うことが多くなりました。なぜこの方法が効果的なのかこの方法が効果的な理由は主に三つあります。まず、何回も吟味することで、本当に自分に必要な本かどうかを見極められます。次に、その本の内容を知りたいと思える「今」という瞬間を大切にできます。そして、待つ間に、無意識のうちにその本の内容を知りたいという欲求が高まります。修行の師弟関係との類似点この方法は、昔の修行における師弟関係に似ているかもしれません。師匠はすぐに弟子に教えず、雑用をさせて待たせます。弟子の学びたい気持ちが高まってから、ようやく教えます。これにより、弟子の学習意欲と吸収力が高まります。本の買い方も同じで、待つことで本の内容を知りたいという意欲が高まり、読んだ時の吸収力が格段に上がるのです。実践の結果この買い方を実践した結果、最近購入した本は読んでよかったと強く感じ、何度も読み返したくなり、売りたくないと思えるようになりました。そのような本は、思い切ってマーカーやペンで線を引き、何度も読み返すようにしています。まとめ本を買わないことが、逆説的に、本当に読みたい本に出会う秘訣かもしれません。すぐに満足せず、じっくりと本との関係を育むことで、より深い読書体験が得られるのです。皆さんも、新しい本の買い方を試してみてはいかがでしょうか。きっと、本との新しい出会い方が見つかると思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
2024.10.10
コメント(0)
-
思春期の子育て、実はただ「見守る」のが正解?
こんにちは。富裕層向け学習塾で働くマモ~です。今回は、思春期の子供との距離の取り方について、私の経験から得た意外な結論をお伝えします。結論:信じて黙って見守る結論から言うと、思春期の子供に対しては「信じて黙って見守る」というスタンスが最も効果的です。これは多くの親御さんにとって意外に聞こえるかもしれません。しかし、私の経験上、この方法が最も子供の成長を促すのです。なぜ介入はNG?一番避けるべきなのは、子供の生活に過度に介入してしまうことです。典型的な例を挙げましょう。- 親が主導で週間スケジュールを作成- 曜日や時間まで細かく指定- 子供に指示・命令してスケジュールを強制私が富裕層向けの学習塾で見てきた多くの家庭がこのパターンでした。しかし、結果はどうだったでしょうか?残念ながら、ほとんど効果がありませんでした。なぜでしょうか?それは子供が「やらされている」状態になってしまうからです。この方法で成績が上がったケースは、私の記憶にはありません。では、どうすればいい?答えは意外にシンプルです。黙って信じて見守るしかないのです。思春期の子供は、親の言うことをほとんど聞きません。口も聞いてくれないかもしれません。この時期、子供自身が気づくしかないのです。だから、私たち大人は「待つ」しかありません。親の不安への対処法「でも、ずっと待っていられない!」と思う親御さんも多いでしょう。受験は迫っているのに、子供は全然勉強せず、別のことばかりしている...。不安になるのは当然です。そんな時は、指示や命令ではなく、問いかけをしてみましょう。例えば:- 「どうしたの?」- 「どうしたいの?」- 「お母さんに何かできることある?」このように、子供の意思を尊重する問いかけが大切です。これは教育者の工藤勇一さんが提唱する「子供の自律性を促すための3つの声かけ」にも通じる方法です。私自身、塾でこの方法を実践し、効果を実感しています。絶対NGワード「勉強しなさい」「勉強しなさい」。これは思春期の子育てにおいて最悪のワードです。この言葉で本当に勉強を始めた子供を、私は見たことがありません。では、どうすればいいのでしょうか?答えは、率直に自分の気持ちを伝えることです。例えば:「あなたが全然勉強しなかったら、お母さんはどの高校にも行けないのではないかと心配になるわ」このように、親の本当の気持ちを伝えることで、子供の心に響く可能性が高まります。「やべー、お袋を心配させちゃってる。なんとかしなきゃ」と、子供自身が考え始めるかもしれません。まとめ思春期の子育ては、親にとって大きなチャレンジです。しかし、この時期こそ「信じて黙って見守る」ことが大切なのです。子供の自主性を尊重し、必要な時だけサポートする。そんなスタンスが、長い目で見て子供の成長を促すのです。皆さんの子育てのヒントになれば幸いです。良い親子関係が築けますように!
2024.10.09
コメント(0)
-
忙しい親御さん必見!5分でできるメンタルヘルスケア3選
こんにちは。今回は特に子育てや家事、仕事に追われる親御さんに向けて、簡単にできるメンタルヘルスケアの方法についてお話しします。なぜメンタルヘルスケアが必要なのか最近の調査によると、日本人のメンタルヘルス状況は年々悪化しているようです。- アクサの「マインドヘルスに関する調査 2024」:日本人の19%が心の病気を抱えている- うつ症状の増加:2013年の7.9%から2020年には17.3%に私自身、以前の会社で働いていた時はメンタルをやられていました。もともと塞ぎ込みがちな性格で、悪いことを考え始めるととことん落ち込んでしまうタイプでした。5分でできるメンタルヘルスケア3選忙しい方でも実践できる、効果的なメンタルヘルスケア方法を3つご紹介します。1. ジョギング2. 瞑想3. ストレッチこれらはいずれも、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を減らす効果があります。しかも、たった5分でも効果が出るんです!おすすめは瞑想(マインドフルネス)瞑想は特におすすめです。その理由は:- ストレスホルモン減少- 幸福ホルモン(セロトニン)増加- IQ・創造力向上- 感情の安定- うつ・記憶力・イライラの改善- 免疫力向上一見、ただ呼吸に集中しているだけに見えますが、1〜2週間続けると変化を感じられます。私は電車通勤中に1分でも目を閉じて呼吸に集中するようにしています。個人的におすすめの運動療法最近、体調も気分も安定しているのは、ランニングを始めたからだと思います。5分でも効果はあるので、家の周りをぐるぐる走るだけでもいいんです。まとめ忙しくてメンタルをやられてしまったら何もできません。だからこそ、事前に対策を!ジョギング、瞑想、ストレッチのいずれかを、毎日たった5分でも実践してみてください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです。良い一日をお過ごしください!
2024.10.08
コメント(0)
-
子どものやる気を引き出す魔法の言葉:「なぜやるの?」
こんにちは。富裕層向け学習塾で働いているマモ~です。今回は、子どものモチベーションアップについて、現場での経験を交えてお話しします。なぜ「やりなさい」は逆効果なのか多くの親が陥りがちな罠があります。それは「宿題をしなさい」「勉強をしなさい」という声かけです。しかし、この方法で本当に勉強や宿題をした例を、私はほとんど見たことがありません。特に注意が必要なのは、第二次反抗期と呼ばれる小学校高学年から中学生の時期です。この時期には「心理的リアクタンス」という現象が起きやすくなります。簡単に言えば、「やれ」と言われるほどやりたくなくなる心理です。逆に「やるな」と言われるとやりたくなる、そんな心理が働くのです。効果的な声かけとはでは、どのように声をかければいいのでしょうか。答えは意外と単純です。「なぜやるのか」を伝えることが大切なのです。例えば、「これをやることで志望校に合格する可能性が高まるよ」や「日々の宿題や勉強の積み重ねが、楽しい学校生活につながるんだよ」といった声かけです。このように目的や意義を伝えると、子どものモチベーションが高まりやすくなります。やる気が起きない時の対処法しかし、人間は完璧ではありません。目的を伝えてもやる気が起きないこともあるでしょう。そんな時は、もう一度目的を考え直すことをおすすめします。次のテストでいい点を取りたい、志望校に合格したい、友達を見返したい、好きな子にすごいと思われたい。こういった具体的なメリットを考えてみるのです。これらを考えることで、やる気が湧いてくることがあります。最後の切り札それでもダメだった場合の最後の手段があります。それは、やらなかった場合のデメリットを考えることです。例えば、お母さんに怒られる、成績が下がって志望校に行けなくなる、先生に怒られる、先生との信頼関係を失うなどです。特に好きな先生との約束を破るのは嫌だな、と思えば、それだけでやる気になることもあります。まとめ子どものやる気を引き出すには、まず「やりなさい」という言葉を避けましょう。代わりに「なぜやるの?」という視点で声をかけてみてください。それでもやる気が起きない時は、具体的なメリットを考えたり、やらなかった場合のデメリットを想像したりするのも効果的です。この方法を試してみると、きっと子どものやる気に変化が見られるはずです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。この方法で、お子さんとの関係がより良くなることを願っています。良い一日を!
2024.10.07
コメント(0)
-

「自由な時間が多すぎても幸せになれない」という残酷な真実
こんにちは。今回は「そんなに自分の時間があっても困るよね?」というテーマでお話しします。待ち望んだ「自由な2日間」先日、妻と娘が義理の両親と2泊3日でディズニーリゾートに行っていました。その間、私も仕事を休みにして、ほぼ丸2日間、自分一人の時間を過ごすことができたんです。こういう機会って、半年か1年に1回くらいしかないので、めっちゃ楽しみにしていました。1ヶ月前くらいからその2日間を心待ちにしていたんですよ。理想と現実のギャップ結果としては、充実した時間を過ごせました。でも同時に「あれ?やることないな」と感じて、何とか時間を潰した感もあったんです。やりたかったことは、- このような発信活動- 運動- 読書でも、これって普段もやっていることなんですよね。丸々自由な時間をもらっても、やりたいことはそんなに変わらないんだと気づきました。雨の中の2日間あいにく2日間とも雨で、車もないので遠出もできず。基本的に家で過ごしていました。- ひたすら考え事をする- テキストベースで書く- 集中力が切れてきたらマトリックスを初めて見たという感じの2日間でした。「理想の自由時間」についての驚きの事実ここで思い出したのが、『人生が充実する時間の使い方』という本の内容です。「人生が充実する」時間のつかい方 UCLAのMBA教授が教える“いつも時間に追われる自分”をやめるメソッド [ キャシー・ホームズ ]この本によると、1日の自由に使える時間(可処分時間)は、2〜5時間程度が理想的だそうです。- 2時間未満だと少なすぎる- 5時間以上あっても幸福度は上がらないというデータがあるんです。私の経験から今回の2日間、つまり24時間すべてが自由時間だった経験から、普段の休日に5時間くらい自由時間がある時と大差ないと感じました。つまり、「もっと自由な時間があれば充実するはず」というのは、案外幻想かもしれないんです。バランスが大切逆に、自由時間が2時間未満というのは確かにきついです。仕事、子育て、家事に追われている方、特に共働きの妻なんかはそうかもしれません。そういう場合は、- 仕事を減らす- 子育てや家事を親族やサービスに頼むなど、何とか2時間以上の自由時間を作る工夫が必要かもしれません。まとめ結論として、自由時間は「少なすぎず、多すぎず」がポイントだと感じました。みなさんも、自分の自由時間について考えてみてはいかがでしょうか?何かの参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
2024.10.06
コメント(0)
-
他人に期待しない方が幸せになれる?
こんにちは。今回は少し変わった視点から、人間関係の悩みを解消する方法についてお話しします。結論から言うと、他人に期待しないことをおすすめします。えっ?と思った方もいるかもしれません。でも、これが意外と効果的なんです。なぜ全ての悩みは人間関係の悩み?アドラーは「全ての悩みは対人関係の悩みである」と言いました。一見、人と関係ない悩みもあるように思えますよね。例えば…- 昇級したい- キャリアアップしたいでも、よく考えてみてください。昇級したいと思うのは、自分より年収が高い人がいるから。キャリアアップしたいのも、周りと比較して「もっとスキルが求められる仕事がしたい」と思うから。つまり、根底には必ず「人」が関わっているんです。私の人間関係の悩みが減った理由実は、私自身、3〜4年前と比べて人間関係の悩みがグッと減りました。その大きな理由の一つが、他人に期待することを頑張ってやめたことなんです。完全に期待しないのは無理です。でも、極力期待しないように心がけています。冷たく聞こえるかもしれませんが、意外とうまくいくんですよ。具体例:上司が冷たい場合例えば、上司が冷たくて厳しい。これが悩みだとしましょう。この悩みの根底には、「上司はもっと温かく接してほしい」「優しくしてほしい」という期待がありますよね。その期待が満たされないから悩むわけです。ここで、期待をしないようにすると…「まあ、そういうもんか」と割り切れるようになるんです。親子関係でも同じことこれは職場だけでなく、親子関係にも当てはまります。例えば、子供が勉強しない、成績が下がる、口を聞いてくれない…。親としては悩みますよね。でも、これも親の期待が満たされないから悩むんです。「もっと勉強してほしい」「成績を上げてほしい」「話をしてほしい」…こういう期待があるから悩むんです。ここで、「まあ、そんなもんか」と受け入れられれば、悩みは減るんです。「でも、親が期待しないで誰が期待するの?」そう思う方もいるでしょう。確かにその通りです。親だからこそ子供に期待するし、だから熱心に関わるんですよね。でも、私が学習塾で見てきた多くの家庭では、**期待しすぎ**なんです。それが子供の重圧になっている。「もっと勉強しろ」「いい大学に行け」…こういう期待が子供にのしかかっている。だから高い塾代も払うわけです。期待は確かに活力になりますが、同時に重荷にもなるんです。注意:期待しない≠愛していないここで誤解しないでほしいのは、他人に期待しないことは愛していないことではありません。私の考えでは、愛とは存在そのものを受け入れること。愛おしく思う感情です。一方、期待は行動や結果に対するものです。だから、子供に期待しないことが、愛していないことにはならないんです。まとめ人間関係をうまくやっていくコツの一つは、他人に期待しないこと。特に親子関係や職場の人間関係では、この考え方が効果的だと思います。みなさんも、ちょっと試してみませんか?案外、悩みが減るかもしれません。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日を!
2024.10.05
コメント(0)
-
満員電車に乗らなくていい幸せ。昼出勤のメリットを再確認した話
こんにちは。現在、学習塾で昼から夜まで勤務しているマモ~です。今回は、昼出勤のメリットについて、最近経験したエピソードを交えながらお話しします。昼出勤の最大のメリット昼出勤の最大のメリットは何といっても、満員電車に乗らなくていいことです。私は教室まで電車で通勤していますが、昼頃の電車は比較的空いています。ほぼ毎回座れるので、最寄り駅まで快適に移動できるのです。この快適さは、朝の満員電車を経験した人にしかわからない贅沢かもしれません。満員電車の恐ろしさを再確認先日、妻と娘が義理の両親とディズニーリゾートに行く際、空港まで見送りに行きました。その時、久しぶりに満員電車を経験したのです。朝の通勤・通学ラッシュの時間帯で、スーツケースを持っての移動だったこともあり、ここ最近経験したことのないほどの混雑に驚きました。体を押し付けられ、動くこともままならない状況に、昔の通勤時代を思い出してゾッとしました。この経験から、改めて昼出勤の素晴らしさを実感しました。以前の会社では毎日このような満員電車での通勤を余儀なくされていましたが、今思えば本当に大変だったんだなと感じます。心身ともに疲れる満員電車通勤から解放されたことで、仕事へのモチベーションも上がっているように思います。昼出勤のデメリットしかし、昼出勤にもデメリットがあることは認めざるを得ません。最も大きな問題は、平日夜のイベントに参加しづらいことです。例えば、私が参加しているスポーツサークルは夜8時以降に活動があります。多くの人は仕事後にサークル活動に参加できますが、私の場合はちょうど仕事の時間と重なってしまうのです。参加するには休暇を取る必要があり、spontaneous(衝動的)な社交の機会を逃してしまうことも少なくありません。まとめ昼出勤は一長一短ありますが、個人的には満員電車に乗らなくて済むメリットが大きいと感じています。朝のストレスフルな通勤から解放されることで、より充実した一日を過ごせるようになりました。皆さんはどう思いますか?通勤時の満員電車について、あなたの経験や感想をコメントで教えてください。働き方や通勤スタイルの違いが、日々の生活にどのような影響を与えているのか、みなさんと一緒に考えていけたら嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください!#昼出勤 #満員電車 #働き方 #通勤ライフ
2024.10.04
コメント(0)
-
幸せを感じる瞬間は年齢とともに変化する。だからこそ今を大切に。
こんにちは。今回は「幸せを感じる瞬間は年齢によって変わる」というテーマでお話しします。みなさんは、どんな時に幸せを感じますか?私の場合、年齢によって幸せだと感じる瞬間が変化してきました。振り返ってみると、おもしろいほど違いがあるんです。大学時代:オールナイトの青春大学生の頃は、友達とオールで遊ぶことが最高の幸せでした。朝まで飲み歩いたり、カラオケで熱唱したり、ボーリングで盛り上がったりしました。私は運動が好きだったので、友達とラウンドワンのスポッチャで朝までひたすら遊んだりもしていました。今思えば、体力の限界に挑戦するような日々でしたが、それがとにかく楽しかったんです。社会人1年目:同期との絆社会人になりたての頃は、同期との時間が何よりも幸せでした。仕事終わりに一緒に食事をしたり、飲み会で盛り上がったりする時間が本当に楽しかったですね。新しい環境で同じ境遇の仲間と過ごす時間は、かけがえのないものでした。恋愛期:二人の世界妻(当時は彼女)と出会ってからは、二人で過ごす時間すべてが幸せでした。一緒に飲みに行ったり、外食を楽しんだり、お互いの家でまったり過ごしたりする時間が何よりも幸せでした。恋する気持ちで胸がいっぱいだった時期ですね。結婚後:新しい形の幸せ結婚して同居を始めると、幸せの形がまた変わりました。もちろん妻と一緒に暮らす日常は幸せですが、同時に一人で本屋に行ったり、個人的な運動の時間を持ったりすることにも喜びを感じるようになりました。二人の時間も大切ですが、個人の時間の大切さも実感するようになったんです。現在:家族との穏やかな時間今は5歳の娘もいて、家族との時間が何よりも幸せです。日曜日に家族でのんびり過ごすことが特に幸せです。妻と娘がくつろいでいる様子を眺めているだけで「ああ、いいな、この瞬間」と思えるんです。それと同時に、一人で本を読んだりスポーツをしたりする時間も大切にしています。家族との時間と自分の時間のバランスが、今の私にとっての幸せなんです。仕事における幸せプライベートでの幸せは変化しましたが、仕事での幸せは昔も今も変わっていません。それは「自分の言動や行動で人が良い方向に向かい、成長に関われたと感じる時」です。これが私にとっての仕事での幸せです。コンビニ本部での経験新卒で入社したコンビニ本部では、新規オーナーさんや店長さんの成長を見守る機会がありました。最初は何も分からない状態から、日々の指導を通じて少しずつコンビニオーナーらしくなっていく姿を見守れることが、仕事のやりがいでした。特に印象に残っているのは、脱サラしてコンビニ経営を始める方々です。彼らは最初、アルバイトさんよりも経験が少ないんです。「こんなに仕事があるんですか」と驚く姿がよく見られました。でも、一つ一つ丁寧に指導していくと、1ヶ月、3ヶ月とたつにつれて、どんどん成長していくんです。最初は何もかもわからなかった人が、自分の指導した内容を理解して行動してくれる。その姿を見るのが本当に嬉しかったですね。現在の学習塾での経験今は学習塾で働いていますが、ここでも同じ喜びを感じています。半年前まで勉強に興味がなかった子が、人が変わったように勉強に打ち込む姿を見ると、本当に成長を感じます。特に小学5年生から中学2年生の間は成長期と言われる時期で、ものすごく成長するんです。そういった子どもたちの変化を見守れることが、今の仕事での幸せです。まとめ:今を大切にこのように、幸せを感じる瞬間は年齢やライフスタイルによって変わっていきます。でも、それぞれの時期にしか味わえない幸せがあるんです。今の私には、大学時代のようなオールナイトの遊びは苦痛でしかありません。体力が有り余っていた時代だからこそできたことなんですね。でも、当時はそれが最高の幸せだったんです。だからこそ、今あなたが幸せを感じていることは、思う存分楽しんでください。今感じている幸せが、いつまでも続くとは限りません。だからこそ、今この瞬間を大切に、幸せをかみしめてください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆さんにとって素敵な一日になりますように。
2024.10.03
コメント(0)
-
リモートワーク全盛時代に逆行?対面コミュニケーションこそ希少価値になる
こんにちは。今回は「対面でのコミュニケーションが希少に」というテーマでお話しします。リモートワークへの憧れと現実数年前、みなさんはリモートワークや好きな場所でいつでも働ける働き方に憧れませんでしたか?私は強く憧れていました。前職の人材会社では、コロナ禍の影響でリモートワークを経験。パソコンやスマホ一台で稼げる働き方に「かっこいいなぁ」と憧れを抱いていました。SNSを見ると、そんな働き方をしている人が多く、自分もそうなりたいと思っていたんです。変化した価値観しかし最近、その欲求が薄れてきました。理由は単純です。人と対面で話すのが楽しいと気づいたんです。今は富裕層向けの学習塾で働いていて、毎日通勤して現場で働いています。この経験から、リアルな対面でのコミュニケーションの方が良いという考えに至りました。未来の働き方と対面コミュニケーションの価値ここで、ふと考えたんです。リモートワークが主流になったら、対面でのコミュニケーション能力が下がるのではないか、と。ZoomやTeamsでのミーティングが当たり前になると、リアルで話す機会が減り、いざ対面となった時に戸惑う人が増えるかもしれません。そうなると、普段から対面でコミュニケーションを取っている人の方が、その能力が高くなり、むしろそれが強みになるのではないでしょうか。私の体験:コミュニケーション能力の衰え大学2年生の夏休み、私は約1ヶ月間ほとんど誰とも会わない生活を送りました。家族以外との会話はバイト先だけ。そんな生活の後、久しぶりにサークル活動に参加したんです。結果は散々でした。全然喋れない。どうコミュニケーションを取ればいいのか分からなくなっていたんです。この経験から、コミュニケーション能力は使わないと衰えると痛感しました。現在の仕事と対面コミュニケーション今の仕事では、毎日たくさんの人と対面で話します。生徒や親御さんとの面談、電話での会話、講師として10人近くの人と話し、生徒ともたくさん会話します。同僚とのコミュニケーションも含めると、かなりの量の対面コミュニケーションをこなしています。未来の仮説:対面コミュニケーション能力の希少価値化これらの経験から、一つの仮説を立てました。リモートワークが主流になればなるほど、対面でコミュニケーションを取れる人が少なくなるのではないか、と。そうなると、今の私の仕事のように対面でバリバリコミュニケーションが取れる人が希少になり、その能力こそが価値を持つようになるのではないでしょうか。完全な妄想仮説ですが、何かの参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
2024.10.02
コメント(0)
-

中学受験はゆるく!?塾講師が語る新提案
こんにちは。富裕層向けの学習塾に勤め、100組以上のご家庭の受験サポートをしてきたマモ~です。今回は「中学受験編・ゆる受験のすすめ」というテーマでお話しします。はじめにこの記事は、子供に中学受験をさせようか検討中の方、中学受験を決めて学習塾に通わせている親御さん、そして中学受験を控えた子供本人に読んでいただきたいと思います。中学受験、本当に必要?率直に申し上げると、私はほとんどのご家庭には中学受験は不要だと考えています。その理由は主に経済力の問題と子どもの主体性にあります。経済力の問題中学受験には莫大な費用がかかります。集団塾の月謝、長期休暇中の講習費、さらには個別指導塾の費用など、まるで課金ゲームのようです。うちの塾の費用はかなり高額ですが、多くの生徒は集団塾と掛け持ちで通っています。さらに、中学入学後も私立学校での生活や交友関係維持にお金がかかります。経済的な余裕がないのに無理して受験するのは得策ではありません。子どもの主体性また、子どもの主体性も重要な問題です。私の塾に通う生徒の中で、本当に主体的に中学受験に取り組んでいる子はごく一部です。多くは親のエゴによるものであり、特に医師家系に多く見られます。子どもは遊びたい盛りなので、勉強のフリをして遊んでいたり、自習室で遊んでいたりすることもざらにあります。やらされている勉強は身につかず、お金も時間も能力も無駄になってしまいます。ゆる受験のすすめそこで私が提案したいのが「ゆる受験」です。このアイデアは「RANGE」という本からヒントを得ました。RANGE(レンジ) 知識の「幅」が最強の武器になる [ デイビッド・エプスタイン ]この本では、早期専門特化よりも、様々な経験をしてから遅めに専門を決めた方が後々成功すると主張しています。なぜゆる受験か?現状では、多くの受験生が勉強漬けの毎日を送っています。しかし、11〜12歳という時期は成長期であり、多様な経験をすべき貴重な時間です。スポーツや芸術、趣味に打ち込む時間を確保することが重要です。これは将来への布石にもなります。スティーブ・ジョブズの言う「コネクティング・ザ・ドッツ」のように、多様な経験が将来思わぬところでつながる可能性があるのです。具体的な方法具体的には、勉強時間を絞り、余白を作ることをおすすめします。その時間でスポーツや芸術、趣味に打ち込んでほしいのです。中学受験は人生を決めるものではありません。経済力があり、子どもが主体的に取り組むなら、ゆるく受験するのが良いでしょう。最後にこの大切な成長期に、本当に勉強だけでいいのでしょうか?ぜひ考えてみてください。参考になれば幸いです。良い一日を!
2024.10.01
コメント(0)
-
コミュ力より笑顔?インタビュー体験から学んだこと
みなさん、こんにちは。今回は「コミュ力より笑顔」というテーマでお話しします。コミュニケーション能力の重要性コミュニケーション能力が重要なのは言うまでもありませんよね。私なりの定義を言うと:1. 相手の言わんとすることをきちんと理解する力2. 自分の伝えたいことを相手にわかるように話せる力これらをテキストや口頭でやるかの違いだと考えています。企業の新卒採用でも、コミュ力はトップ3に入る重要スキルです。堀江貴文氏も「人間がやることは最終的に遊びとコミュニケーション」と言っていますしね。AIの台頭とコミュニケーションの変化最近の生成AI台頭で、多くのスキルが陳腐化しています。デザインやプログラミングなど、AIに取って代わられつつあるスキルも多いです。そんな中、人間にしかできない「共感を伴うコミュニケーション」の重要性が増しています。弁護士の例面白い例が弁護士です。AIで真っ先に淘汰されると言われていましたが、実際は違うんです。- パラリーガル(過去の事例調査など)→減少- 弁護士→年収増加なぜか?弁護士の仕事の中心が「カウンセリングやコミュニケーション」にシフトしているからなんです。コミュ力の高い弁護士ほど仕事が増えているそうです。驚きのインタビュー体験ここまでの話を聞くと「やっぱりコミュ力大事!」と思いますよね。でも、最近のある体験で「コミュ力より笑顔じゃない?」と感じたんです。きっかけは、Zoomでのインタビュー。相手の方の笑顔が素晴らしくて、目を奪われました。私の苦手意識実は私、自分のことを話すのが苦手なんです。普段は聞き役に回ることが多いくらい。だからインタビューを受ける前は正直気が重かったんです。笑顔の力ところが、インタビュアーの方の笑顔に触れた途端、心を開くことができたんです。普段なら話さないようなことまで、どんどん話してしまいました。後で冷静に考えると、相手の質問力やコミュ力よりも、その素敵な笑顔に影響されたんじゃないかと。日常での気づきこの体験以外でも、「いいな、もっと一緒に仕事したい、もっと知りたい」と思う人って、共通して笑顔が素敵なんです。通勤電車を見渡しても、みんなムスッとしていませんか?(一人で笑顔でいるのは確かにちょっと怖いですけどね笑)笑顔の魅力考えてみると、笑顔が素晴らしい人には次のような特徴がありますよね:- 重宝される- 一緒に仕事したくなる- 信頼関係が築きやすい- もっと知りたいと思わせるまとめ:コミュ力vs笑顔コミュニケーション能力ももちろん大切です。でも、それ以上に「笑顔」を大事にした方がいいんじゃないか。そう感じた体験でした。みなさんはどう思いますか?コメントで教えてくださいね。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください!
2024.09.30
コメント(0)
-
夢がないのは当たり前!? 中高校生が将来の方向性を探る2つの方法
こんにちは。富裕層向け学習塾で講師をしているマモ~です。これまで100人以上の生徒さんと向き合ってきましたが、よく耳にする悩みがあります。「将来の夢がないんです...」「やりたいことが見つからなくて...」正直、この悩みを聞くたびに「そりゃそうだよな、当たり前じゃん」と思ってしまいます。なぜでしょうか?やりたいことが見つからないのは当然のこと私の塾に通う生徒さんの多くは、こんな生活を送っています:1. 勉強にめっちゃ時間を使う2. ちょっとだけ部活をする3. 少し友達と遊ぶ4. 電子機器で娯楽を楽しむこの生活リズムで、将来の夢につながるようなやりたいことが見つかるわけがありません。だから、「夢がない」「やりたいことがない」というのは、むしろ正常な状態なんです。でも、それでも方向性を探りたい人へただ、それでも何か将来の方向性を見つけたいという人もいるでしょう。そんな生徒さんに、私は2つのアドバイスをしています。これは自分の経験にも基づいているんですよ。1. 興味関心の輪を広げる勉強や部活以外にも、小さな興味ってあるはずです。例えば:- 恐竜- 薬- 運動- 音楽こういった興味を広げるために:- 恐竜が面白い → 博物館に行ってみる- 宇宙船に興味がある → 科学館に行ってみる時間がなくても30分〜1時間でいいんです。これまで触れてこなかったものに触れてみることをおすすめしています。2. 感情が動く瞬間を振り返るこれは良い自己分析の方法だと思います。人によって感情の動き方は全然違うんですよね。私の場合:- 生徒の成長を感じた時に嬉しくなる- 特定の人へのメールを書いている時に没頭するこんな風に、自分の感情が動く瞬間を探してみてください:- どんな時に嬉しい?- どんな時に悲しい?- どんな時にイラつく?- どんな時に満足感や充足感を得る?これらの共通項を見出すと、大まかな方向性が見えてくるかもしれません。最後に:焦らないで繰り返しますが、今やりたいことがないのは全然問題ありません。むしろ、それは当たり前のことなんです。ただ、それでも何か行動を起こしたい人は、上記の2つの方法を試してみてください。大学で学びたいことを決める時にも使えるかもしれません。実は、これは高校生だけでなく大人にも使える方法なんです。親御さんが試してみても面白いかもしれません。私自身も、この方法で興味関心を広げたり、やりたいことの方向性を見つけたりしています。自分の感情と向き合うことで「こういう時に感情が動くんだな、だったらこんな仕事が楽しいかも」という仮説を立てたりしているんです。焦らず、でも少しずつ行動してみる。それが将来の方向性を見つける一番の近道かもしれません。参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。#教育 #キャリア #自己分析 #塾講師の本音 #高校生の悩み
2024.09.28
コメント(0)
-
新しい習慣を始める前に、まず何かを"終わらせる"べき理由
こんにちは。今回は、人生をより良くするための習慣について、少し違った角度からお話しします。多くの人が「新しい習慣を始めよう」と考えますが、実は「何を終わらせるか」を先に考えた方がいいんです。なぜそう思うのか、私の経験も交えながら説明していきますね。新しい習慣は続かない?「英語の勉強を始めよう」「運動習慣をつけよう」...こんな風に思ったことありませんか?でも、数日経つとなかなか続かなくなってしまう。実は私も同じ経験をしています。最近始めた運動習慣は1ヶ月近く続いていますが、正直この先も続くかは分かりません。時間の壁新しい習慣を始めようとする時、多くの人は「何を始めるか」ばかりに注目しがちです。でも、その前に「何を終わらせるか、やめるか」を考えるべきなんです。これは私の独自の考えというより、Xで見かけた独立研究者の山口周さんのツイートがきっかけです。本当にその通りだと思いました。24時間の壁人間誰しも、1日24時間しかありません。偉大な経営者でも、私のようなポンコツでも同じです。仕事、家事、子育てと、みんな忙しいですよね。新しいことを始めようとしても、時間が足りない。だから、何かを削るしかないんです。習慣が身につかない最大の理由私は、習慣が身につかない最大の理由は「時間の確保」だと考えています。だからこそ、まず不要なものを削る、やめる、終わらせるというアプローチが大切なんです。自分を俯瞰してみる「時間が作れない」と感じているあなたにこそ、自分を客観的に見てほしいんです。「この時間、本当に必要?」「これやってる意味あるのかな」と思う瞬間、ありませんか?SNS閲覧時間を削る私の場合、最も効果があったのはSNSの閲覧時間を減らすことでした。今では1日15分程度、時には全く見ない日もあります。基本的にXだけを見て、それも特定の人のツイートに限定しています。昔は「あっという間に30分経過」なんてことがザラにありました。でも、結局何も得られていなかったんです。むしろ、成功している人と自分を比較してテンションが下がることも...。飲み会参加をやめる私の場合、幸いシフト制の仕事なので飲み会に誘われる機会は少ないですが、以前の仕事では頻繁にありました。でも、途中で参加をやめました。理由は単純、あまり意味を感じなくなったからです。驚くべきことに、参加をやめても職場の人間関係は悪くなりませんでした。むしろ「あいつはそういうキャラ」と受け入れられ、良い結果になりました。時間の使い方を見直す1日24時間、睡眠8時間、仕事8-10時間...残りは6-8時間しかありません。全ての良い習慣を始めることは不可能なんです。だからこそ、「何をやらないか、削るか、終わらせるか」を考えることが重要です。「この時間本当に必要?」「この活動は自分を充実させてくれる?」こんな疑問を持つことで、何を削るべきか見えてくるはずです。おわりに新しい習慣を始める前に、まず不要なものを終わらせる。この考え方が、あなたの人生をより充実したものにするヒントになれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください!
2024.09.27
コメント(0)
-
「自分らしさ」なんて幻想?むしろ変わり続けることが大切。
こんにちは。今回は「自分らしさって変わるよね」というテーマでお話しします。よく「自分らしく働こう」というようなキラキラメッセージを目にしますよね。実は、過去の私もこの「自分らしく働く」とか「自分らしく生きる」ということにすごく魅力を感じていた時期がありました。でも今となっては、ちょっと違う考えを持つようになりました。そもそも自分らしさって常に変わっていくものじゃないですか?だとしたら、「自分らしく生きていこう」とか「自分らしく働こう」って言っても、最後までそれができているのかどうかわからないんじゃないの?って思うようになったんです。自分らしさを構成する4つの要素自分らしさを構成する要素って何だろう?と考えてみました。(実は生成AIにも聞いてみたんですけどね笑)そうしたら、大きく4つのことが浮かびました:1. 価値観2. 自己認識3. 好きなこと4. 得意なことあ、嫌いなことも含めてもいいかもしれませんね。でもね、これらってどれも変わっていくんですよ。嫌いなことは比較的安定しているかもしれませんが、他の4つはどんどん変わっていきます。価値観の変化例えば、私の価値観。社会人3年目くらいまでは、組織の中で出世することが「善」だと思っていました。肩書きを持って組織内で働くことが、より良い社会人だと考えていたんです。でも、起業家や有名な実業家の本を読むうちに、「いやいや、全然違うじゃん!」って思うようになりました。組織で出世するよりも、自分のスキルや得意を活かして働き、価値を提供する。副業や起業で成果を出す方がよっぽどいいんじゃない?って。組織での出世に何の意味があるの?ってくらいに考えが変わっちゃいました。自己認識の変化自己認識も変わります。これは「自分はこういう人間だ」というセルフイメージのことですね。私の例を挙げると、3年前くらいまでは「自分は内向型の性格だから、一人で黙々と働くのが性に合っている」と思っていました。デスクワークでパソコンとにらめっこして、ただ一人で黙々とやる。そんな仕事の方が自分に合っているって信じ込んでいたんです。ところが最近、全然違うぞって強く思うようになりました。今の仕事は、その「黙々一人で作業する」という仕事の真逆なんです。いろんな人と会話をして仕事を進める。なのに、これが意外と性に合っているし、むしろ楽しいんですよ。自己認識ってこんなにガラッと変わるんだなって実感しました。好きなことと得意なことの変化好きなことも変わります。例えば、今までキャンプをやったことがなかった人が、友達に誘われてキャンプに行ってみたら、めちゃくちゃ楽しくて、そこからキャンプにドハマりした...なんてこともありますよね。得意なことも環境によって変わります。私の例で言うと、前の会社では事務作業が本当にダメダメでした。周りの人たちがすごすぎて、自分の事務能力の低さを痛感していました。でも、そこで鍛えられて、人並みにはできるようになりました。そして今の会社に転職したら、なんと事務作業がめちゃくちゃできる方になっちゃったんです。他の人より早くできてしまうので、事務系の仕事をどんどん任されるようになりました。前の会社で苦手だった事務作業が、今の会社では得意なことになっちゃったんです。得意不得意って、周りとの相対的な比較で決まるんですよね。だから、場所によって変わるんです。例えば、「自分はマーケティングが得意だ」と思っても、マーケターだらけの世界に入ったら平凡だったり。逆に、マーケティングの知識や経験がゼロの職場に行けば、その人はマーケティングのエキスパートになれる。結論:自分らしさは幻想?つまり何が言いたいかというと、自分らしさはこれだけ変わるものなんです。だから「自分らしく生きていこう」「自分らしく働こう」と言っても、変わり続けるものを目指しても、ゴールには辿り着けないんじゃないでしょうか。私は「自分らしく働こう」「自分らしく生きよう」というのは幻想なんじゃないかと思うんです。それよりも大切なのは、今やっていて楽しいこと、嬉しいこと、満足することを追い続けること。今を生きることが大切なんじゃないでしょうか。今楽しいと思っていることが、5年後も楽しいと思えるかどうかは誰にもわかりません。だからこそ、今楽しいと思うこと、やっていて幸せを感じること、充実感を得られることに溢れた生活を送る。それが結局のところ、自分らしさというか、幸せな人生に直結するんじゃないかなと思うんです。いかがでしたか?この話が少しでも参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、良い一日をお過ごしください!
2024.09.26
コメント(0)
-
劣等感を抱くのは悪くない。むしろ大いに結構だ。
こんにちは。最近、市民体育館のトレーニングジムに通い始めました。週2、3回のペースで筋トレにハマっています。そこで毎回感じることがあります。それは「劣等感」です。筋トレと劣等感ジムに行くたびに、周りの人たちの筋肉の凄さに圧倒されます。- ものすごく重そうなベンチプレスを軽々と持ち上げる人- 腕の太さが自分の2倍はありそうな人これらを目にするたび、「自分ってなんてひ弱な体をしているんだろう。筋肉ないなぁ、小さいなぁ」と思わずにはいられません。劣等感は力になるでも、この劣等感を抱くこと自体は悪くないと思っています。むしろ、それが力に変わるんです。1. 「周りすごいな、ちょっと自分も負けずに頑張ろう」というモチベーションになる2. 筋肉ムキムキになった未来の自分を想像できる3. 「もっと追い込んでみようかな」という意欲が湧いてくるつまり、劣等感は自分のエネルギー源になるんです。劣等感と劣等コンプレックスの違いただし、注意点があります。劣等感をこじらせると「劣等コンプレックス」になってしまいます。劣等感- 自分が他人より劣っていると感じる感情- ちゃんと向き合って力に変えられる劣等コンプレックス- 「自分は劣っているからもうダメだ」と塞ぎ込む状態- 「どうせやっても無駄」「やっぱり自分はダメ」と自分を卑下する- 頑張らなくなる、言い訳に使うさらに悪化すると「優越コンプレックス」に発展することも。これは自分を過度に自慢し始める状態です。劣等感との向き合い方劣等感を劣等コンプレックスに変えないために、日々の思考や行動が大切です。- 「どうせダメだ」と思わない- 劣等感とどう向き合い、力に変えるかを考える今の筋トレでは、劣等感を力に変えられている感覚があります。これは良い状態だと思います。これからの目標筋トレへの意欲は高まっていますが、怪我のリスクも考えて計画的に取り組みたいと思います。- 適切な休養日を設ける- 筋トレだけでなく、有酸素運動も取り入れる劣等感を感じることは決して悪いことではありません。それをどう活かすかが重要なんです。あなたも、日々感じる劣等感とうまく付き合って、前向きなエネルギーに変えてみてはいかがでしょうか。最後までお読みいただき、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
2024.09.25
コメント(0)
-
子育ては「させない」を決めろ!?学習塾スタッフが語ってはいけない教育論
こんにちは。現在、富裕層向け学習塾で働いているマモ~です。親御さん、生徒さん、そして指導講師の間に立つ立場から、今日は子育てについて、ちょっと変わった視点からお話しします。はじめに最近、Voicyで尾石晴さんのお話を聞いて、「なるほど!」と思ったことがあります。それは「子供の教育は何をさせるかより、何をさせないかが大事」というものです。なぜ「させない」が大事なの?多くの親が悩むのは、「子供に何をさせるべきか」ということ。でも、実はそれを逆転させた方がいいんです。理由は主に3つ。1. お金の制約2. 時間の制約3. 子供のキャパシティお金の制約正直、全部はできないんですよね。中学受験のための塾、スポーツ、音楽...全部やらせようと思ったら、お財布がパンクしちゃいます。時間の制約子供の1日は24時間。そのうち学校に行ってる時間を引いたら、残りはわずか。土日も含めて、習い事や友達付き合い、家族との時間...全部詰め込むのは至難の業です。子供のキャパシティこれが一番大事。富裕層の家庭を見てきて思うのは、お金があるからといって全部やらせるのは逆効果だということ。子供がキャパオーバーになっちゃうんです。「させない」を決めるコツ人間って面白いもので、「これをしたい」より「これはしたくない」という気持ちの方が強いんです。だから、「させない」を決めれば、自然と「させる」ことが見えてくる。大きく分けると、子供の習い事は3つ。1. 学習塾(中学受験など)2. スポーツ3. 芸術(音楽、絵画など)この中から、「絶対にさせないもの」を決めるんです。私の場合:学習塾はNG実は私、学習塾で働いているのに、自分の子供には絶対に塾に行かせたくないんです。なぜか?1. 10代の貴重な時間を、好きでもないことに使わせたくない2. 子供の興味や関心を育てたい3. AIの台頭で、受験勉強の意義が薄れてきている特に最後の点。5年後、10年後を考えると、従来の受験教育って意味あるのかな?って思うんです。日々、親御さんや生徒さんと接する中で、このジレンマを強く感じています。我が家の選択うちの娘(5歳)の場合、音楽(ピアノ)や絵画はちょっと違うかな。でも、スポーツ系、特にダンスや歌が好きそう。今は体操をしていて、楽しそうです。最後にもちろん、最終的には子供の意思が一番大事。でも、親としての方針は持っておいた方がいいと思うんです。あなたも、「させない」を決めることから始めてみませんか?意外と子育てが楽になるかもしれませんよ。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。良い一日を!
2024.09.24
コメント(0)
全89件 (89件中 1-50件目)










