全2277件 (2277件中 1-50件目)
-

あの感動をもう一度
諏訪市出身の伊藤千代子さんの生涯を描いた「わが青春つきるとも」の再上映を字幕つきで9月23日(月・振替休日)の午後2時から諏訪市文化センターで行うことになりました。今日、記者会見をさせていただきました。不肖、私が実行委員長をつとめさせていただきます。一度視たからという方もぜひ字幕つきでじっくりご覧下さい。
2024年07月18日
-

軽井沢町の日本型ライドシェアの視察
おはようございます。大変な雨になっています。災害がおきませんように。昨日の総務企画警察委員会の最後は軽井沢町が県下で先行実施している「日本型ライドシェア」について伺ってきました。軽井沢は年間800万人の観光客が訪れる観光の町でオーバーツーリズムも問題になっています。世帯数16000余にたいし、別荘16000戸と一大避暑地でもあります。タクシー事業者は5社営業していますが、繁忙期は全く足りず移動難民がでる状況の中、タクシー会社が隙間時間を利用して働くドライバーを時間給で雇い運行するというもの。運転手は2種免許がなくても2年間無事故で過去に免停処分のないひとを本業との関係で一次スクリーニングをかけて採用するとのこと。応募435名に対し、採用14名。9名面接中だそうです。支払いはすべてキャッシュレス。車にはライドシェアのマークをつけて、動かすのはタクシー会社の車。5月から運行開始したばかりで日が浅いなかですが、課題は閑散期と繁忙期の調整が難しいこと、ドライバーの希望に沿う働き方を確保することが難しいことだそうです。今後とも安全安心が担保できるのか注視していきたいとおもいます。
2024年07月11日
-
宿泊税調査で福岡県へ
県として宿泊税を導入しているところは東京、大阪、福岡ですが、長野県も検討しているため、福岡県の状況を調査。福岡県では宿泊に対し一律一泊200円を徴収していますが、福岡市と北九州市も独自に徴収しています。両市に対し、県への納入は50円としていますが、お互いに話し合い調整するなかで、総務省も入って決めたそうです。長野県でも阿智村と白馬村が独自の税を徴収する方向でいるため、そこをどうやって決めていくのか知りたいと思っていたのでよくわかりました。税導入の宿泊への影響は令和2年より実施していますが、あまり明確にはならないようです。いずれにせよ法定外目的税のため、使途を明確にすること、県下の全ての自治体に宿泊8、日帰り2で配分し、使い方は方針に沿って柔軟にやっており、1年間で使い残したお金は基金として積み立て3年間有効との事でした。聞いてみなければわからないこともあり、たいへん有意義でしたが、長野県としての導入の是非などについて、慎重な検討が必要だと思いました。
2024年05月27日
-

2月議会委員会で質問
議会は常任委員会が続いています。6日は産業労働部、7日は観光部、今日8日は企業局と3日間連続で質問させていただいています。産業労働部では〇伝統的工芸品産業支援〇航空機産業と軍事利用〇男女の賃金格差の是正について。観光部では〇宿泊税について〇オーバーツーリズムについてうかがいました。今日は水道事業の危機対応、マイクログリッドについて質問するため準備をしています。宿舎のボイラーの調子が悪く、入浴中にお湯がでなくなりブルブル。緊張の日々を控え室の花が癒してくれています。
2024年03月08日
-

特別支援学校の給食室の拡充、専門性ある年度任用職員の正規化をと一般質問
【毛利栄子議員】 特別支援教育について教育長に伺います。 党県議団は、この間幾度となく、特別支援教育の環境改善について本会議や委員会で取り上げてきました。 松本養護学校、若槻養護学校の改築が始まること、千曲川の浸水域にある上田養護学校の移転改築に向けて具体的に検討していただいていること等を歓迎します。また、図書室や蔵書も不十分で図書スペース程度しか確保されていない学校があり、子供たちが楽しみにしているのに大変残念な事態だと思っておりました。特別支援学校の図書室が改善され、蔵書も拡充されることに期待しています。少子化の中にあっても、特別支援学校の児童生徒は増え続けており、慢性的に教室が不足している状況で、必要に迫られて教室の増設をしていただいているところです。 県教委としては、中長期的な視点に立った改築と応急的な対応として、増築、施設整備の修繕改修等を10年間計画で取り組んでいくとしていますが、根本的な解決のためには、改修、新設のスピードアップが必要と考えます。現状で不足している教室数はどのくらいあるのか。改善に向けてどのように取り組んでいくのか伺います。【内堀教育長】 御質問を頂戴いたしました。特別支援教育についてのお尋ねでございます。 特別支援学校の教室不足の現状認識と改善に向けた取組についてでございます。 県立特別支援学校の児童生徒数は、平成元年度に1,591人であったものが、令和5年度には2,588人と、少子化の中にあって約1.6倍に増加し、文部科学省令和3年度公立特別支援学校における教室不足調査においては、狭隘な教室も含め67教室の不足が見られたところです。 県教育委員会では、特別支援学校の狭隘化や老朽化への対応は極めて重要との認識の下、中長期的な視点から、建物の老朽化や狭隘化等を踏まえた改築等の環境整備を行うこととしており、現在松本養護学校と若槻養護学校で取り組むとともに、上田養護学校においては、施設の移転も含めた対応の検討に今後着手してまいります。 一方、急な児童生徒数の増加に対しては増築で応急的に対応することとしており、現在5校で34教室の増築を行っているところです。 今後も児童生徒数の将来推計や学校の現状把握をより丁寧に行った上で、中長期的な視点に立った改築等と応急的な視点に立った増築等の適切な組合わせにより、必要となる教室の確保に取り組み、学びの場の保障を行ってまいります。【毛利栄子議員】 児童生徒が増えることによって、学校内の施設設備が足りなくなってきている課題が様々あります。昨年共産党県議団で上田養護学校を視察した際に、児童生徒の増加によって、児童生徒・教員分全員の給食を提供するための給食調理施設設備がキャパを超えてしまい、教員の一部は弁当を持参しているとお聞きいたしました。稲荷山養護学校でも同じように給食調理施設が手狭になっており、一部の教員への給食提供ができないと聞いています。 山積する特別支援学校の施設整備。中でも、調理設備施設が拡張できず児童生徒と教員へ給食提供がされていない学校はどのくらいあるのか、お聞きいたします。給食は大事な食育の一環です。児童生徒と教員全員分の給食が提供できる調理設備施設にすべきと思います。教育長に改善に向けた取組をお聞きします。【内堀教育長】 特別支援学校の児童生徒等への給食の提供状況と改善策についてのお尋ねでございます。 担任が子供と同じ給食を取ることは、食事の指導や食育を行う上で大切であることから、年々増加する児童生徒数とそれに伴う教員数の増加に対応するため、これまで厨房の拡張工事や改修工事等を行い、児童生徒と教員への給食の提供に努めてまいりました。 このような中、本年度児童生徒については、もともと給食を提供していない学校や、アレルギーを理由に自ら昼食を持参するなどの場合を除き、全員に給食を提供できておりますが、教員については4校で一部提供できてない状況であります。 今後も児童生徒数や教員数の将来推計を丁寧に行った上で、必要な給食数を提供できるよう、将来を見通して計画的に厨房の拡張等を行うほか、給食の製造機器の大型化や、調理するラインの工夫等も行ってまいります。通級指導教室について【毛利栄子議員】 次に通級指導教室について伺います。 通級指導の場合は特別支援学級と違い、通常学級に在籍して、通常授業のほかに一部の授業を別の教室で受けることで、障がいによる困難を解消できるよう、子供の特性に合わせて、担任の先生と通級の指導教員と連携して、教育支援計画、指導計画を作成して、丁寧な指導がされています。発達障がいなど子供の持つ力を伸ばす適切な学びの場になっていると思います。特別な教育的支援を必要とする児童生徒の学びを充実するため、小中学校の通級指導教室を来年度も増設していくと提案されたことを歓迎します。 通級指導教室の設置は、毎年度増やし続けていただいています。この間の設置数の推移と来年度の増設数についてお聞きします。【内堀教育長】 通級指導教室についての御質問でございます。初めに通級指導教室の設置数の推移と来年度の増設数についてのお尋ねでございます。 通常の学級で学びながら、一部個々の教育的ニーズに応じた学習を別の教室で行う通級指導教室につきましては、平成28年度に75教室であったものを、本年度は156教室とし、さらに来年度は18教室増設して174教室とする予定であります。【毛利栄子議員】 通級指導に当たっていただく教員は、専門性と経験が必要になります。そのための教員を今後も増員する必要があります。どのように進めていくのでしょうか。また、通常学級で学びながら、一部の授業を別の教室で受けるためには必要な教室を確保しなければなりません。どのように確保していくのかお聞きいたします。【内堀教育長】 通級指導教室の増設に当たって、教員等教室の確保についてのお尋ねでございます。 通級指導教室の担当教員につきましては、障がいの理解や指導方法など、特別支援教育に関する高い専門性が求められます。このため、通級指導教室の担当教員に対する各種研修会の実施や、小中学校と特別支援学校間の人事交流、さらには、担当教員を複数配置してOJTによる資質向上を図る取組等により、担当教員の専門性向上に加え、担当できる教員の確保に努めてまいりました。 また、新たな教室の確保につきましては、児童生徒数が減少傾向にある中、小中学校の設置者である市町村教育委員会において、空き教室等の活用により確保していただいているところであります。 今後も市町村教育委員会等と連携しながら、通級指導教室で学ぶ児童生徒の教育的ニーズに応じた支援が十分に行えるよう取り組んでまいります。【毛利栄子議員】 小中学校で通級指導教室で支援と教育を受け、高校受験を経て高校に入学をする生徒においても、個別に特別な支援が必要な生徒に対しては手だてが講じられる必要があります。高校における通級指導教室は様々な検討を経て、2018年度から制度が運用開始となりました。長野県では、高校の通級指導教室は中信、東信、南信に設置されています。いまだに設置されていない北信については今後どう対応していくのか。以上、教育長に伺います。【内堀教育長】 高校の通級指導教室が未設置である北信地域への対応についてのお尋ねでございます。 県立高校への通級指導教室は、平成30年度に国で制度化されると同時に、箕輪進修高校と東御清翔高校に設置し、令和2年度には松本筑摩高校に設置しましたが、議員御指摘のとおり、北信地域は未設置となっております。 このため、北信地域の高校に対しましては、本年度新たに、長野養護学校へ高校を巡回する専任教員を配置して、相談支援等の強化を図っているところです。今後は、県教育委員会、高校、外部関係機関等を構成員として、今年度設置した高校における特別支援教育の在り方検討ワーキンググループにおいて、通級指導教室の機能充実に関する検討を行う中で、高校再編の動向も踏まえ、北信地域への設置についても検討してまいります。 以上でございます。【毛利栄子議員】 稲荷山養護学校では、新年度は児童生徒増もあり、何と100食も足りなくなるのではないかと言われています。子供たちと同じものを食しながら、あれがおいしかったね、これはどんな栄養があるんだなどと共感を持って話ができることは、教育効果を一層高めるものと期待します。一日も早く全員給食できる体制を構築していただきたいことを願って、次の質問に移ります。会計年度任用職員の任用について【毛利栄子議員】 会計年度任用職員の任用について、総務部長に伺います。 会計年度任用職員は、給与の面では、時給単価の引上げ、期末・勤勉手当の支給等によって、令和6年度から一定の改善が図られます。しかし依然として低賃金であり、雇用は1年ごとの契約で不安定であることに変わりはありません。 会計年度任用職員制度の運用では、国は公募によらない再度の任用の上限回数を2回とし、3年目は公募による採用をする、いわゆる公募による雇いどめが3年目の壁と問題になりました。 一方長野県では、公募によらない再度の任用の上限回数を4回にすることで、5年継続の雇用を可能にしてきました。来年度が5年目になります。県の5年目の壁を、どのように認識しているのか伺います。またどう対応するのか、お伺いいたします。【玉井総務部長】 ご質問をいただきました。 公募によらない任用条件である5年目の壁に対する認識についてでございますが、本県における会計年度任用職員の任用の取扱いでは、原則として同一の業務に従事する会計年度任用職員は公募によらず、年度単位で5年間の任用が可能でございます。 総務省の事務処理マニュアルでは、会計年度任用職員の任用に当たっては、できる限り広く募集を行うなど、適切な募集を行った上で、客観的な能力実証を行うこと。また、地方公務員法第13条の平等取扱いの原則を踏まえ、年齢や性別にかかわりなく均等な機会を与えることとしており、本県ではこうした趣旨を踏まえ、その職を希望する方々に広く門戸を開くこと、業務の円滑な執行という二つの観点からこうした設定としており、法の趣旨等から適切に対応しているものと認識をしております。 また、どのように対応するのかというお尋ねでございますけれども、地方公務員法の趣旨にのっとり、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。 また、5年の任用上限を超えて同一の者が同一の職務内容の職に応募することは妨げられておらず、その職は公募による公正な能力実証の結果、再度任用されることも可能でございます。【毛利栄子議員】 会計年度任用職員の果たしている役割は、消費生活相談員について言えば、現場では上司の正規職員に消費生活相談員の資格はなく、専ら資格を持つ会計年度任用職員の相談員が、買物や契約のトラブルを抱えた相談者に、法律に基づき丁寧な助言をしています。また、業者との間に立って解決を促すあっせんには、1〜3か月とかなりの時間を要する場合もあり、御苦労いただいています。 過日の信毎でも、資格さえあればできる仕事じゃない。簡単に人を切っていいんでしょうか。専門職が大事にされない現状は、行政のサービスの質を落とす形で市民のためにもならないと、県内の自治体の消費生活相談員が本音を語っていることが報道されました。県においても同様ではないでしょうか。まさに県民益を損ねることにつながると思います。 第3次長野県消費生活基本計画では、県消費生活センターの機能強化、住民に最も身近な市町村消費生活相談体制の支援強化、適格消費者団体など関係団体等との連携強化を推進すること等が言われています。消費生活相談員は国家資格を有し、多様化、複雑化する消費生活問題に対し、適切な助言、情報提供を行えるよう、研修もしながら蓄積した知識を持っています。さらに日々の相談活動による経験は、容易に得られるものではありません。きちんとした評価をすべきではないでしょうか。 2022年5月、売春防止法から66年を経てようやく新たな女性支援の枠組みを構築する根拠法、女性支援新法、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立し、4月の施行が目前に迫っています。 県としても基本計画の策定が義務化され、ただいま策定中です。女性相談支援センターの設置の体制強化を図っていくことになり、今議会にも関連の条例案が提案されています。 複雑多様な問題を抱える女性の被害からの心身の回復、生活再建ができるよう、女性相談支援員は、当事者を主体とした各種サービスのコーディネートや同行支援、女性自立支援施設等の利用の調整を行うなど、専門的な知識、経験を生かしながら、被害回復支援、日常生活回復支援、同伴児童への支援、さらにアフターケア支援、支援調整会議等々、多岐にわたる継続的で重要な役割を果たすことが求められています。 現行の女性相談員がその役目を担うことになろうかと思いますが、現在はそのほとんどが非正規です。このように採用時に資格が必要であったり、高度な専門性を有している生活相談員や女性相談員は、会計年度任用職員ではなく正規職員として採用するべきと考えます。総務部長に伺います。【玉井総務部長】 資格や専門性を有する会計年度任用職員の正規化についてでございます。会計年度任用職員については、総務省の事務処理マニュアルでは、常時勤務を要する職に従事する業務の性質に関する要件、すなわち、相当の期間任用される職員を就ける業務に従事する職であること、また、勤務条件に関する条件として、フルタイム勤務とすべき標準的な業務量がある職であることのいずれの要件を満たす職と定め、その要件に合致しない職を非常勤の職として明確に区分してございます。これに基づき本県においてはこれまで担ってきた業務内容や業務量を精査した上で、常勤職員・非常勤職員の区分を行っております。 一方で、県民のニーズや社会を取り巻く状況の変化に合わせまして、雇用形態を柔軟に見直していくことも重要であると認識しており、今後必要に応じまして、県民サービスの向上につながる最適な雇用形態について見直しをしてまいりたいと考えております。 以上でございます。環境保全研究所・安茂里庁舎について【毛利栄子議員】 環境保全研究所安茂里庁舎について環境部長に伺います。 環境保全研究所安茂里庁舎は、安全・安心な生活環境と県民の健康を守るため、県行政を科学的見地から支える中核拠点でありながら、本館は築56年、別館は築50年で老朽化し、大規模地震発生時には災害拠点施設としての役割を十分発揮できないという課題があることは、これまで何回も指摘してきました。移転・改修といった建物の在り方の検討と併せ、環境、健康福祉、総務の3部局による組織の在り方についても検討がなされてきたところです。 いよいよ新年度には諏訪湖環境研究センターが開所されることになり、現在の安茂里庁舎で扱っている水質部門などの業務が諏訪へ移ることになります。安茂里庁舎で継続して行う業務は一定少なくなり、庁舎内の狭隘な状況は若干改善されますが、老朽化が進む安茂里庁舎の今後はどのようになるのか。組織の在り方の検討と併せて環境部長に伺います。【諏訪環境部長】 環境保全研究所安茂里庁舎を今後どうするのか、それから研究所の組織の在り方の検討状況はどうかとの御質問でございます。 議員御指摘のとおり、安茂里庁舎は建設から50年余が経過して老朽化が進んでおり早急な対応が必要であることから、関係部局とともに検討を進めているところでございます。建て替えや既存施設の活用など、様々な方法が考えられますが、その規模や設備場所の検討に当たっては、まず近年の社会情勢の変化などを踏まえて、研究所の機能や体制の具体的な方向性を決定する必要がございます。 特に新型コロナ感染症対策の教訓を踏まえ、現在、健康福祉部が策定中の第3期信州保健医療総合計画では、研究所の機能や役割の充実について触れるなど、新興感染症の発生に備えた検査体制等について必要な検討を進めているところでございます。 この4月に研究所の一部機能を移管した諏訪湖環境研究センターを開設することも踏まえ、飯綱庁舎も含めた研究所の組織の在り方と庁舎についての検討を一体的に進め、早期に方向性を出せるよう鋭意努めてまいります。【毛利栄子議員】 DVであったり、性被害に遭ったり、また貧困状態であったりと、過酷な状況に置かれた女性を最前線で支える高度な知識と専門性を持った職員が、雇い止めの不安にさらされながら、官製ワーキングプア状態の会計年度任用職員の身分のまま対応するのは、あまりにひど過ぎるのではないかと思います。また、担っていただいているのは圧倒的に女性の職員の方々です。誇りとやりがいを持って従事できるよう、正規職員での任用を切に求めて一般質問を終わります。
2024年02月28日
-

JAXAの研究 日進月歩
県議会産業観光企業委員会の2日目の視察はJAXA筑波宇宙センターへ。センターでは人工衛星を活用した地球観測や災害監視、通信や放送。世界15ヵ国の国際協力で建設された宇宙ステーション「きぼう」の運用や利用、ロケット輸送システムの開発など最先端分野の開発・研究・試験などを主に行っています。展示館で実物や模型をみながら説明をうけましたが、開設以来50年、ロケットひとつとっても20cmほどのペンシル型から全長50メートルのH2まで飛躍的に進んできたことが驚きでした。宇宙服の展示もありましたが120キロもの重さがあり無重力でなければとても着られないとのことです。毎年世界で1800基ものロケットが打ち上げられており、宇宙ゴミも深刻化するなか、回収の研究もされています。近年、安全保障目的も含めた役割を負う方向にもなってきていますが、宇宙戦争に利用されないか気になります。
2023年11月01日
-

長野県のアンテナショップ 銀座NAGANOへ
県議会産業観光企業委員会の県外調査。午後一は長野県東京事務所と銀座NAGANOの調査。銀座NAGANOは28日〜29日に開店9周年の感謝祭を終えたばかり。2階のイベントスペースでは栗ご飯と飯山の坂井芋を使ったおやきの体験が行われており20人くらいの女性の皆さんがウキウキ楽しそうに調理中。1階の販売スペースも大にぎわい。長野の発信拠点として頑張っていることがわかりました。来店者に真っ先目に飛び込んできたのがリンゴアート。アルクマくんも見事!長野の売りのりんご、ぶどう、野菜が迎えます。岡谷の人気お菓子「クルミやまびこ」もありました。
2023年10月31日
-
CIC Tokyo調査 規模の大きさにカルチャーショック
東京虎ノ門にある「CIC Tokyo」を視察するということではじめは何の会社?と思いましたが、今日議会委員会で視察させていただき、世界を視野にグローバルな起業支援を行っている会社であることを知り、取り組みの大きさが半端ではないことにカルチャーショック。CICはケンブリッジ・イノベーション・センターの略でアメリカの不動産サービス企業。虎ノ門ヒルズビジネスタワーの15〜16階を借りて280社2000人がサポートを受けながら新たなイノベーションに挑戦しています。東京都も一角を構えていましたが、福岡県、静岡県、宇都宮市なども入居し、起業に必要だということで金融機関や弁理士法人、弁護士事務所、監査法人なども入居していました。世界とも繋がるとのことで、説明にあたった女性は「あら、今日は日本にいたの?」というくらい、バイリンガルで各国を飛び回っているようです。コワーキングスペースなどを利用されている皆さんは若い方々が多く、半分は女性。あらたな事業をおこすためには、利用者同士のコミュニケーションが大事だとのことで誕生会やスポーツ大会など様々なイベントも実施しているそうです。
2023年10月31日
-

9月議会一般質問をおこないました
長野県ゼロカーボン戦略の推進について【毛利栄子議員】 長野県ゼロカーボン戦略の推進について、環境部長並びに産業労働部長に伺います。 7月後半以降の記録的な猛暑について、気象庁の異常気象分析検討会は、今年の夏の平均気温は1898年統計開始以降の125年間で最高との見通しを示しました。8月10日には石川県小松市で最高気温40度、上田市では8月18日に38.4度を記録。長野市では7月16日以降53日間にわたり連続30度以上の真夏日で、過去最長を記録しました。 国連のグテーレス事務総長は、地球温暖化どころか「地球沸騰化の時代」「人類は地獄の門を開けた」と警告しています。気候危機と呼ぶべき非常事態になっていることを、長野県民もまざまざと認識せざるを得ない夏になったと思います。 猛暑ばかりではなく、干ばつや異常な豪雨、洪水、森林火災、台風なども起こっており、CO2削減に真剣に向き合わなければ、人類と地球環境は破局的な事態に陥ってしまうのではないかと危惧されます。 国連の気候変動に対する政府間パネルIPCCは、今年3月、世界の平均気温は産業革命前から1.1度上昇していると公表し、このままでは1.5度に抑えるのは困難であるとしています。 地球を守り将来世代に豊かな環境を引き継ぐために、私たちは諦めるわけにはいきません。この期に及んでも石炭火力と原発しがみつき、環境NGOから何度も「化石賞」を受賞する日本政府の姿勢は恥ずべきものであり、責任は重大なものがあります。 地方自治体の本気の取組を推進するとともに、県民一人一人が気候危機打開の取組を一層進めることが求められています。 省エネについて伺います。 長野県は温室効果ガス排出量を2050年に実質ゼロを目指し、2030年度までに2010年度比で60%削減するとして、再生可能エネルギー生産量を2倍増、再生エネルギー消費量を4割削減するとした野心的な目標を掲げ取り組んできていますが、最新実績はどうなっているか伺います。【諏訪環境部長】 ただいま質問をいただきました。順次お答え申し上げます。 まず、再生可能エネルギー生産量、最終エネルギー消費量の最新の実績はどうかとのお尋ねでございます。 県では毎年度、国の統計調査等のデータから県内における再生可能エネルギー生産量及び最終エネルギー消費量を把握しております。直近の再生可能エネルギー生産量は、2021年度が約3万テラジュールであり、2010年度比で約1.3倍に増加しております。また、最終エネルギー消費量は、暫定値でございますが、2020年度が約16万1,000テラジュールであり、2010年度比で約17%の減少となっているところでございます。 なお、温室効果ガス正味排出量は2019年度1,213万トン CO2であり、2010年度比で約22%の減少となっているところでございます。【毛利栄子議員】 3月策定の「ゼロカーボン戦略ロードマップ骨子」によると、2019年度実績では、基準年に対して、産業部門・業務部門が25%削減となって全体を引っ張り、寄与度が大きくなっています。これは一定規模事業者に対する事業活動温暖化対策計画書等の作成、県への提出、公表を義務づけ、事業者を総合的にサポートしていたことによる効果が大きいと思われますが、進捗状況を伺うとともに、中小規模排出事業者の自発的な参画も広がったと思われますが、どのような状況なのか伺います。【諏訪環境部長】 「事業活動温暖化対策計画書」制度の進捗状況についてでございます。 まず、計画書制度の参画事業者ですが、2021年度が334者、2022年度が856者、そのうち自発的に参画している中小規模排出事業者が2021年度が21者、2022年度が530者で、500者以上増加しているところでございます。 また直近で把握しております2021年度の参画事業者の温室効果ガス排出量は、2019年度比で0.2%の削減となっており、これは設備更新や再エネ電気の切り替え等により排出削減が進んだ一方、経済活動の回復により、製造業において生産量が増加した結果であると考えられます。 産業業務部門全体で見ますと、直近で把握している2019年度の排出量の実績は、計画書制度の運用を開始した前年度の2013年度と比較して約21%削減されており、計画書制度が産業業務部門の排出削減に貢献しているものと考えているところでございます。 温室効果ガス排出量を削減するには、まず自らのエネルギー使用状況を見える化することが必要であり、計画書制度はそのための有効な手段であると考えております。2030年度に2010年度比6割減の目標を達成すべく、引き続き本制度も活用しながら、事業者の排出削減を促進してまいります。【毛利栄子議員】 電気代なども高騰する下で、中小企業エネルギーコスト削減助成金が大変好評で、事業者が省エネ冷蔵庫に替えたり、電気をLED化したりと利用しています。実績を伺うとともに、ぜひ継続してほしいとの要望も出されています。 募集期限の延長などを実施していただいていますが、産業・業務部門の削減をさらに進めるためには、時限的ではなく、一定のスパンを持って継続実施していただきたいと思いますが、産業労働部長、いかがですか。【田中産業労働部長】 「中小企業エネルギーコスト削減助成金」について御質問をいただきました。 中小企業エネルギーコスト削減助成金は、令和4年6月補正から令和5年6月補正までの間で合計約42億円の予算額を計上し、4回の募集を実施したところでございます。 この直近の9月4日の募集までで合計2,674社から、ほぼ予算額の約42億円の申請をいただいており、そのうち、本年9月15日時点で約16億円が支給されているところでございます。 本事業は国の交付金を財源としまして価格高騰対策として緊急的に実施してきた事業でありますが、追加の実施等につきましては、今後のエネルギー価格の動向や国の新たな経済対策を踏まえた上で検討してまいります。 また一方で、この省エネ設備などの導入は、コスト削減による企業の経営基盤の強化につながるものでございます。今後、本助成金事業を通じて把握しました設備ごとのコスト削減データの有効活用や、設備投資時の資金回収シミュレーションなどができる支援ツールの提供などを予定しておりまして、企業の自主的な省エネ設備等の導入を、継続的に支援していきたいと考えております。 以上でございます。【毛利栄子議員】 2030年度までに乗用車の1割、10万台をEV車にとの目標を持っていますが、環境にはいいと分かっていても、まだまだコストが高いためになかなか切り替えできないというのが現実ではないでしょうか。 県では充電器に対する助成などを実施していただいていますが、国の自動車購入補助金に加えて、県内でも幾つかの自治体で購入への直接補助制度なども設けているところがあります。県としても実施している自治体と協働するなど支援策を検討していただきたいが、いかがでしょうか。【諏訪環境部長】 EV、電気自動車でございますが、これの推進に対する支援についてでございます。EVの普及を促進するためには、EVの購入に対する支援と、EVを利用しやすい環境の整備といった両面での取組が必要だと考えております。EVの購入につきましては、国が補助上限額を引き上げるなど支援策を拡充していることもあり、県といたしましては、まずはEVを安心して快適に使える環境を整備するため、多くの方が利用する道の駅をはじめとする主要道路沿いの施設等への充電設備の設置に対して補助をするなど、充電インフラの整備を重点的に進めているところでございます。 日本ではまだ販売されているEVの車種も限られております。今後、各メーカーによる新たなEV車種の投入が見込まれており、選択肢が増えることにより購入意欲も上がってくるのではないかと思慮されます。 こうした市場の動向も注視し、国や市町村とも連携しながら引き続きEVの普及に取り組んでまいります。【毛利栄子議員】 再エネの普及拡大について伺います。 2019年の都道府県別県内総生産は580兆7,600億円、長野県は8兆4,500億円です。財務省貿易統計によると、2022年の化石燃料輸入総額は35兆円。単純に長野県に当てはめてみると、1.45%分、およそ5,000億円です。 これが海外に流出しているわけですから、もし流出せずに県内で循環したとすれば、どれほど地域が潤うかと思うと、高くて不安定で持続性に欠ける輸入化石燃料に依存せずに、現在の電力需要量の7倍の潜在量を持つ再生可能エネルギーをもっともっと拡大させることのほうが、どんなに県民益にかなうかと考えます。エネルギーの地産地消をさらに推進させるべきではないでしょうか。 長野県で再生可能エネルギーのポテンシャルの高いのは、太陽光と小水力です。この間東北震災を機にFIT制度が始まり、県内では森林伐採や大規模な環境破壊をして、野立てメガソーラーをはじめとした太陽光発電が各所で行われ、防災面や環境面、景観面などで近隣住民とのトラブルが頻発してきました。 しかし、度重なる規制強化と買取価格の引下げによって、認定件数は2013年の3,701件から2022年は89件へと激減していきました。しかし、依然としてトラブルが発生していることもあり、今回条例提案となりました。 私たちはずっと県条例の制定を提案してきていたので、遅きに失した感はありますが、半分以上の市町村が条例を持っていないことを考えればルールは必要であり、屋根置きを徹底的に追求しつつ、野立ての場合は遊休農地、未利用地などの活用が望まれます。 「ゼロカーボン戦略ロードマップ骨子」では、屋根ソーラーを現状の個人住宅9万件から22万件にする、事業所9,000件を1万5,000件にするとの計画を持っています。目標に到達するには毎年2万件程度を設置していかなければならない計算になります。 太陽光は各家庭にとっては再エネへの関心を高め、地域にとっては地産地消の電源であり、災害時の電源確保としても重要ですので、一層の取組の強化を求めるものです。 先番の議員とのやり取りの中で、新築住宅への設置義務化の方向性も話されていますが、設置拡大をどのように推進していくつもりなのか伺います。【諏訪環境部長】 屋根ソーラーの推進についてでございます。 本県は、豊富な日射量と冷涼な気候により発電効率が高く、全国的にも太陽光発電に適していることから、県では建築物の屋根を活用したいわゆる屋根ソーラーを推進しております。 導入件数の把握が可能な個人住宅については、設置率は全国第2位となっているものの、いまだに約1割の設置にとどまっており、さらなる普及が必要です。 県といたしましては、これまでの補助制度や共同購入事業に加え、新築建物への設置義務化の検討を進めるとともに、設置メリットの周知、導入時の初期費用がかからないPPAモデルの普及・促進など、あらゆる取組により設置を進めてまいります。【毛利栄子議員】 諏訪市では、市役所本庁舎の屋上と諏訪中学校の体育館屋根を信託会社に無償で貸し、発電した電力を2施設が使うオンサイトPPA方式を活用して、エネルギーの地産地消を進めるとのことです。 庁舎は年間使用量の20%、諏訪中学校では50%をそれぞれ賄え、蓄電池も併せて導入し、災害時の夜間電力としても活用できるようにすると言います。 電気代の高騰が続き、今後も不透明な状況も続くもとで、自家消費型や地産地消を進め、災害時や停電時にも活用でき、利益や地域に還元でき、地域おこしにも役立つ地域内電力をもっと進めるべきと考えますが、県としての考え方を伺います。【諏訪環境部長】 災害や地域おこしにも役立つ地域内電力の推進に関する見解はどうかとの御質問でございます。 昨今のエネルギー価格の高騰や電力系統の容量不足、再エネそのものの価値の高まりを踏まえますと、自家消費も含め、再エネ電力の地消地産に取り組むことは極めて重要であると考えております。 また、平成30年9月の北海道胆振東部地震に伴う北海道全域での停電の際、太陽光発電により電気が使えたという例もあるなど、再エネの地消地産は、自然災害が多い本県においても、災害に強い地域づくりにも大きく寄与するものでございます。 県といたしましては、再エネをつくることにとどまらず、地域でどのように再エネを活用していくかという視点に立ち、エネルギー自立地域創出支援事業において地域マイクログリッドの構築を支援対象とするなど、再エネの地消地産のための取組を推進してまいります。【毛利栄子議員】 小水力発電は現状98.7万キロワットから、2030年度に103万キロワットにするとのことで、年10件ペースで普及するとしています。現状では年数件程度です。ここも相当ハイペースで実施しなければいけない状況ですが、どのような取り組みを行っていくのか伺います。【諏訪環境部長】 小水力発電の普及に向けた取組についてのお尋ねでございます。 本県においては、豊富な水資源と急峻な地形により小水力発電の適地が多くあるものの、小水力発電の事業化に当たっては、建設コストや各種法令手続、地域との合意形成などのハードルがございます。 このため県では、事業者に対し、これまでも収益納付型補助金による資金調達支援や、小水力発電キャラバン隊による許認可手続のサポートを行ってきましたが、現状、目標の導入ペースには届いておりません。 そこで、今年度からは、さらに直接的な導入支援として、設置の障壁となりやすい地域の合意形成に関し、企業局と連携し、候補地選定や地域調整にも県も関わることによりスムーズな事業化につなげる取組を開始したところでございます。 これらの取組と併せ、砂防堰堤などの施設も有効活用しながら、小水力発電の普及を加速してまいります。【毛利栄子議員】 脱炭素社会の実現は、私たち一人一人の決意と行動にかかっていると思います。県には思い切った施策を展開していただきながら、利潤第一主義でない、地球と将来の世代のために、立場の違いを超えて省エネと再エネに本気で取り組むために、共に力を合わせることを呼びかけたいと思います。特別支援学校の環境整備について【毛利栄子議員】 特別支援学校の環境整備について教育長に伺います。 特別支援学校は老朽化、過密化、狭隘化が進み劣悪な環境になっています。共産党県議団は改善を求め、この10年間だけでも本会議で16回にわたって質問を重ねてきました。 大規模改修はようやく若槻養護と松本養護に手がつけられ始めましたが、今いる子供たちは、新しい校舎で学ぶことなく、我慢を強いられたまま、劣悪な環境下で卒業せざるを得ません。 6月議会の高村京子議員の質問に対し、教育長は、特別支援学校の劣悪な環境に対しては、できるだけ早期の環境整備に取り組んでいくと答えています。 私たちはこの間、伊那養護学校や上田養護学校などを視察し、障害児学校教職員組合の方々とも懇談させていただいてきました。臭くて古い和式トイレ、厨房設備は人員増に追いつかず、弁当持参の教師。図書室もなく、蔵書も閉校した学校からもらい受けて対応。屋根つき車寄せスペースが狭く、雨に濡れながら待っている児童。雨漏りする寄宿舎、掃除機2台使用でブレーカーが落ちる寄宿舎など、緊急に対応しなければならない課題が全ての特別支援学校に山積しています。 ここに至るまで迅速な手を打ってこなかった県教委の責任は大きく、緊急の対応が必要と考えます。何でこんなことになってしまったのか、教育長に認識を伺います。【内堀教育長】 御質問を頂戴いたしました。 特別支援学校の環境整備についてのお尋ねでございます。 県立特別支援学校の児童生徒数は、平成元年度1,591人であったものが、本年度2,588人と、少子化の中にあって約1.6倍に増加しており、教室不足等の狭隘化が課題となっております。県教育委員会では、学校の新設校舎の増築分教室の設置、中信地区と長野地区の再編整備等により対応してまいりました。 また、学校の新設時期が比較的集中しているため、現在建物が築30年以上である学校は、18校中15校であり、施設設備の老朽化が進んでおります。 このため、中長期的な視点に立った改築等と、応急的な対応である校舎の増築、施設設備の修繕改修等に併せて取り組んできたところであり、平成28年度からは、修繕改修予算をそれまでの約3倍に増額し、また、令和3年度からの中長期修繕・改修計画実施以降は、さらに2倍近くに増額してまいりました。 本県特別支援学校において、施設設備の狭隘化や老朽化に課題がある原因につきましては、児童生徒数の想定外の増加や、施設設備の改築や修繕等の必要な時期が重なったことなどにあると考えておりますが、現在ある課題につきましては、できるだけ早期に改善できるよう、引き続き計画的な環境整備に努めてまいります。【毛利栄子議員】 6月議会で、教育長は、特別支援学校整備基本方針に基づく中長期的な視点に立った大規模改修計画とともに、応急的な改修・修繕の両面で学習環境を整えていくと答え、応急的な対応として、令和3年度から10年間を計画期間とする修繕・改修計画に基づき、予算を大幅に増額して計画的に取り組んでいると述べています。 私は、この10年間かけての修繕計画はあまりに悠長過ぎると思わざるを得ません。もっと短時日でスピーディーに取り組むことはできないのか伺います。【内堀教育長】 中長期修繕・改修計画のスピーディーな実施についてのお尋ねでございます。中長期修繕・改修計画は、国のインフラ長寿命化計画に基づき計画期間を10年間とするもので、施設ごとに必要となる修繕や改修工事を適切な時期に着実に実施することで、長寿命化等を計画的に行い、財政負担の軽減と平準化を図ることを目的としております。 この計画には、現在老朽化や故障等の課題が生じているものに加え、劣化度調査等を踏まえて、今後課題が生じると想定されるものを盛り込んでおります。特別支援学校では、この計画をベースとしつつ、緊急な対応が必要な工事等と併せて、毎年度の環境整備に取り組んでいるところでございます。 県教育委員会といたしましては、児童生徒の安全で安心な学習環境を実現するために、引き続き特別支援学校への現地調査を実施したり、保護者など関係者の御意見も丁寧にお聞きしながら、今後も必要な修繕改修を計画的に行ってまいります。 以上でございます。リニア建設工事における尾越工区の残土処分について【毛利栄子議員】 リニア建設工事における尾越工区の残土処分について、建設部長並びにリニア整備推進局長に伺います。 リニア建設工事に伴う中央アルプストンネル掘削工事で出る残土は、南木曽町で180万立方メートルと言われています。急峻の地形の上に土砂災害で非常に苦しんでいる地域であり、処分に対して住民の間から、不安の声が寄せられています。 県議団は9月6日、南木曽町内で学習懇談会と現地調査を行いました。 JR東海は尾越工区のトンネル掘削を始めるに当たり、県の盛土条例を受けた住民説明会を重ねています。この工区で発生する残土は110万立方メートル、9月5日には処分候補地4か所のうちの一つ、「尾越」の工事概要を示しました。 一級河川蘭川右岸沿いの段丘にある特殊精鉱工場跡地1.6ヘクタールで、沢地形を盛土造成し建てられた場所ですが、この盛り土を含む敷地の上にさらに9万立方メートルの残土を盛り土する計画で、最大高さは約23メートルにもなります。処分地の一部は、土砂災害防止法の「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警戒区域」に指定されています。 南木曽町は年間の降雨量が2,500ミリを超える地域であり、2014年7月には、死傷者も出る土石流災害も発生していて、住民の皆さんは、「蛇抜け」と称して土石流災害を警戒しています。 下流域の吾妻地区の皆さんは、大雨で盛り土が崩れ、川に流れ込むようなことになれば大災害になる、南木曽のようなところに大規模盛り土はやってほしくない、おちおち寝ていられないと不安を語ります。ほかの工事として示めされている「ホテル木曽路」の裏山は、詳細は示されていないものの、盛り土高さが70メートルにも及ぶことが予想されます。 今後JR東海は、県の盛土条例に基づき、木曽建設事務所に盛り土の許可申請を出し、県はその内容を精査して、許可、不許可を決めていくことになると思います。 これだけ大規模の盛り土を県機関だけで決めていくことは負担が大きいと思われます。条例制定時に、許可権者としての知事が判断できる専門家から成る第三者委員会設置などの仕組みづくりが必要だと求め、当時の田中建設部長は高度な技術的判断が必要な場合には、第三者の専門的知見を検討すると答えておられます。 過去に例を見ない大規模盛り土が計画されていることから、ぜひ、地質、地形、水象、気象などの環境条件や工法の設計内容など多方面から検討できる第三者委員会を設置して、専門的な見地から対応してほしいと思いますが、建設部長、いかがでしょうか。【新田建設部長】 御質問いただきました。 県の盛土条例における第三者委員会の設置についてのお尋ねでございます。 本条例では、面積が3,000平方メートル以上、または高さ5メートル以上の盛り土を行おうとする者は他の法令により許可を取得している場合などを除き、知事への許可申請が必要となっております。 特に高さが15メートルを超える大規模な盛り土の場合、安定計算に加え、過去の施工実績等を踏まえて、工学的に盛り土の安定性及び耐久性について十分検討をし、必要な構造を満たすよう申請者に求めているところです。 また、高さ15メートルを超える盛り土の許可に当たっては、地盤工学や砂防学に関しての専門的な知見を有する第三者による有識者会議を設け、盛り土の形状や、盛り土を支える擁壁などの土工構造物の安定性に関する意見を聴取することとしています。 このように大規模な盛り土が行われる場合は、現地の地形や地質、構造等に応じ有識者の専門的な知見を活用しながら、安全な盛り土がなされるよう条例に基づき適正な審査を行ってまいります。【毛利栄子議員】 当該の皆さんは、申請に関して住民の意見がどう反映され、どのような審査が行われるのか経過を知りたいと言っています。審査の経過が公開されるのか伺います。【新田建設部長】 審査の経過の公表についてのお尋ねでございます。 本条例では、盛土工事の許可に際して、まず申請者が工事内容を周辺地域へ説明を行った上で申請することとし、申請書類については、条例、規則、取扱要綱及び条例に係る技術的基準に基づいて、県が審査することを定めています。 審査は土工構造物、地盤の安定性、排水計画の妥当性等について行い、それぞれの基準については、県のホームページで公表しているところでございます。どのような観点で審査を行うかを、県民の皆様にも確認いただけるようにしているところでございます。 また、個別の案件については審査中は公表しておりませんが、許可後は希望される方が申請書及び許可書について閲覧することを可能としてございます。【毛利栄子議員】 盛り土完了後の恒久的な維持管理は、土地所有者の責務に委ねることになっています。住民にしてみれば、「盛ってしまえば、はい、終わり」ではなく、末代まで安全・安心に過ごせるのか気になるところです。 許可した県の定期的な事後チェックをしていただきたいと思いますが、いかがですか。【新田建設部長】 盛土工事完了後の事後チェックについてのお尋ねでございます。 本条例では、盛り土が完了し申請者からの完了の届け出があった際には、県は、当該盛り土が条例の基準に適合しているかを確認することとしております。完了後、盛り土の崩落により他者に危害を及ぼさないよう土地を適正に管理することは、議員御指摘のとおり、本条例においては土地所有者の責務となっております。 また、本年5月に宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法が施行され、現在、県において規制区域の指定のための基礎調査を行っておりますが、その規制区域内においても、土地所有者が土地を安全に管理することが規定されております。 県といたしましては、本条例には県の責務として、土砂等の崩落等の災害を防止するために必要な施策を総合的に推進すると規定しており、また将来的に盛土規制法に基づき、規制区域を指定した際には、区域内の既存盛り土についても、県と中核市が調査をすることとなっていることを踏まえ、盛り土完成後も状況を把握し、災害防止に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。【毛利栄子議員】 国土地理院の地質図幅「妻籠」によれば、尾越地区の工区の非常口付近には、貴金属のアンチモンが鉱脈状に分布しているとの記載があり、住民からも、かつて採掘した跡があるとの情報があります。 アンチモンは曝露すると呼吸器系の障害を起こすおそれがあると言われ、平成29年には三酸化アンチモンは特定化学物質に追加されました。また水質汚濁に関わる人の健康の保護に関する環境基準等において、公共用水域や地下水の要監視項目にもなっています。 尾越工区からの残土2万6,000平方メートルは、町内十二兼地籍の木曽川右岸道路の仮設工事で長野県が使うことになっています。 重金属を含む要対策土は、長野県としても特段の対策が必要だと考えますが、どのように対応するのか、リニア整備推進局長に伺います。【斎藤建設部リニア整備推進局長】 リニア建設発生土の木曽川右岸道路工事での活用についてのお尋ねでございます。 要対策土につきましては、一般的に県を含め、公共事業における建設工事では、土壌汚染対策法で特定有害物質に指定されている重金属を含有している可能性がある場合には、同法に基づき検査し、基準値未満のものは普通土として活用し、また、基準値以上となることが確認された場合においても、要対策土として適切な処理を行い活用できることとしております。 一方、JR東海ではリニア建設工事に伴う発生土に関し、要対策土は一般の発生土置き場には搬出しないこととしており、県が事業主体であります木曽川右岸側道路工事についても同様の扱いとなります。このため特段対策は必要ないと考えております。 なお、議員の御質問にありましたアンチモンについては、土壌汚染対策法の規制対象物質として指定はされていませんが、懸念されるとの御意見も一部にあることから、受入れ側である県として、まずはJR東海に対し、状況の把握をするよう要請してまいります。 以上でございます。【毛利栄子議員】 熱海の土石流災害以来、県民は盛り土に対して非常にセンシティブになっています。そもそも平坦地の少ない長野県には処分適地は少なく、谷や沢を安全に埋めていくことなどは皆無に等しいのではないかと思われます。 公共事業であれば一定の時期を区切りながら事業の再評価をしていくのに、あるときは全幹法に基づく国家的事業と言い、あるときは私企業の事業だと強弁し、事故報告も消極的で、やみくもに突き進んでいくやり方はあまりにひど過ぎます。 JR東海は一旦立ち止まり、再検証すべきだと求め、質問を終わります。
2023年09月29日
-
岡谷市福祉大運動会 楽しく交流
第44回岡谷市福祉大運動会。小井川小体育館。車イス競争、血圧測定(風船割り)、パン食い競争、大玉送りとたくさん楽しませていただき、カップヌードル、あんぱん、ジュースと景品もかかえきれないほどゲット。4年ぶりにはじけた1日。皆さんも本当に楽しそうでした。
2023年09月16日
-

介護保険への国庫負担の増額を求める意見書提案
日本共産党県議団を代表し議第14号「将来にわたり安定的な介護保険制度の構築を求める意見書」(案)につきまして提案説明をいたします。介護保険制度は23年前に「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み」として導入されました。介護費用は40歳以上の国民から徴収する介護保険料と市町村12、5%、都道府県12、5%、国25%の公費と利用料で賄われています。高齢化の進展に伴う需要の増加により介護費用が増えてくる中で、制度が始まった2000年度導入時は65歳以上の保険料は全国平均2911円でしたが現在では6014円と2倍以上になり低年金、物価高の中でますます負担感は大きくなっています。政府はこの間全世代型社会保障改革の名のもとに毎年、社会保障予算の自然増を数値目標を持ちながら削減し負担増・給付削減を実施してきました。介護報酬の連続削減、1割負担の利用料の2割・3割への引き上げ、介護施設の食費・居住費の負担増、要支援1・2の訪問・通所介護の保険給付外し、要介護1・2の特養入所からの締め出しなど、利用者・家族の負担を増やし、介護サービスを受けにくくする制度改変を行って介護現場の苦難に拍車をかけ「保険あって介護なし」ともいえる状況をつくってきました。介護現場では、若い職員の離職や志望者の減少が続き、深刻な人手不足が起こっており公的介護制度の存廃を脅かす重大問題となっています。こうした事態を引き起こしてきた最大の要因は、介護従事者の過酷な労働環境と処遇が低く抑えられてきたことにあります。今後団塊の世代が後期高齢者になり介護サービス需要の急増が予測される中、必要なすべての人が安心して介護を受けられるようにするには、政府の進める介護ロボットやICT機器の整備では限界があり、命や安全が守れません。無資格者や日本語指導が必要な外国人を安価に雇って人材不足を補うという方向ではなく保険料や利用料に連動しない介護報酬を改定し、介護人材の処遇を改善するとともに将来にわたって安定的な介護保険制度となるよう国庫負担割合の引き上げを行うことが不可欠です。措置の時代には国の負担割合が5割だった経緯もあります。高齢者も現役世代も安心できる持続可能な介護保険制度の構築のため、国による財政措置を求め提案説明とさせていただきます。ぜひご賛同いただきますようお願いいたします。結果は賛成少数で否決!
2023年06月30日
-

中日大使が県議会を表敬訪問
長野県は中国河北省と友好提携していますが、今日は呉江浩(ごこうこう)中日大使が夫人とともに長野県と県議会に表敬訪問に来られました。議長、各会派の責任者がお迎えし歓迎のことばをそれぞれ述べさせていただきました。私からは「国と国の間には緊張感がありますが地方から友好関係を強める中で、国の対応に影響力が持てるよう頑張りましょう」とコメントさせていただきました。呉大使は伊那自動車教習所で車の免許を取得したことや夫人がスキーで長野に訪れたことがあることなど紹介し、大変身近に感じました。次につながるフレンドリーな時間をすごせて良かったです。
2023年05月25日
-

改選後初の議会で議長副議長選挙 高村さん議長選に
今日は議会正副議長選。統一協会との関わりが指摘されていた佐々木祥二氏(自民・7期)が議長に立候補を表明するなか日本共産党は話し合うなかで高村京子さん(7期)をたて、9年ぶりの選挙戦に。全員協議会での所信表明会を経て本会議で投票に。高村さんは統一協会と県議との関わりや現職県議が逮捕されるなど議会と県議への県民の信頼が大きく損なわれていることを懸念し、信頼回復と説明責任がもとめられている、さらに議会のバリアフリー化や政務活動費の透明性向上、少数意見の尊重などいっそうの議会改革が必要と堂々と所信を述べ、選挙戦に臨みました。結果は高村県議9票、佐々木県議42票、他議員1票、白票5票で議長は佐々木祥二氏に。高村さんは共産党票以外に3票獲得しました。ある自民党県議は選挙後、「白票5票は高村さんへの票だ。選挙をやって良かった」と言ってくれました。負けたとはいえさわやかな選挙でした。前列左 高村京子(7期) 中央もうり栄子(5期) 和田明子(5期)後列左 両角友成(4期) 中央藤岡義英(3期) 山口典久(3期)
2023年05月10日
-

放課後等デイサービス事業 教育費の保護者負担軽減で一般質問
1、 放課後等デイサービス利用における障害児支援の充実について(健康福祉部長)にうかがいます。この事業は平成24年の児童福祉法の一部改正により、支援を必要とする障害のある学齢期の児童に対し、放課後や休日に学校や家庭とは異なる時間・空間・人・体験等を通じて個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的にスタートした事業です。制度の創設から10年、長野県の小中学校における発達障害児童・生徒数は平成24年の4662人から令和4年の9786人と倍化しているなかで、放課後等デイサービス事業所数や利用者も急増し、全国的な課題として事業所の中には障がい児の発達支援が十分提供されていない、ゲームやテレビだけの単なる居場所になっている、全国展開する事業者によって儲けの対象にされているなどといった質の問題が課題となってきました。 そんなおり、信濃毎日新聞で飯田市内の放課後等デイサービス事業所で2021年度に子どもの首に「×」印を付けたカードを掛けたり、四つんばいになった子どもの背中を机代わりにして職員が連絡帳を書いたりしていたことが報道され、子どもへの心理的虐待にあたる事例があったことが報道され愕然としました。圧倒的多数の事業所は障害児支援に熱心な職員が、様々な障がいを抱える児童・生徒に対し厚労省作成の「ガイドライン」等を参考に、試行錯誤しながら最大限の努力を重ねていることは承知しています。 そこで健康福祉部長に伺います。① 質を担保していくためには事業所における職員に対し、障害者権利条約、障がい者虐待防止法、障がい者差別解消法、障がい者共生条例などといった関係法令を周知・徹底することが必要ですが、周知・理解のための研修などはどのようにされているでしょうか。 ② 長野県の放課後等デイサービス事業所の実態はどうなっているのでしょうか。事業所数や利用者についてこの間の推移はどうなっているか。また課題は何か。あわせて事業形態についてお示しください。 ③ 質の向上のために事業者間の実践交流や研修の機会が必要で、全県レベルではおこなわれているようですが、現場を離れられない事情もあることから「保健福祉事務所単位くらいの規模で、職員が出やすい時間帯を設定して実施して欲しい」との要望があります。県がかかわりきめ細かな質的支援の体制を構築していただきたいがいかがでしょうか。 ④ 事業には最低定員1日10人が必要で、町村部では確保が難しいところもあり家庭ですごさざるを得なくなるかあるいは遠くまで時間をかけて通うか、学童クラブで過ごさざるを得なくなっているところが少なくないとおもわれます。県としての課題の認識と対応策について伺います。 ⑤ 職員は児童指導員や保育士、看護師、理学療法士など専門職の配置が求められているため人的な確保ができず小規模の事業者が閉鎖に追い込まれているとの事例も聞くが、県としての課題の認識と人的確保策について伺いたい。⑥ 学校と事業所での対応がまちまちだと質の高い支援もできないため事業所と学校での連携が必要ですが、なかなか学校との連携が難しいとの声も聴きます。より支援を充実させるための学校との連携について県としての対応策を伺いたい。 ⑦ この間の報酬引き下げによってより支援を充実させようとすればするほど厳しい運営を迫られていると伺いました。事業維持に不可欠な家賃や駐車場の借り上げ料などに「補助があると助かる」との声を聴くが県として対応策を検討できないか伺います。 お訪ねした事業所では次々「ただいま」といって帰ってくる子供たちがおやつを楽しそうに食べ始めていました。最初はみんなと食べることのできなかった子も他者とかかわりながら食べられるようになり、土日や長期休暇の際にも様々な取り組みに参加してみんなと協力しながら挑戦し、成長している様子も教えていただきました。一人ひとりその子の特性に合った対応が日々求められており試行錯誤の連続だと現場の大変さもうかがってきましたが、豊かな放課後を保障してこそその先の地域での生活もあると語っていただいたことが印象的でした。 2、 教育費の保護者負担の軽減について(教育長)に伺います。内閣府が2020年に行った意識調査では「育児を支援する施策として何が重要か」との問いに対し「教育費の支援・軽減」が断トツトップの69、7%に上っています。党県議団はこうした保護者の思いにこたえるために、これまで学校徴収金の見直し、給付型奨学金の創設・拡充、高校タブレットの貸与、学校給食費の無償化などを求めてきました。学校徴収金については県教委としても2010年に「学校徴収金の基本的な考え方」を策定し、必要最小限の額の徴収につとめながら少ない費用で大きな効果が出るように努めてきていただいているところです。 令和3年度を見てみるとこの10年間では小学校で最高時の82207円から76531円と7%の減、中学校で122139円から104263円と15%減、高校で89212円から79197円と11%減になっています。しかし一方学校徴収金以外のいわゆる「隠れ教育費」は急激に増えており、特に小学校、中学校、高校入学時にランドセルや制服、運動着や教科書の購入などがあり、膨大な支出に悲鳴が上がっています。文科省も平成6年度より隔年で学校外活動を含めた子どもの「学習費調査」を実施しており、令和3年度は公立小学校の年間学習費総額は35万2566円、中学校で53万8799円、公立高等学校全日制で51万2971円と公表していますが年々増加傾向にあります。そこで教育長に伺います。① 先ごろ県民文化部子ども若者局から公表された「長野県子どもと子育て家庭の生活実態調査」は衝撃的でした。困窮世帯のうち年所得210万円未満の割合が、5年前から11,4%増えて44、7%になり、一方700万円以上の世帯の割合は5,5%増えて20,5%になったとのことで格差と貧困がますます広がってきていることがうかがえます。お金が足りずに「食料が買えないことがあった」は困窮世帯の73、2%にも及んでおり貧困化が進んでいることの証ではないかと心が痛みます。教育長はこの結果や国の学習費調査の結果をどう受け止め、子供や家庭に対しどのような配慮が必要だと考えているのでしょうか。所見を伺います。➁「隠れ教育費」は特に入学時に膨大なお金がかかることが保護者にとって大きな負担になっています。例えば小学校入学時にはランドセル、運動着、給食着、上履き。中学校入学時にはそれらに加えて制服、入る部活によって楽器やスパイクなど。高校はそれらに加えてタブレットなど。今市町村ではこの大変さに何とか応えようと就学援助金を入学前に支給するとり組みなどが進んでいます。入学時以外にも辞書、水着セット、絵の具、彫刻刀、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、書道セット、裁縫セットなどを購入せざるを得ません。県教委として「隠れ教育費」の実態をつかんでいるのでしょうか。また負担軽減のためにどのような対応がされているのか伺います。③ 県教委は令和4年度から高校入学時にBYODによるタブレット端末の所持を求めています。制服や運動着、定期代などの入学準備に加えて一層保護者負担が増大し、「学校で使うものならなんで学校で用意しないのか」の疑問なども寄せられています。令和5年度も同様の方針が示されていますが、電気代、ガス代、食料品などの異常な物価高騰が続く中で長野県の消費者物価指数は全国を上回る5、1%となり、家計は限界に達し、新たな門出が手放しで喜べなくなっている家庭もあります。県教委としてBYODによるタブレット所持にあたり、貸与や一部補助等の対応の検討はされたのか伺いたい。④ 新入生がタブレット端末を用意するために、周辺機器も含め、実際どれくらい費用が掛かっているのか実態把握が必要ではないでしょうか。個人購入をした一人一人の費用の詳細まで調べることは難しいかもしれませんが、さしあたって学校斡旋端末による購入価格を調べ、傾向を把握することは可能だと考えますが、端末購入費用の概要について伺いたい。 再質問改めて教育長に伺います。この間知事申し入れなどの際に何度かやり取りさせていただきましたが、県教委は「タブレットは学習にも使っているが、日常自由に使えるものなので自分持ちにしている」「生活困難家庭には貸与している」と言っています。しかし学習に使わないのだったら、日常生活ではスマホでも十分間に合い新たに買う必要はないのではないかと思われますし、特別の生徒に貸与すれば生活困難家庭とみなされて差別され、肩身の狭い思いをするのではないかと思われます。全国的にはおよそ半数の県で貸与がされています。ぜひ長野県としても公費での貸与を検討し保護者負担を軽減していただきたいのですがいかがでしょうか。
2023年02月28日
-

地域訪問で重たい課題
フクジュソウが春を先取りするように咲いています。伺ったお宅は子ども4人中3人が精神障害、知的障害などの障がい者とのこと。みんな成人しているが作業所の工賃だけでは生活していけない。障がい者福祉の充実をと。気丈に頑張っておられるお母さん。どんなに大変なことか。障がい者の就労は皆さんからだされます。当事者からもいただいています。重い課題に何とかこたえねば。
2023年02月26日
-
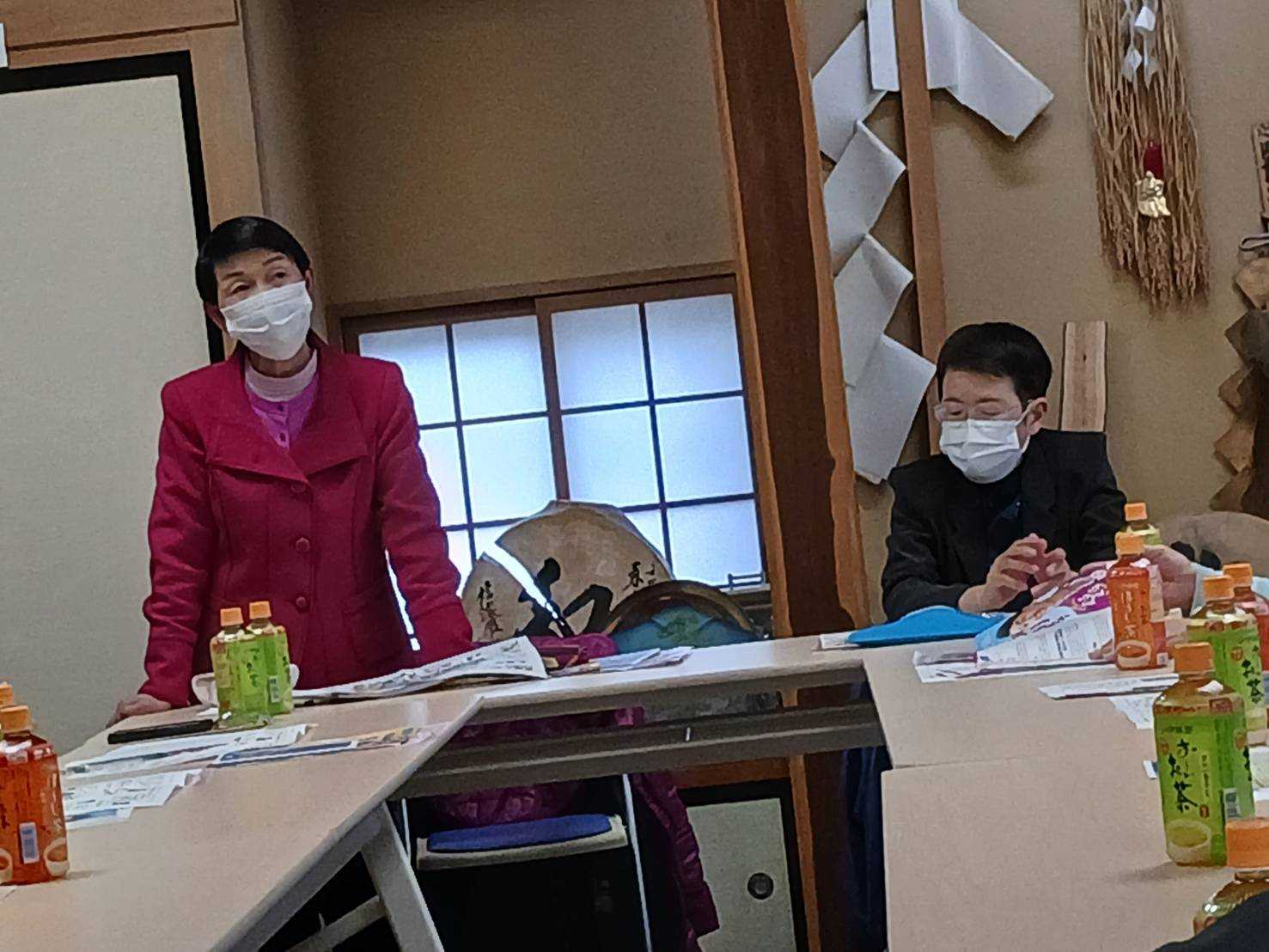
ミニ集会で貴重な意見
冷たい雨ふりのなか、あまり開催したことのない地域で、上田すみこ市議候補とともにつどい。沢山の皆さんに来ていただき感謝。免許返納後の地域交通、投票率アップについて、除雪の充実、諏訪湖の堆積土砂の 問題、加齢性難聴における補聴器購入補助についてなど沢山の意見、要望がだされ、充実したつどいとなりました。終わってみんなで、やって良かったねと。
2023年02月19日
-

ヨシに覆われていた横河川の除草としゅんせつ開始
岡谷市内を流れる一級河川、横河川の伸び放題のヨシと堆積土砂の撤去がはじまっています。ビフォー、アフターをご覧下さい。ワカサギの遡上や野鳥の居場所、環境に気を使っていただきながらの作業です。行政や工事関係の皆さんに感謝です。
2023年02月17日
-

平和のメッセージをのせて9条凧揚げ
恒例の岡谷市湖畔公園での「諏訪9条の輪」主催の平和を願う9条凧揚げ。いつもは100枚の連だこなども揚げるのですが今日は風がなく時折走り周りながら落とさないように揚げました。「子ども達に平和な未来を残そう」などメッセージが書かれた凧があちこちで上がるのは壮観です。風を読みながらの凧揚げは難しかったのですが楽しくできました。今年が新たな戦前にならずにずーっつと平和が続きますように。正念場の年です。
2023年01月09日
-

諏訪大社秋宮前で新春のごあいさつ
あさ一番は地元今井15社の元旦祭。いつもは寒くてホッカイロを貼って参加しますが今日は本当に穏やかな日で助かりました。終わって下諏訪に移動。藤野保史前衆院議員、岡谷、下諏訪の予定候補、支部の皆さんとで参拝者に新年のごあいさつ。立ち止まって最後まで聞いてくださる方、車の窓からあるいは歩きながら手を振って激励してくださる方など大いに励まされました。今年1年が皆様にとって実り多い1年になりますように。
2023年01月01日
-

14年目となった生活困窮者支援
あのリーマンショックの年越し派遣村をうけ、ここ諏訪の地でも「SOSネットすわ」をたちあげ、食料支援や相談会を毎月行ってきましたが、今日はなんと14年目の年末。スタッフの皆さんの粘り強い取り組みに敬意を表し、わたしもささやかながら、お手伝いさせていただきました。お米、缶詰め、切り餅、長ねぎ、お味噌、醤油など袋に詰め20人近い皆さんにお渡しさせていただきました。何人か知っている方も来られて、親しく挨拶を交わさせていただきました。お元気で良かった(^-^)
2022年12月26日
-

クリスマスプレゼントはもうり栄子事務所びらき
クリスマスプレゼントはもうり栄子事務所開き。駅近くのメインストリートにお借りできお披露目。コロナ禍なので簡単にとのことでしたが、どんどん人がきて80人を越え立ち見も。ここを拠点にさあ、ダッシュ。野沢元県議、遠藤岡谷市議、藪内市民連合共同代表から心のこもった激励をいただきました。ありがとうございました。岡谷市議候補の笠原征三郎さん、早出すみ子さん、上田すみこさん、下諏訪町議候補の金井敬子さん、松井節夫さん、花岡進さんからも力強い決意表明がありました。
2022年12月25日
-

切実な要望256項目を新年度予算に反映してと知事へ
2023年度の予算編成にあたり日本共産党県委員会と県議団で知事に256項目の要望を行いました。知事は「方向性は一致しているが、細かいところではあれもこれもできない」と言っておられましたが、国の悪政の防波堤になって県民の命と暮らしを守る予算になるよう求め、頑張っていきます。(カメラがたくさん入りあちこち向いていたので私の目線がどこか変?)
2022年12月21日
-

荒れた河川敷を見るのはつらい なんとかして
岡谷市内を流れる県管理の一級河川横川がありますが諏訪湖に流れ込む最下流が「土砂とヨシで埋まっていて景観上も防災上もよくないので対応してほしい」との留守番電話。早速現場を見に行くとなるほどひどい!渇水期なので水はさほど流れていませんでしたが、川幅いっぱいに枯れたヨシでおおわれていました。建設事務所に電話してお願いすると「今年やったはずだが」とおっしゃいますので、工事実施したところの続きがひどいのでとお話するとグーグルで見てくださり「ああ、わかりました。現場を見させていただき対応します」とのこと。 コロナと物価高で気持ちが沈みがちな市井にあって荒れた場所を見るのはなお気持ちに追い打ちをかけます。
2022年12月20日
-

下諏訪町議選に挑戦する花岡進さんと諏訪湖の見える高台で宣伝
来年の4月は諏訪地方は全自治体が統一地方選挙です。私の選挙区の岡谷市、下諏訪町でも県議選と市町議員選挙があります。下諏訪では現有3議席確保目指し、増沢昌明さんから新人の花岡進さんに代わります。花岡進さんは諏訪共立病院で38年間事務方としてがんばって来られた方で「誠実を絵にかいたような人」です。今日は初めて一緒に街頭に立ち、時々みぞれの降る中、町政への思いを語っていただきました。現職の6期目を目指す金井敬子さん、2期目を目指す松井節夫さんとともに3議席確保のために私も力を尽くしたいと思います。
2022年12月18日
-

コロナ禍の施設内死亡、県営住宅の承継、ケアリーバー支援について一般質問
11月議会一般質問を行いました。ご覧いただきご意見などお寄せください。毛利栄子議員 日本共産党県議団の毛利栄子です。新型コロナウイルス感染症対策につきまして、知事並びに健康福祉部長に伺います。新型コロナウイルス感染症が急増し、新規陽性者は11月23日は4,328人という爆発的な多さとなりました。人口10万人当たりの新規陽性者数では、12月8日現在全国6番目、確保病床使用率も11月14日に医療非常事態宣言を発出し注意を促しているものの、12月4日には70.8%と、これまた全国トップレベルとなり、確保病床以外でも347人の入院を受け入れ懸命の対応をしていただいていますが、厳しい状態が続いており、関係者の御苦労には本当に頭が下がります。死亡者数も、高齢者中心に増えており、現在524人となっています。亡くなられた皆さんに心からお悔やみを申し上げます。 知事は、重症化リスクの高い人を中心に、救える命が救えないことのないように取り組むとされ、基礎疾患のある方、65歳以上の方を中心に対応に注力されています。医療機関が逼迫していることは理解しますが、問題は、高齢者施設などでクラスターが広がったり感染者が出ても施設内での療養を余儀なくされ、入院できないまま命を落とされる高齢者がいるということです。 オミクロン株は重症化リスクが低く、比較的軽症だと言われてきましたが、7波になって亡くなる方の数は急速に増え、特に10月末からのほぼ1か月間で全体の4分の1を占め、11月は10月の死者数の4.4倍と急増しています。 国が推進してきた施設内療養ですが、21世紀・老人福祉の向上を目指す施設連絡会の調査によると、全国の特別養護老人ホームや養護老人ホームの5%近い施設で施設内療養中に亡くなった入所者がいるとのことです。医療機関につながらないまま命を落とすことはあってはならないことです。 県は第7波の発生状況と対策の振り返りを公表し、9月25日までの状況を明らかにしていますが、それ以降、現在までの高齢者施設でのクラスターの発生状況、施設内療養の状況、高齢者施設内での死亡者の状況についてお示しください。 また、そもそも高齢者施設は生活の場であって医療の場ではないことから、施設内療養の該当職場では、保健所からの指導を受け懸命に対応しているものの、職員も感染し、もう限界だとの声が上がっています。無理があると考えますが、原則施設内療養とする現在の方針を見直すことや、施設内療養を続けるとすれば、現状の支援策をさらに強化することが求められると思いますが、健康福祉部長、いかがですか。 県では現在54の医療機関に531床のコロナ病床を確保していますが、確保病床に対する使用率が7割を超し、介護現場のみならず医療機関も逼迫し、懸命の努力の中、疲労困憊の状況が続いていると伺っています。 コロナ禍で高度急性期・急性期の治療に当たる病院の役割が再認識されてきています。知事は、地域の実情に応じた医療提供体制の構築に努めると言われていますが、国が進める地域医療構想の下、2015年から2021年の6年間で、高度急性期・急性期の病床数は1,447床も減っています。これほどまでに病床数が減っていなければ、コロナ対応がより十分にできたのではないかと思われますが、病院の機能転換が果たしてどうだったのか、検証が求められていると思います。 知事の見解を伺うとともに、感染症がこれからも形を変えて蔓延することも懸念されます。これ以上は高度急性期・急性期のベッド数は減らさず、充実することこそ必要だと思いますが、知事の所見を伺います。 県内のコロナの陽性者数は既に33万人を超え、県民の16%が感染したことになります。これからの季節、インフルエンザの流行の可能性も指摘されており、発熱外来をはじめ、ますます医療が逼迫することが懸念されます。徹底した換気や手洗い、消毒、マスクの着用を実行するとともに、ワクチン接種の促進と、大規模な検査の実施が求められているのではないでしょうか。 小学生から64歳以下は、基本的に抗原検査キットによる自己検査が推奨されております。体調が悪化してから購入するために出かけるわけにはいきません。加えて、購入する場合でも注意事項を聞いたり書類を書いたりと、お金も時間もかかります。身近に薬局のない地域もあります。 そこで県として全世帯規模で検査キットの無償配付をするなど、抜本的な対応を検討していただきたいと思いますし、薬局等での無料の一般検査を12月31日で終了するのではなく延長すること。年末年始での臨時検査拠点の設置などを求めますが、いかがでしょうか。 ○福田健康福祉部長 新型コロナウイルス感染症の高齢者施設での施設内容について御質問を頂戴しております。 9月26日以降12月7日までの間に高齢者施設で発生をいたしましたクラスターは266件でございまして、また県内には入所型の高齢者施設1,350施設ございますが、施設内療養はそのうち321施設で行われております。また、施設の死亡につきましては、現在、高齢者が地域で安心して暮らせる地域包括ケア体制の構築を進めております。そのため近年、施設や御自宅で看取りが行われるケースもかなり増加をしている状況でございますが、コロナによる死亡者について申し上げますと、発生当初から令和4年12月7日までに公表した死亡者516名のうち、施設内で療養中に亡くなられた方は76名確認されております。 施設内療養につきましては、令和3年10月25日付の国の通知により、入院が必要ない場合は施設内療養が可能とされたところであり、また病床所逼迫時には、患者受入れ病院に過度の負担をかけないためにも必要であると考えているところでございます。 施設内療養を行う高齢者施設への支援につきましては、これまでクラスター発生時における感染管理認定看護師の派遣や、抗原定性検査キットの配付、保健所等による相談や助言等を行ってきたほか、11月28日には施設内での重症化予防をさらに進めるため、抗ウイルス薬投与等に係る研修会を開催したところでございます。 また、施設内療養に要する経費や従事する職員の超過勤務手当等につきましては、施設種別ごとに上限額を設けて定額で補助しているところでございますが、さらなる支援として、その上限額を原則2倍にする予算案を今議会に提出しており、支援を一層強化してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○阿部知事 新型コロナに関連して大きく2点御質問いただきました。 今も医療現場、介護現場で御尽力いただいている従事者の皆様方に改めて私からも感謝と敬意を表したいと思います。 御質問にありました、まず病院の機能転換とそれから急性期病床の充実についてという御質問であります。 本県、現在1万9,000床余りの病床を有しているところでありますが、今後2025年にかけては本県の人口は194万人まで減少し、後期高齢者の割合も20%まで上昇という見通しであります。どんどんどんどん御高齢の方が増えてそして、いわゆる現役世代が減少しているというのが大きな流れになっております。 そういう観点で、こうした人口減少、そして人口構造の変化に伴って、医療の在り方もしっかり見直していかなければいけないというふうに思います。そういう観点で、重篤な病気や手術に対応する急性期病床の必要性は減少してきている一方で、リハビリや長期療養のための回復期・慢性期病床の増加が必要だという状況の中で、この医療資源を適正化するための機能転換の取組が行われてきているわけであります。こうした取組は今後とも重要だというふうに考えております。 他方で、コロナ対応につきましては、本県の場合は公立・公的病院を中心に担ってきていただいております。新たに県立病院機構の病床も、さらにコロナ対応を増やしていくということで予定をしているわけでありますけれども、こうした機能については、今回のコロナ禍の教訓も踏まえ、今後とも充実・強化をしていく必要があるというふうに考えています。 次期医療計画の策定に当たりましては、各地域の中核的な病院を中心に災害医療と同じような観点があります。要は、どのような感染症になるか分かりませんので、その段階でしっかり柔軟にかつ的確に対応していくということが必要でありますので、平時から感染拡大時に転用できる病床を確保していくということと併せて、専門人材の養成などの取組を進めていきたいというふうに考えております。 こうしたことを通じて、新興感染症等の感染拡大時に、医療機関の連携役割分担の下で、適切な対処を行うことができるように取り組んでまいります。 続きまして、今後の検査キットの配付、それから年末年始における検査拠点の設置等について御質問いただきました。 現在のオミクロン株の流行下におきましては、若くて基礎疾患がない方はほぼ重症化することがないという状況の中で、そうした方には、体調不良時の自己検査、そして陽性の場合の軽症者登録センターの登録の呼びかけということを行わせていただいています。これは、外来診療に過度な負荷がかからないようにという観点にお願いをしているところであります。 こうした中で検査キットについてでございますけれども、8月31日からインターネット販売も開始されているところでありますので、県としては、あらかじめ各自で御購入いただくようお願いしているという状況であります。 その一方で、これまでも重症化リスクが高い方が多い高齢者施設等や低所得の方など、必要性の高い方に対しては無償で提供させていただいておりますほか、外来診療逼迫時には、診療検査医療機関からも無償で配付いただくこととしているところであります。 また、年末年始に向けましては、必要な方が検査を受けることができるよう、引き続き対策を検討してまいります。なお、年末年始の帰省時の対応としては、長野駅及び松本駅前に臨時の検査拠点を設置をして、無料検査を行っていきたいというふうに考えておりますし、また、薬局における無料検査でありますけれども、現在12月末までというのが国との間の期限になっておりますが、これは延ばしていただかなければいけないというふうに思いますので、延長をするべく、国と協議をしていきたいというふうに思っております。 引き続き必要な検査、必要な対応ができるように、またコロナの感染状況も見極めながら、適切な対応を行っていきたいというふうに考えております。 以上です。 ○毛利栄子議員 無料検査の延長や主要駅等での検査を実施していただくということで、そのことについては歓迎いたします。 昨日の知事答弁で、陽性者数に占める死者数の割合は、第5波までの1.08%、第6波の0.16%に比べて第7波は0.11%と低くなっているとのことですが、問題は率ではなくて、いかにして亡くなる人が少なくするかではないでしょうか。そのためには、感染を広げないための陽性者の早期把握と隔離、必要な医療が迅速に適用されることが必要だと思います。 大阪府では抗原検査キットの配付を、9歳以下の子供がいる家庭に、個人もしくは保育所学校などから申込みを受けて行っており、既に60万件の注文があると聞きます。緊急事態なので、長野県でも限定的な、先ほど御答弁のような限定的な対応ではなくて、大規模な検査が手軽にできるよう、検査キットの無償配布など、実情に即した対応を求めます。 次に、県営住宅に関する諸問題について建設部長に伺います。 公営住宅は民間の賃貸住宅に比べて低廉な家賃が設定されており、住宅に困窮する低所得者にとって入居がしやすいため、住宅セーフティーネットの役割を果たしています。従来県営住宅の入居に際し、連帯保証人をつけることを求めていたため、その保証人を引き受けてくれる人が見つからずに、入居申込みができずに困っている方々が少なからずおりました。 今回、県営住宅条例改正案が提案され、保証人が撤廃されることは歓迎しますが、敷金3か月分については見直しがありません。民間では既に敷金を徴収していないところも出ている中で、県として敷金の見直しの議論はどのように行われたのでしょうか。所得の低い方々にとって、入居時にかかる費用も負担になっています。敷金は廃止していただきたいと思いますがいかがですか。 次に名義人が死亡、もしくは離婚などでいなくなった場合の入居者の承継について伺います。承継は、長野県の場合は障害者などの特別扱いはあるものの、原則配偶者のみとなっています。親子3人で住んでいた方が母親が亡くなり、その後名義人の父親が亡くなったため親子間承継が認められず、住み慣れた住宅を退去するよう言われて困っているなどの例もあります。どこかに出て行くように言われても、今の家賃と同じ低廉な条件で住めるところはありません。 住まいは人権であり、自分の責任に属さない理由で出なければならないのも理不尽ではないでしょうか。自治体によっては子や孫まで広げているところもあります。長野県としての承継の枠を広げる運用していただきたいがいかがでしょうか。 県営住宅プラン2021では、2030年には県住の余剰が2,000戸出ると推計し、低層住宅を中心に管理戸数を減らし、用途廃止をしていくとしています。入居者が1軒もいなくなり除却対象になっている団地が幾つも出てきていますが、除却が進まず背丈ほども伸びた草や木が大きく茂り、治安や景観の上でも支障が出て、近隣の住環境を悪化させている例が散見されます。建設事務所などでも除草に御努力いただいていますが、用途廃止となった住宅の管理と除却スケジュール、跡地利用についてどのように取り組んでいくのか伺います。 次にケアリーバー支援について、こども若者局長に伺います。 児童養護施設や里親家庭で育ち、進学や就職を機に、施設などを離れるケアリーバーと呼ばれる若者への支援の在り方が改めて問われています。社会的養護の下で育った若者は、従来原則18歳、最長でも22歳で施設を退所し、自立することを求められてきました。 しかし、親など身近に頼れる人がいないために、退所後、生活費や学費を工面できず、社会生活の知恵がないまま1人になり、相談相手もいない中で挫折や孤立するなど、問題が指摘されてきました。 6月に成立した改正児童福祉法では、2024年4月から年齢制限を撤廃し、施設などが自立可能と判断したときまで継続入所できるようになり、年齢制限の緩和は関係者の悲願であっただけに、歓迎をされております。 長野県内の児童養護施設で18歳を超えて入所している若者の実態についてお聞かせください。また、高校等を卒業するなどして、施設を退所した者についての退所後の進路状況について伺います。 また、平成27年4月1日以降、ルートイングループからの寄付金を活用した「飛び立て若者!奨学金給付事業」をスタートし、月額5万円の給付があるわけですが、給付実績はどうなっているのでしょうか。生活費が続かず、大学を中退する学生も少なからずいるとのことです。給付の停止についても伺います。 厚労省の調査は、施設や里親を通して調査票を配ったとのことですが、住所が不明といったことから、本人に送付できたのは対象の僅か35%にとどまったとのことです。このことは施設退所後の支援がほとんどされていないことの反映でもあると思われますが、長野県では、退所者の暮らしぶりの把握や一人一人の状況に応じた継続支援はどのようにされているのか伺います。 今年、長野県社会福祉協議会や児童福祉施設連盟、株式会社レントライフ、NPOホットライン信州など6団体が、社会的養護出身の若者サポートプロジェクトを立ち上げて、アパートの確保などの居住支援、何でも相談、就労支援などに乗り出しました。 社会的養護から巣立った若者との支援ルートが、施設だけの単線からネットワークとして広がろうとしていることは、ケアリーバーにとって重要な支援となる取組だと思いますが、県としての評価と関わり方について見解を伺います。 国は20年4月から退所前後の一人一人に寄り添った支援を強化するため、施設が自立支援担当職員を配置できるようにしました。しかし、人材確保が難しいことや、個々の施設に余裕がないため、配置が進まないと聞いています。措置費の増額が必要ではないでしょうか。現状と強化方向について伺いたいと思います。 ○田中建設部長 私には県営住宅に関して3点御質問いただきました。 まず、県営住宅の敷金の検討経過に関するお尋ねです。 今般の連帯保証人の見直しを検討する中で、まいさぽをはじめ、住宅福祉の審議会委員など、有識者から敷金の在り方についても御意見をお聞きしてきました。有識者からは、生活に困窮し、一括で納めることが困難な場合があるという御意見の一方、敷金を廃止すると退去時の負担が大きくなるなどの御意見もいただきました。 こうした意見を踏まえて検討した結果、現行制度を維持しつつ、まいさぽの自立支援事業を受け入れる入居者には、分割納付を認めることとしたところです。 次に、入居名義人が死亡した場合などの承継に関するお尋ねです。 県営住宅は、住宅確保が困難な方へのセーフティーネットとしての機能を有することから、限られた戸数を真に住宅を必要とする方に提供する責務があります。そのため、承継できる方は原則として配偶者としていますが、高齢者や障害者等、特に居住の安定が必要な方についても承継を認めており、引き続き、個々の事情を丁寧に把握して適切に対応してまいります。 最後に、用途廃止した県営住宅団地の管理に関するお尋ねです。用途廃止とした県営住宅は、他の用途での活用などを検討した上で、利用見込みがないものから順次除去しております。除去までの間は施錠を徹底し、周辺の防犯や住環境保持の観点から随時見回りを実施するなどの管理を行っています。 また、最近の跡地活用としては、市町村産業用地や学校法人の認定こども園敷地としての売却実績があり、引き続き有効活用を図ってまいります。 以上でございます。 ○野中こども若者局長 私には、ケアリーバー支援について五つ御質問いただきました。 まず、施設に18歳を超えて入所している若者の実態と、ケアリーバーの進路状況と課題についてでございます。 児童福祉法においては、児童養護施設等入所者のうち、進学や就職をした者の生活が不安定であったり、障害や疾病等の理由により進学や就職が決まらない児童など、継続的な養育を必要とする者については、自立して生活できるめどがないまま措置解除することのないよう、満18歳を超えて満20才に達するまでの間、引き続き措置を行うことができるとされております。 県内の児童養護施設では、定時制高校等に在籍をしていたり、障害者グループホームへの入所調整に時間を要しているといった理由により満18歳を超えて入所している者が、令和3年度末時点で11名おります。また、本年3月に高校等を卒業して、県内の児童養護施設を退所した若者は33名おり、その進路状況につきましては、大学等への進学者が11名、就職者が16名、その他グループホームへの入所者等が6名というふうになっております。 児童養護施設退所後の若者につきましては、頼れる大人が身近にいないケースが多いため、不安や悩みを相談できないまま、生活苦に陥ったり、離職や退学に追い込まれるといった課題を抱える可能性があると考えており、各施設では退所後も継続して相談に乗るなど、個々のニーズを踏まえた柔軟かつ丁寧な支援を児童相談所など、関係者と共に連携して行ってきているところでございます。 次に、「飛び立て若者!奨学金給付事業」の給付実績についてでございます。 県では児童養護施設や里親等へ入所・委託措置されていた児童が、保護者からの経済的支援を受けられないことを理由に大学等への進学を諦めることがないよう、ルートイングループ等からの寄付金を活用した「飛び立て若者!奨学金」により、入学一時金及び生活費を支援しているところでございます。 当該奨学金制度を創設した平成27年度以降、合計66名に対して給付をしており、そのうち卒業した者が30名、現在受給中が23名、休学により停止中の者が1名、中途退学により支給を取りやめた者が12名という状況でございます。中途退学の理由につきましては、勉学意欲の喪失や人間関係の悩み、進路変更とお聞きをしているところでございます。 次に、ケアリーバーの暮らしぶりの把握や継続支援についてでございます。児童養護施設を退所する際には、児童相談所において、面談等による本人の意向確認、施設や地域の支援者との支援会議などを行い、安定した就学や就労に結びつくように丁寧に対応しているところでございます。 また、施設退所後は児童養護施設においてアフターケアが必要な児童の住居や就業先を訪問し、悩みや問題を抱えている場合には助言をしたり、就学・就労先等の関係機関に退所者の状況等を説明し理解を求めにいくといった丁寧な対応を行ってきており、県では、こうした対応結果について定期的に報告してもらうことで、退所者の状況把握に努めているところでございます。 退所児童にとっては悩み事を一番相談しやすいのは施設であり、児童と信頼関係ができている施設職員が相談支援を行うことが効果的な自立につながるものと考えております。県といたしましては、退所者のアフターケアを行う施設等の活動費や人件費を補助することで、施設の取組を後押ししてまいります。 次に、社会的養護出身の若者サポートプロジェクトに対する県の評価と関わり方についてでございます。 自立に向けて入所等措置を解除された児童は、日常生活や金銭管理、進学先や就職先での新しい人間関係の構築などに関する様々な悩みや不安に直面する可能性があり、その支援には入所施設や児童相談所だけでなく、様々な機関が関わっていただくことが重要であると考えております。 そうした中で、今般、社会的養護出身者の仕事や住まいなどに関する包括的相談支援と支援のための社会資源の開発を行うことを目的として、長野県社会福祉協議会など6団体によります、社会的養護出身者の若者サポートプロジェクトというものが立ち上がりましたことに関しましては、民間団体等様々な機関の協力を得た幅広い支援体制が構築されるということにつながり、支援の充実に向けた非常に有効な取組であると考えております。 県では本プロジェクト立ち上げ前から、県社会福祉協議会からお話をいただいており、関係機関への周知等に協力をしてきたところでございます。今後も引き続き本プロジェクトと連携をいたしまして、ケアリーバーの支援の充実に取り組んでまいります。 最後に自立支援担当職員の配置の現状と支援強化の方向性についてでございます。 現在県内にある14か所の児童養護施設のうち6施設において自立支援担当職員を配置し、退所後にアフターケアを必要とする者の職場や自宅を訪問するなどして、相談支援に当たっていただいているところでございます。 各施設に対して、来年度の予定を調査したところ、さらに3施設が新たに配置をすると回答いただいており、来年度からは9施設において自立支援担当職員が配置される予定となっております。あわせて、配置を予定していない施設に聞き取りを行いましたところ、国の措置費制度で定める支援退所者数や支援回数の要件を満たすことが困難であるということや、支援スキルを持った職員を配置できないといった課題もあるというふうに承知をいたしております。 県におきましては、こうした課題に対応するため、今後施設職員を対象とした研修において、既に自立支援担当職員を配置した施設における支援事例の共有、医療や福祉に関する各種制度の周知・研修を通じ、支援スキルの向上を図るとともに、自立支援担当職員に係る措置費制度の改善についても国に対して要望してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○毛利栄子議員 過日、児童養護施設にお邪魔させていただいて、様々なお話を伺ってまいりました。一時保護を含めて、入所者の中で被虐待児が8割というふうなお話を伺いました。その子たちに寄り添いながら、職員の皆さんは一人一人に心を砕き頑張っておられる様子を伺い、本当に頭が下がる思いでありました。 低賃金、物価高、コロナ禍の中で児童養護施設を離れた若い皆さんが、孤立して悩み挫折することなく、困ったときには、「ただいま」と安心して帰ってこられるよう、サポート体制が一層の充実発展する長野県になってほしいことを期待して質問を終わります。 ありがとうございました。
2022年12月09日
-

諏訪湖畔でピースウォーク
81年前の12月8日。日本がハワイの真珠湾を奇襲し、アジアと太平洋に戦争を拡大した日です。前後して諏訪地方ではピースウオークを実施しています。今年はとりわけ自公が敵基地攻撃能力の保有で合意し、戦後守ってきた専守防衛からアメリカと一緒になって先制攻撃を仕掛けるという大転換を行おうとしている矢先での集会となりました。同時進行で軍事費を2倍化し11兆円にするという大軍拡も行われようとしています。暮らし破壊、戦争につながる動きをやめさせ岸田内閣に代わる新しい野党と市民の願いの叶う政権を打ち建てることが望まれています。党を代表しあいさつさせていただきました。立憲民主党参院議員の杉尾秀哉さんからも熱い連帯のごあいさつがありました。黄色いものを身に着けてとのことで私は黄色のマフラーをつけて参加。
2022年12月04日
-

11月議会に向けた知事申し入れ
11 月県議会に向けた申し入れ 1. 電気料金をはじめ燃料費や食料品などの生活必需品の異常な価格高騰が暮らしを直撃してい ます。これから訪れる厳しい冬を乗り越えて安心して新年を迎えることができる支援が必要で す。コロナ禍で収入が減った人に生活費を貸し付ける緊急小口資金、総合支援資金の返済が負 担になり、生活再建が困難になる事態が予測されます。返済の免除・猶予の拡充とともに、生 活困窮者の思いに寄り添い年末年始を乗り切るためのワンストップで対応する特別相談支援 体制をとって困窮者の救済をすすめてください。2. 県内の中小企業・小規模事業者に、長引くコロナ禍、物価・原材料の高騰、過剰債務の三重苦 がのしかかっています。過剰債務に陥った場合には、金融機関からの新規融資が受けられなく なり、資金繰り倒産に追い込まれてしまいます。新たな資金調達が可能となるよう、コロナ対 応融資(無利子・無担保のゼロぜロ融資)は別枠にし、事業継続に必要な新規融資が受けられる ようにしてください。また、返済の猶予など倒産に追い込まれないよう対応してください。3. コロナ感染対策でオミクロン株の特性を踏まえて感染対策が見直されています。一方、学校で は学級閉鎖や学校行事中止などによる児童・生徒の負担が重く、感染対策の見直しを求める声 も出ています。感染対策の丁寧な説明、これまでの取り組みの検証とともに、児童・生徒、保 護者の意見を聞き見直しも検討してください。4. コロナ感染拡大は 11 日、県内病床使用率が 50%を超えました。県は、重症化の危険性が高い 高齢者などを守る行動の要請と、若年層など重症化の危険性が低い人には簡易検査キットによ る自己検査を促しています。高齢者や一人暮らしの方が入院や療養施設で受け入れてもらえる よう体制を強化してください。厚労省はコロナ検査キットを「体外診断用医薬品」「第1類医薬 品」での検査を呼びかけていますが入手困難なうえに安価ではありません。県として検査キッ トの無料配布や無料PCR検査を実施してください。5. 財務省は全額国費で賄っているワクチン接種を廃止し自己負担とするよう示唆していますが、 家計が苦しくて接種をためらう人が相次げば新たな感染拡大と死者数の増加を招く危険性が あります。コロナ対応では、ワクチンの無料接種の継続を国に働きかけてください。6. 大半を輸入に依存する肥料、飼料、燃油や資材価格の高騰から農家を守ることは引き続き緊急 の課題になっています。価格高騰対策として、肥料価格は高騰分を、飼料価格は価格安定制度 の仕組みを改め高騰前の価格との差額分に拡大することや、手続きの簡略化を求める声があり ます。使いやすい制度を検討して実施してください。7. 国は 2024 年度中に「保険者による保険証発行の選択制」を導入し、マイナ保険証への切り替 え誘導をおこない「保険証の原則廃止」を目指しています。保険証が原則廃止となればマイナ ンバーカードを持たない人は公的保険診療から遠ざけられる結果となりかねません。マイナン バーカードの取得はあくまでも任意です。マイナンバーカード取得強制につながる「健康保険 証の原則廃止」方針の撤回を国に求めてください。
2022年11月22日
-

穀田恵二衆院国対委員長を迎え演説会
統一地方選挙まで4月と迫る中安曇野市内で穀田恵二衆院国対委員長を迎えて演説会。県下各地から久しぶりに会場いっぱいの参加者。オンライン併用で開かれました。会場には立憲民主党参議院議員の杉尾ひでやさん、社民党県会議員の中川博司さん、信州市民連合共同代表の松本猛さんが激励に来てくださいました。穀田さんは時々ユーモアを交えながらわかりやすく長野県政の問題点や共産党県議団の活躍ぶりを紹介し、今の岸田政権がいかにひどい政権かを語り、長野県から日本を変えていこうと呼びかけました。県議候補の紹介とそれぞれが一人1分のごあいさつ。長野市・上水内郡区の和田あき子さん、山口典久さん、松本市・東筑摩郡区両角ともなりさん、上田・小県郡区の高村京子さん、佐久市・北佐久郡区の藤岡義英さん、飯田市・下伊那郡区の熊谷みかさん、上伊那郡区の瀬戸じゅんさんと私の8人の公認候補、推薦の須坂市。上高井郡区の小林君男さんが挑みます。個性あふれる発言に大きな声援が飛びました。終わって外に出ると雨が降っていましたが、皆さんから暖かい激励をいただきました。さあ、決意新たにがんばろう!
2022年11月20日
-

映画「わが青春つきるとも」伊藤千代子の青春上映会
今日はこの間取り組んできた諏訪市湖南出身の伊藤千代子の映画の自主上映会が岡谷市で開催されます。伊藤千代子は1905年に生まれ、常に生活に苦しむ人々に心をよせ、世の中の矛盾と不公平さを許さず積極的に活動しましたが、治安維持法により、逮捕され24才の若さで短い生涯を閉じました。ロシアがウクライナを侵攻して3ヶ月。戦争だけはさせないために、千代子の生きざまをいまに引き継ぐうえでも期待高まる上映会です。27日午後2時岡谷市カノラホールにぜひおこしください。受け付けで1000円の入場料を払ってご覧いただけます。28日午後2時諏訪市文化センター29日午前10時、午後2時、午後6時30分茅野市新生劇場30日午後2時、午後6時30分下諏訪総合文化センターでも上映いたします。都合のつく会場におでかけください。
2022年05月27日
-

障がいのある人もない人も共に暮らす長野県条例の新設
更新しばらくぶりです。2月議会報告をさせていただきます。1. 「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」案と障がい者施策について【毛利栄子議員】 「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」案と障がい者施策について知事に伺います。 国内の障がい児者数は約936万人、国民の約7.6%とされていますが、国際的には15%以上は何らかの障がいがある人だといわれています。障がい者が長い間、障がいや病気や外傷等から生ずる個人の問題であるとして、自己責任、家族責任を押し付けられ、旧優生保護法下では不妊手術を強制されるなど、いわれなき人権侵害と差別に苦しんできました。 日本が2014年に批准した障害者権利条約は、障がい者は障がいのない人と同様の当たり前の暮らしをするために、あらゆる権利を保障し、支援を行う社会的責任が国や自治体にあることを宣言し、障がい者自身に関わることを障がい者抜きに決めないでとの意思決定過程における障がい当事者の関与が定められています。 知事初当選以来の公約であった障害者差別禁止条例は、関係者の長年の努力の中で、10年余を経てようやく形となって、今議会に提案されていることを心から歓迎します。 振り返れば、阿部知事当選後初の2010年9月議会で、当時の石坂ちほ県議が、当県議団が全国に先駆けて制定した千葉県に調査に行き、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の制定過程や、施行後3年を経ての成果を引き合いに、障がい当事者を加えて幅広く意見を聞きながら、制定してほしいと求めてきた経緯もあります。当時条例を制定していたのは、千葉県と北海道だけでしたが、今では36の都道府県が既に制定しています。 そこで、知事に伺います。今回の条例案は、関係者が大変な努力をされて、まずは差別事案を募集し、さらに社会福祉審議会の専門分科会で検討を重ね、条例骨子案報告書への意見募集を募り、骨子案公表後は、パブリックコメントを取り、現在に至っています。着手から10年、丁寧に取り組んでこられたこの間の経過と、時間をかけた理由についてお聞かせください。また長野県らしさ、知事の思いはどう反映されているのでしょうか。【阿部知事】 私には、「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」案と障がい者施策について何点か御質問を頂戴いたしました。 まず、今回の条例案提案までの経過と時間をかけた理由、長野県らしさや私の思いの反映という御質問であります。御質問にも触れていただいたように、私が最初に知事選挙に立候補させていただくときの基本政策集「信州底力全開宣言」と称していましたけれども、その中で、「障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる条例(仮称)」制定ということを掲げさせていただいたところであります。 その後、当選した後、平成23年度から24年度にかけて、研究会を設けて障がい者差別をなくすための条例の検討を進めてきたところであります。ただその間、国においてその法律制定の動きが本格化してまいりました。そういう意味で、平成25年の6月に障害者差別解消法が成立をし、差別の禁止、あるいは合理的配慮の提供の規定が設けられましたことから、まずは法律の周知、あるいは相談員の配置、こうしたことに取り組んできました。またその後、平成27年度には長野県手話言語条例の制定であったり、あるいは福祉のまちづくり条例の一部改正、こうしたことを通じて、障がいのある方が暮らしやすい社会づくりを進めてきたところであります。 その後、障害者差別解消法の施行から3年も経っても、なお県の相談窓口に対する相談件数が減らないという状況に鑑みて、令和元年度から今回の条例の検討を始めたところであります。実効性のある条例とするため、県民の皆様との意見交換など丁寧に時間をかけて進めてきた結果、このたびの条例案の提案ということにつながったところであります。 法律のほうは、障がい者の生きづらさを解消するという、いわばマイナスをゼロにするという中身になっていますけれども、今回の条例案は、紛争解決の仕組みといったものを盛り込むことと併せて、県として取り組む11の政策分野の方向性を盛り込ませていただいています。いわば生きづらさのマイナスの解消、マイナスをゼロにするということにとどまらず、障がい者の方々の自立と社会参加、プラスにまで持っていくと、こうしたことを目指した条例案になっています。 また、検討の過程では、コミュニケーションの格差、やはり人間として生きていく上でコミュケーションは一番重要だということで、こうした観点での話を多くの方々からお伺いをしました。聴覚、あるいは視覚に障がいがある方の情報へのアクセス、非常に重要な要素だというふうに認識をしておりますし、また、障がいに加えて、例えば女性であるゆえの生きづらさなどの切実な話。これは複合的要因という形になりますけれども、こうした問題意識を承った中で、今回の条例案の基本理念の中にも情報のバリアフリー、あるいは性別や年齢など複合的要因のある障がい者の方への配慮、こうしたことを特徴的に盛り込ませていただいているところであります。 そういう意味では、時間をかけさせていただきましたが、その間当事者の方々の思いも承り、また有識者の方々の御意見をいただく中で、いろいろな観点を盛り込ませていただいたところであります。10年以上前に、私がこうした条例が必要だというところから大変時間が経ってしまって申し訳ないなというふうに思っておりますけれども、ぜひご議決をいただいて、しっかりと適切な運用を行うことによって、障害がある人もない人も、本当に希望を持って生きられる長野県づくりに努めていきたいというふうに思っております。【毛利栄子議員】 条例案では、差別解消のための手立てとして相談体制が規定されています。障がい者が差別されたと感じ、葛藤や悩んだときに、個人の問題として解消されるのではなく、行政が関わって対応してもらえる中に大いなる安心感と信頼があると思います。 そのために現在も相談を受け付けていただいていますが、差別されたと感じた障がい者が気軽に相談ができ、紛争になった場合の対応など、条例の趣旨に沿った役割を十分果たすことができるワンストップの相談センターとしての機能を持ったものにしていただきたいが、いかがでしょうか。【阿部知事】 ワンストップの相談機能についてという御質問であります。平成28年4月の障害者差別解消法の施行に合わせて障がい者差別相談窓口を設けさせていただき、障がいを理由とした差別や合理的配慮に関する相談に対応してきたところであります。今回、条例案の提出に先行する形で、昨年の10月から相談員を増員をさせていただき、相談対応の強化を図らせていただいているとこであります。今回御提案させていただきました条例案におきましては、相談窓口の機能として、必要な助言及び情報の提供、関係者間の調整、関係行政機関への通告・通報等こうしたことを規定をさせていただいたところでございます。 障がいを理由とする差別の解消を図るためには、相談に対応してきめ細かな対応を行い、当事者双方の合意形成を図っていくということが大変重要だというふうに考えています。条例案を御議決いただければ、この障がい者差別相談窓口をワンストップの相談センターとしてより強力に周知をさせていただき、県民、事業者の皆様方が相談できる体制をしっかり整えていきたいというふうに考えております。【毛利栄子議員】 障がい者差別が解消し、障がいのある人もない人も共に生きる人権尊重の長野県にしていくためには、あらゆる差別の禁止や、合理的配慮を行うことは当たり前だという行政や県民、事業者への啓発が重要だと思います。啓発活動をどう行っていくのか伺います。【阿部知事】 障がい者差別の禁止や合理的配慮の啓発についてという御質問であります。私も、多くの皆様方が思いを共有していただくということが大変重要だというふうに考えています。当事者の方々とお話をさせていただき、なかなかの当事者でないと分からない、気づかない、そうしたことも多いなというふうに実感をしているところであります。 今回提案させていただいております条例案は、障がい者が感じている生きづらさの原因は、障がいのない人を前提につくられた社会の仕組みにあり、是正するのは社会の責務であるとする障がいの社会モデルの考え方をベースにさせていただいております。こうした考え方は、ぜひ広げていきたいというふうに思っております。 そのため、庁内連携会議を立ち上げて、健康福祉部のみならず、県職員全体の研修に努めていきたいというふうに思っておりますし、また組織の意識改革を図っていきたいと思ってます。また所管する部局を通じて、県民、事業者皆様にも、こうした条例の考え方や内容の周知を図っていきたいというふうに考えております。 また、障がい当事者の方にも御協力をいただきながら、市町村はもとより、県民、事業者の皆様に対して合理的配慮の具体的事例について周知を図るとともに、優良事業者の認定制度を設けることなどにより民間の優れた取組を広げていきたいというふうに考えております。こうしたことを積み重ねながら、県民の皆様の自主的な取組も促進して、様々な主体が共生社会づくりを進めていただく担い手となるよう後押ししていきたいというふうに考えております。【毛利栄子議員】 条例が制定されれば、県が差別解消や合理的配慮に努めなければならない責務が生じてきます。さしあたって2点について、早急に対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 一つは、同じ福祉医療なのに子どもの医療費は窓口無料となり喜ばれていますが、障がい者の医療費は現物支給となっていません。年金も下げられ、物価の上昇も続く中、継続した治療が不可欠なため、いったん全額払うのは負担、ぜひ窓口無料にしてほしいとの要望も長年いただいていますので、条例制定を契機に、障がい者の医療費も現物支援にしていただきたいが、今後の見通しについて伺いたい。 二つは情報保障の在り方です。条例では、障がいのある人が容易に県政に関する情報を取得することができるようにするため、手話、要約筆記、点字、その他の障がいの特性に応じた意思疎通並びに情報の取得、利用及び発信のための手段を利用して情報を発信するよう努めるものとすると規定されています。和田県議が11月議会で取り上げましたが、知事会見は手話だけではなく、リアルタイムでの字幕表示をすぐにでも実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。【阿部知事】 障がい者の医療費助成の現物給付化についての御質問でございます。福祉医療制度につきましては、医療費の窓口負担を軽減する現物給付を行った場合には、国が国民健康保険の国庫負担金等の減額調整措置、いわゆるペナルティー的措置を講じているところであります。 私もこうした措置はやめてほしいということをずっと言ってきているわけでありますが、いまだに一部残っているわけであります。子どもの医療費の現物給付化については、これも再三、国に働きかけた結果として、平成30年度から未就学児までの医療費助成に対するペナルティーが廃止をされました。その動きを踏まえて、本県では県と市町村とで足並みをそろえて、子育て支援、少子化対策を一層推進するための観点で、中学校卒業まで、これは一部ペナルティーがかかっている部分も含めて、広めに現物給付化を実施をさせたところであります。従ってペナルティー分はまだ県民の皆様の税負担で賄わせていただいているという現状が続いているわけであります。 一方で、この障がい者の医療費助成については、依然としてペナルティー措置がそのままかかり続けているという状況であります。国に対しては、引き続き全ての年齢を対象としてこのペナルティーの廃止を強く求めていきたいというふうに思いますし、また国レベルでの社会保障として、この医療費助成制度、子ども医療費助成はもう全ての県が行っていますので、もう国の制度としてぜひ創設すべきだということも引き続き求めていきたいというふうに考えております。 現物給付化を行うことによって、その利用者の自主的な負担は変わらないですけれども、県としての負担が変わってしまうということでありますので、そういう意味で、まずは国の対処をしっかり求めていきたいというふうに考えております。 続きまして、知事会見のリアルタイム字幕表示の実施についてという御質問であります。平成31年の4月の会見から手話通訳を導入をさせていただいておりますが、中途失聴者など手話を理解できない方々もいらっしゃいますので、字幕表示等を行うことの必要性については私どもも認識をしているところであります。 新型コロナの感染拡大防止への協力のお願いなど、収録して行う映像については、手話通訳と字幕を挿入し配信等を行っているとこるでありますが、会見、私の会見のようにリアルタイムで配信するものの字幕表示については、正確性を確保するため、今の時点でまだ実現できてないという状況であります。 これちょっと私の話し方を音声認識アプリでやると、少し誤変換したりするということもあります。また正確な表記を、例えば要約筆記を行っていただく上では、私の発言メモを事前に提供するというようなことで対応することも可能ではありますけれども、ほとんど私の会見は時前の原稿なしで行わせていただいているということもあって、なかなか課題がたくさんあるなというのが今の認識であります。今後様々な手法の検証を行いながら、導入の可能性について検討していきたいというふうに考えております。以上です。【毛利栄子議員】 私の障がい者に係る質問の肝は、二つの最後の要望の実現ということだったのですけれども、障がい者医療費の現物給付に対しては、国のペナルティーがあるということなどの理由を挙げられて、まだまだ時間がかかるということを実感いたしました。とても残念に思います。障がい者の立場に立った施策として、1日も早く実現できることを求めます。2. 教員のわいせつ事案に対する県教委の対応について【毛利栄子議員】 続いて、教員のわいせつ事案に対する県教委の対応について教育長に伺います。暮れに検証結果が報告された教員のわいせつ事案に対し、校長や対応した県教委の認識があまりに一般社会の認識とかけ離れていることに驚きました。 そもそも生徒と車に乗って日帰り温泉施設に行くこと自体尋常ではないし、耳たぶを触ったり手を握ったりすること自体、セクハラ、わいせつ行為です。県教委に報告もせず、事件をもみ消そうとした校長の対応は全く不適切であり言語道断ですが、報告を受けた県教委の対応も、平成18年以来、「懲戒処分等の指針」を策定し、平成25年からは「非違行為に係る公表ガイドライン」を運用、平成28年からは、「わいせつな行為根絶のための特別対策」を講じ、信州教育の信頼回復に向けて対応してきていただいているにもかかわらず、わいせつ事案だとの認識や受け止めもなく、生徒と教員を引き離すために退職か休職を勧めるなどとんでもない指導であり、厳しい自己分析が求められます。 そもそも県教委の中に通報相談窓口があるのに、通報した教員は、教育に関わることをなぜ総務部のコンプライアンス行政経営課に相談したのか。県教委に相談してもまともに取り扱ってもらえないと判断したのではないかと思わざるを得ません。 その後の新聞報道によれば、3月末まで療養休暇を取り退職した教諭は、4月から私立の学校に再就職し、事件が社会問題化した昨年12月に辞職したとのことです。事案をまともに対応しなかったことで、教諭は何の処分も受けず、知らずに就職させた私立高校は、そのまま在職していれば生徒が同じような被害に遭っていたかもしれないことを考えれば、県教委の指導には重大な落ち度があったと思います。 そこで伺います。教育長は今回の一連の出来事に対し、当時から継続して関わっていた唯一の教育行政のトップとして、どう責任を感じ、どのような見解をお持ちですか。通報した教員は、教育委員会幹部がわいせつ行為を行った学校の関係者であったために隠蔽が行われたのではないかと訴えているようですが、教委の隠蔽疑惑に関して報告書は触れていません。見解をお伺います。【原山教育長】 教員のわいせつ事案に対する県教委の対応についての御質問でございます。 まず、今回の事案の責任と見解についてというお尋ねでございます。このようなわいせつな行為を教員が行ったこと、そしてその事実を校長や教育委員会事務局職員が把握しながら、処分せずにそのまま退職させるに至ったことは、長野県教育の信頼の根幹に関わる重大な事態であり、特に直属の部下である当時の高校教育課長を処分することになったことは、教育長としての責任を痛感しているところでございます。本事案により被害に遭われた生徒及び保護者、県民の皆様に対し、改めて心からお詫びを申しあげます。 教育委員会の隠蔽の疑惑に関しての見解でございます。今回の事案において、当時の高校教育課では、元教諭の行為がわいせつな行為に当たらないと判断し、その後の事案の対応を進めたものであり、議員御指摘のような隠蔽は行われていないものと認識しております。また、当時の高校教育課職員に対する聞き取りの中で、学校の関係者であったことがわいせつな行為の判断に影響したということはないとの確認をしているところでございます。【毛利栄子議員】 当時の高校教育課長は、減給10分の1、3ヶ月、校長は10分の1、2か月の処分を受けました。教育長は特別職のため処分対象にはなりませんでしたが、自主返納とのことで、給料の10分の1、3か月との対応を取られました。減給処分となった2人の処分理由について伺うとともに、自主返納の返納割合と月数を、元高校教育課長と同じにした理由について伺います。【原山教育長】 当時の高校教育課長、校長の処分理由についてでございます。高校教育課長については、元教諭のわいせつな言動について、高校教育課の部下職員に事案の内容を詳しく把握し、必要な調査等を行うよう命じることなく、わいせつな行為等とまでは至らない内容であると認識し判断を誤ったこと。その結果、当該教諭に対する懲戒処分等を行うことができた立場にもかかわらず、当該教諭が定年退職し、懲戒処分等が行われないという事態を招いた。これにより長野県教育への信頼を大きく失墜させたことから、不適正な事務処理を理由に処分したところでございます。 校長については、当該教諭の行為を把握した際、県教育委員会で報告すべきものであったにもかかわらず、保護者から申し立てがあるまで報告を行わなかったこと、さらに当該教諭による被害生徒への詳細な発言内容について報告しなかったこと。これらのことから非違行為の隠蔽に当たると捉え、処分したところであります。 私の自主返納を高校教育課長と同じとした理由であります。今回直属の部下である当時の高校教育課長の誤った判断によりこのような事態を招いたことは、私の管理監督責任であり、自らの判断で自主返納を行うことといたしました。その額や期間については、私自身が管理監督責任の重さを熟慮し、その結果として今回の自主返納をさせていただいたところでございます。【毛利栄子議員】 検証結果報告書では、性暴力根絶のための対策が示され、中でもわいせつな行為について、昨年6月に公表された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」の目的を引用しながら、児童生徒の尊厳や権利を擁護するという基本認識が徹底されていなかったことを挙げています。 性暴力に対する考え方は、刑法の性犯罪に対する改正や当事者が勇気を持って声を上げることで、日々変化しています。その変化に県教委の時宜を得た対応ができているのか疑問に思わざるを得ません。生徒はどんなに人権を傷つけられ、恐怖を感じ、その後の生活の中でトラウマを引きずりながら苦しい生活をしているのかと思うと、取り返しがつかない思いです。 教職員によるわいせつ事案が後を絶たない中で、現場の教職員への研修や啓発の必要性は当然ですが、私は今回の事案を踏まえ、県教委事務局や教育事務所など指導的立場にある部署が私ごととして捉え、性暴力に対する子どもの権利を主体とした厳格な捉え直しをすることがまず大事だと思いますが、見解を伺います。 さらに、県教委事務局として、今回の事案を踏まえ、身内が身内を調査するのではなく、客観性を持たせるために、調査段階から第三者を加えて対応すること、さらに、今後同様の対応を絶対に起こさないための再発防止策と決意について伺います。【原山教育長】 指導的立場にある部署における性暴力の捉え直しについてであります。今回の事案を検証する中で、県教育委員会の組織の中での生徒の人権に対する意識の希薄さを痛感したところでございます。今後は、県教育委員会事務局や教育事務所の全ての職員が、児童生徒への性暴力は児童生徒に対する人権侵害であるという認識を共有し、自分のこととして根絶に取り組む必要があるというふうに考えております。 第三者を含めた調査についてでありますが、今回の調査結果報告を踏まえて、児童生徒への性暴力事案を調査するに当たりましては、児童生徒への聞き取りに当たって、必要に応じスクールカウンセラー等の専門家に聞き取りを依頼し事実確認を行うこと。被害を訴えた行為が性暴力等に該当するかの判断に当たっては、コンプライアンスアドバイザーの協力を得るといった、調査や判断に客観性を持たせるための第三者の関与の仕組みなどを構築したところでございます。 今後の再発防止策につきましては、今後同様の対応を絶対に起こさないため、児童生徒が上げた声が担当課にとどまることなく、私を含めた関係者に確実に伝わるような情報伝達のプロセスを構築すること。児童生徒、保護者及び教職員が、学校を通さずに直接通報できる窓口の周知といった取組を行ってまいりたいと思います。 再発防止に向けた決意についてでありますが、児童生徒への性暴力は、児童生徒に対する人権侵害であるという意識を徹底するとともに、再発防止の仕組みを確実に運用し、二度とこのようなことが起こらないよう、県教育委員会全体で取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。【毛利栄子議員】 フランスの詩人、ルイ・アラゴンの名言の中に「学ぶとは心に誠実を刻むこと。教えるとは共に希望を語ること」があることはあまりに有名ですが、この言葉は時代を経てもなお、真実をもって迫ってきます。教師と子どもということで、子ども権利を主体として捉えるのではなく、教えてやる対象、管理の対象として捉える子ども観から脱却し、魂の殺人と言われる性暴力が一日も早く教育現場からなくなり、とかく閉鎖的と言われがちな教育委員会が風通しの良いものになることを願って、質問を終わります。
2022年03月16日
-

福祉灯油の実施を リニアの工事は中止を 特別支援学校の環境改善をと一般質問
12月2日議会一般質問を行いました。持ち時間14分。要旨を報告します。✽✽生活困窮者への光熱費補助について✽✽ 毛利 世界的な原油の高騰により、日本でもガソリン、灯油の値上が りや食料品などにも影響が出ている。県内で福祉灯油を実施する自治 体が広がりつつあり、国では実施自治体に対し特別交付税で措置する との方向を示した。なかなか実施に踏みだ出せないでいる自治体を後 押しするためにも、県として生活困窮者に対し、光熱費の補助を実施する自治体に半額 を負担するなど、積極的な支援策を講じていただきたい。健康福祉康部長市町村において支援の必要性を判断してもらうことになるが、実施する 場合は今回の特別交付税措置を活用できるため、実施の後押しになると考える。県とし ては、今後示される国からのこの措置に関する情報を市町村に速やかに提供する。 ✽✽リニア中央新幹線工事について✽✽ 毛利 豊丘村の伊那山地トンネル坂島工区で 11/8 に発生した崩落事故について、事故 連絡が遅く、範囲も狭いことはいかがかと思う。県の見解と対応は。 リニア整備推進局長 連絡すべき事故の種類や程度、連絡する市町村の範囲が明確に定 められていなかったことが原因と考える。JR 東海に対し連絡体制を見直すよう要請し改 善が図られた。今後も新たな連絡体制に基づき市町村への速やかな情報提供を求める。毛利 坂島工区における事故原因の調査も再発防止対策もできていない中で、どんどん 工事を進めることは作業員を命の危険にさらすことであり、原因究明と再発防止対策が 明確になるまで、県内の全ての工事は中止するよう JR に求めていただきたい。 知事 工事を中断している坂島工区への対応も含めて、JR 東海に対してどのような要請 が必要か、報告内容を十分に精査した上で検討していきたい。 ✽✽特別支援学校の環境改善について✽✽ 毛利 校舎の老朽化や教室不足、長時間にわたる通学をはじめとして各学校の差し迫っ た現状や声にどう応え、新年度具体的にどう着手するのか。新たな設置基準に応えるた めには分校や分教室ではなく、新設校が必要ではないか。 教育長 現在築年数や劣化状況から、早急な対応が必要な松本養護学校と若槻養護学校 については検討懇談会を開催し、保護者や関係者等からご意見いただき、学びのあり方 と環境整備に検討を重ねてきた。できるだけ早期 の環境整備に努めていく。長時間通学者の解消は 丁寧にニーズを把握の上、必要な対応に努める。 今後の児童生徒数の推移を見極め、まずは設置基 準を満たした整備を進める方策を検討していく。
2021年12月02日
-

高校生のタブレット購入への助成を!
議会文教委員会があり①町田市のネットでの小6女児のいじめ書き込み自殺事件に触れてセキュリテイ対策と情報リテラシー教育の重要性②来年度の高校入学生から全員がBYOD(自前のタブレット用意)に移行することに伴い公費助成を③8月の豪雨災害で破損した大桑村の薬師堂の改修に県費補助の充実をの3点を質問しました。長野県では持ち帰りタブレットに対し99%独自のIDとパスワードを入れるよう対応している、子どもや保護者対象に情報リテラシーをわかりやすく実践している県下の優れた事例を紹介し、普及している。BYODは学校徴収金などの負担軽減で対応する努力を行っている。自分のタブレットがあった方が使い勝手が良い、薬師堂の本格復旧はまだだが、かかる費用の半分を補助できるよう対応したいとの答弁がありました。
2021年10月05日
-
一般質問で取り上げた内容のご紹介
1、8月豪雨災害について建設部長及び危機管理部長に伺います。8月の前線豪雨並びに9月5日の大雨による災害で亡くなられた方々に心からお悔やみ申し上げますとともに被災されたすべての皆さんにお見舞い申しあげます。また、対応された行政関係者、消防団、建設業者、地域の方々やボランティアの皆さんに感謝申し上げます。8月前線豪雨はとりわけ諏訪、上伊那、木曽地域に甚大な被害をもたらしました。9月5日には茅野市高部の下馬沢川で土石流災害が発生し、大規模な被害が起こっています。わずか1か月の間にこのような大災害が同じ諏訪地域でおこることはかつてなかったことであり、気候危機のすさまじさを感じています。 (1)8月13日から15日までの岡谷市の総雨量は350mm。特に8月14日は深夜3時から4時の時間雨量が44mmとなり、早朝5時29分、川岸駅前の渓流「中大久保沢」で土石流が発生し、母子3人がなくなるという大変痛ましい事件となりました。現場は土石流警戒区域に指定はされていたものの、普段は水も流れていない小さな沢での出来事であり、近隣住民の皆さんは「まさかこんなところで土石流が起こるとは思わなかった」「早朝ドーンと大きな音がしたのでビックリして飛び起きてみたら向かいの家に土砂が流れ込んでいた」と突然の出来事に驚いています。すでに諏訪建設事務所に対応いただき応急復旧はされていますが、依然として避難指示は発令されたままです。土石流の原因と隣の「大久保沢」を含め、今後の本格復旧の見通しについて建設部長に伺います。 (2)今回の土石流は平成18年湊及び橋原の死者8人を出した同じ西山地域で起きており、小田井沢川や本沢川も同じように今回も荒れており、当時設置していただいた砂防堰堤は山腹崩壊による流木と土砂で完全に埋まっていて、もしこの堰堤がなければ再び惨事に巻き込まれたのではないかとゾッとする状況です。危険な渓流や沢は数えきれないほどありますが、岡谷市では平成18年の災害以前はたった4基だった砂防堰堤でしたが、災害復旧や下流域に保全施設がある地域を優先的に対策し、現在は40基の砂防堰堤があるそうです。これから台風シーズンにもなり、地域の皆さんは安全に過ごせるか心配し、堆積土砂の撤去を切望しています。優先順位を考えながら堰堤にたまった土砂のしゅんせつをしていただいて機能回復を図っていただきたいがいかがでしょうか。また、県下にたくさんある堰堤も同じような状況かと思いますが点検体制と適切なしゅんせつが必要だと思いますが対応について伺います。 (3)次に大きく陥没し、通行止めが続いている国道142号線について伺います。ここも「大久保川」に大量の水が流れ込み、横断する道路下部を洗堀して土砂が大量に流れ、周辺の約40件に避難指示が出されました。道路には直径30センチの水道管や下水道管が通っており、かろうじて破損しなかったことが不幸中の幸いだったと町長も語っています。現在は不安定な土を取り除きブルーシートがかけられたままになっていますが、道路陥没の原因と復旧の見通しについて伺います。 近隣住民の皆さんのお話ではこの川は平成18年の豪雨災害の時にも氾濫し「また今度も同じように荒れた。繰り返さないように抜本的な対策をとって欲しい」と口々に言っておられます。道路の復旧とともに雨が降れば安心して寝られないという「大久保川」上流部の抜本的な治水対策を住民の皆さんの意見などもよく聞きながら図っていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 (4)今回県下の被災された皆さんに対し国の生活再建支援法の対象にならない方々に対して「信州被災者生活再建支援事業」で救済するための補正予算が盛られていることは歓迎します。しかし、被災地を回って要望いただいたことは住宅は損壊しなかったが、土砂が敷地内に入りこむことによってエアコンの室外機や給湯器などが使えなくなったが買い替えには費用がかさむため支援はあるかということでした。これらに関する公的支援はあるのでしょうか。見舞金や民間の保険だけでは救済されない場合もあり、今後何らかの支援策を検討する必要があると思いますが危機管理部長の見解をうかがいます。 (5)土砂災害や洪水の危険性に対し、命や財産を守るためにはハード面の対策とともにソフト面での対策の重要性を改めて認識しているところです。各地で防災ガイドやハザードマップなどがつくられています。いったんは全戸に配っていてもなかなか日常的に自分たちの住んでいる地域がどんな状況にあるのか、自覚することが少ないと思われます。犠牲者を一人も出さなかった茅野市高部の住民の取り組みは今後大いに教訓としなければならないと思いますが、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、浸水区域などハザードマップの住民への啓発や周知、防災や減災への備えについて伺います。 (6)次に避難所の環境改善についてうかがいます。 被災された方々は学校体育館や公民館、地域コミュニテイ施設、提携する旅館などに避難されておりました。不安を抱えながらの避難生活。簡易テントなどが入り、プライバシーは守れたものの冷たい床にシート1枚、毛布1枚ではつらい、食事も弁当やインスタントなので温かいものが食べたい、中には弁当は自分で買って食べている、毛布も自分でもってきたという声も聴かれました。TKB(トイレ、食事、ベッド)を中心に避難所の環境改善のため県では「避難所運営マニュアル策定指針」を示し、市町村と取り組みを進めています。しかしまだまだ県下をみても地域ごとにアンバランスがあり、避難所の環境改善の取り組みには課題があると痛感しています。いっそう市町村と認識を共有して避難所の環境改善を進めていただくこと、簡易テントや段ボールベッドなど備蓄に対する支援、さらには高齢者等避難指示が出ても要配慮者は体育館等には避難できないとの声も聞かれます。要配慮者への避難のあり方についても伺います。 2、国道20号諏訪バイパスについて建設部長に伺います。 半世紀前に一旦とん挫した国道20号諏訪バイパスですが平成28年11月に山側ルート案が示されて以降環境アセスが都市計画変更手続きと併行して進められています。準備書への住民意見は261通提出され関心の高さが伺えます。具体的な中身が明らかになりバイパスの姿が見えてくるにつれ住民から不安の声があげられ、県の技術委員会でも議論が重ねられていますが、いくつかの点について部長に伺います。(1)諏訪バイパスは8割方トンネル掘削する計画ですが、温泉・湧水、水源や諏訪5蔵、植生など環境面への影響はないかとの不安が広がっています。下諏訪町の6月議会では下諏訪温泉旅館組合、慈雲寺、諏訪大社が「町民の意見を反映し自然環境を保持するよう求める陳情」を提出し、全会一致採択されています。町長も議会で「住民の声を聞き、不安や疑問を解消したうえで進めることが大切」と答弁されています。住民からの不安や疑問にどのように対応されていくのかご所見をお聞かせください。 (2)事業地一体を長年研究対象としてきた信州大学名誉教授の小坂共栄(ともよし)先生から知事や技術委員会に要望書が提出されています。ここでは調査が著しく不十分でトンネル掘削する地域が、過去に長地トンネル、湖北トンネル、塩嶺トンネルと大規模な出水事故や陥没事故があったことに触れ、不十分な水質データによって「掘削による温泉源泉への影響は軽微である」と結論付けていることに対して根拠薄弱だと指摘、また、準備書では地質に関する調査がたった2日間だけであり、ほぼ文献調査で済ませいるのは論外だと厳しく指摘しています。 先生はトンネル掘削による影響評価を実施するためには地質学的な調査とともに水理地質学的な調査を長期間にわたって実施・観測することが必要だと述べています。温泉や酒造りに影響が出て観光や経済活動にダメージが生じたり、また陥没事故などが起こり近隣に土砂などが入って被害が出てからではとり返しが付きません。専門家の指摘にどう答えていくのか県の姿勢も問われます。見解を伺います。 (3)今回の豪雨による土石流災害をみても、中央構造線と糸魚川静岡構造線が交わる地域の断層に沿って計画がされていることに「安全性は大丈夫か」との声も聞かれます。特に明かり部になっている下諏訪町高木の大沢川や津島公園一帯は土砂災害警戒区域になっており、8月の豪雨で大規模な土砂崩落がおきた場所でもあります。安全性についての検証をどう行うのか伺います。 (4)掘削工事による建設発生土は約150万㎥と予測し、うち21万㎥を盛土材として再利用し、残りの129万㎥を区域外へ搬出するとされています。住民の皆さんの中でも発生土をどこにもっていくのか、工事用車両の交通量はどの位なのか、アクセス道路が狭いのに安全性は保たれるのかと心配の声が上がっていますが準備書には記載がありません。発生土の搬出先や運搬するトラックの台数などはどうなっているのか伺います。 100年に一度どころか19号台風、去年の7月豪雨、今年の災害と毎年のように大規模な災害が起こり、その大きな原因に気候変動が挙げられています。災害への備えや復旧・復興とともに気候危機に対する本気の取り組みは待ったなしです。長野県は2030年までに10年比で二酸化炭素を60%削減する野心的な目標を掲げています。その達成のために覚悟をもってともに県民運動を盛り上げることを呼び掛けたいと思います。 諏訪バイパスを心配する皆さんは植生や地質や水源問題など自分たちの問題であるとともにこれからの子どもたちにとって本当に住みよい地域になるために何が大事かと真剣に学習を重ねています。この声に真摯に耳を傾けていただきたいことを重ねて求めます。 3、次に新型コロナウイルス感染症対策についてこども若者局長及び健康福祉部長に伺います。(1)年末年始を控え第6波が懸念されます。ワクチン接種が進み、社会全体に免疫力が広がることが期待されますが、ワクチン接種対象外の10歳未満の陽性確認や若年者の多いのが5波デルタ株の特徴です。一日当たりの感染者数に占める10歳未満の子どもの割合は8月平均は7.6%でしたが9月は保育所などで集団感染が発生し比率が4割近い日もありました。未来ある子ども達を感染から守らなければなりません。保育所や児童館、児童センター、学童クラブなど密にならざるを得ない環境下で子ども達を感染から守るための取り組みをどのように実施しているのか伺います。国で児童福祉施設に簡易検査キットを配るとされていますがその事業内容と必要数が配られているのか伺います。保育園に配るだけでなく、園を通じて家庭にキットを配布し子どもの場合家庭内感染が主なので不安があればまず自主検査を迅速にやっていただき早期発見に努めていただきたいがいかがでしょうか。 (2)抗体カクテル療法の実施体制が整えられつつあることは歓迎しますが、あまり経験したことのない治療法のために医療機関に戸惑いもあり研修の要望もあります。県内30の医療機関で実施できる体制を整えているとのことですが保健所などが主導して研修の機会を設けるなど丁寧な取り組みを進めていただきたいがいかがですか。 (3)これから冬に向かいコロナとともに、風邪や季節性インフルエンザに対する対応など発熱外来の利用がいっそう増加してくると見込まれます。昨年度は「発熱患者等診療体制確保事業」が実施され、検査に対する補助などがありましたが、今年度は予定されておりません。RSウイルスの流行もあり発熱によって医療機関を受診する小児も増加してきていますが、このままでは医療機関の持ち出しとなり経営の圧迫が懸念されます。長引くコロナ対応で医療関係者は疲弊しており「使命感だけではやっていけない」と悲鳴が上がっています。第6波を見据え初期対応として重要な事業なのでせめて昨年同様実施できるよう県としての財政支援を求めますがいかがですか。小さい子供たちはしばしば発熱します。マスクもつけられず保護者や保育者と密も避けられない環境下で神経を使って保育していただいています。無償の検査キット配布は必要だと重ねて申し上げ質問を終わります。
2021年10月01日
-

9月議会で一般質問
一般質問で①8月豪雨災害について②国道20号諏訪バイパスについて③新型コロナ感染症対策について質問させていただきました。詳細は後日答弁とともにアップさせていただきます。
2021年09月29日
-
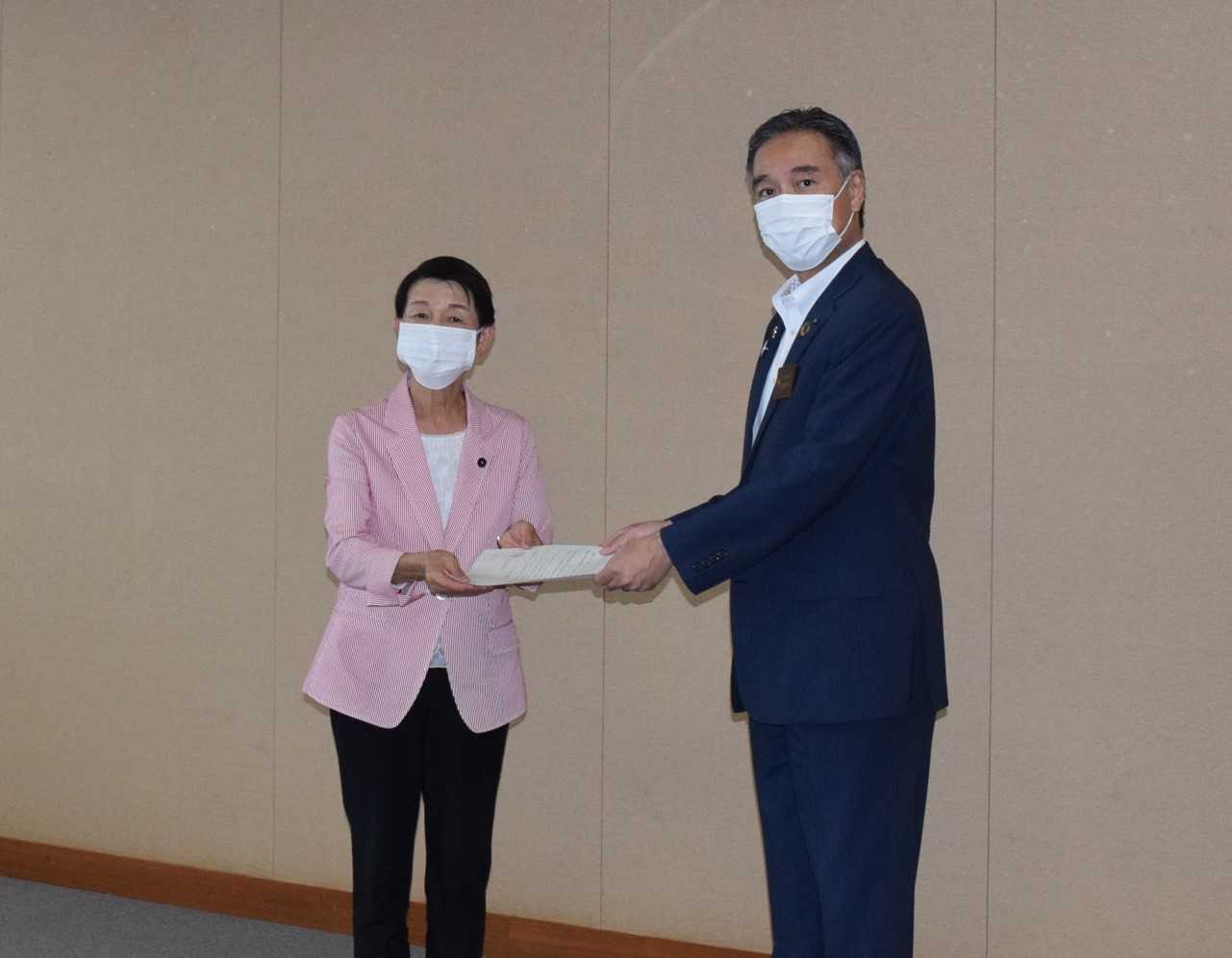
切実な要望を知事申し入れ
9月県議会にむけた申し入れ 1、コロナ感染が急増し医療体制がひっ迫、自宅療養者が増えています。自宅療養者への 連絡や健康観察、食事提供など万全のフォロー体制をとってください。 2、 感染者の早期発見・保護のために、県が地域と期限を限定して実施している社会的検 査の対象をさらに拡充し、全県的な大規模検査を実施してください。 3、 限られた医療資源を最も効果的に活用するために、感染拡大の最大時に対応できる臨 時の医療機関設置を準備してください。 4、飲食業などへの営業時間の短縮・休業協力金は、経営が限界に達している事業者にし っかり支援が届くように増額してください。また、国に家賃補助支援金や持続化給付 金の再支給を求めてください。 5、 国の制度の対象外になった事業者への「新型コロナ中小企業者等特別応援金支給事業」 については、さらに対象期間が延長され額も倍になったことは歓迎しますが、減収率 の条件を3割程度に引き下げて事業者を支援してください。 6、 児童に感染が広がっているなか、放課後児童健全育成事業が安全に行われるように従 事者や利用者の抗原検査などを行うとともに、学校の空き教室の活用などで密を解消 する方策を市町村と検討してください。 7、 先ごろの大雨・豪雨により県内でも尊い人命が失われ、道路や河川の決壊、床上・床 下浸水や林地、農地の崩壊などが多発しました。危険カ所の点検の実施、堰堤の浚渫 など早期の対策や住民への情報提供などの改善が求められています。また、災害復旧 は原状回復だけでなく地元住民の声をしっかり聞いて改良復旧をすすめてください。 激甚災害指定の要望が出ている自治体に対し指定が可能となるよう支援をしてくだ さい。 8、 今回の災害では「コロナ感染が心配で避難所に行けなかった」という声や、毛布1枚 では寝られない、温かいものが食べたいなど避難所環境についても要望が出されてい ます。市町村に運営ガイドラインを徹底するとともに、力を合わせて避難所の設置・ 運営の改善、見直しを進めてください。また県・市町村の避難所の備蓄品の拡充に取 り組んでください。 9、 コロナ禍で貧困の広がりが深刻です。県の生活困窮者への食料支援を強化するととも に、各種団体の支援活動が十分に成果を上げられるように団体からの聞き取りを行っ て支援を強めてください。
2021年09月21日
-

東京都議選で19議席に躍進
昨夜は東京都議選の投開票日。結果に釘付け。テレビやネットで様子をさぐっていたら大田区で藤田りょうこさんがトップ当選。長野県も応援した新宿区の大山とも子さんもトップ当選と嬉しいニュースが飛び込んできました。2人区の文京区と日野市で新人の福手ゆう子さんと清水とし子さんも激戦を制して野党と市民の共闘で見事当選。改選18議席から19議席へと躍進。衆院選に向けてはずみが付きました。素晴らしい。
2021年07月05日
-
6月議会でオリンピックの中止や再延期の検討を求め意見書提案
7月23日から東京オリンピック、パラリンピックが始まろうとしています。しかし、東京では再び感染が広がり、全国的に人流がおこればまたパンデミックになり命の危険にさらされることになります。長野県議会として再検討を求める意見書提案をさせていただきましたが、残念ながら否決となってしまいました。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の 開催について再検討を求める意見書提案説明 2021・6・25 もうり栄子 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催がまぢかに迫っています。 18日、政府のコロナ対策分科会の尾身茂会長など26人の専門家が、5輪に よって感染リスクが増える危険を強く警告し、リスクを直視して「無観客が望 ましい」と提言していたにも関わらず菅義偉政権はじめ開催者側はあくまで「観 客あり」にこだわり1会場1万人を上限に1日20万人の観客を入れての開催 を決定しました。 60万人動員予定の児童・生徒たちによる「学校連携観戦」、IOC やスポン サー関係者などは観客ではないとして上限とは別枠で入場させるといいます。 東京都医師会長の尾崎治夫氏は「東京の感染状況は改善されておらずリバウ ンドの兆しがはっきりと見えている。この状況で1か月後の 5 輪に観客を入れ て人流を増やせばさらに感染者は増えそのしわ寄せは医療に来る」と無観客や 中止の検討を求める意見書を組織委員会などに送っています。 厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」では国立感染症研究所な どの専門家がインドで見つかった変異株の広がりによっては7月前半か5輪期 間中にも東京でまた「緊急事態宣言」が必要になる可能性があるとの見通しを 示しています。 専門家の科学に基づく提言を無視して、5輪期間中多くの人が東京を中心に 国内を動きまわれば感染症対策にとって最も重要な「人の流れを極力抑制する」 とは正反対の状況となり、5輪の名のもとに世界と国民の命をいっそう感染リ スクにさらすことになります。 いまさらどうにもならないと思う向きもあるかもしれません。しかし、オリ ンピック・パラリンピックの開催は自然災害とは違い人間が行うイベントであ り、どうするかも人間が決めることです。共同通信社の世論調査でも開催によ り感染が拡大する不安を感じるとの回答が86、7%に上りました。 国会及び政府は「開催ありき」「観客ありき」でなく国民の声に真摯に耳を 傾け、国民の命と暮らしが脅かされることのないよう今こそ中止や延期を含め た再検討の決断をするべきと申し上げ議員各位のご賛同をお願いし、提案説明 とさせていただきます
2021年06月25日
-

県立美術館4月10日いよいよオープン 見学に
県立美術館が4月10日、長野市城山の善光寺隣りにオープンします。今日は議会の合間に、団の皆さんで現地見学。白をコンセプトにガラスをふんだんに取り入れ、採光もよく県産材をたくさん使ってあります。オープンテラスなども広くとってあり、善光寺はもちろん周囲の山々が眺望できます。美術館を身近に利用していただくとともに、ホットスペースとしても多くの方に無料で楽しんで利用していただける施設です。オープンイベントなども用意されるので機会を見て是非どうぞ。東山魁夷館ともつながっています。
2021年03月15日
-

2月議会で一般質問させていただきました
おはようございます。新型コロナウイルスで亡くなられた方々に、心からお悔やみ申し上げます。また、罹患された皆さんにお見舞いを申し上げます。 東京五輪について知事に伺います。 3月末から聖火リレーもスタートし、長野県でもホストタウンの準備は待ったなしです。女性蔑視発言での組織委員会会長交代騒動や、世界的に新型コロナが収まらない中で、開催の判断が迫られています。国民世論の8割以上は、「中止」、または「延期」です。ワクチン接種も始まりましたが、国における格差も起きており、フェアな大会ができるか心配です。 国においては五輪開催ありきでなく、立ち止まってゼロベースから開催の可否を早急に再検討すべきではないかと考えますが、1998年、70の国・地域から集まり、3万2,000人のボランティアが大会を支える中で、感動的な長野冬季五輪を成功させた長野県として、阿部知事の見解を伺います。【知事】毛利議員のご質問に順次お答え申し上げたいと思います。 まず、東京オリンピックについてのご質問であります。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、大会の成功に向けて、これまで大変長い間、組織委員会、東京都、政府をはじめ、多くの関係者の皆様方が大変なご努力を重ねてきていただいていることに、まずは敬意を表したいと思います。 今、日本のみならず、世界中が新型コロナウイルスと闘っている状況であります。そういう意味で、今回の大会実施を進めていく上で前提となるのは、やはり、この新型コロナウイルス感染症に対して、国民はもとより、世界の国々が理解していただけるような対策を講じていくということが重要だというふうに考えています。 今、アスリートの皆さんはもとより、ボランティアの皆さんをはじめ、多くの方たちがこのオリンピック・パラリンピックの行方に注目をしているという状況であります。関係者の皆様方には、ぜひオープンな議論を行っていただき、そして、多くの皆さんが納得し、共感できる対応策を見いだすべく最善を尽くしていただきたいというふうに考えております。新年度施策について【毛利栄子議員】◆毛利議員 11月議会で山口議員が、新年度予算はコロナ禍の下で財政難の中でも命を守る手厚いケアが保障される長野県づくりが大切、医療・介護・福祉施策の抜本的強化と、働く皆さんの待遇改善を求めました。知事は、命を守り育む県づくりをしあわせ信州創造プランに掲げており、医療・介護体制の充実や働いている人への支援は喫緊の課題であると答えています。新年度予算と施策にどのように反映されたのか。健康福祉部長に伺います。 【健康福祉部長】 医療・介護分野における新年度の予算、施策についてのお尋ねでございます。 新型コロナが医療・介護分野に深刻な影響を及ぼす中で、来年度当初予算においては県民の命と健康を守り抜くとの強い決意の下、関係施策を構築しているところでございます。 まず、目下の最重要課題である新型コロナ対策につきましては、入院病床や宿泊施設の充実強化により県民が安心して療養できる体制を確保するほか、医療・介護現場で働く人を支える施策として、最前線で対応に当たる医療従事者の特殊勤務手当への助成や、医療・福祉施設の応援職員派遣に対する支援などに取り組んでまいります。 また、アフターコロナを見据えた中長期的な観点からは、信州回帰の流れを追い風に、医師、看護職員の確保や、偏在是正、介護人材の誘致・定着に努めますとともに、しあわせ信州創造プラン2.0の着実な推進に向けて、医療機能の分化・連携に資する施設整備補助、地域包括ケア体制の構築のための市町村支援などに取り組むこととしております。 施策や各事業の目的を職員としっかりと共有をし、着実な成果を上げることができるよう取り組んでまいります。 以上でございます。【毛利栄子議員】◆毛利議員 この1年余、県下の公立・公的病院はコロナ入院患者の大半を受け入れ、使命感に燃えて献身的に診療に当たってくださいました。しかし、この期に及んでも、国は公的・公立病院の統廃合の加速化を推し進めようとしています。国の統廃合計画は県民の命を切り捨てることにつながり、絶対に容認できません。改めて、知事の認識と決意を伺います。 【知事】 続きまして、公立・公的病院の統合に関する認識と決意についてというご質問であります。 公立・公的病院の皆さんにも、今回のコロナ対応には本当に大きな役割を果たしてきていただいているというふうに考えております。厚生労働省が行った公立・公的医療機関等の再検証における分析、これはこの場でも申し上げてきていると思いますけれども、急性期機能に限定されたものでありまして、地域の実情には必ずしもそぐわないものというふうに受け止めています。 そのため、県としては、これまでも国に対して県民生活を支える一次医療や、回復期、慢性期機能等を再検証の観点に入れることなどを要望してきているところであります。この点につきましては、国においても、分析結果は急性期機能に着目して診療実績等のデータを分析したものであり、今回の分析だけでは判断し得ない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら、地域において議論してほしいというふうにしているところであります。 県としては、少子高齢社会が急速に進展する中で、限られた医療資源の有効活用を図り、医療ニーズの変化に対応した医療提供体制を構築していくことが重要だというふうに考えております。そのため、公立・公的病院が担う幅広い医療機能や地域の実情等を踏まえながら、医療機関の役割分担と連携強化が進められるように、医療圏ごとに地域の関係者間での丁寧な議論が行われるよう促してまいりたいと考えております。【毛利栄子議員】◆毛利議員 コロナ禍で、困っている人にどう寄り添うかが一層鮮明になりました。新年度事業として、環境部が食品ロス削減のためフードバンクの推進を掲げました。既に社協や民間団体が実施し、生活困窮者や独り親世帯、こども食堂などに提供していただいていますが、それらの団体と協力して、健康福祉部、環境部、県民文化部、農政部が連携して、想像以上に窮迫する県内学生の食料支援をしたらどうかと考えますが、知事、いかがですか。 私も3回ほど学生食料支援のお手伝いをさせていただき、20人、30人と、チラシやネット、友人の紹介で来てくれた学生と話す機会がありました。私自身も貧乏学生の1人でしたが、聞けば驚くような話ばかりでした。「アルバイトが激減したが、親の仕送りにも頼れない」「野菜といえば、もやしばかり食べている」「1日1食しか食べないときもあり、学校に行かないので体力を消耗しないように寝ている」「父親が大病し離職したので、弟のことも心配だし退学も考えている」などと語る大学生に心が痛みました。 若者は長野県の希望であり、宝です。必要な県内学生に、民間任せでなく県がリーダーシップを発揮して支援することを求めます。【知事】 学生に対する食料支援というご質問でございます。コロナの影響で、学生たちは本当に様々な影響を受けています。学業もオンライン化されたり、あるいはなかなか友達と交流する機会もなく、そしてご質問にあったように、アルバイトの道もなかなか閉ざされている中で、非常に資金的にも苦しいという中で、食費を切り詰めて生活している学生もいるということは我々も認識をしております。 松本市や長野市において、有志やフードバンク団体等が協力して学生に対する食料の無料配布を実施した際には、多くの学生が利用をされています。こうしたことから、県としても生活に困窮する学生の食料支援は必要だというふうに考えています。 これまでも関係する部局が連携しながら、フードバンク団体等を支援してきています。例えば、食品取扱事業者、あるいは農業者団体等に食料提供の呼びかけを行ってきております。また、県庁、そして10の地域振興局において、フードドライブを今年度は延べ43回開催をしております。また、フードドライブの認知度向上や食料提供を目的とした新聞広告の掲載も行っています。 今後は、大学や短大等とも連携をしてまいります。また、フードバンク団体等への支援も充実をしてまいります。こうしたことを通じて、学生に対する食料支援を進めていきたいと考えています。【毛利栄子議員】◆毛利議員 中小業者の支援について伺います。飲食・観光・宿泊関係を中心にコロナの影響は深刻であり、営業が立ち行かなくなっています。お話を伺った方は、「ランチやテイクアウトはやっているが気休め程度。来店者も少ない。店を閉めようと思っているが閉めても使ってくれるところがない」と肩を落とします。 スナックや居酒屋など、県下で1,400店が加盟する飲食業生活衛生同業組合では、既に75店が廃業、294店舗がこのままでは廃業せざるを得ないという状況が報告されショックを受けました。事業主や雇用されている方が生活の糧を失い、食文化や夜の交流の場が3割も消える危機に瀕しています。 新年度予算では、中小企業融資制度資金が過去最高の1,500億円確保されています。当座を乗り切る上で有利な資金の調達は必要ですが、返さなくてはならないために借りるのにもちゅうちょがあると言います。営業を丸ごと応援する施策が必要ではないでしょうか。国に持続化給付金の再度の実施を本気で迫るとともに、感染拡大防止に取り組んでいる飲食業や喫茶店などに50万円の応援を開始した徳島県のように、県としても直接給付を考えていただきたいが、いかがでしょうか。知事に伺います。【知事】 飲食・観光・宿泊等に対する支援として、国に持続化給付金の支給を要請せよ、また、県としても検討せよというご質問であります。 まず認識としては、飲食・宿泊等の事業者の皆さんが大変厳しい状況にあるということは共通の認識であります。県としても融資制度、あるいは様々な補助金等を通じてこれまでも支援をしてまいりました。 ご指摘の持続化給付金については、私からもかなりしつこく国に対して要請をさせていただいています。県独自でも要請しましたし、全国知事会を通じても要請をしています。また、近々全国知事会のコロナ対策本部会議をオンラインで開催予定になっておりますので、その場でも改めて要請をしたいというふうに考えています。 加えて、持続化給付金のみならず、いわゆる一時支援金、これは、緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する支援という制度ができたわけでありますけれども、これは、私のほうからは緊急事態宣言が発出された地域以外の地域も幅広く対象にするようにということで求めてきています。一定程度対象になってくる状況にはなっておりますけれども、極力こうした支援金も県内の多くの事業者が対象になるように引き続き求めていきたいと考えております。 また一方で、事業者への支援、様々な支援の在り方があると思います。感染が拡大しているときにはなかなか活動自体を抑制していただくという形になりますが、現下の感染状況を考慮すれば、やはり経済活動を動かしていくということが重要だというふうに考えています。 我々も様々な取組をこれまでもしてきています。テイクアウト、デリバリーの支援をはじめ、また、いろんな対策を講じているお店をしっかり発信するということで、信州がんばるお店の応援プロジェクト、また、安心なお店をこれからどんどんPRして利用促進も図っていきたいと考えています。 加えて、経済団体等とも協力して、やはり感染防止対策をしっかり講じながらも、しかしながら、一方で飲食店の利用も行っていきましょうということをアピールする取組も、今、検討している状況であります。観光については、ご承知のとおり既に家族宿泊割から、順次、県としての支援策も講じて取り組んでいる状況であります。 引き続き感染状況にしっかり我々は配慮しながらも、その一方で経済活動を過度に自粛をするということがないように県民の皆様方にもお願いをし、県民の支え合いの中で、飲食・宿泊事業者、あるいは、より広く影響を受けているサービス事業者の皆さんを応援をしていきたいというふうに考えています。 以上です。3.県民の命を守る新型コロナウイルス感染症対策について【毛利栄子議員】◆毛利議員 県民の命を守る新型コロナウイルス感染症対策について、健康福祉部長並びに知事に伺います。 感染警戒レベル5以上の地域の医療・介護などの従事者の自主的検査に対して補助制度を創設したこと、医療機関や高齢者施設などで1人でも陽性者が出た場合には、関係する従事者、入院患者、利用者全員の積極的疫学検査を実施したこと、松本市内の一定規模以上の高齢者施設では大規模に社会的検査を実施したこと、クラスターが起きた飲食街の従事者への広範な検査を実施し、陽性者の把握・保護に努めたことなど、発生状況に応じてPCR検査を拡大してきていただいていることは評価します。 しかし、後追いでは感染拡大を防げないのが実態ではないでしょうか。第3波は収束に向かっていますが、変異株などもあり、このようなときこそ一層の取組が求められます。「喉元過ぎれば熱さを忘れる」であってはなりません。 過日の政府感染症対策分科会で、昨年12月の5人以上のクラスターの件数の内訳が報告されました。医療・福祉施設が45%、次が飲食関連で19%、教育施設15%、職場関連12%と続きます。県内でも医療機関や高齢者施設、障害者施設でクラスターが立て続けに起こり、感染が爆発的に広がって亡くなる方も増え、背筋が凍りました。 長野県の第3波のクラスターの発生状況はどうなっているのか。健康福祉部長に伺います。【健康福祉部長】 新型コロナウイルス感染症対策について順次お答えをしてまいります。 まず、第3波における県内のクラスターの発生状況についてのお尋ねでございます。 11月1日以降、5名以上のクラスターは、保健所の疫学調査で確認できた中で29件あったと把握しております。このうち医療機関・福祉施設が10件で34%、飲食関連が12件41%であり、そのほかには教育施設が1件、職場が関連が4件、その他が2件でございます。【毛利栄子議員】◆毛利議員 無症状者も2割近くいることを考えれば、一刻も早く無症状感染者を把握し、保護し、感染を広げないことが重要です。 知事は、陽性者のいないところで網羅的に広くやっても有意義ではないという国の考え方を取られています。 第3波を振り返ったとき、県内医療従事者がメディアを通じて涙ながらに訴えた医療への負担を軽減する上でも、感染拡大が収まっている今が重要です。医療機関や高齢者施設、障害者施設などの従事者や、入院・入所者に、一斉定期的な社会的検査が無料で実施できるようにしていただきたいが、いかがか。知事に伺います。【知事】 私には、PCR検査等の実施についてご質問を頂戴いたしました。 ご質問の中でも引用いただきましたけれども、私ども長野県としては発生状況に応じたこの検査を行ってきております。 国の考え方を粛々と実行しているという考え方も毛頭ないわけでありまして、例えば、濃厚接触者以外の接触者に対しても必要に応じて幅広く検査を行ってきておりますし、ご質問でも引用していただきましたように、感染拡大地域においては、高齢者施設等の従事者に対する無症状の方も含めた幅広い調査等も行って、かなり戦略的にこれまで検査を行ってきております。 そういう中で、検査についてはやはり検査前確率が高い状況で有効に活用していくことが基本的には重要だというふうに考えております。このことについては、専門家懇談会でも大分議論をしたところでありますけれども、地域の実態、感染状況等を踏まえて必要な検査をしっかり行っていくということが重要だと思っています。 検査の在り方も、昨年からずっと検査体制も強化されてきましたので、国全体の考え方も少しずつ変わってきていますし、我々も順次必要な検査の在り方ということについては知見を重ねてきております。 今の感染状況、落ち着いている状況でありますけれども、さらに今後、感染拡大が起きるというような場合が生じたときにも、我々として何が必要なのかということをしっかり考えて、この戦略的な検査をしっかり行っていきたいというふうに考えております。 以上です。【毛利栄子議員】◆毛利議員 医療提供体制が逼迫し、医療緊急事態宣言を発してきましたが、病床使用率が国の基準と県の基準で違うことや、実質病床利用率を公表したり、病床逼迫率を公表したりと、実態が分かりにくく切迫感が伝わってこないとの声があります。もっと実態に即して、シンプルに分かりやすく公表すべきではないかと思いますが、健康福祉部長に伺います。【健康福祉部長】 医療提供体制の分かりやすい情報発信についてでございます。 県民の皆様と危機感を共有するため、実態に即した正しい情報をできる限り分かりやすく発信するよう努めているところでございます。1月15日分から長野県独自の指標として全県と4ブロックごとの病床逼迫度を公表しておりますが、この指標は重症者用や小児用などの特別な病床と一般的な病床の利用状況を分けたことにより、それぞれの区分で入院できる病床がどの程度逼迫しているかということが分かること、また、医療圏内で病床が逼迫した場合、主に隣接する医療圏と入院調整を行うため、4ブロックごとの公表でおおむね地域的な傾向を把握できること、そういった点を考慮したものでございまして、それ以前の公表方法を改善し、充実が図られたものというふうに考えているところでございます。 今後も県民の皆様のご意見をお聞きしながら、必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。【毛利栄子議員】◆毛利議員 さらに北信・東信・中信・南信の公表ではくくりが広過ぎて、生活している医療圏ごとの提供体制がどうなっているか分からないため、自分がかかったらどこにいくのかと不安が広がりました。保健所ごとに情報を公表していただきたいと思いますが、いかがですか。健康福祉部長に伺います。 【健康福祉部長】 病床逼迫度の保健所ごとの公表についてでございます。 保健所ごとの数値の公表につきましては、検討を重ね、医療機関等関係者のご意見もお聞きをしたところでございます。医療機関の少ない圏域は患者を受け入れている病院が特定され、医療従事者が差別や誹謗中傷の対象となるおそれ、患者の受診控えを招くおそれがあるといったこと、病院が特定されることを恐れて患者受入れに消極的になり、県の病床確保、入院調整事務の遂行に支障が生じるのではないかといったこと、そういった否定的なご意見が多く、現段階では難しいものと判断しているところでございます。【毛利栄子議員】◆毛利議員 保健所職員の疲弊が長期に及び、深刻になっています。保健師、検査技師など臨時的な確保に努めていただいていますが、国の新年度予算では、保健師の恒常的な人員確保のために、増員が交付税算定されることになっております。人口170万人の標準県では、88人から102人への増員を見越して算定されると聞いております。 昨日の答弁では、新年度は定数を1.5倍にするとのことでしたが、保健師を正規で増員していただきたいと思います。新年度ではどのような対応をされるのか伺います。また、その増員は交付税措置に見合ったものなのか。健康福祉部長に伺います。 【健康福祉部長】 正規の保健師の増員についてでございますが、昨日、知事が荒井議員のご質問に対し「令和3年度におきましては、保健所の感染症対策に従事する保健師の定数を1.5倍に増員していきたいと考えております」というふうにお答えをしているところでございます。 これを具体的な人数で申し上げますと、来年度保健所における保健師の定数を12に増やしてまいりたいと考えております。この点につきましては、交付税措置に見合ったものと考えているところであります。今後も正規職員の採用などにより、必要な人員の確保に取り組み、保健所の体制強化を図ってまいります。【毛利栄子議員】◆毛利議員 陽性者を受け入れた医療機関では、高齢者の入院が多く、中には認知症の方もいるため介護的なお世話も必要な場面があり、病院の負担は限界に達していると看護協会から伺ってまいりました。使命感だけではとてもやっていられないとの悲鳴も聞こえてきます。その上、軽症化し退院するときはケアの調整を病院がやっていて、他院や介護施設を探さなければ退院させられない事態にもなっています。 患者の受入れだけでも大変な中で、地域包括ケアのコーディネートを病院に任せるのでは医療崩壊を招きかねません。県としても、この大変な実情をつかんでおられるのでしょうか。改善方向について伺いたいと思います。【健康福祉部長】 高齢者の転・退院の支援についてでございます。 高齢の患者が入院した後、身体機能が低下して、そのまま感染症病床に長期間入院するといった事例が病床逼迫の一因となり、また、現場の病院も苦慮されている状況は県としても課題として認識しているところでございます。限りある医療資源を有効に活用するため、新型コロナ治癒後は、リハビリや基礎疾患の療養などを行う一般病棟や、他施設への転出・転院を円滑に進めていくといったことが重要でございます。 そこで感染症病床から転出可能となる基準や受入先での対応をお示しし、関係者が安心して患者の受入れができるよう、専門家懇談会の皆様に転出・転院の目安を作成していただき、2月上旬に関係者向けに周知をしたところでございます。 周知後、感染症病棟から一般病棟への移行が進んだ例もあることから、引き続きこうした取組などを通じて、患者受入医療機関とリハビリや基礎疾患の療養を担う関係機関との連携・協力体制の構築に努めてまいります。【毛利栄子議員】◆毛利議員 また、後遺症が問題となっています。東京都のモニタリング会議で、国際医療研修センターを退院した患者63人の後遺症について疫学調査結果が紹介されました。全体の76%に、咳や呼吸困難、倦怠感、嗅覚障害があり、発症後2か月で48%の人に後遺症が残っていて、就労にも影響があると言います。県でも一定期間の後追い調査と継続して相談できる体制をつくっていただきたいがいかがか。健康福祉部長に伺います。【健康福祉部長】 後遺症についてでございます。 新型コロナウイルス感染症の後遺症につきましては、現時点でまだ不明な点も多く、国内におきましても日本呼吸器学会などが調査研究に着手しているところと承知をしております。 感染された方への対応といたしましては、転院、または療養を解除された後、4週間は自己健康観察を行っていただくようお願いしておりまして、その間、随時、保健所が電話等で健康確認を行い、後遺症も含めた体調不良のある方には健康相談を実施した上で、必要に応じて医療機関の受診につなげているところであります。 また、この期間経過後も引き続き後遺症など心身に不安を感じる方からの相談には、丁寧に対応をしてまいりたいと考えております。 調査につきましては、実態や傾向を把握する上では一定の調査件数が必要であり、まずは国の研究結果を注視してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。【毛利栄子議員】◆毛利議員 ワクチン接種について、小岩副知事に伺います。 感染防止のために、ワクチン接種に期待が高まっています。一方、特例承認という形での実施であり、未知の部分もある上に、供給数について国の対応も曖昧なために、いつ接種できるのか、安全性、有効性、副反応などはどうかと、不安の声も少なくありません。 国に迅速な情報開示を求めるとともに、市町村や県民に速やかな情報提供をし、対応していただきたいと思いますが、そのための体制やシステムはどうなっているでしょうか。【副知事】 ワクチンに係る情報提供についてご質問をいただきました。 ご承知のとおり、国では2月17日より開始の先行接種2万人につきまして、併せて健康調査を実施しているところでございます。この調査結果につきましては、県民の皆様はもとより、ワクチン接種に関わる全ての関係者にとって大変関心の高いものでございます。 既に全国知事会としても、数次にわたる緊急提言の中で、ワクチン接種のエリア、副反応などの情報を積極的に周知・広報することであったり、ワクチンの供給量、時期をいち早く自治体に示すことなどを国に対して求めてきたところでございます。 今後、接種が進んでいく中で、安全性、有効性、副反応などの知見について、速やかに、かつ分かりやすく周知が図られるよう引き続き全国知事会のワクチン接種特別対策チーム等を通じまして、国に対して求めてまいります。 また、今月15日には国と自治体との連携を一層強化するため、厚生労働省内に自治体サポートチームが設置をされました。このチームには、本県からもリエゾン職員を派遣をしております。このサポートチームを通じまして地域の実情や現場の声を届けるとともに、積極的な情報収集にも努めてまいります。 県といたしましては、国からの情報はもとより3月上旬からの医療従事者等向けの優先接種や、その後の高齢者向け接種など、ワクチン接種を進める中での副反応等の情報や、ワクチンの配送先につきましても県民の皆様に可能な限り幅広く発信してまいりたいと考えておりまして、そのための体制の強化を現在検討中でございます、速やかに整えたいと考えております。 以上でございます。【毛利栄子議員】◆毛利議員 クラスターの発生状況等につきましては、国と同様の傾向があるということが分かりました。 年度末や年度初めを控え、3月20日から4月9日を感染対策強化期間として知事メッセージが発せられています。人の移動や会食によって感染爆発が起こった第3波の年末年始と同じ状況にならないか心配です。医療機関や介護・福祉施設などに従事されている皆さんや、入院・入所されている皆さんの安心を担保するために、検査の抜本的拡充が重要だということを重ねてお願いさせていただきます。長野県DX戦略について【毛利栄子議員】◆毛利議員 長野県DX戦略について企画振興部長に伺います。 国のデジタル庁創設やコロナ禍もあり、デジタル化が一気に進められようとしています。県はスマート自治体を推進するとして、県と市町村の共通業務に着目して共同利用を推進し標準化するとしています。 各種給付事業には自治体ごとに違いがあり、個人情報もそれぞれの自治体の条例で規制されています。行政の効率化の名の下に共通化、標準化を進め、行政データを最終的に国が一元管理し民間活用するようになれば地方自治がないがしろにされ、職員削減や民営化が進みきめ細かな住民サービスの後退にならないか懸念されますが、そうした心配はないか。企画振興部長に伺います。【企画振興部長】 長野県DX戦略に関しましてお尋ねです。 まず、市町村の情報システムの共同化、標準化によって、職員が削減されるなどによって住民サービスの後退につながるんじゃないかというお尋ねですけれども、国におきましては、市町村の情報システムの共通化、標準化に当たりまして、住民サービスの安定向上と業務の円滑化、効率化を旨といたしまして、各自治体の取組状況等をきめ細かく把握し、丁寧に意見を聞きながら推進していくとしております。 県といたしましても、諏訪地域をはじめ県内市町村で行われています共同化の取組も参考に、地域の実情を踏まえ最適な形で進められるよう支援していきますとともに、市町村間の取組に齟齬が生じないように国に要望してまいります。 人口減少に伴いまして職員の確保が困難になりつつある中で、複雑多様化する住民ニーズに迅速、的確に対応し、質の高い行政サービスを安定的に提供できるようにするため、行政事務のデジタル化を推進してまいります。【毛利栄子議員】◆毛利議員 県内では既に広域処理されている地域も幾つかあり、システムが変わればスキルも変わり、現に使用しているICT機器の更新時期も違うため、移行に伴うリース料の解約も生じてきます。広域処理されている地域の課題をどう検討されているのでしょうか。 また、小規模自治体では、デジタル化を専門に担当する職員の確保も難しいと思われますが、どのような支援策を考えているか伺います。【企画振興部長】 情報システムが広域処理されている地域の課題に関する検討と小規模自治体への支援策ということですけれども、既に広域処理されています地域の課題ということですが、国は市町村の主要な17業務を処理する情報システムの標準化、共通化を2025年度までに進めるとしております。 このシステム移行経費につきましては国費で支援するとしておりまして、通常5年程度でとされております機器更新の時期に合わせてシステムを移行することによりまして、負担を抑制することができると考えております。 現在、国が検討しております枠組みの詳細が判明次第、県内の全市町村が参加いたします先端技術活用推進協議会におきまして、市町村と連携して課題を共有し、諏訪、上伊那などの先行事例も参考にしながら、取組の方向性について検討してまいりたいと考えております。 また、小規模自治体の支援ということですけれども、県におきましては来年度新たにDX推進課を設置いたしまして、これを核として、今、述べました協議会ですとかパートナー連携協定締結企業からの人材の派遣、さらには国で現在予定されております外部人材確保のための制度も活用しながら、小規模自治体の負担軽減と人材確保を支援してまいりたいと考えております。【毛利栄子議員】◆毛利議員 デジタル化の一環としてキャッシュレス化が叫ばれているさなかに、ドコモ口座を通じた銀行預金の流出などが表面化して被害が拡大し、セキュリティー対策の脆弱性を露呈しました。行政サービス情報をデジタル化する場合、プライバシー保護やセキュリティー対策などはどのように検討されているのでしょうか。【企画振興部長】 デジタル化を進めるに当たってのセキュリティー対策ということですけれども、行政事務のデジタル化の進展に伴いまして、情報セキュリティー対策は一層重要になっていくと認識しております。県におきましては、平成14年度に定めました情報セキュリティーポリシーに基づきまして、人的、技術的両面から二重三重の対策を講じているところであります。 令和4年7月の情報ネットワーク更新に合わせて実施いたします次期情報システム整備におきましては、基本的にパソコンにデータを保存しないというシンクライアントシステムを導入してセキュリティー対策をさらに強化し、県の情報資産の漏えいや不正アクセスなどの脅威からしっかり守っていきたいと考えております。 また、先ほどの協議会を通じまして、市町村とも情報を共有しながらセキュリティー対策を進めてまいりたいと考えております。【毛利栄子議員】◆毛利議員 6年たってもマイナンバーカードの取得が僅か国民の25%と進まない中で、健康保険証や免許証などにもひも付けされる動きがありますが、マイナンバーによる個人情報の国による管理に懸念を示す県民も少なくありません。カードの取得を強制すべきではないと考えますが、いかがでしょうか。【企画振興部長】 マイナンバーカードの取得を強制すべきでないということでありますけれども、国ではデジタル社会の構築のため、令和4年度末にほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目的としております。 こうした中、マイナンバーを用いた個人情報の名寄せが行われ、集約された個人情報が漏えいするのではないかといった懸念の声があることも事実であります。この点に関しましては、国は、各行政機関が管理いたします税や年金などに関する個人情報が、マイナンバーによって一元管理されているわけではないことから、これらの個人情報が芋づる式に漏えいすることはないとしております。また、マイナンバーカードには様々なセキュリティー対策が施されております。 国においては、さらなるマイナンバーカードの利便性向上について検討しておりまして、多くの方が安心してそれらの利便性を享受できるよう、その普及に向けた取組を市町村とともに進めてまいります。 以上です。BYODによる一人1台端末所持方針について【毛利栄子議員】◆毛利議員 BYODによる1人1台端末所持方針について教育長に伺います。 県教委は、高校1年生のタブレット所持率が現状では5.4%とされている中で、新1年生には全員一斉に購入、所持させる方針を示していましたが、現場から混乱の声を受け過日スマホでもいいと変更しました。 過去に学校徴収金の多さが問題化し、学校徴収金の基本的考え方を策定し必要最小限の徴収を求めてきた経過もあります。しかし、その努力にもかかわらず、この10年で高校全日制の学校徴収金は1.7倍、年間8万9,000円と過去最高になっています。 コロナ禍で家庭の生活環境が困難になる中、制服や運動着、通学定期代に加え、さらにタブレットを個人持ちにさせれば、新たな負担を強いることになり、あまりに乱暴で配慮がなさ過ぎると思いますが、どのような経過でこのような方針が示されるに至ったのか。また、見直しした理由について教育長に伺います。【教育長】 BYODによる1人1台端末方針を示した経緯等についてのお尋ねでございます。 GIGAスクール構想によりまして、今年度中に県立高校の校内Wi-Fi環境がほぼ整うことになります。また、令和2年度2月補正予算案で、国の補正予算を活用し低所得者世帯等の生徒が使用するタブレット端末を貸与する予算をお願いしているところであります。 そういったことを鑑みまして、令和3年度から生徒が保有するスマートフォン、またはタブレット端末による1人1台端末を活用した学びの充実を全高校で目指しているところでございます。 生徒が自分の日常生活の道具としてICT機器を自在に使えることが必要な時代となっているというふうに考えております。一方で、学校の備品として整備しそれを家庭において使用する場合は、何らかの制限をかける必要が生じることとなります。 このことから、高校段階においては端末はBYODとし、生徒が日常で自由に使えるようにする中で学習にも自立的に活用できるようにしたいというふうに判断したところでございます。 また、令和4年度からは中学校において1人1台タブレット端末の環境で学んできた中学生が高校に入学してまいります。そうした生徒については、BYODの端末としてタブレットの活用が望ましいと考えたところでありますが、令和3年度の入学生からの先行導入の可能性についても検討したところであります。このため、各学校に対してその検討を依頼したところでありますが、導入を進めたいという声がある一方、準備期間が必要であるということなど様々な声が寄せられたところでございます。 それを踏まえまして、令和3年度入学生については、スマホ、またはタブレットの活用によるBYODとしたところでございます。【毛利栄子議員】◆毛利議員 令和4年度は、中学校で1人1台端末を経験した生徒たちが入学してきます。令和4年度はどういう方針にするのか伺います。市町村では1人1台端末を公費で用意し、通信費も公費で負担しているところがあります。本来は、市町村のように県予算で措置し貸与すべきと考えますが、いかがでしょうか。【教育長】 1人1台端末、令和4年度の方針ということでありますが、先ほどご答弁申し上げましたように、令和4年度の入学生からはBYODの端末としてタブレットの活用が望ましいというふうに考えております。その場合、クラウド化に伴って見直すことのできる教材費等、例えば、今まで導入してきた電子辞書をやめたり、あるいは紙ベースの教材を転換したりするなど様々な工夫が考えられるのではないかというふうに思っております。 各学校の実態も様々でありますので、BYODによる豊かな学びと、保護者負担の軽減の両方の課題について検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。【毛利栄子議員】◆毛利議員 教育長に再度伺いたいと思います。今ほど、令和3年度の所持の問題については、各学校に投げかけたところ、いろいろな声があり見合わせることにして、スマホでもいいようにするというようなお話でございました。 そもそもICT教育の推進ということで、教育上最低限必要な機器ということであるならば、個人持ちにさせずにきちんと予算要求すべきものではないかと思います。スマホでもいいという考え方も、あまりに安易だと思います。画面が小さく目を酷使し、健康上よくありません。教育委員会として知事部局に予算要求する必要があると思いますけれども、その考え方について伺います。【教育長】 BYODの端末、あるいは実際に授業等で活用する端末として、スマホではなくてタブレット端末、それを予算要求すべきではないかというお話でございます。 今回タブレット端末のみならず、スマートフォンについても、自ら所有している端末を学校の授業でも、また家庭でも活用できるということをまずは進めていくべきだろうと思っております。 学校における授業の活用については、どういう活用方法が望ましいかということについてもしっかり検討する中で、ICT教育、あるいはICTの活用が最も有効な方法は何かということを検討していきたいというふうに思っております。【毛利栄子議員】◆毛利議員 知事に今の問題で伺わせていただきたいと思います。 やり取りをお聞きいただいたかとは思うんですけれども、学校教育の中で必要だということで、しかも義務教育の中では国からもお金が出て全員1人1台持たせている。義務教育じゃなくて高校は自由だという考え方もありますが、進学率はほぼ99%、こういう中では、やはり必要な機器として行政がきちんと手立てをして貸与する、そのことが筋だと思います。 知事、公立高校の全生徒に公費で持たせるには、およそ13億円あれば足ります。これは新年度予算の僅か0.12%です。学びの県づくりを標榜する長野県です。ぜひ公費購入での貸与を検討していただきたいと思いますが、いかがですか。【知事】 GIGAスクール構想、高校生のデバイスをどうするかというご質問でありますけれども、私も今、質疑のやり取りを伺っていて、教育委員会を呼んで少し状況を把握しなきゃいけないなというふうに思いながら、そこでご質問を伺っていました。 BYODで、これは教育長からご答弁させていただいたように、やはり家庭でも使える自分の使いやすい端末を使うということは、基本的に私は是としているところでありますけれども、今後このICT教育をしっかり進めていく上で、スマートフォンの利用というようなことであったり、あるいは低所得者対策、これは端末の購入だけじゃなくて通信費の問題等も出てくるわけでありまして、そうすると、これは教育委員会だけの問題ではなくて、かなり予算が重要なポイントになってきますんで、そういう意味で、予算編成権、提出権は私にありますので、教育長とどういうやり取りが学校との間で行われて、どういう判断をしているのかということは十分聞き取らせていただいた上で、県全体としての方針をしっかり固めたいというふうに考えています。 以上です。2050ゼロカーボンを目指す取り組みについて【毛利栄子議員】◆毛利議員 2050ゼロカーボンを目指す取組について環境部長に伺います。 諏訪湖の御神渡りに期待が集まりましたが、今年も残念ながら出現しませんでした。八剱神社関係の皆さんが連日湖上に出て観察をされていましたが、600年前からの詳細な記録があるとのことで、諏訪湖にまつわる地球温暖化の進行が、研究者の手で解かれようとしていることは興味深いことです。 ゼロカーボン戦略が、環境審議会の地球温暖化対策専門委員会で検討されており、令和3年度に策定される予定になっていますが、現在の進行状況と今後の予定、また戦略の柱についてお聞かせください。【環境部長】 ゼロカーボン戦略に関しましてご質問を頂戴いたしました。 1点目、ゼロカーボン戦略の策定状況、戦略の柱についてのお尋ねでございます。 ゼロカーボン戦略につきましては、昨年11月に環境審議会に策定を諮問し、地球温暖化対策専門委員会において、専門的な見地からご議論をいただいているところでございます。並行いたしまして、庁内にゼロカーボン戦略推進本部を設置いたしまして、部局横断で施策の構築を進めてきております。 また、県民の皆様の思いやご意見を計画に反映させるため、産業界など関係団体との意見交換や県民と知事が直接対話するゼロカーボンミーティングを開催するなど、県民総参加での計画づくりを進めているところでございます。 こうした過程を経まして、今月5日にはゼロカーボンを目指す上でポイントとなります交通、建物、産業、再エネ、学び、及び吸収・適用の各分野を柱とする重点施策案を公表いたしました。この重点政策案について県民の皆様と対話の機会を持ち、いただいたご意見やアイディアを反映した形で、新年度のできる限り早い時期の策定を目指してまいります。【毛利栄子議員】◆毛利議員 2050年といえばあと30年ですけれども、2030年、SDGsの目標に合わせて2030年の目標をきちんと示す必要があると思いますが、そのことについても伺います。【環境部長】 2030年度の数値目標についてのお尋ねでございます。 ゼロカーボン戦略自体は、2050年を見通しながら、2030年までの10年間で重点的に取り組む施策を戦略に盛り込んでいくものでございます。 その2030年度の目標値につきましては、ゼロカーボン戦略の前身であります環境エネルギー戦略の策定段階におきまして、気候危機突破方針でお示しした2050年度の目標値と、2020年度の見込み値を直線で結んだ値を2030年度の値といたしまして、専門委員会にお示ししております。具体的には、2030年度の最終エネルギー消費量を、2010年度比34%減の13万2,000テラジュール、再生可能エネルギー生産量は同じく85%増の4万1,000テラジュールとする案となっております。 ゼロカーボン戦略における2030年度目標値につきましては、引き続き専門委員会のご意見も伺いながら設定してまいります。 以上でございます。
2021年02月26日
-

新年あけましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。9時から地元今井15社の元旦祭。社殿は一段高いところにあるため、ホッカイロを背中に貼っていったのに寒かった。ブルブル。終わって恒例の諏訪大社下社前での新春ごあいさつ。武田良介参院議員、ながせ由希子4区予定候補、下諏訪町議団揃い踏み。支部や後援会の皆さんにもおいでいただきました。寒さはありましたが好天。でもコロナのせいか参拝客いつもよりかなり少なく、観光バスの入り込みもなくちょっとさみしい感じ。今年は参院補選、衆院選の年。政権のチェンジめざし、頑張ります!良い年にしましょう。
2021年01月08日
-

長野県党旗びらき
長野県党旗開きが3密対策を講じて参加者を制限するなか開催されました。選挙の年ということかマスコミ各社も多数取材に。立憲民主党衆議院議員・県連代表篠原孝さん、社民党県議池田清さん、信州市民アクション共同代表松沢佳子さんが心のこもった連帯あいさつを寄せてくださいました。藤野やすふみ衆院議員・比例代表、ながせ由希子長野4区・県書記長から力強い決意表明。参院補選で羽田雄一郎さんの遺志をつぎ議席を守る。衆院比例で藤野さんの議席を確保しさらに2議席をめざす。小選挙区は全て野党が議席を獲得し政権交代を!の決意を固めあいました。私も県議団を代表し、あいさつさせていただきました。夕方からは大雪警報が県北部にでています。豪雪は災害。沢山降らなければいいのですが。
2021年01月07日
-

山下よしき副委員長を迎え該当演説 盛況
岡谷市蚕糸公園前の街頭演説。ひときわ冷え込んだ曇天のなか、沢山の皆さんにご参加いただきました。立憲民主や社民党、市民連合の皆さんから大型宣伝カーにビックリされながらもそれぞれ心のこもった激励あいさつ。ながせ由希子さんは長野県にジェンダー平等の女性国会議員を!藤野やすふみ衆院議員は長野県でおきた2.4事件にふれながら再び物言えない社会にはさせない!山下よしき副委員長は7つの政策のフリップを掲げ、コロナ後は医療、介護などケアに手厚い希望ある日本に!と訴え。終わって初参加の30代女性が「前回もうりさんに入れたんです!」と、ながせさんのお誘いで来たと話しかけてきてくださり、居合わせた若手スタッフにきてもらいご対面。さっそくメール交換し、こんごの行事に参加いただけることに!新たな出会いと感動を共有できたいい街頭演説でした(^-^)
2020年10月19日
-

9月議会で一般質問させていただきました!
9月議会では①コロナ感染症対策と生活困窮者支援②特養あずみの里事件について一般質問いたしました。全文は以下をご覧ください。テープ起こしは県議団が行ったものです。毛利栄子議員/コロナ感染症対策について知事に伺います。 最初に検査体制についてです。県内の第2波は7月中旬以降感染者が拡大し、8月28日は1日で19人が確認され、上田広域圏で連日新たな感染者が発表されるたびに、蔓延するのではないかと緊張が走りました。しかし、県や市、保健所、医療機関、商店街、地域住民の皆さんが果敢に立ち向かう中で抑え込んできました。 第2波は、無症状の感染者が少なからずいるという特徴があります。無症状の感染者は、濃厚接触者として検査する中で、陽性確認されることが多いことを踏まえれば、症状のないまま病原体を保有し、市中で生活している人が少なからずいるのではないかと推測されます。 この間、医療機関や福祉施設、学校、事業所などでPCR検査を広げて来ていただいておりますし、上田圏域では、クラスターの発生した地域の接待を伴う飲食店で、希望者にPCR検査が行われました。8月のPCR検査は7,000人近くに広がり、4月の1,300人余からは5倍以上に拡大しております。 県の専門家懇談会座長の県立病院機構理事長も、「検査対象を厳密に定義された濃厚接触者以外に広げたことが、感染症の早期発見と拡大防止、感染抑止につながった」と述べています。大規模な行動制限は社会的ダメージが大きいため、感染拡大防止と社会経済活動を両立させるためには、PCR検査の積極的な拡大が待ったなしです。 厚生労働省は8月7日、「自治体の判断により、現に感染が発生した店舗等に限らず、地域の関係者を広く検査することが可能であるため、積極的に検査を検討していただきたい」と事務連絡を出しています。 第3波が懸念されます。発熱などの症状のある場合は、すぐに検査を受けられること、クラスターが発生した場合は、上田でも要望がありましたが、関係施設、関係者だけでなく地域を面的に網羅的に検査し、陽性者を確認した場合には直ちに保護・隔離し、感染拡大の防止と封じ込めをすべきだと考えますが、地域に広げる考え方について知事に伺います。 また、高森町や下條村、南牧村など、安全安心のために市町村が1検体・2ないし4万円の検査費用を負担して、自主的に検査を行うところも増えてきています。地方自治体が積極的に行うこれらの社会的検査について国の支援を求めるとともに、県としての支援も検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 県内のコロナ対応医療機関は、先ほど来、議論がありましたが、厳しい経営が強いられております。1か月1億から2億の赤字、この状態が続けば、医療崩壊にもつながりかねないと危機感を募らせています。県は補正予算を組み、患者受入れ病院に対して空床確保料や危険手当などの措置をしてきており、今議会にも追加提案されていますが、あまりにも不十分です。 諏訪圏域の公立病院の関係者からお話を伺ってまいりました。「医療機関は患者の命を救うために必死の努力をしている。クルーズ船の患者を初めて受け入れたときは、担当の看護師が怖くて泣き出す状況まで出てきて、看護師長がなだめながら励まし任に就いてもらった。努力不足で経営が悪化しているわけではない。減収補塡の仕組みをぜひつくってほしい」と訴えておられました。 一生懸命やればやるほど赤字が増え、経営困難に陥る現状があります。この間の支援は、本来ベッドが稼働していた場合と比較しても、半分にも満たないとの声が上がっています。知事はこの現状をどう認識しておられますか。 自治体病院を開設する県内17の首長から知事宛てに要請が出され、医業収益が減少する中、実効性のある「損失補塡」を求めています。医療崩壊を防ぐために、国に対してぜひ減収補塡を求めていただきたいがいかがでしょうか。 また、昨日の小林君男議員の質問に対し、知事は「県としても、経営状況を見極めながら必要な対応を行ってまいりたい」と答えておられますが、国の包括支援金の枠を超えた県独自のさらに踏み込んだ補償や支援策を講じていただきたいがいかがですか。 続いて健康福祉部長に伺います。 3波、4波も予想される中で、1波、2波の対応はどうだったのか、県としての振り返りを求めてまいりましたが、9月28日の本部会議で一定のまとめがされたことは重要です。コロナ対策は、経済対策を含め種々ありますが、感染状況の幅広い把握と、陽性者を確認した場合の保護・隔離をいかに迅速に行い感染拡大を防ぐかが鍵を握ると考えます。 過日、諏訪保健所の取組を伺ってまいりました。諏訪保健所では、1波の取組を様々な角度からきちんと分析し、2波にどう取り組むか緻密な整理がされ、課題が明らかにされていて、住民の命や地域医療を守る保健所としてのリーダーシップを果たす姿勢がつぶさにうかがえました。 感染症対策を担う健康福祉部として、この間の取組の医療圏ごとの検証をやっていただき、前進面や課題を明らかにして今後の対策に生かしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、季節性インフルエンザ対応の中で「保健所が地域の実情に合わせて対応する」とのことですが、保健所ごとの取組の現状と課題について伺います。 6月議会で両角議員が指摘したように、この30年間で、長野県の保健所数は統廃合でほぼ半減、人員も半分に減らされました。通常の業務もぎりぎりの人数でこなし、今回のようなことが起きると、通常業務を先延ばししたり過重な働き方を余儀なくされています。 補正予算で、各保健所に臨時に人を配置していただいたことは大変歓迎されており、搬送なども委託することでほっとしたとの声も聞かれています。先の本会議で部長は「保健所の体制強化は重要かつ喫緊の課題」だと答弁されています。数年に及ぶとも言われているコロナに対応するには、他所の応援や臨時的な人員確保では限界があります。県は今後61人を確保し、保健師はさらに13人確保するとのことですが、具体的なスケジュールと雇用形態について伺います。 次に、生活困窮者支援について部長に伺います。 長野労働局の速報値では、解雇や雇い止めは85事業所で1,109人、うち派遣が551人とほぼ5割を占めていますが、労働局把握の範囲だけなので氷山の一角とも言えます。有効求人倍率が1倍を割り込んだのは2013年12月以来、しかも、また直近で0.01下がったと先ほど報告がございました。全国平均を4か月連続で下回っております。 先日も、東信地域の公園で「死にたい」と言っていた21歳の青年が北信地域に流れ着き、行政につないで対応する出来事もありました。アルバイトの激減で学生生活が困窮し、民青同盟信大松本班が実施したお米や野菜、レトルト食品などを無料提供する「食材もってけ市」には学生が殺到し、始まる前から80人が並び、急遽40人分を追加する事態も起こっています。 緊急小口資金、総合支援資金などの特例貸付利用が3月から9月25日までに1万1,234件、貸付総額32億1,600万円と爆発的に広がっており、今議会に積増しの補正23億が提案をされております。当初9月末までだったものが12月末までに延長され、貸付期間も3か月から最大6か月に延長されましたが、期限が迫る利用者の生活が心配です。県としての生活困窮者に対する支援策を伺います。 阿部知事/新型コロナウイルスに関連して、3点ご質問を頂戴いたしました。 まず、PCR検査等の抜本的な拡充についての御質問でございます。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合には、速やかに検査をしていくことが望ましいというふうに私も考えております。相談数に占める検査数のこれまでの状況を見ますと、第1波は5. 8%でありましたが、第2波は43.9%ということで飛躍的に相談に対する検査件数の割合が増えてきています。多くのご相談を速やかに検査につなげることができているものというふうに考えております。 また、クラスターが発生している地域における検査は、上田地域において、今回中心市街地の接待を伴う飲食店等に勤務をされる方を対象として無料で実施をさせていただきました。今後とも、地域における感染状況を踏まえて、感染拡大を防止する必要があるというふうに考えられる場合には、例えば医療機関、あるいは高齢者施設等に勤務される方、あるいは入院・入所者を対象として検査の実施を行うということも含めて、積極的に検査を行うことを検討していきたいと考えています。 また、幾つかの自治体では、高齢者とそのご家族、あるいは帰省する学生等が希望する場合にPCR等検査費を補助する事業を実施されておりますが、国の新型コロナの臨時交付金を活用されるなどして対応されているものというふうに承知をしています。 県としては、市町村や医師会とも協力し、まずは季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えた検査能力、検査体制の向上・強化に全力を傾注していきたいと考えております。 それから新型コロナウイルス感染者の受入れ病院の現状、経営についての現状認識というご質問であります。 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、私も県内の病院関係者、あるいは公立病院を有する市町村長との意見交換をさせていただく中で、経営状況についてお伺いをさせてきていただいております。先ほど申し上げたように、非常に厳しい経営状況に置かれているという認識を持っております。 日本病院会等の調査によりますと、経営実態は、やはり患者を受け入れていない病院よりも受け入れていただいている病院の方がより減収幅が大きいという状況になっています。また、月別には5月が最も厳しい状況で、6月、7月については幾分持ち直している状況だというふうに認識をしております。 こうした中で、県独自のさらに踏み込んだ補償支援についてというご質問でありますが、患者受入れ医療機関への支援については、これまで診療報酬も数度にわたって引き上げが行われてきています。また、重点医療機関の病床確保料についても、4月にさかのぼっての引き上げということが行われています。県としてもご答弁申し上げてきているように、これまで数次の補正予算で医療機関に対する支援を行わせていただいております。ただ、こうした支援が、まだ医療機関に支払われるに至っていないという部分もありますので、一日も早く医療機関の皆様方に支給できるように、県としても努力をしていきたいというふうに考えております。 また新型コロナウイルス感染者を受け入れていただいている医療機関の経営の問題は、これは我々としても直視をしてまいりますし、また一方で、全国的な問題でもございます。知事会を通じて、あるいは市長会、町村会と共同で国に対して要請活動を行わせていただいております。 県としては、これまでも様々な支援に取り組んでまいりましたけれども、今後とも病院の経営状況をしっかりと見極めた上で対応してまいりたいと考えております。 以上です。 土屋健康福祉部長/3点お尋ねをいただきました。 最初に1波、2波の対応の検証と今後の対策、また、季節性インフルエンザ流行期に向けた保健所の取組状況についてでございます。 各保健所における対応につきましては、クラスター事案や医療機関での感染事案などにつきまして、入院患者の受入れ調整、徹底した検査の実施、そして患者の搬送など対応に苦慮した点を中心に検証をそれぞれ行っております。今後に生かすべく、保健所長会議において共有を図っているところでございます。 また、季節性インフルエンザ流行期に向けた対策につきましては、かかりつけ医等身近な医療機関において相談、診療、検査を行える体制を基本に、それぞれの地域の実情を踏まえ、保健所が中心になって郡市医師会や市町村と調整を始めているところでございます。 これまでに診療検査に対応をいただける医療機関について、対応できる検体採取の方法も含めて調査をいたしました。季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の両方の検査が同時に行える抗原迅速キットを活用するためには、鼻咽頭の検体採取が必要でございます。これに対応していただける医療機関がまだ少ないといったことが課題であると考えているところでございます。 今議会に補正予算として計上いたしました医療機関や郡市医師会に対する協力金を活用して、調整を加速してまいりたいと考えております。 次に、保健所の人員確保のスケジュールと雇用形態についてのご質問でございます。 保健所の体制強化を図るため、これまでに任用した保健師12名に加えまして、さらに保健師、臨床検査技師、事務職員を確保するため、9月9日から10月30日までを期間として募集を行っているところでございます。今後、面接等を行った上で随時に任用してまいる予定でございます。 なお、その雇用形態につきましては、新型コロナウイルス感染症対策による一時的な業務量の増加に伴う任用であることから、臨時的任用職員としておりますが、臨時的とは申しましても期間の定めのあるということで常勤の職員であり、もちろん資格や経験を有していることから確かな戦力になるものと考えているところでございます。 今後も、正規職員の採用も含め必要な人員の確保に取り組みますとともに、外部委託の活用や市町村保健師による協力体制の構築などにより、保健所の体制強化を図ってまいります。 次に、生活困窮者に対する支援策についてでございます。 生活福祉資金の特例貸付につきましては、令和2年9月25日現在で緊急小口資金及び総合支援資金を合わせまして、延べ1万1,234件、32億1,000万円余の貸付けが行われております。今回、貸付期間が12月末まで延長されたことに伴い、9月補正予算案において貸付原資の積増しとして23億円余をお願いしたところでございますが、今後の貸付状況等も注視をし、必要に応じて国にさらなる貸付期間の延長を要望してまいりたいと考えております。 また、特例貸付の償還についてでございますが、国の償還免除措置に加えまして県独自に償還金の一部を補助することとしており、躊躇せず申請していただけるよう周知を図ってまいりたいと考えております。 生活に困窮される方が安定した生活を取り戻すためには、まずは就労先の確保が不可欠であり、生活就労支援センター「まいさぽ」を中心に、ハローワーク等関係機関と緊密に連携しながら、引き続きお一人お一人に寄り添ったきめ細かな支援に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 毛利栄子議員/保健師や検査技師など緊急に臨時に対応することはやむを得ない面もありますが、今後に備えるためにも専門職は正規で拡充することを望みます。 また、特例貸付が増えている中でも生活保護は横ばいです。どうしても生活の立ち行かない世帯には、最後の砦、権利としての生活保護についてもしっかり広報し、水際作戦で追い返すことなく柔軟に対応していただきたい。通常、車の保有は生活保護利用のネックになっていますが、コロナ禍では特別扱いになっているので、福祉事務所に対し指導の徹底をお願いいたします。 次に特養あずみの里事件について、健康福祉部長に伺います。 7月28日、東京高裁は特養あずみの里業務上過失致死事件の控訴審判決で、第1審長野地裁松本支部の罰金20万円の有罪判決を破棄し、無罪判決を言い渡しました。検察は「適法な上告理由を見出せない」と上告せず、8月11日、完全無罪が確定しました。 おやつの配付後に起きた不幸な病死が、個人の業務上過失致死罪を問う事件となり、6年半もの間、准看護師は長く苦しい闘いを強いられ、介護の現場には衝撃と萎縮、不安が広がりました。 この判決は、人手不足の中で頑張っている全国の介護現場と関係者に、安心と未来への希望を与えるものになりました。それにつけても、識者の中ではそもそも長野県警が根拠なく乱暴に捜査の対象とし、医学的原因を解明することなく過失致死事件として送検したことがおかしいとの声も上がっています。 介護の質や高齢者の人権、よりよい介護行政を担っていただいている健康福祉部長に無罪判決の受止めについて見解を伺います。 入所施設と警察との関わりについて伺います。 介護施設入所者の死亡について、平成27年12月1日付で、「警察活動へのご協力について」という通知が、社会福祉施設の入所施設関係の長宛てに、健康福祉部長から出されています。中身は、施設入所の方が亡くなられた場合、病院に搬送後に亡くなられた場合も含め、事件性を判断するために亡くなられた方の身体確認、入所施設の状況、貴重品類について警察の確認に協力を求めるというものです。入所者が施設で死亡すれば、全て警察が確認に入るのかと混乱と不安を与えております。 そもそも医療機関や福祉施設における患者、入所者の死亡に関し、警察官が介入できるのは刑事訴訟法による犯罪捜査の場合のほか、警察官の職務執行法に基づく諸権限を発動する要件がある場合だけです。各医療機関・施設とも医師法21条に基づき適切な対応をしている中で、このような通知は関係者を不安におとしめ、あずみの里裁判と重ね合わせると、警察権限発動の要件が曖昧な中で県が協力要請を発出することで、任意性を超えて事実上強制の役割を果たすことになり、適切ではないと思います。この際、通知を取り消していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 土屋健康福祉部長/特養あずみの里事件について2点お尋ねをいただきました。 最初に判決の受止めについてということでございます。 本件は介護施設の食事中の事故で、個人の刑事責任が問われた事件であることから、介護職員が萎縮し、サービスの低下につながるのではないかと介護関係者の大きな注目を集めた裁判だと認識をしております。 介護保険法に基づく人員、設備及び運営に関する基準においては、入所者の立場に立ってサービスを提供すること、また、施設における介護事故防止について義務づけられているところであります。介護施設においては、入所者の転倒や誤嚥等のリスクがありますので、各施設において今後とも安全管理を徹底していただいた上で、利用者に寄り添った質の高いサービスを提供していただけるよう県としても助言や指導をしてまいりたいと考えております。 次に、社会福祉施設に対する警察活動への協力依頼についてでございます。 議員ご指摘の平成27年12月の健康福祉部長通知については、警察本部からの依頼に基づいて発出されたものと承知をしております。通知の趣旨としては、社会福祉施設の入所者が亡くなった場合に、警察から法律に基づいて施設の状況等を確認したい旨の依頼があった際には、警察活動の趣旨にご理解をいただいた上で社会福祉施設に協力を求めるものでございます。 施設に対応を強制するものではなく、通知は適切なものであると認識をしております。 以上でございます。 毛利栄子議員/何に忖度されたのか、部長から裁判の結果について見解が伺えなかったことは非常に残念であります。 健康福祉部長に再度伺います。 平成27年12月15日には、先ほど適切だと言った通知について、説明不足だったとして「警察活動へのご協力に関する趣旨について」の文書が出され、そこでは各施設に多大な不安と心配をかけたと深いお詫びが述べられた上で、この文書は死亡時の医師及び警察の対応ということで、医師法の内容に沿って届け出た場合に、警察から依頼があった際には確認に協力してほしいとの趣旨だと述べられています。 しかし、現実はそうなっていない場面もあります。現に訂正通知を出した後でも、ある施設で心肺停止になった入所者を病院へ搬送。そこで病死死亡を確認。ところが警察が施設に来て現場検証まで行ったということです。 従来は照会程度だったものが、そのような対応は施設を驚愕させています。こんなことがあれば、介護施設は安心して介護に当たることはできません。重度の人はいつ急変するか分からないので、受け入れなくなるのではないでしょうか。 食事どきの急変・死亡に対し東京高裁は「おやつを含め食事は人の健康や身体活動を維持するためだけでなく精神的な満足感や安らぎを得るために有用かつ重要、介護における食品の提供は医薬品の投与等の医療行為とは違う」と高い見識を示しました。 正確さを欠いた不適切な通知は、撤回もしくは破棄するのは当然ではありますが、適切だというふうに言い切っておりますので改めて健康福祉部長に伺います。 あずみの里事件は安易な警察の介入が冤罪を生みかねない事件でした。以前と同じ医師法21条に基づく対応でいいということで確認をさせていただきますが、いかがですか。 土屋健康福祉部長/平成27年12月15日に、趣旨についてという形で追加で通知を差し上げてございます。先の通知において、全ての死亡事例についてそういった対応をお願いするといったような誤解が施設側において生じて少し混乱を来したといったことから、その趣旨を改めて徹底するために通知を申し上げてご理解をいただいたというふうに承知をしてございます。 この件につきましては、法律にのっとって適切に処理されるものであるというふうに理解をしております。 以上でございます。 毛利栄子議員/コンプライアンス・行政経営課を設けている長野県であります。行政文書は、ややもすれば朝令暮改と揶揄される面もないわけではありません。一つ一つの通達について、原則は何か説明できる根拠を明らかにして対応していただきたい。このことを節にお願いし、質問を終わります。
2020年10月02日
-

思い立って入笠山に 変更して杖突峠
午後思い立ち、連れ合いと富士見パノラマのゴンドラに乗って入笠山に行こう!と意気投合。現地までいったのは良かったのですが、人、人、人で大混雑。 マウンテンバイクでのぼる人が8割位いて長蛇の列。せっかく諏訪6市町村在住者ということで往復無料の券をいただきましたが、こりゃ、だめだと予定を変更。 急きょ茅野に戻って杖突峠に。かつての峠の茶屋の喫茶店で眺望を楽しむ。以前に知人にあそこに行ったらチーズパン食べないとと言われていたことを思い出し、注文。焼きたてをいただきながらコーヒー飲んでしばし癒しのひと時を過ごし、リフレッシュしました。
2020年09月22日
-

9月議会に向けての知事申し入れ
議会前にはいつも補正予算への反映などをお願いするために知事申し入れをさせていただいていますが、本日も7項目の要望をさせていただきました。知事は「いま補正予算を作成しているところだが、要望の中身は共有できるものが多い」と応じました。要請の内容は以下の通りです。 2020 年9月16日 長 野 県 知 事 阿 部 守 一 様 日本共産党県議団 団長 毛 利 栄 子 9月県議会にむけた申し入れ 1. コロナ感染症は、感染力の強い無症状者が全国的に広がり、県内の感染者も増加傾向にありま す。集団感染の危険性が高い医療機関や介護施設、学校教育現場に限らず、クラスターが発生 した事業所の周辺や関係者への行政検査が受けられるようにしてください。また、市町村や地 域などで自主的に行われている社会的検査に、県として支援をしてください。 2. 命を守る最前線で活動している医療機関では、防護具などの衛生資材が不足しています。県と して医療や介護の現場で不足している資材を支給してください。 3. 新型コロナ関連による減収で厳しい経営状況にある県内の医療機関・介護事業所への減収補て んを国に求めてください。また、医療崩壊・介護崩壊を防ぐために県としても独自の支援策を 検討してください。 4. 中小企業や観光・飲食業などの経営と働く人の雇用を守るために、今後、自粛要請を行う場合 には補償と一体で対応してください。 5. 教育現場におけるソーシャルディスタンスの確保など感染拡大の防止、子どもたちの命を守る とともに学びを保障して継続するため、全国知事会や小・中・高・特別支援学校長会が国に要 望している小・中学校と高校の少人数学級の実現を、県としても改めて国に強く求めるととも に、実現のために県独自でも教職員の増員を検討してください。また、特別支援学校の過密解 消のために手厚い支援をしてください。 6. リニア中央新幹線の工事は、大量に発生する残土置き場をめぐって各地で災害の発生の危険性 が指摘され、住民の不安が広がっています。また、飯田市の新駅建設計画では説明が不十分で あること、また、移転条件の改善を求める住民が少なくありません。JRや行政が住民の不安 や疑問などに真剣に耳を傾けることが必要です。この計画はいったん立ち止まり、中止を含め た再検討を求めてください。 7. 突風や降ひょうにより農産物に被害を受けた農家に対して、農業を継続できる新たな支援をし てください。この間の一連の災害を受け、県が推奨しているリンゴの新わい化栽培は倒木し災 害に弱い状況がみられるので検証してください。 以上
2020年09月16日
-

県議クルーで下諏訪レガッタに出場
コロナ禍のなかですが、体温測定やマスク着用、消毒の励行などの細心の注意を払い下諏訪レガッタが開催されました。諏訪地域の5人の県議もクルーを組んで6市町村の首長や議長の皆さんとともに毎年300メートルのエキシビジョンに出させていただいています。昨年は全員そろっての練習が1回だけだったせいか3位。今年は何とか挽回をと早朝5時からの練習を3回実施して当日を迎えました。朝起きたら雨が降っていましたが、ボートは風がなければ決行とのことで漕艇場に。レースの前に少し練習をと思いましたが、時間がなく断念。アッという間に本番に。なんと今年は皆さんの息がぴったり合って1位!2位は首長さんたち。3位が議長さんたちでした。みんなで大喜びをしましたが、首長さんたちからは盛んに「忖度!忖度!」の声が飛びました。居ながらにしてボートに乗れる環境にあることは素晴らしいことだと思います。私はコックスの役目。何とかロスなく真ん中を走れました。ご尽力いただいた関係者の皆さんお疲れさまでした。ありがとうございました。また来年!
2020年09月13日
-

諏訪地区教育7団体で県教委に要望
例年行っていますが、今日は諏訪地区教育7団体が新年度の要望に来庁され、地元県議として同席させていただきました。要望項目は大きく4つです。1つは公立高校の募集定員を適正に決定し、生徒や保護者、教職員の声を反映した高校開会の実施2つは特別支援教育の充実3つは少人数教育推進と多様化する子ども達への支援体制の充実、臨時教員の待遇改善4つは教育条件整備の国への働きかけ です。諏訪地区の臨時教員比率は15%にもなっていることに改めて驚きました。先生方がきちんと正規で雇用され落ち着いて教育活動に当たれるために、いっそうの改善が求められます。特別支援教育に関わって発達障害などが増える中で通級指導教室の町村への設置や複数教員配置の必要性が切実に訴えられました。皆さんの願いが少しでも叶うよう、頑張ってまいります。遠路お疲れさまでした。
2020年09月04日
-

新型コロナウイルス感染症等対策条例案への討論
6月議会の主な焦点の一つは知事がコロナ感染症対策に必要とのことで提案した「新型コロナウイルス感染症等対策条例案」を採択するかどうかでした。党県議団はあまりに拙速な条例であり、第1波の検証もないまま特措法の枠を超えて私権の制限を加える条例を決めるのは慎重であるべきとの立場から継続を主張しましたが、採決に持ち込まれたため反対しました。49:6で可決。本会議で反対討論を行いましたので以下ご紹介します。 日本共産党県議団を代表し長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例案に反対の意見を述べます。 新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、まん延を防ぎ、県民の命と健康を守ることは行政の大きな役割であり、対策が成功するか、効果を上げることができるかは県民の協力を得られるかどうかにかかっています。 国の特措法の枠によらずに私権を制限する条例を制定し、県民の協力を求めるという以上これまで長野県がコロナ感染症対策として取り組んできた「三密を避ける取り組み、外出自粛要請、施設利用の休止、山小屋および観光・宿泊施設の休業要請、学校の休校措置、協力金、支援金、検査体制」などの施策等について多方面にわたって検証を行うことが、大前提であると考えます。 議会審査を通じて、理事者側はひと通りの振り返りを行う中で「観光宿泊施設に対する休業要請の取り組みには一定の効果があった、第2波においても必要最小限の範囲で休業を検討するなどの協力を求める仕組みを構築する必要がある。課題は見えてきた」との説明はされましたが、具体的にどうだったのか検証が不十分で、第2波に向けた課題についても抽象的と言わざるを得ず、なぜ条例が必要なのか、なぜ今急ぐ必要があるのか、条例がなければ協力はえられないのかなど納得できる説明や答弁はありません。こうした中で条例を制定することは、新型コロナウイルス感染症対策への協力が、要請ではなく事実上、知事の強制力を持つものになることが懸念されます。 知事から第2波、第3波に備えるために条例を制定したいと議会に投げかけがあってからわずか2か月。パブリックコメントも「指針」で定める原則30日でなく、最低限のたった2週間しかとらないまま、あわただしく議会に提案するやり方はあまりに拙速だと言わざるを得ません。日本共産党県議団は、県民の基本的人権に対する制約や経済活動への影響が大きいがゆえに、十分な時間をかけ、大いに県民各界から旺盛な論議を巻き起こしたうえで県民にとっての条例の必要性を判断すべきとの立場であります。しかし、ことここに到り、可否の判断を求められているため、賛同できない旨申し上げ討論といたします。
2020年07月03日
-

新型コロナ問題で臨時議会 質疑に立ちました!
令和2年4月臨時議会 毛利栄子議員 (2020年4月28日) 毛利栄子議員/新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、粉骨砕身のご奮闘をいただいている医療関係者の皆さん、行政関係者の皆さんに心から感謝を申し上げます。日本共産党県議団を代表し、質疑をさせていただきます。 最初に検査体制について知事に伺います。 感染の拡大やクラスターを防ぐためにPCRの検査体制の抜本的な拡充が必要であり、検査センターを設置してほしいと医療関係者や議会が一致して求めてきましたが、今回の補正で県内10圏域に新たに1 ~3カ所程度、全県で20カ所の初期診断と検体採取ができる感染症外来検査センターを設置する10億円余の予算が提案されています。 現状88検体から300検体へと、検査能力が3.4倍に広がることは大いに歓迎します。医師会やDMAT、大学や市町村の協力を得ながら早期に体制が整い稼働することを切に望みます。 そこで、この間の経過を踏まえ以下3点質問いたします。 一つは、発熱があり感染が心配で保健所に電話しても検査してもらえないという訴えや、検査が必要だと判断した患者もなかなか検査にたどり着けないという指摘が医療関係者の間でもされてきました。どのような基準で検体検査の必要性を判断しているのでしょうか。その基準について伺うとともに、見直しや改善も必要だと思いますがいかがですか。また、外来検査センターを設置することによって必要な検査が迅速に行えるようになるのか伺います。 二つ目は運用の仕組みについてです。まず保健所の窓口に連絡し感染の疑いがあると判断された場合に予約できる仕組みであり、これでは今でも相談業務に忙殺されている保健所の負担が軽減されるどころか、さらに増えることが懸念されます。今後ますますPCR検査が増えてくることが予想される中で、保健所を通さなければ受けられない合理的理由は何でしょうか。 三つ目は、一般的に体調が悪い場合はかかりつけ医に相談することが多いと思います。そのかかりつけ医が新型コロナの感染を疑い、必要と認めれば外来検査センターを紹介し、そこで検体を採取していただいたほうがスピーディーかつ大量に検査ができるのではないでしょうか。そうした迅速な取組こそ、感染防止やまん延防止に役立つと思います。今までの検査の仕組みを改め、かかりつけ医から直接センターを紹介し検査できる仕組みにしていただきたいと思いますが、知事の見解を伺います。 次に、長期休校における子どもと保護者への対応について教育長に伺います。 2月27日の首相の一斉休校の要請以来、春休みを含め子どもたちは2カ月近く外出自粛の下、友達と遊ぶこともままならないまま自宅での生活を余儀なくされています。子どもも保護者も生活のリズムが狂い、疲労感や不安、ストレスを抱え、親子げんかや兄弟げんかが絶えないという話も聞いています。 新型コロナウイルス感染拡大の異常事態の中でも、憲法と子どもの権利条約に基づき子どもの命と健康を守り、学習権を保障していくことは行政の大きな責務であると考えます。 子どもの学びをどう保障したらいいのか。県教委も地教委もそれぞれの年代に合った動画を工夫して作成し提供している努力は認めます。補正(予算案)では、県立学校のオンライン学習をサポートするための環境整備予算が6億円余盛られています。これを否定するものではありませんが、さまざまな理由によりICT環境が十分整っているとは言えない家庭もあったり、情報リテラシー教育が不十分なままネット漬けになったり、保護者などが仕事でいない下で使いこなせなかったり、健康への影響が心配されたりなど、課題は多いと思います。家庭の経済格差が学力格差につながることも懸念されます。休校のさらなる長期化も予想される下で、全ての子どもの学びを保障するためにどのような取組を行うのか、教育長の見解を求めます。 教師が家庭訪問をしたり、電話をかけたり、登校日を設けたりして、子どもたちの様子をつかむ努力をしている学校もありますが、宿題一つとっても、げた箱に置いておくので持ちに来るようにと機械的な対応しているところもあるとお聞きしますし、校庭や遊園地で遊べず居場所がなかったり、入学式で初対面のまま新たな担任の先生の人となりも分からずコミュニケーションを取れなかったり、給食がないために栄養が偏ったり、食費の増大が家計を圧迫したりと、保護者も子どもも不安定でイライラ感を募らせている実情を少なからず聞いてきました。 感染防止に最大限の配慮をしながら、週1回程度は分散登校する、保護者が先生と話す日を設ける、LINEなどでつながるだけでなくお便りを出すなど、心の通う取組、あらゆる場面で子どもの心のケアへの気配りがあってもいいのではないでしょうか。 学校や先生方の自主的な取組を尊重しつつも、県教委としても休校中の学習や生活、体力づくりの目安を示し、子どもも保護者も見通しを持った毎日を過ごせるよう対応を考えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 阿部知事/私には、検査に関連して3点ご質問いただきました。 まず、検査の必要性の判断基準というご質問でございます。本県ではこれまで、保健所における相談者からの相談の基準は、これは単に国の基準どおりということではなくて本県の考え方も加味しまして、広く帰国者・接触者外来につなげるという取組を行ってきております。保健所や地域の医療機関における検体採取なども含め、医師が必要と判断するものに対してPCR検査を行ってきているところでございます。 新型コロナウイルス感染症につきましては、軽症者あるいは無症状者の方が多く見られるということであります。感染拡大の要因となる可能性もありますので、医師の判断でできるだけ幅広く検査につなげていくことが重要だというふうに考えております。今回、補正予算に計上しております外来検査センターを設置する中で、検査体制の強化に合わせて幅広く検査に結びつけられるよう取り組んでいきたいと考えております。 続きまして、保健所を通さなければ検査を受けられない合理的理由というご質問であります。県民の皆さま方の不安軽減、まん延防止という観点から、有症状者相談窓口、そして帰国者・接触者外来の設置をして運用を行ってきておりますが、保健所を通すということによりまして、感染の疑いがある方を確実に診察、検査へと誘導するとともに、帰国者・接触者外来の受診に当たって、あらかじめ動線を分けるなど、適切な感染対策の下で患者、そして医療従事者双方にとって安全・安心な体制を確保することが必要というふうに考えております。 最後に、かかりつけ医の紹介で検査できる仕組みをつくってはどうかというご質問でございます。 現状におきましても、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症の疑い、PCR検査の実施の必要性や、あるいは帰国者・接触者外来の受診の必要性を認めた場合には、PCR検査、あるいは受診につなげているところであります。今後は、これまでの電話相談体制も維持しながら、感染者の大幅な増加も想定して具体的な仕組みを検討していくことが必要というふうに考えております。 各圏域において外来検査センターの運用方法等について検討を進めるに当たりましては、ご質問にありましたかかりつけ医から直接センターを紹介する仕組みについても視野に入れて、地域の実情に応じた準備を進めていきたいというふうに考えております。 以上です。 原山教育長/全ての子どもの学びを保障するための取組についてのお尋ねでございます。 臨時休校が長期間にわたっている中で全ての子どもたちの学習を保障するためには、一人ひとりの学びの環境や特性に応じた支援が必要であるというふうに考えております。このような個別に最適化された支援を行うためには、子どもの特徴を把握するとともに、子どもや家庭との信頼関係に基づいたきめ細かな対応や、その子の学びの進捗状況に合わせた課題の提供と適切なフィードバックを行うことが大切だというふうに考えております。 こうした取組には、家庭との緊密な連携による十分なコミュニケーションを図っていくことが大変重要だというふうに思っております。また、オンライン学習については、低学年児童への配慮や家庭の状況による学びの差ができる限り生じないよう対応するとともに、タブレット等の貸し出しを行えるよう整備を早急に進めてまいりたいというふうに考えております。 全ての子どもたちの学びが保障されるために、こうした観点に立った取組を県・市町村・学校一体となって進めてまいりたいというふうに考えております。 次に、休校中の学習や生活、体力づくりの目安についてであります。 本県においては、従来から健康観察や学習の取組を記録する1週間の計画表の作成に多くの学校が取り組んでいるところでありまして、今回改めて県教育委員会から計画表のひな形等、必要な情報を提供したところであります。 学習については規則正しい生活習慣を身に付け学習を継続できるよう、各校においては教科書等に基づく家庭学習を課したり、必要に応じて家庭訪問等によって学習状況の把握と指導を行っているところであります。生活面では、毎日の検温などの体調管理と手洗い等の感染症対策を行い、十分な睡眠、バランスの取れた食事など心掛けることとしております。体力づくりでは、1日おおむね30分といった運動時間や、ストレッチ、縄跳びといった運動量を示し、自ら取り組めるようにしているところであります。 今後は、各校の取組の中でも優れた実践例を収集し、子どもも保護者も充実した毎日が送れるよう、さらなる情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。 毛利栄子議員/再度知事に伺います。国はこれまで検査センター設置には消極的でしたが、世論の高まりの中で17日の記者会見で総理は、検査センターをつくる、かかりつけのお医者さんが必要だと判断したら直接センターに行ける、検査もできるようにすると考え方を変えてきています。 それなのに、国の補正予算には検査センター関連予算が1円も盛られていません。これだけ大事な機能に国のお金が1円も入らないというのは異常です。国に対し予算の保障を求めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 続いて教育長に伺います。学習の遅れを取り戻すと全国的には夏休み返上が話題に上っている向きもありますが、子どもへの多大なしわ寄せが懸念されます。今回、学習指導員追加配置事業費2,600万円余が補正に盛られ、市町村立小学校に補習のための学習指導員108人を追加配置する案が示されています。 人的配置は歓迎しますが、土曜・日曜授業などを行う場合も考えられるため、その場合には子どもの負担を考慮し、子どもたちの実態を一番よくつかんでいる現場の先生方を中心に知恵を集めながら、教育課程の編成を丁寧に行うことを求めますがいかがでしょうか。 未曾有のコロナ禍の下で、今回の補正を第一弾とし、命を守る、生活を守る、地域を元気にする、自粛を求めるなら休業補償と一体で行うべきと国に求め、適切な時期に第二、第三弾の大幅な補正が行われるよう求めながら、議会も、県当局、県民と一丸となってこの難局を乗り切っていく決意を申し上げ、私の質疑を終わります。 阿部知事/外来検査センターの設置についての国の支援を求めるべきだというご質問であります。 今回の予算計上させていただいております新型コロナウイルス感染症外来検査センターにつきましては、約2分の1国費を入れさせてただいているところであります。 全体的に県財政が厳しい状況でありますので、新型コロナウイルスの対応のための地方創生臨時交付金の増額も含めて、そうした措置は国に強く求めていきますけれども、この検査センターにつきましては国費が入ってるということでご理解いただければというふうに思います。 以上です。 原山教育長/新型コロナ感染症の終息を見極めることがなかなか難しい中で、今後とも厳しい制約条件の下での教育活動が営まれることを余儀なくされるというふうに考えております。 そういった中で、子どもたちの学びを保障するために、現場の教員の皆さんとともに県教委一体となって工夫を重ねて子どもたちの学びを保障していきたいというふうに思っております。
2020年04月30日
-
コロナ特措法に基づく緊急事態宣言がでているなか、緊急要望
小池 清本部長様第3回県議会新型コロナ感染症対策本部連絡協議会への要望 2020年4月22日 日本共産党県議団 団長 毛利 栄子1、知事へのお願いこの間知事部局に対し各会派や議会対策本部を通じて様々な要望を行ってきましたが、どのような対応をされたのかご報告いただけておりません。すべてについての対応報告を求めるものではありませんが、可能な限り県議会対策本部に対し対応報告をいただきたい。 2、検査体制の強化と医療崩壊を招かないための支援①PCR検査は現在県内3か所で88検体できることになっていますが、検査体制の抜本的な改善と拡充は緊急の課題です。「帰国者接触者相談センター」(保健所)を介さなければ検査ができないというこれまでの体制を改め、かかりつけ医が検査を必要と判断した場合は「PCR検査センター」で診察と検体採取を行って検査を実施し、陽性の場合には保健所に連絡するとともに重症者・中等症者は指定病院・協力病院に入院し、軽症者は指定された宿泊療養施設で隔離をするよう改善を図っていただきたい。そのために「PCR検査センター」を県内各地に設置できるよう早急に検討し実現をはかっていただきたい。 ②病院が新型コロナ患者を受け入れるためには病室をパーテーションするだけでは安全性が確保できないため、フロアーもしくは病棟全体を空きベッドにして対応しなければなりません。空床にし、一般診療や入院患者数を縮小することで減収となり、病院の存続にも多大な影響を与えるため、財政的な補償が必要です。現状を把握し、国に要望するとともに県としての助成を検討していただきたい。 3、休業要請に伴う問題について県が感染拡大対策として接客を伴う飲食店などの県内事業者に対し休業を要請し、応じた事業者に30万円の協力金・支援金の支給を決定したことは歓迎します。一方休業する事業者に食材などを納入している業者への波及が心配されます。どのような支援ができるのか検討する上でも、県として影響などの把握をしていただきたい。 4、児童・生徒の心のケア①小中高校特別支援学校が長期にわたって休校となり、自宅にこもっていることにより児童・生徒・保護者の不安やストレスは高まっています。児童・生徒・保護者の不安や学習の遅れ、体力づくりなどに対し、安全性に配慮した登校日を設けるなど見通しをもって過ごせる対策を検討していただきたい。②厚労省から事務連絡が出ていますが、要支援児童など虐待が心配されます。登校していないことにより教師の観察や児童の話を聞く機会もないため、地域協議会が連携して状況把握と対応ができるようにしていただきたい。 5、人権問題について知事は会見のたびに風評被害や差別・偏見など人権侵害に対してアピールをしていただいていますが、当事者や家族の皆さん、関係する事業所・職場はひどいバッシングで苦しんでいます。そうした事態がまかり通れば体調不良があっても検査をしない場合も出てくることが考えられ、感染防止・まん延防止にもならないことになります。医療従事者や医療機関には大変な中で限界まで頑張っていただいていることに対し感謝の気持ちを表すとともに感染された方々も被害者であるので、ことあるごとに差別や偏見、風評被害や人権侵害をなくしみんなで乗り切るようCMなどのメディアやSNSのツールなども含めいっそう強力なアピールをしていただきたい。
2020年04月22日
全2277件 (2277件中 1-50件目)
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 楽天BF4日目☆【購入品】安くておいし…
- (2025-11-28 10:34:16)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- *ほんわかするダックス姉妹。
- (2025-11-28 14:25:46)
-
-
-

- 政治について
- 電波・音波を使った凶悪犯罪!主導し…
- (2025-11-28 15:50:08)
-








