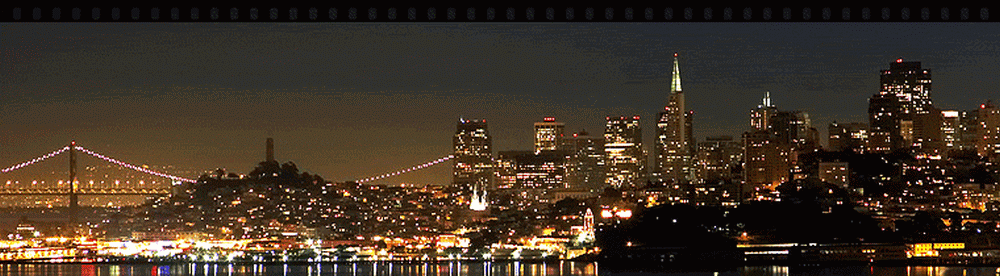2010年04月の記事
全88件 (88件中 1-50件目)
-

お庭神社
お庭神社明治4年(1871年)の廃藩置県により、磯邸が、鹿児島における島津本家の生活の場になりました。その後本丸御殿をはじめ各地に散在していた下記の諸神社を大正7年(1918年)に新築合祀しました。朝日、厳島、鶴ヶ岡八幡、八幡、菅原、鷹屋、大国、春日、諏訪、愛宕、稲荷、狐、御所大明神
2010.04.30
-

猫屋
猫グッズ 猫屋仙巌園内にあります、猫のグッズや招き猫など、猫関連の商品がたくさん揃っているお店です。みんなにこにこ いつもにこにこ金銀の招き猫右手を上げている猫は金運を招き、左手を上げている猫は人運を招く。と書かれていました。金と銀の招き猫が1匹ずつ入って「福おいで猫セット」¥588-.でした。猫窓ブランコに乗った招き猫
2010.04.30
-

ばくちのき
ばくちのき(はだかのき・Prunus Zippeliana Miq)暖地に自生する珍しい樹で、「ばくちのき」又は「はだかのき」と呼ばれています。樹皮は灰褐色で5月頃皮が大きく剥げ落ちた後は紅黄色の美しい幹肌になります。皮が剥げ落ちて裸になることからバクチ(博打)の木と名付けれたそうです。葉からはバクチ水が採れ、せき止めに利用されます。また、木材はマホガニーの代用として、家具器具に用いられ、八丈島では樹皮からは黄色染料を採るそうです。裸=博打っていう図式が面白いですね。植物の名前を付けた方も色々な方がいらっしゃるから面白いですね。遊歩道に落ちていた葉っぱと実バクチの木の葉と実ではありません。あしからず。
2010.04.29
-

曲水の庭周辺
曲水の宴周辺曲水の庭に至る石段や、江南竹林の前にて、「篤姫」のロケでは、若き日の小松帯刀(肝付尚五郎)の鹿児島城下でのシーンが撮影されました。放水して雨を降らせたり、スモークを焚いたりして、雨の城下風景シーンなども撮影されました。曲水の庭に至る石段曲水の庭周辺 石垣の塀曲水の宴の風景パネル
2010.04.29
-

千尋巌へ行く遊歩道入口からみた桜島
仙巌園の奥の方から見た桜島磯御殿の上には立席茶席「竹徑亭」があり、その上には、猫グッズの「猫屋」があり、猫屋の横には猫神様があり、その上にはろ過地や迫ン太郎、筆塚、観音岩があり、更に上に遊歩道の入口があります。遊歩道を登っていくと、時雨の滝が見えてきます。さらに進むと、観水舎跡があり、筆塚跡があります。ここまで行くと千尋巌が間近に見えてきます。更に進むと集仙台跡があります。仙巌園、とっても奥が深いです。
2010.04.28
-

発電用ダム跡
仙巌園の発電用ダム跡仙巌園の奥の方にある「発電用ダム跡」です。発電用ダム跡 29代島津忠義が建造した工場、「就成所(しゅうぜいじょ)」の送電発電用の貯水槽跡です。 これは、落差を利用して水車を回転させ、電力を得るというしくみで、明治25年(1892年)からはこの電力を使って邸内や庭のアーク灯に灯りを点し、就成所から邸内へ通じる自家用電話にも利用していました。 なお、「集成館(しゅうせいかん)」でもすでに、水力発電が実現しており、庭園背後の山の尾根伝いに導水路が残っています。 鹿児島市内の電灯の始まりは明治30年(1897年)、電話は明治39年(1906年)のことでありましたが、島津家はその先駆をなしたといえます。(以上現地案内板より)
2010.04.28
-

水道橋周辺
水道橋周辺NHK大河ドラマ「篤姫」のロケが行われたそうです。東屋篤姫のロケ風景のパネル
2010.04.28
-

千尋巌
千尋巌 (せんじんがん)仙巌園にて巨大な岩石に刻まれた11メートルにも及ぶ「千尋巌」の大文字は、27代島津斉興(なりおき)が文化11年(1814年)4月に完成させたものです。これを刻むために延人員3900人と三ヶ月もの日数を要し、工事の際は磯山の杉や竹で足場を組んで作業を行ったといわれています。このように岩に文字を刻む作庭方法は日本庭園では大変珍しく、中国文化の影響と思われています。仙巌園の中心部にあります磯御殿の裏山の上の方の岩に「千尋巌」と刻まれています。千尋巌の意味は、「とても大きな岩」というような意味があるそうです。延人員3900人と三ヶ月もの日数を要して刻まれた「千尋巌」、なぜこのように大きな文字を刻んだのでしょう。しかも、なぜ「千尋巌」と刻んだのでしょうね?磯御殿と千尋巌江南竹林と千尋巌江南竹林(以下現地案内板より) 江南竹林とは中国南部産の毛竹の別称で、わが国に伝えられた後、孟宗竹と呼ばれるようになりました。 21代島津吉貴が、元文元年(1736年)、中国から琉球国を通じまだ繁茂していない竹二株を取り寄せ移植したのが、わが国における孟宗竹の歴史の発端であるといわれています。磯山の麓に植えつけられた二株の竹は見事に生育し、ここから全国に移植されるようになりました。 現在のこの竹林は、平成5年(1993年)崖崩れにより流出し、平成8年(1996年)に再植栽したものです。
2010.04.28
-

磯御殿の中庭
中庭中庭の紅葉が美しかったです。紅葉と牡丹窓から中庭を見ると一枚の絵のようでした。池に映る牡丹と紅葉白い牡丹と紅葉池と紅葉
2010.04.27
-

磯御殿のふすま
仙巌園 磯御殿の襖ふすまに描かれた絵が素敵ですね。畳、襖、欄間・・・。日本家屋っていいですね。磯御殿の調度品
2010.04.27
-

磯御殿の前の池
化粧間の前の池 離婚したわけではないのですが、昔の名前「全喜楽」(ぜんきらく)へ、ニックネームを戻しました。懐かしい方には懐かしい名前ですよね。気分一新、また日記を更新していきますので、どうぞよろしくお願いします。 そういえば、全喜楽から楽天得子へニックネームを変えた時も、鬱陶しいコメントにうんざりして、前のブログを泣く泣く閉鎖し、やけのやんぱちで「楽天得子」という名前で新しいブログを立ち上げました。今回は、タイトルとニックネームを変えただけで、ブログの削除はしませんでした。 お気に入りの登録などをしてくださっている方々には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、今後ともどうぞよろしくお願いします。もう、タイトル名を変えることもニックネームを変えることも無いと思います。これからは、嫌なことは嫌ときっぱりと言っていこうと思っています。 ホームページ「九州旅倶楽部」とタイトルを同じにして、ホームページの更新にも力を入れていきたいと思っています。写真も情報もすごい量が貯まってきましたので、これからがんばってUPしていこうと思っています。 色々と私の勝手でご迷惑をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いします。 全喜楽(ぜんきらく)
2010.04.27
-
全喜楽の九州旅倶楽部
楽天得々紀行から「九州旅倶楽部」へタイトルを変更しました。楽天得子から「全喜楽」(ぜんきらく)へ名前を戻しました。これからもどうぞよろしくお願いします。
2010.04.27
-

化粧間
磯御殿の化粧間
2010.04.27
-

磯御殿にて琴の調べ
磯御殿にて琴を演奏中でした。日本家屋、琴、和服、牡丹が素敵でした。
2010.04.27
-

牡丹と池
ボタンと池ボタンと部屋朝日という名の牡丹牡丹の花言葉は、高貴、富貴、壮麗、恥じらい、誠実など
2010.04.27
-

磯御殿の屋根
磯御殿の屋根島津家の家紋、丸に十字が施された瓦
2010.04.27
-

磯御殿
仙巌園 磯御殿仙巌園の中心に磯御殿があります。明治17年(1884年)に大規模な改築が行われ、明治21年から10年間あまり、29代島津忠義が本邸として使用していました。現在は、島津忠義が使用していた部屋や、後の30代島津忠重が幼少期に暮らしていた部屋などを公開しています。
2010.04.27
-

仙巌園内の白い建物
仙巌園にて辺りを見回したのですが、案内板をみつけることができませんでした。これは何の建物なんでしょうね?
2010.04.26
-

門から桜島
仙巌園から桜島門から桜島
2010.04.26
-

私の好きにさせてください。
仙巌園にて人には人夫々のペースがあります。人には人夫々の都合があります。人には人夫々のブログの仕方があります。人は人夫々なんです。他人に自分の物差しを押し付けないで下さい。時間がたくさん余っている人ばかりではありません。忙しい中、時間をやりくりしてブログを続けている人がたくさんいます。私もその一人です。そしてブログの時間を気分転換にしています。それなのに、他人にとやかく言われたくありません。ほとんどの方は楽しくて、人の立場やペースを理解して、とっても優しくて、思いやりがあって、賢くて、状況判断ができて、他人に自分の物差しを押し付けたりする無粋なことはしない方ばかりです。ほとんどの方が、楽しいコメント、勉強になるコメント、嬉しいコメント、優しいコメント、応援コメント、素敵なコメントを下さる方ばかりです。でもたま~~~~~に、そうじゃない方がいらっしゃるんですよね。その方のコメントにやんわりと返事をしてもちっともわかって下さらないんですよね。何度も何度もやんわりと信号を送っているのですが、全く気がつかないのです。それが苦痛になってきました。そんなこんなでコメント欄を閉鎖しました。私のわがままをどうぞお許し下さい。ここは私のブログ。好きにさせてくださいね。
2010.04.26
-

獅子乗大石燈籠
獅子乗大石燈籠 (ししのりおおいしとうろう)この獅子乗大石燈籠は、畳八畳ほどの大きな笠石の上に、逆さの獅子が乗った大きな灯籠です。これだけ大きな石をみつけてくるのも大変だったでしょうね。
2010.04.25
-

鶴燈籠
鶴燈籠(つるとうろう)鶴が羽を伸ばしたように見えるところから鶴灯籠と呼ばれます。島津斉彬は、御殿からこの灯籠までガス管を引いてガスの実験を行いました。日本で初めてガス灯を灯けた鶴灯籠広い庭の中でも一際目立つ存在です。
2010.04.25
-

対の燈籠
磯庭園の対の燈籠庭も広く、燈籠も大きいですね。
2010.04.25
-

島津家水天渕発電所記念碑
島津家水天渕(すいてんぶち)発電所記念碑島津家の家紋、丸十紋が大きく施されていました。水天渕発電所は明治40年(1907年)に、島津家が経営していた山ヶ野金山(やまがのきんざん)(横川町・薩摩町)に電力を供給するため、姶良郡隼人町に建てられた発電所です。ヨーロッパ風の石造りの建物当時としては珍しく、昭和58年まで使用されていました。その後、九州電力の株式会社のご好意により、ここに記念碑として譲りうけたものです。
2010.04.24
-

近代薩摩焼発祥の地
近代薩摩焼発祥の地 極東の宝石といわれ、西欧諸国で「SATSUMA」と呼ばれ珍重された近代薩摩焼はこの地で誕生した。幕末の薩摩藩主島津斉彬は、西欧の近代産業を導入した工場群「集成館」をこの地に設置し、軍艦製造を中心としたさまざまな産業をおこした。 そして、その一環として、海外との積極的な貿易振興を目的に、在来の薩摩焼きの製法に改良を加え、貿易品として近代薩摩焼きを創製した。 斉彬はこの地に御庭窯を気築き、多くの陶工たちとともに研究を重ね、藩窯としての風格を備えた華麗な焼き物を完成させている。また、「SATSUMA」の名は、明治時代以後日本各地で製造され海外に輸出された美しい陶器の総称にもなった。(以上 現地説明板より)
2010.04.24
-

薩摩お土産処 亀鶴荘
薩摩お土産処 亀鶴荘仙巌園の中にある売店です。仙巌園限定や生産量限定の本格焼酎や有機の緑茶・紅茶・黒酢も取り揃えています。
2010.04.24
-

仙巌園の桜島小みかん
桜島小みかん仙巌園の庭園に桜島小みかんとボンタンと晩白柚子が実をつけていました。一番小さなみかんと一番大きなみかんが両方植えられているのが面白いですね。桜島小みかんは、小さいけれど、味が濃くて、甘くて美味しいですね。
2010.04.23
-

仙巌園のボンタン
ボンタン仙巌園の庭園にてボンタンとも文旦(ブンタン)とも呼ばれますね。バンペイユ(晩白柚)晩白柚(ばんぺいゆ)は、ミカン科の果物の一種で、ザボンの一品種です。名前は、晩(晩生)・白(果肉が白っぽい)・柚(中国語で丸い柑橘という意味)に由来します。むくのが大変ですが、美味しいですね。
2010.04.23
-

仙巌園 正門の近くの蔵
仙巌園にて仙巌園の正門の近くにこのような蔵がありました。詳しい説明をみつけることができませんでした。
2010.04.23
-

昇平丸
昇平丸(しょうへいまる)これは、仙巌園に展示されています実物の6分の1の模型です。斉彬が建造させた、我が国初の本格的洋式帆船です。3本マストのパーク型です。安政元年(1853年)12月に完成しました。推定排水量:370トン全長:17間(約31メートル)砲16門を搭載翌年、幕府に献上され「昌平丸」と改名されました。昌平丸
2010.04.23
-

錫門
錫門 (すずもん)仙巌園の錫門(すずもん)です。 錫門(すずもん)は、かつて薩摩藩の特産で屋根を葺いた朱漆塗り(しゅうるしぬり)の門です。錫瓦葺き(すずがわらぶき)の建造物としては、わが国唯一のもので、嘉永元年(1848年)の庭地拡張までは、仙巌園の正門として使用されていました。 この門は、19代島津光久(しまづみつひさ)の時に建てられたと伝えられており、その優美な姿を今日に伝えています。(以上 現地案内板より) その当時、谷山地区(鹿児島市南西部)の山から錫鉱山が発見され、薩摩藩主が早速技術者を集め、採掘を始めました。錫は金・銀に並ぶ高価な金属でしたので、島津藩の財源を担うほど、多量の錫が採掘されていました。現在この地区では、錫は採掘されていませんが「錫山」と言う地名が残っています。
2010.04.22
-

正門の丸十と五七の桐
丸に十字島津氏の家紋「丸に十の字」です。この十の字は何を表しているのかということは諸説あります。(1)「十字を切る」という形の呪符からきたとする説。(2)二本の箸を交叉して出陣戦勝の呪いにしたのが始まりという説。(3)キリスト教の印とする説。(4)二匹の龍を組合せたもの。龍がからみあって昇天する様を表すという説。(5)轡紋から転じたとする説。※(1)の説が有力とされています。五七の桐桐を使った紋の種類は色々ありますが、花の数を単位とした五三の桐、五七の桐などが有名です。五七の桐は、3本ある茎の真ん中の茎に7つの花があり、両脇の茎にはそれぞれ5つの花があることからそう呼ばれます。五七の桐の紋は、菊の御紋に次ぐ高貴な紋章とされていました。足利尊氏や豊臣秀吉なども五七の桐を天皇から賜っています。このため五七桐は、政権担当者の紋章という認識が定着することになりました。正門
2010.04.21
-

仙巌園 正門
仙巌園 正門正門 (以下現地案内板より) 明治4年(1871年)に廃藩置県が行われ、翌年、薩摩藩最後の藩主29代島津忠義夫人達は、鶴丸城から磯に居住を移しました。明治21年には、忠義本人も鹿児島に移り、その後、明治28年(1895年)に鹿児島の大工、大重伊三治に命じて建てさせたのがこの正門です。用材は裏山の樟を使い、島津家の家紋である丸十と五七の桐が掘り込まれています。 現存する、本門は昭和58年~59年(1983年~1984年)に解体修理を行ったものです。
2010.04.21
-

薩摩藩 百五十斤(ポンド)鉄製砲復元
薩摩藩 百五十斤(ポンド)鉄製砲 復元150ポンド砲百五十斤砲薩摩藩 百五十斤(ポンド)鉄製砲 復元以下 現地案内板より 幕末、薩摩藩主島津斉彬が反射炉で鋳造しようとした鉄製150ポンド砲の模型です。 1840年代、薩摩藩は、日本の他地域よりも早く、通商を求める西欧列強の外圧にさらされました。その軍事力、特に大砲を多数装備し、海上を自由に動き回る蒸気軍艦の存在に脅威を抱いた薩摩藩は、海岸要衝に砲台(台場)を建設し、大型の台場砲を配備するようになりました。当初、台場砲は、日本の在来技術で鋳造可能な青銅で造られていましたが、嘉永4年(1851年)薩摩藩主に就任した斉彬は、西欧指揮の溶鉱炉・反射炉を導入して鉄製砲を鋳造するようになりました。 斉彬の側近、市来四郎は安政4年(1857年)、鉄製150ポンド砲の鋳造に成功したと書き残しています。150ポンド砲は当時の最大砲で、重量150ポンド(約70きろ)の弾丸を焼く3,000メートル飛ばすことができました。翌安政5年に鹿児島を訪れたオランダ海軍将校カッティンディーケは、「砲台でみた150ポンドのパイアン砲(青銅砲)はきれいに鋳上げられたいたが、工場(集成館)で見た鉄製砲はあまりよい出来ではなかった」と書き残しています。また、文久3年(1863年)の薩英戦争では2門の150ポンド砲が使用され威力を発揮しました。
2010.04.20
-

仙巌園 せんがんえん
名勝 仙巌園 (磯庭園)所在地:鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1近代日本発祥の地と島津家別邸敷地は、50,000平方メートルにも及びます。島津家別邸仙巌園は、海に面した景勝の地に位置し、隣接する島津家の歴史資料館・尚古集成館では、薩摩の歴史を海から捉えた展示を行っています。仙巌園は、万治元年(1658年)、19代島津久光が別邸として構えたものです。その後、歴代の踏襲らによって受け継がれました。
2010.04.20
-

クリスマスローズ?レンテンローズ?
クリスマスローズ本来クリスマスローズとは、クリスマスの頃に咲く花だそうです。2~3月に咲く花はオリエンタリスは、キリスト教の四旬節(レント)の頃に咲くのでレンテンローズと呼ばれるそうです。でも日本では一般的に、まとめてクリスマスローズと呼ばれているそうです。ってことで、クリスマスローズでいいかな?うつむき加減のクリスマスローズクリスマスローズってちょっとうつむき加減に咲くから、写真を撮るのが難しいですね。
2010.04.19
-

ビオラ?パンジー?どっちにしてもスミレの一種!
紫のパンジービオラかな?花の直径が3~5cm以上のものがパンジー、それより小さいものがビオラだそうですが・・・。これはビオラかな?ビオラかパンジーかわからないけれどおじさんに見える花このお花、おじさんの顔にみえませんか?
2010.04.19
-

スノーフレーク
スノーフレークスノーフレークは、オオマツユキソウ(大待雪草)、スズランズイセン(鈴蘭水仙)とも呼ばれます。花言葉は、美、慈愛、純潔、純粋、清純、無垢な心、皆をひきつける魅力などです。妖精がこぼした涙の雫のようですね。清楚で可愛いお花ですね。
2010.04.19
-

カロライナジャスミン
カロライナジャスミン実家の玄関にあった鉢植えの花です。カロライナジャスミンは、サウス・カロライナ州の州花にもなっています。カロライナジャスミンは、ジャスミンという名前がついていますが、モクセイ科ソケイ属のジャスミンとは全く違う種だそうです。リンドウ科やキョウチクトウ科などに近縁のマチン科に属する植物です。ジャスミンのような優しい香りはするのですが、実は・・・、全草にゲルセミシン、ゲルセミン、センペルビリンなどの有毒成分を含む有毒植物です。あわわわわ~恐いですね。美しいものには毒がある??サスペンスに登場しそうなお花ですね。
2010.04.19
-

実家に咲いていたピンクのお花
実家の庭にて大分の実家の庭にいっぱい咲いていました。キク科の一種でしょうか?お花の中央が、カスタードクリームにちょこんとイチゴジャムをのせたみたいでした。可愛いお花です。
2010.04.19
-

雷山でみかけた黄色い花
雷山散策中にみかけたスイセン雷山(らいざん)は、福岡県糸島市と佐賀県佐賀市に跨がる標高955メートルの山です。脊振山地に属し、山頂は福岡県側に位置しています。中央の花びらがフリルになっているスイセンヒイラギナンテンの花ヒイラギナンテン(柊南天)の花、とってもキュートな黄色でした。トウナンテン(唐南天)ともいうそうです。葉はヒイラギ(柊)に似ていて、実がナンテン(南天)に似ていることから両者をあわせてヒイラギナンテンと名付けられたそうです。はっぱの棘は、ヒイラギより優しく、実は、ナンテンの実は赤ですが、ヒイラギナンテンの実は緑色だそうです。
2010.04.19
-

咲いた咲いたチューリップの花が♪
チューリップ春と言えば、チューリップ。チューリップって可愛いですね。最近は種類も豊富で、様々なチューリップを見ることができます。こんなにたくさんのチューリップが咲いていると、ひとつ位、親指姫が隠れていてもよさそうですね。
2010.04.18
-

謎の芝桜事件発生
芝桜(シバザクラ) 山口県岩国市のJR岩国駅前で、4月16日(金)、ロータリーの花壇に植えられたシバザクラの苗約100株が何者かに根元から掘り返されるという事件が起こりました。丁度ピンクのお花が見頃でした。 岩国署は器物損壊容疑で捜査を開始しましたが、聞き込みや鑑識活動からは不審者が浮かびませんでした。 付近の監視カメラの映像を分析してみると、意外な犯人が映っていました。 それは数羽のカラスだったのです。くちばしで器用に1本ずつ掘り返すと、転がして遊んでいたそうです。 捜査は打ち切られましたが、17日の夜も数羽が再犯を敢行。捜査員の神経を逆なでしたそうです。 (以上 朝日新聞 4月18日(日)朝刊より) カラスの行動ってけっこう謎なんですよね。食べるためだけではなく、いたずらや、あそびの行動が結構ありますね。 しかし、お花を引っこ抜いて転がして遊ぶのは止めて欲しいですね。
2010.04.18
-

アイスホーリー
アイスホーリー水仙(スイセン)の一種です。可憐で上品なお花ですね。「アイスホーリー」ってどんな意味でしょう?ホーリーって、聖なるっていうような意味だけど、アイスとホーリーがくっつくとどうなっちゃうのかな?
2010.04.18
-

プリムラ・ジュリアン
プリムラ・ジュリアン花言葉は、永続する愛情・青春の喜びと悲しみ・運命をひらく・可憐・美の秘密・永続する愛情などです。サクラソウ科サクラソウ属の園芸植物です。葉っぱがなんだか野菜っぽくて、美味しそうですね。
2010.04.18
-

菜の花畑
菜の花菜の花を見ると思い出すこと。中学1年生の春、声楽部の入部試験。先生や先輩、入部希望者の前で「朧月夜(おぼろづきよ)」を歌いました。菜の花畑に 入日薄れ見渡す山の端 霞深し春風そよふく 空を見れば夕月かかりて 匂い淡しその試験でソプラノに決定。ついこの間のことのような気がするのに、もう30年以上も前のこと。うそみたいです。
2010.04.18
-

たんぽぽを見ると思い出す方
たんぽぽ以前お仕事でお世話になった方。◆日新聞の記者だった方。色々な本も出版している方。優しくてダンディで色々なことを教えて下さいました。「ダンディライオン」がたんぽぽの英名だと教えて下さいました。dandelionは、フランス語でライオンの歯だと。ダン=ド=リオン(dent-de-lion)。たんぽぽのギザギザした葉がライオンの牙に似ているから。私は、ライオンのたてがみとたんぽぽが似ているのかと思いましたが、違っていました。ライオンの牙だったんですよね。実際に取材した事件で、吉川線(よしかわせん)を発見し、自殺ではなく、事件だということに警察より早く気がついたこと。色々な事件を取材したお話、すごく興味深く伺いました。今は職場が変わり、なかなかお会いする機会がなくなりましたが、その方のお話はいつも面白く、そして勉強になりました。時々電車でお会いすると、気軽に声をかけてくださり、隣の席に移動してきてくださり、私が降りまるで色々なお話をして下さいます。また、電車でお会いできる日を楽しみにしています。
2010.04.17
-

春のお花畑でひなたぼっこ
白い花春のお花畑でピクニック優しい風がお花畑の上を通り、私のほほを撫でていく。優しい陽射しがぽかぽかと背中を暖めてくれる。心地よい陽だまりでひなたぼっこ。色とりどりのお花を眺めながらひなたぼっこ。紫の花オレンジの花
2010.04.16
-

丹下梅子のブロンズ胸像
丹下梅子のブロンズ胸像丹下梅子(たんげうめこ)の生誕地が山形屋鹿児島本店1号館付近ということで、山形屋の前にブロンズ胸像があるようです。丹下梅子は、日本の栄養学者で、日本初の女性農学博士です。女性で初めて帝国大学に入学、卒業した方です。ビタミンの研究などを行い、82歳で死去するまで独身を通し、女性化学者の先駆者として学究一筋の生涯をおくりました。鹿児島市内のガスのマンホール中町ベルクの記念撮影用顔出し看板坂本龍馬とお龍さんが露天風呂に入浴中。上にいるのは、いのししかと思いきや、「カライモモグラ」と書かれていました。
2010.04.15
-

昭和28年11月 電車どおりから見た山形屋全景
昭和28年11月 電車どおりから見た山形屋全景の写真山形屋鹿児島のショーウィンドウ
2010.04.15
全88件 (88件中 1-50件目)
-
-

- ☆留学中☆
- 米国大学院2年目の学費
- (2025-07-02 00:03:00)
-
-
-

- ヨーロッパ旅行
- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…
- (2025-10-28 17:31:03)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 2025年12月15日 静岡県袋井市 🏯 秋…
- (2025-11-15 00:00:10)
-