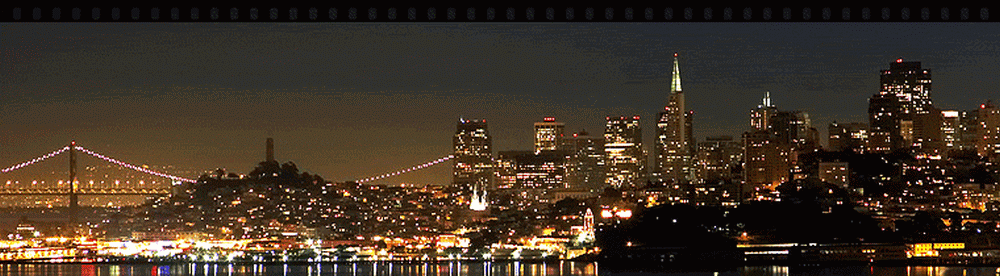2010年11月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

福澤茶屋
福澤茶屋のとり天定食 ¥750-.所在地:大分県中津市留守居町591福澤諭吉の生家の駐車場内に隣接しています。営業時間:10:00~17:00 定休日: 月曜日(祝日の場合はその翌日)とり天とり天は、鶏肉にしょうゆ・しょうが・塩コショウなどで下味を付けて、天ぷら衣をつけて揚げた大分県の郷土料理です。大分ではポピュラーな料理です。お持ち帰り弁当のおかずなどにも入っています。そのまま食べたり、酢醤油やかぼす醤油をつけたり、塩や抹茶塩をつけて食べたりもします。中津はからあげも美味しいお店が多いのですが、とり天も美味しいお店があります。
2010.11.30
-

華やかな菊
大貞八幡宮 薦神社 菊花展にて可憐で華やかな菊ですね。昨今は結婚式にも菊を使うことが増えてきたそうですが、これだけ可愛くて華やかだったらいいですね~。鮮やかな色の菊。 九州場所も終わり、これから冬将軍の到来ですね。寒くなりそうですね。皆様も暖かくしてお出かけしてくださいね。では、今週もぼちぼちいきましょうか
2010.11.29
-

柊 ひいらぎ ヒイラギ 銀木犀じゃなかったのね。
柊 (ヒイラギ)博多ぶらぶら中、優しく甘い香りがしていたので、そばに近寄ってみると、白い可愛いお花がいっぱい咲いていました。最初は銀木犀(ギンモクセイ)かな?と思ったけど、葉っぱが違う。ギンモクセイは葉っぱにとげがなくてすべすべのはず。柊木犀(ヒイラギモクセイ)かな?とも思ったけど、それにしては、葉っぱの棘が鋭い。通りがかった近所の素敵な奥様にお尋ねしたところ、「柊(ヒイラギ)ですよ。」と教えてくださいました。ヒイラギというと、玄関にイワシと一緒に吊るしている魔よけのイメージが強かったのですが、こんなに可憐で可愛いお花が付くのですね。しかも優しくて甘くて切ないような素敵な香りが漂っていました。ヒイラギファンになりました
2010.11.27
-

パンダタクシー
パンダタクシー博多の町をぶらぶらしていたら、パンダタクシー発見可愛い~。ドライバーの方が快く写真撮影を許可してくださいました。しかも、「写真を撮ってくださってありがとうございます。」とまでおっしゃってくださいました。と~っても感じがいい方でした。当日は博多ぶらぶら中でしたので、タクシーには乗りませんでしたが、いつかきっとパンダタクシーに乗りたいですドライバーの制服は、白いシャツ、黒のベストとパンツ、そして赤い蝶ネクタイタクシーと統一感があり、きちっとされていて好感度パンダタクシーは、初乗り¥290-.です。安いですね~ジャンボパンダタクシーもあるそうです。詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。パンダタクシー の公式サイト
2010.11.26
-

雷山千如寺大悲王院の大銀杏
雷山千如寺大悲王院の大銀杏大銀杏も色づいていました。雷山千如寺を開創された清賀上人は、千如寺をはじめ、旧怡土郡の七ヶ寺を建立されました。雷山千如寺大悲王院の開山堂には、国指定重要文化財の木造清賀上人座像安置されています。左手に経巻、右手に念珠を持ち、経典を唱えている御姿です。耳がすごく大きく、口を開き、歯と舌が見えます。かなり個性的なお姿でインパクトがあります。
2010.11.25
-

雷山千如寺大悲王院の大楓
勅願道場雷総本坊 別格本山 雷山千如寺大悲王院の大楓所在地:福岡県糸島市雷山626政務天皇の418年(178年)、雷山の地主神である雷大権現のお招きで渡来された天竺霊鷲山の僧侶 清賀上人の開創と伝えらています。大楓の紅葉は散り始めていました。もう少し早く伺えばよかったかな?国指定重要文化財の本尊十一面千手千眼観世音菩薩像(一丈六尺・像の高さ:463.6cm)が本堂に安置されています。僧侶が千如寺の歴史などを説明してくださり、その後、健康安全などの祈願をしてくださり、さらに観音様のすぐそばを通ることができます。ありがたいです千如寺の大楓(おおかえで)鎌倉時代の作品と言われています十一面千手千眼観世音菩薩は、頭部に十一面、本体に四十二本の手、光背に千の手があり、千の慈眼、千の慈手を持っていらっしゃいます。すごく大きくて、穏やかで優しい表情の観音様です。千如寺 大悲王院 の公式サイト
2010.11.24
-

満月寺の膝から下が地面に埋まっている仁王像
満月寺(まんがつじ)の仁王像 阿形像国宝臼杵石仏を造らせたと言われる真名長者の発願により、蓮城法師(れんじょうほうし)により創建されたといわれるお寺。ここにはなぜか膝から下が地面に埋まっている仁王像があります。満月寺の仁王像 吽形像こちらの仁王像は、膝から下が地面に埋まっているのも不思議ですが、表情が独特でユーモラスで、かなりインパクトがあります。しかし全体的には力強い作風で、不思議な雰囲気を持っています。凝灰岩製で、鎌倉時代後期以降、室町時代前期頃までの間に設立されたと推定されているそうです。満月寺(まんがつじ)満月寺は、臼杵石仏の縁起に欠かせない真名長者(まなのちょうじゃ)の発願により、三重町内山蓮寺を開いた蓮城法師によって創建されたという伝説があります。あくまでも伝説で正確なことは未だ判明していないそうです。
2010.11.17
-

国宝 臼杵石仏
古園石仏 大日如来坐像平安時代後期~鎌倉時代にかけて彫られたと言われています。切れ長の目に引き締まった口元、その口元には紅が残っています。美しいアーチを描いた眉、端正で気品溢れる表情です。ふっくらした頬など優しさと慈悲深さも感じます。当日は曇天の為、湿度が高く、色が鮮やかに見えました。古園石仏中央が大日如来坐像、向かって右側が伝無量寿如来坐像、向かって左側が伝阿?如来坐像です。中尊の大日如来像は、以前は台座の上に仏頭が安置されていました。平成6年3月に胴と仏頭が一体となり、現在の御姿になりました。臼杵石仏といえば、こちらの大日如来像の仏頭のみの御姿が印象的でしたが、元の御姿に修復されてなんだかほっとした気持ちです。じっと見つめていると反対に見つめられているような気持になります。国宝 臼杵石仏 公式サイト
2010.11.16
-

大相撲九州場所のふれ太鼓
大相撲九州場所のふれ太鼓平成22年11月13日(土)博多の街にふれ太鼓の音が響き渡りました。昨日11/14(日)大相撲九州場所の初日を迎えました。初日の取組表を配ってくださり、初日の取組を案内してくださいました。「魁皇は~安美錦とじゃぞ♪」「白鵬は~栃ノ心とじゃぞ♪」と語尾が「じゃぞ」になっているのが面白かったです。博多の街をふれ太鼓の音が響く光景は、情緒があっていいですね。さて、今週~来週は、大相撲中継をみたいので会社からダッシュで帰ってきます。日本相撲協会公式サイト
2010.11.15
-

うすき竹宵 羽ばたくオブジェ
竹ぼんぼりのオブジェ臼杵の町並みを最大限に活かして竹ぼんぼりを飾り、美しく温かい竹灯りとみごとな細工を施した竹を組み合わせ、街のあちこちに様々なオブジェが飾られていました。色とりどりの竹ぼんぼり様々な工夫を凝らし、色とりどりの竹灯りが暗闇を幻想的な世界に変えています。うすき竹宵 オフィシャルウエブサイト
2010.11.11
-

般若姫行列 うすき竹宵
うすき竹宵 般若姫行列祇園様(八坂神社)から街中へと般若姫の行列が進みます。うすき竹宵は、年に一度、都より長者夫妻の元へ里帰りする玉絵箱(般若姫)を、里人が竹に火を灯してお迎えする行事です。般若姫(はんにゃひめ)可愛らしく綺麗な御嬢さんが「般若姫」に扮していました。般若姫の行列には、3つの御輿車があり、玉絵姫(般若姫の娘)、玉津姫(般若姫の母)、般若姫が其々の車に乗っていました。般若姫伝説 (以下うすき竹宵の公式パンフレットより) 炭焼き小五郎(後の真名長者)の妻を玉津姫といい、二人の間に般若姫という気高く美しく、世間で評判の娘がいました。その噂を聞いた朝廷は、妃として都へ差し出すよう命じますが、長者はそれを拒み、代わりに姫の姿を描き写した「玉絵箱」を差し出しました。 ところが、箱の絵を見て恋心を抱いたのが橘の豊日の皇子(後の用明天皇)でした。 皇子は般若姫に逢うため、牛飼いに身をやつし、長者の元へやって来ました。やがて愛し合う二人は結ばれ、幸せな日々を過ごしますが、朝廷に呼び戻され、身重の姫を残し都へ帰っていきました。その後姫は、玉絵姫というかわいい児を出産しました。やがて姫は当時の習わしのために、生まれたばかりの玉絵姫を残し、都へ上がりましたが、途中で嵐に遭い帰らぬ人となっていました。 悲嘆のつのる長者は姫のお供養のために石仏を彫らせました。そのことを聞いた朝廷は、年に一度、夫妻のもとへ玉絵箱の里帰りを許しました。 秋の陽はとっぷり暮れ、里人たちは竹に明かりを灯し、姫をお迎えするために足元を明るくしました。
2010.11.09
-

うすき竹宵
うすき竹宵 臼杵竹宵 うすきたけよひ2010.11.6(土)~2010.11.7(日)にうすき竹宵が開催されました。うすき竹宵は、年に一度、都から真名長者夫妻のもとへ里帰りする玉絵箱(般若姫の絵)を、里人が竹に火を灯してお迎えする行事です。神社仏閣、町並みが幻想的な竹灯りで照らされ、幽玄な雰囲気を醸し出しています。江戸時代の名残を伝える臼杵城下町を細工を施した竹ぼんぼりやオブジェが彩っていました。街中が観光客で埋め尽くされるほどの人出でした。うすき竹宵の二日間で4万人以上の人々が訪れるそうです。出店などもたくさん出て賑わっていました。楽しい時間をすごすことができました。
2010.11.08
-

旧松本家の食卓
旧松本家(西日本工業倶楽部)にておしゃれなキャンドルですね。キャンドル・ジュンさんじゃないですが、キャンドルって幻想的で温かくておしゃれでなんだかいいですね。ただ、火事には気をつけなくっちゃ。旧松本家の食器食器には「KM」のイニシャルがデザインされていました。家主であった松本健次氏のイニシャルです。どのようなお料理が盛られていたのでしょうか? 急に冷え込みましたね。これできっと紅葉も進むかな~?と、思いは週末へ・・・。今週は祝日があったので、1週間経つのが早く感じます。さぁて、今日もぼちぼちいきますか
2010.11.04
-

旧松本家のステンドグラス
旧松本家 ステンドグラス和田 三造 作たわわな葡萄の房と白雲をモチーフとした七色のガラスは洋館に華やかさと癒しを与えています。政策は大正中期ではないかと言われています。日本人の手によるステンドグラスとしては初期のものと言われています。葡萄の樹の下を優雅に飛び交うツバメが気持ちよさそうですね。洋館の一階から2階へと続く階段の踊り場の壁に3枚のステンドグラスがあります。
2010.11.02
-

旧松本家一般公開 西日本工業倶楽部
旧松本家 洋館現在は、西日本工業倶楽部所在地:北九州市戸畑区一枝1-4-33設計:辰野金吾(洋館の設計)建築面積:624.9平方メートル構造:木造二階建この建物は、明治専門学校(現在の九州工業大学)の創立者のひとりであった松本健次郎が、明治41年から44年にかけて自らの住宅と学校の迎賓館を兼ねて建てたものです。10/29(金)と10/30(土)の二日間、旧松本家の一般公開がありましたので行ってきました。洋館は、外観および室内意匠、家具とも大変優れたアール・ヌーボー様式でデザインされていて、外観はもちろん、室内、家具などひとつひとつ大変見ごたえがありました。旧松本家 日本館建築面積:466.1平方メートル設計:久保田小三郎(洋館の建築監督もしてました)洋館と日本館は廊下で繋がっています。西日本工業倶楽部のホームページ
2010.11.01
全15件 (15件中 1-15件目)
1