-
1

朧月夜の尚侍(かん)の君 -1-
「かわいい女性」という条件で私の頭の中を検索すると、第一番目にヒットするのは、源氏物語に登場する「朧月夜の尚侍の君」です。南殿で桜の宴が催された春の夜、藤壷の宮に会える機会を狙って、源氏の君は弘徽殿のあたりを忍び歩いていました。ちょうど細殿の三番目の戸が開いていたので、そうっと入ってみると「朧月夜に似るものぞなき~」と、若くかわいい声で歌いながらこちらに来る女性がいます。酔った勢いで彼女の袖を引くと、「まあ、気味が悪い。あなたは誰」と言うものの、さしたる抵抗もしません。原文では「あさましきに あきれたるさま、いとなつかしう をかしげなり。わななく わななく、『ここに、人』と のたまへど」とあって、突然の出来事に呆然としている様子がたいへん幼げでかわいらしく、わななく声で「ここに人が」と言うのもどこかあどけなく、可憐に聞こえるような描き方です。父・右大臣はこの六番目の女君を、女御として入内させようという腹積もりがあったのですが、この事件のために尚侍(ないし)という、職業的身分で参内させざるを得なくなりました。この尚侍の君が発熱してお里退りしているときのこと、二人は示し合わせて「夜な夜な対面し給ふ」のです。尚侍におなりになった朧月夜の君は、活き活きとした華やぎのある魅力的な女性で、今が一番美しいお年頃なのです。
April 3, 2006
閲覧総数 1993
-
2

末摘花 -8-
源氏の君は、それが誰ともまだ見分けることがおできになりませんが、ご自分の正体を知られたくありませんので、抜き足でその場を退き給うのです。すると男がつと寄って来て、「私を置き去りになさった恨めしさに、ここまで御送りつかまつりました。もろともに 大内山は出でつれど 入るかた見せぬ いさよひの月(ご一緒に内裏を退出したしたはずですのに、入った場所はお教えくださらないのですね。あなたはまるで、いつ入ったか知れぬ十六夜の月のようだ)」 と、嫌味を言いますのもいまいましいのですが、『頭中将であったか』とほっとなさいますと、少し可笑しくもお思いになります。「人の後を付けるとは、思いもよらぬことをするのですね。里わかぬ 影をば見れど 行く月の いるさの山を たれかたづぬる(月はどの里も分け隔てなく照らすものですよ。その月の後を付けて、入る山にまで尋ねて行く人などあるものですか)」 癪に障るので、そうお返しになります。すると頭中将が、「私がこのように御後を付け回したら、どうなさいますか」 と、申し上げます。「まさにこのような御忍び歩きには、随人が大事でありましょう。お供しだいで事がうまく運ぶというものです。これからは私をこそ、お連れくださるのがよろしいでしょう。ご身分を隠した御忍び歩きには、軽率な事も起こるでしょうから」 と、反対にお諫め申し上げるのです。
July 17, 2010
閲覧総数 438
-
3

若紫 -27-
源氏の君は僧都にお仕えする小さな童に、尼君への御文を持たせます。「夕まぐれ ほのかに花の色を見て 今朝はかすみの 立ちぞわづらふ(昨日の夕ぐれに、ほのかに見た少女の愛らしさを忘れることができません。帰京する今朝は我が心にも霞が立ち、出立しかねております)」 尼君からの御返事には、「まことにや 花のあたりは立ち憂きと かすむる空の 気色をも見む(花のもとから離れがたいとの仰せでございますが、霞がかかった空の気色のようなあなたさまの御心ざしのほどを、私も拝見させていただきましょう)」 と、優雅な筆使いでたいそう上品に、しかもさりげなく書いていらっしゃるのです。 御車にお乗りになる頃、左大臣邸より、「何処へとの御連絡もなくお出掛けになりましたので」 と、お迎えの人々や左大臣の公達が、あまた参上なさいました。源氏の君をお慕い申し上げる、頭中将や左中辨、その他のご子息達も、「このような時こそお仕えしたいと存じておりまするのに、思いがけず私どもを置いてけぼりになさるとは」 とお恨み申し上げるのですが、「それにしても、このようにみごとな花を愛でもせず京に帰るのは、もったいないことですな」 と、言い合うのです。
May 13, 2010
閲覧総数 1163
-
4

中将の君@幻
紫の上を失った後の源氏は、魂も抜けたような毎日を送ります。 中将の君という女房は、生前紫の上がかわいがっていた女房です。 「中将の君の、ひんがし面(おもて)にうたたねしたるを、あゆみおはして、見給へば」 中将の君が東面の自分の局でうたたねをしていました。そこへ源氏がいらしたのですが、たいそう細く小柄でかわいらしい格好をして、「起きあがりたり」起き上がりました。 「つらつき、花やかに匂ひたる顔を、もてかくして、すこしふくだみたる髪のかかりなど、いと、をかしげなり」 寝起きなものですから、頬のあたりが花やかに赤みを帯びてつやつやしていますのを扇で隠していますが、髪が乱れてふくらんで、肩にかかっているのもたいそううつくしく愛らしいのです。 この時、中将の君はまだ喪服を着ているのですが、その「裳・唐衣もぬぎすべしたりけるを、とかく、ひきかけなどするに」腰に着ける裳や、一番上に着る唐衣の脱ぎすべらせているのを、慌てて腰や肩にひきかけようとしている、というのです。 小柄でかわいらしい女房が着衣の紐をゆるめたり、身体から脱ぎ滑らせたりしてくつろぎながら「うたたね」しているのですが、紫の上が亡くなったあとにひょいと出てくるこの場面は、のどかでユーモラスで、なにかとてもほっとするものを感じさせます。
July 6, 2008
閲覧総数 3296
-
5

演歌「さざんかの宿」の歌詞に対する倫理的考察
「くもりガラスを手で拭いて、あなた明日がみえますか」くもりガラスはもともと向こうを見通せるものではないので、手で拭くという行為は無意味であり、不自然である。だが反語として捉えるならば、「みえない明日」を強調するための「くもりガラス」となり、非常に屈折した表現であるといえる。「愛しても、愛しても、ひとの妻」「自分の妻」に対して裏切り行為をしておきながら、「他人の妻」には惜しみなく愛情を注げることに、身勝手さと理不尽さを感じる。しかしまた、これを逆に考えるならば、「他人の妻」だから愛せる、或いはここでの「愛する」ことの条件が、あくまで「他人の妻」であることと捉えることができる。「抜いた指輪の罪のあと、噛んでください、思い切り」結婚指輪を抜くことに象徴されるのは「背徳感」と「罪悪感」であり、しかもそこを「噛んでください」と相手に要求しているところに、自虐性と自己憐憫がある。しかしそれは罪の代償とはなりえない。「明日はいらない」刹那的で退廃的な表現の中に、陶酔した自己憐憫が感じられる。「せめて朝まで腕のなか、夢をみさせてくれますか」「朝までいっしょにいられない関係」であることを承知していながら、それを要求する「ないものねだり」の心理に、幼稚な甘えがある。いずれは別れるべき相手であるという覚悟がないのだが、しかしそれを知ってはいるらしく、だからこそ「夢」を見たいという。そこに自己矛盾が生じるのだが、矛盾と捉えていないようである。考察この世界には「ひとの妻」と人目を忍ぶ「卑屈な逢瀬」があって、それを奪い取ってでも正式に「自分の妻」にしようという積極的で建設的な愛の姿勢がみられず、「さだめ哀しい」或いは「春はいつ来る」と常に受身な諦念があり、さらにあくまで屈折した罪悪感と自己憐憫というステージで、じっとりと湿っぽく展開されている。・・・と、いえるのではないでしょうか・・・。
September 10, 2006
閲覧総数 14130
-
6

玉鬘 -25-
六条院に姫君をお迎えするお部屋を考えてみますと、さしあたって源氏の大殿と上がお住いの南の町には空きがありません。紫の上のご勢力は格別で女房たちも多く住んでいますので、人の出入りも多く目につきやすいようです。秋好中宮のおわします西南の町は、参内なさる間は御留守でいらっしゃいますので姫君が住むには好都合なのですが『お仕えする女房と同列に思うかもしれぬな』とお考えになり、『少し目立たないが、花散里のいらっしゃる東北の町の文殿をよそに移して』とお思いになります。『一緒に住むにしても、花散里の君は控えめで気立てのよいおん方でいらっしゃるから、きっと良いお話し相手になるであろう』と思っていらっしゃいます。紫の上にも、かつての夕顔の君との事情をお話しなさいます。上は、大殿がこんなふうに御心に秘めていらした事をお恨みになります。「仕方がないのですよ。この世に生きている人なれば問わず語りにでもお話し申しましょう。しかしとうの昔に亡くなったのですからね。それをこの折に隠し立てせず全てをお話しするのは、あなたさまを特別な御方と思えばこそではありませんか」と、たいそうしみじみと思い出していらっしゃいます。「我彼の身の上でも多くの例を見て参りまして、それほど愛情のない間柄でも女というものの愛執の深さを見聞きするにつけ『今さら好色がましい気持は起こすまい』と思ったものですが、ついついそうばかりもいかない人と数多く付き合って参りました。その中でしみじみと愛おしく感じたのは夕顔の君だったと思いだされるのです。もし生きていたならば、北の町にお住いの明石の上と同じくらいにはお世話したでしょうね。個性というものは人それぞれだが、夕顔という女君は、利発で気の利いた趣味という点では劣っていたけれども、品があって弱々しく可愛らしかった」とお話しになります。
January 29, 2013
閲覧総数 6
-
7

葵 -17-
女は風情のある扇の端の方を折って、「はかなしや 人のかざせるあふひゆゑ 神のゆるしの 今日を待ちける(頼みになりませんわね。逢う日として神も許すこの日を、こうしてお待ちしておりましたのに、あなたさまは他の方と同乗していらっしゃるなんて)しめ縄の内には、とても入れませんわ」と書いてあります。その筆跡をよくご覧になりますと、何とあの典侍ではありませんか。源氏の大将は、「やれやれ、年甲斐もなく派手な事をするものだ」と憎く、みっともないとお思いになります。「かざしける 心ぞあだに思ほゆる 八十氏人に なべてあふひを(浮気者のあなたがかざした葵は私にではなく、たくさんの人に向けてなのでしょう。今日は誰かれなく逢える日ですからね)」 典侍はこのお返事を、『ひどい』と思いました。「くやしくも かざしけるかな名のみして 人だのめなる 草葉ばかりを(葵の祭りが逢う日だなんて名ばかりですわ。あてにならない草葉を頼みにしていたなんて、悔しくて)」と、申し上げます。
July 3, 2011
閲覧総数 1353
-
8

御伽草子・一寸法師 -1-
摂津の国難波の里に、おじいさん(老翁)とおばあさん(老婆)がおりました。 おばあさんは四十歳になるまで子供のないことを悲しみ、住吉にお参りをしていました。すると住吉の大明神がこれを憐れに思し召して、四十一歳という年齢のときにお子ができたのです。おじいさんの喜びはたいへんなものでした。 やがて十月経って、かわいらしい男の子が生まれました。 しかし生まれ落ちてからずっと、背丈が一寸しかなかったものですから、やがて一寸法師と名付けられました。年月が経って、早十二三歳になるまで育てたのですが、背丈は伸びず生まれた時のままでした。 おじいさんとおばあさんがよくよく考えるに、「これはただ者ではない。きっと化け物の類にちがいない。私たちがどんな罪の報いでこんな化け物を住吉からいただいたものかのう。全く、情けないことよ」と、その嘆くさまは傍から見ても気の毒なほどなのでした。
March 3, 2009
閲覧総数 138
-
9

賢木 -12-
藤壺の宮は三条の里邸にお渡りになります。兄宮でいらっしゃる兵部卿の宮がお迎えに上がります。雪が降り、風が激しく吹き、院の内はしだいに人の出入りが少なくなっていきますところに大将が参上なさり、昔のお話などなさいます。お庭の五葉の松が雪に萎れて下葉が枯れていますのをご覧になり、兵部卿の宮、「陰ひろみ 頼みし松や枯れにけん 下葉散りゆく 年の暮れかな(広い陰を頼みとしておりました松も、今や枯れてしまいました。庇護のなくなった下葉も散り散りになっていく、寂しい年の暮れですね)とりわけすぐれたお歌ではありませんが、この場にふさわしくもの哀れですので、大将のお袖はたいそう濡れるのでした。池が一面に凍っていますので、「さえわたる 池の鏡のさやけきに 見慣れし影を 見ぬぞ悲しき(氷の張り詰める、まるで鏡のように澄んだ池の水面に、いつも見慣れた院の影を見る事が出来ないのは、何とも哀しいものです)」と、大将殿がお詠みになります。思いつくままなので、あまりに幼くはあるのですが。王の命婦は、「年暮れて 岩井の水も氷とぢ 見し人かげの あせも行くかな(年が暮れ、岩間から湧く泉の水も凍てつき、見慣れてきた人影もしだいに褪せてまいります)」このついでに詠める御歌はたいそう多いのですが、これ以上書き続けるべき事でもありませんので。藤壺の宮が里邸にお渡りになる儀式は昔と変わらないのですが、これが最後と思いますと何となくもの寂しく、三条のお邸にお帰りになりましてもまるで他人の家のような心地がなさいます。日ごろは院のお傍で暮らす事が多く、お里住みなど絶えてなかった年月を、お思い出しになるのでございましょう。 にほんブログ村
September 20, 2011
閲覧総数 202
-
10

私訳(現代語訳)・源氏物語について -11-
藤壺の宮のお歌袖ぬるゝ 露のゆかりと思ふにも なほうとまれぬ やまとなでしこ について、すこし私見を述べたいと思います。 私はこれを、「あなたさまのお袖を濡らす涙の種ではありましょうが、それでも私には撫子を疎ましく思うことができないのでございます」 と訳しました。 藤壺の宮は源氏との密通に罪悪感と後悔の念を抱いていますし、御子まで為した関係を疎ましく思ってはいますが、決して源氏のことが嫌いなのではありません。故に生まれた皇子についての「疎まれぬ」は「あなたさまにとっては涙の種かもしれませんが、私にとっては疎ましく思うことができない(可愛い存在)のです」という、母親らしい素直な否定の意味と捉えていました。 ところが岩波・古典文学大系では「大和撫子、即ち御身(源氏)の袖が濡れる涙の露の縁(種)だと思うにつけても、私はやっぱり、自然に疎まれ(嫌な気がし)てしまうのであった。大和撫子(若宮)が」また、新古典文学大系の解説でも、「藤壺の歌。あなたの袖を濡らす露(涙)のゆかりと思うと、やはり大和撫子(若宮)をそっけないものに思ってしまう、の意。『うとむ』は疎遠である意。『ぬ』は完了の助動詞。打ち消しとする一説はとらない」 とあって、明確に「打ち消し」を否定しているのです。しかし残念ながら、その理由までは説明されていません。 藤壺の宮はこの後源氏とタッグを組んで若宮を帝位につけるほどの頭脳的・策略的な女性で、しかも源氏との秘密を一生胸に納めたまま出家し、この世をさります。私はこの藤壺の宮の「弱者としての女」あるいは「女の被害者意識」を強調しない生き方に、ある種の潔さと好ましさを感じています。 それにしてもこの歌の解釈の違いは、訳していての面白味の一つだと思いました。
November 14, 2010
閲覧総数 2523
-
-
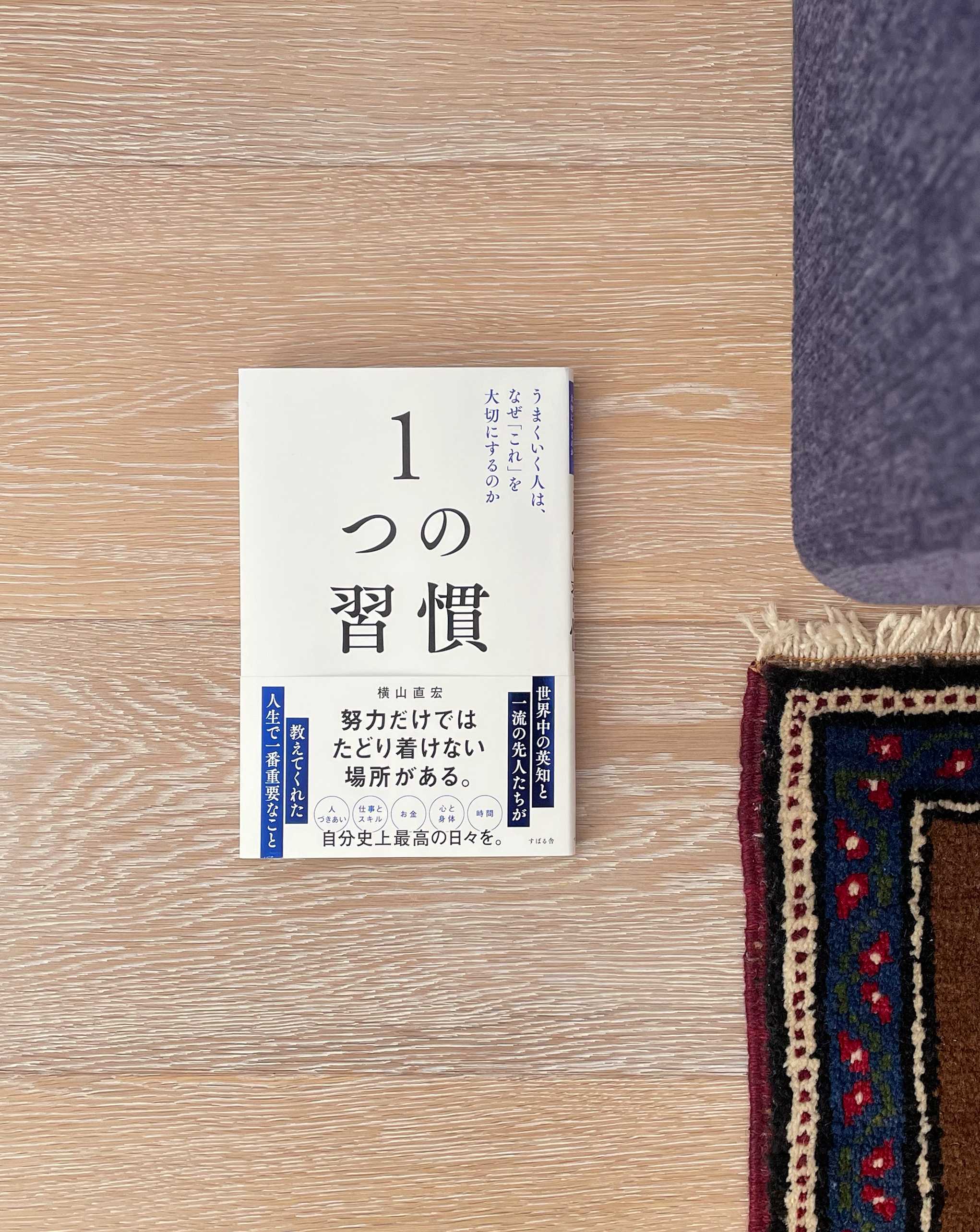
- 読書
- 横山直宏さんの『1つの習慣』を読む
- (2025-11-20 23:58:57)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- マンガハックさん閲覧数総まとめして…
- (2025-11-17 11:55:02)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0935 成長を支援するということ
- (2025-11-21 00:00:26)
-







