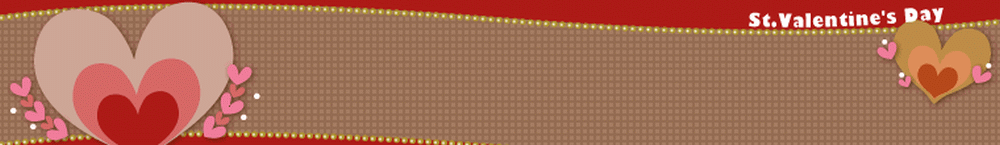2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年08月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
台湾の中元祭りと日本のお盆
先日、言語交換の相手とお盆について話しました。初めて聞いたので、お盆の由来について、ちょっと調べてみました。台湾の中元祭りとお盆とは、旧暦の七月15日を中心に日本で行われる祖先の霊を慰める行事です。台湾の中元祭りと似ているところが多いらしいです。台湾社会には、一年に一度、鬼の霊が地獄から人間を訪れるという説があるので、夏に祖先や鬼の霊を供養する風習となるわけです。今年のお盆と中元はそろそろですね。最近、デパートやスーパーからのチラシ、お目玉品は、ほとんどお菓子です。実は、供物としてのお菓子です。一般的に言えば、台湾人は、お菓子、果物、飲み物、鶏肉、豚肉、魚などを供えます。もともとは、祖先や鬼の霊を慰めるために供養しますが、どんどん自分の仕事、勉強、恋愛、家庭、人間関係などを祈るようになってきます。というわけで、台湾人は、中元祭りの間に、「旺」、「福」、「来」などの字が付けられた商品を好みますから、特に、パイナップル(台湾語の発音は、旺に近いので、盛んという意味をする)、粽(中国語の発音は、「中」に近いので、あたりという意味をする)、「旺旺」という米餅(名前が好運を表す)、「孔雀」というクッキー(赤っぽい包装が好運を表す)、コーラ(赤っぽい包装が好運を表す)は、人気が集まっています。一番高い売り上げは、この時期なのです。なぜかというと、台湾人は、それを供えると運が開くことを信じているからです。実は、それは、経営者が「弊社のお菓子を供物としてすれば、霊を喜ばせるに限らず、運も開ける」と人目を引き付けるコマーシャル手法ばかりだと思います。現代人は、五感を刺激されて、洗脳を受けつつ、しらずしらずのうちに、物欲に目がくらむようになるようです。昔から伝われてきた行事も、さまざまな商売の手法で変身し、ますます本来の意味を失っていくのです。行事を行っている人々も目がなくなっているようです。祖先を慰めるというよりも、自分を慰めようと思うと言ってもいいです。人間は、わがままな生き物だと思います。ふりまわされ易くて、騙されやすい人間は、やはり、感情的になされた決定をするときが多いのですね。
2007.08.25
-
乗馬の旅の思い出
夏の旅行を振り返って、一番印象的な思い出と言えば、何と言っても馬に乗って喀納斯に行った旅です。特に、図瓦族のガイドとカザフ人の一家と一緒にユルトで過ごした体験です。 喀納斯(カナス)ほど美しい場所は、ないという話しもあります。モンゴル、ロシア、カザフスタンと国境を接する喀納斯(カナス)という地域では、雪化粧した山々、生い茂ている森林、広く果てしない高原だけでなく、カザフ、図瓦族、モンゴル人という珍しい民族も昔ながら生活を送っているとよく知られています。その中に、わずか2000人が残っている図瓦族は、今中国政府に特別に保護されている民族だそうで、絶滅危機人種だといえます。 図瓦族は、主に、カザフスタンとの国境に近い禾木村、白哈巴村、喀納斯村の集落で住んでいます。主に、自給自足の放牧をしています。禾木村から喀納斯村へ観光バスがあります。道路の状況もいいし、それに楽に綺麗な景色も見えるし、とても便利です。しかし、バスに乗ったら、多くの観光客や車の音がうるさいということを我慢しなければならないし、ゆったり自然を楽しむことができないので、やっはり、馬での移動のほうがいいと思いました。というわけで、私たちは、二日間かけて、馬に乗って禾木村から喀納斯へ行くことにしました。でも、最も気になっていたのは、このルートを歩くなら、坂を登ったり、下がったりするのは、もちろん、急流を乗りこえたり、谷や湖を越えたりすることも多いので、本当に険しいルートということです。 私たちは、もう危険を冒す覚悟で現地のガイドと馬を雇って、翌日の朝5時に出発することにしました。二日間の旅を通して、フウという図瓦族の男性のガイドに、私たちと馬たちの世話と道を案内してもらいました。私たちは誰も馬に乗ったことがないと彼に言うと、出発の直前に、「怖がることはないよ。わたしに任せてください。気をつければ、大丈夫だよ。」と言われたが、私たちは、物事が期待通りにうまく行くかどうか心配でした。 朝、4時ごろ起きて、5時に村から出発しました。丸木橋を渡ったり、坂を登ったり、思っていた通りに、凸凹道や曲がりくねた道ばかりでした。 空が明るくなるとともに、高原の遠くから日の出が見えるようになりました。高い丘に近づいていくと次第に壮観な名前も知らない山々が迫ってきます。少し残っている雪が被っている峰が、湖に映っています。一面の花々が絨毯のように、広がっています。景色を楽しめながら、山の奥へ向かって行きます。私たちは、雪化粧した山々、森林、せせらぎ、そして、青空に囲まれ、ガイドの牧場に辿り着きました。四時間、休憩なしに馬に乗り続けたわたしたちは、やっと一時の休みが取りました。40歳ぐらいのガイドHさんは、牧畜をやっているかたわら、乗馬のガイドをしています。ここのあたりには、観光客があまりいないのですが、お小遣いを稼ぐため、予約も受けるそうです。 彼は、羊が百頭、馬が80頭、牛が60頭がいるといいました。 さすが、馬の背に生まれ、育てられてきた子だけあって、馬を手懐ける時の立派さは、言うまでもありません。 彼の家族の皆さんは、私たちを親切に歓待してくれました。親切だといえば、親切ですけど、人なつっこいウイグル人とちょっと違って、彼らは、照れ性です。でも、牧民の彼らは「客が幸運を運んでくる」ということを信じていて、大量のご馳走で私たちを招待しすることを喜びとしているようです。彼の家でミルク茶を飲み、揚げパンを食べながら、一休みをしました。一時間の休みが終わってたら、彼の家を離れて、また旅を続けました。 しかし、彼の家を出た途端、大粒の雨がばらばらと降り出しました。レインコートを持っていない私は、雨に濡れながら、馬に乗っていました。心配そうなガイドは、わたしのために、わざわざお隣の遊牧民から手作りのレインコートを借りってくれました。 ガイドが私にコートを手渡した瞬間に、私の馬がびっくりして、前足が飛び上げたので、私は背中から引き落とされてしまいました。 私は、馬から落ちてしまいました。地面にしりもちをついたとき、大きい衝撃で体が再び前に飛んでしまいました。一瞬のことですから、皆がびっくりしました。実は、わたしもショックでした。 ガイドがて私の側で「大丈夫?大丈夫?」と叫びましたが、わたしは、驚きと痛みのあまり、声も出せないまま10秒もじっとしていました。ガイドは、返事ができなかった私を見て驚いたに決まっています。 「私、大丈夫。でも、痛い」と言いました。 痛くても全力で立ち上げたら、顔だけでなく、全身も泥だらけになってしまいました。私は、その光景を見て泣いたらいいのか笑ったらいいのかわからなかったのです。幸いなことに、お尻を痛めても、大怪我をすることなく、体も、背負っていたカメラバッグも、大丈夫でした。 皆がほっとしました。 わたしは、お尻の痛めを我慢していて、宿泊のユルトに着くまで、また四時間も休憩なしに馬に乗り続けました。夜の7時に湖畔の遊牧民のユルトに着きました。ここに泊まりました。馬から降りると、お尻も足も膝も、全身が泣きたいほど痛かったのです。私だけでなく、皆もそうでした。のろのろテントに入りました。ちょっと移動することさえも死にたいほど辛いのです。 カザフ人の夫婦は、忙しそうに、木を刈ったり、絨毯を敷いたりしています。私たちの食事と宿泊を準備しているようです。手伝ってあげる元気もない私たちがテントのなかに横たわって休憩するしかなかったのです。 日が山の遠くに沈みつつ、白いユルトも夕焼けに染まてきます。牛、羊、馬などが牧場で草を食べています。穏やかに流れているせせらぎを聞きながら、気持ちが落ち着いてきました。 皆が、静かにユルトから景色を眺めています。 幻の景色を初め見た感激といったらありませんでした。 知らず知らずのうちに、皆は、眠りに落ちてしまいました。 私が仮眠をしようとする頃、ガイドが私の側にやってきました。彼も私の側に腰を掛けました。 「また、痛いですか。大丈夫ですか、どこか、怪我をしましたか」と心配そうな彼は、私の具合を確かめて聞きました。 「原っぱには、鋭い石がいっぱいがあるので、あのとき、あなたは、石にぶつかたかなと思って、心配でした。万一、大怪我をすると、わたしもひどい目にあうのよ」と彼が言い続けました。「今日は、心配をかけてすみませんでした」と私が言いました。 「あなたの目は赤っぽいですね。疲れたのでしょうか。ちゃんと、休んでください。あした、旅も長いですよ。」と彼が何度も念を押して言いました。 仮眠をしようと思ったわたしは、急に寝る気がなくなって、彼とおっしゃべりをしたくなりました。 わたしは、図瓦族のことについて聞きました。 彼も私の質問に対して詳しく教えてくれました。特に生活習慣とか、価値観とか、お互いに意見を交換していました。 彼らの収入は、わずか私の収入の30分の1しかないのです。 収入は十分とはいえないまでも、彼らは、自給自足の生活を満足そうに過ごしているようでした。素朴な彼らと比べたら、私たちは、無駄使いをしすぎて、本当に浪費家だと自分で考えさせられました。さらにいえば、我々は、さまざまな生活の快適さを手に入れたかわりに、我々は取り返しのつかないほど自然を破壊してしまったのではないでしょうか。、科学の発達は人間の生活を便利で豊かにする反面、環境を汚し、素朴な人間さを失わせることになるのではないかでしょうか。 言い換えれば、彼らの生活こそ、贅沢だと思います。欲が少ない彼らは、もっともありがたいものをもっています。それは、純粋そのものだと思います。空気、水、食べ物、そして人間の優しさが、全て純粋なのです。 彼らは、純粋なものを大自然からもらって、感謝の気持ちをこめて、そのまま大自然に返すというのは、我々が模範として目指さなければならないのではないでしょうか。 やっと夕食です。 「これ、ボーサク(揚げパンみたいな食べ物)なんです。お口に合うかどうかわからないんですが」と遊牧民のおばさんが夕食と朝食を作ってくれました。 翌日、馬に乗るとき、お尻が針の上に座っているように痛かったですが、わたしは、どんどん乗馬に慣れるようになって、馬を操縦するのも上手になりました。今回の旅のおかげで、わたしは、牧畜のことや乗馬のことなどよく勉強になりました。もし、私が再びカナスに行く機会があるなら、現地の少数民族にもっと馴染んで彼らの生き方や物の考え方などを詳しく記録してみたいと思います。馬に乗るのは、体力も時間もかかりますけど、身近に自然を親しむことができるというよさもあります。馬に乗りながら、そこの独特な雰囲気を身をもって味わったのは、忘れられない体験だと思います。今回の旅をきっかけとして、私と姉が乗馬のことに興味を持つようになります。来年、中国の四川省とチベットの間の高原へ行くつもりです。十五日間の乗馬とハイキングの旅を計画しています。
2007.08.24
-
新疆とは
新疆という名前を耳にしたことがなくても、シルクロードを知らない方は少ないのではないでしょうか。シルクロードと言う言葉を聞いて思い浮かべる地域、大雑把に言えば、その一部に新疆があります。新疆とは、日本語の読み方は、「しんきょう」、漢語では、「シンジャン」といいます。元々は清朝の乾隆帝が征服した領土で、新たな(平定した)疆域」という意味を表す漢語訳の名前です。中華人民共和国成立以後、新疆ウイグル自治区と名称が変わりましたが、現在も一般的には新疆と呼ばれ、中国最大の省区となっています。新疆の総面積は160万平方メートルで、中国の国土の約6分の1を占めます。その面積は実に日本の4.5倍に相当します。中国の西北に位置する新疆は、東北はモンゴル人民共和国、西北はロシア連邦、カザフスタン共和国、クルグズ共和国、タジキスタン共和国、そして南部はアフガニスタン、パキスタン及びインドと国境を接し、国境線は5400キロメートルにもわたります。新疆ウイグル自治区(新疆)は中国最大の省区だといっても、そこの民族、文化、宗教などが中国の多数派(漢族、ハン族)と大きく違っています。中国文化に育てられてきた私にとってさえも、新疆にいたときに、異国にいるような感じがしました。地味の町には、中国語ができない人が多くいます。言葉が通じない場合に、わたしは、身振り手振りをして意味を伝えていました。それは、旅の醍醐味の一つともなります。今回の旅は、区都のウルムチから、モンゴル人民共和国、ロシア連邦、カザフスタン共和国と国境を接する喀納斯(カナス)、天山山脈の野原、中部の伊犂(イリ)谷を歩いてきました。私たち(私、姉、台北からのIda、北京からのBessie、あわせて4人の女性)が17日間近くにわたって旅行しました。地図と情報に関しては、下記のサイトを参考しました。http://www.geocities.jp/vinira2126/ditu.htmhttp://home.m01.itscom.net/shimizu/yultuz/silkroad/history/index.htm
2007.08.23
-
夏特村
限られた時間に追われての、慌ただしい旅行でしたが、私にとって一番思い出深い出会いは、やはり初めて思い出深い出会いはを訪ねた時だったなあと思います。新疆の真ん中を貫く天山山脈の中に位置されている夏特村は、伊犂谷から南疆と呼ばれる天山以南の地域に入る門戸なので、ここから南に向かって、天山の木札爾特峠を超えるのが、久しいルートでした。木札爾特峠は5000すぎメートルの標高ですから、おっかない道でした。玄奘もこの道を歩いたときに、相当の苦労を食いましたという歴史が<大唐西域記>という本に書いてあります。昔ながら、馬に乗らないと歩けないこのルートには、死霊が居ついていたのでしょうか。馬でこの道を通って、南疆に行くなら、少なくとも三日間がかかるということで、私たちは、このルートを歩かずに、ただ町を巡って歩きました。残念ですが、夏特人の若い娘に出会って、彼女の家を見学したのは、思いがけない体験で嬉しかったです。わたしは特に古い民家に興味がありますから、夏特人の民家を尋ねた時の喜びを言うまでもありません。古い雰囲気が溢れてる夏特村の家並みは今では珍しいです。屋根は、草葺が主体ですが、壁や床が草と土の混じりの素材で建てられたのです。魅力的で独特な民家です。民家の内部を見せてくれればいいなぁと思った途端に、ある若い娘を見かけました。わたしは、勇気を持って挨拶しました。私が「あなたの家を見学させてくださいませんか」と大胆に彼女に伺っていました。「いいですよ」と彼女が私たちを案内して彼女の家に入りました。やっと珍しい夏特民家の内部を見ました。好奇心が深いわたしは、沢山の質問をしたり、写真を撮ったり、しました。彼女は、たどたどしい中国語で私の質問を答えました。彼女の家はとても広い!驚いたことに、ただ女性しか出会いませんでした。それは、当たり前のことですね。なぜかと言うと、昼間に、男は外で稼いでいるのからです。中国語が通じないお婆さんとおばたちが私たちの手を繋がって、親切で家のあちこちを案内してくれました。彼らの笑顔は、もっとも綺麗な風景だと思います。たどたどしい会話ながらも確かに心を通い合わせることができた時の嬉しさは、他ではなかなか味わえないものです。干されている牛の糞が庭の真ん中に並んでいます。菜園、部屋、露天の台所、家畜小屋、ナンを焼く用の土炉などを見学させていただきました。この地方は、冬が来ると、すごく寒いので、彼らのベッドは、高床で、床も壁もジュータンのような毛織物がかかっていました。日ごとに消えてゆく古い民家とその町の生き方を訪ね歩く旅なら、地域を違えることやそれぞれに違った特色をもつ風土にふれることができます。これが旅の楽しさだし、感動でもあると思うのだが、そこでそれらの消えてゆく姿に接するなら、愛惜を噛み締める旅もなるでしょう。外人に入らせたことはない彼女の家を部屋から庭まで見せてもらいました。でも、どのように、彼らの歓待に返したらいいのか、迷っていました。わたしは、彼女の家を離れたとき、台湾から持ってきたチョコレートをプレゼントとして彼女にあげました。彼女と夏特村の人々が幸せになるように、祈っています。
2007.08.22
-
トイレのこと
以上の写真は、私が用を足したところの三ヵ所です私、新疆に旅行したとき、便意あるいは尿意が起きたら、野外で用を足すことが多いです。下品ですが、ずばり言えば「野ぐそ」です。旅行したところは、殆ど砂漠、草原、高山ですから、トイレがないから仕方なく野外でしているにすぎません。運転手のHさんは、時々、合う場所を探すなんてなかなか気が利いている人です。たとえば、大きい石とか、雑草の生い茂った森林とか。困ったことに、草原には、石も木もない場合なら、どこでしたらいいのか、迷うことも多いですね。最初は、ちょっと恥ずかしかったが、今まで育ってきた文化なんか一切考えないようにしたら、かえて楽になりました。何だか慣れてきたような感じがしました。いつでもどこでも好きな時に用が足せるようになっていますから、知らず知らずのうちに、野外式のトイレが好きになりました。実は、便所があっても、野外ですることが多いです。なぜかというと、多くの公衆便所は、仕切りとドアがないので、順番待ちの人と目が合うこともあり、ひどく心理的プレッシャーを感じるのからです。人前で排泄するのは、なかなかできない私は、公衆便所より、一人静かに野外で用を足すほうがいいと思います。特に、綺麗な花畑や森林の中で世を足せるとということの何と幸せなことか!景色も綺麗し、空気も新鮮し、それに、ストレスがないので、最高です。しかし、偶には隣で羊やら牛やらがじっと見守っているので、何となく居心地が悪いということと、夜は夜で電灯がないためどこにいるのかわからないので、危ないということなど、気をつけなければいけないのです。わたしは、野原である毒草(地元の人が蠍子草と呼ぶ)に触れて、ひどい目に遭った経験もあります。お尻や足が毒草に刺されて、三時間も痛めてたまらなかったので、大変でした。それは、旅の刺激の一つなのではないでしょうか。
2007.08.21
-
哈密瓜(ハミ瓜)
新疆の人々は、スイカやメロンなどの果物を多く食べます。新疆のピチャンはシルクロードの果物として有名な哈密瓜(ハミ瓜)の原産地として知られています。ハミ瓜は細長い形をしており、50センチ以上の大きいものまであります。果肉は柔らかくジューシーで、美味しいです。今では新疆の各地で栽培されていますので、あちこちで美味しいメロンを食べられます。新疆に旅行した時、夏バテで食欲が無い日に、果物で自分を元気にしたい気持ちで、夕食の代わりに、メロンを食べていました。実は、新疆の伊犂谷には、哈密瓜だけでなく、西瓜、メロン、桃、りんごなど果物が最高だそうです。フルーツに目が無いわたしは、初めて伊犂谷に行った時、蜂が花に引かれるように道の側に並んでいたフルーツスタンドに魅せられた。美味しくて安いので、大満足でした。
2007.08.20
-
無事に帰国しました
18日間の旅が終わりました。シルクロードからから無事に帰国しました。しばらく記事を書いていなかったので、日本語が下手になってしまった気がしますね。今、旅の写真と資料の整理に忙しいです。これから一週間に、記事も書くことのもできません。正常の暮らしに戻らないと。
2007.08.19
-
いよいよシルクロードへ
いよいよシルクロードへ出発。今度の旅では、どんな風景に出会えるのか、どんな人に触れるのか、想像するだに胸がどきどきします。新疆ウイグル自治区の区都、ウルムチを台湾語で読むと、「おろもちぇ」に近いので、台湾語の「おろもちぇ」は、中国語に訳すと、「乱七八糟」と言う意味です。日本語で言えば、「滅茶苦茶」という意味に似ているのです。いつの間にか、台湾人は、「ウルムチは、滅茶苦茶の町だ」というイメージを持つようになります。冗談みたいですが、知らず知らずのうちに、その冗談は、当たり前のことになってしまって、皆がそう思うようになるのです。母も、「ウルムチ?あぁ、わかった。おろもちぇね。あの滅茶苦茶の町じゃないか。どうして、そんなところへ行くのか。」と口にしました。わたしが答えられるのは、苦笑しかありませんでした。確かに、私たちと遠く隔たっている新疆というところは、さすがに風変わりが湛えた遥か所だと思います。情報によると、新疆ウイグル自治区の区都、ウルムチは、世界で最も海から離れた内陸都市だそうです。大陸乾燥性気候に属し、寒暖の差が激しく、降水量が少ないという特徴を持ちます。過去、最高気温は1973年8月1日に42.1度、最低気温は1951年に-41.5度を記録しています。一日中の気温差は少なくとも30度以上を達するのは、普通だそうです。そこの331MMらいの平均降水量から見ると、3000MMぐらいの平均降水量に恵まれている台湾人にとっては、いかにも不毛なところなのでしょう。気候は、もちろん、文化や風景も独特の雰囲気が溢れている場所なんです。新疆(シンジャン)には、ウイグル、漢、回、カザク、満、モンゴル、シボ、オロスなど13の主体民族があるということです。中国の一部といっても、まるで異国のような地域といえます。あとは、二日間しかないので、旅の準備をしなければいけません。今回の旅の間によく日焼けする場合が多そうですから、黒くならないように、日焼け止め、帽子、マスクなどが欠かせないものを持たなければいけません。もっとも気になるのは、YURT(ユルト:遊牧民のテント式住居.)に泊まることなんです。わたしは、馬に乗ったことがないので、一日中6時間で馬に乗るなんて、わたしはできるかなと、ちょっと心配です。ユルトのあたりには、シャワーどころか、トイレもないのです。水のことも大事なことだと思います。そこには、水道水もなさそうです。とりあえず、タオルと寝袋を用意しておいたほうがいいと思います。楽しみにしています。
2007.08.01
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 道の駅めぬまにあるバラ園に行きまし…
- (2025-11-15 11:08:11)
-
-
-

- ディズニーリゾート大好っき!
- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート
- (2025-11-15 13:34:40)
-
-
-

- 温泉旅館
- 錦秋の東北へ 米沢・白布温泉 湯滝の…
- (2025-11-13 06:46:38)
-