PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(108)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(25)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(68)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(50)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(131)徘徊日記 団地界隈
(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(24)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(35)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44
ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」
徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり
佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247
週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)
佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246
週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)
週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)
コメント新着
キーワードサーチ
日本語をずーっと通して、わしづかみしたいという人に、一番スタンダードで、かつ、評価も高い日本語の概説が、 金田一春彦 の 「日本語(上・下)」(岩波新書) でしょう。
多分、一番新しい、素人向け(かな?)の概説が、 沖森卓也 という人の 「日本語全史」(ちくま新書) かな。
金田一春彦 は、一時はやったマンガ、 「金田一少年の事件簿」 のモデルかもしれませんが(少なくとも名前は)、ホントはちがうけど、実はそうかもしれません(笑)。
 というのは、彼のお父さんが 金田一京助
という 「アイヌ語」学
の創始者で権威、かつ、 「明解さん」
で有名な三省堂という出版社の国語辞典のドンのような国語学者なのです。
というのは、彼のお父さんが 金田一京助
という 「アイヌ語」学
の創始者で権威、かつ、 「明解さん」
で有名な三省堂という出版社の国語辞典のドンのような国語学者なのです。
文学史上も有名な人物で、明治の歌人である 石川啄木 の、 盛岡中学 以来の友人です。一応、上級生なのですが、親友といっていいと思う人物です。
というのは、 金田一京助 という人は自らの学生時代から結婚当初まで、盛岡中学を中退し、北海道から東京へと流浪つづける極貧の友人、 石川啄木 とその一家を支え続けた人なのです。
たとえば、 春彦 が生まれたばかりの 金田一家 のタンスの引き出しから 京助 の妻の晴れ着を持ち出し、質屋で流して金にするというような、まあ、無法なことが許されていたのが 石川啄木 だったということがどこかに書かれていましたが、それを昔語りに母から繰り返し聞いた少年 春彦 は、 啄木 を石川五右衛門の末裔だと思っていたという話が落ちなので、どこまで本当かはわかりませんが、まあ、そういう関係だったことは事実でしょうね。
これは戦後のことですが、探偵小説を書いていた 横溝正史 が 「本陣殺人事件」 (だったと思う)で、初めて 「金田一耕助」 という名の探偵を登場させ、その後、 「八つ墓村」、「犬神家の一族」 、と活躍させたのですが、これらの作品群は、 1970年 代の 角川文庫 の 「観てから読むか、読んでから観るか」 という、映画とセットにしたキャンペーン企画のドル箱小説でした。ウソか、本当か、1000万部売れたそうです。
まあ、当時、ぼくも、彼のたいていの作品は、文庫で買って読んで、そのうえ、映画も見たのですが、一作の例外もなく、映画より、小説のほうが、怖くて面白かった。
「映画にもなってるやん。」
「うん。エライ流行ってんで。」
と、まあ、そういうことですが、その 金田一探偵
の名前が、 金田一京助
の名のもじりだというのは、かなり有名な話です。その後ブームになった マンガ
の 金田一少年
は、たしか、小説の金田一耕助の孫だったと思います。それぞれ、本家に許しを得たのかどうか、それは知らないのですが、国語学者一家の金田一家と探偵の血筋の金田一家は縁がないわけではないということです。ホント、どうでもいい話でした。
さて、本論に戻りましょう。 「日本語(上・下)」
ですが、 言語学
の視点から、
世界の中の日本語
の特質から語り始め、 発音、語彙、文法、表現法
まで語りつくしてある本です。
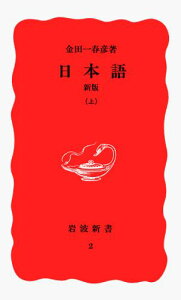 今では、1000点を超えた、 岩波書店
の 「新赤版」新書
が 1988年
に始まるのですが、ちなみに、その no1
は 大江健三郎「新しい文学のために」
。 no2,no3
がこの 「日本語〈上・下〉」
、記念出版に近い評価だったんでしょうね。 「岩波文化」
という言葉がありますが、マア、代表的スターだったんでしょうね。
今では、1000点を超えた、 岩波書店
の 「新赤版」新書
が 1988年
に始まるのですが、ちなみに、その no1
は 大江健三郎「新しい文学のために」
。 no2,no3
がこの 「日本語〈上・下〉」
、記念出版に近い評価だったんでしょうね。 「岩波文化」
という言葉がありますが、マア、代表的スターだったんでしょうね。
以来、 2017年
に 53刷
ですから、
「スタンダード」
と、ぼくがいう意味は分かってもらえるのではないでしょうか。ただ、惜しむらくは、少々冗長で、今となっては少し古いと思います。
そこで最新の、と考える人には 沖森卓也「日本語全史」(ちくま新書)
があります。
こっちは、 「全史」
と銘打っている通り、日本の古代前期、無文字社会の日本語は相手にしようがないからでしょうが、 奈良から平安にかけての日本語
から始めて、 「文字表記」「音韻」「語彙」「文法」
の部立てに従って 第六章「近代」
まで、画期的変化に伴い、各時代ごとに丁寧に記述されていて、まさに
全史
です。
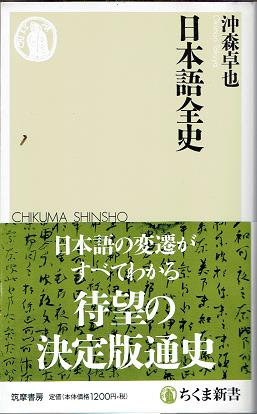 特に、高校の国語程度の古典文法なんかに疑問と興味を持っている人にはお勧めかもしれません。
特に、高校の国語程度の古典文法なんかに疑問と興味を持っている人にはお勧めかもしれません。
中でも、まあ、教員はしていた、あるいは、しているけれどという、ぼくのように、 国語学
が 苦手
、 文法が嫌い
という、大雑把で生半可な知識の持ち主には、割合ピタリとはまるかもしれません。いわゆる役に立つタイプの参考書と言っていい本だと思います。
整理が簡潔で、時代的変遷が明快。古典語の係り結びの変遷や、音韻の変化に伴っての詳細な文法の変化もきちんと追いかけられています。
ただ、これも、新書というより辞書に近い分厚さ、 430ページ
を超えますから、読み通すには、結構、根性とヒマがいるかもしれませんね。こんな本を読む、ヒマだからというおじさんとか、子どもの勉強がが気にかかるママとかというのは、ちょっと想像しにくい厚みですね(笑)。
というわけで、まず総論的おススメを案内しましたが、次は、ちょっと面白みもという「案内」をもくろんでおります。まあ、図書館か書店で手に取ってみてください。両方とも、ちょっと大きめの書店にならあるでしょう。(S)
追記2022・10・20
あらゆることが 「わかりやすい」
マニュアル化している現代ですが、20歳前後の、例えば、 「国語の教員」
を目指している女子大生とお出会いして話をしていると、一応、 「知っている」
のに、説明できないという 「国語」
についてのあれこれがたくさんあることに驚きます。
ウキペディアで調べれば 「知っている」
ことになるようですが、それって 「知っている」
っていうことなのでしょうか。
新書本を1冊読むのもネットで検索するのも、まあ、 「知っている」
という状態を作るうえでは大きな差はないのかもしれませんが、ページを繰って 「読む」
というとき、目の前の分厚さの苦痛は、 「わからない」
ということを実感させてくれます。読み終えると、読み終えた達成感で、ちょっといい気になります。
でも、
「なんか、よくわからん」
頭の中で、もう一人の自分がそういうのです。勉強は、そこから始まるんじゃないでしょうか。 「わからない」
を体験したことのない人が教室で 「わかりやすいマニュアル」
を配っているのは、やっぱり変ですね。 「読む」
ことの苦痛なしに 「わかりやすい」
にたどり着くのって、やっぱり、ウソだと思うのですが(笑)。
追記
ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

ボタン押してね!
ボタン押してね!


-
週刊 読書案内『高等学校における外国に… 2022.02.02
-
週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ… 2021.07.11
-
週刊 読書案内 山田史生「孔子はこう考… 2021.04.17










