PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(107)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(24)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(30)読書案内「近・現代詩歌」
(50)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(130)徘徊日記 団地界隈
(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(24)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(29)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5) 週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)
週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)
徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり
徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」
ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244
NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245
週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)
フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21
アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243
週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)
週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)
徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり
徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」
ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244
NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245
週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)
フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21
アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243
週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「日本語・教育」
山田史生「孔子はこう考えた」(ちくまプリマー新書)
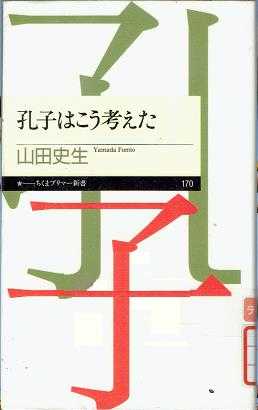
以前、おなじ 「ちくまプリーマー新書」 の一冊で 「受験生のための一夜漬け漢文教室」(ちくまプリマー新書) という参考書(?)を案内したことがありますが、今回のこの本、 「孔子はこう考えた」 は同じ著者 山田史生さん の 「論語」入門書 といっていいでしょう。
大学入試突破のお手伝いをする現場から離れて3年たってしまいました。その頃は、センター試験とか、そうはいっても、毎年解いていましたが、今では「問題」を見るどころか、いつあったのかすら気付きません。高校の国語の内容も大きく変わると評判になっていますが、実情についてはよく知りません。
で、今頃、なんで 「論語」 なんか読んでいるのか、というわけですが、そこはやはり昔取った杵柄というか、 孔子先生 の言葉を借りれば 「学びて時に之を習う、亦、説しからずや」 。という感じでしょうか。
「これって高校生にいいんじゃないの」 と気づいた本は手に取る、まあ、癖のようなものはまだ残っていて、先日、市民図書館の棚で見つけたのがこの本です。
大学入試に即していえば 「漢文」 は、 「古典」 という教科の中の一科目ですが、個々の大学の入試で 「漢文」 を課す大学は、ぼくが、仕事を辞めるころにはもうありませんでした。かろうじて、センター試験の中の 「国語」 200点のうち50点が 「漢文」 の問題という所に残っているだけだったと思います。
ところが、公立の高校入試の場合は100点中、20点ほどの割合で、毎年、出題されていたのですが、今はどうなっているのでしょうね。
「漢文」なんて、役に立たない、お得にならない教科なのでしょうか。そのあたりを、ゴチャゴチャ議論するのはやめますが、一つだけ言えば、 「論理国語」 なんていう教科を新設するくらいなら 「漢文」 の時間数を増やした方が、目的に対しては「お得」で「役に立つ」と思うのですが、でも、まあ、すくなくとも、2020年現在の 「文部大臣」 や 「総理大臣」 といった方々は、 「漢文」 どころか、漢字そのものの常識も疑わしいわけですから、まあ、世の流れで 「漢文」 なんて見向きもされないのはしようがありませんね。
まあ、そういうわけで、本書の案内ですが、この本では 「自分のことを好きになろう」 というテーマを第1章に掲げて、 「孔子」 について語り始めています。
最近の世相を見ていて、ちょっと面白いなと思ったのは、 「論語:公冶長」編 にあるこんな文章を取り上げていたところです。本文では、巻末にまとめてありますが、まず、肝試し代わりに白文を引用します。読めますか?
こちらが書き下しです。
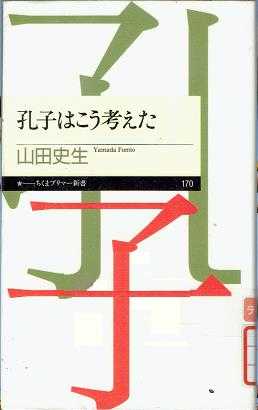
以前、おなじ 「ちくまプリーマー新書」 の一冊で 「受験生のための一夜漬け漢文教室」(ちくまプリマー新書) という参考書(?)を案内したことがありますが、今回のこの本、 「孔子はこう考えた」 は同じ著者 山田史生さん の 「論語」入門書 といっていいでしょう。
大学入試突破のお手伝いをする現場から離れて3年たってしまいました。その頃は、センター試験とか、そうはいっても、毎年解いていましたが、今では「問題」を見るどころか、いつあったのかすら気付きません。高校の国語の内容も大きく変わると評判になっていますが、実情についてはよく知りません。
で、今頃、なんで 「論語」 なんか読んでいるのか、というわけですが、そこはやはり昔取った杵柄というか、 孔子先生 の言葉を借りれば 「学びて時に之を習う、亦、説しからずや」 。という感じでしょうか。
「これって高校生にいいんじゃないの」 と気づいた本は手に取る、まあ、癖のようなものはまだ残っていて、先日、市民図書館の棚で見つけたのがこの本です。
大学入試に即していえば 「漢文」 は、 「古典」 という教科の中の一科目ですが、個々の大学の入試で 「漢文」 を課す大学は、ぼくが、仕事を辞めるころにはもうありませんでした。かろうじて、センター試験の中の 「国語」 200点のうち50点が 「漢文」 の問題という所に残っているだけだったと思います。
ところが、公立の高校入試の場合は100点中、20点ほどの割合で、毎年、出題されていたのですが、今はどうなっているのでしょうね。
「漢文」なんて、役に立たない、お得にならない教科なのでしょうか。そのあたりを、ゴチャゴチャ議論するのはやめますが、一つだけ言えば、 「論理国語」 なんていう教科を新設するくらいなら 「漢文」 の時間数を増やした方が、目的に対しては「お得」で「役に立つ」と思うのですが、でも、まあ、すくなくとも、2020年現在の 「文部大臣」 や 「総理大臣」 といった方々は、 「漢文」 どころか、漢字そのものの常識も疑わしいわけですから、まあ、世の流れで 「漢文」 なんて見向きもされないのはしようがありませんね。
まあ、そういうわけで、本書の案内ですが、この本では 「自分のことを好きになろう」 というテーマを第1章に掲げて、 「孔子」 について語り始めています。
最近の世相を見ていて、ちょっと面白いなと思ったのは、 「論語:公冶長」編 にあるこんな文章を取り上げていたところです。本文では、巻末にまとめてありますが、まず、肝試し代わりに白文を引用します。読めますか?
顏淵季路侍。子曰、盍各言爾志。子路曰、願車馬衣輕裘與朋友共、敝之而無憾。顏淵曰、願無伐善、無施勞。子路曰、願聞子之志。子曰、老者安之、朋友信之、少者懷之。 マア、読めなくても大丈夫です。 この文章に対して、 山田先生 はこんな前振りをして解説を始めます。
「空気が読めない」という言葉がある。「KY」と略したりするようである。 そういう人なんですね、 山田先生 は。続けて、書き下し分と、口語訳がついています。
若者が「お前空気読めよ」といっているのが聞こえてくると、イヤな感じがする。
こちらが書き下しです。
顏淵、季路、侍す。子曰く、蓋(なん)ぞおのおの爾(なんじ)の志を言わざる。子路曰く、願わくは車馬衣軽裘、朋友と共にし、之を敝(やぶ)るとも憾(うら)むこと無けん。顔淵曰く、願わくは善に伐(ほこ)ること無く、労を施すこと無けん。子路曰く、願わくは子の志を聞かん。子曰く、老いたる者は之を安んじ、朋友は之を信じ、少(わか)き者は之を懐(なつ)けん。 続けて口語訳
顔淵と子路(季路とも)とが先生のそばにいたときのこと。先生「こうありたいという願いをいってごらん」。子路「乗り物や着物や毛皮を友達と共有したら、たとえ使いつぶされてもイヤな顔をしないようにしたいです」。顔淵「どんなに善いことしても自慢せず、ひとさまに迷惑をかけないようにしたいです」。子路「先生の望みもお聞かせください」。先生「年寄りとはリラックスしておしゃべりし、友だちとはざっくばらんにつきあい、若いひととも気がねなくやりたいね」。 かなり、くだけた調子ですが、問題ないでしょう。さて、ここからが解説です。
子路はもと遊侠の徒だったからガラがわるい。しょっちゅうドジをやらかすんだけど、どこか憎めない。
「おまえの望みをいってみよ」といわれて、「待ってました」とばかり子路はいう。オレの愛車や革ジャンをダチに貸してやって、それがボロボロにされてもはらをたてないような、そんな男になりたいっす。
孔子と顔淵とは困ったような顔をしている。いやはや、子路らしいな、と。お里が知れるといったところである。子路にしてみれば、どうしして困られちゃうのか、さっぱりわからない。子路は、果たして空気が読めない男なのだろうか?
それにひきかえ顔淵の答えは、いかにも優等生である。模範的な答えで、もちろん文句のつけようはない。その文句のつけようのないところが、どうしようもなくダメである。自分の答えがつまらないことに(そして孔子も頭の片隅でつまらないとかんじているということに)顔淵は気付いているのだろうか?もし気づいていないとしたら、顔淵もまた空気が読めない男なんじゃないだろうか。
子路にせがまれ、孔子はいう。先輩からは「こいつにまかせておけば安心だ」と信頼してもらえ、同輩からは「かれといっしょならやってみたい」と仲間にしてもらえ、後輩からは「このひとのようになりたい」と慕ってもらえるような、そんな自分でありたいと。
子路は、孔子の望む人間像とは正反対の男である。先輩からは危なっかしがられ、同輩からは煙たがられ、後輩からは軽んぜられるという、どうしようもない問題児である。けれども、そんな子路のことを孔子はこころから信頼している。
と、まあ、 山田先生
の論は、 「KY」
という流行語をネタに、秀才 顔淵
と比較しながら、 子路
の発言にあらわれた 「空気を読まない」
、 「空気が読めない」
ことの正直さを考えることを読者にうながし、 「自分のことを好きになろう」
というテーマに向かって、
「朝(あした)に道を聞かば、夕べに死すとも可なり。」
という結論へ進むわけですが、ぼくがおもしろいと思ったのは、別のことで、 「そんたく」
という最近の流行語にを思い浮かべたことでした。
「忖度」
と漢字で書くこの言葉が、はやりはじめた詳しい経緯は知りませんが、ここ十年、高校の教室でハヤッテいた「空気を読む」をいう同調圧力の共有による、ニヤニヤ笑いの「平和意識」が、いよいよ一般社会でもあきらかな汚職の「合法化」用語として出回り始めているのだなと思うのですが、現在の「ものわかりのいい」諸君は、少なくとも、世事は知っている、正義漢 子路
どころか、「理想」に対して朴訥無双の 顔淵
からもはるかに遠いところにいることに、思わず気づかされたというおもしろさでした。
落ち着いて考えれば、暗澹とする世相ですが、まあ、 「論語」
あたりから読んでみるのも面白いのかもという、思いがけない発見の書だったということです。
皆さんも 「論語」
とかいかがですか?
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「日本語・教育」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内『高等学校における外国に… 2022.02.02
-
週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ… 2021.07.11
-
週刊 読書案内 阿部公彦他『ことばの危… 2021.02.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.















