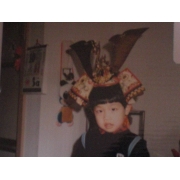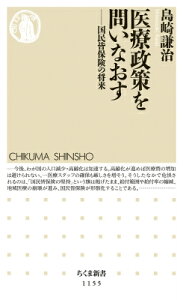PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
コメント新着
カテゴリ: 音楽・テレビ・映画・小説
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
地域医療構想の策定や在宅医療・地域包括ケアの推進など医療制度改革が矢継ぎ早に進められている。そして2018年には、次期医療計画や医療費適正化計画の策定、改正国民健康保険法の施行、診療報酬と介護報酬の同時改定など、一連の改革が結節する。そうしたなかで、国民皆保険を堅持するために、今、我々は何をなすべきなのか。医療政策の理論と実務に通暁した著者は、国民皆保険の構造の考察や人口構造の変容の分析を行い、わが国の医療政策のあるべき方向性と道筋を明快に展望する。医療問題に関心をもつ人すべてにとって必読の1冊。
【目次】(「BOOK」データベースより)
序章 問題の所在/第1章 日本の国民皆保険の構造と意義/第2章 歴史から得られる教訓と示唆/第3章 近未来の人口構造の変容/第4章 人口構造の変容が医療制度に及ぼす影響/第5章 医療政策の理念・課題・手法/第6章 医療提供体制をめぐる課題と展望/第7章 医療保険制度をめぐる政策選択/終章 結論と課題
島崎謙治(シマザキケンジ)
1954年生まれ。政策研究大学院大学教授。東京大学教養学部卒業後、厚生省(当時)入省。千葉大学法経学部助教授、厚生労働省保険局保険課長、国立社会保障・人口問題研究所副所長、東京大学大学院法学政治学研究科附属比較法政国際センター客員教授等を経て、2007年から現職。2013年から医療政策コースディレクター。博士(商学)。社会保障審議会専門委員。独立行政法人長野県立病院機構理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
かなり骨太の議論でした。
過去の医療政策の経緯から医療政策のあり方を展望しています。
特に、地域格差についての目くばせもしており、参考になりました。
人の生活は「地域」と切り離して存立しえない以上、まちづくりを含め地域における連携体制の構築も必要になる。
その具体的なあり方は地域によって異なる。
たとえば、都市部では関係者がネットワークを組むタイプの形態がなじむのに対し、過疎地では基幹的な病院・施設が中心となって地域包括ケアを推進するほうが適している場合が多い。
ちなみに、ここでいう地域とは市町村という行政管轄エリアよりも狭い。
実際、同一市町村の中でネットワーク型の地域と基幹病院中心型の地域が併存することは珍しくない。
象徴的なのは尾道市である。
筆者が知る限り、全国的に見て、尾道モデル(在宅主治医と病院主治医が中心となり他職種とともに「退院時ケア・カンファレンス」等を行うことにより連携体制を構築するモデル)はネットワーク型、御調モデル(公立みつぎ総合病院を中核として地域包括ケアを実施するモデル)は基幹病院中心型モデルの最高峰に位置する。
そして、尾道市と御調町は2005年3月に市町村合併したが、その後も2つのモデルは市内で併存している。
その方が地域の実情に合っているからである。
その意味では、地域包括ケアや在宅医療の最適解は地域の数だけ存在するといっても過言ではない。
非常に地理的な視点で興味深い事例でした。
地域の数だけ地域包括ケアが存在するということで、その多様性の実態とその要因を分析することが課題となります。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[音楽・テレビ・映画・小説] カテゴリの最新記事
-
高杉さん家のおべんとう 2024.10.04
-
TSUTAYAプレミアム 2020.03.08
-
単著 2019.04.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.