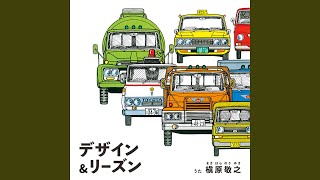2006年07月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-

6年生は「一休さん」を見よう
娘たちとアニメ「一休さん」をたまたま見た。いやはや実に面白く、そして勉強にもなった。「一休さん」が放映されたのは確か私が小学生4年生のころ。当時、何か困ったことが起きると、なめた人差し指を頭で回し、座禅をくんだりしたものだ。その「一休さん」を小4の娘と見たのだ。時の流れを感じ、何やら感慨深くもあった。一休さんはなぜ安国寺にいかねばならなかったのか。小4の私にはよく分からなかった。日本史の勉強も何もしていなかったのだから仕方がない。しかし今日見て、ああそうだったのか、と思うところが多々あった。一休さんは後小松天皇の皇子であったのだ。1392年、南北朝が合一したときの天皇である。また室町時代の様子も何となくよくわかる。足利義満も出てくる。それに第1話は、狂言「ぶす」的な話もある。これは1学期の社会の授業で話した内容でもある。もちろん一休さんのとんちも面白かった。なるほどこうするのかあといたく感心した。6年生諸君、勉強の合間にでも「一休さん」を見てみよう。
2006.07.31
コメント(2)
-
遅々として進まず
夕方から箕面祭りがある。娘たちは楽しみにしている。しかし私は原稿がまだ終わらずである。結局、娘たちは連れ合いと友達家族とで祭りに参加。私は一人家に残り原稿書き。早く終わらせたいのだが遅々として進まず。
2006.07.30
コメント(0)
-
まごわやさしいこ
15%クラブ 食の安全を考える学習会 まごわやさしいこ~元気で丈夫な体を作る安全な基本食~あなたのお子さんは毎日どんな食事をしていますか。「食」は「人を良くする」と書きます。私たちの体は、私たちが食べたものでできています。毎日の食事が、子どもたちの心と体の成長に大きく関わっているのです。元気で丈夫な子に育てるには、どんな食事がいいのでしょう。どんな食事が、子どもたちを蝕んでいるのでしょう。頭が良くなる食べものって何なのでしょう。小学校で独自の食育を実践している原田先生の話を聞いて、食について考えてみませんか。日ごろ疑問に思っていることを一緒に考えていきましょう。講 師 原田誉一日 時 2006年8月20日(日) 午後2時~4時場 所 みのお市民活動センター参加費 200円主 催 15%クラブ連絡先 072-727-0106(杉林) 090-9168-6596(橋本)
2006.07.29
コメント(4)
-
1日3食たべてみる
1日1食をつづけて1年9ヶ月になる。体調は、すこぶるいい。快食・快眠・快便だ。8月20日に「食」の話をすることになった。1日1食の話も隠しネタとして準備しておくつもりだ。1日何食とるのがいいのか。1日1食・2食・3食・4食・5食。いずれも私は経験済みである。その経験に基づいたネタを仕込んでおきたい。そんなこともあり、今日は久しぶりに1日3食にしてみた。1年9ヶ月ぶりである。朝 シリアル昼 懐石風定食夕 カレー結果、どうであったか。これは、8月20日の隠しネタにしておこう。
2006.07.29
コメント(2)
-
朝勉で鍛える
今朝は2:20に目覚めた。まだまだ暗いのだが、涼しい。涼しいうちに原稿書きをやってしまうのだ。6:30に娘と愛犬ゴロウの散歩に行く。今日は久しぶりに森に入る。生ゴミ堆肥化装置に入れる枯れ葉を取りに行くためだ。枯れ葉はやや腐葉土化していた。直径1cm弱の大きなミミズ数匹とびはねる。これらも手づかみで袋に入れた。家に帰り焙りたて挽きたての島珈琲を飲む。今朝はブラジル=カンターナ=コロアである。娘たちはホットケーキを焼いて食べていた。その後、朝勉。朝の勉強の時間である。名文音読をして百問計算をする。小2の娘は百マス計算。小4の娘は百問わり算。私も同じ百問わり算をする。今朝も娘たちの方が早くできた。次は、国語の予習である。まずは2学期に習うところの音読。読めない漢字はそのつど教える。娘は素早く読みがなを書く。音読後、問題を出す。クイズ形式で気軽に口頭で解かせる。明日もこの調子で涼しいうちに楽しくやるのである。
2006.07.28
コメント(1)
-
キャンプ帰りの娘に2つの変化
きのう娘が2泊3日のキャンプから帰ってきた。かなり紫外線を浴びたようで真っ黒だ。こんなに日焼けをしたのは生まれて初めてである。来年のキャンプ参加は見直さなければならない。娘が変わったのは皮膚だけではない。少々小生意気になった。連れ合いとも少し口論する。まあまあ2人ともなかよくしましょう。私はそう言うのだが連れ合いはやや本気で怒っていた。今朝、私は出勤する前に置き手紙を書いた。「おはよう。 名文音読と百マス計算・百問わり算をしておくこと。 お父さんより」夕食前に帰宅し聞くと娘たちはきちんとやっていた。小生意気ではあるが、やることはやる、よし、と思った次第。明日は早朝の朝勉(朝の勉強)をしよう。2学期の成績を上げるためだ。
2006.07.27
コメント(2)
-

うまいつゆが簡単にできる作り方
そばつゆを作る。わりと簡単に作れる。それに思った以上においしい。オルター食材だから安心安全だ。用意する物はビン。広口ビンやつゆの入っていたビンでもいい。そこに酒3・みりん3・醤油4の割合で入れる。これを鍋にうつす。15cm角の昆布を加えて2~3時間おく。昆布は、細かくちぎると後で食すときに食べやすい。鍋に火をかける。沸騰したら弱火にし、鰹節をそっと入れ5~7分煮る。勢いよく鰹節を入れると、ボワッと青白い炎が上がる。びっくりしたが、まるでフランス料理のようだと一人で感心する。もちろん鰹節は削りたてが一番うまい。火を止めてザルや茶こしでビンに入れる。ビンを割らないように注意。たったこれだけだ。好みによって、甘みや酸味を加えればいい。私は甘蔗糖と自家製梅酢を加えた。今夜はこれで、そばとひやむぎをいただいた。文句なしにうまい。味にはうるさい連れ合いも、「おいしい」と一言。参考文献〈うおつか流〉台所リハビリ術(129頁)
2006.07.26
コメント(2)
-
2学期国語の予習(1)
国語の教科書には上巻と下巻がある。下巻は2学期に配ることになっている。したがって今は上巻しかない。これでは2学期の予習が少ししかできない。きのう書いたのはそういうことである。上巻にある2学期の教材文を読んでみた。娘の教科書は東京書籍のものである。「『くらし百科』の時間です」という題。「話す・聞く」の教材である。内容も面白い。「卵のからを食器洗いに使う」「お茶がらを肥料にする」といった捨てる物を生活に役立てる工夫が書いてある。生ゴミ堆肥化や雨水利用・省エネなど、我が家でやってることに直結する内容だ。これなら娘も話す内容に困らない。生活に役立つ工夫なら私も話すネタがある。娘に聞かせることもできるのだ。この教材は、いただきである。後は下巻の教科書をどうするかだ。
2006.07.25
コメント(0)
-

2学期の国語を予習するのだが…
小4の娘はキャンプに行った。出かける前の30分、夏休みの国語・算数を終了。あとは帰ってきてから答え合わせをすることにした。もちろん、私は解説をする。読解問題や文章問題の解き方を伝授するつもりだ。これで自由課題以外の夏休みの宿題は完了である。そうして、2学期の国語を予習に入る。2学期の成績を上げるためである。まずは、音読だ。教科書をくりかえし音読する。範読・連れ読み・一人読みといった音読をするのである。読めない漢字は教える。漢字は先習い漢字学習を行う。2学期はもちろん3学期に習う漢字も先習いする。読み方・筆順・熟語読みを確認してから書く練習をする。唱え書き・ゆび書き・なぞり書き・写し書き・試し書きの順で行う。試し書きの前に〈つがわ式〉世界一やさしい「超」記憶法の手法も取り入れる。〈つがわ式〉世界一やさしい「超」記憶法これで音読と漢字は完璧だ。しかし、困ったことに気づいた。教科書は「上」しかない。「下」は2学期になってから配布されるのであった。「下」の教科書がないと、2学期の予習は少ししかできない。先習い漢字もやりにくい。5年・6年の先習い漢字用のドリルはあるのだが、4年生のはない。う~ん、どうしよう。小4の娘は明後日キャンプから帰ってくる。
2006.07.24
コメント(0)
-
2学期の成績を上げるために
2学期の成績を上げてやろう。小4の娘の通知票を見てそう決心した。「2学期の通知票、国語を全部『よくできた』にしよか」「うん、いいよ」娘も了解である。娘の通う小学校の通知票は観点別評価である。国語はつぎの8つの観点だ。 目的に応じて筋道をたてて話す。 話の内容を正しく聞き取る。 目的に応じて組み立てを考えて書く。 正確に朗読する。 文章の内容を理解する。 漢字を正しく書く。 文字をていねいに書く。 言葉のきまりを理解する。 1学期は全て「できた」。これを2学期は全て「よくできた」にするのである。まずは自信を持たせること。つまり「私は国語がよくできるんだ」という自信を持たせることである。この自信さえ持てば、娘の場合、観点にある話す聞くは問題ない。ではどうやって自信を持たせるか。夏休み中に2学期の予習をすればいい。もちろん夏休みの宿題は早々に終わらせる。ということで自由課題以外の宿題はもうほとんど終わらせた。ではどんな予習をするのか。それは後日、書いていくことにしよう。
2006.07.23
コメント(2)
-
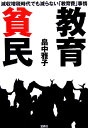
お金をかけずに教育する
『教育貧民』によると教育にはお金がかかるらしい。公立小学校時にかかる教育費は308万円(53頁)。その大半が塾代。そして最近では子どもの携帯電話代に月2000~5000円もかかるという。さらに私立中学に進学するなら入学までに300万円の準備がいる(86頁)。私立中学進学とは10年間、高額の教育資金を負担することだからだ。加えて夏期講習・合宿など進学塾代にかかる出費も覚悟せねばならない。教育貧民確かに、こう見ると、お金がかかる。とすると、お金がない家はどうするの。格差社会は子どもたちにも影響しかねない。それでは教育の機会平等ではなく『機会不平等』だ。勉強のできない子はどうなるのか。できないままでいいのか。「できん者はできんままで結構。 戦後50年、落ちこぼれの底辺を上げることばかり注いできた労力を、できる者を限りなく伸ばすことに振り向ける。 100人に1人でいい、やがて彼らが国を引っ張っていきます。 限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです」 (三浦朱門・前教育課程審議会会長)40頁機会不平等塾に行かなくても、読み書き計算の確かな学力をつけることはできる。親と教師が協力すれば、そんなに難しいことではない。家ですることは次の3つくらいだ。 1 早寝早起き 2 宿題は毎日確実にやる 3 テレビはあまり見ない(テレビを見る時間があれば本を読む)どれもお金はかからない。省エネだから節約できる。本は図書館で借りればいい。この3つさえできていれば、学校だけで確かな学力はつくと常々考えている。小2・小4のうちの娘たちは、塾に行っていないし、携帯電話も持っていない。私立中学なんかは全く考えてもいない。通知票を見ると、「がんばろう」はなかった。まあ、「よくできた」より「できた」の方が多かったが…。
2006.07.22
コメント(4)
-
市の環境教育実践校にもなる
大阪市の環境教育実践校に選ばれた。そのため昨日は午後から大阪市教育センターに行く。環境教育プロジェクトなる会合に実践校の担当が集まった。実践校は本校の他に4校。各学校がどんな環境教育を実践するのか概要をのべる。他の4校はビオトープや自然園での実践であった。本校は他の4校とは違った実践だ。「ほんまもんに学ぶエコロハスな生活様式」これが本校の実践主題。環境の現場で活躍されている方々(ほんまもん)から多くを学び、エコロハスな生活様式を実践するきっかけをつかむのだ。今日は朝からその実践計画を練っていた。2学期以降また一つ楽しみが増えたのである。
2006.07.21
コメント(0)
-
終業式、教室に中学生乱入?
講堂での終業式が終わり、2時間目は教室でお楽しみ会をする。各係が持ち時間1人あたり1分でクイズなどの出し物を行っていた。そこへ突如、中学生がやってきた。廊下でニコニコと教室の様子をうかがっている。出し物のクイズが終わったところで私は中学生たちを手招きした。「こんにちはー」と礼儀正しく入ってくる中学3年生男子5人に女子1名である。4年前、私が今の学校に赴任して受け持った子らなのだ。手にはそれぞれ今日もらったばかりの通知票がある。終業式になるとこうして通知票を見せに来てくれるのである。6年生の子どもたちも先輩の通知票に興味津々だ。みんなよくできている。中学校は10段階の相対評価。10になるのは各教科上位4人ほどだという。その10、そして9や8といった評定がたくさんならんだ通知票なのだ。通知票を披露してくれた後、6年生や私に熱く語ってもくれた。「中学3年生の上位20人のうち、半分は原田学級の生徒です」「百問わり算を毎日していると頭がよくなります」「ぼくは5年生のとき百問わり算をして勉強のできる頭に構築されました」「枕草子などの古典を中学で習います。名文音読で覚えていたから簡単です」「原田先生から教えてもらった環境のことを作文に書き、環境作文コンクールで入賞しました(「全日本中学校長会会長賞」入賞)」「ラグビー部の先生は、原田先生の後輩の○○先生です」ええ、そうなの。それでは今度、中学に行って、久しぶりにラグビーをしましょうか。
2006.07.20
コメント(4)
-

読むだけで「書く力」が劇的に伸びる本
今月中に仕上げねばならない原稿が1冊ある。来月中に仕上げねばならない原稿が2冊ある。そんななか読んだ本がこれ。読むだけで「書く力」が劇的に伸びる本この本を読んで次のように変わった。今月中に完成させたい原稿が1冊ある。来月中に完成させたい原稿が2冊ある。今は書きたくて書きたくてうずうずわくわくしている。「書く力」をつけるには文章術も国語力も必要ない(22頁)「自分」を語ることで、もっと「伝わる文章」が書ける!(151頁)自分が経験した「伝えたいこと」を自分の言葉で読者に語るように書けばいい。要はそういうことなのだ。ああ、これでずいぶん気が楽になった。また「ストーリー作文」(76頁)の手法は作文の授業に応用できる。描写・感想・エピソードを挿入すれば簡単だ。「夢作文」(208頁)は自分でも書きたい。これで夢が「憧れ」でなく現実のものとなる。さあ、書くぞ。
2006.07.19
コメント(0)
-
それなら常設のテントを設置せよ
今朝、学校について驚いた。飼育小屋の上にテントがひっくりかえて乗り上げている。それも2つ。竜巻の後、車がひっくりかえっている写真を見たことがある。そんな感じである。小雨の降る中一人でテントを撤収するのは難しいし危険だ。ましてや飼育小屋の上に上らなければならない。軽い高所恐怖症の私である。応援を待つことにした。しかし待ってても仕方ないと思いプールサイドに向かう。う~ん、どうしよう。しばし呆然とする。今年は台風が来ないので安心していたのに…。急な突風でも吹いたのだろうか。そんなことを思いつつ一人で撤収作業に取りかかった。ヒモをはずし、重しをとる。一人でやれるだけのことをしておこう。しかし応援は現れず、結局、一人で飼育小屋の上に上った。家の屋根に上って煙突掃除をしたことを思えば楽勝である。ただし小雨のなか足下が滑りやすい。慎重に慎重に上ったのだ。1つめのテントを撤収しおわると、応援の方がきてくれた。そうしてようやく2つめも撤収できた。子どもたちが登校する前に撤収できてよかった。テントは脚が3本へし折れていた。修理できるかわからない。早速、事務担当の方が業者に連絡をとってくれた。修理費などのことで教育委員会にも電話をかけてくれた。すると教育委員会にいやみをいわれたそうだ。「本来ああいうテントは毎日かたづけるもの」確かにそうだろう。しかし8つものテントを毎日出し入れするにはそれなりの人数と時間がいる。4人そろってやれば1日にテントの出し入れで2時間かかる。ただでさえ手の足りない現場では不可能だ。今は短縮授業期間で昼から授業がない。それでもみんな休憩休息がとれないのが現状である。久しぶりに昼からずっと職員室で仕事をしていたが、だれ一人、休息休憩はとれていない。書類作成・保護者への対応などに追われているのである。そんな現場の現状をおそらく教育委員会は知らないのだろう。予算の少ない中でテントをそろえ、なんとかやりくりしてきているのである。台風接近とあれば協力し合ってテントを撤収する。いやみを言う教育委員会に一言申し上げたい。そんなことをおっしゃるのなら、常設のテントを各学校・幼稚園に設置して下さい。環境省のマニュアルにあるとおり、紫外線による影響は子どもたちの将来を脅かすのですから。
2006.07.18
コメント(2)
-

晴耕雨読、寿司をおかずにごはんを食べる
机の上にたまりにたまった書類の山。これを一挙に片づけスッキリする。机横の積ん読から2冊の本をとり読了。積ん読は書類の山のようにはいかない。それでもスッキリする。夜は連れ合いの実家で寿司をごちそうになる。寿司だけではたりないからごはんも炊いてもらう。ごはん命のわたしなのだ。寿司をおかずにごはんを食べる。おかわり3杯(2合分)。おけ寿司ゆえ少々遠慮しがちに食べる。ガリなどもしっかりおかずにした。本日読んだ本どちらも前作の方がよかった。 この国のけじめ石に言葉を教える
2006.07.17
コメント(2)
-
もぎたて生トウモロコシの味
庭の畑にトウモロコシが6本なっている。少し小ぶりだが去年より大きい。去年は全部アリに食べられ悔しい思いをした。昨日1本とってみた。鮮やかなうす黄色の実が、ぎっしりつまっている。アリによる被害はない。今日は1本とってその場で食べる。3つに折って娘たちと食べたのだ。あまい。一粒一粒の実からジュワ~ッと甘い汁があふれてくる。もぎたての生で食べるトウモロコシ。こんなに甘くうまいなんて初めて知った。アリが欲しがるのもムリはない。
2006.07.16
コメント(8)
-
学力研の全国大会が近いというのに
8月に学力研の全国大会が大阪である。5日(土)と6日(日)の両日。常任委員の私はもちろん参加する。6日(日)には2年生の分科会で報告もする。ところが2ヶ月つづけて常任委員会を欠席した。6月は、通天閣で知るほんまもんの準備。7月は、エネルギー教育実践校の説明会のため東京に行った。7月末にある袋詰め作業にも参加できそうにない。残念。この日は、NPO法人一杯のコーヒーから地球が見えるの総会がある。私は同法人の理事で、今度出版する本の確認もしておきたい。本といえば、今月中に仕上げねばならぬ原稿があった。来春出版予定の本である。若い先生対象にした、基礎基本の指導法を紹介する本だ。私は2年生の国語を担当している。この原稿を仕上げ学力研の大会で価値ある報告をしたいと思う。今月中といえば、エネルギー教育実践校の指導計画も提出しなければならなかった。授業の内容はもちろん、特別講師・教材・教具などの予算もたてる。プロジェクターなど高価な機器も買えるのだが、3社見積もりをとらねばならぬという。一体どうやってとるのか。そんな話を大阪教育サークルはやしの例会でした。話していくうちに芋ズル式にやることがどんどん出てきたのだ。やはりこうしてはいられない。
2006.07.15
コメント(0)
-
百問わり算5分以内に全員終了
4分30秒。全員が百問わり算を終了するのにかかった時間である。百マス計算ではない。百問わり算なのだ。学級の子30名全員もれなく、百問わり算を5分以内に終了する。私が秘かに立てていた目標である。それが本日、達成できた。4月当初、百マス計算から始めた。たし算→ひき算→かけ算と進んだ。全員が3分以内にできるようになるたびに次へと進んだ。そして百問わり算である。これは手強い。5分をきるのはなかなかである。しかし本日全員それができたのだ。当初、計算の苦手だった子がみるみるできるようになっていった。「先生、○○くん、今日、百問わり算できてた。 わたし、びっくりした」休み時間そう言いにくる子もいた。「6年1組30名全員、5分以内に百問わり算ができるようになりました」次の時間、子どもたちにそう言うと、歓声と拍手が自然と起きた。しかし、実は1人だけ、6年1組にはまだ5分をきれない人物がいる。担任の私である。家で娘としているが、5分で80問しかできないのだ。がんばらねば…。
2006.07.14
コメント(0)
-

鉛筆を正しく持てていますか
子どもたちの鉛筆の持ち方が気になる。正しく持てていないのだ。正しい持ち方に近い子は2名のみ。残る28名はそれにはほど遠い。鉛筆が正しく持てないと、いろいろな弊害が出る。・正しい字が書けない。・書くのに時間がかかる。・姿勢が悪くなる。・すぐ疲れる。・集中力が持続しない。正しい鉛筆の持ち方は、低学年で身につけさせたい。6年生だともう手遅れかもしれない。しかし今からでも遅くはない。ユビックスを使えば何とかなる。児童かきかた研究所の高嶋喩先生考案のスグレモノだ。(たしか今年の『小学1年生』の付録にはドラえもんのユビックスがありましたね)私もユビックスで正しい持ち方ができるようになった。子どもたちにもユビックスを使わせたい。鉛筆の正しい持ち方が身に付くもちかたくんユビックス 右手用'☆'鉛筆の正しい持ち方が身に付くもちかたくんユビックス 左手用'☆' 高嶋式子どもの字がうまくなる練習ノート徹底反復たかしま式文章がきれいに書ける視写プリント高嶋喩の脳いきいき!大人の書き方プリント
2006.07.13
コメント(2)
-

1学期中に6年生で習う181字の漢字を書けるようにする
「今日は私が答え合わせをします」そう言うと子どもたちの目が俄然真剣みをおびた。全漢字試験のことである。いつもは近くの子同士で答え合わせをしている。隣・前後・斜め関係という具合に。答え合わせをすることで客観的に漢字を見ることができる。しかかも短時間で結果がわかるので有効なのだ。今日は先生が見る、ということで子どもたちも気合いが入ったのだろう。両面印刷の全漢字試験をいつもは片面10分の計20分で行う。早い子は片面を8分で書き終える。「書けた人から持ってきなさい」15分ほどで子どもたちが持ってくると思いそう言った。ところが、20分をすぎても誰も持ってこない。みんな慎重に漢字を書いているのである。はねるところは、はねる。はらうところは、はらう。とめるところは、とめる。一画一画ていねいに書く。いい加減な字には×をつける。私の採点基準を知っているからか実に慎重に書いている。結果、殆どの子が殆どの漢字を書けていた。字もびっくりするくらい丁寧である。6年生で習う181字の漢字。全員100字以上は書けていた。170字以上がほとんどである。 学力ドリル漢字(小学5年生)学力ドリル漢字(小学6年生)本日の時間割1体育 クロール・平泳ぎ・自由形 遠泳2国語 全漢字試験3理科 生物と環境 まとめ4算数 体積「確かめよう」個人懇談会初日
2006.07.12
コメント(2)
-
風船おみこし実践報告掲載
明治図書から8月号の『楽しい体育の授業』が送られてきた。特集「人気のアイデアスポーツ18を授業する」。5月に実践した「風船おみこし」の報告が22頁に載っている。表紙には何とその「風船おみこし」絵。これはうれしい。〆切に追われつつ書いた原稿であるだけにやって良かったと思う。
2006.07.11
コメント(0)
-
やはり32℃の教室は暑いのだ
教室は32℃。以前の私なら汗をかきかき授業をしている気温である。しかし1日1食になって余分な脂肪がとれたせいか、汗っかきではなくなった。それでもやはり今日は暑かった。算数の授業では計算まちがいをすることもあったほどだ。ボーっとするのである。そんな中、5時間目のプールはうれしい。6時間目の社会はスッキリ気分で授業ができた。明日から短縮授業である。本日の時間割1家庭 洗濯のコツと洗剤の成分を発表2国語 漢字ドリル (算数問題)3算数 体積・特殊形の求積問題4総合 (算数問題)南極「氷点下80度の世界」5体育 水泳 泳力検定追試・写真撮影(卒業アルバム)6社会 長篠の戦い 気づいたこと 問題
2006.07.10
コメント(0)
-

カニの卵は小粒のイクラ
朝の散歩の帰り道、側溝でカニを見つける。網ですくって長女と2人で家に持ち帰る。よく見ると腹を開いている。イクラのごとき卵がぎっしり。直径2,3ミリの橙色のきれいな卵だ。庭のバケツ田圃にそっと入れる。ここで卵がかえるといいな。娘はもちろん私も期待する。
2006.07.09
コメント(0)
-
荻野さんの記事のみ熟読
マドンナ古文の荻野文子さんの記事を読む。本日の讀賣新聞に見開きである。荻野さんの記事のみ熟読。他はざっと見るだけ。
2006.07.08
コメント(0)
-
自己評価どの子もしっかり勉強したい
通知票の3段階の評価基準を話す。例えば試験で言うと、次の図のようになる。 C B A A…よくできた0点~70点~90点~100点 B…できた C…もう少しもちろん試験だけで評価はしない。これに日頃の学習の様子を加味する。宿題・提出物・授業態度・発表など。その後、子どもたち自身に自己評価をさせた。学期末恒例の「○学期をふりかえて」である。各教科・総合・その他と自己評価する。仲の良い友達の名前も書く。ウラ面には「先生へのお便り」を書く。「静かな教室なので集中して勉強できる」「勉強がグ~ンとできるようになった」「環境や食べ物のことなど知らないことを教えてくれた」30人全員もれなく知的好奇心旺盛である。どの子も勉強ができるようになりたいのだ。私もさらに勉強して授業力を上げる決意である。本日の時間割1道徳 1学期をふり返って2家庭 試験「衣服・洗濯」3国語 試験「新聞の研究・推論」4社会 試験「室町時代」5算数 体積 特殊形の求積問題
2006.07.07
コメント(0)
-

子どもの話にどんな返事をしてますか?
最近、子どもとうまくいっていない。どうも話が通じない。子どもが言うことを聞かなくて困っている。そんな方にぜひ読んでもらいたい本がある。親はもちろん先生にもオススメだ。子どもの話にどんな返事をしてますか?1日1冊で本を読むようにしているが、この本は3日かけてじっくり読んだ。それぞれの場面で、自分の子や教室の子どもたちを思い浮かべながら読んだのだ。ああ、あのときこう言えばよかったなあ。なるほど、子どもはそんな思いをもってこんなことを言ういうのかあ、と。いい関係を築くには心に寄り添うことが大切だ。言葉の背景(ウラ)にある意味をくみ取り共感しつつ返事をする。そんな気づきを改めて与えてくれた本である。おかげで、家では娘たちがよく話してくれるようになった。教室でも子どもたちが何かとよく話に来てくれる。私は子どもたちの話を幸せ気分で楽しく聞いている。
2006.07.06
コメント(6)
-
シャツを入れましょう
シャツを出して着る。そんな着方をしている子どもたちを見かけるようになったのは、今の学校に来てからのことだった。標準服のシャツだけでなく、体育着までシャツを出して着る。それまでそんな着方をしている子なんて今までほとんど見なかった。私が中学生のころ、当時「不良」と呼ばれていた生徒は判で押したようにそんな着方をしていた。彼らはそれがかっこいいと思っていたのだろう。しかし私は、みっともなくだらしない、と思っていた。5年前、今の学校に赴任した。自分の学級の子どもたちには、そんな着方をさせたくなかった。「シャツを入れましょう」ことあるごとに私は言った。そのせいか、少し荒れた雰囲気やだれた空気が教室を支配することはなかった。私が学級開きのときまずやることはそんな着方をさせないこと。「シャツを入れましょう」この5年間ずっとそうである。そんな着方をさせないで、きちんとシャツをいれさせましょう。何回かそんな提案をしたことはあったが、「シャツを入れる理由がわからない」ということで受け入れられなかったこともある。ところが、今日また提案したのだ。せめて体操服ぐらいは、シャツをいれましょう、と。野球選手もサッカー選手も、シャツを出している人はいないのだから。するとそれは通ったのだ。
2006.07.05
コメント(8)
-

佐高信『小泉よ日本を潰す気か!』
小泉よ日本を潰す気か!激辛評論家の佐高信さんが、20代の編集部員の疑問に答える形でまとめられた本。「『語り』をまとめることによって、もっとナマに私の怒りが出ている。 ホンネというか思想というが、よりストレートに表現されているのである」(197頁)全くその通りで、しかも実に分かりやすい。ああ、あの問題の真相はそういうところにあるんだな、と納得できた。新聞を読んでいるだけでは見えない裏事情もあぶり出してくれる佐高さんの語りである。「敗戦後にアメリカに押しつけられた憲法を、戦後60年がたった今こそ日本国民が自ら憲法を決めるべきという主張が、なかば正論のように言われている。 しかし、改憲も実はアメリカの押しつけなんだよ。『押しつけ憲法』論者は、なぜ改憲も押しつけられてると誰も言わないのか」(44頁)
2006.07.04
コメント(0)
-
平泳ぎのコツ
水泳授業の4回目。今日は平泳ぎのコツを教えた。「平泳ぎのコツを教えます。 4つあります。 1つめ、ける。 2つめ、のびる。 3つめ、かく。 4つめ、パッ。息継ぎです。 これを、けってのびてかいてパッ、けってのびてかいてパッ、と覚えます。 みんなで言いましょう。 けってのびてかいてパッ、サンハイ」「けってのびてかいてパッ、けってのびてかいてパッ…」これを数回くりかえす。「覚えた人は立ちましょう」全員すぐ立つ。そこで平泳ぎが上手な子に25mを泳いでもらう。その子が泳ぐとすぐ私は、「けってのびてかいてパッ、けってのびてかいてパッ…」をその子の動きに合わせて言う。見ている子どもたちは目と耳で平泳ぎのコツを学習する。鏡神経細胞系の効果に加え、耳からの情報でもって平泳ぎのコツをつかませるのだ。後は実際に練習あるのみ。徹底反復である。たったこれだけのことだが、実に多くの子が平泳ぎができるようになった。中には今日初めて平泳ぎができうれしい、という子もいた。なおこの指導法は原田独自の指導法で参考文献等はない。7年前、当時4年生の子らに指導したのが最初である。
2006.07.03
コメント(4)
-
箕面駅で平川さんに合いました
歩行読書で図書館に向かう。箕面駅西口の交差点で信号を待つ。向こう側の道を白いトレーニング服の男性が歩いている。競歩のごとく早歩きである。よく見ると平川さんだ。漫才コンビWヤングの平川幸男師匠である。「平川さ~ん」「おお、久しぶり」「ひょっとして石橋から歩いて来はったんですか」「うん、そうや」「すごいですね」「走ったり歩いたり、走ったり歩いたり…」平川さんの家は石橋駅の近く。そこから箕面駅まで4km以上ある。箕面駅を折り返しまた石橋駅まで走ったり歩いたりするという。往復8km以上。そう言えば、平川さんはNGK(なんばグランド花月)に行くとき、梅田から難波までよく歩いていくのである。これも4km以上である。「ちょっと、おトイレ行くから。また…」「失礼します」そう言って平川さんと別れ再び歩行読書で図書館に向かう。平川さんから元気とやる気をいただき感謝感謝である。
2006.07.02
コメント(0)
-

さらに積み重なる山も何その
エネルギー教育実践校の説明会に参加した。どっさりと書類もいただいた。これをこれから書いていかねばならない。いろいろとややこしい手続きもありそうだ。しかし2学期から本格的に始めるエネルギー教育のためである。これくらいのことは何のそのである。2学期が楽しみだ。朝から始まった5時間以上の説明会。終わると素早く大阪に帰った。せっかくの東京なのだがまだまだよやりたいことが山積みなのだ。こうしてはいられない。きのう東京に行く途中で『1日5分で運が良くなる魔法の授業』を読んだ。やる気が出るのだ。「肯定心っていうのは、不可能も可能にする」(47頁)のだ。1日5分で運が良くなる魔法の授業
2006.07.01
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1