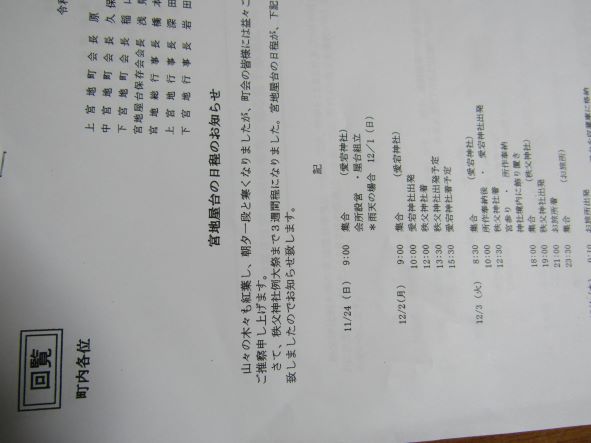2012年07月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
こんな映画を観た~家族の庭
この日本語タイトルは内容とまったく関係がない。ポスターやチラシにある「喜びは2倍に、悲しみは半分に」もまったく関係がない。イギリス演劇の伝統を感じさせる登場人物のキャラクターの構築が見事な、そして痛烈な風刺がきいた映画である。これといったストーリーもドラマ展開もなく、もちろんクライマックスもないからカタルシスもない。かといって教訓映画でもなく、ダメ人間を突き放して描くマイク・リー監督の冷徹さが潔いほどすがすがしい。とはいえ、観る人によっては、つまりダメ人間は自分の姿を見るようで不快になるにちがいない。というか、この映画を観てまったく理解できず不快に感じたとするとすでにダメ人間か、ダメ人間になる素質が十分な人にちがいない。原題は「アナザ・イヤー」。2010年のイギリス映画。この映画は、監督の立場が主人公の夫婦(知的でエコロジカルな生活を夫婦一緒に楽しんでいる、そこそこ裕福で安定した人たち)と同一であると考えるとわかりやすい。弁護士の息子を持つこの夫婦の家を訪れるのが、夫婦の同僚や友人ではあるが不安定でダメな人たち。夫の友だちで体重管理のできない独身男、妻の同僚で料理が不得意で離婚と不倫を経験している大酒飲みでタバコも吸う女といった人々。特にこの女はもうひとりの主人公ともいえる。いい歳をして自分をコントロールできず愚痴ばかりで向上心も、ついでに預貯金もない。こうしたダメ人間を、それでも優しく包み込む夫婦の暖かさ、家庭があることの良さを印象づけるように描くのがふつうだろうが、リー監督はそうしない。「自分の人生には自分で責任を持つこと」「貴女にはプロカウンセラーが必要よ」とカウンセラーの仕事をしている妻をして言わしめる。排除はしないが、暖かく受け入れることもしない。こうした人間関係はイギリスではふつうなのだろうか。そうだとすると、いささかイギリスという国と国民に興味もわく。家庭菜園やガーデニングや料理を二人で楽しみ、タバコは吸わず、テレビも見ず読書を好む夫婦がますます幸福になっていくのに対し、自己コントロールできない中高年男女はますます孤独に、ますます哀れになっていく。「格差」は自分が選びとったものであり自己責任だというリー監督の視点は鋭いし正しい。それを象徴するシーンはいくつかあったと思うが、ダメ女のメアリーがタバコを吸い始めると屋外にもかかわらず全員が彼女から離れていくシーンは最も明快な例。みな舞台俳優出身ではないかと思えるほど「表情」で演技のできる俳優を集めたキャスティングが見事。なかでも、「イタイ女」メアリーを演じているレスリー・マンヴィルには、いらいらさせられる役どころにもかかわらず演技力で感嘆させられた。夫婦の妻よりも美人な女優を配した監督の慧眼には敬服させられる。美人には美人であるがゆえに異性を見る目の育たなかった人が多いが、美人は美人ではない女性よりも不幸な人生を送りがちという冷厳な事実をリー監督はしっかり見抜いている。夫婦にトムとジェリーという名前をつけたり、こうした典型的に中流な人たちを戯画的に描く部分もある。まったく一筋縄ではいかない監督である。
July 30, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMF-GALAコンサート
音楽監督ファビオ・ルイジがPMFの本拠地で指揮をする最後の室内コンサートを含む「PMFガラコンサート」に、第1部の後半から行った(28日、札幌コンサートホール大)。札幌という都市のよさは、ホールにしても映画館にしても都心もしくは交通の便のいいところに立地しているので、はしごのようなことがしやすい点にある。これで都心に常設のオペラハウスでもあればウィーンやミュンヘンといい勝負だが、東京だとこうはいかない。東混の演奏会は3時20分に終わったが、キタラホールまでの移動は20分かからない。着いたときは、3時に始まったガラコンサート第1部の前半がちょうど終わったところだった。この最終コンサートはソールドアウトになることがほとんどだった。数年前までは少し余分な枚数を買っておいたくらいだ。しかし今年は満席にならなかった去年よりさらに空席が目立つ。メーンの「アルプス交響曲」は実演で聴く機会の少ない曲であり、札幌では過去2回しか演奏されたことがない。ルイジは9月からチューリヒ歌劇場の音楽監督に就任しいきなりヤナーチェクのオペラを指揮するが、到達できるポストとしてはすでに世界の最高位にいる指揮者の見納め、聴き納めになるかもしれないというのに、翌日の野外コンサートには1万人近くも集まるというのに、これはいったいどうしたことか。札幌の主なコンサートが厚生年金会館(当時)で開かれていたころは、いつもゲネプロにもぐりこんでいた。客席にほとんど人のいない状態だとホールは格段とよく響く。客席が埋まった本番との音響の落差にいつも落胆させられたが、音響面では空席の多い方が好都合だ。だからなるべくクラシックのコンサートには来ないように。特に最前列中央の席は買わないように。ソロや室内楽、協奏曲の場合はその席に座り、オーケストラ曲の場合は1階後列の中央からやや右よりの座ることにしているので、こうした席もなるべく買わないように。いちばん音響がいいのは天井桟敷であるというのは常識だから、どうしても聴きたければ最安席を購入することだ。前後左右に人のいない状態で聴く一流の音楽ほど王侯貴族のような気分にしてくれるものはほかにないので、わたしが行くようなコンサートには誰も来ないのが望ましい。第1部後半はヨハン・シュトラウス(シェーンベルク編曲)の「皇帝円舞曲」で開始。フルート、バイオリン、ビオラ、チェロ、クラリネット、コントラバス、ピアノという編成で、声部の動きがよくわかる編曲はさすがシェーンベルクといったところ。管楽器は教授陣、その他はアカデミー生による演奏だったが、教授陣の音楽性の豊かさ、特にフルートのホスクルドソンのそれは際だっていて、ほかは邪魔に感じられたほど。ファゴットのダニエル・マツカワが指揮したグリーグ「ホルベアの時代」からの「前奏曲」とチャイコフスキー「弦楽セレナード」第1楽章は、可もなく不可もない出来。マツカワはフィラデルフィア管弦楽団の首席奏者なので、フィラデルフィアのような音が聴けるかと期待したがあてがはずれた。ホルストの「ジュピター」を田中カレンが編曲した「PMF賛歌」で、巨大クラッカーの爆発と共に第1部が終了したが、この編曲がひどかった。聴衆が一緒になって歌うようになっているが、素人に歌わせるには音域が高すぎるのだ。半音上がる後半の転調も経過句が素直でなく転調しにくい。第2部はPMFオーケストラ演奏会。ブラームスの二重協奏曲とR・シュトラウスの「アルプス交響曲」。30日には東京でも演奏される。ブラームスのソリストはメトロポリタン歌劇場管コンサートマスターのデイヴィッド・チャンと首席チェロ奏者のラファエル・フィゲロア。やや速めの引き締まった演奏で、二人の丁々発止のかけ合いは見ものであり聴きもの。硬質のチャンのバイオリン、豊かに歌うフィゲロアのチェロというちがいはあるものの、アメリカという国のバイタリティを感じさせるアグレッシブな演奏。歌い込んでもテンポが遅くならず、少し速めのテンポの中で目一杯歌うといういい演奏の条件を満たしていて、いささか冗長なところもあるこの曲を一気に聴かせた。メーンの「アルプス交響曲」は圧巻。前半はPMFアカデミー生だけによる演奏だったが、この曲では教授陣が首席の位置に座る。「氷河で」や危険な瞬間」でマーク・J・イノウエのトランペットをロバート・ワードのホルンが引き継ぐといった演奏はPMFならではで、鳥肌もの。その鳥肌がおさまらないうちに、フィラデルフィア管弦楽団やシカゴ交響楽団、メトロポリタン歌劇場管弦楽団の木管奏者たちのきらめくようなアンサンブルが明滅してまた鳥肌が立つ。「頂上にて」でのユージン・イゾトフのオーボエ・ソロを引き継ぐ金管セクション、思い出したらまた鳥肌が立ってしまったが、鳥肌がおさまらないうちに次の鳥肌が立つという、生まれて初めての経験をした。この「頂上にて」の盛り上げはオペラ指揮者ルイジの面目躍如。息の長いフレーズをまったく弛緩なく周到に盛り上げていったが、クライマックスにおけるパッションの表出は溶鉱炉のような熱さだった。この曲のアプローチには2種類ある。この曲の発想の元となっているガルミッシュ・パルテンキルヒェンはごつごつした岩山だが、そうしたごつごつした感じを出した起伏の大きい演奏。もう一つのタイプは、こちらの方が多いのだが、作曲者自身がつけた各部分のタイトルの内容に沿いつつ、統一した音楽作品としてとらえてオペラのように流れを大事にしたもの。しかしルイジの演奏は、ごつごつした起伏の大きな演奏でありながらも流れのよさを確保したもので、この二つのタイプを高度に止揚した演奏といえようか。アラン・ロンバールのような荒削りの演奏が実は好きなのだが、聞き終わったあとの興奮ではない充実感はこういう演奏の方が得られるものだ。ひとつだけ難点をあげれば、静かな部分の音量が少し大きかったこと。音色もやや固く感じられた。ウィーン・フィルのような柔らかい音色は望むべくはないにしても、たとえば武満徹作品の演奏経験があれば、ああいう音色をこの曲の演奏に反映させるようなことはできたと思う。これで札幌でのPMFの室内コンサートはすべて終わった。24日間の会期中に開かれた30ほどのコンサートのうち行くことができたのは3分の1ほど。来年は少なくとも半分は行くようにしたい。アカデミー生はバーンスタイン没後に生まれたような人たちの割合が増えている一方、客層はバーンスタインの壮年以前に生まれたような人がほとんど。PMFの聴衆は比較的年齢層が低かったが、ここへ来て様相が変わってきた。この日のコンサートには10本ものマイクが立てられていたが、テレビ収録はなかった。これは前代未聞のことのような気がする。NHKは経費節減で再放送ばかりやっているが、こんなところにも影響が出ているのだろうか。録音は残っても、映像として記録されないとすればこんな残念なことはない。先々週の「悲愴」にしても、神技としか思えない指揮の瞬間があった。ファサード席から見たかったと思ったことである。
July 28, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~東京混声合唱団 札幌特別演奏会
芸術には2種類ある。大衆芸術と限界芸術である。大衆芸術とは表現主体と観衆が分離しているもので、限界芸術とは両者が一体となっているものである。合唱や吹奏楽はその両方にまたがっていて、観客の多くは自分でも演奏する人か出演者の身内だが、そうでない人も混じっており、音楽会が初めてという人もいる。音楽ファンではない人の割合が多く、しかもそういう人が音楽が好きになるきっかけになりやすい最大のジャンルではある。東京混声合唱団を聴くのは20年ぶり以上か。前回聴いたときのメンバーはひとりもいないのではないかと思う。若手からベテランまでバランスよく揃っているのが、高齢化が目立つアマチュア合唱団との大きな差。東京混声合唱団、略して東混は、毎年8月に「8月の祭り」を開催し、林光の「原爆小景」を演奏している。このコンサートにはずっと行きたいと思っていた。しかしチケットがソールドアウトのことが多いし、お盆前の時期なので動きにくく、行けないでいるうちに林さんは亡くなってしまった。林さんが指揮する「8月の祭り」を聴くのが人生の目標のひとつだったのに、果たせぬままに終わってしまった。だから「原爆小景」の完結版が北海道初演されるこのコンサートに、ある種の贖罪のような気持ちで出かけた。PMFガラの室内楽コンサートとだぶったが、こちらに出かけることにした(28日、札幌教育文化会館大ホール)。後半ではその「原爆小景」(完結版)が作曲者追悼ということで演奏された。完結版とは、1958年と71年に作曲された3曲に、2001年の「永遠のみどり」が加えられたもの。この「永遠のみどり」は調性感の明るい、そして短い曲。この曲が加わることで、前衛的なイメージの強いこの曲が、全体としてはむしろ「わかりやすい」音楽であるという印象になった。東混はこの曲を何度もレコーディングし、何百回も演奏している。そして作曲者からの直接の薫陶を受けてもいる。演奏は、そうした東混ならではのよくこなれたもの。ただ、初めてこの曲に取り組むような団体の緊張感はなく、なめらかで優しい曲作り。これは流麗な音楽を作ることで知られる指揮者・大谷研二の個性の反映でもあるのだろう。この芸術的に密度の高い音楽のあとには、東混の愛唱曲5曲とアンコールに武満徹の「翼」。この6曲の選曲や編曲はどれも見事で、帰り際には、こうした音楽会には縁のないような人たちが口々に「来てよかった」と語り合っていた。1500の会場を満席で埋めた聴衆は、背中の丸くなったような人がほとんどだが、オーストラリアの原題作曲家リークの「コンダリラ(滝の精)」は現代曲にもかかわらずこうした聴衆にもアピールしていた。男声合唱だけがステージにのり、女声は客席のあちこちに配置される。自然音を模した響きが会場全体にこだまし、コンセプチュアル的ではあるものの(したがって同じ手は使えない)不思議な空間感覚の創造に成功した佳曲だった。こういう音楽のよさは録音では決してわからない。前後左右すべての方向から美しい人間の声に包まれる体験というのはライブでしかありえない。橋本国彦の「お菓子と娘」は林光の粋で洒落た編曲に耳を奪われる。宮沢和史の「島唄」(若林千春編曲)は、優れた編曲のためもあって最も感動的だった。よく知られた沖縄音階のメロディが豊かなハーモニーや効果的な擬音、口笛を伴って大ホールに響いていく。この音楽に永遠に浸っていたいとさえ思ったほど。いま思い出しても涙が出るほどだが、この懐かしくも美しい音楽は万人を魅了するだろう。黒人霊歌「ジェリコの戦い」は、ホーガンのモダンな編曲が素晴らしく、この日のコンサートに大きなクライマックスを作った。合唱を聴いていつも思う不満は、アタックが優しく、攻撃的な音楽が生まれにくいことだが、東混はさすがだった。24人という少人数にもかかわらず、迫力あるダイナミックな、それでいて機敏な演奏にプロの底力を感じた。最後は三善晃編曲の「ソーラン節」。凝りに凝った芸術性の高い編曲とやはりダイナミックな演奏に「高齢者ばかりの」会場も沸いた。アンコールの「翼」は気品と格調を保って優美に歌われた。前半は「東混と歌う会・結」との合同で信長貴富の「初心のうた」(木島始の詩による)と、札幌の陣内直が東混を指揮してハンガリーの現代作曲家レヴェンテの「美しく~愛と欲望のうた~」。後半の印象が強いのであまり記憶に残っていないが、レヴェンテの曲は古今のいろいろな作曲技法を折衷的に取り入れた洒落た感じの作品。陣内直という人の指揮も端正かつ機敏な素晴らしいものだった。素人が素人を指導していたような傾向の強かった札幌の合唱界に本格的な指導者が現れてきたのを心強く思うが、三陸地方の漁師なみにすすむ高齢化だけは何とかならないだろうか。音楽の敵はいくつもある。この30年では、カラオケとゲームという強力な敵が誕生した。この強力な敵はこんにちますます強大化しているが、こうした「文明」にアナログな文化が死滅させられていくのを眺めるのも一興だと考える。心に血の一滴でもながすことにしよう。コンサートは大谷研二の話をはさみながら進行した。NHK-FMの合唱番組でもおなじみのその語り口は簡潔にしてユーモラス。50代後半くらいと見たが、ポイントだけを押さえた解説と語りかけにはただものではない知性を感じた。このあと聴いたPMFガラコンサートの軽薄な司会とは比較にならない。二人の(誠実さなど人間的にも非常に優れていると思われる)合唱指揮者の発見など、いろいろな収穫のあったコンサートだった。
July 28, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~山田亜希子ピアノ・リサイタル
PMFアメリカ・リサイタルシリーズで独奏・伴奏共にしっかりした音楽を奏でていた山田亜希子のリサイタル。長大な難曲をどう弾きこなすか興味があったし、めったに聴くことのできない曲でもあるので出かけてみた(27日、札幌コンサートホール小)。曲目はベートーヴェンの「ディアベリのワルツによる33の変奏曲」ただ1曲。実のところ、この曲は苦手だ。というか、苦手でない人は稀だろう。ライブ演奏を最後まで寝ないで聴き通せる人は少数だと思う。そう思ったので、じゅうぶんな休養(昼寝)をして出かけた。それでも眠気を押さえるのは、特に前半では苦労した。それは曲のせいであって演奏のせいではない。山田亜希子はこの曲にはよほど自信を持っているらしく、全曲をしっかりした緊張感と構築感を保ちながら雄弁に演奏した。暗譜で、ほぼノーミスの演奏は驚異的ですらある。50分強のこの曲に比べると、60分弱のバッハ「ゴールトベルク変奏曲」やジェフスキー「不屈の民の主題による36の変奏曲」は1変奏ごとに刺激的で退屈することがない。それではなぜこの曲が退屈なのか。端的に言えば、他者の理解をまったくあてにしていない作曲者晩年の「ひとりごと」のような音楽だからだ。聴衆のウケを狙うのではなく、「ほんとうはこういう音楽ばかり書きたかった」という本音だけの音楽なのだ。第22変奏ではモーツァルトの「ドン・ジョバンニ」のレポレロのアリアが唐突に出現し戯画的に扱われるが、なぜここにこの音楽を持ってきたか意味深ではあっても音楽的なつながりもない。このあとバッハに回帰したような音楽も現れるが、そのままバッハ的に高揚していくこともない。長大な割に壮大ではなく、「変奏」と言っても和声進行によって気づかされる程度。前後のつながりもなく、小さな曲が次々に演奏されているような印象を与えるのが「退屈」の原因だろう。この主題による変奏曲の創作はディアベリ自身の発案で、当時の音楽家50人に「提案」されたらしい。その中からアンコールでモーツァルトの次男とシューベルトの作品が演奏された。録音で聴いてよさがわからくてもライブで聴くと驚くほど素晴らしい音楽だったりすることはよくある。しかし「ディアベリ変奏曲」はどちらで聴いても退屈だ。退屈だということは飽きないということでもあるので、無人島に持って行くには最適の1曲かもしれない。
July 27, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMFアメリカ・アンサンブル イヴニング・ウィズ・ベートーヴェン
PMFヨーロッパ・アンサンブルはオール・モーツァルト・プログラムだった。PMFアメリカ・アンサンブルはオール・ベートーヴェン(26日、札幌コンサートホール大)。オーケストラの各セクションがひとりずつの教授陣を中心とした室内楽というと、編成上、曲目が限られる。過去のこのコンサートでも、シューベルトの八重奏曲やベートーヴェンの七重奏曲が繰り返し演奏されてきた。こうしたサロン音楽に毛のはえたような曲目は苦手で、大金を払って聴くようなものでもない。しかしそれではなぜ出かけることにしたかというと、PMFアメリカ・リサイタルシリーズを聴いて、このアメリカの一流オーケストラのプレーヤーたちに興味を持ったから。最安席1000円という入場料も後押しした。この日のプログラムは3曲。すべて作曲者20代のころの作品で、フルートとバイオリンとビオラのための「セレナーデ」、管楽八重奏曲、七重奏曲。アンコールに七重奏曲の第3楽章がリピートされた。演奏はすべて見事の一語に尽きる。ヨーロッパの演奏家たちと比べると陽性というか外向的な演奏。ダイナミックだが決して乱暴にならず、繊細なニュアンスも神経質にならない。特筆されるのは音程のよさ。曲にはさほど魅力がなくても、美しい音の美しいハーモニーを森林浴のように浴びるだけで、寿命がのびるような気がする。こうした音楽は「音楽浴」とでもいうべき態度で鑑賞すべきなのだろう。「セレナード」ではホスクルドソンのフルートの格調高い演奏が印象に残る。「八重奏曲」ではPMFオーケストラメンバーが4人加わったが、教授陣にまったくひけをとらない演奏だったのに驚いた。ただ、その中でもホルンのロバート・ワードの名人ぶりは際だっていた。後半の「七重奏曲」は、ディヴィッド・チャンのリードのもと、熱演が繰り広げられた。「オーケストラの基本は室内楽」といわれるが、メンバーがみな自発的に演奏し、しかもそれが個性のぶつかり合いにならず、共通の音楽イメージの創造にダイレクトに結びついていく、そうした光景はめったに見られるものではない。そうしたアンサンブルの理想が実現されていたが、コントラバスのハロルド・ロビンソンやチェロのラファエル・フィゲロア、バスーンのダニエル・マツカワといった低音部を支える人たちが強力だったことが成功の大きな原因だろう。ただの名人を集めてもこのように高度な音楽は生まれないものである。PMFアメリカの教授陣で、もしひとりだけ来年も聴きたい演奏家を選べと言われたら、ハロルド・ロビンソンだろうか。PMFには6回目の参加ということだが、来年以降も毎年来てほしいものだ。この日も客席はすいていた。おかげで最前列中央で「音楽浴」できた。PMFが初期の盛り上がりを取り戻す日は来るだろうか?来年の音楽監督がまだ決まっていないという「惨憺たる状況」はいつ解決されるのか。
July 26, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMFアメリカ・リサイタル2
24日のシリーズ1も7割程度と客席は寂しかったが、この日はさらに寂しい。おかげで最前列中央に、しかも両サイドにまったく人がいない状態で最高の音楽を堪能できた(25日、札幌コンサートホール小)。前日よりも空席が目立った理由はわからなくもない。何せ、知らない曲ばかりなのだ。知っている曲ばかり聴きたがる音楽ファンの悪癖、未来より過去に生きる人々のおかげで、今回もまた極上の音楽を優雅な気分で堪能できた。会場で会った音楽評論家は「空席がもったいない。ブラスバンドをやっているような中高生にぜひ聴かせたかった。主催者は招待してはどうか」と言っていたが、その意見には反対だ。学生割引を使うと学生は2000円で聴くことができる。それ以上の「若者優遇」は優遇ではなくスポイルだ。自分でコツコツ稼いだお金で聴くから真剣に聴く。70年代までの若者は、食費を切りつめて芝居や映画やコンサートに通った。そうして行くから身につくし実になるのだ。このコンサートシリーズは未来永劫、ガラガラであってほしい。11曲中、知っていたのはブラームスのピアノ曲「ラプソディ第1番」だけ。ほかの10曲は札幌で演奏されるのは初めてだろうと思う。ボーエンの「ファンタジー四重奏曲」は4つのヴィオラのための作品。この曲のみPMFオーケストラメンバーが参加。偶然だろうが、3人ともアジア系のファーストネームを持つ人たちで、第一ヴィオラをワシントン・ナショナル交響楽団首席のダニエル・フォスターが担当。哀愁を帯びた、ハーモニーの微妙な移り変わりが美しい曲。アーノルド・バックスやディーリアスの音楽に雰囲気が似ている。初めて聴いたがじゅうぶん楽しめた。ベックス「ヴェイディミーガム(バス・トロンボーンのための入門書)」は2010年に作られた曲だそうで、3つの部分からなる。モダンなハーモニーと変化に富む構成が見事で、特徴的な音型から魅力的な音楽が生まれていくさまが目で見えるような印象の曲。20分近い大曲を余裕さえ感じさせたメトロポリタン歌劇場管弦楽団首席奏者ポラードは神技。この曲でのピアノの山本真平のサポートはポラードに位負けしないくらい見事だった。コルグルス「4つのドラムとヴィオラのための変奏曲」は、編成から唯一の現代音楽風の作品を予想していた。4つのドラムの音程は曲ごとに変えられていたが、4つの音しか出せないというドラムの制約を逆に音楽創造に生かした、その創造力と発想力には圧倒された。決して奇ををてらった音楽ではなく、打楽器音楽特有のエキゾチズムへの逃避もない。非常に高度な前衛ジャズの即興のような対話も随所に見られ、間然するところのない20分だった。ヴィオラはフォスター、打楽器はボストン交響楽団首席ティモシー・ジェニスが担当。後半は前日と同じ山田亜希子のピアノソロで幕開け。ブラームスの「ラプソディ第1番」は、演奏は立派だったが、この日のプログラムの中では異質でとってつけたような印象を免れない。フィラデルフィア管弦楽団首席コントラバス奏者のハロルド・ロビンソンが演奏したのはボッテジーニの「エレジー」とフランソワ・ラバトの「スペイン頌歌」。豊かな響きで歌心たっぷりに演奏された「エレジー」もよかったが、ピチカートだけで演奏される「スペイン頌歌」は曲・演奏共に圧巻。激しさを秘めた瞑想的な音楽もさることながら、深い呼吸で、まるで即興演奏のような自在なロビンソンの演奏には痺れるような快感を味わった。会場も沸き、前日に続いて耳が痛くなるような歓声が飛んだ。その興奮がさめやらないうちに登場したのはサンフランシスコ交響楽団首席トランペット奏者のマーク・J・イノウエ。エネスコの「レジェンド」を演奏したが、スピード感のある音、正確無比のテクニックには脱帽。この人が世界一のトランペット奏者と紹介されたら、100人うち100人が納得するだろう。PMFアカデミー出身で、いまは教授陣の中心になっているファゴットのダニエル・マツカワ(フィラデルフィア管弦楽団首席)が演奏したのはルシエの「パッセージ」。乾いた感傷とでもいうべき魅力をたたえた作品。共感豊かに演奏され、短い曲にもかかわらず深い感動に誘われた。トリをつとめたのはPMF初参加のサンフランシスコ交響楽団首席ホルン奏者、ロバート・ワード。ベルグマンの「レ・ルトゥール」、ガベーユの「春のセレナード」、ポートの「レジェンド」という20世紀の作曲家の3作品を演奏。ホルンの名手はいろいろと聴いたきたつもりだが、今まで聴いてきたのはいったい何だったのかと思うくらいの腕前。これほどミスのない完璧なホルン演奏はありえないものと思っていたが、あり得たのだった。ホルンは最前列より、少し離れたところで響き全体を楽しみたい。翌日のPMFアメリカ アンサンブル演奏会にはこのワードも出演するので、きゅうきょ行くことにした。ひとつ、いい勉強をした。知っている曲より、知らない曲の多い演奏会の方が楽しめるということ。有名曲のだめな演奏に失望することは多いが、知らない曲なら失望のしようがない。というわけで、人とは逆に、知らない曲、知らない演奏家のコンサートに行くのを心がけることにした。ベックスの曲以外で伴奏をしたのは山田亜希子。少しピアノを鳴らしすぎる部分があったが、アンサンブルは完璧。ピアニストにありがちなひとりよがりが全くなく、PMFで重用されるのもわかる。
July 25, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMFアメリカ・リサイタル1
いったいどれくらいの数のコンサートが開かれているのだろうか。ジャズクラブのようなところを加えればジャズが圧倒的に多いだろうが、そうでなければクラシックのコンサートがいちばん多いにちがいない。ちょっと計算してみても、世界中で毎日千以上、年間では数十万回のコンサートが(少なめに見積もっても)開かれている。しかしそんな中でも、PMFヨーロッパとPMFアメリカのリサイタルシリーズほど素晴らしい音楽会は稀だ。なぜなら、世界の超一流奏者が入れ替わりで次々と演奏するコンサートは、PMFやタングルウッドのような大規模な教育音楽祭でなければ開催不可能だからだ。風邪のため先週のPMFヨーロッパ・リサイタルは欠席したので、PMFアメリカ・リサイタル1には前日から十分な休養をとって出かけた(24日、札幌コンサートホール小ホール)。当日でも最前列に空席がある。観客の多くはアカデミー生で、アカデミー生のホームステイ先のファミリーなども多く、普通のコンサートとは雰囲気が少しちがう。有料入場者は100人に満たないのではないだろうか。楽器学習者には黄金のような価値のあるコンサートだというのに、音大生の姿もない。でもそんなことはどうでもいい。これら極上の音楽は自分が楽しめばそれでいい。こういうのは行った者勝ち、聴いた者勝ちなのだ。最初はメトロポリタン歌劇場管弦楽団首席奏者、ステファン・ラグナー・ホスクルドソンの吹くバッハ「無伴奏フルートのためのパルティータ」。ホスクルドソンはアイスランド出身だそうだが、ドイツやフランスともちがう流麗なバッハにはやはりアングロサクソンの文化を感じる。ドイツ的な構成感を残しながら、華やかで流れのよい親しみやすいバッハ演奏は、インターナショナルな感性によるバッハとしては最上級。フルート奏者の中には、一流でもフルートの歌口から音が出ていると感じさせる人がいる。しかしホスクルドンは、楽器が全部鳴っている。歌口から入った空気がしっかりと管の中を通り、楽器全体を鳴らしているという印象がある。タンギングもていねいかつナイーブで、激しい部分でも決して荒々しくなく気品がある。各楽章がバラバラになることのない、緊張の糸が一本通った集中力も見事だが、「自分はバッハのこの曲をこう感じる」という信念がすべての音に感じられる。そしてそれが実に真摯でごまかしのない、純度の高い音楽になっている。次はクリーブランド管弦楽団の第2バイオリン首席、スティーブン・ローズでやはりバッハのソナタ作品番号1016。アメリカのオーケストラを聴くと、その音量に驚くことが多いが、ローズのバイオリンも実によく鳴っている。朗々と歌い、もってまわったところがない素直な音楽にはアメリカの音楽家の長所を感じる。前半の最後はメトロポリタン歌劇場管弦楽団の専属ハープ奏者、安楽真理子が登場。ヘンデルの「プレリュードとトッカータ」、サルゼードの「古代様式の主題による変奏曲」を演奏した。この演奏、特にサルゼードが当夜のハイライトだった。こんなに雄弁なハープ演奏を聴いたのは初めてかもしれない。どちらの曲でもまったく弛緩のない、音楽的密度の高い演奏が繰り広げられていく。ヘンデル作品では真摯で深い音楽が印象に残るが、その印象もさめないうちに始まったサルゼードは、難曲で名人芸も要求されるのに名人芸の存在をまったく感じさせない。音楽そのものに入り込んで一体化した地点から音が奏でられていくので、聴き手もまったく気を抜くことができない。冷房のきいたホールにもかかわらず、終わったときにはすっかり汗をかいてしまったし、会場の拍手は文字通り爆発的だった。今後、安楽真理子を聴く機会を決して逃すようなことはしないと固く決意したことである。後半はまずシカゴ交響楽団首席オーボエ奏者のユージン・イゾトフがテレマンの幻想曲から2曲を演奏。「軽い」オリジナル楽器のスタイルとは異なる伝統的なスタイルによる演奏だが、ソリスティックな吹き飛ばしはまったくなく、ごまかしのない自分の音楽をやっている。オーボエを吹いている、のではなく音楽をやっているのだ。次は22日に北広島の公演にも登場したメトロポリタン歌劇場管弦楽団コンサートマスターのデイヴィッド・チャンと、やはり首席奏者のラファエル・フィゲロアによるハルヴォルセン「ヘンデルの主題によるパッサカリア」。実はこの曲と彼らの演奏をもう一度聴きたいと思い、この曲目当てに来場したのだが、さらに音響のよいキタラ小ホール最前列で聴くのは至福のひとときだった。これは重音奏法を多用する曲で、後半にいくほど技巧的な難易度が高まっていく。超絶的な名人芸がぶつかり合うさまは壮絶だが、ここでも名人芸の存在を後景においやる誠実で真摯な音楽が圧倒的な感動を呼ぶ。会場の興奮も最高潮で、終わった瞬間の歓声は耳が痛くなるほど。山田亜希子がひくショパンの前奏曲「雨だれ」に続いて登場したのはメトロポリタン歌劇場管弦楽団首席トロンボーン奏者のデンソン・ポール・ポラード。グノーの「愛の音楽」を夢見るような美しさで演奏した。いちおう、古い時代から近代へと配慮されたプログラムだったが、後半のメーンにおかれたのはサン=サーンスのクラリネット・ソナタ。メトロポリタン歌劇場管弦楽団副首席奏者のジェシカ・フィリップ・リスキがが演奏。この人はPMFには初参加だそうだが、地味だが堅実な音楽をやる人。コロンビア大学で政治学を学んだ経歴もあるが、音楽一筋の人とはどこかちがう、思慮深さのようなものを演奏から感じた。最後はチャンのバイオリンと安楽真理子のハープで「タイスの瞑想曲」。終わってみればあっという間の2時間。
July 24, 2012
コメント(0)
-
旅の記憶-8-
このときの旅で持っていったのは「地球の歩き方ヨーロッパ」と「ヨーロッパ2000円の宿」というユースホステルのガイドブックだけだったので、ベルリンの詳しい地図や細かい観光名所は載っていなかった。そもそもベルリンという街には何の関心もなかったのでそれでよかったが、翌日は街を歩いてみた。適当に歩いていると、真ん中がかすかに盛り上がっている道路があった。その道路の向こう側に酒屋があるので、歩きながらビールでも飲もうと店に入ってみた。するとどうだろう。値段がびっくりするくらい安い。道路のこちら側の店と比べて、同じ商品が2~3割も安い。しかも道路の向こう側は家が何となくくすんでいる。それで気がついたのだが、その道路は、「壁」があったところなのだ。3年前にベルリンの壁は崩壊し、壁は削られてなくなっていたが、かすかにその名残があった。壁はなくなっても東西の差が残っていたのであり、不思議な感じがした。ベルリンには3泊するつもりで来た。小澤征爾の指揮するベルリン・フィルを3回聴こうと思ったのだ。しかし、2日聴いてじゅうぶんだと思ったので、3日目の夜はベルリン国立歌劇場に行くことにした。旧東ベルリン地区にある、旧東ドイツが国家的威信をかけて運営していた瀟洒なオペラハウスである。しかしここでも「東」に遭遇した。生まれてから一度も笑ったことがないのではないかと思える無機的な女をドイツではときどき見かけるが、このオペラハウスのチケット売り場の老婆と、マントを着た客席係の若い女は、そろってこうした「無機的無情女」だった。こういう人間がこの世にいるかと思うとぞっとするくらい、人間性そのものの欠落を感じる。どうもプレミア公演なので一般席の売り出しはないということのようだったが、不親切というより「気持ち」を感じないのだ。まごついている客はぼく以外にもいた。日本なら、きょうは一般公演ではないので申し訳ありませんが入場できませんと「気持ちのこもった」アナウンスがされるところだが、そういう「感情」を感じさせるものがまったくないのだ。これは融通のきかないドイツ人の民族性もあるだろうが、このオペラ・ハウスには「東」がまだ保存されていたということだろう。世の中はゆっくりとしか変わらないものなのだ。3泊目の同室者は高校生の二人組だった。朝起きると、二人のうち一人が好奇心を抑えがたいという感じで話しかけてきた。驚くほどへたな英語で、どこから来たかとか聞いてくる。日本から来たがミュンヘンに滞在していると話すと、ミュンヘンのオータムフェスタがどうのとしきりに話す。「酔っぱらい」という英語がどうしても思い出せないらしく、話がつまるが、言いたいことはわかった。酔っぱらってアホみたいになる人間がたくさん出る、と言いたいようだった。逆に、彼らの旅の予定を訊いてみた。すると、大学ノートを見せてくれた。そこには分刻みで旅の予定が書き込まれていたが、何でも計画しなければ気の済まないドイツ人気質は若い世代も変わらないのかと呆れた。天気だって、交通機関の事情だってどうなるかわからないのに、せっせと勤勉に旅をする姿は日本人とどこか似ている。高校時代、船でしか行けないユースホステルに行こうとしたことがあった。しかし、港に着いてみると高波で欠航だという。バスで行く手もあったが、そうすると海岸を4時間以上も歩かなければならない。そうした長時間の歩行に抵抗のある同行者がいたので困ってしまった。常にセカンドチョイスを考えておくこと、予定を立てすぎるのは賢明ではないということを学んだ。レイルパスの関係で電車には夜7時過ぎに乗ることにしていたから、出発の日は時間があった。宮殿を見たり一通りの観光をして、それでも時間があったので博物館と美術館に行くことにした。ルーベンスの絵があるというので見てみたいと思ったのである。日本の感覚だと1~2時間もあれば余裕で見られるだろうと思ったが、途方もなく広い。全部見ていたら何日もかかりそうなくらいの展示物がある。「見る」「集める」ということに対するヨーロッパ人の執着というか執念を思い知ったはじめての体験だった。部屋から部屋へ走りながら移動しているうち、絵の印象などすっかり忘れてしまった。ヨーロッパの美術館や博物館で大事なのは、どの部屋をカットするか、どの展示物をカットするかを事前に決めておくことだ。あれもこれもと見ていると、肝心の展示物にたどり着く前に疲弊してしまう。ミュンヘンに戻る途中で寄り道をした。ロマンティック街道の宝石と言われる街、ローテンブルグに寄ることにしたのである。「危険」と言われる南行の列車に乗り込むと、博物館疲れですぐ寝込んでしまった。朝起きると、オーストラリア人とおぼしき青年が青ざめた顔して通路に立っていた。寝ている間にウェストポーチの中身を全部とられたという。パスポートなど貴重品が入っていたらしく、車掌には話したが打つ手がなく呆然としていた。まったく気がつかなかったというから、もしかすると催眠ガス強盗にやられたのかもしれない。気の毒だったのでポケットにあった10マルク札を渡したが、彼のおかげで泥棒にあわずに済んだのかもしれないので後払いの保険料のようなものだ。ローテンブルグはたしかに美しい街だった。メルヘンチックな旧市街には小さな店や雰囲気のあるこぢんまりとしたペンションやガストホフが趣味よく立ち並んでいる。駅で自転車を借りられたので短時間でくまなく回ることができた。ロマンティック街道のツァーはたくさんあるが、自転車で縦走するといいだろうと思った。古風な町並みの中にとけこんだ地味で質素だが趣味のいいペンションを眺めていると、いかにも若いカップル向けな日本のペンション村の軽薄さを思い知らされた。嫌味でキザな言い方になるが、ホンモノを知ってしまうとキッチュなニセモノには興味を持てなくなるのだ。だいたい、高原にビーチサイドが似合うようなペンションを作ってどうしようというのだ。いくつかのペンションを見てみたが、だいたい、シングルだと3000円、二人以上だとひとり2000円くらいで泊まれるようだった。左側通行の交通ルールを見てわかるように、戦前の日本はヨーロッパの文化を取り入れていた。戦後取り入れたのは戦勝国アメリカの文化だ。アメリカ文化の本質とは大量生産の大量消費であり、日本人を大きく変えたのはアメリカ文化だったことが、このほんとうに宝石のように美しい街に来てみると痛感される。ローテンブルグで驚いたのは日本人ツァー客の多さ。うんざりしたが、向こうもけたたましいブレーキ音をたてて走り回るぼくの姿を見てなんだあの日本人はとうんざりしたにちがいない。ドイツの自転車は、ペダルを逆回転させることでブレーキがきくようになっている。そうとは知らずに、ハンドルについているブレーキを多用したものだから、キーキーとやたらにうるさかったのだった。このあとミュンヘンに戻り、郊外にあるダッハウという街に行った。ダッハウもローテンブルグに似た美しい街である。しかしダッハウにはナチスの強制収容所があり、多くの政治犯やユダヤ人がガス室で殺された。ローテンブルグやダッハウのような美しい街を作り上げたドイツ人、そのイメージと大量虐殺がどうしても結びつかない。もしかすると、こんなにも美しい街を作り上げる、その美的感性は大量虐殺を生む選良意識と一体のものではないのか、と疑ってみることもできる。美しいものを見て美しいと素直に感動できない世界に生きるのは不幸なことだが、美しいものに無邪気に感動するだけの人間は、再び大量虐殺に加担していくことになるだろう。
July 23, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMFアンサンブル北広島公演
7月22日はPMFアンサンブル演奏会が道内5カ所で開催された。いずれも主会場である札幌からは100キロ圏内。その5つのうち、札幌に最も近い北広島で行われたコンサートに行ってみた(北広島市芸術文化ホール)。PMF出身者はベルリン・フィルなど世界の一流オーケストラで活躍している。一般の音楽ファンが群がる国際コンクール入賞を経てソリストといった道を歩む人とは異なるので、彼らの演奏を聴く機会はほとんどない。オーケストラに就職してしまえばなおさらだ。しかし、PMFのオーディションに合格すること自体、世界で通用する実力であることを認められたのと同様であり、そうした若者たちのアンサンブルが悪かろうはずがない。指導陣も超一流である。そうしたことを重々承知した上で出かけたのだが、予想をはるかに超えるレヴェルの高い演奏が続き驚かされた。前半はニールセンの木管五重奏曲とブラームスの弦楽六重奏曲第1番の前半2楽章。ニールセンは演奏時間26分の大曲。牧歌的な雰囲気の佳曲だが、ニールセン特有の個性的な音型があちこちに出てくる。演奏はニールセンのこうした音楽の特徴を明快に表現したもので、その開放的な演奏には、会期後半を指導するアメリカの教授陣たちの影響が感じられた。中ではカロリーヌ・マルシェッソーという女性フルート奏者がフランス風の音色で地味な響きに明るさと柔らかさを加えていたのが印象的。ブラームスの弦楽六重奏曲第1番は、ブラームスの最高傑作ではないかと思っている曲。全曲が聴けるものと期待して来たが、前半だけというので落胆した。しかし、この演奏では二人の優れた演奏者を知ることができた。ビオラのダニエル・キムとチェロの荒井結子である。100人超のPMF参加者を毎年のように眺めていて、優れた演奏家は顔でわかると思うようになった。どんなジャンルでも、優れた人間からは黙っていてもオーラが出ていてすぐわかるものだ。PMF参加者はみな若いので若者特有の明るく陽気な「気」が出ている。そんな中でも、つらがまえがしっかりしていて、しかも表情が豊かな人というのはそう多くない。各パートに数人である。見ていると、そうした学生が首席や副首席、いずれにしても前の方に座ることが多い。六人全員が素晴らしかったのだが、荒井結子は突出していた。誰に習った人なのか、師匠を知りたいと思ったほどだ。第2チェロ、つまりこの特異な編成の最低音部分を担当したが、リズム感が抜群に優れている。リズム感とは規則正しく拍子を刻む能力のことではなく、音量の微細な変化で音楽に躍動感や落ち着きを与える与える才能のことだが、彼女は完璧だった。機敏さといいい音楽の先を読む力といい、これほどのアンサンブル力のある音楽家にはそう出会えるものではない。彼女に触発されたのか、第1楽章は実に生気に富んでいたし、第2楽章の少し感傷的な音楽は崇高な美にまで高められていた。ビオラのダニエル・キムは、荒井結子の峻厳な音楽に比べるとたおやかで叙情的な音楽性が素晴らしい。西洋人音楽家にしばしば感じる「エゴ」を彼の演奏から感じることはない。映画俳優のような甘いマスクの青年だが、少しアジア系の血が入っているように見える。彼なら武満徹の「ア・ストリングス・アラウンド・オータム」のような曲を見事に演奏できそうだ。こうした優れた奏者の発見に「興奮」して迎えた後半。PMFアメリカの教授二人、バイオリンのデイヴィッド・チャンとチェロのラファエル・フィゲロア(二人ともメトロポリタン歌劇場管弦楽団によるハルヴォルセン「ヘンデルの主題によるパッサカリア」には絶賛以外の言葉が見つからない。PMFアカデミー生の演奏は、優れていてもどこか呼吸が浅い。フレーズ感もやや短く感じる。というのは、この二人の演奏を聴いたからそう思うのだが、それほど、この二人の演奏は白熱した時間が長く続く。8分ほどの曲だが、一瞬の弛緩もなくひとつながりの音楽として聴かせた彼らの力量、そしてアメリカの音楽家の底力には打ちのめされるほど圧倒された。最後のドヴォルジャークの弦楽四重奏曲「アメリカ」は、演奏としてはこの日の中では最低だった。第1ヴァイオリンのアイファ・ジャンとヴィオラのエリカ・ブシュチュウカは優れた奏者ではあるものの、「自分のパートをひいている」というだけで、他の奏者の音楽と対話しようという姿勢が乏しい。いや、乏しくはないのだが、第2ヴァイオリンの佐藤奏やチェロの吉岡知広に比べると少ない。そのため、どこか音楽が無機的に響き瞬間ができてしまう。後半では、この日本人奏者ふたりが驚きに値する「発見」だった。この両名ともコンクールで入賞していたり本選にノミネートされたりしたことのある経歴の持ち主のようで、すでに立派な自分の音楽を持っている。特に佐藤奏の機敏さには瞠目させられた。吉岡知広は日本のオーケストラならすぐにフォアシュピーラーをつとめられるのではないだろうか。ダニエル・キム、荒井結子、佐藤奏、そして吉岡知広。クラシック音楽は死んだと思っていたが、死んだのは大指揮者や名歌手が不在のオペラやオーケストラの世界のことであって、こうした無名の若手たちの中にしっかりと生きている。コンサート通いは、こうした発見と遭遇があるからやめられない。
July 22, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMFオーケストラ演奏会
20日と21日に、ほぼ同内容のPMFオーケストラ演奏会があった。ちがうのは指揮者で、20日はファビオ・ルイジが、21日はPMFコンダクティング・アカデミーに参加した4人の指揮者が指揮をした点。2日目を聴いて、両日聞き比べるべきだったと後悔した。というのは、PMFヴォーカルアカデミーの出演者が、それぞれ一曲しか歌わなかったから。二日共聴けば、ほんとうの実力がさらにわかっただろうし、ルイジのようなベテランと駆け出しの若手指揮者たちのちがいもわかって面白かったと思う。プログラムはオペラ・ガラで、実質的にはPMFヴォーカルアカデミー演奏会といえる内容。モーツァルト、ヴェルディ、ロッシーニ、プッチーニの有名なアリアに、オペラの序曲や間奏曲をはさんだ構成。このコンサートも最安席は1000円。指揮者は4人ともなかなかの才能の持ち主と見た。山崎隆之は棒のテクニックは抜群。端正な音楽作りに日本人指揮者の長所を感じる。カナート・オマノフというアジア系の風貌の指揮者は、どこかゲルギエフの指揮を思い出させる。オペラ指揮者の適性を感じさせる歌心豊かな指揮が個性的。女性のカリーナ・カネラキスと、まだ少年のような風貌のイリアス・グランディは舞台度胸がさすが。第一回のPMFに参加した佐渡裕ら3人の指揮者に遜色のない実力の持ち主ばかりだが、中ではカナート・オマノフのような個性は注目に値する。好悪は別にして、自分の信じる音楽に没入するような音楽家は珍しくなったからだ。出演した8人の歌手では、前半と後半のトリをつとめた二人の日本人、バリトンの後藤春馬とソプラノの中村真紀が優れていた。マスコミ風に書くなら「健闘目立った日本人参加者」といったところだが、すぐにでも国際的なオペラハウスの舞台に立てる実力の持ち主。もう一人の日本人参加者、バリトンの大野浩司にも将来性を感じた。他の出演者も、60代のミレッラ・フレー二やニコライ・ギャウロフより豊かで機敏な演奏を聴かせていた。これくらいのコンサートが1000円や2000円で聴けるなら毎日でも行きたいくらいだ、というか行くだろう(21日、札幌コンサートホール、マチネー)。
July 21, 2012
コメント(0)
-
こんな映画を観た~タイム
SF映画にはいくつかのタイプがある。現代社会や現代文明を鋭く風刺するSF映画というのはあんがい多い(そう気づかない人も多いが)。この「タイム」(原題はIN TIME)は、そういうタイプの優れたSF映画。見終わってしばらくは「時間」と「お金」に対する感覚が変わってしまったほどだ。この映画では、遺伝子操作で25歳になると成長(老化)が止まり、残りの寿命は23時間という未来社会が描かれる。この社会での通貨は「時間」で、何を買うにも、何をするにも「時間」で払うし賃金は「時間」で受け取る。上流階級は永遠に生きることができ、貧困層は時間(お金)の工面に失敗すると死んでいく。ギャングは警察(時間監視庁)と結託して時間泥棒も行っていく。労働者階級の剰余価値を資本家階級が搾取によって奪い取る資本主義社会の本質を明快に描いている。資本主義そのものを「時間」という概念を導入することによって風刺したこの映画のアイデアは秀逸だ。両親の仇を討とうとする青年と、富裕層の少女が恋に落ち、二人で少女の親が経営する金融機関を襲撃してはそのお金(時間)を貧しい人たちにばらまいていくが、その間に時間監視庁のベテラン刑事とのやりとりがあったり、ギャングとの対決もあり、まったく弛緩のない109分が続く。ただ、義賊が盗んだものをばらまいたところで、こうした社会の矛盾はなくならない。かといって資本家を打倒する革命映画にしてしまってはステレオタイプに陥ってしまう。娯楽映画としてはこれでいいかもしれないが、もう少し含蓄のあるラストというか展開にできなかったかという思いは残る。時は金なりとはよく言った。時を盗む者は金を盗む者に等しい。逆に、金を浪費する者は時を浪費するに等しい。学生時代、時給でアルバイトをしていたときの感覚、つまり、買い物などをするときに、「これが時給3時間分か、その価値はないな」などと考えていたのを思い出した。結末や展開には残念な部分はあるが、映画として抜群に面白いし、アイデアがいい。激しいカーチェイスなども少なく、二人の主人公はひたすら走って逃げる。制作費をかけなくても面白い映画を作ることができるという好例だと思う。
July 20, 2012
コメント(0)
-
こんな映画を観た~マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙
マーガレット・サッチャーの伝記映画など、蠍座で上映するのでなければ絶対に観なかった。しかし、これがなかなか興味深い作品に仕上がっていた。映画を観るばあいにいちばん大切なのは映画館選びである。亡き夫の記憶にとりつかれた日々を送る老サッチャーの日常に、過去をフラッシュバックさせていくような映画の作り方が効果的。主婦の会話のように時系列ダラダラ進むのではなく、節目節目の過去に飛ぶ。メリル・ストリープの迫真の演技以外にさほど観るべきところのないこの映画を退屈せずに観ていられた。この映画はどちらかというとサッチャーに同情的な立場で作られているように思う。政策というより、人気とりに終始する政治家に比べて「強い信念を持つ」サッチャーのような政治家のあり方を称揚しているように感じる。映画でもサッチャーをして言わせているが、大事なのは正しさであって国民の支持ではない。これは政策だけでなくあらゆる事柄に通じる普遍的な真理である。もう一つ、サッチャーが父から学んだという言葉が印象に残った。「気持ち、気持ちなんてどうでもいい。大事なのは考え。考えが言葉になり、言葉は行動となる。それはやがて習慣になってその人の人格を作る。 そして人格はその人の運命となる。考えが人を創る」その通りだ。運命は自分の考えが招いたことであり、誰かに転嫁して済む話ではない。サッチャーがすすめた経済政策の多くは、いまとなっては正しさが証明されていると考える。サッチャー以後の揺り戻しで、イギリスは無法者が暴動を起こすような社会になってしまった。食料品店の娘という、階級社会イギリスでは低い階級の出身であったことは初めて知ったが、中小企業の繁栄とバランスシートを重視する姿勢はこうした出自によるものだろう。「幸せな時間」のあとで観たので、人間の「老い」や人生の結末についても考えさせられた。監督のねらいも少しはそこにあったと思う。よく練られたムダのない脚本、イギリス映画に特徴的なほどよいテンポ、そして考えさせられる言葉の数々・・・メリル・ストリープの迫真の演技あってこそだが、こうした美点が集結した佳作といえる映画だった。
July 19, 2012
コメント(0)
-
こんな映画を観た~幸せな時間
この映画は制作過程が面白い。というか、こういう制作過程でなければ作ることのできなかった、非常にユニークな映画になっている。学生の武井彩乃という人が自分の祖父母をうつした5年分の録画テープを、友人の映画作家・横山善太が72分のドキュメンタリー映画に編集したものらしい。ハンディタイプのビデオカメラで撮った私的な録画。それが編集でここまで「見せる」映画になるというのが驚きあり、身内の人間ならではの優しい映像にどこか救われる。映画は普通の老夫婦の日常を撮した前半と、祖母が認知症を発症してからの後半からなっている。つまり、前半で「幸せな時間」が、後半では「不幸せな時間」が撮されている。認知症になる前となった後の変化は、身近に体験したことのない人はかなり衝撃的だろう。メッセージ性のある映画ではなく、淡々とした日常を撮しただけなので、まだらぼけの様相を呈しているこの祖母の姿に、未来の自分を重ねる人は多いかもしれないし、醜いものは観たくないと目をそむける人もいるかもしれない。だがこういう映画は、自分の身や家族にひきつけて観るべきだ。「幸せな時間」がいかに大切か、それは逆に「不幸せな時間」を経てからでないと決してわからないからだ。そして「不幸せな時間」から「幸せな時間」に戻ることはもうできない。老夫婦の妻が認知症になり、夫ががんで先に死んでしまう。ありふれた話であり、そうした話はよく聞く。しかし、映像で観ると、50年におよぶ夫婦の生活、ひとりの人生の重みに慄然としてしまう。辛い映画だが、観てよかったというか、気が進まないのに観るという決断をしたのは正しかった。人はいつか死ぬ。人間はそれをつかの間忘れてのんきに生きている。しかしその冷厳な事実を思い出させてくれるのが芸術の力だと思うが、ドキュメンタリー映像のそのストレートな力には粛然となる。いまビデオカメラは所有していないが、こういう使い方もあるのかと思うと、また手に入れてみようという気になる。
July 18, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~ファビオ・ルイジ指揮PMFオーケストラ
9日夜に発熱しこの週のPMFコンサートに行けなかったのはかえすがえすも残念だ。特に東京カルテットの解散記念コンサート(13日)を逃したのは痛恨のきわみ。それでも、瀕死の身でありながら来日し第一回のPMFで空前の名演をのこしたバーンスタインの恩に報いるべく、重い体をひきずって出かけた。曲目はストラヴィンスキーのペトルーシュカ(1947年版)とチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」(14日、札幌コンサートホール、マチネー)。ポピュラーな、しかもバーンスタインが名演をのこしている2曲にもかかわらず、客席の入りは7割未満。ルイジの人気のなさを表しているが、それがルイジのせいなのか、札幌の聴衆がミーハー趣味なのかはよくわからない。たぶん両方なのだろう。1991年以降、PMFの最も優れた音楽監督はルイジだと思う。もちろん、ハイティンクやムーティといった指揮者もいたが、トレーナーとしての手腕と音楽家としての力量を総合的に見たときルイジに軍配があがる。ハイティンクやムーティはあくまで客演指揮者に過ぎなかった。しかしそれではなぜ現在、指揮者が得られる世界最高のポストを手にしている彼の人気がいまひとつなのだろうか。それは、たとえばバーンスタインならマーラーやシューマン、カラヤンならワーグナー、小澤征爾ならラヴェルやベルリオーズといった、ルイジでなくては、というレパートリーの不在が原因だろうと思う。また、巨匠性もいささか不足している。そんなわけで、この日のコンサートは、ルイジの長所と欠点を同時に感じさせるものになった。「ペトルーシュカ」は、実は「春の祭典」よりも演奏が難しい。指揮も難しい。オーケストラ泣かせの曲である。へたをすると、異なる音楽をただ継ぎ接ぎしただけのような演奏になってしまう。アンサンブルに気をとられすぎるとつまらない演奏になる。しかしルイジの統率は見事でPMFオーケストラも立派だった。この曲の諧謔味やグロテスク一歩手前のおどろおどろしさも、ちょうどいいバランスで表現されていた。名手ぞろいとはいえオーケストラ経験の少ない人たちをまとめあげる力量はさすがで、メトロポリタン歌劇場首席指揮者だけのことはある。後半の「悲愴」も立派な演奏ではあった。PMFヨーロッパの指導陣が加わったせいもあるが、響きが格段にまとまっていた。トレーナーとしての手腕はそうした響きを一聴しただけで明らかだ。この曲はマルティノンに代表されるスタイリッシュな演奏と、バーンスタインに代表されるユダヤ的な情緒纏綿な演奏の両極端の解釈がある。多くの指揮者はトスカニーニの厳しいスタイルをベースにした演奏をする。どんな解釈にもそれぞれの良さがあり、一概にこれがベストだとは言えない。しかし、一つだけはっきりしているのは、この曲は交響曲の歴史上、初めて両端楽章が静かにゆっくりと終わる曲であるということである。死と絶望を主題とした初めての交響曲であり、ベートーヴェンの第5交響曲に典型な、苦悩や闘争を通して勝利をかちとる音楽ではない。マーラーがあの交響曲第9番で「悲愴」と同じ構成を踏襲しているのは偶然ではないだろう。そうしたことから導き出されるのは、この曲を「音楽的に美しく」演奏することよりも、聴く者をして絶望と恐怖のどん底に突き落とすことの大事さだ。トスカニーニとバーンスタインの演奏は、スタイルは正反対といえるほどちがうが、その点において共通している。映画「メランコリア」ではないが、絶望を知る者だけが魂を救済できるのだ。ルイジの演奏は手練手管がなく、ごく正統的だ。第一楽章の213小節でのリタルダンド、第3楽章305小節からのディミニエンド=クレッシェンドなどは実に自然で音楽的な生理にかなっている。しかしチャイコフスキーはスコアにそういう指示を書いてはいない(自筆譜を参照したわけではないが)。そのどちらの部分も、あえて無表情に機械的に演奏することで非情さが生まれる。だから「音楽的に美しく人間的な呼吸の生理に合っている」ルイジの演奏解釈は間違っていると思う。神は細部に宿るので、こういう人為的な「自然さ」は致命傷となる。優れた指揮者の条件にはオペラの経験が必要とされる。しかしオペラ指揮者の長所がオーケストラ指揮においては短所に転じることもある。ルイジも決して若いという年齢ではない。彼の年齢ですでに巨匠性を獲得していた多くの指揮者を思い起こすとき、イタリア版サヴァリッシュのような指揮者で終わる懸念なしとしない。これまでに聴いた数十回のこの曲の生演奏ではベストに思えるこの演奏も、幾多の巨匠たちの名演の前では影が薄く、10年後には聴いたことすら忘れてしまっているだろう。
July 15, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~PMFヨーロッパ・アンサンブル演奏会 イヴニング・ウィズ・モーツァルト
PMFの前半を指導するヨーロッパの一流オーケストラ・メンバーを中心とした室内楽コンサート。前日に聴いたアンドレア・バケッティがあまりに素晴らしかったので急きょ行くことにした。これだけの出演者で最安席1000円の入場料はヨーロッパよりも安い。金管アンサンブルによる「魔笛」序曲と「夜の女王のアリア」でスタート。金管アンサンブルのような華やかなサウンドでコンサートが始まる趣向は好ましい。日常から非日常への切り替えが、最初の数秒でスムースにできるからだ。やけに上手なトランペットだと思ったらベルリン・フィルのタマーシュ・ヴェレンツェイだった。柔らかい音色で吼えないホルンだなと思ったらシュターツカペレ・ドレスデンのロベルト・ラングバインだった。要所をしっかり決めるトロンボーンだなと思ったらドレスデンのニコラ・ノードだった。これら名手とひけをとらないPMFメンバーの力量もたいしたものだが、やはり細部のあらは目立った。続く「フルートとハープの協奏曲」では、前日の「英雄」でのスター・プレーヤーだったカール・ハインツ・シュッツと、シュターツカペレ・ドレスデンのアストリッド・フォン・ブルックがソリスト。指揮者なしでの演奏。オーケストラにはやはりPMFヨーロッパ指導陣がちらほら。以前、シュターツカペレ・ドレスデンを聴いたとき、ハープ奏者の音楽性に驚嘆したことがあった。それで期待もしていたのだが、ややソリスティックな表現に走りがちのシュッツとアンサンブル重視のブルックでは音楽的に相性がいまいちで、標準的なできというべきか。アンサンブルの精度も十分ではなく、楽しむ分に不足はないが、この曲の天国的な美しさ、美しさの奥に感じられる明るい哀しさのようなものを感じ取ることはできなかった。後半はいよいよバケッティの登場。「木管とピアノのための五重奏曲」と「ピアノ四重奏曲第2番」をPMFヨーロッパのソリストたちと競演。ウィーン響とシュターツカペレ・ドレスデンのメンバーである。そういうメンバーだったせいか、大ホールでの演奏にもかかわらず、家庭での親密な会話のような暖かみのあるモーツァルト演奏が続いた。とくに弦楽奏者にそうした志向を感じたが、聴き手に訴えかけるというより、聴き手の耳を引きつけるような表現にヨーロッパの音楽家、特にドイツ・オーストリア圏の音楽家ならではの良さを感じた。バケッティは協奏曲よりもさらに見事だった。スコアの中の重要な音をさりげなく目立たせ、後景に退くべきところは退く。そうすることによって音楽に奥行きと立体感が生まれる。モーツァルト自身が生き返って演奏してもこうはできないだろうというくらい、楽譜を対象化した上で消化している。一度聴けばもうじゅうぶん、という演奏家がほとんどの中、バケッティの演奏、特に室内楽のそれは、知的にエキサイティングでもあり、いつまでも聴いていたいと思わせる。「木管とピアノのための五重奏曲」は、モーツァルトの室内楽の中でも傑作の一つだと思うが演奏される機会は少ない。ドレスデン・シュターツカペレの超美人オーボエ奏者セリーヌ・モネをガン見しながらバケッティのピアノを聴く。右脳は陶酔しつつ左脳が明晰に覚醒していく、こんな体験をしたのは初めてかもしれない。
July 9, 2012
コメント(0)
-
こんなコンサートに行った~イェンセン指揮PMFオーケストラ演奏会
23回目のPMFが始まった。去年のPMF参加者のレベルは低かった。今年はどうかと危ぶまれたが、この日の演奏を聴く限り過去の平均的なレベルまで回復したようだ。やはり、去年は震災と原発事故の影響が大きかったのだろう。今年はノルウェーの若手指揮者、エイヴィン・グルベルグ・イェンセンが登場。ベルリン・フィルを指揮したこともある俊英ということなので期待した(7月8日、札幌コンサートホール)。バーンスタインの「キャンディード」序曲はいささか生真面目で華やかさや面白味にかける演奏。リズムが重い。資質的にこの指揮者にはバーンスタインだけでなくアメリカの音楽は合わないのではと思う。続くモーツァルト(ピアノ協奏曲第17番)も平板。もっと室内楽的にのびのびとオーケストラを開放的に演奏させる方がいいと思った。しかしソリストのアンドレア・バケッティの演奏には度肝をぬかれた。モーツァルトで度肝をぬかれるというのはいささか誤解を招く言い方だが、たとえて言えば国際コンクールの入賞者などにはまったく不可能な演奏。自己顕示やけれんが全くなく、ひたすら音楽が要求する表現に忠実。ピアノがときおりチェンバロやエオリアンハープのような響きをたてるのにも驚いた。冒頭こそ2拍早く飛び出すという大きなミスをしたが、そういうキズがまったく気にならない感興豊かな演奏。このピアニスト、軽薄なマスコミ風に呼ぶなら、現代のグレン・グールドといっていい資質を持っているように思う。イタリア人にしては小柄で、大ホールでロマン派のコンチェルトをバリバリと弾くタイプではないが、これほど楽譜を深く読むこむことのできる音楽家はヨーロッパといえども少ないのではと思う。アンコールで弾いたスカルラッティのソナタイ長調の、最初の右手で弾く下降音階の4つの音の何と素朴だったこと。厚化粧というか板金化粧のような演奏が流行する中、音楽の地肌を根気よく磨いて輝いた素肌の美しさには耳が洗われる思い。まるでチェンバロのような響きがした。アンドレア・バケッティ。年齢不詳だが小柄なので20代にも、40歳くらいにも見える。いずれにしてもこういう演奏家はヨーロッパではきちんと評価されていくものなので、ブレイクしてギャラと入場料が跳ね上がらないうちにできるだけ聴いておくべきだ。後半はベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」。この曲ではオーケストラの響きががらっと変わった。やけに上手な首席フルートだなと思ったらウィーン・フィル首席のシュッツだったが、要所にこうしたメンバーが座るだけで世界の一流オーケストラに遜色ない響きになるから驚きだ。演奏はピリオド奏法による軽いベートーヴェンとは対極にある伝統的なスタイルの演奏。ドイツ的ながっしりとした構えの、それでいて躍動感ある演奏で、久しぶりに「立派なベートーヴェンを聴いた」という印象。この「英雄」は去年、ウィーン・フィル定期で聴いた曲だが、フィナーレのソロをシュルツは外しまくっていた。一方、シュッツはそつなく演奏し(少し転んだが)、実力の違いを見せつけた。「英雄」には何カ所かキメのポイントがある。最大のものは第一楽章のクライマックス。最高音が半音で激突する、あの部分。第二楽章の葬送行進曲でも、ティンパニが「運命」のリズムを発狂したかのように連打する部分があり、あの高揚はベートーヴェンの作品中でも群をぬく。そうした部分をきちんと意識して対象化した演奏とは言い難かったが、輝かしく力感に満ちた演奏にはバスチーユ蜂起からブリュメール18日にいたるフランス革命の混沌やパッションと共通するものを感じたから、この演奏は成功といえるだろう。ルンペン・プロレタリアートとブルジョアジーと国王派が血みどろの戦いを繰り広げたあのフランス革命を音楽で表現するとこの曲になる。音は血しぶきとなって聴き手に降り注ぎ、数え切れない死体の上に青々とした緑が生い茂っていく。
July 8, 2012
コメント(0)
-
こんな映画を観た~メランコリア
この映画について、蠍座の田中支配人はこう書いている。「オープニングの音楽と映像美にまず魂をもっていかれた。そしてラストシーンに鳥肌が立った。こういうのが出現するからわたしは映画を見ることをやめられない」その通りだった。ラース・フォン・トリアー監督は初期の「奇跡の海」を見て、この監督の作品は二度と観るまいと思っていたのだが、「ダンサー・イン・ザ・ダーク」で評価を変えた。しかし「アンチクライスト」を観る勇気はなかった。本作もかなり迷ったが、田中支配人の評価を信じてよかった。唯一無二の境地に達した映画で、大衆的な人気とは無縁だろうが、ヨーロッパ映画のひとつの到達点として永遠に記憶されるべき映画だ。この映画を観て「奇跡の海」に対する評価さえ変わってしまったくらいだ。人間の魂は何によって救済されるのかというのがこの監督の生涯をかけたテーマだということがわかったからだ。オープニングの音楽はワーグナーで、全編にわたって使われている。あれは「トリスタンとイゾルデ」だったと思う。音楽同様、オープニングの映像自体は幻想的なもの。映画の本編とは無関係に思えたが、きっと関係があるにちがいないと思って集中して見ていたら本編の内容を見事に暗示するものだった。「トリスタンとイゾルデ」を聴くときにさえ、もうこの映画と切り離しては聴くことができないと思えるほどのインパクトのあるオープニングである。もし地球滅亡のときが来たなら、世界のすべてのオーケストラはこの曲を演奏し、すべての放送局はこの音楽を流すべきではないだろうか。人類はこの音楽に包まれながら終末を迎えるべきであり、絶望やカルト宗教に逃避してはならないのだ。映画は前半と後半にわかれた二部構成。前半は、結婚式当日に奇矯な行動をとる美人の妹と分別のあるさほど美人ではない姉の対比が描かれる。描かれる、というのは全体を観た後でそう感じるのであって、その場で観ているときは、ひたすら躁鬱病か統合失調症としか思えない妹の奇矯な行動に登場人物同様、観ているこちらも翻弄される。メランコリアという大惑星の衝突によって地球が滅亡する後半では、この姉と妹の関係が逆転する。狼狽し右往左往する姉とは対称的に、躁鬱病の妹は冷静さを保つ。絶望を知らない者(姉)は危機に際して精神の安定を保つことができない。一方、絶望を知る者(妹)はそのときを最も美しいやり方で迎える。このラストほど力強く美しい、逆説的な人間精神への讃歌は、あらゆる芸術を俯瞰しても皆無である。トリアー監督は、正常な人間は実はみな狂人であることをこの映画で証明してみせた。トリアー監督自身、鬱病からの回復者だそうだが、狂気を知る者だけが人間の魂を救済することができる、あるいは狂気こそが魂の救済なのだという深遠なテーマをこのラストで文字通り爆発的に表現している。感動的、などという言葉が空々しくも軽々しく感じられるラストだった。地球滅亡という「絶望の極北」を描いたあとトリアー監督はどこへ向かうのか。間違いなく映画の最前衛、最前線にいるデンマークのこの異能の人から目を離してはいけない。
July 6, 2012
コメント(0)
-
こんな映画を観た~LOFT 完全なる嘘
父親とキャッチボールをしたことのない女性には映画「フィールド・オブ・ドリームス」の良さはわからないだろう。また、設定や題材だけで嫌ったり否定する人も多いから、5人の男が「秘密の隠れ部屋」を共有するというこの映画は、そうした設定だけで言下に「くだらない」と色眼鏡で見る女性は多いにちがいない。しかし、これは紛れもなくサスペンス映画として一級であり、映像・脚本・構成・キャスティングなどどれをとってもレベルが高い。ベルギー映画をリメイクしたオランダ映画だそうだが、蠍座のような映画館で上映されるのでなければ知らずに終わったと思うと非常に得をした気分になる。みなからの信頼の厚い建築家のよびかけで、5人の男が新築マンションの最上階にロフトルームを共有する。ほとんどは妻帯者。彼らはそこで秘密の情事を楽しんでいた。しかし、ある朝その部屋で一人の女が死んでいた。部屋の鍵を持っているのは5人だけで、必ずその中に犯人がいる。5人は集まってお互いのアリバイを確かめながら犯人を探していく。誰が犯人だったかを推理で当てることのできる人はいないと断言できるほど、各人の秘密や嘘が絡まって、こみいった事情がさらにわけがわからなくなっていく。断片的な会話の、意味の含有率の高さに圧倒される。女性にもてない男の悲哀、女の残酷さやずるさも上手に描かれている。いちばん犯人らしくない男が実は犯人だがほんとうの殺人犯はいちばん犯人らしい男だった、しかし殺すつもりはまったくなかった誤認殺人だったというのが結末。この映画が「浮気はダメ」の教訓映画にならなかったのは、5人の男のうち、娼婦をほんとうに愛した精神科医とその娼婦の再会シーンがラストにおかれているから。誰もがその再会を祝福したくなるわけではないだろうが、いい映画を題材だけで否定するバカを識別するのに使える映画だ。
July 5, 2012
コメント(0)
-
こんな映画を観た~笑ってさよなら
TV番組が元となったドキュメンタリーの劇場版を観てきた。トヨタの四次下請けをしている小さな町工場で働く50代の3人の主婦を追ったもの。工場主の小早川弘江という人が10年間稼働した工場を閉鎖するまでを描いている。この主婦3人、特に工場主の弘江さんが明るく元気でたくましい。たくましいだけでなく気配りも細やかで、職場にこういう人がひとりいるだけで灰色の単調な繰り返し作業も遊びのように楽しくなるだろうと思わせる。大きな工場ではこうはいかない。中小にも入らない、こうした零細な町工場ならではだと思う。トヨタの経営危機をきっかけに将来を考え、仕事があるうちに廃業するという決断をし、その最後の日に至るまでを描いているが、彼女の決断力にも刮目させられる。男なら、むしろ優柔不断なまま何となく続けてしまうのではないだろうか。株の損切りと同じで、ダメなものは手遅れにならないうちに切るべきなのだ。世にも珍しい「明るい廃業物語」になったのは3人の主婦の転身・転職がうまくいくせいもある。下請けにしわ寄せする親会社の無情さを告発するというような視点ではなく、下請けの小さな現場から巨大企業の経営危機というテーマを描いたのが外国でも高く評価された理由だろう。すでに英語版が世界120ヶ国で放映されているというが、外国人にぜひ観てもらいたい映画だと思った。働く主婦の一典型といえるような3人、そして弘江さんの夫や部品の配達と回収を担当するドライバーなどに律儀で真面目で、他人を思いやる日本人ならではの良さが感じられるからだ。「日本人理解」に貢献するという点でこの映画ほど優れた素材はないと思う。日本人じしんも自分たちの姿を見なおすきっかけになるかもしれない。東海地方の「四畳半工場」の明るい廃業物語に勇気づけられ、弘江さんのエネルギーをもらえる60分。
July 4, 2012
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1