全646件 (646件中 1-50件目)
-
税理士変更?
このところ、税理士変更のお客様がちらほら出てきました。豊田市 工務店様 事業再生中 事業再生コンサルタント様からのご紹介。前の事務所は名古屋の会計事務所。 今後は、事業再生コンサル会社さんと一緒にサポートしていきます。西尾市 小売店様 前の会計事務所の税理士となかなか会えないとのこと。相談ができなかったそうです。前の事務所 と同じ料金で、お引き受けいたしました。税理士変更をお考えの方はこちらからまた、今年も税理士から受けるストレスを我慢しますか?
2015/11/16
コメント(0)
-
平成27年12月の税務
平成27年12月の税務12/10 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付1/4 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>--------------------------------------○給与所得の年末調整○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
2015/11/16
コメント(1)
-
基準地価 三大都市圏で上昇
基準地価 三大都市圏で上昇------------------------------------------------------------------------- 国土交通省は2015年の基準地価を公表しました。全国の地価の平均(全用途)は前年度比0.9%下落。昨年のマイナス1.2%から0.3ポイント縮小し、6年連続で改善しました。住宅地、商業地ともに地価の下落は依然として続いているものの縮小傾向にあります。一方地方圏では、交通網が整備された中枢都市で地価が上昇したものの、それ以外の地域では下落が継続していることが分かります。 各都道府県が調査した基準地価は、毎年7月1日時点の全国の地価を不動産鑑定士が鑑定したものを基にしていて、土地取引や固定資産税評価の目安になります。 15年の調査結果では、東京、大阪、名古屋の三大都市圏の地価は、住宅地で前年比0.4%、商業地で2.3%、工業地で0.9%と、それぞれ前年に引き続いての上昇となりました。一方、地方圏では全用途で1.6%の下落で、下落幅は4年連続で縮まったものの、約7割の地点では地価下落が続いていることになります。人口減少率全国1位の秋田県は、住宅地が4.0%、商業地が4.6%下落し、前年に引き続き最大の下落幅となりました。 だが地方圏でも、鉄道や高速道路など交通網の整備した地点は地価上昇に結び付いているようです。今年3月に北陸新幹線が開通して発着駅となったJR金沢駅周辺の上昇率は16.8%で、商業地で全国1位でした。地価の回復基調になる都市と、人口減や高齢化などで地価下落が続く地域で、二極化が鮮明になっている現状が明らかとなっています。 全国で基準値が最も高かったのは、住宅地では東京都千代田区六番町6番1外で、1平方メートルあたり326万円、商業地では東京都中央区銀座二丁目2番19外の2640万円でした。<情報提供:エヌピー通信社>
2015/11/02
コメント(0)
-
争族にならないように60分相続無料相談
相続税や生前対策はこちらまで60分無料相談実施中!
2015/10/29
コメント(0)
-
法人様・個人事業主様
今の税理士さんに満足ですか、税理士 変更はこちらまで
2015/10/29
コメント(0)
-
平成27年11月の税務
平成27年11月の税務11/10●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付11/16●所得税の予定納税額の減額申請11/30●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●所得税の予定納税額の納付(第2期分)●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付--------------------------------------○個人事業税の納付(第2期分)
2015/10/29
コメント(0)
-
平成25年1月の税務
1/10 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)1/31●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●源泉徴収票の交付●支払調書の提出●固定資産税の償却資産に関する申告●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> ●給与支払報告書の提出-----------------------------------------------○個人の道府県民税・市町村民税の納付(第4期分) ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
2013/01/18
コメント(0)
-
平成23年2月の税務
2月10日●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付2月28日●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> -----------------------------------------------○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
2011/02/02
コメント(0)
-
平成22年分 所得税の主な改正事項
平成22年分 所得税の主な改正事項 表示されるまで時間がかかる場合があります。
2011/01/20
コメント(0)
-
給与所得控除の見直しに3案提示 役員退職金の2分の1課税見直し
2011年度税制改正では、個人所得課税の見直しが焦点の一つとなっている。税制調査会は、給与所得控除については給与所得者の必要経費が収入増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと等から、一定額を上回る給与所得者について給与所得控除に上限を設け、過大な控除を適正化し、一定の負担を求める。見直し案としては、1.1,200万円(給与所得控除額230万円、120万人程度が影響)、2.1,500万円(同245万円、50万人程度が影響)、3.1,800万円(同260万円、30万人程度が影響)の3案を提示した。 また、高額給与の役員については、給与所得控除のうち「勤務費用の概算控除」部分が2分の1であることを前提に、一般の給与所得控除の上限の1/2を上限とする見直し案も示した。役員については給与の自己決定度合いも高いと考えられるため、給与所得控除に「他の所得との負担調整」部分は含まれないとの考え方だ。高額給与の水準は、資本金10億円以上の平均役員報酬(1,655万円)を参考にする。 退職所得については、累進緩和措置(2分の1課税)が採られているが、法人役員が短期で退職慰労金を受け取る場合、その対象とする合理性は乏しいことから、平均在任期間が7年程度であることや、退職金と同じく2分の1課税が採用されている譲渡所得については、「5年以下」の短期譲渡所得は2分の1の適用がないことを参考にして、役員の退職慰労金について、2分の1課税を見直すことを提案している。
2010/12/07
コメント(0)
-
長期化傾向にある税務調査日数 調査で「申告是認」は4件に1件
東京税理士会がほぼ毎年行っている「税務調査・書面添付アンケート調査」の2010年度結果(有効回答数1,474会員)によると、税務調査件数は2,516件で、有効回答数からみて1回答者(法人)平均1.7件(前回2.9件)の調査があったことになり、ここ3年間では最少だった。また、調査件数なしの回答は676通あり、うち関与先に調査がなかったのが590件。その他関与先がない74件、不明12件。法人税調査は2,002件(前回3,136件)あり、うち所得税の確定申告期に行われたものは98件で、4.9%(前回比0.1%減)となっている。 調査日数について、「1日」で終了したものは、日数が明記してあるもの2,357件のうち、516件で21.9%(前回比1.9%減)、「2日」で終了したものは、1,125件で47.7%(同4.5%減)と、合計で約7割となっている。一方、「3日~4日」が431件で18.3%(同1.6%増)、「5日以上」が285件で12.1%(同4.8%増)と、税務調査日数は長期化傾向にある。特に5日以上の割合は過去3年間と比べ最も高い数字となった。 調査結果については、内容記入のあった2,417件中「申告是認」が593件で24.5%(前回比1.0%減)、「修正申告」は1,759件で72.8%(同0.6%減)、「更正」は65件で2.7%(同1.6%増)。また、修正申告及び更正1,824件中、重加算税処分となったものは281件で22.8%(同1.1%増)だった。 今回の調査で、申告是認のうち書面で通知があったものは、59件で9.9%(同1.6%増)と、ここ3年間横ばい状態が続いている。
2010/12/06
コメント(0)
-
平成22年12月の税務
12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付12月20日●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出1月4日●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> -----------------------------------------------○給与所得の年末調整 ○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
2010/12/01
コメント(0)
-
年末調整改正点のポイント
年末調整改正点のポイント ご参考になれば幸いです。
2010/11/22
コメント(0)
-
平成22年7月の税務
平成22年7月の税務7月12日●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付7月15日●所得税の予定納税額の減額申請8月2日●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●所得税の予定納税額の納付(第1期分) ●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> -----------------------------------------------○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
2010/07/01
コメント(0)
-
平成22年6月の税務
6月10日●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付6月15日●所得税の予定納税額の通知6月30日●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
2010/05/31
コメント(0)
-
平成22年5月の税務
5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付5月17日●特別農業所得者の承認申請5月31日●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 -----------------------------------------------○自動車税の納付 ○鉱区税の納付
2010/04/30
コメント(0)
-
経営セーフティ共済が拡大 節税効果もビッグに
経営セーフティ共済が拡大 節税効果もビッグに提供:エヌピー通信社 平成22年度税制改正で延長・拡大が決まった「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」。内容拡充となったことにより、同共済を活用した節税があらためて注目を集めています。 同共済は、取引先の予期せぬ倒産から、中小企業の連鎖倒産を守るため設けられたもの。現状では、毎月掛金を積み立てていれば、取引先起業が倒産した場合や、売掛金、受取手形などの回収が困難になった場合、掛金総額の10 倍以内の融資を無担保・無保証人・無利息で受けられます。 加入対象は、1年以上事業を行っており、従業員数や資本金、また業種など一定の要件をクリアした中小企業者となっています。 同共済を使った節税が注目されているのは、掛金が税法上、法人であれば損金、個人であれば必要経費として処理することが認められているためです。 現在は、貸付限度額が3200万円までですが、同22年度税制改正により8千万円まで拡大されます。また、掛金も月額最大8万円、総額320万円から、月額最大20万円、総額800万円まで拡大される予定です。これにより、節税効果もかなりアップしたといえそうです。 さらに、同共済は解約が自由にでき、解約手当金が受け取れます。その金額は、納付12カ月以上なら80%、40カ月以上なら100%です。 法人なら、その解約手当金について、支給を受けた時点の益金、個人は事業所得として処理しますが、事業が赤字のときに解約すれば、税負担を軽減できるメリットがあります。たとえば、毎月20万円で40カ月、800万円積み立てたとしたら、100%の金額が支給されるため、最大で800万円の所得が圧縮できることになります。 ただ、重複契約はできないほか、法人税を滞納している企業や継続的な取引状況を把握することが困難な企業・個人、さらにはすでに貸付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っているなどの理由がある場合には同共済に加入できないので注意しましょう。<情報提供:エヌピー通信社>
2010/04/06
コメント(0)
-
平成22年3月の税務
3月10日●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付3月15日●所得税確定損失申告書の提出 ●前々年分所得税の更正の請求 ●個人の青色申告の承認申請 ●前年分所得税の確定申告 ●贈与税の申告 ●前年分所得税の総収入金額報告書の提出 ●確定申告税額の延納の届出書の提出 ●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 3月31日●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 ●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
2010/03/15
コメント(0)
-
共通番号の導入に住基ネットの活用検討!?
政府は社会保障と税の共通番号制度で住民基本台帳ネットワーク(以下:「住基ネット」)を活用する検討に入ったとの報道がありました。全国民に固有の番号が割り振られている既存のシステムを使うことで、システム設計にかかるコストや時間を抑える模様です。 もし、住基ネットの採用が固まりますと、共通番号の具体的な活用策をめぐる議論の早期着手につながりそうです。 共通番号を使えば税務当局が所得を正確に把握しやすくなり、社会保障給付にも役立つとみられています。 政府は2010年度税制改正大綱に共通番号制度の導入を明記しており、2011年の通常国会に関連法案を提出し、準備期間をおいて早ければ2014年の利用開始をめざすとされています。 ただ、名古屋市では市民への周知不足などを理由に、現在は慎重に判断する姿勢を見せておりますが、名古屋市長は住基ネットを「国民総背番号制につながる」などと批判しており、2月19日には原口一博総務相に離脱を視野に予算計上するか否かを検討している旨を伝えていたことをみても、共通番号の導入に住基ネットを活用することには、今後とも留意が必要です。(注意)上記の記載内容は、今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2010/03/05
コメント(1)
-
《コラム》税金の場合の消滅時効
■時効制度とは 時効とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度です。■破産制度も 破産も債権債務関係を強制的に変動させる制度で、特に自己破産の場合は、破産宣告を受けて、免責を受けると、債務がゼロになり、ゼロからの再チャレンジの機会を得ることになります。 ただし,税金等の公租公課や養育費や扶養義務に基づく支払債務などは公序良俗的理由から例外的に免責されません。■国税の時効 国税徴収権の消滅時効の期間は法定納期限から5年です。ただし、刑事告発されるような「偽りその他不正の行為」が発覚した場合には、時効の完成は7年に延びます。 租税債務は破産でも消滅しないのですから特別扱いなのですが、時効についても何か特別扱いがあるかというと、そういう規定は特にありません。 逆に、「その援用を要せず、またその利益を放棄することができない」とされていて、納税者に有利な規定となっています。■税金の場合の時効消滅 国税徴収官には、滞納税金の消滅時効を回避保全する事が義務付けられています。滅多なことでない限り単なる期間の徒過による時効消滅はありそうではありません。 それでは、納税者が破産宣告を受けた後でも、督促状が送り続けられてきた上で、破産後5年経過前に時効中断措置が採られるものなのでしょうか。 形式的にはそういうことになるのでしょうが、実際には民間の債権債務の貸倒処理と同じく、滞納税金が少額であるとか、回収費用がかかりすぎるとか、回収そのものが困難とかの場合には、時効回避保全事務を解除する措置をとりますので、督促状も来なくなり、滞納税金も時効期間の経過とともに消滅することになります。
2010/02/23
コメント(0)
-
バリアフリー改修対象範囲に要注意
「超高齢化社会」に突入しつつある日本。独居老人の孤独死などが問題となるなか、高齢者に適した住宅づくりが急務とされています。 政府も「高齢者が安心し自立して暮らせる」住宅のストックづくりに力を入れており、政策で後押ししています。そんな後押し制度のひとつが、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」、いわゆる「バリアフリー改修促進税制」です。同税制は平成21年度末までの時限措置でしたが、このほど発表された同22年度税制改正により、2年間の延長が決定されました。 同税制は、5年以上のローンを組んで30万円を超えるバリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合、年末借入残高の一定割合を5年間にわたって所得税額から控除できるというものです。年末借入残高は1千万円が上限です。うちバリアフリー改修工事費部分(200万円まで)の控除率は2%、それ以外の部分は1%となります。一般の住宅ローン控除の要件も満たしていれば選択適用が可能です。 同税制の適用対象者は、50 歳以上の人、要介護認定者、障害者、65 歳以上の親族と同居している人など。 対象となるバリアフリー改修工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、手すりの設置などです。 ただし、同税制を利用する際には「対象とならない借入金」に注意しなければいけません。 たとえば、1.土地購入にかかるローンの年末残高しかない場合2.使用者または事業主団体からの無利子または1%を下回る低利率による借入金3.使用者または事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%を下回った借入金――などは同制度の対象外となります。<情報提供:エヌピー通信社>
2010/02/16
コメント(0)
-
医療費明細の早期準備について
確定申告の時期になりました。医療費控除を受けられる方は、平成21年分の医療費の領収書やレシートなどを集め、支払った医療費を早期に準備確認しましょう。 家族全員の医療費が1年間で原則100,000円(または合計所得金額の5%)を超える場合には、確定申告による医療費控除の適用を受けることで税金が軽くなります。持病で毎月通院している人などは、くすり代も含めて100,000円を超えることはよくあります。 通院で使った電車・バス・タクシーなどの交通費も認められますので、各人別、治療目的別に紙に書き出しておくと良いでしょう。 振り分けが終わったら、まとめた順に合計額を出し、家族全員の医療費の総額を計算します(あくまでも、1年間に支払った医療費の総額を計算します。)。 そのほか、入院などで高額な医療費を支払った場合には、月間別の金額も調べてください。健康保険の対象になる医療費(食事負担分は除く。)には高額療養費という制度があり、同じ人物が、同じ月間内に、同じ医療機関・診療科で自己負担限度額を超えた医療費を支払うと、超えた分は払い戻されます。所得区分で一般の人ですと80,000円台から対象になり、21,000円を超える支払いが複数あれば世帯で合算することも可能になります。 自ら申請が必要なケースも多々ありますので、該当すると思われる方は加入中の健康保険に早期に確認をしてください。 申告書には支払った医療費の領収書やレシートなどを添付することが必要となります(電子申告をされる方は添付が不要になります。)ので、早めに準備をして、医療費の総額を把握しておきましょう。
2010/02/09
コメント(0)
-
平成22年2月の税務
2月10日●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付3月1日●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>-----------------------------------------------○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
2010/02/01
コメント(0)
-
医療費明細の早期準備について
確定申告の時期になりました。医療費控除を受けられる方は、平成21年分の医療費の領収書やレシートなどを集め、支払った医療費を早期に準備確認しましょう。 家族全員の医療費が1年間で原則100,000円(または合計所得金額の5%)を超える場合には、確定申告による医療費控除の適用を受けることで税金が軽くなります。持病で毎月通院している人などは、くすり代も含めて100,000円を超えることはよくあります。 通院で使った電車・バス・タクシーなどの交通費も認められますので、各人別、治療目的別に紙に書き出しておくと良いでしょう。 振り分けが終わったら、まとめた順に合計額を出し、家族全員の医療費の総額を計算します(あくまでも、1年間に支払った医療費の総額を計算します。)。 そのほか、入院などで高額な医療費を支払った場合には、月間別の金額も調べてください。健康保険の対象になる医療費(食事負担分は除く。)には高額療養費という制度があり、同じ人物が、同じ月間内に、同じ医療機関・診療科で自己負担限度額を超えた医療費を支払うと、超えた分は払い戻されます。所得区分で一般の人ですと80,000円台から対象になり、21,000円を超える支払いが複数あれば世帯で合算することも可能になります。 自ら申請が必要なケースも多々ありますので、該当すると思われる方は加入中の健康保険に早期に確認をしてください。 申告書には支払った医療費の領収書やレシートなどを添付することが必要となります(電子申告をされる方は添付が不要になります。)ので、早めに準備をして、医療費の総額を把握しておきましょう
2010/01/27
コメント(0)
-
ガソリン課税について
1月18日、政府税制調査会は、2010年度税制改正でガソリン価格の高騰時にガソリン税の上乗せ課税を停止する新しい仕組みを決定しました。 レギュラーガソリンの小売価格が3カ月間、1リットル当たり160円を上回って推移した場合には、ガソリン税(1リットル当たり53.8円)のうち暫定税率(同25.1円)を廃止し、代わりに暫定税率と同額の「特例税率」を創設して、現在と同じ課税水準を維持します。 あくまでもガソリン価格に応じて停止・復活させるのは、この特例税率の部分となりますので、ご注意ください。 ガソリン価格は、総務省が毎月公表している物価統計調査を基準とします。停止後に3カ月間の価格が130円を下回った場合には課税を再開します。課税の停止・解除はともに大臣が告示した翌月に実施されます。 また同様に、2010年度から軽油にかける軽油引取税の特例税率(1リットル当たり約17円)についても、ガソリン税の特例税率に連動して停止・復活させる模様です。 増減税で影響を受けるガソリンスタンドに減税分の還付措置などを行い、混乱を防ぐといわれています。 この課税停止制度は、2011年度以降で検討している地球温暖化対策税(環境税)の導入までとする模様です。(注意)上記の記載内容は、平成22年1月18日現在に基づいて記載しております。今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2010/01/25
コメント(0)
-
80年代が懐かしく‥
今回は、ドルッティ・コラムとフェルトをどーぞここにあります。
2010/01/18
コメント(0)
-
80年代 音楽
ダンソサThe Danse Society - 2000 Light Years From HomeTHE DANSE SOCIETY - Heaven Is Waiting (Extended Version) - 1983ヴァージニア・アストレィVirginia Astley "Love"s is a lonely place to be"シスターズ・オブ・マーシィーThe Sisters of Mercy - Walk Awayここで聴けます。癒しあり、ダークあり、ストーンズのカバーありの音です。
2010/01/17
コメント(0)
-
ガソリン税の暫定税率のゆくえ
今月7日、政府・民主党は、ガソリン税の暫定税率(2010年の3月末にいったん廃止するものの、仕組みを変えた上で現在と同水準の課税を継続)に関し、原油の高騰時に課税を停止するガソリン価格の水準を1リットル155~160円の間で検討していることが分かりました。もし、停止されることになれば、1リットル当たり約25円安くなります。 今後、政府・与党内で調整を進め、課税停止価格を確定させた上で、今月18日召集の通常国会に提出する税制改正関連法案に盛り込むと報道されています。 民主党の小沢一郎幹事長が2009年12月、政府に申し入れた重点要望では、暫定税率を維持する代わりに、原油価格高騰時に暫定税率部分を停止する措置を求め、政府側もこれを受け入れた形で2010年度税制改正大綱に反映させました。 民主党幹部は「財務省はもっと高い水準を想定していたが、それでは(停止措置を)やる気があるか(国民には)分からない」と説明しています。 停止する水準を高めに設定すれば、国民から「意味がない」と反発されかねないとして、党主導で低めに設定したとみられています。(注意) 上記の記載内容は、平成22年1月7日現在に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
2010/01/11
コメント(0)
-
明けましておめでとうございます!
本年もよろしくお願いします。1月5日より、業務開始します。
2010/01/01
コメント(0)
-
今年1年も大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。来年は1月5日業務開始となります。
2009/12/28
コメント(0)
-
マンション経営 自販機設置で消費税還付? 節税テクに
会計検査院はさきごろ、マンション経営で租税回避を行う手法が横行しているとし、実態を調査するよう財務省に要請しました。その内容は、決算検査報告書に盛り込まれる予定です。 手法とは、賃貸マンションやアパートを建設した際に合わせて自動販売機を設置し、消費税還付を受けるというものです。 マンションやアパートといった賃貸物件を経営する場合、建設時に払った消費税は本来ならば還付を受けることはできません。原則、多重課税を避ける観点から、事業者は売上げにかかる消費税から仕入れにかかった消費税を引いた額を国に納めます。逆に仕入れにかかった消費税の方が多ければ税金は還付されます。ですが、住居用賃貸物件の賃料は非課税であり、計算の元になる売上げ消費税がないため消費税還付の対象外です。 ですが自販機を設置するだけで、「合法的に還付を受けられる」のです。 これは、消費税の仕入税額控除の「95%ルール」を使ったもの。95%ルールとは、仕入税額控除の計算上、課税売上げ割合が全売上げの95%以上を占めれば、事業にかかる仕入れ消費税額の全額を控除できるという制度のことです。 初年度の課税期間の賃貸経営売上げをゼロにし、自販機売上げのみとすれば、自動的に課税割合は100%となります(ほかに事業を行っていない場合)。これにより95%ルールがクリアとなるため、「賃貸経営の仕入れ消費税(実際はゼロ)+自販機の売上げ消費税」から「賃貸経営の仕入れ消費税+自販機の仕入れ消費税」を差引くことができます。 これまで国も存在は認知していましたが、法改正の動きはなく、具体的な対策は先送りされてきた格好です。 規制を行うとなると、1.個別対応方式の税額計算を義務化 2.仕入額控除の税額調整を免税業者にも適用――などが考えられますが、一長一短。今後の動向に注目が必要です。<情報提供:エヌピー通信社>
2009/12/28
コメント(0)
-
年末調整で間違えやすい点について
年末調整の時期と事務手続きとその準備 給与の総額等と徴収税額の集計 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計 していますか。 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。前の会社からまだ源泉徴収票をもらっていない人は、会社によっては時間がかかる場合もありますので、早めにお願いしてください。前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。 年調年税額の計算給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。 確定申告した税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙の下の部分が「控除証明書」になっていますので、必要事項を記載した上、「年末残高等証明書(金融機関から送付されます)」を添付して提出します。 また、平成11年から平成18年に入居した人で、所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれなくなった場合は、お住まいの市区町村の税務課等へ「市県民税住宅借入金等特別控除申告書・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」を提出すれば、住民税から控除することができます。詳しくはお住まいの市区町村の税務課等にご確認ください。 不足額の徴収、過納額の還付等年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。
2009/12/26
コメント(0)
-
法定調書の主な提出義務者
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。 以上の法定調書の提出期限は、例外を除き、その年の翌年1月31日となっています。また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。 「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出します。 (注)詳しくは、税務署、国税局、市区町村で配付している法定調書の作成・提出に関する パンフレットを参考にしてください
2009/12/18
コメント(0)
-
平成22年1月の税務
1月12日●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付2月1日●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●源泉徴収票の交付●支払調書の提出●固定資産税の償却資産に関する申告●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●給与支払報告書の提出-----------------------------------------------○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
2009/12/15
コメント(0)
-
平成21年12月の税務
12月10日●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付12月21日●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出1月4日●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>-----------------------------------------------○給与所得の年末調整○給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
2009/11/30
コメント(0)
-
年末調対象となる人、ならない人
年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。 年末調整の対象となる人次のいずれかに該当する人(1) 1年を通じて勤務している人(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人(3) 年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人 死亡により退職した人 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。) 年末調整の対象とならない人次のいずれかに該当する人(1) 上記 年末調整の対象となる人に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が 2,000万円を超える人(2) 上記 年末調整の対象となる人に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被 害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対 する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)(4) 年の中途で退職した人で、上記 年末調整の対象となる人(3)に該当しない人(5) 非居住者(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
2009/11/21
コメント(0)
-
寄贈や見舞金は交際費から除外
過ごしやすい気候の秋は、全国各地で祭りなどのイベントが増える時期。会社も地域の一住民として、神社の祭りに参加することが多々あります。社員の参加のほか、費用の面からバックアップすることも珍しくありません。 神社の祭礼に寄贈金を支出した場合は、原則寄付金として処理します。交際費と考える向きもありますが、神社の祭りは通常、会社の事業と直接の関係はありません。事業に関係のない相手への金銭贈与なので寄付金扱いになるのです。 神社の祭礼への寄贈金のほかには、社会事業団体、政治団体に対する拠出金も寄付金です。 では、地震などの災害にあい、営業が出来なくなってしまった取引先に見舞金を送る場合はどうでしょうか。事業に直接関係がある相手に対する金銭贈与なので交際費だろうか・・・という心配は無用。取引先に対する災害見舞金については、交際費から除いてよいことになっています。この場合の災害見舞金とは具体的には、「被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、取引先に対して行った支出」であり、事業用資産の供与、役務の提供のために要した費用も含まれます。 交際費とは、得意先・仕入先そのほか事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。しかし、杓子定規にそう分類されるわけではなく、災害見舞金の例のように血の通った措置も講じられているわけです。もちろん、交際費から除外したら税務署に交際費認定されるという逆の場合もよくあるので、交際費かどうかの判定は実態に沿って慎重に行いましょう。提供:エヌピー通信社
2009/11/12
コメント(0)
-
中小企業庁が年末年始の資金繰り対策等を公表
中小企業庁(経済産業省)が「中小企業向け年末対策」を公表しました。年末年始に向けて資金需要が高まる中小企業の資金繰りを支援するための「総合的な政策パッケージ」ということです。 この対策の主な内容は以下の通りです。1.中小企業資金繰り対策2.中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予3.下請代金支払遅延等防止法の厳格な執行 この中で特に気になるのは、やはり「中小企業資金繰り対策」でしょうか。内容は特に目新しいものではなく、従来から公的金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会)が行っている緊急支援対策等(30兆円の緊急保証枠、15兆円のセーフティネット貸付枠、1.5兆円の条件変更目標)の利用が広く進むように取り組むという内容です。各支援策について「公的金融を利用したことのない中小企業を含めて」「中小企業の経営実態や特性を十分に踏まえ」「対象業種を見直し」「使いやすくするため運用を見直す」等の対策がとられるようです。 12月以降、公的金融機関の相談窓口や営業時間の拡充も予定されていますので、相談してみてはいかがでしょうか
2009/11/06
コメント(0)
-
平成21年11月の税務
11月10日●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付11月16日●所得税の予定納税額の減額申請11月30日●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●所得税の予定納税額の納付(第2期分)●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付-----------------------------------------------○個人事業税の納付(第2期分)
2009/11/04
コメント(0)
-
20年度の法人税 黒字申告割合が初の30%割れ
国税庁が「平成20年度における法人税の申告事績について」を公表しました。それによると、平成20年度の法人税は、申告所得金額、申告税額とも前年度から大きく落ち込んでいるようです。 なお、今回の公表より、集計対象期間が従来の7~6月申告ベース(7月1日~翌年6月30日までに申告があったもの)から、4~3月決算ベース(4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度)に変更になっています。従って、今回の公表は「平成20年4月1日~同21年3月31日までに終了した事業年度に係る申告」についての集計結果ということになります。 公表によると、平成21年6月現在の法人数は300万2千社でほぼ前年同月並み。この1年で法人の数はあまり変わっていません。平成20年度に法人税を申告した件数も280万5千社で前年度比0.2%の微減です。 しかし、その申告のうち納税額があった申告(黒字申告)の割合はなんと29.1%。初めて3割を下回り過去最低となりました。さらに、黒字企業1件あたりの所得金額4653万円が前年度の6470万円に比べて28.1%も減少しました。一方、赤字企業1件あたりの欠損金額は1546万円で、前年度の871万円に比べて78.5%も悪化しています。 その結果、申告所得額は37兆9874億円で前年度の58兆8244億円より35.4%(20兆8370億円)減と大幅に減少。申告税額も9兆7077億円で前年度の14兆5321億円より33.2%(4兆8244億円)減と大幅に減少しています。
2009/10/30
コメント(0)
-
本日は営業日
8月決算の会社様は、結構多いので本日は営業中です。8月決算の中小法人は、10月末日(今年は11月2日)が税務申告期限になります。申告期限に遅れないためにも、月に1度は土曜日出勤をしております。来月の出勤日は、11月21日の予定です。5年ほど前に税務調査があった会社様に、また税務署さんから調査依頼が何社か入っています。めぐり合わせなのでしょうか?5年周期でやってきます。一方、会社を設立してから、1度も調査がなかった会社様にも調査依頼がありました。さすがに、平成2年に作られた会社様なので、1度くらい調査もありますね。ベストをつくします!
2009/10/24
コメント(0)
-
研修
昨日は午前中は仕事で12時に車で出発、刈谷でJRに乗換、1時過ぎに名古屋着。会場途中のコンビニさんでおにぎりを購入。会場にて、おにぎりを食べ(失礼しました)1時半より研修を受けてきました。タイトルは、伸びる会計事務所の作り方セミナーです。私たちも皆様同様ひび悩んでおります…どうしたら、お客様の満足度を上げられるか?自分たちの付加価値をもっと上げることができないか?どうしたら、お客様に新規のお客さまのご紹介をいただけるか?ちなみにこのセミナーの参加者はわずか10名程度でした…参加者の数の少なさに、まだまだいける!チャンスはある!と新たな闘志がわきあがってきました!
2009/10/22
コメント(0)
-
新政権での税制改正論議がスタート
平成21年度の第1回政府税制調査会(会長 藤井財務相)が10月8日に開催され、平成22年度税制改正に向けた本格的議論がスタートしました。なお、同日をもって政権交代前の政府税制調査会は廃止されています。 政府税制調査会は、国や地方の税制に関する事項を調査・審議する首相の諮問機関です。ただ、前政権においては与党の税制調査会が実質的に税制改正を取りまとめていたため、政府税制調査会はどちらかというと中期的な視点で税制のあり方を考える役割を担っていました。 今政権はこの2つの税制調査会を一本化。国税を所管する財務省と地方税を所管する総務省の大臣、副大臣、政務官、および各省庁の担当副大臣をメンバーとした新しい政府税制調査会を設置し、税制改正を一元的に取りまとめていく方針です。 今回、鳩山首相は、政府税制調査会に「マニフェスト(三党連立政権合意書を含む)の実施」「既得権益の一掃」「所得税の控除のあり方を根本から見直す」「国と地方が対等なパートナーとして地域主権を確立」など7項目について諮問しています。これを受けて、政府税制調査会では、ガソリン税などの暫定税率の廃止、租税特別措置法の抜本的見直し、所得税の扶養者控除等の見直しなどを議論されることになります。また、各省庁にも税制改正要望の見直しを10月末までに提出するよう要求しました。 なお、政府税制調査会の会議は原則として傍聴、およびインターネット中継で公開されるそうです。
2009/10/20
コメント(0)
-

懐かしい写真 その2 チワナベ
2009/10/20
コメント(0)
-

3年前の茶美うさぎ
2009/10/19
コメント(0)
-

くーたんと茶美 二見浦シーパラダイスにて
2009/10/19
コメント(0)
-
インフルエンザの予防接種 会社で受けたら?
厚労省はさきごろ、新型インフルエンザ予防接種の優先順位案を発表しました。1.医療従事者、2.ぜんそくや糖尿病などの基礎疾患のある人と妊婦、3.1歳から就学前の小児、4.1歳未満の乳児の両親となっています。これらに次いで、小中高生や高齢者が優先されるとしています。 また、予防接種の費用は実費負担と決定。季節性のインフルエンザの予防接種費用はひとり当たり3~4千円で、新型インフルエンザの場合、予防接種を2回受ける必要があることから、トータルで6~8千円ほどの負担になるとみられています。 新型インフルエンザワクチンは一般の人にはなかなか回ってこないようですが、冬が近づくにつれ流行が予想されるのは新型ばかりではありません。毎年死者が出ることもある季節性のインフルエンザに対しても十分準備をしておきたいところです。 顧客や取引先への感染が懸念されるなど、業務上「接種の必要性がある」と判断されるとき、会社負担でインフルエンザの予防接種を行うことがあります。この際、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用は福利厚生費などとして損金算入することが可能です。 また、新型インフルエンザの場合も、受ける条件に当てはまった人から随時一律に受けさせていくのであれば、損金とすることができます。 インフルエンザ対策として予防接種のほかに、うがい液やマスクといった衛生資材の備蓄を行う場合、それにかかった費用も「常備薬」などと同じ扱いで福利厚生費などで処理することになります。 しかし、どれだけ気を付けていたところで、集団感染が起きる可能性は捨てきれないもの。これを機会に、災害が発生したときの事業継続計画(BCP)を策定しておくことが望ましいでしょう。(エヌピー通信社)
2009/10/19
コメント(0)
-
平成21年10月の税務
10月13日●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付10月15日●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知11月2日●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>-----------------------------------------------○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
2009/09/28
コメント(0)
-
平成21年9月の税務
平成21年9月の税務9月10日●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付9月30日●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
2009/08/31
コメント(0)
-
平成21年8月の税務
8月10日●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付8月31日●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告-----------------------------------------------○個人事業税の納付(第1期分) ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
2009/08/07
コメント(0)
全646件 (646件中 1-50件目)
-
-
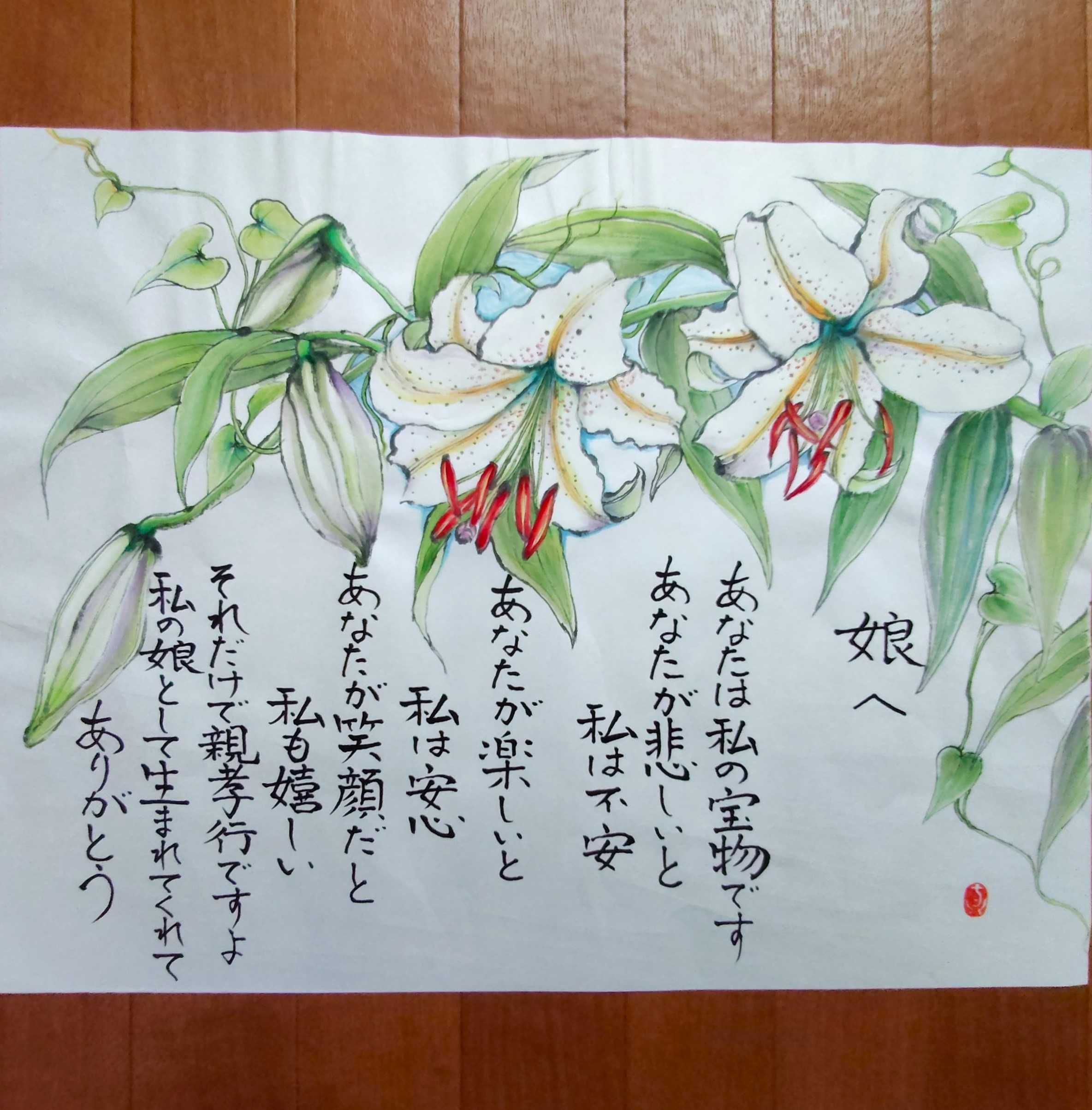
- 楽天写真館
- 南足柄市民文化祭 絵手紙展・水彩画…
- (2025-11-28 14:46:39)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- *ほんわかするダックス姉妹。
- (2025-11-28 14:25:46)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-








