2014年09月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-

マンガで分かる心療内科(8)
「カッツの反応増幅説」「報復不全症候群」「ボトムアップ説・トップダウン説」 「ネット依存症」「自己愛性パーソナリティ」「ホーナーの成功恐怖理論」。 今巻で扱っているのは、心療内科で本筋と言えるものなのかな? 若干、ネタ切れ感が漂い始めた気もします。 その中で、「ショック療法」は、精神治療の歴史を描いており、 「らしさ」の感じられるものでした。 薬剤の使用が始まったのが1952年ということなど、 知識として、なかなか持ち合わせていないかも知れません。ただ私としては、今巻で一番印象深かったのは、「ホーナーの成功恐怖理論」についての、「Y医師のよく分かる解説」。 結局、人生の差なんて、それだけなんです。 どれだけたくさんサイコロを振っているか。 一人一人のサイコロの目の出やすさなんて、ほぼまったく違いはないのです。 ただたくさん、サイコロを振った人こそが、成功している。それだけです。 ですのであなたも、不満を言う前に、 とにかく、一度でもいいので、サイコロを投げてみてください。 サイコロに「0」や、「マイナス」の目なんてありません。 振りさえすれば、それは必ず、プラスにつながっていくんですよ。これは、なかなか良いお話しでした。
2014.09.30
コメント(0)
-

銀の匙(12)
八軒は御影の土地を借りて、黒豚の放牧を始める。 そして、大川が社長に、自分が副社長になって会社を立ち上げることに。 迅速に仕事をやってのける大川。 さて、八軒は父親から、出資金を獲得できるだろうか。 その頃、野球部は、北北海道ブロック決勝戦。 その会場に飛行機で向かう駒場。 一方、馬術部の新部長には御影が就任。 インターハイ北海道予選・団体戦は御影、石山、栄が出場。今巻は、大きな進展はあまりなく、助走期間といった感じ。しかし次巻では、豚の放牧やピザ作りで会社がいよいよ動き始め、馬術部も決勝に進み、八軒が大活躍しそう。そして、何と言っても駒場君の活躍が待ち遠しいです。
2014.09.29
コメント(0)
-

中村勘三郎最期の131日
『精神医療・診断の手引き』の序文で、 「診断と治療をめぐる精神医療の混乱そのものを映し出している」ものとして、 本著のことが取り上げられたいたので、読んでみました。 なるほど、これは本当に辛い状況だと思います。 コロンビア旅行中、耳鳴りが始まり、痙攣でブルブル震えだした勘三郎さん。 旅行を切り上げ、懇意にしている先生が勤務するA病院に入院します。 そこで精神科の医師が、うつ病の本を携えて病室に現れ、 勘三郎さんの話をじっくり聞くこともなく、突然「うつ病」と診断されます。そして、あなたは56年間ずっと躁病だったが、今うつになった。これは恐い状況で、もう舞台に出ることは考えず、後進に道を譲り、指導者となるべきだと言われてしまいます。数名の俳優の名前を挙げ、こういう病気になった人はセリフを喋れないとも。懇意にしている先生が、そのことを知って、主治医は替わることになり、デパスとアナフラニールが処方され、時間通りに飲みながら休養して一週間、勘三郎さんは許可を得て退院し、夫婦でアリゾナで2週間ほど過ごします。そこでは、薬を飲み、ボーッとしながらも、ゴルフや登山を楽しみました。しかし帰国後、A病院に再入院した際、ホームドクター的存在の副院長にこう言われます。 「おかしいですね、ウツ病患者には見えないな。 哲さん、ウツ病ではないんじゃないかな」それを受け、奥様の好江さんが主治医に確認すると、次のような言葉が。 「ご主人はウツ病ですよ。 そんなに心配なら一年間ぐらいアリゾナから帰ってこない方がいいんじゃないですか。 そうすれば、お互いにのんびりできるんじゃないですか。 ご主人はもう定年なんだから、出たいときに一日ぐらい舞台に出て、 あとは静かに暮らせばいいじゃないですか」その後のやりとりも、腑に落ちないことばかりで、結局B病院に問診に出かけます。そこで精神科の3名の医師に診察を受けると、「うつ病とはっきり診断できません」とのこと。ちょっとB病院に入院し、整理することになったものの、そこへ今度は准教授が現れて、うつ病と診断され、ジプレキサと抗うつ剤睡眠薬が処方されることになりました。その二週間後、外泊が許可され、病院に戻ってくると、准教授が、「えっ!?誰が許したの?冗談じゃない」と言って、その薬の強さを奥様に告げます。それを知った奥様は、以後、薬をビタミン剤に入れ換え始めます。ウツ病の本を読んで、それがとても危険な行為であることを知りながら。B病院を退院してから、奥様は勘三郎さんに薬を入れ換えていたことを告げます。そして、C病院でカウンセリングを4日連続で受けた後、そこの医師にこう言われます。 「遠回りをしましたね。ウツのような症状だったかもしれないけど、 あなたはウツ病じゃありません」そこでは、もう一度薬を飲み、3~4か月かけて抜くことになります。そして、約4か月後、治療の終了が告げられます。それは、A病院に入院してから、半年余りが経った頃のことでした。しかし、その後も耳鳴りが治らないので、テレビで見かけたD先生に診てもらいます。この先生は、薬を一切出さない医師でした。そのため、勘三郎さんはB病院にも通い、カウンセリングを受け、薬を処方してもらいます。そして、勘三郎さんは、B病院で再度入院し、仕切り直すことを提案されますが、そのことを奥様から聞いたD先生に説得され、入院はしないことを決断します。その後も、本調子には戻らないものの、舞台に立ち続け、最初の入院から一年余り経った時点で、やっと舞台で完全復活を宣言します。しかし、奥様からすると、その病から勘三郎さんが完全に抜け出せたのは、最初の入院から、1年半ほど経ったときとのことでした。 ***第2章からは、食道がん・ARDSとの闘病の日々が綴られています。その辺りのことは、以前、テレビの番組で見ていたので、その時のシーンを思い返しながら読んでいましたが、本当に壮絶なものでした。しかし、勘三郎さんだからこそ、あそこまでの治療がなされたのだとも思います。にもかかわらず、第一章の闘病については、あまりにも病院・医師のブレが大きすぎます。もちろん、一方からの情報だけで、その中には誤解等もあるかもしれませんが、それにしても、その時々で、医師によって、診断や治療方針が二転三転し、勘三郎さんが大きく振り回され、辛い状況だったことに間違いはないでしょう。これは、どこの病院でも起こっている、現状なのでしょうか?これでは、医師を信じて、治療を進めたくても、疑心暗鬼になるのは当然です。でも、大野先生が例に挙げるくらいですから、これが現実なのでしょう。しかし、せめて同じ病院の中では、同じ診断・治療が行われるよう連携してもらいたいです。
2014.09.29
コメント(0)
-

「うつ」は病気か甘えか。
衝撃的なタイトルです。 「うつ」になっている当事者にとっては、なおさらでしょう。 しかし、これが多くの人の本音の疑問だというのも事実でしょう。 それだけに、きちんと考えねばならないと思います。 週刊誌で、様々なスキャンダルについての記事を読むように、 外野席から読む分には、とても面白いと思います。 しかし、当事者にとっては、ハッキリ言って、気分を害するような書き方です。 「うつ」が改善していない状態の方は、読まない方がいいと思います。 うつ病に似た状態は、甘えということも十分にありえる。(p.180)しかし、先にも書いたように、これが世間の多くの人たちが抱いている疑問・本音だとすれば、ある程度の状態が整った段階では、読み進めるべきでしょう。書籍なら、ページを捲る手を止めてしまうことはできますが、社会に出れば、周囲の人たちの視線や本音と、向き合わざるを得ませんから。そして、著者もちゃんと書いてくれています。 内因性うつ病なら、間違いなく病気である。脳の病気だ。(p.233)しかし、医師の下す診断が、実は問題だったのです。 だがうつ病と呼ばれているものの中には、メンタルヘルス不調が相当に含まれている。 メンタルヘルス不調の中には、病気未満が相当に含まれている。 あらゆる程度の不調、あらゆる種類の不調が含まれている。 あらゆる不調を「病気」と名づけ、医療化する。 一丁上がりで広大な市場がそこに開ける。 医療化はすべてを蹴散らして進む。(p.210)そう、うつ病に似た状態まで、診断書に「うつ病」と書かれている現状があるのです。それは、主観至上主義の医療のため?それとも主観市場主義、市場至上主義の医療になってしまっているから? ひとりでにおこる「うつ」。原因のない「うつ」。 本来のその人とは違ってしまった「うつ」。 すなわち「内因性うつ病」。 精神医学が真のうつ病として認知してきた内因性うつ病だけをうつ病と呼ぶ時代では、 もはやなくなっていたのだ。 一定以上の症状があれば、公式にはそれはうつ病。 原因は診断名とは無関係。現代ではそれが公認されたうつ病になった。(p.237)その結果、診断書に書かれた「うつ病」は、本来の「うつ病」とは違うものまで含んでしまうことになっています。 診断書に書かれている「うつ病」。 それは、休養すなわちドクターストップを命ずるための便宜的な記号にすぎない。 その記号の意味するものは、人間の心身のあらゆる不調だ。メンタルヘルス不調。 そこには甘えも含んでいる。怠けも含んでいるかもしれない。 それはもはや、医学的な診断名ではない。 だから、うつ病の診断書を見たら、人はこう問わなければならない。 うつ病とは何か。 本書で繰り返し書いてきたこの問い。 しかし今回は意味が違う。 次のように言い換えることができる。 診断書に書かれている「うつ病」とは、何を意味する記号か。 それによって、周囲の人々の取るべき行動は違ってくる。(p.243)専門家が書いた診断書が、当てにならない現状。これが、多くの人に『「うつ」は病気か甘えか。』という疑問を抱かせてしまう原因となっていたのです。では、どうすればいいのでしょうか? 時間をかけて綿密に診察し、内因性うつ病の特徴が認められるかどうかを聴き出していく、 それが最も信頼できる診断法である。(中略) 「原因がない」「それまでのその人とは変わってしまった」はポイントであっても それだけでは診断できない。さらなる診察が必要である。 内因性うつ病は、心因性とは症状の質が違う。 「落ち込み」「不眠」「意欲低下」など、症状を単語に解消すると区別がつかなくなるが、 十分な経験ある精神科医が注意深く診れば、違いが確かにある。 これは講堂で教えるのは無理で、 臨床実習や臨床研修で人間を肌で見てはじめて身につく技術である。(p.275) もし内因性のうつ病だったら、抗うつ薬で治療することができ、 自殺を防ぐことができたはずだということである。(p.277)専門家である精神科医の能力や姿勢が問われるということでしょう。そうでないと、本当に「うつ病」の人たちまで、世間から疑惑の目で見られ、さらに苦しむことになってしまいます。そして、私が本著で知ったのが次の理論。 うつ病になるかならないかは、 ストレスの強さと個人の脆弱性という二つの要因のバランスで決まる。 ストレスが非常に強ければ、個人の脆弱性が小さくてもうつ病になる。 逆に個人の脆弱性が大きければ、ストレスが小さくてもうつ病になる。 これをストレス脆弱性理論と言う。 最近のうつ病裁判の判決文に必ず引用されている理論である。 ストレス比例理論は誤りだが、 ストレス脆弱性理論は、精神医学界でも正しい理論として広く認められている。(p.303)その他にも、人を助ける仕事に付きまとうヒポクラテスバイアスや技術者に付きまとうハンマーバイアスも、本著で知ることが出来ました。また、本著に登場した、笠原嘉さん著の『軽症うつ病』は、機会があれば読んでみようと思っています。
2014.09.29
コメント(0)
-
ガダラの豚
1993年3月に出版された、中島らもさんの作品で、 第47回日本推理作家協会賞を受賞した、598頁に及ぶ大作。 『今夜、すべてのバーで』や『牢屋でやせるダイエット』 とは違い、 純然たるエンターテイメント作品かつコアな労作。 超能力とトリック、アフリカの呪術、そしてバイオレンス。 得意分野の麻薬にアルコールを絡めながら、各キャラが見事な大活劇を演じる。 かなりのボリュームの作品にもかかわらず、一気に読み進めさせる筆力はスゴイ。 中島さんが、頭脳明晰で素晴らしい才能の持ち主だったことが、強く伝わってくる。それでも、やっぱり一つの作品を、きちんと終わらせることは難しい。大作になれば大作になるほど、読者の各キャラへの思い入れも強くなるので、多くの読者の共感を呼ぶエンディングを創造することは、至難の業。予想外の放置……村上さんの手法も頷ける。
2014.09.26
コメント(0)
-

精神疾患は脳の病気か?
何年か前に、本著のタイトルに興味を持ち、読もうと思ったことがある。 しかし、実際には長い間手にすることなく、やっと今回読むことになった。 だが、それで正解だった。 もし、何年か前に、本著を手にしていたら、きっと頓挫していただろう。 本著の副題は「向精神薬の科学と虚構」。 今年『ヒーリー精神科治療薬ガイド』や『精神科の薬がわかる本 』、 『なぜうつ病の人が増えたのか』等を読んだが、それらの予備知識がなければ、 薬学が専門ではない私には、本著はとうてい理解できなかったと思う。本著の内容については、「監訳者あとがき」に適確に述べられている。 本著は、精神疾患は脳の病気であるという近年の精神医学が拠って立つ根本命題に挑戦し、 それが虚構である可能性を指摘している。(中略) 本書の言うところのいわゆる生物学志向の高い精神科医の一人である監訳者も、 強いインパクトを受けた。(中略) 精神科医のみならず、精神医療に携わる者や精神薬理学の研究者から、 患者さんとご家族まで、一読に値するだろう。 特に、精神科医には必読の書と言ってもいいのではないかと思う。(中略) ただし、本書に詳細に書かれている薬物療法の否定的側面だけを メッセージとして受け取って欲しくない。 本書は、著者も言うように 薬物療法の有効性を否定しようとするものでは決してないのである。 むしろ、薬物療法に偏るのではなく、 精神医学はもっと豊かなものであるというメッセージが含まれている。 本書で特に読み応えがあるのは、向精神薬の発見からプロモーションに関する歴史である。 (p.319)監訳者お薦めの部分では、初期の向精神薬のすべてが、偶然に発見されたことに驚かされた。精神疾患に有効な治療法がなく、薬の必要性が高かったので、それらは採用されたのである。うつ病の人には、セロトニンとノルアドレナリンの欠乏があると言われているが、執筆時点では、患者の脳のそれらの濃度を測定することは出来ず、あくまで推定だ。 神経化学と薬の作用の神経薬理の知識は大いに増したが、 理論のほうはここ50年ほとんど変わっていない。 現在までに、薬理学的知見や技術が大いに進んだ。 ところが情動に関する生化学的研究は、 脳に全部で100以上あると推定される神経伝達物質のうち、 せいぜい3つか4つのものとの関連にかぎられている。(p.145) どの精神障害であっても、 原因や薬の作用メカニズムはわかっていないというのが本当のところだ。 それにもかかわらず、精神障害は生化学的なバランスのくずれによって生じるという理論が、 広く受け入れられている。(p.217)そして、これに関連して、監訳者は、こう記している。 アミン酸仮説では、脳の障害による構造的変化は想定しておらず、 機能的な変化を想定している。 しかし、MRI画像などの技術の急速な進歩により、 うつ病は脳の構造的変化をともなうのではないかという知見が蓄積されてきた。 うつ病は脳の機能的変化である、 という考え方から器質的変化である、という方向にシフトしてきている。 こうした背景のもと、 ストレスホルモンの受容体を標的にした抗うつ薬の開発などもさかんに行われており、 製薬会社がたんにセロトニンなどのアミンにこだわっている時代はやはりすぎさりつつある。 (p.321)上記の文章が書かれたのは、2008年1月。ここで述べられている「脳の構造的変化」とは、「神経細胞新生仮説」に繋がるものなのだろうか?その辺りは、私には分からなかった。 次に興味深かったのが、精神障害の治療法をめぐる二つの派閥の勢力争い。『うつに非ず』や『精神科医が狂気をつくる』で記された対立が、ここでも紹介されている。 精神障害の治療法を比較検討する研究はすべて批判の対象となりうる。 たとえば、精神療法が効き目が小さいとする研究が出ると、 それは経験不足の精神療法家が行ったからであり、結果はあまり当てにならないと言われ、 薬物療法があまり有効でないと結論する研究には、投与量が適切でないとか、 最新の薬が使われなかったという具合に批判が出る。 薬の有効性を疑う人たちは、薬の副作用や、 再発を防ぐためにずっと薬を投与しつづけることの危険性を口にする。 精神療法に批判的な人は、自殺などの好ましくない結果があると、 不適切で効果のない精神療法のせいだと批判する。(中略) 様々な治療法についての研究の行われ方、結果と評価の受け止められ方は、 薬を処方できる精神科医と 処方のできない心理士やソーシャルワーカーの間の縄張り争いを反映している。(p.279)そして、本著の中で、私が最も考えさせられたのが、次の記述。精神障害の治療について、核心を突いたものだと思った。 精神障害の患者と家族は、彼らが抱える問題が 精神的なものではなく身体的なものであると考えたがる傾向がある。(中略) 精神障害が好まれない大きな理由の一つは、精神障害と診断されると スティグマ(社会的烙印)をともなうことになるのではないかという危惧である。 精神的問題は、その人が弱い人間であり、 問題を克服する努力が足りない証拠だと信じる人が、いまだにたくさんいるのである。 それはちょうど、アルコール依存症の人を、 意志が弱く道徳心に欠けると非難するのと同じである。 精神障害であると診断されると、 患者の家族は自分たちが非難されているように感じることがよくあるし、 実際、家族が違った接し方をしていたら問題は生じなかったかもしれないと考える人もいる。 その上、もし問題が生化学的なものだということになれば、 薬で治すことができるように思えるし、 さらにまた精神療法家にも誰にも、個人的なことをさらけ出したくない人も多い。 問題が身体的なものであるならば、その必要もないのである。(p.285)
2014.09.24
コメント(0)
-

プロ野球構造改革論
岡田彰布氏の著作は、これまでに何冊か読んでいるが、 今回は、これまでのものに比べ完成度が低いような気がした。 「もう少し、丁寧に推敲して文体を整えれば良いのに……」と何度も思った。 何かの事情で、出版を急ぐ必要があったのだろうか? テープ起こしをしたことがある人なら分かると思うが、 話をしているときというのは、思っている以上に同じ内容を繰り返し述べている。 さらに、書き言葉とは違う、独特の言い回しもある。 それらを、岡田氏の特徴として、今回のライターさんは、そのままにし過ぎている。 まるで、スポーツ新聞のインタビュー記事を読んでいるような感じがした。さて、表現の方は、そういう風にシックリこないものを感じたが、内容については、岡田氏の行動や考えていることがよく分かった。選手会長として岡田氏が取り組んできたこと、そして、今後、選手会が取り組んでいくべき重点は何なのか。さらに、チームやグラウンド、試合への思い、それらが、立場によって、見る観点や考える観点が変わること。そして、プロ野球30球団構想。実現すれば、とても面白いと思った。
2014.09.22
コメント(0)
-

今夜、すべてのバーで
1991年3月に出版された、中島らもさんの作品。 第13回吉川英治文学新人賞、第10回日本冒険小説協会大賞特別大賞を受賞。 自身の体験に基づくお話しであるだけに、 その内容や描写は、リアリティに溢れている。 もちろん、このお話しはフィクションである。 しかし、その根っこには、著者の本音がある。 なぜ、酒を飲むのか。 それは作品全体を通じて、強烈に発散され続ける。そして、ドラッグについても。 アメリカはいざしらず、日本の政府にはその「資格」がある。 ガンの元凶である煙草を専売し、公営ギャンブルでテラ銭をかせぎ、 酒税で肥えて太ってきた立派な「前科」があるからだ。 ギャングにドラッグの利権を渡すくらいなら国が汚名をかぶって管理すればいい。 そしてその利益の何十分の一かを、中毒者たちの療養に還元すべきだ。 日本の政府には、ドラッグ常用者を逮捕する資格はない。 アル中を量産している形而下的主犯は政府なのだ。 犯罪者に犯罪者を逮捕する資格はない。(p.119) タバコ、酒に比べれば、ヘロインもコカインも物の数ではないと言える。 ましてや、常習性のないマリファナやハッシッシなど 子供のキャンディみたいな存在でしかない。 おそらく百年たってから今の日本を法律や現状を研究する人は、 理不尽に首をひねるにちがいない。 タバコや酒を巨大メディアをあげて広告する一方で、 マリファナを禁じて、年間大量の人間を犯罪者に仕立てている。 昔のヨーロッパではコーヒーを禁制にして、違反者をギロチンにかけた奴がいたが、 それに似たナンセンスだ。 まあ、いつの時代でも国家や権力のやることはデタラメだ。(p.121)このお話のエンディングは、主人公・小島が、さやかという女性とバーのカウンターで、ミルクで乾杯をするシーン。このシーンを、著者はどんな思いで書いたのだろうか。これは、著者の本音だったんだろうか。
2014.09.22
コメント(0)
-

マンガで分かる心療内科(7)
今巻は「連合弛緩」「真の自尊感情」に加えて お決まりの性的問題としては、「夢分析」と「セックスレスの治療法」。 そんな中に「光トポグラフィー」まで登場するといった守備範囲の広さは、 この作品自体が「言葉のサラダ」状態?(本当は一応メンタル関連事項です)。 そんな中でも「第64回 うつの人への最高の接し方」は、 基本姿勢について、よく伝わっていると思います。 もちろん「Y医師のよく分かる解説」は、ぜひとも合わせ読んだ方が良いし、 本当にうつの人に関わる機会があるなら、もう少し詳しい本を読んだ方が良いです。さて、私が今巻で一番興味を持ったのは「第69回 ストレスは数値にしてみよう」。精神科では、やたら「何%位ですか?」という質問をされることが多いと思っていたのですが、その理由が分かり、「なるほどな」と思いました。”all or nothing"の思考回路に陥らせないようにするためだったんですね。でも、自分の気分や感情を数値化するというのは、結構難しいものです。まず、どれだけの状態を100%とするのかで悩んでしまいます。「5段階でいうとどれ位ですか?」という質問紙への回答でも、「3か4位なら無難かな……」と、いつも思ってしまう私です。
2014.09.16
コメント(0)
-

マンガで分かる心療内科(6)
第53回「人間にとってもっとも大きなストレスとは?」 答えは「孤独」だそうです。 しかし、悪意をもって関わられるより、無視された方がマシな気も…… それも「投影」と考えれば、やりすごせますか……でも、きついですよね…… 第55回「自殺のサインの見分け方」 これは、ギャグに埋もれることなく、上手く伝えていると思いました。 第60回の「ハインツのジレンマ」や第61回の「モーニング・ワーク」も 「なるほどな」と言える、良いお話しだったと思います。そして、今巻の中で、私が最も印象に残ったのは、「第57話 パーソナリティ障害って何ですか?」。中でも代表的なものとして「境界性パーソナリティ障害」が紹介されています。その特徴は、 1.二極思考 ものすごく幸せであるといいうプラスの気分と ものすごく不幸であるというマイナスの気分を揺れ動く 2.対人関係の障害 別の人にたいしても「境界」があるように プラスとマイナス両極端のイメージを揺れ動きます 3.自傷・衝動行為 自分に対して「境界」のようなキズをつけるように 衝動的に自分をいじめる行為をすることがあります20代に多く、8割が女性というこの障害、30代なかばを過ぎると改善に向かうことが多いとされているそうです。また、アメリカの調査では、この障害と診断された人の40%が、1年後には診断基準を満たさなくなるとも。「一生ものではないので悩みすぎないで」ということのようですが、なかなか、その期間中の対応は難しそうです。周囲の接し方としては、ハッキリ境界を決めて、できること・できないことを明確にするよう説明されていますが……やっぱり難しそう。
2014.09.16
コメント(0)
-

マンガで分かる心療内科(5)
今巻で、まず興味深かったのは「投影」について。 心理テストとしては面白いのですが、『あなたがもっとも「嫌い」と答えた人物は あなたがもっとも「うらやましい」と感じている人物なのです』と断言されると、 「そうかなぁ……」というのが、私の本音です。 「嫌い」は「好き」や「うらやましい」のウラ返しのこともあるでしょうが、 全部が全部、そうとは言いきれないような気がします。 確かに、誰かに攻撃されたとき、「嫉妬している」とか「うらやましいと思われてる」 というふうに考えることができれば、少しは気が楽にはなると思いますけれど。それと、今巻は「うつ」関係の内容が多かったです。「PMS」や「双極性障害」「エモーショナル・ディスクロージャー」「認知的斉理論合性」についての説明と「ガヴェインと老婆の物語」。最後のお話しは、なかなか感動的なものですが、ちょっと心配も。というのは、「Y医師のよく分かる解説」には、ちゃんと「常に相手の判断に任せればいいというわけではありません」として、「自殺したい」「もう仕事をやめたい」「もう離婚したい」という人に「あなたの判断が一番だから」と言うのはあまり良くないと補足しています。心配になるのは、この補足部分を、皆が皆、ちゃんと読んでくれるかどうかということ。マンガ部分だけ読んで、文字がズラッと並んでいるこの部分をスルーされると、間違った対応をとりかねないのでは?(読者層からすると、その可能性が結構ありそう……)私としては、マンガの中に、そのことも盛り込んでおいて欲しかったなと思いました。
2014.09.15
コメント(0)
-
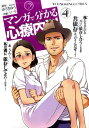
マンガで分かる心療内科(4)
今巻は、フロイトにキュープラー=ロスといった有名どころが登場。 特にフロイトは、「錯誤行為」の箇所でスゴイ露出度ですが、 これでは、イメージ悪化は免れない展開ですね。 アルフォンス・デンケンの名は、今回初めて知りました。 その他、「摂食障害」や「認知症」といったものの説明に加えて、 「メンタルクリニック」がどんなところかを紹介したり、 「カウンセリング」における質問のしかたについて解説してくれています。 「睡眠時無呼吸症候群」も、興味深いところでした。そんな中、私の最も印象に残ったのは「夫婦関係で、うつにならない方法」の次の記述。 実はアメリカの心理学者であるトラフィモウらは400名の大学生にたいして 「人にしてあげた親切な行動」「人にしてもらった親切な行動」を それぞれ書き出させました このとき思い出したエピソードの数はどれくらいの差があったと思いますでしょうか? その比率なんと35対1 「人にしてあげた親切な行動」を35倍も多く覚えていたのです(中略) 実際に「親切を受けた状態」というのは「借りがある」ということにもなり 心の重荷になります だからこそ すぐに忘れたりしてしまうわけです 逆に「恩を売った」というのは 心地いいことなので 強く心に残ります なるほど……人の記憶は 都合がいいんですね……(p.110)確かに、人間は自らの存在を護るためとはいえ、誰もが「自己中心的」な所があるのでしょう。
2014.09.15
コメント(0)
-

マンガで分かる心療内科(3)
今巻では「強迫性障害」や「非定型うつ病・新型うつ病」と共に 「社会不安障害」「妄想」といった、かなり深刻な精神障害について紹介。 もちろん、「ED」や「フェティシズム」といった性的な事柄や 「過食症」「ニコチン依存症」にも言及しています。 相変わらずのダジャレ&お色気路線のギャグマンガですが、 まぁ、ターゲットとしている読者層と掲載されている漫画誌からすれば、 いたしかたないとは思います。が、やはり少々(いや、かなり)違和感を感じます。 この漫画を読む人たちにとって、紹介されている知識は役に立つのでしょうか?まぁ、そう硬いことを言わずに、ギャグマンガとして楽しめば良いと思うのですが、中途半端で曖昧な知識の伝達が、かえって面倒な問題を引き起こさないかと、少々心配。もちろん、「Y医師のよく分かる解説」では、文章できちんと説明がなされているのですが、そこは、読み飛ばしてしまう読者も、結構いるのではないかという気もします。そういう人たちにとって、この漫画を読んだ後、頭の中に何が残るのか……色んな人たちに心療内科について知ってもらうというメリットは大きいと思いますが、その知識が、どんな人たちに、どんな使われ方をすることになるのか?扱っているテーマが、深刻な問題を含んでいるだけに、考えさせられます。でも、取り敢えず、発行されている続巻については、読み続けるつもりです。
2014.09.15
コメント(0)
-

マンガで分かる心療内科(2)
そもそもこの作品は、どんな人たちをターゲットにしているのでしょう? 深刻な問題を、こんなギャグマンガにしたら、気を悪くする人もいるのでは? ということで、この作品のターゲットについて調べてみることに。 そして、その答えはすぐに見つかりました。 最終ページに「ヤングキング 平成22年第12号~第19号掲載作品」との記載。 そして「ヤングキング」というのは、このホームページを見ればわかるように、 「ヤンキー系漫画誌」と形容されることがあるもののようです。 かなり違和感を感じるけれど、深刻な精神疾患の人が目にする機会はなさそう。いやいや、しかしながら、本著のようにコミックスになってしまえば話は別。ヤンキー系漫画を好む若者たちだけが、手にするとは限らないでしょう。それに加え、この作品はWebコミック版として、ネット上で誰でも見ることが出来る。例えば、本著「対18回 露出症の治療法は?」だと、こんな感じ。見比べてみると、Web版では「第六回 露出症の治療~どこからが病気?」となっており、コマ割もセリフも違っていて、コミックスより簡略化され、ギャグも控えめです。さすがに、ゆうメンタルクリニックについて調べようとホームページを訪れた人に、コミックスの内容のままでは、刺激が強すぎ、気を悪くする人も出そうですから。 ***それでも「第24回 後悔を抱えたときの たった一つの考え方」は、読んでいて「なるほどなぁ」という内容でした。 たとえば想像してください 朝に1万円拾った! 夜にその1万円をなくしちゃった! このときあなたは『プラスマイナス0だ』と思えますか? おそらく なんでなくしちゃったんだろ! なくさなかったらトクしてたのに!くやしい! このように思うのではないでしょうか このように同じ価値の場合『プラスの喜びよりもマイナスの悲しみの方が大きい』のです さてここで二択の話です 人間が何かの選択で迷ったとき 基本的に『同じ価値』だから迷うのです 明らかに片方の価値の方が高いと分かっていれば迷いません ここで『どちらかを選ぶ』というのは 『もう一方を失う』ということになります ここで先ほどの価値関数では 『同じ価値の場合 得た喜びより 失った悲しみの方が強い』わけですから 人は何かの選択をしたとき「必ず後悔する」ようにできているのです! 同じ後悔するのなら とにかく『自分で決めて その方向に進む』方が よっぽどいいんです だから心配しないでください 『やり直す』必要なんかないんです あなたの選んだ行動なら それは決して間違っていないんですよなかなか説得力がある説明だと思いませんか?まぁ、私は、あまりくよくよと後悔することがない方だとは思っていますけれど。
2014.09.14
コメント(0)
-

マンガで分かる心療内科(1)
当事者にとっては深刻な問題である精神疾患等について、 ギャグマンガで紹介していくという、大胆不敵な作品。 原作は、2008年に「ゆうメンタルクリニック」を開院したゆうきゆうさん、 作画はソウさんで、現在11巻まで発行されている。 本巻では、「うつ」についての記述が最も多く、「SSRI」にも触れている。 また、「幻聴」や「認知症」に関するものや「診療費」、 さらには、「ロリコン」や「ED」と、幅広いテーマが扱われている。 もちろん、紙幅に限りがあるため、紹介される知識量はさほど多くない。それでも、うつ病の特徴的な症状として紹介されている心気妄想(自分は病気なのではないかと強く思い込むこと)、罪業妄想(自分は罪深い存在だと思うこと)、貧困妄想(自分は貧乏なのではないかと思うこと)の3つを、微少妄想(自分は小さい存在であるという妄想)ということを、私は知らなかった。また、第7回の「実は男は女になりたい」で示された男女共に「メリットが多いのは女性」だと思っているという調査結果は、意外だった。私は「メリットが多いのは男性」だと思っていたから、そう感じたのだけれど。でも、男性に「社会的に責任をかぶってしまうことが多い」というデメリットがあり、「ストレスや感情を外に出せない」ことから、うつになって自殺する率は男性の方が多いという説明をされると、「なるほどなぁ」と思ってしまった。
2014.09.14
コメント(0)
-

All You Need Is Kill(2)
今巻は、まず、リタ・ヴラタスキをメインに、お話が進んでいく。 「ギタイ」に両親を殺された彼女は、 3歳年上の難民女性のパスポートを盗み出し、防疫軍に入隊。 そして半年後、異質なギタイを倒してからループに巻き込まれたのだった。 周回を重ねる度に、そのギタイを護るギタイが増えていく。 前回の彼女の動きを憶え、それを押さえるため適確に増援を配置される。 彼女はループを抜け出すため、その仕組みを解き明かそうとする。 そして、ギタイのネットワーク全てを破壊しなければならないと気付く。タキオン粒子を出すギタイ・サーバのアンテナを破壊し、バックアップのギタイを破壊、そして、ギタイ・サーバ本体を破壊し、211周のループの後、彼女は初めての時からのループを脱出した。時のループを手に入れたリタは、ギタイに唯一対抗できる決戦兵器として、世界中を駆け廻り、戦い続けた。リタは、一度目の戦いで全体の被害を確認し、二度目の戦いで有利な戦況を展開した。しかし、ループを終わらせるには、誰かの死に目を瞑るしかなかった。そして3年後、リタはカイジに出会う。自分ではなく、彼がループしている世界で。それは、カイジの159回目のループ。その翌日、二人は初めて一緒にギタイと戦う。カイジは1回目の戦場で、偶然ギタイ・サーバを倒してしまったため、イレギュラーとして目を付けられ、ループに巻き込まれることになった。しかし、2~158回目にギタイ・サーバを倒したのはリタ。ループを終わらせるには、カイジがギタイ・サーバを倒さなくてはならない。カイジがギタイ・サーバのアンテナを破壊し、リタがバックアップを破壊、そして、カイジがギタイ・サーバ本体を破壊しようとした、その時……ループ……次は、カイジの160回目のループ。スカイラウンジでコーヒーを飲もうとしていたカイジとリタをギタイが襲う。そして、カイジがギタイ・サーバのアンテナを破壊、次にリタがバックアップを破壊……のはずが……リタはカイジに襲いかかってきた。リタは、何度もループを繰り返すうち、ギタイがアンテナから過去へ送信する電気信号を受けて脳が変質し、ギタイのアンテナと同じ性質を持つようになっていたのだった。そして、それは、カイジも同じ。 キャリア・ケイジというバックアップアンテナがある限り リタ・ヴラタスキはループを脱けられないし リタ・ヴラタスキというバックアップアンテナがある限り キャリア・ケイジはループを脱けられない ループを脱出できるのはひとりだけだカイジはリタを倒し、ギタイ・サーバをぶち壊し、残った敵を一掃した。 ***最後は、私の理解力が足らないせいなのか、分かったような分からないような、ちょっともの足らなさを感じるエンディング。ギタイとの戦いは、まだまだ続くようですが。
2014.09.13
コメント(0)
-

All You Need Is Kill(1)
明日、初出撃を迎える機動ジャケット兵、キリヤ・ケイジ。 彼は、人類を皆殺しにしようとしている「ギタイ」と呼ばれる化け物と 戦場で戦い、殺されたが、戦いの前日に蘇っていた。 その後も、死んでも死んでも同じ日に蘇る、即ちループ。 死ねば必ずループする。 記憶を引き継いだまま、出撃前日の朝に戻る。 どこで死んでも、どういう死に方をしても、同じ。 そういう世界に、彼は存在している。そのことに気付いたケイジは、この世界に反抗し、生き残るために戦いを続け、ガンメタリックレッドのジャケットに巨大なバトルアクスを携えた無敵の兵士リタ・ヴラタスキの戦いぶりを参考に、実戦で戦闘技術を高めていく。そして、158周目。最初の戦場で闘った敵に遭遇し、リタにも出会う。そして、彼女の口から発せられたのは、「おまえ、今……何周目なんだ……?」 ***映画化されてますが、まだ見ていません。なので、この作品を見るのは、本著が初めて。お話しの着想は面白いと思うし、小畑さんの絵も上手い。さて、次巻で完結ですが、どういう展開になるのか全く予想できません。
2014.09.13
コメント(0)
-

幽麗塔(8)
天野はドアの向こうに続く通路を発見する。 しかし、山科は死番虫に頭を拳銃で撃ち抜かれ、テツオを思いながら絶命する。 天野と沙都子は、遂に財宝へと辿り着くが、そこに死番虫が現れる。 その正体は、陣羽笛警部だった。 陣羽笛に襲いかかったのは文で、陣羽笛は文を倒したのだった。 天野は、拳銃で陣羽笛の顔面を撃ち抜き、崖下へと突き落とす。 そして、そこへ丸部とテツオが現れる。 テツオは、財宝で、男である天野の戸籍を手に入れたかったと告白する。それに対し、天野は戸籍は譲れないと答える。山科の夢であった「マイノリティーが差別されない社会」を作る運動を、自分が起こすために。そんな目標を持った天野から、テツオは離れていこうとする。一方、丸部はミイラ化した灰色の服を着た女と対面していた。それは、越後屋伊兵衛の最後の子孫・お夏。藤宮たつが屋敷を手に入れる前の当主であり、丸部が14歳の時に出会ってから愛し続けた女。そして、幽霊塔の内部から脱出した丸部のもとに現れたのはテスラ。その口から、丸部の実の娘の名が、藤宮麗子であることが語られる。丸部とテツオは、テスラ、Qと共に屋敷を出て行く。その後、沙都子は天野と共に行動する中で、丸部がお夏と対面した際に手にしていた桐で出来たへその緒入れに「輪田阿夏、丸部道九郎、命名れい」と書かれていたと告げる。それを聞いた天野は、途中で丸山巡査を加え、沙都子共に丸部とテツオの行方を追う。その際、天野は、彼が好きだった花園さんの元婚約者・三村に出会う。天野は、三村が今も花園さんを思い続けていることを知る。天野、沙都子、丸山は、テスラの祖父・ポール・レベルの足跡を辿り西宮へ。そこで、顔は牛で身体は人間の「件」についての情報を手に入れる。件の名が里見久枝であったことから、天野は久枝がQではないかと推理する。その久枝名義で、裏六甲に土地の登記があった。その頃、テツオは裏六甲にある、羊の置物の門をくぐった幽麗塔にいた。そこで、テツオは、死体の山を発見する。そこにステラが現れ、自らが蘇生させた死番虫をテツオに見せる。彼は両手両足を失い、モルヒネが効かぬほどの激痛を感じながら、年老いて寿命がくるまで、テスラによって、命を守られ続けるのだと言う。そして、そこに丸部が現れ、自分が何をしようとしているのかをテツオに語る。それは、丸部とテツオの脳みそを入れ替えること。丸部はお夏という女になりたかったのだ。そのために、お夏と寸分違わぬ美しさを持ち、臓器移植でも拒絶反応が出にくく、適合する可能性が高い血縁者・実の娘の麗子・テツオを探していたのだった。そして、お互いの心が望んでいる、異性の身体を手に入れ、二人で本当のセックスをしようともちかけるのだった。 ***今巻当たりで結末を迎えるのかと思っていましたが、そうではありませんでした。しかし、色んな謎が解明されてしまったので、お話しとしては、これ以上続けるのは難しそう。ですから、次巻では、そろそろ終了という気がします。しかし、何とも倒錯した世界です。
2014.09.13
コメント(0)
-

精神医療・診断の手引き
ネットで予約注文していたものが昨日届いたので、 早速読んでみました。著者は大野先生、 副題は「DSM-3はなぜ作られ、DSM-5はなぜ批判されたか」で、 2014年9月10日印刷、2014年9月20日発行となっています。 まず感じたことは『「うつ」を治す』などに比べると、 専門家でない私にとっては、読み進めるのにかなり労力が必要だったということ。 一般向けに書かれた書物では、大野先生の著作はとても丁寧で、読みやすいのですが、 本著は、専門的であり、内容ももちろん最新のものなので、私が知らないことだらけ。「DSM-5の概要とDSM-4からの変更点」などは、特に難しく感じました。それでも、DSM-3がつくられた経緯はよく分かりましたし、DSMによる過剰診療や過剰治療の問題や、DSM-5について、野村先生がどのように考えておられるのかも、よく伝わってきました。それに加え、認知行動療法について最新の情報が述べられていたことが、私にとっては、とてもありがたかったです。本著で紹介されている文献に当たったり、ネットのサイトを見て、さらに、勉強していきたいなと思っています。
2014.09.12
コメント(0)
-

最新脳科学で読み解く 脳のしくみ
2009年5月7日発行。 脳について、そんなに専門知識が無くても、 スイスイ読み進めることが出来ます。 そんなに難しい専門用語が頻出するわけでもないし、 説明の仕方も丁寧でわかりやすく、気楽に読めます。 これを一冊読めば、脳のしくみがわかるというよりも、 色んな最新知識を散りばめられ、こんなことがわかってるんですよ とうことを、あれやこれやと教えてくれる感じ。 本文とコラムを読む順番は、一工夫しないといけないと思いますが。 *** 「脳の成熟の遅れ」で青年期の行動を説明するのは魅力的な考え方で、 ジャーナリストらによって盛んに論じられている。 反抗、危険をいとわない行動、結果を無視する傾向などは青年期につきものだから、 ティーンエージャーの脳がまだ完成されていないということを示唆する研究に、 親たちが興奮するのも不思議はない。 非行は脳の成熟の遅れの結果だと考えれば、気持も軽くなるだろう。 親は悪くないし、子供も悪くない。 そしてなにより、成長するにつれて自然と解決する問題だってことだからね。(p.125)こんな感じで、全体を6つのブロック、31の章に分けて説明してくれる。色んなことが分かってきてるんだなぁと思うと同時に、まだまだわからないことだらけだというのも、伝わってくる。それほどまでに、脳の世界は、深く広い。
2014.09.11
コメント(0)
-
牢屋でやせるダイエット
麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕され、 22日間の拘置後、大阪地裁で、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた 中島らもさんが、拘置所での生活や裁判について、自ら綴ったエッセイ。 本著は、判決が出てわずか2か月余の、2003年8月1日に出版されている。 しかし、翌年7月に、飲食店の階段から転落して、全身と頭部を強打、 脳挫傷による外傷性脳内血腫のため、52歳で死去した。 コピーライターや作家として活躍し、人気を得たものの、 アルコールや薬物に依存し、精神疾患から逃れることは出来なかった。 *** これらの薬は、おれにとって命綱のようなものである。 おれには躁うつ病という持病がある。 一時期、精神安定剤の服用を中断していたが、 逮捕される少し前から再び処方してもらうようになっていた。 中断していたのは副作用がうっとうしかったからだ。(中略) ただ、躁うつ病というのはなかなか完治しにくい病気で、いつまた再発するかわからない。 再発予防措置という意味で、副作用に用心しながら服用を再開していたのだ。 さらに重度の不眠症がある。 ここ三十年というもの、睡眠薬、あるいはアルコールの力を借りないで眠ったことは、 ただの一度もない。 拘置所の中でまさか酒が飲めるとはおれも思わなかったが、 睡眠薬が取り上げられるとは予想外だった。(p.34)そして、アルコールや睡眠薬だけでなく、マリファナにも手を出す。らもさんは、裁判のときにまで、「大麻解放論」をぶった人である。 現在、マリファナはアムステルダムではフリー(ただし三十グラム以内)、 イギリスでは合法化、アメリカでは五、六州が合法化し、 その州数は増加する傾向にある。(中略) マリファナはとてもおだやかな平和な嗜好物で、緑内障に効くということも発見されている。 だいたいが、酒に酔っ払って人を殺したりケガをさせたりというのは無数にあるが、 マリファナで狂って人殺しをしたなんて話は一例もない。 マリファナの合法化は世界のすう勢なのだ。(p.117)現在、精神疾患において、薬物療法は欠かせないものだと思う。しかし、そこにアルコールが絡んでくると、事態は一気に深刻化してしまう。ましてや、麻薬や覚醒剤となると、その影響は計り知れないだろう。ちなみに、本著に登場する、らもさんの飼い犬の名前は「アスカ」だった。
2014.09.11
コメント(0)
-
精神科医ですがわりと人間が苦手です
2008年3月に発行されたけれど、今は古本しか入手できない。 香山さんの本は、たくさん世に出回っていて、 それらのうち、何冊かは私も読んだけれど、 精神科の医師としての自分について書いてあるものは、初めてかも。 本文中では、自身を「脱力系」としておられるけれど、 きっと、仕事の方は、日々シャキシャキとされているんだろうなと思う。 それは、診察室でも教室でも。 そのことは、本著で書かれている色んな場面での対応のされ方で伝わってくる。でも、香山さんの本当のところの興味・関心は、精神科医としての仕事の中にあるのではないようにも感じた。でないと、あんなに頻繁にマスコミに露出したり(最近は減ったように思うが)、あれだけの大量の著書を発行したりは、きっと出来ないだろうから。
2014.09.10
コメント(0)
-

雪の女王 七つのお話でできているおとぎ物語
先日『アナと雪の女王』を見ました。 そして、その作品のヒントになったのが、 アンデルセンのこのお話しと知り、 読んでみました。 でも、確かにヒントにはなっていると思いますが、 お話しとしては、全く違うものでした。 それより、宮崎駿さんにとって、このアニメ作品がの運命の作品と言われる理由が、 よく分かる気がしました。一読すれば、このお話しに登場する主人公の少女・ゲルダこそ、宮崎さんが生み出した、数々の作品のヒロインたちの原点だということに気付きます。そこで描かれる世界観も、共通するものです。『アナ雪』よりも、『宮崎アニメ』を知ることに繋がる作品でした。
2014.09.08
コメント(0)
-

親の認知症が心配になったら読む本
認知症とその対応について書かれた本。 このジャンルの本を読むのは初めてだったので、 とても参考になりました。 初心者にも読みやすく、分かりやすい一冊でした。 早期に発見して、受診をすすめ、検査を受ける。 そのために、予めどんな病気なのか、どんな症状が出るのかを知っておく。 そして、認知症と分かったら、介護に向けて、ケア態勢を整える。 その際、直面する事柄について、一つ一つ丁寧に説明がなされていきます。例えば、同じことを言ったり、食べてないと言い張ったり、徘徊したりするとき。また、ものとられ幻想、嫉妬妄想、収集癖、性的逸脱、失禁、暴力、落ち込み等々、以前の元気だった頃には考えられなかった行動に、どう対処すればよいのか、そのヒントが、ひとつひとつ紹介されていきます。また、これまでの生活を続けていける工夫をし、家にこもらず外出をする。食事・排泄・入浴は出来る限り自力でしてもらい、口腔ケアに気を配る。誤嚥(ごえん)や脱水症状、便秘等に注意する。日々の生活の中でも、気をつけなければならないことは多々あります。そして、介護保険の手続きやサービスの利用の仕方についても、とても丁寧に詳しく書かれています。そこで思ったのは、介護する側もされる側も、大変な時期が続くので、介護する側は、一人で抱え込まず、とにかく利用できるものは最大限利用するということ。そうでないと、双方共に不幸なことになってしまいます。そのためにも、やはりある程度の知識を持ち合わせていることが重要。今、その問題に突き当たっている人にも、これから突き当たりそうな人にも読んでみて、読んでおいて、損はない、お薦めの一冊です。
2014.09.06
コメント(0)
-

うつ病の人の気持ちがわかる本
2011年6月に第一冊発行。 著者は大野先生ですが、『「うつ」を治す』を読んだ方なら、 スイスイ読み進めることができると思います。 逆に「うつ」関係の本を初めて読む方にも、 ポイント毎に上手くまとめ、やさしく書かれているのでお薦めです。 「うつ」関係の本は、何冊か読んでいても、 それぞれの本で、やはり新たな気付きがあります。 本著では『「休み方」がわからない』(p.32~)や 「精神疾患は外見からはわかりにくい(p.34~)」が、そうでした。また、「うつ」になった人にとって、「将来の展望がない」ことが、さらに悩み落ち込む原因となること。治療や経済的なこと、復職に向けての動き等について、分かっている限りのことを示してもらうことが出来れば、それだけで、本当にありがたい。さらに、「孤独」がうつ病の大敵であること。入院してしまえば、主治医の方をはじめ様々な方とコミュニケーションをとる機会があるので、そうでもないのですが、実は、自宅療養に入ってからの方が、その機会が減ることもあることを、知ってもらいたいと思いました。
2014.09.05
コメント(0)
-

うつに非ず
2013年9月11日に第一冊発行。 著者は、精神科医でノンフィクション作家の野田先生。 私が、これまでに読んだ「うつ」関連の本の中でも新しいもののひとつであり、 最も激しいタッチで記された一冊。 著者は、アメリカ精神医学協会によって書かれた DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)が、 高橋三郎、大野裕、染矢俊幸の三氏によって日本語に翻訳されるとき、 「精神障害」が「精神疾患」に詐訳されたと指摘する。 その影響は大きく、薬の添え書きでも、厚生労働省の公文書でも 精神疾患と書かれるようになっている。 曖昧な「精神障害」を疾患であると思い込ませ、 「精神疾患」の診断方法が確立されたかのように誤解させる詐術が用いられてきた。(p.39)また、田島治(私が読んだ『ヒーリー精神科治療薬ガイド』の監訳者)氏の論文を引き、抗うつ剤の作用について、その危険性を説く。さらに、冨高辰一郎氏の『なぜうつ病の人が増えたのか』を引いて、製薬会社による抗うつ剤プロモーションに言及する。 製薬会社の戦略の要諦は、精神医学界における有力者への働きかけである。 彼らが広告塔となった抗うつ剤プロモーションの帰結として、 いまや一部の精神科医は、うつ病とは脳の神経内分泌の欠乏、 主にはセロトニン欠乏症だと信じるに至った。 ビタミン欠乏症と同じような発想で、 薬さえ飲んでいれば良くなると思い込んでいる医師たちがいる。(p.66)そして、福島第一原発の事故により、避難を強いられた末に自殺した人たちに対して、厚生労働省の「精神疾患で薬を飲んでいなければ災害関連死とは認められない」とする姿勢、東電の「事故により病気になって自殺したと証明されなければ賠償しない」という姿勢を、強く批判している。また、「自殺未遂で運ばれた病院の怠慢」(P.130~)で描かれた光景や、「自死遺族をさらに苦しめる」(p.133~)で描かれた、自死後に生ずる、遺族への、家主や不動産関係者からの多額の金銭の取り立ては、まさに驚くべきものであった。そして、「精神科医を育てる環境の貧しさ」(p.148~)で述べられている精神科医療を担っている医師たちの力量の実態が、現在の、様々な弊害を生み出す根源となっている。 近年では、とりわけアメリカの精神医学において大脳の生化学的研究が盛んになっており、 日本でもその分野の研究者の論文が評価され、教授に選ばれやすい。 元もと精神病理学や社会精神医学など学んだこともない身体科や基礎医学の教授が、 精神医学の教授を選考するのである。 すると大脳の生化学の研究者が、 臨床的な精神医学や精神病理学もできるかのように振る舞う。 こうして臨床のできない教授のもとで、 臨床的なトレーニングを積んでいない医師たちが育っていく。(中略) 近年では、医学部卒業後の2年間の研修は希望する市中の病院で一通りの診療科を回ればすむ。 臨床精神医学の研修をほとんど受けていない医師が、 うつ病キャンペーンによって精神科の外来患者が増えているから経済的に成り立つと考え、 クリニックを開業している。 こうして多くの問題が起きている。(p.148)さらに、「製薬会社が学会を作る」(p.150~)と「抗うつ剤ムラの精神科医たち」(p.152~)とを読むと、現在の精神医学界の内部で、大きな対立があることに気付く。 日本うつ病学会をはじめ、こうした学会の理事や委員には、 樋口輝彦氏(独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長)、 大野裕氏(同センター認知行動療法センター長)、 野村総一郎氏(防衛医科大学校病院院長)らの常連の医師が名を連ねており、 理事長や委員長は持ち回りかと疑われるほどである。(中略) この種の医師たちは、1990年代以降のうつ病キャンペーンにおいて 厚生労働省のなかに拠点を設けることも怠らなかった。 近年、うつ病をはじめとする精神科関連の研究には文部科学省の科学研究費だけではなく、 厚生労働省の疾病研究としても多くの予算が投じられるようになっている。 そうしたカネとポストを精力的に動かしている精神科医グループがいるのである。 前述のような学会を作る人たちとメンバーは重なっている。(p.152)海堂尊作品もビックリのドロドロとした世界である。
2014.09.05
コメント(0)
-
ONE PIECE 巻75
ウソップの奇跡の一撃でシュガーが気絶、 そして、オモチャにされていた人々は、元の人間の姿へと戻る。 一方、コロシアムの戦いを勝ち抜き、メラメラの実を手に入れたのは、 ルフィーのもう一人の兄、革命軍参謀総長・サボだった。 ルフィーとゾロ、ローは、ドミンゴのいる王宮を目指す。 ドミンゴは、それを阻止すべく、「鳥カゴ」で島を覆うと共に、 ルフィーたちに懸賞金をかけ、民衆に首を獲れと迫る。 しかし、コロシアムたちの猛者たちは、ルフィーと共にドミンゴを目指す。途中で立ちはだかったドンキホーテファミリー最高幹部・ピーカにはゾロが、海軍本部大将・藤虎にはサボが立ち向かう。そして、ルフィーとローは、王宮の一段下のひまわり畑へ、ロビンやレベッカも小人族と共に、ひまわり畑を目指す。今巻は、お話しがグイグイ進みましたが、次巻は、壮絶な戦いの連続になりそうな予感。まだまだ、ドミンゴは、そう簡単にブッ飛ばすことはできなさそうですが、ドミンゴの弟・コラソンを慕うローとの因縁の対決は、今から楽しみです。
2014.09.04
コメント(0)
-
私、こんなに「うつ」なんです。
せっかく、いいお医者さんに巡り会えたのだから、 ちゃんと言うことを聞いて、治療を進められていればなぁ……と とても残念に思いました。 親身に支えてくれる友人もおられただけに、その思いは一入です。 せっかくの薬も、量を守らなかったり、 アルコールを飲み続けると、こんな風にもなってしまうものかという ある種の怖さを感じました(絶対に真似をしてはいけません)。 最初に処方されたのが、パキシルにグッドミン、ナウゼリンなんですから……。副題が「そして、本当に知りたかった薬のこと」とあるように、著者のこれまでの様子を描いたマンガの後は、著者からの質問を受けての、東大の澤田先生による解説。こちらの方が、私には有益でした。まず、「人によって薬の効き方に違いがあるのはなぜですか?」という質問に対して、 1.遺伝子の違い(個人の体質の違い) 2.他の病気の有無(肝障害、腎障害などがあるかどうか) 3.他に飲んでいる薬の有無(薬の飲み合わせ) 4.生理的状態の違い(年齢、性別など) 5.食生活の違い(食事、飲食物など) 6.個人の嗜好の違い(タバコ、飲物、サプリメントなど)(p.164)「人それぞれ違うんだから当たり前」と、疑問にすら感じていなかったのですが、こうやって説明されると、「なるほどな」という感じです。その他、「モノアミン仮説」という言葉や「神経細胞新生仮説」、BDNF、海馬での神経新生がうつ病の改善に関係しているらしいことも、本著で知りました。まだまだ、勉強しなくてはならないことがたくさんあると、強く思いました。
2014.09.04
コメント(0)
-

精神科の薬がわかる本
精神科で使われる薬剤については、 これまでに『ヒーリー精神科治療薬ガイド』を読みましたが、 それは2009年7月に発行されたもので、 そんなに古くもないけれど、新しくもないものでした。 というわけで、最新の薬剤の知見が知りたくて購入したのが本著。 第2版は2011年6月に発行されたものです。 NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)については、 その存在を、私は本著で初めて知ることになりました。しかし、本著について素晴らしいなと思ったのは、そういった新しい薬剤を知ることが出来たということよりも、それぞれの薬剤の処方の仕方だけでなく、その対象となる症状の様子や副作用について、著者の臨床体験に基づき丁寧に書かれていること。おかげさまで、これまで得ていた「うつ」等の知識に、脳の働きや薬剤の知識を絡めて考えることが出来るようになりました。また、「てんかん」や「認知症」等の老年期の障害についても知ることが出来たので、読んで本当に良かったと思いました。ただ、「抗不安薬」についての記述は、ちょっとあっさりしているかなと感じました。まぁそれは、『ヒーリー精神科治療薬ガイド』が、「不安」について、結構、紙幅をとって、細かく書かれていたから、そう感じてしまうのかも知れませんけれど。
2014.09.03
コメント(0)
-

精神科・心療内科の上手なかかり方がわかる本
「この本の存在をもっと早く知って、読んでいれば、 色んなことがどれだけスムーズに行っただろう……」と後悔させられる程、 「うつ」になった人が、本当に必要とする各種基本情報が簡潔にまとめられ、 読みやすく、分かりやすい、奇跡のような完成度の一冊。 これまで、私が読んできた「うつ」関係の本の中でも、 現時点では、間違いなく手元に置いておきたい本のNo.1。 「うつ」になったとき、これから何をどうすればよいのかという道筋が、 スッキリ、くっきり示されています。そして、本著を読んで、全体的な流れを把握した後に、各事項について、より詳しい書籍に当たっていけば、なお良いかと。ただ、「うつ」になってしまった当事者は、自身でこの本を見つけ出し、冷静に読み進められる状況にはないと思われます。ですから、家族や職場の方、友人など身近な人が、とにかく本著を手にし、ここに書かれた情報を駆使しながら、支援して頂ければと切に願います。「うつからの脱出」のスタートは、まず信頼できる医師に出会うこと。そのために、大いに手助けとなる一冊です。
2014.09.02
コメント(0)
-

叱られる力
『聞く力』の第二弾。 これもまた、楽しませてもらいました。 前回よりも、1つのテーマについて、紙幅を大きくとって書かれていますが、 その点をどう評価するかは、人によって違ってくると思います。 それにしても、佐和子さんの父上・弘之氏の暴君振りと、 それにずっと耐え続ける佐和子さんと母上…… 今の家族では、ありえないだろう光景に驚嘆致しました。 古き時代の日本の家族です。そして、現代の家族というのは、おおよそ次のような感じ。 親が優しくて、何でもしてくれて、親の家がこよなく居心地がよかったら、 家を出たいとは思わないでしょう。 どんなに遅く帰ってきても怒らないし、寝坊しても文句も言わず、 おいしいご飯を作って、選択も部屋の掃除もして、経済的援助も惜しみなくしてくれる。 稼ぐお金はすべて自分のお小遣い。 そんな親元にいたら、面倒な恋愛をして、 あれしろこれしろとわがままを言う女の子(男の子)と一緒に暮らすなんてことは、 できるだけ先延ばしにしたいと願うのも無理はありません。(p.121)でも、これで良いのか、親も子も?まぁ、「これでいいのだ!」という人が多いので、こういう現状になってるんでしょうけれど、それでも、せめて次の点だけは、何とかお願いできないものでしょうか。 真っ当なことを言うようで少々こそばゆいですが、 金額のいかんに関わりなく、子どもを養うにはお金がかかる。 養育の義務があるとはいえ、親にそれだけの負担をかけている以上、 子どもが子どもなりの礼を尽くすのは当然ではないかというのが、 基本的な私の考えです。(p.137)
2014.09.02
コメント(0)
-

うつ病をなおす
野村先生の本は『精神科にできること』を読んだばかりですが、 立て続けに読むことになりました。 本著は2004年11月発行ですから、2年余り新しいものになりますが、 それでも、今から10年も前に書かれた書籍です。 本著では、様々なうつ病について、それぞれケースを示し、 分かりやすく説明してくれています。 私の「うつ病」関連の読書も、かなり進んできたので、 登場するケースも「なるほどな」と理解が早くなってきました。それでも、新しい発見や再確認させれることは、まだまだ多いです。例えば、うつ病が「いかにも元気なく」見えないことが少なからずあるということ。 うつ病者はしばしば「必死で無理をして」「まわりにウツを気づかせないようにし」 「その必死さがばれないように、また必死で努力する」という性向があるので、 結構動き、結構明るくしているように見えることがあるのだ。 もちろん、これはまだ初期の段階でのみ可能なことであって、 重症になるとそんなことは不可能になってくるが、 いずれにしろうつ病理解のためにはこのことを知っておく必要があろう。(p.56)これは、私自身は心の底から納得しました。人は、他人の心の中を覗き見ることはできませんから、外部に表れてくる表情や動作、声などからその状況を判断するしかありません。そして、外部に現れてくる微妙なものに気づくことができる人は、案外少ないものです。また「不登校とウツの境界」については、「環境への不適応の悩み」のせいでなく、不眠が続き、とくに朝が目覚めにくく、昼過ぎからは元気な「リズムの障害」があり、「抗うつ薬が効いた」場合は、「子どものうつ病」と判断されるという記述には、「不登校」に関わる際は、頭に入れておかねばならないことだと思いました。 治療法の研究は世界的に非常に盛んで、確実に進歩したことは断言できる。 ただ、まだ完全ではない。それは脳の病気としてのうつ病の病態生理が、 根本的に未解明だからである。(p.114)これは、10年前も現在も同じ状況。まだまだ、分からないことだらけだと、再認識させられました。そして、本著では薬物療法の「アルゴリズム」については、これまでに私が読んだ、どの書籍よりも丁寧に説明してくれていました。
2014.09.01
コメント(0)
-

精神科医は腹の底で何を考えているか
本著の著者である春日さんについては、 これまでに『不幸になりたがる人たち 』や 内田先生との対談『健全な肉体に狂気は宿る』を読んだことがありましたが、 それらに比べても本著は興味深く、精神科医について知ることができました。 「ろくに診察もせずに処方箋を出して患者を副作用で苦しめる医師」では、 中島らもさんが服薬によって、失禁やふらつき、目の調節障害などが見られ、 自力では原稿用紙の升目を埋められず、口述筆記をしていたのに、 服薬をやめたら、視力を取り戻せたことが紹介されています。そして「無責任きわまる投薬によって、患者を犯罪者にしてしまった医師」では、リタリンを処方された患者が強盗事件を起こした際、著者が司法精神鑑定に関わり、医師にとって、リタリンが覚醒剤の一種であることは、周知の事実であったため、リタリンを処方した医師の責任こそ問うべきと発言したのに、結局、被告は求刑よりは軽いが懲役刑となり、医師の責任は問われなかったと述べています。また「臨床を小手先の技術と考え、だから面倒なだけであるとしか認識できない傲慢医師」では、次のような医師を例に挙げています。 しかし件のG医師は私に向かって、 「俺はもう臨床は十分マスターしたよ。ドグマチールで全部やっていけるし、 だから診察は君たち若い人に任せたいなあ」と語ったのであった。 ドグマチールで全部治せるんなら医者は不要であろう。 それに医師の仕事は薬を出すことだけではあるまい。(p.55)ここで出てきた「ドグマチール」は、「スルピリド」の商品名で、もともと胃潰瘍の薬として開発されたのですが、少量ではうつ病、量を増やすと統合失調症にも効くことがわかった薬です。次にカウンセリングについては、こう述べています。 カウンセリングでは、悩みに対していちいち具体的な解決を医療者が与えることはない。 (中略)目指すのは、患者なりクライエント自身が自分を客観的に眺め、 「論理をより精緻にすることにより視野を広げること」の重要性に気づき、 それを以て人格的に成長することであるという。(中略) ちまちましたこだわりから脱却せよ、 そうすれば心も広がって今までの悩みもアホらしくなってくるさ-そんな論法に近い。 (p.108)次は「脳萎縮」の告知について。 昨今は、癌は告知をするのが当然とされている。(中略) では脳萎縮はどうか。 認知症の症状が出てしまっていればともかく、 理解や判断力がどうにか保たれているケースである。 この脳では、遅かれ早かれ認知症を呈しますと本人に伝えるべきか(p.162)春日さんは、自分が担当医なら、本人がどう感じ、どう振る舞うかを推測する必要があるので、予め家族と相談してから、判断すると述べています。次は「うつ病が治る」ということについて。 うつ病の場合、内因性うつ病と称されるタイプでは、抗うつ薬で綺麗に治る。 風邪が治るのに近い形で治る。(中略)これは精神科において珍しい。 もっとも、うつ病の発症には性格や体質的なものが大きく関与するから、 治ってもいずれ再発する可能性はある。 ただし一年間に風邪を二度ひいたからといって風邪が再発したという人はいないのである。 (中略)同じ論法ですっきりと「治った」と言って差し支えない。(p。180)最後は、引きこもりは「心の病」か、について。 小手先の解決法を模索してみても効果はない。 現実的な対応は、まずは家族の硬直した価値観を変えることから始まるだろう。(中略) そしてじっくりと時間をかけて本人と親、双方が 「ああ、もっと別な考え方、別な生き方だってあるんだ」と思えるようになって 互いに牽制し合うことから脱却した状態を、「和解」と称することになるだろう。 そう言った意味では、引きこもりは病というよりは 家族病理を和解へと至らしめるためのプロセスとみなすべきかもしれない。(p.210)
2014.09.01
コメント(0)
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 禁忌の子/山口 未桜
- (2025-11-16 18:00:05)
-
-
-

- 楽天ブックス
- 【[2025] 09月の新作】 ○ ‐ 千葉…
- (2025-11-22 20:31:07)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【ゆるこもりさんのための手帳術…
- (2025-11-20 00:00:13)
-







