2022年07月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

ピーター・バーンスタイン+3 『ストレンジャー・イン・パラダイス(Stranger in Paradise)』
ゆったりと軽快なギター演奏 ピーター・バーンスタイン(Peter Bernstein)は、米国ニューヨーク生まれのジャズ・ギタリスト。1967年生まれの彼は、1990年代以降にいくつものリーダー作を吹き込んでいるのだけれど、筆者はごく一部の作品でしか、彼の演奏を知らない。 本盤『ストレンジャー・イン・パラダイス(Stranger in Paradise)』は、2003年に日本のヴィーナス・レコードによって吹き込まれ(録音場所はニューヨーク)、その翌年にリリースされた。“裸体ジャケ”が得意なヴィーナスの作品とはいえ、“パラダイス(楽園)”だからゴーギャンのタヒチの裸体婦人画というのは多少安直にも思えるが、正直なところ、このジャケット・イメージと作品内容の相関性はあまり大きくないように思う。 実際、演奏そのものは、特に南国楽園風というわけでもないというのが、個人的な印象である。豪快かつ軽妙な1.「ヴィーナス・ブルース」に始まるが、3.「ルイーザ」や4.「ハウ・リトル・ウィー・ノウ」のように、時にゆったりまったりと、また時に軽やかにギター演奏を聴かせる。 そして、本盤は、後半に進むにしたがって、アルバム全体のトーンのようなものが見えてくるように思う。中途半端な(決して悪い意味ではなく、敢えてこう表現できるように思う)まったり感は、バーンスタインの演奏の特徴と言えるだろうか。決して先を行く機敏な動きという感じではなく、ゆったりと頭の中の音を実際に響くギターの弦の音に置き換えていく。そんな感じの演奏が本盤の魅力ということになるのかもしれない。 [収録曲]1. Venus Blues2. Stranger in Paradise3. Luiza4. How Little We Know5. Bobblehead6. Just a Thought7. This Is Always8. Soul Stirrin'9. That Sunday, That Summer10. Autumn Nocturne[パーソネル、録音]Peter Bernstein(g), Brad Mehldau (p), Larry Grenadier (b), Bill Stewart (ds)2003年8月24~25日録音。 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2022年07月29日
コメント(0)
-

ザ・ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス 『エレクトリック・レディランド(Electric Ladyland)』
ギターの神様、“ジミヘン”のマスターピース ジミ・ヘンドリクス(Jimi Hendrix)は、1970年に27歳の若さで不可解な死を遂げた。一般に、死因は睡眠中の窒息死とされるものの、救急隊が病院へ搬送した際に居合わせた人たちの証言に食い違いがあったり、マネージャー(マイケル・ジェフリー)が彼の殺害を告白し、その上、飛行機事故で死んだはずのこのマネージャーがその後も生きていたという証言があったり、何かと不審な点があると言われたりもする。 死の真相はともあれ、彼の存命中にリリースされた3つのスタジオ作のうち、最後の作品となったのが、本盤『エレクトリック・レディランド(Electric Ladyland)』であった(なお、ライヴ盤も含めると、翌年、急死の前に『バンド・オブ・ジプシーズ』という作品がリリースされている)。本盤は、今でこそ1枚のCDにすべて収まっているが、LP時代には2枚組の大作で、これまでのチャンス・チャンドラーに代わってジミ自身がプロデュースを担当したアルバムとなった。 ザ・ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンスは、ジミのほか、ノエル・レディング(ベース)、ミッチ・ミッチェル(ドラムス)の3人から成るが、本盤には様々なゲスト・ミュージシャンも参加している。例えば、4.「ヴードゥー・チャイル」には、スティーヴ・ウィンウッド(ハモンドオルガン)やジャック・キャサディ(ベース)、6.「長く暑い夏の夜」にはアル・クーパー(ピアノ)が参加している。他にも、デイヴ・メイスン(3.と15.、12弦ギターおよびコーラス)、ブライアン・ジョーンズ(15.、パーカッション)、マイク・フィニガン(10.と13.、オルガン、参考過去記事)らが演奏に加わっている。 全体がコンセプト・アルバムになっているというわけではないのだけれど、ジミ・ヘンドリックスの頭の中に鳴り響いていた音を実際の音に表現した演奏として、本盤はその集大成的仕事である。否、生き続けていれば集大成作はその後にも生み出されたのだろうから、その死によって集大成作になったという方が正確なのかもしれない。ともあれ、“ジミヘンを聴いてみたいんだけど”なんて人がいるとすれば、筆者はまずこの盤を勧めることは間違いない。 ちなみに、本盤はUS盤とUK盤とでジャケット・デザインが異なっていた。英盤は19人の裸の女性が収められた写真が2枚組仕様で折りたたまれたジャケットの表面と裏面をあわせた形でデザインされていたが、ジミ・ヘンドリクス自身はこのジャケットを気に入っていなかったという(個人的には、最初に本盤を知ったのがUKジャケだったので、こちらの方がしっくりくるのだけれど)。現在では遺族の意向で、ジミの顔写真をあしらった米盤ジャケット・デザインの方が使用されている。 [収録曲](LPのA面)1. And the Gods Made Love2. Have You Ever Been (to Electric Ladyland)3. Crosstown Traffic4. Voodoo Chile(LPのB面)5. Little Miss Strange6. Long Hot Summer Night7. Come On (Let the Good Times Roll)8. Gypsy Eyes9. Burning of the Midnight Lamp(LPのC面)10. Rainy Day, Dream Away11. 1983... (A Merman I Should Turn to Be)12. Moon, Turn the Tides...Gently Gently Away(LPのD面)13. Still Raining, Still Dreaming14. House Burning Down15. All Along the Watchtower16. Voodoo Child (Slight Return)1968年リリース。 エレクトリック・レディランド [ ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2022年07月24日
コメント(0)
-

アル・クーパー 『クーパー・セッション(Kooper Session)』
実にハイレベルな“二匹目のドジョウ” 『スーパー・セッション(Super Session)』(1968年リリース)の続編とも言えるのが、この『クーパー・セッション(Kooper Session)』(1970年リリース)というアルバムである。といっても、その表題は、ほとんどダジャレ(“スーパー”→“クーパー”)でしかない。アル・クーパー(Al Kooper)によるセッション企画の第二弾のアルバムということになるわけだが、『スーパー・セッション』を超えるとは言わないまでも、この『クーパー・セッション』は、ただの二番煎じとは言えない、実にハイレベルな好盤なのである。 本盤の参加メンバーで最も注目すべきは、ギタリストのシャギー・オーティス。本盤では、彼の存在感とテクニックが半端ない。この人物は、R&Bシンガー、ジョニー・オーティスの息子であり、しかも、この当時まだ15歳という、まさしく“若き才能”であった。 収録された7曲の演奏は、どれも素晴らしく、全編を通して聴くことをお勧めするが、いくつかの曲を聴きどころとして挙げておきたい。まずは、1.「ベリー・マイ・ボディ」。リズム感に乗って勢いのある曲調が印象的で、その後の収録曲への期待を抱かせるに相応しいオープニング曲である。もう一つ、前半でぜひとも触れておきたいのは、2.「ダブル・オア・ナッシング」。アルのオルガンとシャギーのギターの組み合わせが醸し出すスリリングさがいい(このスリリングさは3.でも継続し、4.で息抜き的にリラックス感が出ているのも、構成の妙と言えるように思う)。 LPでは、1.~4.がA面で、“The Songs”、5.~7.がB面で、“The Blues”と銘打たれている。後半のインストルメンタル演奏もどれも素晴らしいが、何と言っても圧巻は、5.「12:15スロー・グーンバッシュ・ブルース」で、シャギーの演奏を堪能できる。同じく7.「シャギーズ・シャッフル」も聴き逃がせない。 それにしても、アル・クーパーという人は、パフォーマーなのか、裏方ないしは仕掛人なのか。彼のいろんな作品を聴くたびに、この疑問がしばしば湧いてくるのだけれど、きっと正解は“両方”なのだろう。実際、本盤でも、ヴォーカルとしての役割、そしてオルガン・プレーヤーとして聴き手の耳に残るパフォーマンスを披露している。しかし、彼が只者でないのは、仕掛人としての才能である。セッションものやその他いくつかのプロジェクトものでのアル・クーパーの役割は、ただのアーティストには容易にできないマルチぶりの賜物である。そのようなわけで、企画者としてのアル・クーパー、プレイヤーとしてのシャギー・オーティスという、簡単には揃い得ない組み合わせが実現されたことにより生み出された稀有な盤ということになるのだろう。[収録曲]1. Bury My Body2. ouble or Nothing3. One Room Country Shack4. Lookin' for a Home5. 12:15 Goonbash Blues6. Shuggie's Old Time Dee-Di-Lee-Di-Leet-Deet Slide Boogie7. Shuggie's Shuffle1970年リリース。 クーパー・セッション/アル・クーパー[CD]【返品種別A】 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2022年07月20日
コメント(0)
-

トレイシー・チャップマン 『クロスロード(Crossroads)』
聴衆の支持を集める中でのセカンド作 1988年にデビューし、セルフタイトルのデビュー作が高い評価を得て、「ファスト・カー」のヒットや翌89年のグラミー賞3部門受賞で一躍有名となったトレイシー・チャップマン(Tracy Chapman)。そんな中、同89年にリリースされた第2作が、この『クロスロード(Crossroads)』というアルバムだった。 前作との大きな違いとしては、第一に、同じプロデューサーでありながら、チャップマン自身もプロデュースに加わった点が挙げられる。それから、第二に、演奏に用いられている楽器に幅が出ている点だと言える。これら二点は互いに関係していたのかもしれない。自身がプロデュースに携わることで、やりたかったこと(言い換えれば、ファースト作ではできなかったであろうこと)を取り入れることができたことだろう。そして、その一つが、ギター弾き語り風の雰囲気は保ちつつも、もう少し多様な楽器と演奏を取り入れることだったのではないだろうか。 その結果、“アコギ1本で歌う”のようなイメージで本作を聴くリスナーの期待にそぐわない部分はあっただろう。けれども、この音はいま聴いても全然古さを感じさせないし、それでいて、ファースト作で世間の評価を集めた彼女のよさが十分に発揮された内容に仕上がったと思う。 個人的に気に入っている曲としては、表題曲の1.「クロスロード(Crossroads)」。アルバム表題もこの曲名もなぜか日本語表記は単数形(“クロスローズ”ではない)なのだけれど、淡々と歌う内省的なナンバー。上述のサウンドの変化がよくわかるものとしては、ネルソン・マンデラに捧げた3.「フリーダム・ナウ」、それから、6.「サブシティ」、7.「ボーン・トゥ・ファイト」なんかが私的には気に入っている。あと、9.「ディス・タイム」は“自分を愛する”というテーマのやはり内省的な内容の曲だが、妙に心に染みるナンバーで、筆者には特に印象に残っている。 最後に、筆者の手元にあるCDのブックレット(歌詞カード)には、英語の詞のほかに、独・仏・西・伊の翻訳を合わせた計5言語が記載されている。たまたま入手したものがそういう仕様なのか、あるいは日本盤とかもそうなっていたのか、詳細は分からないが、米国におけるマイノリティというチャップマンの立場や考えと関係しているのだろうか。[収録曲]1. Crossroads2. Bridges3. Freedom Now4. Material World5. Be Careful of My Heart6. Subcity7. Born to Fight8. A Hundred Years9. This Time10. All That You Have Is Your Soul1989年リリース。 【輸入盤CD】Tracy Chapman / Crossroads (トレイシー・チャップマン) 【中古】クロスロード [Audio CD] トレイシー・チャップマン 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2022年07月16日
コメント(0)
-
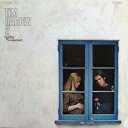
ティム・ハーディン 『ティム・ハーディン2(Tim Hardin 2)』
早逝のシンガーソングライターのセカンド作 ティム・ハーディン(Tim Hardin)が、1966年のデビュー盤(参考過去記事)の翌年に発表したのが本作『ティム・ハーディン2(Tim Hardin 2)』だった。ジャケットには窓から外を見るハーディン自身の写真があしらわれているが、横にいる身籠った女性は、妻のスーザン・ヤードリーとのこと。第2作と言っても、ファースト作の後に一から作られたというわけではなく、ファースト作よりも前に録られた音源からファースト作がリリースされた頃までの音源(1964年11月から1966年8月)が本盤には収められている。 さて、本アルバム全体のトーンは、ファースト作に比べるとやや落ち着いたものとなっている。特に前半(LP時代のA面に当たる1.~5.)は、フォーク・シンガーとしての彼の持ち味がより前面に出ている曲が目立つに思う。その一方、後半(B面)を中心にして、フォークの枠を飛び出た演奏も多く含まれ、朗らかだったりノスタルジックだったりする楽曲が並ぶ。 本盤のいちばんの注目曲と言えば、1.「イフ・アイ・ワー・ア・カーペンター」だろう。パーカッションを効かせつつも淡々としたバックの演奏で、静かにかつ熱く語りかけるようなパフォーマンスは、本盤収録曲の中でもベストだと思う。そして、何よりも、この曲はいろんなアーティストによってカバーされていくスタンダードとなった。本盤リリースの前年には、ボビー・ダーリンがこの曲を歌って全米8位のヒットとなり、その後もジョーン・バエズ、フォー・トップス、ジョニー・キャッシュらがヒットさせたほか、ロバート・プラントやボブ・シーガーなんかもこの曲をカバーしている。 他の気になる曲もいくつかだけ挙げておこう。4.「レディ・ケイム・フロム・ボルティモア」はソフトタッチのフォーク調のラヴソングで、さらりとした歌い口がいい。6.「ザ・グレイス・オブ・リヴィング」は、フォークから万人に聴きやすい音楽へという、当時の彼の試行錯誤が感じられる。10.「ハンク・ウィリアムスに捧ぐ」は、文字通りカントリー歌手のハンク・ウィリアムズへのトリビュート。この人物の短い生涯について歌われていて、このカントリー・シンガーの各方面への影響(フォーク、ロックなどの様々なアーティストに影響を与えた)の一端を見ることができる。[収録曲]1. If I Were a Carpenter2. Red Balloon3. Black Sheep Boy4. The Lady Came from Baltimore5. Baby Close Its Eyes6. You Upset the Grace of Living When You Lie7. Speak Like a Child8. See Where You Are and Get Out9. It's Hard to Believe in Love for Long10. Tribute to Hank Williams1967年リリース。 ティム・ハーディン2 [ ティム・ハーディン ] 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2022年07月11日
コメント(0)
-

INDEXの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-B)へ → つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-L)へ → つづき(M-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありが たいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2022年07月06日
コメント(0)
-

ビクトル・マヌエル 『エル・イホ・デル・フェロビアリオ(El hijo del ferroviario)』
作曲家として、歌い手として、円熟の余裕盤 ビクトル・マヌエル(Víctor Manuel, 本名ビクトル・マヌエル・サン・ホセ・サンチェス)は、スペイン人のシンガーソングライター。1969年にデビューし、現在も活動を続けている。 そんな彼の代表曲ともいえるナンバーは1970年代にいくつも発表されているが、その一方で、1990年代後半から2000年代前半のいわば円熟期の諸作(それらは筆者がリアルタイムで経験した諸作でもあったりする)は、彼のキャリアの中でも好盤が相次いで作られた時期でもあると思う。 2001年リリースの『エル・イホ・デル・フェロビアリオ(El hijo del ferroviario)』(“鉄道員の息子”の意)は、ビクトル・マヌエルの生年が1947年なので、50歳代前半のときの作品ということになる。本盤の次作に当たる『ガレージの犬』のところでも述べたように、声と歌のよさだけでなく、アーティストとしての余裕のようなものが本盤からも滲み出ている。 筆者が特にお気に入りの曲は、まず冒頭の1.「ナダ・ヌエボ・バホ・エル・ソル」と表題曲の2.「エル・イホ・デル・フェロビアリオ」。いずれも詩的で懐古的で、以前にも書いたように、ヴォーカルが何よりも惚れ惚れとする魅力的な声なのである。同じように、4.「アイ・マス・デ・ドス・カラス」、7.「ポル・ミ・クルパ」なんかもいい。 アルバム全体を見渡した時、曲ごとのアレンジや演奏の工夫はあるものの、これといって派手な曲やアップテンポの曲があるわけでもなく、どちらかというと淡々と進んでいく感じである。そんな中で好曲が次々にさらりと流れていくと言えばいいだろうか。言い換えれば、繰り返して聴けば聴くほど、細部に気がつき、好きなところが増えていく。そんなタイプの作品と言っていいのかもしれない。 [収録曲]1. Nada nuevo bajo el sol2. El hijo del ferroviario3. Dueña y señora4. Hay más de dos caras5. A la mar fui por naranjas6. No es bueno que el hombre esté solo7. Por mi culpa8. María de las Mareas9. Veinticuatro horas10. Si nos llegaran los niños11. Las vidas de un pantalón12. El hombre sin recuerdos13. Eres una isla14. Ojalá tengas suerte2001年リリース。 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2022年07月03日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-
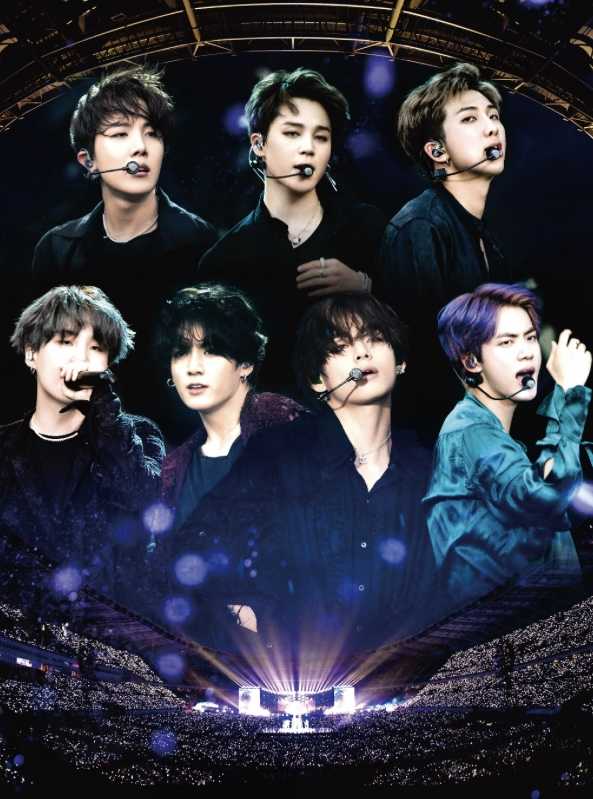
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-







