2025年02月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

アナ・ベレン 『ビーダ(Vida)』
健在ぶりを示したうまさと安定感の作品 アナ・ベレン(Ana Belén)は、1951年マドリード生まれのスペイン人アーティスト。歌手としてだけでなく、俳優や監督などマルチな活動を展開してきた。2018年にリリースされた『ビーダ(Vida)』は、60歳代後半となった彼女がまだまだ元気で安定感があることを示す作品となった。 とにかくこの人のヴォーカルは歌そのもののうまさと表現力の豊かさが秀逸である。1.「イスラ・ケ・アビタス・エン・ミ」は軽妙な歌いっぷりが見事と思えば、2.「ムヘール・バリエンテ」ではしっとりと歌い上げる。アルバム前半で特に聴き逃がせない印象的な曲の一つは、5.「エスタ・ビーダ・エス・ウン・レガロ」である。軽快なリズムに乗って“この人生は贈り物”と軽やかに歌い、アナ・ベレンらしいヴォーカルが展開される。 アルバム後半では、バラード調の8.「エベレスト」で聴き手は引き込まれる。また、表題曲の9.「ビーダ」は、長年のパートナーであるビクトル・マヌエルの楽曲。“人生”をテーマに淡々と歌い上げるこの曲の説得力は、年齢を重ねキャリアを重ねたからこそと言えるだろう。管楽器をフィーチャした10.「アルゴ・キシエラ・セール」は、お洒落感とヴォーカルのうまさが際立った1曲。キューバ出身のパブロ・ミラネスがスペイン詩人アンヘル・ゴンサレスの詩にメロディをつけたものである。[収録曲]1. Isla que habitas en mí2. Mujer valiente3. ¿Quién manda ahí afuera?4. Cuando te encontré5. Esta vida es un regalo6. Tú, yo7. Soy lo que soy8. Everest9. Vida10. Alga quisiera ser11. Cuentos para dormir2018年リリース。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月26日
コメント(0)
-

バネーサ・マルティン 『トランパス(Trampas)』
個性的なヴォーカル世界 バネーサ・マルティン(Vanesa Martín)は、スペイン南部のマラガ出身の女性シンガー、シンガーソングライター。2006年にデビュー盤『アグア』を発表し、その後、所属レーベルを変更した後に2009年に発表されたセカンド作が、この『トランパス(Trampas)』だった。デビュー盤の方は決して売れたわけではなかったけれども、ミラノ録音となった本セカンド盤は売り上げを伸ばし、以降の成功への足掛かりとなった。 全曲自作曲で固められていて、ヴォーカルの面においても曲の面においてもバネーサの独自世界が展開されている。彼女の歌声は好き嫌いがわかれそうなタイプであるが、筆者の好みにぴったりはまっていて、個人的にはなかなか魅力的な声の持ち主だと思っている。 表題曲の1.「トランパス」に見られるように、弾き語り調の曲をナチュラルな感じのサウンドにアレンジして演奏した楽曲が目立つ。2.「カプリチョソ」は、最初のシングル曲ということもあってやや派手なアレンジだが、後々の彼女の成功につながる楽曲イメージがこの時点でできあがっていて、本盤収録曲の中では特に注目のナンバーと言えそう。もう少しパンチがあってもよかったかもしれない気がするものの、4.「アトラベサンドテ」も彼女の魅力がよく表れた好曲である。 アルバム後半の注目曲としては、7.「ラ・ビーダ」はテンポよく流れるメロディラインが印象的で、さりげない好ナンバーと言える。バラード調の9.「プエド・ジャマールテ」や11.「ア・ラ・デリーバ」は作曲のよさが光る。本アルバム全体を見渡すと、楽曲のよさが際立っていて、アレンジの工夫が本盤の成功の鍵になったのだろうという気がする。[収録曲]1. Trampas2. Caprichoso3. Si me olvidas4. Atravesándote5. Cada uno por su lado6. Déjame a mí7. La vida8. Hago música9. Puedo llamarte10. Donde11. A la deriva12. No matemos el tiempo2009年リリース。 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年02月23日
コメント(0)
-

ホアキン・サビーナ 「ポスダータ(Postdata)」
サビーナ曲選 PART 2(その5) さて、ホアキン・サビーナ曲集、第2弾の最後の曲は、「ポスダータ(Postdata)」です。これまでのところ最後にリリースされたスタジオ作(2017年の『ロ・二エゴ・トド』)に収められたさりげない好ナンバーです。 映像はガイコツ人間(?)が出てきて、なんだかメキシコの死者風ですが、特に詞がそういう内容というわけではありません。表題の「ポスダータ」は“追伸(英語のP.S.)”の意味で、詞の内容は、主人公が女性に(自分のものとは認識されないかもしれない)ささやかな歌を捧げるといったもの。主人公の想いと曲の軽妙さがうまく嚙み合った楽曲だと思います。 この曲のライヴ音源等は公式なものがなさそうで残念ながらここに掲載できません。とはいえ、上記のアルバムのリリース後にはスペインだけでなくメキシコなどでもライヴ・ツアーをしていて、この楽曲も披露していたようです。前項にも書いたように、筆者的には、“後聴き”でどんどんはまっていったサビーナなのですが、機会を見て、今後も彼のアルバムや楽曲を少しずつ紹介したいと思っています。[収録アルバム]Joaquín Sabina / Lo niego todo(2017年) ↓ LP盤です ↓ 【輸入盤LPレコード】【新品】Joaquin Sabina / Lo Niego Todo【LP2019/5/10発売】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月21日
コメント(0)
-

ホアキン・サビーナ 「コンティーゴ(Contigo)」
サビーナ曲選 PART 2(その4) ホアキン・サビーナ(Joaquín Sabina)曲選の第2弾の4回目です。今回の曲は、「コンティーゴ(Contigo)」というナンバーです。1996年のヒット盤『ジョ・ミ・メ・コンティーゴ』に収録され、シングルとしてもリリースされた1曲です。紡いだ詩/詞を歌う彼らしい楽曲です。 筆者的には、この曲を含む上記のアルバムは、発売当時、店頭にCDが並んでいるのを日々見ながらすぐには買わず後聴きになったのを後悔した作品だったりします。その時にアルバムを手にしていれば、この曲や、同じくこの盤に収録の「イ・シン・エンバルゴ」にもっと早く出会ていたのですが。 それはさておき、この曲のライヴでの演奏もご覧いただきたいと思います。ライヴでも定番の曲として披露されており、複数のライヴ盤にも収録されています。 [収録アルバム]Joaquín Sabina / Yo, mi, me, contigo(1996年)Joaquín Sabina / Nos sobran los motivos(2000年)Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina / Dos pájaros de un tiro(2007年) ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月19日
コメント(0)
-

ホアキン・サビーナ 「イ・ノス・ディエロン・ラス・ディエス(Y nos dieron las diez)」
サビーナ曲選 PART 2(その3) 今回は、少し曲調の異なるホアキン・サビーナ(Joaquín Sabina)のナンバーを取り上げたいと思います。1990年のアルバム『フィシカ・イ・キミカ』に収められ、シングルとしてもヒットした「イ・ノス・ディエロン・ラス・ディエス(Y nos dieron las diez)」です。 洒落た曲調や弾き語り風といったサビーナらしい特徴というよりは、ラテン系のトラディショナルな曲調が印象的なナンバーですが、サビーナのシングルとしてはよく知られ、他のアーティストによるカバーも複数あったりする楽曲です。 この曲には有名なエピソードがあり、サビーナは、この曲の最初の部分となる詞を紙ナプキンに書き記し、ロス・セクレートス(Los Secretos)のメンバーだったエンリケ・ウルキーホに渡したそうです。その後、お互いが続きの詞を書いて曲として仕上げ、その結果、ロス・セクレートスの「オホス・デ・ガタ(Ojos de gata)」という曲は、この「イ・ノス・ディエロン・ラス・ディエス」と出だし部分が同じ歌詞という、“姉妹曲”になったとのことです。 そのようなわけで、ロス・セクレートスの「オホス・デ・ガタ(Ojos de gata)」(“猫の目”という意味の表題です)もお聴きください。 [収録アルバム]Joaquín Sabina / Física y química(1990年) ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月17日
コメント(0)
-

ホアキン・サビーナ 「キエン・メ・ア・ロバード・エル・メス・デ・アブリル(¿Quién me ha robado el mes de abril?)」
サビーナ曲選 PART 2(その2) 続いては、1988年のアルバム『エル・オンブレ・デ・トラッヘ・グリス(灰色のスーツの男)』に収録されたホアキン・サビーナ(Joaquín Sabina)の楽曲です。 「キエン・メ・ア・ロバード・エル・メス・デ・アブリル(¿Quién me ha robado el mes de abril?)」とカタカナにすると長ったらしい曲名なのですが、“誰が私から4月という月を奪っていったのか?”という、なんともサビーナらしい詩的な表題にして歌詞という楽曲です(余談ながら、アルバム表題の“灰色のスーツの男”も詞の中に登場します)。 今回はライヴでの演奏シーンもご覧ください。ジョアン・マヌエル・セラーとの共同名義のライヴ盤『ドス・パハロス・デ・ウン・ティロ(一石二鳥)』では、通常盤には収録されていませんが、コンプリートと銘打った限定版の方には、このナンバーが収められています。2007年のツアーからのライヴ映像です。 [収録アルバム]Joaquín Sabina / El hombre del traje gris(1988年)Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina / Dos pájaros de un tiro(2007年)*限定発売のコンプリート版のみに収録。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月16日
コメント(0)
-

ホアキン・サビーナ 「カジェ・メランコリーア(Calle Melancolía)」
サビーナ曲選 PART 2(その1) ホアキン・サビーナ(Joaquín Sabina)は、1949年、スペイン南部出身のシンガーソングライター、詩人。ただのシンガーソングライターやポップシンガーというのではなく、詩的世界が独特のアーティストです。このブログでは、以前に“サビーナ曲選”なるものをやったのですが、今回はその第2弾という形で5回ほどに分けてお届けしたいと思います。 さて、1曲目は「カジェ・メランコリーア(Calle Melancolía)」というナンバーです。アルバム『マラス・コンパニィーアス』(1980年)に収録され、シングルとしても発売された楽曲です。 映像は、マドリード(?)と思しき町の夜景にネオンサインで歌詞が浮かび上がっていますが、この曲の詞をイメージしてのものです。“カジェ”というのは、スペイン語で通り(ストリート)のことですが、“メランコリーア通り7番地”に住む人物が語り手となった詞です。そして、“メランコリーア”とは、“憂鬱”。“喜び”の街へと移り住みたいと思いながら、“憂鬱”な通りに住み続けているという人物が主人公なわけです。 もう一つ、映像は動かないのですが、20年近く後のライヴでのこの楽曲の演奏をお聴きください。2000年発表のライヴ盤『ノス・ソブラン・ロス・モティーボス』に収録のものです。 [収録アルバム]Joaquín Sabina / Malas compañías(1980年)Joaquín Sabina y Cia. / Nos sobran los motivos(2000年) 【輸入盤】 Joaquin Sabina / Nos Sobran Los Motivos 【CD】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月14日
コメント(0)
-

ハンブル・パイ 『サンダーボックス(Thunderbox)』
ルーツとなる音楽が強く打ち出された盤 ハンブル・パイ(Humble Pie)は、ピーター・フランプトンとスティーヴ・マリオットを中心に形成された。既にミュージシャンとして知られた2人によるいわゆる“スーパーグループ”だったが、やがてこのバンドはマリオット色を強め、フランプトンは脱退することになる。 そのマリオット色というのは、ブルースやソウルに根差しながらもハードな演奏を披露するという音楽性である。1974年に発表されたこの『サンダーボックス(Thunderbox)』は、ソウルやR&Bといった、彼のルーツとなる音楽的な“黒っぽさ”が前面に出た作品だと言える。 1.「サンダーボックス」をはじめ、マリオットによるナンバーが含まれる一方、アルバム収録曲の半数を超えるナンバーが、ソウル、ゴスペル、R&Bといった彼にとってルーツとなる音楽のカバーとなっている。そのようなわけで、オリジナル曲もいいのだけれど、どうしても注目がいくのはそれらカバー曲ということになる。 2.「グルーヴィン・ウィズ・ジーザス」は、ヴァイオリネアーズ(The Violinaires)のカバーで、表題通りのグルーズ感がいい。3.「アイ・キャント・スタンド・ザ・レイン」はアン・ピーブルズのヒット曲だが、8.「ナインティー・ナイン・パウンズ」というもう一つの彼女のカバー曲も本盤には含まれている。アーサー・アレキサンダーの4.「アンナ」は、ビートルズの演奏でもよく知られるナンバーだが、なかなかソウル感の強いカバーに仕上がっていると思う。 10.「ノー・マネー・ダウン」は、チャック・ベリーのカバーで、これまたソウルフルな仕上がりがいい。11.「ドリフト・アウェイ」は、ドビー・グレイのナンバー。そして、12.「オー・ラ・ディ・ダ」は、ステイプル・シンガーズの曲で、ゴスペル・ソウル系のノリが昇華した好演奏である。[収録曲]1. Thunderbox 2. Groovin' with Jesus3. I Can't Stand the Rain4. Anna (Go to Him)5. No Way 6. Rally with Ali 7. Don't Worry, Be Happy 8. Ninety-Nine Pounds 9. Every Single Day10. No Money Down11. Drift Away 12. Oh La-De-Da 1974年リリース。 サンダーボックス/ハンブル・パイ[SHM-CD]【返品種別A】 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年02月12日
コメント(0)
-

INDEXページの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいです) をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2025年02月09日
コメント(0)
-

レナード・コーエン 『ある女たらしの死(Death of a Ladies' Man)』
フィル・スペクターのプロデュースによる第5作 レナード・コーエン(Leonard Cohen, 1934-2016)は、カナダはモントリオール出身のミュージシャン、詩人。シンガーソングライターとしては、1967年のデビュー盤(参考過去記事)以降、アルバム作品を発表していった。本作『ある女たらしの死(Death of a Ladies' Man)』は、1977年にリリースされ、第5作に当たる。 コーエンと言えば、孤高の詩人で、語るように歌うミニマリスト的なイメージがあるかもしれないが、本盤はフィル・スペクターがプロデューサー・作曲者として参加し、音の面で前作までとはかなり異なる。初めての人にもかなり聴きやすく、個人的には、“コーエンは怖い”(笑)などとという印象を持っている人にはぜひ試してもらいたい作品であると思っている。 無論、従来のコーエンの作風と異なるということで、当時にも賛否両論があった。コーエンの詞にスペクターが曲をつけ、スペクターらしいきらびやかで厚みのあるサウンドに仕上がっているというのは、サウンド面では初期の作品(例えばこちらやこちら)とは対極に位置する。けれども、筆者的には、1970年代後半のこの段階でよい新境地が切り拓かれるようになった作品だったのではなかったかと感じている。つまりは、弾き語り的なコーエンと分厚いサウンドのコーエンのどちらがよいとかいうのではなく、どっちもありというのが答えだったのではないかという気がしている。 個人的におすすめの曲をいくつか挙げておきたい。1.「真実の愛」は、どこかに素朴さを残して従来のコーエンらしさを彷彿とさせながら、工夫の凝らされた演奏が印象的なオープニング・ナンバー。4.「回想」はサックスを大幅にフィーチャし、壮大な演奏に仕上がっている。表題曲でアルバムの最後に収録されている8.「ある女たらしの死」は、本盤に収録された楽曲の中で個人的にはベストではないかと思う1曲である。[収録曲] *( )内は邦盤の日本語曲名。1. True Love Leaves No Traces(真実の愛)2. Iodine(ヨードチンキ)3. Paper Thin Hotel(紙のように薄い壁のホテル)4. Memories(回想)5. I Left a Woman Waiting(ぼくは女を待たせた)6. Don't Go Home with Your Hard-On(興奮したまま家に帰るな)7. Fingerprints(指紋)8. Death of a Ladies' Man(ある女たらしの死)1977年リリース。 ある女たらしの死 [ レナード・コーエン ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年02月07日
コメント(0)
-

ジョン・ホール 『ラヴ・ダズント・アスク(Love Doesn’t Ask)』
豪華ゲストを迎えた成熟の盤 ジョン・ホール(John Hall)は、1948年、ボルチモア出身のミュージシャン。1970年にソロ・デビューし、オーリアンズというバンドでの活動などで知られる。そんな彼は、21世紀に入り、政治家への変身を遂げた(ニューヨークから選出の下院議員)。しかし、それは、ミュージシャンとしての限界から転身したわけではなかった。ミュージシャンとしていかに成熟していったのかを考えると、20世紀最後の盤となった本盤『ラヴ・ダズント・アスク(Love Doesn’t Ask)』は、このアーティストの成熟ぶりをよく示している作品だったと言えるように思う。 表題曲の1.「ラヴ・ダズント・アスク」からして、特別に目新しいことをしようとしているわけではない。どちらかと言うと、淡々とそして着実に彼がやってきた音楽を紡いでいくといった印象である。そんな中、個人的な好みでは、4.「カルカッタ」がなかなかの名曲。がっつり弾き語り調だったと思われる曲をベースにしながらも、ヴォーカルよし、アレンジの工夫よし、楽器の演奏よしと三拍子そろった心に響くナンバーに仕上がっている。 ほかに筆者が気に入っているナンバーをさらにもう少し挙げてみたい。6.「サークル」もアレンジと演奏のよさが特に目立つ好曲で、かなりおすすめのナンバー。8.「アイル・ドゥー・マイ・デイズ」は心に響く真っ直ぐなヴォーカルが印象深い。13.「オクトーバー・チャイルド」や15.「モーニング・ライト」は、この手のアーティストにありがちな曲調と言ってしまえばそれまでなのかもしれないけれど、シンプルにいい曲だと言える。何より、筆者的にはこういう曲にこそ、ついつい惹きつけられてしまう。 ちなみに、本盤にはジョン・ホールの人柄と音楽性を反映するようなミュージシャンたちがゲスト参加している。ロビー・デュプリー(ハーモニカ、1.,11.)、ガース・ハドソン(キーボード,6.)、ジョン・セバスチャン(ハーモニカ、12.)なんかに注目しつつ聴くというのもこの盤の楽しみかたの一つということになるように思う。[収録曲]1. Love Doesn't Ask2. Usurper3. Only Got Today4. Calcutta5. Home6. Circle7. Don't Go There8. I'll Do My Days9. Litany 10. Moving Target11. Can't Take It with You12. Quiet Place13. October Child 14. Don’t Look Now15. Morning Light1999年リリース。 【中古】 ラヴ・ダズント・アスク/ジョン・ホール ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年02月03日
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪久保史緒里、自宅での写真…
- (2025-11-26 12:59:33)
-
-
-
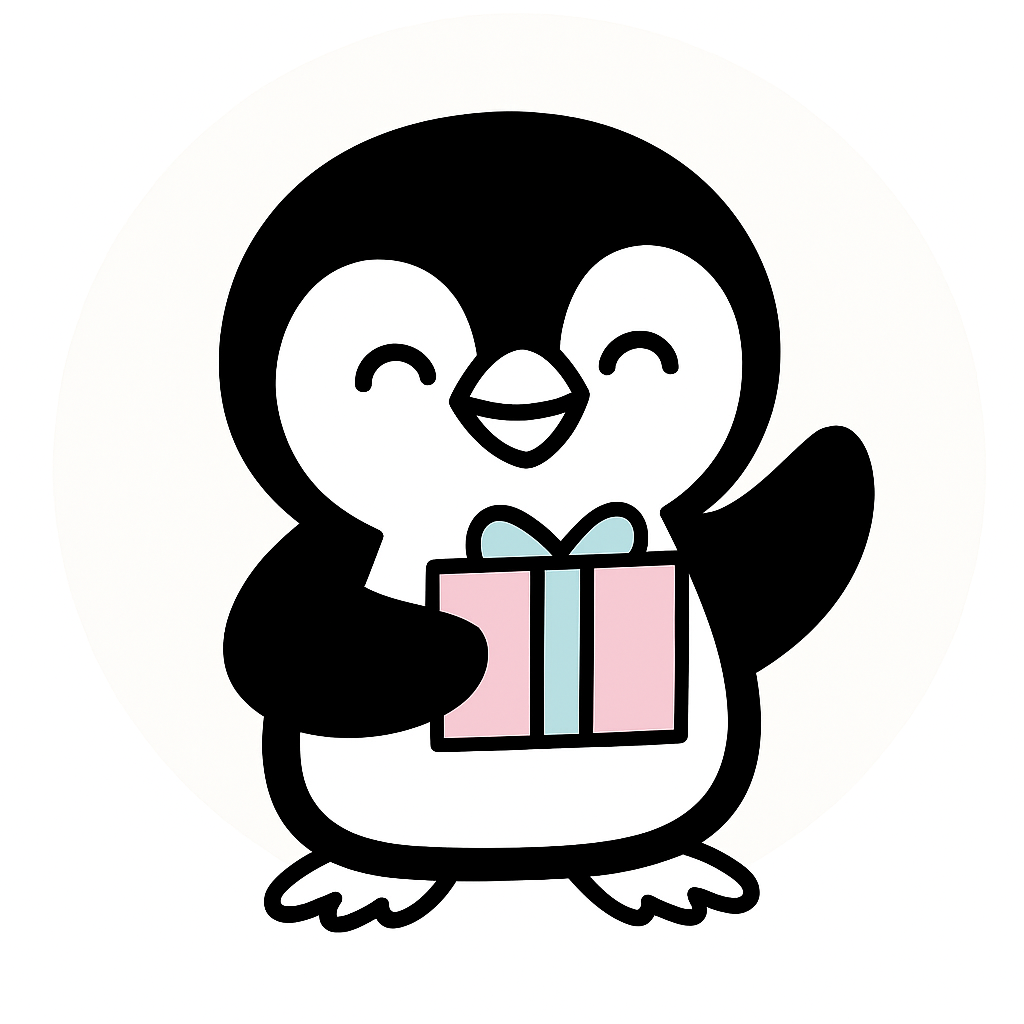
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-







