2025年10月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

スティング 『ブルー・タートルの夢(The Dream of the Blue Turtles)』
ソロ・アーティストとしてのスティングの姿勢が明確化された好作品 1984年にポリスが活動休止となり、その翌年にメンバーだったスティング(Sting)はソロとしての第一作を発表した。それが、1985年リリースの本盤『ブルー・タートルの夢(The Dream of the Blue Turtles)』である。 ポリス時代の諸作とは違い、本作ではスティング個人の音楽的志向性がはっきりと示されている。ケニー・カークランドやブランフォード・マルサリスなどのミュージシャンが参加し、ジャズ寄りのサウンド、1980年代半ば当時の華やかなロックシーンには異質の方向性の作風が展開されている。 オープニング・ナンバーの1.「セット・ゼム・フリー」は、先行シングルとして発売され、全米3位のヒットとなった。2.「ラヴ・イズ・ザ・セヴンス・ウェイヴ」もシングルとしてリリースされたナンバーで、個人的にはお気に入りのナンバー。3.「ラシアンズ」は東西冷戦体制を批判した楽曲で、こちらもシングルとして注目を集めた。 アルバム後半では、6.「黒い傷あと」や9.「バーボン・ストリートの月」が筆者の好み。特に後者の重く寂しいトーンは最初に聴いた当時から印象に残り、当初から忘れられない1曲となっている。また、アルバム表題曲の8.「ブルー・タートルの夢」が短い演奏ながら、もはや単なるロック/ポップのアルバムではないということをよく示している。 これ以降、スティングは秀でた作品をいくつも制作していくことになるわけだが、その最初となったこのアルバムもまた聴き逃がせない名盤の一つと言っていいように思う。[収録曲]1. If You Love Somebody Set Them Free 2. Love Is the Seventh Wave3. Russians 4. Children's Crusade 5. Shadows in the Rain6. We Work the Black Seam7. Consider Me Gone8. The Dream of the Blue Turtles 9. Moon Over Bourbon Street 10. Fortress Around Your Heart1985年リリース。 ブルー・タートルの夢/スティング[SHM-CD]【返品種別A】 ブルー・タートルの夢 [ スティング ] 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2025年10月31日
コメント(0)
-

ポール・デイヴィス 『アイ・ゴー・クレイジー(Singer of Songs - Teller of Tales)』
カントリー、ソウルをバックグラウンドにした西海岸的AOR盤 ポール・デイヴィス(Paul Davis)は、1948年ミシシッピ生まれのシンガーソングライター。ソウル、カントリーなどの音楽的背景を持ちながらも、西海岸的サウンド、レイドバック風のヴォーカルで成功を収めた。その代表盤とされるのが、ソロ5作目の本盤『アイ・ゴー・クレイジー(Singer of Songs - Teller of Tales)』(1977年)である。 邦盤では収録されたヒット曲をアルバム表題にしている(このやり方はチャラいものの、「商品」を売るためには鉄壁のパターンなのだろう)けれど、英語の原題は“歌の歌い手、物語の語り手(シンガー・オブ・ソングス、テラー・オブ・テイルズ)”である。つまりはシンガーソングライターとしてのこのアーティストのスタンスが示されている表題と言え、実際、収録された10曲中8曲が彼のペンによるナンバーである。 1.「アイ・ゴー・クレイジー」は、1978年にシングルとして全米7位を記録したポール・デイヴィスの代表曲で、40週という長期間にわたってトップ100入りし、アルバム自体の商業的成功にもつながった。べったりぴったりど真ん中のバラード美曲であり、ヒットにつながったのも頷ける。 これ以外にもいかにもAOR的なナンバーが並ぶ。上記1.以外に個人的に特に好曲だと筆者が感じているのは、2.「ブラインド・ニュー・ラヴ」(とにかく曲がいい)、7.「もうひとつの愛」、8.「ジャスト・ア・ローズ」、10.「エディトリアル」(ピアノをバックに歌い上げる熱唱が印象的)といった楽曲である。 ここまでの話からすると、聴衆受けを狙った大衆迎合的なナンバーばかりが並ぶのかと思ってしまうかもしれない。けれども、アルバムの随所に彼のルーツとなる音楽性が顔をのぞかせるという側面もあるように思う。6.「ハレルヤ・サンキュー・ジーザス」は、彼がカントリーのソングライターであったことがよくわかるし、9.「バッド・ドリーム」は古き良きロックンロール音楽をうまく当時風にアレンジしているという印象を受ける。[収録曲]1. I Go Crazy2. I Never Heard the Song at All3. Darlin'4. Sweet Life5. Never Want to Lose Your Love6. Hallelujah Thank You Jesus7. I Don't Want to Be Just Another Love8. You're Not Just a Rose9. Bad Dream10. Editorial1977年リリース。 アイ・ゴー・クレイジー [ ポール・デイヴィス ] 次のブログランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月27日
コメント(0)
-

テッド・カーソン 『ライヴ・アット・ラ・テト・ドゥ・ラール(Live at La Tete de L'Art)』
隠れた好ライヴ演奏盤 テッド・カーソン(Ted Curson)は、1935年フィラデルフィア生まれのジャズ・トランペット奏者で、2012年に77歳で没している。10歳でトランペットを手にしたという彼は、セシル・テイラーやチャールズ・ミンガスとの録音にも参加した経験を持つ。ワールドワイドに名が知られた演奏家というわけではなかったにせよ、フィンランドではよく知られたミュージシャンで、ポリ・ジャズ・フェスティヴァルには1966年の初回から毎年参加していたという。 この『ライヴ・アット・ラ・テト・ドゥ・ラール(Live at La Tete de L'Art)』は、カナダのモントリオールで1962年に録音されたライヴ演奏盤。テッド・カーソンのトランペットとアル・ドクターのアルトをフロントにしたクインテット編成の演奏である。決してレコーディングの音質は良好というわけではないけれども、テッド・カーソンのトランペットの魅力が存分に発揮された好演奏を楽しむことができる一枚である。 冒頭の1.「クラックリン・ブレッド」は穏やかに始まり、端正な演奏が印象的。この“端正”というのは、テッド・カーソンの形容によく使われるようだが、“ハンサム”な演奏と言い換えてもいいように筆者は思っている。とにかくいい意味で整っていてシャキッとしているのである。この特色は、2.「テッズ・テンポ」のようにモード的インプロヴィゼーションが展開されてもしっかりと維持されていて、そこがなかなか面白いところだと思う。3.「プレイハウス・マーチ」は勇壮なテーマに続き、これまた端正なトランペット演奏についつい聴き惚れてしまう。 アルバム後半(元のLP盤のB面)に入り、収録曲のうち最も尺が長い(12分半)の4.「ストレート・アイス」でも、ややもすると間延びしかねない展開の中、このシャキッとしたトランペットが聴き手の集中力を持続させるという演奏が繰り広げられる。5.「クイックサンド」はシリアスな雰囲気を醸し出している楽曲であるが、ここでもテッド・カーソンのトランペットの端正さが際立っている。決してよく知られた盤ではない(というよりほとんど知られていない盤なのだろう)が、これを聴かないのはもったいない、そんな好盤だと言えるように思う。[収録曲]1. Cracklin' Bread2. Ted's Tempo3. Playhouse March4. Straight Ice 5. Quicksand[パーソネル・録音]Ted Curson (tp, piccolo-tp), Al Doctor (as), Maury Kaye (p), Charles Biddle (b), Charles Duncan (ds)1962年録音。 テッド・カーソン / テッド・カーソン|フォー・クラシック・アルバムズ [CD] 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月24日
コメント(0)
-

ガブリエル・リバーノ 『アサード・クリオーリョ(Asado criollo)』
バンドネオン奏者による意欲作 ガブリエル・リバーノ(Gabriel Rivano)は、1958年、アルゼンチン出身のバンドネオン奏者。バンドネオン奏者というと、“ああ、タンゴね”となりがちかもしれないが、彼の音楽は、タンゴとクラシックとジャズというトライアングル(三角形)の中に成り立っているというのが適当なのかもしれない。 本盤『アサード・クリオーリョ(Asado criollo)』は2006年にリリースされたアルバム。表題の“アサード・クリオーリョ”というのは、アルゼンチン風のバーベキューのこと(地方によって肉の種類は、羊だったり、山羊だったり、豚だったりするらしい)。この“アルゼンチン的”表題からも窺えるように、本作はとくにアルゼンチン・フォルクローレからの影響を受けた作品である。 リバーノ自身が述べているところでは、本盤の着想は1997年のアサード(バーベキュー)に始まる。けれども、様々なプロジェクトで本格化できずに時が過ぎ、2000年にギターのビクトル・ビジャダンゴス(本盤の2.でギターを披露している)とともにこの作業を開始したという。結果、2005年に録音を行い、本盤の形に結実したとのことである。 フォルクローレの有名曲である1.「ラ・テレシータ」から本盤は始まる。続く2.~5.は組曲になっていて、「パタゴニア組曲」と名づけられている。その後、6.「グスターボ・デ・シンコ・ア・セイス」を挟み、再び7.~10.は組曲となっており、こちらの方は「アルゼンチン組曲」となっている。最後は、タンゴの定番曲11.「ラ・クンパルシータ」でアルバムを締めくくる(なお、ボートラとしてギタリストのリカルド・モヤーノと共演した3.の別ヴァージョンが収められている)。[収録曲]1. La Telesita《Suite Patagónica》2. Asado Criollo3. zamba de Mayo4. Ñancul5. Zamba Junina6. Gustavo de 5 a 6《Suite Argentina》7. Tren de las Nubes - Norte8. El Argentinito - Este9. La Luminosa - Oeste10. Pampa - Sur11. La cumparista 12. Zamba de Mayo [bonus track]2006年リリース。 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月21日
コメント(0)
-

ラス・フリーマン/チェット・ベイカー 『カルテット(Quartet)』
端正でメリハリの利いた爽快盤 1950年代、ラス・フリーマン(Russ Freeman)は、チェット・ベイカー(Chet Baker)との共演を何度も行った。そして、この2人が組んだ最後となり、なおかつ出色の出来の演奏を披露しているのが、この『カルテット(Quartet)』という盤である。アルバム表題の通り、演奏内容は、チェット・ベイカーのトランペットのワンホーン・カルテット。ラス・フリーマンのピアノの他は、ベースがルロイ・ヴィネガー、ドラムスがシェリー・マンという面子である。 ラス・フリーマンのピアノがしばしば小気味よく打楽器的な感性を滲ませる。シェリー・マンは持ち前の軽快かつ安定のドラミングを見せる。ベースのルロイ・ヴィネガーは、いつもながらの安定感・安心感のある演奏。そして、チェット・ベイカーのトランペットは、この人らしい軽妙さが存分に発揮されている。無論、ここの演奏が優れていても全体としてうまくいくとは限らないわけだが、本盤に関しては、4人のオリジナリティが合わさって、このメンバーでのオリジナリティに結びついていると言えるように思う。 私的な好みから注目の演奏を何曲か挙げておきたい。ベイカーのトランペットの軽快さにドラムスとピアノが見事に呼応している1.「ラヴ・ネスト」は、間違いなく本盤の聴きどころとなる演奏。4.「アン・アフタヌーン・アット・ホーム」は、このカルテットの息が合っているのがよくわかる好演奏に仕上がっている。6.「ラッシュ・ライフ」は、フリーマンのピアノとベイカーのトランペットをじっくりと堪能できる1曲である。8.「ヒューゴ・ハイウェイ(ウーゴ・ハイウェイ)」は、ベイカーのトランペットが個人的に気に入っている。[収録曲]1. Love Nest2. Fan Tan3. Summer Sketch4. An Afternoon at Home5. Say When6. Lush Life7. Amblin'8. Hugo Hurwhey[パーソネル、録音]Chet Baker (tp), Russ Freeman (p), Leroy Vinnegar (b), Shelly Manne (ds)1956年11月6日録音。 チェット・ベイカー=ラス・フリーマン・カルテット [ チェット・ベイカー/ラス・フリーマン ] 【中古】 チェット・ベイカー=ラス・フリーマン・カルテット/チェット・ベイカー,ラス・フリーマン,リロイ・ヴィネガー,シェリー・マン 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月19日
コメント(0)
-

INDEXページの更新
1か月ほど間が空いてしまいましたが、INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。最近記事へのリンクを追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも ありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月17日
コメント(0)
-
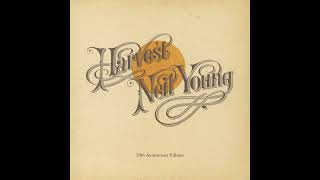
ニール・ヤング 「オールド・マン(Old Man)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その5) “秋を感じさせる”という個人的思い入れ(思い込み?)でニール・ヤング(Neil Young)の楽曲を取り上げてきましたが、今回の5曲目で一区切りです。最後は何と言ってもこの曲、「オールド・マン(Old Man)」です。初回に取り上げた「週末に(アウト・オン・ザ・ウィークエンド)」と同じアルバム(1972年の『ハーヴェスト』)に収録されています。「週末に」がアルバムのオープニング・ナンバー(A面1曲目)なら、今回の「オールド・マン」は、元来のLP盤のB面のオープニングのナンバーということになります。 イントロのギターを聴くと、何か凝った曲なのかなという印象を受けるかもしれませんが、歌が始まるとド直球の弾き語り風かつニール・ヤング節のナンバーです。 最後は、この曲のライヴでの演奏シーンです。第1回目の「週末に」と被ってはしまうのですが、その時にリンクを貼ったのと同じBBCライヴの演奏シーンです。ギターの弾き語り調がストレートに刺さってくるところ、そして何よりも若きニール・ヤングの声の伸びがお見事なライヴ演奏です。 [収録アルバム]Neil Young / Harvest(1972年) ハーヴェスト<リマスター>/ニール・ヤング[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月13日
コメント(0)
-

ニール・ヤング 「イッツ・ア・ドリーム(It's a Dream)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その4) 前回の「ザ・ペインター」が収録されているのと同じニール・ヤング(Neil Young)のアルバム(過去記事)から、もう1曲取り上げてみようと思います。「イッツ・ア・ドリーム(It's a Dream)」というのが、その楽曲です。ピアノ弾き語り風の、どちらかというと地味な曲なのですが、筆者的にはこの哀愁と寂しさの漂う感じが何とも言えない魅力になっているナンバーです。 この曲のライヴでの演奏もご覧いただきます。リリース当時の2005年、ライマン・オーディトリアムでの演奏シーンです。 鍵盤を前にしての演奏ですが、ギターを弾きながら、ピアノを弾きながら(さらにはハーモニカ演奏を披露しながらというパターンもあります)といずれも味わい深さを発揮できるのは、ニール・ヤングの魅力であり強みであるのだろうとあらためて思ってみたりします。[収録アルバム]Neil Young / Prairie Wind(2005年) 【中古】 プレーリー・ウィンド/ニール・ヤング プレーリー・ウィンド[CD] [輸入盤] / ニール・ヤング 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月12日
コメント(0)
-
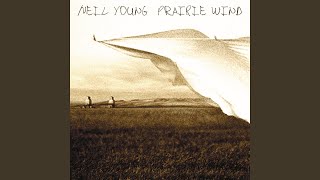
ニール・ヤング 「ザ・ペインター(The Painter)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その3) 秋という季節と絡めてのニール・ヤング(Neil Young)曲選の3回目です。前2回の曲から時は一気に進んで、2005年のアルバム『プレーリー・ウィンド』に収められた「ザ・ペインター(The Painter)」というナンバーです。 この曲が収録されたアルバムは、リリース年としては離れているものの、『ハーヴェスト・ムーン』(2005年)と並んで『ハーヴェスト』(1972年)の続編的内容と見なされる作品で、そういう意味では、楽曲の雰囲気も通底している部分があります。 続いては、発表当時(2005年)のステージの模様をご覧ください。アルバム収録のもとのヴァージョンと同様のまったりした雰囲気が魅力といったところです。 [収録アルバム]Neil Young / Prairie Wind(2005年) プレーリー・ウィンド[CD] [輸入盤] / ニール・ヤング 【中古】 【輸入盤】プレイリー・ウィンド/ニール・ヤング ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月11日
コメント(0)
-

ニール・ヤング 「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ(After the Gold Rush)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その2) 筆者の中ではなぜだか秋という季節と結びついているニール・ヤング(Neil Young)のナンバーの2曲目です。今回の楽曲は、彼の作品の中でも代表作として1,2位を争う(と筆者は思っている)名盤『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』に収録のナンバーです。 まずは、上記の盤に収められた表題曲「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ(After the Gold Rush)」をお聴きください。 なぜ“秋”なのかという点については、結局のところ感覚的なものでしかないのですが、この“頼りなさげな”(もちろんいい意味で)が筆者にそう思わせるといったところなのでしょう。 今回は、後世のライヴ映像もご覧いただきたいと思います。1998年、ファーム・エイドでのステージの様子です。上記のヴォーカルの魅力(そしてハーモニカ演奏部分も実に魅力的です)が存分に発揮されています。 [収録アルバム]Neil Young / After the Gold Rush(1970年) アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ [ ニール・ヤング ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月10日
コメント(0)
-
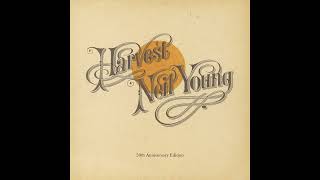
ニール・ヤング 「週末に(Out on the Weekend)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その1) 今夏の連日の猛暑もようやく収まってきて、少しは秋が感じられる日も増えてきました。そんなわけで、“秋の風を感じるニール・ヤング曲選”をお届けしたいと思い立ちました。ニール・ヤング(Neil Young)が必ずしも秋と結びつくというわけではないのですが、個人的にはそういうアルバムがあることをこちらの過去記事(『ハーヴェスト』)にも書きました。他のいくつかのニール・ヤングのアルバムでも、なぜだか秋とシンクロするものがあって、今回はそうした中から彼の楽曲をいくつかピックアップしていこうと思い立った次第です。 最初の曲は、上記『ハーヴェスト』に収録の「週末に(Out on the Weekend)」というナンバーです。アルバムのオープニング曲にしては何とものどかというか素朴なナンバーなのですが、筆者の個人的思い入れとしては、秋風が吹く山道をドライヴするのに最適な1曲だったりします。 もう一つ、ライヴ演奏もお聴きいただきたいと思います。発表当時(というか厳密にはアルバム発表の前年)の1971年、BBCライヴでの弾き語り演奏の模様です。 [収録アルバム]Neil Young / Harvest(1972年) ハーヴェスト<リマスター>/ニール・ヤング[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月08日
コメント(0)
-

アルカンヘル・ウルバーノ 『レジェンダス(Leyendas)』
“都会の天使”によるメキシコのアーバン・ロック アルカンヘル・ウルバーノ(Arkángel Urbano)は、メキシコの4人組ロック・バンド。直訳すると“都会の大天使”というのは何ともベタな名前に思えるが、その演奏スタイルもメキシコの大衆層向けのベタなロックというもの。メンバーは、ロベルト・カルロス(通称ダニーロ、ヴォーカルとリズム・ギター)、セサル・クルス(ベース)、ホアキン・ガジョソ(リード・ギター)、ダビー・アルバレス(キーボード)、ウリシス・ロサード(ドラムス、パーカッション)という5人組である。メキシコでその手の盤を多く手掛けるデンバー・レコードから2015年にリリースされたのが、本盤『レジェンダス』である。 1.「ラ・ジョローナ」は、ややヘヴィメタル寄りのシリアスな演奏がビシッと決まっている好曲だが、夜な夜な聞こえる女性の泣き声というメキシコの民間伝承を表題にしているというミスマッチが面白い。収録曲全体を見ると、ブルース/ロック・ベースのメキシカン・ロックが中心で、筆者に刺さるナンバーとしては、3.「アモール・インポシブレ」(“かなわぬ愛”の意味)、8.「フリアン」、12.「ティエンポ・デ・トリウンファール」(“勝利のとき”)といった辺りだろうか。 他の収録曲の中には、若くして母となった少女に捧げた7.「ア・ウナ・ホベン・ママ」、メキシコシティ近郊の高山を表題にした9.「イスタックシワトル(白い女性)」、イエス・キリストの名と曲調が見事なミスマッチ(?)を醸し出す10.「エル・ラメント・デ・クリスト」(“キリストの嘆き”)のような曲がある。かと思えば、日本人的にはやや仰天の11.「ゲイシャ」(“芸者”)なんて曲も含まれている。中途半端なバラード調の演奏にのせて、“月のごときゲイシャ~、白い肌、君のことが忘れられない~”といったような歌と演奏(もちろん本人たちは大真面目)。こうした部分も、“何でもあり”の面白さということで楽しめばいいのだろう。[収録曲]1. La llorona2. Recuerdos3. Amor imposible4. El blues de la verdad5. La historia de un perdedor6. Flores negras7. A una joven mamá8. Julián9. Iztaccíhuatl (mujer blanca)10. El lamento de Cristo11. Geisha12. Tiempo de triunfar (David Severo Carmona)2015年リリース。 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月06日
コメント(0)
-

ジョアン・マヌエル・セラ― 『エル・スール・タンビエン・エクシステ(El sur también existe)』
カタルーニャ人シンガーが“文学を歌う” スペインはカタルーニャ出身のシンガー、ジョアン・マヌエル・セラ―(Joan Manuel Serrat)の19枚目のアルバムとして1985年にリリースされたのが、本盤『エル・スール・タンビエン・エクシステ(El sur también existe)』である。セラーの有名曲の一つ「カンターレス」は、スペインの詩人アントニオ・マチャードの詩に音楽をつけたものとして知られているが、実はこの曲が収録されたアルバム(1969年の『詩人アントニオ・マチャードに捧ぐ』)そのものがそういうコンセプトであった。これと同様に、マリオ・ベネデッティを題材としたのが、本盤ということになる。 マリオ・ベネデッティは、ウルグアイ生まれの小説家、ジャーナリスト、詩人で、軍政下の祖国からアルゼンチン、ペルー、キューバ、スペインへと逃れて亡命作家生活を送った。亡命生活の最後の時期に当たるのが、ちょうど本盤の頃であった。そのベネデッティの詩を題材にして音楽にのせてセラーが歌うというのが、このアルバムのコンセプトである。 表題曲の1.「エル・スール・タンビエン・エクシステ(南もまた存在する)」は、世界におけるいわゆる南北格差が歌われており、南米出身のベネデッティならではの説得力がある。どの曲に関しても、セラーの歌唱力が生かされているが、筆者の好みでは4.「アガモス・ウン・トラート(取引をしよう)」、5.「テスタメント・デ・ミエルコレス(水曜日の遺言)」、6.「ウナ・ムヘール・デスヌーダ・イ・エン・ロ・オスクーロ(裸の暗がりの女性)」、10.「デフェンサ・デ・ラ・アレグリーア(歓喜の擁護)」なんかがいい。8.「アバネーラ」は、キューバのハバナがテーマとなっていて、これもまたベネデッティの亡命生活から生まれたテーマである。 上述のような“文学的な”盤ながら、リリース年から翌年にかけて4曲もがシングルカットされている(発売順に6., 3., 7., 4.)。文学作品がポップやロックの曲に化けるというのは、日本語では想像しにくいかもしれないが、この辺りはやはりラテン語の流れを汲む文化圏の底力なのかもしれない。それと同時に、亡命生活にある作家の声を聴衆に届けようというシンガーとしてのセラーの心意気があって誕生した盤ということであろうか。[収録曲]1. El sur también existe2. Currículum 3. De árbol a árbol4. Hagamos un trato5. Testamento de miércoles6. Una mujer desnuda y en lo oscuro7. Los formales y el frío8. Habanera9. Vas a parir felicidad10. Defensa de la alegría1985年リリース。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月03日
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-







