2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年12月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

すみませんが、お知らせ
ちょっと、忙しくて、年末まで更新できそうにもありません。申し訳ありませんが、これからも、ご贔屓してくだされれば、本当にありがたいです。年明けから、再開します。よろしくお願いいたします。
Dec 14, 2006
コメント(0)
-
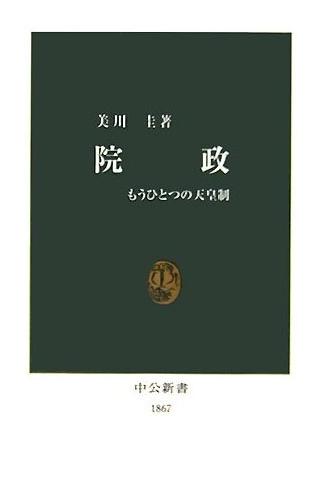
★ 美川圭 『院政 もうひとつの天皇制』 中公新書 (新刊)
良い本だわ。 素敵。 貴方にも、ぜひ、読んでほしいの。天皇だけでは、日本は分からない。 上皇も、入れなくてはね。院政とは、直系の子や孫を天皇位に付けることができた、譲位・隠退した「太上天皇」のみ行える政治なのよ。 名称は、中国のパクリなんだって。 弟に譲っても、父がいても、院政をおこなうことはできないの。 「院政」で有名なのは、白河・鳥羽・後白河の3代だけど、かの後三条上皇まで、「上皇」は16名も存在するんだって。奈良時代の「上皇」は、「女帝」だらけで、男性は「聖武」のみだったけど、平安時代になると、男性の上皇が大量に出現することになるわ。 これは、幼少期の天皇が即位できないので、「中継ぎ=女性天皇」で代用していた奈良時代から、「摂政」制度が定着して、幼年でも天皇が即位できる時代への移行を示すんだって。 「天皇のミウチ」が権力中枢を掌握する「即位しない一族=藤原氏」の摂関政治と、女帝の不在がパラレルな関係にあるとは、驚きよね。 なぜ、私が子供の頃、教えてくれなかったのかしら。宇多天皇以降、後三条天皇にいたるまで、170年間、藤原氏が外戚だったらしいの。 筆者は、白河院政以降ではなくて、後三条上皇を院政の基点においているわ。 実際の院政は、黒沢勝美以来、通説となっていた、「摂関家政所政治」から「院庁政治」ではまったくないの。 嘘っぱちなのよね。 どちらも、朝廷こそ中枢機関で、院宣などで「太政官機構」を動かしていたんだって。 院で御前会議が行われるようになったのも、鳥羽上皇の頃から。荘園制についても面白いわ。 摂関期以来の荘園は、武士などの在地領主層の所領形成と寄進を軸に考えられていたけど、実は違うんだって。 摂関政治の時代は、国家的給付の方が多いの。 白河院政の荘園整理令なんて、出たらめもイイトコロ。 荘園建設のピークは、12世紀半ば以降で、摂関家も王家も大量の荘園を集積したらしいわ。 また貴族たちは、寺社の強訴を恐れて、積極的に武士を取り立てたの。 院政秩序に一番適応したのは、平家だったのだそうよ。ご存知、保元の乱と平治の乱も、楽しい。 王家と摂関家、2大「権門」の拡大は、国家的組織よりも個人的主従関係の強化を生んで、統制がとれなくなるの。「実子ではない」という噂で、王家は分裂して、摂関家もゴタゴタ。 保元の乱を契機として、清浄の血であるとされた京都で、死刑が復活して、政争が武力で決着するようになるわ。 後白河上皇は、とっても不安定な王権で、鳥羽上皇の荘園をもらえないの。 普通、「平治の乱」以降、後白河上皇の院政が始まると思うんだけど、これが全然違うのよ。 二条天皇の「親政・院政」なんて知ってた? 二条死去後、高倉天皇が即位(1167年)するんだけど、高倉天皇の母親の外戚、平氏への遠慮を生み出し、平家の強大化を生むんだって。 平家あっての後白河院政。 平治以降、源頼政を除けば、平家は院の武力から独立した「権門」となるそうよ。 小学生の頃からの謎が解けたような気がするわ。清盛と後白河の対立は、清盛の妻の妹、建春門院の死去のせいで、傍系天皇にすぎない後白河の手足となってくれる「院近臣」層と平家の人事をめぐる争いが発端ですって。 1179年、平氏の武力で後白河院政が停止。 高倉院政が始まるの。 清盛が天皇の外戚になろうとした、古代的だ、と批判されるけど、それはウソなの。 源頼朝、承久の乱以降の鎌倉幕府と同様、院政を外部から操ろうとしたんだって。 魅力的な説よね。 以仁王って、なんか「綸旨」だけが有名で、おバカな王に見えるかもしれないけど、広大な所領を持っていた、美福門院の娘の庇護を受け、彼女の養子になっていた、って意外だったわ。 おまけに、反乱の時には権門寺社まで味方につけていたのよ。 源義仲は、以仁王系だったから、後白河と仲が悪かったの。その後、頼朝と後白河の間柄なんだけど、後白河は姉の関係者である頼朝にゾッコンだったのですって。 操りやすい義経に懇請され、頼朝追悼の宣旨を出したものの、清盛クーデター以降、効き目がなくなってしまい、義経は悲惨な末路に向かうの。後鳥羽院政は、わずか19歳、1198年に始まるわ。 最初にしたことは、政治ではなく、遊興。 それも和歌。 和歌は、1199年頃から始めたのに、1205年には勅撰『新古今和歌集』を作っちゃう、超一流の歌人。 素敵ねー。 卑官が作った『古今和歌集』とは違う、「文化の政治性」を示す国家的大事業なの。 今のおバカな天皇一家が詠んだ、ダサダサの和歌や俳句をニュースで聞かされるたびに、後鳥羽上皇の爪のアカを煎じて呑め!!といってやりたくなるわ。 おまけに、周囲をみんな味方にしてしまう力の持ち主。 歌の才能のない、「院近臣」実務層たちとも、「無心衆」と名づけたりして、「狂連歌」という笑いの絶えない、歌遊びをやるんですって。 管弦の才能もピカイチで、琵琶の名手。 ほんと風流な方で、私の敬愛する唯一の天皇といえるかしら。 そんな後鳥羽上皇は、討幕を狙っていなかったんですって。 源実朝と後鳥羽は義理の兄弟。 藤原定家の門下生。 歌を通じて実朝に影響力を行使しようとしたんですって。 面白いわよね。 実朝も「子どもを生めない体」と知っているので、大納言、右大臣就任と、源氏の家格を挙げようとしていたの。 しかも「承久の変」は、幕府の内部抗争の波及による京都の戦乱で、京都大内裏が消失したことが発端。 大内裏の再建の夫役を諸国に命じて果たされかったため、後鳥羽は討幕に走ったそうよ。 なんか子どもっぽいけど、ちょっと面白かったわ。 後鳥羽院政崩壊以降、院政はかわるわ。 制度的には、太政官制を「王」の「権門」が乗っ取る形で、他の「権門」を圧伏させていたのが、それまでの院政。 それが後嵯峨院政からは、院庁とは違う、国家制度として「院政」が整備されてしまうの。 親政も、院政も、同じ機関が担当するんですって。 ところが、強訴の対策を始めとして、軍事指揮権は、院ではなく、幕府に移ってしまうの。 摂関家の人事権についても、院は幕府に奪われ、「皇位選定権」も、北条家が握ってしまうわ。 しかし、院宣は、公的、国家的文書になっちゃう。 不思議よね。 院政をおこなう上皇や、親政をする天皇のことを「治天の君」と呼ぶのは、この頃から。後醍醐政権は、なかなか面白い政権みたいね。 後鳥羽以降、貴族支配の動揺を受けて、「本家職-領家式-預所職-下司職-公文職」という重層的土地支配構造に、雑訴評定・聴断など裁判を通じて、関与し始めていたんだって。 そこに御家人外と結びつくことで、鎌倉幕府が関与できなかった惣領決定に、後醍醐天皇は関与してゆくんですって。 新たな権力の次元が切り開かれていて、とても面白いわ。 院政は、足利義満でもって、終焉してしまうの。 とにかく、古代日本史に興味のある殿方なら、たまらない本でしょうね。 荘園をもち、権門とされる存在は、白河上皇(鳥羽殿)にしても、藤原摂関家(宇治)にしても、後白河(法住寺殿)にしても、平氏(六波羅)にしても、都市領主として独自の都市を構想して実現させていた、ってご存知かしら。 摂関家の登場は、院政期以降。 なぜなら、天皇の外戚でなくても、摂政関白につけるのだから…というのも、言われてみれば当然の話よね。 源義家が朝廷から遠ざけられたのは、金貢納の滞納であって、武士を恐れたというのは根も葉もないことなんだって。 後白河と摂政藤原(近衛)基通は、男色関係にあったそうよ。 誰か、「後白河×藤原基通」本を描いてくれないかしら。 ねー。 天皇が外交使節に会うのは穢れるのでダメ、ということで、後白河も、平清盛も出家入道になって、福原で宋の使節と謁見したというのは、ギャグよね。 天皇アキヒトも、出家したらどうかしら。 そういえば、慈円『愚管抄』によれば、承明門院は、藤原通親と密通して土御門天皇を産んだそうよ。 土御門の血筋以降には、アマテラスの男系DNAは混じっていないのよ。 これって、男系天皇神話の破綻よね! 反対派はどしどし宣伝して頂戴!! (笑)ただ、疑問点もあるわ。 『後醍醐天皇は、親政を目指していたんではない。 後鳥羽院政以前の「天皇の人事権」「軍事指揮権」の回復、「本来の院政の姿の回復」を目指していたんだ』という指摘は、面白いけど言葉遊びにすぎないのではないかしら。 すでに、国家機構は、「院政」「親政」も、同じ機構になっているんではなくって? ならば、院政であって親政ではない、と言うことに、どれほどの意味があるのかしら。 面白いけど、「狙いすぎ」な感じがしてしまうわ。 さらに、いただけないのは、院政が実質的に義満で終わったとされてしまったことかしら。 たしかに、義満以降、天皇制そのものが後景に退くわ。 室町以降復活を唱える人もいるけど、少なくとも国家機構でみれば、存在感はないわね。 それでも、「院」について、ざっとでいいから、触れておいて欲しかったわ。 とっても、いい本だけど、ちょっと、固有名詞が多すぎて、困っちゃったのもタマにキズね。 ここまでの本を書くなら、新書の巻末に人名・地名索引をつけてほしいわ。 これからの、中公新書の課題かもしれないけど。とはいえ、私のお薦め。 こんな本が、新書で出されるのは嬉しい限りだわ。みんな、本を買って、「洛陽の紙価を高らしめ」なくては、ダメね。評価 ★★★★価格: ¥ 861 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 13, 2006
コメント(1)
-
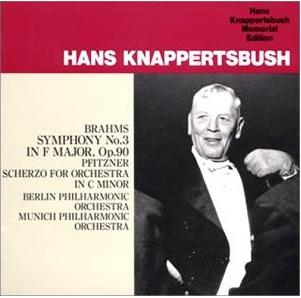
★ 『のだめカンタービレ』 を糾弾・爆砕せよ続編 ブラームス交響曲3番と指揮者クナッパーツブッシュ
▼ ドラマ版『のだめ』を聴いてしまったせいか、ブラームス狂いが再発してしまった。 おかげで、何十枚もあるブラームス全集を再び探し出す日々を送っている。 理想のブラームス演奏にはとっくに出会えている、というのに、僕は何枚買えば気が済むんだろう。▼ とりあえず、クルト・ザンデルリンク『ブラームス交響曲全集』ベルリン交響楽団を持っていないので、それを買いたくて仕方がない。 評判がいい交響曲全集だけど、若干高い。 初心者はやめておいた方が無難なのだけど。▼ 漫画『のだめ』のフランス編をすでに読まれている方は、ご存じだと思うが、今現在、のだめはフランスに留学している。 そこで、アナリーゼという、楽曲分析のクラスに参加。 友達になったリュカと、楽曲の分析にいそしむのだけど、最初のお題は、ブラームス交響曲3番、第3楽章である。 ▼ うーん、アナリーゼには驚かされたなあ。 恥ずかしながら、僕は、未だに「調性が変わったね」と指摘されても、分かんない人間なので。(笑)▼ そんな、クラシック初心者が騙されやすいのが、音楽評論家、宇野功芳氏である(笑)。 とにかく、この人のクラシック評論に騙されて泣いた人間は、吉田秀和の比ではないだろう。 とにかく、偏りすぎ。 指揮者だと、モロに現れてしまう。 朝比奈隆を褒めちぎり、小沢征爾をけなしまくる。 ヴァントは持ち上げるが、チェリビダッケは嫌い。 フルトヴェングラーとワルターとムラヴィンスキーは礼賛するが、トスカニーニやカラヤンは「親の仇」のようだ。 ▼ たしかに、この人のおかげで、フルトヴェングラー指揮『シューマン交響曲4番』とかの絶品にも出あえたけれど、クズも随分とつかまされた。 所詮、評論家と趣味があわないと、クラシックは聴いても感動はしないもの。 その辺、『のだめ』でにわかに興味を持たれた方は、十分、注意してほしい。 あなたの感性を評論家に合わせる必要などありません。 ▼ そんで。▼ そんな宇野功芳氏のお薦めの名盤CDのひとつに、ドイツ人、クナッバーツブッシュ指揮『ブラームス交響曲3番』ベルリンフィル、1950年、というものがある。 『クラシックCDの名盤』(文春新書)でお薦めとされている。 宇野功芳のクラッシク業界における罪状(功績?)のひとつは、「クナッバーツブッシュとシューリヒトの発掘・普及」というのがあるだろう。 ▼ おそらく、ここまでクナッバーツブッシュが持ち上げられるのは、日本クラシック界くらいなものではないか? この人は、メジャーではなく、マイナー・メジャーな指揮者だったし。 ワーグナーやブルックナーの素晴らしさを力説してくれるのだが、あいにく、「ブルックナーは神の音楽だぞ!!」と力説されても、神ならぬ人でしかない私には、理解できない。 ▼ そんで、偶然、この『ブラームス交響曲3番』(ベルリンフィル、1950年)のCDを中古CD屋で600円で発掘してしまったのだ。 冒頭の画像CDにも収録されているのだけど、海外版でちがうもの。 とにかく、狂喜乱舞しましたね。 こんなに安ければ、買ってもいいだろう。 ▼ 聴いてみた。 聴いてみた。聴いてみた。……▼ なんですか、これは。(笑) ▼ 一読して大爆笑しましたね。▼ 冒頭が凄い大爆音。 「天地創造」って、宇野先生、そりゃ、言いすぎでしょう。 金管が唸りをあげて、ファンファーレを吹き鳴らし、凄まじいテンポ・ルパート。 なんつったって、普通のブラームスを聞き慣れている身にとっては、音楽が「止まる」「止まる」。 ほとんど、冗談にしか聞こえない怪演奏のたぐい。 (笑)▼ というか、ブラームスじゃないだろう、これは(笑)。 許光俊は、「クナッバーツブッシュ受容は、偉大な芸術家とゲテモノ演奏家の2通りある」と書いていたが、まさしく、ゲテモノの類。 こんな演奏をブラームスの名盤でござい、と薦めるのは、さすがにどうかしていると思う。 こういうのは、通常、どのような演奏がスタンダードなのか、理解した上で聴くべきだろう。▼ この人のブラームス3番でも、↑こちらの1944年版の方は、ここまで「狂っていない」演奏だけど、彼にブラームス演奏を求めるのは、酷だろう。 普通に、チェリビダッケや、ザンデルリンク、ヴァントなどのブラームス全集で聴いておきたいものだ ……… チェリビダッケなどは、ブラームスこそ素晴らしいと思うのだけど、ブルックナーの方が評価されている。 うーん、交響曲2番、4番なんて、最高だと思うんだけどね。▼ あと、『クラシックの名盤』において、メンゲルベルク指揮『マタイ受難曲』アムステルダム・コンセルトヘボウ、1939年版を、評論家2名が名盤に挙げているが、これも「バッハではない」演奏だ。 拍節感皆無。 「こんなバッハは聴いたことがない」くらい、凄い演奏。 たしかに「ベートーヴェン第九」的なドラマ感溢れるマタイ受難曲。 オペラちっく、とも言えるかも知れない。 その合唱には圧倒されることは確かなんだけど、初心者は普通にカール・リヒターにしておくべきだろう。 峻厳なバッハが楽しめて良い。▼ とりあえず、趣味のあう音楽評論家を見つけるまでが大変。 その大変さもまた、楽しみの一つと開き直るしかないだろう。クラシックCDの名盤 (新書) 評価 ★★☆価格: ¥ 924 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 11, 2006
コメント(2)
-
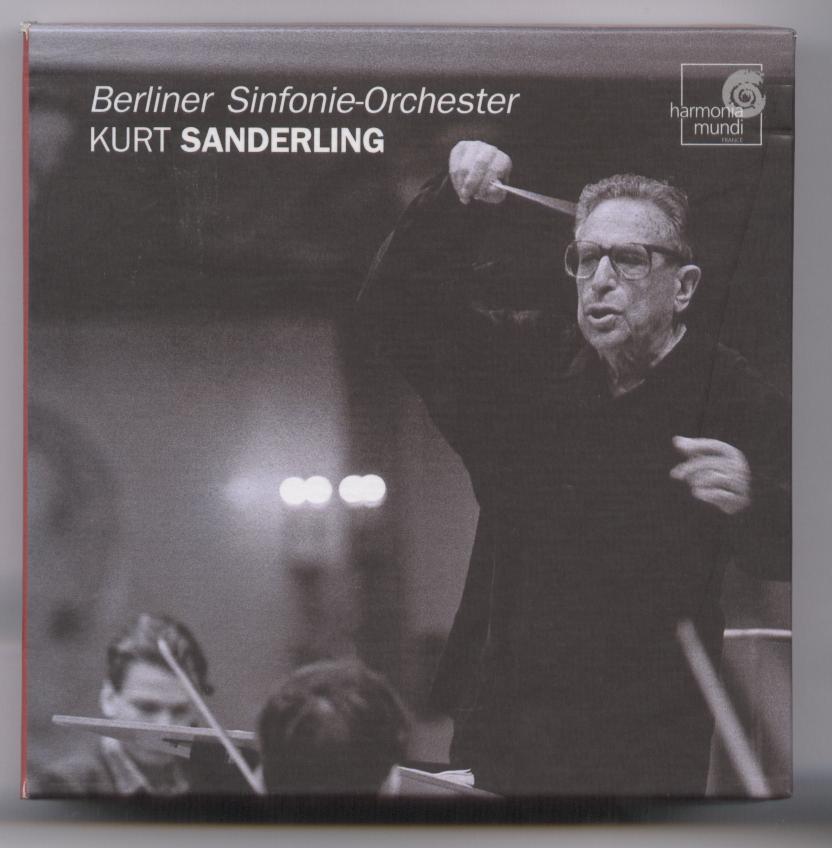
★ テレビドラマ 『のだめカンタービレ』 を糾弾・爆砕せよ!!!!
もー、許せない。 ぜ~ったい、許せないわ。 もちろん、ドラマ版『のだめカンタービレ』のことよ。これまで私、ドラマ版『のだめカンタービレ』って、見てこなかったわ。 なぜなら、私は大の『のだめ』ファン。 指揮者ミルヒーが、竹中直人って、許せるわけないじゃない。 おまけに主演が上野樹里。 たしかに、映画『スイング・ガール』は良かったわ。 で、「ジャズの夢よ、もう一度!」とでも言いたいわけ? あんまりじゃない。 そうなの。 私、見ると、絶対怒っちゃうって、分かっていたのよ。 だから見るのを我慢していたの。 ところが、周りから聞こえてくるのは、雑音ばかりなのよ。 「のだめカンタービレは、とても面白いね」「竹中直人に味があるんだよ」「原作をきちんと踏まえて作られて好感が持てる」「原作が生かされている」 嘘よ!嘘だといって!お願い!!それでも、私、半信半疑だったわ。 ミルヒーは、どうやらドイツに帰ったみたい。 これで竹中直人を見なくてもすむわ。 そろそろかな、と思って、FMラジオで、とうとう、音声のみだけど、ドラマ番組を聞いてしまったのよ。 もー、ちょー、最悪。 死ね、って感じ? どうして、番組内で使われるBGMが、みんなクラシック曲ばかりなわけ? 『銀河英雄伝説』アニメ版で、ドラマにクラシックが似合わないことは、とっくに知られたことじゃない。 古典期ハリウッド映画だって、BGMは通俗クラシックばかりよ。 クラシック音楽は、存外、使われていないのよ。 クラシック音楽を使いまくるのは、それこそ田舎モノのコンプレックスでしかないの。 私、見ていて、とても恥ずかしかった。 それでも、ガーシュウィンや、ロマン派音楽なら、私、耐えられたわ。 ドラマチックだし、素敵な曲も多いわ。 それなのに、どうしてバロック音楽の最高峰、バッハ『マタイ受難曲』最終コラールを使うわけ?!! 十字架で死んだ後、復活したキリスト。 死と救済への、喜びと悲しみ。 その気持ちが渾然一体に謳いあげられる、崇高な合唱。 いったい、視聴者をどういう気分にさせたくて、使ってるのよ?マタイを使うなんて、どーゆー、シチュエーション?。 あんなダサい使い方は、許せないわ! キリスト教への冒涜よ!そもそも、「R☆S(ライジング・スター)オーケストラ」そのものが変よ。原作では、シューマン「マンフレッド序曲」、モーツアルト「オーボエ協奏曲」、ブラームス「交響曲第一番」の3本立て演奏会。 シューマンとブラームスの重なりは気になるけど、バランスのとれた演奏会だわ。 それなのに、マンフレッド序曲が削られてるじゃない。 いったい、どういうことよ。 今年は、シューマン没後150周年だというのに、シューマンに喧嘩を売ってるのかしら、脚本家は。 これでは、片肺演奏会じゃない。ちょー、最悪なのは、ブラームス『交響曲1番』よ!!!!私、ブラームス交響曲1番は、ブラームスのラブソングだと思ってるの。 ブラームスの師匠、ロベルト・シューマンが残した、若き未亡人クララ・シューマン。 その彼女に、ブラームスが永遠の愛を誓った、ラブソングではなくって? 第4楽章。 もし、ブラームス交響曲1番を持っている方なら、「ホルン-木管-金管」と引き継がれる「クララ・シューマンのテーマ」の使い方をよーく見てくれないかしら。 少しも先の見えない、絶望の淵にたつブラームス。 そこに、クララ・シューマンが訪れる。 その姿に打たれるブラームス。 そこからおもむろに、第4楽章の主題が流れ出し、ブラームスは、絶望の淵から帰還するのよ。 むろん、それだけじゃないわ。 その希望さえ打ち砕かん、と荒れ狂い襲いかかる「絶望」から、救い出すのも「クララ・シューマンのテーマ」。 そして、第4楽章最後、救済への階段を登っていくブラームスを、天上にあって祝福するのも、「クララ・シューマンのテーマ」じゃない。 そうよ。 「クララ・シューマンのおかげで私は救われたのです」と告白するベタベタな作品こそ、交響曲1番。 これがラブソングじゃなくて、なんと言うのかしら。 それなのに何よ。 「このオーケストラは美しい」。 おまけに千秋真一。 きっと、ギュンター・ヴァント指揮北ドイツ放送響のように、颯爽と高速かつ高密度に、第1楽章のテーマを処理してくれるに違いないわ。 そう思って期待していたら、まったく逆で、漫然として緊張感のない、第1楽章じゃない。 肩透かし、失望もいいところよ! おまけに、いきなり第4楽章の再現部手前に飛んだ後、また飛んで今度は第4楽章コーダ(終結部)よ。 「クララ・シューマンのテーマ」も、「ベートヴェン第九交響曲のパクリ」といわれた第4楽章の主題も、演奏しないなんて許せると思う? これでブラームス交響曲1番でござい、なんて断じて認めないわ !!!!! それだけじゃない。第4楽章コーダで、千秋の言うセリフがまたひどい。「悲劇から希望へ」よ。いったい、脚本家は、なにを考えてるのよ!。 原作では、「悲劇から希望と救済へ」になっているわ。 当たり前よ! 第4楽章のコーダでは、とっくに希望を通りこして「救済」されている段階じゃない。 どうして、ドラマの中で現に流れている音楽と全然あっていないセリフを千秋に言わせるわけ?もちろん、簡単なことだわ。 『のだめカンタービレ』の脚本を書いている人間も、音楽をつけている人間も、監督も、クラシック音楽を何も分かっていないのよ。 「原作をきちんと踏まえて作られている」「原作が生かされている」なんて、ウソよ。 「原作をそのまま使わなければ、クラシックの無知がバレてしまう」からだわ。 もう、テレビ番組紹介を初めとしてウソばっかり。 『スイング・ガール』の良い思い出が台無し。 こんなものに騙されてるのは、よほど音楽経験のないバカなのね、としか言いようが無いわ。 もう、失礼しちゃう。 プンプン!!あまりにも怒って疲れちゃった。 『のだめカンタービレ』の「口直し」に、ブラームス交響曲1番を聞きなおしてしまったわ。 聞いたのは、チェリビダッケ指揮RSOシュツットガルト、ヴァント指揮北ドイツ放送響、クルト・ザンデルリンク指揮ドレスデン・シュターツカペレね。 良かったわ。 とくに、意外と良かったのが、かつては「名盤」と呼ばれたこともある、クルト・ザンデルリンクよ。 昔から好きだったけど、聴きなおして、さらに好きになったわ。 燻したような東ドイツのオーケストラの音色が、ブラームスにとても合うのよね。 ザンデルリンク指揮『ブラームス全集』(ドレスデン・シュターツカペレ)は、1700円前後でタワーレコードで売ってたとき、買ったのだけど、今も手に入るのよね。 世の中、モノの価値が分からないバカ、って多いのよね。 これは、安さと質に関しては、比類ないCDだから、探してぜひ聴いてあげて。 お願い。 あと、興味があるなら、ザンデルリンク引退演奏会のCDが、絶対お薦めだわ。 モーツアルト「ピアノ協奏曲24番」の内田光子の演奏には涙が零れ落ちるほど感動させられるの。 もう、一音、一音が天上の音楽。 わたし、これでモーツアルトの音楽の素晴らしさをやっと理解できたわ。 これを聴かないで、「モーツアルトの音楽は心地よいわ」なんていってる人間になってはダメよ。 内田光子は、ザンデルリンク引退コンサートで、本当に素晴らしい仕事をしているわ。 他の彼女のCDと聴き比べても段違いよ。 欲しい方は、ぜひ、ゲットしてほしい。ブラームス交響曲全集評価 ★★★☆価格: ¥ 1,290 (税込) ザンデルリンク引退CD評価 ★★★★☆ 価格: ¥ 3,500 (税込)追伸 お姉さま言葉は疲れました. もうしません. 許してください ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 6, 2006
コメント(3)
-
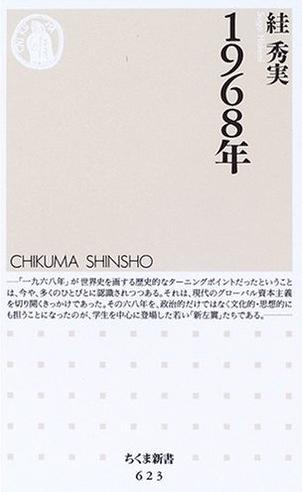
★ 糸圭 秀美 『1968年』 ちくま新書 (新刊) 後編
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ 第4章は、「華青闘告発」で浮上した、マイノリティーについて語られる。 女性、在日、部落民、障害者、琉球人、アイヌなどの問題の噴出……… それは、マジョリティー=自治会組織に包摂されないことで出発した、全共闘運動の帰結である、という。 もはや正史は、この段階には、存在しない。 ▼ この「偽史」の創出と実践は、「世界革命」という大きな物語への批判として展開された。 とはいえ、この「偽史」への転換を先取りしていたのは、新左翼ではなく、三島由紀夫。 かれは、「偽史」への滑り落ちを防ぐために「天皇」というジョーカーを必要としたのだ、という。 この意味では、偽史的想像力に彩られたかにみえる、吉本隆明『共同幻想論』でさえ、「正史」の優位性、「核」を前提とした、相対化にすぎない。 吉本隆明の影響下にあった新左翼は、このような「硬い核」をもとめる、ナショナリズムにすぎなかったという。 ナショナリズムの克服においても、偽史的想像力、ヴァーチャルな思想に逸脱する他はなかった。 「異端趣味」を越えた「偽史の時代」、オカルト・ブームの到来であり、歴史や政治ではなく、「虚構と幻想小説」の季節の到来であった。 網野史学も、この一翼に連なるながら、「正史」を主張する強力なもの、であるという。 また村上春樹の文学も、この一翼をなすという。 ▼ 第5章は、華青闘の突きつけた課題が、内ゲバとどのように結びついていたのか、丁寧に論じられていて、かなり刺激的な内容である。 フェミニズムとエコロジーは、今でこそ新左翼のもたらした果実の2枚看板であるものの、「統一と団結」を阻害するものであって、マイノリティー運動ともども、「革命」まで臥薪嘗胆すべきものであった。 この時期では、上野千鶴子が批判したように、「ウーマン・リブ」のある種「本質主義的」段階であって、社会構築主義段階にいたっていない。 しかし、この「本質主義的」違和感が、革命によっても解決されない課題の存在を認識させ、マイノリティー運動を準備していく。 華青闘告発にもっとも鈍感だったのは、新左翼創設と60年安保を主導した、吉本隆明であり黒田寛一であり、また革マル派だった。 マイノリティー運動の課題にもっとも誠実に取り組んだ中核派は、「不可能な囲い込み」を行おうとしたのではなかったか。 「日本人が革命の主体になりうるのか?」という、あまりにも回答できない問いかけ。 その問いかけへの誠実な回答こそ、内ゲバという「暴力革命」の遂行に他ならない!!!!! われわれは、内ゲバが革命でないことを知っている、しかしそれを革命として遂行しなければならない。▼ この論理こそ、武装蜂起と呼号しながら、その手前に留まって暴力闘争を実践するアイロニカルな方策であったという。 連合赤軍が、武装蜂起の前で「セミナー的共産主義」を実施した挙句、過労死することは避けなければならない。 もはや近代的規律・訓練によって形成される「主体」は存在しない。 どこまでも軽い主体。 ▼ ここに、革マル派と他派の決定的差異が存在するのではないか、という提起こそ、本書の白眉かもしれない。 規律・訓練的主体形成に全力を注ぎ、蜂起の日を永遠の彼方においている革マル派は、1968年以降、新左翼各派から追放の憂き目にならざるをえない。 どこまでも軽い主体が陥る、シニシズムの罠を切断すべく、革マル派が実施したのは、内ゲバの「首謀者」である「はず」の中核派・本多書記長の殺害と、殺害の後、当然到来しなければならない、「テロ停止宣言」であった。 しかし、内ゲバは収まらない。 中核派のテロは、最高指導者の命令に従うようなものではない。 すでに、そのような主体は解体しているのだ。 かくて革マル派は、「権力の謀略論」を唱えることになる。 われわれは、内ゲバが「権力の謀略」でないことを知っている、しかしそれを謀略として断定しなければならない …… あたかも、中核派のシニカルをなぞるかのように。 これだけで、立花隆『中核派 VS 革マル派』を読んだことがある人には、お釣りがくるというものだ。▼ もはやレーニン主義的機動戦は有効ではない。 グラムシ主義的な多様な市民・社会・文化集団による陣地戦=ヘゲモニー闘争の積み重ねが、革命に至る道 ……… それはマルチチューど(by ネグリ)の行う革命ですら、同様であるという。 社会構築主義に拠る限り、革命は陣地戦以外ありえない。 しかし、グラムシ主義は、マイノリティー問題を進める上で不可欠であるにもかかわらず、革新自治体などの成果をあげたにもかかわらず、結局、何の進展も生まなかったとして退けられてきた。 また、その動きは、多文化主義の擁護という形で、「本質主義」に加担せざるを得なかった。 シャンタル・ムフやジジェクのように「決断主義」に走るのか、「構造改革主義」にとどまるのか。 飛べばいいのではないか。 われわれは飛べるのではないか。 とはいえ、飛べないがゆえに、われわれが生存しているのではないか…… 本書の考察は、そこで、閉じられる。▼ 全般的に、かなり貴重な回顧録といえるかもしれない。 日本の新左翼は、ルカーチやサルトルを参照せず、吉本隆明「自立主義」の流儀のためか、国内文献のみだけで論じていたらしい。 太宰治は、戦後共産党に入党していたことがあるらしい。 石原慎太郎人気の秘訣とは、「教養主義=穏健なリベラリズム」に対する切断であり、大正デモクラシーに対するマルクス主義や宮本顕治「敗北の文学」の反復である、という視点も斬新でいい。 また、吉本隆明『転向論』において、「中野重治>宮本顕治」と論じられた中野重治でさえ、「硬い核」たる正史と党から隔たりながらも、転向者としてその「核」に寄り添うことで、狂気から逃れようとした人物である、とされる。 中野重治論としては、一読しておきたい部分だ。 ▼ また、思考方法も、とても楽しい。 『「民主か! 独裁か!」と竹内好が問いかけたとき、なぜ誰一人として、「然り、独裁である(プロレタリア)」と返答できなかったのか?』 『連合赤軍事件を見て「武装闘争はいけない」というのはおかしい。 あれは、武装闘争に入る前のいうなればセミナーにおける過労死だ』団塊おじさんらしい、目からウロコのようなものといえるだろう。 ▼ とはいえ、問題点は、言い出せば、キリがないだろう。 ▼ まず、新左翼は敗北していたように見えるけど、実は勝利していた。 ただし「新自由主義」として、という思考自体が、本人は気の利いたことを言ってるつもりかもしれないが、ただの「強がり」というか、敗北主義的にしか見えない。 さらに、新左翼の「ナルシシズム=ナショナリズム」の転換点として「華青闘」を挙げるのは、一般的に「ナショナリズム」に対する反省と、「左翼=反ナショナリズム」の出発点としては適切だろう。 議論的に新味が乏しいものの、われわれのイメージの由来なのだから。 しかし、そこで「ナルシシズム」は、転換できているのか。 「ナショナリズムを否定できる自己というナルシシズム」という形で、その構図は、温存されたままではないのか。 「ナルシシズム=ナショナリズム」という分析項を導入しているのはいいが、最終的に、議論の足を引っ張っているようにみえなくもない。 ナルシシズムの構造転換、の方が議論がスマートに思える。 ▼ 何よりも、結論が意味不明であって、読者は途方に暮れるしかない。 結局、「構造改革主義」を唱えたいのか、「決断主義」を呼びかけているのか、まったく定かではない。 だいたい、ジジェクの「決断主義」は、ムフのそれと同じなのか。 ジジェクのそれは、イデオロギーの自壊を促進させるため、という一面をもっているのだから、ここで「決断主義」を連合赤軍幹部の言説とともに称揚するのは、辻褄があっていないだろう。 真にイデオロギーが実践されたとき、それは自壊するしかないのだから。 また、スラヴォイ・ジジェク、シャンタル・ムフたちの議論を読んでいない左翼からすれば、斬新な議論かもしれないが、読んでいると理論適用の仕方が、正直、うざくて仕方がない。 かつて、小林よしのりの漫画分析に、「俗情との結託」(by 大西巨人)を適用したようなもの。 いかがわしくて仕方がない。 ポスト・モダン以降特有の現象であることを説明する、「内ゲバ」分析は、たいへん面白かったが、それ以外はやりすぎだろう。▼ 右翼・保守言論界の現状は、かつての新左翼と同じ。 その姿は、朝日新聞社刊行『アエラ』先週号で、憐憫マジリのカラカイを受けている惨状である。 まあ、八木秀次の「白い共産主義」という造語には笑うしかないのだが、右翼の方々にとっても、何か裨益するところがあるのではないか。 ▼ とまれ、一読はお勧めしておきたい。 評価 ★★★☆価格: ¥ 903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 2, 2006
コメント(2)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…
- (2025-11-16 04:53:29)
-







