2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年09月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

★ 高橋哲哉 「国旗・国歌訴訟 判決を『異例』にせぬために」 『朝日新聞』 2006年9月30日朝刊 /メモ
● 私の視点・ウィークエンド 国旗・国歌訴訟 高橋 哲哉 判決を「異例にせぬために」 1891(明治24)年1月、世に言う内村鑑三不敬事件が起こった。第一高等中学校の英語教員であった内村が、教育勅語奉読式で十分な拝礼をしなかったとして、天皇に対する「不敬」を社会的に指弾され、学校をやめざるをえなくなった事件だ。 学校行事での日の丸・君が代の強制が進む昨今の自体を見るにつけ、私はいつも内村の事件を思い出す。 東京都教育委員会が教職員に「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを義務づけた03年の「10・23通達」以来、君が代斉唱時の不起立などを理由に処分された都内の教職員は約350人にのぼる。君が代斉唱時の生徒達の声量指導を求めた東京都町田市教委や、声量調査と指導が実際に行われた福岡県久留米市のような例もある。 教育勅語への頭の下げ方が足りないといって排除されるのと、起立しなかったとか声の大きさが足りなかったといって処分されるのと、どれほどの違いがあるだろうか。100年以上前の内村の事件が、すでに過去のものになったとは言えない社会を私たちは生きているのではないか。 東京地裁は21日、都教委の「10・23通達」と、それに基づく職務命令を違憲・違法とし、それらによる処分を禁止する判決を出した。 印象的だったのは、原告側も被告側も一様に、この判決に大きな驚きを表していたことだ。「1%も敗訴は予想していなかった」という都教委職員がいれば、「夢のような判決で信じられない気持ちだ」という原告の教員がいる。これは、現在この国で、教育の自主権がいかに尊重されず、上意下達が当たり前のことになってしまっているかを示しているのではないか。 判決の核心は、現場の裁量をいっさい許さない通達や職務命令によって起立斉唱を迫ることが、憲法19条に保障された思想・良心の自由の侵害であり、教育基本法10条で禁止された「不当な支配」に当たるという判断にある。現憲法と教育の理念を定めた教育基本法の立法趣旨からすれば、ごくまっとうな判断であるように思える。 どうやら私たちは、現憲法や教育基本法の趣旨に忠実な今回の判決が、「夢のよう」に思えたり、「1%も」よそうできなかったり、「異例」で「画期的」で「歴史的」な判決と評される社会に生きているらしい。都教委は判決を不服として、29日に控訴した。しかも、いまや憲法と教育基本法の全面改正を掲げる安倍政権が誕生したところなのだ。 現憲法と教育基本法のもとでなら、強制を「不当な支配」として「違法」と断ずる審判がまだ可能だ。しかし、国民の自由と権利の制約を強める改憲案や、教育の主体を国民から政府・行政に移す教育基本法改正案が通ってしまえば、そうした可能性そのものがなくなってしまう。 思想・良心の自由や教育の自由を大切に思う人たちに、今回の判決は「まだ希望はある」と感じさせた。だが、現在の政治の大きな流れが変わらなければ、この「画期的」な判決も過去の単なる一エピソードとなり、やがては忘れ去られてしまうだろう。 民主主義が目指してきた姿が本当に「夢」になってしまわぬように、何ができるのか―――。私たち一人ひとりが胸に問いかけてみたい。 ◇ 56年生まれ。著書に「教育と国家」「靖国問題」など。▼ おおむね、妥当な見解で、ケチのつけようがない。 あまりにも正論すぎて、むしろ胡散臭いくらいだ。▼ そもそも、学校教育の現場で、都教委がゴチャゴチャ自主性を重んじない命令を出すのは、「不当な命令」以外のなにものでもない。 読売の社説は、『 そもそも、日の丸・君が代に対する判決の考え方にも首をかしげざるをえない。「宗教的、政治的にみて中立的価値のものとは認められない」という。そうだろうか。各種世論調査を見ても、すでに国民の間に定着し、大多数の支持を得ている』と、わざわざ書くことで、ゴミ売新聞が「過去の戦争を侵略と認めるだけの、ただの全体主義新聞社」にすぎないことをあらためて明らかにしてくれた。▼ バカか、ゴミ売新聞。 多数派は、どんなに多数でも、「中立的」になるはずがないだろう。 「部分」が存在するようなものは、断じて普遍ではないし、中立的たりえない。 「人間は2本足」が中立的か? 足が失われた人はどうなる。 もしも「国旗・国歌はマナー」というなら、マナー共同体だけの間でやればいい。マナー共同体の外にある、別の規範をもつ共同体に適用してはならない。 それが「良心の自由」の制度的担保というものだろう。 国旗国歌問題とは、マナーなる共同体でしか通用しないような、規範をめぐる問題ではない。 あくまで、「法」の次元で裁かれなければならない問題であろう。 ≪「通達」は、憲法・教育基本法という、より高次な判断基準に従っているか≫について、今回の裁判では問われたにすぎない。 そして、高橋哲哉の言うとおり、当然のように、違憲判断が下されたのである。▼ とはいえ、私自身としては、どんなもんかな、という感じである。 私が先生なら、「日の丸・君が代」の際、起立して歌いなさい、と言われれば、さて従うかどうかとなると、たいへん微妙な所ではあったりするのである。 どうするべきなんだろう。▼ というのも、「国旗・国歌なる思想そのものを認めない」という人間だからである。 だいたい、「人民」(別に国民でも市民でも可)とそれによって作られた国家の尊厳が、「国旗」「国歌」にこめられている、という考え自体、迷信・物神崇拝・カルト教団の教義としか言いようがない。 どうみても、ただの布きれ、ただの音波でしかないように思うんだけど。 そんなものに、どうして崇高さを感じたりできるのだろう。 挙げ句の果てに、「崇高さを感じさせる教育をわざわざ施したがる」というのだから、変態人間はどうして他人を道連れにしたがるのかねえ、以外の感想は抱きようがない。▼ 要するに、みんなが「崇高」というから、「崇高」と感じる、反省的知性に乏しいということなんだろうね。 変態は、変態共同体を作って自分たちだけで変態的に暮らしていればいい。変態じゃない他人まで、まきぞえにしないでほしいんだけど。▼ 老人党を結成した、なだいなだ氏によれば、「イズム」とつくものは全部中毒と表現すると本質がみえてくる、アルコホーリズムは「アルコール中毒」というように―――と提言している。 ナショナリズムは国家中毒、マルクス主義はマルクス中毒と言うようにしよう、というのだ。 なるほど、言い得て妙、と膝をハタと打った次第である。▼ それは別にしても、「日の丸・君が代」なるものが、どんなにバカバカしいものなのか。 少し以下の事態を思い浮かべてほしい ――― ボロ雑巾が国旗で、ジョン・ケージの「4分33秒」や、騒音のような「フリージャズ」が国歌である状況を ――― さすがに、どんなに国家中毒の人間でも、萎えるのではないだろうか。 どのみち崇高なのは、みんなが崇高だと思っているから、すなわち「関係性の産物」にすぎない。 そんな関係が自明のモノでない人間にとっては、ただのカルトな妄想にすぎない。 ▼ だからこそ、これが「日の丸・君が代」になると、どんな対応をとるべきのかについて、逆に困ってしまうのだ。 こんな本質的にマヌケな国旗・国歌なんかの反対運動は、バカバカしいから参加しないというのが筋なのか。 それとも、思想信条の自由とは、行動について保障されなければ意味をなさない、として、断固反対闘争に参加するのが筋なのか。 はたして、どちらが「正しい身の処し方」なのだろう。▼ まあ、そんな決断が必要となるような事態を防ぐためには、憲法改正反対、教育基本法改正に反対しておいた方が無難なんだろう。 やれやれ、本当は改憲派なんだけどなあ、僕は ……←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 30, 2006
コメント(8)
-
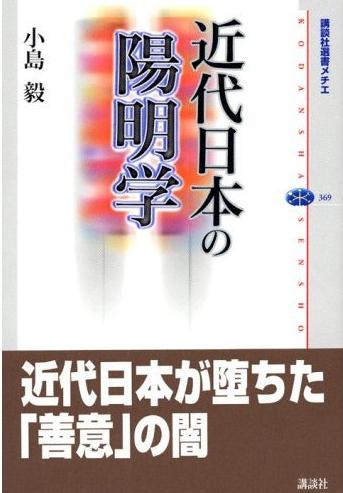
★ 小島毅 『近代日本の陽明学』 講談社選書メチエ (新刊)
▼ 靖国神社は神道ではない! 伊勢神宮参拝と靖国神社参拝は、本質的に違う! 靖国神社とは、「儒教教義に基づいた社」なのだ…▼ 実に平明な文章で、高橋哲哉『靖国問題』でさえ、見落としていた史実を丁寧に拾う。 それをまとめると、「靖国神社と遊就館」は、具体的中身がない、純粋動機主義の陽明学が、「英霊」の語の由来、藤田東湖に代表される、天皇中心的独善的「大義名分論」の水戸学(朱子学)と結合したものである、というのだ。 靖国神社は、設立以後を見ても理解できない。 われわれは、今も江戸時代の延長に生きているのだ……。▼ 簡単にまとめておこう。目次は次の通り。 1 大塩中斎―やむにやまれぬ反乱者 2 国体論の誕生―水戸から長州へ 3 御一新のあと―敗者たちの陽明学 4 帝国を支えるもの―カント・武士道・陽明学 5 日本精神―観念の暴走 6 闘う女、散る男―水戸の残照▼ エピソード1では、大塩平八郎というよりも、江戸期陽明学が描かれる。 陽明学者は、陽明学を師匠から伝授される必要がない。例外なく、朱子学の学習によって陽明学者、自称「聖学の徒」になるという。 そのため党派意識が乏しく、内部分裂も激しい。何ごとにも囚われない「良知」ゆえに、「近代的精神」と評価を受けてきた大塩の思想について、孔孟の教えの実践であると解く。▼ エピソード2では、藤田東湖に代表される、江戸期の水戸学が描かれる。 「開祖」徳川光圀編纂『大日本史』は、神功皇后を「皇后」とする(=最初の女帝は推古)、大友皇子を即位させる(=天武天皇は簒奪者)、南朝正統(=『太平記』好きのため)という「3大特筆」をおこなうものの、藩財政の1/3を費やさせ、水戸には納豆とウメボシしか残らせない。 推古以後も皇后でいいはずなのに、女帝にしたのは、仏教功労者の聖徳太子を即位させるのは、朱子学過激派として許せなかったためだという。 江戸時代の儒教は、五山仏教(臨済宗)との決別と神道への接近から始まり、神道そのものが儒教的に変質して、「日本古来の伝統(=国体)は儒教的であった」という言説が成立してゆく。 その中で、歌道から始まった「国学」が、儒教から独立したという。▼ エピソード3では、御一新後の敗者たちの生き様をあつかう。 漢学教育の私塾、二松学舎を設立して、「四句教」を座右の銘とする、大正天皇の教育にあたった三島中州。 『王陽明』伝で、ショーペンハウエルやカントを引き合いに出しながら、普遍主義的な思想であることを強調した、国粋主義者、三宅雪嶺。 とくに、内村鑑三が面白い。 西洋人向けに『代表的日本人』を書いた内村は、キリスト教徒でもないにも関わらず、西郷隆盛のような人物が日本にいるのは、キリスト教にかわる精神支柱、「陽明学」を奉じていたためだ!!という。 日本では、真摯な儒教徒ほど、熱心なキリスト教徒になってゆく。 それも、信者が内面の良心の命ずるままに、「聖書」に示された神の教えを実践してゆく、いわゆる無教会主義プロテスタントに改宗する陽明学的キリスト教徒になるらしい。王陽明を投影した人物としての、イエス・キリスト。 神社・仏閣でお辞儀する必要のない、開放感。 「良知」は「良心」に、「万物一体の仁」は「隣人愛」に、「四書」が「聖書」に、置き換えられたにすぎないのではないか。 内村鑑三不敬事件などを引きあいに出しながら、この視角を打ち出すのには、唸らされるほかはない。▼ エピソード4では、カントと陽明学、武士道をつなげる、驚愕の地下茎が明らかにされる。 その地下茎の名は、帝国大教授、井上哲次郎。 江戸時代儒学を「陽明学」「朱子学」「古学」に3区分して、「哲学史」として叙述することの創始者。 ペルソナに「人格」という訳語をあてた人物。 日清戦争勝利によって、ひたすら「西洋化」を目指した従来の路線は、微妙に修正され、開花か国粋かの対立は揚棄。「アジアの古き良き伝統を守りつつ近代化」したことが、アイデンティティとなってゆく。 その中で、政治・経済・科学技術も、全面的にドイツに倣うことになる。 とはいえ、ドイツ哲学、とくにカント哲学が日本では好まれた理由は、「独立自尊」を尊ぶ武士道が、理性の独立自尊を説いたカント哲学に近いためだという。 やがて、陽明学の本流は日本にあり!という言説がまかりとおり、固定的教説を指さない「良知に従って誠実に生きていく実行主義精神」として、独立自尊の志士の精神、すなわち「自分の頭で考えた末の国体護持主義」としての≪白い陽明学≫理解が定着した。 その反面「維新の志士」を称揚するため、幸徳秋水・山川均たち社会主義ラインからも、陽明学を革命精神と捉える≪赤い陽明学≫も出現する。 陽明学者はキリスト教徒になり、社会主義者にもつながっていく過程が分かって、なかなか面白い。▼ エピソード5では、国家社会主義者たちの群像が面白い。 高畠素之は、「階級的搾取以前から国家は、支配統制のために必要」「社会主義においてこそ国家はいっそう重要になる」といい、「万物一体の仁」的な性善説にのっとり、政府を転覆すれば理想社会が出現すると信じてやまない、社会主義者たちと袂をわかつ。 大川周明も、国家主義的革命家としてのレーニンを高く評価する。 またエピソード6では、三島由紀夫と社会主義者山川菊栄の邂逅をえがく。 非常時に文学的快楽に浸っていた平岡公威は天皇の玉音放送、草莽崛起を期待して「憲法擁護、日中友好、女性解放、非武装中立」をかかげた山川菊栄は、その草莽に裏切られてゆく。 三島由紀夫切腹事件は、「決起しない自衛隊員」を前提とした、自衛隊総監を儀式の証人とする、常軌を逸した計画性をもっている。 三島自体、陽明学的精神の対極にある人物であって、陽明学への傾倒や当日の檄文は、本気のフリをしたにすぎない。かなり刺激的な内容であることが分かるだろう。▼ とにかく概説として、たいへん面白い。 おまけに文体も流麗。 スラスラ読むことができる。 明治時代の東洋哲学史では、カントの位置に、王陽明が置かれていたという。 われわれのイメージする陽明学者(吉田松陰、西郷隆盛)は、「体制派=朱子学」「反体制派=陽明学」の公式をあてはめることによる、後世の図式にすぎない。 終いには、元田永孚まで、陽明学者にカウントされていたらしい。 大川周明は、無茶苦茶漢文が読める人で、高校の時「伝習録」を講じていたこと。 吉川英治『宮本武蔵』が、安岡正篤『日本精神の研究』の武蔵観に依拠していること。 三島由紀夫の石原慎太郎批判が、組織に属しながら組織外にむかって内部批判を公言する、武士道に背く西欧的態度、無責任さにあった(不満があれば諫死すべし)こと。 会沢正志齋が「大政委任論」であるのに対して、吉田松陰が「天皇親政」、「哲学」のみならず「理性」の訳語を作った人物は西周、「啓蒙」は大西祝などの豆知識は、たいへん素晴らしい。 とくに「英霊」とは、天地の正気が集まって正しい道理を実現して死んでいった祭祀対象(=神)であって、断じて「心ならずも戦場で命を落とした人たち」の謂いではない、と批判する下りには、蒙が啓かれる思いがするにちがいない。▼ ただいかんせん、いささか大風呂敷を広げすぎて眉唾部分と、概説部分との差がありすぎるような気がする。 とくに、社会主義と陽明学を一緒にする下りには苦笑せざるをえない。良知の実践が陽明学??? マルクスは、「フォイエルバッハのテーゼ」で、「哲学者たちは世界を様々に解釈してきたにすぎない。重要なのは世界を変革することである」と言っている以上、定義上、あらゆるマルクス主義者は陽明学者にならざるをえないではないか。 陽明学から性善説が来て、社会主義者は云々という下りは、たんなるデタラメにすぎないだろう。 いったい、レーニンを批判したローザ・ルクセンブルクは、陽明学的性善説に基づいているとでも言う気なのか。▼ 山川菊栄にいたっては、性善説的マルクス主義者以外には、陽明学とは無縁の存在。 いくら、「血のつながり」が面白いからといって、こんなデタラメな議論をされても、読者は置いてきぼりだろう。 てか、あとがきで、「エピソード 1」などの表現が、「スターウォーズ」から取ったことを嬉々として書いてあるのだが、この辺の態度と、通底しているような気がしてならない。▼ 図書館で見かけたら、読む。買うのは遠慮、というのが正しい態度と思われる。 そのためやや辛い評価を付けさせてもらった。評価 ★★★価格: ¥ 1.575 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 26, 2006
コメント(3)
-
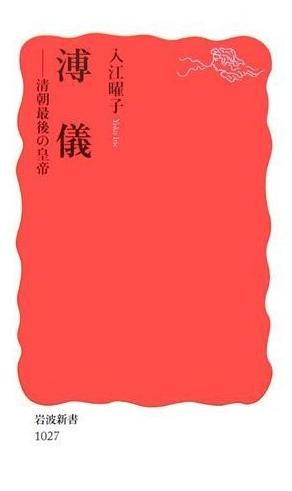
★ 入江耀子 『溥儀』 岩波新書(新刊) <2>
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ かくて後半生、「人間改造という実験」が開始される。日本人による収奪に加えて、内戦と天候不順で、飢餓に苦しんだ、撫順戦犯管理所の所員たち。 親類・知人を殺した日本人戦犯たちは、シベリア抑留時代の「卑屈さ」とはうってかわって、「戦争捕虜であって戦犯ではない」「新成立の国家に収監権限はない」などと居丈高に所員に議論をふっかけた。 「コーリャン飯」を出した日には、これ見よがしに捨てたという。 中国は、朝鮮戦争で、負けるかも知れない。 そうなると、日本人戦犯の自己確認の手段は、シベリアでは読経・謡曲の歌唱にすぎなかったのに、中国では「宮城遙拝」「君が代合唱」「教育勅語暗唱」という、大日本帝国のシンボルに変容させ、かつての支配者意識を剥き出しにするようになる。 なんでこんな奴らに、「白飯」「一汁三菜」を与えなければならないのか。 周辺の農民が、管理所から見たこともないような豪華な残飯を発見してしまい、管理所に苦情が殺到した。 管理所所員の9割が、「こんな人間を矯正することなんてできません」と転勤願いを出す始末。 周恩来に辞表を提出した所長は、懸命に慰留されるありさまだという。 管理所所員の懸命の努力(いったん土葬した死体の火葬改装ほか)や管理所の状況がわかるにつれて、日本人戦犯は徐々に心を開いてゆき、有名な「認罪運動」「告発大会」へとつながることになる。 日本人戦犯よりも真摯に自己を改造したのは、管理所の所員であったという指摘は、感動的というほかはない。 もっとも、人間改造の最大のターゲットは、溥儀その人。 その詳しい状況は、確認してほしい。 人間改造に尽力した、李文達、金源といった人々は、皆、文革で失脚させられるのだが。 ▼ とにかく、20世紀中国史を網羅するスケールの大きさには、感嘆させられる。 清朝の皇位継承が、「公開建儲制」→「秘密建儲制」→「懿旨建儲制」と移行したこと、「輩字」による一世代一皇帝制だったことは、指摘されるまで気付かなかった。 袁世凱は、帝制運動の際、袁世凱家と清朝皇族の間に縁戚関係を取り結び、「溥儀の岳父」になって「清朝へ大政奉還」しようとしている、と遺臣たちに思わせていたらしい。 その手練手管には、あきれかえるだろう。 シノアズリー(東洋趣味)をもつジョンストンは、溥儀の近眼に気付き、後にトレードマークとなる、丸「眼鏡」をかけさせたことで、家庭教師には収まらない信頼を溥儀から勝ちえたという。 また、満州国の皇室は、イザナギ・イザナミを模して、溥儀と婉容から開始される、としたため、かの溥傑でさえ、皇族ではなかった。 譚玉齢病死後、不特定日本皇族との婚姻(指婚)をもとめたものの果たせなかった溥儀は、最終的に子供を産むのをあきらめ、「幼い少女を自分の手で養育する」ことを願い、李玉琴をめとったという。 東京裁判で溥儀を偽証まがいの弾劾に駆り立てたのは、ソ連側の教唆ではなく、信頼した皇室や自己を利用した日本人が、「漢刊」として裁かれる自分に対して、慰めの言葉をかけるどころか、弁護に名を借りて糾弾をおこなう日本人への嫌悪にあった、という指摘には、あらためてうならされるほかはない。 ▼ また、人間改造後帰国するまで、自主的な食事管理が認められて、温室野菜栽培をおこなっていた日本人戦犯は、国民党系戦犯たちとは違い、管理所の外側での「大躍進」による大飢饉によって、管理所所員が次々と倒れていたことに、まったく気付かなかったという。 溥儀夫妻は、旧い身分意識を決して捨てようとしない、日本人嵯峨浩を妻に持つ溥傑夫妻と、「新中国」成立後、感情的仲違いしていたこと。 溥儀が、腎臓ガンにおかされる中で、前妻と後妻がいがみあってしまい、「一緒に入れないでほしい」という遺言を守って、結局3度移転した溥儀の墓所と違う所に、後妻李淑賢は埋葬されているという。 こうした秘話は、なかなか面白い。 ▼ なによりも、前半生では「復辟」、後半生では「自己の生存」のため、「権力」をもつものにすりよってゆく溥儀の姿は、あたかもカメレオンのようだ。 溥儀も共産党も、「改造された溥儀」を必要とするためお互い演出をいとわない。 その真摯な姿は、滑稽みさえ帯びてくる。 主演・溥儀のメンツに配慮しながら、脚本・共産党は「改造」をすすめるものの、もともと改造されていないため、溥儀はそのシグナルを理解できない。 認罪運動を始めとして、失敗をかさねてしまう。やがて、薫陶よろしく、「共産党の期待を先取りすることができる人間にきちんと改造」される、溥儀。 李玉琴とは離縁するものの、「改造された家庭」をもってほしい、当局期待に応え、溥儀はさっそく看護婦李淑賢と結婚する。そのため、彼の認罪書である「自伝」は、ドキュメントとして面白くするためにも、溥儀の行動の整合性のためにも改訂がおこなわれざるをえなかったという。 しかし、そのような生き様は、「日本の期待を先取り」できるような人間、すなわち漢奸とどのような質の変化があるというのだろうか。 ▼ もはや、冒頭の問いは、とっくにでているのだろう。 溥儀は、なにひとつ「人間改造」されていない。 そもそも、かれが退位後、紫禁城の奥で学んだ「帝王学」とは、いったい何なんだろう。 「帝王学」とやらは、この世に存在するのだろうか。 あるというなら、マニュアルとしてまとめられば良いだろうに、そんなものは、つゆ聞かない、帝王学。愛子内親王、悠仁(ひさひと)の教育に必要といわれ、本来皇太子とは違い受けていないはずの秋篠宮が、近年、天皇の側にいることで、いつのまにか「伝授され」「身につけた」とされる、摩訶不思議な「帝王学」。 「帝王学」をまとう王者も、人間改造をうけた公民も、この世には存在しない。 あるのは、「関係」によってそのたびごと規定される、「私」だけなのではないか。 溥儀の生涯をみて感じるのは、溥儀の中にある、途方もない「空虚」である。 ▼ そのため本書は、溥儀の2面性に着目するというものの、どこがどう2面性をもっていたのか、最後まで分からなかったのが惜しまれる。とはいえ、力作の本書。秋の夜長に一読されてみてはいかがだろうか。評価 ★★★★価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 23, 2006
コメント(0)
-

★ ふざけんな!毎日新聞は、朝日新聞と将棋連盟に土下座して謝罪しろ!
▼ 将棋名人戦 共催、新たな試み 連盟を支え、条件協議 2006年09月19日(朝日新聞) 朝日新聞社と毎日新聞社が19日に協議入りを表明した将棋名人戦の共催は、七つある将棋のタイトル戦や、囲碁のタイトル戦でも、全国紙同士では過去に例のない形だ。将棋界最古のタイトル戦での新たな動きに、日本将棋連盟の米長邦雄会長は「両新聞社の読者が一番喜ぶことになるよう願っています」とコメントした。 日本将棋連盟と主催社との間で結ばれるタイトル戦の契約は、七番勝負や五番勝負で行われる「挑戦手合」と、挑戦者を決める予選などの棋譜を独占使用するため、その対価を契約金などの形で将棋連盟に支払う内容となっている。 名人戦では、第36期(78年)以降、朝日新聞社に代わって再度主催社となった毎日新聞社が第65期まで3期ごとに契約を更新。第64期の契約金は3億3400万円だった。 一方、米長会長のもとに設けられた経営諮問委員会から名人戦契約の移管を打診された朝日新聞社は今年3月17日付で(1)契約金は年3億5500万円(2)将棋普及協力金は年1億5000万円(3)朝日オープン将棋選手権に代え、契約金が年4000万円の棋戦を実施する――という5年契約の条件を提示した。 5月になって米長会長は朝日、毎日両新聞社に名人戦の共催を提案。棋譜を使用する観戦記などは両社で独自に掲載する▽両社の関係は対等である▽契約期間は5年間との基本線を示したほか、共催する両社の拠出額の合計が、現在の名人戦の契約金と朝日オープン将棋選手権の契約金の合計(約4億7000万円)を上回るよう求めていた。 毎日新聞社が共催の協議入りを表明したことを受け、米長会長は「5月の(共催)提案をたたき台にして話し合っていきたい」と述べた。契約金の分担や棋譜使用などについて将棋連盟を交えた3者で協議するとともに、朝日新聞社が提示していた将棋普及協力金や朝日オープン将棋選手権に代わる棋戦についても、改めて話し合う。 ◇ 〈毎日新聞社社長室広報担当の話〉 日本の伝統文化である将棋の振興に寄与することを第一に考えたうえ、将棋界の将来を担う現役棋士の皆様からの強い要望などを考慮し、対等の立場での名人戦共催の協議を始めることを決めました。 〈朝日新聞社広報部の話〉 将棋はわが国が誇る伝統文化です。毎日新聞社と対等な立場で共催し、より多くの読者に名人戦を伝えることは、将棋文化の発展・振興に寄与することにつながると考えます。実りある話し合いにしていきたいと思います。 ▼ さすがに呆れかえるほかはない。 毎日新聞が「名人戦共催」を受け入れるという回答を将棋連盟によこしたことについて、である。 毎日新聞は、記者が署名記事を原則とする、良い意味で「記者に個性」があるため、政治的立場が「あいまい」になりがちだが、「懐の深い」メディアと高く評価してきた。ここまで、節操・志操、信義というものがない新聞社が、かりにもジャーナリズムを名のっているとは恥ずかしくて仕方がない。▼ そもそも伝統ある名人戦は、ファン、棋士、スポンサーといった、ステークホルダー全体にまたがる、パブリックな財産にほかならない。 あろうことか、その財産を「毎日新聞の名人戦を守ります」と、毎日新聞の一所有物に貶めた挙げ句、将棋連盟と朝日新聞に対して、ネガティブ・キャンペーンを張りつづけたのだ。▼ そのネガティブ・キャンペーンのひどかったこと、ひどかったこと。 他社の週刊誌を使い、米長の女性関係疑惑をかきたてさせ、自らの紙上では「将棋連盟を金の亡者」呼ばわりした。 中原誠副会長が、契約更新しない旨を記した通知書を渡しに、毎日新聞社を訪問したときの態度について、ネチネチと非礼よばわりしたことは、心底、その陰湿さには怒りさえ覚えた。非礼を理由に文書を「撤回しろ!」として、引き下がらない。 むろん、文書を撤回させないと、毎日名人戦を継続させることができないためだ。 中原の非礼など、「言いがかり」にすぎない。 とはいえ、いくら林葉直子への「突撃」で名を落としたとしても、かりにも「棋界の太陽」とよばれた人格者、「大名人」中原誠に対してする仕打ちか!!!▼ その将棋連盟から「共催」を提案されても、蹴ったのは当然の見識だろう。名人戦は主催新聞社のものだ、という論理なら、「共催」なんてありえない。 「単独開催」のみに賭けて、失敗したらおりるのが、筋を通すというものだ。かくいう私は、「毎日新聞は王将戦をビッグタイトルにすべき」派ではあるし、「名人戦を守る」など偉そうにほざきながら、100万円アップ「3億3500万円×7年」契約というシミッタレにはあきれた。 だが、さすがに「棋士総会」で受け入れられければ、名人戦主催社から降りるのだろうと思っていた。 毎日新聞の歴史的「所有権」なるものを「総会」で否定されてしまえば、毎日新聞が名人戦をやる根拠はどこにもない。 さすがに恥というものを知っていれば、共催を断って、王将戦に金をつぎ込むかするだろう。▼ それがこの体たらく。 あきれるのは、「日本の伝統文化である将棋の振興に寄与することを第一に考えたうえ、将棋界の将来を担う現役棋士の皆様からの強い要望などを考慮し、対等の立場での名人戦共催」のくだりだ。 そもそも毎日新聞は、5月16日付社説において、朝日新聞から名人戦を自分たちが強奪したことに触れることなく、「一方、共催案に前向きな朝日新聞は将棋と囲碁の名人戦を共に主催するのを強く希望してきたと聞く。…… 自前の棋戦を知恵を絞って日本一に育て、相応の資金を棋界に提供するのが文化貢献のあるべき姿なのではないだろうか」とタンカきったのである。▼ さすがに、言いだしっぺ。 自前の棋戦、王将戦を知恵を絞って日本一に育て、相応の資金を棋界に提供するのか?と思っていたら何のことはない。 毎日は名人戦に固執してもいいし、共催にのってもいいが、朝日は共催にのってはダメ、日本一棋戦を棋界に提供しなければならないらしい。 ダブスタメディア、毎日新聞。 いったい、どこまで根性が腐りきった新聞社なのか。 こんな恥知らずは、今まで見たことがない。▼ むろん、将棋連盟には、心よりお喜びをもうしあげたい。 まったくの部外者であるが、実は名人戦問題を解決する、腹案があった。 それは、名人戦は朝日新聞に移すが、順位戦は毎日に残して、順位戦を母体とした大型新棋戦(順位戦のトップを王将にしてもいい)を立ち上げることである。 名人戦は、A級順位戦をそのまま新規名人戦に移すが、もっと降昇格の自由度の高いリーグにする。どうせ朝日は名人戦が欲しいだけ。 しかも竜王戦を主催する読売新聞にとっても、「名人戦の権威」が低下する分、利点は大きい。 そう考えていた。 むろん共催でもそれなりに良いだろう。 双方、それぞれ2億5000万は出さなければならない。 従来よりも余分に金が入る。連盟としては、それでいい。大事なスポンサー様なのだから、強気にでるのもヘンな話である。▼ また、朝日新聞には、よく罵詈雑言に耐えた、と心より感謝したい。 本来、棋譜の独占掲載権がない、共催なんかに何の利益もありはしない。 それを「棋界の発展」のために、「共催」受入とは …… ウソからでたマコト、「断ると思ってたのに…」という気分かも知れない。 正直、朝日新聞がアマ棋界にお金を使っていることを知っている人間からすれば、今回名人戦単独主催してしまうと、アマ棋界に使った金が、何か不純な、名人戦を手に入れるために使われたような気にさせられてしまう。 こんなもんで良かったのかも知れない。 とにかく、ありがたいことだ。▼ だがファンとしては、断じて毎日新聞を許すわけにはいかない。 最初から毎日新聞が共催を受け入れていれば、将棋界がここまで毎日新聞のネガティブキャンペーンで傷つくことはなかった。 共催よりも新棋戦で貢献せよ!と他社に要求したことをケロリとなかったことにする毎日新聞の変節漢ぶりを徹底的に糾弾しなければならない。 将棋ファンをなめるにもほどがある。毎日新聞ふざけんな!と思う人はクリックお願いします↓↓↓↓↓↓↓ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 20, 2006
コメント(2)
-
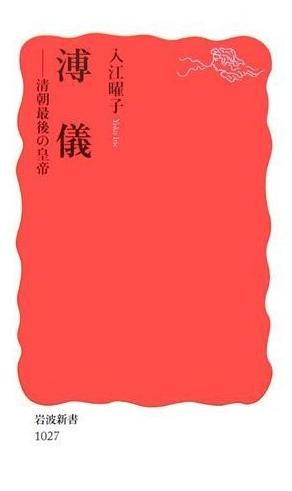
★ 入江耀子 『溥儀』 岩波新書(新刊) <1>
▼ 『週刊新潮』によれば、秋篠宮家のご息女、眞子・佳子両内親王が、このたびネットでひそかなブームになっているらしい。「高貴なお血筋」「美貌」のプリンセス萌え~~~~なんだとか。驚いた。なるほど、国技館に、大相撲の観戦に来たのか、相撲をとりに来たのかさえ判然としない、天皇家の「呪い」をあまりにも濃厚に受けついだ、「悲劇のヒロイン」愛子様と比べれば、ルックスは断然、両内親王がいい。それは認めよう。しかし、愛子様よりもブサイクな女性など、この世では希少価値ではないのか。『プリンセスといえば、ミネバ様かアザリン様!』 (←古い)と刷りこまれてきた身からすれば、眞子・佳子両内親王で「萌え」られるとは、無欲・博愛の即身成仏の精神なのか、図々しさ・不敬の極北なのか、いまいち良く分からない。 ▼ 狂想曲は、まだ終わらない。秋篠宮家に生まれた男児は、悠仁(ひさひと)と名づけられた。近年「悠」は、人名漢字としての使用が認められ、「悠人」「悠真」などが上位にくるなど、たいへん人気が高い。そこに、41年ぶりの皇室の男子誕生だ。それにあやかって、名前に「悠」を使うブームの予兆があるのだとか.........。やれやれ。ここが中国なら、たいへんな不敬である。皇帝権の本場中国では、至尊の「名前」を使ってはならない、「避諱(ひき)」という習慣が存在した。「悠」だの「仁」だの使えば、不敬罪。命の保証すらない。皇帝が変わるたびに、地名・人名の漢字が変更されてきた。中国歴代皇帝の名前に、結構ヘンな名前が多いのは、一般人があまり使わない漢字で命名される配慮がなされたことが多かったためなのだ、、、、って皆さん、ご存じでしたか?。今回、ご紹介するのは、そんな本場中国のラストエンペラー、宣統帝溥儀(1906年2月7日~1967年10月17日)の生涯をえがいた伝記である。悠仁(ひさひと)生誕記念で、ラスト・エンペラーを読んでみるのも、これまた一興であろう。▼ 溥儀とは、なにものか。生涯3度、皇帝の座につき、最後には思想改造によって、「人民という名の共和国の主人」となる、奇跡的偉業をなしとげ、「中国共産党の広告塔」となった男。その姿は、映画『ラストエンペラー』でもおなじみだ。しかし、本書は問いかけをやめない。溥儀は、はたして、本当に改造されたのだろうか、と。 ▼ 1908年11月23日、西太后の懿旨が下り、次期皇帝が内定した溥儀。「終身禁固の囚人になる」として、養育係が溥儀を手放そうとしなかったことは、その後の未来を暗示しているかのようだ。翌24日西太后死去。12月2日、即位。憲法と国会開設をもとめる立憲派の政治プログラムを約束しながら、袁世凱を追放、皇族「親貴内閣」の成立と続いた。さしもの立憲派も、清朝を見放して、離反してしまう。そこに辛亥革命が勃発。袁世凱は、革命派・清朝宮廷・外国公使館を巧みに操り、2ヶ月におよぶ御前会議の末、保皇派を追放する。1912年2月2日、隆裕太后に「優待条件」とひきかえに、宣統帝退位の上諭を出させることに成功して、自ら中華民国大総統の地位に就任する。 ▼ 溥儀の2度目の登極は、1917年7月1日。俗に「張勲の復辟」という。弁髪軍の反乱は、紫禁城に投下された爆弾3発(中国最初の空襲)によって、たちまち蹴散らされ、12日後に退位を余儀なくさせられる。依然、維持されていた北京の「小朝廷」。いつとも知れぬ、「復辟」をこいねがい、「帝王学」にはげみながら、まったく報われない日々は、いつしか溥儀の心中に、イギリス留学の夢をはぐくませる。1922年、天津租界でイギリス風教育を受けた婉容と、文綉の2名と大々的に挙式した翌年、イギリス留学を敢行せんとするも、情報がもれてしまい失敗してしまう。年間700万両が必要とされる清朝皇室維持費は、退位時定められていた、400万両さえ満足に払われることがない。紫禁城から次々と宝物が流出する日々。そんなさなか、1924年奉直戦争において、日本軍部の工作によって、馮玉祥が張作霖に寝返ったのは良いものの、かれは「優待条件」解消を持論とする、クリスチャン・ゼネラルだった。11月5日、紫禁城から溥儀は追放されてしまうのだ。軍閥に殺されかねない中で、仮住まいである「北府」は危険だ。いったい、どこの公使館に移るべきなのか。イギリスへ行きたい!。その溥儀の身柄は、間一髪で、日本公使館の手に落ちる。 ▼ 1925年2月以降、天津租界での生活は、イギリス留学も、日本渡航も実現しない、モラトリアムの日々といえるだろう。紫禁城とはちがう気ままな生活だったものの、財政は破綻寸前に追いこまれていた。張作霖爆殺では、一時、天津を抜け出して、満州に行こうとしていたらしい。租界でくらす日々も、乾隆帝と西太后の陵墓盗掘事件などで、溥儀の心は深く傷つく。「側妃」文綉は、一夫一妻制がドミナントである天津租界で暮らしていくうちに、自分のおかれた環境に気付き、皇帝相手に前代未聞の離婚訴訟をおこしてしまう。 ▼ 満州事変では、日本軍の手を借りて「復辟」をかなえられると信じて天津を抜け出したものの、「五族協和」の欺瞞に鬱屈させられる。溥儀は、1935年4月の訪日において、皇太后節子の心温まる待遇をうけたことが、「傀儡」皇帝として生きる中で、心の支えになっていったらしい。これ以降、「天皇と私は平等、一心一体」の実感をいだき、日本人には天皇と同様の扱いをもとめたという。建国神廟建設による、儒教から神道への満州国「国教」変更計画はまだしも、アヘン中毒の皇妃婉容に子が産めないことを見越して、溥儀に男子なき場合、皇帝が天皇に直接願い、日本の男子皇族を皇太子―――具体的には義宮正仁、現在の常陸宮―――を継がせる計画まであったのだとか。その傀儡ぶりには、開いた口がふさがらない。1937年、貴人として迎えた譚玉齢の病死(1942年)は、後の東京裁判では、「反満抗日」を恐れた日本側による「譚玉齢貴妃毒殺事件」(そもそも、中華民国の刺客の幻影に脅えていた溥儀は日本人医師を頼らざるを得ないのだが)として、証人として出廷した溥儀に弾劾されることになるが、ここまでくると、いい気味だとしか思えない。関東軍支配で禁止されていた清朝儀礼が、満州国帝宮の奥深く、溥儀と「清朝王族」の満州族青年たちの手によって、おこなわれていたという事実には、うそ寒いものを感じてしまう。▼ 満州国崩壊後、8月18日、飛行機で日本にむかうはずだった溥儀は、日本側の命じた飛行ルートの変更にしたがった所、なぜか奉天飛行場で、飛来したソ連空挺隊に捕らえられてしまい、シベリア捕虜収容所に送られてしまう。嫌々ながら「溥儀亡命」を受け入れた日本政府の一部が仕組んだ罠ではなかったか、など諸説あるが、真相は今も不明らしい。ひそかに国民党政府とつながっていた満州国の中国人官僚とは違い、売国奴で極刑が免れられない溥儀は、シベリアに抑留され続けること、あわよくばヨーロッパに亡命することを願い、国共内戦の永続化を望んだものの、1950年7月、中国に引き渡されてしまう。 (続きはこちら応援お願いします 長すぎて1日では終わらなかった…)評価 ★★★☆価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 18, 2006
コメント(0)
-
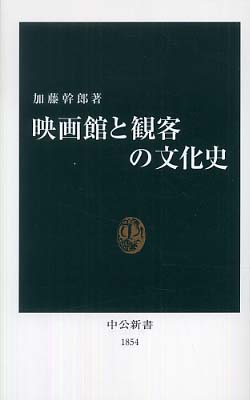
★ 加藤幹郎 『映画館と観客の文化史』 中公新書(新刊) <2>
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ 「第二部 日本編」も、興味が尽きない。アメリカで古典ハリウッドの時代が始まる1915年頃、洋風建築で建てられた大手常設映画館でさえ、宣伝は「大絵看板・幟・呼び込み」であって、映画ポスターではなく、地方の芝居小屋を改装した映画館では、下足制の雛壇式畳座席だったという。アメリカとは違い、名物弁士がいても、楽士が軽んじられたのは、歌舞伎/浄瑠璃の「義太夫語り」の伝統に起因するらしい。1930年代半ば、世界映画史的に見ればとっくに説明者が姿を消していたにも関わらず、日本の映画館で「弁士」が影響力を有していたのは、1917年「弁士免許制」が導入され「公的認知」されたことも大きいという。アメリカ映画館の「合唱」の慣習は日本にもみられ、人口に膾炙した小唄を下敷きにして、「小唄映画」―――風景(サイレント映画)に歌詞がつけられ、脇の女性歌手が歌う―――が作成され、浅草オペラ以外では成立していなかった「歌手」という職業を興行として成立させる大きな力になった。サイレントからトーキーへの移行は、人間的音声から機械的再現音への変化だけではなく、男性弁士から女性歌手への、変容であった。移行期には、映画を実演するダシモノさえあった。1920年代末のアメリカと同様、1930年代半ばには、日本にもニュース専門映画館が建設されてゆく。▼ 「映画都市の都市の誕生―――戦後京都の場合」では、地域における映画館文化を明らかにする。映画そのものよりも、映画館の快適性、快適な鑑賞環境―――「空調」「待合室」「喫茶室」「公衆電話」だけでなく、「雰囲気」も―――を約束することで、1950年代、映画館は「日本映画の全盛時代」を準備したという。それは、景品の提供だけではなく、映画鑑賞システムにまで及び、「流し込み制」「定員交流制」「定員入替制」などの試行錯誤がおこなわれた。とくに京都では、いつどこでどんな映画撮影がおこなわれているのか、京都新聞に情報が掲載されていた。それは、観客としてだけではなくクルー(という幻想)として映画に参加することを通して、蓄積された歴史を映画の中で発見=「映画都市京都の再発見」が行われたという。映画にあって、テレビにないモノは、「共同性の構築」である。そう警鐘が鳴らされて、本書は終わる。▼ なによりも、視点が楽しい。「テレビ/ビデオ文化」の登場は、1890年代エジソンの「キネトスコープ」や、1940年代の映画ジュークボックス「パノラム」といった「一人で見る映画」の再検討を迫っているのではないか。ハリウッド映画は、故郷や民族や宗教、あるいは父親といった同一性の拠り所を失った男たちによる、そうした人間たちのための無意識的ノスタルジーの娯楽ではないか。3つの視線―――カメラの視線、登場人物の視線、観客の視線―――の統合と視線のリレーによって成立している古典的―――古典期(1917年~)以前には登場人物の視線(主観ショット)はない―――ハリウッド映画のパワーは、「切り返し」編集―――見る主体、見られる主体のショットをつなぎ合わせる―――が前提とする「カメラの偏在性」を通した、≪超越的な見る主体≫としての「観客」を作り出す「観客生産」能力にあり、そのことがネイティブ・アメリカンたちが白人カウボーイの視点から西部劇を楽しんだりする現象を産み落としたのだ、という指摘には、唸らされる他はない。▼ また、トリビアも面白い。映画の起源にある多様な「映像」文化の指摘。「黒人劇場」の存在したアメリカ。サイレント時代、活動写真「弁士」が大きな役割を占めていた国は、タイと日本だけだったらしい。1907~9年まで、アメリカの公開映画の半分から2/3は、外国映画だったという。航空機の外に巨大スクリーンを設置しての映画鑑賞。「劇場、駐車場、ホテル」が合体した「シアター・モーテル」では、モーテルの窓から映画をみることができた、のだとか。他にも、日本では、映画と演劇を融合させた「連鎖劇」が映画草創期にみられこと。サイレントからトーキーへの移行が「小唄映画」の文法を踏襲していたこと。戦後直後、戦災を生き延びた地方映画館に、美空ひばりなどが続々歌謡曲を歌いにきたこと。巨大スクリーン「アイマックス・シアター」が大阪万博に展示されたものを原型にしていたり、などの指摘もなされていて、たいへん面白い。 「ブロック・バスター」映画の隆盛とともに、世界中に「テーマパーク」が建設されてゆく。近年では、薄汚れたダウンタウンにしかすぎなかったハリウッドの町並まで、ハリウッド・ホテル移築、あのグリフィス映画「イントレランス」のセットの復元、テーマパークと化しているのだという。▼ とはいえ、冒頭で書いたとおり、私にはあまり面白いとは思えなかった。▼ 『今日のポルノ映画館は入場者を観客というよりも恋人として生産している』『「リアリズム」とは、新たなリアリズムにとってかわられるまでのあいだ、みずからを「リアリスト」と僭称することのできるひとつの技術的関数にすぎない』など、有益な箴言の数々にもかかわらず。▼ たとえば、北田暁大の気の利いた所論『弁士が俳優よりも先んじてスターシステムに組み込まれていた』(213頁-216頁)に対する、加藤幹郎の批判は、部外者からみて、さっぱり「分からない」。そもそも「弁士スターシステムは成立していない」ことの証明は、弁士中心主義に対する批判が見られたこと以外、加藤幹郎は提示していないのだ。目を皿にして確認しても、見あたらない。「俳優のスターシステム」に対する批判が言われていたら、「俳優のスターシステムは成立していない」とでも言う気なのか? どうみても、スターシステムの定義が、噛みあっていないのではないのか。というより、批判する側より「された側」の方の議論の方が、はるかに面白いように感じさせてしまう時点で、批判の体をなしていない。なにか、私怨でもあったのだろうか。▼ さらにいえば、アメリカ・日本を描いていながら、観客動員数・公開本数がダントツ世界一、超大国インドを取りあげていない時点で、この本がはたして「映画館と観客の文化史」を語る資格があるのか、はなはだ疑問に感じてしまう。言いすぎだろうか?。そもそも、「ドライブ・イン・シアター」など、アメリカ(せいぜいカナダ、オーストラリア)以外のどこで可能なのか。ただのアメリカ文化史ではないか。そもそも「踊る観客」でしられるインドでは、「映画館は静謐の空間」とする、通俗的概念が成立しているのか。インドこそ、「映画の観客の不動性」「静謐性」なる理念そのものが、「歴史的」どころか「空間的」産物でさえある、格好の例証ではないか。インドを除外することによって、成立するような「映画史」など、議論として成立しているとは、とうてい思えない。▼ なによりも、上記と関係するが、「映画館と観客の文化史」といいながら、他の同様のエンターテイメントと比べて、「映画館と観客」がどのような特質をもつのか、さっぱり分からない。本書では、映画館成立以前に上映されていた、「劇場」「芝居小屋」「博覧会会場」などから、「映画館」が析出して、やがてテレビやビデオの文化が生み出されたことが述べられる。まさしく、現代の娯楽スペクタクルが、網羅されている。「映画館」ならびに「観客」は、宝塚や、新劇、クラシック音楽会、レンタルビデオ屋のそれとは、どのように違うのか。「場」に着目するといいながら、そこに流れ込んだ川上(パノラマ館、劇場、芝居小屋)と、そこから流れ出した川下(テレビ、DVD他)の存在を指摘するだけで、その「場」と「観客」の特異性がまるで分からない。それは、近代西欧における娯楽の変容についての考察や、宝塚の事例研究と比べても、劣っているといわざるをえない。羊頭狗肉、といったら、言いすぎだろうか。 ▼ とはいえ、映画を通したアメリカ文化史を見るならば、汗牛充棟の出来映えであろう。星3つ程つけさせていただいた。ご一読あれ。評価 ★★★価格: ¥ 903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 13, 2006
コメント(3)
-
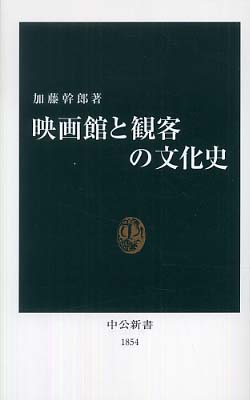
★ 加藤 幹郎 『映画館と観客の文化史』 中公新書(新刊) <1>
▼ 本来面白い「はず」なのにも関わらず、なぜ、こんなにつまらないのだろう…▼ 世の中、こんな首をひねるような現象が訪れることは、少なくない。さしずめ、今回とりあげる本書は、私にとって、そんな代表的な本であるといえるかもしれない。もちろん、折角の力作について、「つまらない」という、ある種不合理な批判を受ける当人にとっては、たまったもんではあるまいが。▼ 内容を簡潔にまとめておこう。▼ 映画史は、「作品と作家」の歴史として描かれてきた。写真と映画は違い、むしろ演劇との親和性が高い。映画が立ち現れる場所、映画館を訪ねる以外、映画には「起源」がない。どのような環境で上演され、観客はどのような態度で観覧したのか。媒体と場所が違えば、体験はまったく異なるのだから………このような視点から、アメリカと日本、2つのフィールドを軸に、映画館と観客の歴史を追体験していこうと試みる。▼ 映画の前史には、360度ぐるっと絵が描かれた、パノラマ館という視覚装置があるらしい。 「映画の観客の不動性」は、映画史初期から古典期への移行過程でえられた、歴史的産物にすぎない。1895年、映画上映は、仏のリュミエール兄弟に始まるものの、1905年頃までは、劇場などで他の出し物と一緒に上映される存在にすぎなかったという。アメリカでは、「ヴォードヴィル劇場」という、ダンス・コントなどのライブ・パフォーマンスをおこなう劇場でおこなわれ、音楽の伴奏とともに映画の上演がおこなわれた。19世紀前半までの男性中心主義的な公共圏とは違い、ヴォードヴィル劇場は、20世紀「映画館」と同様の、女性・年齢・階級に関わりない空間であったという。ライブ・パフォーマンス性が映画館から駆逐されるのは、「張り出し舞台のない映画館」で究極の静寂と機械音の支配する、1980年代のシネ・コン出現まで待つ必要があるとのこと。▼ 「ニッケル・オディオン」と呼ばれる常設映画館がアメリカに出現したのは、1905年。こうした貸店舗などの小規模映画館は、「スライド」や「サイレント映画」が、ピアノ伴奏による歌手・観客の大合唱で埋められながら上演される祝祭空間であった。1905年~13年「ニッケル・オディオン」は、新移民を中心とする観客たちによって爆発的に流行、それに併せて、制作=配給=興行の分業、安価な商品(映画)を配給元から取りよせるスタイルが普及する。ニッケル・オディオンは、異郷の地で映画を通して、そこで生きるに相応しいアイデンティティの獲得を行わせる公共圏的機能を果たしていた。ハリウッドは、1880年代のロシアのポグロムによる、200万人ものユダヤ人のアメリカ移住が遠因として―――ユニーヴァーサル、フォックス、パラマウント、MGM、ワーナー・ブラザーズなどの創始者は皆、ロシア・東欧・中欧からの移民ユダヤ人―――ユダヤ人娯楽産業として出発する。館内合唱は映画の長大化がすすむ古典期になると衰退して「静粛化」が進むが、それは大衆音楽の需要構造の「楽譜からレコード」への変容と軌を一にしているという。 ▼ 1913年頃、短編映画から長編映画への転換にあわせるかのように出現したのが、ピクチュアル・パレス(映画宮殿)と呼ばれる大規模映画館。豪華絢爛、オーケストラピッドをそなえた宮殿のような映画館は、テーマパークと同様、非日常の空間に他ならない。もはや「ニッケル・オディオン」期のような、外国語が話されたり、黒人・低所得層によって分化しているような、多様な空間ではない。とはいえ観客は、人種的、階級的、イデオロギー的に均質化されてしまうものの、「序曲」「行進曲(ニュース映画)」「本編」などにはオーケストラが伴奏でつくなど、音楽会と見まごうような多様な音楽が奏でられたという。ところが、トーキーの登場と世界恐慌に、このピクチュアル・パレスは対応できなかった。1930年代以降、中規模サイズのトーキー映画館経営に転換していく中で、音楽会的興行プログラムは変容するものの、生演奏自体は続いた。いったんは静粛になった映画館は、途中入退館と観客が自分で座席を探す(以前はボーイが案内)ため、再びうるさくなったという。▼ なによりも、1933年ニュージャーシー州に誕生した、「ドライブ・イン・シアター」なるものには、日本人ならば、驚く他はない。広大な駐車場で、車を降りることなく、巨大スクリーンと駐車場脇にある音源によって、映画と楽しんでいたんだとか。排ガスで曇るし見えにくいという欠点があるものの、赤ん坊が泣いても、周囲に迷惑をかけない、プライバシー空間であった。 「ドライブ・イン・シアター」は、喫煙、うたた寝、ダンス、飲酒、SEXなどがおこなわれた空間であり、「テレビと居間」や、今でいえばDVDプレイヤー・モニターを車に乗せる行為の先取りをしていたという。1957年頃、この「ドライブ・イン・シアター」は最盛期をむかえ、普通の映画館よりも観客動員は多かったらしい。ただし、それは、映画のテレビ化プロセスと重なっており、テレビ保有率が8割に達したときだったという。夜、映画をみる以外には、昼には、教会の屋外説教にも使われた。「ドライブ・イン・シアター」が衰退して、その跡地に建てられたのが、ショッピング・モールであり、シネマ・コンプレックスなのだとか。▼ 1980年代以降、ショッピング・モール内に展開するシネマ・コンプレックスの登場とは、テレビの多チャンネル化に完全に敗北した証拠であるが、その「社交的交際」の性格ゆえに、今もなおテレビと競争することが可能になっている、のだという。一本の映画の製作と宣伝に可能な限り予算を投入して、可能な限り高収益をねらう、1970年代登場したスタイル、「ブロック・バスター映画」。「ブロックバスター映画」は、「収容能力の異なる複数の劇場をもつ映画館」にとっては、ヒットの大小にあわせて収容能力の違う劇場を自在に変更できることから、たいへん都合がいい。そのため、シネコンによる全国同時放映のスタイルが生まれてしまい、「2番館」「3番館」制度はビデオ・レンタルやDVD販売によって無意味化、「映画等級付け」制度の崩壊を招いてしまったらしい。「ブロック・バスター映画」の興隆は、万人受けする内容でなければならないので、ハイコスト・ハイテク・ハイスピードの世俗的均質の坩堝のような映画の横行、ならびにアート・シアターの廃館と外国映画上映の機会を剥奪をもたらしてしまう。その結果、「外国映画の再映画権の売買」なる、価値の高い外国映画がしばしばハリウッド映画として再映画化されて世界のシネコンに輸出するビジネスが生まれたというのだから、驚く他はない。 (続きはこちら応援お願いします 長すぎて1日では終わらなかった…) 評価 ★★★価格: ¥ 903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 10, 2006
コメント(0)
-

★ 男系天皇・女系天皇について雑感
▼ 何でも、昨日、皇室に41年ぶりに男子が生まれたらしい。おめでたいことである。▼ むろん、過去の日記で、「ご隠居」の言葉に仮託して、共和主義者的本音を語らせている以上、「おめでたい」に底意があることを隠せる訳もない。これで、いよいよ、天皇制は迷走することになり、天皇制に愛着を感じる女性は、天皇制固有の差別的本質に直面することになるのではないか。むろん、直面したからといって、動揺を期待するほど、「おめでたい」訳ではないのだが。▼ それはともかく、男系天皇と女系天皇について、前回の日記で語れなかったことがある。それは、「氏(姓)」と「苗字」の問題である。▼ 「氏(姓)」というのは、少なくとも、古代以降、ヤマト王権によって与えられた、父系血縁集団の名前である。分りやすくいえば、「藤原」「源」「橘」といった所。天皇には「姓」がないのは、「氏(姓)」が「臣下」に与えられるものだからに他ならない。天皇家の子女が、臣籍降下の際、「姓」がつくのも、そのためなんですな(正確にいえば、氏と姓は違う)。▼ 一方、「苗字」はちがう。これは、わかりやすくいえば、「経営集団」単位の名前。この出現は平安時代にさかのぼる。皆さんも、いつのまにか、藤原四「家」とか、「藤原」一族の名前が消えて「九条」「一条」「二条」「鷹司」「近衛」などの名前が出てきたなあ、と感じたことがあるかもしれない。これは皆、家産を保持する経営体の名前だと思って、間違いはない。鎌倉時代以降には、「苗字」は一般的になってくる。商人の「屋号」だのも、この手の類に他ならない。▼ だから前近代、人は姓と苗字を持っていた。たとえば徳川家康は、徳川次郎三郎源朝臣家康と書くらしい。ここで確認しておかなければならない苗字と姓の違いは、「苗字」は結婚してかわることはあっても、「姓」は結婚しても変わることがないことにある。この区別は、明治時代になって消滅してしまう。われわれは「姓名」と書くし、「夫婦別姓反対!」という文字を目にしても、おかしいと思うことはない。そもそも結婚しても、本来の「姓」ならば、もともと反対してもしなくても、「別姓」であるという事態は、かわるはずもないのだが……。▼ しばしば、皇室典範改正反対派の議論のひとつとして、以下のような議論があった。それは、愛子天皇が「女性天皇」ではなく「女系天皇」になる、有史(継体朝)以来維持されてきた「男系天皇」が断絶されてしまう、というものである。愛子天皇の出現によって、ご息女に天皇位を継がせる場合、父方の「姓」が入りこんでしまう。そのため、愛子天皇を認めなければならないと考える「男系天皇」制維持派の中には、皇室の血を引く人々を愛子天皇の旦那さんにあてがおうとするものさえいた。▼ しかし、よく考えれば、これって変な話である。だって愛子天皇は、天皇なのである。「苗字化された氏(姓)」を前提とするから、こんな問題が引きおこされてしまう。そんな発想自体、伝統とはかけ離れたものだ。そもそも「氏(姓)をもたない」愛子天皇が、自分の子息に「氏(姓)」を与えなければいいだけの話だろう。自動的に父系親族集団である「姓」がつくはずだ? ならば宇多天皇が、臣籍降下によって、「賜姓」されていたにも関わらず、剥奪されて天皇即位できた事例を思い出せばよい。「姓」を剥奪してしまえばいいのである………そして天皇とは、そのような、「姓」を剥奪しうる超法規的力と伝統をあわせ持つ存在なのだ………▼ と考えてみたものの、別段「伝統派」と名のる人々が、このような議論をしている所を見たことがない(あるならば教えて!)ことを考えると、「男親をたどれば神武(極端な例ではない場合、継体)に行き着く」という理論抜きのロマンが、「男系天皇マンセー!」の虚構を支えてるのだろう。男系でいいならば、原則上、確認できる該当者は無数にいるし、とりたてて誰がなってもいいはず。「姓」「父母」など、様々な「男系以外」の要素が支えているはずなのだが…… 所詮は小生の意見など、部外者の臆見。今回の出産を機会として、皇室典範改正は遠のいたし、後の経過が楽しみでならない。▼ 一番つまらないのは、今の愛子女史と生誕した男子が、イトコ同士で結婚してしまい、「皇位継承」問題が、雲散霧消してしまうことである。飛鳥時代から奈良時代にかけて、近親婚が続いたしなあ。また、雅子女史が男子を産むのも、面白いとはいえない。▼ まだまだ迷走しそうで、観客としては、楽しい日々が続きそうだ。 (本の紹介は、のちほど)追伸 昨日のアクセスが1500近いのですが、 どこか奇特なブログが紹介してくれているのでしょうか…… ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 7, 2006
コメント(4)
-
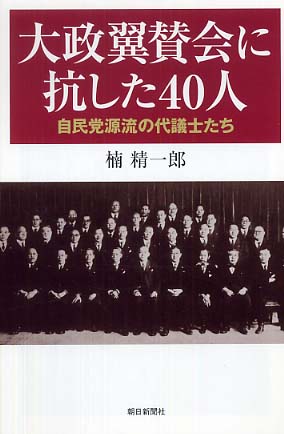
★ 楠精一郎 『大政翼賛会に抗した40人-自民党源流の代議士たち 』 朝日選書 (新刊)
▼ かつて、週刊『自由民主』誌上に、「気骨ある政治家たち-翼賛体制に立ち向かった37人」と題されて連載されていたものが、増補の上、一冊の本にまとめられ、朝日選書から出版されました。戦時の一時期、同交会(1941年11月~1942年5月)に結集した、議会政治家たちの戦い。それが、伝記という趣で収録されていて、なかなか楽しめるものになっています。▼ その内容は、25回連続当選を果たした「憲政の神様」尾崎行雄を初めとして、田川大吉郎、植原悦二郎、鈴木文治、岡崎憲、大野伴睦、星島二郎、世耕弘一(あの自民党世耕弘成の祖父)、坂東幸太郎、岡崎久次郎、本田弥一郎、福田関次郎、北 日令(れい)吉(戦後鳩山内閣の幻の司法大臣)、宮脇長吉、原口初太郎、名川侃市、一松定吉、芦田均、安藤正純、片山哲、若宮貞夫、鳩山一郎(首相:鳩山由紀夫元代表の祖父)、石坂豊一、川崎克(川崎二郎厚生労働相の祖父)、百瀬渡、丸山弁三郎、大石倫治(大石武一環境庁長官の父)、「ネズミの殿様」斉藤隆夫、芦田均、林譲治、服部岩吉、森幸太郎、板谷順助、松尾孝之、牧山耕蔵、田中亮一、木檜三四郎、工藤鉄男。総揃37名全員の伝記。 これに、大政翼賛会から、「戦後民主化」「保守合同」と歴史トピックの解説をはさみながら、「同交会」結成には加わらなかったキーパーソン、河野一郎(河野洋平衆議院議長の父)、三木武吉、松木弘たちの伝を交え、重層的に戦中・戦後の政界を描き出そうとするもの。▼ とかく多彩な人士である。松尾芭蕉の俳聖堂建設をおこなった川崎克は、文学から書画茶陶芸にまでおよぶ、文人政治家としてしられ、その人物伝を江戸川乱歩が執筆していたらしい。斉藤隆夫「除名決議」のとき、官僚出身で同じ選挙区(定数3)から選ばれていた政治家、若宮貞夫は、斉藤隆夫のような立派な政治家を議会に戻すために、自ら議員辞任をおこない、さっそく「補欠選挙」に持ちこもうとしたいう。初当選直後でありながら、軍部への内田外相の弱腰対応を批判した、政友会代議士芦田均(京都3)は、戦後、河野一郎への反発から、鳩山自由党ではなく、進歩党を結成したのだとか。牧山耕蔵は、米内光政の人格・識見に感服して、東郷平八郎元帥に直談判、予備役編入(1928年)を未然に阻止したという。検事や裁判官出身者(一松、名川)、実業家(岡崎、本田、福田)。森・服部が戦後滋賀戦争をおこなうかとおもえば、東京1区と同選挙区でありながら、終生、兄弟のような仲であった、安藤正純と鳩山一郎。同交会に集った社会主義者たちは、戦後は社会党から出馬する田川大吉郎を含め、敬虔なキリスト教徒たちであったことは、社会党・無産運動の右派に、キリスト教徒が集まっていたことを考えると、なかなか面白い。▼ また、いずれも、きわめてリベラルな政治思想の持ち主であったのが嬉しい。坂東幸太郎は、「婦人参政権論者」。また、目白の広大な屋敷地を次々と売りはらった「井戸塀政治家」でしられる星島二郎も、「普通選挙」「婦人参政権」「公娼廃止」をとなえただけではなく、普選決定時に激しく治安維持法反対をとなえた代議士だったという。戦後岸内閣(最高裁長官の田中耕太郎も含め、『3権の長』全員が、旧制岡山中学出身者)の下、「警職法」強行採決の責任をとって、衆議院議長を辞任させられたのは、何の因果か。 植原悦治郎にいたっては、その急進的デモクラットぶりは、日本国憲法の源流。国民主権をとなえ「民本主義」吉野作造と対決。軍部大臣現役武官制廃止、枢密院改制、陪審制導入、知事・町村長民選………そのいずれも戦後になって実現したことには驚く他はない。戦後は、内務大臣に就任して憲法改正案に副署したものの、日本国憲法には不満を抱いていた。その理由は、現代の改憲派主流の迷妄である「押し付け憲法」論について、「陛下の詔書と、貴衆両院の絶対多数で可決された以上、民意である」とばっさり切り捨てた挙げ句、以下のようにのべる。軍備をもたないと国連加盟後の義務も果たせない衆参が同じ直接選挙では重複してしまう地方自治はいいが、財源がない実際は改憲不可能になってしまう首肯すべき点の多い、リベラルの鏡ともいえる議論ではないだろうか。▼ 総じて感じさせるのは、国民的世論にも支えられた、「軍部・ファシズム・独裁」といった特色をもつ政治勢力に立ち向かうには、政治家個人の思想信条も大事ながら、選挙区民の政治家に対する圧倒的信頼が欠かせないことかもしれない。戦前、現役軍人に選挙権はなかった、のだから、ある意味当然だろう。とかく、斉藤隆夫といい、尾崎行雄といい、「木堂宗」「世耕宗」「愕堂宗」と呼ばれた、利益誘導に目もくれない、政治家に惚れた選挙区民たちが、「翼賛選挙」―――最悪の官憲による選挙介入、たとえば「尾崎行雄不敬事件」で知られる―――でさえ弾き返して、かれらを国会へと送り出した。この政治家への厚い支持が、また、政治家の所信を貫徹させる。芭蕉の「俳聖堂」の完成は、なんと戦時下42年9月のことなのだ。▼ 翼賛選挙では、「政友会鳩山派」を中心とした大政翼賛会に参加しなかった「同交会」の連中は、次々と落選してしまう。斉藤隆夫「いたずらに聖戦の美名に隠れ」で知られる『反軍演説』のための除名決議は、大政翼賛会体制を生むが、このとき144名の棄権者、7名の反対者の内、4名が同交会に属していた。その4名とは、芦田均、名川侃市、丸山弁三郎に、鉄道マニアならおなじみの名前、宮脇長吉(陸士卒将校、三土忠造の実兄)だったという。その宮脇長吉を翼賛選挙で落選させてしまうのが、何あろう、東京選挙区から移ってきた三木武吉だという。なにか因縁を感じさせます。それでも、戦後衆議院選挙で次々と復活して、戦後保守政治に参画する。 ▼ むしろ本書の白眉は、片山内閣評価にあるのかもしれない。「左派の造反」で潰された経緯。加えて、左派主導だった社会党の『党史』においては、「大衆が離反」と低評価しか与えられていない片山内閣に、筆者が高評価を与えているのは、たいへん面白い。旧内務省改革、警察民主化、労働省の設置、公務員を「全体への奉仕者」とした国家公務員法制定、改正民法………ため息が出るほどの民主化推進内閣である。吉田内閣がGHQに対してサボタージュを繰り返したのに対して、積極的担い手であったことが強調され、かなり刺激を受ける。片山本人も「やることはやった」と言っていたという。われわれは、ついつい東条英機や吉田茂に目を奪われてしまいがちなだけに、かつての大戦を考える上でも、時宜を得た、大きな価値がある書物といえるでしょう。▼ ただ、全体として眺めると、「トリビアの泉」的な部分を除けば、生ぬるくて、辟易させられるのも事実。そもそも、総動員体制下における1エポックにすぎない「同交会」だけが採りあげられるのは何故なのか。まったく不明になってしまっている。そもそも、「同交会」だけが、大政翼賛会体制に抵抗していたわけではない。興亜議員連盟や、1942年翼賛選挙における「非推薦」で当選してきた85名が触れられていないのは、あまりにも片手落ちで、抵抗の全体的イメージがうまく結びついてくれない。また、無産運動によって選ばれた政治家、たとえば、西尾末広・賀川豊彦・安部磯雄・松本治一郎・水谷長三郎といった「無産運動右派=社民(社会民衆党)系」を中心とする代議士たちは、どこにも伝がのせられていない。わずかに、「同交会」に加入していたというだけで、片山哲と鈴木文治(友愛会:東6)、岡崎憲が触れられるにすぎない。これでは、とても、包括的・体系的・分析的なものとはいえない。▼ なによりも許せないのは、「同交会」は「自民党の源流」とは言いがたいことが隠蔽されていて、単なるプロパガンダに堕してしまっている点にある。この2つについて、無理やり「継続性」なる意味をあたえて、結び付けようとしたため、どちらもかなり中途半端なものになってしまっているのだ。 ▼ なるほど、「同交会」の末裔たちは、自由党を結成して、自民党に流れ着いたかもしれない。しかし、そこで彼らはなんと呼ばれていたか。「党人派」ではなかったか。保守本流3派は佐藤・池田・岸であって、決して「同交会」の連中ではない。自民党の中心は、大政翼賛会=国家総動員体制において、官僚主導の統制経済を運営した人間「官僚派」によって担われたのであって、「同交会」の流れをくむ党人派の代議士たちの出番は、脇役以外少なかった。それは、社会党についても、いうことができる。戦後出発した社会党は、無産運動三派合同によって、労働運動の統一の輿望をにない誕生するものの、片山・西尾・安部といった大政翼賛会に抗した連中は、西尾統制問題を契機として、日労・日無といった中間派・左派によって、党外に追放される(民社党結成)。いうなれば「同交会」が、自民党の源流にも、社会党の源流にもなれなかったからこそ、今の政治はかくも貧困なのではないのか?と、皮肉の一つでも、筆者にいってやりたくなってしまう。「同交会」と「自民党の源流」、どちらも描ききれていない上に、その関係については、こんな体たらくでは、生ぬるいとしか言いようがない。▼ こんな自民党へのオベッカ、阿諛追従のような本を書くくらいなら、大政翼賛会に協力・旗振り役をつとめた、前田米蔵や大麻唯男、日労系の三輪寿荘・麻生久、それに赤松克麿たちの内面を、きっちり「同情」をこめて描いてくれた方が、どれほど面白かっただろうか。鳩山にしても「お坊ちゃまの『気骨』」をたたえる前に、文相時代のことも書く必要があるだろうに。書き直しをしてほしいくらいである。▼ という訳で、かなり評価は厳しくなってしまった。もし、図書館で手にとることがあれば、上記の点に留意しつつご閲覧アレ、といった所かも知れない。評価 ★★★価格: ¥1.260 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Sep 1, 2006
コメント(2)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










