2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年06月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

★ 柄谷行人 『世界共和国へ ―資本=ネーション=国家を超えて』 岩波新書(新刊)
▼ 資本・ネーション・国家の異なる3つの原理が、それぞれ接合して形成されている資本主義。ソ連崩壊以後、資本主義に対抗するために、どのような世界を構想すればいいのか。その難問に答えようとする本が、岩波新書から出ています。著者は、柄谷行人…NAMをほったらかして何をしているんだか…。▼ 本書を貫く視角は、国家やネーションを交換様式でみるとどうなるか、である。これはなかなか刺激的であった。 ▼ 柄谷は、「統制-自由」「平等-不平等」の軸で、19世紀~20世紀の政治・経済史の理念軸を整理する。統制・平等を指向するA「互酬-ネーション-国家社会主義」。統制・不平等容認のB「再分配-国家-福祉国家資本主義」。自由・不平等容認のC「商品交換-資本-リベラリズム・新自由主義」。一方、自由にして平等なる、D「X-アソシエーション(真の社会主義)-リバタリアン社会主義」は、理念として折にふれ構想されてきたものの、かつてこの世に出現したことは無い。▼ 生産とは、人間と自然との物質的交換様式に他ならない。生産様式だと、廃棄物・自然破壊を見ることができない。柄谷は、マルクスが以前提唱しながら発展させなかった交換様式(交通形態)から入ろうとします。氏族的社会は互酬。アジア的、古典古代的、封建的な各社会は、再分配。資本主義社会は商品交換が支配的交換様式であるという。アジア的社会(構成体)では、互酬的共同体を下部にかかえつつ、再分配が支配的な社会であって、すでに常備軍・官僚制など、国家機構を完成させていたらしい。古典古代・封建社会は、アジア的帝国の周辺に成立した社会にすぎない。資本主義社会では、互酬が「想像の共同体」ネーションとして回復される。国家は、福祉国家の相貌をとり、資本=ネーション=国家という結合環になる。この社会では、商品交換によって開かれた自由の上に、互酬的交換を回復しようとするDのラインの社会運動、アソシエーションが生まれてくるという。▼ 交換が共同体と共同体の間に発生するように、国家は「共同体と共同体の間」に発生する。交換の際の略奪を防ぐ。それが国家と法の機能なのだという。そのため国家は、商品交換に先行するし、国家は、決して共同体や社会に還元できない。互酬原理は、国家=再分配の原理が登場してもなかなか消えない。古典古代、ギリシアの民主主義は、ヘロドトスのいう「東洋に対する西洋の優越」ではない。互酬的共同体の名残であって、集権化できなかっただけにすぎない。周辺であるローマ帝国のそのまた周辺で生まれた封建社会。それは、被支配階級レベルはいうに及ばず、支配階級レベルでも互酬原理の支配する社会であったが、その「自由都市」は後のブルジョア社会を育んだという。「C 貨幣(資本)」は、商品世界の共同作業であって、AやBとは違い、人間に対等な関係をもたらしてくれる。しかし、商品と貨幣は非対称であって、これを補うのが信用であるという。Dラインは、普遍宗教として立ち現れる。呪術から宗教へ移行するには、互酬的関係が断ち切られる必要があるらしい。普遍宗教とは、貨幣による交換が支配的な社会、都市に基盤をおいた共同体・国家への反逆であり、商業的資本主義にも抗して互酬的共同体を回復する試みであるという。▼ 第三部「世界経済」も面白い。国家、産業資本主義、ネーション、アソシエーションの順番で、考察がすすめられてゆく。福祉国家が生まれたのは、近代ではない。また産業資本は、商品流通における特殊商品、使うことが生産過程である労働力商品を見いだすことによって成立するという。その剰余価値は、労働者の買い戻し、すなわち「流通過程」にしか存在しない。この様な、資本主義の自己再生的システムも、本来商品にならない労働力と土地を商品にしたことで、その限界にぶち当たる。労働力は、需要の多寡で廃棄や増産ができないからである。資本に対抗するためには、労働者が資本家に対して不利を強いられる生産過程(現場)ではなく、消費者として現れる地点で戦わなければならない。ネーションは、宗教に替わって人々に不死性・永遠性(B・アンダーソン)を与える。国家と資本主義経済という異なる交換原理は、ネーションという想像力によって、結びつけられる、あたかも感性と悟性が想像力で結びつけられるように…。▼ 普遍宗教は、ネーションの成立とともに、その本来的性格を取り戻すというのは、なかなか意表をついていて楽しい。教会=国家的システムに回収される普遍宗教を批判しない限りアソシエーショニズムは実現できないが、アソシエーションは普遍宗教が開示する自由な互酬性(相互性)の上に立脚しなければならない。資本主義、すなわち貨幣と商品の非対称性があるかぎり、アソシエーションの実現は不可能である。19世紀社会主義が、平等と友愛を取り戻そうとして国家にたどり着く中で、プルードンだけは自由に立脚して友愛を切り捨てようとした。友愛は、個人の犠牲(自由の犠牲)を引き出す。そのため国家的強制は、友愛によって強化されやすい。プルードンもマルクスも―――バクーニンの批判とは異なりプルードン派であったという―――国家が共同体と共同体の間にあることを忘れ、その廃棄が一国レベルの問題ではないことをみていない。革命は、一国でも世界同時でもできない。「下から」とともに「上から」国家を押さえ込まなければならない。▼ それこそが、カントの提唱する『世界共和国』の理念であるという。国民国家枠組無効論、新「帝国」概念の出現―――それはネグリ&ハートでも同じことだが―――いずれも、国家が資本とは別の交換様式として存在していることをみていない。カントは、永遠平和のための国家連合が、理性や道徳ではなく、反社会的社会性、すなわち戦争によって達成されると考えていたという。国家を内部から否定するだけでは揚棄できない。われわれに可能なのは、軍事的主権を徐々に国際連合に譲渡させて、「上」からの押さえ込みをはかる、この道筋しかない。そう語られて本書は閉じられる。▼ 何よりも、国家とは内部からできるものではなく、他の国家、外部との関係においてのみ存在するものなのだ、という考え方には、元ネタはレヴィナス~デリダから採ったのですか?などと思ったものの、なかなか感動させられた。またマルクスは、Aラインの人物と考えられているが、実はDのラインというのもお約束。国家の自立性を見ようとしないことが、後のマルクス主義が国家社会主義に転化する原因になったらしい。絶対王政とは交換様式BとCの結合によってもたらされたものである、呪術師から祭祀階級への移行は交換様式AからBへの移行である、などという明快な整理には、唸らされるものがあります。「暴力の独占」「貢納制ではなく商品交換に立脚」「国家とは、安寧と服従の交換である」「臣下として均一化されない所に、市民は出現しない」…国家の本質は絶対主義王政段階にあらわれる。国家を手段視するものは国家に手段とされる、など箴言の類も、相変わらず面白い。複雑な親族構造を部族間における女性の互酬的交換からみるレヴィ=ストロースなど、文化人類学まで幅広く狩猟されていて、たいへん楽しめた。▼ ただ読了後、いささか落胆したのも、まぎれもない事実である。そもそも、国際連合による「上」からの国家掣肘を!!、という、ごく普通の結論に至るまで、ここまで紙幅を費やす必要があったのか。 ファンでないものは、はなはだ疑問に感じてしまうだろう。 そんな、意味不明なロードマップを読むくらいなら、より過激に「ヤマト保険」などとふかしていた、かわぐちかいじ『沈黙の艦隊』(講談社)を読んだ方が、はるかに有意義ではないか?。 むろん、これにはカントの「統整的理念」と「構成的理念」の区別立てを持ち出していることからわかるように、アソシエーショニズムは前者であって後者ではありません、という言い訳がきちんと用意されている。とはいえ、決して達成されるものではない故に、たえず現状を批判するものとしてあり続けるもの。その距離の取り方は、柄谷が激しく批判してきた「シニシズム」「アイロニズム」の構造そのものではないのか。どのように考えているのか、いまいちよく分からない。▼ また日本は、アジア的ではなく封建的であるとか、周辺ではなく亜周辺であったから中国など文明の影響を選択的にとりこむことができたとか、他者にもたれかかった安易な議論が多すぎる。これでは、「新しい教科書を作る会」や『国民の歴史』とほとんど変わらない。また、「自由・平等・友愛」は、3つの交換様式(それぞれ商品交換、再分配、互酬)を表したものだという下りも、読んでいる分には面白いが、いざ考えてみると、後ろ2者の順番は逆でもあてはまるのではないか?(平等=互酬、友愛=再分配)という疑念も、チラホラと湧きあがってきて、なかなか脳裏からぬぐえない。▼ ただ、一読をお勧めしたい本ではあります。評価は70点といった所でしょうか。評価 ★★★☆価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです (おまけ)柄谷行人『可能なるコミュニズム』太田出版 1999年 ¥1,680 かわぐちかいじ『沈黙の艦隊』講談社 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 29, 2006
コメント(0)
-

★ 論座編集部 『リベラルからの反撃』 朝日選書(新刊) <1>
▼ 自称「保守」の堕落など、今さら声高に言うほどのことでもあるまい。「弱き」「動物」の群れ。「愛国」をなのる、ゲスの集団。ここ15年、防衛的ナショナリズムの下、ひたすら、ジコチュー的に「右傾化」する日本。ところが、左翼陣営側からの反撃は、一向に見られない。これは一体、どうしたことなのだ…といった声が騒々しい。そんな中で、待望久しい、「反撃」を名のる書が、この世にあらわれた。かつてのメインストリーム、マルクス主義陣営ではなく、かつてマルクス主義者が保守以上に攻撃した「リベラル陣営」からの反撃表明であるのが、いささか残念ではあるが…。さて、その試みは成功しているのか。本書の概要は以下の通り。第一章 保守リベラルから政治家は「勇ましい姿」より「ちょっと待てよ」の気概を真の保守主義再生しかない自民党の≪変貌≫ と保守・右翼層の≪分裂≫ 第二章 憲法改正 「“護憲的改憲”を目指せ」「今の日本には護憲が得策」日本の立憲主義よ、どこへ行く?九条削除論 ――憲法論議の欺瞞を打つ第三章 靖国と外交戦後60年の日本・アジア・世界靖国参拝が壊したアジアとの和解眠れる外交「靖国」の土俵から降りなければ展望は開けない第一章は、3つ。「久間章生×太田昭宏×仙谷由人」の対談では、自民党がタカ派的なポピュリズムに流されている様子が、生々しく明らかにされていて面白い。メディア選挙では、ポピュリズムに走らなくてはならない。若手政治家とのギャップを感じるものの、右傾化とまでは思わず、「慎重な選択」「ハト派の存在」を強調する久間。この対談で、意外に感じられたのが、リベラルの観点から見た仙谷由人の見識の高さか。国連憲章と自衛隊、改憲と国連改革のリンク。一国主義的な護憲批判。官からNPO・宗教団体・自治体に「公」を取り戻そう…単純な左ではない所に、新しさを感じる。佐伯啓志「真の保守主義再生しかない」は、イラク戦争に賛成することで、ネーションの独自性よりも自由・民主主義を上位におき、アメリカ的なものからの独立を蔑ろにした保守主義の欺瞞が糾弾される。現実的観点からは、保守に飲み込まれてしまった左翼。理念を見失うことで現実主義になだれ込み、「広義のサヨク」と化した保守。これは、イラク戦争に始まったことではなく、社会主義の崩壊によって左翼が保守に投降するとともに、リベラリズムの勝利を宣言することで、保守が左翼進歩主義に回帰した、必然的帰結であるという。もはやリベラルも保守も、アメリカ的価値観の一部でしかない。今必要なのは、真の保守主義の再生である。「善き社会」をどのように構築するべきか。コミュニタリアンの立場から提唱される。櫻田淳「自民党の≪変貌≫と保守・右翼層の≪分裂≫」では、戦後自民党を支えた支持層、「明治体制≪正統≫」「1940年体制寄生」「民族主義者」、3層の幸福な結合構造が、2005年総選挙によって解体されたことが示唆される。「1940年体制寄生」「民族主義者」による「明治体制≪正統≫」に対する不満こそ、自民党内の小泉批判であるという。この前2者の後者に対する巻き返しは、現実には期待できない。と同時に左翼層も、保守・右翼層を十把一絡げにしないことが求められるという。民主党は、狭隘な「政治活動家」の党から脱皮して、利害調整を任とする「政治家」の党になれるのか。また自民党は、安倍晋三に保守・右翼知識人が「政治活動家」を期待するあまり、旧来の社会党のような「政治活動家」の党に堕してしまうのか。第二章も3つで構成されている。大沼保昭×船曳建夫『「“護憲的改憲”を目指せ」「今の日本には護憲が得策」』の対談が、かなり面白い。「憲法9条」「平和憲法」は、従来、戦争責任に向かい合いたくない日本が、悪いことをしないことを世界に発信するための、「代替」的機能を果たしてきたが、本来、9条が果たすべき役割ではない。アメリカの世界戦略の中で、「押しつけ憲法を改正」することは、別種の「押しつけ憲法」をつくることに他ならない。日本の平和を守ったのは、9条と安保である。「憲法はシニシズムを生んでいるか」「9条は世界の流れを先取りしているのか」をめぐって、軍隊を持つことを認めている者同士が、細かい部分で激しい討論をおこなっていて楽しめる。長谷部恭夫「日本の立憲主義よ、どこへ行く?」のエッセイは、読みやすくて秀逸。近代、価値観が多様化する社会。そこでは、個人の価値観を追求する私的領域と、社会のすべてのメンバーの利益について話し合い決定を下す公的領域の2つに、生活領域を裁断するため、立憲主義がもとめられている。価値観や道徳、心構えなどを入れようとする改憲。「義務」という法律ですむ話を、わざわざ憲法にのせようとする改憲。改憲するために何でもとりこんじゃえ改憲…これらの志や立憲主義を忘れた改憲論を批判し、「あまり面白みのない」地道な利害調整の政治に戻るよう求めるエッセイ風の文章は心憎い。井上達夫「九条削除論」は、皆さんにはぜひ読んでいただきたい出来映えである。改憲派・護憲派双方の欺瞞が、一刀両断。改憲派とは、「押しつけ農地改革」を糾弾しない、「おいしいとこ取りの輩」であって、主体性のなさ、では護憲派と変わらない自己欺瞞にすぎない。「憲法のおかげで平和だった」とのたまう護憲派は、殺されても殺し返さずに抵抗して道義的なアピールをおこなう、絶対平和主義の峻厳な責務を引き受ける気がないまま、本来なら拒否すべき防衛サービスを享受しようとする「現実への倫理的ただ乗り」の輩である。9条は端的に削除せよ!!。護憲派は、その上で、自衛隊廃止と絶対平和主義に向けた真摯な努力をおこなえ!。この骨格といえる部分の他にも、この論考が論座に乗ったとき、護憲派の側から寄せられた批判への再反論が、補論として載せられており、痛快という他はない。(長くなりましたので、<2>に続きます。暖かい応援をおねがいします)評価 ★★★☆価格: ¥ 1,260 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 25, 2006
コメント(1)
-

★ 伊藤宣広 『現代経済学の誕生』 中公新書(新刊) 2
(承前)▼ ジョン・メイナード・ケインズ。ケインズ革命とは、あくまでマーシャル的伝統、ケンブリッジ文化圏内の出来事にすぎない。ケインズはマーシャルの掌心から逃れたことを自負して「革命」を唱えたものの、ピグー・ロバートソンにとっては釈迦マーシャルの掌心から逃れていない孫悟空であったという。1920年代まで、正統派マーシャリアンだったケインズ。ケインズとマーシャルは、デフレをめぐって、結論こそ正反対であるものの、思想的・理論的には見かけほどの違いはないらしい。『一般理論』は、処方箋では従来と変わらないが、理論的空隙を埋める理論闘争の書物であり、それまでの「古典派」が完全雇用という「特殊」な状況下でしか該当しない理論に対して、「一般」であるのだという。「古典派」では≪投資-貯蓄の調整機構が利子率≫≪利子率は忍耐への報酬≫なのに対して、『一般理論』では≪貯蓄は、所得の関数であって、所得水準の変化を通して投資と均衡≫≪安定的消費関数をベースに、投資の乗数倍だけ有効需要が増加する≫≪利子率は流動性を手放すことへの報酬≫する。『一般理論』の強みは、ケンブリッジ学派に共通にみられる、公共事業や産出量・雇用量に着目したことにあるのではない。それは、マーシャルやピグーが持たなかった、「有効需要の原理」という所得水準決定・雇用水準決定の理論を持っていたことにあるという。またケインズの「流動性選好」とは、予備的動機・取引動機についてマーシャルに対応概念があり、マーシャルにおける実物利子論(投資・貯蓄で決定)・貨幣利子論(貸付需給で決定)の2つの利子概念の内、後者を発展させたものにすぎない。あくまでケンブリッジ学派の枠組での整理は、たいへん示唆に富む。▼ 結構、意外なことが指摘されていて、かなり楽しめた。フィッシャーやヴィクセルよりも早く、実質利子率と名目利子率の乖離が投機を招くことを指摘。またデフレを良いものとする評価を与えた、マーシャル。先学を蔑ろにするケインズに反発して、袂を分かつ形になったロバートソン。とはいえ近年、「マネタリストの祖先」とロバートソンやホートレーが扱われていることに対して、筆者は断固違うと否定する所など、なかなか楽しかった。ホートレーとロバートソン、「実務派エコノミストVSアカデミズム」の対決。将来に対する予想=期待が現在を決定するというのは、マーシャル以来、ピグーと続くケンブリッジの伝統であって、ケインズ固有の特徴ではないという。また、ピグーに代表されるように、正統派経済学=自由放任という図式も事実ではないらしい。▼ ここまで読まれた方は、なかなか面白い本かな、と思われたかもしれない。実際、読み物としては、かなり面白い。ところが、いざ書かれていることを要約しようとすると、凄まじい苦痛であったことを告白しておこう。というか、記述が行きつ戻りつしていて、その記述がなんのためにあるのか分かんない部分が多かった。ケインズとピグーは、結局「どの程度」、貨幣賃金の硬直性について見解に差があったのか。ピグーが賃金引き下げを述べたかどうか、延々と述べられながら、曖昧にしていたことが明らかにされる。それなら、延々と書かなくてもいいよ、「曖昧にしていた」という結論だけ書いてくれよ、といいたくなることもしばしばであった。というか、博士号取得のため提出した、博論での自分が明らかにした学術的価値のある部分。ならびに、新書として求められる、経済学者の伝記としての面白さ。どちらにも、軸足をおこうとした結果、スラスラ読みやすいけど、ちっとも頭に入らず、右から左へ内容が抜けてしまう、不思議な書物になってしまった嫌いがある。何が凄い人だったのかなあ。そう思い、勉強のために読みなおすと、読みやすい印象はどこへやら。かなりわかりにくいのである。▼ また、「現実に答えるための経済理論」こそ、ケンブリッジ学派のエッセンスである!…と言われても、そんなの高橋亀吉を含めて、実践派エコノミストなら誰でも持っていただろう…とボヤきの一つぐらい入れたくなるというもの。さらに、ケンブリッジ学派のみの論述にとどまってしまい、ケンブリッジ学派の外、とくに大陸経済学や、W・バジョットなどの実践的エコノミストたちの流れが与えた影響が、ロバートソンに関して以外、ほとんど触れられていない。とくに、ホートレーに関する整理には、一抹の危惧というか、「眉唾」感を抱かざるをえない。ケンブリッジ伝統外のホートレーという。そもそも、そんな人は、伝統の外にいるのではないか?▼ とはいえ経済思想史を学ぶ上で、これくらいタメになる本も珍しい。何よりも、アルフレッド・マーシャルがどれくらい卓越した経済学者であったのか。これを読むことで、始めてストンと飲み込むことができたことを感謝したい。思想史、または経済に興味のある方は、一読をお勧めしておきたい。追伸 「宣広」って…「広宣流布」から取ったのかなあ…評価 ★★★☆価格 ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 19, 2006
コメント(0)
-

★ 伊藤宣広 『現代経済学の誕生』 中公新書(新刊) 1
▼ ケインズは革命児ではない!▼ マーシャル以降のケンブリッジ学派の発展的継承者でもあったのだ…▼ 現実を見失なわない。それでいて現実の事後的追認ではない理論的彫拓が求められる経済学。本日ご紹介するのは、アルフレッド・マーシャル以降、ケインズ出現までの、錚錚たるイギリス・ケンブリッジ学派とその流れを描いた一冊です。現在、アメリカに制覇されている、経済学。今では、ほとんど忘れられたA・C・ピグー、D・H・ロバートソン、R・G・ホートレーなどを丁寧に追い、「ケインズ革命」の「虚と実」を明らかにします。これが新書とは、とても思えない大著で、なかなか面白い。▼ アルフレッド・マーシャル。限界革命の時代、実践と古典派経済学の乖離に対して、独自の時間概念を駆使して総合を試み、古典派の継承的発展、「新古典派」を作り出した人物。帰納的な経験科学を志向し、部分均衡分析の創始者。マーシャルは、生産費説と効用価値説の調停をおこない、物理学ではなく生物学になぞらえることを好んだ。また、「貧困の再生産」を問題視して、その克服のため「高賃金の経済論」を唱え、教育による社会改良をもとめた。さらに、有機的成長のヴィジョンに体現される社会改良の思想の持ち主で、3生産要素に4つ目として「組織」を加え、自然条件下における収穫逓減を覆す、キーとしての位置づけを与えたという。とはいえ、「完全競争」&「収益逓減」は、現実には企業の「収益逓増」と矛盾している。これを「外部経済」を導入することで妥協させようとしたマーシャル経済学の体系は、スラッファによって崩れ去ってしまう。スラッファは、完全競争の仮説を放棄、「市場の不完全性」、独占理論によって収益逓増論を構築する。一企業にとっては外部的であっても産業全体にとっては内部的である「外部経済」は存在しない…この後、不完全競争分析に向かうケンブリッジ学派。そんなマーシャルの体系は、理論的精緻化の道が閉ざされたもので、1890年代以降、アングロサクソンの経済学はマーシャル体系への注釈であると言われていたらしい。▼ アーサー・セシル・ピグー。スラム街の貧困に胸打たれ、人間生活の厚生の増大に一身を捧げた経済学者。厚生経済学3原則(A 国民分配分の平均量が高いほど、B その貧者帰属分が大きいほど、C 年較差の小さいほど、経済的厚生は大きくなる)の提唱、「租税」を通して介入することで、私的生産物(費用)と社会的生産物(費用)の乖離を埋め、社会的厚生を増大させる…こうした実践の反面、スラッファとのケンブリッジ費用論争では、「外部経済」―――企業の個別限界費用と産業の総限界費用の差額―――にこだわるあまり、「光明と果実」の舵取りをうまく果たせず、マーシャル経済学の一般均衡分析、理論的精緻化に没入してしまう。とはいえ、知識の役割を重視する実物的景気循環論、失業分析、マーシャルの現金残高数量説の定式化などにおいて、伝統をふまえ次代に引きつぐ役割を果たしているという。当初、ケインズ革命を理解しなかったピグーは、後にその評価を変えることになる。しかし、「経済分析の武器庫に非常に重要な、独自なまた貴重なものを附加した」として最後まで「革命」とは認めなかったというのは、たいへん興味深い。▼ デニス・ホルム・ロバートソン。古典派を修正しつつその「現代版」を提示しようとしたマーシャルのひそみにならい、伝統的マーシャル体系を引きつぎつつ、その「現代版」を提示しようとした「最後のマーシャリアン」。ケインズの弟子・友人であり、また後に激しく敵対することになる人物でもあった。マーシャル経済学では、例外的現象として扱われたため手薄だった景気循環論が研究テーマ。過剰投資とその反動=不況をもたらすものは、彼によれば、供給側要因として「投資の懐妊期間」「投資の不完全な分割性」「扱いづらさ」「資本財の寿命の長さ」、需要側要因として流行・戦争・関税・農業政策という。その際、大陸経済学の影響も受けつつ、実物的波及過程を描くため、実物的景気循環論=「貨幣なき実物」というアプローチがおこなわれた。あたかも、近年のキドランド&プレスコットの実物的景気循環論とは表面上同じ様に見えるとはいえ、1910年代から既に不況対策に公共事業を提唱したロバートソンとは、ヴィジョンそのものがまったく違うものらしい。彼は、ケインズとともに「投資-貯蓄アプローチ」を行い、「強制貯蓄」概念を提出して、「投資-貯蓄」が一致しない状況を論じる一方、物価安定を目指す銀行政策と、資本形成のための資金を供給する銀行政策、この2つが両立しないことを明らかにしたという。▼ ラルフ・ジョージ・ホートレー。大蔵省金融研究局長などの官庁勤務。直接マーシャルの謦咳に接したことのない、ケンブリッジでは傍流。とはいえ、古典派にみられる貨幣ヴェール観を徹底的に批判して実物ヴェール説を主張。実物よりも貨幣・信用を重視した彼は、不況下にあっても財政政策よりもスピードに優る金融政策を重視、金融的景気循環を唱え、ロバートソンとは激しく対立した。ホートレーは、商人重視でひときわ異彩をはなつ。貨幣数量説(貨幣量と物価の機械的比例関係としての)を批判して、商人の抱える在庫がバッファーとして働くことをのべただけではない。商人在庫の存在は、数量調整の方が価格調整よりも先であることを意味する。またホートレーの経済理論では、マーシャルからロバートソンまでの産業主導の経済理論という伝統に対して、金利感応度の高い商人(故に金融政策が重視される)が決定的な役割を果たすモデルが提示されていて、今見てもたいへん面白い。(長くなりましたので、<2>に続きます。暖かい応援をおねがいします)評価 ★★★☆価格 ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 17, 2006
コメント(0)
-

★ 2002年W杯 韓国-イタリア戦の感動と、イタリアが優勝するための条件とは
▼ スポーツを観戦して、感涙にむせぶことなんて滅多にない。だからこそ、そんな瞬間に立ち会える幸せをもとめ、ついついスポーツ番組を見てしまう。しかし、それは稀にしか訪れることがない。サッカーを観戦して、もう何十年になる。しかし、そんな瞬間は、今まで前回W杯の「韓国-イタリア」戦だけしか体験したことがない。▼ あの日、僕は友達と外国にいた。だから、不満・鬱憤がネットにぶちまけられることになる、日本におけるテレビ中継の「韓国贔屓」とは縁がない。あの試合、とある大画面のテレビの前に、韓国人が百名近く集まっていた。彼らは、赤いユニフォームを着て、「テー、ハン、ミング!」と大合唱していた。その様子を、周囲の日本人と同じく、不快に感じながら眺めていたことを覚えている。サッカーファンで、韓国チームを応援するような奴は、日本人にはいないだろう。サッカーファンにはあるまじき、「ドイツサッカーファン」の私であっても、当然の様にイタリアを応援していた。▼ ところが、である。先制すると、早速、ゴール前に鍵を掛けたイタリア。その鉄壁のカテナチオに、韓国サッカー選手は、突っ込む。守備では手荒いファウルを浴びせ、全局面で走りまくり、技術的に上回るイタリアを自陣に押しこめて、土壇場で同点に追いついてしまう。おまけに、トッティ王子は退場。なんたる凡戦。なんたる判定。イタリアには、敗色さえ漂う。とても、マジメに見ていられる試合ではない。ふざけんな。▼ そう思った瞬間、韓国人サッカー選手が、テレビ画面をよこぎった。凄まじい形相。つった足。ビッコを引き、苦痛に顔をゆがめながら、転びそうになりながら、それでもゴール前に走ってゆく。精神が肉体を超越するさまを目撃したとき、涌きあがる言葉にならない感動が私を襲った。このふざけきった試合は、私にとって聖なる試合に変わった。その直後のことだった。安貞桓が決勝ゴールを決めたのは。爆発する韓国人サポーターの歓喜に交じることなく、私は茫然となりながら自室へと引き揚げる。なすすべなく敗けた、同W杯の日本-トルコ戦、昨日の日本-オーストラリア戦とは、対極にある試合といって過言ではない。▼ 感動とは、言語化できないもの。否、言語の効果として立ち現れる、言語で説明できない剰余なんだろう。韓国-イタリア戦は、技術的にも、戦術的にも、フェアプレイの観点からも、何一つ誉められる試合ではない。もっと素晴らしくて美しい試合はいくらでもある。ところが、よりによって、こんな試合に感動を覚えてしまった。モレノ審判員の買収話を書き立てる『週刊誌』や2ちゃんねらーをみるたびに、憫笑していたものだ。対ポルトガル戦や対スペイン戦では、韓国に憎悪すら覚えているものの、「韓国-イタリア」戦をみることができたことは、今でも感謝している。▼ イタリアは韓国に完全に力負けをした。それだけは間違いない。アイデアのない中盤。意図のないカウンター。守備的なだけの選手たち。負けて当然。そんなサッカーの質しか、イタリアには備わっていなかった。疑うものがいるなら、1982年スペインW杯のビデオを見るがよい。ブラジル-イタリア戦だけでなく、決勝のイタリア-西ドイツ戦、イタリア-アルゼンチン戦も見てほしい。残酷なまでに、美しいカウンター。守備だけでなく、攻撃があまりにも素晴らしかった。82年に比べれば、02年W杯のイタリアなど、出来の悪い模造品でしかない。▼ まったく破綻することのない、マンツーマンディフェンスと、それを締めるシレアのカバーリングのすばらしさ。今みても、まったく遜色がない。日本がお手本にしてほしいくらいである。それぐらい美しかった。▼ 何よりも、マルコ・タルデリと、ブルーノ・コンティの活躍は筆舌に尽くしがたい。大会6得点、ジーコ・ファルカンのブラジルを沈めるハットトリックを決めたロッシ。40歳の主将、鉄壁のGKゾフ。この千両役者2名に隠れて目立たないが、イタリアの中心は明らかにタルデリとコンティだった。タルデリは、フィールドの全域に出没して攻守をつなぎ、コンティは独楽のように踊り回りながら、ドリブルで堅陣を切り崩す。西ドイツ、アルゼンチンは、この2名にやられたといっても過言ではない。タルデリは、サッカー歴代ベストイレブンに選びたいぐらいだ。▼ 結局、イタリアが20年間、W杯に優勝できなかったのは、タルデリとコンティの役目を果たせるプレーヤーがいなかったためだろう。ロッシの代役はいた(バッジョ)。ゾフの代役もいた(ブッフォン)。アントニオーニの代役もいる(ジャンニーニ、ピルロ)。グラッツィアーニの代役もいる(トニ、ビエリ、ビアリ)。シレアやカブリーニや、ジェンティーレの代役はいなかった時がない。バレージ、ネスタ、マルディーニ、コスタクルタ、カンナバーロ… ましてや、オリアリに事欠かない。しかし、タルデリとコンティの代役だけは、1982年以降、見つけることができなかった。この2名だけは、どうしようもないのだ。デ・ロッシとカモラネージでは、とてもタルデリとコンティの代役は果たせそうにない。▼ 圧倒的なブラジル優勢が囁かれている2006年ドイツW杯。イタリア・イングランドなどの、ヨーロッパ勢の健闘がもとめられている。イタリアが歓喜につつまれるとき、それはタルデリとコンティの代役が、見つかった時であろう。永遠を思わせるコンティのドリブルと、神出鬼没のタルデリの走力・判断力。2名にかわるサプライズが、イタリアに訪れることを願ってやまない。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 13, 2006
コメント(11)
-
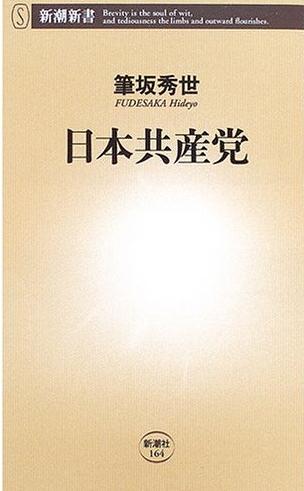
★ 筆坂秀世 『日本共産党』 新潮新書(新刊)
▼ ご存知、セクハラで止めさせられた、元・日本共産党NO.4による、日本共産党の内部告発本。期待値も高い。これまで、共産党モノといえば、立花隆『日本共産党の研究』(講談社文庫)以外には、礼賛本か、それとも罵倒本か、どちらか一方しか存在しなかった。マトモじゃない状況というのが、マトモという、妙な業界だけあって、一読してみると…▼ 他の新書の売り上げ数全部併せても、『バカの壁』一冊に及ばない。そんな新書の惨状も、『国家の品格』の出現で一息ついたのか、イケイケムード。今度は、『日本共産党』を出してきた。実際、読んでみると、ギトギトとした怨念がゆらめいているとはいえ、なかなかバランスのとれた日本共産党入門になっている。門外漢も、手に取りやすいのではないだろうか。簡単にまとめておきましょう。▼ 「常幹」「幹部」がやたら幅を聞かす組織、共産党。創立84年。「日本最古の政党」=共産党は、「中央委員会」を頂点とする組織として、鋼鉄の団結、職業革命家である必要もあって、民主主義的な中央集権制を掲げている。中央委員会総会が開催される間は、幹部会、なかでも「常任幹部会」(常幹)が実権を握っているという。その幹部会は、幹部会委員長の元、毎週月曜日開催され、その報告と指示が「都道府県委員会」「地区委員会」「支部」と、順繰りに下におりてくる。地区委員会まで専従活動家がいて、その数およそ数千名らしい。▼ 議員よりも、議員秘書の方が「強い」共産党日本共産党員は、赤旗を配り、集金し、選挙運動をおこない、政治運動をおこなわなければならない。むろん、よく知られているように、党から与えられた任務として、議員になるという。党が止めろ、というなら止めない訳にはいかない。一方、「調査の共産党」を支える秘書軍団は、党本部が採用する。党本部各部署の人事異動の結果、職員として赴くのだという。だから秘書は、議員よりもはるかに特定分野の専門家で、議員は質問さえつくれないのだとか。本部他職員と秘書に給与差をつけられない。そのため秘書給与は、党本部にいったんプールされ再配分、差額が「自主的献金」となるが、かなり法的にアブナイ。▼ 常任活動家の給料は、遅配が当たり前。募金攻めにあう共産党員公式のプロフィールと実態は随分違う。政党助成金をもらわないなど、一見高邁に見える日本共産党の財政は、恒常的に火の車らしい。自民党などが良く流す、年間収入300億円はウソ。赤旗発行経費も180億円もかかるからである。肝心の赤旗日曜版(日刊は30万部程度)は、全盛期の350万部の半分以下、160万部強しかなく、「党勢拡大運動」に邁進しても、かえって減少しているという。活動家の妻は教師か看護婦でもないと勤まらない。かつては民主主義的政党・団体に「物質的条件を提供する」ことを憲法草案で謳った共産党とは思えない対応。聞いていると、まるで統一教会か、新興宗教のようだ。▼ 地区・都道府県・中央委員会各委員、中央委員会議長選出の茶番劇そもそも彼らは落選が想定されていない。宮顕・不破の一存で「人事」が決められていくという。ご自慢の「民主集権制」も、党大会議案の党員読了率が3割の状況下では、完全に形骸化しまっている。中央委員まで、たびたび「理解が浅かった」と自己批判する始末だという。党員活動率は3割にすぎず、一部の運動家に過度の負担がかかっている革命政党。若手ですら、60代という状況らしい。おかげで末端の支部委員には成り手がいない。また理論闘争も、宮本顕治・不破哲三の40年以上の支配によって、無きに等しい。民主主義が形骸化している様が断罪されていておもしろい。▼ 不破哲三の陰湿かつ衝撃的な志井委員長イジメ党内には、不破委員長、ナンバーワンしか存在しない。他の人間は、何も力をもっていない。幹部たちは、今でも志井には「面従腹背」のありさまという。議長・名誉議長などの役職についていても、共産党では代表者・党首とは限らない。中央委員会では、議論がほとんど行われず、「大言壮語」「自己批判」ばかり飛び出す始末。不破の前に圧倒的な実権を握っていた宮本顕治勇退(当時88歳)も、周囲の必死の説得でおこなわれたもので、議長の座に固執し続けたらしい。▼ 『聖教新聞』上の池田大作先生と匹敵する、不破「野党外交」の面白さ「現代のマルクス」不破委員長の迷走もすばらしい。拉致問題「棚上げ」発言なども、執念深く収録され、「名刺外交」「沈黙の交流」など、近年の『赤旗』を賑わす野党外交がケチョンケチョン。無党派と連携して、民主連合政府をつくるなんて、夢のまた夢。選挙の敗北の総括は、つねに「正しかったが」「逆風によって負けた(メディア・国民に責任転嫁)」ので「負けないような大政党をつくるため党員と赤旗購読を増やそう」というものであるらしい。そんな中で、「中立・自衛(最小限の軍隊を保有)」(1973)→「自衛隊廃棄」(1994)→「自衛隊活用」(2000)→「自衛隊反対」(2005)と、コロコロかわる防衛政策の迷走ぶりには、ため息すらこぼれてしまう。▼ 共産党に関しての知られていない実態も、明らかにされていて面白い。大企業・官公庁に潜む党組織は、あくまで党の影響力を拡大するためにある。そのため党幹部にも、存在が秘匿されていて、会うことができないらしい。共産党は、「横のつながり」がないため、選挙は見知らぬ人ばかりを選ぶことになり、むしろ積極的に活動して有名な人に不信任票が入る体たらくであるという。最高幹部間で交わされる「指導部」とは、不破氏のことらしい。「党名さえ変わればなあ」という党員の不満には、同情さえ感じてしまう。▼ 手厳しくもあり、絶ちがたい愛もあり、隠しきれない恨みもあり。そんな共産党の内幕を暴いた本書は、「止めない内に気づいて、何とかしろよ、筆坂!」という不満さえ抱かなければ、かなり楽しく読むことができるのではないでしょうか。特に、拉致問題についての共産党の対応への批判は、五十嵐仁の兵本達吉『日本共産党の戦後秘史』批判(1)・(2)への再批判にもなっていて、なかなか面白かった。ただ、やはり残念なのは、戦後日本共産党の通史にはなりえておらず、ここ10年ほどの状況しかわからない点だろうか。とくに、1970年代の「社共共闘」時代には、ぺーぺーの平党員でしかなかったため、一番共産党が面白かった時期については何も分からない。残念な話である。▼ 今後は、年配幹部党員などからの証言資料収集などをおこない、戦後日本共産党史の執筆を期待したい。皆さんもぜひ手にとってお読みになることをお願いしたい。評価 ★★★☆価格: ¥ 714 (税込み) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 10, 2006
コメント(5)
-

★ 甚野尚志編 『東大駒場連続講義 歴史をどう書くか』 講談社選書メチエ(新刊)
▼ 歴史を書き換えを図る「歴史修正主義」、「新自由主義史観」が登場して何年もたつ。上野千鶴子までが従軍慰安婦論争に参戦して、「構成主義 VS 実証主義」の対決さえ帯びたのも今は昔の話。東大駒場キャンパスでおこなわれた、この歴史学講義。「歴史学の今」を測定するには、格好のテクストといえるでしょう。▼ 内容を簡単に紹介しておきたい。▼ 第1部は「儀礼と王権」と題して3本立て。第1章、義江彰夫「日常生活をとおして見る歴史の再構成」は、古代から中世にかけての衣服の変遷をたどる。最古の「貫頭衣」は、朝鮮半島からの影響を受けて、支配層では「左前」式の衣服や、中国的衣冠束帯を着用していく。それが、平安後期になると、衣服の大型化・寛闊化が始まり「強装束」に移行していくとともに、貴族から庶民まで、「おくみ」のついた「垂領」(たりくび)型衣服を着用するようになる。その変容は、旧来の村落共同体的な土地所有――― 「初穂」を租庸調に置き換え、税金として徴収―――から土地の「私有」への転換という、律令国家の地殻変動が横たわっており、貴族・豪族・庶民の一体感・統合を醸成するものであったという。第2章は、三谷博「天皇の即位儀礼」は、孝明・明治・大正の3代の即位儀礼が、「中国風」→「和風」→「西洋風」という変遷を遂げたことをたどることで、王政復古が≪宮廷外勢力によるノットリ≫であることが示される。第3章、甚野尚志「ヨーロッパ史における『王権』の表象」は、自らを「キリスト教ローマ帝国」の後継者と位置づけることで世俗権力に対抗しようとした、教皇の即位儀礼の分析が行われる。亜麻布を燃やして現世の移ろいやすさを教皇に理解させる「灰の儀式」など、王権を庶民に誇示するための儀式の様子は、読んでいて面白い。▼ 第2部は、「モノで読む歴史」と題した4本立て。第4章、折茂克哉「モノで語る歴史 考古学と博物館」は、原始人がどのように博物館展示において復元されているか、詳細に述べられる。皮膚の色や体毛、知能レベルや精神活動(芸術や信仰)、有機物の道具などは、出土することはない。そのため、研究者のイメージに頼らざるえない。マンモスの「追い込み猟」は、よくコマーシャルなどで見られイメージとして定着しているものの、現実にはありえないという。第5章、平川南「古代国家と稲」は、1200年前の品種札の発見から、古代律令国家において、予想以上に品種などについて、稲作管理が行われていたことを明らかにする。品種は、早稲・中稲・晩稲の3種があって、農繁期において労働力を他地域から投入するためにも、郡を単位にほぼ品種統一がなされていたらしい。税負担よりも、春に種子を貸し付け5割の利息を秋に徴収する「出挙」の方が重要で、農民に一律に種子を貸し付けていたという。そういえば、そんな話、聞いたことがある。▼ 本書のキモとなるのは、第6章、三浦篤「≪オランピア≫の変貌」と、第7章、今橋映子「写真史が生まれる瞬間」かもしれない。前者では、造形物がどのような歴史的文脈で生成したのか、そのプロセスを明らかにして作品の解釈・意味づけを与える≪美術史≫の方法が、具体的に実践されてゆく。その題材は、マネ「オランピア」。旧来の裸婦像に対し、斬新な裸婦像を提起、「平面性と造形の自律」を指向する西洋近代絵画史を起動させた、マネ「オランピア」の革新性。発表当時のスキャンダルと悪評は、印象派~抽象絵画など、後の「モダニズム美術史」の中において、ゴーガン、ピカソなどによって、「近代絵画のイコン」として賛美される存在に≪解釈・意味づけ≫が変貌してしまう。解釈に正解はないのだ。また後者では、写真≪史≫なるものがどのように生まれるのか。著者は、ウジェーヌ・アジェをどう関係者が位置づけたか、その言説を検討することによって、その≪発生の瞬間≫を明らかにする。アジェの活躍した時代は、アマチュアによるスタジオでの肖像写真撮影を仕事にしていた、「絵画のような写真」を取ろうとするピクトリアリスムの時代だった。1928年に死去する彼は、大陸などではベンヤミンたちによって「シュルレアリスムの先駆」とされる一方、アメリカでは「都市ドキュメンタリー写真の始祖」として、後代の写真家・写真史家によって祭り上げられてゆく。その丁寧な追跡は、スリリングのひとことである。▼ 第3部は、「歴史とアイデンティティ」。ここには、民族や集団のアイデンティティと歴史記述について語った3つの論文が収録されている。第8章、井坂理穂「植民地期インドにおける歴史記述」は、インド社会でエリート層にあたるゾロアスター教徒が、どのようにアイデンティティを持つようになったのか、その内容と過程を描く。10世紀、ペルシャからインドへ移住する(とされる)彼らは、19世紀、イギリスのインド統治期に台頭する。ゾロアスター教徒は、「自分たちの歴史」を描く際、西欧「歴史学」の枠組・手法・観点を借用し、栄光の古代から苦難を経て、19世紀以降、再び栄光の時代を迎えるという歴史像を描いたという。第9章、瀧田佳子「文学は歴史をどう書くか」では、第二次大戦中の日系人の強制収容所での体験を描いた、日系アメリカ文学の作品が論じられる。決して正史=「大きな歴史」として残されることがないが故に、オーラル・ヒストリーや日系アメリカ文学は、歴史の証言として貴重な価値をもつことが説かれて止まない。第10章、伊藤亜人「歴史の多声性 歴史観の人類学的考察」では、人類学の立場から、とりわけ「主体性」を重視してしまう韓国人の歴史認識の有り様が分析される。中華的な王朝史観、檀君神話の民族史観、族譜にみられる門閥史観、反正統的な逆賊などを拠り所とする民衆史観。韓国の歴史認識は、いずれも「人物」に主眼がおかれ制度的視点が弱いらしい。檀君神話と皇国史観の類似性。また、構造的周縁であることを自覚せざるを得ない故に出てくる韓国「民衆史」と、周縁の自覚に乏しく生活世界にすぎない日本の「郷土史」との違いは、たいへん興味深い指摘といえるでしょう。 ▼ 雑学も、多岐にわたっていて面白い。女官の「重ね着」は、「対の屋」「釣殿」が「渡り廊下」で結ばれるようになってから出現しただけでなく、男性が女官の支配する宮中に介入する時期と符節をあわせるかのように現れてくるという。また、教皇即位儀礼の中心が、ローマ司教座の置かれたラテラノ大聖堂からサン・ピエトロ大聖堂へ移ったのは、自立性を深める都市ローマに自由に立ち入ることができなかったためらしい。ドキュメンタリー写真とは、「過去・現在・未来に対しての直観」を備えた「未来への考古学」でなければならないこと。また正統的な美術史とは、対象となる造形物を観察して言語化することに基盤があり、歴史学と美術史では、対象と資料が逆転しているという指摘も興味深い。なによりも、韓国人の歴史認識についての議論は、蒙が解かれる思いさえさせられた。世界で類例のない韓国の父系の親族体系が庶民・全国レベルまで浸透するのは、なんと、19~20世紀にことにすぎないらしい。ただ、この「門閥」氏族によって、その数だけ歴史が編纂され、個人にルーツと社会的威信を供与するだけでなく、人々は祖先の歴史を共有し、組織的に団結して助け合うことになる。それが、主体性、人物重視の歴史認識を産み落としているらしい。このような土着的歴史認識を「否定」した上で、近代歴史学の覇権がもたらされた日本・韓国。歴史を共有するとは、歴史の多声的実態を尊重することだ、とされて本書は締めくくられている。▼ ただ、全体的評価となると、「まあまあ」といった感じがしないでもない。▼ 第1章の≪服装による一体感≫だが、どうだろう。「みんな一致していた」貫頭衣の時代と、「一致していない」古代と、「再び一致する」垂領の時代(古代後期)。この3つ位相とその変動を説明できるとは、とても思えない。第3章は、教皇を世俗王権とみて、即位儀礼の分析をするのだが、もともと世俗王権は、カトリック教会を模倣して儀礼をおこなったのではなかったか?。世俗王権の即位儀礼と教皇即位儀礼の比較もされている。しかし、教皇即位儀礼の分析にどのような意味があったのか。ましてや「歴史の書き方」となんの関係があるのか。どうしても疑問を感じてしまう。第4章は、ちょっと退屈。言わずもがな、という感じ。第8章は、ある一人の19世紀のゾロアスター教徒が書いた「自分たちの歴史」が、何の注釈もないまま、現代ゾロアスター教徒の歴史観にまで適用されてしまう。いいのか?そんなことして? 現代インドの教育は、彼らに何の影響力も与えていないのだろうか。階級差・性差・地域差・「時代差」を考慮しないで、「大きな影響」と大ざっぱに語られても、眉唾の域を出ていない。第9章は、たんに退屈。オーラル・ヒストリーの重要性は言うまでもないのであって、改めて言われても…。▼ 面白いのは、第2章、第5章、第6章、第7章、第10章あたりかも。ただ、値段の高い選書なので辛くつけてあるが、優れた本であることに変わりはありません。図書館で見かけたら、皆さんにもぜひご一読いただきたい。評価 ★★★価格: ¥1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 4, 2006
コメント(1)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…
- (2025-11-16 04:53:29)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 【書籍感想】暁花薬殿物語5
- (2025-11-17 21:23:35)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 206冊目「王太子妃になりたくないの…
- (2025-11-17 22:00:04)
-







