2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年08月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

★ 靖国問題を考える:メモ
▼ 最近読んだ靖国論で、なかなか過激で、面白かった靖国神社への批判があったので、ネット史料として、メモがわりにのせておきます。新聞夕刊に掲載されていたものですが、皆さん、どうでしょうか。● 靖国問題を考える 加々美 光行 神国不敗、総玉砕強いた国家指導者の責任当然 7月20日、靖国神社へのA級戦犯合祀に関する昭和天皇の批判的見解が「富田メモ」の形で公表され、さらに8月15日、小泉首相が靖国参拝を強行したため、靖国や戦争責任をめぐる論議が俄然熱気を帯びるようになった。 戦後60年余を経て、先の戦争評価について国民的論議が高まるに至ったこと自体は歓迎すべきことだ。だが、戦争評価を巡る論議は「両刃の剣」であり、私たちの国家を危険な方向へと導く結果にもなる。その点、特に若い世代から戦争は「普遍的悪」だから、戦争責任について勝者か敗者かを区別するべきでなく、敗者の国家指導者のみに責任を転嫁するのはおかしいとする意見が聞かれるのには、危惧を感じざるをえない。★ 問題は勝者か敗者かを区別する点にない。日本が遂行した先の戦争を古今東西の戦争一般と同一視し、その特異性を見ない点に問題はある。1930年代以後の日本の戦時国家体制が人類史上、類例を見ぬ体制だった事実を忘れてはならない。戦時体制はまず天皇神格化による個人崇拝と陸軍部による独裁を特徴としたが、それだけなら古今東西、前例はある。 その類例のなさの第一は「神の国」として「常勝不敗」を不可侵として奉じたこと。それゆえ第二にいかなる意味でも「勝利なき終戦」を許さず、敗北を余儀なくする場合は一切の投降を認めず、総員「玉砕」を義務づけた。第三に国民に日本の常勝を信じさせるため、大本営発表によって自軍の勝利戦果をねつ造し、戦況の実状を国民に一切知らせなかった―――この3点にある。 43年5月のアッツ玉砕、44年のサイパン玉砕、グアム玉砕、同年秋の神風特攻隊編成の下命、45年の硫黄島玉砕、そして沖縄玉砕戦は、まさにこの異様な戦時体制のゆえに生じた。この総玉砕戦は「勝利なき終戦」を許さぬ結果、日本全国民の消滅を想定し遂行された。実際、上述の玉砕戦では軍人のみが総員死を遂げたのではなく、島民である民間人もすべて総員死を強いられた。★ 現実には43年以後日本は配色を濃くし、国家指導者なら「勝利なき終戦」への解決を求めて当然の状況だったが、そうした解決を口にすることは、「常勝神話」の不可侵性を犯すこととなるから、自身の生命を賭ける勇断を必要とした。むそんそのような勇断を敢えてなした国家指導者はいない。38年公布の「国家総動員法」、40年の大政翼賛体制の発足、41年東条英機陸軍大臣の起草になる「戦陣訓」、とくに「本訓其の二の第八 名を惜しむ」にある「生きて虜囚の辱を受けず」に始まる「玉砕論」こそ、総玉砕を作り出した元凶だった。 私の三兄は45年3月、大本営の無謀な作戦指令によるボルネオ島の「死の行軍」の直後、戦病死を遂げたが、この「玉砕論」がなければ生還し得た。さらに言えば、同じ論理からこの「神国日本」に敵対するすべての人々は、軍人か民間人かによらず「人」として認められなかった。中国大陸、朝鮮半島、アジアにおける日本軍の残虐行為はそうした病理から生じたのだ。 こうした史上前例のない異様な“カルト的”戦時体制を構築した当時の日本の国家指導者の戦争責任を追及せずして、その罪を日本国民一般や他国の戦争指導者の罪と同列に論じ、結果的にこれを免罪してしまうことが、いかにおかしなことか、他国の裁きや判断にまつまでもなく、日本人みずからもっと早くその犯罪性を認識すべきだったのである。私はこの意味で当時の国民一般と国家指導者とを戦争責任において厳密に区別すべきだと考える。★ 72年9月の日中国交正常化に際し、周恩来は、対日戦争賠償請求の放棄を言明、その理由を説明して「日本人民も戦争被害者。賠償請求は日本人民の肩に莫大な重荷として降りかかる。それは中国の望まぬこと。賠償請求放棄は中国人民への子々孫々にわたる友好の証しとしての贈り物」と述べた。この言明を「国家指導者と国民を分ける区別論」という。 靖国へのA級戦犯合祀に中国が強く反対する理由もそこにある。しかし今日、この周の「区別論」を中国の「陰謀」とする議論が聞かれる。「陰謀説」はむろん日本の戦時体制の病理を直視せず、むしろ美化しようとするものである。周がどう言ったかが問題ではなく、日本人としては「区別論」に立ち、戦争指導者の誤りを明らかにすべきではないか。この点を最後に、戦争を知らない若い世代に問いかけたい。▼ 紹介した私がいうのも、変かもしれないけど、ちょっと、言いすぎじゃないの?という部分も多いです。一読して、ちょっと混乱しているのではないか?推敲が不十分ではないか?といいたい箇所も、見え隠れしてしまう。たとえば、類例のなさとして、3つほどあげられているものの、実際には2つ目いかなる意味でも「勝利なき終戦」を許さず、敗北を余儀なくする場合は一切の投降を認めず、総員「玉砕」を義務づけたを除けば、世界各国で見られる現象なのではないか。戦勝報告の捏造など、大なり小なりおこなわれているだろうし。▼ ただ、これをメモとして残すのは、日本側からの「2分論」の典型的言説だから。そこに使われる道具立ては、日本と世界、その同質性よりも異質性を強調・摘出して、その責任を追及すること。たしかに神風アタックなんて、異質性の最たるもの。富永恭次中将なんか、「最後の一戦で本官も特攻する」「諸君たちは、すでに神である!」と訓示をたれ、部下達を死地に追いやりながら、自分はさっさと敵前逃亡、挙句のはてにシベリアで捕虜。天寿を全うした訳ですし。▼ 今では、国民責任を免責する議論は、左派ではまったくメイン・ストリームではありません。批判されてしまうでしょう。右派では、国民と指導者、両方免責して、人と人の「間」の媒体、すなわちメディア、分かりやすくいえば「朝日新聞」に責任転嫁する議論が一般的でしょう。まあ「媒体」に責任転嫁するのは、「主体」の自立性を徹底的に剥奪する、思想の洗礼を浴びたものとしては、いや~そのとおり!良く分かってんじゃん!!とばかり、賛意を示したいのですが、なぜか論者はトンデモが多いですな。 それなら当然、日本語、日本文化の責任にでも転嫁が可能な訳で、へんちくりんな「媒体」責任論のオンパレードになりそうで、却下したいです。てか、また、反論とばかり「主体性論」が復権するだけなんじゃなかろうか。人間は、「主体」なのか、「主体」たりえないのかが、永遠に蒸し返されるのか………い、いかん、話が逸れてしまった。▼ 気持ちよく「2分法」に分かつのは、今では珍しくなってしまった。しかし、戦後直後には、「一億総懺悔なんてふざけんな!」「悪いのはお前ら軍人だろ!」と、反軍的雰囲気が瀰漫するなかでは、大いに受け入れられたものではあるはずです。形をかえて、今も受け継がれるこの論理は、周恩来の「子々孫々への贈り物」とする温かい(だからこそ、政治的に素晴らしい)言葉とともに、一読しておく価値があるでしょう。加々美光行(かがみ・みつゆき) 氏愛知大学国際中国学研究センター所長。1944年生まれ、大阪府出身。東大文学部卒。アジア経済研究所主任研究員などを経て91年から愛知大教授。著書に『現代中国の挫折 -文化大革命の省察』『アジアと出会うこと』『中国世界』など。←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 28, 2006
コメント(0)
-
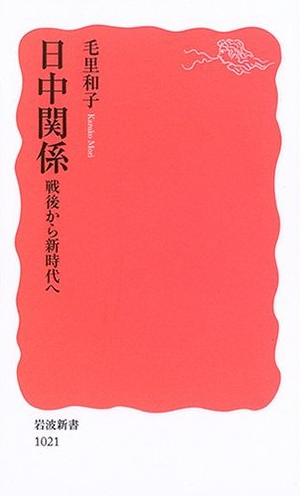
★ 毛里和子 『日中関係』 岩波新書 (新刊)
▼ 現代中国研究の大家、毛里和子氏による、待望の日中関係を分析した本が、上梓されています。「日中関係を分析することは日本を分析することと同じ」ことを認識しながらも、注意深く、日中現代史が俯瞰されていて、たいへん面白い。初心者のみならず、研究者にとっても、参考になるものといえるでしょう。▼ 簡単にまとめておきます。▼ 英米の対立(中華人民共和国を英は承認)によって、大陸と台湾、双方とも参加が認められなかったサンフランシスコ対日講和条約は、冷戦下、米国主導の下、中国・ソ連包囲網の最前線の役割を担わせるためのものだった。市場としての中国を求める日本財界。しかし、米国の日中分断戦略から阻まれ、1950年代以降、両国とも中国のかわりに東南アジアへ進出先をもとめてゆく。そのため、日本にとってアジアとは、市場、もしくは日本が主導権を握って束ねる「客体」であるにすぎず、今にいたる日本とアジアの疎遠な関係の遠因にもなったという。「以怨報恩」で知られる蒋介石の対日賠償要求放棄も、日華条約調印直前まで、賠償要求をおこなうつもりだったらしい。当初は中国も、党レベル、政府レベル双方で、具体的政策をもたずに、日本に対応したものの、1953年頃には今日まで続く対日外交の大原則、日本軍国主義と日本人民を分ける、いわゆる「2分論」が出現するようになる。対日賠償放棄方針も、1964年頃には定まっていた。▼ 1973年10月、田中角栄と周恩来のわずか4日間の交渉によって、劇的に展開した「日中国交回復」。それまで積み重ねられてきた、超党派&民間レベルでの「日中貿易推進」の積み上げの成果であるという。1969年頃から始まった米中の接近。ベトナム宥和・対ソカードに使いたいニクソンのアメリカは、「台湾独立を支持しない」「対中国交正常化確約」など、かなりの譲歩をおこない、上海コミュニケに結びつけたという。72年7月の「竹入義勝・周恩来」会談で、中国側は台湾問題の口頭約束で処理、対日賠償放棄、日米安保の容認など、日本側にとってかなり有利な条件を提示していた。にもかかわらず、日本側は「中国は請求権を放棄する」という原文から「権」を削り、「戦争の終結」ではなく「不正常な状態の終了」という表現をのませるなど、さらなる譲歩を「中国側が日本の主張を理解する形で」勝ち取ることに成功したという。▼ ただ、この日中国交正常化の過程では、日本側には「戦略の欠如」「国内政治の延長としての外交」「外交感覚や歴史的センスの貧しさ」という今も続く病弊が見られる一方、中国側にも「国際政治の戦略性過多」「道義にもとづく大原則(日本国民の負担になる賠償請求はできない)あって、具体的政策なし」「国内世論無視」という、方法論的に致命的な欠点を抱えていたという。どんなに、日本側が日中戦争の問題、いわゆる「歴史問題」に決着がついたと考えたとしても、一枚の紙切れによって、決着がつくはずがない。対日賠償請求放棄は、日本が台湾との政治関係を切ることに使われたという指摘には、江沢民が執拗に「歴史認識をとりあげよ!」と言った背景とも連なっていて、「そうだったのか!」とあらためて驚かされるだろう。▼ この「72年体制」が、台湾民主化による「一つの中国論」の破綻、主要敵ソ連の崩壊、日本の政治構造の変化、対外開放とインターネットによる中国における世論の強大化によって綻びを見せ始めたこと。これが、日中関係の難しさを生んでいるという。もはや日本側は、大平首相時代のように、「強くて安定した中国」を望み、ODA借款を供与することはない。ただ中国側は、日本のように「環境保護」「国際的相互依存」「人道主義」としてODAを捉えず、「国家利益の最大化」としてODAを捉えるものの、賠償放棄したのだからODA供与は当たり前、という言動は見せたことがないらしい。1990年代初頭には、天安門事件に対する日本側の穏和な姿勢、「日本がアジアに帰ってきた」「日本の再アジア化」と、日本がアジアにおいて地域安全保障に関して役割をはたすことに対して、賛意をしめす動きさえあった。それが、1996年の台湾海峡危機や、日米安保再定義、中国の急激な台頭によって、日中関係は構造的大変動をとげてゆく。▼ ポスト冷戦期である現在は、無制限な経済的相互もたれあい、政治的・経済的・戦略的競合関係へのシフトの中で、両国国民とも感情的な関係に入りながらも、日本は強大化する中国にどう対応していいか分からず、中国は軍事力&日米同盟を強化する日本にどう対応していいのか分からない、不透明な時代であるという。今や、周恩来・毛沢東の2分法が、インターネットで「奇談怪論」呼ばわりされる一方、「戦後は終わった」意識の日本では、対外的には反省と謝罪する「外の顔」と、A級戦犯を祭る靖国神社にお参りする「内の顔」、≪両者の使い分け≫が陰を潜め、かつての「内の顔」が「外の顔」になり、密教が顕教化するようになる。この変容を、中韓は許容できない。しかも、日中のナショナリズムは質的な違いがある。日本では、政界における、伝統的日本主義に回帰する動きだけが突出しているが、中国では「自己愛」「大国意識」「不平等感」によって、大衆的・情緒的ラディカリズムが出現する一方で、冷静な「対日新思考」外交の提唱などの、≪思潮の多様化≫と≪社会の多元化≫が特質であるという。靖国神社問題は、「内政問題」「文化の問題」「文化相対主義の問題」では片付けられない、「国際政治の問題」と一刀両断されていて、右派結集の軸「台湾との接近=歴史の見直し」についても手厳しい。日中ともに、アジアを軽視してきたことを指摘。日中関係再構築には、関係の理性化、リーダーの定期的接触、歴史問題の公的機関の設置、レベル毎に異なるチャンネルを形成して「利益」をシェアすること、多国間レジームの形成(東アジア共同体)とならんで、日中による共同事業が提唱されて、本書は締めくくられる。 ▼ 1995年頃、日本人は戦後が終わったと考えた。しかし、中国は考えていない… 何よりも日中国交回復に参与できなかった中国人にとって、戦後はやっと90年代から始まったのだ… 靖国神社参拝とは、中国政府の提示した、日中戦争の解決の方法、「2分法」のシンボルであるが故に絶対に譲れない。4人組に罪を負わせた文革と同様に、とりあえず「解決」させるための中国的作法なのだ……。▼ これらの見解には、近年、韓国ですすむ歴史の見直しとも重なっていて、目の覚めるような思いさえさせられる人が多いのではないだろうか。日中国交回復以前、中国側は政経不可分、日本側は政経分離を原則にしていたものの、政経分離の交流など「長崎国旗事件」でもろくも崩れてしまった………安倍晋三首相候補の対中外交が失敗におわることは、どうやら歴史的にみても明らかのようだ。また、ニクソンやキッシンジャーは、米軍の撤退にともなう「日本軍国主義復活」を懸念する周恩来に、「日米安保ビンのフタ」論による日本「封じ込め」を確約しただけではない。周もキッシンジャーも、「日本=島国集団」論で意気投合していたことなど、興味深い内容が盛りだくさん。とくに、日華条約は「台湾が範囲」と定めてあるため、日中戦争の終戦処理は終わっていない。村山談話は談話であって、「立法措置」ではない、という批判もあるらしい。「72年体制」を軽々しく変えることを主張することが、日本にとってどれほど不利益か、他にも中国共産党が、民族主義で権力を奪い取った政権といった常識に類することが、実に適切にまとめられていていて心地よい。▼ これまで日本は、戦後和解の枠組の精神にもっとも忠実だった中国が提示した枠組の上で、何も考えずに「ただのり」してきたことだけは間違いない。卓抜な和解枠組であった「72年体制」を、最大の受益国でありながら否定する、日本右翼の愚かしさ。おまけに靖国を肯定して、台湾独立まで介入しようとするありさま。それでいて、なお「日中関係が不安定化なのは、中国側の責任である」などという妄言は、まったく通用しないだろう。「国益」をかかげて主張するならば、当然、日本側自ら、その責任について指弾され批判されることは、甘受せねばなるまい。中国で湧きあがる毛沢東・周恩来「2分法」批判。それに付和雷同するかのように、「72年体制」を否定するなら、いかなる和解枠組を新たに提示できるのか。▼ 「美しくない」「学歴詐称男」安倍晋三首相には、途方もない宿題が、求められていることだけは確かであろう。日中と靖国問題を考えるなら、ぜひお買い求めいただきたい新書になっています。評価 ★★★★価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 24, 2006
コメント(1)
-

★ 靖国神社参拝騒動が隠蔽する、「卑怯モノ」化する日本
▼ 小泉首相の靖国神社参拝が15日行われ、余震が続いている。読売新聞によると、首相の靖国参拝「支持」53%とのことらしい。▼ ところで、このブログを読む貴方は、以下の内閣府調査について、どのように思うだろうか。この調査は、朝日新聞8月6日朝刊の日曜版にのっていたもので、世界同時調査らしい。▼ 「戦争が起きたら国のために戦うか?」 中国 はい 89.9% いいえ 3.1% イスラエル はい 75.1% いいえ 18.3% 韓国 はい 74.4% いいえ 25.3% 米国 はい 63.3% いいえ 25.5% イタリア はい 51.8% いいえ 34.4% ドイツ はい 33.3% いいえ 42.3% 日本 はい 15.6% いいえ 46.7%▼ 総じて、侵略を受けた国が高い(ベトナムは中国よりも高い)。そして、第二次大戦で、枢軸国側になった国がとりわけ低い。朝日の特集では、「日本は敗戦で付箋を誓った。この結果を『情けない』という必要はないと思う」という、暖かい言葉で結んでいる。しかし、この調査は、前掲の「靖国神社参拝賛成派」が53%もいる、という調査と重ね合わせると、俄然、その意味がかわってくるだろう。なんと、「小泉靖国参拝」賛成派の「3人中2人」、ヘタすると「6人中5人」(なぜなら、参拝反対派にも国のために戦おうとする人はいるはずだから)が、「国のために戦わない」連中だったのだ!!!▼ かなりショックな話ではないか。いったい、何のために、彼らは死んだのだろう。そもそも靖国神社は、国家が責任を持って、国家のために戦争によって死んだ人を祭る神社(BY 麻生外相)ではなかったのか。靖国神社という「国家のための死」を顕彰する神社へ、国家の指導者が参拝することに賛意を示しながら、国家のために戦おうとは、まったく思わない人間。そんな人間が、最低で「3人中2人」、最高だと「6人中5人」までいることを示す、内閣府調査と読売新聞調査なのである。「自分の代わりに他人が死んでくれ」「自分は死にたくないけど、他人が死んでくれるならそれを顕彰してあげよう」。そんな人間が、日本ではかなりの割合で増殖しているみたいなのだ。▼ 「日本は右傾化している!」「いや、普通の国のあり方に戻っているだけだ!」▼ このいずれも、私は間違っていると思う。日本は右傾化してはいないし、普通の国にもなっていない。ただ単に、日本人は、どんどん卑劣になっているだけにすぎない。耐震偽装事件に始まり、ライブドア・村上ファンドなどにいたるまで、法の網をかいくぐって稼ごうとする人々の増殖。「勝ち組」「負け組」など、セチガライ雰囲気の瀰漫。そんな傾向と、軌を一にするかのように増える、ナショナリズム現象。どうしようもなく、卑劣な人間だからこそ、「国家」の観念にすがるとしか言いようがない事態の出現。国家のために死んだ人を思うことで、卑劣な自己を直視せず、隠蔽しているだけにすぎない。まこと、国家という遮蔽幕は、真実を見えにくくするものである。▼ 今年、そんな連中が、8月15日、靖国神社に25万人も集ったという。昨年より5万人も多いのだとか。あまつさえ、靖国神社反対派との間で、衝突さえ起きたらしい。むろん、リアルに「国家のために戦う」ことを実践しているはずの自衛官が、当直勤務を休んで、「靖国の英霊」の前に集うことなど、考えられもしないだろう。靖国神社参拝者のほとんどは、「国家のために戦う」ことを口先では言うものの、実際「実践に移す」段階になると、ためらって何もしない連中にすぎない。靖国参拝右翼が、「国家のために戦う」かわりに行えることなど、「チマチョゴリを切り裂くこと」「靖国参拝反対派と喧嘩すること」ぐらいなのだ。なんというか、情けないお話である。▼ それを思えば、加藤紘一・元自民党幹事長の実家に放火した右翼は、なんと清清しかったことだろう!! 毎日新聞のコラムでは、瀰漫するナショナリズムとこの右翼に対して、事件後、右翼陣営から「文化人らが過激な言辞を競い合うため、右翼は体を張るしかないと思い詰めている」といった声が出たなどと、「過激な言辞」と「行動」を分けて、前者が後者を生み落としたという議論を展開している。そのためなのか、靖国参拝賛成派のブログなどでは、「彼らと自分たちは違う」と、右側の人々が躍起になって、言論の自由を否定した「放火右翼」の行動の批判さえ始めているみたいだ。ちょっとみると、マトモな議論のように思えなくもない。▼ だが、それは違う。毎日新聞の社説も、過激行動を批判する「靖国参拝賛成派」の右翼も、常識に囚われるあまり、誤認しているのではないか? 両者とも、「放火した右翼」を批判することで、「放火した右翼」こそ、主張と実践を一致させた、倫理的存在であることを見落としてはいないか? そして、「放火した右翼」を口先では批判する「靖国参拝賛成の右派」こそ、主張と実践を一致させず、他人には「国家」を強調・強制しながら、自分はその言説に隠れて、こっそり「国家のために戦わない」ことを永続化しようともくろむ、もっとも非倫理的存在であることを忘れてしまってはいないか?? 「放火した右翼」と「過激な言論右翼」の2分法、ならびに「放火した右翼」批判は、過激なナショナリズム言説こそ、「国家のために戦わない」アリバイ・免罪符を提供していることを巧みに隠蔽しているが故に、弾劾されなければならないのである。 ▼ 良く考えてもみよう。 「放火右翼」は、テロリストが守らなければならない、最低限の倫理的基準「他人の命を奪う行動にでる場合は、自己の命もまた奪わなければならない」を実践しているではないか。人を殺せるような所業をおこなう以上、自らも殺さねばならない。放火した直後に、割腹自殺しようとしたこと。この倫理性だけは、評価できる。ところが、どうだろう。過激なナショナリズムとやらによって、「靖国神社参拝」に賛成している人々は、そして「放火右翼」を批判する人々は、倫理性が存在するだろうか。「国家」という崇高なメッキが剥がれてしまえば、靖国神社に祭られた人々は、「人殺し」(そして「人殺され」の側面をもつ)でしかない。国家のため、「人殺し」(「人殺され」)になるのが嫌な奴が、そんな人の死を顕彰(または追悼)しようとすること自体、お笑い草ではないか。そして、「国家のために戦う」と口では言いながら、自衛官に志願もしないような人間も、倫理性のカケラも存在していまい。▼ かつて、靖国神社どころか国立追悼施設さえ批判する高橋哲哉の『国家と犠牲』(NHK出版)のレビューで、『「英霊」ではなく、「靖国の論理」の墓標こそ、靖国神社ではないのか』『高橋哲哉が提起すべきだったのは、靖国の廃棄ではなく、靖国シンパたちが「靖国の論理」を正確・忠実・過激・徹底的に実践することだったのではないか』と書いた。この気持ちは、8月15日をすぎて、ますます強くなっている。靖国問題とは、断じて中韓の外交問題ではない。靖国神社参拝賛成派の急増は、日本人の卑怯モノ化でしかない。参拝賛成派でさえ「国家のために戦いたくない」からこそ、靖国神社が必要になるのだ。▼ 「靖国神社の論理」の一刻も早い、靖国シンパによる実践。これこそ、逆説的ながら、靖国神社を無用の長物にさせ、靖国問題の解決につながるだろう。右派の方々には、靖国神社参拝賛成にとどまることなく、徹底的な実践をお願いしたい。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 19, 2006
コメント(17)
-
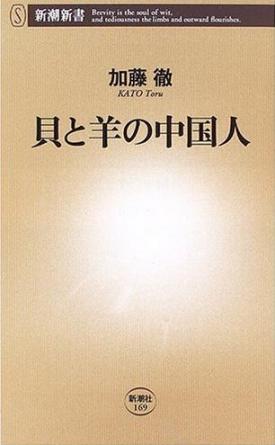
★ 加藤 徹 『貝と羊の中国人』 新潮新書 (新刊)
▼ たいへん痛快な中国人論である。安くて、面白くて、おまけに間違っていない。この簡単に見えるようなことが、どれくらい難しいことか。▼ 対立を煽るでもなく、幻想に酔いしれることもなく、たんたんと中国文化を語る。なんとも難しいことをスイスイとやってのける怪著。高校生や中学生の方は、夏休みの宿題「読書感想文」にこの本を取りあげてみてはいかがだろう。むろん、大学生・社会人にも、何よりもお勧めしたい一冊である。▼ 中国人は、<「貝」=「殷人」=農耕民族=多神教的=物財重視=道教的>と、<「羊」=周人=遊牧民族=一神教的=イデオロギー重視=儒教>の、この2つの気質の違う集団が現代にも引き継がれ、中国人は貝と羊の2つの顔を徹底的に使い分けているのだという。意欲的というよりも、暴走気味。弥生人と縄文人で、現代日本を論じようとするようなもの。本来なら、バカか!それでは何も言ってないことと同じだろうが!と叩きつけたくなるはずなんだが、まったくもって、飽きさせることのない、優れたエッセイ、入門書に仕上がっているのである。▼ 適当に、本書の内容を見つくろって、ご紹介しよう。神社やお寺の境内に、御神籤やお守りを売って商売するのは、中国の影響医・食・人的ネットワークを駆使しての多彩な流浪ノウハウをもつ中国人12世紀、疫病を恐れたからか、急に肉や魚の刺身を食べなくなった中国人我々は中国人ではない、「華人」だ!と主張する、東南アジアなどの華僑たち死刑囚から臓器抜き取りを容認する、死を特別視しない中国人「功」と「徳」を分け、「徳」を評価して「功」は評価しない中国人靖国問題も、社会主義市場経済も、外見に表すことに拘る「体用論」の影響物や知的所有権などに対して、縄張り感覚が大らかな、中国人「大づかみ式合理主義」中国と「分析的合理主義」欧米感覚表現はともかく、時空・数字・料理…とかく「外向的」な言語である中国語無制限な資源は、人と土しかなく、人管理=「政治的文明」を余儀なくされた中国4世紀以降純粋な漢民族統一王朝がない?中国(趙匡胤・トルコ?永楽・高麗)周辺出身者の忠誠心を利用するのが巧みな、歴代為政者中国2千年の黒幕、「士大夫階級」支配を支えた、儒教・科挙・漢字歴史に美学をもとめ、京劇的「善玉」「悪玉」の区分が厳しい、中国人現代は、フビライ、康煕帝期に次ぐ3度目の「万里の長城のくびき」からの解放質実剛健・軍事・政治に優れる「北」と、才気煥発・文化・経済に優れる「南」アヘン戦争まで文明間戦争を経験したことのない中華帝国のアキレス腱とは?チベット・ウイグル族の独立をさまたげる、ソ連崩壊のトラウマ日本をのぞけば、地域呼称が存在せず、政権名しかない、東北アジア地域地域呼称のない不便さを解消するため発明された呼称、「支那」「震旦」近代以降、流行した佐藤信淵『混同秘策』を元に中国人が捏造した田中上奏文ホンネとタテマエ、日本人と中国人は似ている部分も多い現代中国は昭和初期日本という補助線を引くと分かりやすい東アジアには「交流」はない、一方通行の「直流」のみだった!!!!……▼ どうです?なかなか興味深い内容ではありませんか?▼ 西洋文明とは違い、競合的協力者を持てなかった、中国文明の悲劇が綴られていて、なかなか興味深い。会津藩士の若松コロニーが全滅したにも関わらず、太平天国の残党たちは、新大陸に渡って過酷な鉄道建設に携わりながら、その流浪の知恵で生き残ってしまったという。流浪の英雄は、中国にいても、日本にはいない。「国名」の付け方でさえ、日中両国は、両極端・正反対の国であるという。理念名称のみの中国と、地域名称のみにして、立国理念を付けることを拒否したアジア唯一の国、日本。似ているようでまったく違う、「和魂洋才」と「中体西用」。他方、周辺出身者の忠誠心を引き出すのがヘタだった日本という指摘は、なかなか胸を痛めさせられるものがあった。反乱の根拠にもなった創世記アダム神話に対して、紐を泥水に浸してぶんぶん飛沫をとばして泥から人間を粗製濫造した創世神話をもつ中国の比較は、中国では命が羽毛のように軽いことを見れば見るほど、考えさせられてしまう。「神武天皇」に対抗して発見・創出された、「黄帝」「檀君」と「黄帝紀元」「檀君紀元」。国土の「中央」においてはならない、近現代の大陸国家の首都………などなど、比較を通した幅広い視点は、たいへん啓蒙させられる。▼ むろん、周辺のさまざまな分野も、手広く扱われていて、たいへん楽しい。華人たちが1777年、ボルネオに作った「蘭芳公司」は、世界最初の民主的共和国だったらしい。かつて清朝のときは、「唐人」と名のった様に(ただし「唐人」は、日本では朝鮮人~西洋人も含まれる)、こうした移民たちは、祖国に対して屈折した思いを抱いているという。ただ、中国政府もさるもので、出国したい優秀な人間は留学生としてどしどし送り出した。短期的に故郷への送金で潤っただけでなく、長期的に中国人のプレゼンスは向上。今では、中国の経済発展で、かつての留学生の帰還が相次ぎ、技術・情報をどんどん持ち帰り、「産業スパイ」呼ばわりされているという。 「坊主めくりのできない国」中国という喩えには、ニンマリとさせられてしまうだろう。毛沢東のみが「大づかみ式合理主義」で農民にも分かる言葉で社会主義を語ることができた反面、たった一人を批判したことで、3億も人口を増やしてしまったこと…………なによりも劉備と曹操の評価が分かれたのは、「侠」に徹したモノと、「侠」にも「士」にも徹しきれなかったものの差なのである、という指摘はたいへん面白かった。▼ むろん、いい加減な議論も多い。ユダヤ教徒を指す現代のユダヤ人の人口と、ダビデ王統治下のユダヤ王国の人口を比較して、「3倍しか増えていないのは、激しい迫害のため」というのは、お笑いにしか思えない。また、人口規模500万=王国の法則って、そんなのあるのかね? 紙と絹は、資源節約をしたい事情から生まれたもの、と断定されているものの、絹については説明がなくて途方にくれてしまう。商業が政治に対抗しうるパワーであった西洋と、政治に従属した中国というありきたりな比較も、「港市国家」「(ギリシャ)ポリス」の様に、商業そのものが政治の統制下にあった歴史の方が、人類史では一般的であることが忘れられている。また、「支那」という呼称の問題について、「嫌がらせ」で「支那」を使う日本人右翼に対して、的確な例をあげながらタシなめていて、たいへん好感がもてる。ただ、日本における「中国」呼称の定着は、「中国」+「満州」=「支那」という、満州を含まない地域名称という側面が強かったことが触れられても良かったのではないか?。 また、明代後期以降の特殊性を考慮することなく、皇帝と士大夫階級の寒々とした関係、として崇禎帝の最後を例としてあげるのは、読者をミスリードさせるようにも思える。 ▼ このような数々の欠点はあるものの、それでもお奨めしたい。そんなこと、些細に思える位、この本は魅力的な本なのだ。柔らかい文体で、縦横無尽に中国を語り尽くすエッセイ。『国家の品格』より売れていないこと自体、日本の恥。『国家の品格』をお読みになった人は、ただちに本屋に急行してもらいたい。評価 ★★★☆価格: ¥756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸 とはいえ驚かされたのが、田仲一成の洞察力である………え?なんのことか分からない? 本書を読んで確認してほしい。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 14, 2006
コメント(1)
-
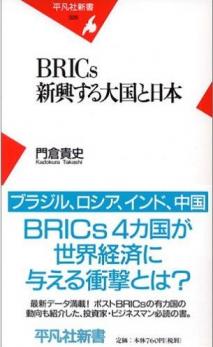
★ 門倉 貴史 『BRICs 新興する大国と日本』 平凡社新書 (新刊)
▼ 超大国は生まれるのか。今、話題になっている、次なる経済大国、ブラジル・ロシア・インド・中国。この4カ国の経済を2時間で理解できるという、かなりお得な新書が出版されています。ご興味のある方は、ぜひ、お買い求めください。▼ 内容は以下の通り。第1章 なぜBRICsが注目されているのか?第2章 台頭する中産階級第3章 資源獲得競争第4章 BRICsの軍事力第5章 国際会議で影響力を増すBRICs第6章 BRICsと日本の関係第7章 ポストBRICsとして注目を浴びる国々▼ 近年BRICsが注目されているのは、天然資源と人口(生産年齢)の豊富さ、積極的な外資導入、購買力を持った中産階級の登場によって、豊かさでは先進国の水準にはかなわないものの、30年後にはG7を凌駕する経済規模になるためらしい。インドでも、対内直接投資の拡大によって、輸出や国内固定資本形成が促され、一人あたりのGNPの拡大が生じた。ただ、先進諸国よりも貧富の差が激しく、富裕層・ニューリッチは、欧米の比ではない。パソコン消費などにみられる、中産階級によるマクロ消費押し上げ効果は、限界が見える恐れがあるという。しかも、経済統計には問題が。インド・ロシアでも、経済統計は税逃れのため、付加価値の過少申告がなされやすい。ただ現在の資源価格高騰は、インフレ圧力を強め、成長の阻害要因にもなりはじめている。二酸化炭素排出量の激増は、地球環境問題を招いておきながら、ロシア以外は京都議定書に入っていない。確実に地位を低下させているG7に、あらためてBRICs諸国が加わる日は近いという。▼ 以下、国別にまとめてみよう。▼ ブラジルは、左派のルーラ大統領再選可能かどうかに対して、懸念材料があり「為替リスク」も抱えこんでいるものの、一次産品輸出が好調。1%の富裕層が5割の富を握る国で、富裕層の88%が白人であるという。パソコンの普及率は、2004年には、ロシアとならんで1割をこえ、中国の2倍、インドの5倍の水準だとか。ブラジルは、新規油田開発が盛んで、98年には外資系企業に参入が認められたこともあって、ここ25年の間に推定埋蔵量は8・5倍に膨れあがり、アルジェリアを抜きそうらしい。自給率も9割。しかもフレックス車(アルコール燃料)が普及していて、原油消費量が伸びていない利点があるという。意外なことにブラジルは、世界四位の航空機会社エンブラエルをかかえている武器輸出国。ところが、日本とブラジルの経済関係は、極めて見劣りがする現状にあるらしい。日本の対ブラジル・インドの貿易比率は、0.6%というお粗末さ。ブラジル第2位の貿易相手国に躍り出た中国。資源確保のためにも、中韓より先んじて、ブラジルとのFTA締結を急ぐべきだと提言されている。▼ ロシアは、先進国の矜持もあって、このBRICsの名称を嫌っているらしい。基本的に世界1位の産出量(2004年)を誇る石油価格に左右される不安定な経済構造であるものの、6%前後の成長が可能。ただ、マフィアが4割の経済活動を配下に納め、経済活動の7割が何らかの形で結びついているなど、リスクとして「治安面」の問題が大きい。人口の2割の富裕・ニューリッチ層は、2大都市に集中。輸出の6割が、石油関連商品。そのため、インフラ・鉄道整備が、急ピッチで進められているらしい。世界は、化石燃料の天然ガス化という流れ。世界生産量の2割、埋蔵量25%をもつロシアの天然ガスの日本への輸出は、敷設コストの高さから日本に大口需要者が現れない内に、「サハリン1」の利権は、中国に取られる形勢らしい。世界最大の天然ガス企業・ガスプロムは、欧米メジャー級の強力なエネルギー企業に成長。ただ近年、外資規制の強化にのりだしており、投資の落込みによる経済への悪影響が懸念されるらしい。プーチン政権は、武器輸出も強化。中国・インドに大量売り込みを図っている。一方日ロ経済関係は、ロシアWTO未加盟ということもあって、近い割には小さい(1%)が、資源価格高騰と加入を間近に控えて、近年急速に伸びているという。▼ インド経済は、印パ紛争の再燃や、頻発する労働争議、インフラの未整備、マンモハン・シン政権が共産党の圧力に耐え経済開放政策を続けられるか、というリスクをかかえるものの、もっとも成長が期待できる国であるらしい。民主国家であり、富裕層は、財閥経営者が多いという。ニューリッチ層は、7.3%。とはいえインドのカースト制は、貧富の差を拡大させており、経済発展の恩恵は、バラモン・クシャトリア・バイシャ層にしか行き渡っていない。下級カースト・指定カーストを中心とした貧困層の比率は、ネパール・バングラデッシュと、依然同じレベルなのだとか。富裕化の進展も、インドのみ飼料用作物需要を伸ばしていない。原油は輸入に依存。依存率は7割、使用量1億2000万トン。インド石油天然ガス公社は、世界各地に石油資源をもとめ、スーダン・リビア・ロシア・キューバ・ベトナムで開発を目指し、近年では中国とは資源外交でも歩み寄りを見せているという。インドの軍拡は、武器輸入途上国第1位にもあらわれている。仮想的国「中国」とパ3度の印パ紛争をおこした核保有国パキスタンが連携していては、インドの核廃棄はありえない。政治・経済両面でアメリカ・インドの幅広い提携がおこなわれている反面、非常に遅れている日印関係。日本は、日系企業の対インド投資にともなう、中長期的な貿易拡大にまかせるだけではいけない。インドからのサービス輸入も日本側輸出に均衡するように増やさねばならない。そのためにも、ソフトウェア・サービス取引のおける源泉課税問題を解決しなければならないという。▼ 中国は、現在BRICs諸国の中で、最も高い経済成長率を誇っている。経済成長率は9%以上。目立ったリスクは、鳥インフルエンザと「法令・運用の不透明性」。2005年12月の統計大改訂で、2004年末のGNPは、16.8%も上方修正された。富裕層は、不動産・自動車・海外旅行といったものに走るものの、都市部では耐久消費財消費が一巡。後は、農村部にどれだけ売れるのか、にかかっているのだという。資源問題は、深刻のひと言。年間使用量、現在3億2000万トン。2020年の石油依存率7割の予測。推定埋蔵量7・5年分しかない石油は、近年1ヶ月を目標とした石油備蓄政策を始めているらしい。インドと激しい石油争奪戦は、資金力の差で連戦連勝。中国人民解放軍は、装備面でも近代化がすすみ、台湾海峡ではすでに台湾に対して圧倒的優位を築きつつあるという。▼ ポスト4カ国としては、南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、メキシコ、トルコ、中東欧三カ国(ポーランド、チェコ、ハンガリー)、インドネシア、ベトナムなのだとか。ベトナムは、政治不安もなく、中国沿海部における労賃の高騰を受けて、良質かつ均質な労働力を手配できる魅力から、生産基地を移転する動きが活発化しているという。南アフリカは、豊富な天然資源とW杯開催もあって、5%成長を続け黒人中産階級も形成されつつあるが、通貨ラントの値上がりと深刻な失業率に喘いでいるという。ナイジェリアは、インドの主要石油供給基地となりつつあるが、反政府組織との深刻な政情不安にあるらしい。トルコもインフレ抑制に成功。天然資源に恵まれないものの人口増加も激しく、高い成長率にあるのだとか。東欧では、ポーランドがEU向け生産基地の地位にあるものの、2005年10月に誕生した現政権は、民族主義的で投資には慎重さがもとめられるという。▼ 楽しめた点としては、筆者の手際のいい分析手法。経済の実態に比例して変動する電力需要量の動向で、経済成長率の統計が正しいかをチェックすると、中国では20世紀には「成長率>電力」と過大申告気味だったのに対して、21世紀以降「電力>成長率」で、かなり乖離しているのだとか。ロシアの株価指数が原油価格と連動している、という指摘も面白い。他にも豆知識も、豊富。天然ガスがもてはやされているのは、環境保護の観点でクリーンで効率の良い燃料である上に、各地に点在しているので中東依存の必要がないためだという。中国・ロシアの乳製品需要激増が、世界のチーズ価格を押し上げる。2006年1月下旬のダボス会議(世界経済フォーラム年次会合)でも、テーマは「インドと中国」の台頭。244もある分科会の内、日本絡みは1つしか開かれなかったというから、その存在感の希薄さには恐れ入る。▼ ただ、中国経済については、他の新書でも色々語られている。この本では、初心者向けの入門書の域をこえていない。インドも、『週刊東洋経済』のインド特集と、いい勝負でしかないでしょう。ところが、ブラジル・ロシアは、大変面白かった………これって、評者の知識量の差に、由来しているのは、あまりにも明らか。つまり、これは4カ国の個人投資家・機関投資家になるための、入門書というのが一番実態にちかい。しかも、当該国経済についての詳しい解説・説明をぬきにした、発展可能性のみにしぼったもの。分かりやすくいえば、この本の使い道は、あなたが海外に株式・ファンド投資をおこなう際、どの国を選ぶか、目鼻をつけるために使うものでしかありえない。てか使い道がない。当該地域の詳しい経済状況を知りたければ、別の新書・専門書を探すべき。断じて、こんな本を読んではいけない。あくまで、次の投資先はどこがいいだろうか……につかう投資案内であります。その意味で、たいへん微妙。▼ インドや中国よりもずっと経済水準の高い、南アフリカ・インドネシアがなぜ、ポストBRICsなのか。アルゼンチンとかパキスタン、イランとかは、入れなくていいの? 当然、こんな深刻な違和感を感じない訳にはいかないだろう。むろん、投資案内として近年推奨される諸国を解説するという本書の性格からすれば、そうならない方が可笑しい。 そんな疑問を感じたものの、割合面白かったのも事実。▼ とりあえず、4カ国知らない人には星3つ半。4カ国とも知ってるよ、という人には、星2つ半。真ん中をとって3つと採点した。ご参考にしてください。評価 ★★★価格: ¥798 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 10, 2006
コメント(0)
-

★ 靖国神社参拝における日経新聞「富田メモ」をめぐって:保阪正康 毎日新聞7月28日
▼ ネット史料として、毎日新聞にのった、保阪正康の議論をあげておきます。アホなことをいう奴のブログ・掲示板には、コピペして貼ってあげてください。なお秦郁彦氏の論説はこちらにあります。● 宮司の歴史観に怒り 保阪 正康 (作家)健康に不安をもった天皇の「公式」発言A級戦犯合祀への不満を追認するもの 富田朝彦元宮内庁長官の在任時のメモが発見され、そこには昭和天皇の靖国神社への不満が直截に語られていることが明らかになった。各メディアでもこの富田メモについて多様な視点から論じられているが、しかし何かが欠けているとの感が否めない。 このメモの靖国神社についての部分は字数にしてわずか125字程度だが、きわめて歴史的な意味をもっている。昭和天皇の個人的直話が明らかにされるのは逝去後の「昭和天皇独白録」以来のことと思われるが、今回のこの直話はいささかの推測を重ねれば、昭和天皇自身が自らの健康に不安をもち、これだけは語っておきたいとの強い意志があったことが窺われるのである。しかも昭和天皇は側近に対してもその職務に応じて、話す内容を変えるのだが、宮内庁長官にその意思を伝えたことはこれは公式のものであり、いずれ明らかになったとしてもかまわないという考えがあったとさえ思える。 一部の論者がこの富田メモについて、その信憑性を疑っているが、この125字が伝えている歴史的事実を検証すると、そういう疑い自体があまりにも史実に鈍感だということがわかる。私の見るところ、この富田メモが伝えている内容はすでに知られていることであり、ただひとつ欠けていたのは、昭和天皇自身のそれを裏づける史料があるかないかということだった。今回のこのメモはすでに語られていることが追認されたとの意味をもっている。 昭和天皇は1975年11月に靖国神社の参拝に赴いてから以後は一度も足をはこんでいない。松平永芳が靖国神社の宮司に就任して、すぐにA級戦犯を合祀したのは、78年の例大祭の折である。昭和天皇が靖国神社参拝に行かなくなったのはこのことに不快感をもっていたからだと考えられてきた。 そのことを侍従(その後、侍従長)でもあった徳川義寛氏が、「侍従長の遺言」(97年刊)で裏づけた。昭和62(1987)年8月15日の御製として「この年の この日にもまた 靖国の みやしろのことに うれいはふかし」があるが、これは合祀への不満、それに伴う混乱を憂えていたと書いている。 さらにこの富田メモでの昭和天皇の怒りは松平宮司の歴史観にもあるように思う。というのは、松平氏は戦犯合祀について宮司職をはなれたあとにある講演で、日本の戦争状態は1952年4月28日までのアメリカを中心とする連合国の占領下でも続いていたと自身の歴史観を披露した。したがってこの間のA級戦犯の死者は(絞首刑の7人以外の7人)も戦死扱いだというのだ。東京裁判は戦時下の不当な軍事裁判ということになる。この歪んだ戦争間に、昭和天皇は怒りをもっていたことがわかる。それが「松平(注・永芳氏の父慶民氏。天皇側近)は 平和に強い考えがあったと思うのに 親の心子知らずと思っている」という表現である。 さらに最後の「それが私の心だ」は、天皇の怒りは頂点に達しているとの意味である。私はこの最後に記されている7文字を読みながら、天皇が2・26事件時の本庄繁侍従武官長を叱りつけた強い表現をなんども思い浮かべた。▼ 瑣末な出来事にこだわって、描き出す全体像がかなり陳腐だなあ、という印象を保阪正康氏の昭和史に関する著作を読むたびに感じていたのですが、今回はかなりまともな歴史研究者の一員という感じです。おいらは、靖国神社・国立追悼施設に反対どころか、「死者を追悼することさえ必要ない」「悲しむな、死は必然なのだ」な~んて考えている人間ですが、そこに安らぎを感じる方々を本格的に批判したいとは思わない。肉親の死のつらさが分からない人間ではいたくない。私には資格がない。ただ、それをテコにして、メモはニセモノだ~って、根拠も乏しく逆ギレされてもなあ………。それは違うだろう、と思うんですよ。▼ 描き出す全体像がでかいだけの研究者は、このような時にはお呼びではないのかもしれません。保阪正康氏←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 6, 2006
コメント(10)
-
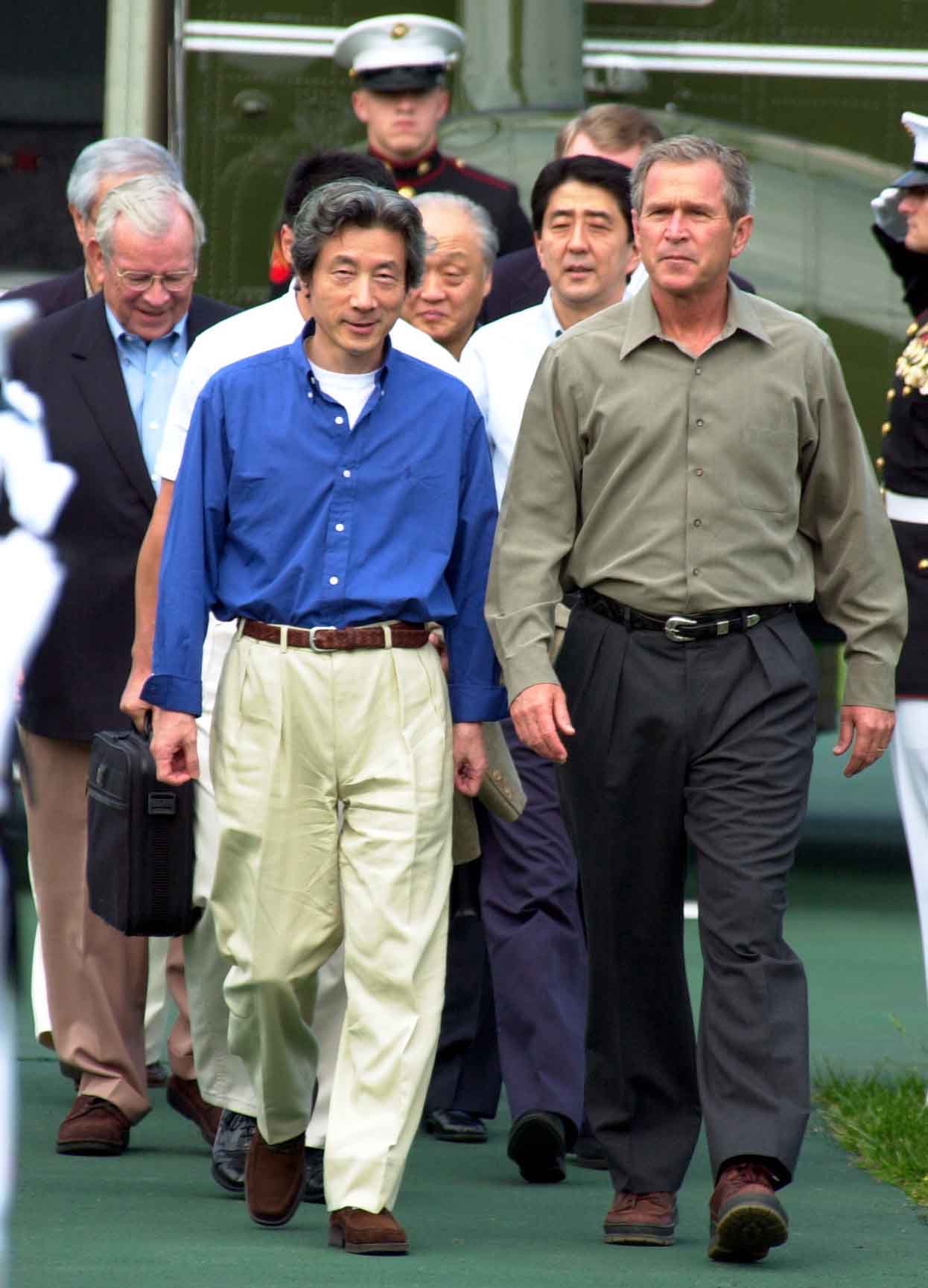
★ 富田メモ & 「美しい国」の美しくない安倍晋三
▼ なんでも、 安倍晋三官房長官が、4月15日、周囲にバレないようにこっそりと靖国神社に参拝していたらしい。わざわざリーク先は、安倍晋三周辺というのが笑える。個人の思想信条なら、堂々と参拝すればよかろうに、あいかわらず肝っ玉小さい奴だネ。無い知恵絞って編み出した参拝方法とは、コソコソ報道陣に見つからないように、靖国神社参拝をおこなうことだったらしい。コソ泥も真っ青である。▼ 世にいわれる、「○○○主義者」といわれるような人たちは、信じる思想を選び実践する人たちではない。逆である。思想に選ばれた人たち、それが「○○○主義者」なのだ。共産主義者、自由主義者、フェミニスト、ファシスト、イスラム原理主義者…彼らは、みな思想に選ばれた人たちなのであって、その逆では断じてない。だからこそ、実践が要求されている。思想に選ばれた人たちだからこそ、己の肉体をその思想に差し出すことを許すのだ。世界革命、「不滅の自由」、男性支配打破、ユダヤ支配打倒、イスラム革命…数々の観念・理想に捧げられたことで生まれた、まがまがしい生贄たちの群れ。思想は、中途半端な人たちなど相手にしない。▼ 安倍晋三は、『美しい国へ』(文春新書)の執筆者らしい。安倍晋三は、『美しい国へ』あこがれているのだろう。必要なのだろう。しかし、その『美しい国』は、果たして安倍晋三を必要としているのだろうか。安倍晋三は、その理想を実現するために、わが身を差し出しているのだろうか。実践しているのだろうか。彼は何もしていない。そもそも、思想信条で参拝といいながら、記者にも隠れてコソコソ参拝しているのだ。彼にとって『美しい国』とは、自分が思うような美しさを他人に強制することで果たされるものなのだろう。下品にして卑劣な心性。『美しい国』には、下品な安倍晋三は必要あるまい。美しくない「北朝鮮」にでも、移住されたら如何か。むろん、デブで美しくない福田和也・宮崎哲哉ともども処刑してもよい。「皇国に下品な男は不要だ」(伊武雅刃の声で)▼ さて、冗談はさておき。富田宮内庁長官のメモのお話である。週刊新潮が、「富田メモはニセモノだ!」と力説するHP・ブログをソースに、ほとんどまるまる盗作・引用の記事を作っていて驚いた。いいのか?アレ。まあ、右翼さんは、日経新聞に「メモが天皇の発言とする根拠はなんだ!」「メモを検証しろ!」「誤報だ!」と騒いでいるようだ。そりゃあ、根拠は本質直観に決まっとるだろうに。一々、日経に突っ込む前に考えろよ。流れはこんな感じか。 「メモ帳全体を読んで、天皇の言葉使いや天皇しか知らない話がい~っぱい出てきた → 天皇の談話が記されたメモだ → 該当部分も天皇に違いない(本質直観) → どうやらそんなに違わないらしい(検証) 」。実際秦も、公開は無理といってるくらいのものなんだから…………▼ な~んて思っていたら、日経新聞が昨日(8月2日)から富田メモ特集である。張り切りすぎて怖い。とりあえず、1については写真もあるし、電子化されてもいるので、2をあげておきます。● 昭和天皇との10年 富田メモから 2 長官就任「男なら諾」気さくさ、包容力に敬愛の念 富田朝彦氏は1974年に内閣調査室長から宮内庁次長に就任した。次長時代も含めると14年間、昭和天皇に仕えたことになる。以後、これほど長く天皇に仕えた長官はいない。 78年に長官に就任した当初は、約25年間在任し名物長官といわれた前任の宇佐美毅氏と比較されることもあった。前年の77年の日記には宇佐美氏から長官就任を打診され、ためらう気持ちがつづられている。 「宇佐美さんより話を聞く。私未(いま)だその任に到らずと辞すもいかなるか。宮内庁幹部に関する人事問題を漏らさる。未だ咲きのこと。考えるべきこと思いを擬すべきこと多からん。家人に何も語らず。何かを覚らせんとも思うが、未だ固まらず」(2月28日) 「宇佐美さんに心境の一端を申し、宇佐美さんにすすめられる判断をお聞きした。『幾度かお願いしたように心に決めていただきたい。次長(富田)に宮内庁に来て戴(いただ)いたときから考えていた。また来てもらうについては色々の人に意見を聞いた』」(5月14日) 富田氏は78年5月に次長から長官に就任する。前月の4月16日付の日記には「自分はその地位(長官)を何ら求めたことはない。今回予想されることは2年前からの話。しかし男ならそう言われて諾と言わざるをえない。一番苦しい時代と考えている」と重責への覚悟を述べている。 富田氏の親族は、警察官僚出身の富田氏にとって、「宮中の諸事」にはとまどいも多かったと話す。しかし、昭和天皇に接していくうちに敬愛の念が深まり、長官職の責務への自負心も強まっていったという。 79年1月14日付の日記では、天皇が老朽化した長官公邸の修理を勧め、それに富田氏が感動する場面がある。「古いけれど風格のある建物ですから、自然と共にいるように自分を鍛えるよう努めます旨申し上げる。“そうかい”と合点され立ち際に“長官大事にね”と2度も仰せがあった」。このころには天皇と深い信頼関係で結ばれていたことを感じさせる。 「警察庁長官の進講。陛下、誠に明晰(めいせき)に数ケのご質問あり。それには内心驚嘆せり」(85年7月3日付日記)と天皇の明晰さに驚かされる一方、気さくさと包容力に親愛の情が増していく様子もうかがえる。 「本年は至らぬこと多く恐縮しております、と申し上げたら、色々よくやってくれて満足していますと仰せがあり、更(さら)にそれでね長官と、また若干お話する。何か大海原に向かって晴れた地平線を見るごとき感を抱く」(82年12月28日付日記) 「陛下より卜部(侍従)を通じ、先日私が言ったのは誤りがあった。長官にとのお話。有難く、これだからと思う」(86年7月15日付日記) 昭和天皇晩年の87年、88年の富田氏の手帳を見ると、スケジュール欄には週2回程度「言上」(天皇への報告)という文字がある。その文字は他の項目と違い、丸く線で囲まれている。富田氏にとって最も重要な公務であると同時に、心待ちにしている特別な時間でも合ったのではないだろうか。▼ なんか木戸日記、本庄日記みたいな感じになりそうですねー。まずは日記の価値の高さ、天皇との心の交流で、「資料的価値」を強調する作戦のようです。楽しみですネー。えっと、保阪正康の評価をあげていなかったので、後であげておきます。▼ それでは。←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 4, 2006
コメント(3)
-
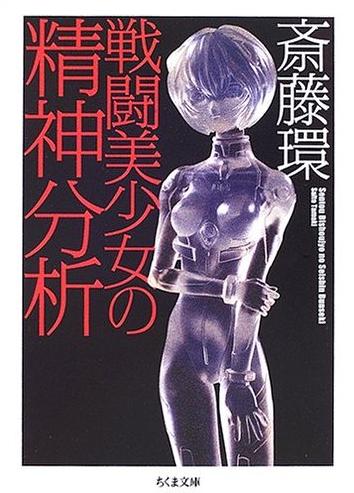
★ 斉藤環 『戦闘美少女の精神分析』 ちくま文庫(新刊) <2>
(承前)▼ 視覚的領域におけるメディア手段の多様化は、内容と形式の貧困化・単色化をもたらす。こうした画像情報の貧困化の頂点こそ、アニメ絵なのではないか。われわれの想像界に共有可能なコード系列の導入がおこなわれたことが、多型倒錯的な要素―――セクシャリティ―――の導入を招き、自律的欲望の対象の自立―――それも現実の性的対象の代替物ではない、現実という担保を必要としない「虚構」―――の前に「現実」が額づいてしまう、原因にあたるのではないのか。「虚構」「現実」の区分けが厳しく、「図像そのものが性的魅力を帯びるべきではない」西欧的文化。それに比べ、春画・ポルノコミックなどの隆盛は見られる日本では、「描かれたもの」が「リアリティ」をもつことが許されている。そうした虚構のリアリティを支えるものこそ―――この虚構の世界は、象徴的去勢を被らないが故の「去勢否認」に満ちた過剰な性的倒錯の空間であり、そこではハイ・コンテクストであるが故に「了解可能性の減衰」が生じてしまうので、その減衰に抵抗するには欲望を帯電させ続けなければならないのだ―――セクシャリティに他ならない。▼ 両性具有・変身・能動性・被動性が奇妙に混在する戦闘少女は、意味のレベルにおいては、複数の想像的現実として多様な「倒錯」を掻きたてながら、外傷が欠如した「ファリック・ガール」―――彼女たちの外傷(トラウマ)や復讐が作品内で主題化されることは決してない―――として、空虚なペニスに同一化した存在である。彼女は、ヒステリー化した存在であって、虚構の日本的空間にリアリティをもたらす欲望の結節点である。彼女たちは、トラウマによって、日常的リアルに汚染されることがない。われわれが、ヒステリーに魅了されるとき、エロス化された実体としての身体イメージから出発して、その深層にある外傷へと欲望が向けられる。一方「ファリック・ガール」に対して、「戦闘」という享楽に魅了され、エロスの魅力と混同されることで、萌えが成立するのだ……… ▼ 戦闘美少女ブームから、「今、女の子が元気である」という議論を導いてはならない。そのような議論は、「虚構=現実の模倣」を前提としているだけでも無効なのだが、主体の転移を要請する「もうひとつの現実」を忘れてしまっているが故に一貫して無効なのである……… まことに良くできた精神分析になっていることがよく分かるでしょう。 「おたく論」としては、斉藤環氏当人がオタクであることも手伝って、違和感のないものに仕上がっていてうれしい。『白蛇伝』の女性に憧れた過去を「虚構によって強いられた不本意な享楽」と捉え、アニメファンを嫌うようになった宮崎駿。ピグマリオン系戦闘美少女の系譜としてエヴァ以降のブームを捉えるのも、なかなか面白いものがあります。 「おたく史」にいたっては、オタクにはむしろ、物足りないといえるような手堅さが感じられるほど。なによりも、ラカン理論の解説がありがたい。想像界とは、イメージや「意味」や「体験」の領域のこと。 「空虚」であることで、欲望やエネルギーを媒介する女性のことをヒステリーとよぶ……… ご当人の意図とはかけ離れているとはいえ、「良く分かるラカン」といった趣きさえ感じられます。「解離した生」こそ倫理的である!!! そう主張して、自らのセクシャリティを利用しながら、「神経症者の生」を生き抜くことを提唱する姿は、たいへん共感できるものがあるのではないでしょうか。▼ ただ、『バフィー 恋する十字架』などをめぐって、海外での戦闘少女モノが紹介されているものの、過小評価されてしまい、行論の中で位置づけられていないのが気にかかってしまう。1990年代後半のアメリカにおいて、「戦闘美少女」というジャンルの台頭が述べられているものの、アメリカでのメディア環境とどのような関わりがあったのか、ほとんど示唆されることなく終わってしまっている。現代日本特有の環境の強調は、精神分析にはあるまじき「早すぎる歴史化」ではないのか。 また日本製の「ゲーム」について、ほとんど触れられていないのも、かなり減点する必要があるでしょう。とくに90年代以降は、加速度的にゲーム、とくにギャルゲーやエロゲーの増殖が見られた時期。ゲームを分類対象に入れないで、13類型がどれほど有効な分類なのか、いささか疑問に感じてしまう。▼ 何よりも、ラカン派精神分析固有の問題点としては、「戦闘美少年の精神分析」はどうしたのか、という問いかけをせざるをえないことにあろう。異常増殖が見られることは、戦闘美少女も戦闘美少年も変わらない。美少年たちもまた、美少年であることを止めることなく、戦いに赴くのではないか。そうなると、男性オタクが戦闘美少女を好むように、女性のオタクは戦闘美少年を好んでいるのだろうか。美少年のエロスとリアリティは、どのように結びつくのか。そもそも「女性は存在しない」のであるならば、女性の愛とは何か。たちまち浮かび上がるこれらの問題は、まったく解決の糸口が与えられない。ラカン派分析は、どうしても「ヒステリー」に偏ってしまうからだ。女性は常に分析の対象であっても、女性の対象が分析された所にお目にかかったことはない。今回も然り。誠に残念なことである。▼ とはいえ、なかなか面白かった。様々の問題があるとはいえ、やはりサブ・カルチャー研究の古典というだけの面白さはあった。ご興味のある方にはお勧めしておきたい。 ▼ それにしても、ちくま文庫は大量の絶版本を抱えている。なんとか復刊してくれんかしらん。『テロルの現象学』なんか、ブックオフにも落ちてないし。評価 ★★★価格: ¥ 840 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 2, 2006
コメント(0)
-
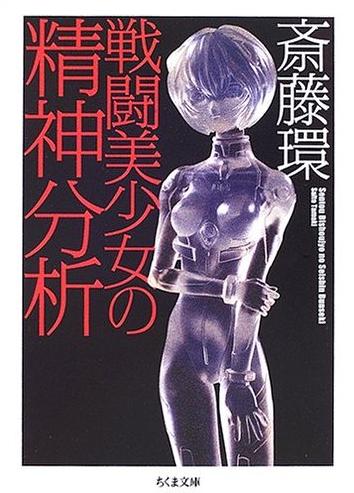
★ 斉藤環 『戦闘美少女の精神分析』 ちくま文庫(新刊) <1>
▼ いやー、うれしいことです。サブ・カルチャー分析の古典、先駆けとして知られる本書が、「ちくま文庫」で文庫化されました。なによりも、現役精神科医が「アニメ」評論を手がけるなんて、当時はあまり考えられなかったことです。まずは、たいへん喜ばしい。すなおに喜びたい。▼ 日本では、何故、かくも「少女が戦う」というモチーフに彩られているのか。これは、ロリータ思考を意味しているのか。無垢や可憐さを完全に維持しながら、思春期の少女が戦いに赴く。これは、欧米の「戦う女性」とは明らかに違う。そこに筆者は、「ファリック・マザー」を援用した「ファリック・ガール」(ペニスをもつ女性)概念を導入して、分析を試みようとするのだが………▼ 斉藤環は、「オタク」の定義として4つをあげる。「A 虚構コンテクストに親和性が高い人 」「B 愛の対象を所有するために、≪虚構化≫という手段に訴える人 」「C 二重見当識ならぬ多重見当識を生きる人 」「D 虚構それ自体に、性的対象を見出すことができる人 」 ▼ フェティシズムの一種としてのマニアは、文明の起源まで遡りうるらしい。マニアは、その趣味においては、「実体=オリジナル」のアウラや有効性にこだわるのであって、オタクのように「虚構=複製物」に目を向けることはない。オタクは、受手になったり、製作者になったりするなど、「自己の立場理解」を様々にかえる(多重見当識)。オタクは、実体ではないものにセクシャリティを「想像的」に感じる一方、現実世界にあっては性倒錯者ではない。かれらは、ヒロインを偶像化しつつ、「現実の女」という代替物で我慢しているのではない。ロリコンとは、性的倒錯のアリバイ証明であって、「性の虚構化」の手続きに過ぎないのだ、という。▼ 斉藤環氏は、大沢真幸のオタクの定義『 「自我理想」(超越的他者)と「理想自我」(ナルシスティックな自己イメージ)の近接』や、「オタク共同体」分析といった手法をとらない。なぜなら「我々は言語を獲得して以来、未来永劫神経症者でしかありえない」からである。非おたく的主体とおたく的主体には差異はない。▼ 第2章「オタクからの手紙」は、オタクの生態がどれほど「虚構としての倒錯」と平行した「健全な性生活」になっているか。その主体の乖離ぶりが明らかにされていて楽しい。また、第3章「海外戦闘少女事情」は、必見に近い。「戦闘少女」というジャンルの突出ぶりは、海外と比較してみると、歴然としている。日本は極端に多い。海外アニメファンの多様な生態とともに、日本のオタクのもつ奇妙な共同性―――多様性よりも一種の単調さをもたらす、雑食性と演技性―――が指摘される。また、海外漫画の一部には日本的コンテクストを使ってファンタジー性を強調するオリエンタリズムさえ見られるものの、1990年代後半には日本の影響を受けた戦闘美少女作品が増殖しているという。第4章「ヘンリー・ダーガーの奇妙な王国」は、圧倒的なパワーだ。公開を前提としない完全な閉じた世界で繰り広げられる、≪ペニスをもった戦闘少女≫たちの世界。なかなか怖い世界といえよう。本書では、「ファリック・ガール」の創造者としての地位が与えられている。▼ 第5章「戦闘的美少女たちの系譜」では、サブカルチャーの歴史が再確認されていて飽きない。石森章太郎『サイボーグ 009』におけるバイオレンスとセクシャリティの特異的結合の発見。『サインはV』『アタック NO.1』における「少女らしさ」を犠牲にしない表現の開拓。「成熟=悪」の構図の出現……… 1970年代、セーラー服を着ない任侠女性だったものが、1980年代には、「セーラー服」「美少女」として実写化されてしまう『スケバン刑事』。こういった様々なエポックが、1970年代後半の女子プロレス・ブーム、大友克洋『童夢』のリアリズム、などに触れられながら、描かれてゆく。▼ 筆者によれば、戦闘美少女の系統は、紅一点系、魔法少女系、変身少女系、チーム系、スポコン系、宝塚系、服装倒錯系、ハンター系、同居系、ピグマリオン系、巫女系、異世界系、混合系…の13種類で分類にされるらしい。その類型化の力技には驚くほかはない。ただ、このような戦闘美少女の系譜は、1989年『トップを狙え』(混合系)の出現をもって完成し、1990年代の戦闘美少女モノは、引用とパロディ、オマージュとして存在しているという。こういう世界では、アニメの伝統や文脈に無知な作家は、決して良質なアニメを作れない。アニメを愛することとは、アニメの美少女に萌えることに他ならない。萌えた彼らがまた美少女を産出してゆく結果、その連鎖として成立するアニメ文化。「自分には女の子は書けない」という荒木飛呂彦の述懐は、たいへん興味ふかい。▼ 第6章「ファリック・ガールズが生成する」は、本書のキモの部分だろう。想像的空間は、基本的に倒錯と親和性が高く、大衆文化は比較的単純な欲望原理に支えられていることは、世界共通である。とはいえ、日本の「漫画・アニメ空間」では、他には見られない、「無時間」「ハイ・コンテクスト」「多重人格空間」という特異性を持っているという。映画的・アメコミ的・石森章太郎では、クロノス的時間が流れているのに対して、アニメではカイロス的時間=「無時間」性を特質としている。加えて、日本の「アニメ・漫画空間」では、瞬間瞬間が「高密度」で描かれながら、それが「高速度」で展開するという、他の国ではまったく見られない、逆説的な特質をもつ。これを可能にしているのは、想像的なモノを象徴的に処理する能力に他ならない!!。この特徴は、日本語においてハイレベルに要請されるものであることを考えあわせると、アニメと日本語は、かなり酷似したメディアであるという。漫画・アニメは自由度が乏しい故に、高度なハイコンテキスト性をもち、画像・セリフなどの各コードが、補完しあいながらユニゾン的に同期しなければならない。この空間では、送り手と受け手の距離は限りなく近く、瞬時に了解されてしまう。(長くなりましたので、<2>に続きます。暖かい応援をおねがいします)評価 ★★★価格: ¥ 840 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 1, 2006
コメント(2)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月4日分)
- (2025-11-18 01:03:49)
-
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(青木祐子)・・その百五十…
- (2025-11-13 20:57:17)
-







