2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年03月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

★ 海野弘 『秘密結社の世界史』 平凡社新書(新刊)
世界は、こんなにも、陰謀で覆われていたのか…一読後、深くため息をついた人も多いのではないか。平凡社新書から、「秘密結社の世界史」と銘打った本が出版されている。朝日朝刊広告では、さっそく「忽ち重版」となっているから、人気を博しているのだろう。簡単にまとめて紹介しておきたい。本書によれば、秘密結社は、古代からあるものの、ルネサンス、18~19世紀の激動の時代に盛んに結成されているらしい。宗教的、政治的、犯罪的。様々に分類されているが、過去の遺物となることなく、今では盛大に復活しつつあるというのだ。法や慣習の危機の時代、秘密結社は復活を遂げる。本書によれば、現代のカルト宗教のようなものは、すでに古代の秘密結社オルフェウス教あたりから現れているらしい。富裕な人々のための、現世ご利益・来世の救済を願う、秘密結社。近代的秘密結社の先駆けは、アサシン(イスラム暗殺教団)とされる。アサシンは、政治的武器としてのテロを計画的・組織的・長期的におこない、信義と自己犠牲を可能にするイデオロギーがあった点で、類例のない組織であるという。中世ヨーロッパは、マニ教の影響を受けたカタリ派キリスト教の出現を除けば、秘密結社が少ない時代だった。ただ、テンプル騎士団は、頭目を殺しても組織が崩壊しない点で、かの「アサシン」さえ恐れる秘密結社だったらしい。武士と僧侶を兼ねた修道会、テンプル騎士団は、巡礼保護のために銀行業務を兼営し、莫大な寄進をうけ、絶大な財力を誇ったものの、14世紀初頭、フランス王フィリップ4世によって壊滅させられてしまう。ルネサンス期、地域共同体をこえて、地縁血縁を超えた友愛団。もう一つは、同業組合という結合が生まれてくる。同業組合から出発してオープンに開かれていったのが、近代的秘密結社フリーメーソンであるという。とはいえ、古代・カタリ派・テンプル騎士団の系譜が流れこみ、後のフリーメーソンへの道筋をつけた鍵となる秘密結社は、16~17世紀の「薔薇十字団」であるらしい。彼らは、秘密結社の存在を印刷技術で宣伝。今のインターネット的な、「幻影」としての秘密結社の先駆けであり、またフリーメーソンからロイヤル・ソサイエティにまで影響を与えているという。しかし、本書のキモは、やはりご存じ、フリーメーソン。アメリカ建国の際、全国組織を持っていたことから、非常に大きな影響を与えたらしい。また、フランス革命時、ルイ16世処刑に賛成した王族、オルレアン公フィリップは、メーソンの大棟梁であったという。他にも、ユダヤ人とフリーメーソンの陰謀説は、19世紀末に出現して、ナチスに受け継がれていくという。19世紀は「イルミナティ(啓明結社)、薔薇十字の復活、アメリカ」の世紀として描かれる。18世紀末出現して短命に終わったイルミナティは、1920年代、ネスタ・H・ウェブスターによって、フランス革命からロシア革命の裏で、世界転覆を図る一大陰謀組織として(書物の上で?)蘇らされた。ユダヤ人=イルミナティ=フリーメーソンの図式を初めて提出したのは、彼女だという。また、西洋科学の思潮に反発して、オカルティズム・魔術に近づく人々が現れ、それにともない、薔薇十字が復活する。「黄金の夜明け」のメイザーズは、カバラ・錬金術・タロット・占星術・薔薇十字伝説を総合し、それを引き継ぐような形でブラヴァツキー夫人は「神智学協会」を設立してゆく。一方新大陸では、中産階級プロテスタントの男性を中心に、成長過程での通過儀礼として、友愛結社の秘密儀礼を用いることが盛んだったらしい。そのため、アメリカでは、秘密結社が網の目のように張りめぐらされ、友愛運動の結社には男子人口の1/4が加入していたという。20世紀は、秘密結社復活の世紀である。なんといっても、1872年、ネイサン・フォレスト将軍を頂点に抱き、テロの疑いで解散命令を出されたKKK(クー・クラックス・クラン)が、グリフィスの映画『国民の創生』によって、「黒人を操り南部を攻撃する北部」から守るためと称して、劇的な復活を遂げてしまうのだ。19世紀末、神智学はドイツ・フェルキッシュ運動と結びつき、独特のオカルト結社を生み、ヒトラーの周囲には「新テンプル騎士団」を初めオカルト関係者がたむろしていたらしい。しかも、今もその流れは存在して、「アトランティス」だの「UFO」だのを秘儀に取り入れているのだという。現在、大流行なのは、「三百人委員会」による「新世界秩序」の陰謀、ウェブスター嫡流の「イルミナティ」。筆者によれば、メーソンやユダヤ人は攻撃するには具合が悪いので、攻撃しやすい空想的な敵として、イルミナティがもて囃されているんだそうな。真顔で、イルミナティは宇宙からやってきたエイリアンと主張する人たち…ここまでくるとさすがにさっぱり分からない。こんな話ばかりでは困るとでも思ったのだろう。最後は、ケリー&ブッシュの大統領選で有名になったスカル・アンド・ボーンと、カルト教団、テロリスト、マフィア、中国の秘密結社などを一通りとりあげてるとともに、「社会のカルト化」「カルトの企業化」に警鐘を鳴らし、秘密結社ブームとは「社会が透明化される一方で、肥大化する不透明さによるパラノイア」と断じられて、本書は締めくくられている。やはりというか、秘密結社とは、基本的に男性のモノ、農耕民族のモノ、であるらしい。秘密結社は、カタリ派しかり、「秘密」と「秘密ゆえの階層制」を軸にして成立していることを改めて痛感させられた。一応総ざらいというだけあって、片っ端から秘密結社の解説書になっていて、あまり深く考えずにさらさらと読んでいくなら、かなり楽しめるのではないか。死海文書とクムラン教団。医学革命のパラケルスス。古代の密教的な知の集大成、グノーシス派キリスト教は、現世を悪・禁欲をとなえ、イエスを否定したという。ダンテ「神曲」は、グノーシス派・東方キリスト教・カタリ派など様々な秘教的要素を総合してキリスト教化したものらしい。1470年代、イタリアで誕生した私的アカデミーが、公的機関に転化していく過程で、裏アカデミーが秘密結社になっていったのではないか、という仮説の提示など、因果関係はともかくとして、前後関係については面白かった。『ダ・ヴィンチ・コード』についても丁寧な解説がある。ただ、ひとつひとつ、本書を丁寧に理解していこうとすると、雑すぎてとても耐えられない本であることも、残念ながら確かなんですね。なによりも、結局、秘密結社が何なのか、さっぱり分らないというのが、本書最大の難点ではないだろうか。当たり前であるが、「秘密があります」と叫んでおけば、それはもはや秘密結社なのである。秘密結社が結局何なのか、秘密結社を単純に並べただけでわかるはずもない。社会儀礼・成人儀礼程度・クラブ・サークルから、カルト宗教・テロリストにいたるまで、筆者によれば「秘密結社」なんだそうだ。それではあえて、秘密結社が「秘密結社」を歴史において名のっていた意味(それは、普通のクラブやサークルが名のらない意味と表裏の関係にある)なんて、一体どこにあったんだろう。気をてらうあまり、歴史的に有名な「秘密結社」を社会に即して理解するという、もっとも単純かつ根気の必要な作業が、本書ではまったく見られない。さらに、『トンでも本の世界』に出てくるような本と、一応真面目に研究してそうな本が並列して扱われ、何の留保もつけられていないのが多い。結局、その記述、信じるべきなのかどうかすら、読者はよく分からないのだ。何とかしてほしい。『トンでも本』を読んでいないと、信じかねないんで、非常に困るんですけど。まあ、陰謀論総まくり、という感じになっているので、現代の陰謀論を知りたい人にはお勧めしたい。しかし、秘密結社を知ろうとする人は、読まない方がいいかもしれない。評価 ★★☆価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 28, 2006
コメント(0)
-

★ 鈴木静夫 『物語 フィリピンの歴史』中公新書 1997年
2001年、アストラーダ政権打倒で、再び世に知らしめた「ピープルパワー」その姿を恐れ、今月初頭、戒厳令を出した、アロヨ政権少し年配の方なら、「ニュースステーション」で、若き日の安藤優子アナが実況していた、1986年のマルコス大統領打倒の様子を思い出される方もいるかもしれません。ほとんど知られていない、「近いけど遠い国」フィリピン。フィリピンとは、いかなる国なのか。本日ご紹介するのは、そんなフィリピン500年の歴史をまとめた概説書です。ほとんど知らない国であるだけに、これがなかなか素晴らしい。スペイン到来以前、海上交易などに従事していた、フィリピンの民。イスラムだけでなく、仏教が伝来していた形跡があるようです。有名なトルデシリアス条約で、スペインの領域に入れられてしまうものの、マゼランを戦死させたラプラプ王を初めとして、誇り高きフィリピン人は執拗な抵抗を続けたという。とはいえ、推定人口は50万人前後で国家といえるものもない。ムスリムの楽園は失われ、新大陸と同様のエンコミエンダ制が導入され、過酷な搾取に苦しんだという。税金を払うため首長から金を借りねばならず、そのため首長の奴隷となるものが続出。強制労働も、さかんにおこなわれた。その支配の鍵となったのは、ご存じ、カトリック。カトリックは、強固な宗教や社会組織をもたないフィリピンに、土着信仰を取り入れながら瞬く間に浸透、布教と支配のための集住化政策がとられ、聖俗両面における強大な修道会支配が行われたらしい。原住民の経済とは無関係のガレオン貿易―――アカプルコ~マニラ間の1年1航海で往復する交易。1航海で400万ペソの法外な利益―――などに対しても、教会は盛んに投資をおこなった。教会は、地方政治、貿易、政治、通商まで支配していたという。18世紀以降、スペイン支配への反乱が頻発するのだが、これが実にまどろっこしい。なにせ、外国勢力と手を結んでの反乱で、失敗だらけなのだ。やがて、輸出型農業への転換の中で、中国系メスティーソが、土地をもてないながらも勤勉さと商業的才能によって台頭。その中から、ホセ・リサールが登場、フリーメーソン運動などの影響と支持を受けつつ、カトリックの軛に苦しむフィリピン社会の啓蒙にのりだした。それは、独立運動に火をつけ、叛乱の首謀者ボニファシオやリサールの銃殺を招いてしまうものの、フィリピン独立へとつながる―――と思うと大間違い。最大の失敗は、ご存知、米西戦争。セオドア・ルーズベルトとマッカーサー父に、見事にフィリピン独立運動が利用されて、挙げ句の果てに捨てられてしまう。1898年、アギナルドは独立を宣言するものの、成立したばかりの議会は、アメリカの植民地・保護領受け入れに傾き、アメリカとの戦争にも敗北してしまう。タフト・フィリピン委員会委員長(後の大統領)による、すべての公教育を英語でおこなう「友愛的同化」政策の実施によって、「アメリカ的」なものが、指導者層・庶民を問わず、どんどん受け入れられてゆく。とはいえ、1930年代になると、アメリカに無関税で輸出できるため、砂糖・タバコなどの大農園換金作物栽培がすすんだ。そのため、「地主-小作」のパトロンクライアント関係が崩壊してしまい、フィリピンは農地紛争の頻発する社会混乱期に突入してしまう。この情勢下、フィリピンでは共産主義運動が高揚、社会党・共産党が合同して、フィリピン共産党が結成される。初代フィリピン大統領(35年以降、自治領)ケソン政権は、「容共」路線に転換して、日本侵略に備え、左翼勢力と足並みをそろえる。そこへ訪れたのが、ご存じ、太平洋戦争。フィリピン共産党は、フィリピン抗日ゲリラの中核「フク団」を形成し、親米勢力は「米比軍ゲリラ」を結成。一方、反米的愛国者が日本とむすんでつくった、日本軍政下の傀儡政権も実にしぶとい。彼らは、「日本の圧政の盾になる」「アメリカより先に独立を手に入れる」などを理由に政権に参加。1943年11月、フィリピン独立を達成してしまう。それも、日本側の参戦要求を頑として拒んだまま、「戦争状態が存在する」との声明を独立後1年もたって出しただけ、という始末。汪兆銘政権、ビルマなどと比べても、そのしぶとさには驚く他はない。1946年に発足した、フィリピン第三共和制以降は、コラソン・アキノ大統領の夫、暗殺された殉国者、ニノイ・アキノの伝説を軸として描かれていて、これまたたいへん面白い。マッカーサーの命令に背き、祖国解放のため闘った反日ゲリラ「フク団」。戦後、彼らは傀儡政権首脳の赦免、という我が目を疑うような事態を目撃することになったという。彼らの戦いは、米国の再占領を可能にして、エリート支配を復活させただけだったのである。米軍は手のひらをかえして大弾圧。そんな中、ひとりの若者、ニノイ・アキノが登場する。マグサイサイ政権の誕生に、若干21歳でありながら、記者として大きく関与。最年少町長を振り出しに、砂糖業経営者、大統領補佐官、最年少上院議員…上院議員となって以後、ニノイは、ハンチントンの立憲的権威主義をモデルに、社会改革の断行を唱え戒厳令を施行した、マルコス独裁政権に激しく抵抗。病気治療先の米国からマニラ空港に到着直後、「フィリピン人のためなら死ぬ価値がある」の言葉通り、暗殺されてしまうのだ。その後の激しい民主化運動。コラソン・アキノが、国軍改革派・カトリック教会・アメリカ…すべての勢力が受け入れ可能な、マルコス対抗馬として擁立された。不正選挙、人民の勝利集会、国軍の決起、戦車隊を取り囲む群衆、そしてアキノ大統領誕生…ただ、輿望をになって登場したアキノ政権は、マルコス政権同様、農地改革に失敗してしまう。また、国語改革も進んでいない。フィリピンは、今も国際的地位の向上のため英語とタガログ語の2言語教育をとり、政府文書にはなお英語が使われているが、小学校教育の現場では生徒に大きな負担になっているという。そもそも、フィリピンにすむ人々は、マレー・ポリネシア系民族。台湾~マレーシア~インドネシア~太平洋諸島にわたる、広域の文化圏の一部を構成しているという。ところが、歴史が分かるのは、なんと16世紀から。南のインドネシアは7世紀、対岸のベトナムにいたっては、1世紀から歴史が分るというのに、近年、10世紀頃のラグナ銅板碑文が出土するまで、碑文・古文書の類がまったく出土しなかったらしい。スペイン征服の正当化にも使われた屈辱的な「野蛮な民」の汚名を晴らす機会が、今まさに訪れているという。とはいえ、スペイン到来以前は、中国の史書などに頼らざるを得ない状況が続き、「スペイン~米国史観」の呪縛から解き放たれてはいない。たとえば、聖書を読めないフィリピン人が作った独自の聖書『パシヨン』。この民衆長編叙事詩『パシヨン』が、フィリピンのカトリック教会に受け入れられていないように、「反米」または「親日」というだけで、正統な評価を受けられない嫌いがあるらしい。「スペイン~米国」を評価軸とする風潮が、今も幅を利かせるフィリピン。フィリピン史を「抵抗の歴史」として位置づけ直そう!歴史の再評価を!!筆者の提言は、胸を打ちます。とかく、定評のある『物語 ○○史』のシリーズの1冊だけあって、フィリピン史にまつわる逸話がちりばめられていて飽きさせない。世界最初に地球を一周した人物は、何あろう、マゼラン船団唯一のアジア人で通訳を務めた、フィリピン人エンリケ・デ・マラッカ。意外や、スペイン統治初期、フィリピンは倭寇の襲撃を受けていたらしく、植民地政庁は豊臣秀吉の情報を綿密に分析していたという。マルコス大統領は、今でこそイメルダ婦人の冴えない旦那のイメージしかないものの、「抜群の頭脳」を誇り、法学部時代は「ナンバーワン」と言われていたというから、驚かされるではないか。若干古い、1997年に出版された新書。そのため、アロヨ政権誕生後、タイのタクシン政権とも共通する強権政治については、本書では何も触れられていない。また、何故だか知らないが、1992年以降が、まったく触れられていない。ラモス大統領やエストラーダ大統領以前で、叙述が終わってしまっている。ただフィリピンの姿は、ある意味、日本と正反対の部分と、重なっている部分に、きっぱり分かれてしまう感じがある。そのためか、日本の現状を想起しながら読むと、かえって参考になる部分が多い。2言語教育による、フィリピン小学校教育の崩壊は、「英語教育」の強化が叫ばれる中では、他人ごとではないのではないか。そもそも、フィリピンの親米的傾向は、英語公用語教育の成果であるという。1920年代のフィリピン植民地の安定と軌を一にした、社会における英語化の伸展。「米国とフィリピンの国益が同じだ」と考える世代の急増。なにやら、国際化が叫ばれる日本で、そんな考え方が急増し、小泉政権の追い風にもなっていることを考えると、不気味なまでの一致が怖いくらいに感じられてしまう。ところが、そんな親米国家でも、ナショナリズムによって、クラーク・スービックなどの米軍基地撤廃が、アキノの反対にも関わらず決まってしまうし、巧みな外交立ち回りも、唸らせられる部分が多い………総じて、現在のフィリピン分析そのものには問題があるものの、その前史を考えるには、お役にたてる新書のひとつといえるでしょう。ぜひ、探しもとめください。なお、本当に久しぶりの更新になってしまいました。ご愛読いただいてる皆様、申し訳ありませんでした。評価 ★★★☆価格: ¥882 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 24, 2006
コメント(1)
-

★ 清水克行 『喧嘩両成敗の誕生』 講談社選書メチエ(新刊)
良書にめぐりあうのは、大いなる喜びのひとつ。日本特有とされる「喧嘩両成敗」法が、どのように形成されてきたのか。本日、ご紹介するのは、その淵源をたどってゆく著作です。古代的ロマンこそかけているものの、中世的世界は、今とまったく異なる興味深い論理で運営される社会であったことが丁寧に解説されているのです。これが、実に、面白い。内容はこんな感じです。● 強烈な名誉意識・自負心をもち、笑われるとキレる中世人● 武家法・公家法・本所法以外にも、村落などでは別次元で通行していた 「傍例」「先例」といった慣行の強固さ街中殺気に満ちあふれていた中世。大名当主も被官も、そんな荒ぶる時代の住人。復讐や敵討ちは、自力救済が基調の社会では、たとえ制定法では違法であっても放任されていた。一般的な日本人とは、忿怒の情を胸中深く隠蔽し、勝利の日が来るのを待ち望む人々がだったという。この当時の犯罪捜査は、「当事者主義」であって、当事者からの訴えがなければ、公権力は犯罪者の捕縛・捜査をおこなっていなかったらしい。では、腕力も裁判を闘いぬくコネもないものはどうすれば良いか。「遺言」して「自害」すれば、公権力によって「復讐の代執行」がおこなわれたというから驚きではないか。「指腹」―――切腹した刀を送り付けられたものは、その刀で自害しなければならない―――習俗は江戸時代まで続き、かの忠臣蔵も「指腹」をもとめた物語であったという。それは、「抗議の自殺」「死で潔白を訴える」習俗として、欧米ではまったく逆で罪を認めてしまいかねない「自殺」が、今に至るまで日本社会では続いている遠因になっているらしい。● 個人より集団アイデンティティーが強い中世● 公認されていた「落ち武者狩り」「掠奪刑」「流罪人殺害」イエは、公権力の及ばない「駆け込み寺」。そこに、「たのむ!」といわれてしまうと、「主人-下人」関係が生じてしまい、その人を守る義務が生じる、そんな社会だったという。人は、イエなどの親族関係以外にも、様々な「主従関係」「同輩関係」を取りむすんでいた。しばしば京では、喧嘩が市街戦にまで発展したらしい。また、同じ「村」「町」に住んでいるというだけで「運命共同体」とみなされ、復讐の対象にされることも多かった。失脚者や流罪人は、「法」の埒外におかれているとされ、私人による掠奪・落ち武者狩り・殺害の対象になったし、公権力はそのような慣行「私刑」の世界を利用することで「公刑」を実現していたという。● 喧嘩両成敗的措置を生むことになった、中世「衡平主義」「相殺主義」● 中人制・解死(下死)人制以外に、室町時代の様々な刑罰方法の 行き詰まりから出現した、喧嘩両成敗中世社会では、多様な法慣習が存在していた。当然、「当知行(用益事実)主義」と「文書主義」の様に、相互に矛盾しあう道理が多く、為政者は頭をかかえる程であった。中世特有の「目には目を」の同害報復の原理は、騒動を拡大させる一方で自制を促す原理ともなる。それは、双方を同罪・引き分けにすることへの拘りとなり、足して二で割る方法(「折中の法」)を採らせることになった。喧嘩両成敗は、戦国大名による問答無用の裁断ではない。それは、中世社会における加害・被害の損害を「同等」にする考え方から、誕生したものらしい。2者の争いを仲裁する中人制や、加害者が被害者に加害者の同一集団に属す「身代わり」を差し出し「見た」後に解放する解死人制など、復讐をもとめる人々をなだめるため、さまざまな慣行がおこなわれていた。時の政権・室町幕府は、理非を問わず、被害者が何人いても加害者「本人」一人だけに「栄誉ある切腹」をさせる「本人切腹制」を志向していたという。それは鎌倉時代の「理非」を徹底的に極める裁判原則や、当事者の復讐心に配慮して「本人」を特定する解死人制、被害者の責任を問わない点では「喧嘩両成敗」とも違っていた。ところが、「本人」の逃亡・特定困難、是非判断の困難などによって、15世紀後半以降、「喧嘩両成敗」の大波に、日本列島は飲み込まれてしまう。中人にみられる第三者調停を足がかりに、戦国大名は裁判権を確立してゆく。● 喧嘩両成敗は戦国大名の弱い権力の証● 今も過失相殺・被害者への偏見など方々でみられる、中世的精神の残存そもそも、喧嘩両成敗では裁判をする意味がなくなってしまう。当然、喧嘩両成敗を規定していない戦国大名の分国法は、数多い。中世的自力救済から、裁判へ。その流れの中で、喧嘩に走りがちな庶民を、「喧嘩に耐えて訴えでれば、一方のみ成敗する」のように大名裁判へと誘導するための過渡期的な措置、それが両成敗原則であったという。両成敗は、逸脱や恣意乱用を招きかねず、紛争当事者の衡平感覚に配慮しながら、緊急に秩序を恢復するための措置にすぎない。戦国大名・織豊政権が取りこんだ野卑な法慣習は、江戸期以降、文明化されその役目を終え、建前上、適用されなくなる。庶民に流れる「衡平」への願いは、赤穂浪士討ち入り事件や、「過失相殺」という制度―――世界的に見れば被害者側に過失があると損害賠償を受けられないのが一般的―――や、社会保険料・厚生年金の折半制度、「被害者の落ち度」がウンヌンされる現代社会など、さまざまに形を変えて現れているという。 「柔和で穏やかな日本人」という自己イメージは、凶暴性を内面に沈潜させる日本人の執念深さを表しているのだとしたら…本書はそのような警鐘を鳴らして締めくくられている。他にも、日本中世史の豆知識がすばらしい。中世では「盲人・山伏」は、祝詛する人びととして恐れられていたものの、江戸時代以降、反発と信仰の変化から、狂言などでは嘲笑の対象になったらしい。また、処刑すると憚られる南朝関係者や足利氏家中の者には、流罪人にすることで、殺害をおこなったという。姦通では、姦夫・姦婦とも殺すべしという判例は、室町時代から始まって、明治時代まで続いたというから、その息の長さには驚く他はない。室町時代まで、自害の方法として庶民にまで親しまれた(?)切腹が、15世紀以降、「自害を命ずる」刑罰へと変化して、やがて江戸時代、武士の特権へと変化してゆくという指摘には、たいへん感心させられてしまう。中世的世界は、日本人にあまり人気がない。しかし、たしかに日本社会のプロトタイプが形づくられた時期であることがよくわかります。現代にも見られ、世界的に特異とされる「喧嘩両成敗」の丁寧な追跡は、スリリングで実に面白い。ただ、どうでしょう。「喧嘩両成敗」が結局、緊急措置にしかすぎず、とうとう法例としては定着しなかった以上、今もしばしばみられる喧嘩両成敗もまた、所詮、緊急措置としてしか現れてこないものではないのか。小泉純一郎の「田中まき子VS鈴木宗男」の対決然り。欧米との法慣習の違いなど、いかに「潜りこんでいるか」が丁寧にも指摘されているものの、さて、欧米や他の社会の場合、理非を明らかにできず、緊急措置が必要な場合、どのような原理で裁断されてきたのか。いささか疑問が残ってしまう。ほとんど、瑕疵にすぎないことは確かだけれど。とりあえず、一読をお薦めしたい一冊であることは、間違いありません。ぜひ、お買い求めいただきたい。評価 ★★★★価格: ¥1,575 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 18, 2006
コメント(0)
-
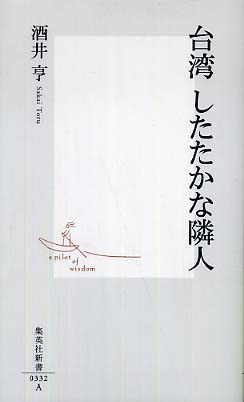
★ 酒井亨 『台湾 したたかな隣人』 集英社新書(新刊)
海峡をはさんでにらみ合う、台湾と中国。現代台湾ハンドブックとしては、たいへん面白い書物が刊行されています。本日、ご紹介するのは、台湾在住の民進党シンパのフリージャーナリストによる、「下」からの民主化、市民の現場からの、民進党政権下の台湾の変貌の報告書です。これがかなり面白い。 台湾化が進む、台湾。その主役、民主進歩党(命名者、謝長廷)。李登輝「上からの民主化」が民主主義として定着できたのは、民進党の台頭に代表される、反原発・環境・女性の人権・弱者の福祉・情報公開など、進歩的な社会運動・市民社会が支えているためだという。若くて活気があり自由で、オープンでまとまりがなく、人脈と理念で派閥があって…。台湾原住民の主流だった平埔族は、母系社会の影響でフェミニズムが強く、これに環境・人権をくわえた運動は、日本よりずっと活発というから驚くではないか。半面、意外と学生運動と労働運動が弱い。当初台湾独立は、国民党独裁政権との対決、台湾民衆に立脚する政治体制をつくろうとする民主的正統性の問題であったため、「独立して中華人民共和国と友好関係を」という主張すらあったらしい。90年代、台湾民主化の過程で、台湾独立が「一つの中国」を拒否する運動へ変容していったという指摘は、蒙をとかれる思いがする。すでに台湾は独立しているとして漸進的な「台湾本土派」(民進党主流派+国民党本土派)と、名実ともなった独立国家を作ろうとする急進的な「台湾制憲建国論」を唱える人びと=「台湾独立派」の潮流があるらしい。このような民進党の誕生には、1970年代、国民党「党外」勢力が台頭して、1979年、人権保障要求デモをきっかけに起きた、「美麗島事件」が大きな役割を果たしている。民主化要求の高まりから、1986年、民主進歩党が結成され議会進出をおこなうものの、終身議員が多かった当時、民意に比べ議席占有率が低かった。そのため、シャンシャン国会を防ぐために、台湾名物「乱闘国会」が生まれ、「街頭抗議デモ」に走らざるをえなかったらしい。94年陳水扁台北市長誕生の頃から、「南北に厚い支持基盤をもつ国民党VS都市浮動票の民進党」の図式から、「北部=外省人=国民党VS南部=台湾人=民進党」という、「族群投票」の流れが開始される。一進一退を続けながら3~4割の得票率をもっていた民進党は、97年の地方選で国民党を逆転。00年の総統選挙では、無所属・外省人・保守派の宋楚兪と国民党連戦の一騎打ちで勝ち目がない、と思われていた所、両陣営の批判合戦の泥仕合と中国の威嚇で、クリーン陳水扁が相対的に浮上。ここに、政権交替は実現したという。ただ、少数与党である民進党の改革は、なかなかうまく進んでいない。民進党政権の長所としては、自由、オープン、参加民主主義があげられるものの、短所はやはり外交オンチ、人心掌握ベタにあるようだ。2001年、李登輝の台湾団結連盟が結成して、側面掩護がおこなわれた。民進党とともに台湾団結連盟は、緑色陣営を形成しているが、そもそも支持基盤・思想がまるで違い(中道右派)、総統選挙以外では野党に等しいという。ただ、03年にはSARS騒動で中国の横車を受けたため、反中国・台湾主権意識が高まり、「正名運動」「(06年)台湾新憲法制定」発言が飛び出すものの、後者の新憲法制定は04年立法委員選挙での過半数獲得で失敗してしまった。とはいえ、五院制を三権分立、環境など左派要素の多い改憲潮流で、この辺、日本の改憲の流れとはまったく違うらしい。また国民党(青色陣営)といえども統一志向ではない。若手を中心に世代交代と脱中国化を求める若手台湾土着派が台頭。台湾には、韓国を民主化の同志として共鳴するものが多い。ポスト陳水扁は、民進党なら謝長廷・蘇貞昌、国民党は馬英九・王金平らしい。なによりも、04年3月、陳水扁の総統再選は、「狙撃事件の同情票」という臆見をキッパリと否定しているのが斬新であった。票読みで定評の民進党直前調査よりも、実は票を減らしているのだという。選挙直後の「当選無効」「選挙無効」騒動での暴力行為で、国民・親民党連合は大きく支持を失ったらしい。また中国は、台湾の併合根拠として両岸の文化的共通性を掲げているものの、福建省南方方言を話すホーロー人(人口の7割)や客家(人口の15%)は、文化的に平地先住民の影響が強く中国語とはいえないという。台湾人にとって中台統一は、「貧しいから嫌だ」から「同じ豊かなら民主主義の方が良い」に変わっている。以前とは違い、中国に独自の魅力がまったくない。また「一つの中国」論は、アメリカ発案で、これによって中国を親米につなぎ止める一方、中台の緊張を高めて台湾に武器を売りつけ親米国家にできる、一石二鳥の策なのだという。完全に意表を突かれた。著者に深く感謝したい。ただ、理論的なツメが甘いのが難点かもしれない。台湾環境運動は、参加民主主義志向と生態主義志向に分けられるという…分けられるのか、それ? 国民党の実態は、地方派閥連合体であるという指摘も、自民党とどう違うのかすら判然としない。一番理解に困るのは、台湾人は政党支持を変えやすいのか(05年地方選挙)、変えにくいのか(04年総統選挙)、筆者ですら一致していない点かも知れない。てか、流動性が高いのか低いのかは、台湾の政党支持が構造化しているかどうかという、大問題のはずなんだけど、矛盾していて平気らしい。これには、本当に参ってしまった。また、日本のメディアの台湾理解の浅さを嘆くのは構わないが、いささか度が過ぎたケチのつけまくりがあいつぎ、何が何だかというのも多い。馬英九はハンサムじゃないことまでケチをつけられても、それがどうしたというのだろう。「長期的戦略をたてることを嫌う」「忘れやすい」…民族性の列挙は、ほどほどにしておいて欲しい。そんな様々な問題点はあるが、一読すべき著作であることは疑いがない。ぜひ、お買い求め、否、お借り求めいただいて、台湾理解を深めてほしい。台湾の明日は、日本の明日かもしれないのだから。評価 ★★★☆価格: ¥714 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 14, 2006
コメント(0)
-

★ 岡田晴恵 『感染症は世界史を動かす』 ちくま新書(新刊)
なに?まだ買っていない?この本の題名をみて、ダサイと思って読むのを止めただと??ならば、ただちに書店・図書館へ急行せよ!これくらい、多彩な新書は珍しい。なによりも、古今東西の伝染病をコンパクトにまとめ、近い将来、確実に日本を襲うであろう、新型インフルエンザウイルスについても展望されているのです。取りあげられている病気は、ハンセン病、ペスト、梅毒、結核。そして、世界を襲うインフルエンザと防疫体制の検討。さぞかし、あなたも目からウロコが落ちる思いをすることでしょう。内容をまとめておきます。● 「地獄門」の外の隔離所「ラザレット」に集住させられたハンセン病患者● 未だに有効なワクチンが開発されていないハンセン病 元々インドなど熱帯の病気であるハンセン病は、潜伏期間も長く感染力が極めて弱いため家族感染が多い。そのため遺伝病と誤解されていたという。また旧約聖書の時代は、中東にはハンセン病は存在していない。イエス・キリストの頃には中東に到達。彼はハンセン病の治療をおこない、中世初期にはヨーロッパに上陸する。ところが、旧約聖書の伝染性皮膚疾患への対処法が、ハンセン病患者への対処法と誤認され、中世キリスト教会は、ハンセン病患者を唾棄すべき汚れたものとして扱った。彼らは、黒いマントに白手袋、山高帽を着用させられ、風下からしか健常人と話をしてはならず、カラカラ、カタカタ、音を立てながら彷徨わねばならなかった。ペスト襲来のとき、ハンセン病患者はペスト患者とラザレットで同居を強いられ、ハンセン病はほとんど全滅してしまう。そのため、稀な病気になったものの、一層陰湿な差別を生み出してしまったらしい。● 根絶できていないペスト● ヨーロッパ都市住民の1/5が感染者だった梅毒 ● ペニシリン以前、唯一の有効な梅毒治療薬、ネオサルバルサン を発明した人物の一人は、日本人、秦佐八郎急性細菌感染病・ペストは、ケオピスネズミノミの腸管に寄生し、クマネズミとともにヨーロッパに蔓延。1348~49年の流行では、ヨーロッパで3000~3500万人を死に至らしめたという。高熱・意識障害・中毒症状を特色とし、潜伏期間は2~6日。腺ペストと違い肺ペストとなると、空気感染になるため、寒い地域では咳とともに猛威を振るったという。ペストの流行は、産業構造をかえただけでなく(人手のいらないワイン栽培や羊飼育)、キリスト教会の権威を失墜させ、中世の終わりをもたらした。東方からやってきたこの新規の伝染病は、毒によるものだ…薬品の知識が深い東方関係者であったユダヤ人は、ペスト蔓延の犯人とされ、西欧各地で集団虐殺がおこなわれた。ユダヤ人が東欧に逃げのびた後でも、集団ヒステリーはやまない。17世紀以降、ペスト蔓延の犯人は、「魔女」とされ、魔女狩りによって大量の生命が奪われたという。一方、性行為によって感染する新大陸産の梅毒は、当初、ハンセン病と勘違いされていたらしい。「娼婦税」を払えば聖職者でさえ情婦をもて、売春宿の最大の商売敵が、女性修道士の無償奉仕だったこの時代、コロンブスのアメリカ到達から20年で全世界的に広がったという。イギリス人・ナポリ人はフランス病、フランス人はナポリ病、オランダ人はスペイン病、ポーランド人はドイツ病と、憎っき宿敵の名前をつけたというから笑えるではないか(日本人は「広東瘡」「南蛮病」)。シューベルト、モーパッサン、ハイネ、ニーチェ、マネなど、多くの芸術家が罹ったという。● 産業革命による人口集中で、表舞台に登場した、「国民病」結核● 抗生物質ストレプトマイシン、BCG(カルメットとゲランの菌、の略称) 接種によって劇的に減少した結核感染結核は、かなり古くからの病気で、ライ病の縁類にあたるらしい。この病気は、劣悪な居住・栄養・仕事の環境によって先進国各地で蔓延したが、日本では「徴兵制度」が加わり、猖獗を極めたという。ショパン、チェーホフ、樋口一葉、正岡子規、石川啄木…患者は数多い。そんな中で、感染症と闘うため、隔離・検疫・衛生委員会・衛生通行証など、現在に続く公衆衛生制度が考案されていった。検疫制度は、12世紀ヴェネツィアで、沖合に40日、船を留めおき病気がないことを確認することから始まったため、英語で検疫のことをクワランティーン(イタリア語の40)というらしい。また、パスポートは衛生通行証が始まりだという。ゴミ箱、上下水道、公衆トイレ…チフスやコレラの蔓延は、こうした公衆衛生の普及によって減ってゆく。それでも、現在、途上国を中心として、全世界で20億人が結核菌に感染しており、毎年2~300万人が死んでいる。日本でさえ、若者を中心に、毎年1万人の新規感染がみられるという。● スペイン風邪に敗れた、ドイツ帝国● 新型インフルエンザ対策を「国家戦略」の重要施策にすえたブッシュ政権インフルエンザは、鴨の腸管を住処にするウイルスであるという。1918~1919年、<スペイン風邪>の流行の際では、20億人中5億人が発症して、2000万~8000万もの人間が命を落としたとされている。変異・増殖の早く、毎年流行ウイルス株がかわるインフルエンザは、人獣共通感染症であるため、迅速な対応が困難。ひとたび、鳥や豚などを媒介にして「不連続抗原変異」がおき、人に感染する新型インフルエンザが出現した場合、1週間で全世界に到達して(潜伏期)、1ヶ月後世界同時流行が始まるだろうという。新たに出現する「新型インフルエンザ」は、今流行している鳥インフルエンザの全身感染、高致死率、強い病原性を引き継ぐ可能性は極めて高いらしい。それなのに、昨年夏までほとんど対策が進んでいなかったという。この窮状は、ブッシュ・ジュニアの昨年夏休みの読書によって、一変。現在では、アメリカのイニシアティブの下、国際規模の協力体制が推しすすめられているという。とはいえ、最悪だと1億人の死者が出ると推測されているにしては、遅々として進まない。このとき、最も発症者が集中するのは、医療機関従事者であって、ここがダウンすれば医療サービスが機能停止になりかねない。ワクチン開発には半年ほど必要。そのため、それまでは抗インフルエンザ薬タミフルやリレンザの備蓄と(使用制限を含んだ)配給計画が必要なのに、まったく進んでいない。タミフルの国内製造を含めた、総合的な対策が提唱されて締めくくられる。なによりも、中世~近世ヨーロッパのたたずまいを巧みに織りまぜながら、伝染病について説明を進めていく、その語り口がたまらない。マールブルクの聖エリーザベト教会。ペスト患者をみとるための「憐れみのマリア」像。特異な服装をするペスト治療医(鳥)………とにかく衝撃的なのは、限界状況における人類の残虐さであろう。この辺、中世の医療行為とヒステリーは、連続していてさして違いがみられない。ペスト治療薬と信じられたテリアカ(アヘン)・ワインの摂取、聖人信仰のエピソードなどは、可愛いものにすぎない。これが、頭を切りひらく「石取り医」、リンパ節切開焼灼、鞭打ち苦行集団、梅毒の水銀治療となってくると、本当にエグい。前近代では、子供たちが医療制度に組み込まれておらず、捨て子が横行していたばかりか、貧しくて子供に構ってられない人々は、ジンやアヘンを子供に与えて眠らせていたという。医学博士。感染免疫学・ワクチン学専攻。そんな人が、神戸市外国語大の国際関係論の授業を受けもち、このような歴史医学の本を書いてしまうとは、正直、驚く他はありません。文化などを手際よく触れながら、人々が病気とどのように向きあってきたか丁寧に明らかにされているのです。タミフルでなぜあれほど騒いでいるのか。いったい、鳥インフルエンザの何が脅威なのか。今となっては、聞くに聞けないこういう素朴な疑問をお持ちの方は、これで確認して欲しい。ヨーロッパの裏の文化まで学べて、たいへんお値打ちな新書になっているのです。社会史部分になると、大雑把すぎる部分もいささか目立つが、目くじらを立てる程のものではありません。むしろ、こういう本は、どんどん出されるべきでしょう。ここの所、ちくま新書は面白くなかったが、吉見俊哉『万博幻想』以来、やっと面白い本が出てきはじめた感じです。お薦めの一品。評価 ★★★★価格: ¥861 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 10, 2006
コメント(3)
-

★ 宮本又次 『豪商列伝』 講談社学術文庫 2003年9月(原本は、日経新書から1970年)
ライブドア粉飾決算発覚、堀江メール騒動、と忙しくすぎた、2006年初頭。「井戸に落ちた犬に石を投げよ」とばかりの狂想曲に、いささかうんざりさせられている人もいるのではないでしょうか。そんな今こそ、読書の出番でしょう。本日、ご紹介するのは、江戸時代の豪商たちの華麗な生態を描いた古典的な概説書。これが、今の「ヒルズ族」と重なってみえる所もあって、なかなか面白いものがあるのです。章立ては、以下の通り1 近世の豪商2 島井宗室3 神屋寿貞と宗湛4 末吉勘兵衛と孫左衛門5 淀屋常安と个庵6 鴻池新六と宗利7 住友政友と蘇我理右衛門8 住友友以と友芳9 三井殊法と高利・高平10 河村瑞賢11 紀伊国屋文左衛門12 近江屋長兵衛13 奈良屋茂左衛門 いずれ劣らぬ著名な人物ばかり。とはいえ、一攫千金のサクセス・ストーリー、『プレジデント』『ダイヤモンド』などで特集されるような、チンケな経営指南書ではありません。なによりも、当時の豪商の論理、日本の商業事情がさりげなく描かれているのが喜ばしい。やはり近世初期の豪商は、御用商人・冒険商人が主流だったようだ。西国の大名や京・堺・長崎・江戸の商人によって担われた南洋への朱印船貿易は、船主に対して、資金の共同出資をおこない、リスクも高いので年利3~5割のリターンを要求するものだったらしい。銀山経営やロウの専売をおこなった神屋家、分割投資によるリスク分散を家訓で説いた島井家や末吉家も、そんな時代の申し子。戦国大名などへの投資などを欠かさず行っていたらしい。やがて徐々にかわりはじめるのが、後に「闕所」となったことで有名な淀屋あたりから。淀屋は、やがて米・魚価格の独占的決定権を幕府から得て台頭したという。鴻池家は、清酒酒屋から海運業へと進出して、両替商になり、いわゆる大名貸を始めたことは商人の「あがり」が、今の銀行にあたる両替商であったことを改めて確認させてくれます。一方、住友家は、銅山事業・「銅吹き屋」から家を興して台頭。その「業祖」にあたる蘇我理右衛門は、西洋人から「南蛮吹き」と呼ばれる技法を盗んだという。その技法とは、銅・銀が雑じっている銅鉱石を亜鉛をまぜて融解、温度を325度以上にあげて、「銅」と「銀亜鉛」の合金に分離して、その合金を灰炉の中に静かに「溶かし吹き」をおこない、「灰吹銀」を抽出する方法らしい。なかなか大儲けしたようだ。ところが、近世中期になると、豪商は材木商が多くなってゆく。いわゆる、近世の「開発の時代」の到来。東回り航路や西回り航路を開拓した河村瑞賢は、「灯籠流し」で使われた茄子や瓜を漬け物にして行商を始めて、土木工事で財をなしたという。三井家は、かの三井高利の母、殊法がまさに女傑。質・酒屋・味噌屋を経営して手腕を発揮。彼女は、息子を各地に派遣し、高利も江戸では始め両替商を経営していたらしい。高利は、兄弟の死後、三井越後屋呉服店を開き、場末の呉服商の商いであった「現銀店前売」や、「掛け値なし」「諸国商人売り(卸売)」をおこない、周囲の商人の強烈な反感を買いながらも、御用商、公金為替取扱の両替商と広げていったという。むろん、こんな固い儲け方の話ばかりではありません。紀伊国屋と奈良屋の財産の浪費など、消費文化などが透けてみえてたいへん面白かった。むろん、豆知識も豊富で楽しいものがあります。河村瑞賢は、新井白石など、学問のオーナーとして振る舞っていたという。意外や、大阪の有名商人には、淀屋を始めとして武士身分あがりのものが多いらしい。住友家を苦しめた、幕府の鉱山への課税。その統制の元締めにあたる「銅座」は、住友の別子銅山のほとんどの荒銅を買い上げ、銅吹き屋に渡して棹銅に精錬して、輸入代金として外国商人に手渡すべく、長崎に回送していらたらしい。他にも、戦国期に石見・生野の銀山がでるまで、対馬が銀産地であったにすぎず、西国は銀使い経済ではなかったというから驚くではないか。なによりも、現代日本の淵源を改めて確認させてくれるのが嬉しい。江戸時代も大店となると、番頭・手代・丁稚の役割分担が定められ組織的運営がおこなわれるばかりか、「店」と「奥」(家族)が分離していく。そこでは、「奥」が「店」に出資をする形をとり、主人は俸給生活者のようになっていくという。今の株主と株式会社の関係が想起されるであろう。また、江戸時代の商人にとっての理想像は、45歳まで蓄積して、それ以降は引退することにあったという。土地や家屋を購入して家賃収入で生活する「仕舞うた屋」(営業をやめた人)になり、遊楽三昧で暮らす夢を追いかけた商人たち。現代アメリカ人ビジネスマンの価値観を見ているみたいで、たいへん微笑ましい。とはいえ、江戸期を通しての豪商は、淀屋といい、河村瑞賢といい、奈良茂といい、たいていが土木工事・木材商などの戦時成金・御用商人である、という実相はたいへん情けない。実は、「土建屋政治」「列島改造」などのゼネコン利権は、江戸時代からあったというのだから恐れ入る。かの高名な紀伊国屋文左衛門も、実はミカンというよりも、材木商になることで金を稼いでいたという。そして豪商が御用商人であることの多さ。かの三井高利も、牧野備後守成貞の引きで、公金取扱をおこなえるようになったのだという。江戸時代から400年、今や平成の世の中。時代は変われど、日本で豪商・大金持ちになりたいなら、所詮、権力と結託するしか方法がないのか。前回の総選挙において、ホリエモンと自民党の共闘、トヨタの総力をあげての自民党支援、などをみると、江戸時代からあまり変化していないことがわかってしまい、あいも変わらぬ「開発独裁」には、ゲンなりさせられてしまう。そんな中でキラリと光るのが、近江屋長兵衛。ご存じ、超優良企業「武田製薬」の創設者。宣伝・広告などが考えられもしない。そして得意先を奪うことが商業道徳上許されなかった時代。そこで、薬問屋から始めて、長崎から薬を仕入れ、地道に得意先を回りご用聞きを行い、一歩一歩拡大させ、やがては世界企業に………一服の清涼剤になっていて、感動的ですらある。こんな豪商をもっともっと出してくれれば、ずっと面白かった…逆に『中堅商列伝』になってしまったかもしれないが。海外貿易の従事者でさえケチケチを重ね、茄子の皮やヘタまで節約して金をためた豪商たち。今こそ、そんなユニークで面白い豪商たちの生き様を学ぶべきでしょう。ほとんどの図書館には入っているでしょうし、これをお読みの皆様は、ぜひご一読していただきたい。評価 ★★★価格: ¥945 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 7, 2006
コメント(0)
-

★ 山下範久編 『帝国論』 講談社選書メチエ(新刊) <2>
(承前)第六章は、アメリカの国際関係研究に氾濫している≪帝国≫論について、議論の整理をおこなおうとする論攷である。ネグリ≪帝国論≫は、アメリカの国際関係研究には、あまり好意的に受け入れられていないらしい。アメリカの国際関係研究における「帝国」論は、主として、主権国家がつくるシステムを前提として古典的覇権論の延長に「帝国」をおく立場と、ネグリと問題意識を共有して、こうした古典的システムが崩れつつあることを強調する立場、あわせて2つの流れがあるものの、圧倒的に前者が多いという。前者は、特定の政体の性格規定に矮小化されやすい。また後者は、現在の国際システムが国家間関係のシステムに還元できない現実を捉えようとする課題の達成には成功しているものの、あらたに提示するシステムが、旧来の資本主義・全体主義批判の論理に回帰する傾向がみられるという。全体から出発する≪帝国論≫と、部分から出発する国際関係研究。「インフォーマルな帝国」分析に際して、両者をどう総合すべきなのか。悩みはつきない。第7章では、ウォーラーステインのアメリカ・ヘゲモニー論を再検討することで、「短い20世紀論」を批判的に総括し、「近世帝国」概念を導入して「長い20世紀」(新しい帝国)概念が歌いあげられている。1918年ロシア革命から説き起こし、1968年頃から≪資本主義的蓄積・国民国家・アメリカの覇権≫の「限界」が始まり、1989年ソ連崩壊とともに時代の終焉をみる、「短い20世紀論」。この視角は、バリエーションは様々あるものの、南北問題を隠蔽して、機能を低下させている主権国家を捉えていないばかりか、スターリニズム・ファシズムとケインジアンに絶対的な線を引いてしまうなどの、深刻な「偏向」を帯びている理論だという。ブローデル~ウォーラーステインの「長い16世紀」に見られるように、資本主義形成と国民国家形成には、2世紀のタイムラグがあった。筆者によれば、その間は「不完全な帝国」の時代だったという。19世紀からの2世紀は「帝国の不在」という人類史の例外状況に他ならない。本源的な生産要素の「擬制商品化」が限度を超えて、「大転換」が生まれたというポランニーの議論も、本源的生産要素のもつ「聖性」は「近世帝国」時代に生まれたものであることを忘れているという。戦間期の「大転換」は、脱市場化ではなく、グローバルな市場の制度化の起点にすぎない。「長い20世紀」は、帝国の不在に終止符を打つ≪帝国≫の時代の始まりである、高らかに宣言されて、本書は締めくくられる。ネグリに触発されたという本書。全般的にどのような評価すべきか、たいへん悩ましい。評価できる章は、第1章、第5章、第6章の3つであろうか。この章は、対象が限定されて面白かった。社会主義における民族問題など、参考になる部分は大きい。ただそれ以外は、あまり評価できない。第2章は、スーザン・ストレンジ「構造的権力」を想起しながら読んだためか、「規制帝国」としてEUを論じることに、どれほどの意味があるのか、評者はまったく理解できなかった。「帝国」を実体的に扱わない本書の方針はどうなったのだろう。第3章のモンゴル土地改革の言説分析は、端的につまらない。様々な根拠づけが使われることを論じているものの、権力が一貫していること自体、幻想ではないのか。もう少し、土地改革に対する地道な実証を心がけた方が、はるかに面白かったと思う。第4章は、もっともらしいが、カール・シュミットの解説をデリダ~ジジェク~東浩紀などの「911」前後の議論に接合させただけにしかみえない。読者はなめられてるのだろうか…。どこに固有の≪帝国≫論があるのか、さっぱり理解できなかった。一番ひどいのは、案外、編者の山下範久執筆部分の第7章かもしれない。ウォーラーステインの世界システム論から帝国を論じる試みなのだが、完全に失敗している思う。評者は、「世界システム論」をかじった程度でしかないし、≪「世界システム論」論≫などには疎い。とはいえ、「世界帝国」と「世界経済」の違いは、前者が政治体制枠内に経済がおさまり、後者はその逆であることくらい理解している。「インド洋世界システム」だの「朝貢体制論」などが唱えられたのは、完全な「世界帝国」なるものは、いまだかつて存在したことがないことの裏返しであろう。それなのに、「不完全な帝国」なる概念(=インド洋などの各種世界経済と同義)をあらためて提起することに、どんな意義があるのか。18世紀、清朝・ムガール帝国、オスマン・トルコをあげて、「近世帝国」の時代と整理。その上、19世紀から始まった「第二の世界経済」が終焉して、今まさに「帝国」の時代が始まっている―――と、「帝国」の時代と「非帝国」の時代の交替論を唱えることに、今ブームになっている「帝国論」におもねる以上の、どれほどの意味があったのか、評者は疑念を禁じえない。おまけに、「大転換」という言葉を使いたいためだけに、ポランニーを引用。挙句、次なる「帝国」の時代は、なんと驚くなかれ、高度技術社会によって展開される「動物」の時代なんそうだ―――稲葉振一郎氏のようなセンスがあるのならともかく、学際とは名ばかりの、様々な学説の「つかみこみ」をここまでセンスなく悪趣味におこなう姿には脱帽の他ない。おまけに、これ、学会で報告したらしい。ちょっと勘違いしていないか。こんな恥ずかしいもの、凡人は怖くて出せないだろう。訳著『リオリエント』などで、この人の著作にはお世話になっただけに、たいへん残念である。面白いといったら、まあフカシ方は面白いのだが…という訳で、あまりお薦めできる作品ではない。まあ、図書館で見つけたら暇つぶし程度で目を通しておきたい。評価 ★★☆価格: ¥1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 3, 2006
コメント(2)
-

★ 山下範久編 『帝国論』 講談社選書メチエ(新刊) <1>
保守・左翼。様々な立場から寄せられる、アメリカ帝国「賛美と批判」。冷戦下における帝国主義批判や帝国批判は、すでに無効となっているものの、アントニオ・ネグリを始めとして様々な潮流が現れていることは、みなさんもご存じの通りでしょう。本書は、そうした「帝国論」の中間決算を目指して、編者が読みたいとおもった研究者に帝国論の寄稿を依頼したものだという。<帝国>を実体として捉えない。そして<言説的権力としての帝国>―――正統化のための言説空間がどのように構築されているのか―――こうした問題設定を軸にして、村田勝幸、鈴木一人、滝口良、重田園絵、松里公孝、芝崎厚志、そして編者のあわせて7名(順番に1章~7章と担当している)が集められた。嫌がうえにも、われわれの期待がかきたてられるというものでしょう。内容を簡単にまとめておきましょう。第1章は、ジュリアーニ前ニューヨーク市長の「コミュニティの信頼に根ざした」「ホームランド・セキリュティ」の論理が俎上にのせられている。帝国と帝国主義を切り離して扱うネグリ≪帝国論≫の議論は「アメリカ例外主義」を隠蔽してしまいかねない!。この批判の下、2つの視角から検討される。人種とジェンダーのトランスナショナル性は、≪帝国≫によってどのように変質したのか。また、「ホームランド」というファンタジーに支えられたジュリアーニの論理は、セキリュティ感覚を通して、その内部からどのように「異質な外部」を再生産し敵視し除去してきたのか。赤裸々に示される、ジュリアー二政権下、NYにおける、マイノリティ(黒人)への人権侵害。ところが、こうしたジュリアー二批判は、「9・11」以降、鳴りを潜めてしまう。これは、≪帝国≫のパワーによって、多様性や異質性を容認しないその空間が隠蔽されてしまっている姿を現しているという。第2章は、EUの≪帝国≫性を論じている。EUとは、貿易・投資・経済などさまざまな関係を通して、かれらのもつ市場活動規制をEU領域外に受け入れさせてゆく、「規制帝国」に他ならない。その際、軍事的な強制を避けながらも、規制の「普遍性」を強調し、「自発的」にEU領域外に受入させてゆく方法が採用されており、事実上の「勢力圏」が形成されている。このEU「規制帝国」は、かつての植民地をもつ「国民帝国」の崩壊の反省から産み落されたもので、民族自決権を前提とした、比較的コストのかからないものという。ただ、アメリカの「規制帝国」としての側面と比較することで、EUのもつ脆弱さが明らかにされる。影響圏は、世界レベルではなく、また比較的富裕な諸国には通用していないし、帝国としての一体性を持ち合わせていない。21世紀型≪帝国≫は、規制帝国以外の形態をとりえないと提起されて、本章は締めくくられる。≪言説的権力としての帝国≫がどのように作用しているのか。第3章では、近代化とグローバリゼーション、脱社会主義化の3つが同時に進む、モンゴルがケーススタディとして取りあげられている。有史以来、モンゴルで初めて、「土地私有化」が公認される土地所有法は、どのような言説の場におかれてきたのか。アジア開発銀行や国際機関などでは、この法律のメリットとして、「私的所有権を持たないことによる、環境破壊と非有効的な資源利用」が改善されることにがあげれてきた。ところが、モンゴル国内では、まったく事情が違うらしい。私有化は、「土地の主」=「国家の主」=チンギス・カン以来の国土を守る(国家の独立)という、体制移行(社会主義から資本主義へ)後の政治的正統性を強調する言説の下におかれているという。これは、2枚舌なのではない。≪帝国≫という体制下では、「同質化と差異化を同時に推進される」(by ネグリ)のだ。グローバル化の背後に合衆国などの先進国の意図を見出そうとしたり、国家やローカルなものをグローバリズムへの抵抗と看做そうとする思考を拒否するものとして、ネグリが改めて高く評価される。第4章では、反ユダヤ主義・ナチ協力者として悪名高い、カール・シュミット著『大地のノモス』をアメリカ≪帝国≫論として読まんとする試みになっている。近代に成立した「ヨーロッパ公法」秩序が、≪帝国≫アメリカによって掘り崩されていくと捉えた、シュミット。この新しい世界では、旧来の戦争における「正しい敵」は消え、敵は「犯罪者」「治安攪乱者」にすぎない。これは、シュミットによると、「公法」以前のキリスト教的正戦論への復帰ではなく、力あるものによるイデオロギーにすぎないという。これは、≪言説的権力としての帝国≫の真実の一面を捉えていることは疑いない。ところが、そうしたヨーロッパ・日本などで通行する批判的言説は、別種の≪言説的権力としての帝国≫が再強化される―――ヨーロッパを「一枚岩」としてとらえるヨーロッパ中心主義の強化、「均質なる日本」という価値観の強化―――カラクリがはらまれているという。それは、異質なものの排除に向かいやすい。また、≪帝国≫アメリカを強権国家と名指しすることは、世界的セキュリティと治安技術の向上による≪グローバルな帝国≫が出現していることを忘れさせやすい。批判的に用いられてさえ、別所で≪帝国≫を強化してしまう、パラドクス。第5章は、ソ連崩壊以後の、「ロシア帝国論」の動向から、≪帝国≫が問い直されている。レーニン以来ソ連では、特異な「原初主義」的(実体主義的な)民族概念=「タイトル民族」が採用され、民族領域主義によって、行政区画にまで反映されていた(「チェチェン共和国」など)。この民族理論は、社会主義諸国全体に大きな波紋と影響を与え、ユーゴ紛争などの様々な民族紛争を招いた。現在、「構築主義」的理解にもとづく「空間主義的アプローチ」が、原初主義にもとづく「民族中心主義的アプローチ」に対して批判的に提起され、旧ソ連諸国において空前の≪民族≫研究ブームがおきているという。これは、民族の裏にある、ロシア~ソ連の≪帝国≫研究を刺激せずにはおかない。今では、空前の≪帝国≫研究の盛行がみられ、新しい多民族共存のための≪帝国≫という視角が打ち出されているという。ロシアとソ連、この2つの多民族≪帝国≫は、純粋空間主義的行政原理から、民族領域主義に転換して、本来なかった民族エリートを養成して、「分離主義」の蠢動を引きおこすことになった。ある種の≪帝国≫をユーラシアに打ち立てようとするEUとプーチン政権が、純粋空間主義的行政原理への回帰を主張するのは驚くに値しない、と断じられる。(長くなりましたので、<2>に続きます。暖かい応援をおねがいします)評価 ?価格: ¥1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Mar 1, 2006
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月5日分)
- (2025-11-19 00:45:45)
-
-
-

- 楽天ブックス
- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…
- (2025-11-18 10:54:57)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-







